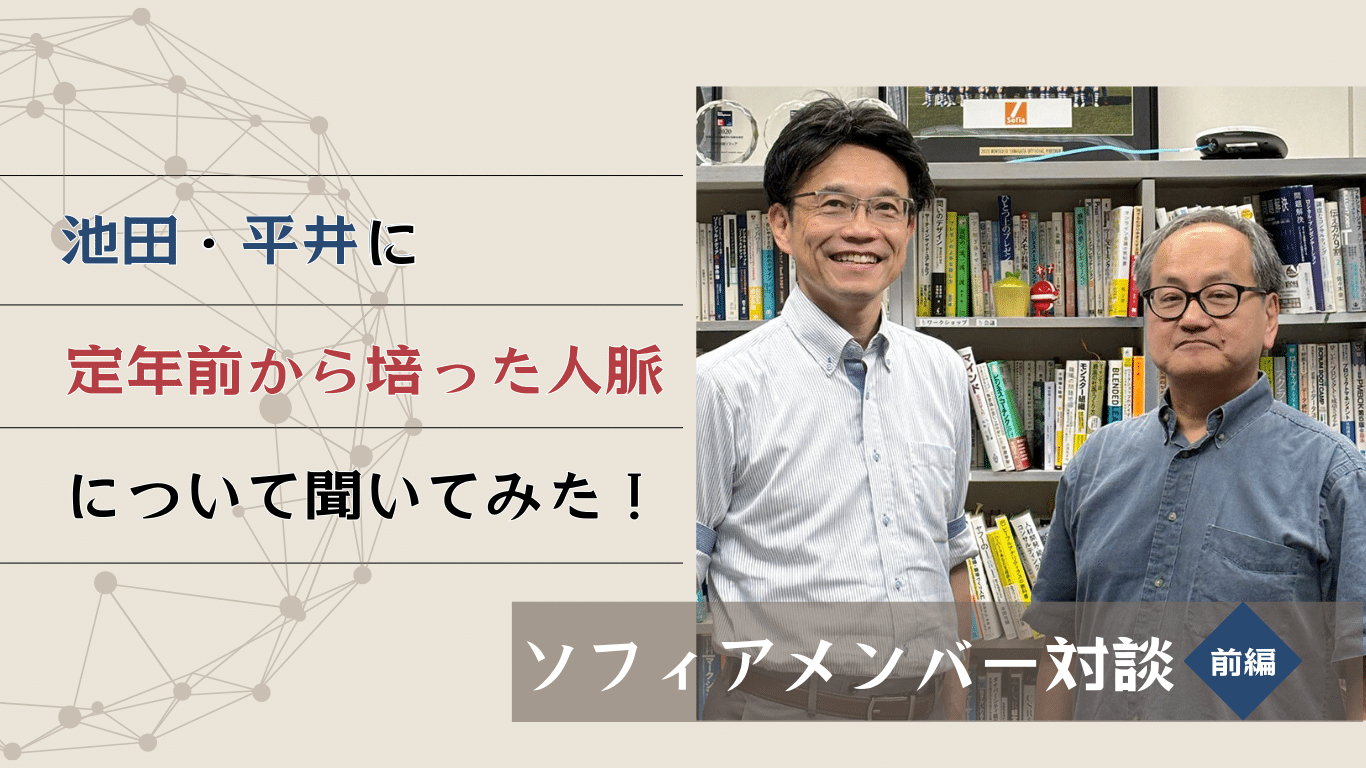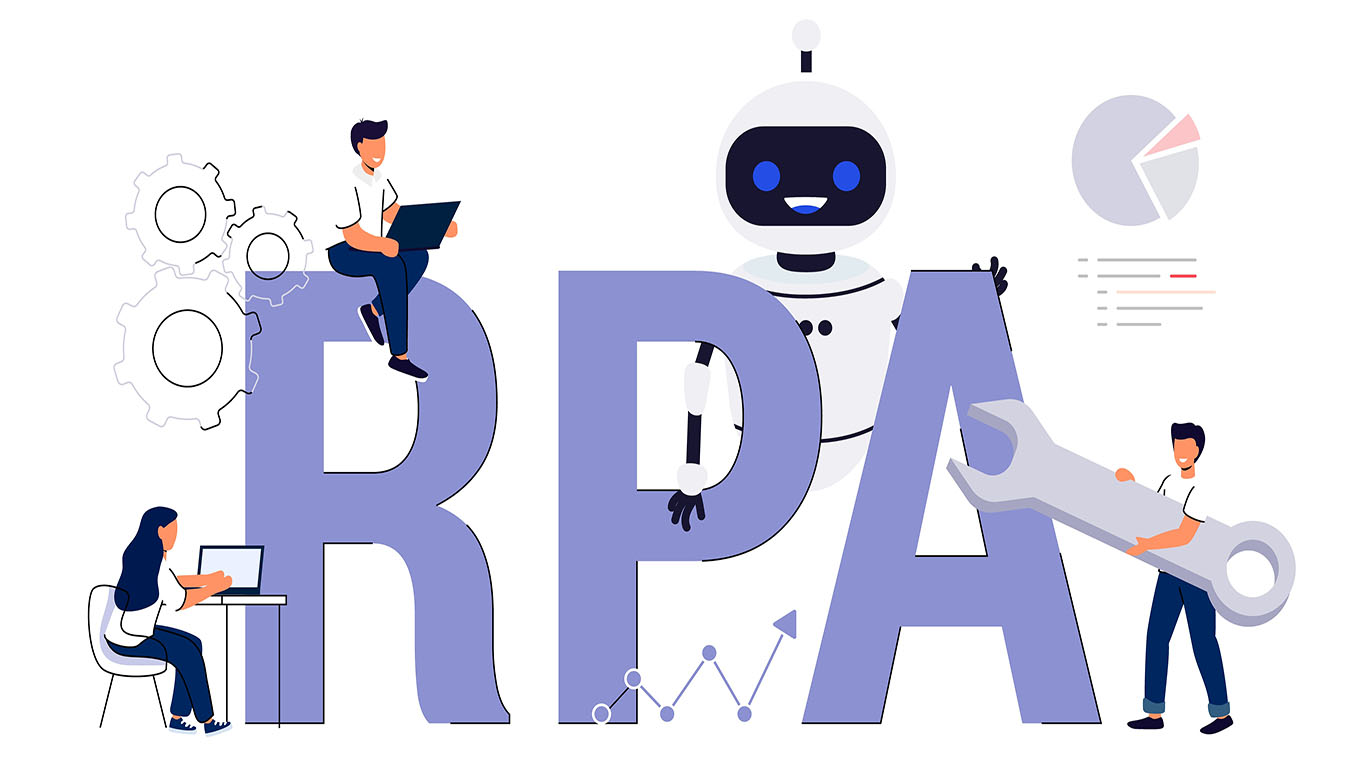マインドフルネスとは?意味や行うメリット、ビジネスで必要な理由とその効果を解説

目次
マインドフルネスとは、意識を集中することで雑念から心を自由にして、現実をフラットに受け入れる状態を指します。昨今のビジネスシーンでは、マインドフルネスがもたらす効果に注目が集まり、導入する企業が増えています。
本記事では、マインドフルネスにまつわる基礎知識やビジネスで注目されている背景、メリットや具体的なやり方について詳しく解説しています。
マインドフルネスとは
そもそもマインドフルネスとはどのような概念なのか、歴史をたどって詳しく見ていきましょう。もともとは仏教の教えから生まれたものが、現代において意味合いを変えながら注目されるようになっています。その変遷から、現代におけるマインドフルネスの輪郭を明らかにしていきます。
仏教におけるマインドフルネスの意味
仏教には重要な教えである「八正道」(はっしょうどう )があります。「八正道」は涅槃(nirvana)に至るための行いを教えるものです。その中の第七支に「サンマ・サティ」というパーリ語の仏教用語が存在します。
「サンマ・サティ」は漢語では「正念」とされ、常に落ち着いた心を意味する概念です。
このような心の状態は、仏教において伝統的に重要視されてきました。
また、マインドフルネスは、仏教の修行の中で、特定の状態や目的を達成するための手段として位置付けられています。具体的には、自己観察や瞑想を通じて、自己との関係を深め、心を穏やかに保ち、現在の瞬間に集中することを目指します。このような修行は、悟りや解脱への道を開くとされ、仏教の中核的な教えの一部として位置付けられています。
現代におけるマインドフルネス
現代におけるマインドフルネスは、1979 年に大学院教授のジョン・カバット・ジンがマサチューセッツ大学の医学センターで MBSR(マインドフルネスストレス緩和プログラム)を開発し、ストレス低減センター(マインドフルネスセンター)を立ち上げたことがきっかけで誕生しました。
マインドフルネスのベースとなっているのが仏教における瞑想です。瞑想とは、呼吸や五感が経験する感覚を通し、感情・記憶・思考といった、意識の中に浮かび上がるイメージや概念にとらわれない心を育成する技法で、主に修行僧や住職が行うことで知られています。
マインドフルネスは身体の五感に意識を集中させることで、心を過去の出来事・問題・先入観といった雑念から自由にし、ありのままの現実をフラットに受け入れる状態を指します。今ここで自身の身体に起きている感情・感覚をあるがままに認識することで思考を解き放ち、雑念にとらわれることなく思考や身体感覚を観察している状態を作り出します。
私たちの五感は、あまり当てになりません。その時その時の感情や記憶、思い込みによって、対象をそのまま見ることができず、歪んだ形で見ています。裁判においても、今では目撃者証言がほとんど重視されなくなってきていることからも、私たちの五感が信頼のおけないものであることがわかります。
とりわけ、世界の宗教の中で、瞑想をもっとも重視したのが仏教であり、その仏教から派生した教えが密教や禅でした。マインドフルネスとカタカナで書けば現代的な響きがしますが、実際には、密教や禅で行われる瞑想を日常生活に取り入れられ、とらわれない心を磨く修行です。
瞑想と言っても、さまざまなものがありますが、共通していることは、一点に集中するという作業です。この一点に集中する対象を目前のビジネス課題に向ければ、より純粋で透明な心で、判断ができるということです。その判断が、雑念や感情にとらわれた判断よりも、よほど的確で広い視野もつことは、当然でしょう。
マインドフルネスとヨガ
一点集中する時には、その時の身体の状態が重要になってきます。痛いところがあったり、固いところがあったりすると、一点集中はできません。それゆえ、瞑想の前段階として体をリラックスさせ柔らかくさせるためのヨガが行われます。瞑想とヨガは不可分なものであり、思考と身体の柔軟性はつながっていることを確認しておきましょう。
ヨガにおいて、呼吸数と心拍数が重要になってきます。一点集中のためには、呼吸数も心拍数もできるだけ少ない方がいいというのがヨガの考え方です。理想を言えば、柔らかな体でリラックして座り、呼吸も鼓動も少なくなっていくことが、ヨガの完成形です。この状態で、仏教僧は生きる意味や世界の構造を瞑想対象にしていくのですが、現代のビジネスパーソンは、マインドフルネスを用いて瞑想対象にビジネス課題を選びます。
マインドフルネスの歴史
マインドフルネスのルーツを整理したところで、より詳しく、マインドフルネスが世の中にもたらした歴史についても見ていきましょう。マインドフルネスは文化や流行として、人々の生き方に変化を与えています。また、西洋と日本では、流行した年代や背景が異なります。
西洋におけるマインドフルネスの歴史
1965 年にアメリカで移民国籍法が成立し、アジアからの移民が流入するようになりました。
これを機に、「マインドフルネスが仏教の中心である」と説きながら、マインドフルネスに関する英語の本が多数書かかれるようになりました。ドイツ生まれのスリランカ上座部仏教僧、ニャナポニカ・テラ(英語版)やベトナム人の禅僧ティク・ナット・ハンといった僧侶たちが代表例です。近年の西洋におけるマインドフルネスの流行のきっかけは移民だったのです。
2000 年代には、アメリカで東洋の思想実践への興味が高まるムーブメントが起こりました。
未来に向かって向上を続けるアメリカの現代社会に不足している「『今』への集中」が、仏教の教えを踏まえると実践できると考えられ、マインドフルネス瞑想が浸透していきました。
日本におけるマインドフルネスの歴史
西洋と比較すると、日本におけるマインドフルネスの浸透はもう少し遅いものになっています。1993年にマインドフルネス関連のワークショップが開催されたことがありましたが、当時はまだあまり関心を集めるテーマではありませんでした。日本においてマインドフルネスが注目されたひとつの大きなきっかけは、2016年にNHKで放送された番組と言われています。
ストレスの対処技法として、マインドフルネスに着眼点を置いた紹介が流れ、多くの関心を集めました。それを機に、徐々に興味を持つ人が増え、近年ではさまざまなメディアで取り上げられるようになっています。SNSでマインドフルネスに関して発信する人も増えていて、注目が集まっているのがわかります。
ビジネスにおいてマインドフルネスが注目されている背景
海外の名のある経営者には、瞑想を取り入れている人物も多く、マインドフルネスという言葉が流行ったのも、そうした先達の影響があったからでしょう。
マインドフルネスには集中力やストレス耐性の向上といった副次効果が期待できるため、社員のパフォーマンスを向上させる手段としてビジネスシーンで注目されています。その理由として価値観の多様化があります。
価値観の多様化により画一化された働く理由が通じなくなったため、マインドフルネスによって自己と向き合い、「何のために働くのか」を再定義してもらうためです。とくに近年はITの急速な発展により情報化が進み、人々の生活スタイルや価値観は平成以前に比べて細分化されています。現代は昔のように「出世して結婚して家を持つ」という明確なゴールがないため、盲目的に仕事をするだけでは自己実現できません。
そこで、マインドフルネスによって多量な情報のバイアスを外し、自分自身の感覚をあるがままに見つめ、仕事観や本当の希望・人生の意義について考える機会が必要とされています。
また、社員の考える仕事への価値観と企業が提供する労働環境の乖離も問題になっています。このような状況を打破するためには組織・行政などによる施策も重要ですが、社員各々がマインドフルネスによって自身の意識と向き合い、現場レベルで対応することも重要だと言えます。日本のビジネスパーソン、とくに経営者層や管理者層もマインドフルネスをマスターし、的確なビジネス判断で他国の企業との互角の成果を出していくために取り入れるべきではないでしょうか。
ビジネスにおけるマインドフルネスの効果とメリット
ビジネスにおいてマインドフルネスを行う理由は、社員各々のパフォーマンスを向上させ、成果を出すためです。では、具体的にどのような成果につながる効果があるのでしょうか。ここでは、マインドフルネスでとくに期待される効果について解説します。
集中力が上がる
マインドフルネスの大きな効果として、集中力の向上があります。瞑想を行い、呼吸や身体感覚に意識を集中することで雑念から解放され、あるがままの状態を俯瞰します。瞑想中に湧き上がってくる思考やイメージについては、「今〇〇と思っている」と客観的に扱い、とらわれない状態をキープします。
瞑想によって俯瞰の視点を手に入れると、雑念をスルーできるようになるため、仕事への集中力が向上します。さらにこの時、集中力が上がると同時にストレス耐性も向上しています。雑念をスルーできるということは、ネガティブな情報・イメージについてもやり過ごすことができるため、ストレスに意識を引っ張られることが減少するからです。
マインドフルネスによる集中力の向上は、継続するほど効果が高まり、持続すると言われています。たとえば仕事前の5分~10分、休憩中に5分ほど瞑想を行うだけでも、思考が雑念の影響を受けにくくなり、クリアな状態で業務に向き合うことができるでしょう。
日本の高校の中には、朝、目を瞑って数分間を瞑想をさせている進学校がいくつかあります。なかでも神奈川の男子高である栄光学園は有名です。それは、このような瞑想の時間が生徒の1日に良い影響を与えると知っているからに他なりません。これは学生に限った話ではなく、企業においても同様の効果が期待できます。
また、慣れていないうちは目を閉じた瞑想と言っても、雑念しか出てこないでしょう。しかし、続けているうちに瞑想対象と雑念を明確に区別することができ、対象がはっきりとしてきます。この静かな心の状態で、瞑想対象を曇りなく見れば、その課題と解決方法が徐々浮かび上がってきます。
仏教僧のように「生きる意味」を瞑想の対象にした場合に、なかなか答えが出ませんが、ビジネス課題であれば、瞑想をうまく活用することによって、簡単に名案が出せる場合があります。
いろいろなアイデアが湧きやすくなる
ビジネスにおいて重要なのが創造性ですが、アイデア出しの領域でもマインドフルネスは効果を発揮します。マインドフルネス状態に入ると余計な思考や雑念が減り、脳が疲れにくくなるため受容能力(情報を受け取る力)が向上し、さまざまな考えに対して思考を巡らせることができるためです。
新たなアイデアとはすなわち、既存のアイデアや情報の組み合わせで生まれるものであり、どれだけ脳が素直に情報を受け取れる状態かによって、アイデアの質が変わってくるものです。マインドフルネスの効果により、常識・慣習・不安など、新規事業の発案や商品開発において弊害となるネガティブな要素にとらわれなくなることは、革新的なプロダクトを創出する手助けになるはずです。
マインドフルネスによる受容能力の向上は、新たなサービスや価値を生み出し続けなければならないビジネスの命題に対しても効果を発揮してくれることでしょう。
自分の内面を見つめ、理解を深めることができる
一人の人間として、自己理解を深めるための手段としてもマインドフルネスは有効です。自身の思考や身体感覚を客観的に観察するため、「今の感情」「欲求は何か」「長所や短所」「不満」「喜び」など、あらゆる自身に関することを見つめることができるからです。
マインドフルネスによって内面を見つめる力を高め、自己理解を深めることにより、自身の感情をコントロールできるようになると言われています。仕事上でトラブルが起きた際、ネガティブな感情は必ず湧き上がってくるものですが、マインドフルネスの瞑想を行っている社員は感情に行動が支配されることが減るでしょう。自身を客観視する内省が自然にできるため、感情にとらわれにくいからです。どのようなトラブルに見舞われても冷静に対応し、常に合理的な判断を持って次のアクションに移せることも強みになります。
ビジネスにおいて、感情のコントロールは非常に難しい部分があります。顧客と共に喜び合う背景には、喜怒哀楽のさまざまな感情が自身を突き動かしたのも事実です。しかしながら感情によって起こる行動原理に注目すると、必ずしも感情の浮き沈みがプラスに作用するとは考えにくい部分もあります。喜怒哀楽は人生の不可欠なものと言われますが、ことビジネスにおいては、感情に支配されないことこそ、成功の第一歩です。
日常生活における幸福感が増す
瞑想によって、自分自身や人生をありのままに見つめるようになった時、つまらない名誉や承認にとらわれたり、同僚との行き違いで感情を動かしたり、業務の本質とは関係ない人間関係に、心を煩わされることが少なくなってきます。今までの客観的な環境が変わっていないのにも関わらず、どうでもいいことから、心を反らし、本当に取り組まなければならないことに集中することによって、手段と目的が明確になり、より効率的な動きを職場で取れるようになります。
瞑想によって、できるだけ本質を見ようとする訓練をすれば、日常生活で、自分が本当に必要な事はそれほど多くないということにも気づかされるでしょう。
私たちの職場や人生における失敗は、本来ならしなくてもよいことに、首を突っ込んだあげく痛い目を見るという場合が大半です。今やらねばならないことに集中すること、どうでもいいことは無視すること、この2つを守るだけで当、その社員の物腰や言葉は軽やかになり成果は自然にあらわれるようになります。欲求も少なくなってくるため、「吾唯知足(われただたるをしる)」を体現するようになり、周囲への感謝の気持ちも出てくるようになります。
マネジメント力が上がる
マインドが整うと、怒りや焦りが生まれにくくなり、不必要に振り回されることがなくなります。周囲に共感する余裕が出てきて、相手を思いやる発言や行動をとれるようになるでしょう。人間関係を良好に築けるようになり、部下がいるような立場の場合は、マネジメント力がアップします。その結果、人から頼られやすい存在になることができます。
ストレス耐性が上がる
マインドフルネスを実践すると、リラックスできるだけでなく、扁桃体(へんとうたい)が小さくなると言われています。扁桃体は不安や恐怖に反応する部位なので、これが小さくなると、自分を失わずに冷静に物事に向き合えるようになります。これにより、ストレス耐性がアップし、トラブルなどの不測の事態の際にも落ち着いて対応できるなど、行動に変化が見られるでしょう。
コミュニケーション力が上がる
マインドフルネスを行うことにより、脳の働きが活性化することも期待できます。短期的な記憶と、瞬発的な情報処理のスキルが向上し、相手の話をしっかり覚えた上で、その時々に適切なリアクションをとることができるようになるでしょう。コミュニケーション能力が高まり、周囲と良好な関係を築けるようになると期待できます。マインドフルネスを行うことによって、関わる人たちにいい影響を与えられる存在となるでしょう。
リーダーに求められるマインドフルネスとコミュニケーション
マインドフルネスは、リーダーにこそ必要なものだと言えます。リーダーは、チームを動かす力はもちろんですが、チームとしてのパフォーマンスをいかに向上させ、キープしていけるか力量が問われます。周囲との関わり、つまりコミュニケーションのスキルを磨くことで、リーダーはリーダーシップを発揮していけるものです。
個々のメンバーとコミュニケーションをとり、それぞれに最適な方法を柔軟に選ぶことができれば、チームは理想的な形で運営されていきます。互いに向き合い、どう対話を重ねてどのような意思決定をするか、議論やスピーチをいかに進めるか、余裕のある心で判断していくことが必要です。そのために、マインドフルネスが役に立ちます。
マインドフルネスのやり方
ここまで、マインドフルネスの背景や効果について解説してきました。続いて、マインドフルネスの具体的なやり方について解説していきます。ここでは、「呼吸を意識した瞑想」と「ボディスキャンによる瞑想」の2つの方法についてご紹介します。
呼吸を意識した瞑想
もっともポピュラーな瞑想法が、呼吸に意識を向ける瞑想です。シンプルであるがゆえ取り組みやすく、入門として適している手法です。以下の5つの手順で行うのが基本の形です。
- イスに座って姿勢を正す 仙骨と呼ばれる背骨の付け根にある骨を立て、背筋をしっかり伸ばして姿勢を正します。目を瞑ってやることが望ましいとされています。
- 深呼吸を大きく5回行う 深呼吸によって呼吸に意識を向け、集中するための準備をします。その時、「吸った」、「吐いた」と呼吸にラベリングをしていくことが初心者の助けになります。呼吸にラベリングがないと意識が雑念に流されることになります。
- 呼吸を継続 深呼吸の流れで通常の呼吸を継続し、そのまま呼吸に意識を集中させましょう
- 雑念が生じたら呼吸に意識を集中 雑念(自然に湧き上がった感情・イメージ)をそのままに、呼吸に意識を戻します。もしできるならこの時、眉間にも意識を集中させましょう。それが無理であれば、呼吸のみでも構いません。
- 意識を自己に戻す 呼吸に意識を集中させることで雑念をやり過ごしたら、そのまま呼吸を通して自己に意識を向け続けます
呼吸を意識した瞑想のポイントは、必ず雑念は生じるものだと理解しておくことです。人によって雑念の量や質は異なりますが、最初から「無」の状態の人は存在しません。雑念は少なければ少ないほど良いということは言うまでもありませんが、雑念は観察の対象となるため、無理やりなくそうとしなくても問題ありません。
また、呼吸を意識した瞑想でもっともトレーニングになる部分は、雑念から呼吸に意識を戻すその瞬間です。そのため、雑念を邪魔者として扱うのではなく、マインドフルネスの力を身に付けさせてくれるパートナーのように考えておくと良いでしょう。しかし、雑念は最終的には捨て置くことができるものです。初心者としては、雑念は途中では道案内しているくれるガイドのような形で考えておけばよいでしょう。いつまでの雑念にとらわれているようであればマインドフルネスの効果も半減してしまいます。
ボディスキャンによる瞑想
呼吸を意識した瞑想の次に定番なのが、身体の状態を観察する手法、ボディスキャンによる瞑想です。身体の感覚を活用した瞑想法で、スキャナーでチェックするように身体に意識を向けます。以下の4つの手順で行います。
- ボディスキャンを行う体勢になる
立った状態、座った状態どちらでも、ボディスキャンを行いやすい体勢になります - 意識によって身体をスキャンする
軽く目を閉じ、身体の感覚を頭から足先に向かってゆっくりとチェックします - 身体の部位に意識を向ける
足先・足の裏・ふくらはぎなど、頭から足先の各部位にスポットを当て、細かく身体の状態を確認していきます - 痛みや不快な情報に対処する
緊張などの不快な情報を確認したら、不快な感覚を息と一緒に吐き出すイメージで呼吸を行います
ボディスキャンによる瞑想は、診察しているドクターのような気持ちで臨むと良いでしょう。身体の隅々まで意識のスキャナーでチェックし、かゆみ・痛み・違和感など、身体に起きている感覚について観察します。
また、いきなり全身を観察するよりも、呼吸への集中から入ると取り組みやすくなります。鼻から出入りする空気の感覚や、呼吸をした時のお腹や胸の膨らみや、へこむ感覚に意識を向け、身体感覚に意識を向けるための準備を行うと良いでしょう。
マインドフルネスを導入している企業例
ここでは、マインドフルネスを実際に導入している企業例を見ていきましょう。その中でも、とくに世界のマインドフルネスブームの火付け役となった企業についてご紹介します。
グーグル(Google LLC)
世界最大のインターネット検索エンジンで世界を牽引するIT企業グーグルは、ビジネスにおけるマインドフルネスの火付け役となった筆頭の企業です。
グーグルのマインドフルネスの出発点は、社内エンジニアだったチャディー・メン・タン氏が集中力の向上やストレス軽減を目的に導入し、1日30分間の自主参加という形でスタートしました。その後、効果が評判となって社内に広がり、一部の社員の間で行われることになります。
さらにグーグルは、2007年から「Search inside Yourself(SIY)」と命名された、能力開発を目的とするマインドフルネス瞑想を実践する研修プログラムをスタートさせます。この研修プログラムでは、1日数分~1時間程度の瞑想を7週間行い、瞑想の効果として、ストレス軽減・自己制御力の向上・生産性の向上などが報告されています。
グーグルの最新の脳科学をベースとしたマインドフルネスの方法論は世界中の企業から注目を集めています。
ゴールドマン・サックス(The Goldman Sachs Group, Inc.)
金融サービスを世界中の企業・金融機関・政府機関に提供している大手金融系企業ゴールドマンサックスも、社員への健康プログラムの一貫として積極的にマインドフルネスを導入している企業です。
ゴールドマン・サックスが注目したのは、人間の回復力(レジリエンス)です。個々の社員の自己管理とセルフケアを行う能力を高めるための手段の1つとして、マインドフルネスが活用されています。
実際、マインドフルネスを取り入れてから2014年には、フォーチュン誌の「もっとも働きがいのある企業」において、前年の90位から45位へランキングを上げています。さらに、マインドフルネスの取り組みについて同雑誌で特集されたため、世界から注目されるようになりました。
また、ゴールドマン・サックスでは福利厚生の1つとして、「瞑想アプリ」の利用を推奨しています。全社を上げてマインドフルネスに取り組む、世界でも数少ない企業です。
アップル(Apple Inc.)
デジタル端末やソフトウェアの開発を手がける大手IT企業のアップルも、マインドフルネスを取り入れていることが知られています。現在アップルの社内には瞑想ルームがあり、瞑想をはじめヨガの講習会を実施するなど、セルフケアに積極的に取り組んでいます。また、ジョブズ氏自身もマインドフルネスを行っており、重要なプレゼンの前には気持ちを集中させるため必ず行っていたと言われています。とくに創造性の向上という観点で、技術者を中心にマインドフルネスが推奨されている企業です。
まとめ
マインドフルネスの実践は誰でもすぐに始められ、効果を感じることができるものです。瞑想によって自己の心の中や身体の感覚に注目し、自動的に出てくる思考やイメージをやり過ごすことで脳がクリアになり、副次的にさまざまな効果を得ることができます。
ビジネスにおいてはとくに、「集中力の向上」「創造性の向上」「自己理解を深める」の3つの効果により、個々の社員のパフォーマンス向上が期待できるでしょう。社員のパフォーマンスの向上は企業全体の生産性にもつながるため、マインドフルネスがビジネスにおいて世界的に注目されている理由がここにあります。
マインドフルネスの瞑想は少しの時間から実践できますので、仕事の前や間に取り入れてみることを推奨します。
日本企業ではとくに、瞑想やヨガというと、美容や宗教と結び付けられ語られますが、ここに日本の精神性の貧困を見ることできます。社内に瞑想ルームがあったり、ヨガルームがあったりすることはビジネス生産性をあげる上でも、効果的なのだという意識改革が必要ではないでしょうか。