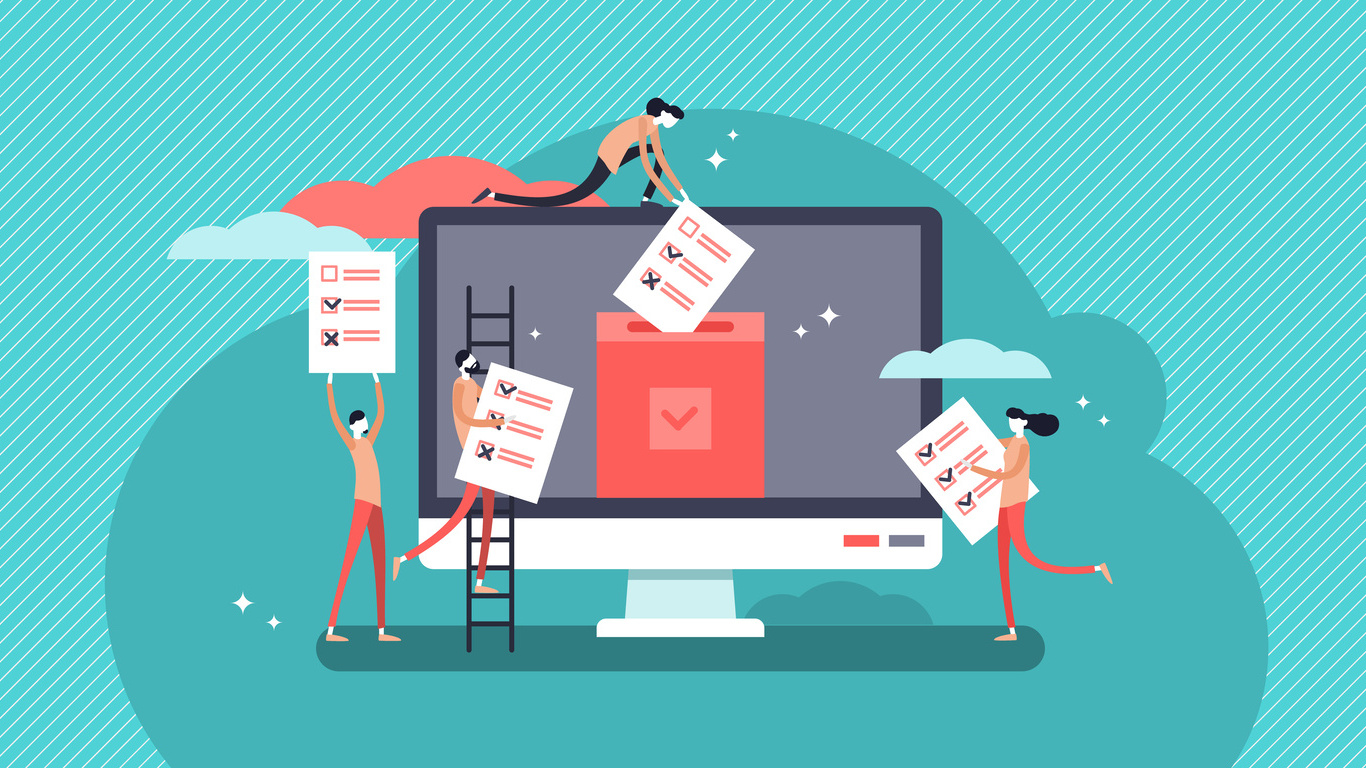コミュニケーション不足が組織に与える影響とは?原因や具体的な解決策を紹介
最終更新日:2024.03.25

目次
組織におけるコミュニケーション不足は、業務の円滑な進行やチームの一体感に深刻な影響を及ぼす要因となります。新型コロナウイルスの影響で増加しているリモートワークなど、働き方の変化によってコミュニケーションの重要性が一段と際立っています。
本記事では、コミュニケーション不足が引き起こす具体的な影響やその原因に焦点を当て、効果的な解決策を紹介します。
コミュニケーション不足が組織に与える影響とは
コミュニケーション不足は、組織にさまざまなマイナスの事象を引き起こすものです。具体的にどのような影響が出るのか、細分化しながら見ていきます。
ミスやトラブルが起こりやすくなる
コミュニケーション不足は、業務におけるミスやトラブルを誘発します。コミュニケーションが足りないと、必要な情報が正確に伝達されにくいため、思わぬかたちで齟齬が発生してしまいます。また、何か迷ったことがあっても質問や確認がしずらく、気をつければ防げるレベルのトラブルが多発してしまいます。
コミュニケーションにおいて誤解やトラブルの発生を避けては通れず、完全になくすことは事実上不可能です。従って、ミスやトラブルに対処する仕方や姿勢が重要なのです。小さなミスや誤解をそのままにしておけば、疑いや不信に変化し大きな問題となるでしょう。
職場内の人間関係と信頼関係が悪化する
人間関係に大きな影響を与えるのも、コミュニケーションの特徴です。普段から良質でオープンな関わり合いをしている場合は社員同士に一体感が生まれ、ヒリヒリとした議論もあったとしても、助け合えるような関係が生まれます。しかしコミュニケーションが足りていないと、信頼関係を損なう原因となり、すぐに他人を責め、陰口を叩くなど、組織内に派閥ができてしまうケースもあります。派閥のような組織内の非公式グループの成り立ちは、他の非公式グループや体制に反発して派生することが多いため、敵がいるからグループになるという「分派」の原理にあたります。逆に言えば、敵がいなければ存在しません。この社会において、分派や分断はどこにでも存在します。
「人間関係がうまくいかない」というよくある小さな事象から、敵と味方に分派し大きな影響力を与えるといった流れはどこの世界にもあるのです。「人間関係がうまくいかない」という状況を軽視しそのままにしておくと、後で問題解決に多大な労力が必要となるかもしれません。
連携不足により業務の質が低下する
コミュニケーションが足りないと、社員同士で業務上の連携がうまくとれなくなります。複数名で進めていく案件の場合は、業務そのものの遂行が危ぶまれる可能性もあります。円滑に進めることが難しく、業務全体の質が下がってしまいます。また、社員同士の関わりが希薄だと、健全な意見交換がなされず、ノウハウがシェアされないという弊害も生じます。イノベーションが起きにく、ビジネスが弱体化していく懸念もあります。
部門間連携における問題解決の場合は、組織の構造改革や、部門の統廃合という形式でしか解決できないのが現実です。原因として、部門間の短期的な利害の不一致や合意形成の失敗から、部門同士、組織内の政治的な影響力から闘争に発展してしまうためです。ここまでくると、最終的な手段は構造改革しかないでしょう。
部門を統廃合する際、部門間の軋轢を避けるためには、事業部門の責任者クラスが合意形成能力や議論力を高めることが重要です。部門長同士が定期的にコミュニケーションをとり、合意形成を図ることで、統廃合をスムーズに進めることが可能となります。そうすることで、中間管理職が膨大な労力をかけて調整する必要がなくなり、合意が得られれば、迅速に取り組むことができます。
顧客からの信頼を失う
コミュニケーション不足は、社内だけの問題ではありません。当然、顧客にも影響を与えてしまうことが考えられます。たとえば、認識の食い違いが積み重なり、納期が大きく遅れてしまう可能性もあります。また、社内の認識レベルが揃っていないと、担当者が多くいたとしても問い合わせに対応できる人は決まった人だけという状況に陥ってしまう場合もあり、顧客からの不信感を抱かれてしまうかもしれません。一つの部署が起こしたミスが原因となり、企業全体のイメージを損ねるケースも往々にしてあるので、コミュニケーション不足を感じたら早急に手を打つことが重要です。
事例として、セールスパーソンが提案したサービスに対し、顧客が契約を決めた合意事項と、実際に提供されたサービスにズレが生じ、顧客が期待していたものと違っていたということがよくあります。このズレは、顧客がサービスを購入し、受け入れ、恩恵を受けるまでの一連のプロセスで顕著にあらわれます。サービス提供者側は通常、複数の部門や担当者で構成されており、最近では人間だけでなく機械やデジタル技術も関与しています。したがって、顧客がサービスに参加するためのエンゲージメントは、サービス提供者側の連携にが重要なポイントです。この連携を支えるのが、各部門や担当者間での円滑なコミュニケーションなのです。
顧客エンゲージメントと従業員エンゲージメントの相関性は、ビジネス環境の変化やテクノロジーの進化により、常に変化しています。従業員のモチベーションや満足度が高ければ、彼らの顧客対応はより積極的になり、顧客エンゲージメントの向上につながります。逆に、従業員のエンゲージメントが低い場合、サービス品質や顧客対応が悪化し、顧客エンゲージメントに悪影響を及ぼす可能性があります。
従業員エンゲージメントの過程は、社内コミュニケーションが非常に重要な役割を果たしています。従業員が組織のビジョンや目標を理解し、自身の役割や貢献が不可欠であることを認識するためには、上司や同僚との定期的なコミュニケーションが欠かせません。また、フィードバックの提供やアイデアの共有など、オープンで透明性の高いコミュニケーションは従業員のエンゲージメントを高めるのに効果的です。そこで、組織内のコミュニケーションチャネルやツールの整備、定期的な会議やチームビルディングイベントの開催などが重要となります。
離職率の増加につながる
モチベーションの低下、ストレスの増加にも、コミュニケーションは深く関わっています。コミュニケーションが足りない場合、実際の業務や人間関係に支障をきたし、社員にとって働きにくい環境が完成してしまいます。こうなると、離職率が増えていく可能性があります。
社員が内向的になる
社員の業務への姿勢を左右することもあります。コミュニケーション不足が慢性化している職場では、社員が内向的になる傾向にあるのです。本来なら他人に気軽にアドバイスを求めて進める仕事でも、コミュニケーションをとる習慣がなかったり、意図的に避けたくなってしまったりすれば、自分で抱え込んでしまうほかありません。仕事に取り組む姿勢が後ろ向きになったり、周囲と協力すべきところで手を組めなかったりという弊害につながります。
不正行為の発生
社内でコミュニケーションが行われないと、社内の雰囲気が悪化し、不正行為が生じる可能性すらあります。コミュニケーションが希薄ということは、お互いの状況に無関心ということです。本来なら組織は、社員同士が多かれ少なかれ監視し合っていることで、平和に運営されていきます。しかし、誰にも監視されていない状態になると、勤務態度が怠慢になったり、不正行為に手を出したりする人が出てきます。
社内でコミュニケーションが不足する原因
そもそもなぜ社内コミュニケーションが不足してしまうのでしょうか。組織によって、人や環境、事業内容などの流動性が高い場合と、低い場合があります。流動性が高い場合は、人や環境が変化しやすく、社内で共有できるコンテキストが低下します。コンテクストがないと、自然とコミュニケーションがなくなっていきます。一方でコミュニケーションが増えると、コンテクストも増加し、コミュニケーションが活発になっていくというサイクルができます。ここでは、環境面と組織の質をもとに原因を考えていきます。
コミュニケーションがローコンテクストで人財の流動性が低い
ローコンテクストかつ組織や人財の流動性が低いという場合、コミュニケーションの必要性も低くなる可能性があります。コンテクストが共有できていない状態では、従業員が前向きにコミュニケーションをとらなくなっても環境や人の流動がないので、コミュニケーションの必然性もないのです。
例えば、大企業グループのシェアードサービス会社や事務処理系の子会社などでは、組織内で業務が徹底的に分業されており、定時業務や定型業務が別々に行われています。そのため、従業員同士のコミュニケーションは必要ありません。また、従業員の雇用形態はパートタイム契約や時給契約が一般的です。
ある意味、このような組織は、機械化、デジタル化が急激に進んでいるため、中長期には人が介在することもなくコミュニケーションも無くなるでしょう。
コミュニケーションがローコンテクストで人財の流動性が高い
ローコンテクストかつ人財や組織の流動性が高い場合は、コミュニケーションそのものの不確実性が高まります。人や事業などの流動性が高い分、将来の状況や方針が不透明であるため、組織への安定感や信頼感が欠如してしまうのです。コミュニケーションの不足や社内派閥のようなものができれば、業績の悪化につながります。
プロフェッショナルファームやプロジェクト型のビジネスをしている組織を例に挙げてみましょう。こういった組織は、プロジェクトの総数が積みあがったうえで組織として体をなしており、組織的なレポートラインや指示命令もありながら、コミュニケーションや人間関係はプロジェクトに偏ってしています。
世界最大のヘッジファンドで、レイダリオ率いるブリッジウォーター・アソシエーツは、その投資実績でも有名ですが、独特な企業文化でも有名です。企業文化として「徹底的な透明性」を追求しており、徹底して真実や事実で議論します。相手の意見や主張を鵜吞みにせずに、批判的思考やクリティカルシンキングから反論を提示する議論やフィードバックを是としています。肩書やポジションをなど気にし、陰で批判する行為は、解雇にすらなり得ます。
上記のようなプロフェッショナルな組織集団は、離職率は基本的には高く、適応できない人は辞めていきますし、離職率が高いこと自体は問題とはしていません。
コミュニケーションがハイコンテクストで流動性が低い
ハイコンテクストかつ流動性が低いという状態は、阿吽の呼吸につながるケースがほとんどです。メンバー同士が信頼で結ばれていて、暗黙の了解が通じる仲になるのです。日本企業の多くがこのような特徴を持っています。
これは、以前の高度経済成長期、日本の大企業では強みだったと捉えられます。事業や貿易条件という外的要因が好調の中で、労働者は共通言語と共通業務が多く、「阿吽の呼吸」と「言わずもがな」という文化がコミュニケーションコストを下げ、教義や神話にすら変化した枠組みです。
一方で、情報が明示的でないため、新しいメンバーが参入した場合に戸惑う可能性があります。長年身を置いてきたからこそ通じ合っているのであって、外から来て暗黙の了解を理解するのは難しいでしょう。
コミュニケーションがハイコンテクストで人財と組織の流動性が高い
ハイコンテクストかつ流動性が高い場合、チームメンバーはお互いの期待や役割を積極的に理解し合うことで仕事が進みます。言葉以外のコミュニケーションも含めて活発になるので、たとえコミュニケーションが不足していても、チームにいるだけで前進感を感じることができます。ただし、このような環境でコミュニケーション不足が続くと、情報共有や理解の不一致が問題となり、将来的なトラブルにつながることも考えられるので要注意です。
組織内のコンテクスト、共通の経験や理解によって形成され、時間とともにローコンテクストからハイコンテクストへと変化していきます。人の入れ替わりが多い場合でも、新入社員を効果的に組織に溶け込ませ、共通の言語でコミュニケーションを取るためには、新入社員のコミュニケーション能力だけでなく、組織内でコミュニケーション能力の高い人材が必要です。
コミュニケーションを活性化することによるメリット
では、コミュニケーションをうまく活性化できると、組織はどのようなメリットを享受できるのでしょうか。以下では、主に期待できる変化を5つ紹介します。
離職率の低下による採用コストの削減
コミュニケーションが充実することで、人間関係や仕事へのストレスを軽減し、仲間同士の結束が深まります。気軽に悩みを相談できる環境が整い、社内で居場所を見つけ出すことができます。そのため、従業員の離職防止にもつながり、採用活動にかかるコストも削減でき、経営面でもプラスの影響をもたらすことでしょう。
新入社員の即戦力化
チームへの順応と新入社員の戦力化を促進するにも、コミュニケーションが欠かせません。新入社員が組織の文化や価値観を理解し、チームメンバーとの関係をコミュニケーションによって構築します。そのため、新入社員は自分の役割や責任を明確に把握し、業務に対する自信を早く築くことができます。また、チームメンバーとの良好な関係が築かれることで、連携が円滑になり、業務の効率化や成果の向上にもつながります。
従業員のエンゲージメント向上
コミュニケーションの活性化によって、組織やその活動をより深く理解することができ、エンゲージメントが高まります。また、従業員の信頼関係が深まり、次の段階に進むためのモチベーションとなります。コミュニケーションの活性化によって、即戦力化したメンバーの成果を適切に評価することで、エンゲージメントが向上し、働く喜びを感じるでしょう。
コミュニケーション不足の解決への具体策
コミュニケーション不足を解決するためには、具体的なアクションをとることが不可欠です。以下では、取り入れたい具体策を5つご紹介します。
➀1on1ミーティングを行う
まずは1on1ミーティングを行うのがおすすめです。上司やリーダーなどと1対1で話す場があると、本心を伝えられるものです。自分の気持ちを汲み取ってくれる組織であることがわかれば、コミュニケーションの頻度が上がり、自身の意思を伝えようという気になれます。
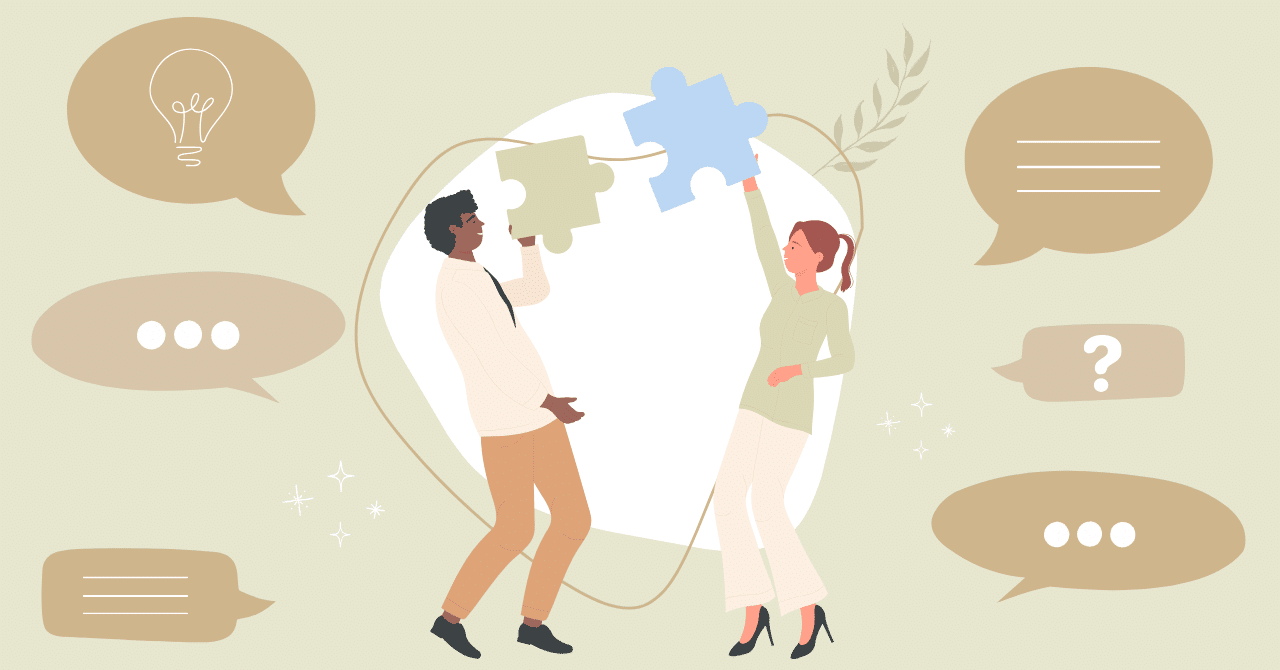
1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介
最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…
➁社内イベントの開催
社内イベントも、コミュニケーションの活性化に役立ちます。イベントでは、普段は関わらない部署の人や、上司、経営層などと話すことができます。業務外だからこそ、気軽にざっくばらんに会話できるのが大きなメリットです。イベントの場で顔見知りになるだけで、業務中に出会ったときに話しかけやすかったり、組織の居心地の良さが高まったりするものです。ワイワイ楽しく話しながら、新しい関係性をつくっていきましょう。
③コミュニケーションツールの導入
コミュニケーション不足の解決において、コミュニケーションツールの導入は効果的な手段の一つとなります。とくに、組織がリモートワークや分散勤務の形態を取っている場合、適切なツールを導入することでコミュニケーションの円滑な実現が期待できます。たとえば、社内チャットツールなどの導入、テレワーク中であっても円滑なコミュニケーションを促すことができます。できるだけ気軽に楽しく意思疎通ができるように、導入を検討してみましょう。
④オフィス環境を整備する
オフィスの環境面から整備し直すことで、コミュニケーションが活発化することも考えられます。たとえば、席を固定せずにフリーアドレス制度を取り入れ、自由に使える休憩スペースを設置するなど、環境によって何気ない会話を増やすことで、生き生きとした雰囲気ができあがっていくでしょう。
⑤シャッフルランチを行う
シャッフルランチとは、部署が異なる社員や経営陣など、普段はコミュニケーションをとる機会がない相手とランチをすることです。交流の機会を設けることで、新しいつながりが生まれ、相談しやすい環境ができるといった効果が期待できます。チームワークが高まり、組織に一体感が生まれるなど、働くモチベーションを高めていくこともできるでしょう。
まとめ
コミュニケーションが不足すると、組織に深刻な影響が出ることがあります。ミスやトラブルが起こりやすくなるほか、職場内の人間関係が悪くなったり、業務の質が低下したり、最悪の場合顧客からの信頼低下に直結するので要注意です。コミュニケーションを活性化するための取り組みを実践してひとつ先の組織を目指していきましょう。