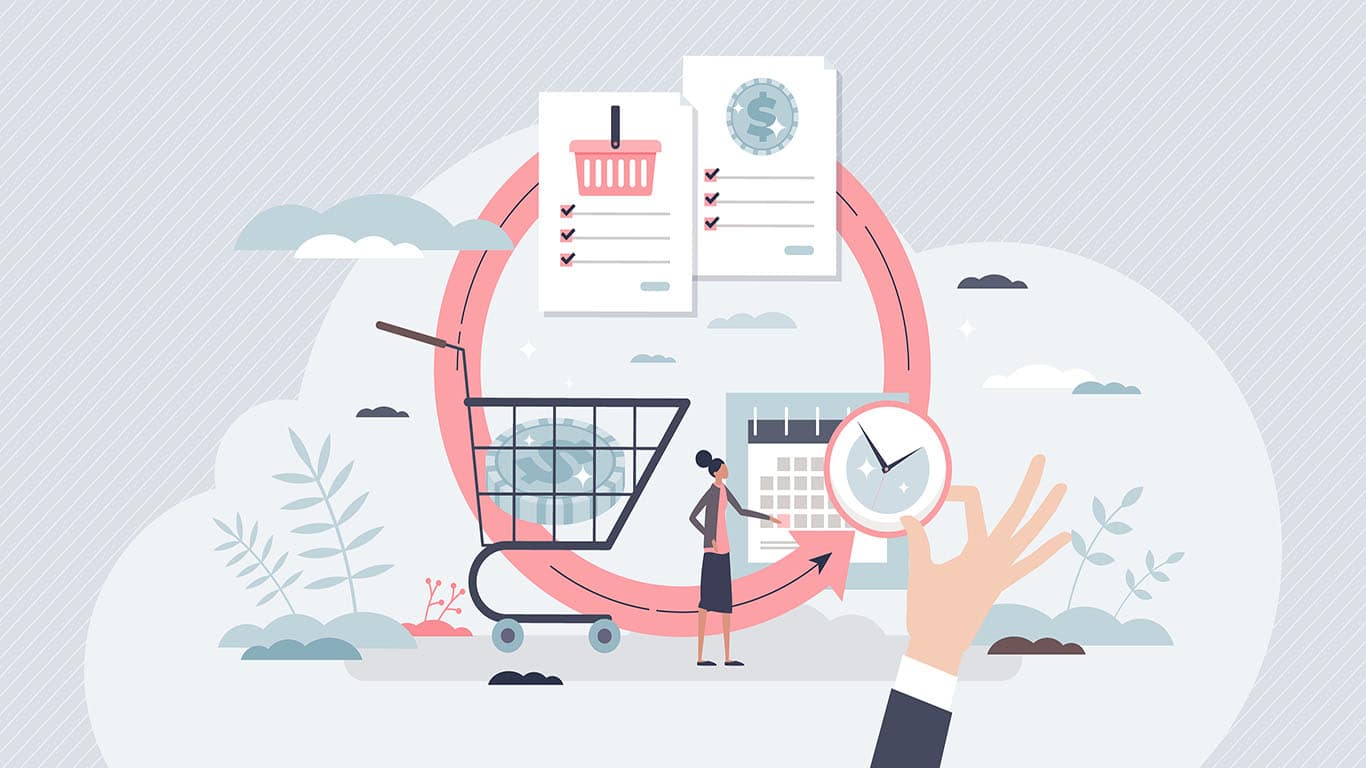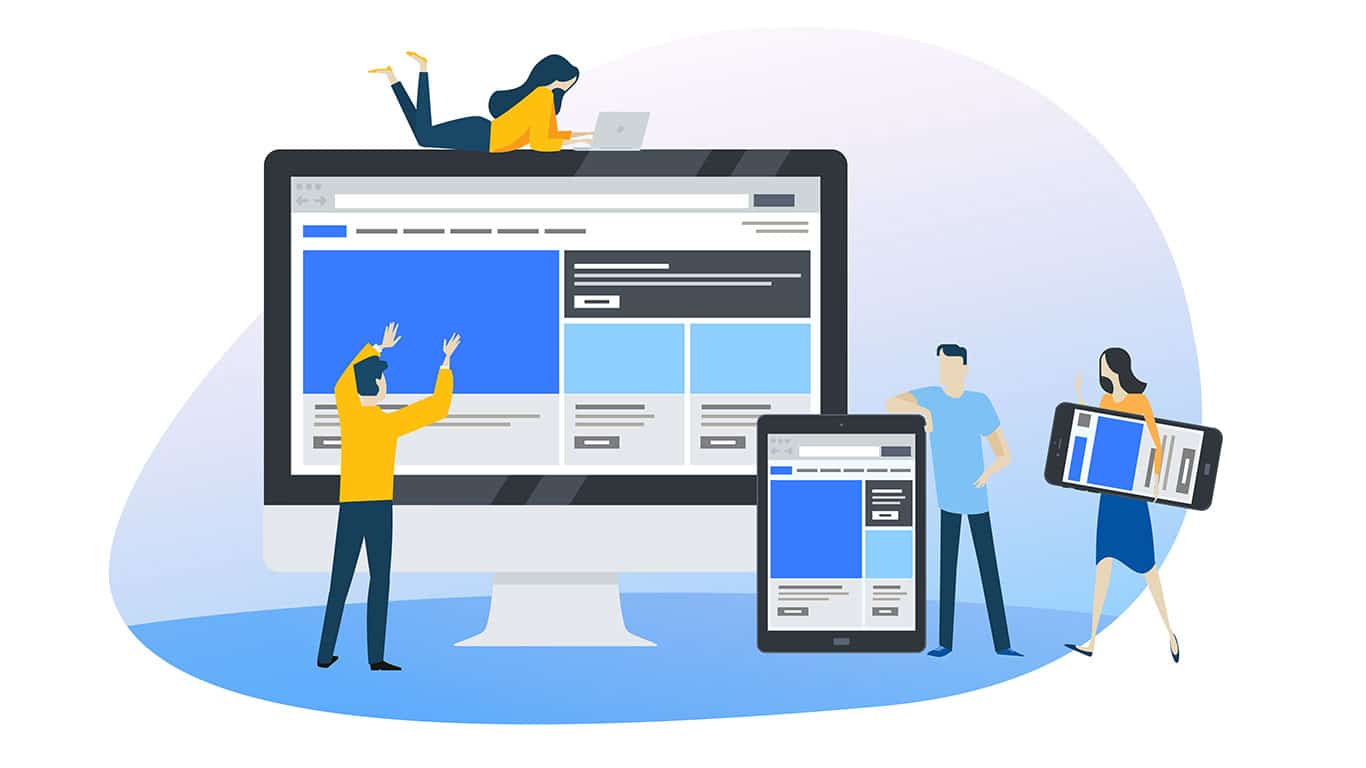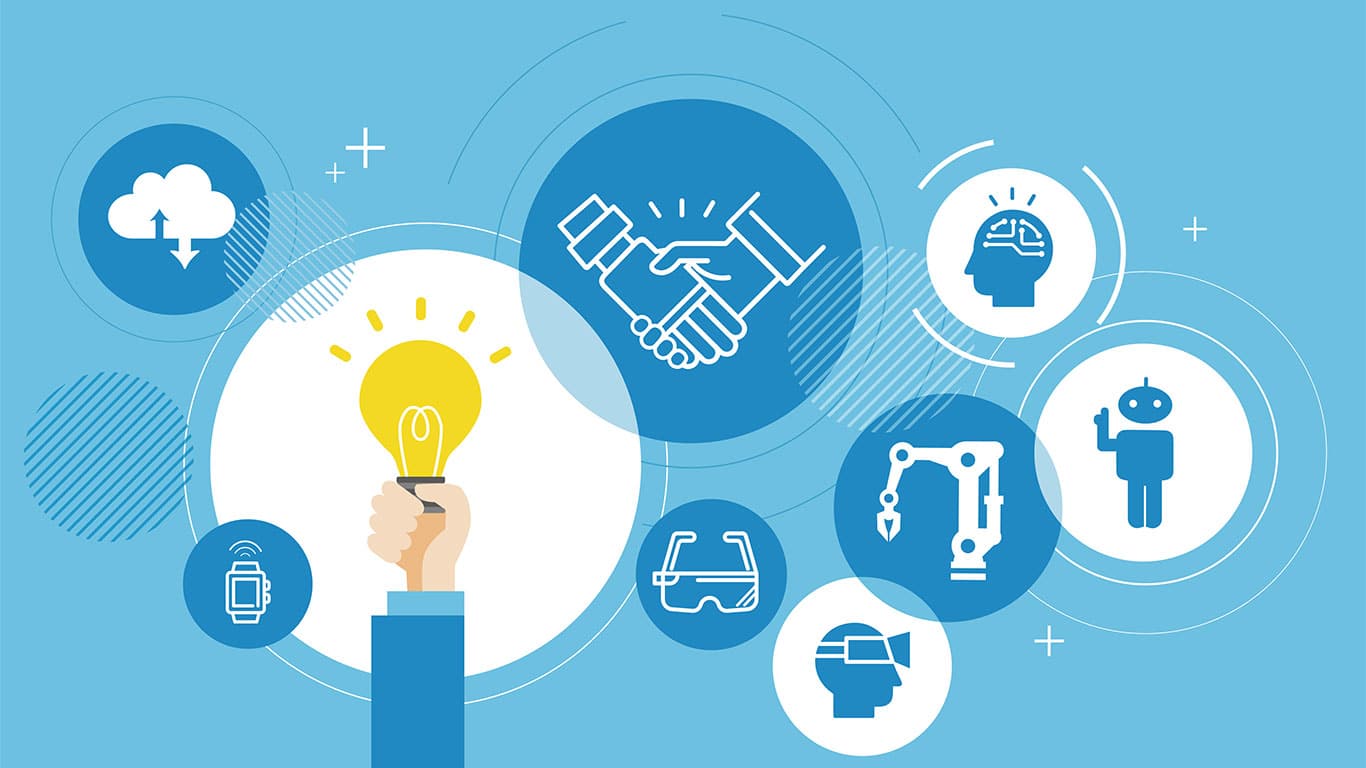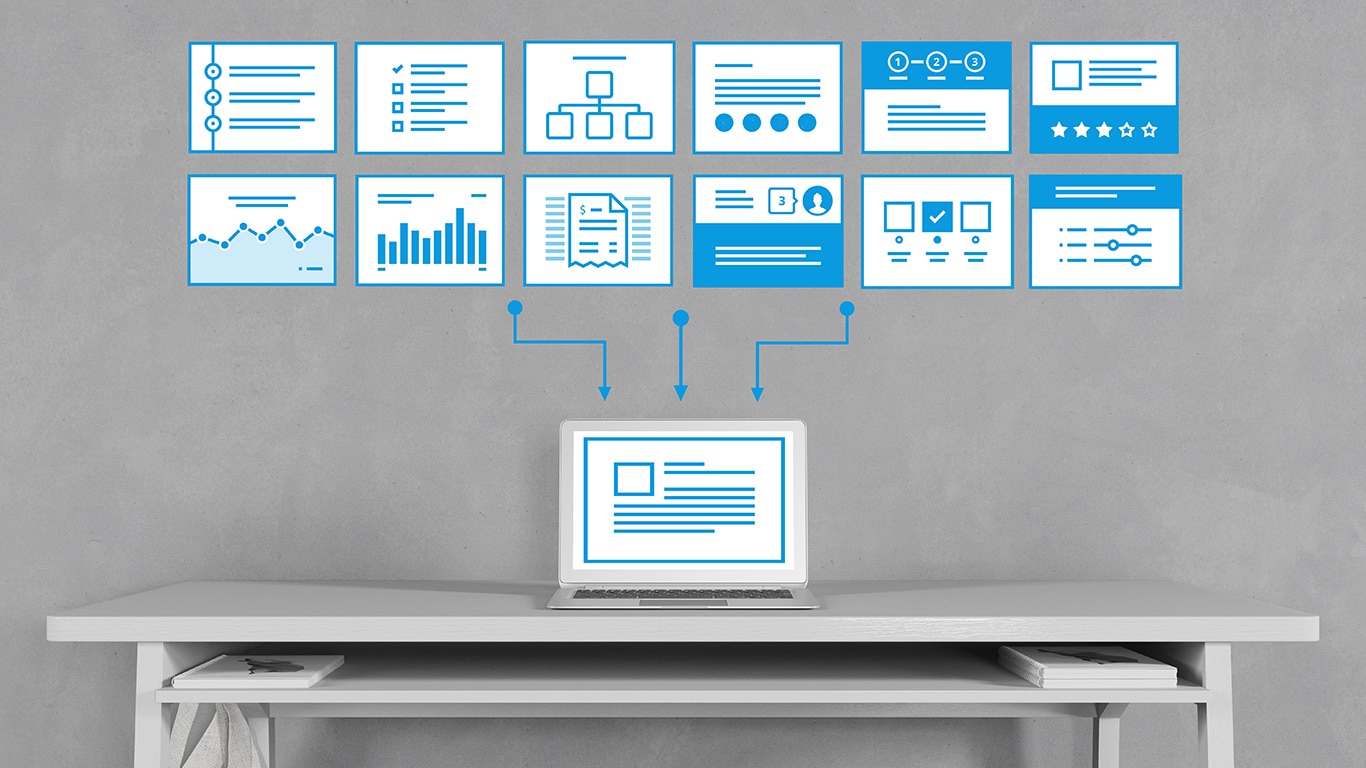職場の人間関係が悪化する原因とは?起こり得る問題と改善策を解説
最終更新日:2025.07.04

目次
職場の人間関係は組織の成果を左右する重要な要素です。人間関係が悪化すれば、社員のモチベーション低下やメンタル不調、生産性低下、さらには離職率の増加につながる恐れがあります。実際、厚生労働省の調査では「職場の人間関係が好ましくなかった」ことを離職理由に挙げた人が男性で9.1%、女性では13.0%にのぼっています。人事・組織開発の立場からも、人間関係の課題は見過ごせないテーマでしょう。本記事では、職場の人間関係が悪化する要因と、その悪化によって生じる問題、さらに人間関係を改善するための方法について解説します。
職場の人間関係に悩む人はどのくらいいるのか?
まず、どれほど多くの人が職場の人間関係に悩みを抱えているのでしょうか。
実は職場の人間関係にストレスを感じている人は少なくありません。
日本労働調査組合が行ったアンケート(2021年月)によると、「職場での人間関係に疲れ・悩み・ストレスを感じている」人は全体の29.2%にも上ることがわかっています。
さらに同調査(20〜49歳の会社員520名対象)では、職場の人間関係に悩んだ結果、退職を検討した経験がある人の割合は約6割に達しました。
半数以上の社員が人間関係を理由に離職を考えた経験があるというのは衝撃的です。
実際、厚生労働省「令和5年雇用動向調査」でも、男性の9.1%・女性の13.0%が「職場の人間関係が好ましくなかった」を離職理由に挙げており、特に女性においては個人的理由を除く離職理由の第1位となっています。
また連合(日本労働組合総連合会)の「コロナ禍における職業生活のストレスに関する調査2022」によれば「職場の人間関係」が30.9%で職業生活で感じるストレス要因の第1位となっており、第2位の「仕事の量」(22.8%)を大きく上回っています。
これらの数字からも、多くの社員が職場内の人間関係に悩みを抱えている現状が伺えます。
社員が職場の人間関係に悩めば、仕事への意欲低下や強いストレスにつながり、結果的に退職を真剣に検討する要因になります。
逆に言えば、社員が安心して働ける組織づくりや離職率の低減には、職場で良好な人間関係を築くことが不可欠です。
人間関係に悩む社員の割合と影響のポイント整理
職場の人間関係に悩む人は約3割
職場で人間関係にストレスを感じている社員は約30%にのぼります。
退職検討者は約6割
人間関係の悩みが原因で「退職を考えたことがある」人も約6割に達します。
人間関係は主要な離職理由
厚労省調査でも離職理由の上位に「職場の人間関係」が挙がっており、特に女性でその傾向が高い。
ストレス要因の筆頭
「職場の人間関係」は多くの働く人にとって最大のストレス要因であり、放置すればメンタル不調や離職につながり得る。
職場の人間関係の悩みやストレスが心身に及ぼす影響・症状
職場での人間関係は、その会社に勤めている限りほぼ毎日続いていくものです。
良好な関係を築けていれば問題ありませんが、もし人間関係がうまくいっていない状態が続くと、慢性的なストレスが溜まり、社員の心身に様々な悪影響を及ぼしてしまうでしょう。
ここでは、人間関係の悩みやストレスが社員の心身や行動にどのような影響・症状をもたらすかを解説します。
精神的影響
まず懸念されるのはメンタル(精神面)への影響です。
人間関係に悩みを抱えながら毎日同じ職場で同じ人々と関わり続けること自体が、大きなストレスになります。
場合によっては、苦手な同僚や上司と顔を合わせるだけで強い恐怖感や焦燥感を感じるケースもあるでしょう。
日頃からストレスフルな人間関係に晒されていると、次第に「会社に行きたくない…」という気持ちが強くなり、仕事への意欲やモチベーションの維持が難しくなります。
深刻なのは、無理を重ねるうちにうつ病や適応障害などの精神疾患に陥る可能性があることです。
実際、厚生労働省の自殺統計などでも職場の対人関係の悩みがメンタル不調の要因の一つとして挙げられています(※)。
職場の人間関係による精神的ストレスは、放置すれば社員の心の健康を蝕み、最悪の場合は休職や退職にもつながりかねません。
(※参考:厚生労働省「令和5年版自殺対策白書」では、勤務問題を原因・動機とする自殺において「職場の人間関係」が主要な要因の一つとして挙げられており、特に20歳代では「職場の人間関係」が15.8%を占めています。)
肉体的影響
人間関係のストレスは身体にも影響を及ぼします。
強いストレスを感じると自律神経やホルモンバランスが乱れ、様々な身体症状が現れることがあります。
たとえば、動悸が激しくなる、緊張で頭痛や腹痛が起こる、めまいがする、といった症状が考えられます。
また、明らかな症状として現れなくても、慢性的な疲労感や倦怠感が続いたり、「なんとなく体調が優れない」状態が長引いたりすることもあります。
仕事で受けるストレスには様々な要因がありますが、人間関係のストレスは特に慢性的・蓄積的になりやすい傾向があります。
その結果、睡眠の質が下がって疲労が回復しにくくなったり、食欲が落ちたりといった生活面への悪影響も生じがちです。
ストレスを感じる職場に勤務し続けること自体が健康リスクとなり、最終的に長期の体調不良や病気につながる可能性も否定できません。
行動面への影響
精神的・肉体的ストレスの蓄積は、やがて社員の行動にも表れてくることがあります。
たとえば、集中力が続かず仕事上のミスが増える、考えがまとまらず意思決定や作業のスピードが落ちる、といった変化が起こり得ます。
また、遅刻や早退、欠勤が増える場合もあるでしょう。
前夜から「明日会社に行きたくない」と思うと朝なかなか起きられず遅刻…といった悪循環に陥るケースもあります。
さらに顕著な例としては、身だしなみに無頓着になる(急に服装が乱れる等)とか、職場で極力周囲とコミュニケーションを取らなくなる(会話を避け引きこもる)といった行動の変化も見られるかもしれません。
いずれも、本人の内面で起きているストレスや意欲低下が外面的な態度や行動として表出したものです。
周囲から見ても「最近あの人の様子がおかしい」と分かるレベルで変化が現れることも多いため、同僚や上司はこうしたサインを見逃さず、声掛けやケアをすることが大切です。
人間関係ストレスによる主な症状のポイント整理
精神面憂鬱感・不安感の増大
職場への恐怖・嫌悪、モチベーション低下。長期化するとうつ病・適応障害などメンタル疾患のリスク。
身体面動悸、頭痛、腹痛、めまいなど
ストレス性の身体症状。慢性的疲労感、不眠など体調不良が続く。
行動面業務ミスの増加、判断力低下
遅刻・欠勤の増加、業務以外での交流回避、身だしなみの変化など行動の変容が見られる。
こうした兆候が現れたら、既に人間関係のストレスが限界に近いサインとも言えます。本人だけでなく周囲も変化に気づき、早めに対策を講じることが重要です。
コミュニケーションエラーとは?
コミュニケーションエラーとは、一言でいうと「コミュニケーションがうまく機能していない状態」のことです。職場でよくある例を挙げてみましょう。
たとえば、上司が部下に対して「資料を作成しておいて」と依頼したのに、期限になっても資料が完成していない状況を想像してください。
上司が部下に進捗を確認すると、部下は「分からない点があったため手が止まっていました」と報告しました。
このとき上司は「なぜ早く相談しなかったんだ!」と部下を叱責します。
一方の部下は「自力で解決しようと頑張っていたのに、叱られるなんて不本意だ」と感じ、不満に思うかもしれません。
また部下の側には「そもそも根本的な知識を上司が最初に教えてくれれば、こんな行き違いは起きなかったのではないか」という気持ちも芽生えるでしょう。
こうして双方の考えに食い違いが生じ、お互いに不満が残る事態となってしまいます。
もし仕事を依頼する段階できちんとコミュニケーションが取れていれば、上記のようなすれ違いは回避できた可能性が高いでしょう。
互いに「どのような姿勢で仕事に取り組むべきか」「分からない点はどう対処するか」などを事前に擦り合わせてから業務を始めるだけで、防げたトラブルだったと言えます。
しかし現実には、このようなコミュニケーション不足・誤解によるトラブル(=コミュニケーションエラー)が発生し、その結果人間関係が悪化してしまうことがあります。
一度トラブルを経験すると、その相手とは次第にコミュニケーションを取りづらくなり、ますます関係悪化に拍車がかかってしまう悪循環に陥りがちです。
コミュニケーションエラーが起きる要因
では、なぜコミュニケーションエラーが起きてしまうのでしょうか。
その原因として注目したいのが、職場の中で「可視化できない要素」への配慮が不足しがちだという点です。
業務プロセスにおいて、目に見える要素(業務手順や進捗、タスク分担、スケジュール等)は多くの現場で管理・共有されています。
一方で、目に見えない要素――たとえばメンバーのモチベーションや相互のコミュニケーションの質、職場の雰囲気や人間関係といった部分は、把握・改善が難しいため後回しにされがちです。
しかし、企業という組織は「功利に基づく契約的な関係」と「感情に基づく人間的関係」のバランスの上に成り立っています。
表向きの形式的なコミュニケーション(建前だけの会話)だけでこのバランスを保つことはできません。
ときには本音の感情や率直な意見を交換する腹を割った対話が必要になります。
こうした率直なコミュニケーションが不足すると、互いの意図が伝わらず誤解が生じ、コミュニケーションエラーにつながります。
また、現代の職場環境ならではの要因もあります。
たとえばリモートワークの普及により、顔を合わせて気軽に会話しにくい状況が増えたことで、それまで意識しなかった新たなコミュニケーション上の課題が生じています。
さらに最近の職場はプロジェクトごとにメンバーが入れ替わり、人間関係を一から構築し直す場面が増えています。
その都度、目に見えない要素まで含めてコミュニケーションを丁寧に図らなければ、小さな誤解や不満が積み重なり大きな摩擦へと発展しかねません。
要するに、形式的・表面的な情報伝達だけでは不十分であり、非公式なホンネの対話や念入りな意思疎通が欠かせないということです。
たとえば南山大学人間関係研究センターの調査・提言でも、「周囲からの支援(上司・同僚のサポート)」が職場ストレスを和らげる重要な要素とされています。
上司や同僚がこまめに声を掛け合い、業務状況だけでなく人の状況(感情やコンディション)についても確認し合う風土があれば、コミュニケーションエラーは格段に減らせるでしょう。
航空業界の例航空機の機長と副操縦士は、離陸前から着陸後まであらゆる手順を声に出して相互に確認し合う徹底したコミュニケーションを行っています。
これはミスを未然に防ぐためですが、この「確認作業」は職場のコミュニケーションにも応用可能です。
仕事上の確認を怠らないことはもちろん、お互いの認識にズレがないか、感情面でわだかまりがないかまで意識して声を掛け合うことで、後々の「こんなはずではなかった」という齟齬を防げます。
各職場でもこのような入念な確認・対話のプロセスを取り入れてみてはいかがでしょうか。
とはいえ、形式的に確認すればそれで十分というわけではありません。
仮に機長と副操縦士の人間関係が険悪であれば、いくら手順確認をしても相手の言葉を斜に構え受け取ってしまい、いざ緊急時に致命的なミスコミュニケーションが起こる可能性があります。
仕事上の状況確認だけでなく、共に働く人間の状況=人間関係にも目を配ることが重要なのです。
仕事と人間関係の問題が同時に起これば、大きな事故や組織崩壊のリスクにもつながりかねません。
各企業では、パイロット同様にメンバー同士の相性や印象をデータ収集し、出来るだけ相性の良いペア・チームを組む試みも行われています。
職場でも、できる範囲でチームの相性や人間関係のマッチングに配慮することで、コミュニケーションエラーを減らし円滑な協働を実現できます。
ポイント整理
コミュニケーションエラーの原因と対策
原因①可視化できない要素の軽視
士気や人間関係といった目に見えない部分がおろそかになると、誤解や不満が蓄積しやすい。
対策非公式な対話の場や本音を言える雰囲気をつくり、感情面も含めて擦り合わせる。上司・同僚がこまめに声掛け・相談する文化を育む。
原因②形式的な情報伝達だけ
対策念入りな確認と対話を習慣化する。
重要な依頼事項は双方で理解を確認し、「わかったつもり」をなくす(パイロットの声出し確認にならい、お互い復唱するなど)。
疑問や懸念があれば早めに相談・質問できる心理的安全性を確保する。
リモートワークや流動的なプロジェクト配属で、雑談や対面コミュニケーションが減少
対策定期的なオンラインミーティングや1on1面談を設け、情報共有だけでなく雑談やフィードバックの機会を増やす。
プロジェクト発足時にはキックオフミーティングで目的や役割をすり合わせる。
職場の人間関係が悪化することで起こる問題
コミュニケーションエラーの放置は、円滑な業務運営の大敵です。
社員が不必要なストレスを感じない職場を目指すには、見える部分(業務フローや制度)だけでなく、見えない人間関係や職場の雰囲気までケアすることが求められます。
現代の職場環境は、多様な人材・働き方・複雑な課題などの要因が重なりトラブルが起きやすい土壌にあります。
「人間関係が悪化しない方が不思議なくらい難しい環境」と言っても過言ではないでしょう。
前述のように、組織全体のコミュニケーションは多くの情報を多数の社員に届ける必要があるため、時間・空間的に分離された抽象的で演出的なスタイルになりがちです。
それに対し、現場の職場単位でのコミュニケーションは具体的でありのまま、時間的・空間的にも同期された環境で行われます。
つまり、組織レベルと職場レベルではコミュニケーションのスタイルが大きく異なり、双方にズレが生じやすい構造があります。
組織が大きくなるほどこのギャップは顕著になります。
どちらが良い悪いではなく、両者のバランス調整が必要です。
もしバランスが崩れれば、まずは現場の職場に問題が起こり、最終的には組織全体の問題へとつながってしまいます。
たとえば、現代の企業はSDGsへの対応など複雑で曖昧な課題を抱え、仕事の目標や意義が不明確になりがちです。
また働く人の価値観やバックグラウンドも多様化し、一人ひとりの役割認識の共有すら難しくなっています。
そのような環境下で、経済産業省の統計によると、日本のGDPの約7割がサービス業(=人の力が価値となる産業)で占められ、就業者数でも7割を占める時代です。
企業が成長するには、以前にも増して職場でのコミュニケーションや人間関係に注力し、丁寧にアプローチする必要があります。
もし人間関係の悪化を放置すると、次のような問題が起こり得ます。
チームワークの崩壊
協力や情報共有が滞り、業務効率が悪化します。コミュニケーション不足による連携ミスが増え、仕事の質も低下します。
組織活力の低下
社員同士の信頼関係が損なわれると、誰もチャレンジや提案をしなくなり組織のイノベーションが生まれにくくなります。
人材の流出
我慢の限界を迎えた社員から順に退職していきます。人間関係の悪さは離職理由の上位であり、優秀な人材も定着しません。
メンタルヘルス不調の増加
人間関係ストレスによる心身不調で休職者が増える恐れがあります。企業にとって人的損失が大きく、生産性の低下に直結します。
企業イメージの悪化
職場環境の悪さは社内だけでなく外部にも伝わり、採用や取引にもマイナス影響を及ぼしかねません(「○○社は社風がギスギスしている」等の評判)。
このように、人間関係の悪化は放置すれば組織全体の問題へ波及し、業績や存続にも関わる重大なリスクとなります。
逆に言えば、人間関係を良好に保つことが組織力向上の鍵だといえます。
近年、「心理的安全性(PsychologicalSafety)」という言葉が注目されていますが、これはまさに「チーム内で対人関係の不安なく率直に意見を言い合える状態」を意味します。
Googleのプロジェクト・アリストテレスの大規模研究でも、心理的安全性の高いチームは離職率が低く、収益性が高く、多様なアイデアの活用に長けているなど、明確に高業績を示すと報告されており、良好な人間関係づくりが企業の成功に不可欠であることは明らかです。
職場の人間関係は自分でつくっている?
人間関係が悪い職場にいると、「なぜ自分はこんな職場に…」と不平不満を感じてしまうかもしれません。
しかし、そもそも職場の人間関係とは一体誰が形作っているのでしょうか。
ここではスペインの哲学者ホセ・オルテガ・イ・ガセットの考え方を参考にしてみます。
彼は人間の存在について「人間とは、人とその周囲の環境である」と定義しました。
つまり、人間が環境をつくり、その環境にまた人間が影響されているということです。
人と環境(周囲)は切り離せない関係であり、どちらか一方だけを独立して考えるのは無理がある――オルテガはそう説きました。
オルテガの哲学では「大衆の反逆」という概念も有名です。
彼は「現代社会では個人は絶えず周囲との相互作用によって存在している」と捉え、エリート支配の昔とは異なる“大衆”の時代の特徴を論じました。
この観点から私たちの職場を見てみると、社員一人ひとりは単なるバラバラの個人ではなく、職場環境の中の社員として存在していると言えます。
つまり、職場の人間関係に不満がある場合でも、その悪い雰囲気を作っているのは、自分を含む職場を構成する一人ひとりの社員なのです。
もちろん自分だけが悪いと言う必要はありませんが、「周囲が悪い」「会社が悪い」と環境だけを嘆くのでは根本的な解決になりません。
だからこそ、もし職場の人間関係に不満や問題があるなら、その改善のために自らアクションを起こすべきかもしれません。
たとえば自分から挨拶や声掛けをしてみる、同僚とのコミュニケーション改善の提案をしてみる、といった些細なことでも構いません。
自分自身が人間関係改善のきっかけになれないか、前向きに検討してみることが大切です。
職場の人間関係は上司や特定の誰かだけが作っているのではありません。
「自分も職場の雰囲気を形づくる一員なのだ」という意識を社員一人ひとりが持ち、お互いに歩み寄ろうと努めることで、少しずつ関係性は良い方向へ変わっていくでしょう。
職場の人間関係を改善する方法
ここからは、職場の人間関係を改善する具体的な方法について解説します。
前述の通り、職場の人間関係や雰囲気は目に見えないものであり、アプローチが難しい側面があります。
そのため、可能であれば組織作りの初期段階から「職場の設計」にこだわっておくことが理想です。
職場環境の設計が悪いと、どんなに優秀な人材でチームを組んでも十分な成果が出ない場合がありますし、人間関係が悪化する要因にもなりかねません。
もし既に組織内の人間関係が悪化してしまっている場合、人事制度の改革や配置転換など思い切った手を打つのも一つの手段です。
特にリーダー(管理職)は職場に大きな影響を与える存在です。
場合によってはリーダーを交代させることで劇的に雰囲気が改善した例もあります。
いずれにせよ、組織として人間関係改善に取り組む際は、以下で述べるポイントに注意しながら改革を進めていく必要があります。
共通言語を作る
同じ組織で働いていても、社員一人ひとり価値観や考え方は異なるものです。
物事の捉え方やコミュニケーションのスタイルにも個人差があります。
当然、その違いから認識の食い違いが起こることもあり、食い違いが慢性化すれば互いに不満やわだかまりを抱えた関係性へと発展しかねません。
異なる価値観を持つ人同士が円滑に意思疎通するための有効な手段の一つが、組織内に「共通言語」を設けることです。
たとえば業界特有の専門用語や社内で通じる略語・用語を統一しておくこと、仕事の進め方に関する共通のフレームワークやルールを定めておくことなどが該当します。
共通言語を持つことで、コミュニケーションの際に毎回いちいち相手の意図や反応を深読みする必要が減り、心理的ハードルが下がります。
結果として、効率的に気持ちや情報を伝え合える関係になれるのです。
また、共通言語は社員同士の一体感や帰属意識を醸成する効果もあります。
社外の人には分からなくても内輪で通じる合言葉のようなものがあると、それを使いこなせる人同士に「自分たちは仲間だ」という連帯感が生まれます。
極端に言えば、共通言語は組織における会員証のような役割を果たし、共通言語を共有することでチームの団結力・忠誠心が高まる面もあります。
会社によっては経営理念やバリュー(価値観)を日常の合言葉として浸透させている例もあります。
たとえば「顧客第一」「チャレンジ」「心理的安全性」などキーワードを掲げ、会議や評価の場でそれを頻繁に使うようにすることで、組織内の共通の価値基準・言語として根付かせるのです。
こうした共通言語の整備により、コミュニケーション時の解釈ブレが減り、人間関係の衝突も和らげることが期待できます。
業務以外のつながりの場を作る
業務上の人間関係がぎくしゃくしている場合、一度仕事から離れて交流してみるのも効果的です。
勉強会や社内レクリエーション、懇親会など、業務とは切り離された場でコミュニケーションを取れる機会を設けてみましょう。
仕事から離れたリラックスできる環境であれば、普段の上下関係や役職の壁を忘れて打ち解けたコミュニケーションができるかもしれません。
一度フラットなつながりを体験しておくと、職場に戻ってからも構えずに話ができるきっかけになります。
「仕事と関係ないレクリエーションや飲み会なんて必要ない」という考え方もあるでしょう。
しかし企業には短期目標だけでなく長期的な目標もあります。
短期目標であれば業務上の円滑なやり取りだけでも間に合うかもしれませんが、長期的な大きな目標を追う場合、それだけ長い時間にわたって協働するため多様なコミュニケーション・チャンネルが不可欠になります。
目標が大きく長期になるほど、一見無駄に思える業務外での交流が実は重要な意味を持ってくるのです。
理想を言えば、レクリエーションや飲み会などを通じて社員同士で仕事以外のさまざまなコミュニケーション経路を築いておき、業務中は最低限の会話でもスムーズに仕事が進む状態にすることですが、仕事以外の場で濃密にコミュニケーションすることによって、仕事中はコミュニケーションに煩わされず業務そのものに集中できるというメリットがあります。
コミュニケーションは目的ではなく手段に過ぎません。
業務以外の交流の蓄積により、いざ仕事に向き合う際にはいちいちコミュニケーション調整にエネルギーを割かずともスムーズに協働できるのが理想なのです。
近年はコロナ禍の影響もあって大規模な社内イベントや飲み会の機会は減りましたが、その代わりにオンライン上で雑談できる仕組み(バーチャルランチや趣味交流のチャットグループ等)を導入する企業も増えています。
組織の長期的発展のためには、業務外のつながりも大事な投資と捉えてみてください。
コミュニケーションツールを取り入れる
職場の人間関係を一から構築し直したい場合、まずはコミュニケーションの頻度を上げることが大切です。
気軽に意思疎通できる環境さえ整えば、小さな誤解が減り、信頼関係も築きやすくなるでしょう。
コミュニケーションにおける心理的ハードルを下げるために、有効なのがコミュニケーションツール(ITツール)の活用です。
たとえばビジネスチャットや社内SNSなどを導入するとよいでしょう。
メールや電話とは違い、ちょっとしたことでもメッセージを送り合えるため、日常的なちょっとした会話や確認がしやすくなり、コミュニケーションの頻度が自然にアップします。
近年はSlackやMicrosoftTeamsといったチャットツールを社内コミュニケーションの主軸に据える企業も多いです。
チャットであればスタンプや絵文字でカジュアルに反応を示すこともでき、堅苦しいメール文化に比べ心理的負担が軽いのが利点です。
リモートワーク下でも雑談用のチャンネルを作っておけば、従来オフィスで交わされていたような何気ないコミュニケーションが生まれやすくなります。
こうしたツールをうまく利用して、「ちょっと聞いてみる・話しかけてみる」ハードルを下げることが、人間関係改善の第一歩です。
ただしツールはあくまで手段です。導入して終わりではなく、たとえば「ナレッジ共有のために業務ログをチャットに残す」「雑談OKの場を設ける」など運用ルールや文化づくりまでセットで考えましょう。
デジタルツールと対面コミュニケーションを補完的に使い、情報伝達ミスや仲間外れ感を生じさせない工夫が大切です。
コミュニケーションスキルを向上させる
最後に、社員一人ひとりのコミュニケーションスキル向上も人間関係悪化の防止において非常に重要です。
以下のようなスキルを組織的にトレーニングすることで、スムーズに人間関係を構築できる土壌ができます。
ディベート(討論)スキル–
さまざまな意見を引き出し、論点を深掘りする力。
お互いの主張を論理的に戦わせ、建設的に批判・検討することで、意思決定の幅を広げます。
ディベートで多様な意見を出し尽くしておくことで、後になって「こんなはずではなかった」という想定外を減らせます。
日本では失敗を忌避しがちですが、ディベート段階であえて反対意見やリスクを洗い出すことが重要です。
対話(ダイアログ)スキル–
相手の感情や価値観の違いを汲み取り、共感をベースに合意形成する力。
日本人は感情や価値観のぶつかり合いを避けがちですが、対話を通じてお互いの本音や気持ちを十分にすり合わせておくことで、いざ実務の段階でスムーズに協働できます。
表面上従っているようで腹の底では不満が渦巻いている状態(いわゆる「面従腹背」)では真の成果は出ません。対話で感情の行き違いを減らすことが大切です。
ディスカッション(討議)スキル–
複数人で合意形成し、結論を出す力。
ディベートで論点を出し尽くし、対話で相互理解が進んだ後は、建設的なディスカッションで合意形成に至る必要があります。
ディスカッションがうまくいっているかは、「話し合いの後に各人が行動に移れる状態になっているか」で判断できます。
もし会議後に誰も動かないのであれば、まだ論点や感情面で整理不足な部分が残っているということです。
ファシリテーションスキル–
議論を円滑に進め、合意形成を支援する力。
議論が平行線になったり結論が出ない場合、第三者的な立場で議論の方向性を示し妥協点を見出す役割が必要です。
これがファシリテーター(進行役)であり、近年は社内研修としてファシリテーションを学ぶ機会を設ける企業も増えています。
ファシリテーターは中立性が求められるため、場合によっては社外の専門家に委託することもあります。
いずれにせよ、適切なファシリテーションによってメンバー全員が納得し行動に移れる結論を導くことが、人間関係のしこりを残さないために重要です。
以上のようなコミュニケーションスキルは、一朝一夕で身につくものではありません。
しかし組織として研修機会を設けたり、日頃の会議で練習する場を持つことで、徐々に社員全体の底上げができます。
論理(ロジック)と感情(気持ち)の両面を整理して意思疎通できる組織は、誤解や衝突が起きにくく、生産性の高いチームへと近づくでしょう。
まとめ
職場の人間関係は、企業の業績を左右するほど重要なものです。
組織のリーダー層をはじめ、経営陣・人事担当者は、良好な人間関係を意識的に構築することで組織力を高めていきましょう。
職場の人間関係を良くするために重要なポイントは、以下の通りです。
原因の大半はコミュニケーション不足
人間関係悪化の多くはコミュニケーションエラーに起因します。
互いの仕事の進め方や姿勢の擦り合わせを事前に行うことで、多くのトラブルは防止可能です。
共通言語を作る
組織内で共通の用語や価値観を持つことで意思疎通のズレを減らし、社員同士の一体感を醸成します。
業務以外でつながる場を設ける
オン・オフ問わずコミュニケーションのチャンネルを増やし、社員同士の関係構築を促進します。
雑談やレクリエーションの場が長期的には大きな効果を発揮します。
コミュニケーションツールの活用
ビジネスチャット等により気軽に連絡・相談できる環境を整備し、日常的な意思疎通頻度を高めます。
社員の対話スキル向上
ディベートや対話、ファシリテーションなどの研修を通じて、組織全体のコミュニケーション能力を底上げします。
心理的安全性のある風通しの良い職場づくりにつながります。
人間関係改善の取り組みは一度やれば終わりではなく、継続的なケアが必要です。
近年ではファシリテーションや1on1ミーティングなど、新しいコミュニケーション施策を導入する企業も増えています。
ぜひ自社の状況に合わせて、以上の方法を取り入れ、生き生きと安心して働ける職場を創り上げていきましょう。
社員同士が信頼し合い本音で語り合える環境が整えば、組織全体のエンゲージメントが高まり、生産性向上や離職防止といった成果も自ずとついてくるはずです。