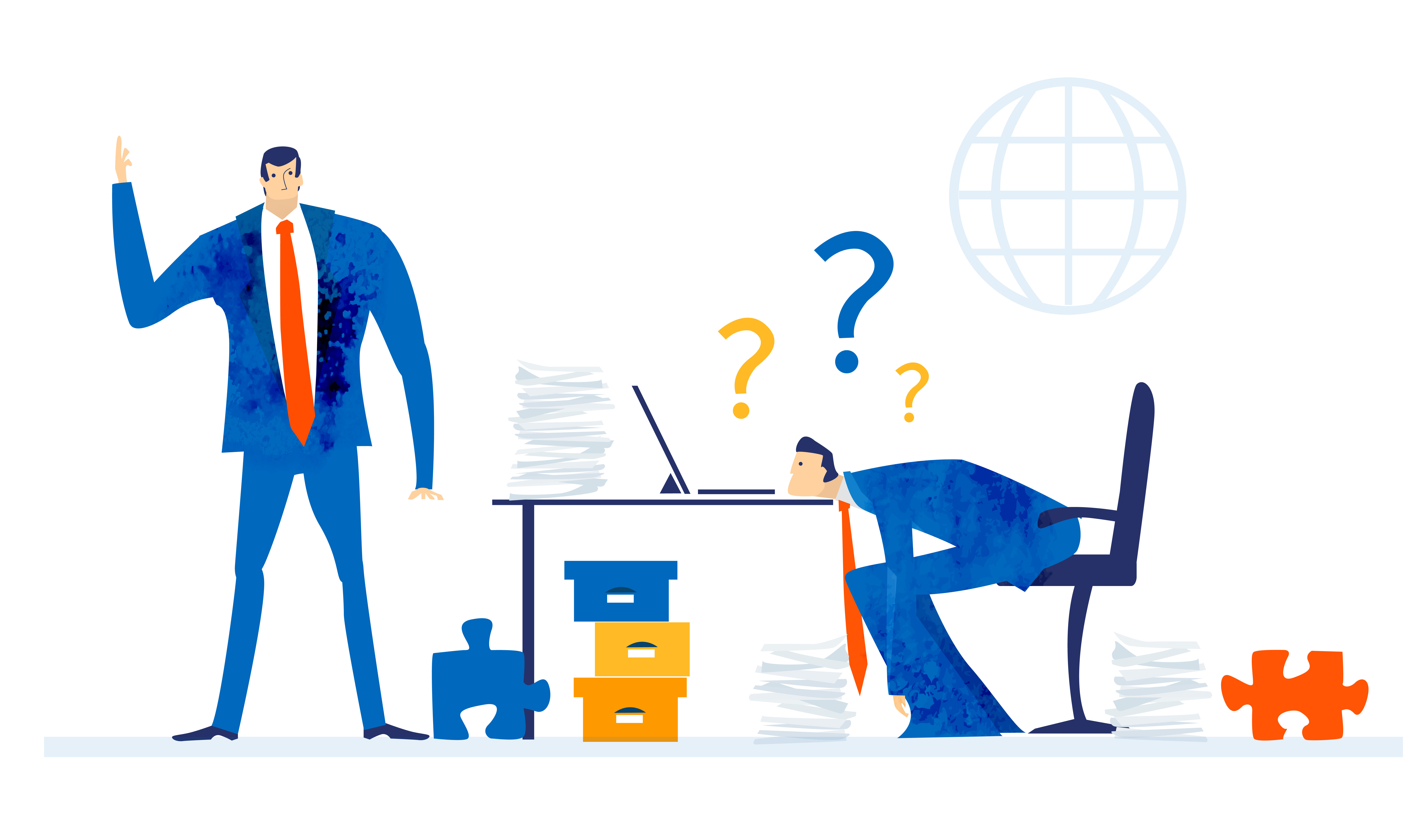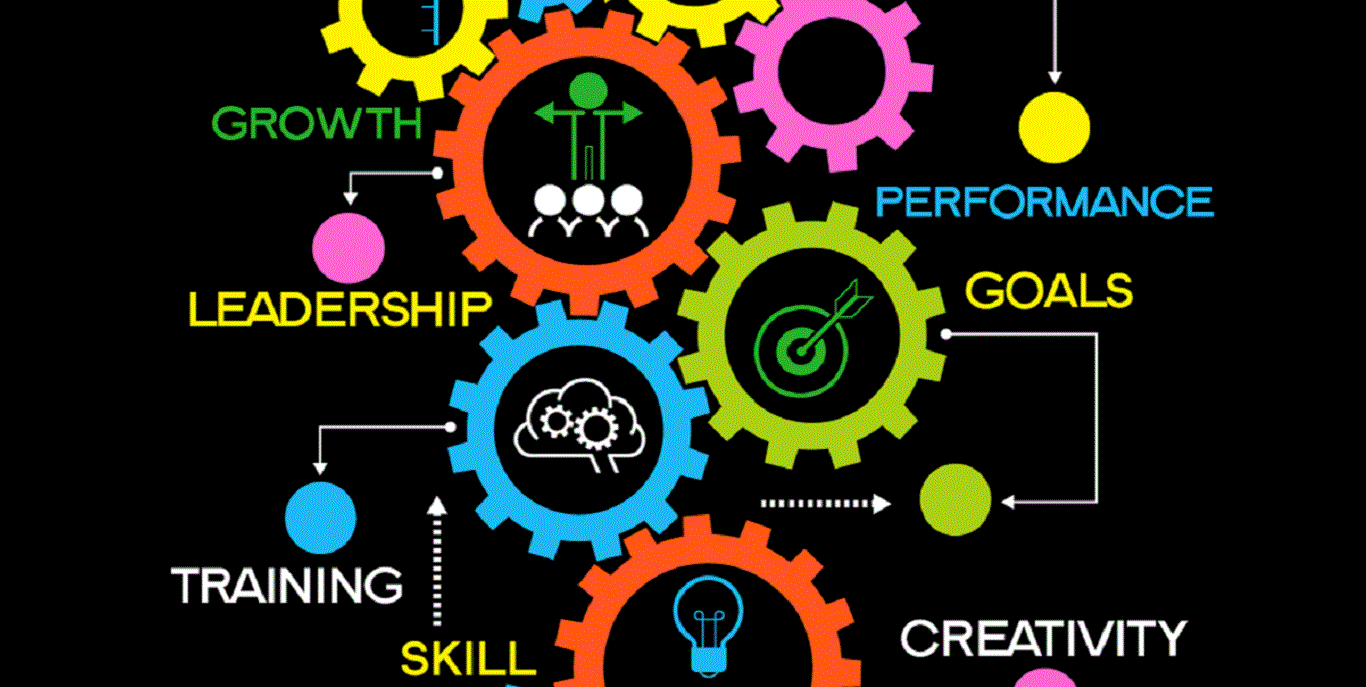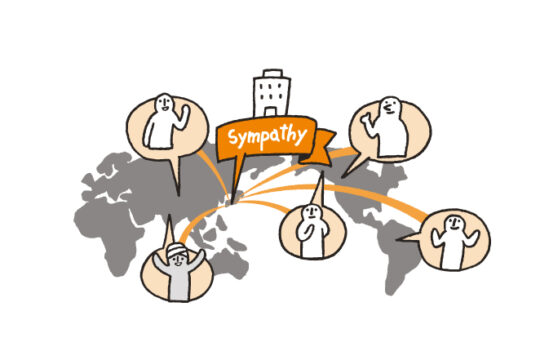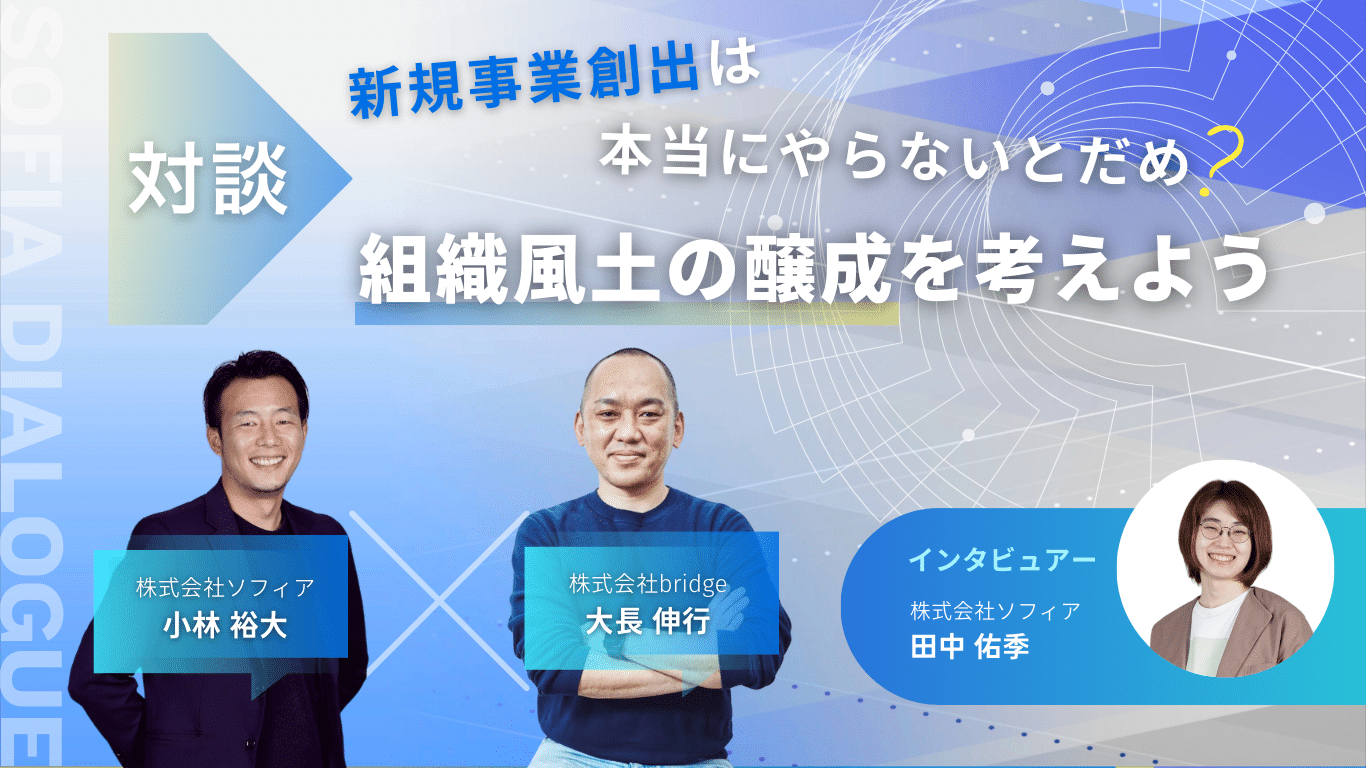組織の発展に欠かせない!従業員エンゲージメントとは
最終更新日:2020.09.02

目次
優秀な人材に長く勤めてもらうために、そして従業員の意欲を高めて労働生産性を向上するために、企業はまず何をすべきでしょうか。組織の発展に欠かせない要素の一つとして挙げられるのが「従業員エンゲージメント」です。
これまで企業で重要視されていた「十分な給与」「福利厚生の充実」「高い従業員満足度」などが実は生産性の向上や優秀な人材のつなぎ止めにあまり効果がなかったとして、米国では1990年代から「従業員エンゲージメント」に注目が集まりはじめました。
日本においても、雇用スタイルや働くモチベーションについて多様な価値観を持ち合わせているミレニアル世代に代表されるように、従来型の画一的なマネジメント方法には限界が生じてきました。そこで近年、日本企業も従業員エンゲージメントに着目するようになっています。
今回はあらためて「従業員エンゲージメントとは何か」「従業員エンゲージメントを高めるとどうなるのか」「従業員エンゲージメントを高めるにはどうすればいいのか」についてお伝えしていきます。
従業員エンゲージメントとは
ここでは、従業員エンゲージメントの一般的な定義と、弊社(株式会社ソフィア)による従業員エンゲージメントの定義を紹介します。
従業員エンゲージメントの定義
「エンゲージメント」という言葉は、約束、従事、没頭などを意味する英語の「engagement」に由来します。人事・組織開発の分野や、マーケティングの分野では、「愛着」や「思い入れ」を表す言葉として使用されます。
「顧客エンゲージメント」というと、顧客がどれだけ自社製品や自社ブランドに愛着を持ってくれているかという意味です。
「従業員エンゲージメント」は、従業員が現在働いている会社をどれだけ信頼しているか、会社にどれだけ貢献したいと考えているかという意味で活用されます。
もう一歩解釈を進めると、「従業員の自発的(内発的)な貢献意欲」になります。
従業員エンゲージメントにおいては、この自発的(内発的)な貢献意欲が重要です。自発的(内発的)な貢献意欲とは、賃金や他者からの評価を得たいといった外部からの動機付けではなく、自身の内面から起こる動機付けを意味します。自身の中から湧き出てくる興味や関心などが行動要因となっているため、その行動そのものが目的となっている状態です。
ソフィアでは、従業員エンゲージメントが高い状態を「従業員の一人ひとりが、会社の成長と自身の成長を結び付け、会社の目標を実現しようとする戦略に則って、自らの力を発揮しようとする自発的(内発的)な意欲をもって、行動すること」と定義しています。
従業員満足度との違い
混同されやすい概念として「従業員満足度」が挙げられます。
従業員満足度とは、会社から与えられる業務内容や業務量、給料や福利厚生などに対する満足度です。よく実施される従業員満足度調査、ESサーベイといわれるものは、「企業そのものや仕事内容、職場の雰囲気や人間関係などにどの程度満足しているか」を問う内容になります。「自発的に企業に貢献したい」と思っているかどうかを示す従業員エンゲージメントとは、この点で異なります。
米国の心理学者、フレデリック・ハーズバーグの「二要因理論」から提唱された「衛生要因・動機付け要因」に照らし合わせるなら、不満足を引き起こす「衛生要因」に焦点を当てているのが従業員満足度であるといえます。不足すると満足どころか不満足になるため非常に重要であるものの、もうひとつの側面である「動機付け要因」にはあまり目が向けられていないと捉えることもできます。
従業員エンゲージメントを高めるメリット
ソフィアでは、従業員エンゲージメントが高まっている状態について下記のように定義しています。
「従業員の一人ひとりが、会社の成長と自身の成長を結び付け、会社の目標を実現しようとする戦略に則って、自らの力を発揮しようとする自発的(内発的)な意欲をもって、行動すること」
このような状態を実現することで、従業員や企業にさまざまなメリットがもたらされます。
従業員のモチベーションアップ、離職率の低下
会社の成長と自分自身の成長を紐づけることによって、従業員のモチベーションが高まり、自発的な貢献意欲が高まった状態となります。
近年では、社会において転職することへのマイナスイメージがなくなりつつあるため、従業員の中で転職を考えている人が顕在的にも潜在的にも多くなっていますが、自発的な貢献意欲によって会社との結びつきが強い状態だと、転職への欲求を抱きにくくなり、結果的に離職率の低下につながります。
サービスレベル・顧客満足度の向上→業績の向上
自分自身の成長と会社の成長が深く紐づき、従業員自身が仕事にやりがいを感じている状態であれば、顧客へのサービスレベルの向上も期待できます。その結果、顧客体験価値の向上、顧客エンゲージメントの向上へとつながり、業績の向上も期待できます。
従業員エンゲージメントを高める方法
従業員エンゲージメントを高める上では、自身の成長と会社の成長の結びつきをいかに育むかということがポイントになります。
そのため、取り組みを考える際は「コミュニケーションの質と量を上げ続ける」ことがテーマになります。
自社の理念やビジョンを土台にコミュニケーションを行う
自社の理念やビジョンを明確に掲げている企業は多くありますが、全従業員がその理念やビジョンに共感し、それぞれの業務に反映できている例は少ないのではないでしょうか。
- 会社は何を大事にし、どこに到達したいのか、そのために何をすべきか
- 従業員は企業にどのように貢献し、それによってどのような成長の機会を得られるのか
- 従業員はどのような視点で自身のキャリアビジョンを描けばいいのか
上記のように、自社の理念やビジョンと従業員の成長とを紐付けたコミュニケーションを行うことが重要です。
社内コミュニケーションの活性化
自社の理念やビジョンをベースとしたコミュニケーションを意図的に発生させることがポイントです。
ある調査では、企業規模を問わず社内のコミュニケーションに課題を感じている企業が多いという調査結果が出ています。その調査では、「どの関係においてコミュニケーション課題があるか」という問いに対して、「部門間(71%)」がトップ、2位は「経営層と社員(56%)」となっています。コミュニケーションが発生しなければ、従業員の成長と会社の成長の結びつきは生まれようがありません。
対面のコミュニケーション、メディアやツールを介したコミュニケーションの両方において、経営と社員、異なる部門間、上司と部下という、多方向のコミュニケーションチャネルを適切に設計することが重要です。
関係性の質を向上させる
マサチューセッツ工科大学のダニエル・キム教授が提唱している、「組織の成功循環モデル」という理論があります。
この理論では、よい組織づくりは、従業員と企業が対話を持つことから始まるとしています(関係性の質の向上)。その結果、自発的に考えられることを求められた従業員は、仕事に動機付けされます(思考の質の向上)。さらに、新たな取り組みやチャンレンジングな挑戦を行うようになるというものです(行動の質の向上)。
この理論に基づけば、コミュニケーションの量や質の向上によって、関係性の質を向上させることが、従業員エンゲージメントの向上にとって重要だと捉えることができます。
従業員エンゲージメント調査を定期的に行う
企業や組織によって従業員エンゲージメントの状態はさまざまです。従業員エンゲージメントの向上に限らず、組織が直面している課題を解決するためには、組織の状態を把握し、課題設定をしたうえで、施策を講じる必要があります。
また、施策の効果が不明であれば、施策継続も難しくなってしまいます。そのため、課題を設定し効果を測定する両面で、従業員エンゲージメント調査を定期的に行う必要があります。
従業員エンゲージメントを高める施策事例
最後に、ソフィアで行った従業員エンゲージメントを高める施策事例をご紹介します。
ビジョン浸透のための施策事例①
総合サービスを提供するコングロマリット企業グループの事例です。同社では事業推進の強みであったトップダウンの文化をあえて崩し、さらに顧客志向の企業体を作るために新しいグループビジョンを制定しました。
しかし、社内で行ったビジョン浸透度調査で98%の理解・共感度という結果だったにもかかわらず、社員の行動面ではこのビジョンがまったく体現されていないことが課題となっていました。前述したように、従業員エンゲージメントを高めるためには、企業のビジョンと従業員の成長が紐づけて考えられる状態になっていることが理想です。
そこでソフィアでは、それまで個別に推進されていたビジョン浸透施策を統合、一元管理し、浸透に向けた中期シナリオを策定。ビジョン浸透度調査の改善とKPIを制定し、浸透シナリオに基づいた具体的な施策の計画立案を実施しました。
施策としては、表彰制度の制定と表彰を受けた社員が参加する事業横断サービス開発ワークショップや、全グループの従業員参加によるビジョンダイアローグ、ほめて伸ばす「Good Jobカード」制度の設計・運用などを実施し、ビジョンが従業員の行動に反映するに至りました。
ビジョン浸透のための施策事例②
同社では売上全体の過半数を海外売上が占め、順調な成長を続ける中、海外で働くローカルスタッフの離職率の高さが課題となっていました。求心力を向上させるために、ローカルスタッフに対して会社の歴史や日本でのポジションなどを伝えることの必要性を認識しつつも、それらが各国の現地駐在員に一任されておりうまく伝わっていない状況でした。
ソフィアは、海外ローカルスタッフの従業員エンゲージメントを高めることが、これらの課題の解決につながると考えました。そこで、長期ビジョンの策定に合わせて「自社の成長を支えた価値観」「お客様に対する想い」「従業員に対する想い」をまとめて、新しく行動指針を策定。その内容を、社内報をはじめとする各種コミュニケーションツールを活用して多言語でグローバル全従業員へ発信しました。
その結果、海外のナショナルスタッフの信頼と共感を向上させることができ、従業員エンゲージメントを高めることに成功しました。
地域向けブランディングのための施策事例
全国各地に拠点を持つ事務機販売会社。同社では、地域の顧客や潜在顧客に対する企業ブランディングが課題でした。顧客に企業と社員をより身近に感じてもらうため、Webサイトで社員紹介ページを作成したいと考え、実現に向けてパートナーを必要としていました。
ソフィアはまず、地域の社員の人柄と仕事への姿勢・熱意が伝わり、会社を身近に感じてもらえるコンテンツを設計。そのうえで、運用担当者が最小限の負荷で高品質なコンテンツ運用できるスキーム設計を支援しました。
具体的には、コンテンツの企画・設計、寄稿者向けのガイドラインや制作・承認フローの整備、その後数年にわたって安定的に運用できるスキームを策定しました。また、Webサイトの社員紹介コンテンツを営業ツールとして活用するための仕組みを提案し、多展開できるコンテンツを可能にしました。
従業員エンゲージメント調査の事例
こちらは学校法人の事例です。官主導で全国的な国立大学法人改革が進められる中、同大学においても中期経営計画に基づく大学運営のさらなる効率化と学生満足度の向上が急務でした。
計画推進にあたっては、教職員主体のボトムアップの活動や学部間の連携が必要と考え、まず現在の学内コミュニケーションの状態を把握すべく、各学部長と教職員に対するヒアリング調査、アンケート調査を実施。
結果的に、教職員や学部長の大学に対する期待や危機意識・問題点を認識することができ、コミュニケーション施策検討の土台となる貴重なデータを収集に成功しました。
その後、調査結果を基礎とした学内コンテンツ施策を展開することで学部間の連携の促進を行うことができ、従業員エンゲージメントを高めることにつながりました。
海外グループ社員に向けたエンゲージメント施策事例
グローバル企業として世界各国でM&Aなどを行う中で、同社は一つの企業体として経営理念・ビジョン・ミッションなどの共通理解が形成できていませんでした。海外のローカルスタッフは、そもそも日本の本社がどんな歴史を持ったどういった会社なのかさえ知らないことが多く、グローバル全体での求心力向上が課題となっていました。
そこでソフィアでは、新しいビジョンが発表されたことを機に、グローバル規模でビジョンの浸透を図るためのツールとして、海外社員向けの英語の小冊子を制作。英語版をもとに中国語・タイ語・ポルトガル語版を制作して世界各国の拠点へ展開しました。
また、グローバルリーダー育成を目的とした研修で撮影したビデオ素材をもとに、理念浸透用映像教材を制作。さまざまな場で使えるよう長さの違う数バージョンを制作し、研修や広報活動などに活用しました。ビジョンを元にコミュニケーションを行うことで従業員エンゲージメントを高めることにつながると考えています。
まとめ
従業員エンゲージメントが重要だと理解はしつつも、取り組むにあたって充分な情報がない、専門の人材がいないなどの理由で二の足を踏んでいる企業も多いのではないでしょうか。
人材育成の領域においては、言葉だけが先行し、取り組みを実施することだけが目的になりやすいので、しっかりと自社の状況を把握した上で、取り組みの目的を固めることが重要です。そのうえで、取り組みを進めるにあたって必要なノウハウや人的リソースが社内で確保できない場合は、外部の専門家にコンサルティングを依頼するのも一つの方法でしょう。
本記事が、各企業の従業員エンゲージメント向上のための取り組みについて、少しでも参考になれば幸いです。また、ご不明な点があればソフィアまでお気軽にお問い合わせください。
関連サービス
- 調査・コンサルティング ―さまざまなデータから、課題解決につながるインサイトを抽出―
- 業務プロセス最適化 ―インターナルコミュニケーションの視点で業務を再設計―
- メディア・コンテンツ ―読者と発信者、双方の視点に立った企画、設計―
- 研修・ワークショップ ―実践型研修とアフターフォローで学習効果を高める―
- イベント企画運営 ―企画力と事務局サポートで記憶に残るイベントを実現―