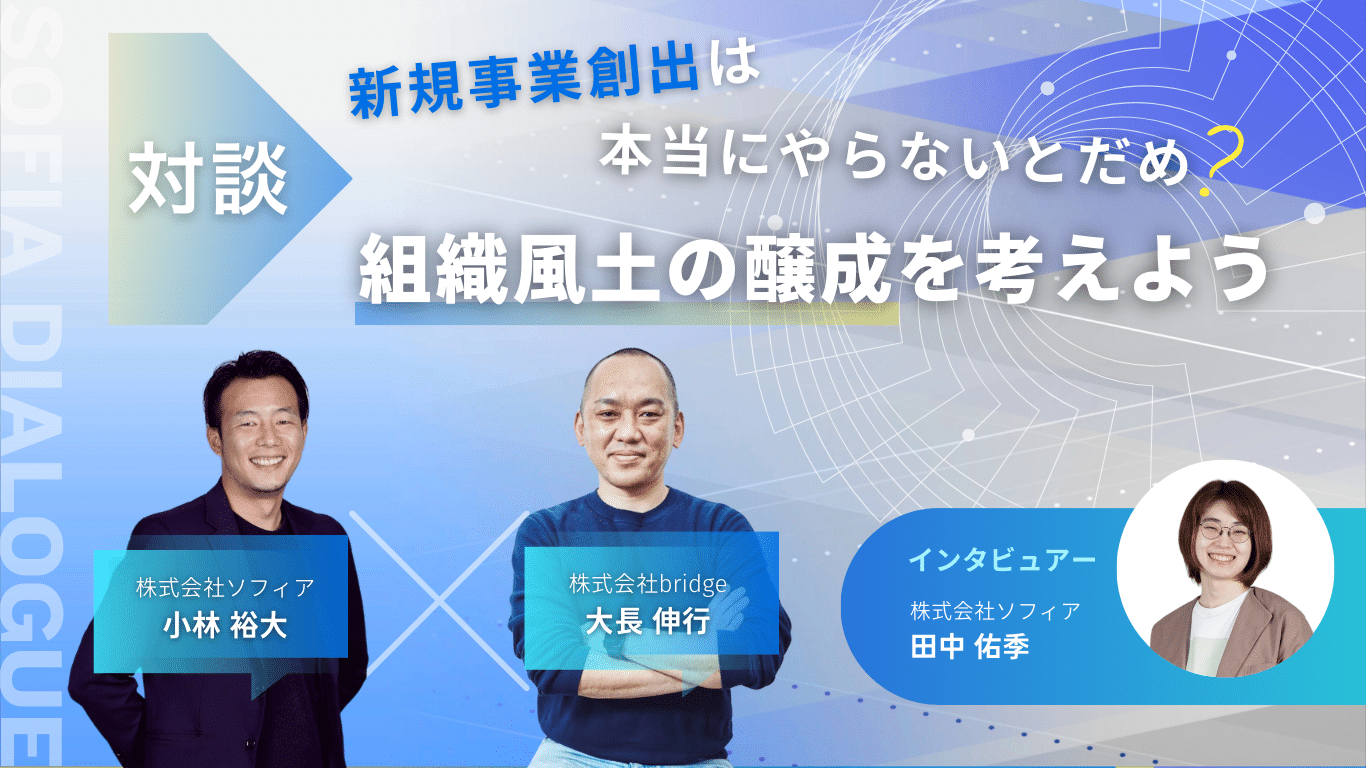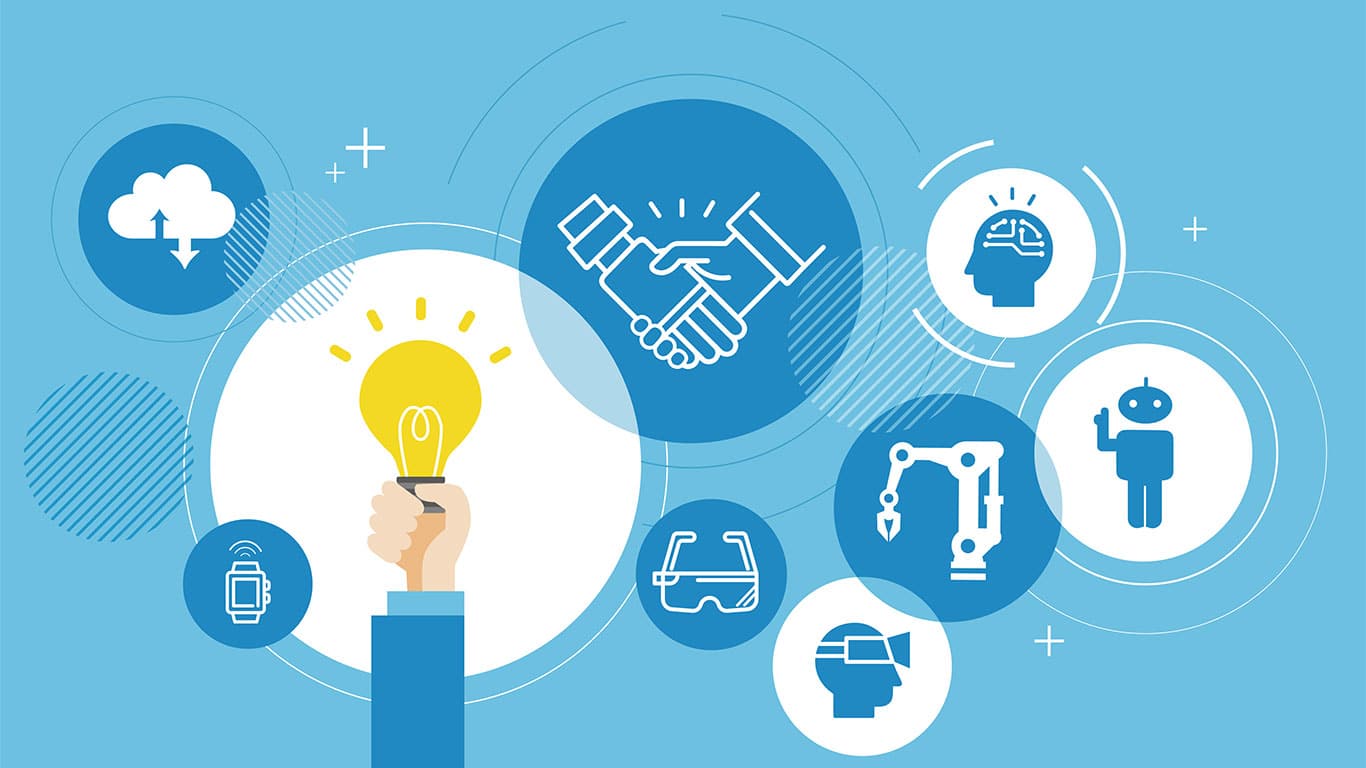大企業の新規事業成功の秘訣は?アイデアの数と推進体制がカギ
最終更新日:2025.07.10

目次
市場や技術の変化が激しい現代において、既存事業の成功に安住せず新規事業に挑戦し続けることは、企業の持続的成長に欠かせない取り組みではないでしょうか。しかし、多くのリソースを持つ大企業であっても新規事業を成功させるのは容易ではなく、その成功率は決して高くありません。
本記事では、新規事業の定義や必要性から始まり、低い成功率の現実や失敗要因、さらには大企業の成功事例を踏まえて、新規事業を成功に導くポイントについて解説します。
新規事業とは
まずは「新規事業」という言葉の意味と、その必要性について押さえておきましょう。企業によって新規事業の形態はさまざまですが、大きく分けて商品・サービスと市場(顧客層)の新規性という2軸で考えることができます。
平たく言うと、既存の商品・サービスを新しい市場に展開する場合は「新市場の開拓」、既存市場に新しい商品やサービスを投入する場合は「新商品の開発」ということになります。一方で、両方が新規となる場合は多角化と呼ばれ、全く新しい分野への挑戦となります。いずれにせよ、自社の事業領域を広げる取り組みが「新規事業」と定義できるでしょう。
なぜ新規事業が必要なのか
なぜ企業は新規事業に取り組む必要があるのでしょうか。この背景には、国内市場の成熟や既存製品のライフサイクル短縮化があります。特に市場や顧客ニーズの変化が速く、技術革新も加速する現代では、既存事業だけに頼っていてはやがて頭打ちになりかねません。どんな優良商品も永遠に売れ続けることはできず、いずれ衰退期が訪れるのは避けられない現実です。
日本企業においても、経済の超成熟化や人口減少による既存事業の停滞を背景に、新規事業の創出が重要な経営課題に浮上している企業が増えています。長期的な企業存続と成長のためには、新しい事業領域への挑戦が不可欠ということです。
また最近では、国もスタートアップ支援を重要施策に位置づけ、大企業の新規事業創出を後押ししています。例えばオープンイノベーション促進税制やスピンオフ税制の拡充により、大企業がスタートアップ企業へ投資したり、自社から新事業子会社を分離・創出したりする動きを促進しています。これが追い風となり、オープンイノベーションや産学連携など外部の力も取り入れながら新規事業に挑戦する企業が増えています。
新規事業の成功率と現実
厳しい現実をお伝えすると、意欲的に新規事業に挑戦しても、成功率は残念ながら高くないのが実情です。
中小企業庁の調査では、新規事業に「成功した」と回答した企業は約28%にとどまり、さらに新規事業によって「経常利益率が増加した」企業となると全体の約14%に過ぎないという結果が出ています。つまり、多くの企業で新規事業は収益化まで至らずに終わっているのが現実なのです。
さらに、大企業のケースでは「新規事業に取り組んだうち累積損失の解消にまで至った割合は7%(裏を返せば93%は失敗)だった」との報告もあります。10件中9件以上は失敗するほど新規事業のハードルは高いということです。
このような厳しい現実があるからこそ、多数のアイデア出しと挑戦を行う中で少しでも成功の確率を上げる戦略が求められます。
新規事業が失敗する主な要因
新規事業の成功率が低い要因として、いくつかの共通した失敗パターンが指摘されています。代表的な失敗要因をご紹介しましょう。
- ノウハウ・人材の不足:
新分野に必要な知識や経験が社内になく、手探りで進めてしまうケース。専門人材の不在により市場分析や戦略立案が不十分になってしまいます。 - 顧客ニーズの見極め不足:
新規事業のアイデアに固執するあまり、市場の本当のニーズを検証せずに商品・サービスを開発してしまうパターン。結果として「良いものを作れば売れる」という思い込みだけで市場とズレた事業を立ち上げてしまいます。 - 資金・リソース不足:
開発やマーケティングに必要な資金・人的リソースが足りず、事業推進が中途半端になってしまうケース。大企業であっても新規事業には十分な予算が割かれないことも多いです。 - 参入タイミングの誤り:
市場が成熟し競合が多い段階で後発参入したり、逆に市場形成前に先走りしすぎたりして、タイミングの悪さから軌道に乗らないパターン。 - 撤退判断の遅れ:
上層部の思い入れが強すぎて不採算事業から撤退できず、損失が拡大してしまうケース。早めに軌道修正や中止判断を下せない企業文化も一因です。 - 関係者が多すぎる:
大企業ほど新規事業に関わる承認者・ステークホルダーが多く、社内調整に時間がかかるため、スピード感を欠いてしまうパターン。意思決定に時間を要しチャンスを逃すうえ、関係者の利害調整に追われて方向性がぶれる危険もあります。
以上のような失敗要因を踏まえると、成功確率を高めるには不足するリソースを補い、顧客視点で検証し、俊敏な意思決定ができる体制を整えることが重要と言えるでしょう。
まとめると、新規事業の失敗要因は多岐にわたりますが、その多くは事前の準備不足と体制の不備に起因していると考えられます。
大企業の新規事業成功例
ここからは、日本の大企業による新規事業の成功事例をご紹介します。自社の規模や業種が異なっていても、成功例から学べるエッセンスは多くあるのではないでしょうか。それぞれの企業がどのように課題を克服し新規事業を軌道に乗せたのか、ポイントを探っていきましょう。
本田技研工業の「ホンダジェット」
世界的な自動車メーカーである本田技研工業(ホンダ)は、社内ベンチャー的に小型ビジネスジェット機の開発に挑戦し、「ホンダジェット」を誕生させました。ホンダジェットは2015年に市場投入されると、革新的なエンジン配置や軽量素材による性能の高さが評価され、2017年以降3年連続で世界の小型ジェット機カテゴリー納入数1位を記録しています。
具体的には、2019年上半期(1~6月)には17機をデリバリーし、カテゴリートップのシェアを獲得したことが発表されました。
この成功の背景には、他社に真似できない独自技術の追求と顧客ニーズを捉えた差別化があります。高速・高高度・長距離飛行が可能というスペック面の強みに加え、「静粛性が高く快適」「燃費性能に優れる」といった付加価値でビジネスジェット顧客のニーズを満たしました。
他業界からの新規参入でありながら自社の技術力を新分野に応用し、ブランド信頼と独自性で市場を切り拓いた好例と言えるでしょう。
三菱商事株式会社の「スープストックトーキョー」
総合商社の三菱商事株式会社では、社内ベンチャーとして立ち上げた外食事業「Soup Stock Tokyo(スープストックトーキョー)」が成功を収めています。
スープストックトーキョーは1999年、当時「女性が一人でも安心して入れる外食のお店が少ない」という着眼点から、「一人でもゆっくり食事ができるスープ専門店」をコンセプトに誕生しました。おしゃれな店内で栄養バランスの良いスープを提供するスタイルは働く女性を中心に支持され、単なるファストフードではなく「食を通じて誰かの一日を変える」という物語性も打ち出したことでブランドファンを獲得しました。
現在では首都圏を中心に全国で約60~70店舗を展開し、2023年度には初めて売上高100億円を突破する規模に成長しています。
外食産業という一見ありふれた領域でも、「ターゲット顧客(働く女性)の潜在ニーズ」を的確に捉えコンセプトを差別化することで成功した例と言えるでしょう。
日本郵政とYper株式会社の「OKIPPA」
日本郵政がスタートアップ企業のYper株式会社と協業して生み出した新規事業が、不在時の宅配荷物受け取りサービス「OKIPPA(オキッパ)」です。
ネット通販の普及に伴う再配達増加という社会課題に対し、生み出されたのが玄関先に設置する専用バッグとアプリで荷物を受け取れるOKIPPAでした。都市部の再配達率の高さで物流に負荷がかかっている問題に着目し、在宅時間が少ない共働き世帯などのニーズに応えた画期的なサービスです。
OKIPPAでは、ユーザーは事前に配達予定をアプリで確認し、留守時には玄関のバッグに荷物を入れてもらうことで再配達を防ぎます。日本郵政という全国ネットワークを持つ大企業のインフラと、YperのIT技術・発想力を組み合わせたオープンイノベーションの成功例と言えるでしょう。
Yper社自体は2017年創業・資本金約2800万円のベンチャーですが、自社単独では難しい全国展開も日本郵政との提携によって実現しました。このように大企業×スタートアップの協業により、大企業側は新サービスで社会課題を解決し、スタートアップ側は大規模市場へのアクセスを得るという双方にメリットのある結果となりました。
富士フイルムの新規事業転換
カメラ用写真フィルムで長年トップ企業だった富士フイルム株式会社は、デジタル化によるフィルム需要激減という逆風に対し、果敢な事業転換で乗り越えたことで知られています。
同社は写真フィルムで培った精密化学の技術を活かし、化粧品や医薬品・再生医療など全く異なる新分野へ次々と進出しました。
例えば、フィルムのコラーゲン技術を化粧品や再生医療に応用し、フィルムで培った抗酸化技術をエイジングケア化粧品の機能性として訴求するなど、既存技術資産をうまく転用しています。
この取り組みにより富士フイルムは従来事業とのシナジーを生み出しつつ時間をかけて事業構造を転換し、現在ではヘルスケア・医療機器や高機能材料などが収益の柱となるまでに成長しました。
フィルム事業という強みを核にしながら、新たなマーケットに挑んで成功した有名な例です。競合であった米コダック社がデジタル化の波に乗り遅れ経営破綻したのとは対照的に、富士フイルムは自社技術の汎用性に着目し異業種へ活路を見出したことが勝因と言えるでしょう。既存技術の新たな応用可能性を見つけることで、業界の構造変化を乗り越えて成功できることを示した事例です。
新規事業成功のためのポイント
成功事例から浮かび上がる新規事業成功のためのポイントを、いくつかの観点に分けて解説いたします。
自社の状況に合わせて取り入れられるヒントがないか、ぜひご確認ください。
多くのアイデアと挑戦機会を確保する
新規事業の成功確率が一桁台~数割程度と低い以上、企業として重要なのはアイデアの母数を増やすことです。つまり、「この一案に賭ける」だけでなく数多くのアイデアを試す(打席に多く立つ)アプローチが求められます。
大企業には人材も資金も豊富にありますから、社内公募制度やハッカソン、事業提案コンテストなどを通じて社員から幅広く新規事業アイデアを募る仕組みを設けるとよいでしょう。
例えばリクルート社は1980年代から「Ring」という新規事業提案制度で毎年多数の事業案を公募し、実際に事業化する取り組みを続けています。こうした試みは”一発必中”を狙うのではなく「数撃ちゃ当たる」戦略で成功のチャンスを広げるものです。
ただし闇雲に数だけを追えば良いわけではなく、後述するように選別と育成のプロセスも重要になります。まずは社内外問わず多様なアイデアが出てくる環境を整え、新規事業の種を絶やさないことが第一歩と言えるでしょう。
成功確率の低い新規事業では、多くの挑戦機会を確保することが成功への確実な道筋となります。
新規事業推進の専門組織・体制構築
次に、数多くのアイデアを着実に事業へ育てる推進体制を築くことが欠かせません。大企業では往々にして新規事業開発が既存事業部門の片手間になったり、通常の稟議プロセスに乗せられてスピードを失うこともあります。
ある調査でも、既存事業部主体での新規事業開発は意思決定が遅く既存事業が足かせとなり成功度が低い傾向が確認されています。このため、多くの企業は新規事業専任の組織(例えば事業開発部、新規事業創出センター、CVC部門など)を設け、トップ直轄で迅速な意思決定を行う仕組みにしています。
専門組織を作るだけでなく、人事制度や評価指標も新規事業向けに調整することが重要です。短期的な利益では測れないチャレンジを評価するため、OKR(Objectives and Key Results)の導入や、新規事業担当者の昇進・報酬に長期視点の評価軸を取り入れる企業もあります。
また、社内起業家を育成・支援するプログラムを用意し、メンターによる指導や事業開発のノウハウ提供を行うケースも増えています。外部の知見を取り入れるためにベンチャー企業や大学との連携、オープンイノベーションプラットフォームへの参加も有効でしょう。
このように、新規事業を生み出しやすく育てやすい組織風土と仕組みを整えること(打率を上げる取り組み)が成功には欠かせません。せっかく生まれた有望な芽を既存組織の論理で潰してしまわないよう、経営トップ自らコミットし後押しする姿勢も求められます。つまり、新規事業の成功には専門組織による迅速な意思決定と適切な育成体制の構築が不可欠ということです。
自社の強みで弱点を補う工夫
新規事業とは未知の分野への挑戦ですが、ゼロから始める必要はありません。自社の強みや経営資源を活かして、市場の隙間や他社の弱みを突く戦略が有効です。
例えば、先述したホンダジェットはホンダのエンジン技術という強みを活かし、既存航空機メーカーが手掛けていない小型ジェット市場に参入しました。また、スープストックトーキョーは商社の資金力と調達ネットワークを背景に、小規模なベンチャーでは難しい全国展開を実現しています。
自社内を見渡せば、技術・ブランド・顧客基盤・人材など必ず他社にない強みがあるはずです。その強みを新規事業で足りないピースを補完するように活用するのです。
逆に、自社に不足するリソースが大きい場合には、OKIPPAのように他社との協業で埋める工夫も一つの手でしょう。社外の力を借りることで自社の弱みを補い、スピーディーにサービス提供体制を構築できます。
要は、リソースの内外を問わず弱点をカバーし、強みを最大限伸ばす発想が成功への可能性を広げるということです。
時代の流れに沿ったビジネス展開
新規事業にはリスクがつきものですが、闇雲にハイリスクな賭けに出れば良いわけではありません。成功のためには時代の変化や技術トレンド、社会のニーズをしっかりと捉えた上でチャンスに挑むことが大切です。環境変化を追い風にできれば、リスクはあっても高い成長が見込めるでしょう。
近年であれば、AI(人工知能)やIoT、脱炭素(カーボンニュートラル)といった大きな潮流があります。これらの時代のキーワードにマッチする事業テーマは、国の支援策も充実していたり、顧客からの注目も集めやすかったりします。
実際に、AI技術を取り入れたサービス開発ではAI専門部門を新設する企業も増えています。自社の新規事業が時代の要請に合致していれば、社内での理解も得られやすく、社外から人材や資金を呼び込むことも容易になるでしょう。
一方で、いくら流行だからといって自社の強みと無関係な領域に手を広げすぎるのも禁物です。重要なのは自社のビジョンやコア技術に照らし合わせて、時代の波に乗れる分野を見極めることです。時流に乗った正しいタイミングで、適切な市場にリーチできれば、新規事業成功の確率を上げることができるでしょう。

インターナルコミュニケーションがうまくいかない原因とは?目的と重要性について徹底解説
インターナルコミュニケーションがうまくいかない原因を、2024年の最新実態調査と「対話・教育・ツール」の3本柱から…
“損失”は”失敗”ではない
新規事業に挑戦する以上、失敗と損失は避けられないものだと心得る必要があります。大切なのは、損失を恐れて萎縮するのではなく、失敗から何を学び次に活かすかです。失敗を経験せずして大きな成功は得られないというのは多くのイノベーターが語るところでもあります。
言わずと知れたカジュアル衣料のユニクロ(ファーストリテイリング)も、かつて新規事業で大きな失敗を経験しています。2002年に子会社エフアール・フーズを設立し有機野菜の宅配販売サービス「SKIP」を開始しましたが、「良い野菜を安く提供する」という自社目線の発想にとらわれすぎたために顧客ニーズをつかめず、農家との連携もうまくいかず供給不安定による欠品が相次ぎました。
その結果、約30億円もの赤字を出した末に事業開始からわずか1年半で撤退することになりました。「顧客起点の考え方に欠けていた」と総括し、撤退の判断自体は早かったためユニクロ本体へのダメージは致命的にならずに済んでいます。
また、SKIPの失敗を経験した担当者は後にユニクロ子会社「GU」の社長に抜擢され、今度は顧客ニーズ重視の戦略で低価格ファッションブランドを成功させました。
このように、一度の失敗で終わりにするのではなく、得られた教訓を次の挑戦に活かすことで結果的に成功を収めるケースもあります。重要なのは、小さな失敗であれば許容し学びに変える企業文化と、撤退すべき時に決断できる経営判断です。
多少の損失に怯まず新たな事業に取り組むマインドと、それを是とする組織風土が、長い目で見れば新規事業成功の土壌となるでしょう。
失敗を恐れずに挑戦し、その経験を次の成功につなげる文化こそが新規事業成功のカギとなります。
インターナルコミュニケーションの活性化
大企業で新規事業を立ち上げる際に意外と見落とされがちなのが、社内のコミュニケーションです。新規事業チームだけが盛り上がっていても、他の部署との連携が取れていなかったり、経営層と現場との認識にズレがあったりすると、思わぬ抵抗や障害が生じることがあります。
新規事業を成功させるには、まずその事業が企業理念や経営戦略に合致していることを社内で共通認識として持つことが絶対条件です。それが欠けると「本業をないがしろにして新規事業ばかり重視するのか」といった反発が現場から起こり、組織の軋轢につながりかねません。
また、既存事業部門の社員にとっては「新規事業にリソースが割かれる=自分たちの仕事が脅かされるのでは」と不安に感じる場合もあります。こうした懸念を払拭し協力を得るためにも、適切な情報共有と対話が欠かせません。
具体的には、新規事業の目的や進捗を定期的に社内報告したり、全社イベントで新規事業チームがプレゼンテーションを行ったりする方法があります。社内SNSやポータルサイトを活用してアイデア募集や進捗共有を行い、社員全体を巻き込んだ形で新規事業を推進する企業もあります。
経営層からも「新規事業は会社の未来にとって重要なチャレンジだ」というメッセージを発信し、全社的な応援ムードを醸成すると良いでしょう。インターナルコミュニケーションを活性化し社内のベクトルを揃えることが、ひいては新規事業の推進力を高めるのです。
新規事業の成功には社内の理解と協力が不可欠であり、そのためには継続的なコミュニケーションが重要ということです。
まとめ
大企業における新規事業の成功は一朝一夕には成し遂げられません。しかし、市場動向を注視し積極的に新たなビジネス展開を模索することは、企業の長期的発展に欠かせない戦略と言えるでしょう。成功率が低いからこそ、多くのアイデアを試し失敗から学び続ける姿勢が重要であり、同時にその挑戦を支える組織的な後押しが必要です。
新規事業開発では、数多くの打席に立って初めてホームランが生まれる可能性があります。そのため、アイデア創出の機会を社内外に広く設け、挑戦の母数を増やすことが第一です。そして生まれた芽を育てるには、経営トップのコミットメントのもとで迅速な意思決定ができる専門組織を整備し、必要なら外部の知見も借りながら成功率(打率)を上げる工夫が求められます。
また、新規事業は孤立した活動ではなく会社全体の未来を担うプロジェクトです。既存事業の現場も含めた社内の理解と協力があってこそスムーズに立ち上がります。インターナルコミュニケーションを密にし、社員一人ひとりが自分事として新規事業に関われるようにすることで、組織全体の力を結集できるでしょう。
最後に、新規事業において「失敗」は終わりではなく成功へのプロセスです。小さく素早く失敗し、そこから学んで軌道修正する文化を持つ企業こそが、結果的にイノベーションを生み出し続けています。
大企業の強みを活かしつつも現状に安住しないチャレンジ精神で、多くの打席に立ち続けてください。その先に、次代を担う新たな事業の成功がきっと待っているはずです。
新規事業のスムーズな立ち上げには、企業内の密なコミュニケーションも欠かすことができない要素です。ソフィアでは、インターナルコミュニケーション活性化のためのバックアップを行っています。お困りの際は、ぜひご相談ください。