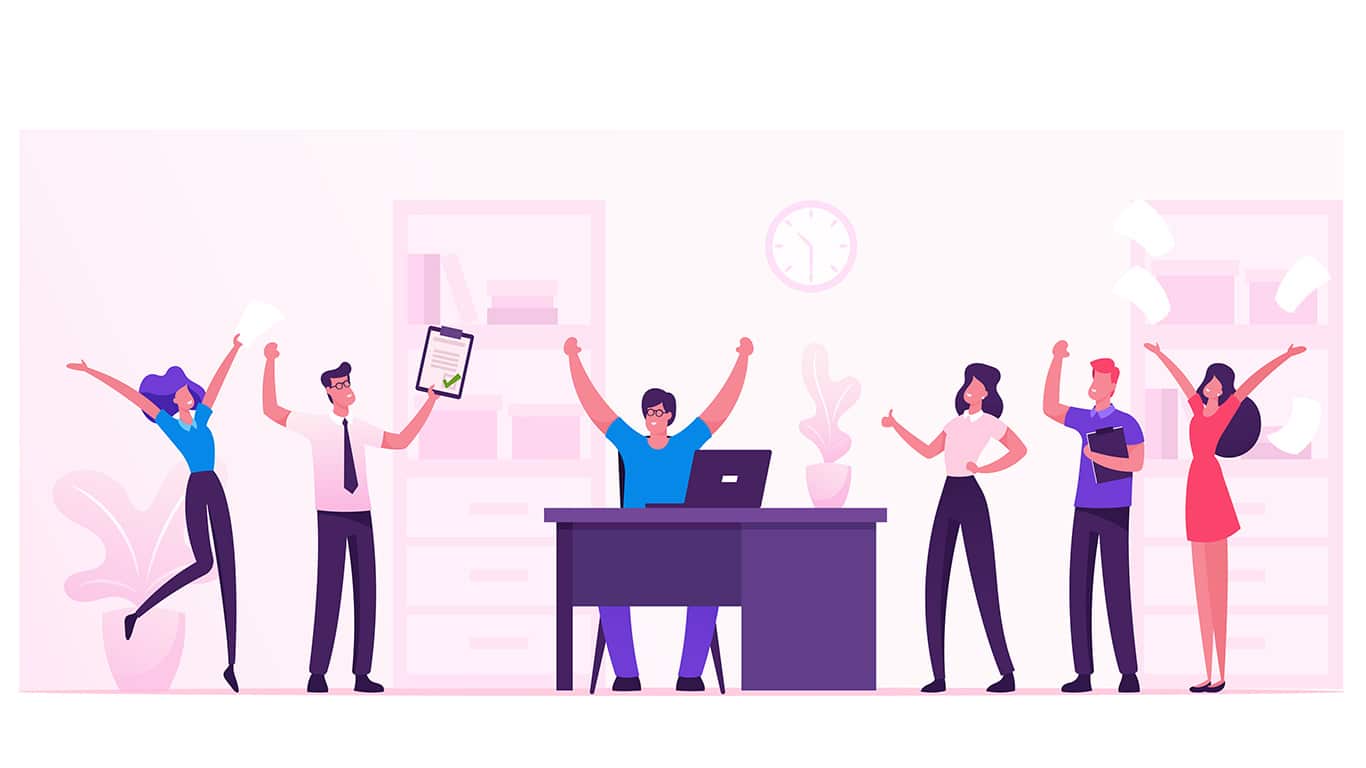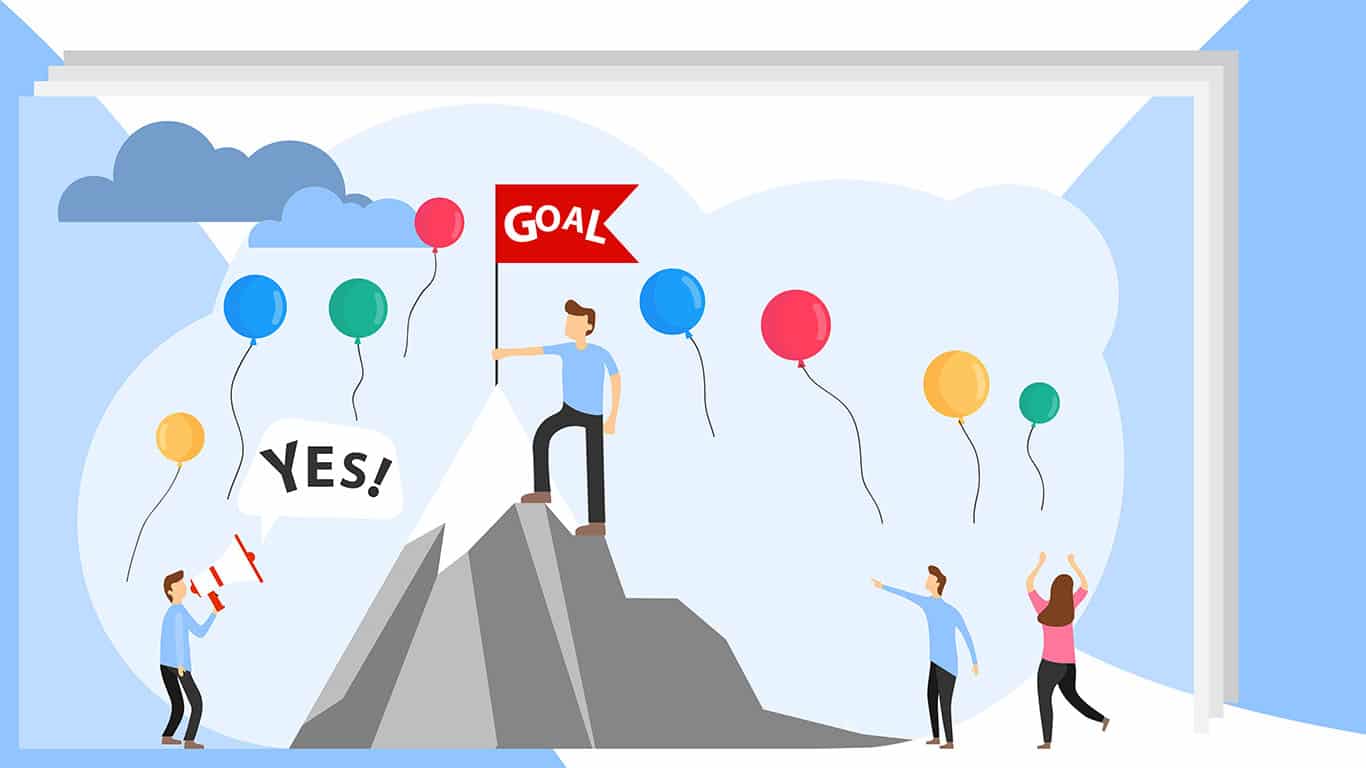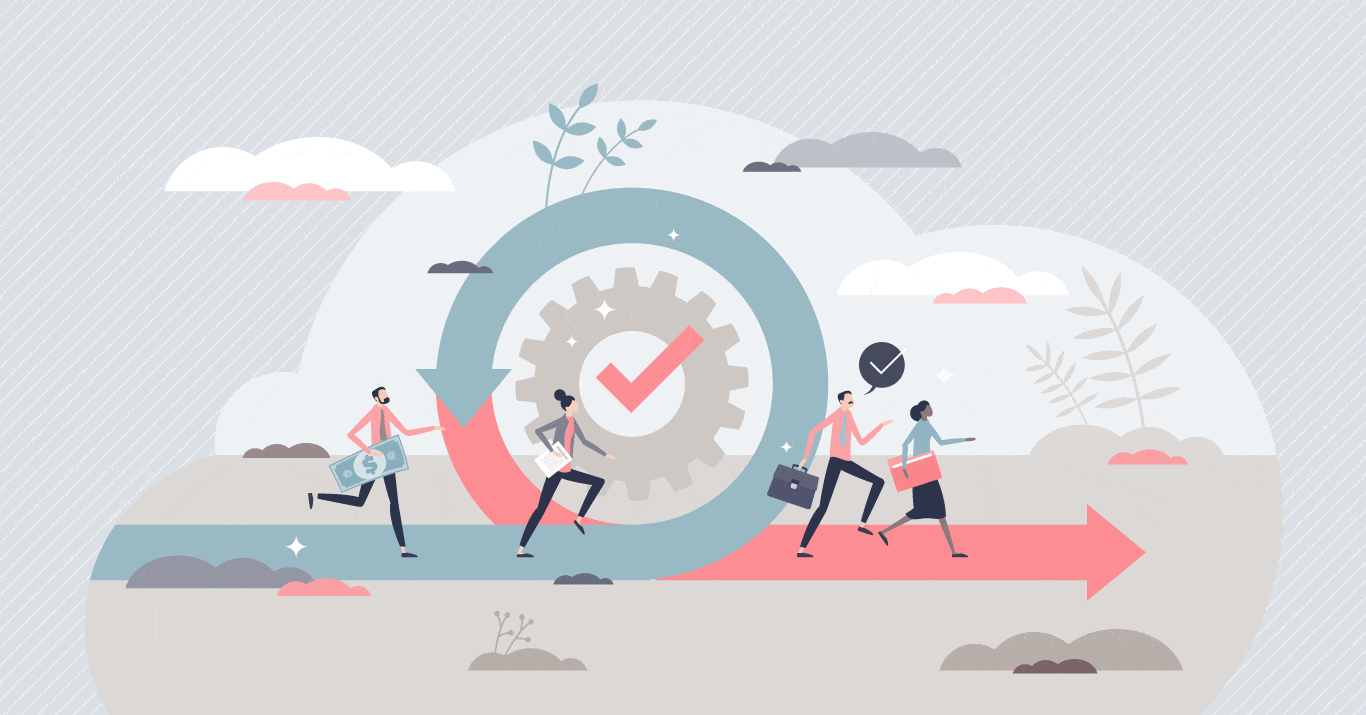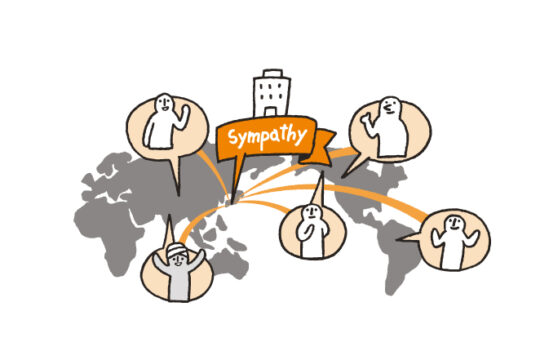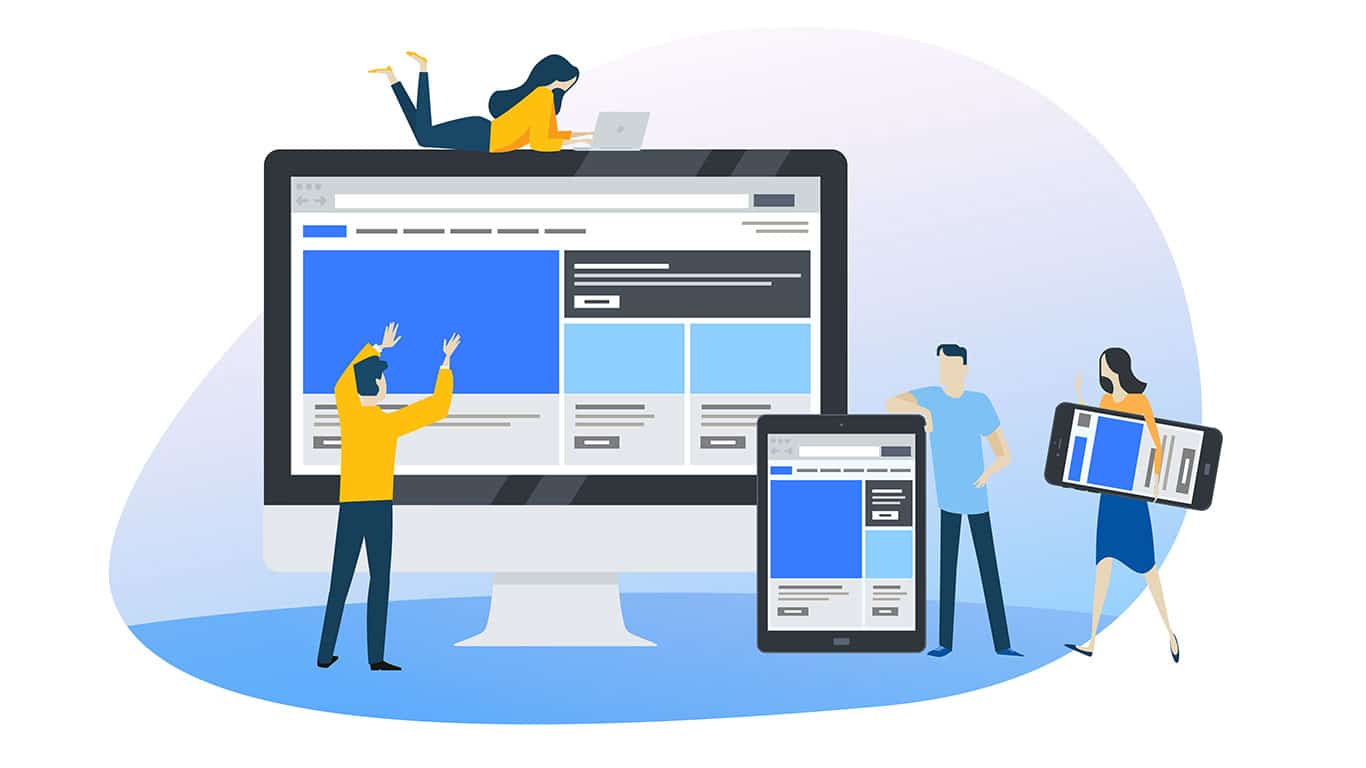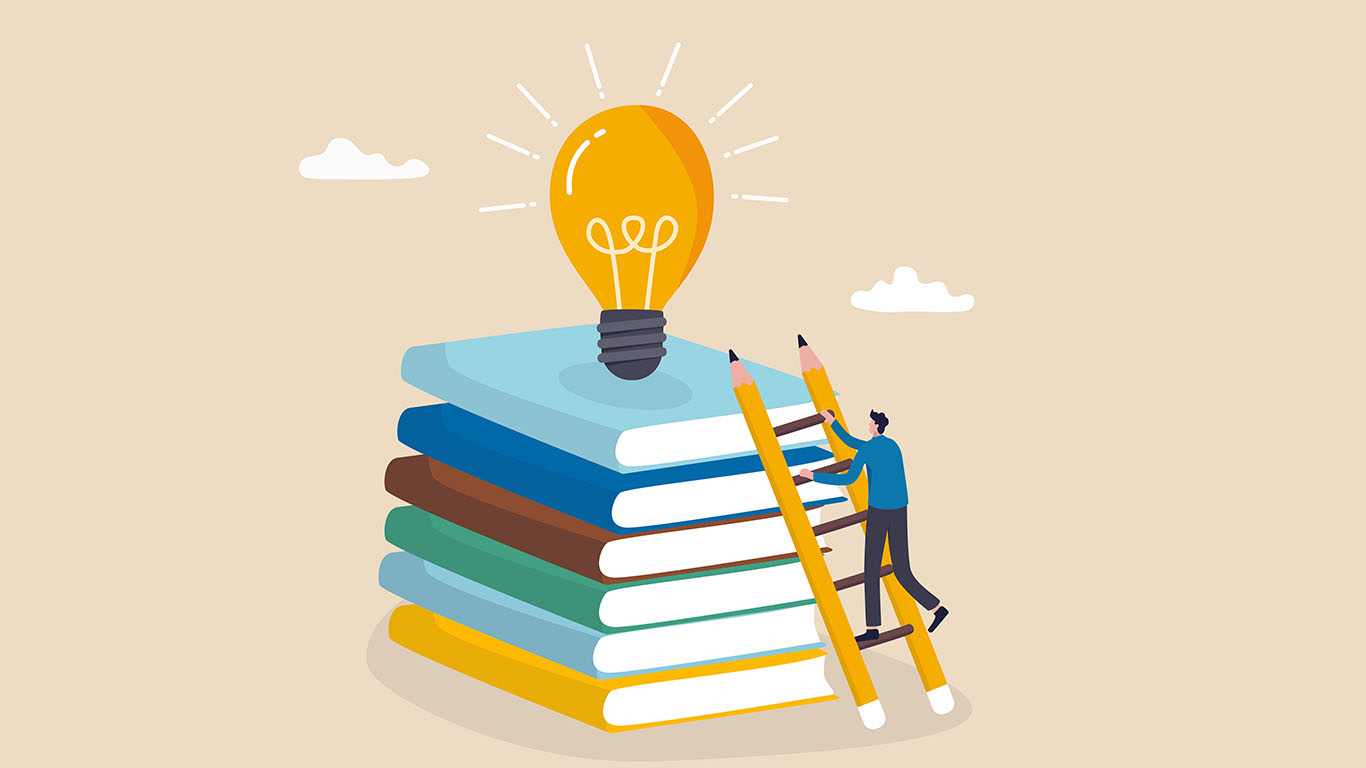行動指針を策定方法は?企業における作り方のポイントと浸透施策の事例をご紹介
最終更新日:2023.06.08

目次
行動指針を策定方法は?企業における作り方のポイントと浸透施策の事例をご紹介
一般的に行動指針とは、なにかしらの行動においてとるべき方針、道標となるものを意味します。企業における行動指針も似たような意味で使われています。
では、企業において行動指針を策定することには、どのような意味があるのでしょうか。本記事では、行動指針を策定するメリットと、行動指針の策定後に必要な「組織への浸透」の活動事例について解説します。
行動指針とは
企業における行動指針とは、企業が活動していくうえで経営者や従業員の行動の指標となるものです。ルールや判断基準を定め、企業の理想の状態に近づくための指標となります。これは企業が行動指針に反した活動をしないよう制限をかけることにもつながるでしょう。
また、行動指針という言葉の意味としての経緯を知ることは重要ですが、言葉の定義にとらわれず、必要性の観点で活用することが重要です。
多くの理念体系の中で、企業理念やパーパスに比べて、行動指針は抽象度が低いと言えます。つまり、より具体的と言えます。その内容は具体的な行動や姿勢に対する記述すが多く、解釈の幅が狭いため、わかりにくいといったことはありません。
企業理念との違い
よく似た概念として「企業理念」があります。企業理念とは、企業が経営上もっとも重要視する価値観や考え方を指します。「なぜこの企業は存在しているのか」「なぜこの企業はこの事業を営んでいるのか」という理由や方向づけにかかわるものです。企業理念に基づいて行動指針が生まれるともいえるでしょう。
企業は、自社の利益や成長だけを追求していれば良いのではなく、社会的な役割や存在意義も求められます。渋沢栄一氏の著書「論語と算盤」で語られているように、企業は社会的に求められている役割(論語)と業績を上げること(算盤)を両立しながら、企業活動を行なっていく必要があるのです。
クレドとの関係性
「クレド」とは、行動指針をさらに実務へと紐づけたものです。ただし、クレドは行動指針と同義で使われる場合もあり、行動指針を記したツールのことを指す場合もあります。ツールとしてのクレドは、業務中に携帯できるカード型のものが一般的ですが、企業理念と行動指針をあわせて記載した冊子を配布している企業もあります。
クレドを活用した企業は、リッツ・カールトンやジョンソン&ジョンソンなどが有名です。リッツ・カールトンが開発したクレドはスタッフが常備していつでも振り返れるようになっており、同社の行動指針を現場へ効果的に浸透させています。
ジョンソン&ジョンソンのクレドは「我が信条(Our Credo)」と呼ばれるもので、企業が負うべき4つの責任(顧客・社員・社会・株主)について記されています。また同社では定期的に「クレド・チャレンジ・ミーティング」が行われ、社員がこのクレドに関して議論を行い、そのときの自社の状況に応じて文言が変更されています。
企業が行動指針を定めるメリット
企業が行動指針を定めることには、さまざまなメリットがあります。
社員が同じ価値観で行動できる
判断の基準となる行動指針が共有されていると、社員全員が統一された価値観で行動できるようになります。すなわち、スピード感を持った判断ができるようになり、現場の即時判断はサービスの品質そのものを向上させることにつながります。
社員の帰属意識向上につながる
行動指針が浸透した状態では、社員が企業の行動指針に納得、共感したうえで企業に属しているため、社員の帰属意識が高まります。いわゆる、エンゲージメントやロイヤルティといったものです。帰属意識が高い状態では生産性が高まるほか、離職率低下といったメリットが得られます。
理念に基づいた企業文化が醸成される
社員一人ひとりが行動指針を体現した企業は、企業理念や経営理念に基づいた、組織のあるべき姿、理想像に近づいていきます。これは、理念に基づいた組織文化の醸成ともいえるでしょう。理念に基づいた組織文化の醸成はインナーブランディングにもつながります。また、自社に適した人材を採用する場面でも有用でしょう。
行動指針を変える必要のある企業の状態
行動指針は多くのメリットをもたらす点で企業にとって欠かせないものですが、企業の状態によっては、これまでの行動指針を変えなければならない場合もあります。ここからは、行動指針を変える必要がある企業の状態について解説します。
大企業病に陥っている
大企業病とは、規模の大きな企業で見られる非効率的な企業体質を指します。一般的に企業は、成長する過程において業容拡大や規模拡大などによって企業のガバナンス上の課題が増えていきます。それに伴って、管理業務が増えていき、各部門の業務が複雑化してしまいます。必要以上に手続きが多く細々して業務が増えている状態です。
業務が複雑化するに伴って、各現場には、行動指針よりも明確で必要性のあるガイドラインやルールが増えていきます。そうなると、現場では業務の仕組みやルールが行動を制限している状態になり、次第に行動指針が形骸化していきます。
ルールや規則などの細則の遵守に比重がおかれ、原則である行動指針が形骸化してしまっては元も子もありません。
その場合は、現状の経営課題を踏まえ、行動指針自体を刷新することも重要です。新しい行動指針に基づいて管理偏重の業務スタイルを変革削減するなど、業務のあり方やルールの見直しが必要です。
ビジネスや環境変化が速い中で、企業や社員がスピード感を持った行動をするには、細則の管理ではなく、行動指針への理解と権限委譲により、社員の行動を促すことが重要ではないでしょうか。
時代に合った新しいビジネスに転換できていない
企業が過去の成功体験から抜け出せず、時代の変化に即した新しいビジネスへと転換できていない場合も、行動指針の策定が効果的です。ビジネス(事業)は創業、成長、安定、衰退というサイクルで展開しますが、成長・安定期の成功体験にとらわれて、すでに衰退期に入っているにもかかわらず、そこから抜け出せなくなる場合があります。これを「サクセスシンドローム」や「経路依存性」などと言いますが、これを打破するためにも行動指針の見直しが効果的です。
「営業は足が命」という言説を嘲笑したCMが流行りましたが、○○神話みたいなものは、行動指針と蜜結合している場合が多くあります。過去の成功体験によってミスリードしないためにも、行動指針の問い直しが必要です。
行動指針の策定方法
行動指針などの上位概念が、さまざまなかたちで機能することがわかりました。では、行動指針を策定するときには、具体的にどのような手順ですすめるのでしょうか。
企業理念・経営理念・ミッションと組織の行動状態を言語化・可視化する
まずは現在の企業理念・経営理念・ミッションの内容を再度チェックするところから始めていきましょう。
今、会社がどのような価値観を大事にしているのか、目指している貢献の形はどのようなものなのかヒアリングやアンケートを実施し、確認しながら、現在の社員や組織の行動の実態を細かく整理していきます。現状を正しく整理することが、このあとの指針策定のベースをつくります。
全員が共通して現状を認識できるように、具体的に言語化したり、数値で可視化したり、丁寧に分析・整理しましょう。
あるべき状態・目指すべき状態を言語化し、現時点との乖離を明確にする
現状を正しく可視化できたら、次は理想的な状態について精度高く言語化・可視化していくステップになります。一般的に、理念やミッションは抽象化された言葉で示されているケースが多いので、掲げられた言葉を字面通りに受け取るのではなく、その背景にあるものを具体化しながら思考を深めます。
理念やミッションで掲げられているものを体現するためには、どのような行動が必要なのか、またどのような価値観を浸透させると、それがスムーズになるのか検討します。目指すべき状態を明確にできたら、次に現状とどのくらいの乖離があるかを把握しましょう。乖離が大きいか小さいかが、このあとの指針策定の段階でヒントになるでしょう。
また、昔から続いている文化のなかで、今後も残すべきものはなにかについても考えましょう。
理念やミッションに反する価値観や行動も考える
理念やミッションのためになる行動を洗い出すことと同じくらい大事なのが、理念やミッションに反する行動を考えることです。「クライアントや顧客に不利益になるような行動は何なのか」、「もしくは自社の目指すべき方向性に合わない行動とは」などを具体的にリストアップしていきます。
避けたい行動についてわざわざ考えるのは、とるべき行動を真逆の視点から洗い出すことができるからです。ふさわしくない行動について思考を深めることで、理想の働き方が明確に見えてきます。
検討した内容をまとめて整理する
続いては、ここまでのステップで考えてきたことを、振り返りながら整理するフェーズです。まずは全体を見返しながら、考えてきた大事なことが、現状や、時代性にあわせて、本当に必要な行動かどうかを精査します。
時代によって価値観は大きく変わるものなので、違和感がないか、客観的に判断しましょう。
また、示したい指針の量が膨大である場合には、スリムにまとめていきましょう。抽象的すぎるものは、具体的にわかりやすく噛み砕き、簡潔に示すことが、行動指針を出す際のポイントです。
整理した内容を標語として言語化する
行動指針の内容が定まったら、最後に、どのように打ち出すのかを考えていきます。できるだけ簡潔な文言で行動指針を示すのが、スムーズな浸透のためには効果的です。キャッチーな標語を決めて、広めやすいようにしましょう。
ただし、キャッチーな言葉だけでは伝わらない場合もあるでしょう。その際は、1、2文で簡潔に説明を加えても良いでしょう。いずれにしても、誰の頭にも残るように、わかりやすく簡単にまとめることがポイントです。
行動指針を浸透させるには?
ここまで考えてきた行動指針を、より早い段階で、深く従業員に浸透させるには、どうしたらいいでしょうか。行動指針をより意味のあるものにするために、押さえておきたいポイントを整理します。
意味づけをする
現在のビジネスと紐づけながら行動指針を示すと、従業員が具体的なイメージを膨らませやすく、早い段階で浸透することが期待できます。もし、現状のビジネスにうまく紐づけできない場合は、今後行われるビジネスと紐づけるようにしましょう。
また、行動指針に沿った行動がとれているか、日々の業務において定期的に振り返る習慣を作ることができると、さらに効果的です。
ストーリーテリングを用いて伝える
ストーリーテリングとは、印象的な物語を織り交ぜることで、より効果的に相手に物事を伝える説明手法です。ストーリーテリングで語りかけると、聞く人を強く惹きつけることができます。この手法を使って行動指針を示せば、人々に深く浸透するでしょう。感情に訴えかけることで、行動変容を促すフェーズまで、スムーズに持っていくことができます。 ※内
社内報など社内広報ツールを利用する
社内報・社内パンフレットを利用するのもおすすめです。社内報や社内パンフレットは、トップダウン型のコミュニケーションにとくに効果的なツールです。アクセスする時間や場所を問わないので、多くの人が自分のタイミングで閲覧できるのが特長です。広い範囲に向けて情報を共有できる点で、効率性に優れています。
イントラネット/社内ポータルを利用する
イントラネットとは、組織に必要な情報やツールをまとめた社内グループウェアのことです。便利なコンテンツを集めて共有することで、社内全体の生産性を向上させているシステムです。社内の多くの人が、習慣的に利用するものなので、このようなグループウェアに行動指針を掲げると、目にする頻度が増え、従業員の意識に効果的に訴えかけられるでしょう。
社内SNSを利用する
社内SNSを積極的に活用するのもおすすめです。社内SNSとはFacebookやInstagramなどのオープンなSNSとは違い、企業内でのやりとりに限定されたSNSです。活発に利用することで、従業員同士のコミュニケーションを促すことができます。このSNSのなかで広い範囲に発信すれば、行動指針を印象づけることが可能です。SNS上の反応から、社員の受け取り方をチェックできるのもメリットです。

コミュニケーション手段に最適な社内SNSとは?おすすめツールの紹介
社内SNSツールはコミュニケーション活性化の有効な手段です。社内SNSとは、FacebookやInstagramなど誰もがフォローで…
対話を行う
対話とは、まずお互いの立場や意見の違いを理解し、そのズレをすりあわせていく行為です。何かしらのテーマに基づいて、それぞれの意見を述べ合います。行動指針を題材に対話を行えば、各々がその内容を強く意識するきっかけになるでしょう。反対意見を持っている人がいた場合も、対話のなかで新しい気づきにたどり着くかもしれません。組織全体で、一体感をもって行動指針を目指していく、理想的な組織の土壌が形成されていきます。
ビデオやYouTubeで配信する
ビデオ配信やYouTubeでの動画公開で、トップメッセージを配信することも効果的な手法です。動画はテキストや口頭だけの情報発信よりも、記憶に残りやすいのが特長です。ビジュアルを駆使して説明できるので、誰にでも理解しやすいかたちでメッセージを発信できます。複雑なメッセージをわかりやすく説明できるというのはもちろん、認識の齟齬を防ぐという意味でも、動画を取り入れるのはおすすめです。
ソフィアが行った行動指針の浸透事例
行動指針の策定が急務な企業において、行動指針を策定すればこれまで挙げた課題が解決できるわけではありません。行動指針の効果を発揮するためには行動指針を社内に浸透させる必要があります。
ソフィアがこれまでに多数支援してきた行動指針の浸透活動の中から、2つの事例をご紹介します。
企業規模10,000名以上のグループ企業Aの事例
同社では、設立120年を機に、現場から発した問題解決やサービス改善の流れを作り出すことを目的として、新しくグループ理念と行動指針をリリースしました。しかし、本来トップダウンの気質が強い企業風土だったため新たなグループ理念と行動指針に対して社員の共感がうまく醸成できていない課題がありました。
そこでソフィアは、行動指針を進んで実践している社員に取材して行動のエピソード集を発行し、社員の顔写真とあわせてそのエピソードを掲載したポスターも作成しました。ポスター5,000枚をすべての事業所に配布・掲示すると、現場社員から次のシリーズを要望する声が挙がり、その後はポスターをシリーズ化して展開。行動指針にそった行動を称賛する流れと、体現する流れをうまく作り出すことができました。
企業規模10,000名以上のグループ企業Bの事例
同社では海外での売上が全体の過半数を占めており、順調な成長を続けている中、海外で働いているローカルスタッフの離職率の高さが問題になっていました。求心力を向上させるために、会社の歴史や日本におけるポジションなどをローカルスタッフに対して伝えることの必要性を認識していましたが、各国の現地駐在員に一任されており、ままならない状態でした。
ソフィアでは、長期ビジョンを策定するとともに「自社の成長を支えた価値観」や「お客様に対する想い」、「従業員に対する想い」をまとめて、行動指針を新たに策定しました。これらの内容を、社内報をはじめとした各種コミュニケーションツールを活用し、多言語でグローバル全従業員へ発信した結果、海外のナショナルスタッフから信頼と共感を得ることができるようになりました。
実務担当者は行動指針の機能と役割を抑えることが重要
人々を求心するための行動指針だけではなく、組織の求心力を高める上位にある概念(理念など)は、絶対的であり、不変的なものであるように見えます。それは組織の一体感を醸成し変革する原動力にもなる一方で、その絶対性から大きく多様性を棄損し、組織の方向性を変えてしまうこともしばしばあります。行動指針など所管する実務担当者は、この行動指針の多様で柔軟な機能を把握し経営と理念の関係を理解することで、事業や組織におけるさまざまな事象を俯瞰して捉える必要があります。
ここでは、行動指針が、集団や組織もしくは事業にどのように機能しているのかを解説することで、自社に必要な行動指針、もしくはその解釈を種別しながらご紹介します。
未来を見据えた行動方針
未来に向けた具体的な行動指針を示すことは、組織の求心力となり、従業員やステークホルダーの共感を集め、成果を結びます。数値や期限を明確にし、創り出すことを標榜することで、組織内での行動変容を促し、ビジネスチャンスを見出すようになります。行動指針は組織の印象も変えるため、未来を見据えた明確な目標設定が必要です。
価値観や判断を示す行動指針
組織には、そのイデオロギーや考え方を示す価値観としての行動指針があります。これは、倫理観や社会性を含む内容で、具体的な行動レベルの目標が掲げられます。従業員は、これを基準にあらゆる物事を判断します。価値観としての行動指針は、現場の意思決定や成果に対する解釈にも影響し、受け継がれる組織風土や文化、社員の学習姿勢にも影響を与えます。
事業の運営における目標達成のための行動指針
商品・サービスの特長や強みを示す、事業としての行動指針もあります。商品やサービスの特長や強みを示すことで、自社の存在価値を明確化することが可能です。この指針は、ビジネスモデルや業務フロー、評価などにも影響を与えます。
事業および、その事業におけるコアコンピテンシーが明確であると、人事制度も明瞭になるでしょう。明確な事業コンセプトに基づいた評価制度は、終身雇用や年功序列に代わる「ジョブ型」の採用・評価を可能にし、経営や人事にとって重要な問題を解決します。
組織内の人間関係を示す行動指針
企業は行動指針を掲げることで、組織内での人間関係が円滑になり、経済合理性を追求する企業でも安定的な組織運営ができます。企業は経済合理性を追求する組織ですが、職場では「仲間」や「家族主義」など、人間関係が色濃く出てきます。経済合理性を追求しながらも、良好な人間関係を築かなければならないというジレンマに陥る企業も多いでしょう。
行動指針で人間の関係性について打ち出すことで、組織風土や文化に強く影響する安全弁を作ることが可能です。企業において示された行動指針は、組織風土や文化に強く影響を与えます。
問題解決の正当性としての行動指針
経営者やマネジメントにとっては、何を問題とし、何を課題とするのか?という根本的な前提が必要です。組織や集団の中での事象を問題や課題として設定するためには、前提にある思想背景が必要です。そのうえで、解決に向けた組織を先導するための正当性も必要になります。正当性の指針となるのが行動指針です。そのため、企業は思想や価値観などの前提を揃えた上で、行動指針により正当性を示さなければなりません。
まとめ
行動指針は全社が一丸となって事業に取り組むために欠かせないものです。さらに、帰属意識を高めたり、理念に基づいた企業文化を醸成したりと、企業の持続力やブランド力を高めるためにも重要です。行動指針が定められていなかったり、「行動指針を変える必要がある企業の状態」に陥っていたりする企業は早急に対策を取る必要があります。
しかし、行動指針は作成すればそれですべてが解決するわけではありません。社内に浸透させて始めてその効果を発揮します。浸透していない行動指針はやがて形骸化してしまうでしょう。行動指針の策定は、企業を成長させるための手段の一つであり、策定することが目的ではないことを忘れないようにしましょう。