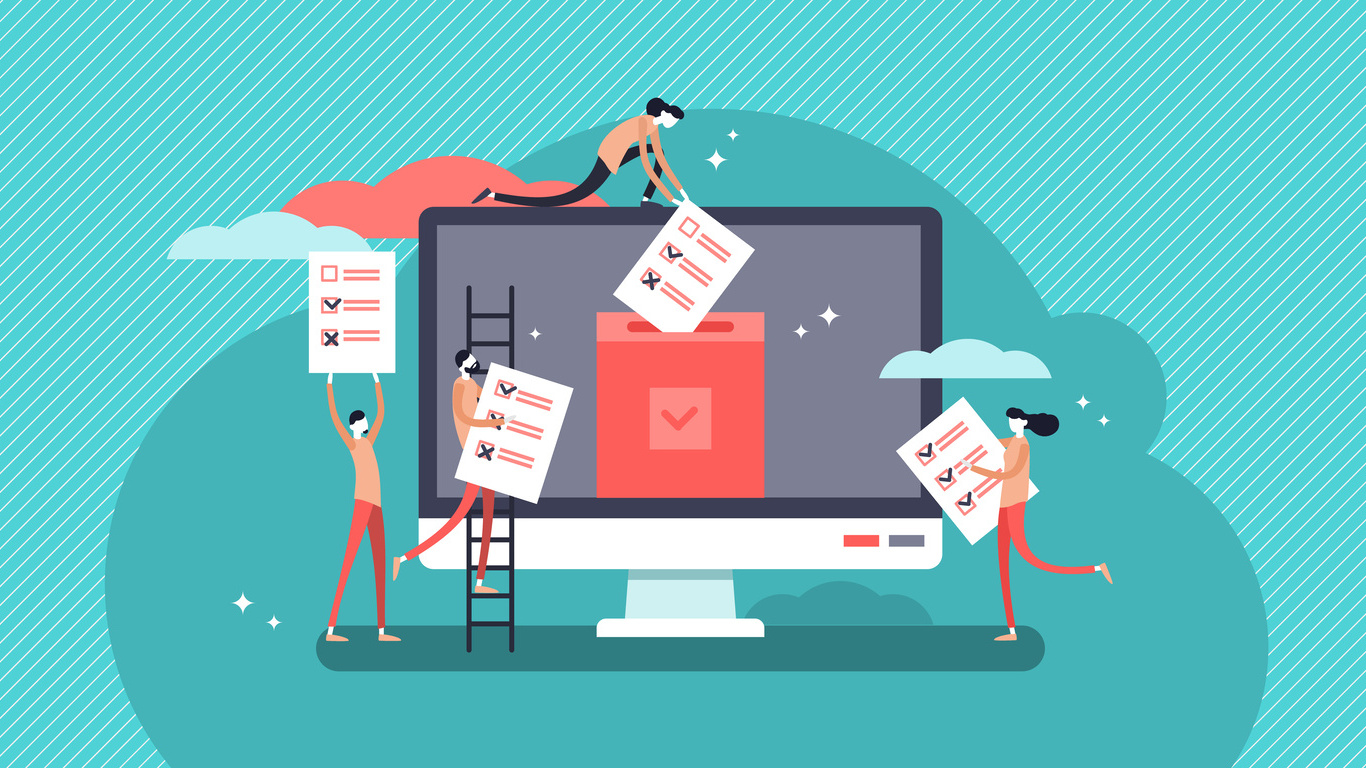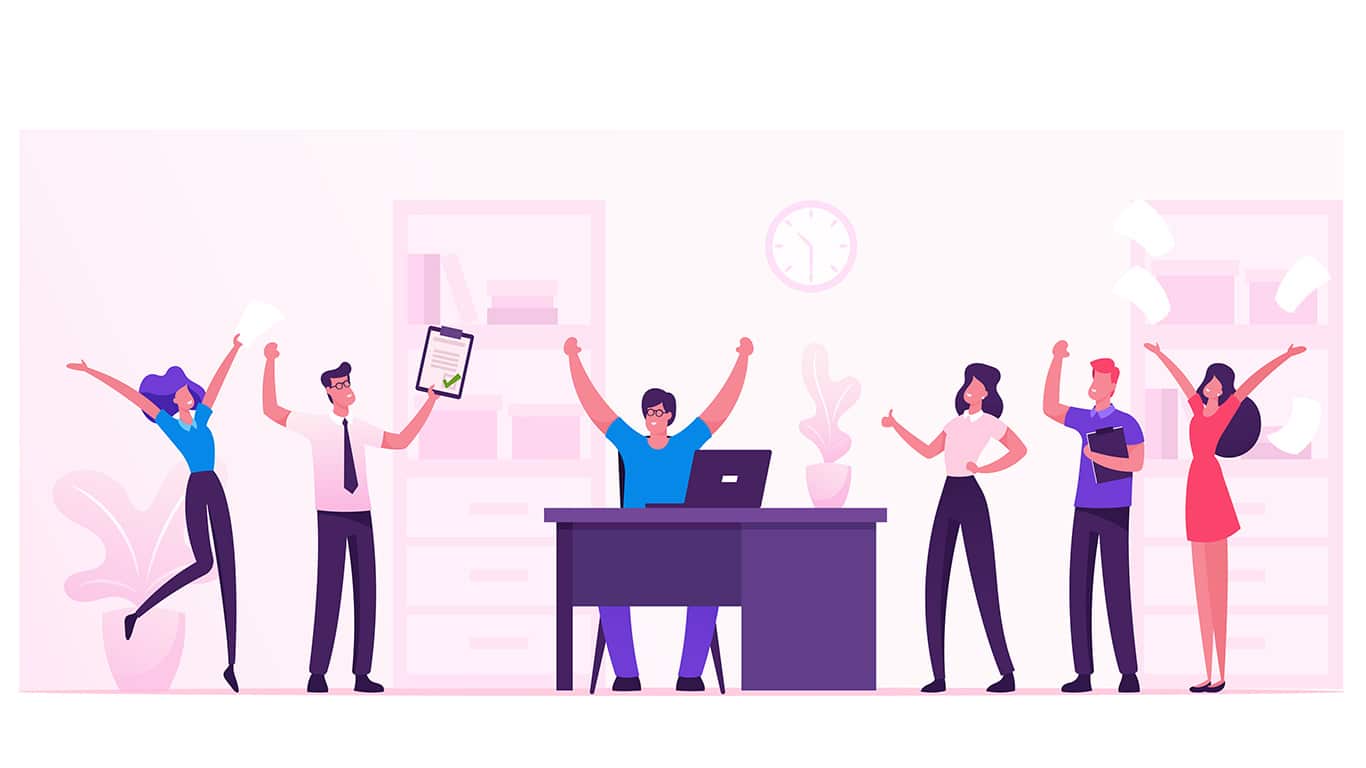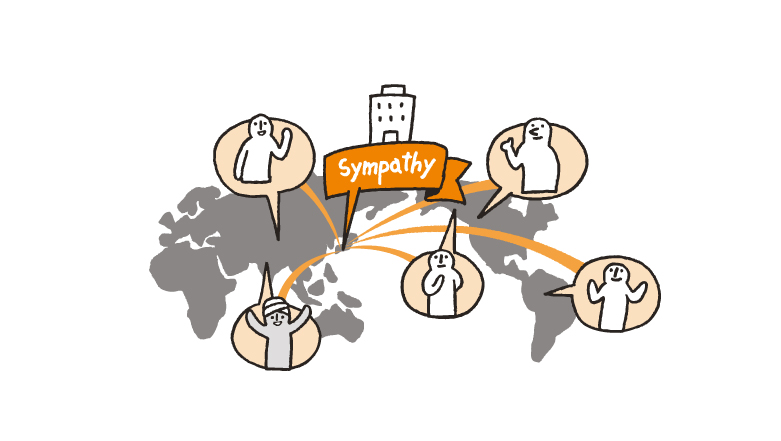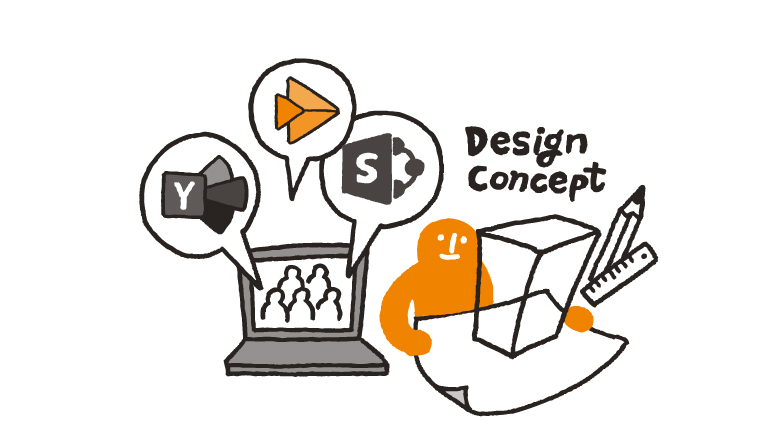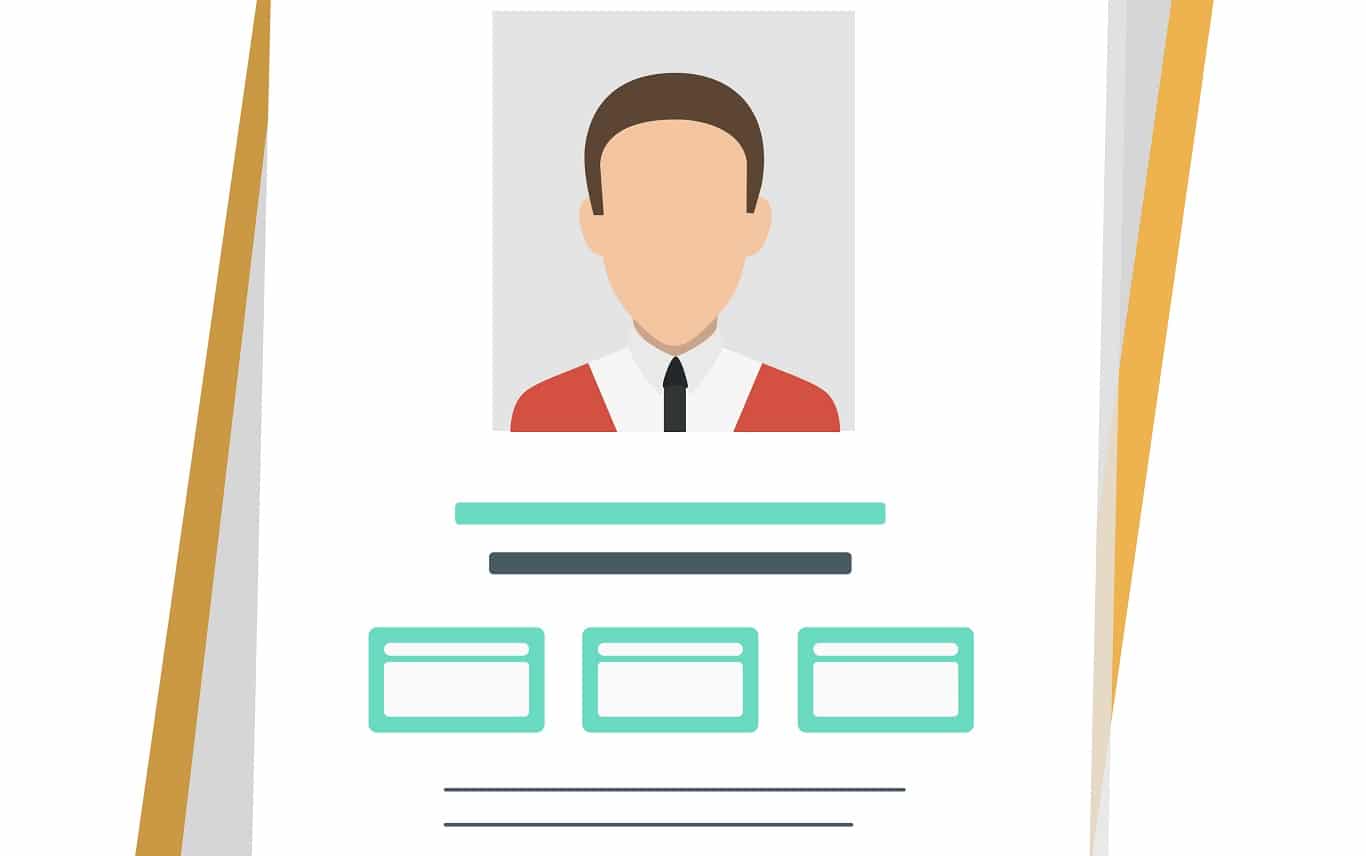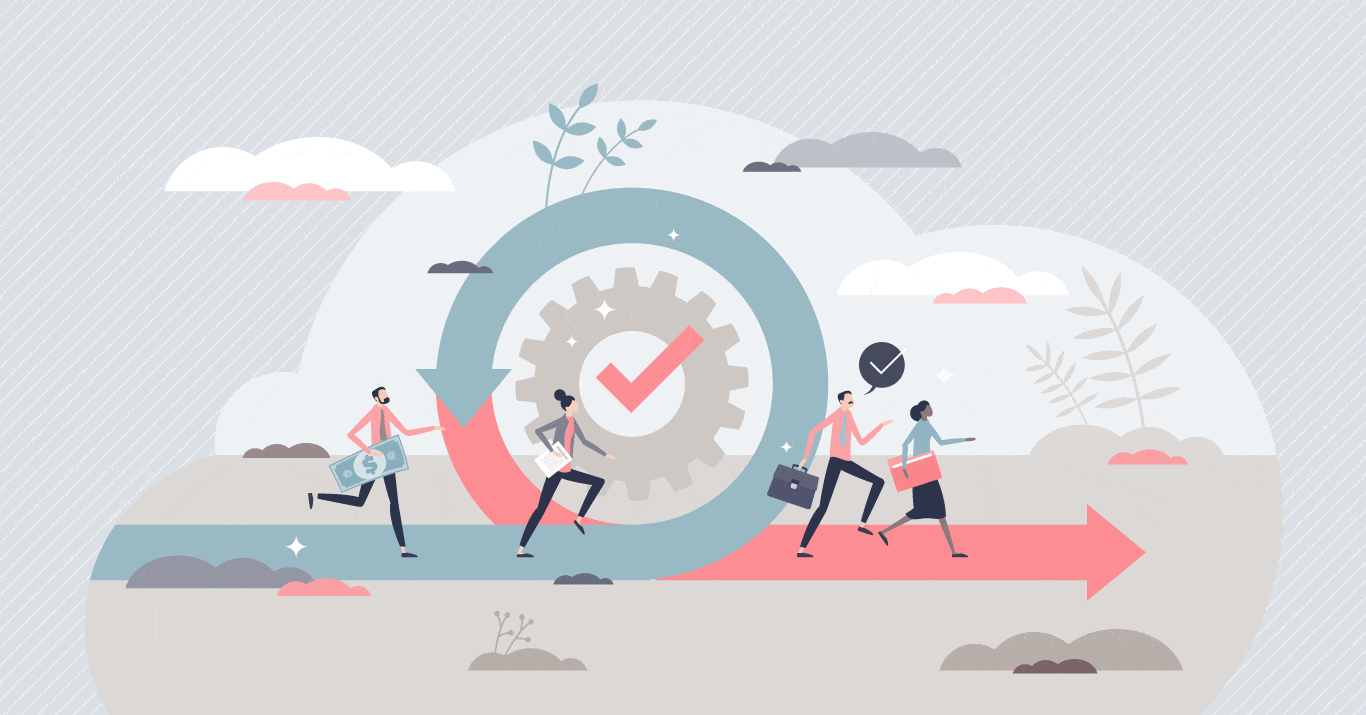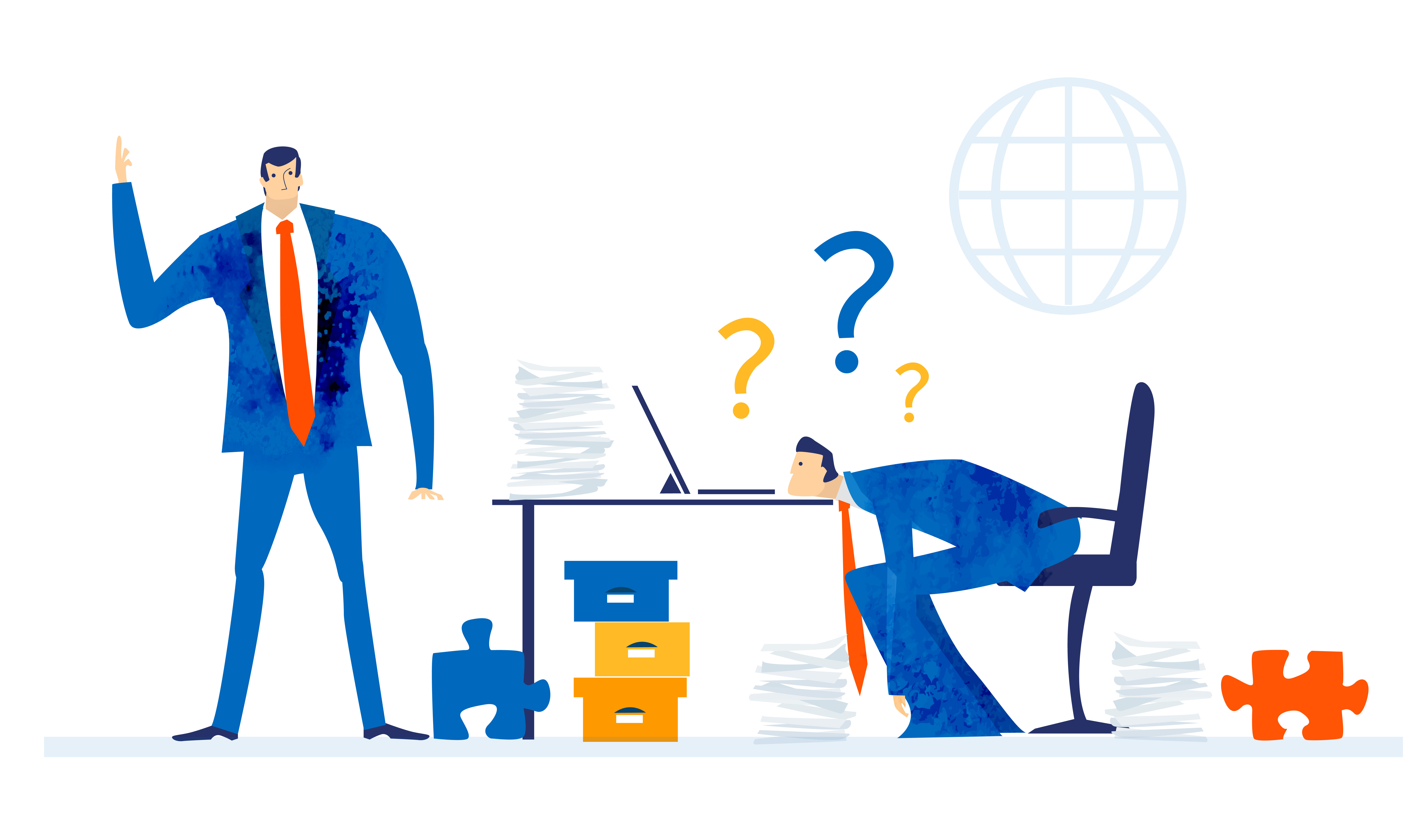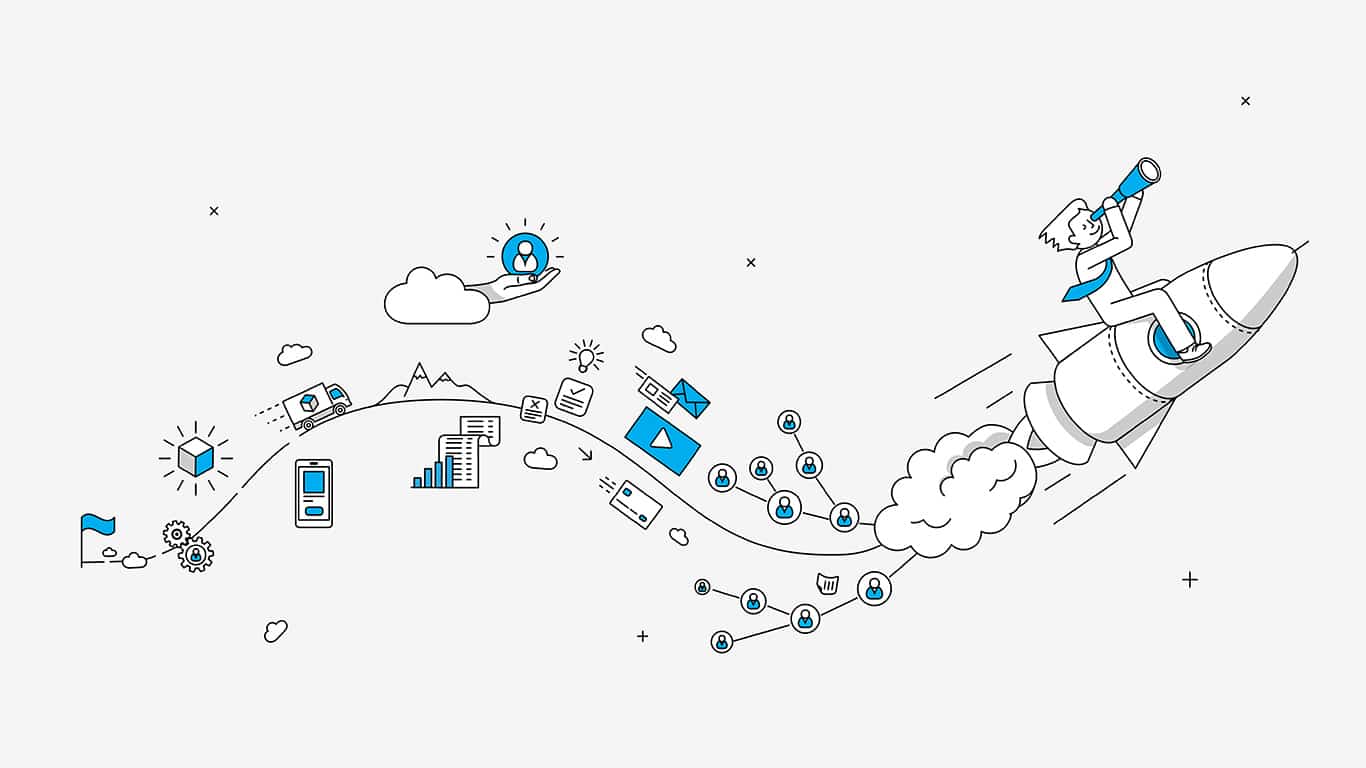インターナルブランディング の目的とは?定義や事例、具体的な手法を紹介
最終更新日:2023.06.12

目次
ビジネスにおいて「インターナルブランディング」というキーワードを聞いたことがある方も多いでしょう。インターナルブランディングは「インナーブランディング」と呼ばれることもあり、どちらも同じ意味で使用されています。
インターナルブランディングは企業のブランド価値を高める取り組みであり、社員のモチベーション向上や、会社の理念に沿った新事業の創造など、企業の成長に欠かせない効果が期待できる概念です。今回の記事では、これからの企業経営において重要な活動になる「インターナルブランディング」について、その目的や定義、具体的な進め方など、事例を交えながら解説します。
インターナルブランディングとは?
一般的にブランディングは、外部に向けて商品やサービス、自社の価値を伝える活動を指しますが、インターナルブランディングは社内(社員)に向けてブランディングを発信する活動を指します。ここでは、インターナルブランディングの、定義・目的・広まった背景についてそれぞれ解説していきます。
インターナルブランディングの定義
インターナルブランディングは、会社の理念や価値を明確にし、自社の社員に共感を促して企業のブランド価値を向上させる活動です。具体的な活動には、社内外の広報活動や教育活動のほか、報酬制度や人事評価制度などのシステム改革も含まれます。
インターナルブランディングにより従業員の自社に対する理解が深まることにより、商品やサービスの品質が向上し、ブランドイメージの改善や向上が望めます。さらに、外部に向けたブランディング活動とインターナルブランディングがバランスよく取り組まれることで顧客の信頼を獲得し、企業の理想的な姿に近づけることも示唆している概念です。
インターナルブランディングの目的
インターナルブランディングは、「ブランドや企業の目標を実現するために、目標実現に向けた行動を社員一人ひとりが自分事化すること」が目的です。企業活動で安定的に成果を生み出し、企業のブランド価値を向上させるためには、社員それぞれが自分の役割を理解し、目標・目的に向かって全員で足並みを揃えて活動する必要があります。
企業ブランディングは、商品やサービスのブランド化だけでなく、企業や組織の理念、ビジョン、価値観を社内に浸透させる「インターナルブランディング」と、顧客や消費者に向けたブランディング活動である「アウターブランディング」の2つがあります。
アウターブランディングは、顧客や消費者に向けたブランディング活動で、商品やサービスのブランド化や広告、PR活動などが含まれます。
インターナルブランディングにより、社員が企業や組織の理念やビジョン、価値観に共感すれば、社員と企業との強い絆を築くことができますが、近年では、インターナルブランディングは、企業や組織の在り方を外部にアピールするためにも重要な施策となっています。
つまり、企業や組織の存在意義や社会的責任、ステークホルダー向けのコミュニケーションなど、より深いレベルでのブランディングが求められているのということです。例えば、社会的課題を解決するためのコンセプトや取り組み(パーパス)、社員が共感しやすいビジョンを掲げることで、自社の存在意義を外部に示しながら、社員と企業の強い絆を築くことができます。
重要なのは、インターナルブランディングとアウターブランディングを同時に進め、一貫性のあるブランディングを実現することです。ただし、インターナルブランディングは、中長期の視点で展開する必要があり、人事評価やインセンティブへの安易な反映は避けなければなりません。あくまで、社内コミュニケーション施策として展開する必要があります。
インターナルブランディングが日本で広まった背景
昨今、インターナルブランディングの普及が日本のビジネスシーンで進んでいる背景には、時代の変化が関係しています。日本的な価値観や常識といったものがテクノロジーの進化と経済の悪化、コロナ渦といった出来事で崩れ、企業は旧来の経営手法では社員とのつながりを強め、自社の価値を高めることが難しくなりました。
ここでは、「働き方の変化」「人材の流動性」の2つの観点から、インターナルブランディングが日本で広まった背景と導入の理由について解説します。
社会ビジネスの変化と企業として安定性の確保
現代では、急速なグローバル化やデジタル化の進展、人口構成の変化など、事業や社会を取り巻く環境は大きく変化しています。このような変化に対応しなければ、企業は生き残りに苦しむことになるでしょう。しかし、企業の変化は、人や組織の変化が背景にあります。人と組織が不安定であれば、企業は変化に対応することができません。したがって、企業にとっても重要なのは、人や組織の安定性を保つことです。
ただし、企業に絶対的な安定性を求めることは不可能です。社会や市場が常に変化しているため、企業も変化しなければなりません。企業の風土やリーダーシップが、変化に対応するための基盤を作ります。企業は、人々の価値観を共有し、自己統制的な組織を作ることで、変化に耐えることが可能となります。また、多様な文化や国籍を持つグローバル人材やダイバーシティ人材を採用することで、変化に対応するためのリソースを組織内に確保することができます。
また、企業は変化に対応するために、パーパスや理念、存在意義を持たなければなりません。これらの概念は、企業がビジョンを持ち、社会的責任を果たすことを意味しています。組織がビジョンに共感し、共有することで、変化に対応するための強い目標を設定することができます。企業は、変化に対応するために、人や組織の安定性を保ちつつ、ビジョンに向かって進むことが必要です。
働き方の多様化
インターナルブランディングの目的は、企業と社員の価値観をすり合わせることで、どんな働き方の社員にも「働く理由」を提供することです。現代では、時代の変化により働き方が多様化しています。コロナ渦によるリモートワークの普及によってデジタルツールを活用したコミュニケーションが一般化し、企業と社員の関係性にも影響を与えるようになったため、企業と社員の価値観をすり合わせのることの重要性が高まっています。
具体的にはインターナルブランディングは、経営理念やパーパスの共感という意味で、求心性としての機能を持ちます。企業が社員に対して自社の価値観や理念を共有し、社員がそれに共感し、それを自身の働き方に反映することで、企業の理念や目的を達成することが可能です。このように、インターナルブランディングは、企業と社員が足並みを揃え、共に成長していくことを促進する役割を担っています。
人材の流動化
インターナルブランディングが日本で広まった背景には、人材の流動化もあります。昨今では終身雇用が崩壊しつつあり、良くも悪くも転職市場が活性化しています。つまり、現代のビジネスパーソンは自身のキャリアを重要視し、転職(キャリアチェンジ)する人が増えてきているのです。
雇用流動性が高まった現代において、優秀な人材を確保するためには企業は転職者に選ばれる会社になる必要があります。そのためには社員同士のつながりや目的意識を強固にすることが重要です。インターナルブランディングを行い、社員全員が同じ方向を向いて業務に取り組んでいることは、転職者が企業を選ぶ判断要素の1つになるでしょう。
また、あらゆる業界で問題視されている人手不足にも、企業と社員の関係性の変化が大きく影響しています。喫緊の課題は、若手の離職ではないでしょうか?
世界の大企業の創業期にこのような美談は事欠きません。世界を見なくても日本の大企業の黎明期に、名も無き社長の理念の数名の若者は物語はあちこちに見いだせる。自分にしかできない、この活動は自分達だけであるという認識は、その潜在力は発揮させ思ってみなかった自分を発見させる これこそ、洋の東西を問わず、わくわくする職場でしょう。若手の離職の遠因は、おもしろくもワクワクしない状態にあり、その礎は、企業のブランドであり思想哲学です。労働と対価の交換という状況に動機付けはされないでしょう。
企業が社員へ働く意義や価値を提供できなければ、人材の流出を止めることは難しいでしょう。インターナルブランディングを取り入れることにより、企業と社員の関係性を構築し直すことは全ての企業の課題です。
インターナルブランディングとインターナルコミュニケーション
インターナルコミュニケーションとは、組織内の従業員や部門間で情報を共有することを指します。
インターナルコミュニケーションは、経営方針や目標、業務内容や進捗状況、その他必要な情報などを、組織内の関係者同士で円滑に共有するために行われます。つまり、組織の運営に必要な情報を、組織内でスムーズに共有し、効率的な運営を目指すことが目的です。
一方、インターナルブランディングは、組織内の従業員に向けて、組織の存在意義や理念を伝えることを目的とした戦略です。具体的には、組織のブランドイメージを組織内に浸透させ、従業員に共感してもらい、組織の理念や目的に賛同し、組織を強化することを目的とします。従業員が組織のブランドイメージを共有し、それを外部に伝えることができるようになれば、組織のブランド価値を高めることができます。
ただし、実態としては、インターナルコミュニケーションとインターナルブランディングは、共通点も多く存在します。たとえば、情報を伝えるためのメディアやインフラには、イントラネットや社内報、冊子、動画、社内SNSなどがよく使われます。それらの情報媒体に対し、インターナルブランディングとインターナルコミュニケーションを分けて運用するのではなく、連携しながら進めているというのが現実です。
最近では、インターナルブランディングの干渉部門が広報やマーケティングが、広報部やブランディング部門だけでなく、人事経営企画情報システム部などインターナルコミュニケーションやインターナルブランディングの活動に参加することが増えています。
インターナルブランディングのメリット
インターナルブランディングには、企業ブランドの価値を作る以外にも、目標達成の過程でいくつかのメリットを享受することができます。ここからは、インターナルブランディングにおけるメリットについて解説していきます。
社員の企業への理解共感が深まる
インターナルブランディングによって、社員は自社の価値や理念への理解を深めることができます。現代では企業の存在意義や姿勢が、社員を引きつける重要な要素となっています。しかし、企業の存在意義や経営理念は、簡単に理解できる内容ではない場合が多くあります。そのため、共感するためのコミュニケーションが必要であり、そのコミュニケーションがない場合は、誤解が生じる可能性があります。
また、経営理念は、固有技術や製造系の企業であれば、その存在意義を明確に打ち出すことが多くあります。メーカーであれば、自社特有の事業活動の領域である「食」や「アミノ酸」を示すことで、絶対的な差別性を生み出すことが可能です。これにより、投資や人材、技術、情報などを効果的に集約することができます。理念は、事業及びコアコンピテンシーを踏まえた上で、どんな人に、どんな評価や賃金、処遇をするかという根本的な考え方に影響を与えています。
人は感情や心で動く生き物であるため、自分が働いている企業の理念や目的を理解し、その価値の共有によって発揮される力は想像を超えるものです。インターナルブランディングによって得たモチベーションの向上は、外圧ではなく内発による動機を高めてくれるため、社員の質の高いパフォーマンスを引き出してくれます。
さらに、自社を理解することで社員同士の一体感が増し、組織としてのパフォーマンスも向上させてくれます。その結果、働いている時間が充実し、社員の満足度の向上にもつながるでしょう。
社員同士のつながりが強くなる
インターナルブランディングによって企業の価値観が社内に浸透し、理念への共感が深まると社員は自社で働いていることに愛着を持つようになります。すると愛着のある自社で働く同僚に仲間意識を持つようになり、働くモチベーション向上につながります。
とくに、日本企業は「家族主義」などの関係性を重視する傾向があります。これは、経済合理性と人間性精神性のジレンマに対する安全弁として機能するためです。
しかし、最近では関係性そのものが、サービスやイノベーションを産み出す根源であり、組織が創り出すものに価値があると考える企業も増えています。社員一人一人の能力や集団組織における基礎として、関係性の理念が最も重要な位置づけをされているのです。
インターナルブランディングによって社員同士のつながりが強くなると組織としての連携が強化されるでしょう。それは大きな困難を乗り越える原動力になり、目標達成に向かって一丸となって取り組むための力となります。その結果、良いパフォーマンスが発揮されて成果につながり、さらに自社への誇りと愛着が増す好循環を生むことができるでしょう。
社員の定着率が上がる
インターナルブランディングによって、社員が自社に対して帰属意識を持つようになると、社員の定着率が向上します。自社の価値観が社内に浸透・共有していると、それ自体が働く動機付けとなり、価値観に共感している人材が離職しにくくなるためです。
理念は、組織内での個人の自己正当化や、団結のために重要です。また、問題解決にも役立ちます。しかし、理念は抽象的な内容が多いため、個人によって解釈が異なり、組織内外での対立が生じることがあります。経営者は多義性や異なる解釈の可能性に配慮しなければなりません。共通認識を深めるために、インターナルブランディングを行うことが大切です。
また、インターナルブランディングは採用においても効果を発揮します。自社の価値観が社内に浸透している企業は、組織全体で目指している方向性が明確です。自社が目指している方向性を軸にした採用活動を行うことで、求職者との価値観のすり合わせをスムーズに進めることができるでしょう。
コンプライアンスへの意識向上
インターナルブランディングによって社員が自社への誇りと愛着を強く持つようになると、自社を守るため社員一人ひとりが自然とにコンプライアンス遵守に努める違反をしないようになります。
企業が掲げる「理念」とは、組織が共有する考え方や価値観のことを指します。これは、組織や社員がどのような行動や価値観を持つべきかの基準となり、現場の行動や言動に影響を与えます。インターナルブランディングによる理念の浸透によって生まれるコンプライアンス遵守の意識は、管理による意識付けではなく、個々の社員が持つ自社への積極的なコミットメントを軸にしています。
現代では、組織や社員は、社会において公器としての役割を持つため、一般社会の価値観と乖離しないように配慮しなければなりません。
また、SNSなどメディアの発達により、いつどこで自社がコンプライアンス違反を指摘され、炎上などに陥るかわかりません。そういった時代だからこそ、インターナルブランディングによる自社への誇りと愛着をベースにした、社員各々がコンプライアンス遵守の意識を持つような働きかけが重要になっています。
インターナルブランディングのデメリット
ここまで、インターナルブランディングのメリットについて詳しく解説してきました。
一方で、インターナルブランディングにはデメリットも存在しています。デメリットを理解したうえで、自社に合った取り組みを実施することが求められます。
効果が表れるまでに時間がかかる
インターナルブランディングは、取り入れたからといってすぐに効果が表れるわけではありません。社内に企業理念や価値観が浸透するまでは時間がかかるため、中長期的な視点で計画的に施策を進めていく必要があります。
自社の現状を把握し、目標とする企業ブランドをゴールに設定して、施策を実行するサイクルを定着させることが重要です。施策を進める際には、定期的に目標の見直しや評価を行い、軌道修正しながら中長期の視点でインターナルブランディングを進行させます。
経営理念は企業の方向性を表す抽象的な考え方であり、実際の仕事とは異なるものです。
しかし、仕事をする上では理念に従う必要があります。一例を挙げると、残業を減らすことが必要だと言われた場合に、理念と矛盾すると社員が企業に疑問を持つことがあります。そこで、経営者は社員に適切に説明し、理念と実務のギャップを埋めるためにコミュニケーションを取る必要があります。また、経営者は常に理念を見直し、実務に適切に反映させることが大切です。
そのような取り組みを通して、社員が自社の理念や価値観を理解し、「自分ごと」として行動が少しずつ変って変わっていくことでインターナルブランディングの目的を達成することができます。
価値観の合わない社員が離職する可能性がある
インターナルブランディングは社員の強いコミットメントを生む反面、自社の価値観とは合わない社員の離職を招いてしまう可能性があります。
当然ですが、社員全員が企業の理念や価値観に共感できるわけではありません。それぞれに主義主張はありますし、キャリアへの考え方も違うものです。インターナルブランディングによって自社の価値観への共感を促すことには多くのメリットがある反面、社員の価値観とは合わなかった場合、離職につながる可能性があります。
採用の現場で「カルチャーフィット」という言葉が、採用担当のキーワードになっています。簡単に言えば、自社に文化にあうかどうかという判断を面接の中で、基準として持っているという事です。組織文化は、価値観と強い影響関係にあり、社員の考え方や価値観は、組織の文化に影響し、または組織文化が、良くも悪くも入社する社員に影響するという事です。朱に交われば赤くなるという事です。
企業の経営理念は、組織の目標や方向性を示す重要なものです。ただし、理念に固執しすぎると、新しいアイディアや視点を排除してしまい、組織の成長を妨げることになる場合があります。
また、理念は権力やパワーの側面も持っているため、正当化のために誤った行動をすることもあります。
このような問題を解決するためには、柔軟性や多様性を持って理念を捉え、コミュニケーションを通じて議論し、多様な視点を取り入れることが大切です。
体験と解釈の齟齬
企業の経営において、単純な数字や事象に固執すると、経営理念から乖離してしまうことがあります。そのため、経営理念に基づいた学習が重要であり、事象や結果をどのように解釈するかという根本的な考え方で振り返ることが必要です。経営理念は、企業活動や結果を見直す際の指針であり、共感することで社員や組織の学習につながります。
たとえば、前年より数字が上がったことは良いように見えます。しかし、数字だけを見るのではなく、経営理念やビジョン、パーパスに照らし合わせて考えるとどうでしょうか。
企業の業績が経営理念に合致するかどうか、ビジョンやパーパスに則っているかどうかを検証することが重要です。
また、現場で上位概念の解釈を確認することで、社員の意識を高め、学習の基盤を築くことができます。経営理念を浸透させることは、企業の長期的な発展にとって重要な要素の一つであり、経営者は常にこれを意識する必要があります。
インターナルブランディングが必要な企業
では、具体的にインターナルブランディングが必要な企業にはどんな特徴があるのでしょうか。ここでは、インターナルブランディングを取り入れるべき企業について解説します。
グローバル企業である
グローバル企業の場合、インターナルブランディングの必要性は高くなります。理由としては、グローバル企業では「ジョブホッピング」と呼ばれる比較的短期間での転職が珍しくなく、様々な背景を持つ多様な人材が出入りすることが当たり前であるためです。
雇用流動性の高さから社員同士や企業と社員の足並みを揃えることが難しく、その結果企業ブランドが揺らぎやすい実情があるため、インターナルブランディングを取り入れることによってブランドを確立し続ける必要があるわけです。
フランチャイズや支社等がある場合、地域性やその土地の文化に即した形でローカライズするケースもありますが、基本的には本社が企業ブランドの方向性を打ち出すことが重要視されています。
成熟した大企業である
巨大な組織に成長した大企業こそ、インターナルブランディングが必要になると言われています。企業規模が大きくなるほど、より多くの案件・事業を統率する必要が出てくるため、リソースが管理業務に割かれるようになっていきます。
その結果、大企業ほど新規事業や創造活動といったチャレンジが後回しになり、現状維持の状態になってしまいがちです。目の前の社内の管理業務ばかりを優先し、将来への投資や成長機会を逃し続ければ、企業は衰退していくことはまちがいありません。
トップダウンの管理体制の経営に無理が生じてきた時こそ、インターナルブランディングによって企業の理念や価値観を社員に浸透させ、事業部門へ管理権限を委譲し、上層部のリソースを確保して企業として新たな挑戦に取り組むことが重要になります。
事業内容が多岐にわたる企業である
「この会社といえばこの商品(またはサービス)」のような、PRによって社外から強いイメージを持たれる企業が存在します。そういった企業でも事業内容が多岐にわたる企業である場合、社外の企業イメージとは異なる業務に従事している社員も多いため、担当する業務に価値を見いだせない社員もいることでしょう。
このような企業は複数の事業を合理的に進めている反面、構造的にサイロ化を生み、部門間の連携や企業と社員のエンゲージメントに弊害を生みます。事業計画としての戦略性は正しくても、働く社員の人間関係やメンタリティにプラスに働いているとは限りません。
そこで必要になるのが、社員が企業の理念や価値観を共有できるようになるインターナルブランディングです。
インターナルブランディングによって社員の認識や方向性の足並みを揃え、企業にコミットし業務に愛着を持てる状態を作り出すことにより、社内の連携の質を上げ、社員各自のモチベーションアップにもつなげることが期待できます。
離職率が高い企業である
離職率が高い企業も、インターナルブランディングを取り入れることによる改革が必要でしょう。離職率の増加の背景には、社員のモチベーションの低さが影響している場合もあれば、社内の風土や評価制度に不満を感じている場合もあります。また、離職率の高さには採用のミスマッチが起こっている可能性もあり、入社前の印象と入社後の実態との乖離が、社員の企業へのコミットを低下させている要因になっていることもあります。
離職率の高さは理由が複数あることが想定されるため、社員へのアンケートを実施するなどし、ヒアリングをもとに道筋を立てて社員目線での解決策を考える必要があります。こうした離職率の改善を行う際にも、インターナルブランディングは施策の中心核として役立つ概念だと言えるでしょう。
インターナルブランディングを推進する際の流れ
ここからは、企業がインターナルブランディングを推進する際の流れについて解説します。大きく5つの段階に分けて取り組んでいきます。
調査する(現在の課題を明確にする)
インターナルブランディングを行うにあたっては、まずは企業の現状を把握することが大切です。現場の人々が自社に対して抱く悩みや思いを収集し、社内の状況を多角度的に分析・理解することが必要です。
そのためには、社員と向き合って話を聞く機会を設けることが重要で、表面には表れにくい社員の本音や価値観を対話的なコミュニケーションによって引き出さなければなりません。さまざまな価値観やモチベーションの社員がいることを知り、傾向を把握することで、社内の課題を明確にして施策を打っていきます。
定義する(目標となる理想の姿を描く)
調査が完了したあとは、実際に目標となる企業ブランドの理想の姿を描いていきます。
そもそもブランドとは、商品やサービスの差別化を図るためのもので、ネーミング、デザイン、キャッチフレーズなど、複数の特徴が複雑に絡み合い、独自性となって魅力を発揮する抽象度の高い概念です。企業そのものをブランド化する場合はとくに難解で、商品やサービスだけでなく、社風や軸足の事業以外の活動も企業ブランドのイメージに付随してきます。
インターナルブランディングによって社員が自社のブランド価値を高めるための行動について考え、自社の成長や変化を自分ごととして捉え、強い責任感を持って業務に取り組んでもらうためには、企業ブランドの理想の姿を定義して目標をはっきりさせることが重要です。
戦略を立てる(目標達成までの計画を立てる)
次に、定義した企業ブランドの理想の姿を企業の理念や価値観に落とし込み、社内へ浸透させて企業全体で足並みを揃えるための計画を立てます。
インターナルブランディングはその難解さから、施策を打ってから目標達成を果たすまでに、ある程度の年数を要してしまいます。企業ブランドの目標は短期間に達成するのではなく、年単位での取り組みになることを社員全員が理解し、継続的な活動として進められる戦略を立てることが重要です。
長期計画として取り組むことにより、目標達成までに起こる中だるみや目標の破綻といった、計画の障害を防ぐことができます。
可視化する(目標と戦略を社内に浸透させる)
目標と戦略が決定したら、それらを社員1人ひとりが把握できるように可視化する必要があります。企業の理念や価値観を論理的に整理して伝えるだけでなく、感情に訴えかけるなど、社員を尊重する対話的なストーリーを活用して発信することにより、共感を生み出します。
企業側が一方的に自社の理念や価値観を伝えるだけでは、個々の社員の意識を改革し、企業の足並みを揃えることは困難です。企業と社員が一体化し、インターナルブランディングを達成するためには、社内報やイントラネットで企業の理念や価値観を言語化して発信し続けることに加え、社内表彰やセミナーといった社員参加型の双方向のコミュニケーションを通して繋がりを感じてもらい、社員に企業への愛情と愛着を持ってもらうことが大切です。
目標と戦略の可視化とは単に言語化するだけでなく、企業への愛情や愛着といった感情的な体験も含まれている、ということを見失わないようにしましょう。
行動する(業務改善、人事評価制度の見直しなど)
社員が企業の理念や価値観を理解し、自分ごととしてしっかり意識を持つことができるようになったら、次は行動に移してもらうフェーズに入ります。
業務に企業の理念や価値観を反映させていくように指示・業務フローを作成したり、価値のある企業ブランドを獲得することに向け、個々の社員やチームが貢献する取り組みをした際に評価できる人事制度を整えたりしていきましょう。
たとえば人事評価の項目として、インターナルブランディング達成に向け、部署別に取り組みの成果や達成度に関して自己評価できる仕組みを設けている企業も存在します。具体的には、1on1ミーティングで上司が社員に評価を伝えたり、サンキューカードをコミュニケーションに取り入れたりすることにより、感情的な繋がりを促進しながら評価を伝える方法が挙げられます。
インターナルコミュニケーションを行う
企業ブランドを確立するためには、企業と社員の双方向の対話を実現するインターナルコミュニケーションにより、社員のコミットメントを高めておくことが重要です。ここからは、インターナルコミュニケーションを行うための方法について解説していきます。
社内システム(ツール)を使ったコミュニケーション
社内での情報交流には、さまざまな媒体を活用することができます。ターゲット社員に応じて複数の媒体を使い分けたり、組み合わせて(クロスメディア)コミュニケーション展開をすることで効果的に情報を伝えたり、現場の意見を集めたりすることができます。
社内報
一昔前までは冊子の社内報が主流でしたが、社内報をデジタル化する企業が増えています。さらに、後述するイントラネットやSNSと組み合わせることで、一方的な情報発信ではなく、オンライン上で議論や交流を促すことができるようになったことも大きな変化です。
イントラネット
イントラネットとは、社内に限定して利用できるネットワークです。業務に関する書類を収納する場として機能し、ポータルサイト上から社内のさまざまな情報にアクセスすることができます。
また、ポータルサイトに掲示板やコメント機能などを持たせたシステムが多く採用されており、アップロードした情報に対して社内のコミュニケーションを生み、意見・情報交換ができるようになっています。
ビデオコミュニケーション
インターネットの普及に伴って動画の利用が一般化されましたが、企業内における動画を介したコミュニケーションも当たり前となってきました。動画で伝達するメッセージはテキストと比較すると圧倒的な情報量を持ち、人の表情や身振りなどにより動的なコミュニケーションを取ることができます。
動画によるメッセージは、経営トップによる社員に向けたメッセージの発信、近く発表される新たな自社商品やサービス、業務に関わる法令改正といった、全社員が周知すべき事柄を動画にして配信するケースなどがあります。
社内SNS
Microsoft Yammerのような、グループウェアを利用した社内SNSを導入する企業も存在します。別のメディアコミュニケーションと組み合わせることにより、企業が発信した情報に対してオンライン上のコミュニケーションを活発化することができる点が、社内SNSの利点です。
また、新サービスなどの自社情報に社員がキャッチアップできるよう、FacebookやInstagramなど、対外向けに情報発信している自社アカウントのフォローを社員に勧めるケースもあります。社内SNSは、社員同士のコミュニケーションの活性化と情報伝達の速度と数を高めることができるツールで、インターナルコミュニケーションにおいては、とくに活用したい社内システムの1つです。
対話集会
経営陣と社員とが情報を共有する場として設けられる集会で、タウンホールミーティングとも呼ばれます。
自社の業績結果や年度目標の共有など、経営層から社員に対してトップダウンの情報発信を行うだけでなく、経営層にとっては、社員の意見を参考にできる機会であると同時に、社員に向けて企業の理念や価値観を浸透させるチャンスでもあります。
一方通行のメッセージの伝達ではなく、ディスカッションや質疑応答の時間を設けることにより、社員との双方向の意見交換を行う場とするのが対話集会です。
Zoom等のWEBカメラツールを使えば、オンラインで大人数の社員に参加してもらって開催することもできます。
社員参加型イベントの実施
イベントでは上司や部下、チームメンバー以外の顔を知る機会になり、普段の業務では関わりのない斜めの関係を築くことができます。
「社内表彰」は、社員の頑張りに感謝を伝え、労うことと同時に、貢献した業務に対して表彰という形で評価を寄与できます。上層部や同僚たちに表彰された社員が認知されることはもちろん、普段関わらない部署やポジションの社員同士がコミュニケーションを図る場としても機能します。
また「社内研修・グループワーク」では、スキルの伝達や課題解決といった目的を果たしつつ、部署の垣根を超え同じ場に集まった社員同士がコミュニケーションを取ることにより、新たな繋がりを作ったり、相互の刺激によって仕事への意識の高まりや新たな発見といった、ポジティブな影響を生み出すことが期待できます。
1on1ミーティング
「1on1ミーティング」も、インターナルコミュニケーションの1つに挙げられます。1on1ミーティングとは、上司と部下が1対1で対話する機会を定期的に設けることで、プライベートの話から仕事における悩みまで、上司が部下の悩みを幅広く聞くミーティングを指します。
「1on1ミーティング」の利点は、上司と部下が1on1の濃密なコミュニケーションを取ることにより、社員それぞれの悩みや価値観にコミットした上下の関係性を作ることが出来る点です。一対一だからこそ話せる内容は多く、大人数の場では言いにくい内容だからこそ、より重要で解決すべき課題・問題が隠れているケースが多いものです。そうした話が聞ける状態は、インターナルブランディングを実現するためにも必要でしょう。
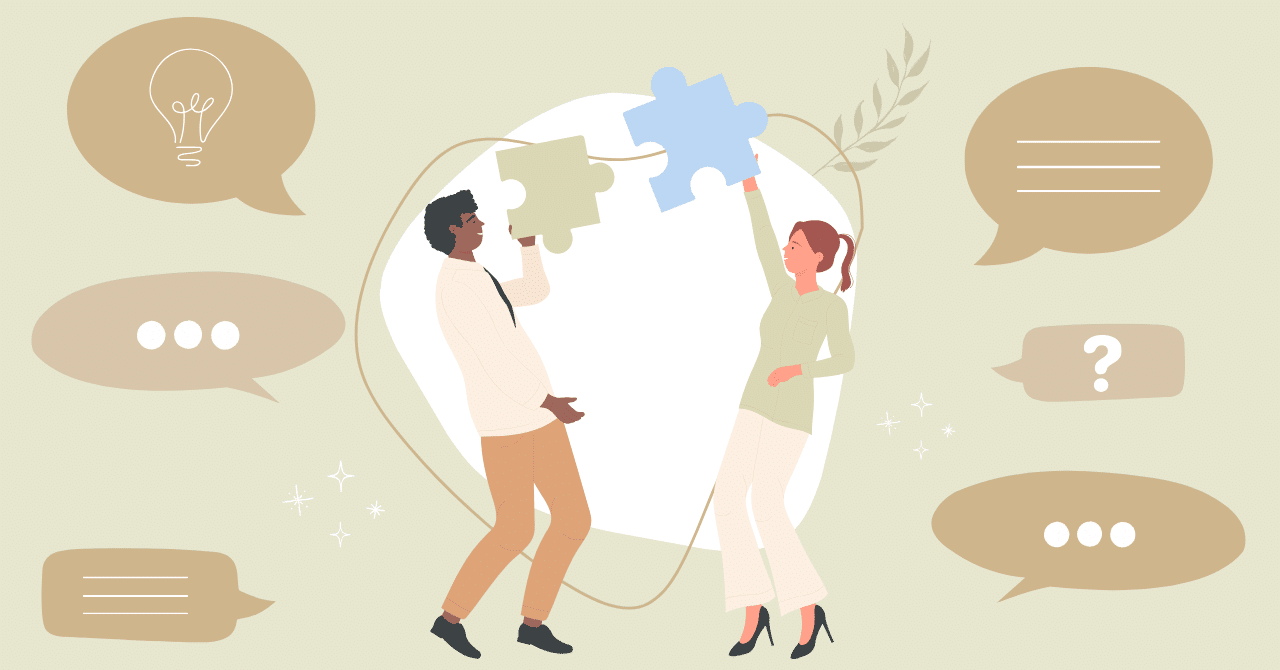
1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介
最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…
オフィス環境を整える
インターナルコミュニケーションは社員同士のやり取りだけでなく、「オフィス環境の整備」を使った方法もあります。何となく配置されているオフィスのデスクや棚といったレイアウトですが、上手く配置すると社員のコミュニケーションを促進させることができます。
たとえば、デスクを四角から丸状のものに変更したり、思い切って配置を変更してみたり、誰でも利用できるデスクや棚を設置してみたりと、空間デザインによって社員の行動を意図的に変えることは、実は企業が社員に向けたインターナルコミュニケーションの一端です。
人間はちょっとした環境の変化で行動が変わってしまう生き物で、その習性を上手に活かすことが出来れば、半分無意識の状態で社員に有用な行動を起こしてもらうことができます。
匿名のアンケート調査
「匿名のアンケート調査」も、インターナルコミュニケーションの方法になります。大勢の前や「1on1ミーティング」では伝えにくい本音を抱えている社員もおり、匿名によってそうした社員から本音を引き出すことができるのが「匿名のアンケート調査」です。
内容は大きく分けて2つで、業務上の不満・問題についてか、社内の人間関係の悩みが主な調査対象になるでしょう。匿名による率直な意見を集めることにより、社員が働きやすい環境を再構築する際の情報として役立てることができます。
インターナルブランディングの事例
実際にインターナルブランディングを活動に取り入れ、企業ブランド確立に繋げている企業が存在します。「株式会社西武ホールディングス」「日立製作所」「ライオン株式会社」の、3社の成功事例について見ていきます。
株式会社西武ホールディングス
1つ目は、株式会社西武ホールディングスの事例です。西武グループでは、現場の風土改善という大きな課題を抱えていました。
活動の手始めとして行われたのは、グループビジョンの策定です。社員全員へのアンケート調査を通してあらためて企業の理念を見つめ直し、スローガンである「でかける人を、ほほえむ人へ。」という理想を策定し、目指すことが決定されました。
インターナルコミュニケーションにおいても、社内表彰やミーティングなど様々な活動を行いましたが、中でも効果を発揮した取り組みが「ほほえみFactory」です。「ほほえみFactory」はグループ各社同士の連携を流動的に行うことを目的としており、毎年グループ各社から派遣された30人ほどが集まり、3~5日間を一緒に過ごします。集会の中では、グループ各社が今後取り組むべき施策などをディスカッションし、結論がまとまったらグループ各社の社長に提案します。
この活動は、これまでのべ300人以上の社員が参加しており、この集会で出たアイディアが施策として採用され現実化した例もあります。切り離されていたグループ各社の社員が客観的な意見を出し合うことで改善策を導き出すという、コミュニケーションを活かした取り組みの好例であると言えます。
こうした一連の施策を通して現場の風土改善を果たし、西武ホールディングスは2014年には東証一部上場を果たしました。インターナルブランディングの成果といえる動きが、実際に現れた事例です。
日立製作所
2つ目は株式会社日立製作所の事例です。日立グループは2004年に、「Inspire the Next」というコーポレートスローガンを制定しました。グループを構成する約900社もの企業の団結を促すべく、「日立」の掲げる価値観やアイデンティティをグループ全体に浸透させる試みです。
活動の1つに、グローバル規模で行う表彰制度があります。毎年行われている取り組みで、日立ブランドの価値をとくに高めた活動に対し、世界を6地域に分けて地域ごとに表彰します。
表彰式では、6地域それぞれの受賞チームの代表者に日本の拠点に集ってもらい、受賞後は受賞チームの代表に日本で日立の歴史やブランドに関する教育を受けてもらいます。
帰国後は、教育を受けた彼ら自身が日立の理念や価値観を伝えるコーチとなり、自社の従業員に働きかけることによって、世界各国に点在するグループ全体により深く日立ブランドを浸透させることを実現させています。
また、受賞者たちの活動は、物語仕立てにして読み物になっていたり、動画にまとめたりされて誰でも見ることができるようになっています。従業員のモチベーションアップや、日立の理念や価値観への理解を深めることができるツールとしても役立っている好例です。
日立グループは、とくにインターナルコミュニケーションに力点を置き、価値のある企業ブランドを作り上げることに成功した事例だと言えるでしょう。
ライオン株式会社
3つ目はライオン株式会社の事例です。同社は年1回、社員に向けて「コーポレートブランディング活動に関するアンケート調査」を行っています。
取り組みの理由は、お客様に「ライオン」の価値を理解してもらうためには、まずは社員に「ライオン」の理念や価値観に共感してもらうことが重要であると考えたためです。「ライオン」と社員が互いにリスペクトし合い、社員全員が一丸となって足並みを揃えないことには、お客様に「ライオン」の本当の価値が伝わらないと結論付けました。
2013年から毎年地道に調査を続けることで、社員の間での企業ブランドの浸透度・共感度が徐々に上がっていきました。その後、業務体制や仕事の方法が変わり、生産的で価値を生みやすくなったという成果や、社員の足並みが揃ったことで方向性が定まり、ニーズを突いたヒット商品の創出にもつながったといいます。
「ライオン」の成果は、たった年1回の社員へ向けたアンケート調査でも、インターナルブランディングをしっかり意識した取り組みであれば成果に繋がる事例だと言えます。
企業ブランド(自社らしさ)を作ることは大切
インターナルブランディングを通して、自社らしさを作ることは重要です。昨今のブランディング戦略では、商品やサービスそのものではなく、企業自体のブランディング化がポイントとなります。
企業ブランドを確立して「自社らしさ」を持ち、消費者、取引先、株主、社会、社員と、企業を支える多くのステークホルダーに共感・支持されることで、事業やさまざまな活動をする際の原動力になることは間違いありません。
価値のある企業ブランドを確立するためには、まずは自社の社員に理念や価値観を理解・共感してもらい、日々の業務に反映してもらう必要があります。企業ブランドが確立できない企業は、いつまでも商品やサービスのブランドに頼り、過去の成功に執着し、新たな価値やサービスの創造といった、挑戦的な事業展開も難しくなってしまうことでしょう。
これからの企業に必要なのは、企業ブランドを確立し、自社を支える複数のステークホルダーとの繋がりを密にし、他企業や他商品・サービスのブランドとの違いを整理して明確化することによって、自社らしさを世界に発信することです。
インターナルブランディング推進する上での注意点
企業が長期間存続し、大きな規模になると、その理念や価値観が形式的なものになってしまい、社長室に飾るだけのものになってしまうことがあります。
しかし、企業の業務や制度は、その理念や価値観から派生しているため、社員は入社時から企業の理念や価値観の影響を受けています。
理念や価値観が形骸化し、その効力が停滞している企業は、どういった点に注意しながらインターナルブランディングを取り入れればよいのでしょうか。
経営理念はアップデートされ続けていることを知る
企業はインターナルブランディングを活用して、理念や価値観を社内に浸透させる必要があります。しかし、そこで注意しなければならないのは、個々の社員や部署によって、企業の理念の解釈が軽微に異なることがあるという点です。
これは、現場の社員がアップデートされた理念や価値観を自分たちなりに解釈して、業務に活かしているためです。このような場合、現場で解釈している理念や価値観が企業全体に浸透していないため、トップ層や経営陣が認知できていないことが少なくありません。この問題を解決するためには、トップ層や経営陣が、現場の社員と対話をして理念や価値観のアップデートを確認し、社内に共通の理解を持たせる必要があります。
現実に即した活動を軌道修正しながら進めていくことが重要
企業にとってフォーマルとは、公式で正式な意味を持ち、コーポレートサイトや報告書などに記載された企業の理念や価値観のことを指します。一方、インフォーマルとは非公式なことを表し、企業がフォーマルに宣言したことが必ずしも実際の活動に反映されているとは限りません。時代や経営事情の変化などがあり、理念や価値観と実態が一致しないこともあります。
インターナルブランディングを取り入れた企業でも、このような現象が起こることがあります。企業ブランド化を成功させるためには、理念や価値観を軸に、現実に即した活動を軌道修正しながら進んでいくことが重要です。
理念には権力やパワーがあることを知る
企業の理念や価値観は、その企業の目指す方向性やビジョンを示す重要な指標となります。しかし、間違った解釈や誤った解釈によって、権力やパワーを背景にした誤った意思決定や行動が行われることがあります。
たとえば、企業の理念や価値観に沿った新規事業が立ち上がった場合、その事業に権力やパワーが集中し、既存の事業を犠牲にしてでも成功させようとすることがあるかもしれません。しかし、このような決定が事業内容を無視して下された場合、失敗するリスクが高まるということがあります。
そのため、企業と社員は常にコミュニケーションを取り合い、理念や価値観が正しく解釈され、間違った解釈や誤った解釈が起こらないようにすることが重要です。また、企業は理念や価値観を柔軟に見直し、時代の変化に対応することも大切です。企業と社員が、正しい方向に向かって行動するためには、コミュニケーションと柔軟性が必要不可欠なのです。
抽象的な理念を具体的に落とし込む必要がある
企業が抽象的な理念や価値観を持っている場合、それを実際の行動や業務に落とし込むことは容易ではありません。
しかし、このような理念を具体的に実践することができるようにすることは、企業にとって非常に重要あり、企業はインターナルブランディングを通じて、従業員に対して抽象的な理念や価値観を具体的な行動やタスクに落とし込むよう指導する必要があります。
一例として、「社員が一人ひとり活躍できる企業」を目指す場合においては、具体的な働き方改革を進めることが必要になります。
しかし、その改革がうまくいかないと、残業が否定されたために、社員が隠れて残業するようになったり、残業代が支払われなかったりするといった間違った風潮が社内に広がることがあります。
もちろん上記は極端な例ですが、企業の理念や価値観は抽象的であるがゆえ、その主義主張だけが一人歩きし、現実に則していない不合理な決定を下してしまうリスクがあるということです。
社員が自律的に行動できるようにする取り組みも重要
インターナルブランディングを行う上では、社員が自律的に行動できるようにする取り組みも重要です。
インターナルブランディングによって、社員たちが企業のビジョンや目的を理解できると、高い視座から業務や活動を見るようになります。つまり、数字だけではなく、自社がどのようなポジションにいるか、自社が目指す方向に向かっているかなども意識するようになるのです。結果として、社員たちはビジネスパーソンとしてのスキルや知識を高めることができ、業務や活動の質も向上します。
まとめ
インターナルブランディングを効果的に行うことで、社員に企業の理念や価値観を共有することができ、人材育成という観点からも企業を内側から改革することができます。
ただし、長期間のスパンで取り組む活動であり、少なからずリソースを割くため、しっかり計画を立てて社員の理解・納得を得ながら、本来の業務に支障を来さない範囲で効率的に行うようにしましょう。
ソフィアでは、さまざまな企業のインナーブランディング活動のバックアップを行っています。どう進めていいのかわからないとお困りの際はぜひご相談ください。
関連サービス