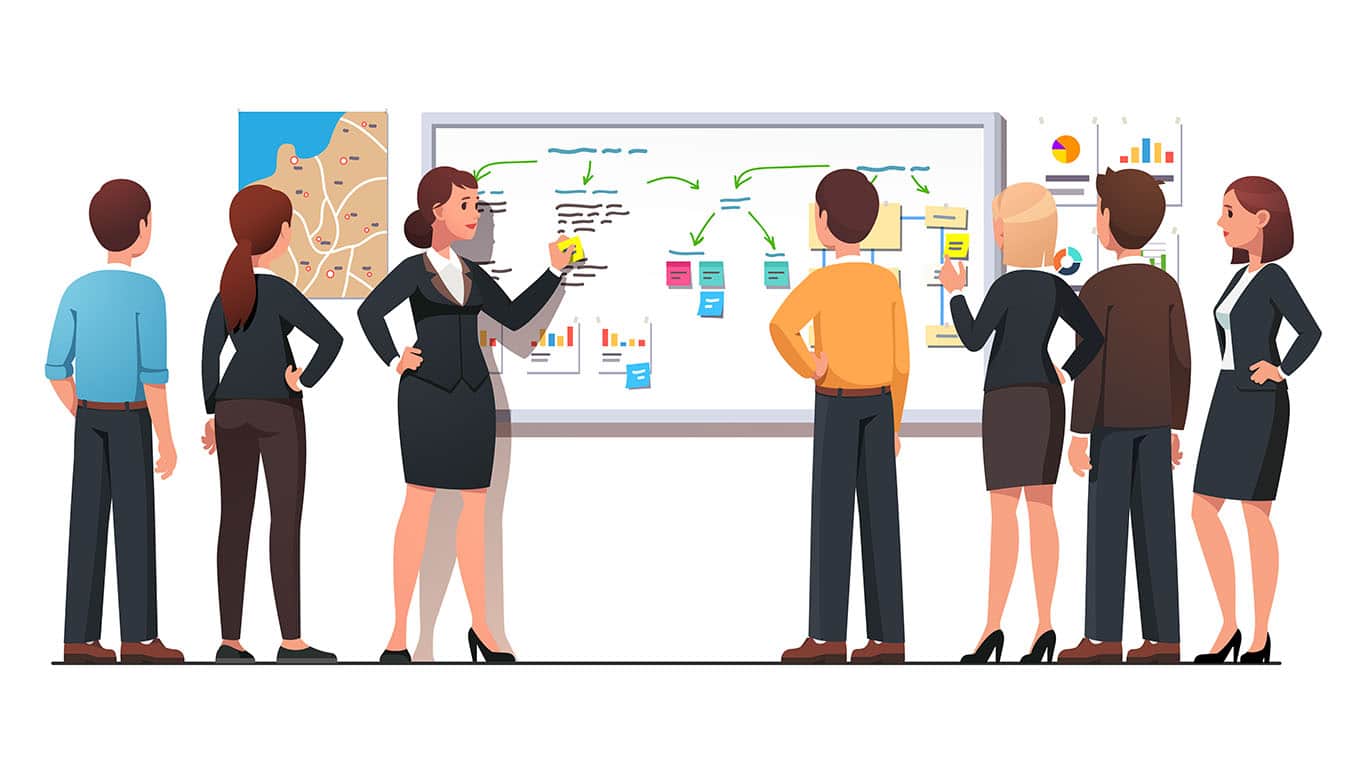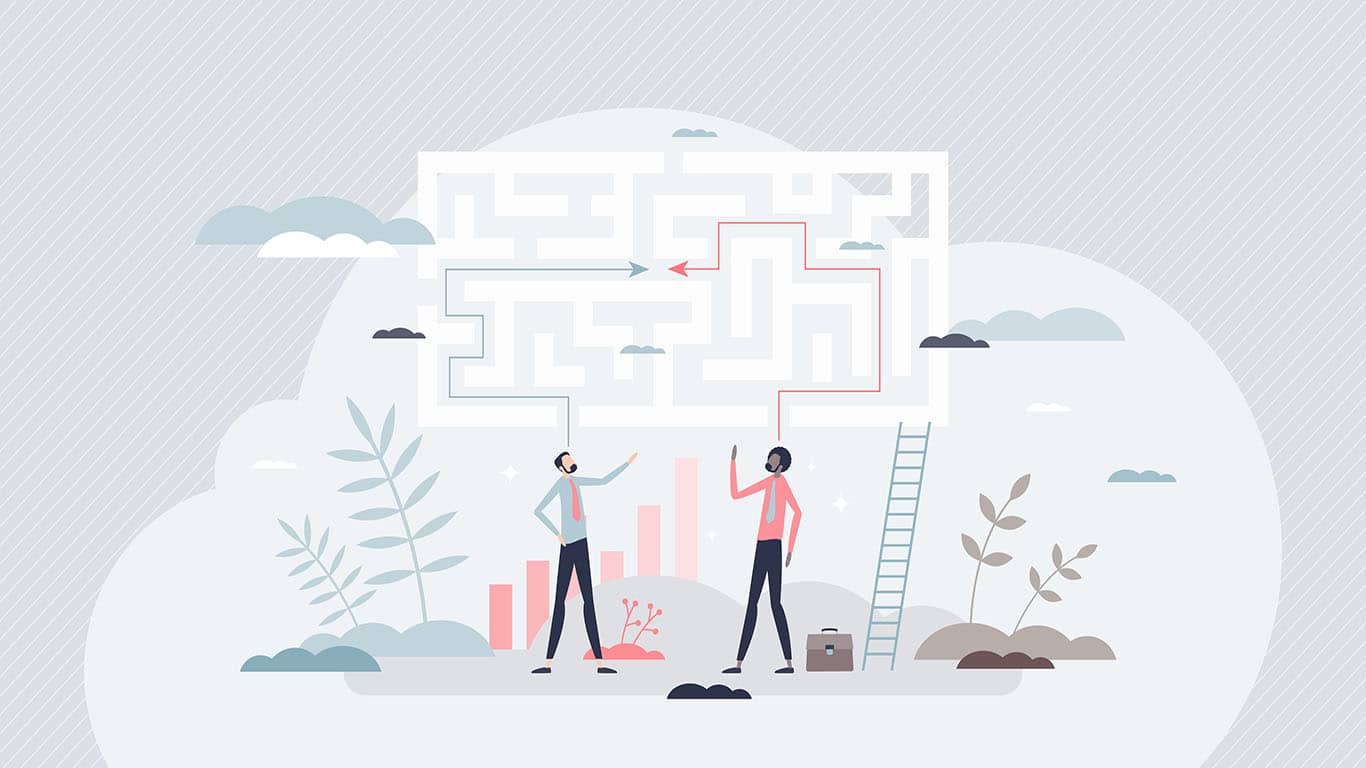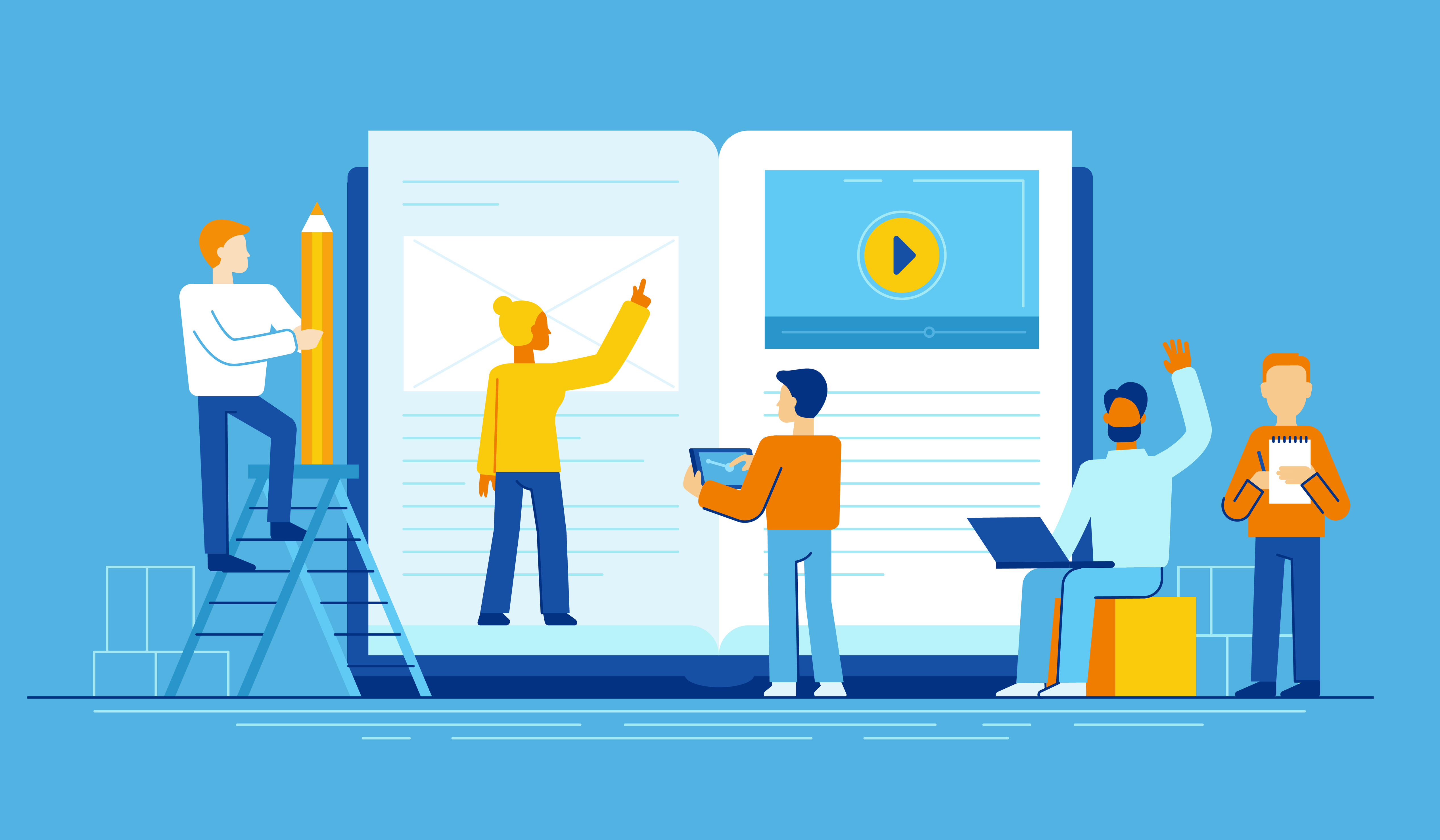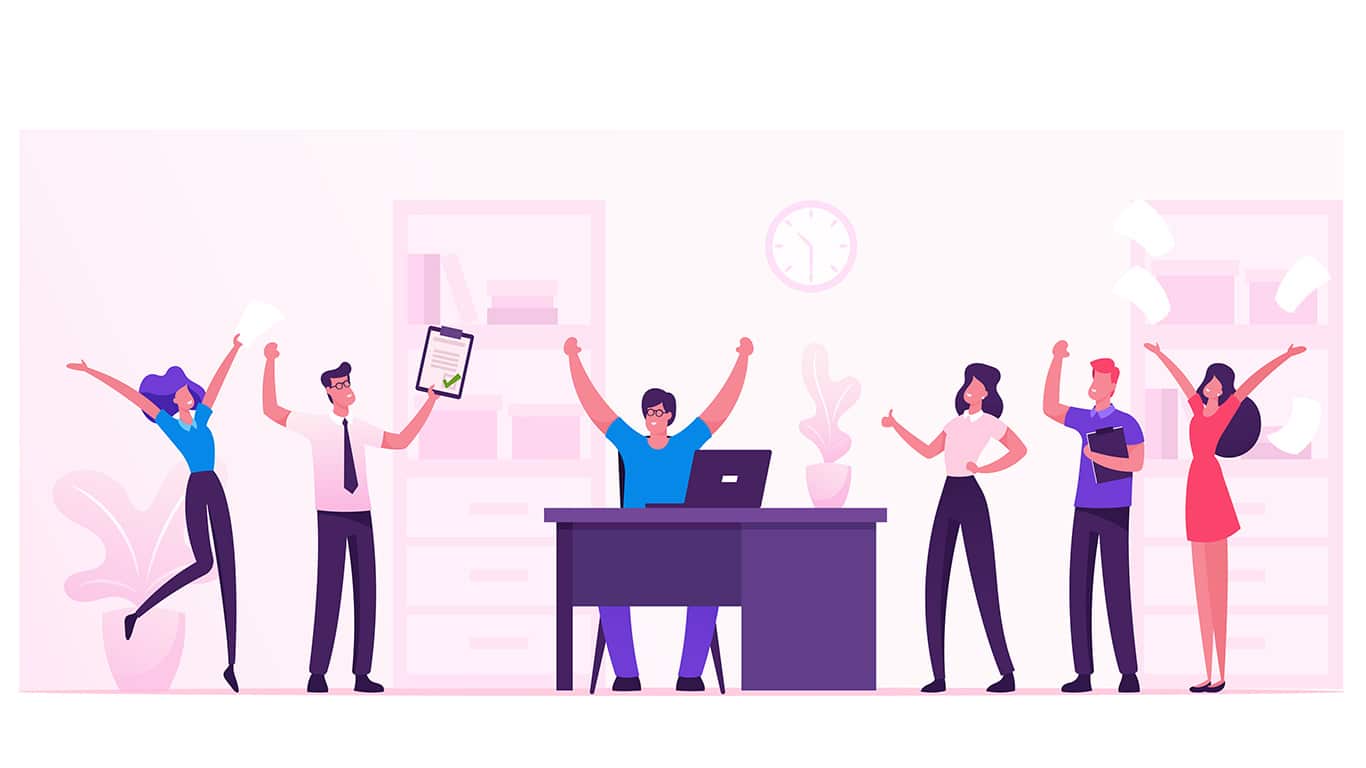経験学習とは?経験学習サイクルの回し方や取り入れるメリットについてご紹介!
最終更新日:2022.07.19

目次
経験から学ぶことで成長していく「経験学習」の考え方は、多くの企業の現場で重視されています。今回は「経験学習」について、効果的に取り入れるための方法や、企業が享受できる具体的なメリットを詳しく解説します。
経験学習とは?
経験学習とは、その言葉の通り、自ら実際に経験をすることで学び、成長していくプロセスを指します。人材育成のために研修を取り入れている企業は多くありますが、経験学習は研修によくあるような座学ではなく、実際に物事を経験することによって成長をうながす取り組みです。
雇用環境が大きく変化している昨今、効率的な人材育成のための手法があらためて見直されています。なかでもよく知られているのは、アメリカの組織行動学者であるデイビット・コルブ氏が提唱した「経験学習モデル」です。同氏は、経験学習とは下記の4つのステップを回して達成するものであると指摘しています。

- 経験する(具体的経験)
- 1.の経験を「反省」する(内省的観察)
- 1.2.から学べたことを「概念化・抽象化」し、汎用性の高い教訓へと昇華させる(抽象的概念化)
- 得た教訓を踏まえてまた「実践」する(能動的実験)
経験学習は特別難しいものではありません。日常のなかで自然に実行しているという人も少なくないでしょう。この4つをひとまとまりのサイクルとして回していくことで、効果的な経験学習を行うことができます。
経験学習と関係の深いアメリカのロミンガー社による調査「7₋2₋1の法則」
「7-2-1の法則」は、アメリカのロミンガー社が提唱したリーダーシップ開発に関する法則です。この法則によると、7割が現場での経験、2割他者からのフィードバックやアドバイス、そして残りの1割が座学などの教育や研修から得られるとされています。
この法則は、学びの大部分が日常の業務を通じた実践から得られることを示しており、経験に勝るものなしということがわかるのではないでしょうか。
一方の受講すればマスターしたとみなされてしまう研修に足りないのは、まさに脳内の情報に紐づいた体験ということになります。
デービッド・コルブが提唱している4つのプロセスからなる学習理論
デービッド・コルブは、学習を経験を通じて行われるプロセスとして捉え、これを「経験学習モデル」として提唱しました。このモデルは、学習が4つのプロセスで構成されています。
- 具体的経験
- 内省的観察
- 抽象的概念化
- 能動的実験
例えば、何か新しいことを体験し、その体験を自身の頭のなかで振り返り、得られた情報を整理する過程で理論や概念にまとめます。それによって蓄積した知識を行動に移すことで学習を深めるというものです。コルブの理論は、経験則と思考が結びつき、学びが循環しることで効果的な学習が深まるとされています。

ナレッジマネジメントとは?AI活用と失敗しない導入手順【2025年版】
ナレッジマネジメントの定義からSECIモデル、ISO30401、最新の生成AI(RAG)活用までを網羅。組織の暗黙知を資産に変え…
経験学習を取り入れるメリット
経験学習はさまざまな場面で応用できるスキルの獲得を目指して行われます。 実際に現場に出て経験を積むことは生産性向上のために重要です。なぜなら、経験は失敗・成功といった具体的な結果を伴うものだからです。
ただし、ここで注意したいのは、失敗も成功も、ただ認識したり受け入れたりするだけではほとんど意味がないということです。重要なのは、結果を受け入れたあと、それを材料に学習をするという姿勢です。
仮に失敗をしてしまっても、原因を観察して改善すれば、重要な教訓を得ることができるでしょう。失敗の原因に気付くことは、個人の成長にもなり、組織にとっても有益な事例となります。
リフレクションフレームワークKPTを意識した経験学習サイクルの実践方法
ここからは、先ほど簡単に紹介した経験学習のサイクルについて、より具体的に見ていきましょう。4つのステップについて、それぞれ説明していきます。
具体的経験 仮説を立てて試行する
第1ステップは、経験です。ここで重要なのは、部下自らが自分の考えのもとで行動・経験をすることです。誰かに言われたとおりに行動してしまうと、自分自身の学びになりません。困難な業務や、初めて取り組む業務など、展開を想定することが難しい仕事ほど、後の学びが大きくなるでしょう。
内省的観察 振返りとフィードバック
第2ステップでは、経験した内容について自分で振り返ります。漠然と振り返るのではなく、どの部分に焦点を当てるのかを明確にするのがコツです。
結果を振り返るのか、プロセスを振り返るのか、自分自身の言動を振り返るのか、周囲の状況を振り返るのか、その切り口はさまざま存在します。あらゆる角度から、客観的に自分の経験を観察していきましょう。その際は、先入観にとらわれずに事実と向き合うことがとても重要です。
抽象的概念化 理解したことに対し自分なりの名前をつける(概念化)
第3ステップでは、内省を抽象化していきます。抽象化することで、概念やルールとして自分のなかで認識できるようになるため、あらゆる場面で活かすことができるようになります。
デイビット氏が提唱した経験学習モデルでは、内省によって経験をルールや知識として変換していくことを「学習」としています。
能動的実験 概念化した知識を活用し新たな仮説をたてる
最後の第4ステップでは、ここまでの気づきをもとに再び実践に取り組みます。これを繰り返し、経験を重ねることで、より信頼性の高い概念やルールを導き出せるようになるでしょう。
上記の流れは、業績が安定して継続的に成長が約束されたビジネスモデルや業務より、新規事業開発や研究開発など領域で効果を発揮します。つまり、未開領域は、過去の杵柄(知識や技術)が通用しない状況であり、経験や実践からノウハウや概念を創造し、生み出す必要があるわけです。
ただ、現在の経営環境において、高度経済成長期のような継続的に成長が約束されたビジネスは、多いとは言えません。つまり、実践や経験に基づいた知識や技術のアップデートをする必要があり、実践や経験を伴わない学習過程は、現在の経営環境にあまり効果がない実務能力開発と言い換えることもできるのではないでしょうか。
経験学習の取り入れ方とポイント
企業の多くは、研修やセミナーによって社員に思考のフレームワークや概念を教え込みます。しかし、社員の経験を適切にデザインできている企業は、そう多くはありません。実際、研修に実践を取り入れたいとなった場合、宿題というかたちで指示を出して済ませてしまう企業も少なくないでしょう。
企業がまず大切にするべきなのは、社員に成功の裏側にある様々な経緯を実際に経験させること、そして経験を振り返らせ、経験が概念に昇華されるまで内省を促すことです。そのためにも、失敗できる企業風土を用意することが大切だと言えます。
周りを見渡せば美談ばかりが拡散されがちですが、失敗から見えるものの見方や発見があるはずです。丁寧な振り返りを企業側がデザインすれば、同じ失敗を繰り返すことは少なくなり、結果的に組織としての成長につながります。
この記事の最後に、企業が経験学習を取り入れるためにはどうすればいいのかをまとめましましたので企業が取り組むべきポイントとして参考にしてみてください。
OJT研修
「OJT研修」は、現場での実践を通して知識を身につける研修です。経験豊富な社員が、知識だけでなく経験も一緒に教えることが多いため、トレーニー(研修生)からすれば、経験を身につけるための絶好の環境だと言えるでしょう。そもそもOJT研修は、経験学習の手法と似通った内容の研修です。OJT研修にうまく経験学習サイクルを組み込めば、効果が増して深い学びを得ることができるでしょう。
人事ローテーション・ジョブローテーション
部署異動によって経験したことのない新しい業務を行うことも、経験学習のチャンスとなります。同じ新しい業務に取り組む場合でも、異動にともなう業務変更であれば会社や周囲も手厚くサポートできるため、研修生は安心して経験学習のサイクルに集中することができます。
上司との1on1ミーティング
大きく環境を変えるのが難しい場合、上司との1対1のミーティングを設けるだけでも環境は変わります。ミーティングによって、普段から自分を客観的に見ている上司の意見を聞くことで、部下にとっては新たな気付きを得る機会にもなります。そして、上司がその気付きをもとに、一緒に学びをサポートすることが重要です。
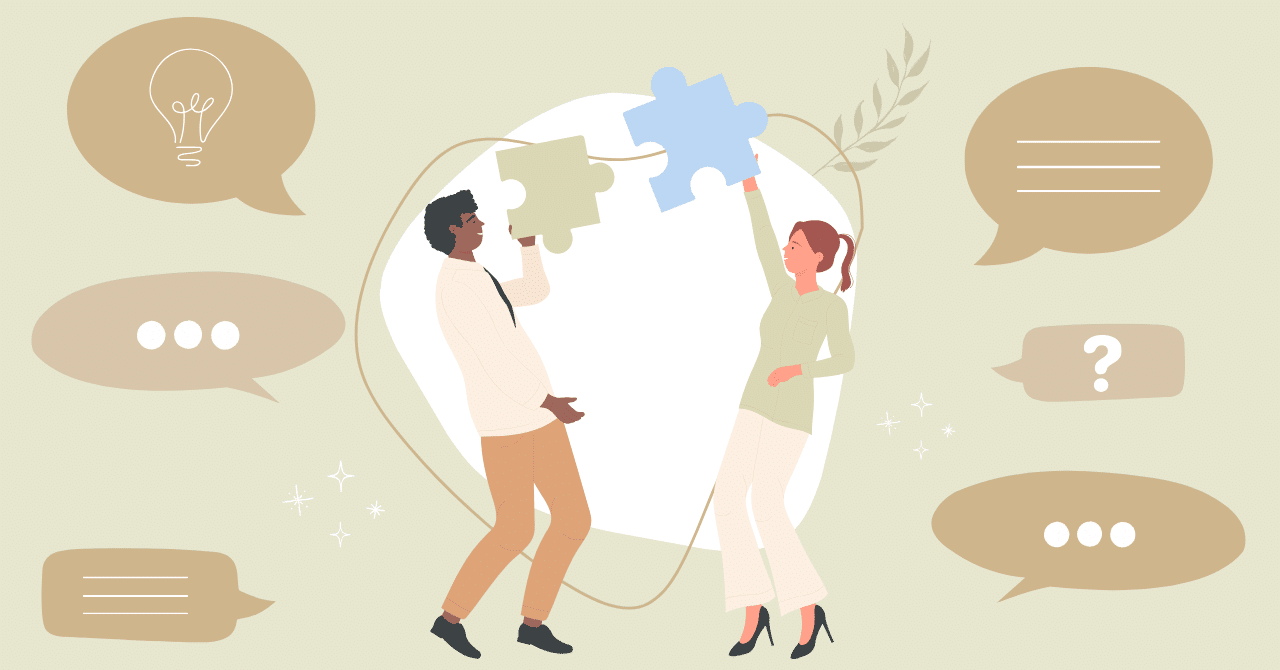
1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介
最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…
プロジェクトベースドラーニングPBL
経験学習には「プロジェクトベースドラーニング」の手法を取り入れるのもおすすめです。「プロジェクトベースドラーニング」は、注目されている人材開発手法の一つで、問題を提起し検証・解決していく学習方法です。課題を通し、問題解決へのアプローチ方法を身につけることで、自ら主体となって能動的に学んでいくことができます。「問題解決型学習」とも呼ばれ、組織開発・人材開発・問題解決に効果的とされている手法です。
経験学習サイクルに関する注意点
経験学習モデルは効果的な学習手法である一方で、実行時にはいくつかの留意点があります。 これらを正しく理解することで、その効果を最大限に引き出すことができますので、注意深く心得て、適切に実施していきましょう。
経験から本質的な学習と能力を産み出すために
上述した内容はごくごく当たり前のことなのですが、「知行合一」の言葉通り、本質な知識や能力は、知る事と行動経験する事が連動し、相互作用から産み出されるものです。
知識や概念の取得だけにとどまらず、実践と経験によってようやく学習としての一連のサイクルが一周するということです。
また、実務やビジネスにおいては、学習後の問題や業務を、学習前に比べて効率的に処理され、解決できたという成果結果につながることでのみ、本質的な実務能力が一段上がります。
つまり、ビジネスにおいては、知識と経験と結果が必要となります。哲学者であり教育思想家のジョン・デューイの著書である「経験と教育」の中で、進歩主義教育と伝統的教育を対比的に論じることに はあまり意味がないとし、それよりも一人ひとりの経験からうまれる好奇心や独創力のほうが、自ら高みを目指し成長を促すと語っています。
極端な例ですが、デジタルやイノベーションになどに代表される新しい進歩的な知識や技術と、伝統的な読み書きそろばんのようなもの、どちらが優れているかなどという議論は無意味であり、むしろ知識や技術などは、問題を解決するため個人の未来をよりよく生きるための手段や道具にすぎず、何を用いてもそれが役に立つという結果や成果がセットになる必要性を強く訴えているわけです。
動機や業務をデザインする
人事部門が設計する階層教育やリスキリングなどDX研修は、事業戦略から事業遂行に必要な人財を定義し、スキルを洗い出し属性に併せて人財母集団に教育を提供するというのが一般的にプロセスです。
しかし、その後に問題や業務を効率的に処理できる、解決できる、という成果結果に繋げる点において課題感を持っている方も多いのではないでしょうか。
ありがちな研修スタイルは業務と学習内容が紐づいていないケースが多く、人事部門が想定するケースについて座学で学びます。想定がすべて間違っているというわけではなく、当人が経験したことが学びの始まりであるかどうかが重要です。
前述のデイビット・コルブ氏が唱える4つの経験学習モデルの始点にあたる「具体的な業務経験」にあるように、経験したことで得られる気づきや、新たな発想といった何かしらの動機が次の省察や概念化につながるからです。そしてそれらをかたちにした試行によってさらなる経験につながり、長い円環をぐるぐると回ります。こうのような経過を経てやがて成果につながるというのが、本来目指すべき研修のありかたです。
教育の機会を提供することは大事ですが、困難な課題/業務の機会を提供しない限り、学習効果は薄く、期待するほどの成果にはつながりません。
ただし、困難な課題/新たな業務の機会が、個人にとって役に立つという動機があるかないかでは、臨むときの姿勢が主変わってきます。つまり、「個人にとって役に立つ困難な課題/新たな業務の設計が必要になります。教育内容やコンテンツは、その前提から設計する事が効果的です。
ビジネスにおいて、不確実及び応えの無い課題、これに対して、動機及びゆうきをもって飛び込んでく、業務の存在し、それが経験、やったことない業務と勇気が経験が産む。
経験をデザインする
前提として、個人の経験を他者は設計デザインし意図的に誘導することはできません。しかし、本質的な学習と能力を生み出す経験を誘発する環境や状況を創りだすことは可能です。少し乱暴に言い方になりますが、新規事業部や組織課題PJなどへの異動です。これは幹部の選抜教育やサクセッションプランとしては、広く活用されています。特定の人財母集団に対するアプローチに限定されます。広く多く母集団へのアプローチとしては、プロジェクトベースドラーニングなどの、業務や課題から設計されたプログラムを設計する必要があります。経験のデザインとはある意味は、やらざる得ない状況を創りだすことです。ここで問題になるのは、「やらざる得ない」状況が、上記の動機とコンフリクトがおきます。従って集合研修などで行われロールプレイングや模擬実習の疑似経験だけではなく、現場や組織の実態の課題や事業の課題を研修の中で取り扱い業務(経験)と集合研修など(知識取得)の連続性を構築する事が重要です。
振り返りをデザインする
振り返りは、経験と結果への洞察を意味します。ゴルブのモデルで言えば、内省的観察/抽象的概念化のプロセスになります。ジョン・デューイは経験だけは、学習になり得ないと言っており、反省的思考(振り返り)の重要性と説いています。振り返りは、個人の頭の中で行われる思考のプロセスです。そして、振り返りは、連続的に個々人で回数や思考プロセスも区々です。これも他者は設計デザインし意図的に誘導することはできません。振り返りの機会を提供することは創ることは可能です。振り返りの場で重要なことは、ゴルブは「客観的」、デユーイは「科学的」という思考が必要と言っています。自己の経験を客観的且つ科学的な思考で整理するとは、経験を論理で整理するという事になります。従って論理的思考が必要になります。より効果的に振り返りを実施する上では、複数の人間で、振り返ることを実施することは、まずは客観性を担保できます。また自己の固有経験を他者に伝える必要が出てくるため、論理で整理しなければ伝わりません。定期的な他者との振り返りの機会を創ることが非常に重要です。
教育コンテンツは、経験を産み出すための動機づけのツールでしかない
ジョン・デューイは、「経験と教育」において、新たな知見や洞察が得られるのは、経験を促進するための動機付けのためであると主張しています。こう述べると、教育プログラムやEラーニングの教材は手段に過ぎず、目的ではないことが言えます。言い換えれば、研修プログラムやEラーニング教材の価値は、学習者が学習を動機付けられ行動に移したかどうかにかかっています。学習者のモチベーションや動機を把握することが、経験学習を展開するためには重要であるとされます。また、知識学習と経験学習を併せて行うことが経験学習の成功の鍵となるものの、必ずしも成功するとは限りません。
まとめ
経験学習は、経験から学んでいくためのサイクルです。個々が意識して行うことで、成長につながり、組織に広がりが見えてきます。このような広がりには職場の環境を整えることがポイントです。失敗も含めたすべての経験から学んでいく学習プロセスであるため、失敗から得るものがあるというポジティブな姿勢が欠かせません。
フィードバックをする立場の方は、部下が前向きでいられるようにサポートする必要があります。たとえば、部下の意見を否定する前に、その意見に至るまでのプロセスを聞いてみると良いでしょう。部下の話を引き出し、考えを言語化してもらうことで、内省をうながすこともできます。丁寧なコミュニケーションをとりながら、フィードバックを返すことが重要です。
組織の環境作りや、組織風土作りについてお悩みの場合は、ぜひソフィアまでお問い合わせください。