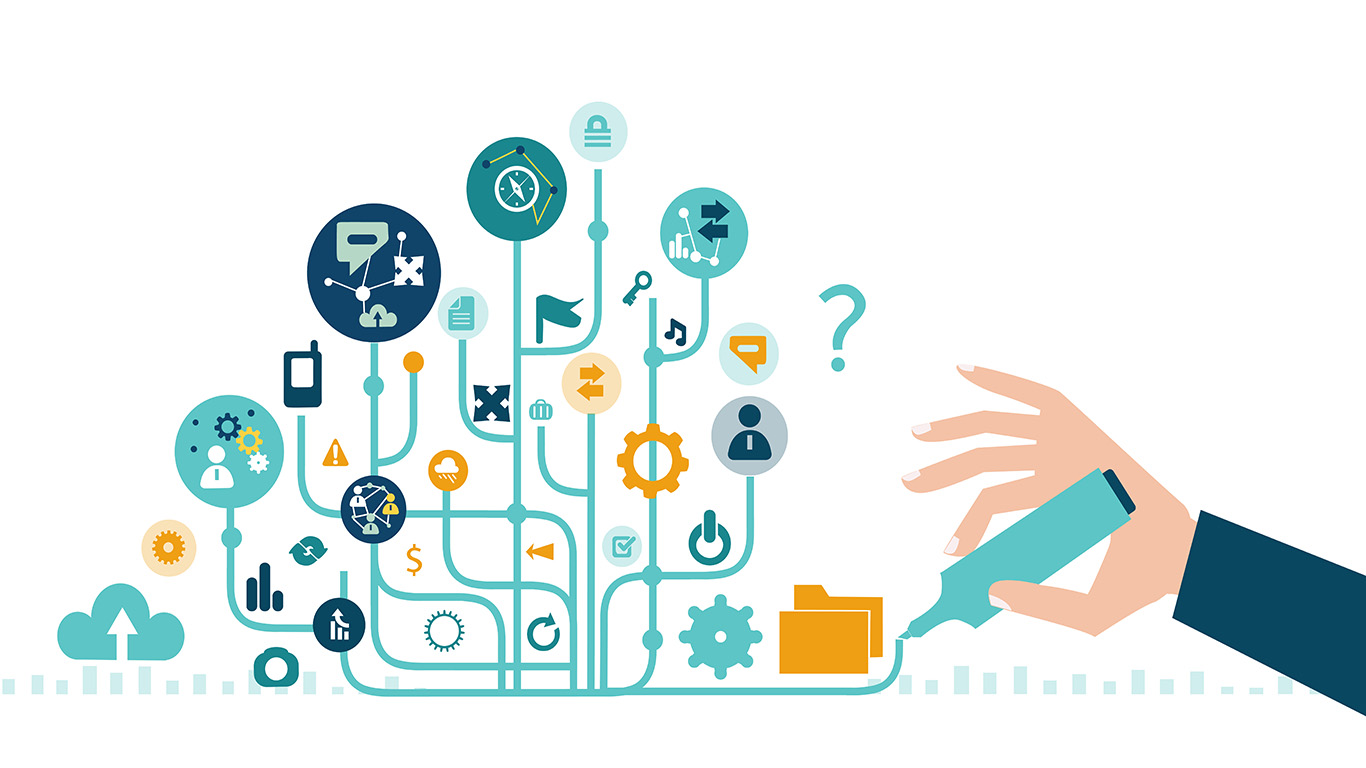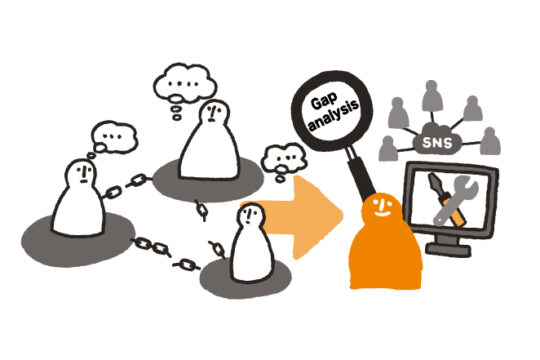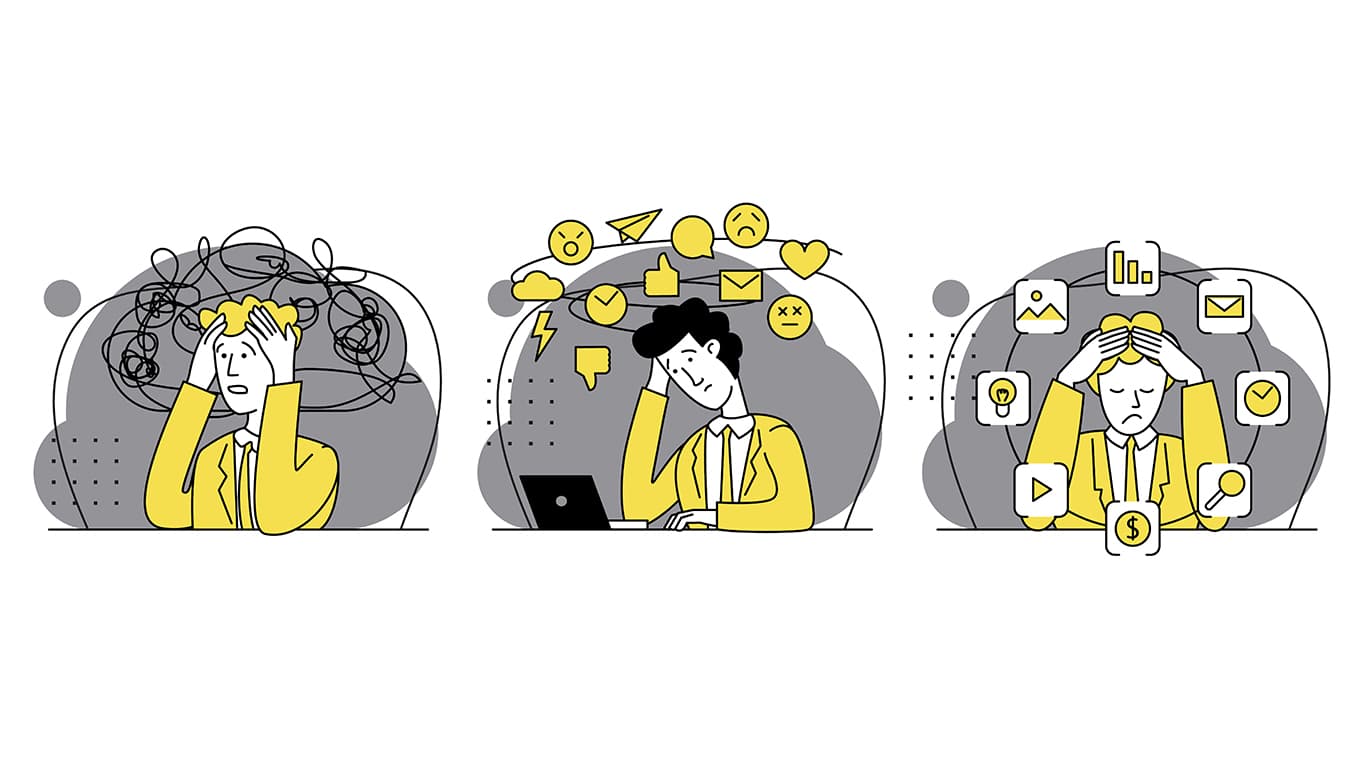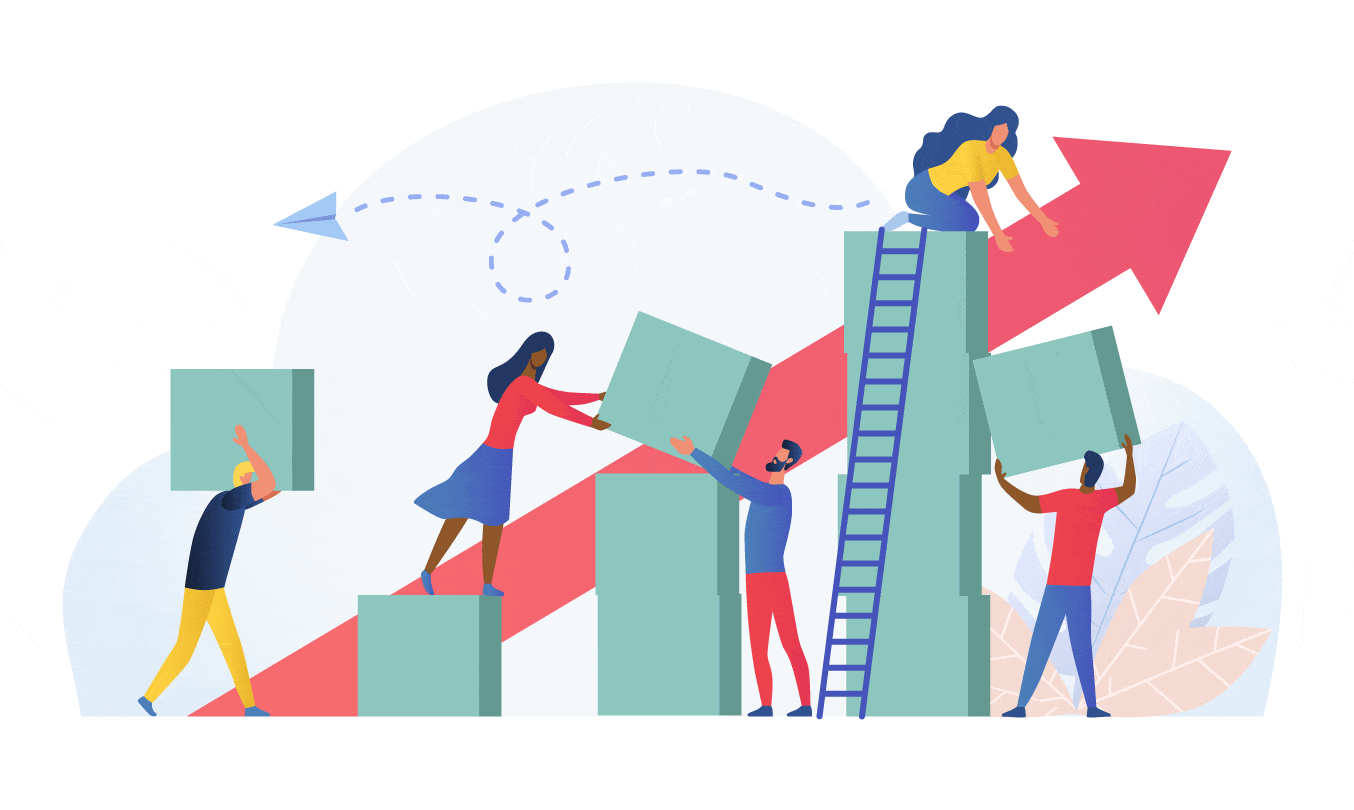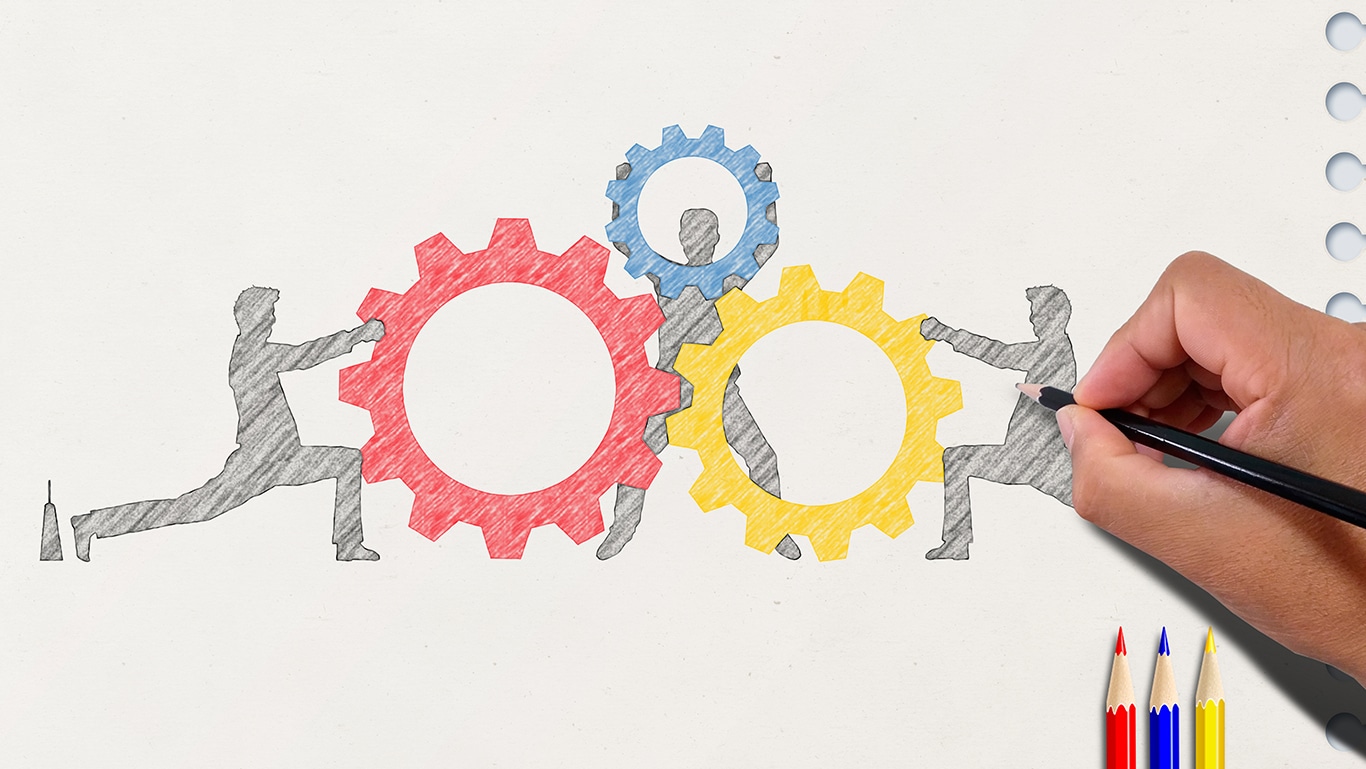ナレッジマネジメントとは?AI時代の導入手順と成功の法則【2025年版】
最終更新日:2026.02.16

目次
「ベテラン社員の退職で貴重なノウハウが失われてしまう」「社内ポータルに情報は蓄積されているはずなのに、必要な情報が見つからない」「部署間の連携が希薄で、同じような失敗が組織内で繰り返されている」——これらは、多くの大企業が直面している深刻かつ構造的な経営課題ではないでしょうか。
DX(デジタルトランスフォーメーション)推進や働き方改革が加速する中、組織内に点在する「知」をいかにして統合・管理し、活用可能な資産へと昇華させるか、すなわち「ナレッジマネジメント」の成否が、企業の競争力を左右する最大の要因となっています。
本レポートでは、ナレッジマネジメントの基礎理論である「SECIモデル」の再解釈から、2025年の最新トレンドである生成AI(RAG)を活用した技術革新、さらには国際規格ISO 30401に基づく標準化の考え方までを網羅的に解説します。また、弊社ソフィアが実施した最新の「インターナルコミュニケーション実態調査2024」のデータをエビデンスとして交えながら、ツール導入だけでは解決できない「対話」と「組織風土」の重要性を紐解き、失敗しない導入ロードマップを提示します。
ナレッジマネジメントとは
ナレッジマネジメントとは、言葉どおりに解釈すれば「ナレッジ」つまり「知識」や「知恵」をマネジメントするということです。想像しにくいかもしれませんが、体系化されたモデルもすでに存在し、組織にとっては欠かせないマネジメント手法でもあります。
ナレッジマネジメントの定義
ナレッジマネジメントとは、企業に属する従業員がそれぞれに持つ知識や経験、ノウハウなどを社内で共有し全社で活用することで、企業の競争力を高めるマネジメント手法です。
なお、社員個人が持っている知識やノウハウは「暗黙知」と呼ばれます。
ナレッジマネジメントの本質
ナレッジマネジメントとは、言葉どおりに解釈すれば「ナレッジ」つまり「知識」や「知恵」をマネジメントするということです。想像しにくいかもしれませんが、体系化されたモデルもすでに存在し、組織にとっては欠かせないマネジメント手法でもあります。
企業に属する従業員がそれぞれに持つ知識や経験、ノウハウなどを社内で共有し全社で活用することで、企業の競争力を高めるマネジメント手法です。なお、社員個人が持っている知識やノウハウは「暗黙知」と呼ばれます。
ナレッジマネジメントは、情報を整理し共有することから始まります。情報を整理できないと、それを検索することも難しくなるでしょう。日本ではとくにホワイトカラーの情報整理が課題です。さらに、製造業では世界的な生産性を誇りながらも、情報の整理が追いついていないことがあります。情報整理はナレッジマネジメントの第一歩と言えるでしょう。
ナレッジマネジメント誕生の背景と歴史
日本においては、野中郁次郎氏が「暗黙知」の概念を実践的に発展させました。彼は暗黙知を「モノづくりの現場に内在する知」と捉え直し、著書『知識経営』を通じて、ナレッジマネジメントの理論として体系化しています。
特に「暗黙知」「形式知」「SECIモデル」といった概念は、日本企業のイノベーション手法を土台に構築され、国内外の多くの企業に大きな影響を与えました。
もともと「暗黙知」という概念は、哲学者マイケル・ポランニーによって提唱されたものです。彼は、暗黙知を「個人の内面に存在し、言語化が難しい知識」として捉えました。この考え方はその後、さまざまな学者に影響を与えました。たとえば、ピーター・ドラッカーは知識社会や知識労働者の視点から、ピーター・センゲは「学習する組織」という観点から、それぞれ暗黙知の価値に注目しています。
現在では、個人が持つ暗黙知を形式知に変換し、組織全体で共有・活用することが、生産性向上やイノベーションの推進において重要な要素とされています。しかしながら、そうした知識変換を再現可能な形で定着させ、継続的に実践できている企業はまだ多くはありません。暗黙知の扱いは、今もなお多くの企業にとって大きな課題であり、知識経営の核心的なテーマとなっています。
「暗黙知」を「形式知」に変えるナレッジマネジメント
社員個人がそれぞれに持つ知識やノウハウを「暗黙知」とお伝えしましたが、暗黙知は体系的でなく属人的で形のないものです。この暗黙知を形にしたもの、すなわち文章化や図式化によって第三者にも説明や表現のできる知識へと変換されたものを「形式知」と呼びます。
暗黙知はそのままでは継承・共有が難しいため、形式知へと変換することで他者や組織に還元します。また、新たに生み出された形式知によってさらに高度な知恵が生まれ、その知恵を生かすことで組織を進化させていくことがナレッジマネジメントの目的です。
ナレッジマネジメントが注目される理由
ナレッジマネジメントの概念自体は1980年代にすでに誕生していました。業務システムを活用して人の持つ知識やノウハウを管理することが技術的に可能となった時代ですが、最近になって再びナレッジマネジメントが注目されるようになったのは、社会の変遷による需要の高まりが背景に存在します。
部門間の連携の必要性
ナレッジマネジメントは人事・総務・広報・経営企画・情報システム部などで、部門を越えた取り組みが活発になっています。また、働き方改革推進室・ESG推進室・HRBP・DX推進など外部環境への対応や、目的・課題別にチームを編成することで、より迅速な意思決定と行動が可能になります。
ナレッジマネジメントはさらに、〇〇プロジェクトや〇〇委員会といった非公式な部門横断チームをも編成させ、全社的な課題・問題解決に寄与することができます。これらの集団・チームが存在することで、部署や部門間の枠を越えて知識を共有でき、ITツールの運用だけでは実現できない、人為的な創造性や協業を取り入れた組織体制を作り出すことが可能になるのです。
労働生産性の問題
ナレッジマネジメントが注目される大きな理由に、労働生産性を改善したいと考えている企業・組織が多いことが挙げられます。ナレッジマネジメントを行うことで、社員が必要な情報やノウハウに迅速にアクセスできるようになり、業務の効率化・品質向上に必要なアクションを起こせるようになります。
その結果、企業・組織全体の労働生産性が向上し、市場での競争力が強化され、経営においてもポジティブな影響を及ぼすことに繋がるでしょう。
また、企業・組織内で知識やノウハウを共有することにより、部門・部署同士や、畑違いの異分野のアイデアが融合し、新たなイノベーションを創造することに大きな期待が寄せられています。異なる立場の者同士の協働は、現代のビジネスにおける企業・組織の成長と発展にとって不可欠な要素です。
ナレッジマネジメントができないということは、AIをはじめとする機能的なツールを効果的に活用できていないと言えます。ナレッジマネジメントは、情報を整理し共有することです。情報を整理できないと、それを検索することも難しくなります。日本ではとくにホワイトカラーの情報整理が課題です。さらに、製造業では世界的な生産性を誇りながらも、情報の整理が追いついていないことがあります。情報整理はナレッジマネジメントの第一歩です。
このように、ナレッジマネジメントは、企業・組織が労働生産性を高め、ビジネス市場で競争力と持続可能性を発揮するために有用な手法です。効果的なナレッジマネジメントの実践は、企業・組織の価値の向上に大きく貢献すると言えるでしょう。
人材流動化に伴う「属人化」リスクの回避
暗黙知は個人の中に蓄積されるものであり、主観的、感覚的であるためそのままでは第三者に共有することができません。一方、形式知は文章や図、数式を活用して暗黙知を第三者に伝わるよう具体化したものです。業務マニュアルがその主たる例です。
暗黙知は個人の資産であり、その暗黙知を持った社員が離脱してしまうと企業から知識やノウハウが失われます。しかし、形式知は企業の資産であり、他の社員に共有できるように形式化されているため、もともとの暗黙知を所有していた社員が退職しても知識やノウハウは形として企業に残ります。
人材が流動化している昨今では、知恵を属人化してしまうと優秀な人材が欠けたときに企業の戦力までも削がれるリスクがあります。そのため、ナレッジマネジメントが着目されているというわけです。
企業の暗黙知を形式知へ転換するために
暗黙知は個人の中に蓄積されるものであり、主観的、感覚的であるためそのままでは第三者に共有することができません。一方、形式知は文章や図、数式を活用して暗黙知を第三者に伝わるよう具体化したものです。業務マニュアルがその主たる例です。
暗黙知は個人の資産であり、その暗黙知を持った社員が離脱してしまうと企業から知識やノウハウが失われます。しかし、形式知は企業の資産であり、他の社員に共有できるように形式化されているため、もともとの暗黙知を所有していた社員が退職しても知識やノウハウは形として企業に残ります。
人材が流動化している昨今では、知恵を属人化してしまうと優秀な人材が欠けたときに企業の戦力までも削がれるリスクがあります。そのため、ナレッジマネジメントが着目されているというわけです。
ISO 30401(ナレッジマネジメントシステム)の策定
2018年、国際標準化機構(ISO)はナレッジマネジメントに関する初の国際規格「ISO 30401:2018 Knowledge management systems」を発行しました。これは、ナレッジマネジメントが単なる「推奨される取り組み」から、企業の品質管理やガバナンスにおける「必須要件」へと格上げされたことを意味します。グローバル市場で戦う大企業にとっては、知的資産の管理が国際的な信用指標となりつつあります。
ナレッジマネジメントで解決する問題
ナレッジマネジメントは、企業の抱えるさまざまな問題を解決する鍵となります。今や企業にとって欠かせない取り組みであることもわかるでしょう。
人材育成の効率化
「暗黙知」を他者に継承するには長い時間を要することはすでに解説したとおりです。教える側が自分の技術を自分自身でも言語化、パターン化できない状態のため、とにかく効率が悪くなります。さらに昨今は企業が人材を一から丁寧に育てる体力を持っていません。できるだけ早く戦力になってほしいというのが本音といえるでしょう。
ナレッジマネジメントによって暗黙知を形式知に変換することで、ベテランの技術を新人に継承しやすい環境を整え、人材育成の効率化へとつなげることができます。
業務の標準化・高度化
暗黙知には、スキルとは呼びにくいもののビジネスの動向を大きく左右するコツのようなものが多分に含まれます。得意先との交渉のテクニックや、顧客のクレームにうまく対処する秘訣、自社商品を営業先で魅力的にアピールする話し方などです。
これらのコツはこれまでは属人化されていることがほとんどで、第三者に共有されることはありませんでした。それが自分とライバルとの差をつける隠し技だったのかもしれませんが、企業からすればそういったコツも全社員に共有し、自社の資産としたいところです。
ナレッジマネジメントを活用することで、こうしたコツも業務へ標準的に取り入れられるようになり、社員がよりレベルの高い仕事を行うことができます。
膨大な知識へのアクセスが可能に
ナレッジマネジメントには、知識を「管理」する役割もあります。たとえば、マニュアル化された知識は社内ポータルのようなツールと組み合わせることで、全社員が部署を超えてアクセスできます。他部門の業務フローを知ることで同じ業務を別の角度から見直す良いきっかけともなり、そこから新たなアイデアが創出されることもあるかもしれません。
蓄積されたノウハウで新たな戦略を立てることができる
ナレッジマネジメントは、経営手法といわれることもあります。自社事業で得た知識やノウハウ、技術をもとにして新たな経営戦略に役立てることができ、ときには新たな事業が生まれることもあるかもしれません。
AIの活用で多くの問題は解決できる
現代のビジネス環境において、企業・組織内にストックされた知識・ノウハウは、市場での競争優位性を獲得するための重要な要素です。しかし、膨大な量のデータや文書が日々発生する現代において、企業・組織内の知識・ノウハウを効率的に管理し、必要なタイミングで必要な人に届けることは容易ではありません。
その点、AI技術を活用したナレッジマネジメントシステムは、企業・組織内の知識・ノウハウを適切に管理し、素早く共有できる便利なツールです。こうしたAI技術を活用することで、大量の情報や文書を自動的に分類、整理し、必要な情報を迅速に検索することができます。また、専門家の知識をデータベース化し、企業・組織全体で共有することで、企業・組織全体の知識レベルを向上させることにつながります。
ナレッジマネジメントの5つの観点
ナレッジマネジメントを効果的に実践するためには、単に情報を蓄積・共有するだけでなく、その知識がどのように生まれ、伝わり、活用されるかを多面的に理解することが重要です。ここでは、知識を組織全体で活かすための視点として注目されている、ナレッジマネジメントの5つの観点について解説します。
Intellectual Capital(知的資本)
知的資本とは、企業や個人が保有する知識・情報・ノウハウといった無形の資産を指します。これには知的財産権、ブランド、人的資本などが含まれ、企業の競争力を高める源泉となります。
特に日本企業では、野中郁次郎が提唱したSECIモデル(暗黙知と形式知の相互変換)を活用して、現場のノウハウを知的資本として蓄積・活用する取り組みが広がっています。知的資本は目に見えない資源であるため、明確な管理や評価が難しい側面もありますが、企業価値の持続的な向上には不可欠な要素とされています。
Community of Practice(実践コミュニティ)
実践コミュニティとは、共通の関心や課題を持つメンバー同士が、経験や知識を継続的に共有しながら学び合う場のことを指します。このようなコミュニティは、業務の枠を超えたつながりを生み出し、暗黙知の伝達やノウハウの蓄積に効果的です。企業においては、ナレッジシェアの文化を醸成し、学習する組織への進化を促す重要な仕組みとなります。自主的な参加と信頼関係を基盤にしたこの活動は、社員のモチベーション向上やイノベーション創出にもつながります。
Social Network Analysis(ソーシャルネットワーク分析)
ソーシャルネットワーク分析は、組織内における人と人とのつながりや情報の流れを可視化し、分析する手法です。誰が情報のハブになっているのか、どこに情報のボトルネックがあるのかといった構造を明らかにし、効果的な知識共有やチーム編成に役立てることができます。また、非公式なネットワークの力を理解することで、形式的な組織図では見えないコミュニケーションの実態に迫ることができ、ナレッジマネジメントの改善に大きく貢献します。
Information Theory(情報理論)
情報理論は、情報がどのように伝わり、処理され、効率化されるかを科学的に解明する学問です。ナレッジマネジメントにおいては、情報の冗長性を排除し、必要な情報だけを正確に伝える設計が求められます。情報理論の考え方を応用することで、組織内の情報フローを最適化し、伝達ミスの削減やナレッジの効率的な流通が可能になります。膨大な情報を扱う現代企業にとって、質の高い情報設計と管理は、業務のスピードと生産性を高める鍵となります。
Constructivism(構成主義的アプローチ)
構成主義は、人は自身の経験や背景をもとに情報を解釈し、知識を構築していくという学習理論です。ナレッジマネジメントでは、知識の「伝える側」と「受け取る側」の理解のギャップを埋めるために、この視点が重要になります。
たとえば、同じ情報であっても受け手の理解度や文脈によって意味合いが異なるため、一方的な伝達ではなく、双方向の対話や実践を通じた学びが求められます。教育や研修の場でもこのアプローチは活用され、個人の成長と組織の知の深化に貢献しています。
知的資本の活用としてのナレッジマネジメント
ナレッジマネジメントにおいて、最も代表的かつ実践的なフレームワークのひとつが、野中郁次郎氏らによって提唱された「SECIモデル」です。このモデルは、暗黙知と形式知の相互変換を通じて知識を創造・共有し、組織の知的資本を高めていくプロセスを体系化したものです。以下では、SECIモデルの4つのプロセスと、それぞれのプロセスを支える「場」の考え方について詳しく見ていきます。
SECI(セキ)モデル
SECIモデルとは、一橋大学の野中郁次郎氏と竹内弘高氏らが示したナレッジ・マネジメントのコアとなるフレームワークです。組織が暗黙知を管理し、それらの知を形式知に変換したり、新たな知を育んだりするための枠組みで、各プロセスの英語表記の頭文字を組み合わせた言葉です。SECIモデルは以下、4つのプロセスで構成されます。
・共同化(Socialization)
共同化は、経験を通して個人の暗黙知を別の個人に伝えるプロセスです。この時点で暗黙知は形式知になっておらず、自社のプロダクトやサービスに関する内容であっても具体的に形容できない状態です。この知識を「なんとなく」レベルでも同じ見解として感じられるよう、あるいは口頭での継承が円滑になるよう、「同じ体験をする(共体験)」ことで暗黙知を伝達していきます。
たとえば、新たなプロダクトの開発において試作品ができた際、実際に全員がそれを試用してみることで、開発者の加えた細かな工夫や、仕様ではわからない実際の使い勝手がチーム内に共有されるというものです。
・表出化(Externalization)
表出化は、個人の暗黙知を「具体化」することでメンバーと共有を試みるプロセスです。表出化の手法としては、言葉によるもの(ミーティングや1on1、引き継ぎなど)だけでなく、実際にモノを作って具体化するもの(プロトタイピング)、音声や映像を使ったもの(録音・録画など)、その他あらゆる手段が活用できます。このような方法で知識が形式知化されていきます。
・結合化(Combination)
結合化は、表出した形式知に別の形式知を組み合わせることで、新たな知を生み出すプロセスです。業務効率化や新たな戦略の立案フェーズがここに含まれます。また、部門を横断してのプロジェクトチームの編成や、多様な人材を一箇所に集めてのブレインストーミングによって知を創出し、その上で実際の効率化や戦略立案を具体的に落とし込んでいくフェーズも含まれます。
・内面化(Internalization)
内面化は、個人が新たに得た形式知を身につけるプロセスです。表出化プロセスは暗黙知の持ち主、内面化プロセスは形式知を受け取るメンバーがフォーカスされると考えるとわかりやすいでしょう。内面化プロセスを経て習得した新たな知は、各個人の中でそれぞれの暗黙知として深化していきます。
こうして醸成された暗黙知が再度共同化プロセスに戻り、これらのサイクルを何度も繰り返すことで個人のスキルアップおよび組織の資産価値向上につながるわけです。
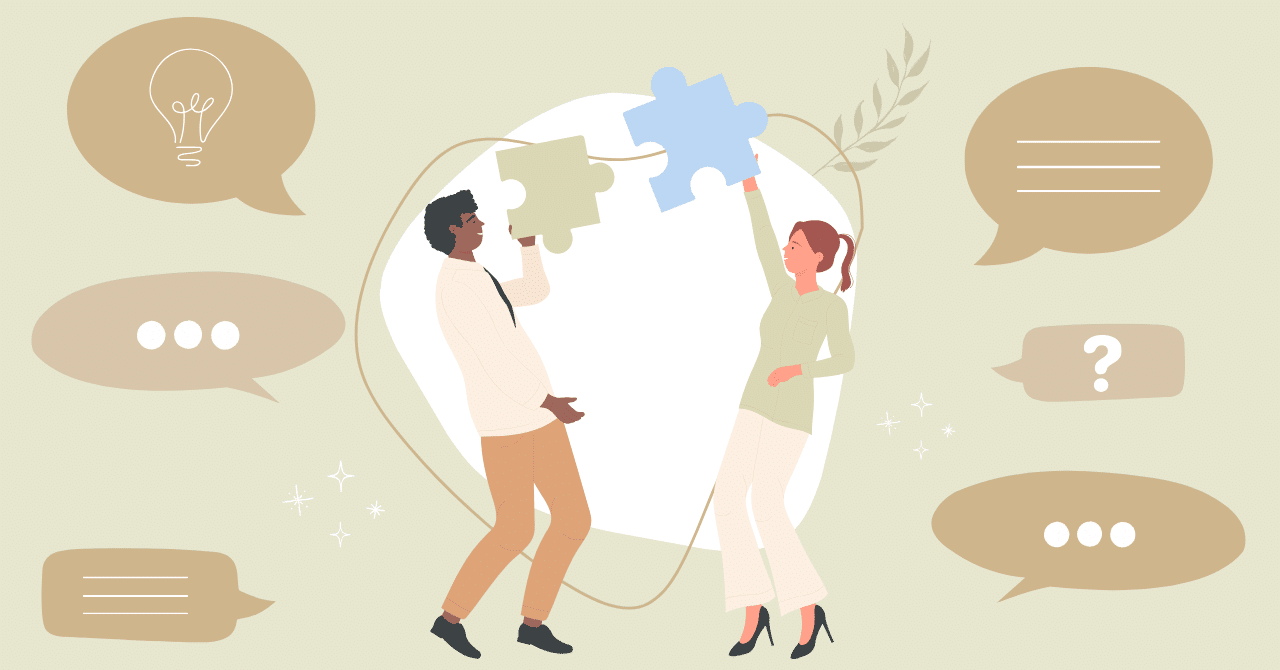
1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介
最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…
SECIモデルの実現に寄与する「場」
組織が知識を創造し、それらを共有、活用し、最終的に蓄積させるには、それぞれに「場」を設けることが必要となります。創造する場、共有する場、活用する場、蓄積する場、というものがそれぞれ必要です。この場がなければ、いくらフレームワークがあってもサイクルが回りません。またこの場をどのようにデザインするかによって、ナレッジマネジメントの成果が大きく左右されます。それぞれの場をSECIモデルの各プロセスに合わせて解説します。
・創発場(共同化に対応)
個人の暗黙知を共有する場です。先述の「同じ体験をする」という、個人の暗黙知を共有する場が該当します。また、日本企業でしばしば行われてきた「背中を見て学ぶ」や「仕事のやり方や技術を『盗む』」などの行為も、この創発場に含まれます。
・対話場(表出化に対応)
個人の暗黙知を言葉にし、対話を通じて形式知に変換する場です。ミーティングや1on1、社内SNSなどが該当します。ここで重要なのは、会話ではなく「対話」であることです。表面的なやりとりに留まらず、知を感覚レベルで共有し、形式知に変換できるよう深いコミュニケーションが必要です。
・システム場(結合化に対応)
形式知を相互に移動させながら、共有・編集・構築していき、新たな形式を生み出す場です。経営企画や人事などの部門がこの役割を担うことが多くなります。
・実践場(内面化に対応)
形式知を個々人の暗黙知へと身体化するための場です。ここでは、単なる形式知の伝達ではなく、形式知に束ねる形で何らかの経験的要素や人間的要素を提供することで暗黙知としての移転・発展を促すことができます。サービス業などでとくに重要な場です。PoC(概念実証)やトライアルの機会がこの場に該当します。
これらを通して個人が得た知識が、また創発場に戻ることでSECIモデルのサイクルが生まれます。そして、これらのサイクルは社内の資産としても蓄積されていくのです。

コミュニケーション手段に最適な社内SNSとは?おすすめツールの紹介
社内SNSツールはコミュニケーション活性化の有効な手段です。社内SNSとは、FacebookやInstagramなど誰もがフォローで…
コミュニティ形成としてのナレッジマネジメント
ナレッジマネジメントは、単なる情報の管理ではなく、共通の知識や価値観を持つことで組織内に「コミュニティ(共同体)」を形成・維持する役割も果たします。これは理念やMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の浸透と深く関係しており、同じ知識を共有しているからこそ、社員同士がスムーズに意思疎通でき、組織としてまとまりが生まれます。
たとえば「共通言語」や「プロトコル(手順・ルール)」が存在することで、社員は迷わずに行動や判断ができます。さらに広い意味では、日本語という言語知識があるからこそ、日本人同士が自然と「阿吽の呼吸」でコミュニケーションできるように、組織にも暗黙の理解や共通認識が必要です。ナレッジマネジメントは、こうした共通理解を育てる基盤となります。
ソーシャルネットワークの分析としてのナレッジマネジメント
ナレッジマネジメントにおけるソーシャルネットワーク分析は、組織内の知識や情報がどのように広がり、共有されているかを可視化し、チームやグループの状態を把握する手法です。従来は、誰が何を教えたか、どのような対話があったかといった記録は主観的に語られがちで、再現性や実務への応用も感覚的に行われてきました。
しかし現在では、社内チャットやメール、閲覧ログなどの客観的データをもとに、どの情報がよく参照されているか、誰が相談されることが多いか、ネットワークのハブとなっている人物は誰か、といった具体的な関係性や情報の流れを分析できるようになっています。
こうした分析は、情報が偏っていないか、コミュニケーションが活発に行われているかなど、組織の健全性を測る指標となり、ナレッジマネジメントの改善にもつながります。
生成AI(RAG)活用によるナレッジマネジメントの進化
ナレッジマネジメントの概念は普遍的ですが、そのツールは2025年現在、劇的な進化を遂げています。特に注目されているのが「生成AI」と「RAG(検索拡張生成)」の活用です。従来のナレッジマネジメントには「検索しても見つからない」「マニュアルを読む時間がない」という課題がありましたが、RAG技術はこれを根本から解消しつつあります。
生成AI×RAGとは
RAG(Retrieval-Augmented Generation)とは、生成AIが回答を生成する際に、事前に学習したデータだけでなく、企業独自のデータベース(社内Wiki、マニュアル、議事録など)から関連情報を検索・参照し、それを基に回答を作成する技術です。
これにより、AIが社内用語を理解し、最新の規定に基づいて「はい、その手続きは〇〇規定の第3条に基づき、以下の手順で行ってください」といった具体的かつ正確な回答を返すことが可能になりました。
大企業における活用事例
実際に、日本の大手企業でもRAGを活用したナレッジマネジメントの導入が進んでいます。
三井住友フィナンシャルグループ:社内規定やマニュアル約130万ファイルをAIが検索し、社員の問い合わせに回答するシステムを構築。金融機関特有の膨大かつ複雑なルール確認業務を効率化しています。
JR東日本:全社員向けに生成AIチャットを展開。社内文書を学習させることで、業務プロセスの確認や過去事例の検索時間を大幅に短縮しています。
東京ガス:独自開発の「AIGNIS-chat」により、専門的な技術用語を含む問い合わせにも対応。ベテラン技術者のノウハウ継承支援にも活用されています。
このように、AIの活用で多くの問題は解決できるようになり、現代のナレッジマネジメントにおいて、AIは単なるツールを超えた「知的パートナー」としての地位を確立しつつあります。
ナレッジマネジメントツールによる促進
企業・組織などでのナレッジマネジメントの運用は、ナレッジマネジメントツールを活用することで円滑に行うことができます。ここでは、ナレッジマネジメントツールの概要、活用するメリット、活用の際の注意点について詳しく解説します。
ナレッジマネジメントツールとは
ナレッジマネジメントツールは、組織内に蓄積された知識や経験を効率的に共有し、活用するためのプラットフォームです。従業員一人ひとりの知恵を結集することで、イノベーションの創出、業務効率の向上、企業価値の増大を実現します。
ナレッジマネジメントツールは、用途や特徴に応じて4種類に分類されます。
1. 専門知識型(ベストプラクティス共有型)
能力の高い社員やメンバーのノウハウや成功事例を共有することで、企業・組織全体のスキルレベルを底上げすることができ、人材流出による業務への影響を抑制し、組織の知識・ノウハウなどの資産を守ることができます。
活用例:営業成績トップの商談動画の共有、技術者のトラブルシューティング事例集。
2. 業務プロセス型(ナレッジ共有・形式知化)
顧客対応や書類作成など、標準化可能な業務プロセスを体系的に管理し、オペレーションの効率化や品質の安定化、人材育成の促進などにも機能します。
活用例:業務マニュアル作成ツール、ワークフローシステム。
3. ヘルプデスク型(顧客知識共有型)
社内FAQをデータベース化することで、社員・メンバーが必要な情報をスピーディーかつ簡単に検索できます。ヘルプデスク業務の負担軽減や顧客対応の迅速化など、幅広いメリットがあります。
活用例:社内問い合わせ対応ボット、FAQシステム。
4. 経営資産・戦略策定型
顧客データ、市場分析、競合分析など、経営に役立つ情報を集積し分析します。データに基づいた意思決定や戦略策定、リスク管理や新規事業開発などに活用可能です。
顧客情報・市場データ・製品情報など、企業・組織内に分散しているデータを統合することで、新たなビジネスチャンスを発見し、データ分析に基づいた筋の良い意思決定を行うことができるからです。
ナレッジマネジメントツールのメリット
ベテラン社員の暗黙知や経験、ノウハウを体系的に記録し、共有することで、企業・組織全体のスキルレベルを底上げすることができ、人材流出による業務への影響を抑制し、組織の知識・ノウハウなどの資産を守ることができます。
その他、情報検索の迅速化と業務効率の向上も期待できます。必要な情報を素早く検索できる検索機能により、社員・メンバーの情報収集にかかる時間を大幅に削減できます。また、業務マニュアルやFAQなどを整備することで、一律に標準化された業務フローを実現し、作業の効率化を促進します。
ナレッジマネジメントツールの注意点
ナレッジマネジメントツールは強力な武器ですが、闇雲な導入は失敗の元です。以下の点に注意が必要です。
成果の定量化が難しい:営業成績のように数字で見えにくいため、貢献度を評価する仕組みが必要です。
コストと工数:ツールの利用料だけでなく、情報を入力・更新する社員の工数コストが発生します。入力の手間を減らすUI/UXや、AIによる支援機能が重要になります。
ナレッジマネジメント導入の流れとポイント
ここまでは、ナレッジマネジメントの定義・概要についてお伝えしました。では、具体的に、企業・組織がナレッジマネジメントを導入する流れは、どのようなものなのでしょうか。成功のためのステップを見ていきましょう。
導入の目的を明確にする
ナレッジマネジメントを実施するには、まずは具体的な導入の目標を設定することが重要です。単に「情報を共有したい」という漠然とした目的ではなく、「顧客対応の効率化」「業務の標準化」「人材育成の強化」など、具体的な目標を設定することで、導入後の活用方法も見えてきます。
FAQや社内Wikiなどの活用も有効ですが、それ以上に重要なのは、社員・メンバーへの丁寧な説明です。なぜナレッジマネジメントを導入するのか、その背景と目的を明確に伝え、目標達成への貢献を意識させることで、社員・メンバーの積極的な参加を促進できます。
共有したい情報を決定する
ナレッジマネジメントの目的・目標を定めたら、次は具体的にどのようなナレッジを集め、社員・メンバーで共有するかを決定しましょう。その際に鍵となるのが、現場で働く社員の「業務上の課題」と「困りごと」を洗い出すことです。
- 素早く商品やサービスの情報を引き出せる仕組み
- トラブル対処に関する具体的な事例
- 自社の製品や事業方針に関する知識
- 手本となるオペレーターの会話技術や対応の事例
情報・事例・ノウハウに関する知識を素早く引き出せるのが、ナレッジマネジメントがビジネスで有効な理由です。
情報共有を行う「場」を整える
ナレッジマネジメントを機能させるには、情報共有の「場」作りが重要です。せっかく蓄積したナレッジも、うまく共有できる場がなければ活かすことはできません。まずは目的・目標に合わせて集めたナレッジを考慮し、どのような「場」にデザインするかを決め、整えていきましょう。
その際、ポイントとなるのは「ナレッジの種類・特性に合った場作り」と「場を継続的に改善する」の2つです。また、ナレッジの情報共有には社内コミュニケーションの活性化も欠かせません。その場合、社内SNSや社内報などを活用し、ナレッジの情報共有を社内に浸透させる試みも有効になります。
重要:ツール導入だけでは失敗する。「対話」の重要性
多くの企業が「高性能なツールを導入すればナレッジ共有が進む」と誤解しがちですが、これは大きな落とし穴です。弊社ソフィアが実施した「インターナルコミュニケーション実態調査2024」の結果からは、ツールだけでは解決できない組織課題が浮き彫りになっています。
弊社ソフィアの調査では、社内コミュニケーション活性化のために最も実施されている施策は「1on1ミーティング」である一方、同時に「効果がない施策」の上位にも挙げられています。これは「形だけの対話」が行われており、本質的な信頼関係やナレッジ共有(共同化)に至っていないことを示唆しています。
また、経営戦略に対する社員の共感度は「わずか1割」という結果も出ており、一方的な情報発信だけでは社員の腹落ち感(内面化)醸成には不十分であることが分かります。
ナレッジマネジメントを成功させるには、ツール(ハード)の整備と同時に、「対話」「教育」「ツール」の3本柱で組織風土(ソフト)を醸成していくことが不可欠です。
ナレッジマネジメントの具体的な導入事例
属人化したナレッジの壁を超える:全社横断のナレッジ基盤整備
長年の事業運営により蓄積された知見やノウハウが、個人や部署に属人化し、業務の再現性や効率性に課題を抱えていたある企業では、全社レベルでのナレッジマネジメントの強化に乗り出しました。まず着手したのは、業務プロセス別のナレッジ分類フレームを定義すること。各部門で行っている業務を整理し、「汎用化できるノウハウ」「個別判断が必要な対応」「FAQで十分なもの」などの観点で仕分けしました。
次に、SharePoint Onlineで構築したナレッジベースを全社へ展開。業務の要点や判断基準、活用事例を誰もが検索・参照できるように整備しました。また、ナレッジの投稿や改善提案に貢献した社員を可視化し、社内報や表彰制度でフィードバックする仕組みを導入。こうした仕掛けにより、情報の「蓄積」から「活用」への転換が進みつつあります。
ベテランの暗黙知を可視化:現場力を全社資産へ転換する社内大学プロジェクト
製造・保守部門を中心に長年現場を支えてきたベテラン社員の知見は、企業にとってかけがえのない財産です。ある企業ではそのノウハウが明文化されず、若手への継承が思うように進んでいませんでした。特にベテランの引退が近づく中で、「知が失われる」危機感が高まりました。
そこで取り組んだのが、ベテラン社員の知識を体系的に抽出・記録し、動画やマニュアルとして共有するプロジェクトです。ヒアリングを通じて「どんな場面で、どんな判断をしているのか」「何に注意しているのか」といった現場感覚を可視化し、撮影や対話形式でナレッジを映像化しました。
さらに、eラーニング化による標準教育コンテンツも整備。OJTに頼らず、誰でも一定水準のスキルを身につけられる仕組みが生まれました。このナレッジ化によって、現場の生産性は向上し、属人性が大幅に解消されました。
「勝ち筋」を組織全体で再現:営業部門におけるナレッジ共有プラットフォームの構築
数千名の営業部隊を抱えるある企業では、顧客と密に繋がりながら、要望をいち早く受け取り、素早く応える従来の営業活動に限界を感じ、「要望が形になるよりも前に、課題を自ら設定して提案していく」スタイルへの変革が求められていました。
顧客の発言が起点となり、それに合わせて情報を探すというプロセスから、営業社員自身が顧客リストを眺めながら、顧客について考え、自分起点で情報を探すプロセスに変えていくために、営業社員は日常的に様々な情報を得ておく必要があります。
そこで同社は、「ナレッジプラットフォーム」を構築する取り組みを開始しました。まずは各営業社員が作成して顧客に提示している「提案書」「企画書」「ディスカッション資料」を収集し、誰でもアクセスできるよう社内サイトにまとめます。そしてすべての資料には、「業界」「商談ステージ」「提供サービス」などカテゴリ別にラベルを設け、他の担当者が状況に応じて検索しやすくなっています。
それら一つ一つの資料の価値をさらに高めるために、受注に至ったプロセスや顧客の反応、セールストーク、さらには失注事例までをヒアリングし、同プラットフォーム上で読み物コンテンツとして発信しつつ、いくつかの実際の資料との紐づけを行いました。
「資料」を知識の媒介として収集する取り組みからスタートしましたが、最も重要なのは、この資料を「どう使うのか」という知恵をどう抽出し、共有するかという点でした。プラットフォームに集められた資料から、ナレッジマネジメントチームが知恵を抽出し、編集し、再度プラットフォームに再展開する活動により、ユーザーに信頼されるプラットフォームとなり、高いアクセス数・利用率を維持し続けています。
まとめ
ナレッジマネジメントは、組織内の知識を体系化し、効果的に管理・活用することを目的とするプロセスです。その導入には、組織文化への適合、ナレッジ共有の仕組みといったポイントが重要です。
さまざまなツールや技術を活用してナレッジマネジメントを支援し、生産性向上やイノベーションの促進を図ることが期待されます。組織全体の知識活用を強化し、問題解決や業務効率化に貢献する重要な取り組みなので、ぜひナレッジマネジメントの導入を検討してみてはいかがでしょうか。