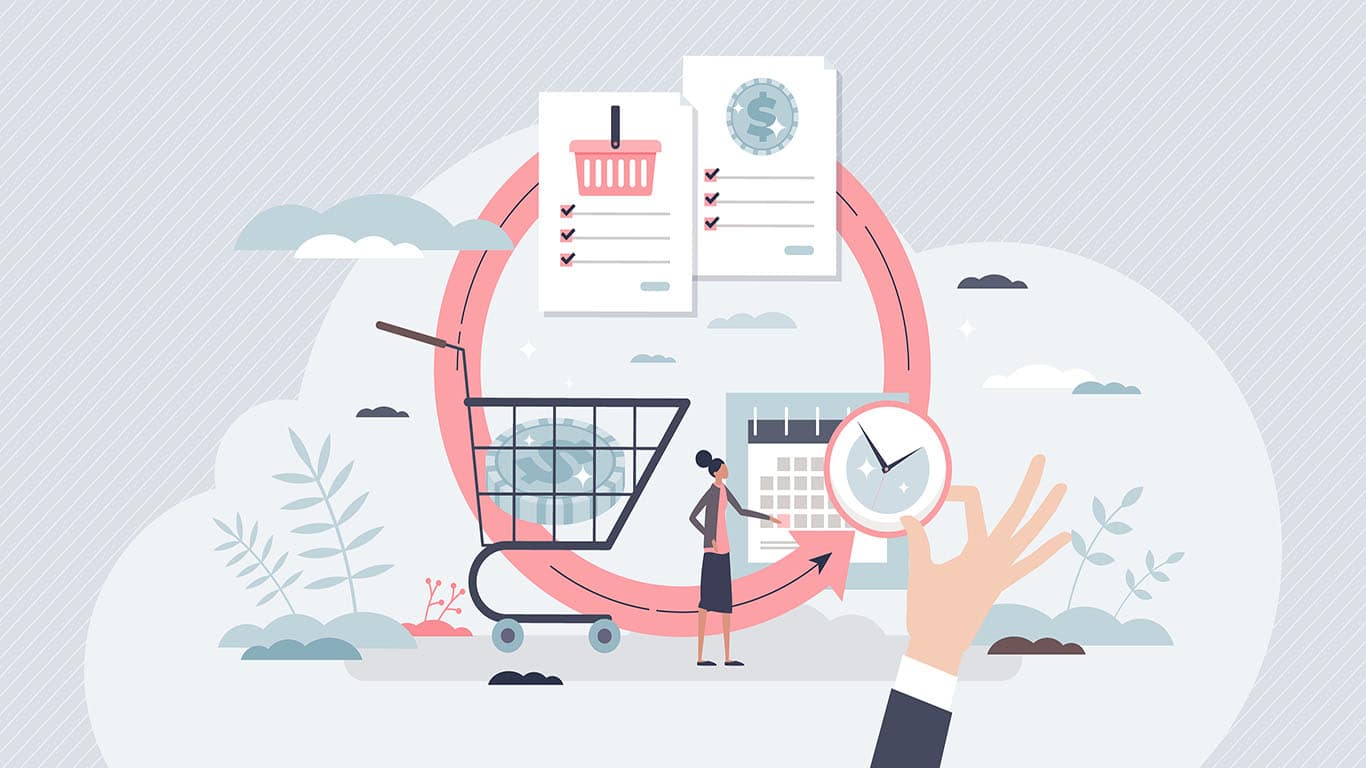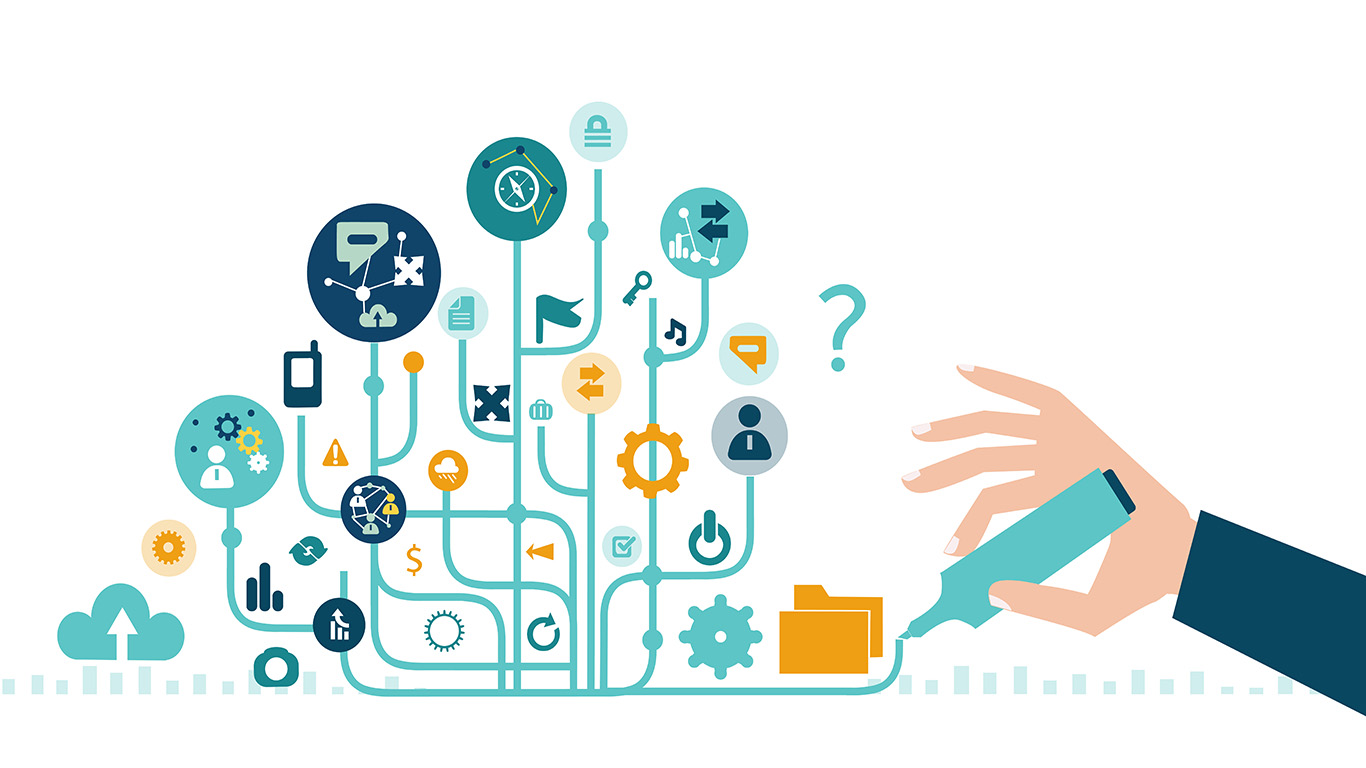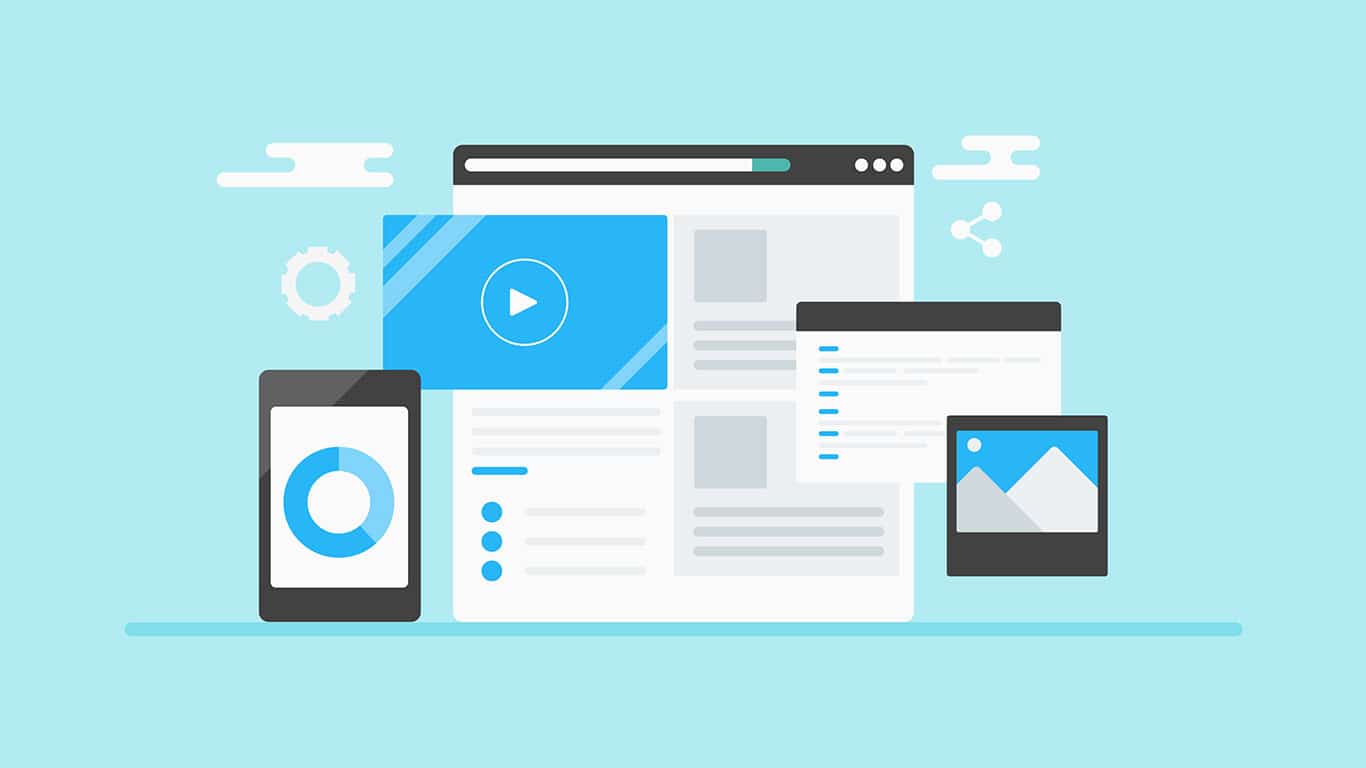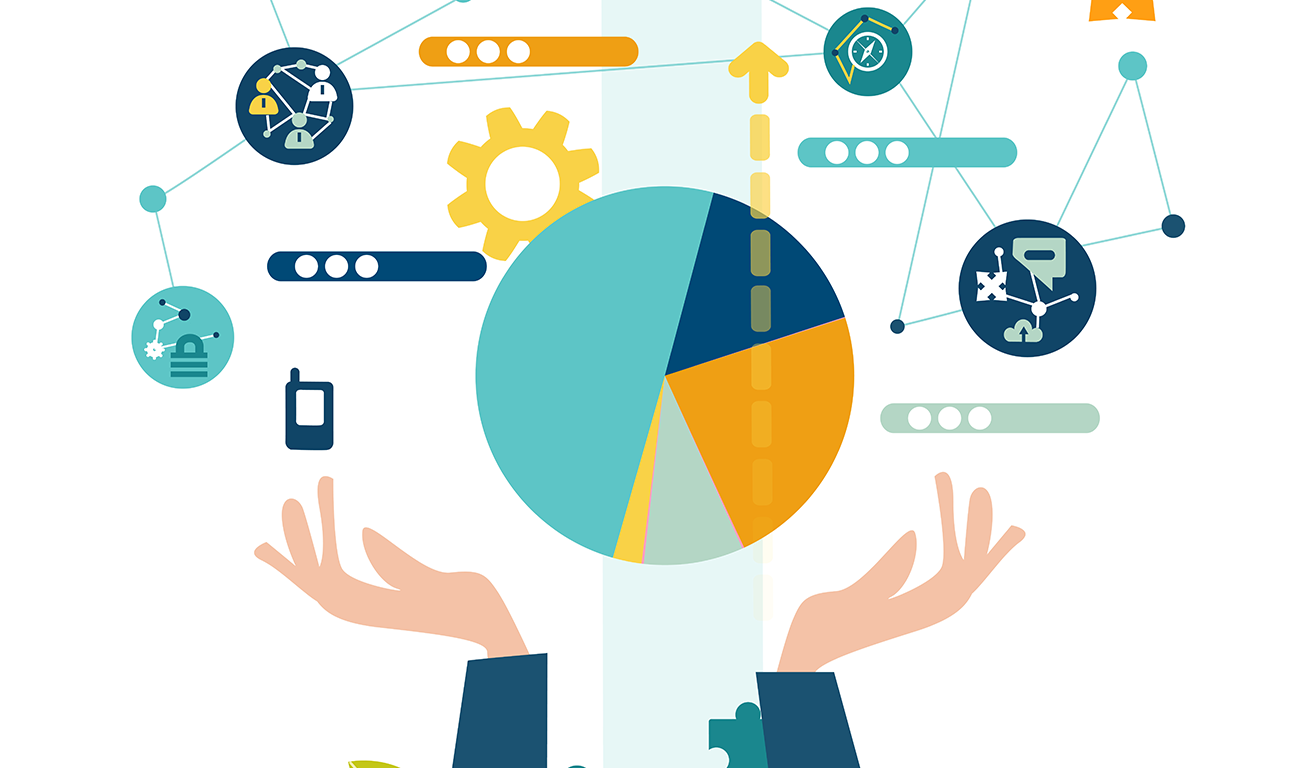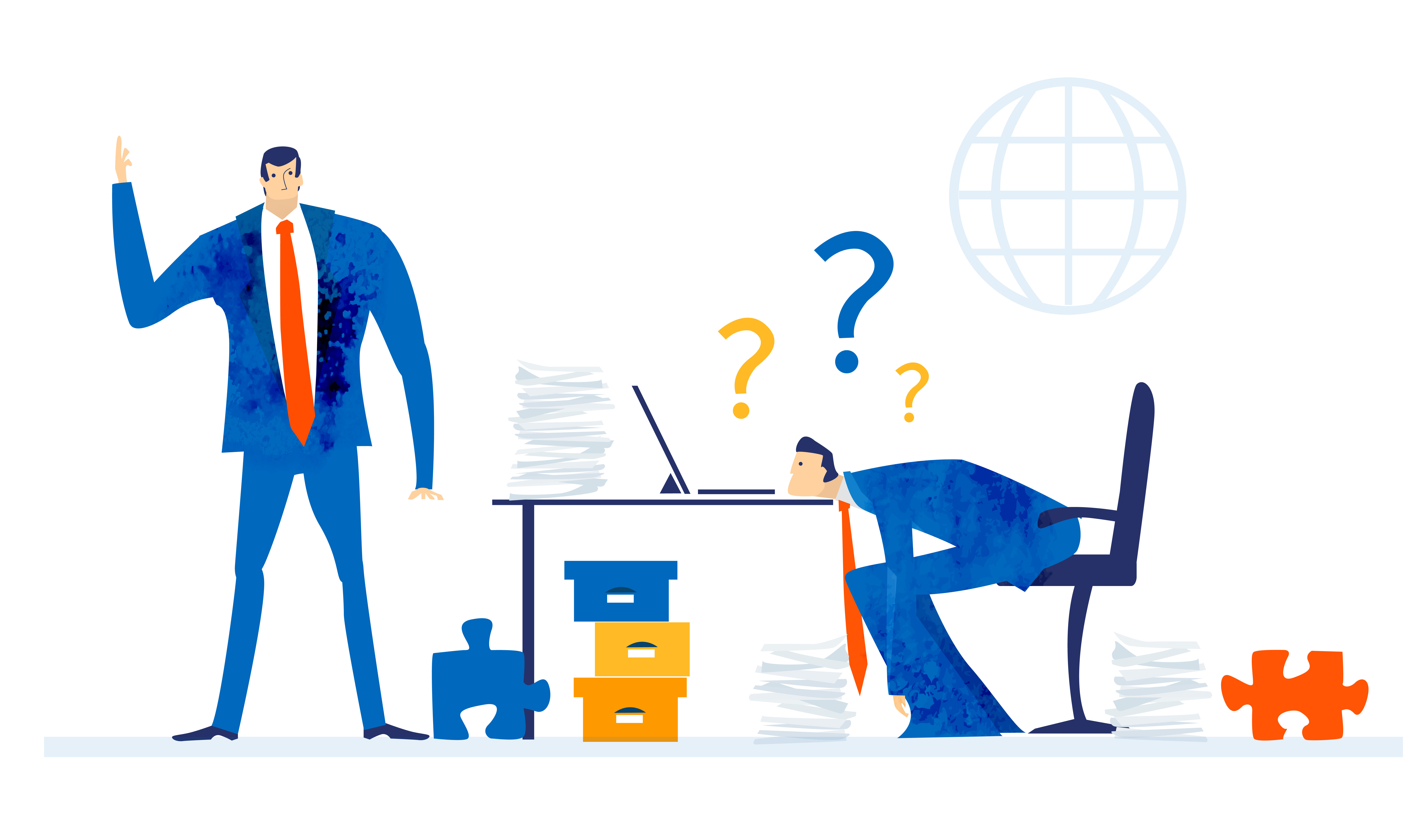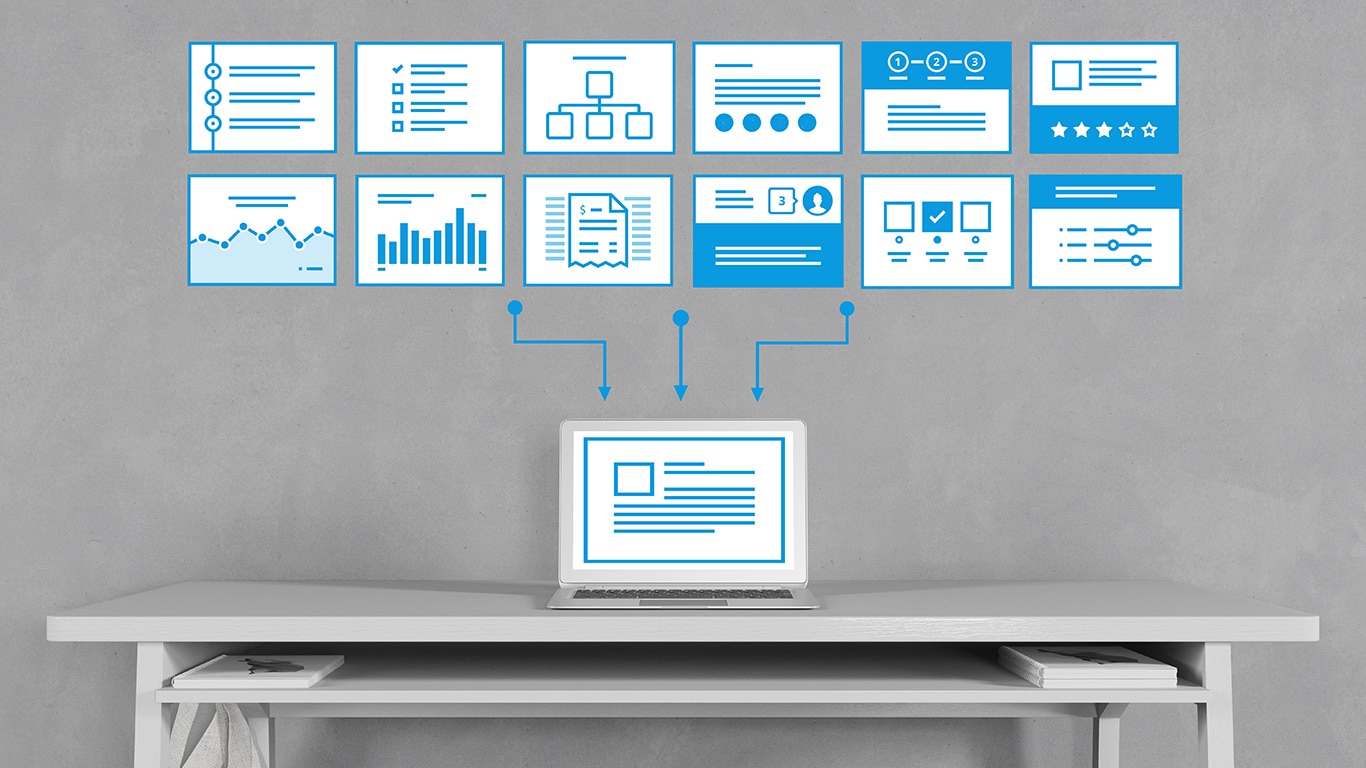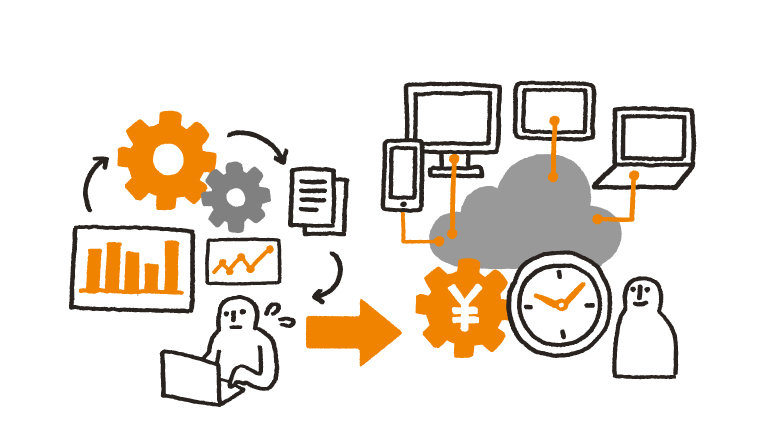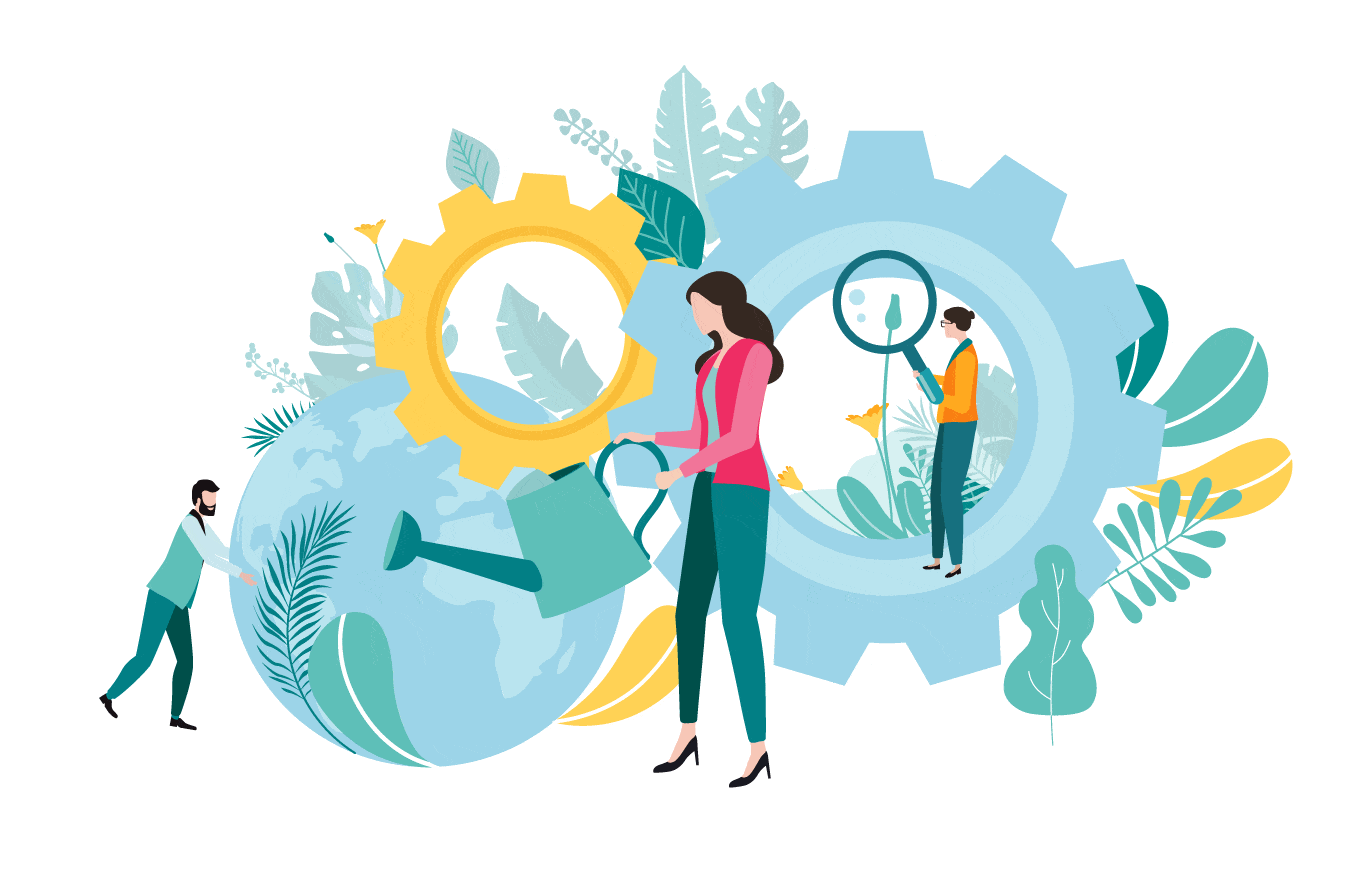社内ポータルサイト導入成功事例:手順・KPI・定着のポイント
最終更新日:2025.07.31

目次
働き方の多様化に伴い、社内ポータルサイトに注目が集まっています。全ての社員が同じ場所で働くことが当たり前ではなくなり、情報共有のタイムラグや社内コミュニケーション不足が目立つようになりました。
その解決策として、効率的に社内の情報を一元化できる社内ポータルサイトは非常に効果的です。本記事では、社内ポータルサイトの役割や機能、導入の実際から成功要因に至るまで、企業の事例を交えて体系的に解説します。
社内ポータルサイトとは?
「ポータル(portal)」という言葉が「玄関」や「入り口」を意味するとおり、ポータルサイトは情報にアクセスする入り口の役割を持つサイトです。その企業版が社内ポータルサイトとなります。
社内ポータルサイトは、社内のさまざまな情報を集約したサイトです。一般的なポータルサイトと異なり、イントラネットを通じて社員だけがアクセスできます。
社内ポータルサイトと社内情報共有ツールとの違い
社内ポータルサイトと似た社内向けツールとして、グループウェアや社内掲示板、社内SNSなどがあります。社内ポータルは情報共有の入口という役割を第一に持ちますが、これら他のツールは目的が異なります。以下に主要な社内情報共有ツールとの違いをまとめます。
-
- グループウェア
スケジュール管理やメッセージ機能、勤怠管理など社内ポータルと一部機能が重複しますが、基本的には業務効率化を目的としたツールです。社内ポータルが全社横断の情報共有基盤であるのに対し、グループウェアはチームや部署内の予定調整、タスク管理、メールなどに特化し、生産性向上を主眼としています。
- グループウェア
-
- 社内SNS
FacebookやLINEのようなSNSを社内限定で利用するツールで、社員同士のコミュニケーション活性化が主目的です。部署や世代を超えた交流促進に強みがありますが、社内ポータルサイトとは異なり業務情報の集約には向きません(情報が流れやすく蓄積しづらい傾向があります)。
- 社内SNS

コミュニケーション手段に最適な社内SNSとは?おすすめツールの紹介
社内SNSツールはコミュニケーション活性化の有効な手段です。社内SNSとは、FacebookやInstagramなど誰もがフォローで…
- 社内掲示板
社員専用の電子掲示板で、従来オフィスの壁に貼り出していた連絡事項をデジタル化したものです。お知らせや掲示情報の周知に用いられます。ただし近年はグループウェアや社内SNSに置き換えられ、導入企業は減少しています。掲示板やSNS、メールなど各種ツールへの入り口を一本化するサイトが社内ポータルサイトといえます。
社内ポータルサイトでできること
社内ポータルサイトでは上述のような他のツールが提供する機能の多くも実現できますが、基本的には社内のさまざまな情報へアクセスする統合入口という位置づけです。社内ポータルサイトで代表的に実現できることを見ていきましょう。
情報の一元管理
会社から発せられる情報を社内ポータルサイト上で集約・一元管理できます。社内の最新情報を一か所に集めることで、社員は必要な情報を探し回らずに済み、業務効率が向上します。
また、全社で一つのポータルを閲覧することで各部署の状況をリアルタイムに共有でき、部署横断の連携強化にもつながります。”ペーパーレス”推進にも寄与し、紙での回覧や掲示を減らせます。
【情報一元管理の主な機能例】
スケジュール管理機能、プロジェクト管理機能、ファイル共有機能など。たとえば各社員がポータルのカレンダーで予定やタスクを共有すれば会議日程の調整が容易になります。プロジェクト管理機能で誰がどのタスクを担当し進捗はどうかを可視化すれば、個別に確認する手間が省けます。オンラインのファイル共有により、リモートワーク中でも円滑に共同作業が進められ、チーム全体の課題把握も容易になります。
申請・ワークフロー機能
各種申請手続きをオンライン化するワークフロー機能も社内ポータルで提供できます。稟議や経費精算などの申請を紙から電子化することで、承認プロセスの迅速化とペーパーレス化を同時に実現します。
従来紙で回覧していた申請をポータル上で行えば、決裁がどこで滞留しているか一目瞭然となり、承認催促も容易です。その結果、決裁リードタイムの短縮や問い合わせ対応工数の削減につながります。
【申請ワークフローの主な機能例】
勤怠管理機能、経費・交通費精算申請、稟議申請機能など。たとえば社内ポータルに出退勤時間を入力することで打刻の代替とし、リモートワークでも勤怠管理が可能になります。
また、経費精算や稟議申請をポータル上で完結させれば、承認者が出張中でもオンラインで決裁できるため業務が滞りません。
コミュニケーション機能
社員同士や経営層と社員間の円滑な情報交換を支えるコミュニケーション機能も社内ポータルの重要な役割です。経営層から全社員へのメッセージ発信と社員からのコメント、社員同士がナレッジを持ち寄り共有する場など、オフラインで不足しがちな対話をオンラインで補完します。特に大企業では普段接点のない他部署同士の交流促進にも役立つでしょう。
【コミュニケーションの主な機能例】
掲示板機能、チャットなどのコミュニケーションツール連携。たとえばポータルの掲示板に社内周知事項やFAQを投稿すれば、社員は誰でも閲覧・質問できます。他部署の人に電話や対面で問い合わせる手間も減り、気軽に疑問を解消できます。またチャット形式のツールを組み込めば、メールほど堅苦しくなく迅速なやり取りが可能です。
普段からスマートフォンのチャットに慣れている社員が多いため利用のハードルも低く、業務連絡だけでなく雑談も生まれ社員同士のつながり強化にもつながります。
これからの社内ポータルサイト
これまで多くの企業はデジタル化の波に乗り遅れないよう、既存業務の電子化を目的に社内ポータルサイトを導入してきたのではないでしょうか。しかし現在、社内ポータルが果たすべき役割は単なる業務デジタル化に留まらず、さらに広がりを見せています。
ここでは、現代の社内ポータルサイトが実現し得ることを3つ紹介します。
スピード感のある情報共有
激しい市場競争を生き残るには、社内の迅速な情報共有と意思決定が欠かせません。たとえば急ぎの決裁案件で決裁者の帰社を待っていては機会損失になり、必要な情報を届けるのに毎回メール作成していては時間がかかります。
社内ポータルサイトを活用すれば、複数人との同時コミュニケーションや情報共有が時間・場所を問わず可能です。チャットツールなどと連携して部署や役職の壁を取り払い、旧来のやり方を変革すれば、情報伝達のスピードを一段と加速できます。
ノウハウの蓄積と業務効率化
社内ポータルには社員の持つノウハウやナレッジを一箇所に集約し、組織の知見として蓄積する役割もあります。多くの企業ではノウハウが特定のベテラン個人に属人化しがちです。しかし人材の流動化が進む中、そのベテランが異動・退職しても業務が回るようにしておく必要があります。
社内ポータルサイト上にナレッジを蓄積しておけば、新人が入社しても迷わず業務を学習できます。多数の人が知見を共有することで内容が磨かれ、結果として業務効率化にもつながります。
働き方改革の推進
社内ポータルサイトは企業の働き方改革にも資するツールです。ポータルが整備されれば社員はいつでもどこからでも社内情報にアクセスでき、「会社でしかできない業務」が減ります。
勤怠打刻もオンラインで行えるため、出社せず自宅やサテライトオフィスから働けるようになります。時間・場所に縛られない柔軟な働き方を全社で実現できれば、従業員満足度が向上し人材定着率も上がるでしょう。
企業のイメージ向上により優秀な人材の採用にも良い影響があります。
社内ポータルサイトの導入手順
実際に社内ポータルを導入・構築する際は、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは一般的な導入手順を順に解説します。
目的の明確化とコンセプト策定
最初に「社内ポータルを導入して何を解決したいのか」を明確にします。情報共有の効率化なのか、ナレッジ蓄積なのか、働き方改革の基盤づくりなのか、目的次第で求められる機能や運用方針も変わります。
目的に沿ったサイトコンセプト(たとえば「全社員が毎日使いたくなる情報共有基盤」など)を定め、経営層の合意を得ます。
要件定義と設計
次に目的に基づき必要な機能要件を洗い出し、設計を行います。具体的には、掲載するコンテンツの種類と構造、アクセス権限(どの部署・役職がどの情報を閲覧できるか)、認証方法(社内ADとの連携やシングルサインオンの有無)などを検討します。
動画コンテンツを載せるなら動画配信サービスとの連携が必要となり、多言語対応が要る場合もあります。現行システムからデータ移行する場合はその計画も設計段階で立てます。
コンテンツ準備と情報設計
ポータルに掲載すべき情報を洗い出し、コンテンツを整理します。社内報記事、就業規則・マニュアル類、よくある質問(FAQ)、各種申請フォームなど、社員が必要とする情報を収集します。
同時に、社員が迷わず探せるようカテゴリ分類やメニュー構成を設計します。情報の優先度に応じてトップページの配置を決め、必要ならタグ付けや検索機能で探しやすさを確保します。
システム構築・デザイン開発
定義した要件に基づき、実際に社内ポータルサイトを構築します。自社サーバー上に構築するか、クラウドサービスや市販のポータルパッケージ(たとえばSharePointやNotes、専用CMSなど)を活用するかも決定します。社内のITリテラシーを考慮し、直感的で使いやすいUI/UXデザインを心がけます。
情報量が多いためシンプルで視認性の高いデザインにし、社内規定のブランドカラー等も反映させます。開発期間は規模により数ヶ月程度かかります。
テスト・レビュー
完成したポータルを試験運用し、動作や使い勝手を検証します。とくにアクセス権やシングルサインオンの認証周り、検索機能の精度などは入念にテストします。
一部部署やパイロットユーザーに利用してもらい、フィードバックを収集するのも有効です。操作に迷いがないか、不具合はないか、社内の反応を確認し必要に応じて修正を加えます。
本番導入と周知活動
十分にテストを終えたら、全社への本格リリースを行います。切り替え時にはアクセス集中などに備えつつ、新旧サイトの移行をスムーズに完了させます。
リリース後は社内への周知徹底が重要です。朝礼や社内報、メールなどでポータルの利用方法やメリットを案内し、各部門のキーパーソンにも協力してもらい現場への展開を図ります。
初期段階で利用を習慣づけてもらうために、研修会を開いたり利用マニュアルを配布したりする企業もあります。
運用と改善
導入して終わりではなく、運用開始後も定期的なメンテナンスと改善が必要です。アクセスログやユーザーからの声をもとに、コンテンツの更新・追加やUI改善を続けます。運用担当者や推進チームを設置し、社内ポータルが常に最新かつ使いやすい状態を維持しましょう。
社内ポータルサイトの運用を成功させるポイント
社内ポータルサイトを、単に業務のデジタル化や業務効率化だけを目的に導入する企業も少なくありません。しかし社内ポータルサイトは、むしろ社内のコミュニケーション活性化や働き方改革を実現させるソリューションとして導入することをおすすめします。
ここでは社内ポータルサイトの運用を成功させるポイントを3つ紹介します。
パーソナライズ機能を搭載する
社内ポータルサイトは、パーソナライズ機能を搭載したものを選ぶことが成功のポイントです。パーソナライズ機能とは、社員個人が使いやすいようにカスタマイズできる機能のことを指します。
情報がすべて一元化されていても、社員自身が必要な情報を探し回らなければならないようなシステムだと、必要な情報が必要としている人に届かない恐れがあります。かといって全社員向けにすべての情報を画一的に表示していては、自分に不要なものばかりが目に入り便利とはいえません。
パーソナライズ機能が搭載されていれば、社員は自分の所属部署やプロジェクト、自身に関連する情報だけを表示するようカスタマイズできます。自分に関係のある重要情報の見逃しが減り、社内ポータルサイトを効率的に活用できるでしょう。
モバイル対応させる
社内ポータルサイトの運用成功にはモバイル対応も重要です。従来は社内PCでの利用が前提でしたが、リモートワークの普及や働き方の多様化により、社員全員が同じオフィスで同時間働くとは限らなくなりました。すべての社員に社用PCを配布できる企業ばかりではないため、私物スマホ等からでも安全にアクセスできる環境整備が求められます。
スマートフォンやタブレット対応のポータルであれば、社員がどこからでも必要情報にアクセスでき、会社からの緊急連絡も迅速に周知できます。最近はモバイルファースト設計で直感的に操作できるダッシュボードやセキュリティ強化機能を備えた事例も増えています。モバイル対応は今や社内ポータルの必須要件といえるでしょう。
従業員の評価を調査し、反映させる
いくら高機能の社内ポータルサイトを作成しても、使い勝手が悪いなど従業員の満足度が低ければ、やがて使ってもらえなくなってしまいます。そのような事態を避けるためには、従業員にポータルサイトを評価してもらい、不満点を改善していくことが重要です。
定期的にユーザーアンケートやヒアリングを実施する、匿名で自由意見を投稿できるフィードバックフォームを設置するといった施策で、従業員が意見しやすい環境を整えましょう。寄せられた要望をもとにUIの微調整やコンテンツ追加を重ねることで、「使えるポータル」に育てていくことができます。
実際に社員の声を取り入れてデザインを改善し、本番運用後も段階的に変更を重ねて成功したケースもあります。
社内ポータル導入の課題と解決策
社内ポータルの導入・運用にはいくつかの課題も存在します。しかし適切な対策を講じることで、それらの課題を乗り越えることが可能です。ここではよくある課題とその解決策を紹介します。
課題1: 情報の更新や管理の負担が増大
ポータルには常に最新情報を載せ続ける必要があり、担当者にとって更新作業が重荷になるケースがあります。また情報が増えるにつれ整理・分類も難しくなり、放置するとコンテンツが陳腐化してしまいます。
【解決策】
運用体制を整備し、更新フローを標準化します。たとえば部門ごとにコンテンツ責任者を置き定期更新をルーティン化する、古い情報はアーカイブや削除を定期的に実施するなどです。
検索機能の精度向上やタグ付けで探しやすい工夫をすることも必要です。AIチャットボットを導入し社員が質問すると関連情報を案内する仕組みを加えるなど、メンテナンス負荷を下げるソリューションも検討できます。
課題2: 情報の信頼性確保
社員が自由に情報を発信・共有できる反面、内容の正確性や最新性をどう担保するかという課題があります。誤った情報や承認前の情報が広まるリスクもゼロではありません。
【解決策】
ポータル上の公式情報と社員投稿情報を区別し、公式コンテンツには管理部門のチェックを入れるルールを作ります。投稿ガイドラインを設け、内容に誤りを発見した場合の訂正フローも用意します。情報の出所(作成者や最終更新日)を明示することで利用者の信頼感を高めることも大切です。
課題3: 社内で十分に活用されない
システムを用意して「どうぞ」と告知するだけでは、なかなか利用が定着しない場合があります。UIが複雑で使いずらく、何が載っているか知られていないと、せっかく導入しても閲覧率が低迷します。
【解決策】
社内浸透施策を積極的に行います。まずポータルの目的と利点を繰り返し周知し、研修や説明会で使い方を教育します。操作マニュアルやFAQをポータル上に用意し、新入社員研修にも組み込みます。また、社内報で活用事例を紹介し、「こんな情報も見られる」と定期的にアピールします。加えて、日常的に使うよう促す仕掛けも有効です。
たとえば社員のブラウザのホームページを社内ポータルに設定しておけば、毎朝必ず目にするため閲覧習慣が付きます。経営トップが重要メッセージをポータル経由で発信し社員に見るよう促す、という形で率先利用することも大きな推進力になります。
課題4: コンテンツ投稿の敷居が高い
導入当初は社員が何を投稿してよいかわからず、情報発信が活発化しないことがあります。とくに双方向コミュニケーションに不慣れな企業文化だと、社員が遠慮してしまいポータルが閲覧専門になってしまう恐れもあります。
【解決策】
最初にできるだけ多くのサンプル投稿やテンプレートを用意し、社員が参考にできるようにします。「週報の共有」「成功事例紹介」「業務マニュアルQ&A」など具体例を示し、投稿フォーマットも提示すれば、何をどの程度書けばよいか戸惑わずに済みます。
投稿者への「いいね」や表彰制度を設けモチベーションを高めるのも有効です。現場で積極的なメンバーをポータル推進アンバサダーに任命し、新着投稿を促すような活動も検討してください。
課題5: 複数の類似ポータルが乱立している
企業規模が大きいほど部署ごとに独自のイントラサイトが存在し、情報が点在しているケースがあります。社員は「どのサイトに何があるか」わからず混乱し、結局十分に使われないという問題につながります。
【解決策】
社内ポータルはできるだけ一本化するのが理想です。グループ各社・各部門でバラバラに運用していたポータルを統合し、UXデザインや情報分類を統一した事例もあります。どうしても複数運用せざるを得ない場合は、メインのポータルから他サイトへのリンク集を設けて入り口を一元化しましょう。統合には時間がかかるため、まずは主要部門から段階的に導入し、効果を確認しつつ全社展開する方法も有効です。
社内ポータル導入の効果とKPI指標
社内ポータルサイトの導入効果を客観的に評価するため、KPI(重要業績評価指標)を設定してモニタリングすることが重要です。
KPIを継続的にモニタリングすることで、社内ポータルサイトが社内でどれだけ活用され価値を生んでいるかを明確に把握できます。数値目標を設定しPDCAを回すことで、社内ポータルを企業文化に根付かせ、より効果的なものへと発展させていくことが可能です。
具体的には以下のような指標が考えられます。
利用率・アクティブユーザー数
一定期間内にポータルへログインしたユニークユーザー数やログイン率は、社員がポータルを必要と感じ実際に使っているかを示す基本指標です。社員の興味や利便性が低ければ利用時間は伸びません。全社員のうち何割が定期的にアクセスしているか、部署別・勤務地別の利用状況も把握しましょう。
平均滞在時間・閲覧ページ数
ユーザーがポータル内で費やす平均時間や、一度の訪問で閲覧するページ数も重要です。短すぎる場合、必要な情報にたどり着けず離脱している可能性があります。逆に長く閲覧している社員が多ければ、ポータル上で充実した情報収集・コラボレーションが行われていると判断できます。
コンテンツの投稿数・反応数
社員による新規投稿(お知らせ記事や掲示板スレッド等)の件数、コメント数、「いいね」などのリアクション数もエンゲージメントを測る指標です。たとえばクリック数やコメント数が多ければ、社員同士の積極的な情報共有が行われていることがわかります。新規コンテンツ作成者の数もチェックしましょう(特定の人だけでなく多くの社員が投稿しているかが望ましい)。
コンテンツ閲覧数(人気・不人気コンテンツ)
ポータル内でどの記事・ページがよく読まれているかを分析すると、社員の関心分野や必要とされている情報が見えてきます。逆に閲覧数が極端に少ないコンテンツは不要または埋もれている可能性があります。閲覧ランキング上位のトピックから有用な情報をさらに拡充し、下位のものは整理・削除することでサイト品質を向上できます。
業務効率への効果指標
社内ポータル導入が実際の業務効率改善にどう寄与したかも定量化します。「社内問い合わせ件数の減少」「意思決定の迅速化」「残業時間の削減」などです。
また、本記事で紹介する事例企業でも、規程類の問い合わせが大幅減(=管理部門の負担軽減)やFAX送信の廃止(毎月600〜700件のFAXをゼロに)といった効果を実現しています。これらはROI(投資対効果)につながる重要な成果です。
社内ポータルの効果を測る際は、導入前後で業務KPIがどう変化したかを追跡し、定量的なメリットを社内に共有しましょう。
従業員満足度
定性的ではありますが、ポータル利用満足度が高い社員ほど仕事へのエンゲージメントが高まり生産性も上がる傾向があり、ひいては離職率低下など人事面のROIにもつながります。調査結果は経営層にレポートし、さらなる改善投資の説得材料としましょう。
社内ポータルサイトの成功事例
ここからは、社内ポータルサイトを効果的に構築・活用した企業の事例を4社紹介します。
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社では、散在していたデータを整理し、すべてを社内ポータルサイト「Global Portal」からアクセスできるようにすることで「情報の探しやすさ」を実現しています。
同社の社員は出社するとまず社内ポータルサイトを立ち上げて、メールチェック、経費処理、社内決済などの業務に入っていきます。あちこちに点在するツールを個別に起動しなくても社内ポータルサイトひとつで業務を始められるため、情報集約の観点で極めて優れた環境といえます。
さらに「Global Portal」では、送り手である会社都合の情報発信ではなく、各部門が自発的に情報を取得する「プル型」の情報共有を実現しています。社員が「自分からアクセスしよう」と思える社内ポータルサイトになっている点も成功の鍵といえるでしょう。
同社はこの社内ポータルサイトの運用によって、社内規程・手続きに関する問い合わせなど管理部門への問い合わせ工数を大幅削減することにも成功しました。
株式会社東横イン
東横インでは2016年に、今後30年の成長ビジョン達成に向けてクラウドを活用した社内ポータルサイトを中心とした情報共有基盤へと全面刷新しました。
社内公募で「T-net」と命名された同グループの社内ポータルサイトは、全社員がパソコンのブラウザを立ち上げると最初に表示されるよう設定されています。社内で必要な各種申請書類を全文検索機能で探せるほか、リンク集、ワークフロー、新入社員向けトレーニング映像コンテンツや接客マニュアルなども一元化されました。
その結果、毎月600〜700件あったFAX送信をすべて無くすことができ、大容量の動画コンテンツも容易に全社で共有できるようになっています。
社名非公開① 事業部ソーシャルの立ち上げ
営業力強化と顧客満足度向上が課題となっていたA社では、顧客最前線の営業部門・サービス提供部門とバックヤード支援部門(本社管理など)の間の情報共有が不足していました。
そこで新たなコミュニケーションプロセスとして社内ポータルサイトを立ち上げ、その中で全社横断の情報共有・コミュニケーション基盤を構築しました。まず主力の営業部門でトライアル導入し、当該部門でコミュニケーションの在り方に変革が起きたことを実証。その上で2カ月ごとに他部門へ順次展開し、全社的に社内コミュニケーションスタイルの変化を実現しています。
社名非公開② 事業部ポータルサイトの再設計
業務システムの老朽化に伴い、B社ではGoogleが提供するG Suite(現Google Workspace)をグループ全体に導入することが決定しました。そこでG Suiteの各種機能をフル活用し、従来のWeb社内報よりもインターナルコミュニケーション効果の高い社内ポータルサイトを構築しています。
Google Workspaceは優れたグループウェアですが、標準のGoogleサイトではデザインや機能を独自開発しにくいため、実現できない部分は他の社内メディアや運用でカバーするよう運用フロー・体制を設計したことが成功の要因となりました。
将来的なポータルの理想像「デジタルワークプレイス」とは?
デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に伴い、社内ポータルは昨今さらに注目を集めています。この延長線上にあるビジネス戦略が「デジタルワークプレイス」です。
デジタルワークプレイスとは、社員の日常業務に欠かせないツールや会社から周知すべき情報、チャットやSNSといった社内コミュニケーション手段をすべてオンライン上に集約し、あらゆるデバイスからアクセス可能にすることで、インターネットにつながればいつでもどこでも業務ややり取りができるようにする新たな働き方のコンセプトです。
具体例としてはMicrosoft社の取り組みが挙げられます。全ツールを「Teams」に統合し、VR対応したSharePointによりVR空間上の社内ポータルサイトも実現しつつあります。まさにDXを具現化したソリューションといえるでしょう。
参考記事:デジタルワークプレイスで実現できる働き方改革とは?
まとめ
働き方改革だけでなく新型コロナウイルス感染対策の流れもあり、社内の情報共有効率化は今後も重要な経営課題として継続していくでしょう。またDXの観点からも、クラウドベースの社内ポータルサイト導入はもはや不可欠といえます。実際、本記事で述べたように社内ポータルの整備によって意思決定の高速化や残業削減など業務改善効果が多数報告されています。
社内ポータルサイトは単なるITツールではなく、柔軟な働き方と組織力強化のための基盤です。自社に最適な社内ポータルを構築・運用するには、目的の明確化から始まり、適切な設計・段階導入、そして運用体制の整備と改善の継続が肝要です。
本記事の内容を踏まえて準備を進めれば、社内ポータルを必要不可欠な社内インフラとして定着させ、組織全体のコミュニケーション活性化と生産性向上を実現できるでしょう。ぜひ高品質な社内ポータルサイトを構築し、組織力強化にお役立てください。