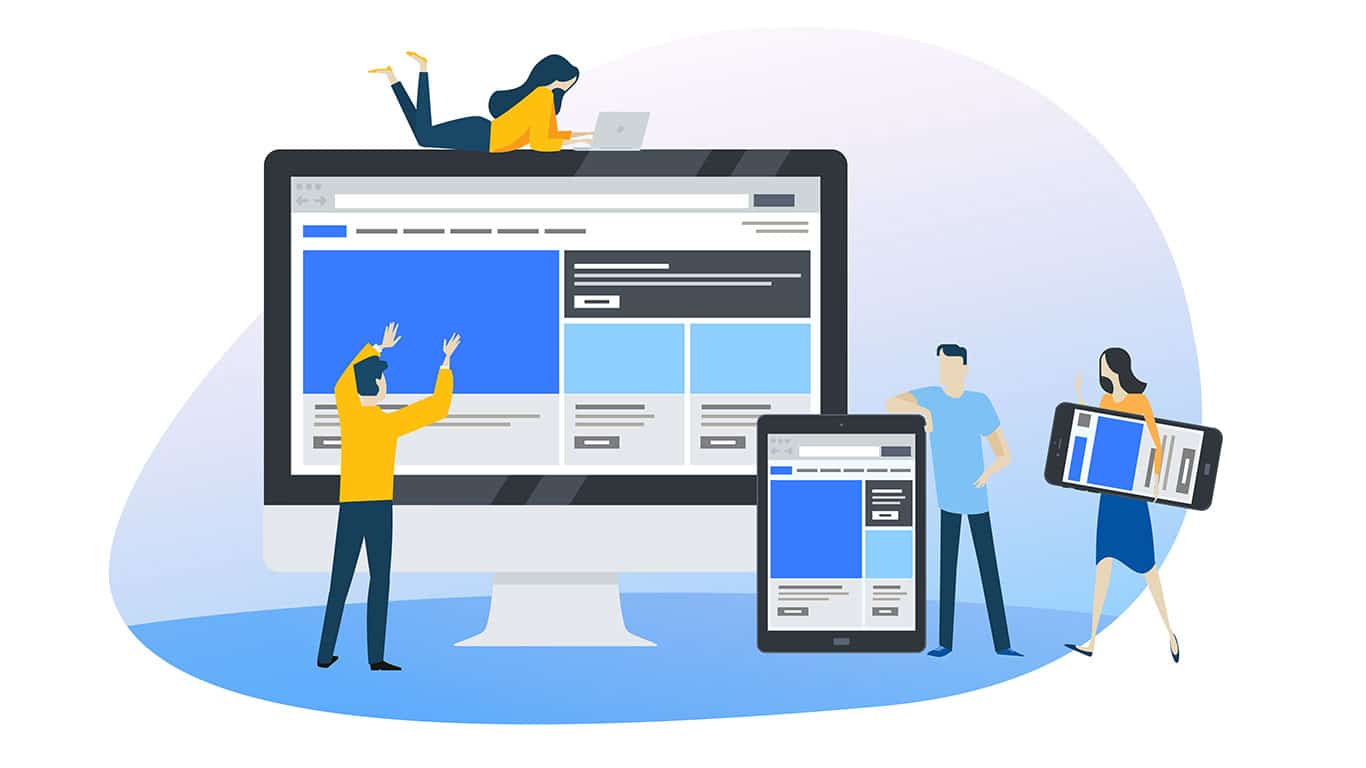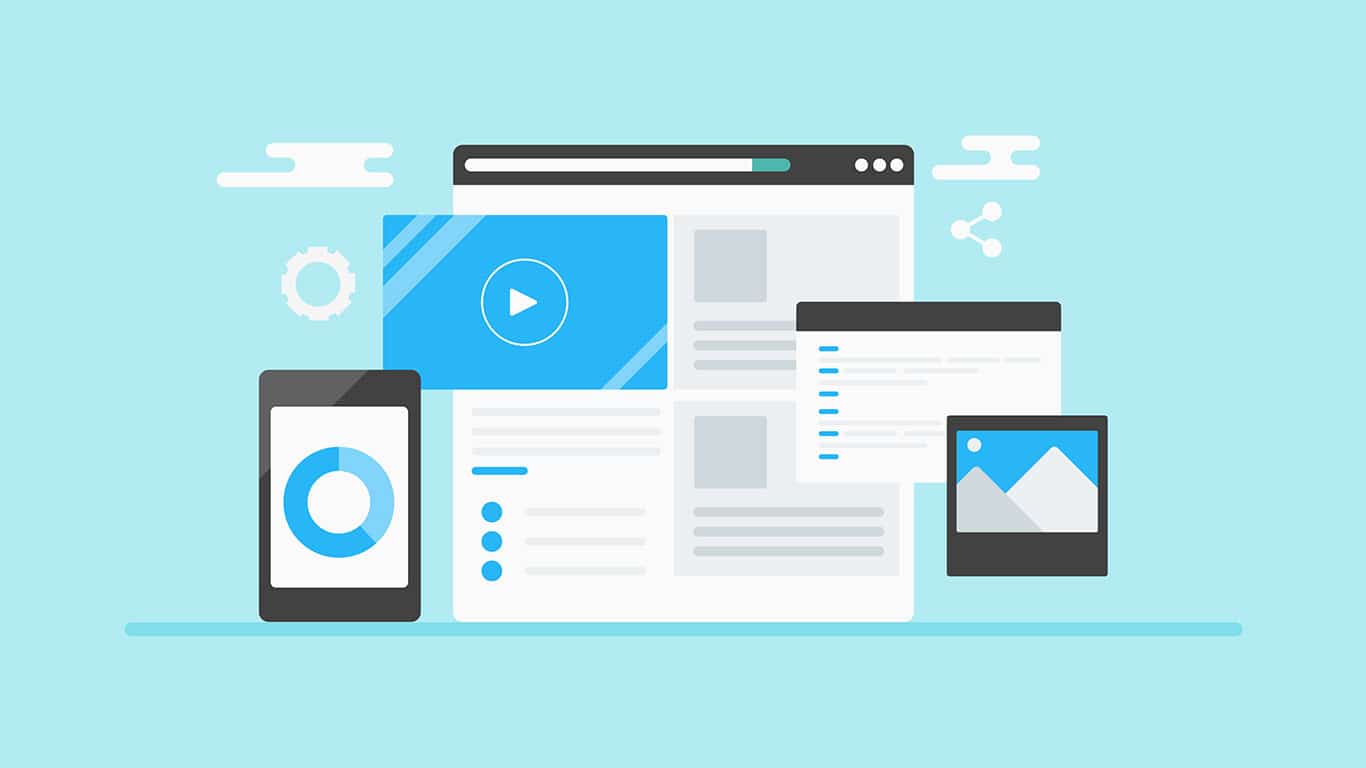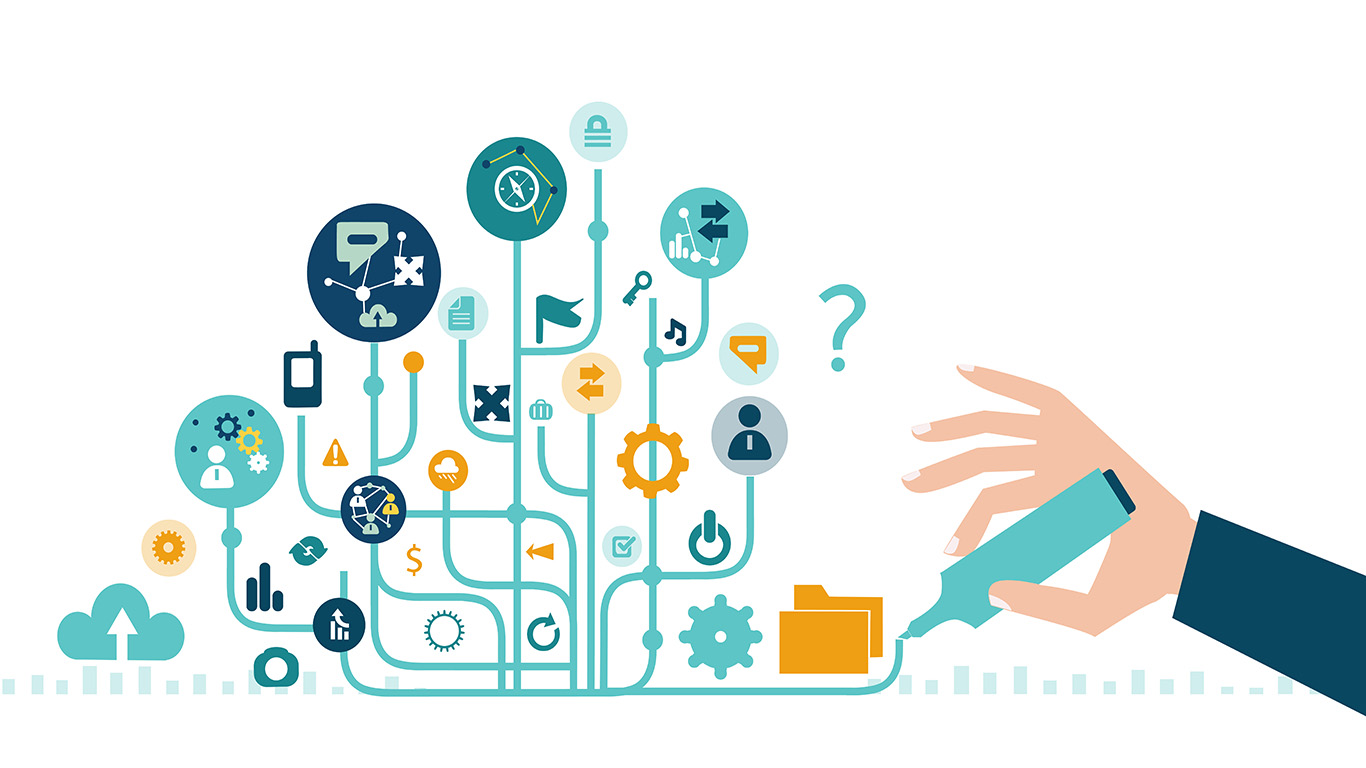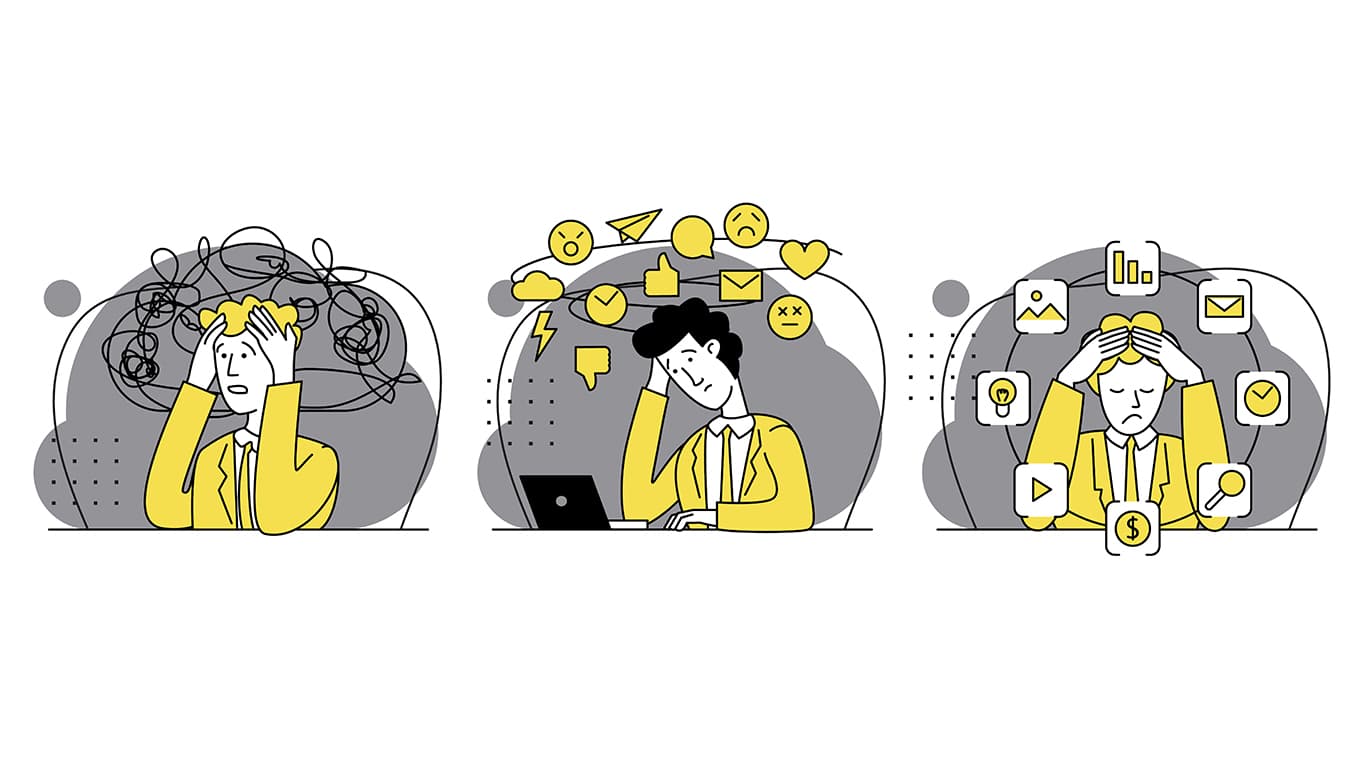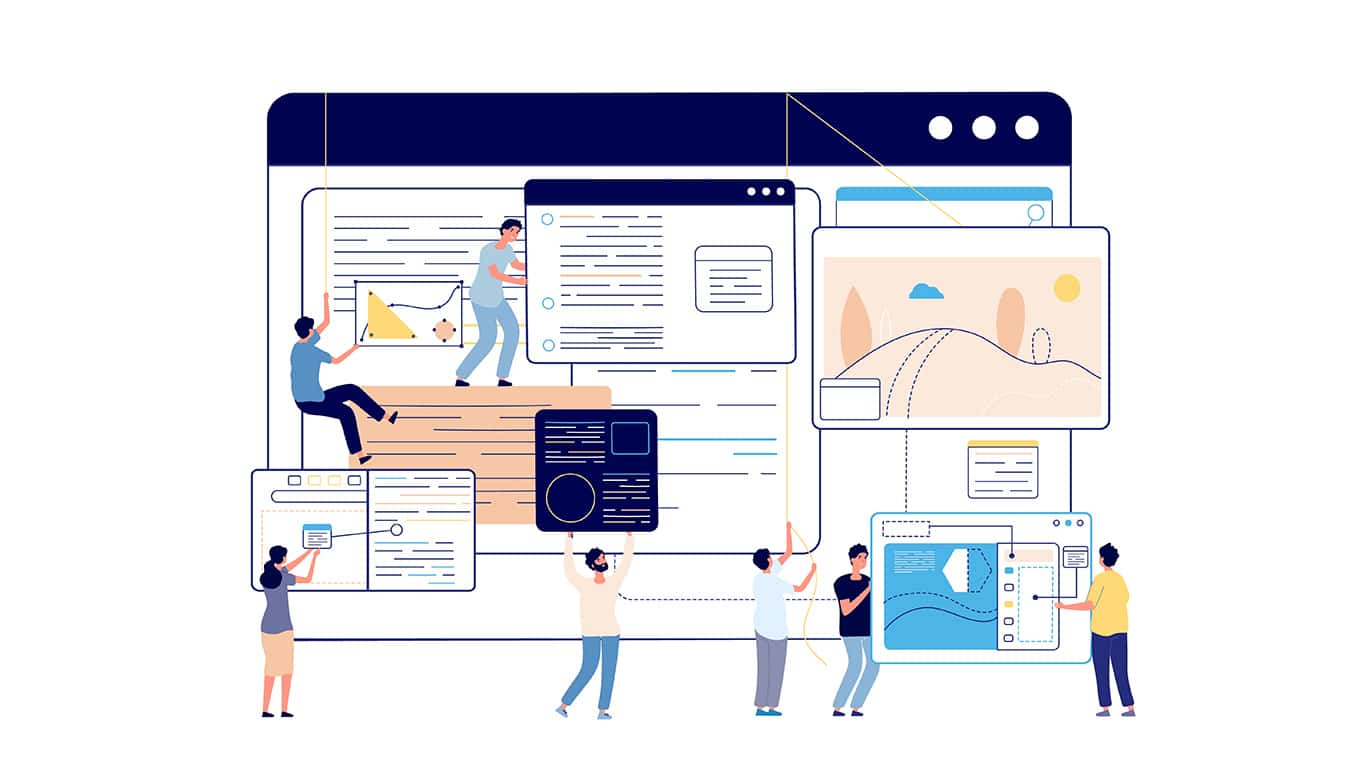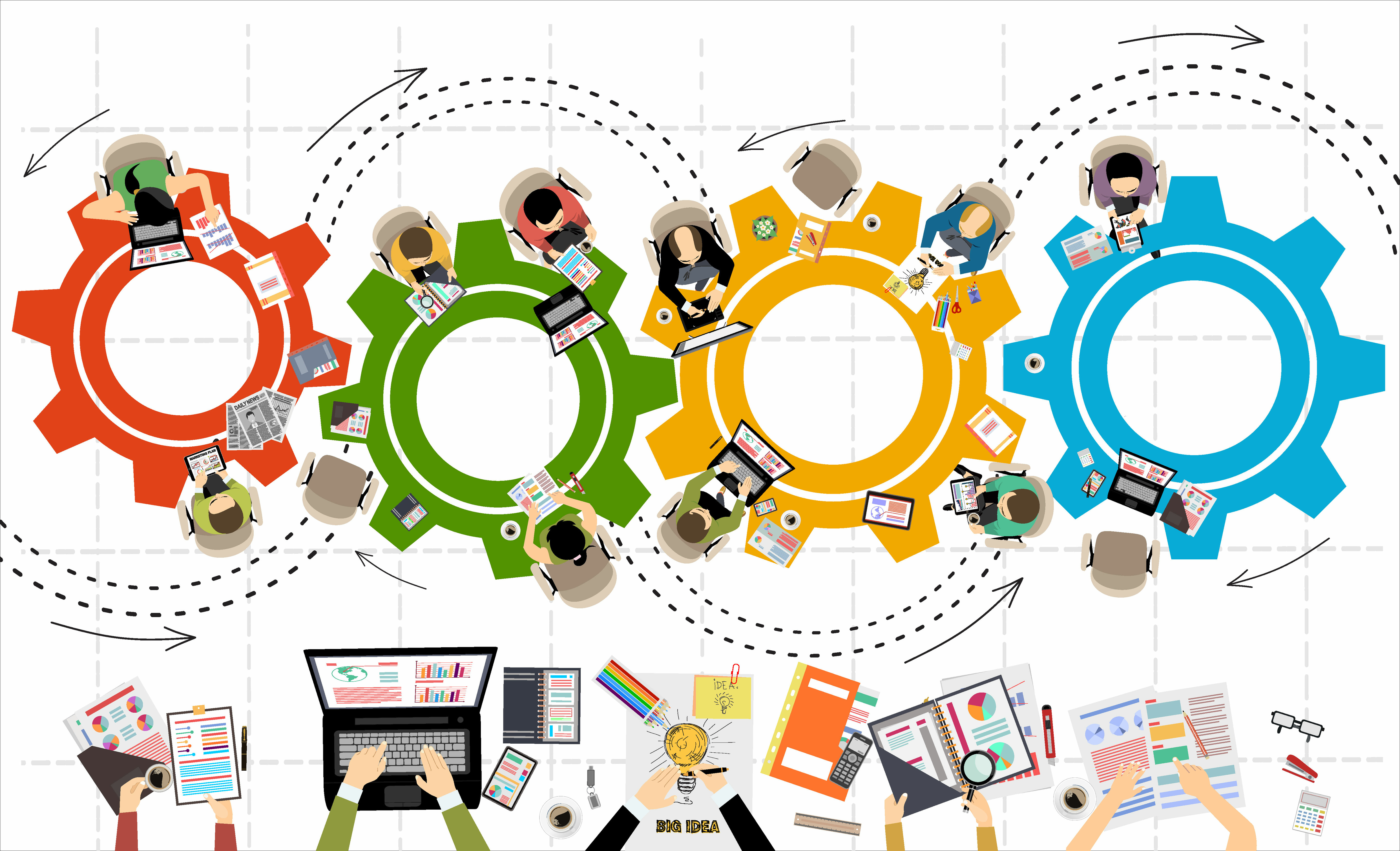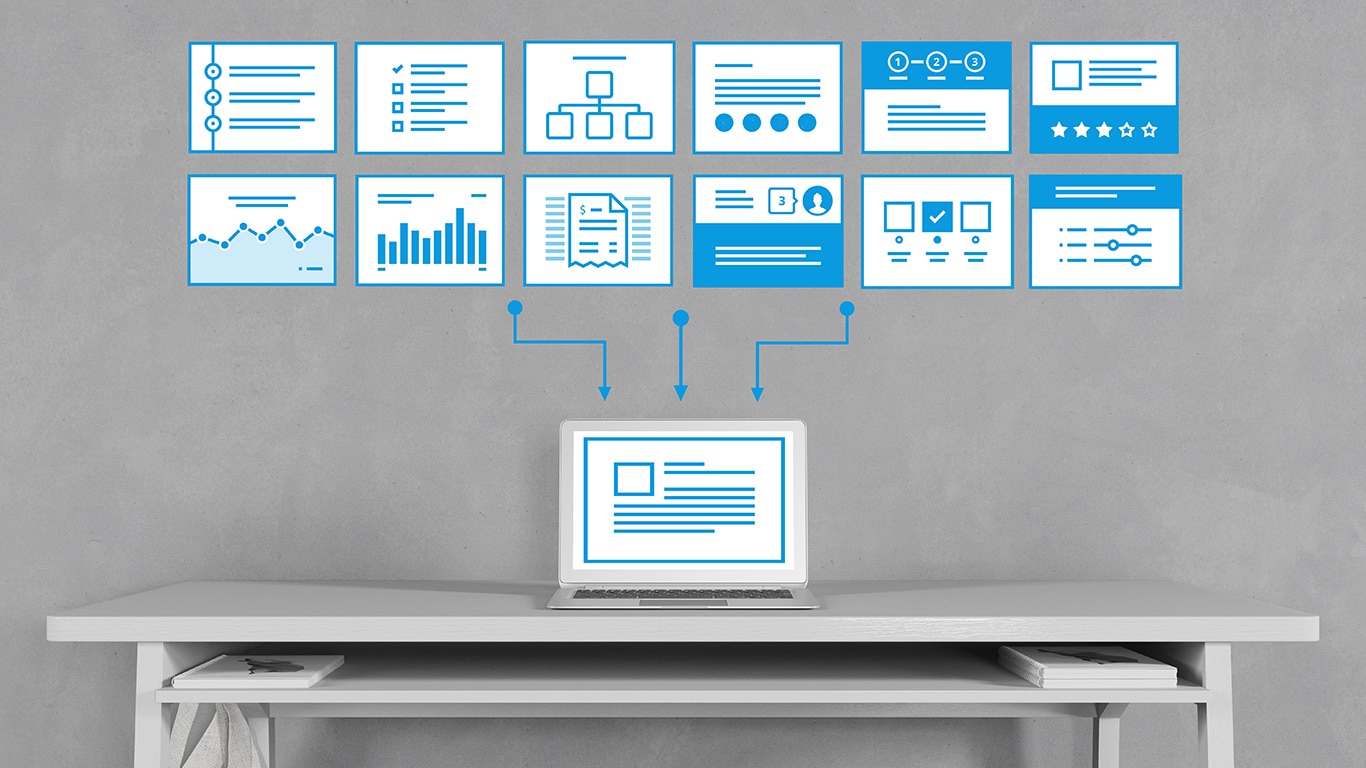社内ポータルサイトのデザインで社員の使いやすさを向上させる方法
最終更新日:2025.11.12

目次
大企業における社内ポータルサイトは、社内の情報共有を支える重要な基盤です。しかし、デザイン次第では社員の利用度が左右され、せっかくの機能も活用されない恐れがあります。本記事では、人事部門の上級管理職や研修企画担当者の方に向けて、社内ポータルサイトのデザインの重要性と、社員が使いたくなるサイトを作るポイントを解説します。UI設計の基本原則からリニューアル時の注意点、成功事例や最新トレンド、導入メリットまで幅広く取り上げます。社内ポータルサイトの新規構築や既存サイトの改善を検討中の方は、ぜひご一読ください。
社内ポータルサイトのデザインの重要性について
社内ポータルサイトは社内情報の一元的な共有基盤 であり、社員が必要な情報に素早くアクセスできれば業務効率が向上し、業務の質も高まります。
わかりにくい構成のままではせっかくの情報も活用されず、社員のストレスや作業ロスにつながってしまいます。反対に、社員にとって使いやすいデザイン を追求すれば、組織内に散在していた情報へのアクセス性が飛躍的に向上し、社員同士のコミュニケーション活性化も期待できます。
コミュニケーションが活発になれば、社内で起きている様々な課題をスピーディーに共有・解決できるようになります。実際に情報共有が円滑になることで意思決定の迅速化や無駄な会議・メールの削減につながった という声も多く、業務効率化・生産性向上の観点でも社内ポータルサイトの果たす役割は大きなものです。
とくに変化の速い現代のビジネス環境では、組織内で情報が部署ごとに分断される「サイロ化」や全体最適が図れない問題が顕在化しがちです。他社に後れを取らない俊敏な対応のため、近年は現場への権限委譲が加速度的に進んでいます。権限を委譲した経営層にとっても、現場の状況を把握するには社内ポータルが有効です。
社内ポータルは経営層と現場をつなぐオープンな情報共有の場として活用 されており、全社員が共通の情報基盤で状況を把握できるようになります。実際、コロナ禍では社内ポータル上に各拠点の出社率などが掲示され、社員が全体状況を把握して各自の出社判断に役立てるケースも見られました。情報格差を減らしフラットな意思決定を促すうえでも、社内ポータルサイトは現代の組織運営に欠かせない存在なのです。
また、社内ポータルは閉じられた社内システムである強みを活かし、アクセス権限の設定によって閲覧者を限定することで住所などの個人情報や社内機密情報を安全に取り扱うことができます 。必要な社員だけが該当情報にアクセスできるよう制御することで、情報の一元管理と保護を両立できる点も重要です。このように、業務効率と情報セキュリティの双方を高める基盤として社内ポータルサイトのデザインには大きな意義があります。
デザインの基本原則
では、ユーザーである社員にとって使いやすい社内ポータルサイトにするには具体的にどういった点に気を付ければよいのでしょうか。ここでは、一般的な社内ポータルサイトのデザインに関する基本原則 を4つに分けて解説します。
レイアウト
ユーザーが必要な情報にスムーズにアクセスするためには、直感的で分かりやすいレイアウトが肝心です。逆にレイアウトがわかりにくいと、目的の情報を探すのに時間がかかりユーザーのストレスとなるうえ、作業効率も低下してしまいます。そこでレイアウトを設計する際には、まず掲載すべき情報を階層構造で整理しましょう。
ヘッダー、フッター、サイドバーなど画面内の領域を活用し、情報の階層ごとに視覚的に区分して配置していくことが重要 です。また、情報の重要度に応じて配置順や目立たせ方を工夫することで、ユーザーに伝えたい情報を強調できます。たとえば重要度の高いお知らせはトップページの見やすい場所に配置し、大きめの見出しや色の違いで目立たせる といった配慮が求められます。
色
色使いにも十分な配慮が必要です。ユーザーの印象に直結する要素のため、自社ブランドのイメージカラーを基調に、明るさやコントラストに注意して視認性の高い配色を心掛けましょう。背景色と文字色のコントラストが低すぎたり、原色に近い派手すぎる配色だったりすると可読性が下がり、社員にとって使いにくいサイトになってしまいます。
たとえば公共性の高いWebサイトでは、色覚の多様性に配慮したカラーデザインガイドラインが定められているケースもあります。社内ポータルでも様々な社員が利用することを考え、誰にとっても見やすい色遣いを意識すると良いでしょう。ブランドカラーを活かしつつも極端に明るすぎたり暗すぎたりしないバランスの取れたトーンに調整 し、必要に応じて色覚異常に対応した配色パターンを採用するなど、あらゆるユーザーにとって見やすいデザインにすることが大切です。
フォント
文字情報が中心となるポータルサイトでは、フォント(書体)選びも重要です。基本は読みやすさを最優先してフォントを選定 しましょう。極端に細すぎるフォントや装飾的すぎるフォントは避け、サイズも含め視認性の高い状態に整えることが大切です。情報量が多く画面が文字であふれがちな場合でも、フォント使いを工夫することで読みやすさを維持できます。たとえば見出しのフォントを本文と変えて太字にするだけでも情報のメリハリがつき、視覚的に内容を整理しやすくなります。また、機械依存文字ではなくWebフォントを利用してブラウザや端末環境によらず一定の表示を確保するなど、安定して読みやすいテキスト表示を心掛けましょう。
アイコン
アイコンは視覚的に機能や内容を示すピクトグラムであり、ユーザーが目的の機能に素早くアクセスする助けになります 。ただし数多くのアイコンが画面上に並ぶ環境では、それぞれ直感的に意味が伝わるデザインであることが重要です。社内ポータルサイト上でよく使うメニューや機能のアイコンは、最初にしっかり選定して統一しましょう。一度決めたアイコンは継続して使用することで社員にとっておなじみの目印となり、認知の負荷を下げる効果があります。たとえばホームを示すアイコンには一般的に家のマークを使う、検索には虫眼鏡のマークを使う、といったように慣例に沿った分かりやすいものを選ぶと良いでしょう。一貫性のあるアイコン運用によって、ユーザーは視覚的な手がかりを頼りに迷わず操作できるようになります。
コンテンツの管理
ポータルサイトでは、どの情報をどの場所に配置するかといったコンテンツ構成の設計もデザインの一部として重要になります。せっかく良い情報があっても、整理されていなければ社員は必要な情報にすぐアクセスできず不便に感じてしまいます。ここでは、コンテンツ管理の観点から社内ポータルサイト作りのヒントをまとめます。
カテゴリー分けの重要性
社内ポータルサイトは人事、総務、経営、各事業部門など様々な部署の情報を扱うため、何の整理もしないと情報が散らばってしまいがちです。ユーザーが目的の情報を探しやすくするには、情報をカテゴリごとに分類・整理して配置する のがおすすめです。たとえば「人事関連」「経営方針」「業務マニュアル」「社内ニュース」など大きなカテゴリを設定し、さらに必要に応じてサブカテゴリを設けます。階層構造で整理されたメニューやコンテンツ一覧を用意 すれば、ユーザーは最小限の手間で欲しい情報に辿り着け、ポータル利用時のストレスも軽減できます。反対にカテゴリがなく情報が羅列されている状態では、自分に関係ある情報を探し出すだけで一苦労となってしまうでしょう。
アクセス制御
社内ポータルサイトでは、全社員で共有すべきオープンな情報のほかに、人事情報や各個人に関わる情報などセンシティブな内容も扱います。住所・給与といった個人情報を掲載する際や、特定部門だけで使う内部資料などは、アクセス権(閲覧権限)を限定して表示することが必要です。ポータル上の特定の情報あるいは機能について、アクセス可能なユーザーを制限することで安全性を高めましょう 。アクセス制御は、社員が安心してポータルを使える環境にするための必須要件です。社員のプライバシー保護や企業機密の漏洩防止のため、誰がどの情報にアクセスできるかを明確に設計しておくことが求められます。
以下のような主な社内ポータルサイトの機能を一箇所に集約しておくと、社員は様々な業務に必要な情報・ツールへ効率よくアクセスできます。
社内ニュース・掲示板:
経営メッセージや社内イベント情報、FAQなどを掲載し、全社員への周知を円滑化します。
ドキュメント管理:
規程集やマニュアル、各種申請書テンプレート、会議資料などを一元管理し、必要なときにすぐ取り出せるようにします。
業務システムへのリンク集:
勤怠管理システム、経費精算、顧客管理、プロジェクト管理など社内で使う各種システムへのリンクをまとめ、ポータルから各サービスにシングルサインオンで入れるようにします。
コミュニケーション機能:
社内SNSやチャット、アンケート機能を統合し、部署を超えたリアルタイムなやり取りを可能にします。必要に応じてWeb会議や動画メッセージの配信機能なども組み込み、双方向の情報発信基盤として活用します。
これらの機能を一元化したポータルサイトを整備することで、社員は「まずポータルを見れば欲しい情報や必要な手続きへの入口が見つかる」という状態を作れます。結果として、メールや電話で担当部署に問い合わせる手間が減り、社内のコミュニケーションコストも削減されるでしょう。
社内ポータルサイトを構築する方法としては、自社開発のほかにもパッケージ製品やクラウドサービスの利用など様々な選択肢があります。
たとえばMicrosoft社のSharePointはMicrosoft 365と高い連携性を持ち複数人でのドキュメント共同編集等に優れますが、デザインの自由度は限定的です。GoogleサイトはGoogle Workspaceとの親和性が高く手軽に構築できますが、ページ階層が限定され細かなデザイン変更が難点です。WordPressでも社内向けサイトを構築可能でデザインの柔軟性は高いですが、セキュリティ対策や保守に専門知識が求められます。このように、各ツールで得意不得意がありますので、自社の目的とリソースに合った構築手段を検討しましょう。
ここまで述べた内容は、一般的なWebサイトと社内ポータルサイトに共通する基本的なサイト設計の考え方 と言えます。レイアウトや色彩、カテゴリ分けや権限管理といった基礎をしっかり押さえつつ、次章では社内ポータル特有の役割について掘り下げます。情報を提供するだけでなく、コミュニケーション活性化の場やデジタルワークプレイスとして機能する社内ポータルサイトならではのデザイン視点を見ていきましょう。
一般的なWebサイトと社内ポータルサイトは何が違うのか
前章までで述べたような基本的なWebデザインの考え方は、社内ポータルサイトにももちろん活かせます。しかし社内ポータルには一般公開のWebサイトとは異なる前提やデザイン上の注意点があります。以下では、一般的なWebサイトと社内ポータルサイトの違いを整理します。
ユーザーは社員である
社内ポータルサイトは、ユーザーが社内の社員に限定されるという点が最大の特長です。一般の人はアクセスできないイントラネット上の閉じられたサイトであるため、機密情報を含む充実したコンテンツを提供できる強みがあります。
一方でユーザーが限定されているからこそ、「社員が本当に必要とする情報は何か」を踏まえた設計が可能 でもあります。社員を対象にアンケートやインタビューを行い 、ユーザーインサイト(ユーザー自身も自覚していない潜在的ニーズ)を事前に把握できるのは社内向けサイトならではの利点 です。にもかかわらず、こうしたユーザー調査を十分行わずに何となくでコンセプトやUIを決めてしまう企業も散見されますが、これは大きな間違いです。
社員は日々の業務でポータルサイトを利用しながらも、そのUIやデザインに多少の不便があっても声に出して指摘しない傾向があります。ポータルが「会社の仕組みの一部」と捉えられているため、多少使いにくくても受け入れて慣れてしまいがちで、不満があっても放置されやすい のです。その結果、社員が口にしない「サイレントクレーム」が蓄積し、いつの間にか業務効率の阻害や社内コミュニケーションの齟齬につながっている場合もあります。
こうした潜在的な不満を前提に入れ、初期段階から社員の声を集めて利便性を高める工夫 をするのが賢明です。一般向けのWebサイトであればアクセス解析やコンバージョン率など数字でユーザーの反応が見えますが、社内ポータルは対象が限られる分だけ数字以外の定性的なフィードバックも重要です。ログデータに加えて社員アンケートやヒアリングを活用 し、「何が使いにくいか・どんな機能が欲しいか」の要望を集めて改善し、利便性向上につなげましょう。
社内ポータルサイトは社員だけが利用する閉鎖的な環境ですが、それゆえに社内SNSやグループウェア、社内掲示板など類似の社内向けツールとの違いを理解しておく 必要があります。社内SNSは主に雑談やカジュアルな情報共有、グループウェアはスケジュール管理や社内メール・ワークフローなど業務効率化が中心ですが、社内ポータルサイトはそれら複数のツールや情報源への玄関口として機能します。たとえばポータル上のメニューから社内SNSや各業務アプリケーションにアクセスできるようにし、一箇所から社内の様々なサービスに飛べるようになっているケースも多いです。
つまり社内ポータルは単独のコミュニケーションツールというより、社内の情報ハブ(中核) として位置づけられます。社員限定サイトである強みを活かし、こうした社内ツール群を統合的に扱うデザイン設計を行うことが重要です。
情報は企業特殊情報であり、整理することは非常に困難
社内ポータルのデザインを考える際、見栄えだけを意識して安易に「かっこよく」リニューアルしてしまうのは危険です。一般向けWebサイトと同じ感覚でデザインを変えてしまうと、「どの情報がどこにあるのかわからない」と社員が戸惑う原因になりかねません。
社内ポータルに掲載される情報は、その企業特有の専門用語や略語が飛び交うハイコンテクストな内容になりやすく、前提知識なしでは理解が難しいものも含まれます。新人や異動してきた社員にとっては社内独自の言葉だらけで不便に感じることもあるでしょう。さらに年月の経過とともに、かつての用語の意味や文脈が変化してもはや現状に合わなくなっている情報も散見されます。そのため社内ポータルでは、情報を正しく整理し直し、誰にとっても理解できる状態にアップデートすることが非常に重要 です。
デザインを一新する際には「見た目が良いか」だけでなく情報アーキテクチャ(情報設計)が適切かを必ず検証 しましょう。リニューアル前後で社員から「必要な情報を見つけやすくなった」「用語の説明が増えて理解しやすくなった」といった反応が得られるようであれば、デザイン改善は成功と言えます。逆に見た目は洗練されたのに欲しい情報がどこにあるか分からないようでは本末転倒です。社内特有の情報を扱う場所だからこそ、ユーザー視点で整理し直し、伝わりやすくする工夫が必要なのです。
社内コミュニケーションの場ともなる
社内ポータルサイトは情報を掲載・保管する場所ですが、昨今では社員同士のコミュニケーションが行われる場としての役割も重視されています。ポータルサイト上に社員が自由に投稿できる社内掲示板を設置したり、部署間で意見交換できるチャット機能を組み込んだり、さらには経営トップからの動画メッセージを配信するなど、双方向の情報発信を可能にするケースも増えています 。単に会社→社員への情報伝達にとどまらず、社員↔社員のやり取りも活発化させられるのが現代の社内ポータルの特長です。
もっとも、せっかくコミュニケーション機能を持たせても自社の文化に合った形で運用しないと定着しません。たとえば形式ばったお知らせしかないポータルで突然フリー投稿の掲示板を開設してもうまく機能しないでしょう。社内ポータルを活用して組織内コミュニケーションを変革したい場合は、自社のコミュニケーションスタイルや社風に合わせた設計・ルールづくりが必要です。投稿時の実名/匿名の設定、コメントのモデレーション方針、投稿頻度やネタ提供のしくみなど、自社にフィットするコミュニケーション設計を施すことで初めて、ポータルが生きた交流の場として機能します。
社内ポータルサイトのデザインのコミュニケーションの設計
社内ポータルサイトは単なる情報の保管庫に留まらず、社内コミュニケーションを促進するインフラへと成長させることが可能です。ここでは、社内ポータルサイトがどのように社内コミュニケーションを深めていくか、その段階的な発展について触れていきます。ポータルサイトの活用度が上がるにつれて、そのデザインに求められる役割も変化し、コミュニケーションの質が向上していきます。
情報の倉庫
導入当初の社内ポータルサイトは、まず便利な「情報の倉庫」として機能します。社内の必要な情報が一箇所に集約され、整理されている ことで、誰もが必要な情報にいつでも簡単にアクセスできる状態です。社員はポータルサイト内で検索機能を使ったり、前述のカテゴリから絞り込んだりすることで、時間をかけずに知りたい情報に辿り着けます。
たとえば多くの社員が疑問に思いがちな事項については、あらかじめサイト上にFAQ(よくある質問)として掲載しておけば、問い合わせ対応の負担軽減にもつながります。情報を常に最新に保つことも重要 で、掲載内容が古いままだと社員から信頼されず利用されなくなってしまいます。適切な頻度で更新を行い、倉庫内の情報の鮮度を保つ運用も心がけましょう。
コミュニケーションの場
次の段階として、社内ポータルサイトは社員同士のコミュニケーションの場へと発展し得ます。単に会社から社員への情報提供だけでなく、社員↔社員、現場↔経営層といった双方向・多方向のコミュニケーションを支えるプラットフォームになる可能性を秘めています 。
たとえばポータル上に社内掲示板やSlackのようなチャット機能を導入すれば、社員はいつでもどこでも必要なタイミングで意見交換や質問ができるようになります。部署の壁を越えて情報や知見が行き交うことで、業務の効率やチームワーク向上にもつながるでしょう。デジタル上で場所と時間に縛られずスムーズに交流できる環境は、とくにテレワークや在宅勤務が増えた昨今において、社員のエンゲージメントを高める効果が期待できます。
さらに、トップダウンのコミュニケーションもポータルを通じて活性化できます。社長メッセージや経営戦略の共有なども動画やブログ形式でポータルに載せれば、社員は日常的に経営層の考えに触れられます。双方向性を持たせたい場合はコメント欄やリアクション機能を設け、社員からのフィードバックを受け付けることで、全社的な対話の場として機能させることもできます 。
ただし社内報・社内SNS等の調査によれば、社員が社内情報を頻繁に閲覧するケースは決して多くなく、月10回以上ポータル等を閲覧する従業員は2割未満との報告もあります。このため、コミュニケーションの場として機能させるには社員が「また見たい」と思うコンテンツを充実させ、閲覧習慣を根付かせる工夫が必要 です。部署紹介のリレー記事や社員参加型のキャンペーンなど、インタラクティブで興味を引く企画を盛り込むことも検討するとよいでしょう。
デジタルワークプレイスとしての活用
社内ポータルサイトをさらに発展させると、デジタルワークプレイスとして活用することも可能です。デジタルワークプレイスとは、物理的なオフィス空間に代わってデジタル上で働く場を提供する概念です。社内ポータルをそのハブに据えることで、個人レベルだけでなく組織全体でナレッジ(知識)が共有・蓄積されていき、コミュニケーションのログも残ります 。
たとえばチャットや掲示板のやり取り、ナレッジ記事のコメントなどが蓄積されれば、必要な情報をあとから振り返って確認することも容易になります。また社員同士が地理的に離れていてもデジタル上で協働できるため、情報共有のハードルが下がり、新たなコラボレーションが生まれるでしょう。
デジタルワークプレイス化を促進することは、結果的に業務の効率化やアウトプットの品質向上など様々な効果をもたらします。社内の壁を越えてアイデアが交換され、新しいプロジェクトが生まれるきっかけにもなるかもしれません。そのためには、情報発信がしやすいデザインにしたり、強力な検索機能で過去の議論や資料をすぐ探せるようにするなど、プラットフォームとしての完成度を高める工夫が求められます 。最近ではAIチャットボットを社内ポータルに導入し、過去のQ&Aやナレッジを学習させて社員からの質問に自動回答する事例も登場しています。新しい技術も適宜取り入れながら、社員がより創造的に働けるデジタル環境をデザインしていくことが大切 です。
なお、デジタルワークプレイスによる働き方改革の効果については、行政機関の調査でも高い成功率が示されています。社内ポータルを充実させることは、柔軟な働き方と組織力強化の両面で大きな意味を持つのです。
社内ポータルサイトをデザインする際のポイント
以上を踏まえ、実際に社内ポータルサイトを作る・改善する際に押さえておきたいデザイン面のポイントをまとめます。目的に沿った効果的なデザインを完成させるために、以下の点に留意しましょう。
情報の整理整頓
まず前提として、載せる情報自体が整理されていなければポータルを作っても意味がありません。社内特有のハイコンテクストな用語については、ポータル上で用語集を作成したり定義を明示するなどして、誰もが共通の前提知識を持てるようにしましょう。同じ前提のもとで社内の全員が情報にアクセスできれば、「○○とは何か」を個別に問い合わせる必要も減り、社内の管理部門や現場担当者双方にとって工数削減につながります 。
また現状、申請書・契約書など各種書類が紙・PDF・Excelデータなど複数フォーマットで混在していないでしょうか。このような非効率は、法務部門が契約書類を統一フォーマットに整備してWebで扱いやすい形式に変えるなど、関連部門と協力して情報自体を整理する取り組みも必要になるでしょう。
また、デザイン以前に「何のためのポータルか」「誰に何を使って欲しいか」を明確に定義し、関係者で共通認識を持っておくことが重要 です。目的がはっきりすれば、自ずと載せるべきコンテンツや優先すべき機能も見えてきますし、運用開始後の評価指標(KPI)の設定もしやすくなります 。闇雲にお洒落なサイトを目指すのではなく、何を実現したいかに即した情報設計を徹底しましょう。
誰にとって最適な情報設計なのかを考える
社内ポータルの主な利用者は多くの場合「自社の従業員」です。ゆえに、従業員が求める情報をいかに効率よく得られるようにするかがデザイン上の最優先事項になります。ここで注意したいのは、情報提供側(サイトオーナー)と利用者(従業員)では関心を持つ情報が異なる場合が多いという点です。
たとえば経営層や情報システム部門などサイトの管理側は、自社の経営戦略や制度、組織構造など幅広い情報を発信したいと思うかもしれません。しかし現場の従業員が日々強く関心を寄せるのは、自分の業務や身近な環境に関わる情報です。人事異動・評価制度・福利厚生といった身の回りに直結する情報はとくに関心が高く、逆にトップメッセージや財務情報などは日常業務に直接影響しない限り優先度が下がる傾向にあります。
そのため、まずは従業員にとって役立つ情報から前面に配置し、サイトへのエンゲージメント(利用頻度や滞在時間)を高めることが第一歩 です。たとえば人事関連のお知らせや経費精算の手順、新入社員向けのQ&Aなど、社員が「これは便利だ」と感じるコンテンツを充実させましょう。エンゲージメントが上がりポータルへの訪問が習慣化すれば、従業員もトップメッセージ等の企業発信情報にも自然と目を通すようになってきます。まず社員の実用的ニーズを満たすことに注力し、その上で徐々に企業からのメッセージ発信も織り交ぜていくのが理想 です。また前述のように用語集の整備など誰でも理解できる情報への変換も重要です。専門用語や社内略語には説明を添え、新人でも迷わない情報設計を心がけましょう。
社員のポータル利用状況を定期的にチェックし、関心を持たれている情報分野に注力するのも有効です。社内広報に関する調査では、社員の約18.6%しか社内情報を月10回以上閲覧していないとの結果もあり、閲覧頻度を上げることが課題となっています。閲覧頻度の低い要因がコンテンツの魅力不足にあるのか、ナビゲーションが悪いのかを分析 し、社員目線で本当に必要とされる情報設計になっているかを常に問い直しましょう。
たとえばアクセスランキング機能を設けて人気コンテンツがわかるようにしたり、「役に立った」「もっと知りたい」といったフィードバックを集める仕組みを取り入れるのも一案です。利用者視点に立った情報設計こそが、結果的に組織全体の情報共有効果を最大化します。
従業員の認知負荷を下げる
昨今はコミュニケーション・テクノロジーの進歩により、人間が処理しきれないほど多くの情報が飛び交っています。組織内コミュニケーションでも同様で、情報量が膨大になれば受け手は必要な情報を選択しなければならず、結果として伝達効率が低下してしまいます。複雑な情報を効果的に伝えるには、受け手の認知負荷を軽減する工夫が不可欠です。
社内ポータルで情報を共有する際も、単に大量の情報を羅列するのではなくポイントを絞った明瞭なメッセージにすることが重要 です。冗長な文章よりも箇条書きや図表を用いて視覚的に整理した方が理解が進みますし、長大な文章であれば要約版や詳細版に分けて読む人が選べるようにするなど配慮しましょう。また、ストーリー性を持たせて情報を紹介する「ストーリーテリング」の手法も有効です。単なる機能説明ではなく、「このような課題があったが、ポータル活用で解決できた」という物語仕立てで事例紹介すると、読む側の興味を引きつけながら伝えたいポイントを届けられます 。
さらに、情報量自体を安易に増やしすぎないことも大事です。掲載する情報は精査し、「なくても困らない情報」は思い切って省く決断も必要かもしれません。とくにトップページは、全社員に共通する必要最低限かつ有用な情報に絞り込み、詳細は各カテゴリページに譲るなど設計にメリハリをつけましょう 。要点を押さえ簡潔にまとめたコンテンツや、インフォグラフィックス・アイコン等のビジュアル要素の活用によって、忙しい社員でも直感的に理解できる情報設計を目指します。こうした工夫の積み重ねが、結果的に社員一人ひとりの情報処理負担を減らし、社内コミュニケーション全体の効率を高めることにつながります。
UIとUXについて
社内ポータルサイトのUI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザー体験)の改善視点も忘れてはなりません。従業員が使い慣れるまでは、凝りすぎたデザインや複雑すぎる機能は避けた方が無難です。文字情報を詰め込みすぎて見づらい画面や、クリックしないと説明が読めない隠れたメニューなども、利用性を下げる原因となります。
一般的に自治体のWebサイトなどは情報量が多く充実していますが、その分画面が情報でぎっしり詰まっており利用しづらいと言われます。同じ轍を踏まないよう、社内ポータルではできるだけシンプルで分かりやすいデザインを心がけましょう 。ただし簡素にしすぎて抽象的になりすぎるのも禁物で、必要な情報が省略されてしまっては意味がありません。そのバランスを取ることが重要です。言葉遣いもできるだけ平易にし、専門用語には説明を添えるといった工夫で誰にでも理解できるUIを目指します。
最近のトレンドとしてはモバイルファースト設計 も重視されています。スマートフォンやタブレットなどPC以外の端末からポータルサイトを見るケースも多いため、画面サイズに応じて見やすく操作しやすいレスポンシブデザインは必須です。外出先からスマホで社内ポータルにアクセスして情報収集・申請が行えるようになれば、社員の利便性は一層高まるでしょう。
さらに、必要に応じて社内ポータルをモバイルアプリ化しプッシュ通知機能を持たせるなど、社員の行動様式に沿ったUX改善も検討 できます。また、UI改善の取り組みとして近年注目されるニューモーフィズム(フラットデザインに陰影をつけ立体感を出す手法)やマイクロインタラクション(ボタンを押した際の小さなアニメーション等)などを適用し、楽しく直感的に操作できる演出を加えるのも有効でしょう。ただし過度な装飾やアニメーションは表示速度低下や視認性低下を招く恐れもあるため、あくまで使いやすさを損なわない範囲で取り入れることが大切です。かっこよさより使いやすさ──社内ポータルサイトのデザインではこの原則に徹し、従業員が日々ストレスなく利用できることを最優先にしましょう。
社内ポータルサイトのデザインは段階的に変化させなければならない
既存の社内ポータルサイトをリニューアルしたり、新たに設計を変えていきたい場合、ユーザーである社員に極力ストレスや抵抗感を与えず進めることがカギとなります。長年使い慣れたサイトが急に大きく変わると、「どこに何があるかわからない」と利用者が戸惑い、場合によっては反発を招く恐れもあります。そこでこの章では、段階的にデザイン変革を起こす方法をまとめます。
社内ポータルサイトのデザイン改善ステップ: 大規模なリニューアルも、小さな改善の積み重ねで円滑に進めることができます。以下はデザイン変更を段階的に行うための主なステップです。
ログの取得:
まずは現状のポータル利用状況を客観的に把握することから始めます。アクセスログを取得・分析し、社員がどのような情報にアクセスしているか、どのページがよく見られているか、逆に見られていないコンテンツは何か、といった行動パターンをデータで確認しましょう。アクセス数や滞在時間、検索されたキーワードなどを分析することで、社員のニーズと課題が浮き彫りになります。
アンケート:
定量データだけでなく社員の生の声を集めることも重要です。ログ分析では見えない使用感や要望を知るため、ユーザーアンケートやヒアリングを実施しましょう。リニューアル前後でサイトの使いやすさ・見やすさについて質問したり、改善してほしい点や新機能の希望を募ったりします。回答率を上げるために、調査の実施期間や回答方法を明確に案内し、できるだけ多くの人からフィードバックをもらうのがコツです。集まった回答は集計・分析し、デザイン改善の方向性を探ります。社員から直接上がった改善案は貴重なヒントとなり、次のアクションプラン策定に活かせます。
デザイン改善案の策定:
ログ分析やアンケート結果を踏まえ、具体的にどの部分をどう改善するかのプランを立てます。社員が求める情報にスムーズに辿り着けるデザインとはどのようなものか、現行デザインの何が障壁になっているのかを検討します。たとえば「トップページに◯◯へのリンクを追加」「◯◯機能のアイコンをより目立つデザインに変更」「専門用語に説明ポップアップを付与」といった具合に、ニーズに沿った改善策を洗い出しましょう。優先度付けも重要です。影響範囲が大きいものや要望件数の多いものから手を付け、段階的に着手していく計画を立てます。
改修と運用:
改善案がまとまったら、本番環境での展開(実装)に移ります。一度に大幅な変更を加えるのではなく、可能な限り小さな変更から始めるのがポイントです。まずはユーザーが直感的に気付ける操作性の改善など負担の少ない変更をリリースし、その都度ポータル上や社内メールで「〇〇をこのように改善しました」と周知してフィードバックを募ります。一気にデザインを変えて社員を混乱させるのではなく、少しずつの変化に慣れてもらいながら段階的に刷新していきましょう。変更のペースは社員の反応や習熟度を見ながら調整します。アップデート後は必ずログやアンケートで効果検証を行い、更なる微調整(マイナーチェンジ)を重ねます。継続的な小改善サイクルを回すことで、大きな抵抗感を生むことなく長期的に見て大幅なUX向上を実現できます。
以上のようにステップを踏んで進めれば、社内ポータルサイトのデザインは社員に寄り添った形で徐々に変化させていくことが可能です。なお、段階的改善を成功させるためには初期段階でポータル運用の体制と目的を明確化しておくことが不可欠です。運用開始後に誰がどのようにコンテンツを更新し、改善提案を取りまとめるのか、社内で責任者やワーキンググループを定めておきましょう 。これを怠ると目的がブレたり改善が属人的になったりして、前述のような導入失敗(3年以内に利用されなくなる)につながりかねません。デザインと運用は車の両輪であり、両者を計画的に設計することで社内ポータルは進化し続けるのです。
社内ポータルサイトのデザインの参考例
社内ポータルサイトのデザインを考える際、実際の事例を見るとより具体的なイメージが湧きます。ここでは社内ポータル導入によって得られた成功例をいくつか紹介します。
たとえば、ある企業では社内のあちこちに点在していたデータやツール類を整理し、すべてを社内ポータルサイトからアクセスできるよう統合 しました。従来は勤怠入力や経費精算など各システムに別々にログインする必要があり社員から不便との声が上がっていましたが、ポータルひとつ開けば各種システムにシングルサインオンで入れるようにしたことで、「業務開始時にまずポータルを開けばよい状態」を実現 しました。情報を探し回る時間が大幅に短縮され、とくに新人社員の立ち上がりが早くなったとのことです。
また、営業力強化と顧客満足度向上が課題だった別の会社では、新たに社内ポータルサイトを立ち上げ全社のコミュニケーションをそこで行えるようにしました。部署間の情報共有が活性化し、顧客対応に必要な知見が速やかに共有されるようになった結果、売上と顧客満足度双方の指標が向上した と報告されています。
まとめ
社内ポータルサイトは、社内の情報共有とコミュニケーションを支える重要なプラットフォームです。社員にとって使いやすいサイトを作るために、コンテンツ配置やUI設計の工夫を重ね、従業員に最適な情報設計になっているかを常に意識してUX/UIを向上させていく必要があります。もし既存の社内ポータルサイトをリニューアルする場合には、社員にとっての目的と価値を明確に示しつつ、抵抗感を招かない段階的な変更を心掛けることが重要です。適切な設計と運用のもと、使いやすい社内ポータルサイトを育てていけば、社内の情報流通が円滑化し、コミュニケーションが深まり、ひいては組織全体の力を高めていくことでしょう。
目的に沿ったデザイン改善と継続的な運用見直しによって社内ポータルの効果を最大化し、情報共有の基盤として定着させることが、これからの柔軟な働き方を支える鍵となります。組織のニーズに合わせて進化する社内ポータルサイトで、社員一人ひとりの生産性とエンゲージメントを高めていきましょう。