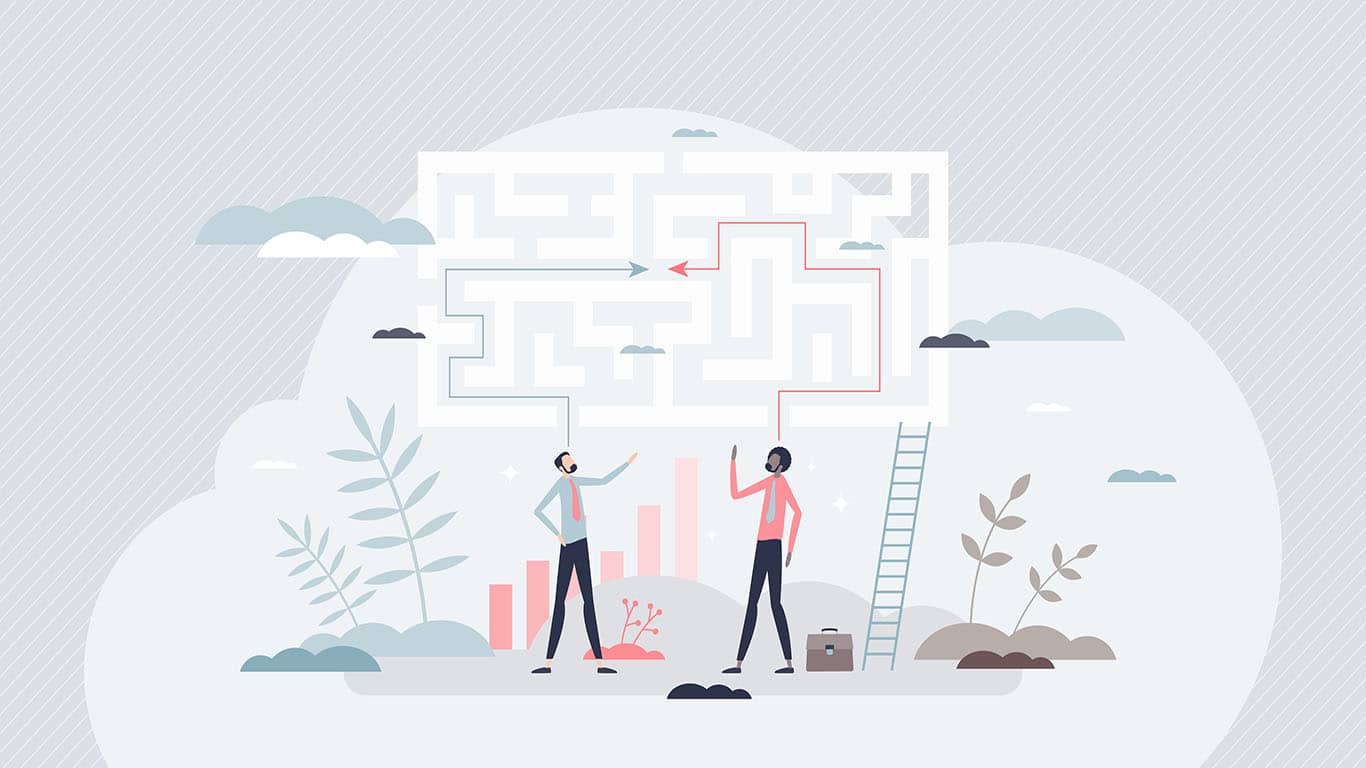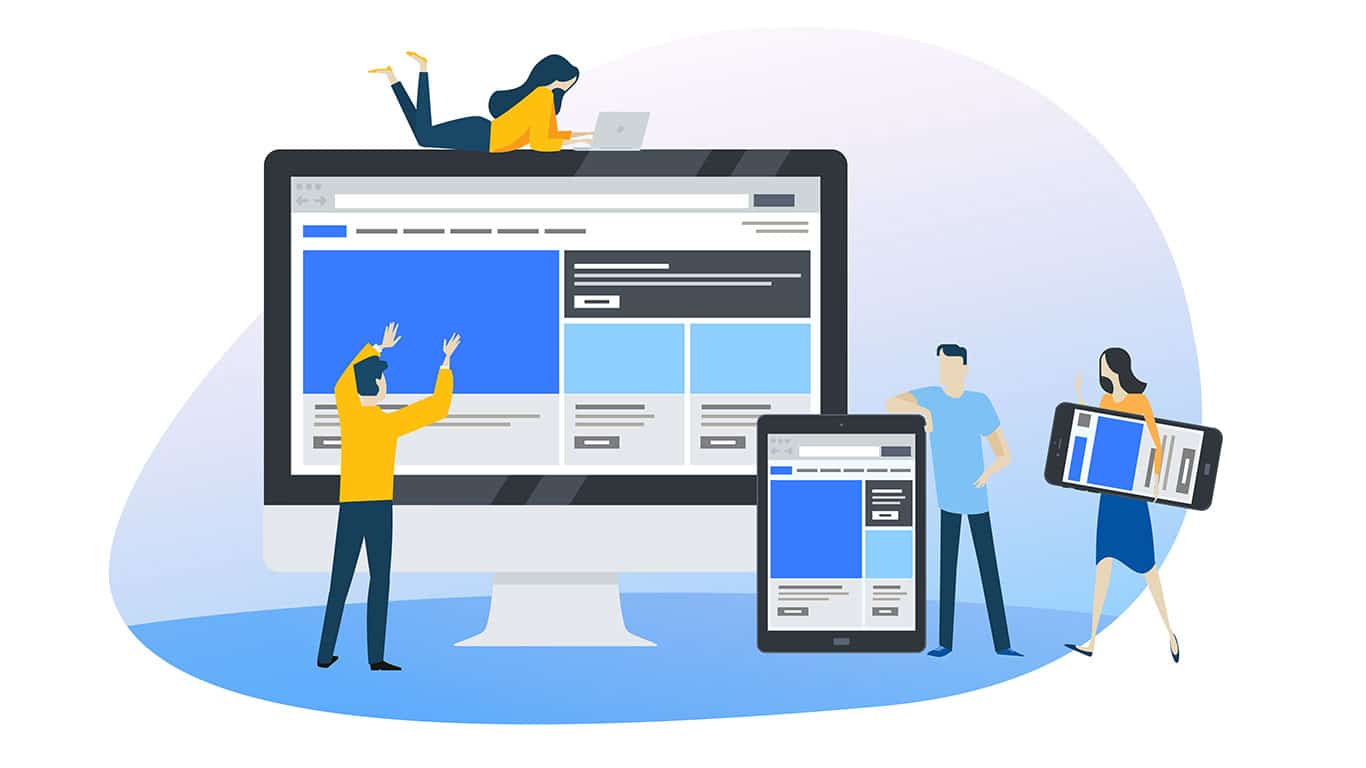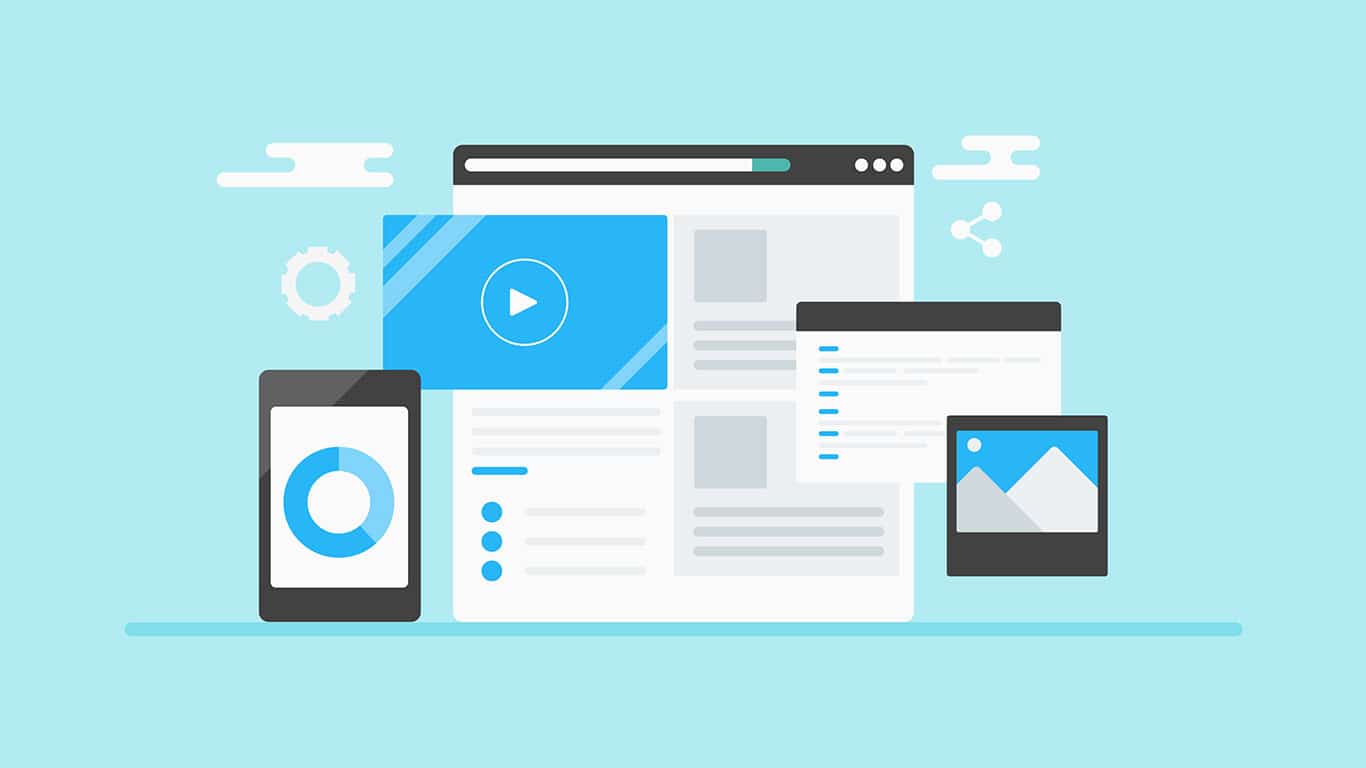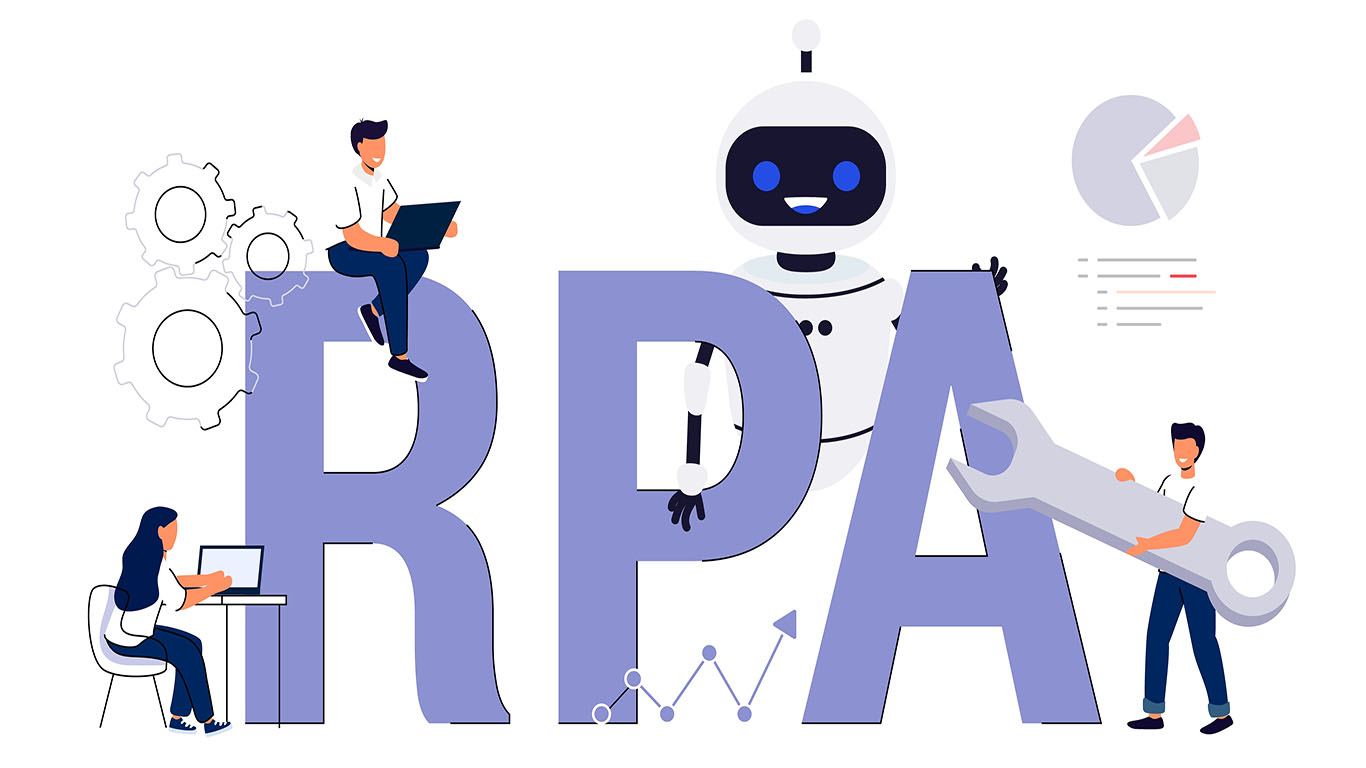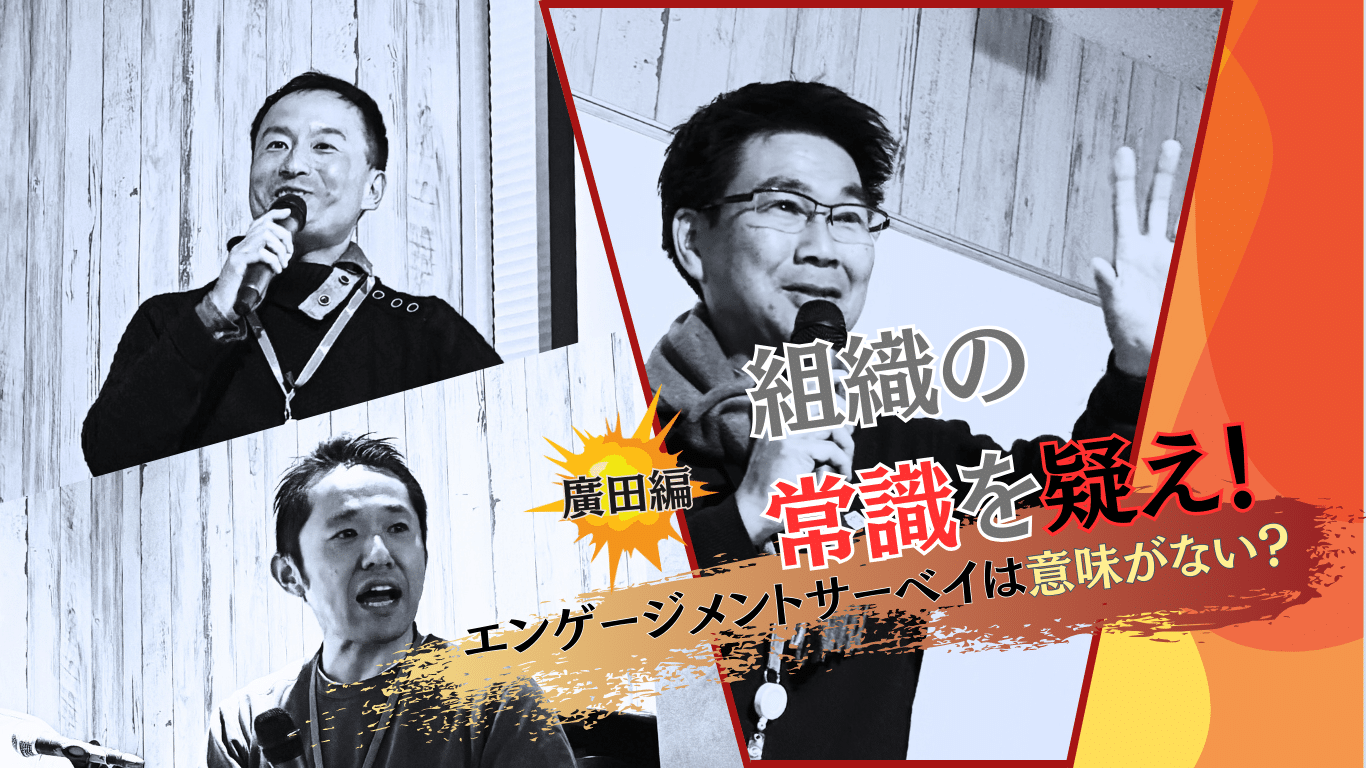社内ポータルとは?機能と役割、構築の手順のポイントと導入事例を解説
最終更新日:2023.05.01

目次
「社内ポータル」は、自社で使ったことのない人にとってはあまり馴染みのない用語かもしれません。簡単にいえば、「社内の情報を集約した入り口のサイト」です。今回はこの社内ポータルについて詳しく解説しながら、構築の際のポイントについても触れていきます。
社内ポータルとは?
「ポータル(portal)」は、「玄関」「入り口」を表す英単語です。冒頭で述べたようにポータルサイトとは、情報の入り口の役割を担うサイトを意味します。
<社内ポータルの概要>
一般的なポータルサイトと社内ポータルサイトを比較して社内ポータルの概要を掴みましょう。一般的なポータルサイトといえば、たとえば「Yahoo! JAPAN」が有名で、さまざまなジャンルの情報へアクセスするための入り口となっています。インターネットを頻繁に使う方なら、こういったポータルサイトによって、自分の欲しい情報が簡単に見つかった経験があるでしょう。
対して社内ポータルは、社内の人間しかアクセスできないイントラネット上に設置されたポータルサイトです。社内ポータルでは、社内のイントラネット内の他のページ、社外のWEBページだけでなく、社員だけが使えるスケジューラーや勤怠ツールなどにもアクセスできるものがほとんどです。
社内ポータルサイトの2つの目的
社内ポータルサイトは、単なる情報の置き場ではなく、社員の働き方や企業全体の成果に大きく影響する重要なツールです。その真価を発揮するためには、ポータルサイトの目的を明確にし、利用者視点に立った設計が欠かせません。以下では、社内ポータルが果たすべき2つの主要な役割について解説します。
1. 情報取得の効率をいかに向上させるか
社内ポータルの最も基本的かつ重要な役割は、「必要な情報にすばやくアクセスできる」ことです。業務上の意思決定や作業の効率化を図るためには、探したい情報がどこにあるのか、直感的にわかる構造が求められます。
その実現には、優れた検索機能はもちろんのこと、情報の分類・整理方法が鍵を握ります。とくに分類の設計においては、「誰が発信したか」ではなく「誰が使うか」「どんな場面で使うか」といった利用者視点に立つことが不可欠です。業務シーンに即した導線を設計することで、迷わず情報にたどり着ける仕組みを構築することが、ポータルの価値を最大化するポイントとなります。
2. 企業戦略に沿った行動を促すことができるか
社内ポータルは、情報を届けるだけでなく、社員一人ひとりの行動を後押しし、企業の目指す方向へと導く役割も担っています。たとえば、イノベーションを重視する企業であれば、アイデア投稿や他部署とのコラボレーションを促す導線を設けるといった工夫が求められます。
そのためには、「どんな行動を起こしてほしいのか」をあらかじめ明確にし、それに沿って情報の配置や導線、画面レイアウトを設計する必要があります。
ユーザーが意識せずとも自然と望ましい行動にたどり着けるようなデザインこそが、戦略的に機能する社内ポータルの鍵となります。
社内ポータルサイトが及ぼす組織への影響
社内ポータルサイトは単なる業務ツールにとどまらず、組織全体の働き方や企業文化に深く関わる存在です。情報の届け方や共有のあり方を工夫することで、社員の意識や行動に大きな変化をもたらし、組織の一体感や戦略の浸透を後押しする力を持っています。ここでは、社内ポータルが組織にもたらす主な影響について見ていきましょう。
社員のエンゲージメント向上と戦略遂行
現代のビジネスにおいて、情報不足は業務の遅延や効率の低下を引き起こす要因となります。社内ポータルを活用して、必要な情報を適切なタイミングで提供することは、社員のエンゲージメント向上に直結します。社員が求める情報に迅速にアクセスできれば、業務の成果をスムーズに達成できるようになり、仕事の質そのものも向上します。
また、社内ポータルは、業務に必要なITツールや各種サービスへスムーズにアクセスできるプラットフォームとしても機能します。特に、福利厚生として提供される便利なツールや、勤怠管理などの必須業務を簡単に行える環境が整っていることは、業務効率の改善につながり、結果として社員の生産性向上にも寄与します。
さらに、社内ポータルを通じて企業戦略に関する情報が共有されることで、社員一人ひとりが自分の業務に対して戦略的な視点を持ち、他部門への影響も踏まえながら行動を変えていくことが可能になります。
このように、必要な情報が適切に届けられる環境は、エンゲージメントのさらなる向上につながります。
社内の認識の共通化
社内ポータルを活用することで、すべての社員が「同じ情報を見ている」という状態をつくることができます。これにより、個人や部門ごとの情報格差が減り、「みんなが知っている」という共通認識が生まれやすくなります。全社的な方針や連絡事項が一元的に共有されることで、部門間の連携もスムーズになり、意思決定や行動にズレが生じにくくなります。
情報の受け手である社員が、自分だけでなく他の社員も同じ情報を得ていると感じることで、安心感や信頼感が生まれ、組織の一体感が高まります。このような共通認識は、日々の業務における誤解や認識のズレを防ぎ、組織運営の安定化にもつながります。
情報の透明性強化
組織の信頼性と健全な運営には、情報の透明性が不可欠です。社内ポータルを通じて、企業の方針や意思決定の背景、各部門の業務進捗などをオープンに共有することで、社員は組織の動きを正しく理解できるようになります。
これにより「なぜこの判断がなされたのか」「今どんな課題に取り組んでいるのか」といった納得感が得られ、不要な憶測や不満の軽減にもつながります。
また、情報の非対称性を解消することは、社員間の公平感を高めるうえでも効果的です。誰もが等しく必要な情報にアクセスできる環境を整えることで、モチベーションの維持や自主的な行動を促す土壌が生まれます。結果として、透明性の高い組織文化が根づいていきます。
「社内ポータル」の担う役割が深化している背景
これまで、社内のニュース・お知らせや業務に用いられるIT関連の情報、書類の電子データなどは、「社内イントラ」や「ファイルサーバー」上にまとめられていました。「社内ポータルサイト」と呼ばれる新たなWEBサイトを各社が整備している背景には以下の理由があります。
- テレワーク・ハイブリッドワークを踏まえた業務効率化
- 社内発信が必要な経営情報の多様化
- 社会からの要請により企業が対応すべき経営テーマの多様化
コロナ禍によって出社しない働き方が普及し、オンラインでの業務・コミュニケーションが占める割合が大きくなりました。そのために必要なツールも多岐にわたり、それらへのアクセスをより効率化するため、整理された入口が必要となります。
同時に、それらの利活用において、困ったときの解決方法・便利な使い方・普段は使わないが特定の場面で必要な機能、など各ツールに関する情報も併せて簡単に取得できることも欠かせません。
さらに、書類・ドキュメントはもちろん、社内でやり取りされる情報が量・多様共に圧倒的に増加しました。緊急のお知らせや、経営ビジョンや戦略、各事業における計画とそれらに関連するリアルタイムな経営情報、サプライチェーンの状況、顧客や市場に関する情報など、会社→全社に対する様々な情報が社内ポータル上で共有されています。ビジネスの複雑化に伴い、これまでは経営層のみが判断のために取得していた情報を、現場レベルでの意思決定を推進するために共有するようになったという背景があります。
また、社会全体・業界全体で取り組まれる、SDGsやDX、働き方変革などの経営テーマについて全社に発信し、社員の共感と実践を促進していくことが求められる中、全社に対する有用な発信の場として社内ポータルサイトが活用されています。
社内ポータルの変化
これまでの社内ポータルは、業務マニュアルや会社からの必要なメッセージを集合させている情報の倉庫といった役割を担っていました。しかし昨今では、情報を発信する側と受信する側の関係性がフラット化し、社内ポータルは利用者同士が直接意見を言い合えるコミュニケーションの場に変化しています。
会社が社員に必要な情報を一方的に発信する場ではなく、会社と社員が双方向に情報や意見を発信できるのが現在の社内ポータルです。
また、デジタルワークプレイスのようなデジタル空間を活用した快適で効率的な仕事空間が普及しつつあり、市場を急速に拡大しているメタバースによってビジネスの常識も大きく変わろうとしています。そういったビジネス現場の激しい変化に付いていくためにも、必要な情報をすぐに受け取ることができる社内ポータルは会社にとって必須のツールといえるでしょう。
社内ポータルを最大限活用するためには、目的と発信すべき情報を整理する
社内ポータルを構築したものの、上手く扱えていないという組織も少なくありません。社内ポータルが活用できていない要因として、発信すべき情報の整理と設計が出来ていないということがあります。これまでの社内イントラやファイルサーバーから、そのまま内容を新しい仕組みに移し替えただけで、内容について再検討がなされていないという状況です。
今後、多くの役割を担うこととなるポータルサイトとして新しい運用設計を考えなければなりません。先に触れた背景を踏まえつつ、ポータルサイトが果たしうる役割について、いくつか例示してご紹介します。
ハイブリッドワーク・オンラインコミュニケーションの支援
社内ポータルはハイブリッドワーク・オンラインコミュニケーションの支援にも有用です。書類の保管場所、業務管理や申請、それぞれの仕事に用いられるツールなど、業務がオンライン化することに併せて、それらの多様なツールやサービスの入口をポータルサイトに集約することで、アクセスの利便性を高めることができます。
また、出社して直接執務室を訪ねたり隣の部署に話しかけに行ったりということが難しくなった代わりに、社内の連絡先等を見る機会も増えたことと思います。さらに、ポータルサイト内に各部門からの発信のためのスペースを設けることによって、部門間連携の礎となるそれぞれの部門のリアルタイムな状況や情報を全社に対して共有するというケースも非常に多くあります。
「オンボーディング」の支援
オンボーディングは、企業・組織から新入社員(中途を含め)へのサポート支援を指しています。情報提供や価値観の共有によって新入社員(中途社員)と既存の社員の関係性を円滑にし、新入社員(中途社員)が企業・組織にすぐに溶け込み、のびのびと業務にあたるために様々な情報提供や機会の提供を行います。オンボーディングの主要な項目として、大まかに、以下の3つが挙げられます。
- 業務の流れ・手続き・規定を知る
- 会社の風土・価値観を知る
- 人を知る・つながる
入社後、新入社員がこれらの情報をじっくり見ていくために社内ポータルサイトが重要な役割を果たします。長年勤めている社員だけが「慣れと経験によってどの情報がどこにあるのか・誰が知っているのかを把握している」という状態であることが多くの会社で起こっていました。これらを誰もが分かりやすく・見つけやすく整理していくことを、社内ポータルサイトの設計時に検討することが重要です。
オンボーディングの取り組みについて、勿論ポータルサイトのみで行うということではありません。その他様々な施策についてもご紹介しておりますので、こちらの記事もぜひご覧ください。
社内ポータルの本質的な機能とは、社員のコミュニケーション行動の媒介
ここまで触れてきた現在の社内ポータルの担う役割を整理すると「全社員が必ずアクセスする場」として「オンラインの社内コミュニケーションの中心となりながら、様々な情報流通や人と人とのつながりを媒介する」ということがその本質的な価値であると言えます。
企業・組織が目標に向かって進むためには、社員同士のコミュニケーションによって意思決定や合意形成を行うことが必須です。社員同士の意思疎通のスムーズさは企業・組織のパフォーマンスにも大きく影響し、長期的に見ると経営にも関わってくる大事な部分です。単なる情報の倉庫やリンク集ではなく、今後の経営や事業を支えるために必要な社内コミュニケーションをイメージしながら、社内ポータルを設計する必要があります。自社の理想とする働き方を捉えながら、促したい社員のコミュニケーション行動(情報の取得・発信)を定義することが、社内ポータル設計に必要不可欠なのです。
ただし、最初から細かな用途を検証することが出来るのは稀で、セキュリティやコストなどを踏まえた導入の判断をすることが多いでしょう。つまり、既に導入されたシステムやツールを用いることを前提としながら、あとからその詳細の目的・用途の設計を行うということになります。
とはいえ、現在多くの組織の社内インフラとして導入されるツールは情報の取得・発信に関わる機能を有しているため、目的・用途を設計した上で、対応する機能をあてはめていくことが出来ます。ただ、用途が明確化されていなければ機能の細かい運用が定まらないため、この設計を解像度高く行うこと・あるいは長期的な運用の中で細かく改善していくことが求められます。本記事では、汎用的なものについてしか触れられませんが、主な機能と、対応する用途について例に挙げて述べていきます。

社内コミュニケーションの目標設定|KPI設計と成功事例で組織を変える【2025年最新版】
社内コミュニケーションの目標設定にお悩みですか?本記事では、大企業のDX・広報・人事担当者向けに、定量・定性デ…
社内ポータルの機能
社内ポータルサイトが一般的に備えている機能についてご紹介していきます。
検索機能
社内ポータルには性能の高い検索機能が搭載されており、これまでに蓄積した会社の情報を検索で簡単に引き出すことができます。すぐに欲しい情報を手に入れられる検索機能は、スピード感が求められる現代のビジネスの現場においては必須であり、多くのユーザーが社内ポータルに求める機能でしょう。
ワークフロー申請
社内ポータル上で、交通費や各種経費の精算、その他稟議など申請に関するワークフローを実装できます。社内の業務効率化に大きく寄与します。
コミュニケーション機能(情報掲示・ファイル整理・双方向)
旧来のファイルサーバーから置き換わるものとして、まずは様々な社内のファイルを整理して設置することが必要です。またそうした機能から派生して、「WEBサイト」「WEBページ」として、情報を伝わりやすく編集して掲載する機能も併せて持っていることが一般的です。そしてそれらに対して社員側・利用者側から何らかのリアクションや発信を行うこともできます。
スケジュール管理
チームや関連部門のメンバーのスケジュールを、ブラウザから一覧で確認できます。メンバーの予定を把握することで、打ち合わせの日程を決めたり、上司が不在の時間を把握したりすることができます。
プロジェクト管理
プロジェクトの進捗状況や参加メンバー、現在のタスクの担当者を確認できます。状況を全員で共有できるため、遅延や抜け漏れが起きにくくなります。また、プロジェクトメンバーだけのチャンネルを作ってチャットを行ったり、定期ミーティングのスケジュールを繰り返し申請したりと、複数のツールを連携して密なコミュニケーションが可能です。
勤怠管理
社内ポータルにログインした時点でタイムカードを打刻したものとみなして、勤怠管理に使うことができるツールもあります。特にテレワークにおいてはタイムカードへの打刻ができないため重宝するでしょう。また社員のログ情報は自動的に集計されるため、コーポレート部門の負荷を大きく軽減できます。
社内ポータルサイトの構築手順
社内ポータルサイトを効果的に機能させるためには、明確な目的に基づいた計画的な構築が不可欠です。ただシステムを導入するだけでは、期待する成果は得られません。利用者にとって本当に使いやすく、業務や組織運営に役立つポータルを実現するには、段階的な設計と改善のプロセスが重要です。
ここでは、社内ポータルサイトの構築手順について、具体的なステップごとに解説します。
目的の明確化
社内ポータルの構築において最初に行うべきは、導入の目的を明確にすることです。例えば、以下のような目的が考えられます。
- 社員間の情報共有を円滑にする
- 業務効率を向上させる
- 会社のビジョンや経営方針を伝える
テレワークやハイブリッドワークの支援を行う情報共有の効率化や業務の生産性向上、企業ビジョンの浸透、テレワーク環境の支援など、目的によって設計方針が大きく変わります。何を実現したいのかを明らかにすることで、必要な機能やコンテンツの選定もスムーズに進みます。
必要な機能の洗い出し
目的に沿った社内ポータルを作るには、必要な機能を整理することが不可欠です。ニュース配信や社内掲示板などの情報共有機能、スケジュール管理やワークフローといった業務支援機能、さらに検索やチャット、セキュリティ対策なども重要です。業務フローを想定し、目的に応じて、必要な機能をリストアップします。主な機能として以下が挙げられます。
- 情報共有機能(ニュース、社内ブログ、掲示板)
- 業務管理機能(ワークフロー、プロジェクト管理、スケジュール管理)
- 検索機能(社内文書や連絡先の検索)
- コミュニケーション機能(チャット、ビデオ会議、フォーラム)
- セキュリティ管理(アクセス制限、ログ管理)
システムの選定
次に、ポータルを構築するためのシステムを選びます。既存のプラットフォーム(例:SharePoint、Google Sites)を活用すれば、導入コストや開発期間を抑えられます。
一方、業務に特化した柔軟な設計を求める場合は、カスタム開発も検討に値します。目的や予算、運用体制を踏まえて最適な方法を選びましょう。
コンテンツの設計
掲載する情報の構成や更新体制を設計します。内容をカテゴリ別に整理し、どの部署が情報を管理・発信するかを明確にします。更新頻度やルールを定めることで、情報の鮮度と信頼性が保たれ、社員にとって価値あるポータルとなります。運用ルールの整備は、長期的な活用に欠かせません。
ユーザーインターフェース(UI)とユーザーエクスペリエンス(UX)の設計
ポータルは誰でも直感的に操作できることが重要です。シンプルなデザインと明快なナビゲーションを意識し、必要な情報にすぐアクセスできる構造を目指します。スマートフォンやタブレットなど、モバイル対応も不可欠です。使いやすさは、活用度や定着率に直結する要素です。
使いやすいデザインを考慮し、以下のポイントを押さえましょう。
- 直感的な操作性(誰でも簡単に使えるようにする)
- モバイル対応(スマートフォンやタブレットでも快適に閲覧できる)
- ナビゲーションの工夫(情報をすぐに見つけられるようにする)
テスト運用とフィードバック
構築後はいきなり全社導入せず、まずは一部のユーザーによるテスト運用を行います。その中で、操作性や機能性、情報の探しやすさ、セキュリティ面の課題を洗い出します。現場からのフィードバックを受けて、改善点を明確にすることで、導入後の満足度と実用性が高まります。構築したポータルサイトを一部の社員に試用してもらい、以下の点を確認しましょう。
- ユーザーが使いやすいか
- 情報の見つけやすさ
- 必要な機能が適切に動作するか
- セキュリティ上の問題がないか
本格導入と継続的な改善
テスト運用で得たフィードバックを反映し、必要な修正や機能調整を行ったうえで、本格的な社内展開を開始します。ここで重要なのは、導入して終わりではなく「運用しながら改善を続けること」です。情報の更新が滞ればユーザーの信頼を失い、使われなくなるリスクがあります。
定期的なコンテンツの見直しや更新、ユーザーから寄せられた意見や要望をもとにした改善対応、さらに業務環境の変化に応じたシステムのアップデートも欠かせません。運用フェーズにおいても、利用状況の分析や定期的なアンケートなどを通じてニーズを把握し、常に「今の業務に合ったポータルを保つこと」が成功の鍵となります。
社内ポータルサイトを構築する際のポイント
目的・用途そして機能を踏まえ、実際に自社で構築する際のポイントを5つにまとめました。
1.社内の多様な観点からポータルサイトが解決する課題を定義する
社内ポータルを取り扱う部署としては、情報システム部(IT推進部)が最も多く、次いで人事や総務が担うことが多いでしょう。そうした際、まず議題にあがるのはITツールやセキュリティに関する通知、勤怠や承認・申請などの仕組みの実装などです。
その他にも、オンラインとオフラインのハイブリッドワークにおける重要な社員の共通基盤として、組織課題の解決に資するコミュニケーションを社内ポータルに組み込むことも重要です。チームの中に、社内広報を担うメンバーや経営企画、SDGsなど経営テーマの推進を担うメンバー、バックオフィスでなく事業側のメンバーが参画することも増えています。社内ポータルサイトの構築を大人数で議論することが出来ない場合でも、何らかの形で様々な観点からの意見を取り入れることが重要です。

社内コミュニケーションの目標設定|KPI設計と成功事例で組織を変える【2025年最新版】
社内コミュニケーションの目標設定にお悩みですか?本記事では、大企業のDX・広報・人事担当者向けに、定量・定性デ…
2.組織課題の解決のための情報発信をはかる
ブラウザを立ち上げて最初に開かれるポータルサイトは、社内でもっとも見られやすいWebサイトであると言えます。閲覧率の高いメディアとして、社員の行動変容に繋がる情報の発信に活用できます。組織課題や事業課題を踏まえ、注力するテーマを決め、それに合致するコンテンツを制作しましょう。
具体的な事例では、「自律的なキャリア開発」を標榜し、社内でのキャリアパスに関する情報発信のサブサイトを設け、そこから人材開発に関する学習コンテンツへと誘導するものや、経営計画やビジョンの解説、SDGsやDXなどに関する社内の取り組みを紹介するコンテンツなどが多くの会社で発信されています。業務に必要なツールとしてだけでなく、社員と共有したい情報の設計にも気を配ってみてください。
3.見つけやすく適宜に分類された情報の配置
社内ポータルサイトを利用して効率のよい作業を送るためには、社内に点在するさまざまな情報やドキュメント、リンクや帳票などが社内ポータル内でどこにあるかをすぐにわかるように設計する必要があります。
目的別(休暇取得や人事制度の確認、相談窓口)、発信元別(人事部発、広報部発)など、さまざまな分類の方法があるので、ポータル設計の際にはユーザーヒアリングを行いましょう。どんなニーズでポータルにアクセスすることが多いのかなどを聞き出し、ユーザー中心で情報設計を行うことが重要です。
4.セキュリティ意識の強化
社内ポータルには社員の個人情報をはじめ、取り扱いに注意が必要な情報が集約されるでしょう。情報漏洩を防ぐためには社員への注意喚起が必要です。
現在ではテレワーク推進期ということもあり、社員の自宅や外出先からのアクセスも予測されます。「テレワークで使用しているPCを他人と共有しない」、「公共の場所でPCを開いたまま席を立たない」など、社員のセキュリティ意識の強化に努めましょう。
参考:テレワークを行う際のセキュリティ上の注意事項(独立行政法人情報処理推進機構)
5.コミュニケーションの場を整理する
社内ポータルでチャットツールや掲示板を導入できても、それがどんな目的で設置され、どう使われるべきなのかを明示しておかないと、場が荒れたり過疎化したりします。コミュニケーションツールを社内ポータルに設置する際は、どのような場にしたいかを整理してから実装しましょう。
定着する社内ポータルの条件
多くのサイトがそうであるように、社内ポータルもリリースして終わりではありません。サイトにとって最新情報の掲載は不可欠です。特に社内の情報は古いものが混じっていると混乱を招いたり、トラブルの元になったりします。「ここへ来ても最新情報が得られない」と社員が感じるようになると、社内ポータルにアクセスしなくなってしまうため要注意です。社内に定着する社内ポータルの条件を見ていきましょう。
使われやすいデザインとインターフェースが採用されている
社内ポータルにどんなに便利なツールと情報が集約されていても、表示されたページが見にくかったり動線が分かりづらかったりすると、思ったように利用されないケースがあります。
社内ポータルのようなサービスのデザインは、UI(ユーザー・インターフェース)を指しています。UIは、ユーザーと物やサービスの接点(インターフェース)を意味しており、社内ポータルをPCで閲覧した場合のページの構成や、メニューの項目・並び順、文字の大きさやフォント、色使い、ボタンのデザインなど、画面上に表示される情報全てがUIを構成する要素にあたります。
社員に社内ポータルを日常的に利用してもらうには、UIのわかりやすいデザインが重要になります。直観的に操作ができ、どこに何のツールや情報があるのかすぐにわかるように構築することが大切です。まずは前項で説明した情報設計をもとにUIを決めていきましょう。
また社内ポータルは作って終わりではなく、社内コミュニケーションやビジネス潮流の変化に併せて、小さなブラッシュアップを行う必要があります。ポイントは小さく変化させ続けることです。急に大きく変更された社内ポータルは社員が適応できず、逆に非生産的なツールとなってしまいます。
上記のことから社内ポータルは、小さな変更ができるツールや、機能アップデートが計画されているツールを選択することが重要になります。さらに最近ではスマートフォンでのWebサイト閲覧も当たり前になっているので、モバイルデバイスにも最適化されたデザインが必要になります。自社でアイデアが浮かばない場合は、社内ポータルの構築実績が豊富な協力会社に相談することでスムーズに制作が進みます。
情報発信の際のテンプレートを用意する
情報発信のテンプレートを用意しておくと、発信する側の時間短縮になるだけでなく、閲覧する側にとっても見やすいポータルサイトを保つことができます。見やすく更新しやすいテンプレートを開発し、活用していきましょう。
社員のセキュリティ意識の向上を図る
社内ポータルを定着させるためには、社員の一人ひとりが情報の価値・リスクを正しく判断し、状況に応じた行動を考えるような意識を醸成していきましょう。
昨今の社内ポータルは外出先からクラウド経由でアクセス可能です。そのため、自宅や立ち寄った場所でパソコンやスマートフォンを開いて閲覧や書き込みができます。これはすなわち、第三者に見られる危険性が非常に高いということです。
また、交通機関内で社内ポータルを見ながらうっかり話した内容が機密情報にあたることも考えられます。とはいえ、仕事にスマートフォンなどモバイル機器を用いることももはや当たり前となり、そのおかげで利便性も大きく向上しています。「セキュリティ」を縛りすぎて何もできなくなってしまうのでなく、社員のセキュリティ意識の向上を図るための研修会などを用いると良いでしょう。
社内ポータルサイトの構築事例
ECサイト的アプローチを採用した事例
参考事例:Amazon型のインターフェース
A社では、従業員が必要な情報に迅速にアクセスできるよう、ECサイトの情報構造を参考にした社内ポータルを導入しました。同社のポータルサイトでは、各種の社内情報やツールへのリンクが、検索で簡単に見つけられるよう整理されています。
現代の購買行動において主要な役割を果たすECサイトでは、多様な商品が検索でヒットするように配置され、カテゴリー分けや階層構造によって体系化されています。これにより、ユーザーは具体的に探しているものがなくても、関連商品群を閲覧しながら必要なものを発見できます。また「人気商品」などのハイライトエリアで特定の商品に注目を集めることも可能です。
A社はこのアプローチを社内ポータルに応用し、社内情報やリソースを「従業員が必要とする情報資産」として扱い、適切なカテゴリーに分類しました。検索機能を備えたグループウェアをプラットフォームとして活用することで、社員が求める情報に素早くたどり着ける環境を実現しています。
ユーザー目的型アプローチを導入した事例
参考事例:ヤマト運輸のような顧客志向インターフェース
B社では、従来の部署別情報発信から、業務シーン別の情報提供へと社内ポータルを刷新しました。宅配サービスのウェブサイトをモデルにしたこのアプローチは、従業員の実際の業務フローに沿った情報アクセスを可能にしています。
サービス提供型のウェブサイトでは、ユーザーの離脱を防ぐため、訪問者の目的に沿いながらも情報量を絞り、必要なアクションを明確に配置しています。
たとえば「法人のお客様」「個人のお客様」といった訪問者区分や、「発送したい」「受け取りたい」などの利用目的に応じた案内が用意されています。
B社の社内ポータルでは、この考え方を採用し、「休暇を申請したい」「経費を精算したい」「顧客提案資料を作成したい」など、日々の業務シーンに基づいた情報ナビゲーションを実装しました。従来の部署別情報発信(人事部からのお知らせ、総務部からの通達など)では、単一の業務に必要な情報が複数部署に散在することが課題でした。
たとえば「長期休暇取得」に必要な情報は、人事部の申請書類、総務部の福利厚生案内、情報システム部のPC取扱いガイドラインなど、複数部門にまたがります。B社の社内ポータルでは、これらの情報が業務シーンごとに集約され、従業員は部署の垣根を意識せず必要な情報にアクセスできるようになりました。この改善により、情報探索時間が大きく削減され、業務効率の向上に貢献しています。
戦略的コミュニケーション型アプローチを実現した事例
参考事例:オウンドメディア運営企業のコンテンツ戦略
C社では、社内ポータルをただの情報リポジトリではなく、企業文化や戦略浸透のための戦略的プラットフォームとして再構築しました。デジタルマーケティングの手法を社内コミュニケーションに応用したこの取り組みは、従業員エンゲージメントの向上に顕著な成果をもたらしています。
現代の企業コミュニケーションでは、従来の実店舗やマスメディアに加えて、自社独自のメディア(オウンドメディア)運営が一般的になっています。価値ある情報を継続的に発信し、閲覧者との関係を構築することで、望ましいアクションを促進する戦略です。
C社はこのアプローチを社内に適用し、日常的に使用される勤怠システムや文書管理機能に加えて、企業ビジョンの理解促進やDX推進に関するコンテンツを戦略的に配置しました。毎日必ずアクセスされるポータルの特性を活かし、経営からのメッセージや成功事例、実践的なヒント、参加型プログラムへの申込フォームなどを効果的に提供しています。
特に注目すべき点は、C社が社内ポータルのコンテンツを「プッシュ型」と「プル型」に分けて戦略的に配置していることです。必須の業務情報(プッシュ型)と自発的に閲覧したくなる価値あるコンテンツ(プル型)を組み合わせることで、従業員の継続的な関心を維持しています。従業員の戦略的重点施策への理解度が向上し、関連プログラムへの自発的参加も増加しました。
これらの事例は、社内ポータルが単なる情報提供の場を超えて、組織の戦略目標達成や文化醸成に貢献できることを示しています。成功の鍵は、従業員の実際の利用状況や業務ニーズを深く理解し、それに合わせたサイト構成を実現することにあります。
将来的な社内ポータルの理想像「デジタルワークプレイス」
社内ポータルは、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進とともに、より注目が集まっています。これを具体化したものが「デジタルワークプレイス」です。
デジタルワークプレイスとは、業務に不可欠なツール群や各種情報、コミュニケーションツールをオフィスからクラウド上に移行し、マルチデバイスでアクセス可能にするものです。インターネットに接続さえできれば時間や場所を問わずに業務や業務上のやりとりができるので昨今のテレワーク時代に即した働き方を実現するビジネス戦略です。
今まで実際のオフィスでやってきたことを、できるだけそのまま、あるいは効率をさらに高めながら、WEB化していくという試みのため、「紙業務の電子化」の更に次の段階と言えるでしょう。気軽に使えるWEB会議ツールや、共同編集可能なPowerPoint、Excelファイルなども、デジタルワークプレイスの考え方に基づくものです。
その他、集合研修や、情報発信の掲示板といったものもWEB化が可能ですし、中にはもっと細かな、「ドアを開け、違う部署の〇〇さんに声をかける」といった動作をWEB化しているアプリケーションもあります。できるだけストレスなく、また本来リアルの場であった細やかなコミュニケーションをも、デジタルの世界に反映していくツールの開発が各社で進んでいます。
具体例として、Microsoftがデジタルワークプレイスの実現に向けた開発を進めています。アプリケーションの「Teams」への統合や、SharePointのVR対応により、Teamsからあらゆることができるようになり、VR化した社内ポータルが作れるようにもなるそうです。これにより、社内ポータルで実現できることの幅がより一層広がっていくと考えられます。
まとめ
社内ポータルとは社員同士のコミュニケーションを円滑化させるツールであり、その副次効果として業務の効率化・社員のモチベーションの向上・テレワークの促進といったメリットが期待できるとお伝えしました。情報を一箇所に集めるため、社員同士で共有されていない情報が最小限に抑えられる効果もあります。
また社内ポータルには、ワークフロー申請や勤怠管理といった、勤務する社員の業務外の手間を簡素化してくれるメリットもあります。経費の精算やタイムカードの打刻が社内ポータルでできるのは、多くのビジネスパーソンにとって小さなストレスから解放される意味があります。これまでアナログで行っていた細かな作業を省ける点も、社内ポータルを運用するメリットです。
社内ポータルは社員が業務遂行のために活用するツールですが、ただ導入しただけではメリットを引き出せずに社員が使わなくなってしまう可能性も高いでしょう。大切なのは社員同士のコミュニケーションを円滑化するゴールを見失わず、社員が業務を遂行させる際のニーズに合わせながら、社内ポータルの機能を更新していくことです。適切にアップデートを繰り返した社内ポータルは社員に定着し、業務のスムーズな進行を手助けしてくれることでしょう。