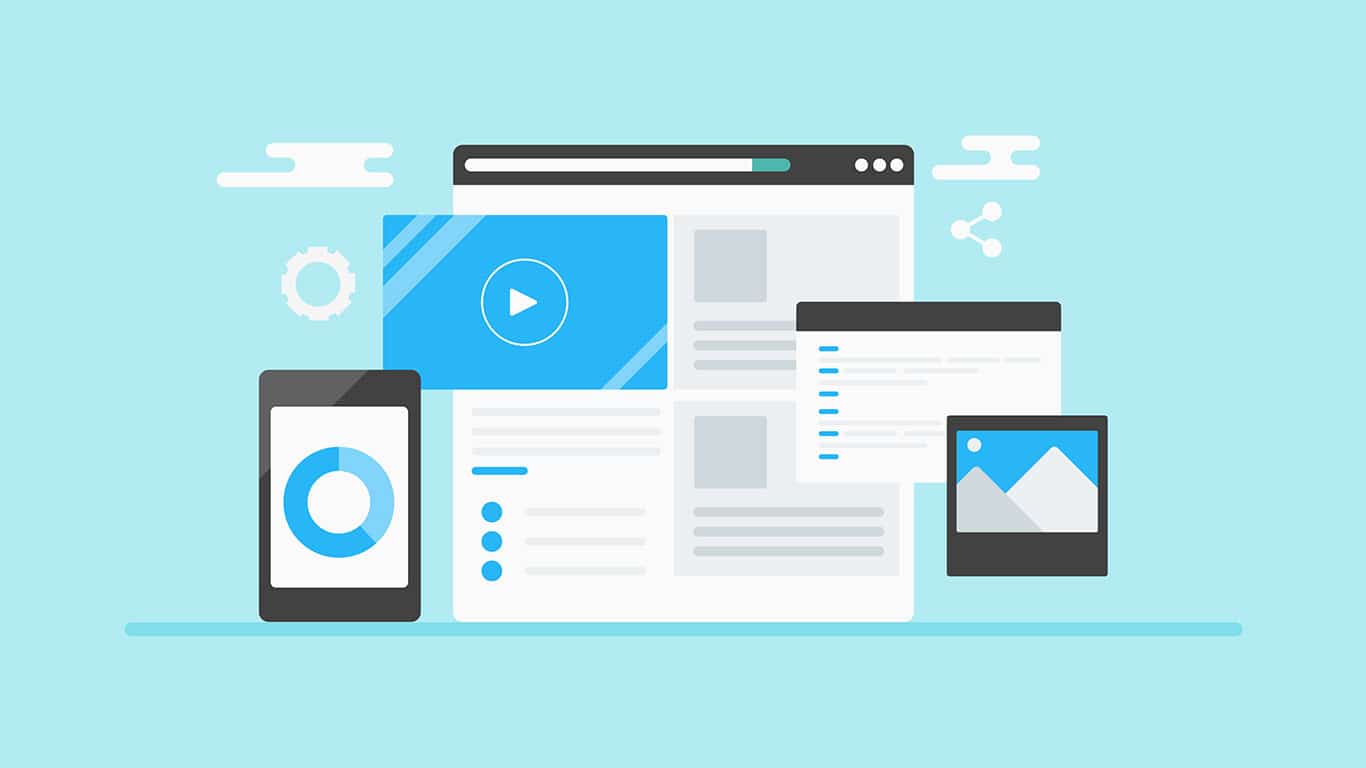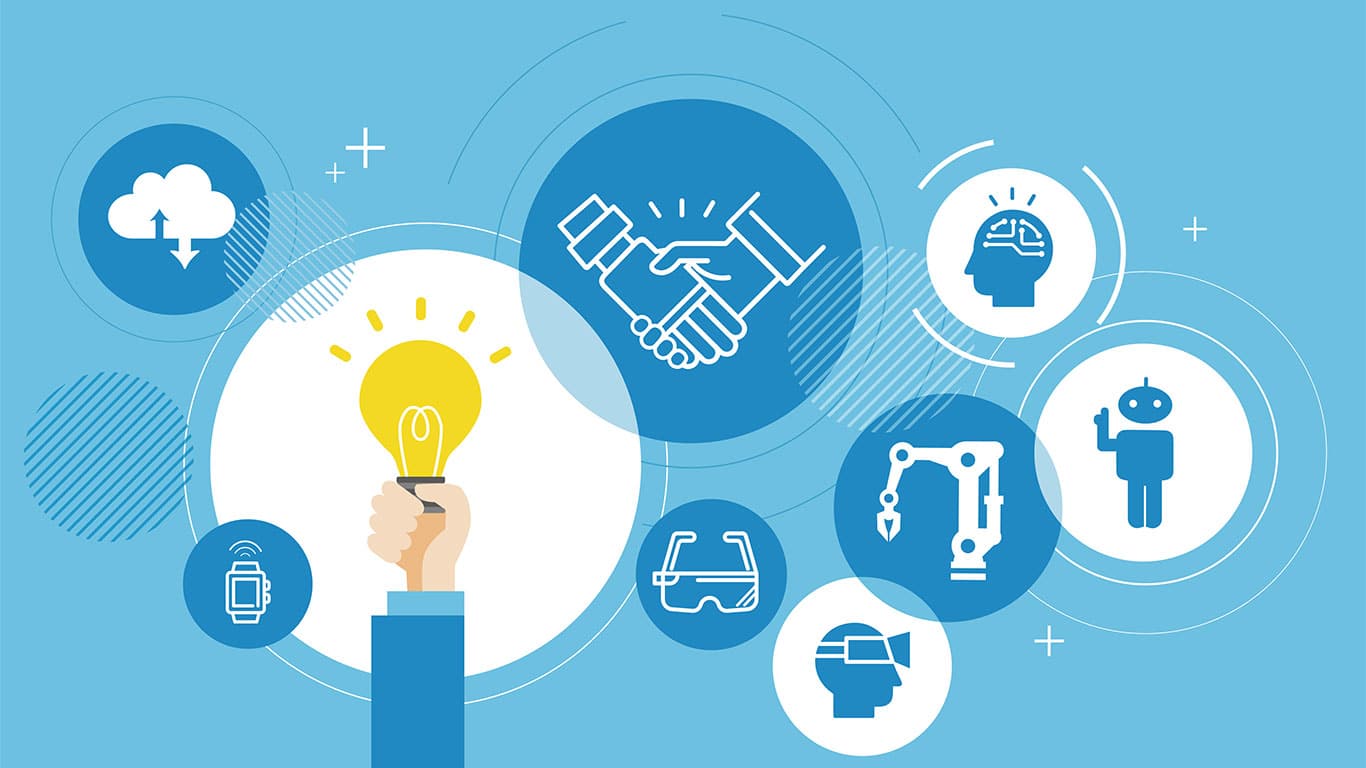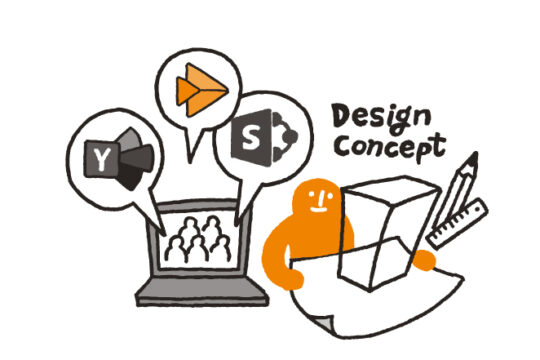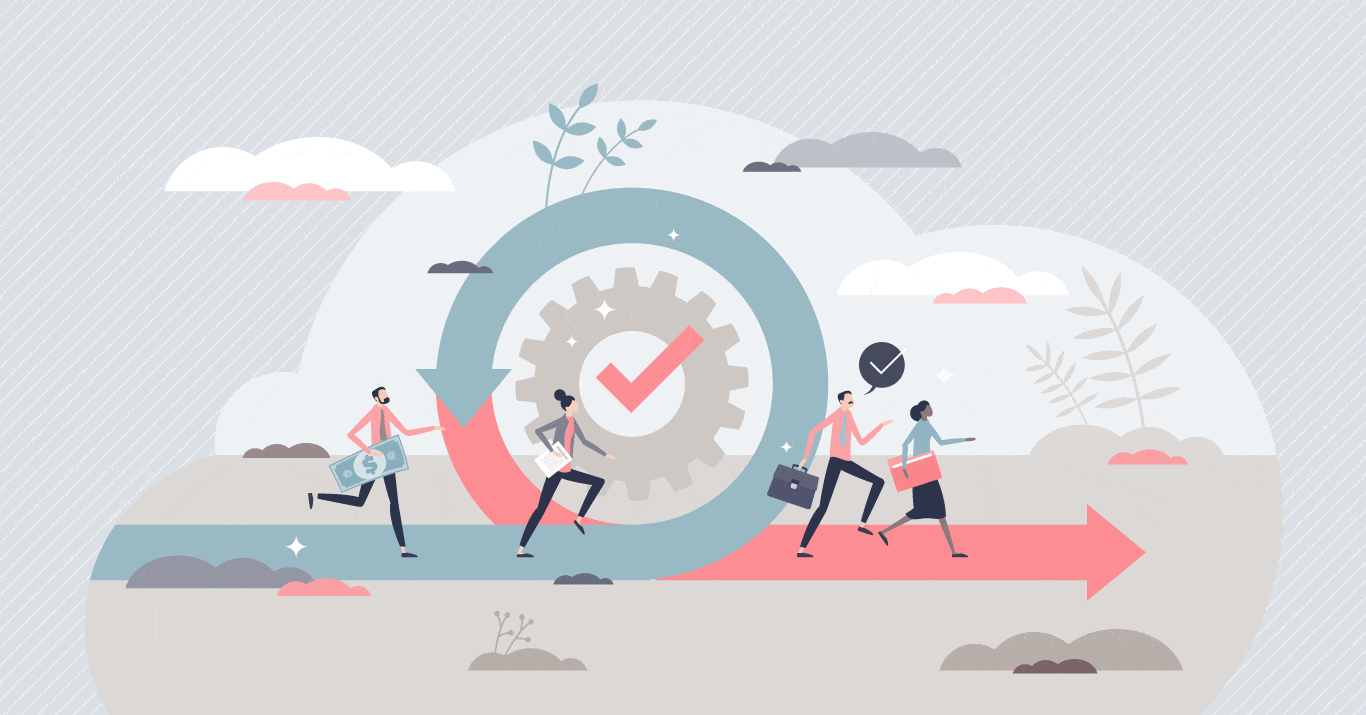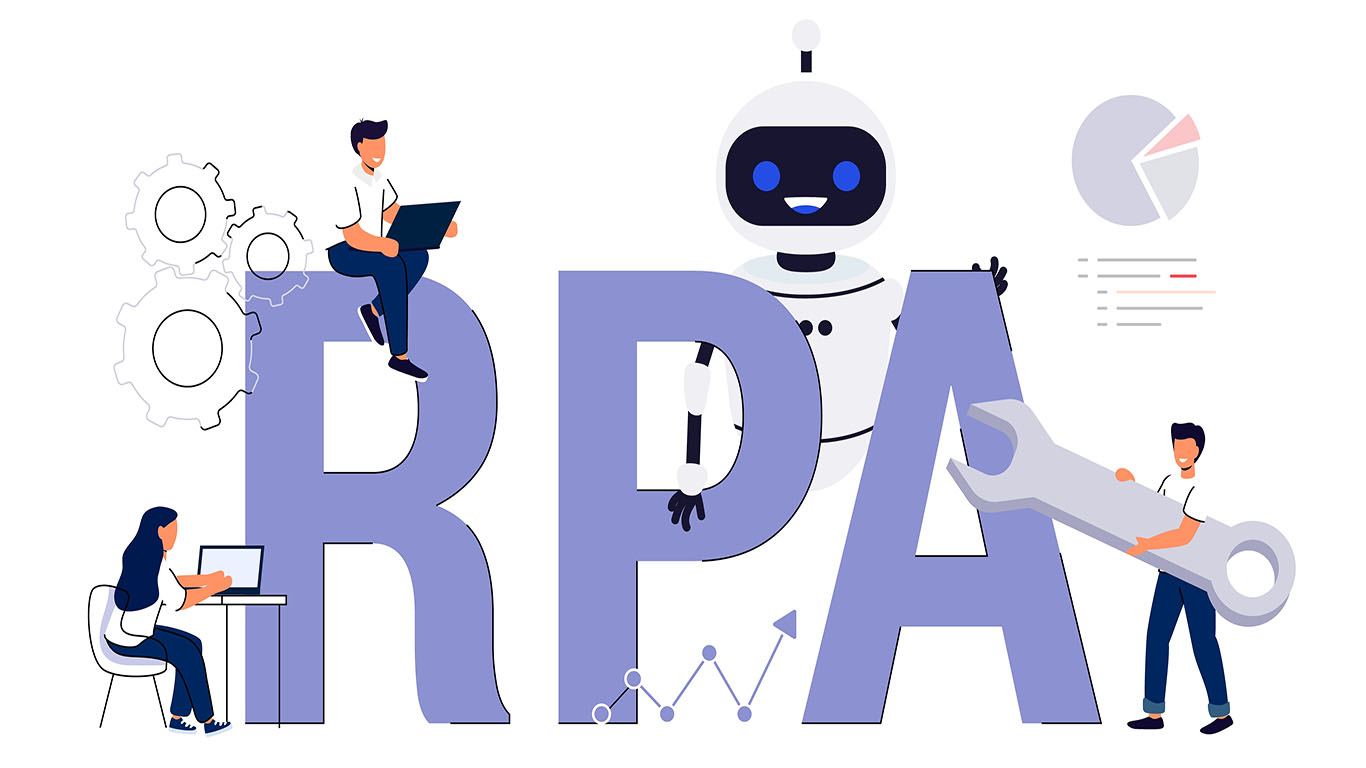情シス業務効率化の課題と対策:社内ポータル構築で実現する5つの方法
最終更新日:2025.07.22

目次
情報システム部門(情シス)は企業のITインフラを支える要として非常に忙しい部署です。日々、ネットワーク障害やPCトラブルへの問い合わせ対応からシステム運用・保守、セキュリティ対策まで幅広い業務に追われがちです。DX推進が急務となっている現在、情シス部門自体がこうしたアナログ業務に忙殺されていては、本末転倒です。率先垂範でデジタルツールを活用して業務を効率化し、その利便性や実証効果を身をもって社内に示していきましょう。
情シス部門が抱える主な課題
まず、情シス部門の現状で押さえておきたい主な課題を整理します。IT人材の慢性的な不足や「ひとり情シス」状態、ユーザーからの問い合わせ対応の多さ、業務範囲の拡大による非効率、業務の属人化、そして情シスの貢献が評価されにくいことなどが代表的です。これらの課題は互いに関連し、結果として情シス本来の戦略業務に注力できない状況を生んでいます。以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。
人手不足と「ひとり情シス」の増加
IT人材の不足は日本全体の深刻な課題であり、情シスも例外ではありません。こうした人材難の中、中小企業を中心に情シス担当者が一人しかいない「ひとり情シス」や他部門と兼任のケースが増えています。実際、中小企業の87.4%で情シス担当者は一人だけというデータもあります。
人員が限られる中で幅広いIT業務を担わざるを得ず、一人ひとりの負荷が肥大化しているのが現状です。特に経営陣にIT分野の理解や重視する意識が乏しい場合、情シス部門への人材投資が後回しにされ、結果として慢性的な人手不足に陥りがちです。「兼務情シス」状態で業務を回したり、IT知識があるという理由だけで本来の職務に加えて情シス業務も任される「ゼロ情シス」(正式な情シス不在)の状態も散見されます。こうした状況では一人に業務が集中しすぎて重要な案件まで手が回らないだけでなく、担当者が不在になると業務が止まってしまうリスクも高まります。
ユーザーからの問い合わせ対応過多
社内のユーザー部門から情シスへの問い合わせ件数が非常に多いことも大きな課題です。特にシステムトラブル発生時には近年はリモートワークや社内DXの推進で新たなITツール導入・アップデートの機会が増え、それに伴い発生するトラブルや疑問への対応件数も増加傾向にあります。ある調査では情シス担当者の66.6%が「問い合わせ対応業務」を生成AI活用によって改善したい課題の第1位に挙げたという結果も出ています。これは、日々の問い合わせ対応がいかに情シスの時間を取っているかを物語っています。
しかし、多くの場合で情シスが事前にマニュアルを用意していても、それが十分に活用されていない現状があります。「どこにマニュアルがあるかわからない」「内容が難しくて理解できない」といった理由から、ユーザーは結局「聞いた方が早い」と情シスに問い合わせてしまいがちです。社内でユーザーがマニュアルやFAQを活用しない主な要因には以下のようなものがあります。
- 利用意識の問題: そもそも自主的にマニュアルを参照する文化が社内に根付いていない。
- 運用上の問題: マニュアルの存在や場所、使い方が周知されておらず、共有方法も適切でない。
- 内容・構成の問題: マニュアル文書が専門用語ばかりで難解すぎるなど、一般ユーザーには理解しづらい。
このような理由でせっかく作成したマニュアルや社内FAQが活用されず、「結局は情シスに尋ねるしかない」という状況が続けば、問い合わせ件数は増える一方で情シスの負担は増加し疲弊してしまいます。初歩的な「ログインできない」「ネットにつながらない」といった定型的な問い合わせ対応だけで情シスの貴重な時間が消費されてしまい、本来注力すべき戦略的業務に手が回らなくなる懸念も指摘されています。
業務範囲の拡大と非効率な運用
情シスが担当する業務範囲は非常に広く、システムの開発・運用保守、ネットワーク構築、ヘルプデスク対応、セキュリティ対策など社内ITに関わるあらゆる分野に及びます。特に中小規模の組織では情シス部門が少人数であるため、「」形で業務が次々と積み重なり、過剰なマルチタスク状態に陥りがちです。その結果、重要度の高いIT戦略の立案やシステムの刷新といった本来注力すべき業務が後回しになり、レガシーシステムの放置やセキュリティ対策の遅れにつながるリスクも生まれています。
また、情シス担当者のスキルセットと求められる業務要件のミスマッチも非効率を招く一因です。本来専門のチームがあるべきセキュリティ領域まで情シスが抱え込み、逆にアプリ開発経験者にネットワーク管理を任せざるを得ないケースもあります。最新クラウド技術やAIツールの活用が求められても担当者がレガシー環境の知識に留まっていれば対応が難しくなるでしょう。このように守備範囲の広さゆえに一人ひとりの担当業務が膨れ上がり、非効率な運用に陥っている例は少なくありません。
さらに前述のとおり、基本的な問い合わせ対応などノンコア業務の比重が大きいと重要なプロジェクトに集中できず、DX推進の足かせとなります。例えば新システム導入計画や情報戦略の検討などは後回しにされがちで、その遅れが企業全体の生産性にも悪影響を及ぼします。定型業務に忙殺される状態を放置すれば、システムの近代化や社内DXも進まず技術的負債が蓄積してしまうとの指摘もあります。
情報システム業務の属人化
情シス業務は各企業のシステム環境や社内体制に応じて内容が大きく異なり、現場の知見が重視されます。そのためノウハウが特定の担当者個人に蓄積・集中しがちで、結果として業務が属人化する傾向があります。現状ではベテラン担当者一人に頼りきりで、「その人しかシステム全体を把握していない」というケースも珍しくありません。属人化が進むと、担当者が休職・退職した途端に誰も業務を引き継げず対応不能になるリスクが生じます。
属人化の弊害として、システムやセキュリティの運用管理が宙に浮いてしまうことが企業リスクにつながります。また、新しい技術情報や社内ニーズの変化に対応するためにチームで知識共有が不可欠ですが、属人化状態では情報共有もうまく機能しません。担当者自身も自分しかできない仕事が増えることで休みづらくなり、精神的・肉体的な負担が増大する悪循環にも陥りかねません。
経営層から評価されにくい現状
情シスの仕事は企業運営に不可欠なインフラ維持・サポート業務ですが、直接的に売上や利益に結び付くものではないため社内で正当に評価されにくい面があります。システムトラブルを未然に防ぎ安定稼働させていても「問題が起きていない状態」が当たり前と捉えられ、貢献が目に見えづらいのです。また、IT知識が豊富でない他部門の社員からは情シスの日頃の苦労が理解されにくく、経営層からも重要性を軽視されがちという声があります。その結果、情シス改善のための予算や人員が十分に割り当てられないことも少なくありません。経営陣が情シスの重要性を認識しないままだと、いくら現場が効率化策を提案しても実施に移すのが難しくなってしまいます。
評価されない状況は情シス担当者のモチベーション低下にもつながり、人材流出の一因ともなります。したがって、情シス部門が抱える課題を解消するには経営層への働きかけも不可欠です。この点については後述する「経営層の理解を得る」施策で詳述します。
情シス業務効率化の主な施策
上記の課題を踏まえ、情シス部門の業務効率化を実現するための具体的な施策を体系的に紹介します。ここでは業務棚卸による現状把握と業務範囲の見直しから始め、社内ポータルサイトでの情報共有基盤整備、FAQ充実とチャットボットによる自己解決支援、RPAなどITツールによる業務自動化、業務の外部委託(アウトソーシング)、社員のITリテラシー向上、そして経営層の理解促進まで、効率化に有効な施策を順に解説します。それぞれの施策が先述の課題にどうアプローチできるのかを見ていきましょう。
業務棚卸と業務範囲の見直し
効率化の第一歩は、情シス部門の現行業務をすべて洗い出し(棚卸)て可視化することです。誰がどのような業務を、どのくらいの頻度と時間で行っているかをリストアップし、業務内容・関係部門・使用ツール・月間工数などを整理します。この業務棚卸作業により、日々当たり前のようにこなしているタスクの全貌が明らかになり、非効率や無駄な手順、重複業務の発見につながります。棚卸結果は表やグラフで共有し、チーム全員で現状を認識することが重要です。
業務棚卸のポイント: 現在の情シス業務をリスト化 → 業務フローを図示してボトルネックを把握 → 業務の重要度・緊急度で分類し優先度を設定 → 「やらない業務」を決める → 手順の標準化・効率化策を検討
上記のプロセスで、まず優先度の低い業務や情シス以外が担当すべき業務を炙り出し、思い切って削減・他部署移管する決断が必要です。情シスが抱える全業務を見直して「やらないこと」を明確化することで、本当に取り組むべき業務にリソースを集中できます。また、残す業務についても標準手順書の整備や作業フローの最適化によって無駄なステップを排除し、効率化を図ります。例えば、ECRS(排除・結合・交換・簡素化)の原則に沿ってプロセス改善点を洗い出すのも有効です。
さらに、情シスの業務範囲そのものを見直すことも検討しましょう。場合によっては「この分野は情シスが担わない」という線引きを経営層と協議し、明確化することも重要です。例えば、情報セキュリティ関連は専任のセキュリティ担当者を置く、日常的なヘルプデスク業務は外部に委託する、などです。そうすることで、情シスは基幹システムや戦略ITに専念できるようになり、結果的に部門全体の生産性が向上します。
業務棚卸と範囲見直しの成果は、社内関係者とも共有しフィードバックを得ましょう。情シス部門が自ら業務を整理して改善策を提示すれば、他部署や経営層の理解も得やすくなります。このプロセスを通じて「情シスの味方」を社内に増やし、協力体制を構築することが効率化成功の鍵となります。
社内ポータルサイトの構築と情報共有基盤の整備
情シス業務の効率化には、社内のIT関連情報を一元的に共有できる基盤を持つことが大きく寄与します。その中心となるのが社内ポータルサイトの構築です。社内ポータルとは、社内の各種情報(マニュアル、FAQ、システム状況、問い合わせ先など)を集約し、社員が必要な情報に迅速にアクセスできるようにしたウェブサイトのことです。
社内にポータルサイトがあれば、PCやネットワークのトラブルが起きた際に社員がまず自分でアクセスして解決策を探せるようになります。その結果、情シスへの問い合わせ件数が大幅に減り、担当者の負担軽減につながります。ユーザー部門にとっても、問い合わせてたらい回しにされるよりポータルで自己解決できたほうが迅速に問題が解決できるメリットがあります。
社内ポータルには以下のようなコンテンツを盛り込むと効果的です。
- システム稼働状況のリアルタイム共有: 現在社内の各システムが正常稼働しているか、メンテナンス情報や障害情報をリアルタイムに閲覧可能にします。ユーザー自身がシステム状況を把握できれば、「動かないが自分だけの問題か?」といった不安や問い合わせを減らせます。
- 各システムの用途・関連情報の周知: 社内で利用している主要システムごとに、導入目的や利用シーン、関連マニュアルへのリンクをまとめておきます。社員が「どの業務でどのシステムを使うべきか」理解を深めることで活用促進につながり、結果的に情シスへの質問も減ります。
- 各種マニュアルの整備・公開: ログイン方法から操作手順まで、よくある手続きをわかりやすく解説したユーザー向けマニュアルをオンラインで共有します。すべてのユーザーを想定し、初心者にも理解できる平易な内容・構成にすることがポイントです。
- FAQ(よくある問い合わせ)集: 情シスへの頻出質問と回答をまとめたFAQを掲載します。FAQについては次項で詳しく述べますが、社員が疑問を抱いた際に真っ先に参照できる「困ったときのガイド」として機能させます。
- 問い合わせフォームやチャットボット: ポータル上に情シスへの質問フォームを設置したり、簡易なチャットボットを埋め込んで即時回答を得られるようにします。対応の自動化によって情シス・ユーザー双方の手間を削減できます。
このように項目ごとに情報を整理・分類してポータルサイトに集約すれば、情シス業務の自動化・効率化につながります。社員は「何か困ったらまずポータルを見る」という習慣ができ、情シスへの問い合わせ前に自己解決を図るようになります。その結果、情シスは細々とした問い合わせ対応をポータルに任せて、本来の重要業務に時間を割けるようになるわけです。
ポータルサイトの整備は、情シスの属人化リスク低減にも効果があります。特定の担当者だけが知っているノウハウや情報をポータル上に文書化・共有していけば、誰でもアクセスできる社内ナレッジが蓄積されます。仮に担当者が交代しても業務を引き継ぎやすくなり、組織としてIT知識が蓄えられるのです。
Microsoft 365の「SharePoint Online」を活用すれば、専門知識がなくても簡単に社内ポータルサイトを構築できます。社内で既にMicrosoft 365を導入済みであれば追加コストをかけずにSharePoint Online上にサイトを作成可能です。テンプレートや部品も豊富に用意されており、他のMicrosoft 365の機能(TeamsやOneDrive等)ともシームレスに連携できるため、使い勝手の面でも優れています。
なお、ポータルサイトを構築して終わりではなく運用面での工夫も重要です。例えば、情報発信の際には視認性を高める工夫をします。重要なお知らせはトップページの目立つ箇所に配置し、緊急度や重要度に応じてアイコンや色分けで強調します。SharePoint Onlineなら「リスト機能」を使ってお知らせ情報をカテゴリ管理し、重要度に応じて色付きラベル表示することも容易です。またFAQ情報も一元管理し、ユーザーがシステム別・用途別に絞り込んで閲覧できるビューを用意すると、必要な情報に辿り着きやすくなります。このようにポータルを単なる情報の置き場にせず、検索性・閲覧性を高める工夫を凝らすことで、社員にとって使いやすいサイトに育てていくことができます。
社内FAQの整備と運用改善
情シスへの問い合わせ削減において、社内FAQ(よくある質問と回答集)の充実は極めて効果的です。FAQを整備することで、社員は疑問が生じたときに自己解決しやすくなり、情シス担当者へ都度問い合わせる必要が減ります。ここでは社内FAQを作成・運用する上でのポイントを整理します。
- 頻出質問の洗い出し: まずは日々寄せられる問い合わせの中から「よくある質問」をリストアップします。緊急度や重要度の高いものから順に回答を用意しましょう。
- わかりやすい回答作成: 回答文は専門用語に頼らずユーザー目線で平易な表現にします。手順をステップごとに箇条書きしたり、画像キャプチャを使って視覚的に示すなど、誰が見ても理解できる内容を心がけます。
- 検索機能と分類の工夫: FAQページにはキーワード検索機能を持たせ、必要な情報を探しやすくします。「パスワード」「メール」などトピックごとに分類した目次やタグ付けを行い、利用者が目的の質問に素早く辿り着けるようにしましょう。
- 運用体制の確立と定期更新: FAQは一度作って終わりではなく、問い合わせ状況に応じた追加・更新を続けることが重要です。そのための運用体制(担当者の割当てや定期レビューのルール)をあらかじめ決めておきます。新しい質問が発生したら速やかにQ&Aを追加し、内容が古くなったものは更新・改善する運用を回します。
- 社内周知と活用促進: 社員に対してFAQの存在と利用方法を周知徹底しましょう。「まずFAQを見てから問い合わせる」というルールを社内ポリシーとしてアナウンスし、新入社員研修などでもFAQの場所や使い方を紹介します。また、FAQページへのアクセス解析を行い、閲覧数の多い質問や検索されているキーワードを分析してコンテンツ改善に活かすのも有効です。
これらのポイントを押さえることで、社内FAQが形骸化せず社員に長く活用される仕組みを作ることができます。「せっかく作ったのに誰も見てくれない」という事態を避けるため、ユーザー目線での継続的な改善が欠かせません。FAQが充実すれば、情シスへの問い合わせ対応工数を効率的に削減できる上、社員側も自己解決までの時間短縮が図れるという双方にメリットがあります。
チャットボット・AIアシスタントの活用
FAQと並んで、チャットボットによる問い合わせ対応の自動化も情シス業務効率化の強力な手段です。チャットボットとは、ユーザーからの質問に自動で応答する対話型システムのことで、近年はAI技術の進歩により高度な対応が可能になっています。情シス部門向けのチャットボットを導入すれば、パスワードリセット方法やプリンタ設定手順など定型的な質問に即座に回答でき、担当者の負担を大幅に軽減できます。例えば、「インターネットにつながらない時は?」といった問い合わせに対し、あらかじめ登録した手順をチャットボットが返答することで、ユーザーは待ち時間なく自己解決できます。
チャットボット導入のポイントは、FAQ上位の質問と回答をあらかじめ十分に学習させておくことです。頻出する問い合わせパターンを網羅するデータベースを用意し、シナリオに沿った回答を返せるよう設定します。近年話題の生成系AI(例:ChatGPT)を組み込んだチャットボットであれば、より柔軟な質問解釈や回答生成も期待できます。ただし、社内の機密データを扱う場合は情報漏えい対策(外部に学習内容を送信しないなど)を講じた専用環境で運用することが重要です。
Microsoft 365には標準で情シス向けチャットボット機能はありませんが、Power Virtual Agentsなど別サービスと連携しサードパーティ製ボットをSharePoint Onlineに埋め込むことが可能です。自社のIT環境に適したチャットボットを選定し、まずは回答しやすい範囲の質問から自動化してみるとよいでしょう。チャットボットが24時間対応のヘルプデスクとして機能すれば、情シス担当者は夜間や休日の呼び出し対応が減り、本来業務に集中できます。さらに、チャットボットの対話ログを分析すれば新たなユーザーニーズや課題の発見にもつながり、今後のITサービス改善に役立ます。
RPA・ITツールによる定型業務の自動化
情シス業務には、定期的・反復的で自動化しやすいタスクも多く存在します。そこで、RPA(Robotic Process Automation)ツールなどを活用して定型業務をソフトウェアロボットに代行させれば、生産性向上に大きく貢献します。たとえば、サーバやネットワーク機器のログ監視・障害検知、定例のシステム設定変更、週次・月次のレポート作成などはRPAに任せることでヒューマンエラーも減らしつつ自動処理できます。実際に「障害を検知したら自動で原因分析し最適な解決策を提示する」といった、AIを組み合わせた運用自動化の事例も登場しています。
また、クラウドサービスの活用も情シスの負担軽減につながります。自社サーバで運用していたメールやグループウェアをMicrosoft 365やGoogle Workspace等のクラウドに移行すれば、インフラ保守やアップデート作業はクラウドベンダー側で実施されるため、情シス担当者は日常の維持管理から解放されます。クラウドの利用により、スケーラビリティや災害対策もサービス側で担保されるため、結果的にシステム停止リスクの低減や安定運用にも寄与します。
その他にも、情シス業務効率化に役立つ各種ITツールの導入は積極的に検討すべきです。例えば:
- ITサービスマネジメント(ITSM)ツールやチケットシステム: 問い合わせ対応の進捗管理やナレッジ共有を体系化し、対応漏れ防止や分析に役立てる。
- 資産管理ツール: PCやソフトウェアライセンス等のIT資産を一元管理し、棚卸やセキュリティパッチ適用漏れを防ぐ。
- 監視ツール: ネットワークやサーバの稼働状況を常時監視し、異常を検知したら通知・自動復旧を行う。
- 開発支援・比較ツール: WinMergeのようにファイル差分を素早くチェックできるツールは、スクリプトや設定ファイルの変更点確認に役立ちます。
これらのツールを導入する際は、現場の情シス担当者のスキルとのマッチングも考慮しましょう。高度すぎるツールを入れても使いこなせなければ逆効果です。必要に応じてベンダーからのトレーニングを受ける、段階的に適用範囲を広げるなどして、無理なく人と技術のミスマッチを解消することがポイントです。
定型業務の自動化が進めば、情シス担当者はクリエイティブな問題解決や企画業務に注力できるようになります。人手に頼った作業から脱却し「攻めのIT業務」にシフトしていくことで、企業全体のIT利活用レベルが向上し、DXの推進にもつながるでしょう。
業務の外部委託(アウトソーシング)
情シス業務の一部をアウトソーシングすることも、有効な効率化策の一つです。社内で対応が難しい領域や慢性的な人手不足を補う手段として、外部の専門業者に業務委託することを検討します。アウトソーシングできる業務は多岐にわたり、ヘルプデスク対応、システム開発・運用保守、クラウドサービスの導入支援、ネットワーク構築管理などがあります。
例えば、日々の問い合わせ対応に追われているならヘルプデスク業務の委託を、自社にない専門知識が必要ならその分野(セキュリティ対策や高度インフラ設計など)だけ外部の力を借りる、といった形です。実際、中小企業の約58%が情シス人員増強のために外部パートナー活用を計画しているとの調査結果もあります。無理に自前で全てを抱え込むより、得意分野に専念しその他はアウトソースする方が結果的に効率的で高品質になるケースも少なくありません。
ただし、アウトソーシングを成功させるには委託先との綿密なコミュニケーションと目的の共有が欠かせません。任せっきりにせず、定期的な状況確認や情報共有の仕組みを設けることが重要です。サービスレベル合意(SLA)を結び、対応品質や速度に関するKPIを設定しておくと、期待値のズレも防げます。また、セキュリティ面の取り決め(機密情報の取り扱いやアクセス権限の管理など)も予め明確にしておきましょう。
アウトソーシングによって情シス担当者はコア業務に集中できますし、委託先から最新知見を得て社内にフィードバックする効果も期待できます。例えば、社内になかった専門スキルを持つ外部技術者と協働することで、チーム全体のスキルアップにつながるという副次的メリットもあります。近年では大企業でも積極的にアウトソーシングを活用し効率化を達成した例が報告されており、自社にとって最適な役割分担を模索することが重要です。
社員のITリテラシー向上と支援体制の強化
情シスの負担を根本的に減らすには、社内のITリテラシーを底上げすることも有効なアプローチです。社員一人ひとりのITスキルやセキュリティ意識が向上すれば、初歩的なトラブルでいちいち情シスを頼らず自力で対処できるケースが増えるからです。現場全体のITリテラシー向上は結果として会社全体の業務効率化にもつながるため、経営的にも推進価値の高い施策と言えます。
具体的には、定期的な社内IT研修の実施が効果的です。情シス担当者が中心となって初心者向けのIT勉強会を開催したり、オンライン学習サービスを導入して自己学習の機会を提供したりする方法があります。新入社員には入社時に基本的なITセキュリティ教育を行い、パスワード管理やフィッシング詐欺への対処など重要ポイントを周知徹底しましょう。
また、社内コミュニティやQ&Aフォーラムを活用して、社員同士が疑問を解決し合う文化を醸成するのも有効です。たとえば社内SNSやチャットツール上に「IT相談チャンネル」を設け、過去の質問と回答を検索できるようにすれば、情シスが回答するまでもなく同僚間で解決してしまうケースも出てきます。情シスはコミュニティをモニタリングし、誤った情報には適宜訂正・補足しつつ、ユーザー同士の自己解決を後押しすると良いでしょう。
重要なのは、社員がITサービスを主体的・積極的に使いこなす風土を作ることです。そのためには経営層から各現場リーダーまで巻き込んだ全社的な取り組みとして位置づけることがポイントになります。例えば「IT利活用アイデアコンテスト」を開いたり、DX推進の成功事例を社内報告するなど、社員の意識改革を促す施策も考えられます。
一方、セキュリティ意識の向上も情シス効率化には見逃せません。社員のセキュリティリテラシーが低いと、いくら情シスが繰り返し注意喚起しても社外で社用PCを無防備に使う等のリスク行動が無くならず、結果としてトラブル対応に情シスの手間が割かれます。重大なインシデント発生前に危機感を持ってもらうため、定期的なセキュリティ教育や疑似フィッシングメール訓練なども実施し、全社員でセキュリティ対策に取り組む体制を築きましょう。
経営層の理解と支援を得る
最後に、経営陣の理解と後押しを得ることも情シス業務効率化には不可欠です。どんな効率化施策も、経営層の協力なしには実行や定着が難しいからです。情シス部門が抱える課題やその解決策の提案について、経営陣に対して継続的に情報発信し、理解を促す努力をしましょう。
特に、効率化に必要なシステム導入やアウトソーシングにはコストが伴うため、予算承認を得るには経営層の納得が必要です。そのためには、情シス業務が非効率なままだと生じるリスク(例えばシステム障害による業務停止や顧客情報漏えいによる信用失墜のリスク)を定量的・具体的に示し、投資の必要性を訴えることが有効です。前述のような公式レポートのデータ(「2025年の崖」でDX遅延による損失が最大12兆円/年など)も引用しながら、危機感を共有しましょう。
また、効率化施策によって得られるメリットや期待効果を可視化したKPIを提示することも効果的です。例えば「FAQ整備によってヘルプデスクの月間問い合わせ件数を○%削減」「チャットボット導入で一次対応の初回解決率(FCR)を○%向上」「RPA活用で定例レポート作成工数を△時間削減」といった目標値を設定し、経営層と合意します。改善後は実績値を定期レポートし、効果をアピールすることでさらなる理解と支援を得られるでしょう。
重要なのは、経営層と情シスが同じ方向を向くことです。情シス効率化は単なるIT部門の問題ではなく、企業全体の生産性向上やリスク低減に直結する経営課題であることを示します。日頃から経営陣とはオープンなコミュニケーションを図り、情シスの取り組みを定例会議で報告したり、成功事例を共有したりする場を設けると良いでしょう。一度や二度説明しただけで理解を得るのは難しいかもしれませんが、根気強く情報発信を続けることが大切です。経営層の理解と支援が得られれば、情シス効率化への投資も前向きに検討され、組織全体でDXを推進する強力な追い風となるはずです。
情シス業務効率化の成功事例
最後に、ここまで紹介した施策を活用して情シス業務の効率化に成功した企業事例を紹介します。ある大手企業A社(製造業)では、社内で複数の業務システムを利用していました。しかし、社員ごとに各システムの認識が統一されておらず、「どのようなケースでどのシステムを使うべきか」が十分に周知されていませんでした。その結果、各種システムの使い方やトラブル対応方法に関する問い合わせが情シスに殺到し、日々の対応に追われて情シスは疲弊していました。また、周辺業務のトラブルシューティングにも追われ、本来取り組むべき重要プロジェクトが停滞する状況になっていたのです。
そこでA社では、社内IT情報をわかりやすく共有できる場を作ろうと、情シス部門主導で社内システムポータルサイトを立ち上げることになりました。具体的に以下のようなコンテンツや機能を整備し、社内のIT関連情報を一元化しました。
- システム最新情報の発信: 社内システムの稼働状況やメンテナンス情報について、緊急性や重要度に応じて優先順位をつけ、ひと目で重要度が分かる形式で掲示しました。例えば、は赤色のアイコン付きでトップに表示し、利用者が重要なお知らせを見逃さないよう工夫しています。
- お困りごとFAQガイド: 「よくある質問と回答」をシステムの種類や用途ごとに分類してFAQページにまとめ、問い合わせの多い質問事項と解決方法を整理して共有しました。これによりユーザー自身が自己解決できるケースが増え、問い合わせ対応に要する時間と工数が削減されました。実際、FAQ公開後は情シスへの問い合わせ件数が徐々に減少し、担当者の負担も軽減しています。
- システム利用マニュアル集の公開: 複数稼働している各業務システムについて、それぞれのユーザー向け利用マニュアルを識別しやすい形で集約し、ポータル上の「マニュアル倉庫」に格納しました。これにより社員が各システムの手順書を探し回る必要がなくなり、参照性・検索性が大幅に向上しました。
- SharePointのリスト機能活用: ポータル内のお知らせ情報はSharePoint Onlineのリスト機能で管理し、情シス担当者が素早く情報発信できるようにしました。各お知らせには種別(障害情報、メンテナンス予定、注意喚起など)ごとに色分けラベルを付与し、情報の重要度が一目で分かる表示としています。またFAQ情報も単一のリストでデータベース化し、運用負荷を下げつつ、ユーザーにはシステム別など条件ごとに絞り込んで表示できるビューを提供することで必要な情報にアクセスしやすくしました。これらの工夫により、情報検索性の確保と運用効率の両立を実現しています。
- チャットボットの導入: 外部で開発したAIチャットボットをポータルサイト内に埋め込み、簡単なレベルの質問や困りごとであれば情シスに問い合わせをしなくても即座に回答が得られるようにしました。例えば「メールの署名を変更したい」といった質問にはチャットボットが手順を案内してくれるため、情シスが対応しなくてもユーザーが解決できます。その結果、情シス・ユーザー双方にとって利便性が向上し、一次対応工数がさらに削減されました。
こうしたポータルサイトの整備により、A社では情シス部門の業務効率化と社内IT利用の活性化に大きな成果が出ました。以前は情シスに集中していた問い合わせの相当数がユーザー自身で解決されるようになり、情シス担当者は重要プロジェクトに充てられる時間が増えています。また、社内のIT関連情報がポータルに集約されたことで、情報共有のスピードが上がり組織全体のITリテラシーも向上したといいます。さらにポータル構築過程で情シス部門内の業務整理が進んだことで、担当者間の知識共有も深まり属人化リスクの低減にもつながりました。
この事例は、情シス自らがデジタル活用と情報共有の良いモデルケースを社内に示した点でも意義深いものです。情シス部門が率先して効率化ツールを導入し成果を出すことで、他部署にもDX推進の機運が波及し、全社的な業務改善の意識醸成につながる好循環が生まれました。
まとめ
情シス部門は企業のIT基盤を支え、さまざまなリスクから守る重要な部署です。しかし現状では、人手不足や対応範囲の広さから業務負担が大きく、本来注力すべき業務を効率的に行えていないケースが多く見られます。情シス業務が非効率であるということは、企業にとってもトラブルやインシデントが起こりやすい非常に危険な状態であることを理解する必要があります。
本記事で挙げたような情シス業務効率化の施策を実践すれば、担当者の負担軽減だけでなく社内全体に多くのメリットをもたらします。例えば、ヘルプデスク対応に追われていた情シス担当者がIT戦略にリソースを割けるようになれば、社内IT環境のアップデートが迅速に進み、全社の生産性向上につながります。また、情シスが本来の業務(システム運用やセキュリティ対策)に注力できれば、重大な業務停止や情報漏えいなどのリスク抑制にもつながります。さらに、属人化の解消や知識共有の促進によって、情シス不在時でも業務を継続できる体制を整えられるでしょう。
情シス部門自体が効率化・高度化を遂げれば、DX時代にふさわしい攻めのIT戦略を牽引できるようになります。既存業務の効率化で生まれた時間を新しい取り組みに充てることで、企業に新たな価値をもたらすイノベーション創出も可能となるでしょう。
一方で、情シス業務効率化を成功させるにはIT分野の知識だけでは不十分です。情報を整理分類してわかりやすく伝えるスキルや、現場の興味を引くコンテンツ発想などコミュニケーション面の工夫も必要になってきます。情シス部門内でのチームワーク強化はもちろん、社内の他部門や場合によっては社外の専門リソースもうまく活用しながら、ユーザーと情シス双方が一層業務効率化を果たせる情報環境の構築をぜひ実現していってください。