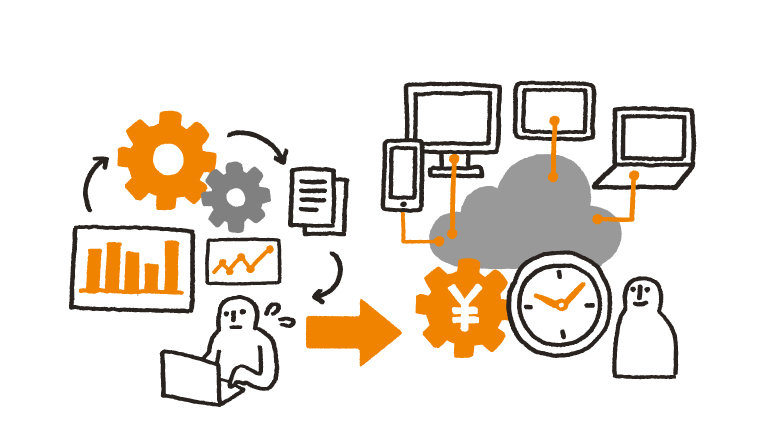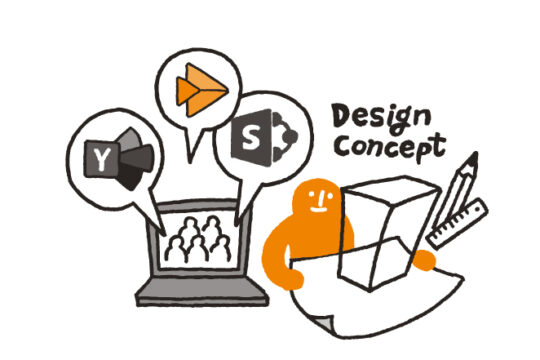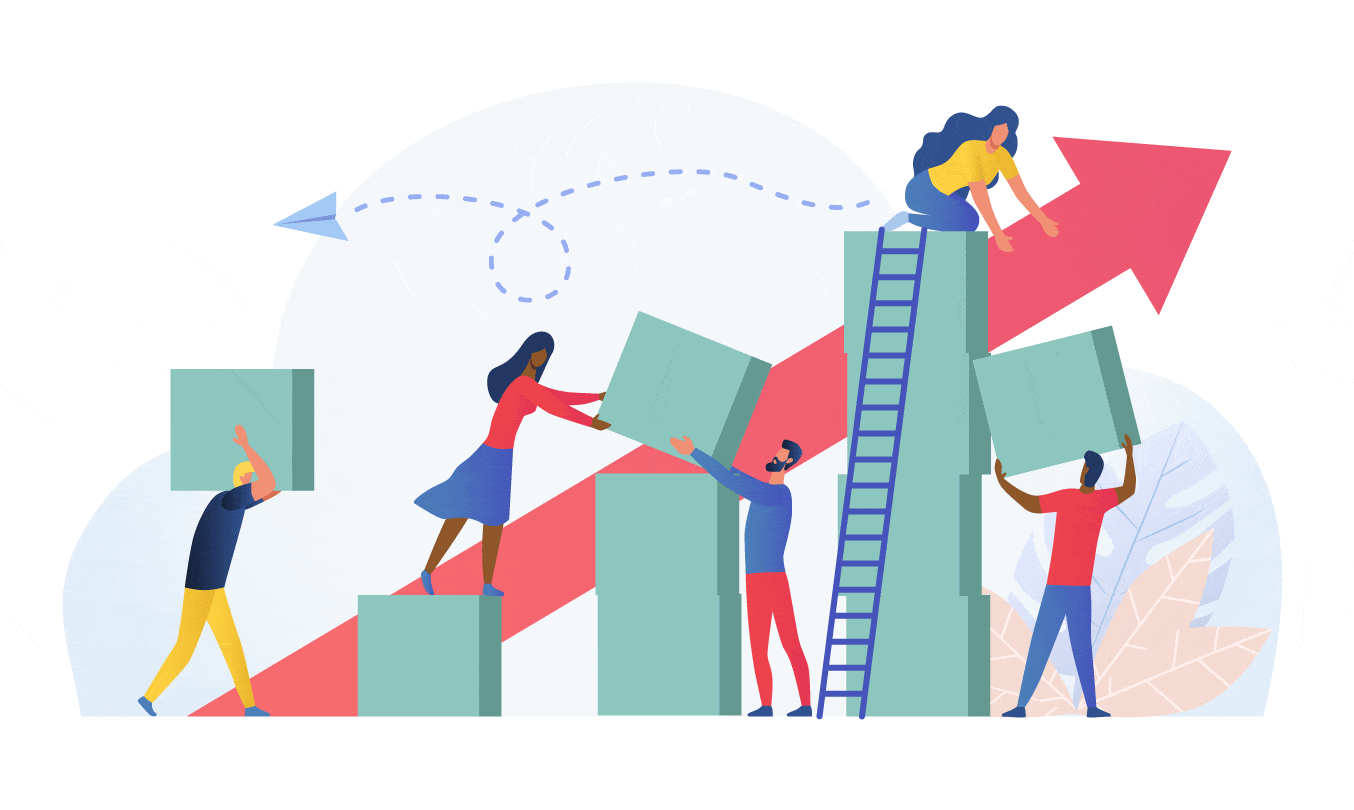Microsoft 365を活用して働き方改革!ツールや事例をご紹介
最終更新日:2020.05.27

目次
Office 365(現 Microsoft 365)は、働き方改革の推進に伴って昨今大きな注目を集めている、「デジタルワークプレイス」の機能を持ったグループウェアです。
デジタルワークプレイスとは、オンライン(クラウド)上にチャットやオンラインミーティング、スケジューラーやToDo、共有ファイルの管理や個人用ストレージなど、業務に必要不可欠なツールを一ヶ所に集約したプラットフォームです。
アクセスする場所が1つにまとまることで、業務効率および生産性に劇的な向上が見込まれるほか、インターネット環境さえあればパソコンに限らずどのデバイスでもアクセスし、作業ができます。
本記事では、Office 365(現 Microsoft 365)に搭載された主なツールについて解説するとともに、実際にOffice 365(現 Microsoft 365)を導入して働き方改革に成功した事例について紹介します。
Office 365(現 Microsoft 365)は働き方改革に劇的な効果
冒頭でも述べましたが、Office 365(現 Microsoft 365)は「時間や場所に縛られることなく自由に仕事ができる」という、働き方改革と極めて親和性の高いデジタルワークプレイスの機能を持つグループウェアです。
Office 365(現 Microsoft 365)の導入でいつでもどこでも安全に仕事が可能に
Office 365(現 Microsoft 365)はクラウド・マルチデバイス対応で、時間や場所を選ばずに、しかもセキュアな環境で仕事ができます。
オフィスワークに欠かせないWordやExcel、PowerPointのファイルは、パソコンだけでなくタブレットやスマートフォンでも編集できる上、複数の人が1つのファイルを同時に編集することも可能です(共同編集)。
そのほか、メーラーやスケジューラー、チャットやミーティング、社内ポータルの閲覧、共有ドキュメントのダウンロードや個人に割り当てられたストレージへのアクセスなどの機能が盛り込まれており、従業員はOffice 365(現 Microsoft 365)にアクセスするだけですべての業務を完結させられます。
また、Windowsの開発企業であるマイクロソフト社製ということで、セキュリティ面でも十分な対策が施されています。
きっかけは日本マイクロソフト社の働き方改革
日本マイクロソフト社は働き方改革を企業戦略とした「働き方改革 NEXT」を打ち出しており、Office 365(現 Microsoft 365)をデジタルワークプレイスとして自社活用しています。
同社は業務効率化や組織力強化の観点から「削減」「向上」「満足」の3軸で自社活用の効果を測定し、「削減」においては前年同月比で月あたりの就業日数を25.4%削減したほか、紙の印刷枚数を58.7%、電力消費量を23.1%削減することに成功しています。また、「向上」軸においては前年同月比で「30分会議(30分以内に終える会議)」の実施を46%、リモート会議実施を21%、社員間の1日あたりのデジタルコミュニケーションを10%増加させています。「満足」軸の効果はアンケート調査によって測定し、これらの自社実践の社内満足度が94%と非常に高く、エンゲージメントの向上にも貢献していると推測できます。
参考:(Microsoft「働き方改革 NEXT」https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/wsi)
Office 365(現 Microsoft 365)の主なアプリケーションとその役割をご紹介
Office 365(現 Microsoft 365)はデジタルワークプレイスとして以下のアプリケーションを1ヶ所に実装しています。
Office online
Office 365(現 Microsoft 365)は「Word」「Excel」「PowerPoint」「Outlook」のオンライン版を搭載しています。これまでのインストール版と異なるのは、マルチデバイス対応であるという点と、複数人によるリアルタイムでの共同編集に対応している点です。前者はパソコンだけでなくタブレットやスマートフォンでの利用を実現し、後者はより正確で効率的なチームでの編集作業を実現させました。
Yammer
Yammerは、Facebookに近い「企業内ソーシャルネットワークサービス」です。自分との関連性や興味・関心を基に情報を収集したり、新たな関係を築けるというSNSのメリットを社内にもたらすことができます。
業務に関係する知見やノウハウの集約、社員同士のゆるやかなつながり、社内イベントの開催告知など、企業によってさまざまな方法で活用されています。
Teams
TeamsはFacebook MessengerやLINEなどに代表されるチャットツールのビジネス版です。テキストチャットだけでなくビデオチャットも可能であり、大手企業ではWeb会議の代表的なツールとして利用されています。後述のOneDriveやSharePointとのシームレスな連携を実現しており、マイクロソフト社はこのTeamsを今後、デジタルワークプレイスの「入口」としての存在にしていく方針を示しています。なお、同社が提供する「Skype」も、将来的にはTeamsへ統合されていくとのことです。
OneDrive
GoogleドライブやDropboxと比肩するクラウドストレージサービスです。堅牢なセキュリティを担保しながら社内外でのデータの共有を実現し、クラウド上に保存されたファイルはマルチデバイスでの共同編集も可能です。
SharePoint Online
拡張性の高いドキュメント管理システムです。共有フォルダや階層構造、リンク集、告知など豊富に用意されたテンプレートとOffice 365(現 Microsoft 365)のアドオンツールなどを活用することで、社内ポータルサイトを制作・運用できます。
SharePointから他のアプリケーションをシームレスに起動できることも、デジタルワークプレイスとしての大きな強みです。
Power Automate
複数のアプリを連携させてその動作を自動化できるアプリケーションです。例えばOffice 365(現 Microsoft 365)のOutlookに届いたメールの添付ファイルをOneDriveに保存するといった連携が可能です。サードパーティーのアプリケーションにも対応しており、Outlookのカレンダーから Googleカレンダーへスケジュールを同期させることもできます。連携のためのテンプレートも膨大な数が用意されており、活用法はほぼ無限大といっても過言ではないでしょう。
PowerApps
プログラミング不要で業務アプリを作成できるツールです。作成したアプリはWindowsだけでなくMac環境のブラウザでも動作するほか、iOSとAndroidにも専用のモバイルアプリが用意されています。ただし、プログラミング不要ではあるものの、若干のITリテラシーとプログラミングの基礎知識が必要となる点にはご注意ください。
Office 365(現 Microsoft 365)で行った働き方改革の事例
ここからは、実際にOffice 365(現 Microsoft 365)をデジタルワークプレイスとして導入し、働き方改革を成功させた企業の事例を紹介します。
事例1:社内コミュニケーション変革
■実際のケース①
「社外のメンバーを含むプロジェクトで円滑かつ漏れなく情報を共有できるようにしたい」という社内の要望がありました。
<導入前>
メールのCC機能を利用して全メンバーに情報を共有していましたが、おのおのがメール内容を確認しているかどうかがわからない状態でした。
<導入後>
社内外の全メンバーをTeamsに招待し、「いいね」機能や「会話」機能を活用することで、それぞれが内容を確認しているかどうかを可視化できるようになり、正確でスピーディーなコミュケーションをプロジェクト内で実現できました。
■実際のケース②
「社内で非公開に進んでいるプロジェクトがあり、社内の関係者だけでコミュニケーションをとれるクローズドのツールがほしい」という要望がありました。
<導入前>
メンバー間での情報共有は基本的にミーティングの中だけで行われ、メールを送信する際には重要度を「高」にして注意喚起を促していました。書類の保管や管理にも細心の注意を払い、何かひとつの行動をおこすにもストレスが絶えない状態となっていました。
<導入後>
強固なセキュリティが確保されたTeamsの「プライベートグループ」に関係者を招待し、Teamsの中でメッセージの送受信やチャット、Office資料の共有を行うことで、ストレスが大幅に低減されました。
また副次的な効果として、Office onlineでは資料のバージョン管理をする必要がなくなり、プロジェクトのスムーズな進行にも大きく寄与しました。
事例2:事業継続性・業務効率化
■実際のケース①
私用のため休暇をとり在宅していた社員が、急を要する社内ミーティングに参加しなければならなくなったというケースがありました。
<導入前>
ミーティングに参加するためだけに1時間かけて出社し、ミーティング後にまた1時間かけて自宅に戻ることになり、当該社員に私用の時間を調整させてしまいました。
<導入後>
Teamsのビデオチャットによって、出社することなく自宅からミーティングに参加してもらえるようになりました。必要な資料はTeamsによってあらかじめ共有できるようになったため、事前準備が必要なミーティングも支障なく進められ、社員に負担を強いることもなくなりました。
■実際のケース②
オフィスと離れた場所で仕事をしている社員に指示をする際、複雑な内容を伝えることが困難で業務に支障が起きていました。
<導入前>
他の社員と同様にメールと電話でやりとりをしていましたが、やはり指示がうまく伝わらず、実務が滞ったほか、チーム内の人間関係がギスギスしたり社員をイライラさせたりといったコミュニケーション不全が生じていました。
<導入後>
Teamsのビデオチャットを利用し、複雑な内容の指示をする際は資料や画面の共有によりうまくお互いの認識を合わせることができ、業務が遅滞なく正確に遂行されるようになりました。また、人間関係の不和も生じなくなりました。
事例3:デジタルトランスフォーメーション/デジタライゼーション推進
実際のケース
社内の集合研修において、研修を行うこと自体が目的になってしまい、参加者の満足度はそれなりに高いものの、効果がその場限りになってしまっていました。
<導入前>
該当者を集めて1日〜3日間の短期間で集合研修を行っていましたが、詰め込みすぎて知識の定着率が低く、実務に応用できていないといった状況が見受けられました。
<導入後>
研修期間を半年に延長し、研修と課題をオンライン上でマイクロサイズに分割し、任意のタイミングで受講できるようにしました。
加えて、SharePoint Online上に「グループコミュニティ」を設置し、課題の提出や、研修の内容を実践するためのコミュニケーション、理解促進のための追加情報の提供をそこで行うようにしました。
さらにオンラインの研修をマルチデバイス化してスマートフォンでも受講できるようにしたほか、学習履歴の記録や達成した研修の認定証贈呈などの施策も追加で実施しました。
社員からは、「1回の受講が短いので集中力が保てる」「実務に生かすためのディスカッションをSharePoint上でできたので、すぐに現場で使えた」「まわりの人の受講認定証を確認できるため、自分もやらなければという気になった」という感想が多く、経営層にも納得してもらえる研修になりました。
Office 365(現 Microsoft 365)をデジタルワークプレイスとして導入・活用する際のポイント
Office 365(現 Microsoft 365)は、企業規模にかかわらず、働き方改革を推進するにあたってどの企業においても導入を検討すべき優れたサービスです。最後に、Office 365(現 Microsoft 365)を導入してデジタルワークプレイスを企業内で活用する際のポイントを紹介します。
企業ビジョンとの整合性をとる
デジタルワークプレイスを活用して実現したい業務変革が、会社の掲げる理念やビジョン、経営層の方針に即していることを必ず確認しましょう。
「業務を効率化しなければ」「従業員の満足度を高めなければ」などといったミクロな視点ではなく、会社という組織が発展するためにデジタルワークプレイスをどのように活用できるのかというマクロな視点での導入目的・活用方法を戦略的にストーリー化しておくことが必要です。
活用のメリットを従業員にも提供する
「会社のために」というストーリーが前提としてあるものの、実際に利用する現場にも明確なメリットがないと、デメリットばかりが指摘され、活用頻度はどんどん低下していくでしょう。そして導入の経緯や社員へのメリットは、「使えばわかる」ではなく、クリアに説明できることが不可欠です。
もし従業員へのメリットよりも会社都合のほうが大きいのであれば、利用に応じた景品など、具体的な恩恵を用意する必要もあります。
現場の課題解決からスタートさせる
特に大手企業においては、目的より手段がとかく優先しがちです。すなわち、手段であるOffice 365(現 Microsoft 365)の導入が、実現したい目的が定まる前にあらかじめ決まっている状態です。これはトップダウンの意思決定が強い企業においてしばしば陥りがちなケースです。
最初に現場スタッフの困りごとや課題、手の届いていない部分をヒアリングし、Office 365(現 Microsoft 365)を活用することでどのようにそれらを解決できるかをきちんと設計しておくことが重要といえるでしょう。
限られた部署・事業部単位でスタートさせる
デジタルワークプレイスに限った話ではありませんが、業務フローを大きく変えうる規模の施策を最初から広範囲でスタートすることは、極めて高いリスクにつながります。
まずは部署単位、事業部単位でトライアル的に導入し、十分な活用実績を上げたのちに他部署、他事業部へと徐々に展開していくことが、デジタルワークプレイス導入における成功の鍵となります。
リスクマネジメントを徹底する
デジタルワークプレイスを導入することで、社内の既存ルールやセキュリティポリシーに抵触しないかどうか、関係各所に確認が必要です。従業員が安心して活用できるよう、想定されるリスク要因はすべて洗い出した上で検討し、利用方法をきちんとルール化しておきましょう。
デジタルワークプレイス活用時の資源管理を検討する
デジタルワークプレイスの導入によって事例のようにテレワークなども実現できますが、その際は従業員宅にワークスペースとしての環境が整っているかなど、必要なリソースとその負担についてもあらかじめ想定し、手配を検討する必要があります。在宅勤務であれば、インターネット回線や備品などが考えられます。
導入後も継続して効果測定と品質管理を行う
デジタルワークプレイス導入後も、それが効果的に機能しているかを継続的に測定し、常に改善を図ることが重要です。必要に応じて現場からの問い合わせを受け付ける事務局を設置するという手段も有効でしょう。
まとめ
普段使うツールが一ヶ所に集約され、そこにアクセスしさえすれば場所や時間を問わずすべての業務が行えるデジタルワークプレイスは、今後の働き方を大きく変える可能性を秘めたサービスです。しかし、働き方改革が一朝一夕で実現できるものではないように、どれだけ便利なツールであってもただ導入しただけでは活用にはつながりません。導入にあたっては関係各所の理解と協力を得るようにしましょう。
また、利用できるツールの機能についてしっかりと把握しておくことも重要なポイントです。それらが現場におけるどんな課題をどのように解決するものかを想定しておかないと、どんなに便利なツールでも利用されることはありません。
デジタルワークプレイスは非常に有用ですが、きちんと目的を定めないと導入の意義を失ってしまうということを念頭に置いた上で、慎重に進めるようにしてください。
関連サービス