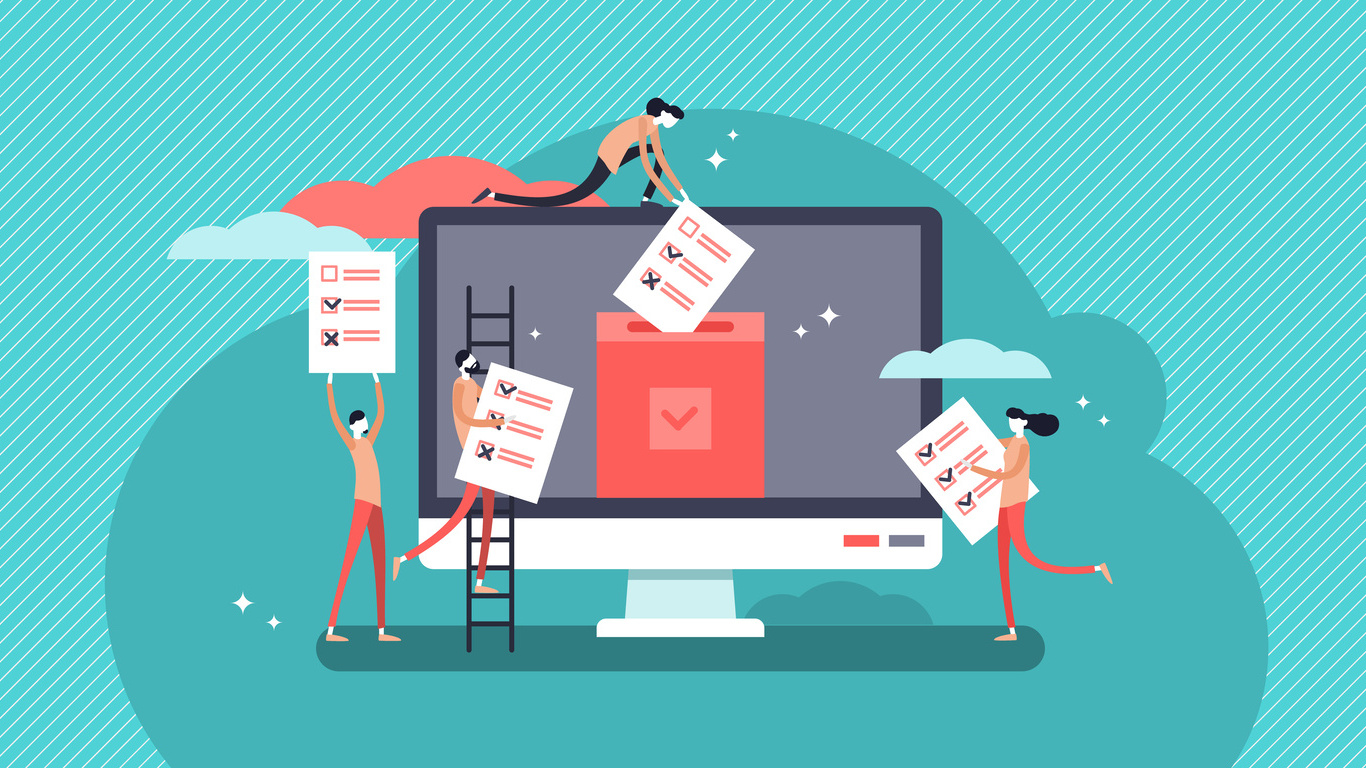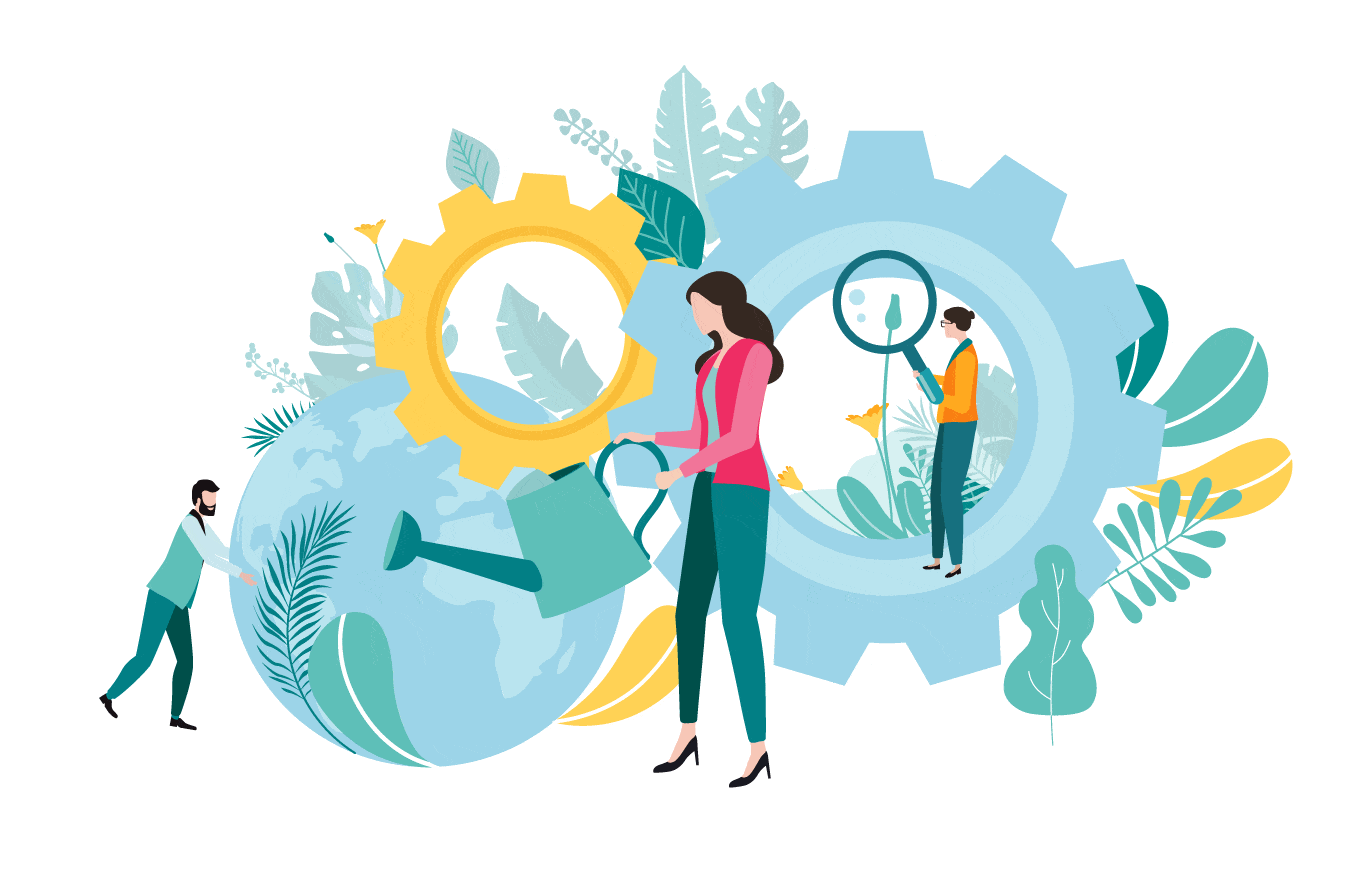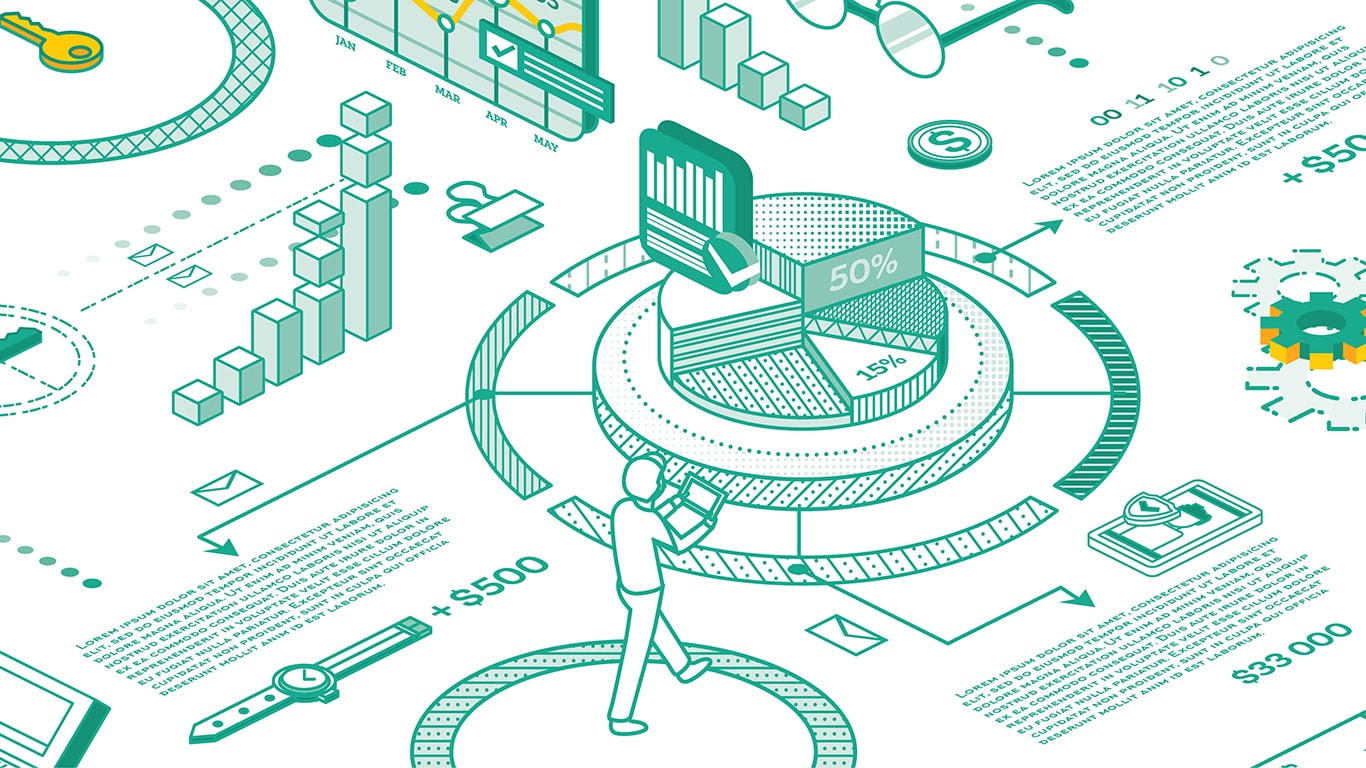大企業のDX推進者必見!システム導入成功の実践ポイント
最終更新日:2025.07.16

目次
自社のDXを加速させようとMicrosoft 365やERPを導入したものの、現場で使われず効果が出ない。そんな悩みを抱える企業は少なくありません。
実際、ある調査ではシステム導入プロジェクトが当初の品質・予算・納期すべてを満たし「成功」と言えるケースは全体の約半数にとどまったと報告されています。
経営層はデジタルツール活用への期待が高い一方で、導入したシステムを使いこなせずDXが思うように成果につながっていない企業も多いのが実情です。
本記事では、ITシステム導入が失敗に終わる原因とその対策を実務的・戦略的な視点から整理し、「システム導入」を成功させるために部門長が押さえるべきポイントを解説します。
ITシステム導入が失敗する二つの原因
戦略部門と現場の”期待値ギャップ”
大きな予算を投じて新システムを導入しても、「思ったほど業務効率化できない」「現場が使ってくれない」といった声が上がる背景には、経営層・企画部門と現場従業員との視点のズレがあります。
経営企画や情報システムなどの戦略部門は、全社的な業務最適化やセキュリティ強化などを狙いに掲げ、複数の業務システムを統合するERP導入など大胆なDX施策を推進します。
一方で現場社員の関心事は「新しいシステムで自分の仕事がどれだけ楽になるか」という点です。
現状の業務フローそのものは維持したまま自動化されることを期待しがちですが、実際には新システム導入によって入力方法やプロセスが変わり、慣れるまで一時的に現場の負担増となるケースも少なくありません。
このように戦略目標と現場メリットの乖離があるまま導入を進めると、利用定着せず失敗に終わります。
また、経営トップの号令で急いでDXに取り組む中で、システム導入自体が目的化してしまうことも大きな落とし穴です。
経営陣にとって新システム導入はDX実現の手段ですが、現場に十分説明せずに「とにかく導入しろ」と押し進めれば反発を招きます。
システム導入はゴールではなく手段であるにもかかわらず、それ自体が社内プロジェクトの目的になってしまうと、本来目指す業務改革の視点が抜け落ちてしまいます。
その結果、新しいITツールを入れただけでビジネスモデルや企業風土の変革に至らず、DXの本来の効果が得られないのです。
現状業務と既存ツールの把握不足
もう一つの原因は、自社の業務実態をIT部門が十分に理解していないことです。
各部署でどんな業務フローがあり、どのようなITツールが使われているか、その目的・効果やコストまで全社的に把握できていない企業は少なくありません。
たとえば現場ではExcelや紙で回している業務が多数あるのに、その課題を精査しないまま「最新の○○システムを導入すれば解決できるはずだ」という具合にツール先行で進めてしまうケースです。
社内のIT資産を棚卸しせず、新システム導入後にどんな業務改善が見込めるのか各部署へ具体的に示せなければ、現場は導入の意義を感じられません。
そのため「○○社の宣伝文句」頼みの画一的な社内告知になり、自社にとって本当に必要なシステムか現場に伝わらないまま導入だけが通知されてしまいます。
この背景には、人材面での課題もあります。 IPA『DX白書 2021』の調査によれば、日本企業の約9割がIT人材の不足を感じている状況です。
専門知識を持つ情報システム部員が足りず、限られたメンバーで社内のあらゆるITツールを管理・支援しなければならない”ひとり情シス”状態の企業も多いのです。
その結果、新規システムの導入検討にあたり現場の業務調査に手が回らず、自社に合わないシステムを選定してしまうリスクが高まります。
流行のツールや他社事例だけを参考に導入しても、自社の業務フローや規模に適合しなければ逆効果です。
必要な機能を明確に洗い出し、関係部門の声を反映した慎重なツール選定が重要だといえるでしょう。
現場を巻き込むことが導入成功の鍵
システム導入プロジェクトでは、現場の業務をどれだけ理解し、巻き込めるかが成功の分かれ目になります。
新システムの主な利用者である各事業部門の協力なしに、業務プロセスの変化や期待効果を正しく見積もることはできません。
導入目的に合ったシステム選定や新業務設計のためにも、戦略部門と各現場部門が密接に連携して進める必要があります。
しかし現実には、事前ヒアリングを十分行わずに導入を決めてしまう例も散見されます。
とりわけ利用範囲が全社横断となるグループウェア(たとえばMicrosoft 365など)の場合、「特定部門のシステムではない」ために誰からヒアリングすべきか定まらず、IT部門だけで進めてしまうことが多いようです。
その結果、導入後に各部署で「使いにくい」「現場のニーズに合っていない」と不評を買い、せっかくのシステムが十分活用されない事態に陥ります。
こうした失敗を防ぐには、早い段階で現場の声を吸い上げる仕組みが欠かせません。
実際にその業務を行う担当者の課題意識や要望を把握しておくことで、導入後の定着率が大きく左右されます。
現場目線で「使いやすいか」という視点はベンダーや経営層には見えにくいため、自社内で丁寧に確認しておくことが重要です。
現場を巻き込む際のポイントは、単に要望を聞くだけでなく協力をお願いする姿勢を示すことです。
IT部門の中には「要望を聞くと対応せざるを得なくなるので最初から聞かない」という声もありますが、その姿勢では導入後に利用が進まず結局困るのは自分たちです。
そうではなく、「新システム導入で一時的に業務プロセスが変わり負担が増えるかもしれません。
しかし最終的には大きなメリットが得られるので一緒に頑張りましょう」と現場に前向きな参加意識を促すことが大切です。
現場との協働体制を築くことで、導入前の不安も汲み取りやすくなり、後述するチェンジマネジメントの土台にもなります。
システム導入はゴールではない:DX実現の視点を持つ
経営陣がITシステム導入に期待するのは「業務のデジタル変革(DX)の実現」です。
DXとは単なる業務のデジタル化ではなく、デジタル技術によるビジネスモデルや企業文化の変革
まで含む大きな取り組みです。したがって、新システムを入れれば即DXが達成できるわけではありません。
IT部門は「新しいシステムを導入すること」が目的になりがちですが、その先にある業務プロセスや働き方の変革まで見据えなければDXの成果は出ないと認識すべきです。
たとえば、従来Excelで個別管理していた業務をERPで統合すれば、経営データの一元管理やリアルタイムな数値把握が可能になります。
しかし本当にDXを成功させるには、単にデータ管理が便利になるだけでなく、そのデータを活用した経営判断の質向上や新たなビジネス価値の創出につなげる必要があります。
つまりシステム導入はDX実現のための一手段であり、真のゴールは企業の競争力強化につながる業務改革です。
ところが実際には、「ひとまずシステムを導入して様子を見る」という姿勢でプロジェクトが進み、肝心の業務プロセス改革や社員の意識改革が伴わないケースがあります。
これではDXの看板を掲げても中身が伴わず、現場からも「結局何が変わったのか分からない」と不満が出てしまいます。
そうならないために、新システム導入を企業戦略に沿ったストーリーとして語り、従業員一人ひとりに自分事として理解してもらうことが重要です。
たとえば「このシステム導入は、○○な会社を目指すための第一歩です。そのために皆さんには△△の業務で新しいやり方にチャレンジしてほしい」といった形で、導入の目的と期待する変化を具体的に伝えます。
その際、各部門・職種ごとにメリットや役割を噛み砕いて示す高度なコミュニケーション力も求められます。
会社のこれまでの歩みや業務改善の歴史を踏まえ、新システムがもたらす新たな価値を分かりやすく翻訳して共有する作業です。
これができる人材がいなければDXはなかなか前進しないでしょう。
システム導入=ゴールではなくスタートであると捉え、導入後も継続して業務の最適化サイクルを回していく視点を持ちましょう。
新システム導入を成功させるチェンジマネジメント
こうした全社変革まで見据えたシステム導入を成し遂げるには、「チェンジマネジメント」の視点が不可欠です。
チェンジマネジメントとは、組織が新たな変化(こ
こでは新システムの導入)に適応できるよう、人とプロセスの側面から変革を推進する手法です。
日本企業では従来、IT部門が技術面を中心に導入プロジェクトを進めてきました。
しかし、各事業部門とのコミュニケーションや社内啓発には、IT知識だけでなく内部広報・人材育成などのノウハウが求められます。
そのため、IT部門単独ではなく社内のインターナルコミュニケーション担当部署や外部専門家と連携して進めることが重要になってきます。
海外では「チェンジ・コミュニケーション」という専門領域が発達しており、「Head of Digital Communication」や「Digital Community Manager」といった役職の下、外部のコミュニケーション会社やシステムベンダーとタッグを組んでDXを成功させる事例も報告されています。
日本企業でも、大規模システム(利用者数が多いシステム)の導入成功例を調べると、最初は小さなグループでパイロット運用を開始し、そこで出た成功・失敗を踏まえて改善策を打ち出した上で、段階的に展開範囲を広げていく方法が多く取られています。
重要なのは、これらが導入初期から周到にユーザーエクスペリエンスを設計している点です。
決していきなり全社一斉展開して「あとは現場任せ」にしないというわけです。
システム導入成功のロードマップ
実際、システム導入を成功させるには以下のようなステップを丁寧に踏むことが効果的です。
現状業務の課題整理
最初に自社の業務プロセスを棚卸しし、時間がかかっている作業やミスの多い工程、属人化している業務などを洗い出します。
これにより「何のためにシステムを導入するのか」という目的が明確になり、必要な機能要件も見えてきます。
業務フローを可視化しボトルネックを定量・定性的に把握することが重要です。
関係者ヒアリングと合意形成
経営層や情シス部門だけでなく、現場のスタッフにも早い段階でヒアリングを行いましょう。
現場のニーズを把握し要件定義に反映することで、導入後の利用定着率が高まります。
部門横断のプロジェクト体制を組み、各部署の代表者をプロジェクトメンバーに加えるのも有効です。
ツール選定とベンダー比較
要求を満たすシステムの候補を市場から探し、複数ベンダーの提案を比較検討します。
価格や機能はもちろん、操作性やサポート体制、自社システムとの連携性、クラウド対応の有無などを総合的に評価します。
他社導入事例も参考にしつつ、自社の業務規模・ITリテラシーに合ったツールを選びましょう。
「相見積もり」で複数ベンダーから情報を得ることも、失敗リスクを減らすポイントです。
スモールスタートで試行導入
いきなり全社展開せず、まずは一部部署や限られた業務範囲で試験導入してみます。
パイロット運用によって、運用上の課題や想定外のトラブルを事前に把握でき、リスクを最小化できます。
試行期間中に利用状況をモニタリングし、ユーザーのフィードバックを集めて改善したうえで本格導入へ進めるのが成功への近道です。
定着促進と運用体制の整備
導入後こそ気を抜かず、「定着フェーズ」の支援策を講じます。
マニュアル整備、操作研修の実施、社内FAQサイトの用意、サポート窓口の設置など、現場が安心して使い続けられる環境を整えましょう。
また、運用ルールの策定(アクセス権管理やログ監視、データ保護など)も不可欠です。
定期的に活用状況をレビューし、機能追加や業務改善のPDCAサイクルを回すことで、システムは徐々に社内に根付き効果を発揮していきます。
以上のステップを計画的に実行することで、「導入して終わり」ではなく導入後の定着・活用まで含めたチェンジマネジメントが実現できます。
抵抗勢力への対処:現場に根付かせるコミュニケーション
どんな優れたITシステムも、導入後に社員に使ってもらえなければ効果はゼロです。
新しいデジタルツールに対しては、多かれ少なかれ誰もが戸惑いや抵抗感を持つものです。
中には「使い方がわからない」「今までのやり方の方が楽だ」という理由で、せっかく導入したシステムの利用を諦めてしまう社員もいるでしょう。
こうした抵抗勢力にどう向き合うかが、導入プロジェクトの成否を大きく左右します。
まず重要なのは、社員との信頼関係(トラスト)を日頃から築いておくことです。
会社が大きな変化を進めようとするとき、従業員エンゲージメントの高さが協力姿勢に直結します。
「この変革を乗り越えないと会社も自分も生き残れない」という認識を社員一人ひとりが持てていれば、一時的な業務の負担増も前向きに受け止め、変革推進側に協力的になってくれるでしょう。
逆に、自分の目の前の業務しか見えていない社員にとっては、数年先の会社存続より目前の負担増の方が拒否反応が強く出てしまいます。
その意味で、日頃から経営の方向性や危機感を共有し、社員が自分事として捉えられる社内コミュニケーションを行っておくことが土台となります。
実際に導入段階で抵抗に直面した場合は、伴走型のコミュニケーションで乗り越えることが有効です。
筆者がよく提唱するのは「そばで、一緒に」というアプローチです。
たとえば高齢の親にネットショッピングの操作を教える際、URLを送って放置するのではなく、隣に座って実際の操作を見せながら「ここをクリックして…」と付き添うと効果的です。
職場においても同様に、現場で直接寄り添ってサポートするハンズオンの研修など”プッシュ型”の施策を組み合わせると、従業員のデジタルアレルギーは格段に和らぎます。
新人研修でOJTを行うように、システム導入時も最初はマンツーマンや少人数の対面サポートを充実させるのです。
もちろんマニュアル整備やヘルプページ公開といった”プル型”の情報提供も必要ですが、初期段階ではそれだけでは不十分です。
とくにデジタルに不慣れな人ほど、自分から積極的にマニュアルを読むことは期待できません。
押し付けではなく隣に寄り添う支援があって初めて、新しいツールが「自分にも使えるかも」と心理的ハードルを下げることができます。
こうした成功体験を持った社員が増えれば、現場全体のデジタルシフトは加速していきます。
最近では、社員のシステム習熟を支援するデジタル・アダプション・プラットフォーム(DAP)というツールも注目されています。
DAPを導入すると、ソフトウェアの画面上にガイドやチュートリアルを表示でき、操作方法を対話的にナビゲートしてくれます。
いわばデジタルの「そばで、一緒に」教える仕組みであり、マニュアルを読まなくても画面の指示通りに操作する中で学習が進むため、導入直後から現場での活用を促進できます。
現場のITリテラシーに不安がある場合は、こうした最新ツールの活用も検討すると良いでしょう。
最後に、導入後も継続的なコミュニケーションを怠らないことが肝要です。
新システムの便利な活用事例を社内報やイントラブログで共有したり、一定期間ごとにアンケートを取って改善要求を吸い上げたりするなど、利用促進のプロモーションとフィードバック循環を回していきます。
新しいITシステムの導入を「会社から従業員への押し付け」で終わらせず、会社の生き残りをかけた変革への参加へと意識づけることが大切です。
そのためにはIT部門や経営企画部門が各事業部と協力し、社内広報部門や外部専門家の力も借りながら、ヒアリングから導入後の定着支援まで一貫して取り組む必要があります。
まとめ
システム導入は単なるITプロジェクトではなく、企業の未来を左右するチェンジマネジメントそのものです。
貴社で「せっかく導入したシステムが活用されていない」「DX推進が社内に浸透しない」といったお悩みがありましたら、ぜひ私たちソフィアにご相談ください。
ソフィアはインターナルコミュニケーションの専門家集団として、貴社の課題に即したチェンジマネジメント支援や導入推進施策をご提案いたします。
新しいITシステムを真に活かし、組織の変革と成長へつなげるお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
関連サービス