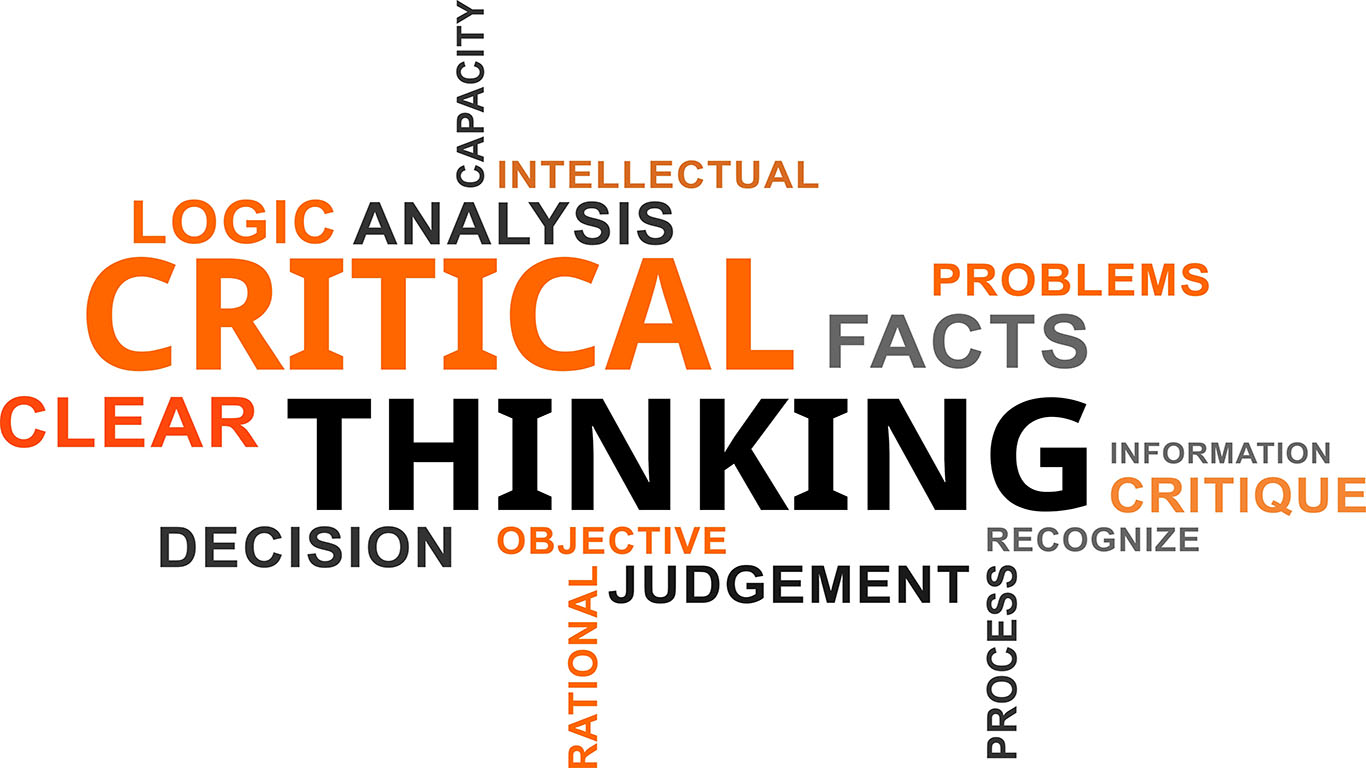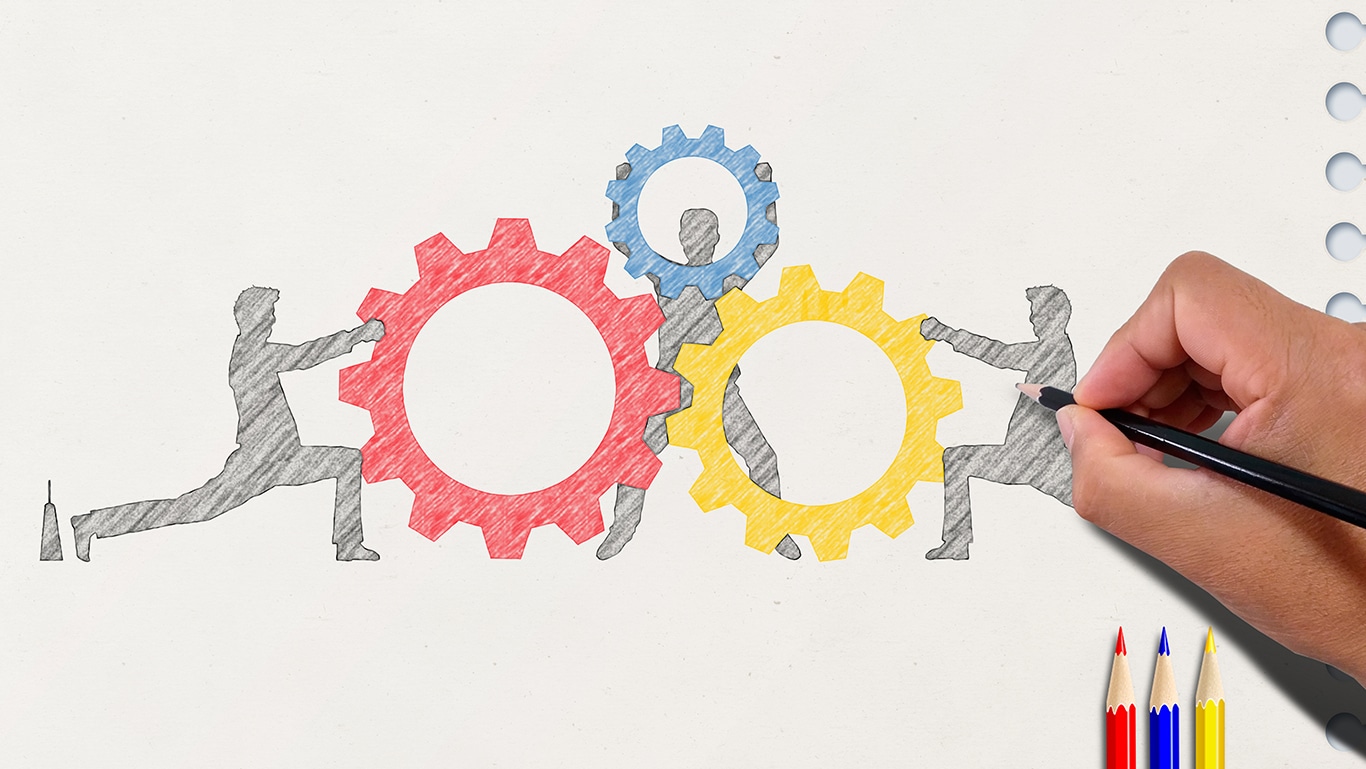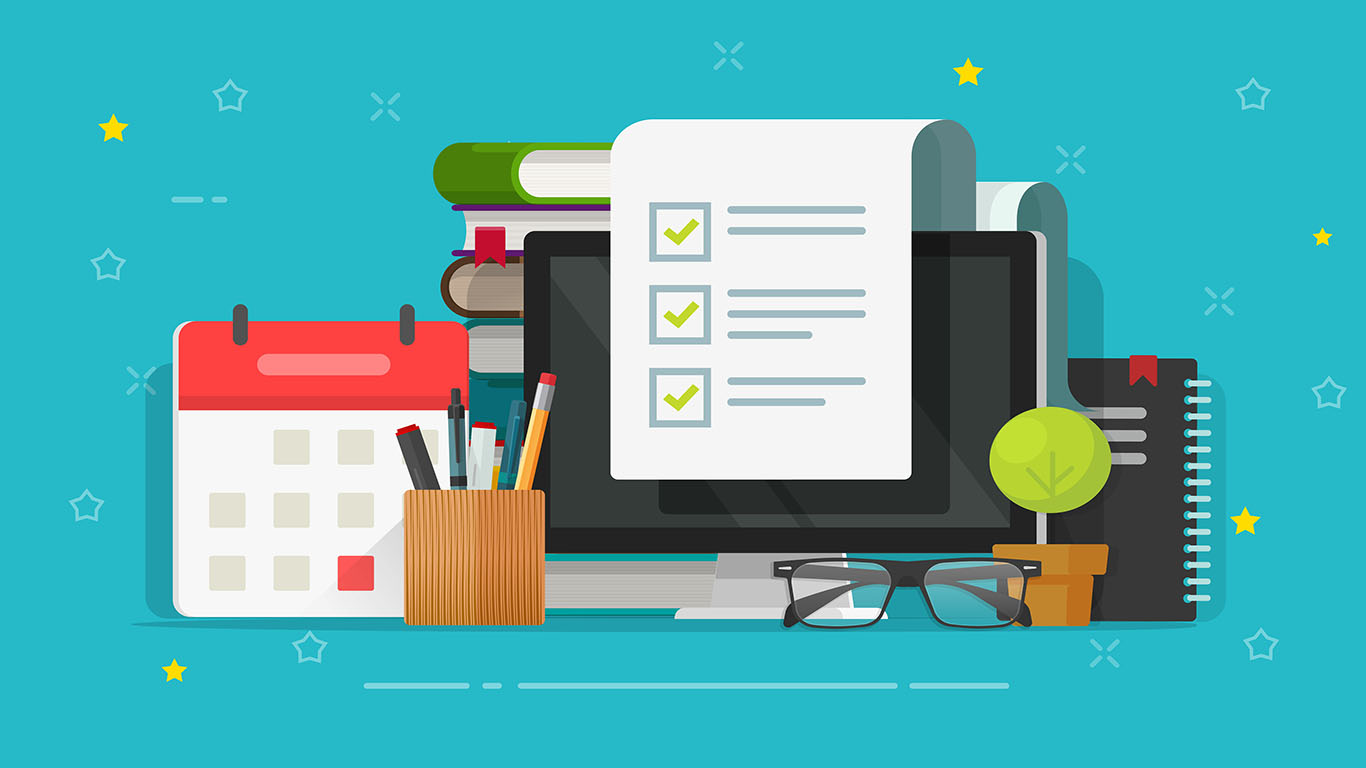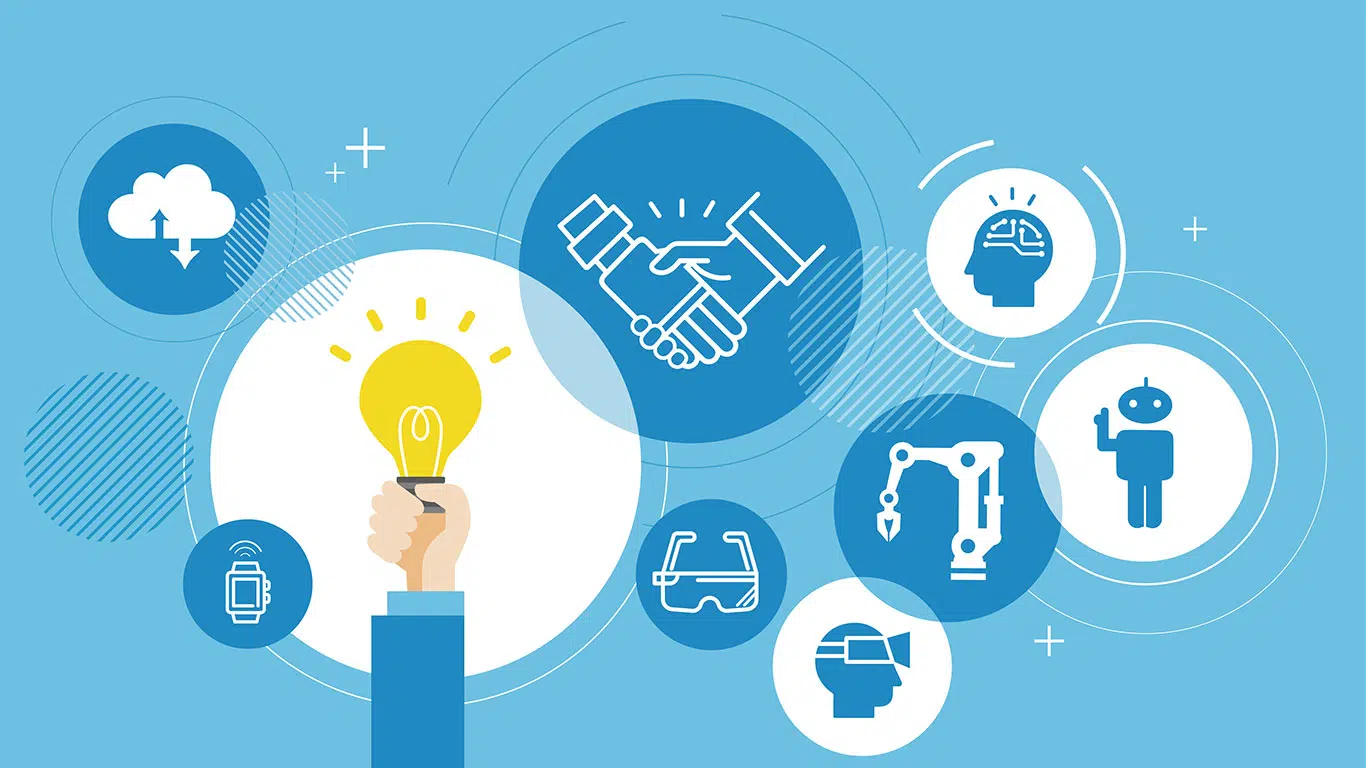新規事業の進め方とは?成功率を上げるポートフォリオ戦略【徹底解説】
最終更新日:2025.07.09

目次
既存事業には詳しいけれど、新規事業の立ち上げ方がわからない…そのような悩みを抱える企業は少なくありません。実際、新規事業の成功率は約3割と低く、一筋縄ではいかないのが現実です。しかし、変化の激しい現代において、新規事業開発は企業の将来を左右する重要な挑戦ではないでしょうか。
そこで本記事では、新規事業を成功に導くための推進プロセスとポイントを、豊富なデータや事例を交えてわかりやすく解説していきます。
新規事業とは何か?なぜ今新規事業が必要なのか
新規事業とは、企業が既存のビジネスモデルや事業領域にとらわれず、新たに立ち上げる事業のことです。平たく言えば、企業にとって「第二の創業」ともいえる大胆な挑戦であり、企業成長や生き残りのための重要戦略に位置付けられています。
例えば、これまで扱っていなかった新しい製品・サービスを開発したり、これまでとは異なる市場に参入したりする取り組みが該当します。既存のビジネスとは別の領域に踏み出すことを、一度は検討されたことがあるのではないでしょうか。
では、なぜこれほど新規事業が重要視されるのでしょうか。その背景には、技術革新や市場変化のスピードが増し、企業の平均寿命が短くなっている現実があります。実際、1960年代には50~60年あった米国大企業の平均寿命が、2010年以降では約18年にまで短縮しているとの指摘もあります。
既存事業だけに安住していては生き残れない時代となり、「イノベーションを起こし続けないと企業は生き残れない」という危機感が広がっているのです。さらに近年では、新型コロナ感染症の拡大やデジタル化の進展により市場環境が激変し、従来のビジネスモデルでは対応できない新たなニーズが次々と生まれています。
こうした変化に柔軟に適応し、新たな収益源を育てる新規事業開発こそが企業の生命線と考えられるのではないでしょうか。また日本政府もスタートアップ支援策を打ち出すなど、新規事業創出を後押ししています。大企業でも社内ベンチャー制度の導入やオープンイノベーションの活発化など、新規事業に挑戦する動きが広がっています。
まとめると、新規事業とは「企業が未来の成長のために挑む新しい事業領域・ビジネスモデル」であり、その重要性は時代とともに増していると言えるでしょう。変化の激しい現代で持続的成長を遂げるには、既存事業の延長線上に無い新たな価値を創造し続ける姿勢が不可欠なのです。
新規事業の成功率はどのくらい?現状と低さの理由
新規事業の必要性は高い一方で、その成功率は決して高くありません。国内外の調査によれば、大企業における新規事業の成功率はおおむね2~4割程度にとどまるとされています。
裏を返せば、半数以上、多くて8割近くの新規事業は思うような成果を上げられていないというのが現実です。例えば日本の中小企業白書2017年版の分析では、新規事業に「成功した」と回答した企業は約3割、「成功しなかった(またはまだわからない)」が7割に上るとのデータがあります。
また、社内公募のアイデアから事業化・黒字化に至る割合はわずか0.3%程度、まさに「新規事業の成功確率は千に三つ」とも形容されます。リクルート社の社内新規事業プログラム「Ring」では応募アイデアのうち事業化に進むのが2%、その中で黒字化できるのは15%ほど(1000件の応募で黒字化3件)と報告されており、大企業であっても新規事業で黒字を生み出すのは極めて狭き門なのです。
では、なぜここまで新規事業の成功率は低いのでしょうか。主な理由として、市場や顧客ニーズの見誤り、アイデアの質の問題、社内の推進体制不足などが挙げられます。実際に2023年に実施された調査でも、新規事業が「成功に至らなかった」原因として以下のような点が上位に挙がりました。
- アイデアの質の問題(21.6%)
– 市場ニーズに合致していない、独自性・優位性に欠けるアイデアでは成功は難しいでしょう - 社内調整の不備(20.5%)
– 関係部署や経営陣との連携・合意形成が不十分で、必要なリソースが確保できず頓挫 - 市場・競合要因(計約30%)
– 「強力な競合がいた」(13.9%)、「市場環境が悪化した」(16.8%)など、競合優位に押され、いいタイミングでの市場参入を逃したケース - 顧客ニーズの誤認(9.9%)
– 顧客の本当の課題を捉え損ね、提供した製品・サービスが刺さらなかった - コスト・収益性の問題(16.8%)
– 開発・マーケティングに予想以上のコストがかかり資金不足、収益モデルの見積もりが甘く赤字が拡大した
このように、新規事業が失敗する背景には多岐にわたる課題がありますが、特に「アイデアの妥当性」と「社内の推進体制」の不足が大きな要因と言えるでしょう。逆に言えば、顧客ニーズを的確に捉えた質の高いアイデアを出すことと、社内外の協力を得て迅速に実行に移す推進力が成功のカギとなるのです。
もっとも、新規事業の成果は時間軸によっても評価が変わります。立ち上げ直後は成果が見えなくても、粘り強く続けることで大きな成功に育つケースもあります。実際、「サントリーのビール事業は黒字化までに46年かかった」という有名な例もあり、途中経過だけで成功・失敗を判断できない難しさも指摘されています。
不確実性は高いものの、挑戦を避ければ何も得られません。ある分析では「もっとも避けるべきは、失敗を過度に恐れて新規事業の検討すらしないこと」だと結論付けられています。不安はあるかもしれませんが、だからこそデータに基づきつつも大胆にチャレンジする姿勢が重要なのではないでしょうか。
新規事業の進め方(推進プロセス)
では、具体的に新規事業を立ち上げるにはどのように進めればよいのでしょうか。手探りで始めるのではなく、新規事業推進のプロセスをあらかじめ描いておくことで、効率的かつ計画的に進めることができます。
一般的には以下のようなステップで進行していくと良いでしょう。
1. 自社の理念・ビジョンやパーパスを明確にする
まず土台として、自社の経営理念やビジョンを再確認しましょう。会社が何のために存在し、将来どんな姿を目指すのかという軸が明確だと、新規事業のアイデアを検討する際の判断基準になります。
魅力的で意義あるビジョンは従業員のモチベーションを高め、新たな人材も引き寄せます。逆にこの軸がないと、目先の短期利益に振り回されて新規事業もうまくいきません。数年後にどんな存在になりたいのか、未来像を描き直し、それに沿った「軸」を定めることが出発点です。
その軸は社会的課題の解決であればなお良く、後のステップでの事業アイデア選定の指針にもなるでしょう。
2. 自社や顧客、業界の課題を見つける
次に、ビジネスチャンスの源泉となる課題の発見です。新規事業のアイデアは「誰の」「どんな課題」を解決するかから考えるのが基本です。
自社が抱える非効率や業界の構造的課題、あるいは顧客の不満や不便はないでしょうか。市場調査やヒアリングを通じて客観的なデータを集め、真の課題をあぶり出します。主観や思い込みで飛びつくのではなく、市場や顧客の声に基づいて問題設定をすることが重要です。
この段階では社内の熱意も大切ですが、あくまでエビデンスに基づき冷静に判断するよう心がけましょう。
3. 事業領域を定め、事業のアイデアを練り上げる
解決すべき課題の方向性が見えたら、事業領域を明確に定義します。つまり「どの分野・市場で」「どんな価値を提供するか」を広い視野で決める段階です。
既存事業とのシナジーや自社の強みも考慮しつつ、取り組む領域を絞り込みましょう。その上で具体的な事業アイデア出しに入ります。ブレインストーミングなどで多くのアイデアを出し、魅力的なものを選別・ブラッシュアップします。
迷ったときは最初に明確化した理念・ビジョンに立ち返り、「そのアイデアは自社の目指す方向に沿っているか」「社会的意義はあるか」を問いましょう。この基準に照らせば、ぶれずにアイデアを評価できるはずです。
4. 事業アイデアを市場分析し、事業性を予測する
候補となるアイデアが定まったら、それを市場の中で分析・検証します。具体的には、ターゲット市場の規模や成長性、競合の存在、有望な顧客セグメント、収益モデルの妥当性など、多角的に評価します。
市場環境やリスク要因を洗い出し、成功の可能性を予測しましょう。必要に応じて試作品やMVP(実験的な製品)を作り、顧客の反応を確かめるリーンスタートアップのような手法も有効です。データに基づく検証を重ねることで、絵に描いた餅で終わらない現実味のある事業計画へとアイデアを磨き上げます。
5. 新規事業立ち上げのための環境を整備する
事業アイデアにゴーサインが出たら、実行に向けた体制構築とリソース準備です。新規事業には人材、資金、技術、情報など様々な経営資源が必要になります。
社内から適任のメンバーを集め、必要なら採用や外部パートナー活用も検討しましょう。昨今、人材不足もあり外部のプロ人材と協業するケースも増えています。また、新規事業に専念できるよう既存業務から切り離した独立組織にするのも手です。
さらに経営陣からの支援や意思決定の迅速化を取り付けるなど、社内の後押し環境も整える必要があります。せっかく良いアイデアがあっても、動かす組織と資源が無ければ実現できません。船出前の準備を怠らず行いましょう。
6. 現実的な行動計画を立案し、事業計画書を作成する
次に、具体的なアクションプラン(行動計画)を作ります。誰が・いつ・何を行うか、マイルストーンと担当を明確に洗い出し、スケジュールに落とし込みます。
ここまで来たら、事業プラン全体をまとめた事業計画書の作成に取りかかりましょう。事業計画書は社内で経営層の承認を得たり、社外で資金調達や提携を進めたりするための重要なツールです。
次ステップで詳しく述べますが、企画書には事業の価値や勝算を分かりやすく示す必要があります。ビジネスモデルや収支予測、必要なリソースと期待効果などを盛り込み、読み手に「やってみよう」と思わせる内容に仕上げます。
7. 各行動の成果を検証し、継続的に改善する
計画に沿って実行に移したら、走りっぱなしにせず定期的に検証と改善を行います。進捗状況をチェックし、予定通り成果が出ているかを測定しましょう。
もし遅延や想定外の問題があれば、その原因を分析し対応策を講じます。新規事業では仮説と違う事態が起こるのが常ですので、柔軟に計画を見直す姿勢が大切です。PDCAサイクルを回し続け、製品・サービスの改良やビジネスモデルの調整を重ねていきます。
改善を繰り返すことで事業の成功確度は徐々に高まります。ここまでが新規事業推進の一連の流れです。
以上のようなプロセスを踏むことで、闇雲に進めるよりも失敗リスクを減らし、成功に近づけるはずです。
事業計画書作成のポイント
新規事業を社内外にアピールし、協力を得るには事業計画書(企画書)の出来が重要です。計画書には「新事業がどんな価値を生み、なぜ成功の見込みがあるのか」を納得してもらう役割があります。
ここでは、事業計画書を作成する際に押さえておきたいポイントをご紹介します。
内容を整理し、盛り込みすぎない
新規事業の検討では大量の情報が集まりますが、計画書には重要事項のみを厳選して簡潔に記載しましょう。読み手が一目で全体像を理解できる構成にすることが大切です。
例えば計画書には次のような要素を盛り込むと効果的です。
- 市場環境や顧客課題の定義
- その課題がなぜ重要か(機会と脅威)
- 課題を解決しビジネス化する方向性
- 具体的なビジネスモデルと実行プラン
- いつ収支プラスになる見込みか(投資対効果)
定量的データで説得力を高める
計画書では主張に対し客観的な根拠を示すことが求められます。市場規模や成長率、ユーザー調査結果など、使える数字は積極的に取り入れましょう。グラフやチャートを用いて視覚的に示すと理解が深まります。
ただし、データの出典や単位の明記を忘れずに。また数字を詰め込みすぎると却って伝わりづらくなるため、エビデンスとなる重要な数値に絞ることもポイントです。
文章は短くシンプルに
経営者や投資家などの読み手がストレスなく読める簡潔な文体を心がけます。専門用語は必要最低限にし、補足説明を付けると親切です。いくら優れた内容でも、伝わらなければ意味がありません。
何度も推敲し、わかりやすい表現に言い換えることで理解度を高めましょう。
自社の個性・強みを活かす
新規事業でも自社ならではの強みは大きな武器になります。計画書では競合他社との差別化ポイントとして、自社の技術力やブランド力、顧客基盤などをアピールしましょう。
また、新規事業によって自社ブランド価値がさらに高まるシナリオを描くことも有効です。読み手に「この会社だから成功できる」と思わせることが大切です。
明確なコールトゥアクションを設ける
計画書を読んだ相手に何をしてほしいのかを明示しましょう。例えば「この企画の承認がほしい」「○○万円の予算承認をお願いしたい」「パートナー企業を紹介してほしい」など、期待するアクションを具体的に伝えます。
提案を受け取った側が次に何をすればよいか分かれば、話が前に進みやすくなります。社内向けでも社外向けでも、最後に明確な呼びかけ(CTA)を用意することを忘れずに。
なお、事業計画書は提出前だけでなく日頃からアップデートしておくと良いでしょう。新規事業のアイデアは常に温めておき、短時間で魅力を伝えられるようにしておくと、いざという時に機会を逃しません。例えばエレベーターピッチのように1〜2分で概要を話せる練習をしておくのもおすすめです。
新規事業を成功に導くためのポイント(社内の取組み姿勢)
最後に、新規事業を推進する上で特に重要な組織的・文化的なポイントを押さえておきましょう。どんなに計画や戦略が優れていても、実行するのは「人」です。
組織として新規事業に取り組む際、以下の点が成功可否を分けると言われます。
良好なコミュニケーション
新規事業では既存事業部門や経営層、他部署との連携が不可欠です。会社規模が大きいほどセクショナリズムや縦割りの弊害で対立が生まれがちですが、社内の壁を越えて協力し合う体制を築かなければ成功は難しいでしょう。
リーダーは権限を持って部下を指揮し、ビジョンを共有しながらチームを統率する必要があります。定期的な情報共有や部門横断プロジェクトなど、コミュニケーション活性化の施策も検討しましょう。
挑戦を支える熱意とマインドセット
新規事業は「やってみなければ成功しない」ものです。一度のチャレンジで成功する保証はなく、むしろ何度も挑戦する情熱がなければ乗り越えられません。
社員の熱意を保つには、経営陣が率先して新しいことに挑み、失敗を責めない文化を醸成することが大切です。トップが革新を是とする姿勢を示せば、現場も安心してチャレンジできます。「馬券は買わなければ当たらない」ではありませんが、まず挑戦する風土を作ることが成果への第一歩です。
経営陣の支援と粘り強さ
新規事業は計画通りに進まないことが多く、失敗する確率の方が高いものです。そのため、経営陣が短期的な成果だけで判断し、「少しうまくいかないから撤退」というようでは、現場は萎縮してしまいます。
むしろ腰を据えて事業を育てる経営の覚悟が欠かせません。例えば、ヤクルト本社はブラジルでの事業が10年間赤字続きでも継続し、その後黒字化したというエピソードがあります。このように、経営側が長期的視点で新規事業を温かく見守り支えることが成功に結びつくのです。
ポートフォリオ戦略で「打席」を増やす
新規事業の成功確率が低い以上、1回の挑戦ですべてを賭けるのはリスクが高すぎます。そこで有効なのがポートフォリオ戦略の発想です。
複数の新規事業に並行して挑戦し、小さく産んでは市場で検証し、成果の出ないものは見切りをつけて、有望なものに経営資源を集中投入する——こうした「多産多死」をいとわないアプローチが合理的だとされています。
いわば挑戦の打席数を増やし、当たった球を大きく育てる戦略です。この考え方はスタートアップ投資の世界では一般的ですが、近年は大企業でもCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)の設立や社内複数プロジェクト並行推進などで取り入れられつつあります。
重要なのは、「失敗すること前提」で全体として成功を狙うマインドセットに組織が切り替わることです。そのために、限られた人材・資金をどの段階でどの案件に投じるかという投資判断のルール(リーン・ステージゲート法など)を整備する企業もあります。
一つ一つの失敗に一喜一憂するのではなく、ポートフォリオ全体で成果を最大化する発想が、新規事業成功率を高めるカギとなるでしょう。
大企業に見る新規事業成功事例
新規事業の取組みは難しいものですが、実際に成功を収めた企業も存在します。その中から大企業の成功事例を2つご紹介しましょう。それぞれ、自社の強みを活かしたケースと外部との協業によるケースです。
富士フイルム株式会社
写真フィルムで培ったコア技術を活用し、医薬品・化粧品・再生医療といった異分野に大胆に事業転換した例です。同社フィルムのコラーゲン技術や抗酸化技術を化粧品や医療に応用し、新規事業を育成しました。
既存技術と新分野の連続性を活用してシナジーを生み出し、時間をかけて事業構造の転換に成功した好例です。写真フィルム需要が激減する中で、培った技術を「第二の創業」に繋げた点は、多くの企業の参考となるでしょう。
日本郵政株式会社(日本郵便)
自社だけでなくスタートアップとの共創で新サービスを創出した例です。日本郵政は宅配の再配達問題に着目し、ベンチャー企業Yper社と協業して置き配バッグ「OKIPPA」を開発・普及させました。
OKIPPAは安価で設置場所を取らない宅配バッグで、アプリ連携により荷物追跡もできる利便性から利用者を伸ばしています。この取り組みにより、慢性的な配達員不足という社会課題の解決に寄与し、新たなサービス分野を切り拓きました。大企業のリソースとベンチャーのアイデアを組み合わせた成功例と言えます。
こうした事例から得られる示唆は、自社の強み技術を異業種に展開することや、外部パートナーとの協業によるオープンイノベーションが新規事業成功の突破口になり得るということです。自社単独にこだわらず柔軟に発想することで、新規事業の可能性は広がるでしょう。
まとめ:失敗を恐れず数多く挑戦を
新規事業の進め方について、定義や必要性から始まり、プロセス、計画書のポイント、組織的な成功要因まで包括的に見てきました。改めて主要なポイントを振り返ってみましょう。
新規事業の意義:企業が既存事業の延長線上にない新たな価値創造に挑む「第二の創業」であり、技術革新と環境変化の中で企業の将来を左右する生命線です。
現状と成功率:現代の新規事業成功率は概ね20〜40%と低水準で、満足いく成果を上げられる例は少ないのが実情です。だからこそ一度の成功に頼らず、数多く挑戦して当たりを引くポートフォリオ戦略が重要になっています。
推進プロセス:新規事業開発は行き当たりばったりではなく、理念の再確認から課題発見、アイデア創出、検証、体制整備、計画策定、実行・改善という段階を踏むことで成功率を高められます。現場での検証や競合分析など地道なステップも欠かせません。
計画書と組織:周到に練られた事業計画書によって社内外の理解と協力を得ることも、新規事業推進には不可欠です。さらに社内のコミュニケーションを円滑にし、経営トップ自らが新規事業にコミットして挑戦する文化を醸成することが成功への土台となります。
成功へのエール:新規事業の立ち上げには困難がつきものですが、もっとも避けるべきは失敗を恐れて何もしないことです。市場が移り変わる中、挑戦を続ける企業だけが次の成長機会を掴むことができます。
今回ご紹介したような手順や戦略、そして数多く挑戦するマインドセットを参考に、ぜひ貴社でも新規事業創出に果敢に取り組んでみてください。
私たちは新規事業に挑む皆様を応援しています。そしてお困りの際には、組織変革や新規事業支援のプロフェッショナルである当社ソフィアにもぜひご相談ください。