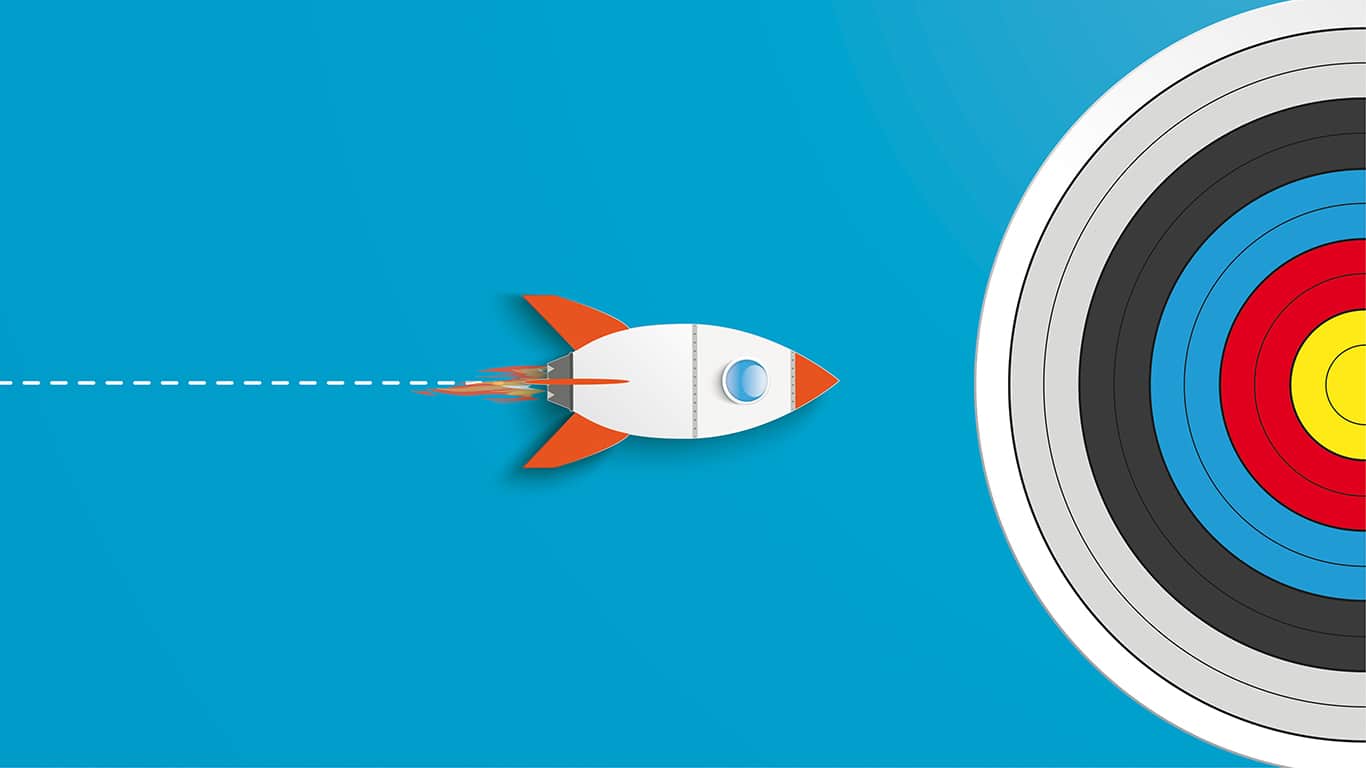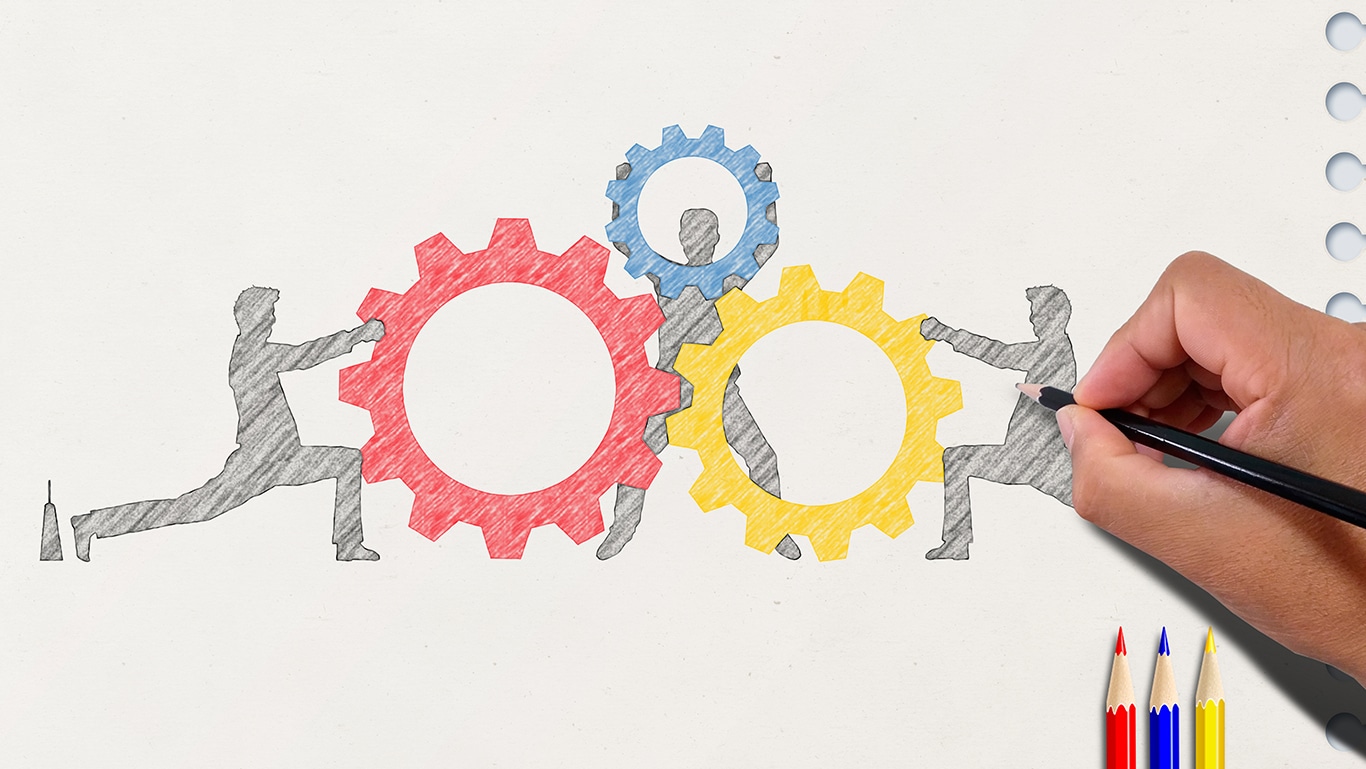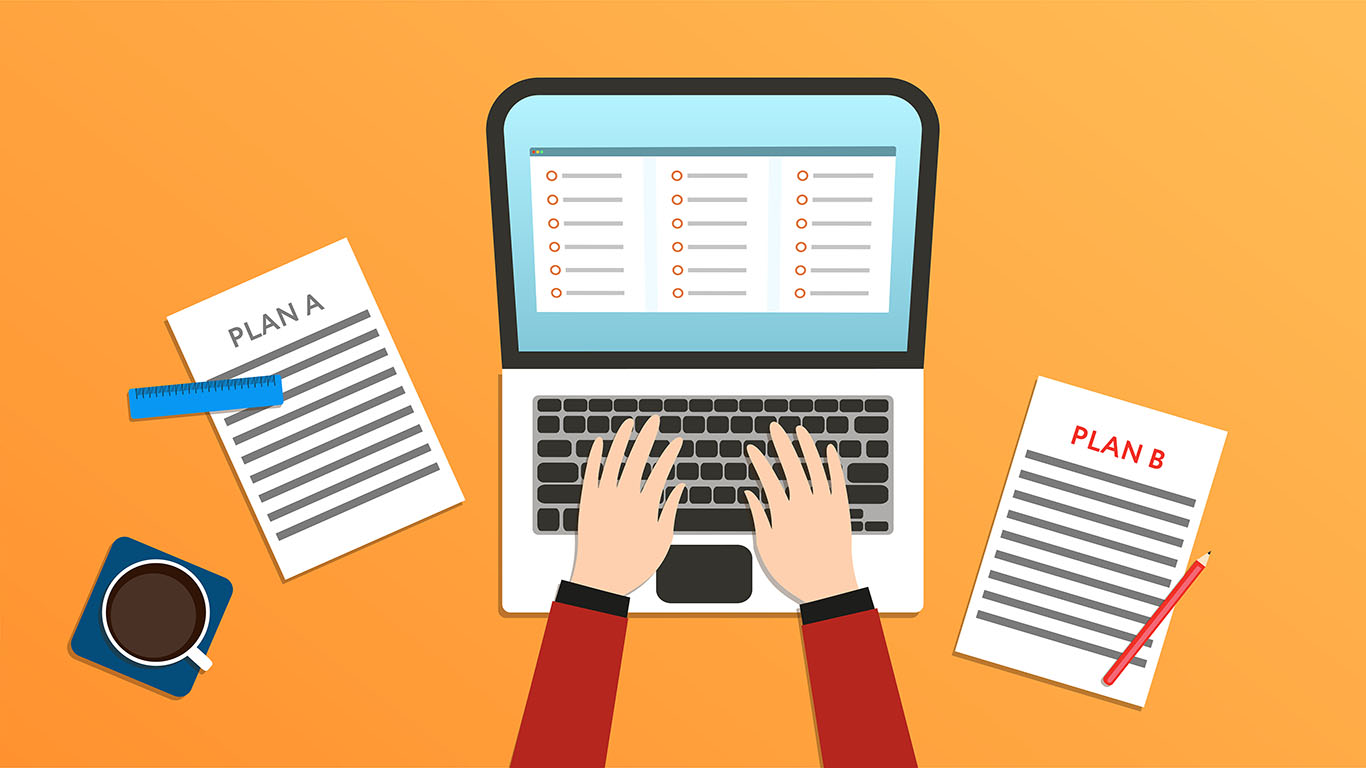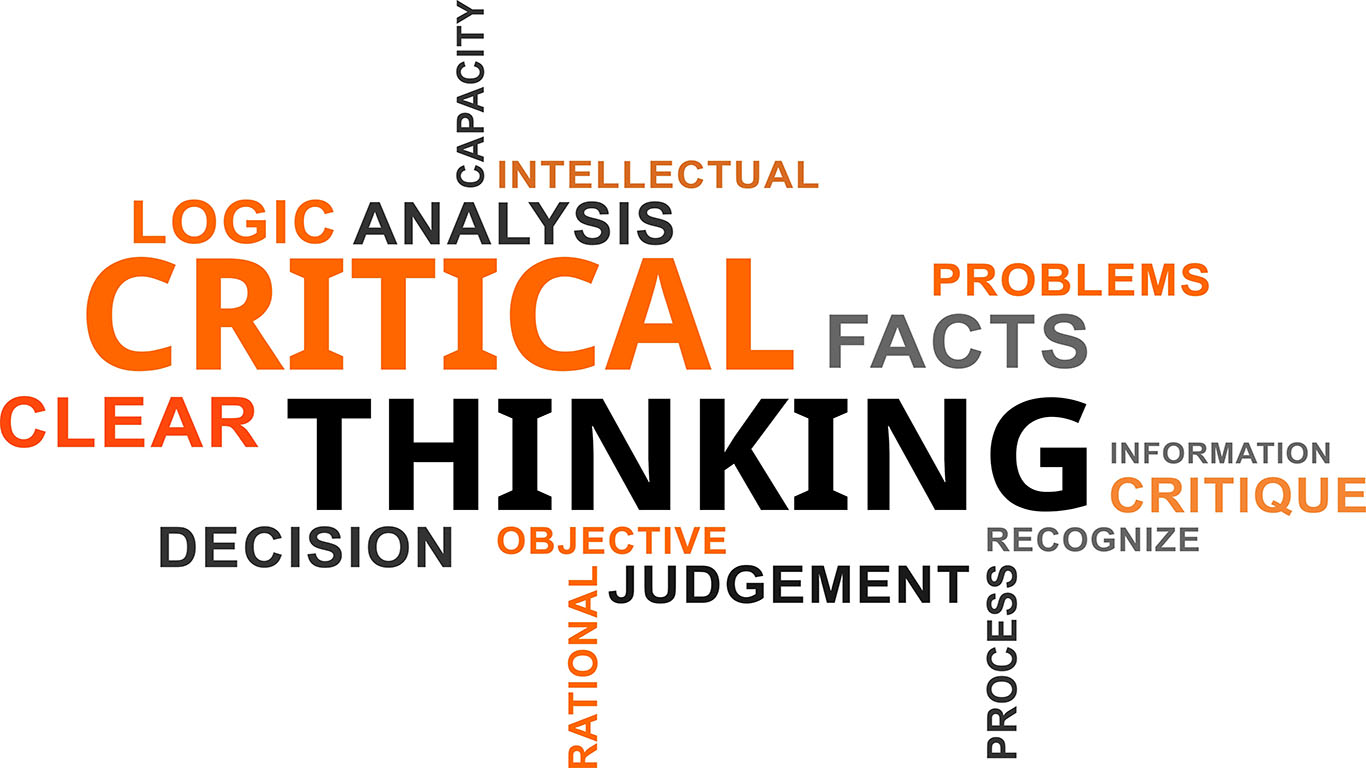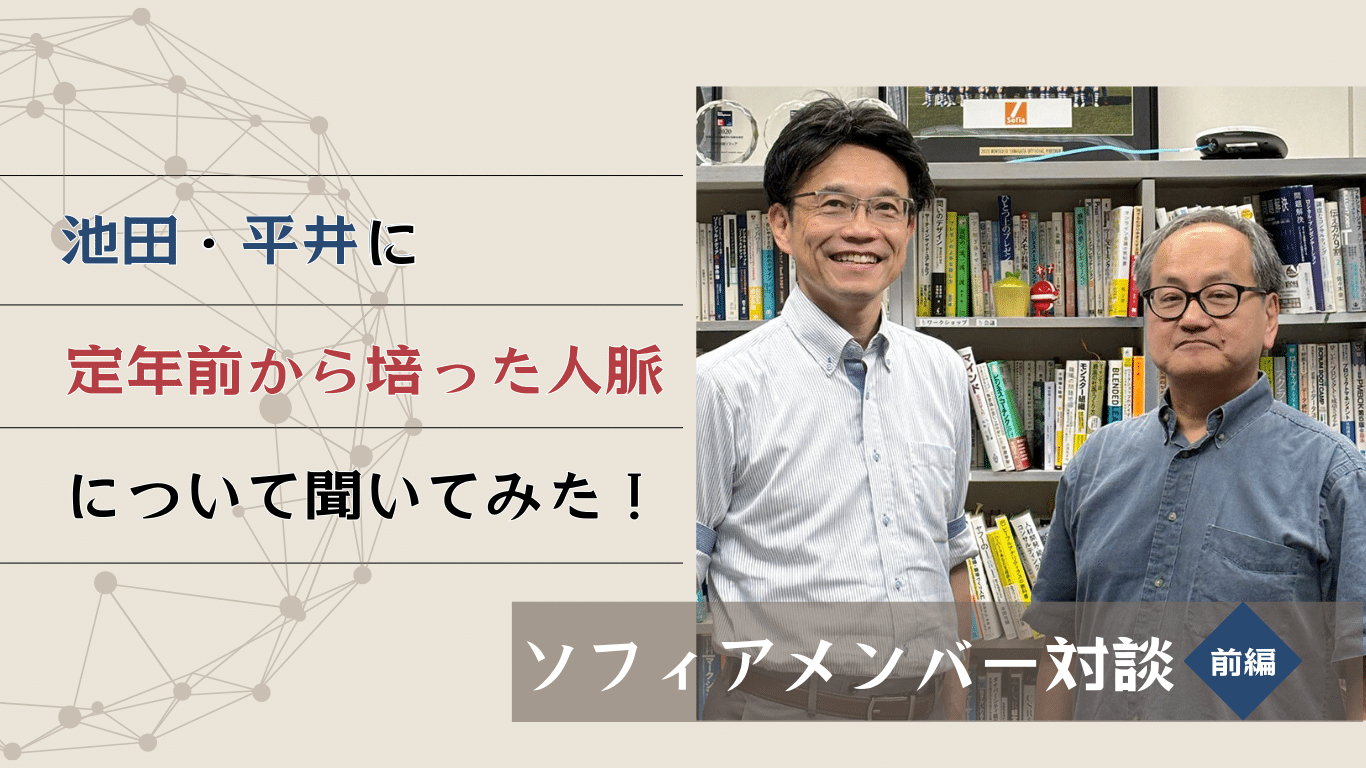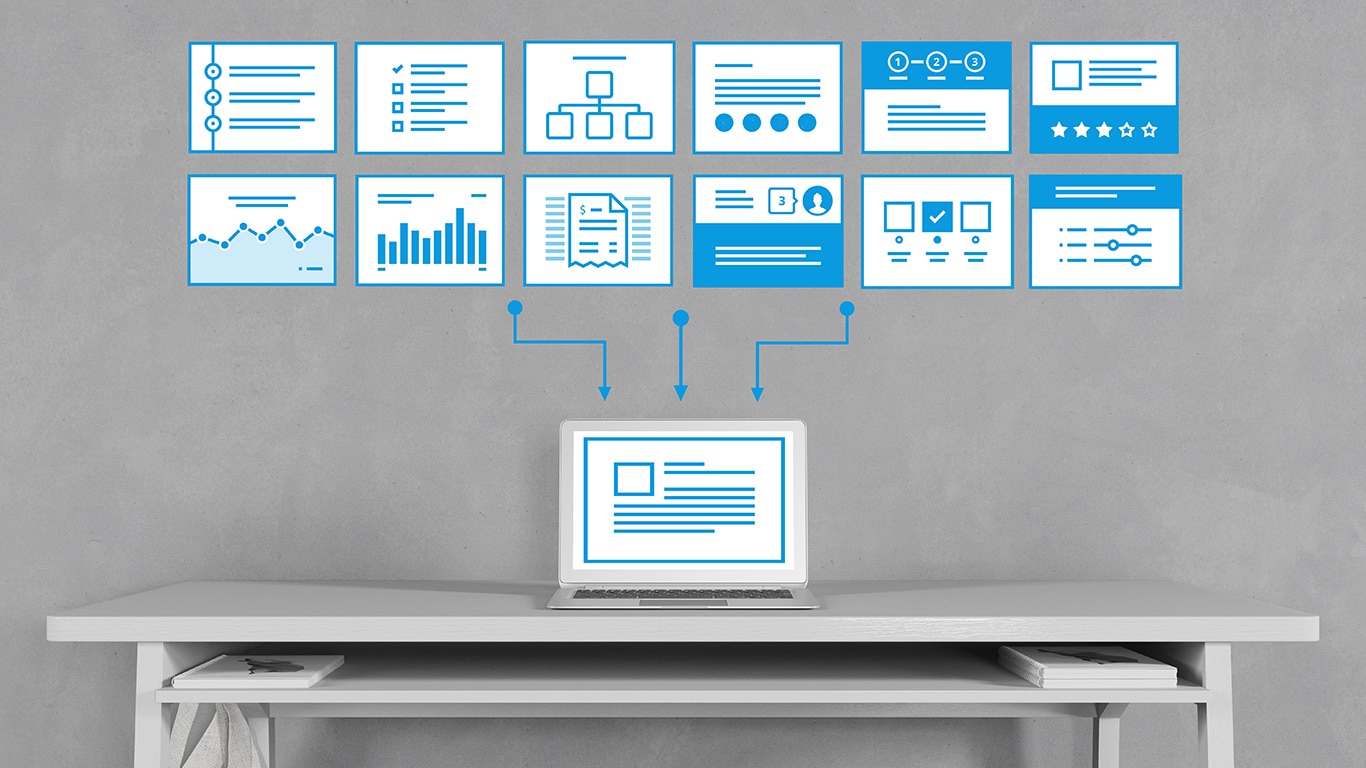長期経営計画とは何か?VUCA時代を生き抜く戦略と策定のポイント
最終更新日:2025.10.02

目次
企業が5年先、10年先の未来を見据えて策定する長期経営計画とは、一体どのようなものでしょうか。その必要性は理解していても、「変化の激しいVUCA時代に長期計画を立てる意味があるのか?」と悩む経営者も少なくないのではないでしょうか。
結論から言えば、長期経営計画とは、企業の経営ビジョン(将来像)と現在の姿とのギャップを埋めるため、通常5~10年程度の長期スパンで策定される経営計画です。平たく言うと、企業が目指す将来像に向かって進むための「羅針盤」のような役割を果たすものと言えるでしょう。
本記事では、長期経営計画の基本から、メリットや作り方、現代ならではのポイントまでを体系的にご紹介します。長期ビジョンと現状とのギャップを埋め、企業が不確実な未来を生き抜くためのヒントを探っていきましょう。
長期経営計画とは?
長期経営計画(long-term business plan)とは、企業の経営ビジョン(将来像)と現在の姿とのギャップを埋めるため、通常5~10年程度の長期スパンで策定される経営計画です。明確な定義はありませんが、一般的に中期経営計画(3~5年)より長い期間で企業の将来像を描くものを指します。
長期経営計画は経営理念・ビジョンに沿って企業の将来的な方向性を定め、経営戦略や施策の大枠を示す羅針盤の役割を果たします。実際、経営計画を持たない経営は「GPSも地図もコンパスも無しに太平洋を横断するようなもの」とも例えられ、計画がなければ経営者は迷走しかねません。
長期経営計画と中期経営計画の違い
経営計画は一般的に「経営理念」「経営戦略」「事業戦略」「数値計画」を中心に、組織設計や要員計画などを数値化していくものです。
多くの場合、経営計画は長期経営計画を指し、中期経営計画とは明確に区別されます。長期経営計画は5~10年程度の期間を対象とし、企業の使命やビジョン、価値観、長期目標を明確に定め、戦略を描くことが目的です。一方、 中期経営計画は3~5年を対象とし、長期経営計画で定めた戦略を具体的な施策や実行計画に落とし込む役割 を持ちます。
長期と中期の両計画は互いに補完し合い、歯車のように連動して機能します。経営計画が企業の将来に向けた方向性を示す「羅針盤」とすれば、中期経営計画はその道筋を具体化する「地図」と言えます。両者を策定・実行することで、企業は持続的な成長と発展を実現できるのです。
長期経営計画と経営ビジョンの違い
経営ビジョンは、 抽象的で未来の理想像を示すものであり、組織の方向性や大切にすべき価値観を前提 として描かれます。その未来像から逆算して考える「バックキャスト」により、目指す姿に向けた行動を導く方針として機能します。
一方、長期経営計画は、経営ビジョンを実現するために具体的な数値目標を設定し、ステップやアクションプランを明確に示すものです。一定期間内の達成を前提としつつ、状況に応じて柔軟に修正できる点が特徴です。
これに対して、経営ビジョンは明確な期限を持ちながらも、基本的に固定された未来像であり、大きく変更されることはほとんどありません。経営ビジョンは企業の理念を基盤に、経営者や幹部にとっての指針としての役割を担います。
長期経営計画はなぜ必要なのか?
長期経営計画が必要とされる主な理由を整理してみましょう。
経済産業省の報告書によれば、経営計画には「①ビジョン具現化機能(将来像を具体化し共有する)」「②経営管理機能(環境変化に対応する)」「③資金提供者への説明機能(投資家・金融機関への説明責任)」という3つの機能があるとされています。
これらを踏まえ、長期計画を策定・公開することで企業にもたらされる具体的なメリットは以下の通りです。
1. 経営の指針が明確になる
長期のビジョンと道筋が定まることで、経営者は日々の意思決定に迷いがなくなります。経営計画がないままでは「場当たり的な航海」となりがちですが、計画という羅針盤があれば最終目標に向かって一歩一歩着実に進めるでしょう。
2. 社内外でビジョンを共有できる
経営計画は経営者の頭の中にある構想を言語化し見える化したものです。計画を示すことで従業員や取引先と将来像を共有でき、全社が一丸となって同じ目標に向かう推進力が生まれます。
3. 金融機関や取引先からの信用が高まる
計画的な企業と無計画な企業では、金融機関や投資家からの信用度に大きな差が出ます。明確な長期・中期計画を掲げている企業は新規取引や資金調達の面で有利になり、結果としてビジネスを円滑に進めることができるでしょう。
4. 組織の結束力が高まる
全社で同じ計画目標を共有することで、従業員のベクトルを揃え組織の一体感を醸成できます。全員が同じ方向を向いて努力する環境は、目標達成までの推進力となり、組織力の向上にもつながります。
5. 現状の課題が見えてくる
長期計画を立てる過程では、まず自社の現状を詳細に分析し把握する必要があります。将来像とのギャップを洗い出すことで、現在の課題や弱点が浮き彫りになり、今後改善すべきポイントが明確になります。
VUCA時代の長期経営計画は不可能か?
VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字からなる専門用語で、現代のビジネス環境の特徴を表しています。
このVUCA時代において、長期経営計画を策定しても、その前提である周囲の環境が変化が早く実行段階において困難な課題となっています。
環境や業績の変動が激しく、 策定した長期経営計画は、達成不可能な未来に思え、リアリティを持たないケースが増えてきています。 また、競合他社の動きが予想できず、差別化を図ることも難しいかもしれません。多様化する顧客ニーズにも対処できず、サービス提供の安定性が維持できない場合もあります。
加えて、急速に進展する技術革新により、新しいビジネスモデルが生まれ、自社の業界全体が変わる可能性もあります。昨今長期経営計画を策定しない企業が増えている理由です。
VUCA時代の長期経営計画に必要なものは、機敏で柔軟な組織と社員
現代社会は、グローバル化やテクノロジーの進歩によって、ますます複雑化しているため、企業が長期的な視野を持って経営計画を策定することは不可欠です。
しかし、VUCAという激動の時代においては、変化のスピードが速すぎて、長期経営計画を作り上げるだけでは対応することができません。企業は、変化に柔軟に対応し、即座に意思決定ができる能力が必要です。そのためには、「柔軟性」「アジャイル・アジリティ」「イノベーション」「協力性」に代表される組織力が求められます。

では、具体的にはどのようにすれば良いのでしょうか?
経営ビジョンと長期経営計画の柔軟な計画変更できる体制
経営ビジョンを支える長期経営計画は、企業が目指す将来像や方向性を示す重要なものです。しかし、環境変化が激しい中では、長期的な計画を立てること自体に限界があるのも事実です。そのため、 計画は柔軟に修正していく必要 があります。ただし、場当たり的に変える「朝令暮改」になってしまうと、現場や品質が安定せず、事業全体に悪影響を与えてしまいます。
こうした状況に対応するためには、社内のコミュニケーションが欠かせません。たとえば、社員一人ひとりが変化を予測しながら、ICTを活用して情報を可視化・共有できれば、変化の兆しを早く察知できます。
つまり、 長期経営計画はあくまで仮説として捉え、変化の要因を見える化し、組織全体で文脈を共有する「相互コミュニケーション」 が重要です。これによって、計画の修正を組織に素早く受け入れさせることができます。コロナ禍での社会の動きを振り返れば、こうした取り組みは決して難しいことではなく、むしろ今後ますます必要になると言えるでしょう。
社員や組織が計画や仮説で学習し、ビジョンは腹落ち
企業が計画や仮説を立て、学習を重視することは非常に重要です。その際に欠かせないのが「ビジョン」です。VUCAの時代では環境の変化が激しく、迅速な対応が求められるため、ビジョンの重要性は一層高まっています。明確なビジョンがあれば、学習の目的がはっきりし、失敗の原因分析や改善にも役立ち、より効果的な学習が可能になります。組織がビジョンを持つことで、変化に対応する方向性を定め、迅速な意思決定につなげられるのです。
一方で、ビジョンが不明確であると、経営戦略そのものが曖昧になってしまいます。長期経営計画は、あくまで一定のシナリオを前提とした「仮説」にすぎません。社員や組織が学びを通じてビジョンを理解し、共感し、計画が現実的な管理へと変換されることで意味を持ちます。
つまり、VUCAの時代においては、 長期経営計画や仮説は学習のための材料にすぎず、「何のために学ぶのか」「何を達成したいのか」を定めるビジョンこそが不可欠 です。ビジョンが定まり、社員が共感し協力できる目的になったとき、計画は初めて実効性を発揮します。
柔軟な組織設計やシステム
柔軟な組織やシステムはとても重要ですが、それを実現するためには一定の固定化や標準化も必要になります。ところが、行き過ぎた管理やルール重視に陥ると、本来の柔軟性が失われてしまいます。そのような状況から脱却し、原則や本質に立ち返る姿勢が大切です。
具体的には、社内ルールや権限の与え方、広く浸透している商慣行や社内での言い回しを見直し、業務を効率化していくことが求められます。
高度でアジリティの高い社員の問題解決とコミュニケーションスキル
基本的には、柔軟性と協調性を確保するためには、原則となるルールや仕組みを可能な限り削減し、個人の判断力とコミュニケーション能力に依存することが必要です。
しかしながら、組織内において円滑なコミュニケーションを実現するためには、 適切な場や環境が整備されていること が不可欠です。複雑で変化の激しい状況に対処するためには、トップダウン型のコミュニケーションだけでなく、現場からトップに向けたボトムアップ的な意見交換も重要です。
さらに、部署や個人同士のフラットなコミュニケーションも不可欠であり、透明性を高めて社内情報を共有し、組織をフラット化することで、個々人のコミュニケーションスキルを向上させることも必要です。
相互の信頼性の高い組織風土
相互に信頼できる組織風土をつくることは、専門性や多様性に適応するうえで非常に重要です。日本企業の強みとしては、高度経済成長期に培われた「阿吽の呼吸」や家族主義的な経営が挙げられますが、行き過ぎると「村社会」となり、現在ではさまざまな問題の要因とみなされています。とはいえ、 自社や社員を冷笑的にとらえ、悲観的に表現してしまうと、信頼関係を壊す危険 があります。
社内には「うちの社員は○○だからダメだ」「うちは大企業だから」などと、組織を家族のように語りながら批判する“スマートな評論家”がいます。一見もっともらしい言い方ですが、その裏には「組織や社員を信頼したい」という根源的な感情があります。 この思いを対話によって丁寧に共有する ことこそ、組織にとって大切です。
その行動は決して経営に悪影響を与えるものではなく、むしろ信頼関係の醸成につながり、健全な風土を育てることになります。
長期経営計画の策定方法
長期経営計画を策定する際には、経営理念の再確認から具体的計画への落とし込みまで、いくつかの段階を踏む必要があります。以下に長期経営計画策定の主なステップをまとめます。各ステップで環境変化への対応策も織り交ぜ、実効性のある計画を作り上げることが重要です。
1. 経営理念や企業の存在意義を再確認する
長期計画の土台となる経営理念・ミッションを明確に再定義します。企業の存在意義や価値観、社会的使命を見直し、「何のために事業を行うのか」という根幹を全社員で共有します。
2. 将来(5~10年後)のビジョンや目指す会社像を設定する
経営者が描く将来のありたい姿(長期ビジョン)を文章やビジュアルで具体化します。例えば「10年後に市場でどのような地位を占めていたいか」「社会にどんな価値を提供したいか」など、将来像を定性的に描きましょう。
3. 長期的な数値目標を策定する
ビジョンを実現するため、5~10年後を見据えた経営目標の定量化を行います。例えば、「10年後の売上高〇億円」「営業利益率〇%」といった具体的なKPIを設定します。
4. 外部・内部環境を分析し戦略オプションを検討する
自社を取り巻く事業環境(市場トレンド、競合動向、技術革新など)と自社の内部状況(経営資源の強み・弱み)を徹底的に分析します。このとき、将来起こり得る環境変化に備えて複数のシナリオを描き、それぞれに対応する戦略を検討します。
5. 中期・短期の具体策に落とし込む
策定した長期ビジョン・戦略を実行に移すため、3~5年の中期経営計画と1年ごとの短期計画にブレイクダウンします。こうした階層化された計画によって、長期ビジョンから日々の業務目標まで一貫性を持たせます。
6. 計画策定プロセスに組織を巻き込み共有する
長期経営計画の策定段階から、可能な限り現場の管理職や担当者を巻き込みます。トップダウンで数値目標を押し付けるのではなく、現場の知見を取り入れたボトムアップ型の議論を行うことがポイントです。
7. 実行に移し、定期的に進捗を検証・見直す
計画策定が終わりではなく、PDCAサイクルを回しながら常に計画を最新化していきます。短期計画については月次・四半期単位で実績との差異をチェックし、問題があれば中期計画を即座に修正するなど、機動的な対応を行います。
以上が長期経営計画策定の大まかな流れです。特にステップ4で触れた「複数シナリオの検討」は、先行き不透明な現代において非常に重要なポイントです。
長期経営計画の策定のポイント
長期経営計画は、VUCA時代を生き抜くために、策定段階から組織力を高めることを目的としています。計画をつくる過程で、メンバーが自分の役割や責任を確認し合い、コミュニケーションを重ねながら進めることで、組織力が強化されます。また、計画の進捗を管理することで、情報共有や課題意識の共有が促され、さらに組織力を高めることができます。
ただし、単に計画を立てるだけでは組織力は向上しません。重要なのは、 計画策定のプロセスそのものを「組織力を育てる場」として活用する ことです。次に、うまく取り組んでいる企業の特徴から、その具体的なポイントを見ていきましょう。
不確実性を減らすシナリオプランニングの活用
近年、ビジネス環境の不確実性が高まっていることが注目されています。このような状況で企業が成功するためには、将来の複数シナリオに対応できる柔軟な戦略が欠かせません。そこで有効なのがシナリオプランニングです。これを活用することで、企業は将来の可能性を想定し、さまざまなシナリオに対応可能な長期経営計画を策定できます。
ただし、一つのシナリオに依存するのはリスクが高いため、複数のシナリオごとに複数の計画を用意することが望まれます。こうした前提で柔軟な戦略を取ることで、企業は変化する市場環境に適応し、競争力を維持できます。
例えば、新技術の登場や競合他社の戦略転換に対応したシナリオを作成し、それに基づく戦略を策定することが考えられます。また、リスクマネジメントを取り入れることで、不確実性への耐性を高めることも可能です。
総合すると、シナリオプランニングを活用して中核となる長期経営計画を策定すると同時に、将来に備えた複数の選択肢を持つことが、企業の持続的な成功に不可欠だといえます。
長期経営計画の指標が業績数字以外も考慮されている
企業の長期経営計画には、財務諸表には現れない非財務指標も重要な役割を果たします。たとえば、従業員満足度やESGへの取り組みといった指標は、株主への対応だけでなく、将来の事業性や社会課題への姿勢を示すうえで欠かせません。これらを示すことで、経営ビジョンに沿った長期的な計画の裏付けとなります。
一方で、こうした指標が揃わなければ、ステークホルダーに十分な説明ができず、社員の協力を得ることも難しくなります。指標が多様化すると複雑さは増しますが、それ自体が経営ビジョンの実現に不可欠な要素であることを理解することが重要です。
解像度の高い議論ができる現場のコミュニケーションスキル
長期経営計画は、経営ビジョンを実現するための戦略的な手段体系ですが、現場との合意形成は必ずしも円滑に進むとは限りません。特に詳細で解像度の高い課題は、議論を紛糾させる要因になりやすいでしょう。
しかし、策定段階からビジネスユニットや従業員など複数の階層を巻き込み、ボトムアップ型で進めることで、成功につながります。こうした議論は、単なる数字の積み上げや責任回避的な意見交換ではなく、変革を取り込んだ実行計画の策定を目的とするものです。
さらに、このプロセスを通じてコミュニケーション能力が高まり、中長期的な戦略に対する組織の理解も深まります。その結果、計画の変更が必要になった際にも迅速に合意形成ができ、持続的なビジネス成長を後押しする基盤となります。
共感と実践度の高い現場のコミュニケーションスキル
長期経営計画は将来への予測と仮説であり、結果が保証されているわけではありません。だからこそ、詳細で解像度の高い議論は大切ですが、その後に合意形成や行動につながらなければ、単なる「評論番組のような会議」と揶揄されてしまいます。つまり、社員の理解や動機づけがなければ意味を持たないのです。
目標達成のためには、組織や従業員が自己成長や努力を重ねる必要があります。その際にはロジカルな議論だけでなく、感情的な共感と動機付けが欠かせません。将来像や目標に対する感情的な共有や説明の機会を設けることが、長期経営計画の策定や変更の場面でも重要になります。
単に数値的な成果を論じるのではなく、学習や振り返りを前提とした継続的な意思疎通こそが、長期経営計画を組織に根付かせる鍵となります。
策定する段階から社内コミュニケーションを徹底している
長期経営計画の策定に限らず、計画を立てる側と実行する側のジレンマは、さまざまな分野で生じます。一般的に、計画策定者は利点を強調し、実行者は不利益に目を向けがちです。そのため、長期経営計画をつくる際には、社員や関係者を早い段階から参加させることが重要です。
具体的には、計画のプロセスや対象者を議論する段階から、オープンなコミュニケーションを重ねる必要があります。これは、計画が完成した後に説明するのとは異なり、策定の過程そのものを共有することで理解と納得を深める取り組みです。こうしたアプローチは、すでに多くの企業で実践され、効果を上げています。
達成向けた変革やイノベーションの要素が明確でシンプル
長期経営計画は、近年では変革やイノベーション計画に近い内容となることが一般的です。しかし「変革」や「イノベーション」といった言葉は曖昧で、都合よく使われることも多く、リーダーが用いるレトリックの一つにすぎない場合もあります。
実際に具体的な行動へ移す段階では、こうした抽象的なキーワードに頼るのは適切ではありません。優れたチェンジマネジメントにおいては、変える部分と変えない部分のバランスを適切に調整し、焦点を当てる範囲を明確にすることが重要です。何でも「変革」として扱えば思考や活動が散漫になり、成果は得にくくなります。むしろ、一定の範囲や制約を設けることで、より的確な提案やアイデアが生まれやすい環境を作り出すことができます。
経営陣がしつこいほどのコミュニケーション
ソフィアが長期経営計画や経営ビジョンの策定・実行を支援してきた中で確認できた成功要因のひとつは、経営陣が継続的にコミュニケーションを行っていることです。科学的に完全に説明できない部分もありますが、実際の支援を通じて確かめられた重要なポイントです。社員やステークホルダーに対して、長期的なビジョンを繰り返し明確に伝えることは、ときに煩わしく感じられるかもしれません。
しかし、節目ごとに長期経営計画とビジョンを結びつけるような、いわば「意味づけ力」を伴った継続的なコミュニケーションは、経営陣の意思や姿勢を伝える上で非常に大きな効果を持ちます。これは企業の成長において欠かせない取り組みであるといえます。
まとめ
長期経営計画とは、企業が5~10年先の将来像を描き、その実現に向けた戦略と目標を示す計画です。中期・短期計画と連動して企業の羅針盤となり、社内外にビジョンを共有し信頼を築く効果があります。
特にVUCAと呼ばれる不確実な時代においては、「計画通りにいかない」ことを前提に柔軟性やアジリティといった組織力を計画に織り込み、シナリオプランニングなどで複数の未来に備えることが重要です。
長期計画を策定するプロセス自体を組織の学習機会とし、財務KPIに限らずESGなど非財務目標も組み込むことで、企業は変化に強い持続的成長の道筋を描けるでしょう。