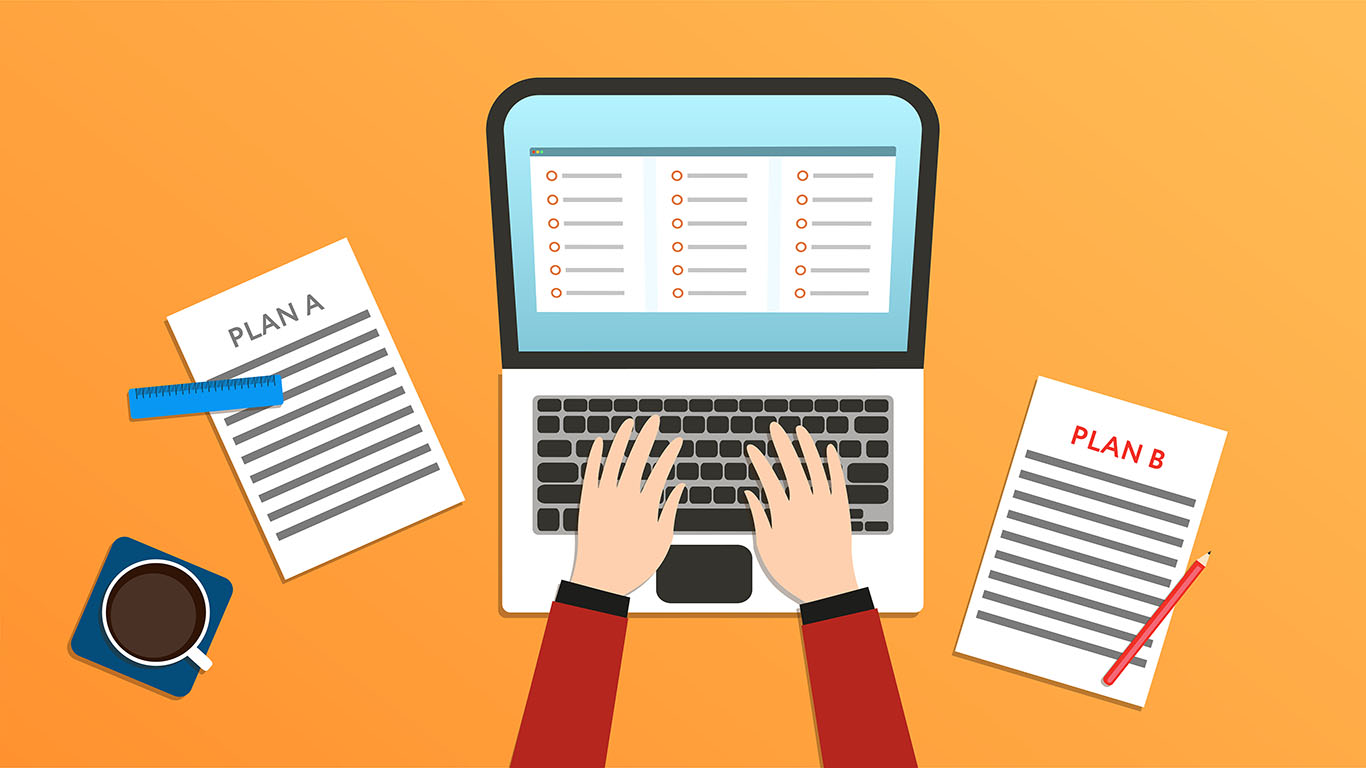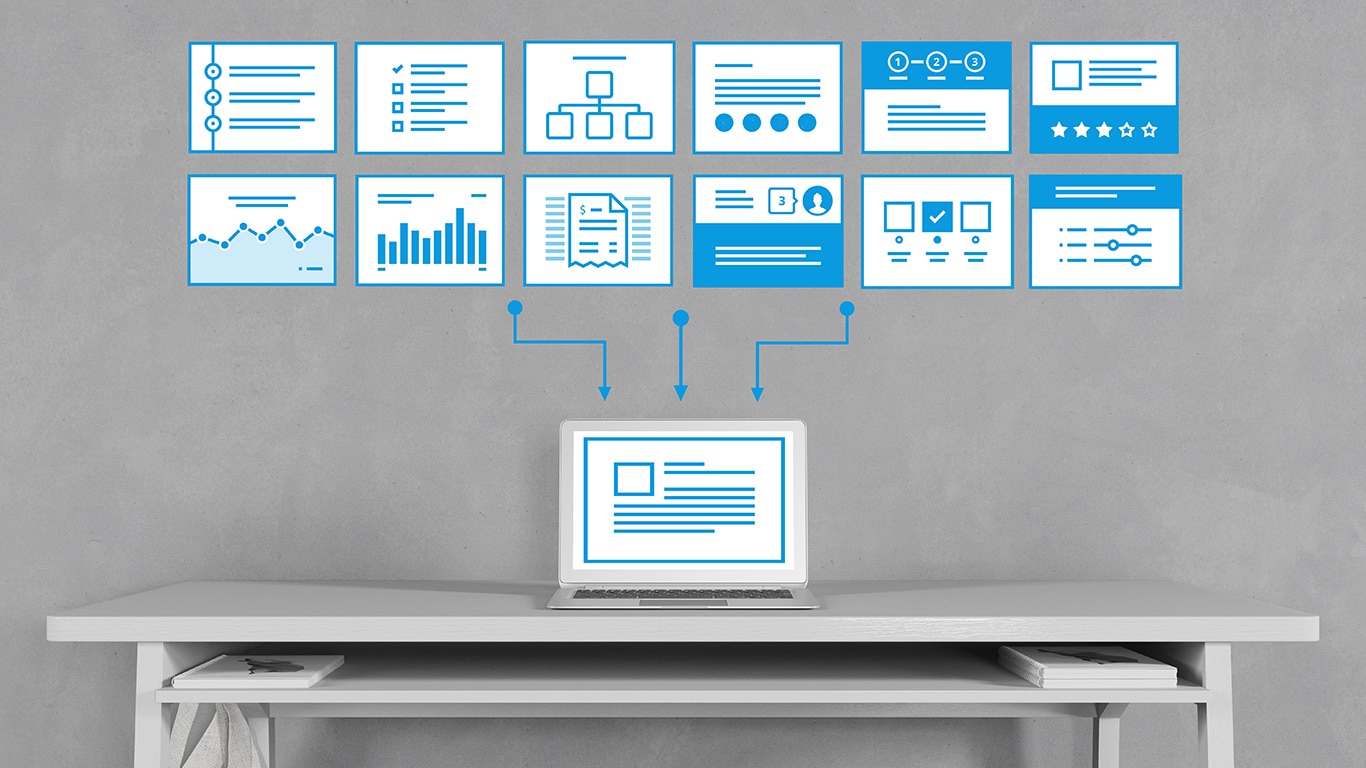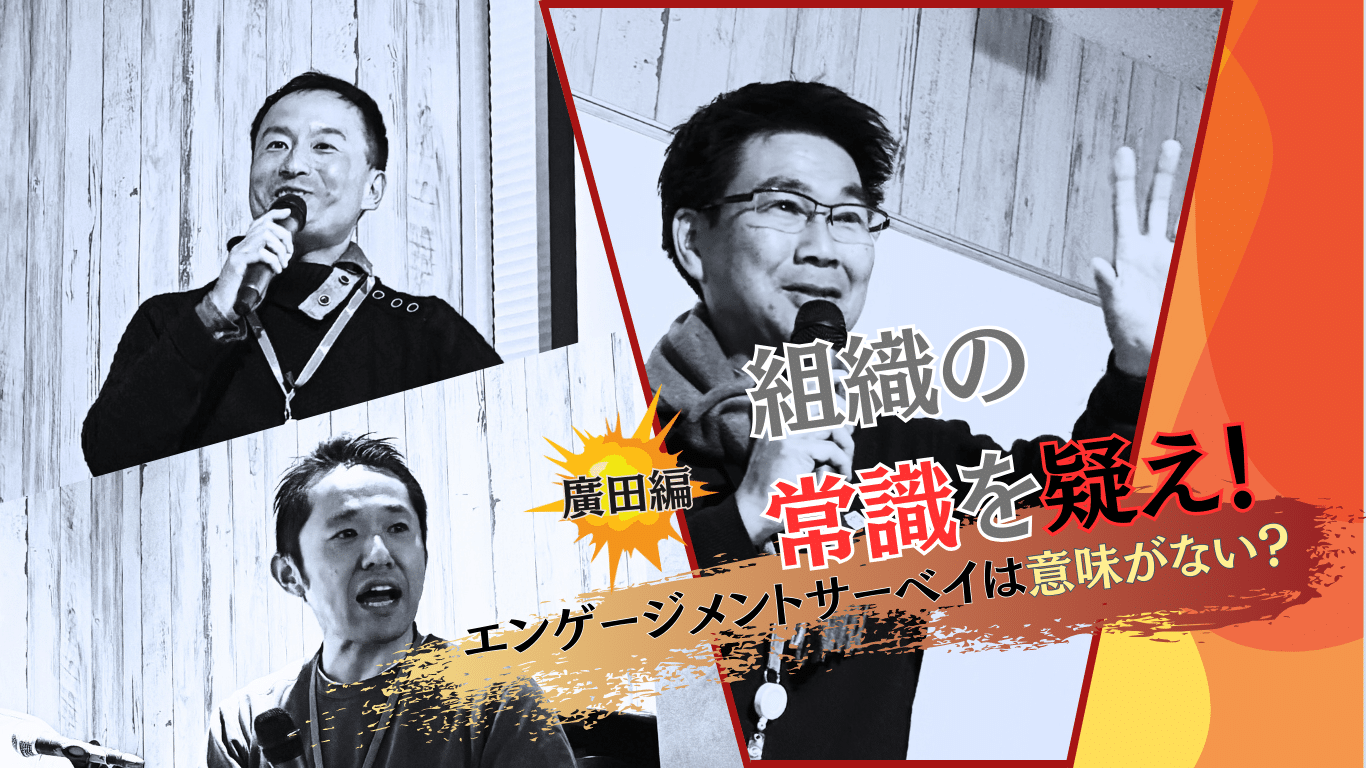新規事業とは何か?定義から成功要因・事例まで徹底解説
最終更新日:2025.07.15

目次
「新規事業」という言葉を耳にしたとき、皆さんは何を思い浮かべますか。企業が生き残り成長し続けるためには、現状に安住せず新たなビジネスに挑戦することが不可欠とされています。しかし、新規事業の立ち上げは容易ではなく、多くの企業が試行錯誤を繰り返しているのが実情です。では、新規事業とは何か、なぜそれほど重要視されるのでしょうか。
本記事では、新規事業の定義から必要性、そして成功・失敗の要因や事例まで、豊富なデータをもとにわかりやすく解説していきます。まず新規事業の定義とその必要性について確認し、企業が新規事業に取り組む背景を明らかにします。次に、近年の新規事業の成功率は約3割前後と低迷している現状や、新規事業開発に要する期間・資金の動向を最新データから読み解きます。
新規事業とは何か?定義と背景
新規事業とは、企業が既存のビジネスモデルや事業領域にとらわれず、新たに立ち上げる事業のことです。例えば、これまで扱っていなかった新しい製品・サービスを開発したり、これまでとは異なる市場に参入したりする取り組みが該当します。平たく言えば、企業にとって「第二の創業」ともいえる大胆な挑戦であり、企業成長や生き残りのための重要戦略と位置付けられています。
近年、新規事業創出の必要性が一段と高まっています。その背景には、技術革新や市場変化のスピードが増し企業の平均寿命が短命化している現実があります。実際、1960年頃には50~60年あった米国S&P500企業の平均寿命が、2010年以降では約18年にまで短縮しています。この劇的な変化は、企業が現状の成功に安住していては生き残れないことを示しています。まさに「イノベーションを起こし続けないと企業は生き残れない」時代となっており、常に新たなビジネスを模索・創出し続ける姿勢が企業存続のカギといえるでしょう。
さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大やデジタル化の進展などにより、企業を取り巻く環境は急速に変化しました。従来のビジネスモデルだけでは対応しきれない新たなニーズや課題が次々と生まれ、既存事業の成長が頭打ちになるケースも増えています。そのため、変化に柔軟に適応し新たな収益源を育てる新規事業開発が、企業の生命線とも言える重要性を帯びてきたのです。
こうした背景を受けて、日本政府も新規事業・スタートアップ支援に本腰を入れ始めました。2022年11月には「スタートアップ育成5か年計画」が策定され、スタートアップへの投資額を5年で10倍(約10兆円規模)に拡大し、加えて既存の大企業によるオープンイノベーション推進を掲げています。この国家的な後押しもあり、近年は多くの大企業が社内ベンチャー制度の導入やスタートアップとの提携など、新規事業創出に向けた動きを活発化させています。
まとめると、新規事業とは「企業が未来の成長のために挑む新しい事業領域・ビジネスモデル」であり、その重要性は時代の変化とともにますます高まっていると言えます。変化の激しい現代において、既存事業の延長線上にない新たな価値を創造できる企業だけが、持続的な成長を遂げられるでしょう。
なぜ新規事業が必要か?その重要性とメリット
新規事業の必要性を考える上で、まず押さえておきたいのは企業成長と存続の観点です。前章で触れたように、市場の変化が激しい現代では一つの事業だけに依存していては将来の安定が保障されません。既存事業が現在順調でも、環境変化や競争激化によって数年後には停滞してしまう恐れがあります。実際、米国の著名企業でもわずか数年で業績悪化や市場退場するケースが珍しくありません。
例えば、かつて書店チェーン最大手だったボーダーズ社やDVDレンタルで一世を風靡したブロックバスター社は、デジタル化の波に乗り遅れ、AmazonやNetflixといった新興企業に市場を奪われて姿を消しました。このような例が示す通り、現状の成功体験に安住すると大企業であっても瞬く間に市場から退場しかねないのです。
したがって、企業が長期にわたり成長・存続するためには、常に新たな事業の柱を育て続けることが不可欠です。特にデジタル革命やAI技術の進展により、ビジネス環境の不確実性は高まっています。今日の常識や成功モデルが明日には陳腐化する可能性すらあります。こうした不確実性の時代において、正解が事前にわからない新規事業への挑戦こそ、人間の創造性と洞察力を発揮する場になるとも指摘されています。言い換えれば、新規事業に挑戦し続ける企業だけが、時代の変化に適応し新たな価値創出を続けられるのです。
また、新規事業への取り組みは企業文化や人材育成の面でも大きな意味を持ちます。現状維持ばかりを志向する組織では社員のチャレンジ精神が育ちません。逆に、新規事業に挑戦する文化を醸成すれば、社員が失敗を恐れず創意工夫する風土が根付き、結果として既存事業にも良い影響を与えます。「新規事業創出の取り組みが組織文化にもたらす効果」にも目を向けることが大切だとする指摘もあります。新規事業への挑戦そのものが、社員の成長機会となり組織に活力を与える側面も見逃せません。
さらに、経営トップや投資家の視点から見ても新規事業への期待は非常に大きくなっています。マッキンゼーのグローバル調査(2021年)によれば、半数以上のCEOが新規事業構築を自社のトップ3優先事項に挙げ、約21%のCEOにとっては最優先課題となっています。また、多くの企業経営者は今後5年間で自社の総収益の50%は新規事業から生まれると見込んでいるとの報告もあります。これはつまり、トップマネジメントが将来の成長エンジンとして新規事業に強い期待を寄せている証拠です。
同時に、投資家の視点でも「既存事業で生み出される1ドルよりも、新規事業で生み出される1ドルの方が評価が高い(市場から歓迎されやすい)」とされるとの指摘があります。要するに、市場や株主から見ても新規事業への投資は将来の企業価値を高めるカギと映っているのです。
以上の点から、新規事業に取り組む必要性を整理すれば以下のようになります。
- 継続的成長とリスク分散:
単一事業依存のリスクを下げ、将来の成長エンジンを複数持つために不可欠。市場変化に対する企業のレジリエンス強化にもつながる。 - 技術革新への適応:
デジタル化・AI時代の不確実性に対応し、イノベーションを起こし続ける組織となるため。既存知識が急速に陳腐化する中で、新規事業挑戦は企業に学習と変革を促す。 - 組織文化と人材育成:
挑戦を奨励する企業文化を育み、社員の創造性やアントレプレナーシップを引き出す。停滞を防ぎ、組織全体に活力と学習効果をもたらす。 - 経営戦略上の期待:
経営トップや投資家から見て、新規事業は企業価値向上の重要施策。CEOの半数以上が重視する最優先課題であり、市場からの評価も高い。
新規事業に取り組むことは、企業にとって単なる選択肢ではなく生き残りと成長の必須条件になりつつあります。環境変化に対応し続けるための柔軟性、組織の活力向上、将来の収益源確保――これらを実現する上で新規事業開発は避けて通れない道と言えるでしょう。あなたの企業でも、現状の成功に安住せず次の一手を育てる準備を進める必要があるのではないでしょうか?
新規事業の現状:成功率の低さと投資動向
新規事業の必要性は高いものの、現実には新規事業の成功率は決して高くありません。国内外の調査結果を見ると、大企業における新規事業の成功率は概ね20~40%程度にとどまることがわかります。つまり裏を返せば全体の半数以上~8割近くは満足な成果を上げられていないのです。
例えば、パーソル総合研究所が2021年に発表した大企業対象の調査では、「自社の新規事業開発が成功している」と答えた企業は30.6%、逆に「成功に至っていない」は36.4%という結果でした。残り約33%は「どちらとも言えない」という回答で、明確に成功と言える企業は全体の3割程度に過ぎません。またこの調査では企業規模や売上高による成功度の差は見られなかったと報告されており、大企業だから有利・成功率が高いというわけでもないことが示唆されています。
さらに経済産業省(中小企業庁)の分析でも、新規事業に取り組んだ企業のうち「売上や利益が増加傾向にある」と答えた企業は3割前後にとどまることが指摘されています。つまり新規事業に挑戦して実際に業績拡大(収益化)まで達成できている企業は3社に1社程度という厳しい現状です。逆に言えば新規事業で期待した収益増を得られていない企業が約70%も存在することになります。
また、アビームコンサルティングの調査(2018年)では、大企業が立ち上げた新規事業のうち累積の赤字を解消できた(損益分岐点を超えた)ものはわずか7%との報告もあります。これは言い換えれば93%もの新規事業が投下資本を回収できず失敗していることを意味し、新規事業の収益化がいかに難しいかを物語っています。
他の調査でも概ね同様の傾向が見られます。2023年に行われたある国内アンケート(スーパーソフトウエア社調査)では、「自社の新規事業は成功している」と感じている層は約40%に留まり、逆に「あまり/全く成功していない」と感じる層が約60%を占めました。この結果からも、6割の企業は自社の新規事業を「どちらかと言えば失敗気味だ」と認識していることがわかります。
実際、前述のアビーム調査をさらに詳しく見ると、新規事業の検討開始から事業立ち上げに至る確率が45%、単年度黒字化できる確率は17%、累損解消まで至る確率7%というデータも報告されており、どの指標をとっても成功へのハードルが高い状況です。このように、「新規事業は千に三つ(千本の矢を放って当たるのは三本程度)」とも表現されるほど低い成功確率が浮き彫りになっています。
では、新規事業への投資規模や資金調達はどのようになっているのでしょうか。調査によれば、大企業が新規事業に充てる初期投資は比較的小規模に始めるケースが多いようです。2023年に行われたmichinaru株式会社の調査では、大企業の新規事業推進部署における初年度予算について、最も多かった回答は「100万円以下」で23.8%、次いで「300万円~1,000万円」が19.0%、「1,000万円~1億円」が11.9%という結果でした。
初年度から億単位の潤沢な予算が付与されるケースは稀で、まずは数百万円~数千万円規模で小さく始め、成果に応じて追加投資するといった段階的投資のアプローチが一般的と言えます。実際、一部の企業では「明確な予算枠を持たず必要な都度に申請」といった柔軟な資金拠出の仕組みをとっている例もあり、スモールスタートで検証し成功の芽が見えれば本格投資という流れが主流のようです。
資金の出所に関しては、多くの場合、企業は新規事業に自社の内部資金(自社予算)を充てているのが実態です。日本企業の場合、政府の補助金・助成金など公的資金の活用はまだ少数派であり、社内にノウハウがないことや申請手続きの煩雑さもあってハードルが高いと指摘されています。野村総合研究所の調査(2022年)によれば、ニューノーマル時代に利用可能な各種補助金・支援制度は増えているものの、それらを実際に活用できている企業はごく一部で、多くの企業にとって公的資金活用の「最初の一歩」のハードルが高い現状が明らかになっています。
一方、グローバルな視点で見ると、大企業による新規事業投資は近年ますます活発化しています。特にコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)と呼ばれる大企業の社内VC部門の設立・活用が顕著です。2020年以降に新設されたCVCは世界で300以上にのぼるとの報告もあり、多くのグローバル企業が自社内部だけでなくスタートアップへの投資を通じて新規事業機会を探索しています。
また経営トップの意識も大きくシフトしており、マッキンゼー社の2023年グローバル調査では半数以上のCEOが「新規事業の構築」を自社のトップ3優先事項に挙げ、CFO(最高財務責任者)の過半数も「最も重要な戦略アクションは新規事業の構築だ」と回答しています。このように海外では、トップ自ら新規事業にコミットし積極投資する動きが一般化しつつあり、市場からの期待も非常に大きいのです。
グローバル企業の新規事業への期待度合いを示すデータとして、EYパルテノンの調査結果も興味深いものがあります。それによれば、大企業の45%が過去に年間1億ドル以上の売上を生む事業を立ち上げた経験がある一方で、そうした年間1億ドル超の新規事業がさらに10億ドル以上の規模(企業全体のゲームチェンジャーとなる規模)に達したケースは全体の10%未満に留まるとされます。
つまり、多くの企業が中規模の新規事業成功(数億~数百億円規模の収益化)までは経験しているものの、企業全体を変革するような超大型事業に育て上げることは極めて難しいことを示しています。この現実も踏まえ、近年では「ポートフォリオ経営」の発想、すなわち複数の新規事業に並行して投資し、その中から一部でも大きく成長すれば全体として成功とみなす考え方が広がっています。
新規事業の現状は成功率20~40%前後と決して高くなく、多くの企業が収益化まで苦戦している実態がある一方で、企業は新規事業への投資自体は拡大傾向にあり、複数の新規事業に挑戦するポートフォリオ戦略が重要になってきているということです。
新規事業が失敗する主な原因とは
新規事業の成功率が低い背景には、様々な失敗要因が存在します。多くの企業が直面する共通の課題を知ることで、失敗の確率を下げるヒントが得られるでしょう。ここでは、最新の調査結果や分析をもとに新規事業が失敗する主な理由を整理してまいります。
主な失敗要因データから見る課題
2023年に実施されたスーパーソフトウエア社の調査では、新規事業が「成功に至っていない」と回答した約598名に対し、「その失敗の要因は何だったか」を尋ねています。その結果、次のような理由が上位に挙げられました。
- アイデアの質の問題(21.6%):
「そもそもアイデアがあまり良くなかった」。市場ニーズに合致していないなど、独自性・優位性に欠けるアイデアでは成功は難しいことを示唆しています。 - 社内調整の不備(20.5%):
「社内調整がうまくいかなかった」。関係部署間の連携不足や経営層との調整が不十分で、社内で合意形成・リソース確保ができずプロジェクトが頓挫してしまうケースです。 - 市場・競合要因(計約30%):
「強い競合相手がいた」(13.9%)、「新規事業の市場環境が悪かった」(16.8%)。競争優位を築けないまま埋没してしまうなど、タイミング悪く市場縮小期に当たってしまった例です。 - 顧客ニーズの誤り(9.9%):
「顧客のニーズがあまりなかった」。顧客の本当の課題を見誤り、作った製品・サービスが刺さらなかったケースです。 - コスト・収益性の問題(16.8%):
「想定よりコストがかかりすぎた」。開発・マーケティング等に予想以上の費用がかさみ資金不足に陥るなど、収益モデルの見積りが甘く赤字が膨らんだ例です。
こうしたデータから浮かび上がるのは、「アイデアの妥当性」と「社内の推進体制(調整力)」が特に大きな失敗要因になっているという点です。実際、同調査でも「今後新規事業成功のために強化すべき能力」として、「実行に向けて多様な人材を巻き込む力」(19.4%)がトップに挙げられています。これは言い換えると、良いアイデアを出すことと、それを社内外の協力を取り付けて実行に移すことの両方が不足しているとの分析です。
失敗パターンの類型と大企業特有の課題
新規事業の失敗要因は今述べたように多岐にわたりますが、フィンチジャパンの分析によれば大きく4つの典型パターンに分類できるとされています。
- 顧客ニーズの見極め不足:十分な市場・ユーザー調査をせず、顧客の本当の課題を捉え損ねたまま製品/サービス開発を進めてしまうケースです。経営層の思い込みや社内論理が優先され、市場から乖離したものになってしまう失敗パターンです。
- 市場参入のタイミングミス:投入時期が早すぎる・遅すぎることで需要を逃すケースです。技術やトレンドの成熟度を読み違え、せっかくのアイデアも時機を逸して失敗に至る例と言えます。
- 経営資源の不足:必要な人材・資金・技術などリソースが足りず計画倒れになるケースです。大企業とはいえ、新規事業には専任人員や十分な予算が割かれず、途中で息切れしてしまうことがあります。
- 協業判断の誤り:他社との提携や社内他部門との連携の失敗によるケースです。コア能力が足りないのに単独で突き進んでしまう、逆に外部パートナーに依存しすぎて主導権を失うなど、協業戦略のミスが原因となるパターンです。
上記のうち、1と2は企画・マーケティング段階での躓き、3と4はローンチ後の拡大・運営段階での失敗と言えるでしょう。つまり新規事業の失敗は「企画段階」と「実行段階」の双方に潜むことがわかります。
特に大企業の場合、これらに加えて特有の組織的課題も指摘されています。よく言われるのが、「失敗を恐れる社風」や「社内手続きの遅さ」です。既存事業で成功した経験があるほど、その延長線で物事を考えがちになり革新的アイデアを阻む風土が生まれるなど、短期的な業績を優先するあまり長期投資に二の足を踏む傾向が強まることがあります。
実際、ソフィア総研の分析でも、「既存事業の成功モデルに固執して新しいアイデアを排除する」ことや「短期業績を優先し長期投資を躊躇する」といった大企業特有の失敗要因が挙げられています。
また、前述のmichinaru社の調査でも、新規事業推進部署の初年度の悩みとして「ノウハウ不足」や「既存事業側の非協力・部署間の壁」が上位に挙がりました。現場レベルでは新規事業に熱心でも、中間管理職層が無関心・消極的であるケースも多く報告されており、経営陣と現場の間で目的やビジョンを共有することの重要性が指摘されています。要するに、社内の理解不足や協力体制の欠如が大きな障壁となっているのです。
失敗要因から学ぶべきこと
以上のように、新規事業が失敗する理由は「顧客」「市場」「社内」「資源」など多面的です。一見ハードルの高さばかりが目立ちますが、逆に言えばこれらの課題を事前に認識し対策を講じることで、失敗確率を下げ成功確率を高めることは可能だとも言えます。実際、成功企業のケースを見ると、
- 徹底した顧客ニーズの調査・検証(顧客起点の発想、定量的な課題把握)
- トップマネジメントの強力なコミットメント(経営陣が率先して支援し、失敗を許容する姿勢)
- 社内外の知見活用と迅速な実験(オープンイノベーションによる知識補完、アジャイルなプロトタイピング)
- 適切な協業による不足リソースの補完(外部パートナーとの連携で自社にない資源を確保)
- 失敗を恐れない組織文化の醸成(チャレンジを奨励し、学習サイクルを回す風土)
といった共通点が見られます。新規事業開発は失敗がつきもののチャレンジングな取り組みですが、社内風土の改革と戦略的なプロセス実践によって成功の芽を着実に育てることができるのです。
新規事業成功のポイント:成功率を高めるために
前章で挙げた失敗要因を踏まえると、新規事業を成功に導くために注力すべきポイントが自ずと浮かび上がります。ここでは、数少ない成功例に共通する要因や、専門家が指摘する成功率向上のための戦略的アプローチを整理していきます。
1. 顧客起点のアイデア創出と市場適合性
新規事業のアイデアは何より顧客ニーズに根差していることが重要です。ただ斬新なだけでなく、市場の不満や潜在的ニーズを的確に捉えたものであることが成功への第一歩となります。成功した新規事業の多くは、ローンチ前に徹底した市場調査とユーザー検証を実施し、自社が提供すべき価値を磨き上げています。具体的には、
- 潜在顧客へのヒアリングや観察によって真のペインポイントを発見する
- 試作品やテストマーケティングを通じてフィードバックを収集しアイデアを洗練する(いわゆるリーンスタートアップ的手法)
- 定量データを活用し、経営層の思い込みではなく客観的根拠に基づいてGo/No Go判断を行う
などが挙げられます。ポイントは、「良い製品を作れば売れる」は幻想だと認識し、「売れる製品とは何か」を顧客から教わる姿勢を持つことです。また、社内のアイデアを活性化する取り組みとして社内ビジネスコンテストの開催なども有効でしょう。社員から幅広くアイデアを募り、多様な発想を引き出すことで、自社のリソースや強みに基づきつつも市場に響くテーマを見出すチャンスが生まれます。
2. 経営トップのコミットメントと社内体制整備
経営陣の強力な支援とコミットメントなくして、新規事業の成功はあり得ません。マッキンゼーの指摘するように、もしCEOが本気でコミットできないなら新規事業に手を出すべきでないとも言われるほどです。トップが果たすべき役割としては、
- 明確なビジョンの提示: 新規事業の位置付けや目指す方向性を示し、組織内に共有する
- 意思決定の迅速化: 大企業特有の承認フローの遅さが致命傷とならないよう、トップ直轄で重要課題を迅速に裁く(ガバナンス体制の工夫)
- 人的・資源的支援: 人材の抜擢や予算配分などで、新規事業チームに必要十分なリソースを与える
- 心理的安全性の担保: 万一失敗しても即座にキャリアを傷つけるようなことはしないと約束し、安心して挑戦できる環境をつくる
特にCEO自らが「失敗しても責めない、一緒に学ぶ」という姿勢を示すことは、社員のチャレンジ精神を引き出す上で極めて重要です。一方で、経営トップだけでなくミドルマネジメント層の理解と協力も欠かせません。現場が新規事業推進に燃えても、中間管理職が既存事業優先で非協力的では前に進みません。
このため、ミドル層にも新規事業の意義を納得させ巻き込むために、定期的な経営トップとの対話や、評価制度の見直し(新規事業に貢献した人を正当に評価する仕組み)などを導入する企業も出てきています。要は、組織全体で「新規事業は会社の未来に不可欠」という共通認識を醸成することが成功の土台となるのです。
3. 十分なリソース投入と外部活用の柔軟性
新規事業は「小さく生んで大きく育てる」ものとはいえ、初期段階から最低限必要な人材・資金は投入する覚悟が必要です。専任チームを置かず兼務ばかりでは事業スピードが出ずに失敗するケースが多いため、思い切って有望人材を新規事業にアサインするくらいの決断も求められます。また資金面でも、前述の通り多くの企業は数百万円~数千万円程度で検証を開始していますが、成果が出始めた段階で適切に追加投資を行うことが成長加速のカギとなります。
さらに、自社に不足するリソースを外部で補完する柔軟性も重要です。技術的に足りない部分は大学やスタートアップと協業する、資金面で有望ならCVCやVCから出資を仰ぐ、公的助成金も使えるものは使う、といったオープンイノベーションの発想です。特に最近は自治体や政府系の新規事業支援策も充実しつつありますから(例:東京都の創業助成事業など)、アンテナを高く張って使えるものは何でも使うという姿勢が成功確率を上げるでしょう。
新規事業開発支援に特化したコンサルやプログラム(アクセラレーター等)を活用する企業も増えています。要は、「社内だけで完結しようとしない」ことが大切です。自社の足りないピースを補うための外部リソース活用は、昨今では恥ではなく賢い戦略と見なされています。
4. 迅速な実行と学習サイクル(スピード重視)
かつて大企業の新規事業は「腰を据えてじっくり検討」が常でしたが、近年はスピードの重要性が強く認識され始めています。前述のBCG調査では大企業の48%が「自社の新規事業の市場投入スピードはスタートアップより遅い」と自己評価しており、多くの経営者が「時間をかけすぎて競合に先を越された苦い経験」を挙げています。
この反省から、「初期段階で迅速に動けば成功率は高まる」という認識が広がり、アジャイル開発やリーンスタートアップ手法を取り入れて開発期間短縮に努めるケースが増えています。
実際、ある大手企業ではアイデア着想から1年以内に試作品を市場投入し、ユーザーからのフィードバックを踏まえて改良を重ねることで、従来数年かかっていた市場投入までの期間を大幅短縮した例も報告されています。平均的には新規事業のアイデア創出から市場投入まで5~6年を要するとの調査もありますが、近年は可能な部分から素早く市場に出し「走りながら学ぶ」姿勢が主流になりつつあります。
成功企業は総じて試行錯誤のサイクルをいかに早く回すかに注力しており、たとえ小さな失敗があっても迅速に方向転換(ピボット)することで大きな失敗を防いでいます。要するに、完璧を期してローンチを遅らせるより、不完全でも市場でテストして学習する方が最終的な成功に近づくという考え方です。
5. ポートフォリオ戦略(多数の挑戦と集中投資)
最後に強調したいのがポートフォリオ戦略の重要性です。新規事業の成功確率が低い以上、単発のチャレンジに全てを賭けるのはリスクが高すぎます。むしろ、複数の新規事業を並行して立ち上げ、小さく産んでは取捨選択し、見込みのあるものに資源を集中するというアプローチが合理的です。いわば「多産多死」を恐れず打席(挑戦機会)を増やす戦略です。
これは単に数打ちゃ当たるという話ではなく、組織として継続的に新規事業創出に取り組むこと自体が能力向上につながるという効果もあります。実際、連続的に新規事業を立ち上げる企業では、失敗した案件から学んだ知見を次に活かすことで成功3に対し失敗1程度の高い打率を実現している例もあるといいます。
前述のEYパルテノン調査にあったように、大企業の約45%が年商1億ドル級の新規事業を立ち上げた経験を持つ反面、それを10億ドル超のゲームチェンジャーに育てられたのは一握り(<10%)しかいません。だからこそ、企業全体を牽引する巨大事業が1つ生まれれば御の字という発想で、同時に10の種を蒔いて1つ当たれば成功というぐらいの挑戦をする価値があります。
ポートフォリオ戦略を実践するには、社内のリソース配分の考え方も変える必要があります。限られた人材・資金をどう振り向けるか、どの段階でどの案件に集中するか、といった投資判断のフレームワーク(例えばリーン・ステージゲート法など)を整備する企業もあります。重要なのは、失敗を前提にポートフォリオ全体で成功を狙うマインドセットです。
新規事業成功事例の紹介
ここでは、大企業が新規事業を立ち上げ成功させた具体的な事例を2つご紹介します。どちらも従来の主力事業から一見「畑違い」に見える新規事業に挑戦し、大きな成果を収めた例です。それぞれのケースから、前章までに述べた成功要因がどのように体現されたかを読み取ってみましょう。
ケース1:富士フイルム – 写真フィルムから化粧品・医療への大胆転換
富士フイルム株式会社は、その社名が示す通り元々は写真フィルムを主力とする企業でした。しかしデジタルカメラの台頭でフィルム需要が急減した2000年代、富士フイルムは培ってきたコア技術を活かしつつ全く新しい分野への展開を図ります。その一つが化粧品事業「ASTALIFT(アスタリフト)」でした。
一見「フィルム会社が化粧品?」と驚かれましたが、実はフィルムの材料研究で蓄積したコラーゲンや抗酸化に関するナノ技術が肌ケアに応用できることに着目したのです。写真フィルムの主要成分であるゼラチン(コラーゲンの一種)を極限までナノ化する技術や、フィルムの色あせを防ぐ抗酸化技術は、肌のハリ維持やエイジングケアに通じるものでした。まさに「非連続の連続」とでも言うべき発想転換で、既存技術の新用途開拓に成功したのです。
富士フイルムは経営トップの決断力も際立っていました。当時の古森重隆社長(後に会長)は、フィルム事業の斜陽化をいち早く察知し「第二の創業」としてヘルスケア分野への進出を打ち出します。周囲に十分な情報が無い中でも直感を信じて大胆に舵を切ったと言われ、研究所内にも「新しいことをやらねば」という前向きな空気が生まれました。
同時に、平時から温めていた技術の”芽”を活かした点も重要です。フィルム全盛期から細々と続けていたコラーゲン研究などの種があったからこそ、追い詰められてから慌ててゼロから始めるのではなく「余裕のあるうちに新事業の芽を摘まずに残していた」ことが成功につながったと分析されています。
結果として富士フイルムの化粧品事業はヒットし、同社はさらに医療診断機器や再生医療など広くヘルスケア領域に事業拡大しました。現在ではヘルスケア・材料事業が写真関連事業を上回る収益の柱となっており、見事に事業構造の転換(第二の創業)を成し遂げた成功例として国内外で高く評価されています。
ケース2:日本郵政×Yper – 社外連携で生み出す宅配ソリューション
2つ目の事例は日本郵政グループがスタートアップ企業と協業して開発した置き配バッグサービス「OKIPPA(オキッパ)」です。日本郵便(日本郵政グループ)はご存知の通り郵便・宅配事業の大手ですが、近年ECの拡大に伴う宅配需要増加で再配達や人手不足が深刻な課題となっていました。
そこで同社は、自社単独では解決が難しいこの課題に対し、ベンチャー企業のYper(イーパー)株式会社と提携。簡易な宅配ボックス代替となる折りたたみ式宅配バッグ「OKIPPA」を共同開発したのです。
OKIPPAは集合住宅のドアに吊して使える簡易バッグで、受取人不在でも宅配物を入れて置ける仕組みです。従来の大型宅配ボックスは高価・場所を取るなどの普及課題がありましたが、OKIPPAは低コストで設置スペースも不要という利点があります。さらに配送各社の専用アプリと連動して配達状況を通知でき、盗難防止ワイヤーも付属するなどユーザー目線の工夫が凝らされています。
日本郵便はこのOKIPPAを2020年に実証実験し、その効果を確認した上で2021年には10万個を無料配布するという思い切った施策に出ました。結果、利用者が急増し再配達率の低減や配達員の負担軽減につながることが期待されています。
この事例は、大企業が新規事業を成功させる上でオープンイノベーションの力をいかんなく発揮した例と言えます。日本郵政グループは自社内にもアイデアや資源はあったでしょうが、課題解決のためにベンチャーの斬新なアイデア・スピード感を取り入れる道を選びました。自前主義にこだわらず「ないものは外から」という柔軟さが奏功したのです。
その他の成功例と共通点
上記2例以外にも、例えばソニーは社内ベンチャーから生まれた家庭用ゲーム機「PlayStation」が既存家電事業を凌ぐ収益源に成長した有名な成功例ですし、リクルートは企業文化として事業創造を奨励し続けることでオンライン飲食予約「ホットペッパーグルメ」等いくつもの新規事業を世に送り出しています。
またヤマト運輸はEC時代を見据えた新サービス開発(宅配ロッカーやITを活用した仕分け効率化など)に積極投資し成果を上げていますし、ダイハツ工業は高齢者向けの送迎支援システム「らくぴた送迎」を立ち上げ自動車の新しい付加価値サービスを創出しています。
これら成功企業に共通するのは、やはり顧客ニーズへの深い洞察と社内外のリソースを結集した実行力、そしてトップの支援の下でスピード感を持って試行錯誤を重ねた点です。
富士フイルムのように自社の強み技術を活かして大胆に事業転換した例、日本郵政のように外部パートナーとの協業で新サービスを創出した例など、大企業の新規事業成功事例からは多くの示唆が得られるということです。
まとめ:新規事業の未来と挑戦へのエール
本記事では「新規事業とは何か」という定義から始まり、その必要性、現在の成功率の実態、失敗要因と成功のポイント、さらには具体的な成功事例まで包括的に見てまいりました。新規事業開発は決して容易ではありませんが、だからこそ挑戦する価値がある営みです。成功確率の低さゆえに尻込みしたくなるかもしれませんが、挑戦しなければ0%が続くだけです。
幸いなことに、公的支援策の拡充やオープンイノベーションの潮流など、企業を取り巻くエコシステムは整いつつあります。重要なのは、本稿で整理した実証データと教訓を踏まえ、自社の状況に合った戦略で粘り強く取り組むことです。それによって、きっと少しずつでも成功の可能性は高まるでしょう。
「千三つ」と言われる壁も、絶え間ない挑戦によって突破できるかもしれません。
ぜひ皆さんの企業でも、恐れることなく新規事業の一歩を踏み出してみてください。その挑戦の先から、次代の主力事業やイノベーションが生まれることを期待しています。あなたの会社の次なる成功例は、もしかしたらすぐそこにあるかもしれません。未来の成長に向けて新たなチャレンジを始めてみませんか?