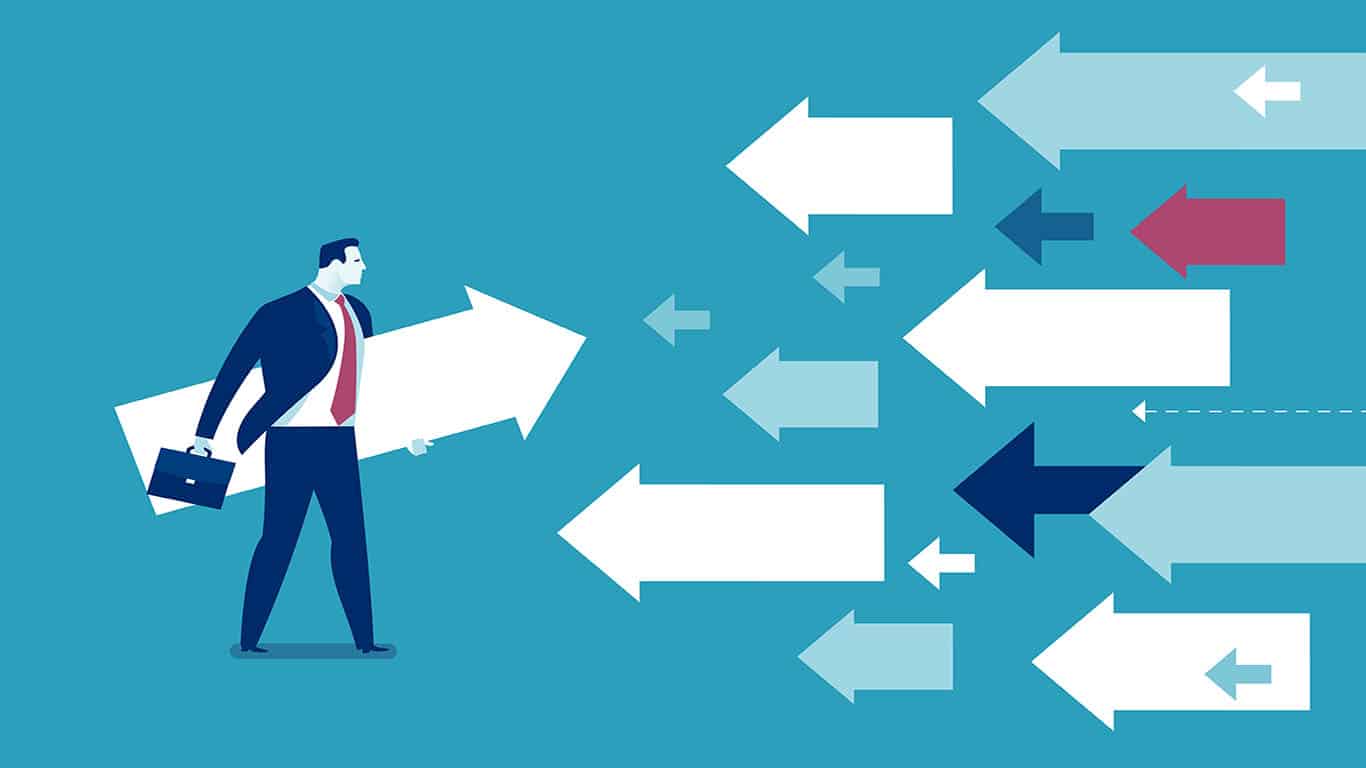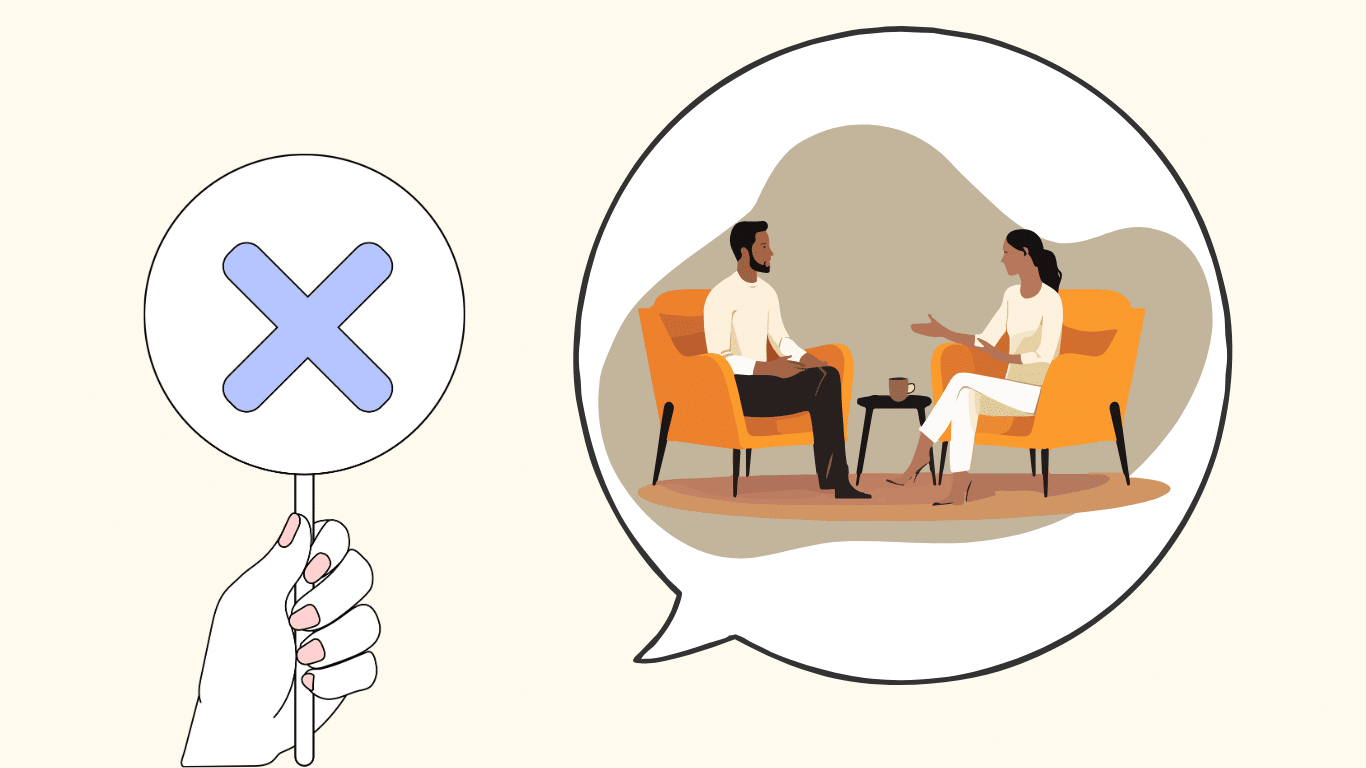ボトムアップとは?トップダウンとの違い・メリット・デメリット・導入法
最終更新日:2023.08.18

目次
ボトムアップ(下意上達)とは、企業経営において現場の意見を経営層が取り入れて意思決定に活かす手法です。
近年、不確実な経営環境に対応するため、現場の知見を積極的に活用するボトムアップが注目されています。
本記事では、トップダウンとの違いやボトムアップのメリット・デメリットを整理し、成功事例や導入ステップ、現場で活かすポイントまで詳しく解説します。
大企業の人事・経営企画ご担当者様にとって、自社の意思決定プロセスを見直すヒントになれば幸いです。
ボトムアップの意味
まずはボトムアップという言葉の意味を整理しましょう。ボトムアップとは、現場の意見を経営層・上層部がしっかり把握した上で意思決定を下す手法です。日本語では「下意上達」とも呼ばれ、従業員のリアルな声やアイデアを経営に取り入れる意思決定スタイルを指します。
現場から吸い上げた意見を活かすことで、商品やサービスのブラッシュアップ、組織の質の向上などにつながることが期待されます。アイデアを提案するのは現場ですが、最終的にその案を採用するかどうかは経営層・上層部が判断します。
ボトムアップでは全員に発言権があり、意思伝達の流れが下層から上層へ向かうため、従来見逃されていた現場の課題解決につながりやすい点が特徴です。一方で対照的な手法であるトップダウン(top-down)は、指示や方針が上位から下位へ一方向に流れるアプローチを指します。
トップダウンは「上意下達」と呼ばれ、限られたリーダー層のみで意思決定を行うスタイルです。両者は意思決定の流れが逆ですが、重要なのは自社の状況に応じて両者の長所を組み合わせて活用することと言えるでしょう。
ボトムアップの重要性
現代は先行きが見通しにくく、不確実性の高い時代です。
数年先の未来でさえ予測が難しく、状況変化が激しくなっています。
そのため、従来のように限られた経営層だけで計画を立てて意思決定を行うトップダウン型のやり方では、変化への対応が後手に回りがちです。
ここ最近の流れとしては、権限を現場に委ねよりリアルな情報や意見をスピーディーに取り入れていくことが重要だとされています。
トップダウン型組織や自立型組織では、このような柔軟な対応が難しく、変化に乗り遅れることで組織の力を落としてしまう可能性もあります。
ボトムアップが組織文化として根付けば、社内コミュニケーションが活発になり、特に上司と部下の間の風通しが良くなります。従業員同士の情報共有が増え、意思決定のスピードも上がり、その内容も柔軟になります。
従業員のモチベーションを高めつつ組織内のコミュニケーションを促進できるのがボトムアップの強みです。
実際、ボトムアップを採用することは、経営層が自らの予測力や計画力に過信せず、社内外から新しい発想を積極的に取り入れる姿勢を示すことを意味します。
現在どんなに好調な業績の企業でも、それは過去の延長でしかなく未来の保証にはなりません。
常に革新を求められる中で、経営層がトップダウン型の「計画通り」に固執するより、現場発の提案を取り入れる柔軟さが企業の持続的成長には欠かせないのです。
また商品やサービスの新規性・競争力を高めるためには、社内外の多様な情報や人材が発信するアイデアの組み合わせ(クロスオーバー)が重要だと言われます。
何がイノベーションの種になるか分からない時代だからこそ、従業員一人ひとりが主体的に意見を出せる環境を整えることが、組織の革新力を高める鍵となります。
どんな社員からどんな新しいアイデアが生まれるか分からない以上、経営者は人事制度上の画一的な物差しだけでなく、従業員の感性や個性にも目を向け、多様な人材が意見を言いやすい風土を作る必要があります。
言い換えれば、「できる変人」と呼べるような個性的で有能な人材をどれだけ多く抱え、活かせるかが新規事業創出の第一歩ともなるでしょう。
トップダウンとボトムアップの関係性
ボトムアップについて詳しく述べる前に、トップダウンとの関係性を整理します。
一見するとトップダウンはボトムアップの反対概念と思われがちですが、必ずしも単純に対立するものではありません。
トップダウンといっても、上層部が現場の意見を全く取り入れず独断で決めるわけではなく、現場の声が意思決定の材料に反映されることもあります。
考えようによっては、全ての意思決定は程度の差こそあれトップダウン的要素とボトムアップ的要素を併せ持つとも言えるのです。
実際には「トップがアイデアを出しトップが最終決定する」度合いが強いか、「現場がアイデアを出しトップが最終決定する」度合いが強いかの違いと捉えられます。
トップダウン型アプローチでは、意思決定のプロセスが一箇所(上層部)に集中するためスピーディーに実行まで移せるという利点があります。
特に緊急対応や方向性の統一が求められる場面では、強いリーダーシップによるトップダウンが効果的です。
一方で、上層部だけで判断することにより現場の細かな状況変化や顧客ニーズを見落とし、誤った指示につながるリスクがあります。
実際、経営陣が現場を十分理解していない場合、トップダウンは現場の実態にそぐわない的外れな指示を出してしまい、従業員のモチベーション低下や非効率を招く恐れが指摘されています。
だからこそ、トップダウンであっても現場からの一次情報をできるだけ取り入れ、経営者自らコミュニケーションを図ることが重要です。
一方のボトムアップ型アプローチでは、現場の最前線で得られた知見が経営に反映されるため意思決定の正確性や納得感が高まる反面、全員の意見を聞いて合意形成するプロセスに時間がかかりがちです。
まさに「船頭多くして船山に上る」という状態に陥り、結論が出るまでにスピード感を欠く場合があります。
また、現場の具体的な問題に集中するため視野が狭くなり、全体最適を見失う懸念もあります。ボトムアップで出た意見が特定部門の最適に偏り、部門間の対立を招くケースも考えられるでしょう。
そのため、上層部は集まった意見をしっかり精査し、組織全体の一体感を損なわないようバランスを取ることが求められます。さらに、多くの意見・提案を集約して検討・フィードバックする必要があり、上層部の負担増大もボトムアップのデメリットと言えます。
現場の声を尊重する姿勢を示すためにも、たとえ採用しない提案であっても理由を説明し、意見を出した社員へ適切なフィードバックを行うことが重要です。
このフィードバック対応にリソースを割く必要がある点も、トップダウンに比べた課題となります。
以上のように双方のアプローチにはメリット・デメリットがあり、組織の状況や目的によって適性が異なります。
たとえば、経営者や上層部に豊富な経験や実績があり迅速な意思決定が求められる場合はトップダウンが効果的ですが、現場の専門知識が重要な業界や複数事業を展開する組織ではボトムアップによって適切な方針決定がしやすくなります。
近年では両者を組み合わせた「トップダウンデモクロシー」と呼ばれるハイブリッド型の手法も提唱されています。
トップダウンデモクラシーでは、経営課題の提示と最終決定は経営陣が行い、その課題解決のための検討や提案出しを現場主導で行うというものです。
このように現場の声を集めながらトップ主導で迅速に意思決定を行う仕組みを導入すれば、変化の激しい環境下でもスピードと現場実態の両立が図れるとされています。
自社のフェーズや課題に応じて、トップダウンとボトムアップを柔軟に使い分けたり組み合わせたりする視点が重要です。
ボトムアップがもたらす効果
では、ボトムアップを導入すると具体的にどのようなポジティブな変化が起こるのでしょうか。
現場の声を経営に活かすボトムアップは、組織の成長につながると言われます。ここではボトムアップがもたらす代表的な効果を整理します。
社員の自己実現とモチベーション向上
ボトムアップを取り入れると、社員の自己実現(self-actualization)につながります。
現場発の具体的なアイデアが組織に積極的に採用されることで、従業員は自分の存在価値を実感し、「会社に貢献している」という手応えを得られます。
こうした経験は仕事への満足度やモチベーションの大幅向上につながり、社員一人ひとりの成長意欲を高めます。自己実現欲求が満たされ能力発揮の機会が増えることで、結果的に各従業員のパフォーマンスが向上し、組織全体の生産性向上にも寄与するでしょう。
社員のモチベーションは必ずしも給与など物質的な要因だけで高まるものではありません。
自分のアイデアや提案が組織に反映され少しずつでも形になっていくこと自体が、従業員にとって大きな喜びであり、働く意義となります。
多くの社員にとって職場は自己実現の場でもあります。
仕事で新しい何かを成し遂げているという感覚は、お金とは別次元で人を奮い立たせ大きな力を発揮させます。
逆に言えば、自分の意見を言っても報われない職場では、「何もしない方が得策だ」という諦めが蔓延しかねません。
前述のような自分の意見やアイデアが無駄になる「言ったもん負け」の文化が根付くと、社員は現状維持に甘んじて挑戦しなくなり、組織の停滞を招きます。
ボトムアップはこの負のサイクルを断ち切り、「自分が発言すれば組織が良くなる」という前向きな循環を生み出す点で意義深いと言えるでしょう。
実際、「言ったもん負け」の対極にある「言ったもん勝ち」の環境を作ることこそが、社員の自律性を促し組織力を高める鍵だと指摘されています。
社員が自主的に行動し意見を述べるようになれば、上司の強いリーダーシップがなくても組織は回るようになります。
上司は明確な目標を示しサポート役に徹するだけでよくなり、現場に任せる範囲が広がるため部下の成長機会もおのずと増えます。
組織全体としても、一人ひとりが判断軸を持ち自発的に動く自律型組織へと近づき、環境変化への適応力が増すでしょう。
このようにボトムアップは従業員エンゲージメント(組織に対する愛着・コミットメント)の向上にもつながるとされています。現場の声が尊重され自分事として会社を良くしようとする意識が芽生えれば、従業員は組織への信頼感や帰属意識を強めます。
実際、ボトムアップ型の制度改革によって従業員のエンゲージメントが飛躍的に高まり、離職率が28%から4%へ大幅改善した企業(サイボウズ)も存在します。
サイボウズでは社員参加型で人事制度を再構築し、制度の充実と全社員への透明な共有を行った結果、社員の会社への信頼と納得感が増し、2005年に28%あった離職率が2012年には4%まで低下しました。
この事例は、ボトムアップにより社員の働きがいが向上し、優秀な人材の定着にもつながった好例と言えるでしょう。
イノベーションの促進
ボトムアップ型の組織では、新しい発想や創造性が組織に生かされやすくなります。
意思決定の過程で社員の小さなアイデアや提案にも耳を傾け、真摯に検討を重ねることで、従来になかった視点のアイデアが生まれやすくなります。
現場から上がってきた斬新なアイデア同士を組み合わせるような柔軟な意思決定が可能になると、社内全体にイノベーティブな雰囲気が醸成され、組織が活性化するでしょう。
ボトムアップによって多様な知見が交流すると、製品やサービスに革新をもたらす可能性が高まります。
実際、近年多くの企業が新規事業の提案制度やデジタルトランスフォーメーションのアイデア募集など、社内からイノベーションの種を見つけ出すボトムアップ施策に力を入れています。
たとえば、株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)では「DelightBoard」という制度を導入し、全社員が自由に新規事業のアイデアや改善提案を匿名で投稿でき、全社員投票により上位案を正式にプロジェクト化する仕組みを構築しています。
このようなボトムアップの取り組みにより、社員発のユニークなプロジェクトが次々と創出され、新規事業の活性化につなげています。DeNAではこのような社内起案制度により、社員提案から生まれた事業が実際に立ち上がっています。
ボトムアップ環境下で社員が自社の未来を主体的に切り拓く動きが出てくること自体、組織のイノベーション力を示すものと言えるでしょう。
さらに、人間には「新しいものを創りだす時に本質的な喜びを感じる」という本能的欲求があるとも言われます。
古くはアリストテレスからヘーゲル、マルクスに至る哲学者たちも、人間の創造性について論じてきました。
マルクスは「たとえ報酬がなくとも人は新しさを創造し続ける」と説きましたが、実際の旧社会主義国では創意工夫が報われない「言ったもん負け」的風土が蔓延しイノベーションが阻害された歴史があります。
この教訓からも明らかなように、前向きな提案が歓迎される組織風土こそがイノベーションを生む土壌となります。
ボトムアップ型の組織では「新しい提案をすれば、採否は別として必ず耳を傾けてもらえる」「良い提案はきちんと評価される」という信頼感が醸成されます。
こうした前向きな姿勢を組織全体で評価する文化があるかどうかが、今後伸びていく企業と停滞していく企業の分かれ道になるでしょう。
顧客満足度の向上
ボトムアップによる現場起点のイノベーションが起これば、従業員のアイデアが反映された新たなサービスや製品が生み出されます。
現場で日々顧客と向き合っている従業員は経営層よりも顧客に近いため、ボトムアップによって顧客ニーズに即した施策を打ちやすくなります。
その結果、製品・サービスがより「顧客が本当に欲しているもの」に近づき、提供価値の向上から顧客満足度アップに直結します。
実際、ボトムアップで生まれた現場視点の改善アイデアがサービス品質を向上させ、顧客から高い評価を得るケースは多々あります。
また、自分の意見やアイデアが採用されモチベーションが高まった従業員は、それまで以上に主体的に顧客対応に取り組むようになります。
現場社員が積極的に顧客とコミュニケーションを図れば、顧客との信頼関係も強化され、結果的に顧客ロイヤルティ(忠誠度)向上にも貢献するでしょう。
一方で、多忙な営業現場では日々の顧客対応に追われ、顧客満足度向上のための施策を考える余裕がないこともあります。
だからこそ、現場のリーダーが率先してボトムアップの姿勢を示すことが重要です。
上司が役職に関係なく最前線の意見に耳を傾ける姿勢を示せば、初めは冷めていた社員も次第に「目の前の業務をどう効率化できるか」「顧客要望をどう製品に活かせるか」を自分事として考え、口を開き始めるでしょう。
逆に、リーダーが何も変わらないまま部下にだけ変革を求めても、社員は動かず最悪の場合は反発や離職につながります。
ボトムアップで顧客志向を高めるには、まず管理職自身が変化を恐れず現場に寄り添う姿勢を示すことが不可欠なのです。
ボトムアップの導入のステップ
ここまでボトムアップの数多くのメリットを紹介してきました。
組織をうまく運営する上でボトムアップは有効な手法ですが、実際に導入する際にはどのように進めればよいでしょうか。
最後に、ボトムアップを組織に導入するための基本ステップを押さえておきましょう。
社員へのアンケート調査の実施
まず、ボトムアップの方針を打ち出す前段階として、社員に対するアンケート調査を行います。
現場から幅広い意見や要望を集め、組織が抱える課題やボトルネックを洗い出すことが目的です。
アンケート結果を分析すると、多くの従業員が不満に感じているポイントが見えてくるかもしれません。
その場合、どの点を改善すべきか、どのような不満があるのかを整理し、具体的な改善案を作成します。現場の声を定量・定性データとして把握することで、経営層も課題の深刻度を認識しやすくなります。
リスクマネジメントの策定
続いて、現状の組織にボトムアップを取り入れる際に想定される細かなリスクを洗い出します。
ボトムアップ導入によって考えられる弊害(意思決定の遅延、対立の顕在化など)や、現場提案を採用した施策が失敗した場合の影響などを検討し、リスク回避策・対処策を事前に定めておきましょう。
リスクが顕在化しても冷静に対処できるよう準備しておくことで、安心してボトムアップ推進に踏み出せます。
経営層にとっても、「最悪の場合の手当」が見えていればボトムアップ型の意思決定にゴーサインを出しやすくなるはずです。
ボトムアップ文化醸成のためのワークショップ開催
いよいよ組織全体でボトムアップを進めていく段階です。まずは経営層から従業員へ、ボトムアップの意義やメリットをしっかり説明し納得してもらいましょう。その上で、現場の雰囲気改革に着手します。
どんな社員でも意見やアイデアを提示しやすい職場の空気づくりを意識的に進めていきます。
具体的には、部署横断のワークショップやブレインストーミングの場を設け、立場に関係なく自由に発言できる機会を増やします。
「発言してもいいんだ」という心理的安全性を高め、参加型の会議文化を育むことが大切です。
併せて、チームビルディング研修やコミュニケーションスキル向上のトレーニングなども実施し、意見交換が活発になる下地を作りましょう。環境面(雰囲気づくり)と人材面(スキルアップ)の両輪からアプローチすることで、ボトムアップ文化をスムーズに浸透・定着させることができます。
ボトムアップのデメリット
ボトムアップには多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。
ここでは考えられる代表的なボトムアップのデメリットと、その対策についてまとめます。
幅広い視野の欠如
前述のように、ボトムアップでは個々の小さな要素に注目するあまり大局的な視野が欠けてしまう恐れがあります。
全体像をうまく把握できないと、プロジェクト単位や事業全体の成功から遠のく可能性があります。
対策として、現場の提案を経営層が採用する際には常に「全社的に見て方向性がずれていないか」をチェックする仕組みを設けましょう。定期的に経営戦略との整合性を検証し、必要に応じて軌道修正することが肝要です。
時間とコストがかかる
ボトムアップ手法は、丁寧に取り入れようとすると意思決定までに時間と人的コストがかかる点もデメリットです。
現場から上がる多数の意見を分析し、試行錯誤を重ねて意思決定するプロセスはトップダウンより複雑で、拙速に進めると破綻する恐れもあります。
対策として、意思決定プロセス自体を定型化・効率化する工夫が必要です。
たとえば、各チームから選出した代表者が一次意見を集約し、経営層との橋渡し役を務めるようにすれば意見集約の効率が上がります。
また、社内公募制度などに応募フォーマットや評価基準を設け、アイデア選別の仕組みを透明化・迅速化するのも有効でしょう。
上層部の負荷増大
ボトムアップでは現場から多くの意見・提案が集まるため、それらを精査して最終判断する経営陣の負担が増える点にも留意が必要です。
従来トップダウンであれば上層部が一方的に決めていた事項も、ボトムアップでは社員との対話や提案対応に時間を割くことになります。
特に提案者へのフィードバックまで丁寧に行おうとすれば、経営層・管理職の工数が圧迫され、本来注力すべき戦略業務に影響が出る恐れもあります。
対策として、提案の受付窓口を人事部やプロジェクト管理部門に設けて一次評価・振り分けを代行したり、管理職間で提案対応を分担したりすると良いでしょう。
加えて、すべての提案に細かく回答するのが難しい場合でも、提案募集の要件を明確化して「あらかじめ提示した条件を満たす提案のみ詳細検討する」などルール化することで、対応すべき案件を絞り込むことができます。
意見の偏り・部分最適化
ボトムアップで収集できる意見は各部門・各職種ごとの現場視点に基づくため、どうしても局所的な問題にフォーカスしがちです。
その結果、ある部門では最適でも他部門では不利益となるアイデアが上がってくる可能性があります。特定部門の意見を重視しすぎると組織全体では不均衡や対立を生むリスクもあります。
対策として、提案を採用する前に経営層が各提案の影響範囲を十分に精査し、他部署への波及効果や相乗効果を評価するプロセスを設けましょう。
全社視点でのメリット・デメリットを検討し、必要に応じて関連部門から追加ヒアリングを行うことで、偏った施策決定を防ぐことができます。
主体性の格差による弊害
ボトムアップを進めると、意欲的に提案・発言する社員と指示待ちで受動的な社員との温度差が顕在化しやすくなります。
放置すると「一部の積極的な社員ばかりが評価され、消極的な社員との間に軋轢が生じる」「発言しない社員がさらに萎縮する」といった弊害につながりかねません。
対策として、マネジメント側が指示待ち傾向の社員へのコーチングを行い主体性を育てることが重要です。
具体的には、発言が少ないメンバーにも個別に意見を聞く場を設けたり、小さな成功体験を積ませる工夫をすることで、自信を持って発言できる人材へと成長させます。
同時に評価制度においても、裏方に徹した人の貢献やチームワークを正当に評価する仕組みを用意し、成果が目立つ人だけが得をする実力主義に偏らないようバランスを取る必要があります。
ボトムアップを成功させるポイント
ボトムアップのデメリットを踏まえても、あらかじめ対策を講じておけばその弊害を最小限に抑えることができます。最後に、ボトムアップを組織で成功させるために押さえておきたい重要なポイントを解説します。
意見を出しやすい雰囲気を作る
ボトムアップでは、従業員から意見が出なければ何も始まりません。
したがって「従業員が上司に気兼ねなく自由に意見を言える雰囲気」を醸成することが第一です。
日頃から上司が部下の声に耳を傾け、提案を歓迎する姿勢を示しましょう。
「こんなこと言ってもいいのかな」と社員が悩むようではいけません。SlackやTeamsなどカジュアルなチャットツールを導入し、役職に関係なくアイデアを発信できる場を用意するのも有効です。
たとえば社内SNS上で「改善提案チャンネル」を開設すれば、普段口下手な社員でも文章で意見を出しやすくなります。
心理的安全性を高める取り組みを継続的に行い、社員が安心して声を上げられる組織風土を育てましょう。
効率の良い意見収集方法の確立
ボトムアップは放っておくと意思決定までに時間がかかりがちです。そこで意見収集の効率化を図ることが成功の鍵になります。先述のようにITツールの活用はもちろん、意見募集→検討→決定までのプロセスを予め定めておくとスムーズです。
たとえば、提案を定期的に募る「アイデア募集イベント」を開催し、期限内に集まった提案を経営陣が一括レビューするサイクルを作るのも一案です。
提案フォーマットも統一し、重要な観点(課題の具体性、期待効果、実現可能性など)を盛り込んでもらうようにすると、上層部も判断しやすくなります。
さらに、中間にミドルマネジメント層を配置して取捨選択や調整を行うことも有効です。現場と経営の両方を理解できる人材に一次フィルター役を担ってもらうことで、経営陣と現場のコミュニケーションが緊密になり、質の高い意見が引き出されやすくなります。
このように、意見を効率良く収集・精査する仕組みそのものをデザインすることが、ボトムアップ推進には欠かせません。
コミュニケーションプラットフォームを充実させる
円滑なコミュニケーションはボトムアップ成功の生命線です。部門の垣根を越えて意見を交換できるプラットフォームを整備しましょう。
具体的には、前述の社内チャットの他にもナレッジ共有ツールや社内FAQデータベースなどを活用し、現場の知見を組織全体で共有・蓄積できる仕組みを作ります。
そうすることで「過去にどんな提案があってどう検討されたか」が社内に蓄積され、提案の質向上と重複防止につながります。
たとえば、社内Wikiに提案と結果を記録しておけば、新しい提案者は事前に類似案をチェックしてから練ることができます。さらに、チャットで場所を問わずリアルタイムに社員の意見を集約できれば、物理的制約に左右されず施策への反映スピードも上がります。これにより、時間や人的コストがかさむ懸念も和らぐでしょう。
双方向・多方向のコミュニケーションを促す
ボトムアップで多くのアイデアを引き出すには、積極的に意見を交わす場を設けることが重要です。
ポイントは一方通行でなく双方向の対話を促進することです。
たとえば経営陣と若手社員との隔月ミーティングや、「現場×経営」のクロストークイベントなどを開催し、お互いの考えを直接伝え合う機会を設けます。
経営層が現場に問いかけ、現場からも経営に質問や提案ができる開かれた議論の場は、組織の凝り固まった上下関係をほぐし新しい発想を生みやすくします。
もし社内に暗黙の上下関係ルールがあり自由な対話を阻害しているなら、それを見直すことも必要です。組織をがんじがらめにしている要素(セクショナリズムや形式主義など)を取り払い、誰もがフラットに議論できる風土を作りましょう。
ミドルマネジメントの活用
ボトムアップ導入時には中間管理職(ミドルマネジャー)の存在が極めて重要です。
ミドルマネジメント層は上層部と現場の橋渡し役として、双方の意図を汲み取り調整する役割を担います。
経営視点と現場事情の両方を理解できる人材が間に入ることで、現場から上がったアイデアを経営戦略に沿う形にブラッシュアップしたり、逆に経営からのメッセージを現場になじむ形で伝えたりできます。
実際、ボトムアップの実施において「ミドルマネジメントができる人材の適切な配置」が成功のカギだと指摘されています。
現場をまとめるリーダー層が機能すれば、上層部と現場のコミュニケーションが緊密になり、現場からもより精度の高い意見が出やすくなるでしょう。ミドル層にはファシリテーター研修などを施し、調整力や対話力を強化しておくことも有益です。
まとめ
経営層・上層部が現場の意見をもとに意思決定を下す「ボトムアップ」は、従業員のモチベーション向上や組織の質の改善につながることが期待され、今や多くの企業が注目しています。ボトムアップの効果を最大限に生かすには、社員が意見を出しやすい雰囲気づくりや円滑なコミュニケーション環境の整備が重要です。
一方で、ボトムアップには時間がかかる・視野が狭くなりがちといったデメリットもあるため、事前にそれらを認識し対策を講じることが肝要です。特に組織の規模や置かれた状況によってはトップダウンの方が適する場面もあるため、自社に最適な意思決定方式を柔軟に選択する姿勢も求められます。
ボトムアップを上手く取り入れる場合は、以上のポイントを意識しつつ組織に合った形で実践してみてください。そうすることで、現場と経営が一体となった円滑な組織運営が実現し、ひいては企業全体のイノベーションと成長につながるはずです。