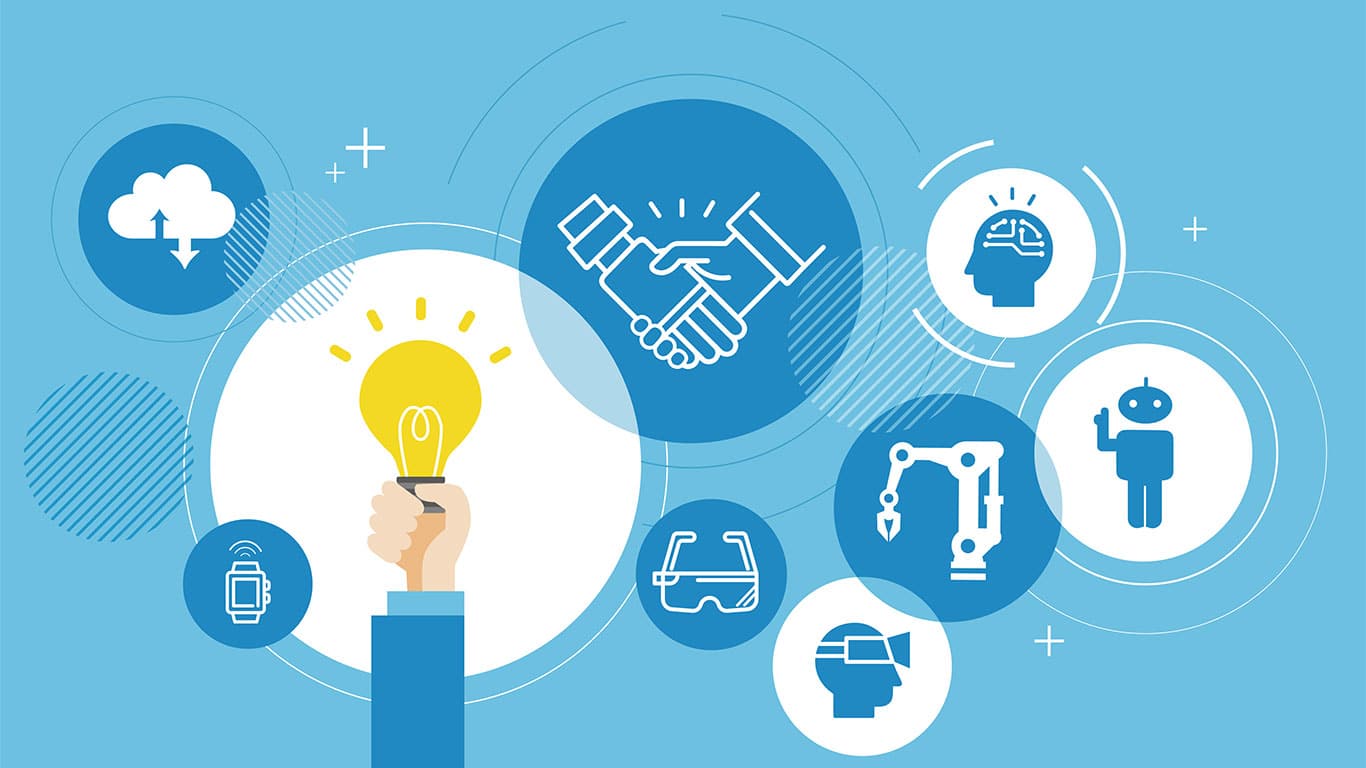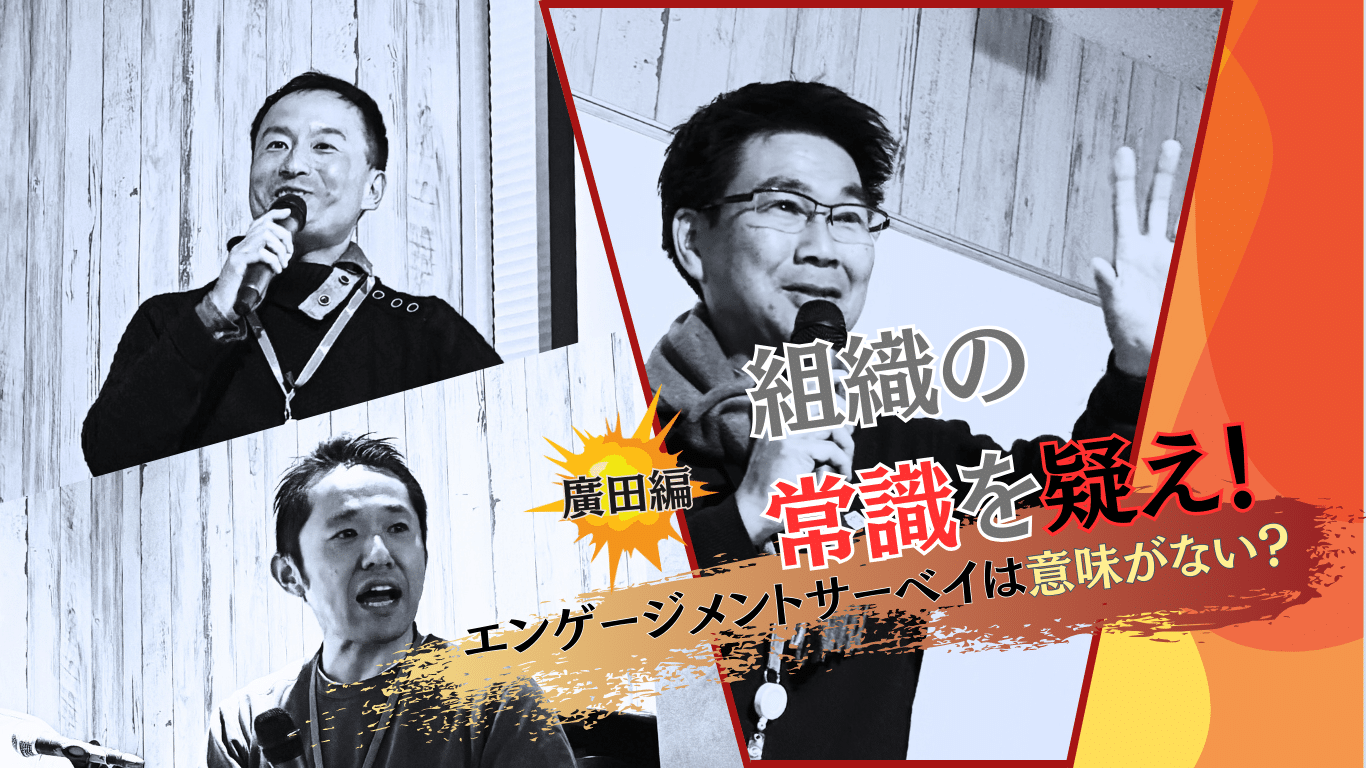提案制度とは?メリットから活性化のコツ、成功事例まで徹底解説
最終更新日:2025.11.02

目次
近年、ビジネスを取り巻く環境変化が激しく、現場の社員が主体的にビジネスの創造や改善に携わることで、より柔軟で変化に強い組織作りを目指す企業が増えています。そして、そのための取り組みの一つとして注目されているのが社内の提案制度です。
提案制度を上手く取り入れて組織力を高めた企業がある一方で、制度だけ作っても形骸化してしまうケースも少なくありません。本記事では、提案制度の概要やメリットから、成功させるポイント、導入ステップ、活性化のコツ、そして成功事例まで詳しく紹介します。
提案制度とはどのような制度か?
提案制度とは、従業員が会社に対して業務改善や新規事業のアイデアを提案し、それを組織的に収集・評価・実行していく仕組みのことです。単なる「提案箱」でアイデアを募集するだけでなく、制度として体系的に運用することで従業員の主体的な参加意識を高め、職場の活性化や業務効率の向上、製品・サービスの品質改善にもつながります。従業員からのボトムアップによる提案は現場の実態に即した具体的な解決策となることが多く、即効性の高い改善をもたらす特徴があります。
提案制度自体は決して新しい概念ではなく、100年以上続く米国企業「3M」でも古くから取り入れられてきた歴史ある手法です。かつて日本企業における提案制度は生産現場のQCサークル(品質管理サークル)のように現場の業務改善が中心でした。しかし現在では、社長や経営幹部では思いつかない現場目線の発想や、新入社員のユニークな視点など社内のあらゆる知恵や情報を経営に活かそうとする取り組みへと進化しています。急速な事業環境の変化により「今までのやり方が通用しなくなるかもしれない」という危機感が広がる中、従来以上に社員の創意工夫を経営に取り入れることの重要性が増しているのです。
提案制度を導入するメリットは何か?
提案制度を導入すると、企業や社員にもたらされるメリットは多岐にわたります。主なメリットを以下に挙げ、その内容を解説します。
経営参画意識の醸成と組織の一体感向上
提案制度を通じて社員が会社の課題解決に関与することで、「自分も経営に参加している」という意識が芽生えます。経営層が会社のビジョンや戦略を共有し、社員の提案を受け止める姿勢を示すことで、現場と経営の間の壁が低くなり社内コミュニケーションの活性化にもつながります。社員一人ひとりが自社の方向性を理解し、自分事として捉えるようになれば経営陣と現場の隔たりが小さくなり、組織全体の一体感が高まります。
弊社ソフィアの調査では、大企業の約8割が社内コミュニケーションに課題を感じていることが分かっています。とりわけ「部門間」(58%)や「経営陣と社員」(42%)の意思疎通に問題があるという結果でした。提案制度はこうした現場と経営層の隔たりを埋め、社員の主体性を引き出す施策としても期待されています。
従業員の問題解決力・提案力の向上
提案制度は社員に「自ら課題を見つけ、解決策を考える」機会を提供します。日々の業務の中で常に改善点を探し、提案を言語化する習慣が身につくことで、社員の課題発見能力や論理的思考力が鍛えられます。実際に「提案すること」を前提に業務へ取り組むと、業務の細部に目が行き届くようになり、創意工夫のスキルアップにもつながります。社員が自身の提案に対するフィードバックを受けるプロセスを通じて、より良いアイデアを生み出す力が飛躍的に向上していきます。
若手社員のモチベーションアップ
提案制度は社員の意欲向上施策としても有効です。自分のアイデアが会社に受け入れられ業務改善に貢献できれば、社員は達成感や自己効力感を得られます。特に若手社員は経営層との距離を感じて意見を飲み込んでしまうケースが少なくありません。提案制度によって上下の壁を取り払い、小さな提案でも実際に試し効果検証まで経験させることで、若手でも「自分の考えで職場を良くできた」という成功体験を積むことができます。この積み重ねがモチベーションアップにつながり、周囲にも良い影響を及ぼします。さらに、会社が社員の意見を尊重し成果を適切に評価すれば、「自分も成長できている」という実感が芽生え、離職防止やエンゲージメント向上にもつながるでしょう。
提案制度にはどんな種類や事例があるか?
ひと口に提案制度といっても、その募集するアイデアの種類や運用形態は企業によって様々です。ここでは、代表的な提案制度の種類とその具体的な事例について紹介します。
新規事業提案制度
主に大企業で多く導入されているのが「新規事業提案制度」です。例えば、リクルートグループでは若手社員を対象に新規事業アイデアを募る制度「Ring」を毎年実施しています。事業プランの公募から一次・二次の審査を経て最終審査まで行われ、社内から将来有望な新規事業を選抜しています。実際にこの制度から結婚情報誌の『ゼクシィ』やオンライン学習サービス『スタディサプリ』など数々の新規事業が創出されました。
また、サイバーエージェントでは新規事業育成制度として、事業の成長段階を営業利益や推定時価総額で区分し、一定期間内で昇格・降格の基準を設けて管理する仕組みを運用しています。同社の新規事業提案制度は社員の成長促進に留まらず、提案者が実際に経営の意思決定に関わるレベルにまで踏み込んでいる点が特徴です。このように、新規事業提案制度は将来の事業の柱を社内から生み出すと同時に、社員にとっては大きな挑戦と成長の機会となります。
商品・サービスなど業務に関わる改善提案制度
日々の業務プロセスや製品・サービスに関する現場目線での改善アイデアを募集する「業務改善提案制度」も、多くの企業や団体で活用されています。例えば自治体では、さいたま市が職員による業務改善の発表会「カイゼンさいたマッチ」を開催しています。職員一人ひとりが日常業務で工夫した改善事例を共有し合い、全体の業務効率向上やサービス品質向上につなげる取り組みです。このように現場の些細な工夫でも組織全体で共有し評価する場を作ることで、職員の改善意欲を引き出しています。
社内制度の改善提案制度
人事制度や福利厚生、教育研修制度など社内制度に対する改善提案を社員から募集する制度もあります。例えば、自社の働き方改革やダイバーシティ推進の一環として、育児・介護支援制度や在宅勤務制度に関する社員の意見を募るケースです。
西武ホールディングスでは、グループ横断の風土づくりを目的に「ほほえみFactory」というワークショップを実施し、グループ各社の社員が経営層に直接アイデアを提案しています。そこでは新規事業や社会貢献の提案だけでなく、社内制度や職場環境に関する改善提案も生まれており、実際に制度改訂につながった例もあります。社内制度の提案制度は、社員の声を経営に反映することで組織風土をより良くし、社員エンゲージメントを高める効果が期待できます。
業務プロセスの改善提案制度
社内の業務プロセスの効率化や安全性向上に特化した提案制度もあります。例えばトヨタ自動車で浸透している「カイゼン活動」は、社員が提案した業務プロセス改善策を実際に実行して効果を報告すれば報奨金がもらえる仕組みです。報奨は1件あたり数百円程度と小さいですが、重要なのは「提案して終わり」ではなく必ず実践して効果検証まで行う点にあります。会社が改善提案をきちんと評価し、わずかでも報酬という形で応えることで、社員の継続的な改善意欲を引き出しています。
例えば岐阜県の未来工業株式会社では、1977年に「1提案につき500円支給」の制度を導入して以来、40年以上にわたり全社員から改善提案を集め続けています。小さな工夫でも積極的に提案させ、それを会社が評価し続けることで、次々と新しい製品開発や業務効率化を実現しているのです。
職場環境に関する改善提案制度
職場環境や働きやすさに関するアイデア募集も有効です。例えば「オフィスに社員がリラックスできるカフェスペースが欲しい」という現場の声から休憩スペースを新設し、部署を超えた社員同士の交流が生まれたケースがあります。雑談を通じて他部署の業務に興味を持ったり、新たなアイデアが思いついたりする効果がありました。
このように、電気の消し忘れ防止の張り紙といった小さな提案でも良しとする風土を作り、提案のハードルを下げることが組織改善には必要です。職場環境に関する提案制度は、社員の働きやすさを向上させると同時に、社員自身が主体的に職場を良くしていく企業文化の醸成にもつながります。
提案制度を成功させるためのポイントは何か?
多くの企業で提案制度が導入され、その成功例や失敗例が蓄積されています。ここでは、提案制度を効果的に機能させるための重要なポイントを解説します。
経営情報をオープンに共有する
提案制度は社員から画期的なアイデアを募ること自体が目的ではなく、提案のプロセスを通じて社員一人ひとりに「自分も経営に参画している」という意識を持たせることも大きな目的です。そのためにはまず、経営側が可能な限り経営に関する情報を社内にオープンにすることが欠かせません。
現場の社員は自分の担当業務の情報は把握できますが、会社全体の状況や経営層の考えは日常業務だけでは見えにくいものです。経営層や管理職が企業のビジョンや戦略、現状の課題を積極的に発信し共有する場を設けましょう。社内ポータルサイトや社内報、全社ミーティング、社内SNSなど様々な社内コミュニケーション手段を活用して、双方向の情報共有機会を作ることが重要です。
経営側からの情報発信によって社員は会社の方向性を理解しやすくなり、自分の提案が経営課題とどう結びつくかを考えられるようになります。こうした土台があることで、社員から建設的な提案が生まれやすくなるのです。
社員の問題意識・解決能力向上を支援する
社員が的確な提案を行うには、提案の前提となる課題認識や目的が明確であることが大切です。新入社員などは、提案というよりただの要望を述べてしまうことも多く見られます。「○○が不便だから改善してほしい」という要望を、「どうすればそれを実現できるか?」という具体的な提案に昇華させるためには、社員への気付き促しと支援が必要です。
まずは日常業務や職場環境で「なぜこれはこうなっているのか」「もっと良いやり方はないか」と身近な問題点を探す習慣づけから始めます。そして、一担当者の視点・事業部門全体の視点・経営者の視点と、徐々に高い視座で問題を捉えられるよう周囲(上司やメンター)が働きかけることが重要です。
例えば上司が「それを実現するにはどんな障害があるだろう?」など問いかけ、単なる不満を建設的な提案に変える手助けをします。社員の視点を引き上げるためにはこうした上司・先輩のサポートが不可欠です。提案制度の運用においては、上司やメンターが提案準備の段階から伴走し、社員の気付きを促してあげる仕組みを取り入れると良いでしょう。そうすることで社員の問題解決力は飛躍的に向上し、提案内容の質も高まっていきます。
若手社員のモチベーションアップにつなげる仕組みづくり
提案制度を活性化させ継続させるには、参加する社員に小さな成功体験を積ませることが有効です。特に若手社員は直属の上司や経営層との距離を感じ、「せっかく良いアイデアがあっても言い出せずに飲み込んでしまう」ケースが少なくありません。そこで重要なのは、どんな小さな提案でも実際に試行させてみて、その効果を検証し評価することです。
提案が採用されたか否かにかかわらず、提案者には「ここが良かった」「ここはもう一工夫」という点をフィードバックし、次につながる学びを提供します(このフィードバック方法については後述します)。小さな成功体験の積み重ねにより若手社員は自信がつき、さらに積極的に提案するようになります。その好循環が周囲の社員にも波及し、組織全体の提案意欲が向上していくでしょう。
また、社員が提案に取り組む時間的・精神的余裕を持てるように、業務負荷の調整やワークライフバランスへの配慮を行うことも大切です。従業員が忙殺されていては新しいアイデアを考える余裕が生まれません。働きやすい環境づくりも併せて検討しましょう。
提案制度導入のステップは?
提案制度をスムーズに社内へ取り入れるために、基本的な導入ステップを押さえておきましょう。
1. 導入の目的と提案レベルを決める
まずは提案制度を導入する「目的」を明確化します。提案制度導入の目的としては、例えば以下のようなものが考えられます。
a. 会社業績への貢献(売上拡大・経費削減) b. 社員の経営参画意識の向上や組織の一体感醸成 c. 従業員の問題解決力向上やモチベーションアップ
自社では何を狙いとして提案制度を始めるのか、経営陣で共通認識を持ちましょう。目的によって求める提案内容やレベル設定も変わってきます。例えば「とにかく社員に数多く提案してほしい」という場合はアイデアの着想レベル(思いつきレベル)でも応募可とし、逆に「社員の高度な提案力育成」を目的とするなら事業計画書レベルのしっかり練り込んだ提案を求める、といった具合です。
提案のハードル(要求レベル)は目的に応じて意図的に設計する必要があります。あまりに高いレベルを最初から求めると応募者が限られてしまうため、まずは参加しやすいレベルから始めるのが無難です。
2. 提案ガイドを作成し、社員へ周知する
制度導入時には、社員が戸惑わず提案できるよう「提案ガイド」を作成して配布・周知しましょう。提案ガイドには次のような内容を盛り込むと効果的です。
<背景と目的>
- 提案制度導入に至った経緯
<期待する効果>
- 制度導入で期待している効果
<提案募集要領>
- 提案期限、提出方法、種類、評価方法、報奨などのルール
<提案書の記入例>
提案の評価方法(賞与に反映するか、人事考査に加点するか、表彰をするか)について事前に決めて公表する場合もありますが、参加する社員にとって「提案すること自体が目的」となってしまわないように、制度設計や伝え方に注意が必要です。制度導入の目的が達成され、会社と応募者の双方にメリットをもたらせるよう、評価方法は慎重に検討しましょう。
提案制度を活性化させるにはどうすればいいか?
せっかく提案制度を導入しても、運用次第では応募件数が減り制度が形骸化してしまう恐れがあります。ここでは、提案制度を社内で定着・活性化させるためのポイントを紹介します。
提案のハードルを下げ、まず量を優先する
制度を軌道に乗せるには、社員が気軽に提案できる雰囲気作りが重要です。最初から完璧で画期的なアイデアを期待しすぎず、「100件に1件良い提案が出れば上出来」という気持ちでまずは提案の件数(量)を増やすことを意識しましょう。
例えば「電気の消し忘れ防止の張り紙を貼る」といった小さな工夫でも立派な提案として受け付けることで、社員は身近なことからどんどん改善案を出しやすくなります。提案のハードルを下げるために、提案件数の目標を掲げたり(月に○件以上は採用する等)、どんな些細なアイデアでも歓迎する旨を周知したりすると効果的です。
改善提案制度で有名な未来工業でも「どんな提案でもNOと言わない」文化を徹底し、小さな提案も含めて年数万件ものアイデアを集めているといいます。まずは質より量を意識し、社員に「とにかく提案してみよう」と思ってもらうことが制度活性化の第一歩です。
どんな提案にもフィードバックと承認を行う
社員が提案しなくなる理由の一つに、提案を出しても放置されたり一方的に却下されたりして報われないことがあります。改善効果の大きい提案しか評価されないようでは、現場の社員は細かな改善案を出しにくくなってしまうでしょう。そうさせないために、提出された提案には必ず何らかのフィードバックを行うことが不可欠です。
たとえ採用しない提案であっても、「不採用とした理由」や「良かった点・不足していた視点」などを丁寧に本人へ伝えましょう。評価担当者(上司)は上から目線の指摘に終始するのではなく、提案者と近い立場のメンバー同士で意見を出し合う場を設けるなど、色々な気付きを得られる工夫をするとベターです。社員にとってはフィードバックを受ける過程も学びの機会となり、次の提案につながります。
併せて、提案したこと自体への承認欲求を満たす工夫もモチベーション維持に有効です。例えば改善が実施された箇所に提案者の名前と提案内容を掲示する、全社メールや社内報で提案者を紹介する等、「自分の提案が会社に貢献した」と実感できる演出を行う企業もあります。そうした取り組みが社員の満足度向上につながり、他の社員にも「自分も提案してみよう」という刺激を与えるでしょう。
提案活動を日常業務に組み込む
提案制度を長く機能させるためには、提案する文化を日常に溶け込ませることが大切です。具体的には、「改善提案は特別なイベントではなく日常業務の一部である」と位置づけます。例えば、朝会や週次会議で各自1件業務改善ネタを発表する時間を設ける、日報や週報に「今週気づいた課題」欄を追加するといった方法で日々提案の種を出す機会を作ります。
現場からアイデアが上がりやすくするために、提案専用のフォームや社内ポータルサイトを用意し、誰でも思いついたときにすぐ投稿できるような仕組みを整備するとよいでしょう。最近ではスマートフォンから手軽に改善案を投稿できる社内SNSや専用アプリを導入し、現場で気づいたその瞬間に提案を共有できるようにしている企業もあります。
また、提案制度の推進担当者(例えば人事部や経営企画部の担当者)が定期的に各部署の提案状況をフォローし、「今月は○件の提案が採用されました!」と発信するなどの働きかけを続けることも定着化に役立ちます。このように提案活動を日常業務フローに組み込み、経営陣も含め組織全体で提案を当たり前の文化にしていくことで、制度は形骸化せず継続的な成果を生み出していくのです。
提案制度の成功事例
最後に、提案制度を活用して社内の課題を解決した成功事例を紹介します。ここでは、総合エンジニアリング企業である三機工業株式会社の取り組みを見てみましょう。
三機工業株式会社では、長年にわたり「これぞ新規事業」と呼べるものが社内から生まれておらず、新規事業の経験者も社内にいないという状況でした。同社では「いかに社員に新しいことへ挑戦させ、イノベーションを起こせる人材を育むか」が大きな経営課題となっていたのです。
この難題に対する打開策として提案されたのが、一風変わった研修プログラムでした。それが、自社が将来ビジネス誌に大きく取り上げられたと仮定して「未来の記事」を執筆するというプロジェクト型研修プログラム「未来記事」です。研修参加者は、自社が数年後に成し遂げた成功を想像し、その内容の記事をゼロから作り上げます。新規事業を自由に企画し物語として描くこの研修は参加者にとって非常に新鮮で、互いの多様な思考や視点が混ざり合う中で、従来にない斬新なアイデアが次々と生まれる結果となりました。
この取り組みにより、社内に新規事業創出の機運が高まっただけでなく、社員自身も「新しい発想で挑戦する」マインドセットを身につける大きな成果が得られました。提案制度をうまく活用したこの三機工業のケースは、停滞していた新規事業開発を社員主体のアイデアで打開した成功例と言えるでしょう。
まとめ
ビジネスを取り巻く環境が激しく変化する中、その変化に対応できる組織だけが生き残れます。提案制度は、変化に強い組織風土を醸成し、社員の当事者意識と能力を引き出すための有効な施策です。しかし、提案制度は導入して終わりではなく、導入後の運用こそが重要です。
形骸化させないためにも提案活動を日常業務に組み込み、適切な評価を行って社員全員が継続して参加できるようにすることが必要になります。提案制度は上手く運用すれば、会社の業績向上と社員の成長・モチベーション向上を両立させる強力な仕組みとなります。