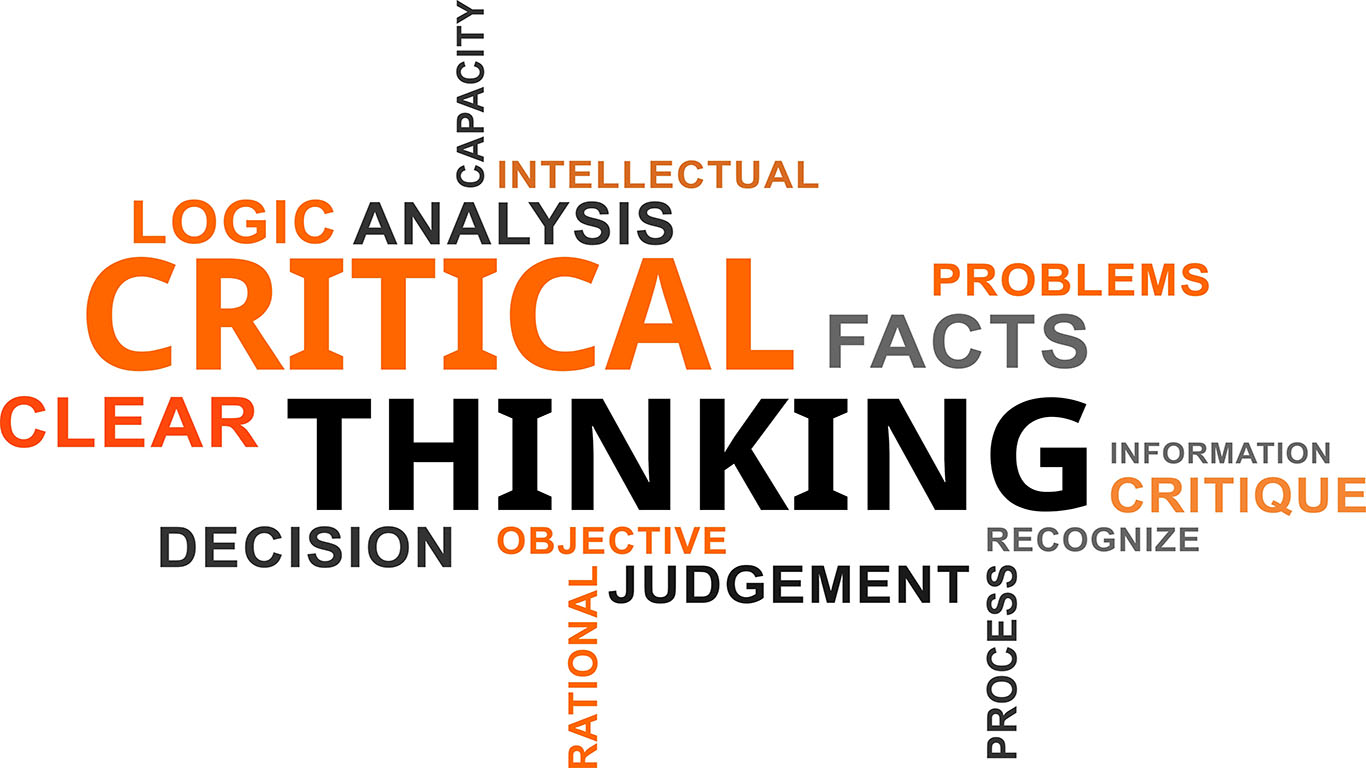コミュニケーション能力が高い人の特徴と鍛え方【大企業管理職向け】
最終更新日:2025.07.07

目次
最近、部下との何気ない会話が思わぬ誤解や摩擦を生んでいませんか?大企業の上級管理職の中には、昔ながらのやり方に頼ったコミュニケーションで失敗し、ハラスメント問題を引き起こすケースもあります。組織の生産性向上や職場トラブル防止のためには、コミュニケーション能力の再点検とスキルアップが欠かせません。
本記事では、コミュニケーション能力が高い人の特徴や考え方、スキルを紐解き、現代の職場で求められる対話術を具体的に解説します。また、メタ認知や言語化といったキーワードにも触れながら、上級管理職や研修企画担当者が「自分ごと化」して実践できるポイントや、スキル未更新によるハラスメント・職場問題のリスクについても考察します。
そもそもコミュニケーション能力とは
コミュニケーション能力は、相手と円滑な意思疎通を図る能力を指します。ビジネス環境では、このコミュニケーション能力の有無が業績や評価に直結することもあります。情報の伝達だけでなく、相手の感情や価値観など深いレベルで理解し合うことが求められるため、単なる情報伝達だけではコミュニケーションの本質を捉えるには不十分です。
コミュニケーションの語源は、複数の言語学的資料で確認されているように、ラテン語の「コミュニス(communis)」で、「共有・共通」を意味します。つまりコミュニケーションとは単に情報を伝えるだけでなく、お互いに情報や思いを共有する双方向のプロセスです。実際、コミュニケーション能力は対人関係構築に不可欠な能力であり、仕事を円滑に進めるうえでも欠かせません。たとえば企業調査でも、「コミュニケーション能力の高い人材」が最も求められる資質として挙げられており、その重要性が広く認識されています。
一方で、「コミュニケーション能力が高い=社交的で話し上手」というイメージがありますが、必ずしもそうとは限りません。外交的に自分の言いたいことばかり一方的に話す人は、実はコミュニケーションがうまいとは言えません。コミュニケーションは常に双方向のキャッチボールであり、相手の反応や理解を踏まえてこそ成立するものです。そのため、相手にわかりやすく伝える力(言語化能力)と、相手の話を受け止める力の双方をバランス良く備えることが大切です。
コミュニケーション能力が高い人の特徴
コミュニケーション能力が高い人にはどのような共通点があるのでしょうか。ここでは、コミュニケーション能力が高いと言われる人に共通しているポイントを整理してみます。高い人ほど、自分本位ではなく相手を重視したコミュニケーションを行っている点が特徴です。
「伝える」ではなく「伝わる」話をしている
コミュニケーション能力が高い人は、言いたいことを単に伝えるだけではなく、どうすれば相手に伝わるかを意識して工夫を凝らしています。
論理的に話すことで理解のすれ違いを防いだり、身近な例を適宜挙げることで抽象的な表現を噛み砕き、より深い理解を促したりしています。これは、単に自分の言いたいことを伝えるのではなく、「相手に伝わる」という>結果を重視してコミュニケーションを捉えているということに他なりません。
【「伝わる」とは、相手が「理解した」と感じたとき】
コミュニケーションは状況や目的によって相手の理解や解釈が異なるため、一度きりのものです。コミュニケーションが「伝わる」という結果として現れるのは、受信者である相手が「理解した」「納得した」「行動を起こす」と感じたときです。
この結果が得られて初めて、コミュニケーション能力が効果的に発揮されたと言えます。つまり、ただコミュニケーション能力が高いと言われる人でも、受け手の反応や状況を考慮せずに話していては伝わりません。
発信者は受信者の反応や置かれた状況を予め考慮し、複数のコミュニケーション技術を仮説的に組み合わせて活用する必要があります。その結果として「伝わった」という状態に至るのです。
【対話のバランスが重要】
この「双方向性」こそが高いコミュニケーション能力の肝心なポイントです。たとえば、1対1の会話ではお互いの話す時間が4~6割ずつになると会話が弾むという「ピンポンルール」の経験則があります。
一方が話しすぎると相手は「自分の話を聞いてくれない」と感じ、少なすぎると「興味がないのか」と不安になるためです。
このように、相手との対話のバランスに配慮し、相手本位で結果を意識した伝え方をしている点が、高い人の大きな特徴と言えます。相手に「伝わる」ことを最優先に考え、自分の伝え方を柔軟に調整できることが重要なのです。
ノンバーバル・コミュニケーションの意識
コミュニケーション能力が高い人は、ノンバーバル(非言語)のコミュニケーションにも長けている傾向があります。一般的にコミュニケーションと言えば言葉を使ったバーバル(言語)コミュニケーションを思い浮かべますが、身振り手振りや表情、視線、のトーンなど言葉以外で伝える非言語コミュニケーションも重要です。
これらの要素を組み合わせることで、より深くかつ漏れなく相手と意思を伝え合うことが可能になります。単なる言葉だけでなく、非言語的なメッセージも適切に活用し、バランスよく使いこなす必要があります。
【非言語の重要性】
有名なメラビアンの法則によれば、言語情報と非言語情報(声のトーンや表情)が矛盾している特殊な状況において、人は言語情報7%、聴覚情報38%、視覚情報55%の割合で判断すると言われます。
この法則は、言葉と表情・声色が一致しない場面でのみ適用される限定的な研究結果であり、一般的なコミュニケーション全般に当てはまるものではありませんが、非言語コミュニケーションの重要性を示す参考として理解できます。このように、非言語が伝える影響は非常に大きいのです。
たとえば、表情を和らげたりオープンな姿勢で相手に向き合うだけで安心感を与えられますし相手の感情に合わせて声のトーンを調整すれば、言葉以上に気持ちを伝えることができます。逆に言葉選びばかりに気を取られて表情が硬かったりすると、伝わるものも伝わらなくなってしまいます。
【言葉にならないメッセージを読み解く力】
コミュニケーション能力が高い人は、非言語の使い方と読み取りの両方を重視します。自分が話すときはジェスチャーや視線、相槌(あいづち)を活用して「ちゃんと聞いていますよ」と伝え、相手が発する微妙な表情の変化や声の調子から相手の真意や感情を察します。
たとえば相手が口では「大丈夫」と言っていても声が震えている、笑顔が引きつっているといった場合、不安や不満を抱えているかもしれません。その裏にある本音を汲み取る力こそが、コミュニケーション能力の核とも言えるのです。相手の非言語サインを見逃さず、必要に応じて問いかけフォローすることで、誤解の解消にもつながります。
このように、言葉にならないメッセージを敏感にキャッチし対処できる点も、高い人の特徴です。なお、ペーシング(相手の話す速度や仕草に自分も合わせる手法)のように、非言語を用いて相手との心理的距離を縮めるテクニックも効果的です。非言語コミュニケーションへの意識とスキルが、円滑な対人関係を支えています。
メタ認知能力が高い
「メタ認知(Metacognition)」とは、自分の知覚・思考・学習・記憶などの認知プロセスをより高い視点から客観視することです。客観的に状況を捉えて情報を整理できるため、効率的で正確なコミュニケーションを行えるようになります。
コミュニケーション能力が高い人は、このメタ認知能力を日常的に自然と使いこなしています。
【コミュニケーションの目的からずれていないか俯瞰できる】
コミュニケーション能力の根底には、言葉や身振りで発信する前段階として、明確な目的に基づいた仮説思考が存在します。コミュニケーション能力が高い人は、伝えたい内容や相手の状況を踏まえて事前に「どう話せば相手が動いてくれるか」という仮説を立てています。
そしてその仮説と目的に合わせ、ロジカルシンキングや傾聴など複数のスキルを意図的に組み合わせて対話を進めます。もし仮説や目的と手段が噛み合わなければ、「伝わらない」という結果につながる可能性があります。
したがって、コミュニケーション能力が高い人ほどコミュニケーションの最中でも自分を俯瞰でメタ認知し、当初の目的からズレがないかをチェックしながら話しているのです。メタ認知のないコミュニケーションは、いわば「無意識・無目的・無仮説」であり、行き当たりばったりの伝達に終始してしまいます。
【メタ認知によってコミュニケーションを最適化できる】
メタ認知能力が高い人は、自分を客観視する力があるゆえにコミュニケーション面でも優れています。実際、自分を客観視するスキルの研究では、メタ認知が高い人はコミュニケーション能力が高く、仕事の進行管理や目標設定も得意だとされています。
たとえば、自身の会話のクセや過去の失敗をメタ認知的に振り返り、次の対話では改善する、といったPDCAサイクルを回せるのも強みです。心理学の観点でも、過去のコミュニケーション失敗を冷静に分析し次に活かすことはメタ認知の働きによるものであり、今後の失敗予防につながるとされています。
このようにメタ認知能力に優れている人は、自身と相手の状況を俯瞰して見つめ、最適な対話アプローチを選択できるのです。メタ認知能力は一朝一夕に身につくものではありませんが、訓練によって高めることが可能です。メタ認知を養うことがコミュニケーション能力向上の土台となるでしょう。
「傾聴」に優れている
コミュニケーション能力が高い人は、聞く力(傾聴力)も高いという特徴があります。とにかく相手に寄り添い、まずは耳を傾ける「傾聴」の姿勢を確立している人がほとんどです。
相手の話を途中で遮る、自分の意見をすぐ挟むといったことはなく、最後までしっかりと耳を傾けるのです。適度に相槌を打ち、うなずき、アイコンタクトを取りながら、相手が「きちんと話を聞いてもらえている」と感じるような反応を示します。
さらに、話の途中でわからない点があれば的確なタイミングで質問を投げかけ、相手の考えをより深く引き出そうとします。こうした傾聴力があるからこそ、相手は「この人は自分の話を理解してくれている」と感じ、安心して心を開くことができるのです。その結果、信頼関係の構築につながります。
【傾聴することで認識のズレを防ぐ】
社会の多様化に伴い、人々の前提や常識も多岐にわたっています。このような状況では、コミュニケーションの初期段階や途中で前提が誤っていると、いわゆる「ボタンの掛け違い」と呼ばれる誤解が生じます。
一度誤った前提に基づいて会話が進むと、その認識のズレを修正するのは難しい作業です。そのため、前提を確認しつつ慎重に対話を進めることが重要であり、コミュニケーション能力が高い人はこれを傾聴や質問によって上手に調整します。
相手の話をじっくり聞き、要所で「今の理解で合っていますか?」と確認しながら進めることで、前提のズレを防いでいます。
また、コミュニケーション能力の高い人は決して相手を頭ごなしに否定しないことも傾聴の一部だと理解しています。相手の話にすぐ反論したり否定したりすると、相手は「自分の話を受け入れてもらえない」と感じ、心理的安全性が損なわれます。傾聴力の高い人はまず受け止め、必要なときに質問や要約で確認することで対話を深めます。
【「聞く」ことをメインにすることで建設的なコミュニケーションへ】
一方、コミュニケーション能力が低い人は、相手の話を最後まで聞かず途中で口を挟み、相手が話している間に次に自分が言うことばかり考えていることが少なくありません。そうした悪癖を戒め、「聞く」こと自体を主体的な行動として重視します。たとえば、相手が話し終えるまで意識して自分の口を閉ざし、相手の言葉だけに集中する、といった姿勢です。
このように、「傾聴なくしてよいコミュニケーションはなし」という信念を持ち、聞くことに徹している点が、コミュニケーション能力の高い人の大きな特徴です。結果として、相手の本音や背景事情を引き出しやすくなり、建設的な対話が可能になります。
コミュニケーションの相手に興味を持つ
コミュニケーションの目的は、広い意味では相手の行動や考えに何らかの変化を生み出すことです。相手を理解し共感することは、相手の心を動かすコミュニケーションの土台になります。そのため、コミュニケーション能力が高い人はコミュニケーションの相手に強い興味・関心を持つ傾向があります。
ビジネスの現場でも、上司や部下、顧客といった相手を徹底的に分析し、共通の話題や関心事を見つけようとします。これは相手への誠実さを示す行為であり、発信者と受信者との間に共感と理解の共通基盤を作り出すプロセスです。具体的には、相手の業界や組織、価値観に合わせて用語や表現を選び、相手の興味を引く例え話を用意したりします。一見テクニックにも思えますが、根底にあるのは「相手に寄り添い、理解しようとする姿勢」です。
【興味・関心を持ってくれる相手に、好感・信頼を抱く】
人は自分を理解しようとしてくれる人に対して自然と好感や信頼を抱くものです。相手への関心が深いほど関係は強固になり、長続きしやすくなります。この点をよく理解し、初対面の相手でも共通点を探し、相手の話に耳を傾けて共感するといったアプローチが距離を縮めます。逆にコミュニケーション能力が低い人は他人に興味を持たず、相手の話を真剣に聞けない傾向があります。
自分に関心を持ってくれないと感じた相手は心を閉ざし、表面的な会話しかできなくなります。そうならないよう、相手の立場や気持ちに心を配り、「あなたに関心があります」というメッセージを行動と言葉で示しているのです。たとえば相手の発言に対して「それはどういう背景があるのですか?」と質問したり、「〇〇がお好きと伺いましたが…」と以前聞いた情報に触れるなど、小さな関心の積み重ねが信頼を醸成します。
【発言に信頼性がある】
なお、信頼されやすいコミュニケーションには発信者自身の信頼性も影響します。政治家や専門家、研究者など権威ある人の発信は内容が同じでも信頼されやすい傾向があります。
上司と部下の関係でも同様で、日頃から部下に関心を持ち、誠実に向き合っている上司の言葉は受け入れられやすくなります。コミュニケーション能力が高い人は、こうした人間関係の心理も踏まえて普段から周囲と接しているため、いざという時に発言力を発揮できるのです。
コミュニケーション能力の高い人と低い人の比較
最後に、コミュニケーション能力が高い人と低い人の特徴をいくつか比較してみましょう。コミュニケーションが上手い人ほど相手中心、下手な人ほど自己中心になりがちです。以下の表に、高い人と低い人の具体的な行動の違いをまとめます。
| コミュニケーション能力が高い人 | コミュニケーション能力が低い人 |
|---|---|
| 相手の話を最後まで聴き、共感を示す | 相手の話を途中で遮り、自分の意見を被せる |
| 会話のキャッチボールを意識し、話す・聴くのバランスを取る | 自分ばかり一方的に話し続けてしまう |
| 相手に強い関心を持ち、共通点を探して合わせる | 他人に興味を持たず、相手の話に共感や理解を示さない |
| 相手の性格・状況に応じて伝え方を柔軟に変える | 相手の気持ちや状況を無視し、自分本位に話を進めがち |
コミュニケーション能力の高い人の行動から学び、低い人のNG行動を反面教師とすることで、自身のコミュニケーションを見直すことができます。
コミュニケーション能力が高い人の考え方
コミュニケーション能力が高い人の特徴を踏まえた上で、彼らが実際にどのように物事を捉えているのか、もう少し深い部分に迫っていきます。コミュニケーション能力が高い人の考え方やマインドセットには、どのような共通点があるのでしょうか。対人コミュニケーションへの向き合い方の面で、高い人に見られるポイントを解説します。
情報伝達とコミュニケーションの違いを理解している
コミュニケーション能力が高い人は、情報伝達とコミュニケーションの違いを明確に認識しています。情報伝達は主にデータや事実の正確な伝達に焦点が置かれ、感情や意図といった人間的要素はあまり関与しません。たとえば科学の分野では、正確性が最も重視されるため、誰がどのように伝えても同じ内容が正確に伝われば目的は達成されます。これが情報伝達の世界です。
一方で、コミュニケーションは単なる情報のやり取りではなく、相手との感情や考えの共有、文脈を考慮した意思疎通が求められます。会議や商談の場面では、事実データの伝達だけでなく、相手の反応や理解度に応じて伝え方を調整したり、感情や意図を伝えることが重要になります。
つまり、コミュニケーション能力が高い人は、データの伝達以上に相手との相互理解を重視しているのです。情報伝達が「何を伝えるか」に注目するのに対し、コミュニケーションでは「誰にどう伝えるか」まで含めて考える必要があります。「伝えること」と「伝わること」の違いを深く理解しており、「自分が話したから相手も分かったはず」という独りよがりは持ち合わせません。相手が理解し行動して初めてコミュニケーションが成立すると考えます。そのため、単に自分の言いたいことを言うだけでは不十分で、相手の理解を確認しながら会話を進めます。
これは、コミュニケーションを一方通行の情報伝達ではなく双方向の意思疎通だと捉えているからです。たとえば、話を一通り伝えた後に「ここまででご不明な点はありませんか?」と確認したり、相手の表情を見て理解度を察したりするのもその表れです。高い人に共通するのは、「相手が理解してこそ伝達の意味がある」という意識なのです。
コミュニケーションの限界を認識している
コミュニケーション能力が高い人は、相手の立場や視点を考慮し「自分の伝えたいことが必ずしも相手に完全には伝わらない」場合があることをよく理解しています。
他人の考えを完全に理解し、自分の考えを完全に伝えることは容易ではないという現実を踏まえているのです。人は一人ひとり異なる経験や文化的背景を持っており、たとえ同じ言葉や表現を使っても人によって受け取り方が違うことがよくあります。
また、感情や抽象的な概念に関する考えは、言葉だけでは十分に表現できないこともあります。どんなに言葉を尽くしても、気持ちのニュアンスや背景事情まですべて伝えるのは難しい場合があります。身振りや表情、声のトーンといった非言語の手段を使っても、相手が自分と違う価値観や文脈を持っていれば完全な理解には至らないこともあるでしょう。そのため、コミュニケーション能力が高い人は「100%思い通りに伝わることはない」という前提に立ってコミュニケーションに臨みます。
自分の考えを完全に伝えきることや相手の考えを完全に理解しきることは不可能かもしれないからこそ、少しでも誤解を減らし認識のズレを埋めるために努力するのです。言語・非言語のあらゆる手段を駆使しつつも「それでも伝わりきらない部分が残るかもしれない」と謙虚に捉えています。そのうえで、相手との対話を重ねてより深い理解や共感を生み出すことを目指します。つまり、コミュニケーションの可能性を最大化しながらも、限界点を認識して過信しないのです。
このような限界認識があるからこそ、確認と修正を厭うことはしません。途中で相手の反応が自分の想定と違えば、「もしかして伝わっていないかな?」と感じ取り再度説明するなど、別の案を出したりします。
コミュニケーション能力が低い人は「言ったのになぜわからないんだ」と相手の理解力のせいにしがちですが、高い人は「自分の伝え方に改善の余地があったかも」と内省します。この姿勢の違いが、結果としてコミュニケーションの質の差につながるのです。高い人はコミュニケーションの不完全さを前提とし、だからこそ絶えず工夫とチェックを怠らないと言えます。
相手や状況を理解することが重要であることを理解している
コミュニケーション能力が高い人は、発信のスキルだけでなく、相手や状況の十分な理解こそが重要だと知っています。なぜなら、コミュニケーションは常に双方のやり取りであり、相手の理解や反応を無視しては成り立たないからです。
【相手の文化的背景・価値観の理解と尊重】
相手が誰か、どんなバックグラウンドを持つ人か、どんな状況に置かれているかによって、適切な伝え方は変わってきます。そうした前提条件の重要性をよく理解していて、同じ言葉や表現でも、文化や背景の違いによって解釈が異なることがあります。
たとえば、日本では控えめな表現が美徳とされる場面でも、欧米の文化でははっきり自己主張しないと真意が伝わらない場合があります。このように、相手の文化的背景や価値観を理解することが適切なコミュニケーションの前提になります。相手によって受け取り方が変わることを念頭に置き、「相手に合わせた伝え方」を選ぶのがコミュニケーション能力の高い人の考え方です。
また、相手の文化的背景や価値観を理解し尊重することで、良好な人間関係を築く効果も得られます。仮に相手が自分と異なる文化圏の出身でも、違いを理解しリスペクトして接すれば、相手は安心して心を開きやすくなります。その結果、コミュニケーションが円滑になり、ビジネスでもよい成果につながる可能性が高まります。
【コミュニケーションは相手ありき】
「まずは相手ありき」でコミュニケーションを捉えます。極端な話、自分がどんなに上手に話したつもりでも、相手に響かなければ無意味という考えです。専門知識のない相手には専門用語を避けて噛み砕いて話し、論理より感情に訴えた方が伝わりやすい相手には共感を示す、といった具合に、相手のタイプに合わせて伝達スタイルを変える柔軟さを持っています。
逆にコミュニケーション能力が低い人は、相手も自分と同じ前提でわかっているだろうと決めつけてしまいがちです。高い人はそうした独りよがりを避けるため、事前準備として相手の情報収集を行い、会話中でも相手の反応から理解度や感情を推し量って調整します。
これはコミュニケーション前の準備とも言える重要なプロセスで、会議前に参加者の経歴や関心事を把握したり、提案先企業の文化を調べたりするといった形で実践されています。コミュニケーションは「準備8割、本番2割」で決まるとも言えます。こうした相手・状況理解の徹底が、結果的に伝達精度を高め、誤解のないスムーズな対話を可能にするのです。
コミュニケーション能力が高い人のスキル
コミュニケーション能力が高い人が持っている主なスキルについて整理します。彼らが具体的にどのようなビジネススキルを活用して意思疎通を図っているのか、代表的なものを確認していきましょう。これらのスキルは、日々の業務の様々なシーンで役立ちます。
ロジカルシンキング(論理的思考力)
ロジカルシンキングとは、物事を論理的に考える思考法です。また、論理的に伝えることで認識のすれ違いを防ぐことができます。論理のつながりや順序を意識せずダラダラと話してしまうと、受け手は混乱してしまいます。
ただ思いつくままにしゃべるだけでは、相手の理解にはつながりません。したがって、言葉に出す前に自分の中で考えを噛み砕き、主張の流れを整理することが重要です。話す前に頭の中で論点を構造化し、「結局何を伝えたいのか」「そのためにどんな根拠を示すか」<を組み立ててから話すだけで、伝わりやすさは格段に向上します。
ビジネスシーンにおいては、提案や説得、プレゼンテーションなど幅広い場面でロジカルシンキングが有用です。筋道だった説明は相手の納得感を高め、合意形成をスムーズにします。ロジカルシンキングを実践するうえで、結論を先に述べる(結論先出し)というテクニックがあります。コミュニケーション能力が高い人は、物事を話す際に最初に結論を提示する傾向があります。結論を冒頭に伝えることで、相手との共通認識が持ちやすくなり、会話の目的や方向性が明確になります。
また、端的にポイントを伝えることで相手の注意を引きつけ、効率的に話を進められます。要点ファーストで話す習慣は、相手に「何を言いたいのか」を早い段階で理解してもらうのに有効です。「本日の会議の結論ですが…」と最初に結論を述べ、その後で理由や詳細を説明することで、聞き手は全体像を把握したうえで話を聞けます。このような論理的展開により、聞き手の理解を助け、余計な誤解や質問を減らすことができます。
ロジカルシンキングを鍛えるには、ピラミッドストラクチャー(結論→根拠→事例の順に話す構成)などのフレームワークを学ぶことも有効でしょう。
クリティカルシンキング(批判的思考力)
クリティカルシンキングとは「批判的思考」と呼ばれ、物事の前提や常識を疑い、より深く問いを立てる思考法です。自分を第三者的立場から見る視点を持ち、安易に鵜呑みにせず本質は何かを追究します。
現状の問題点や矛盾点を洗い出し、「本当にそれで良いのか?」「他に見落としている視点はないか?」と批判的に問い続けることで、より深く鋭い洞察にたどり着けます。クリティカルシンキングが優れている人は、相手の話を聞く際も表面的な内容だけでは満足せず、不明点に遠慮なく切り込んで質問することで相互理解を深めます。
これは決して相手を否定するためではなく、より良い結論やアイデアを導き出す建設的プロセスです。ビジネスシーンでは、課題の深掘りやリスクの洗い出し、意思決定の質向上に役立ちます。会議で提案が出たときに「その根拠は何でしょうか?」「別の選択肢は検討しましたか?」と問いかけるのはクリティカルシンキングの表れです。適切な批判的質問は、議論を活性化しチームの思考を深化させます。
クリティカルシンキングにより、コミュニケーションの場では相手への的確な質問が可能になります。相手の話をしっかり理解したうえで疑問点を見抜き、ポイントを突いた質問を投げかけます。その質問によって相手自身が考えを整理したり、新たな視点に気づいたりする効果もあります。部下から企画の提案を受けた上司が、「この提案で想定されるリスクは何かな?」と問いかければ、部下は計画の穴を再点検できます。
こうした建設的な質問力は、傾聴と並んで重要なコミュニケーションスキルです。批判的思考に裏打ちされた質問は相手への関心と理解の証でもあり、質問された側も自分を真剣に見てくれていると感じ信頼が深まります。クリティカルシンキングを磨くことで、対話を単なる伝達で終わらせず、互いにとって有意義な発見の機会へと高めることができるのです。
ラテラルシンキング(水平思考力)
ラテラルシンキングとは「水平思考」とも呼ばれ、固定観念にとらわれず新しい角度から物事を見る思考法です。ロジカルシンキングやクリティカルシンキングが直線的・垂直的な深掘りの思考であるのに対し、ラテラルシンキングは発想を横に広げ、別の切り口を模索する点が特徴です。
コミュニケーション能力が高い人は、対話の中で発想を転換する柔軟さも持っています。たとえば会議で議論が行き詰まったとき、「そもそも視点を変えてみませんか?」と提案し、新たな視野を提供できる人はラテラルシンキングに優れた人です。
ビジネスシーンにおいて、ラテラルシンキングは課題解決やアイデア創出、ブレインストーミングの場面で有効に働き、自由な発想を引き出すファシリテーションにもつながります。相手の発言からヒントを得て、「それは逆に考えるとどうなるでしょう?」などと斜め上の質問をし、一見無関係な事例を引き合いに出して相手の思考を促したりします。これにより、会話の流れに新風を吹き込み、今までにないイノベーティブな解決策を導き出すきっかけを作ることができます。
水平思考は創造性が求められる場で力を発揮し、コミュニケーションを単なる意思疎通ではなく共創の場へと高めます。たとえば、問題が発生した際に「この制約を取り除いたら何ができるか考えてみましょう」と提案することで、思考の枠を広げ新たなアイデアが生まれるかもしれません。ラテラルシンキングを鍛えるには、日頃から様々な分野の知識に触れたり、「Why?」「Whatif?」と問いかけてみる習慣が効果的だと言われます。
対話スキル
対話スキルとは、お互いの立場や意見の違いを理解し、考え方や意見のズレをすり合わせることを目的に行うコミュニケーションスキルです。日常的な会話も二人または少人数での話し合いですが、通常の会話には明確な目的やゴールがないことも多いでしょう。一方、対話(ダイアログ)では何らかのテーマに基づき、お互いの意見を述べ合いながら共通理解を探っていきます。コミュニケーション能力が高い人は、この対話の重要性を理解し、相手との認識のズレを埋める努力を惜しみません。
ビジネスシーンでは、課題解決や少人数のミーティングなどで対話スキルが役立ちます。たとえばプロジェクトのキックオフミーティングで、各メンバーの懸念点や期待値を引き出し、全員が納得できる共通目標を設定する際に対話スキルが活きます。傾聴と質問を通じて相手の真意を探り、言葉の裏にある本音までも引き出しながら合意形成<へ導きます。
対話ではときに意見が対立することもありますが、コミュニケーション能力が高い人は感情的にならず、相手の立場を尊重しつつ自分の意見も率直に伝えるアサーティブな態度を取ります(※アサーション=相手も自分も大切にした自己表現)。そのため、議論が平行線になるのを防ぎ、お互いの理解を深める生産的な話し合いが可能になります。
対話スキルには、上述のロジカル・クリティカル・ラテラルな思考力や傾聴力などが総合的に試されます。とくに現代の職場では、多様な価値観や専門性を持つ人同士が協働するため、対話による相互理解と調整が欠かせません。
コミュニケーション能力が高い人は、会話の流れを俯瞰しながら、必要に応じて話題を整理して問い直し、場をファシリテートすることもできます。たとえば、「今の議論で見えてきた論点は〇〇ですね。一度整理しましょう」と提案し議論を噛み合わせるといった具合です。こうした対話の舵取り役になれる人は組織にとって貴重であり、チーム全体のコミュニケーション品質を底上げしてくれます。
対話スキルを磨くためには、一方通行の指示命令だけでなく対話型のリーダーシップを心がけることが重要です。上級管理職であっても「自分の意見が絶対」と押し付けず、部下や他部署の意見を引き出し統合する対話的姿勢が、結果として組織のエンゲージメントや創造性を高めることにつながるでしょう。
コミュニケーション能力が高い人が実践しているポイント
では、コミュニケーション能力が高いとされる人は、日頃どのようなことを意識してコミュニケーションに臨んでいるのでしょうか。ここからは、実践レベルで取り入れたい具体的なポイントを整理します。日常で心がけることで、誰でもコミュニケーション上手に近づくことができるはずです。
具体的と抽象的に話すことを意識する
コミュニケーションを行う際には、具体的な表現と抽象的な表現をバランス良く使って話すことが重要です。相手にイメージしやすく理解してもらうために、具体例を適宜挙げると効果的です。しかし、具体例ばかり頻繁に挙げすぎると、かえって話が冗長になり要点がぼやけてしまう可能性があります。適切なタイミングで抽象的な表現に戻しつつ、分かりやすい構成で話すことが求められます。抽象的な概念→具体例→再び抽象的なまとめ、といった具体と抽象の行き来を意識すると、話にメリハリが生まれ理解が深まります。
たとえば、新しい企画を説明するときにまず全体像(抽象)を示し、その後で具体的なユーザー事例や数値(具体)を示し、最後に「つまり…」と要点(抽象)をまとめる、といった具合です。ビジネスでは結論や要点を先に提示した上で具体例を示し、最後に再度結論を確認するような話法が有効です(いわゆるPREP法:Point結論→Reason理由→Example例→Point結論の順序)。
コミュニケーション能力の高い人は、この具体・抽象の切り替えが上手で、聞き手に負担をかけません。一方で低い人は背景説明や枝葉の話(具体例)が長すぎて「結局何が言いたいのか分からない」と思われがちです。自分の話が抽象論に終始していないか、逆に具体例の羅列になっていないかをセルフチェックする習慣を持ちましょう。抽象⇔具体のバランス感覚を養うことで、説得力と分かりやすさが格段に向上します。
スピードや表情などにも気を付ける
言葉の内容だけに頼っていては、相手にこちらの意図を正しく伝えるのは難しいものです。大切なのは、非言語の領域も意識することです。身振り手振りを交えたり視線をしっかり向けたりして、自分の想いを立体的に表現していきましょう。
ただし、あまり大げさに動きすぎると逆効果になるので注意が必要です。さらに、話すスピードを相手に合わせて適切に調整することも心がけましょう。早口すぎると情報が追いきれず、遅すぎると退屈させてしまうため、相手の表情を見ながらペース配分を最適化します。相手に違和感を抱かせず思いを伝え合えるよう、相手の反応をよく観察し、自分の伝え方をその都度変えていくことがポイントです。相手が困惑顔なら少しゆっくり話してみる、相手が急いでいそうなら要点を端的に伝える、といった柔軟な対応が求められます。
また、ビジネスチャットやメールといったテキストでのコミュニケーションでも、絵文字やスタンプで感情を補足、要点に箇条書きを使うなど工夫しましょう。リモートワークが増えた現代では、対面での表情・声色といった非言語情報が伝わりにくいため、テキスト上での細やかな気配りが以前にも増して重要です。Slackなどのチャットでメンションを受けたらすぐ既読確認のリアクションを入れる、笑い話には「😄」の絵文字を添えて固い印象を与えないようにする、といった配慮です。こうしたデジタル上のノンバーバル表現も上手に使いこなすことで、相手に安心感や暖かみを伝えることができます。
コミュニケーション能力が高い人は対面・オンラインを問わず、スピード・表情・声・テキスト表現など様々な手段で伝わる工夫を怠りません。自分の発信が一方的になっていないか常に相手目線でチェックし、言葉以外の要素にも気を配ることが大切です。
相手の話に興味を持つ立場に立つ
前述でもお伝えした通り、そもそも相手に興味を持っていなければ、上手なコミュニケーションは実現しません。よいコミュニケーションを行うためには、相手の立場・役割、普段の問題意識、周辺環境、心理状態、要望など多面的な理解が不可欠です。
相手の価値観を尊重して「あなたの話に関心がありますよ」という誠実な姿勢を示すことで、コミュニケーションはより円滑に進みます。相手に興味を持ち、オウム返し(リフレーズ)をする、相槌を打つ、適宜質問をすることで、相手は安心して話せるようになります。具体的には、相手が話した内容を一度要約して「つまり〇〇ということですね」と返し、相手が好きな話題に触れたら「それは面白いですね、もっと教えてください」と深掘りの質問をするとよいでしょう。こうした対応は、相手に「自分の話に興味を持ってくれている」と感じさせ、対話へのモチベーションを高めます。
逆に興味なさそうに聞いていたり、話を変えたがったりすると、相手は心を閉ざしがちです。コミュニケーション能力が高い人は、初対面の相手でも笑顔でうなずきながら聞いたり、共通の話題を探して話を広げたりして、相手本位の会話を展開します。結果として相手の情報や本音を引き出せるため、その後の提案や説得もスムーズに進むのです。
実践ポイントとして、常に「自分が相手だったら」と想像してみる癖をつけましょう。「自分が部下だったら上司にどう接してほしいか」「自分がお客様だったらどんな提案なら興味を持つか」といった視点です。こうした想像力は相手への関心から生まれます。上級管理職の方は忙しさからつい部下との対話がおろそかになることもありますが、「もし自分が新入社員だったら…」と立場を入れ替えて考えることで、適切なコミュニケーションの取り方が見えてくるはずです。相手の立場に立つ=相手への興味関心と心得て、日頃から相手視点を意識した行動を心がけてください。
すぐに否定しない
コミュニケーションの中で相手に対してすぐ否定的な態度をとってしまうと、相手は心を閉ざしてしまいます。相手が誤解して未熟な意見を述べている場合でも、頭ごなしに「それは違う」「ダメだ」と言ってしまっては、その後の建設的な話し合いが難しくなります。
相手が本当は理解していないのにわかったふりをして頷いてしまうなど、心理的安全性の欠如から正直なコミュニケーションが阻害されてしまうこともあります。コミュニケーション能力が高い人は、たとえ相手に改善点があってもまず受容(いったん受け止める)の姿勢を示します。
そのうえで、相手の言い分を尊重しつつ自分の意見を伝えることで、相手も聞く耳を持ちやすくなるのです。良質なコミュニケーションのためには、相手を否定せず傾聴することがポイントです。
たとえば部下からの提案に難点があった場合でも、いきなり「そんなのダメだ」ではなく、「提案ありがとう。ここは〇〇という懸念があるけど、どう思う?」と問いかけるようにします。否定ではなくフィードバックに切り替えるわけです。これにより部下は自分の意見を尊重してもらえたと感じ、前向きに改善策を考えようという気持ちになります。
反対に感情的に「何を考えてるんだ!」などと否定されたら、委縮してしまい二度と意見を出さなくなるかもしれません。これは組織にとって大きな損失です。上級管理職ほど権限がありますから、その分言動の影響力も大きいことを肝に銘じましょう。ハラスメント研修などでも指摘されるように、立場が上の人からの強い否定は受け手に深刻な心理的ダメージを与えかねません。コミュニケーション能力が高いリーダーは叱責ではなく対話によって部下を導くものです。
実践のコツとして、否定したくなったらいったん深呼吸してみてください。そして「なぜ相手はそう考えたのだろう?」と自問し、相手の視点を探ります。否定ではなく質問を返すことで、相手自身に気づきを促すこともできます。「なるほど、〇〇と思ったんだね。ちなみに△△の場合はどうなるかな?」という具合に、対話を継続させるイメージです。すぐ否定せずワンクッション置く習慣がつけば、職場の心理的安全性は大きく高まります。結果として部下からの報告・相談も増え、問題の早期発見やチームの創造性向上にもつながるでしょう。
確認やすり合わせを怠らない
コミュニケーションをとる際に重要なのは、相手の立場を考えてどのように発信するか工夫することです。とくにビジネスでは、「言ったつもり・分かったつもり」が最も危険です。一度伝えただけで満足せず、相手が本当に自分の意図を理解しているかどうかまで確認しなければなりません。
そうしないと、認識のズレに気付かず「伝わった」という思い込みのまま進行してしまい、後で大きなコミュニケーションエラーが起きる恐れがあります。対面で口頭伝達した内容も、念のためメールで要点を書き残したり、会議の終了時に「解釈のすり合わせ」をしたりと、丁寧な確認や合意形成を繰り返すことが大切です。
会議で決定事項を確認する際、「ではA案で進めます。異論ある方いませんか?」と問いかけて全員の同意を取る、ミーティング後に議事録を回覧して認識にズレがないかチェックする、といったプロセスを踏むと安心です。この「確認・フィードバックループ」を回すことで、小さな誤解の芽を早めに摘むことができます。
コミュニケーション能力が高い人は、この確認とすり合わせを徹底しています。相手が自分の伝えたかったことを本当に理解したかどうか、不明点は残っていないか、最後に必ず確認を入れる習慣があります。たとえば、「私の説明したプランについて、ご理解いただけましたか?何か懸念点はありますか?」と質問し、相手の理解度を測ります。相手から「つまり〇〇ということですね」と確認が返ってくれば、「そうです、その認識で合っています」とお互い安心できます。
仮に相手の理解がずれていれば、その場で修正できます。とくに「この理解で合っていますか?」と確認するフレーズが有効です。自分の伝えたいことに対する相手の理解が合っているか確認してこそ、コミュニケーションが深まっていくと実感しているからです。会話やメールの最後に一言「確認」を入れるクセをつけてみてください。それだけで伝達ミスが大幅に減り、相手からの信頼も増すはずです。
コミュニケーションツールを活用する
近年、コミュニケーションを円滑に行うためのさまざまなITツールが登場しています。社内チャットツールやオンライン会議システム、プロジェクト管理アプリなどを活用することで、チーム内外とのコミュニケーションをより手軽で快適なものに変えることができます。これらのツールも積極的に取り入れることで、環境づくりの観点からコミュニケーションの質を高めています。「ツールに振り回される」のではなく、「ツールを使いこなしてチームの生産性を上げる」意識を持っているのです。
日常的な報連相(報告・連絡・相談)をチャットツール上で行えば、情報共有のスピードを上げ、議論の経緯がログに残ります。また、対面だと発言を控えがちな部下もテキストなら意見を言いやすい、というケースもあります。匿名の意見収集ツールを使って会議前にアイデアを募るなど、ツールを組み合わせて多様なコミュニケーションの場を設計することもできます。
重要なのは、自らのチームの状況や課題に適したツールを選定し、メンバーに定着させることです。「うちは昔ながらのメールだけで十分」と決めつけず、SlackやTeams、社内SNS、オンラインホワイトボード等の新しい手段も試してみる柔軟性が求められます。とくにコロナ禍以降、リモートワーク下でのコミュニケーション活性化は経営課題にもなっていますので、管理職自らが模範となってITリテラシーを高め、ツール活用を推進すると良いでしょう。
ツール活用の際の注意点も忘れてはいけません。便利な反面、対面に比べてニュアンスが伝わりにくいメールやチャットでは、言葉遣いや表現により一層の配慮が必要です。たとえば短文で命令調のメッセージを送ると冷たい印象を与えかねません。適度にクッション言葉を入れたり、「お願いします」「ありがとうございます」といった基本的な礼儀を意識するだけで相手の受け取り方は違います。また、オンライン会議では相槌が伝わりにくいので、意識して「うんうん」「なるほど」と声に出したり、リアクションボタンを活用したりすると相手は安心します。
デジタルでもアナログでも、結局大事なのは相手への思いやりである点は変わりません。高度なツールを導入するだけでなく、その中で人間らしい温度感をもって対話することが、コミュニケーション能力の真価と言えるでしょう。
コミュニケーション能力の向上は難しい
日本のビジネスパーソンは、一般的に新卒で企業に入社してから初めて本格的にビジネスコミュニケーションを学ぶ人が多くを占めます。新人研修では、報告・連絡・相談の基本、電話やメールのマナー、あるいは簡単なプレゼンテーションなど、ビジネスコミュニケーションスキルの基礎が教えられます。
しかし、各企業内にはその会社独自のコミュニケーション方法や言語、スタイルが存在するため、多くの人は体系立てて学ぶというより現場の真似でコミュニケーションを身につけていくのが実情です。一度企業内で独自のコミュニケーションスタイルが身につくと、それがその人にとって当たり前のやり方として定着します。そのため、そのやり方が他社や異なる環境でも通用するとは限りません。本質的なコミュニケーションスキルを学ぶ機会は限られており、自社流がなかなかアップデートされないことが、結果としてその人のコミュニケーション能力の伸び悩みにつながっている場合があります。
言い換えれば、「コミュニケーションスキルの固定化」が起きやすいのです。長年同じ組織にいる管理職ほど、「自分のやり方が正しい」と思い込み、時代や相手に合わせたコミュニケーションの見直しを怠ってしまう危険があります。
また、多くの会社で行われるコミュニケーションスキル研修は、対象者が新入社員や若手社員に限られることが少なくありません。上司やベテラン社員に対するリスキリング(学び直し)の機会は限られているのが現状です。
そのため、管理職層のスキルが古いまま組織全体のコミュニケーションが停滞してしまうケースも見受けられます。最近ではこの問題を認識し、管理職全体を対象とした基本的なコミュニケーションスキルのトレーニングを行う企業も増えてきました。
上級管理職のスキル未更新が原因で起こるハラスメントや職場トラブルにも注意が必要です。厚生労働省の令和5年度「職場のハラスメントに関する実態調査」でも、管理職のコミュニケーション不足が職場のハラスメント要因として明確に指摘されています。勤務先でパワハラを経験した労働者の職場では「上司と部下のコミュニケーションが少ない/ない」と回答した割合が、パワハラを経験しなかった労働者の職場に比べて10ポイント以上高いという結果が出ています。
昔の感覚で部下に厳しく接した結果、「指導のつもりがパワハラ認定されてしまった」という事態も起こり得ます。実際、ダイヤモンド・コンサルティングオフィス合同会社が2021年12月に実施した調査(管理職312名対象)では、83%の管理職がハラスメントを恐れて部下への声かけを躊躇した経験があると報告されています。
このように、コミュニケーションにまつわる課題は管理職側にも部下側にも影響を及ぼしています。だからこそ、定期的な研修や振り返りによって上司層のコミュニケーションスキルをアップデートし、>時代に合った対話術を身につけることが大切です。
研修でコミュニケーション能力を高める
前章を踏まえ、コミュニケーション能力を高めるために研修で扱うべきテーマは多岐にわたります。
たとえば、ハラスメント防止のためのコミュニケーションでは「叱り方」「褒め方」「心理的安全性の作り方」を学びます。また、国際化に対応するための異文化コミュニケーション研修、リモート時代のオンラインコミュニケーション研修、管理職向けのコーチング研修(傾聴・質問力の強化)など、組織の課題に応じて専門的なプログラムを導入するとよいでしょう。
官公庁や大手企業でも、コミュニケーション研修を通じて職場の風通しが良くなったとの報告があります。研修を単発で終わらせず、研修後に職場で実践フォローする仕組みも重要です。たとえば研修内容を活かした1ヶ月後・3ヶ月後の上司面談を実施したり、学んだスキルを活用して部下と1on1ミーティングをする、といった定着策が効果的です。
最後に、研修を企画する人材育成・研修担当者の方への提言です。コミュニケーション能力向上の研修は、「足りない人に受けさせるもの」ではなく、組織全体の底上げという観点で捉えてください。全社員対象のワークショップ形式でお互いのコミュニケーションスタイルを理解し合う場を設ける、管理職研修では部下からの360度フィードバックを受けて自分のコミュニケーションを見直す機会を作るなど、双方向の学びを促進しましょう。
コミュニケーション研修自体も一方通行の講義ではなく、ロールプレイやディスカッションを通じて参加者が自ら気づきを得る構成が望ましいです。研修担当者も上級管理職に対しては「過去の成功体験が通用しなくなっている可能性」をデータや他社事例で示し、研修の必要性を腹落ちさせる工夫が必要でしょう。
こうした地道な取り組みが、組織全体のコミュニケーションレベルを引き上げ、ひいては生産性向上やエンゲージメント向上に結びつくのです。
まとめ
コミュニケーション能力は、現代のビジネスシーンにおいて極めて重要視されています。コミュニケーション能力が低いと、ミスやトラブルが起こりやすくなり、職場内の人間関係が悪化したり、業務の質が低下したりといった弊害が生じます。
以下に、コミュニケーション不足が招く典型的な問題をまとめます。
- ミスの増加・業務効率の低下:情報共有や意思疎通が不十分だと、認識違いや伝達漏れからミスが発生しやすくなります。
- 人間関係の悪化:会話が乏しかったり誤解が放置されたりすると、メンバー間の信頼関係が損なわれ、職場の雰囲気が悪くなります。
- ハラスメントの誘発:コミュニケーションが一方通行になりがちな上司は、無自覚のうちに高圧的・否定的な言動をして部下に精神的負担を与えてしまう可能性があります。
コミュニケーション能力は放置すれば低下していくスキルですが、意識的な実践と訓練によって向上させることができます。
本記事で紹介した、普段意識したいこと・取り入れたいポイント(具体⇔抽象のバランス、非言語の活用、傾聴、否定しない対話、確認の徹底など)をぜひ実践してみてください。一朝一夕で劇的に変わるものではありませんが、小さな心がけを積み重ねることで確実にコミュニケーション能力は高まっていきます。
組織の成果は人と人との円滑なコミュニケーションに支えられていると言っても過言ではありません。上級管理職や研修担当者の方々は、自身と組織のコミュニケーションを今一度見直し、改善への一歩を踏み出してみてください。コミュニケーションの質を高めることが、職場全体のパフォーマンスとエンゲージメント向上につながるはずです。
本記事の各種理論や調査結果は、それぞれ特定の条件下での研究成果です。メラビアンの法則は矛盾した情報提示時の限定的な法則であり、一般的なコミュニケーション全般には適用されません。また、実践的な手法については、各職場の状況に応じて適切に調整してご活用ください。