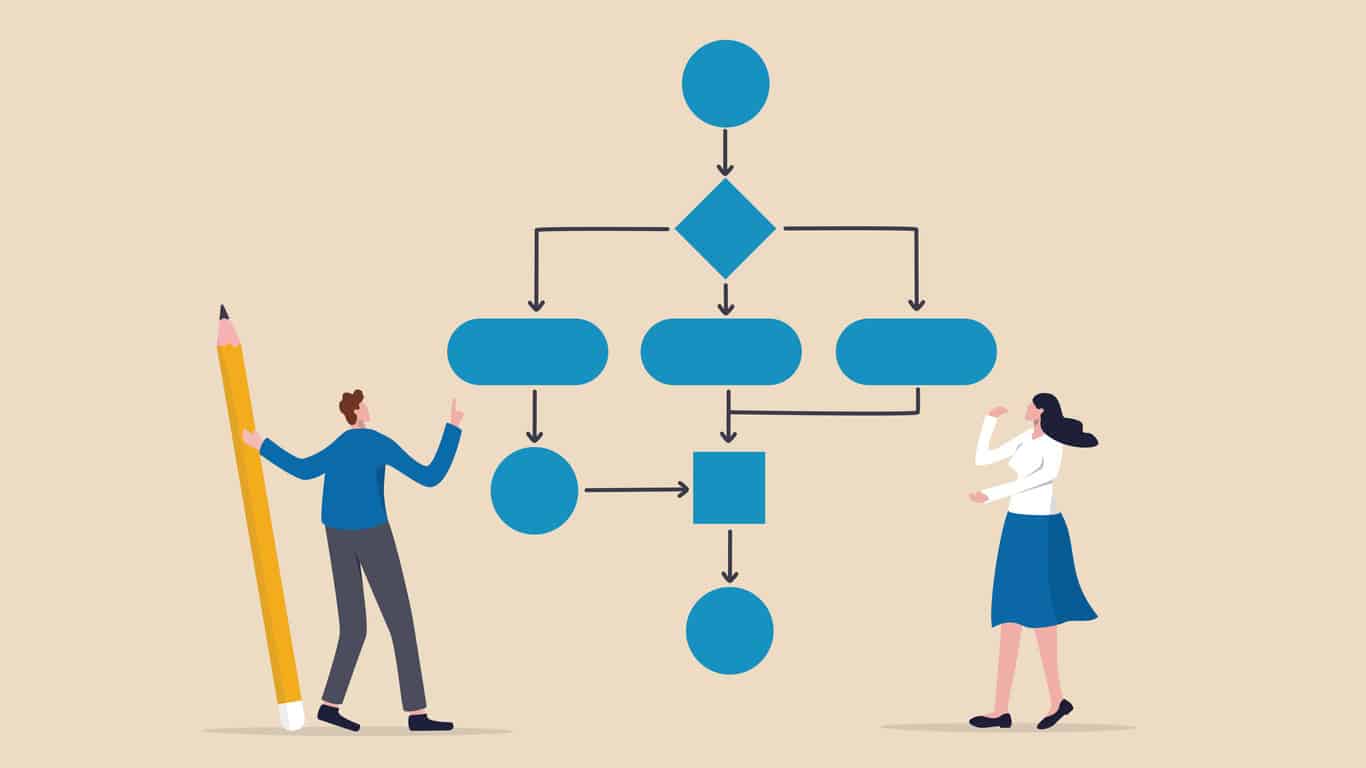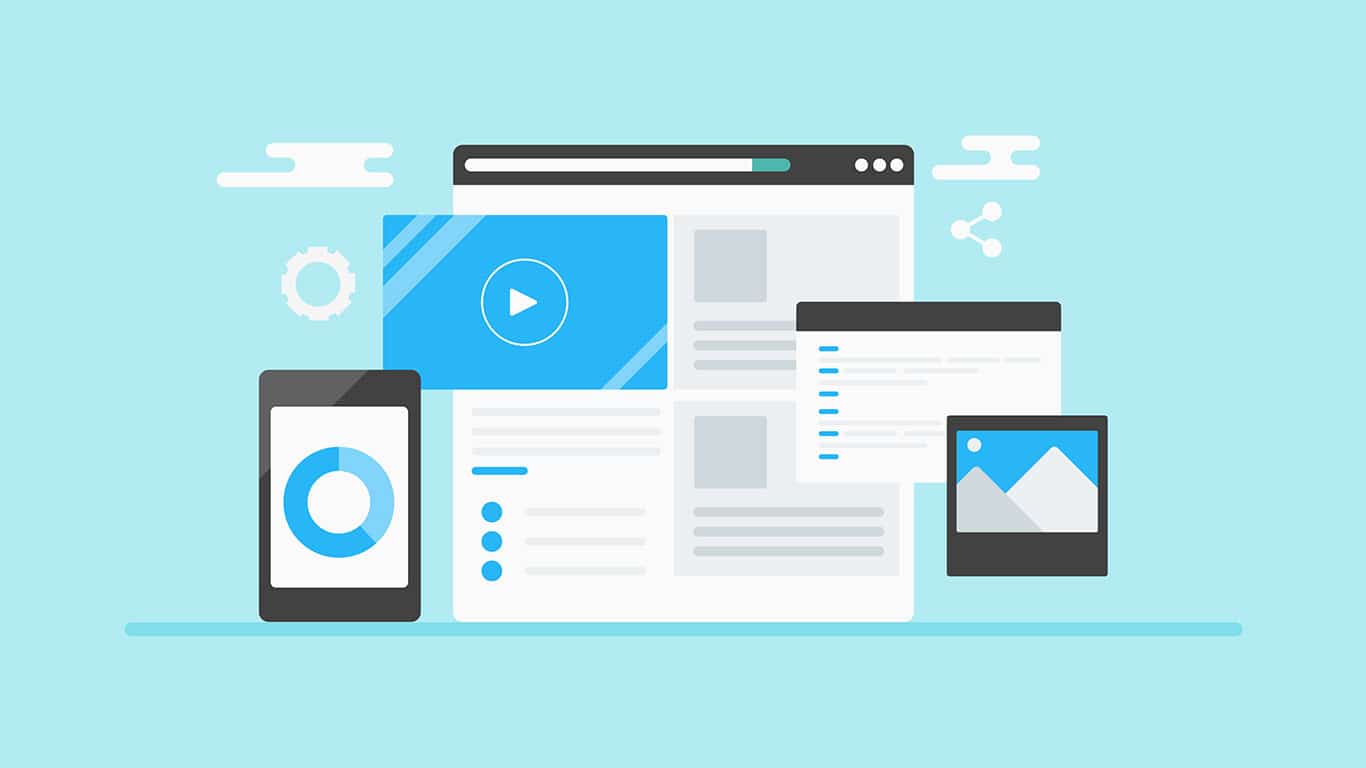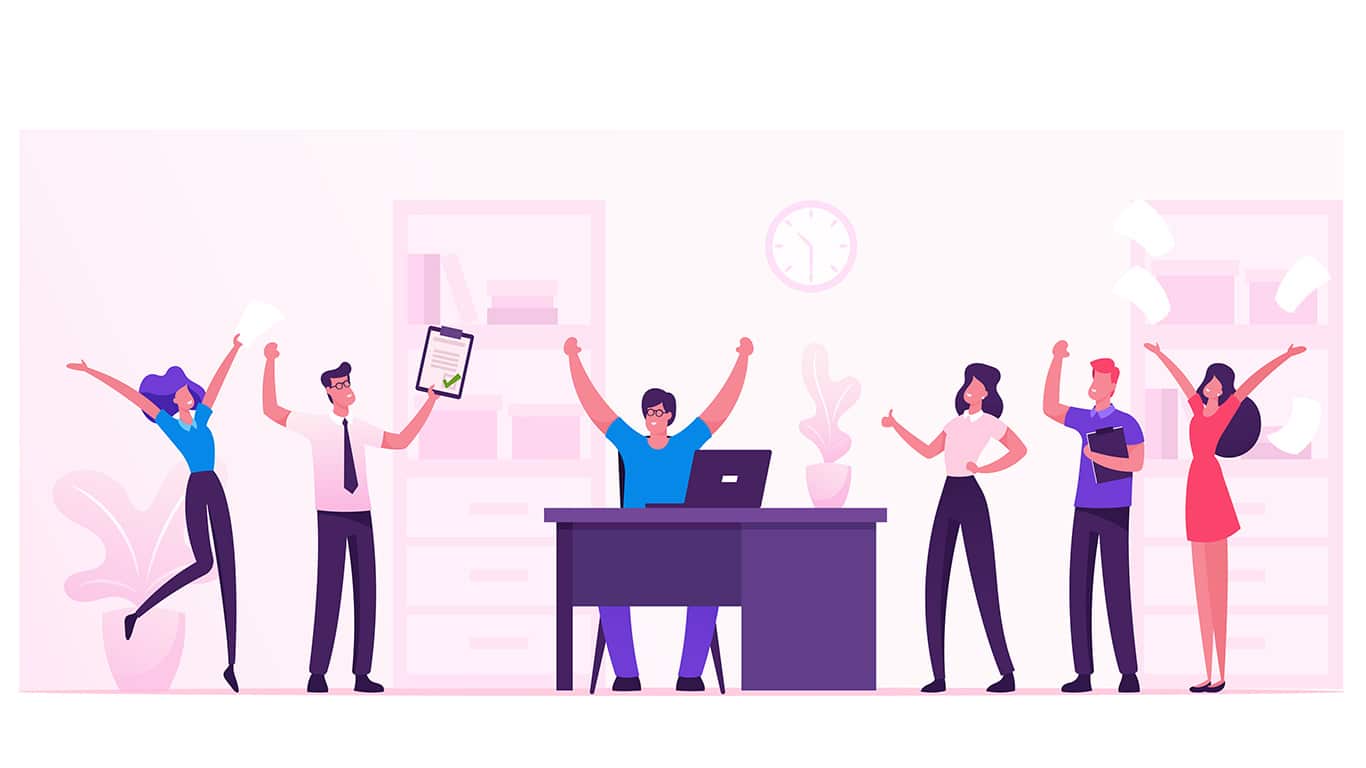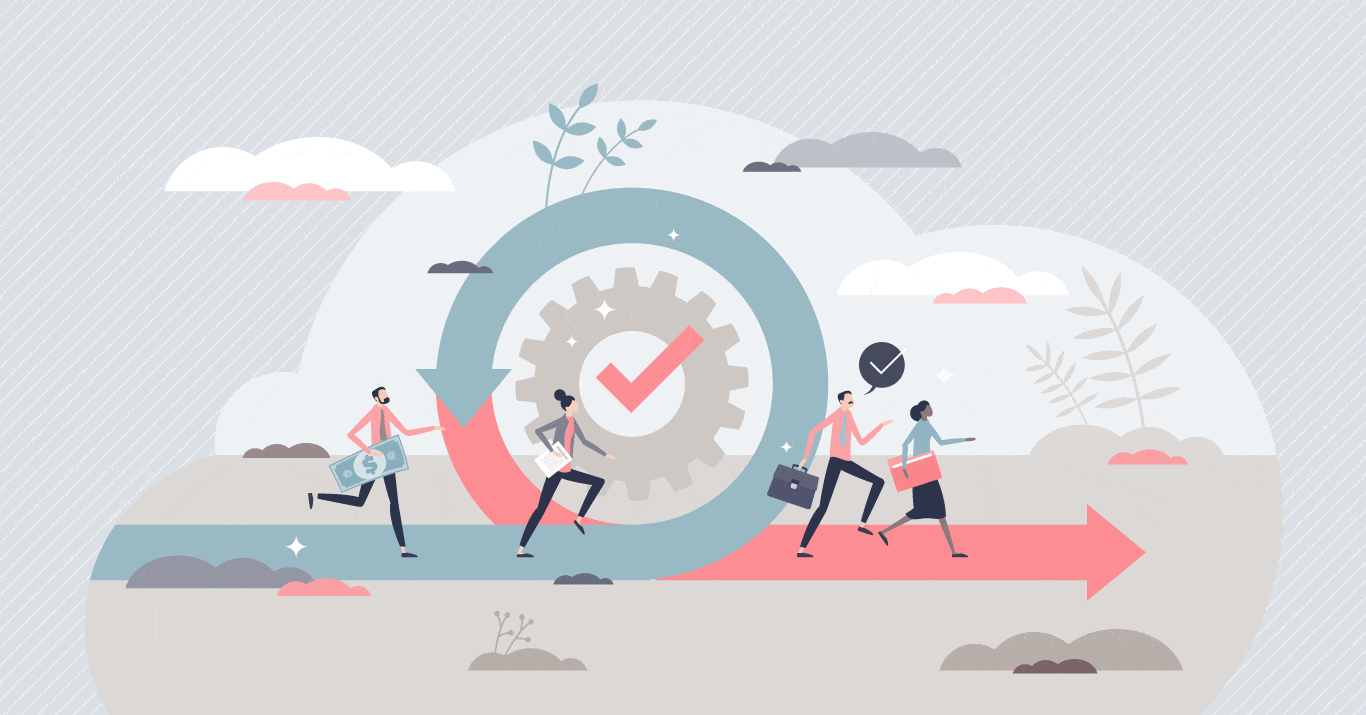ビジネスにおいてコミュニケーションで大切なことは?行動変容を起こすコミュニケーションで知っておくべきことを解説
最終更新日:2023.09.11

目次
コミュニケーションは、ビジネスを円滑に進めるうえで非常に重要なものです。しかし、普段なにも意識せずになんとなくコミュニケーションをとっているという人も多いのではないでしょうか。
現状のコミュニケーションが問題ないように見える場合でも、コミュニケーションを再考することで、企業に何らかのメリットが起こることがあります。コミュニケーションを円滑化することで社内にある課題が解消され、従業員の雰囲気が変わって活気が増すかもしれません。
そこでこの記事では、どのような点に注意すれば、効果的なコミュニケーションが取れるかを整理していきます。また、コミュニケーションについての行動変容を軸に据えつつ、大切なポイントについても解説していきます。
ビジネスにおいてコミュニケーションが大切な理由
コミュニケーションによってビジネスに及ぼす好影響は多岐にわたります。ただ社員同士が仲良くなるだけでなく、業務の円滑化・効率化をはじめ、ひいては事業や経営にまでポジティブな効果をもたらす力があります。
では具体的に、コミュニケーションはビジネスにどのような好影響を及ぼすのでしょうか。重要な影響部分について見ていきましょう。
情報共有や連携が円滑になる
コミュニケーションによって意思疎通の頻度が高まると情報共有が促進され、社員同士や部署間の連携が円滑に行えるようになります。連携が取りやすくなると業務の遂行、問題・課題解決もスピーディーになり、結果として企業の生産性にも寄与できるでしょう。
また、コミュニケーションが日常化することにより、社員同士の関係性が深まり、悩みや業務上の問題・課題について相談しやすくなる利点もあります。会社員は仕事上の繋がりといっても、人間関係における「合う・合わない」「好き・嫌い」は必ず影響してしまうもので、完全に割り切れるものではありません。だからこそ、日々のコミュニケーションによって関係性を深め、業務上のやり取りをしやすくしておくことが大切です。
これらの効果は社内の人間関係だけでなく、取引先や提携する企業とのやり取りでも同じことが言えます。日々のコミュニケーションによる情報共有・連携の向上は、ビジネス全体にポジティブな影響を及ぼすことが期待できるため、意識的・積極的に取り入れていくことが大切だと言えるでしょう。
生産性向上やモチベーションアップ
コミュニケーションが活発に行われることで、社員同士で必要な情報やノウハウの共有が行われ、スピード感を持って状況判断や問題解決のアクションを起こせるようになります。すぐに動ける状態ができていることは、対処の試行回数を増やしたり、複数のアプローチを用意したりといった、質の高い仕事を行う機会を生み出すということでもあります。問題に対して解決のための手数が増えることは、単純に適切な解に辿り着く可能性が高まるため、より良い成果を上げられる=生産性の向上に繋げることができるでしょう。
また、コミュニケーションは社員同士の距離を縮め、上司と部下の関係性や、部署間の関係性といったさまざまな人間関係に良い影響を及ぼす効果もあります。たとえば上司と部下の関係性が良好であれば部下は上司に報告・相談がしやすくなるといった間柄を構築することができます。仕事の悩みの多くは人間関係によるものなので、社内の人間関係が良好になることは社員満足度にも繋がり、社員のモチベーションアップにも寄与することでしょう。
さらに、社員のモチベーションアップは離職率の低下にも繋がり、企業としても採用コスト・育成コストの削減にもなるため、人事の側面でもポジティブな影響を及ぼす事ができます。
イノベーションとコラボレーション
ビジネスにおけるイノベーションは、専門性の違う者同士が協力し合い、コラボレーションすることで生まれる可能性が高いものです。そのため、ただ社員同士でコミュニケーションを取っているだけでは、イノベーションの壁を突破するには不十分だと言えます。
重要なことは、まず異なる専門性・経歴を持つ者同士、あるいはまったくの異業種の者同士がいかに人脈の流れの中で出会えるかどうかです。人脈は思わぬ人間関係から繋がるものであり、ここでも他者との関係性を作るためのコミュニケーションが必要になります。そういった人脈の土台を作るためにも、コミュニケーションは基礎能力として重要になるでしょう。
信頼関係が築ける
社員同士のコミュニケーションが適度に行われることで、仕事への考え方や趣味嗜好、その時々の感情などが分かり、お互いの理解を深めて信頼関係を築くことができます。相手についての情報がないと、たとえ同僚でも不安・不信・心配に繋がるものです。100%相手を理解することが不可能だとしても、ある程度は情報として相手については知っておくと円滑な関係の構築に繋がります。この信頼関係は、個別の関係性やチーム内の関係性、予期せぬ問題の発生時や危機的な状況において、強い柔軟性とレジリエンスを生み出します。
逆に、コミュニケーションを重ねていると、仕事上のやり取りや齟齬、感情的なすれ違いといった、人間関係でのトラブルを予防することもできます。人は誰しもヒューマンエラーを起こすものですし、仕事のやり方の違いや個々の社員によって業務の優先度が変わるなど、すれ違いは生まれてしまうものです。そういった小さなズレを察知して未然に防ぎ、人間関係が必要以上に悪化する前に修正するためには、日々のコミュニケーションによってお互いについて一定の理解をしていることが大切になります。
顧客満足度の向上に繋がる
顧客満足と従業員満足は、密接に関連しています。この関係をさらに強化するために、コミュニケーションが重要な役割を果たします。まず、従業員が満足している場合、その満足感は顧客にも伝わります。従業員が積極的であり、高いモチベーションを持っていると、顧客に対するサービス品質が向上し、顧客の満足度も高まるでしょう。このような状況を作り出すためには、従業員と会社や上司との間での良好なコミュニケーションが重要です。
また、従業員が不満を抱えている場合、その不満は顧客にも波及します。従業員のモチベーション低下やサービス品質の低下は、顧客の満足度を低下させる可能性があります。そのため、従業員が不満を持つ状況を早期に把握し、適切な対応を行うためには、従業員との円滑なコミュニケーションが必要不可欠です。
さらに、従業員の満足度が顧客満足度に与える間接的な影響も考慮する必要があります。満足した従業員は、会社に対する忠誠心を持ち、顧客に対する良い印象を与えます。その結果、顧客との信頼関係が強化され、顧客の満足度も向上するでしょう。
企業イメージの向上
コミュニケーションで社内の人間関係が良好になっている場合、社員は活力を持って働くようになり、顧客・取引先・提携先などの相手から良い印象を持ってもらいやすくなります。企業イメージとはある種のブランドとも言え、その企業の信用・信頼に関わってくる重要な部分であり、商品・サービスの売上や経営にも影響を及ぼすとも言えます。
企業イメージが向上すると、顧客は信頼感を持って自社との商談の席に付き、提携先の企業も「〇〇社さんなら安心して仕事をお願いできる」と信用してくれるようになります。顧客・取引先・提携先など、外部との阿吽の呼吸は経営の追い風となり、企業としてより成長していける土台にもなることでしょう。
さらに、企業イメージの向上は人事・採用の場面にも波及します。求職者に自社の社員が前向きに活発に働く姿を見てもらうことで、「この会社で働いてみたい」と強く感じてもらうことにも繋がり、特別な求人のプロモーションをかけずとも自社の魅力をアピールすることができます。モチベーションの高い求職者が集まることは経営にとってもプラス材料であるため、企業の将来にもポジティブな影響を及ぼすと言えるでしょう。
コミュニケーションで大切なことはコミュニケーションの目的を理解すること
コミュニケーションをとるうえで大切なのは、そもそもそのコミュニケーションが何を目的としているのかを理解することです。
多くの場合、コミュニケーションは2つの種類に分けることができます。
- 相手の行動変容を促すコミュニケーション
- 自分の行動変容を促すコミュニケーション
相手の行動変容を促すコミュニケーションの場合は、何かしらの情報を相手に理解してもらうことが目的とされています。情報を理解してもらうことで、相手の考えや行動に影響を与えることができ、相手が学びを得て行動を少しでも変えてくれるでしょう。また、共通した理解や価値観を形づくることも可能にします。
そのため、相手の行動変容を促すコミュニケーションの際には、相手の気持ちや思考の癖を理解し、相手との信頼関係を築いたうえで進めていくことが重要です。また前提として、相手に行動変容のメリットを感じてもらうべく、相手の抱える問題やニーズを踏まえながら問題を収集・提示することも効果的です。
一方、自分の行動変容を促すコミュニケーションの場合は、自分の意識を変え、振る舞いを変えていくことが目的となります。自分の抱えるニーズや課題を明らかにした上で情報を集め、自分自身に何かしらのアドバイスを与えられるようにコミュニケーションをとります。その際、行動変容を起こしやすいように、自分の心理状態を整えることも不可欠な要素です。
コミュニケーションの不可能性を知ることが大切
コミュニケーションは、考え・感情・価値観を相手に伝え、それを受け手がどう認識したかで伝達した内容が決定するものです。言葉だけでなく、ジェスチャー・表現・声のトーン・視線・置かれた状況など非言語的要素も含まれるため、必ずしも意図した内容が相手に伝わるとは限りません。そのため、1度で伝えるのではなく、会話のラリーを繰り返すことで互いの認識をすり合わせることも必要で、「言わなくてもわかるだろう」や「分かって当然」といった態度は厳禁です。
ビジネス上のコミュニケーションで問題になりがちなのが、上司が部下に言う「同じことを何度言わせるんだ」というセリフです。上司からすると同じことを何度も伝えている認識かもしれませんが、受け手である部下は置かれた状況やその時の思考・感情などにより、上司の意図とは異なった受け取り方をしている可能性があります。
コミュニケーションの種類は多種多様であり、その状況に依存する場合が多いのも事実です。1on1の場で部下を称賛し動機付けしようと褒めても、部下と上司の関係や発言者の声の調子、発音の仕方によって、受容者への侮蔑表現にもなりえます。
上司としては、同じことを何度も繰り返し伝えているつもりでも、実際には伝わっていないことがあるのは、今と過去、そして状況や相手も変化しているためです。「伝わった」という思い込みを持つことは、事実上は「伝わったかな」という程度の認識に過ぎません。これは、良い関係や理解を築く上で重要な認識です。
コミュニケーションは状況に応じて伝わりやすさの起伏が変化するのが当たり前で、常に一定の伝達力がキープされているわけではありません。時には身体的な不調に左右される場合もあり、一見して同じ社員でも、受け手としての状態はその時々によって精度が変わってきます。
このようなコミュニケーションの齟齬はビジネスのあらゆる場面で起きており、そもそもコミュニケーションは伝わらないものという不可能性を見失っていることが原因です。まずは伝わらない前提に立ち、その上で相手に伝えるためのコミュニケーションのアプローチを考えることが第一歩になるでしょう。
行動変容を起こすコミュニケーションで知っておくべき大切なこと
上記で解説したように、コミュニケーションとは自分もしくは他人の行動変容を促すもので、シンプルに見えて実は複雑な行為です。思うように意図を伝え合うことは難しいものですが、それでもコミュニケーションを通して行動変容を実現したいという場合に知っておくべきコツがあります。
以下では、行動変容を起こすコミュニケーションをとるうえで、重要なポイントを紹介します。
相手の視点・背景・立場などを理解する
まずは相手の置かれている状況を理解することです。相手がどのような立場でどのような考えや価値観のもとで生きているのかを理解していきます。これにより相手の気持ちが具体的に想像できるようになり、コミュニケーションがスムーズになります。
発信者が伝えたい内容は重要ですが、同じく受信者との共通点を探り、相手に寄り添うことも同様に重要となります。
人種差別撤廃運動を率いたマーティン・ルーサー・キングの有名なスピーチ「I Have a Dream」は、非常によく知られています。このスピーチは、人種差別に苦しむ人々へのメッセージでありながら、多くの人々に響くフレーズを含んでいます。言い換えれば、キング牧師が自分の視点・背景・立場などを聴衆と共有するために言葉にしたものです。
ビジネス現場では、役員に対して、社員に対して、部下に対して、顧客に対して、理解と納得を得るために、相手の徹底的な分析が必要です。相手の立場、役割、問題意識、周辺環境、心理状態、要望など、できるだけ多面的に理解しましょう。
そして、共通点を見つけ出し、強調し、同じであることを伝えます。この取り組みは、相手に対する誠実さを表します。発信者と受信者の共通点と共感点を見つけることが重要です。
受信者の業界用語や専門用語を、わざと発信者が使うような手法をディコーラム(適切さ)というが、言葉や記号に意味がある訳ではなく、伝わるという目的に意味があるという良い例です。
差異性と双方向性を理解する
行動変容を起こすコミュニケーションを行うには、「差異性」と「双方向性」について理解しておかなければなりません。「差異性」とは人それぞれ異なる部分のことで、「双方向性」とはお互いに興味を持ち合ってコミュニケーションを取り合うことです。
「差異性」「双方向性」がコミュニケーションを取る上でどのように重要なのか見ていきましょう。
差と反復
コミュニケーションにおいて「差(=差異性)」とは、前提事項となる相手と自分の異なる部分を指します。文化的背景・各個人の経験・生い立ちなど、その人の思考や行動を形作っているバックボーンはそれぞれ異なり、同じ物事を見聞きした場合でも、人によって意見・対処に違いが生じてきます。
コミュニケーションを取るためには、相手と自分は違うという前提の「差」を押さえておき、やり取りを繰り返し行いながら「差」と共通性を選り分け、適切な距離感を保ちながら意思疎通を行って理解を深める必要があります。
また、コミュニケーションの起点は、差ではなく同一性や共通性に目を向けますが、価値を創造するためには、差異に目を向ける必要があります。特に創造的なブレンストーミングやヒリヒリとして議論を超えた合意形成においては、差異に着目する必要があります。
日々一緒に働く職場の仲間やプロジェクトメンバーも、昨日と今日では、変化があります。去年と今年ではさらに変化しているでしょう。しかし、人間は共通かつ同一でありたいと思っていることの方がほとんどです。そのため、変化しているのに仮面を被って鳴りを潜めていることの方が楽なのです。
コミュニケーションは、差異と同一という反復の中で、適切に距離感を保つための道具です。微細な変化をしっかりと確認することができれば、突然の部下の離職やメンバーのうつ病など未然に防ぐことができるでしょう。
また、仕事に関する価値観や手法が違っても、共通性で共感し合いながら良好な関係をコミュニケーションで再構築することはできますし、人間関係に「差=違い」があるからこそ、多様で柔軟性を保ち、自己と他者は変化できます。お互いに「差」があり、変化している前提を持つことは、良好かつ良質な人間関係を構築する上で重要な基礎となります。逆に常に変化していないのであれば、コミュニケーションは発生しないと言っても過言ではありません。
双方向性とは
双方向性とは、お互いが興味を持ち合った状態でのコミュニケーションを指します。前項でお伝えしたように、「差(=差異性)」を踏まえた上で共通性を見出し、お互いの主義主張・好み・怒りや不快感を覚える部分に配慮しながら取るコミュニケーションや、お互いの差異から新しい価値や創造を生み出すコミュニケーションです。
このことに関しては、多くの人が直観的に理解できるのではないでしょうか。人と仲良くなるには、同じ趣味や好みを共有するところから入るものですし、嫌な気分になる話題などには触れないものです。ビジネス上の人間関係でも同じことが言え、お互いの共通性を見つけ、配慮に富んだアプローチを双方向に行うことで、コミュニケーションの質を高めることができます。
双方向性は、互いの言語や身振りである見えるコミュニケーションから、相手の人格や考えている事を想像し、自分と違うと思えばイライラし、同じだと思えば安心するという感情的な揺れ動きが生じます。つまり、言葉や身振りである目に見えるものを手掛かりに想像し、葛藤したり、新しい価値に気づいたりするわけです。
日本の伝統的な演芸の落語は、一人の噺家(発信者)が座布団の上で、顔や身体の動きと言葉を使って物語を語ります。このシンプルな状況で、観客(受信者)は笑いを感じるのです。この現象は、映画や演劇と比べて情報が少ないにも関わらず、噺家と観客の間で共有する見えない想像が働いているということです。
ビジネスのコミュニケーションにおいても、ホワイトボードや資料は、通常は見えない想像過程を可視化するツールです。コミュニケーションは相互のやり取りであり、この過程の共有が非常に重要です。ビジネスにおけるドキュメント化や可視化の実践は、この共有過程の重要性を反映しています。落語における笑いと同様に、ビジネスコミュニケーションでも、創造的な協働を生み出す力があります。この過程は、想像から創造へと変わり、その中には喜怒哀楽といった感情が含まれています。会議や集まりの際に、コミュニケーションから創造を生み出すには、ワクワクやハラハラといった感情が重要な役割を果たします。
双方向性において重要なことは創造であり、それを何かしらの形で共有する場やツールは、コミュニケーションにおいて重要な要素です。
メラビアンの法則とは?
コミュニケーション能力を語る際に、紹介されるメラビアンの法則というものがあります。この法則ではコミュニケーションにおいて言語情報は7%、聴覚情報は38%、視覚情報は55%と主張します。
商談や同僚との会話、上司への報告など、重要なビジネスコミュニケーションにおいては、言葉の正確さだけでなく、自分の雰囲気や印象にも気を配ることが肝要です。これはよく言われることですが、成功するビジネスパーソンは、日頃から自分自身を鏡で見つめることを心掛けています。
さらに、メラビアンの法則によれば、感情的なメッセージを伝える際、発言する言葉と声のトーン、ジェスチャーが一致していないと、誤解を招く可能性があります。たとえば、感謝の意を伝える際に、適切な表情や声のトーンを欠いていると、相手には嫌味に受け取られたり、誠実さを感じられなかったりすることがまれにあります。
そのため、ビジネスコミュニケーションでは、言葉だけでなく、自分の雰囲気や印象、声のトーン、ジェスチャーにも注意を払うことで、相手との信頼関係を築き、コミュニケーションの効果を高めることができます。
コミュニケーションにおいて最も重要なのは、相手がどのような反応を期待しているかを理解することです。言葉による情報伝達が全体の7%を占めるとされる中、伝えたい内容や状況、目的に応じて、言語情報だけでは不十分な場合があります。そうした状況では、聴覚や視覚情報をどのように取り入れるべきかを意識する必要があります。これは、コミュニケーションの手段を選ぶ際に重要なポイントです。例えば、チャットではなく対面で話すべきか、ウェブ会議を利用するのが良いか、あるいは1対1の会話が適切かなど、コミュニケーションの形式をその前提に基づいて選ぶことが必要です。
言語・非言語コミュニケーションを理解する
言語によるコミュニケーションとは、言語を用いて情報を伝えたり、考えていることを伝えたりするものです。対面や電話などの口頭での会話、メールやチャットなどの文面での会話など、さまざまな形式があります。
非言語によるコミュニケーションとは、言語以外の手段で情報や考えを伝えていくものです。たとえば相手の目線や声色、身振り手振りやジェスチャーなどが、非言語的なコミュニケーションの代表例です。相手と円滑なコミュニケーションを図る際には、言語による情報だけでなく、非言語による情報も意識して行いましょう。
メラビアンの法則では、言語情報は7%、聴覚情報は38%、視覚情報は55%とされています。動画を簡単に送れるTikTokやYouTubeに代表される個人が動画を活用したコミュニケーションは、文字情報よりはるかに多くの情報を伝えることが可能であるということです。
また、ハラスメント問題においては、言葉自体を拘束するようなルールや規定があります。非言語の部分こそが差別やハラスメントの温床になることを知っておくべきです。
沈黙、無視、避ける行為や視線の使い方によって、相手の感情を傷つけることが十分にあり得るのです。間違ったことを言っていなくても、ノンバーバルなレベルでは相手を傷つけることがあることを管理職は理解しておくべきです。
言語論・記号論の観点では、伝達手段は言語のみとは限らず、服装や身振り、雰囲気など、人は多くの要素を使って情報を伝えていると説きます。その意味で、メラビアンの法則は記号論の流れに位置づけられる研究であり、とくに重要な指摘は、言葉と態度のメッセージが一致すべきだということです。
記号論では、言葉だけが手段ではないため、発信者は他の要素からも常にメッセージを発していることに留意していくべきです。とくに重要な商談や同僚との会話、上司への報告などでは、言葉だけでなく、服装や身振りを含めた自分が漂わせている雰囲気が、メッセージに適しているかどうかを常に気にかけておくべきです。
そして、非言語と言語のコミュニケーションの解釈は、言語部分を調整しても10%以下であり、非言語のコミュニケーションにこそコミュニケーションの本質があるということを理解するべきでしょう。
コミュニケーションには動機が必要
コミュニケーションには、動機が不可欠です。「この情報を伝えたい」「この意見を伝えたい」などの明確なモチベーションがない場合、コミュニケーションは成立しないと言ってもいいでしょう。自分の意見や思いを相手に伝えたいというモチベーションにより、円滑なやりとりが実現します。
同時に、「相手がどれくらい聞きたいと思っているのか」という相手の動機も重要です。互いに動機があることで、情報や意見が活発に交換される良質なコミュニケーションが実現します。しかし、互いにモチベーションがある状態のコミュニケーションはなかなか成立しないケースが多いでしょう。少なくとも発信する側は一方的にでもコミュニケーションへの動機を持っていないと、上手なコミュニケーションは図れません。
フォーマルとインフォーマルのコミュニケーションを理解する
コミュニケーションには、「フォーマルコミュニケーション」と「インフォーマルコミュニケーション」の2種類があります。
「フォーマルコミュニケーション」とは、決められた形式で行われるコミュニケーションのことです。たとえば、会議、プレゼンテーション、報告書などがこれにあたります。
「インフォーマルコミュニケーション」は、決められていない自然な形式で行われるコミュニケーションのことです。具体的には、日常で繰り広げられる会話や雑談、飲み会における会話や、カフェでの会話などがこれにあたります。
状況に合わせて、フォーマルコミュニケーションとインフォーマルコミュニケーションを使い分けることで、真剣に話し合いができたり、会話が弾んだりと、コミュニケーションを充実させることができるでしょう。
論理と感情について理解する
コミュニケーションにおいて、論理と感情を理解することは重要です。論理とは、推論や分析に基づく情報伝達で、感情は人の内面を指すものです。両者は影響しあって、コミュニケーションの形を作っていきます。
たとえば論拠に基づいた話は、コミュニケーションを円滑に進ませますが、相手が感情的になってしまっていると、そもそも論理的な話の展開を受け入れられないことがあります。感情的なコミュニケーションは、相手に強く訴えかけるようなコミュニケーションができますが、背景に論理性がない場合は理解されにくく、正確な情報として受け取ってもらえません。
もし、論理的な話をしたいのに相手が感情的になっていたら、相手の感情にまず寄り添い理解を示すことで、受け止める土壌を作ってもらいましょう。反対に、相手が感情だけの主張をしている場合には、事実や論拠を踏まえて説明するように促しましょう。
このように論理と感情の両者のバランスをとることが大切です。どちらかが失われるとコミュニケーションが妨げられる懸念があります。コミュニケーションをとる際は、現状どのようなバランスになっているのかに注意を払い、適切に働きかけることが重要です。
現在の論理をいくら積み上げても解決できない問題を、熱量や動機の力を借りて解決していく場面や、人間の感情が阻害することにより、簡単な問題がなかなか前に進まない状況もよくあります。
「対話」について理解する
最近、ビジネスで使われる「対話」という概念は、互いの立場や意見の違いを考慮しながら、共通の理解と認識を得るために行われるコミュニケーション方法です。
対話と同様の概念として、「会話」がありますが、対話は特定の目的を持つ一方、会話は特定の目的を持ちません。会話にも感情を込めることはできますが、ビジネス上有効なのは、目的を持った対話です。
対話の場では、自身の行動や発言の背後にある感情や考え方、価値観について掘り下げて話を進めます。これにより、普段は意識していない要素を言語化し、顕在化させることで、相手と自身の双方の立場の視点から、議題や話題について客観的に捉えることができます。
また、対話では相手の感情や心理的な葛藤にも目を向ける必要があります。人は感情的な生き物であり、コミュニケーションの中で喜びや怒り、不安や期待などの感情が絶えず動いています。
これらの感情や心理的要素を無視してコミュニケーションを行うと、相手が抱える本当のニーズや意図を理解することが難しくなります。感情や葛藤に耳を傾け、相手の立場や要望を理解することで、共感的なコミュニケーションが生まれます。その結果、双方が納得し合える解決策や協力関係を築くことが可能となり、本当の価値創造が実現されるのです。
コミュニケーションの「場」を作る上で大切なこと
コミュニケーションをとる際には、最適な「場」を作る意識が重要です。では、具体的に、「場」を作る際にはどのような点を意識するといいのでしょうか。
コミュニケーションには「場」が構造化する
コミュニケーションには、バーバル(言語や身振り手振り)とノンバーバル(空気や関係性など目に見えない要素)の要素があります。場所や状況がコミュニケーションに大きな影響を与えることがあり、同じ内容でも場所が異なれば伝わる意味や文脈が変わります。コミュニケーションの成功には場の整合性が重要であり、場を適切に設計することで共通の足場ができ、円滑なコミュニケーションが可能になります。
たとえば、落語では、落語家が正座しながら語り、動くことで落語噺を聞かせています。観客はこれだけで同じタイミングで笑います。観客が、目に見えない創造物を想像しながら見ていることで、噺家と観客の間に思考の共有が生まれている実感が沸くからです。つまり、場自体が、思考を誘引し想像を誘引しコミュニケーションを産み出すことが可能とも言えます。
ビジネスでも、目に見えない場を一同が同じように捉えることで、同じ思考を共有しているという考えが生まれます。すべて同じ会議室ではなく、そこで産み出されるコミュニケーションにあわせて、物理的構造を変え、コミュニケーションを意図的に誘引することは可能です。
デジタルの場でも一緒で、チャットやメール、社内SNSなどデジタルの場をある方向性に誘引する場として設計されている企業はコミュニケーションが非常に円滑です。
適切な「場」を創造する上でのファシリテーターの重要性
適切な「場」を作る重要さは理解できても、どのように作っていけばいいのか迷う人も多いかもしれません。適切な「場」を作るためには、ファシリテーターの存在が重要です。ファシリテーターが、グループが向かうべき方向や目的、テーマを明示することで、メンバーは安心して場に参加でき、異なる意見や価値観も伝えやすくなります。
ファシリテーターはメンバーに発言を促し、多様な意見を引き出していきます。もし意見の食い違いや対立が起きたなら、その都度フォローし調整していきます。この際、ファシリテーターは常にオープンな態度をとっていることが大切です。信頼関係を築くことで、目的に向かって円滑にコミュニケーションをとっていきます。
コミュニケーションがとれるようになったら、メンバーからのフィードバックに耳をすませ、反映していくことで、より場づくりがうまくいくでしょう。
ファシリテーターの役割や、必要なスキル、メリットについては以下の記事をご参照ください。
コミュニケーションのツールを利用する上で大切なこと
好調な企業の社内の様子を見てみると、コミュニケーションが活発で、風通しの良い職場であることがほとんどです。
従来なら同じ背景を持った、均質化された社員が毎日同じ場所で顔を合わせていたため、活発なコミュニケーションを促すことは比較的容易でした。しかし、昨今ではテレワーク普及や雇用の流動化により、多様性のある個人が遠隔で意思疎通を図ることが求められる状態に置かれています。以前のようなハイコンテクストコミュニケーションが不可能になった中で、多くの好調な企業が導入しているのが、デジタルツールです。
テキストチャットやビデオ会議システム、社内SNS、グループウェア(デジタルワークプレイス)などが代表的です。これらを導入することにより、メールよりもコミュニケーションのハードルが下がり、コミュニケーションの頻度がアップします。イラストを使ったスタンプ機能を搭載しているツールもあり、雑談のようなカジュアルなコミュニケーションがとれるようにもなります。通常の業務では接点を持ちにくかった他部門のメンバー同士が交流するようになり、これまでにないイノベーティブなアイデアが生まれやすくなるという変化も期待できるでしょう。
また、これらのツールは、導入するだけでコミュニケーションを強化できると考えられがちですが、単にツールを導入しただけではコミュニケーションはほとんど活性化しません。コミュニケーションを価値のあるものにするかどうかはあくまでも人です。だからこそ導入の前に、今までどのようなかたちでコミュニケーションをとってきたのかなどを可視化し、現状の課題からアプローチしていく姿勢を忘れないようにしましょう。
組織におけるコミュニケーションの大切さ
「組織」と「従業員」とのコミュニケーションと「職場」内での「従業員間」のコミュニケーションは、いくつかの面で異なります。その最も大きな違いはコミュニケーションのスタイルです。
大企業の場合、従業員数が多く、多くの情報をリアルタイムで伝える必要があるため、マス的な(一方的に多くの情報を伝える)コミュニケーションが主流です。このようなコミュニケーションでは、抽象度が高く、演出の要素が多くなりがちであり、経営陣と社員の間に直接的な関係性を構築することが難しく、一つの社員が組織全体の状況を広く深く理解することも困難です。
一方、「職場」内での「従業員間」のコミュニケーションは、直接顔を合わせて会話ができる環境があります。このため、コミュニケーションは頻度が高く、従業員同士の人となりが反映されやすくなります。職場は、従業員同士が精神的なつながりを求められるゲマインシャフト(共同体)に近く、日々の挨拶やコミュニケーションが重要です。
組織と職場では、異なるコミュニケーションのスタイルが求められます。組織では情報の伝達が重視されますが、職場では従業員同士のつながりが重視されます。両方の側面を均衡させるためには、リーダーシップや従業員のコミュニケーションスキルが重要です。そして、物理的資本よりも人的資本が重要視される現代の産業構造では、職場内のコミュニケーションが人的資本のパフォーマンスを向上させるカギとなります。
しかし、職場内の社員にはコミュニケーションが苦手な人もいます。そのような場合でも、コミュニケーションを通じて社員同士がつながることが重要です。
ビジネス上の円滑なコミュニケーションは利益にもつながる
ビジネスにおける円滑なコミュニケーションは利益につながります。コミュニケーションは情報伝達だけでなく、企業や組織の成果や経営・運営に欠かせない要素です。そのため、コミュニケーションスキルを磨くことは非常に重要です。
人は考えるだけでなく、話すことで他者と情報を共有します。ビジネスコミュニケーションは、人生のあらゆる場面で役立つ要素です。コミュニケーションは誤解が避けられないものですが、それを減らす努力を職場の各個人が行い、円滑なコミュニケーションを楽しみましょう。コミュニケーションはビジネスの利益にも繋がり、それを実感できる職場は成功を約束されています。性別や年齢、経験、人種に関係なく、コミュニケーションの重要性を意識した職場での成功を目指しましょう。
まとめ
コミュニケーションはビジネスを円滑に進める上で大変重要なものです。社内にある課題は、コミュニケーションを円滑化することで解消される場合もあります。だからこそ、なんとなく現状維持するのではなく、現状のコミュニケーションをしっかり見直していきましょう。
コミュニケーションをとる際にまず大事なのは「この情報を伝えたい」「この意見を伝えたい」などの明確なモチベーションです。そのモチベーションをもとに、相手の視点・背景・立場を踏まえながら関わっていくことで意味のあるコミュニケーションが完成します。その際、本記事を参考に「共通性」「差異性」「双方向性」などの細かい要素を意識すると、解像度が上がります。また、より良いコミュニケーションを実現するためには、ファシリテーターが適切に調整を行うことと、コミュニケーションツールを導入してやりとりを活発化させることが効果的です。
コミュニケーションは企業の実績や従業員のエンゲージメントに大きく関わってくるものです。積極的に見直し、改善していきましょう。