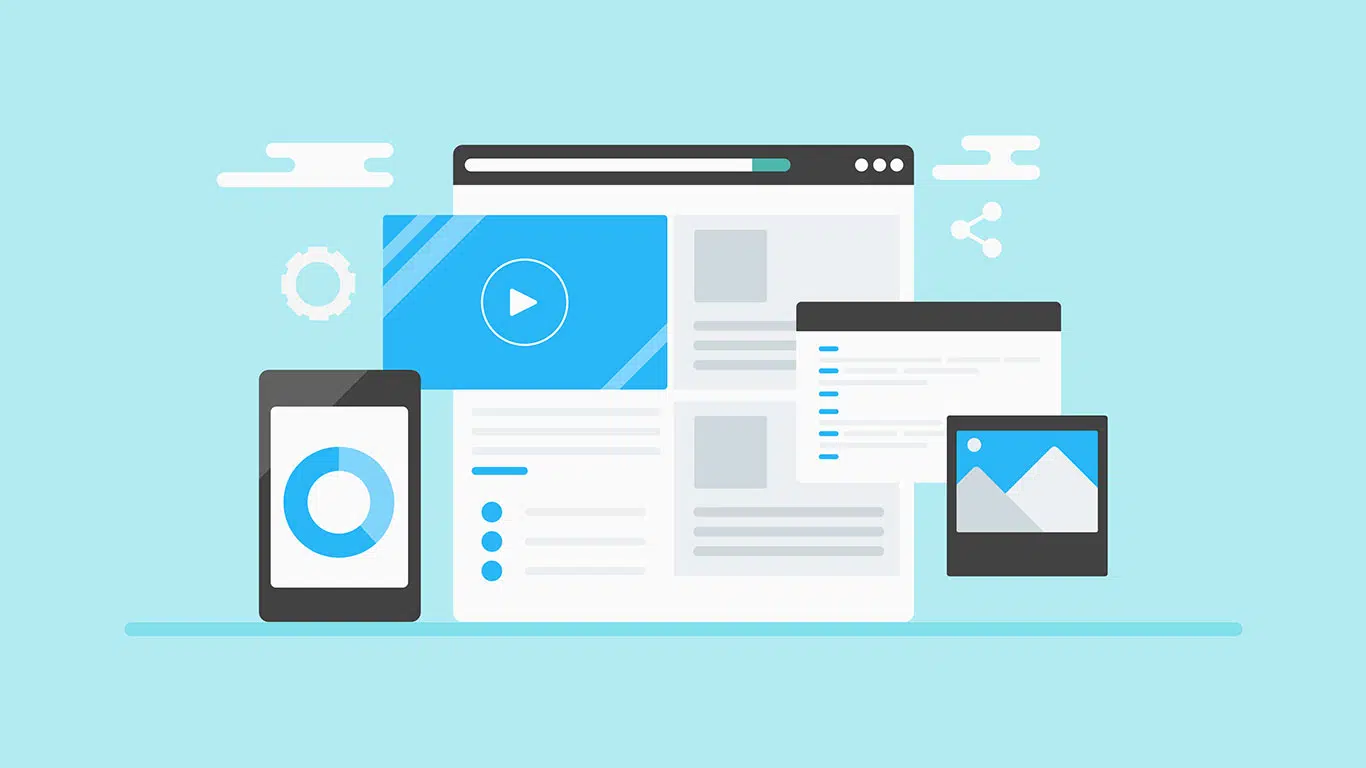リーダーシップとは?リーダーに求められる能力やとるべき行動について解説
最終更新日:2024.05.08

目次
近年は企業・組織で働く社員が多様化し、法規制・コンプライアンス・ハラスメントの明文化など、労働の形が大きく変わってきています。このような複雑化したビジネスの現場では、型にはまったリーダーシップではなく、状況ごとに柔軟に対応し、メンバーを巻き込みながら目標達成を目指すリーダーシップが求められています。
しかし、日々の業務に追われ、日進月歩で変化するビジネスのルール・常識に対応しながら、人を束ねる役職者が旧来のリーダーシップから脱することは容易ではありません。
そこで、リーダーシップとはそもそも何なのか、近年のビジネス環境にふさわしいリーダーに求められる能力・行動について解説しています。
リーダーシップとは?
リーダーシップとは、企業・組織などの集団を導き、目標達成へと牽引する力を指します。従来は管理職・リーダーといった限られた人たちの役割だと考えられていましたが、テクノロジーの進化やグローバル化によって変化の速度が加速した現代ビジネスにおいては、個々の社員・メンバーそれぞれがリーダーシップを持つことが大切です。それぞれが自覚を持ち、周囲を巻き込みながら目的達成に向かうことで、企業・組織全体のパフォーマンスを飛躍的に向上させることが求められています。
リーダーシップの定義
オーストリアの経営学者ピーター・ドラッカーは、「リーダーシップは単なる素養や資質ではなく、〈仕事・責任・信頼〉の3つの要素によって構成される」と提唱しました。
-
- リーダーシップは「仕事」である
リーダーの役割は、企業・組織などの集団の目標を明確に示し、必要な基準や優先順位を設定することです。それらを維持しながら、社員・メンバーを導き、目標達成に向けて行動することが求められます。
-
- リーダーシップは「責任」である
リーダーは、地位・権力・特権を利用するのではなく、立場を活かして社員・メンバーを支援し、業務や行動の責任を負うことが求められます。
-
- リーダーシップは「信頼」に基づくものである
リーダーは、常に一貫性のある言動を心がけ、監督・指導・行動のすべてに責任を持つことで、社員・メンバーからの信頼を獲得する必要があります。信頼関係が築かれることで、社員・メンバーはリーダーに自立的・自発的に業務に臨み、企業・組織全体のパフォーマンスの向上につなげます。
企業・組織などの集団が成果を上げるためには、社員・メンバーそれぞれが自主的に行動し、協働できるようにリーダーが導く必要があります。そのためには、リーダー自身が〈仕事・責任・信頼〉の3つの力を高め、スキルとしてのリーダーシップを磨き続けることが不可欠です。
PM理論とは
社会心理学者である三隅二不二(みすみじゅうじ)氏が提唱したPM理論は、リーダーシップを「目標達成機能(P)」と「集団維持機能(M)」の2つの軸で分析した上で4つのタイプに分類し、リーダーシップの本質をわかりやすく解説しています。
P機能は、組織の目標達成に必要な計画立案・戦略策定・指示・進捗管理・指導などを指します。業務の効率化や生産性向上、規則遵守などを促すことで企業・組織を活性化し、目標達成を導くための能動的な行動を包括したリーダーシップのことです。
M機能は、社員・メンバーへの声かけや配慮、悩み・不満のヒアリング、トラブル・対立の解決、集団内の良好な雰囲気・人間関係作りなどを促し、社員・メンバーの心理的安全性を確保するリーダーシップを指します。チームワークを向上させるための行動であり、チームビルディングや采配の調整といった役割も果たすリーダーシップです。
PM理論では、P機能とM機能のバランスを考慮し、リーダーシップを4つのタイプに分類しています。
【1.PM型】
-
- P機能とM機能の両方が高い水準を持つリーダーシップです。組織をまとめ、目標達成も可能にする理想的なリーダーシップといえます。
【2. Pm型】
-
- P機能は高いが、M機能が弱いリーダーシップです。目標達成は可能ですが、他の社員・メンバーを牽引する求心力は低い可能性があります。
【3. pM型】
-
- M機能は高いが、P機能が弱いリーダーシップです。他の社員・メンバーを牽引する求心力は高いですが、目標達成が難しい可能性があります。
【4. pm型】
- P機能とM機能の両方が低いリーダーシップです。組織をまとめる力も目標達成能力も低く、リーダーシップとしての役割を果たせていない状態といえます。
PM理論は、リーダー自身の行動を振り返り、P機能とM機能のバランスを意識することで、より効果的なリーダーシップを発揮するための指針として役立ちます。
理想的なリーダーは、状況に応じてP機能とM機能を使い分け、組織の目標達成とメンバーの成長を両立させることができる人物です。PM理論を理解し、自身のリーダーシップを磨き続けることで、企業・組織全体のパフォーマンス向上に貢献できるでしょう。
リーダーシップとマネジメントの違い
リーダーシップに似た概念にマネジメントがありますが、この2つは似て非なる概念です。
リーダーシップは、企業・組織などの集団を目標に向かって牽引する能力です。理念やビジョンを共有し、時に社員・メンバーを鼓舞し、変化に対応しながら目標達成へと導く力が求められます。
一方、マネジメントは、目標達成に適した手段や戦略を考え、企業・組織などの集団を管理する能力です。計画立案・実行・評価・改善といったサイクルを回し、効率的に目標を達成するための仕組み作りが主な業務になります。
リーダーシップとマネジメントは異なる概念ですが、この2つは企業・組織の運営にとって欠かせないものです。
SL理論とは
SL(Situational Leadership)理論は、状況に応じたリーダーシップを意味する概念であり、1977年に行動科学者のポール・ハーシーと組織心理学者のケネス・ブランチャードによって提唱されたリーダーシップ条件適応理論の1つです。SL理論では、部下の社員・メンバーの能力や習熟度に応じてアプローチを変えることで効果的なリーダーシップを発揮できると考えます。画一的な指導や管理よりも、状況に合わせてリーダーシップの型・役割を変えることで、個々の社員・メンバーの成長につなげようとすることが大きな特徴です。
SL理論では、以下のような4つフェーズの成熟度があると考えます。
【成熟度1】
-
- 新入社員や未経験者などが、何をしたら良いかわからず、状況を怖れている状態です。
【成熟度2】
-
- 社員・メンバーが、ある程度自身の意思で行動を起こせるようになってきた段階です。何をしたら良いかわからない状態ですが、学びの姿勢を持っている状態です。
【成熟度3】
-
- 社員・メンバーとして能力が向上しつつあり、上司・管理者・リーダーが必要最低限の指示を出すだけで業務を遂行できるようになっている段階です。ただし、指示がなく、1人で業務をこなすことには不安を抱いている状態でもあります。
【成熟度4】
- 社員・メンバーの能力が高い練度・習熟度に達し、専門家として責任を持って担当業務に向き合い、高い成果を出せるようになっている段階です。何をしたら良いか理解できており、積極的に業務を遂行できる状態です。
SL理論においては、大まかに上記のフェーズに分けて社員・メンバーの状態を考え、状況に応じてリーダーシップの型・役割を変えていきます。
リーダーシップは状況が規定している
リーダーシップは必ずしもリーダー自身の主体性によって発揮されるものではありません。PM理論やSL理論を参考にすると、社員・メンバーが置かれた状況によってリーダーシップのあり方が規定されます。
たとえばPM理論は、別名でパパママ理論とも呼ばれています。P機能は、具体的な指示や戦略を策定する「パパ」のような役割であり、M機能は、社員・メンバーのメンタルや関係性のケアを行う「ママ」のような役割です。優れたリーダーは、状況に応じてこの2つの機能を使い分け、パパとして社員・メンバーを鼓舞する厳しさと、ママとして包み込む優しさの両方を兼ね備える必要があります。
またSL理論では、社員・メンバーの成熟度を4つのフェーズに分け、それぞれの段階によって対応を変えるといった受け身の姿勢を重視しています。こちらも状況に応じて対応するリーダーシップの型です。
これらの理論からわかるように、リーダーシップは状況によって規定され、常に柔軟に変化させる必要があります。状況を正確に把握し、適切なリーダーシップのやり方を選択することで、個々の社員・メンバーの成長を促進し、企業・組織全体のパフォーマンス向上につなげることができます。
リーダーシップをとる人が常に同じという状況はありえない
従来、チーム・部署の管理職や責任者といった個人を対象に行われてきたリーダーシップ教育は、リーダーの立場の者がすべての裁量権を持ち、全責任を負うという考え方に基づいて行われていました。ただし、これは現実的には非常にリスキーな考え方でもあります。なぜなら業務に対する課題設定や、各社員・メンバーの成果に対する評価基準などをすべてリーダーが取り決めることになり、独断によるご都合主義の業務判断や、社員・メンバー、あるいは自身に対する恣意的で甘い評価が下される可能性が出てくるからです。
そこで近年注目されているのが、社員・メンバー全体にリーダーシップ教育を広げるという考え方です。これは、リーダーが一人ですべての責任を負うのではなく、社員・メンバーがリーダーシップを発揮し、それぞれの役割を果たすことで、企業・組織全体の活性化やイノベーションの促進、人材育成やリスクの分散などの効果を発揮するやり方です。
リーダーシップを発揮する者を状況に合わせて変化させ、その分野に知見のある社員・メンバーが指揮を取ったり、経験のある者が主導したりすることにより、保守化・硬直化することのない合理的で柔軟な組織・チーム運営を実現することができます。
リーダーを固定することは不可能である
現代のビジネスの現場では、1人のリーダーが独断でリーダーシップを取っている組織・集団よりも、各社員・メンバーが必要に応じてリーダーシップを発揮できる組織・集団の方が、より機能している場合が多くなっています。
構造としてリーダーは1人が担うものですが、状況に応じた適材適所のタイミングで社員・メンバーがリーダー役を引き受け、適宜必要なリーダーシップを発揮することも不可欠です。そのため、集団・組織内においては、社員・メンバーの誰もがリーダーシップを発揮できる関係性作りや、必要なコミュニケーションを促進することも重要だといえるでしょう。
また、リーダー以外のポジションの社員・メンバーがリーダーシップを発揮することは、リーダーが仕事をしていない状態だと思われがちですが、これはリーダーシップ論においては誤った認識です。集団・組織におけるリーダーシップとは、誰か1人に完全に委ねられるものではなく、集団のリーダーを中心に発揮しながらも、部下・メンバーなど従う立場の者も必要に応じて裁量権・責任を持ち、バランスを取ることが重要なのです。
リーダーを固定する組織構造
多くの企業において、企業・組織は階層構造を持ち、責任がある立場になるほど裁量権も大きくなると考えられてきました。また、従来の組織論では、一部の管理職・リーダーに責任感を持たせることで組織運営が円滑になり、経営上の成果の面でも良い影響があると考えられています。しかし、このようなリーダーを固定する組織は目的が手段になりがちで、管理職・リーダーなどの上に立つ者に責任さえ与えれば、組織運営がスムーズになるといった思い込みを生んでしまった側面もあります。
現代のビジネス現場は、複雑なルールや法規制、コンプライアンスなど、さまざまな縛りを受け、人材も多様化しています。高い専門性を持つ社員・メンバーや外国人社員が増え、企業・組織のマネジメントはますます複雑化しています。
このような状況下において、管理職・リーダー個人の問題解決能力に頼るリーダーシップは限界を迎えています。リーダーを固定する組織構造を脱し、社員・メンバー全員が状況に合わせてリーダーシップを発揮すると、より柔軟に働くことができる環境作りに効果的でしょう。
組織も固定できない
固定化から脱する必要があるのはリーダーだけではありません。変化のスピードが速く、未来予測が困難な現代のビジネス環境においては、従来のトップダウン型の構造の企業・組織自体も、固定化された経営スタイルから脱する必要があります。実際に多くの企業では、公式なコーポレート部門による経営サポートだけでなく、非公式な社内プロジェクトや、部門を越えた横断的なチーム作りなどが活発化している流れがあります。これらの取り組みは、企業・組織を柔軟化させ、変化に対応するための重要な役割を果たしています。
ビジネスにおいてリーダーシップが重要な理由
リーダーシップと一言で表しても、その意味や定義は多岐にわたります。MBAや経営学者ピーター・ドラッカーをはじめ、多くの有識者がリーダーシップについて論じていますが、共通しているのは、リーダーシップとは組織・集団の機能を高めながら束ね、目標・目的に向かって牽引する能力であるということです。
実際にリーダーシップを発揮している人物は、歴史上の偉人や経営者だけでなく、映画や漫画といったフィクションの世界にも数多く登場します。当然ですが、リーダー不在の組織・集団は構成員がバラバラに行動し、チーム力を発揮することができません。企業や組織は、個人では達成困難なミッションや目標・目的を、人同士の協働によって力を高め、達成するために存在します。しかし、せっかく人が集まっても、統率が取れていなければ、組織・集団としての十分なパフォーマンスを発揮できず、思ったような成果につなげることは難しいのが現実でしょう。
現代は、将来予測が困難な「VUCA」と呼ばれる時代です。VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった概念で、先行きが不透明で先々の予測が難しい状況を指します。テクノロジーの進歩によるビジネスモデルの多様化や、市場のグローバル化により、さまざまな情報・価値観が絡み合い、経営の舵取りはますます複雑化しています。このような時代においては、旧来のトップダウン式のリーダーシップでは、状況に応じた素早い意思決定を行うことが困難です。
リーダーシップをとる際に求められる能力
リーダーシップは、定義や重要な理由さえ知っていれば発揮できるわけではありません。現在の企業・組織で求められている要素を一旦抽象度を上げて把握し、具体的なアクションに落とし込む必要があります。ここでは、リーダーシップをとる際に求められる能力について見ていきましょう。
自己理解・他者理解
自己理解とは、自分自身の性格や考え方の癖・価値観・行動パターンなどを多角的かつ客観的に理解することです。リーダーシップにおいては、社員・メンバーへの指示やフィードバック、関係構築のためのコミュニケーションなど、さまざまな場面で自己理解が求められます。リーダーとして完璧な姿を目指すのではなく、自分の強みや弱みを理解することで自身の能力では対処困難な状況で他者の力を借りることができ、状況に応じて適切で効果的なリーダーシップを発揮することができます。
また他者理解とは、メンバーそれぞれの視点や意見、考え方を理解することです。簡単に言えば、相手の立場に立って物事を考える姿勢です。社員・メンバーの個性や能力、価値観を理解することで、それぞれの強みを活かしたチーム作りや、個々のニーズに合わせた指導が可能になります。こうした取り組みはメンバーのモチベーションを高め、組織全体のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。
自己理解と他者理解は、優れたリーダーシップを発揮する上で大切であるため、リーダーの役割を担うために身に着けておくべき重要な能力です。
目標設定能力
リーダーシップにおいて、明確な目標設定は不可欠です。リーダーは「いつまでに何を終わらせるのか・達成するのか」を明確にし、具体的な計画に落とし込んで他の社員・メンバーに提示する必要があります。
目標を明確にすることで、各社員・メンバーが何をどうすればいいか明確になり、業務の見通しをつけることができます。業務のゴールまでの導線がはっきりしていると、社員・メンバーの不安を軽減し、モチベーションを高める効果があります。
また、具体的な目標と計画があることで、リーダーは社員・メンバーへの指示も出しやすくなり、円滑に業務を遂行することができるといったメリットもあります。
ただし、目標設定があまりにも高かったり、各人の能力を過小評価したりするような目標設定は避けた方が無難です。高すぎる目標などは達成までの道のりがイメージしづらく社員・メンバーのモチベーションを下げてしまうため、集団・組織としてのパフォーマンス向上にもつながりません。適切ではない目標を設定すると、業務で成果が出なかったり、生産性の低い状態を生み出したりしてしまいます。

社内コミュニケーションの目標設定|KPI設計と成功事例で組織を変える【2025年最新版】
社内コミュニケーションの目標設定にお悩みですか?本記事では、大企業のDX・広報・人事担当者向けに、定量・定性デ…
コミュニケーション力
リーダーシップを発揮し、他の社員・メンバーを統率しながら目標達成を目指す場合、必ず他者とのコミュニケーションが発生します。使う言葉、コミュニケーション自体の頻度、どういった手段でコミュニケーションを取るかなど、意識すべき側面が複数存在することも押さえておく必要があるでしょう。
また、各個人の立場に立ち、その人の視点から現状について考え、その人に合わせたコミュニケーションを適宜取っていく柔軟な姿勢も求められます。リーダーシップにおけるコミュニケーションは、ただ仲良く話せば良いというわけではなく、社員・メンバー全員が協力し合って目標達成するという大前提に対し、状況を見極めた角度から行う必要があります。
巻き込み力
リーダーシップをとる際には、集団・組織全体を統率し、目標達成に向けて牽引する必要もあります。簡単に表すと「巻き込み力」です。巻き込み力を発揮するためには、社員・メンバーからの信頼を獲得することが大切で、信頼を得た上で業務・プロジェクトなどの仕事に巻き込んでいくことが求められます。
巻き込み力については、集団スポーツのキャプテンにたとえるとわかりやすいでしょう。キャプテンはチームメンバーが功績を上げればしっかりと評価し、ミスをすれば励まし、修正点を一緒になって考える組織全体を統率した思いやりのある力が必要です。
また集団スポーツにおいては、キャプテン自らが率先して行動を起こし、お手本となる姿を見せることでチームメンバーの信頼を獲得できる点も同じです。企業・組織のリーダーも、他の社員・メンバーに寄り添いながら、自ら率先して仕事にあたることで信頼を獲得し、業務・プロジェクトに周囲を巻き込んでいくことができるでしょう。
責任感
リーダーシップとは、その状況に責任を持ち、裁量権を持って周囲に指示を出したり、計画を立案したりすることです。つまり、他の社員・メンバーが不手際やミスをした際には、その責任はリーダーシップをとっている者がとる必要があります。
なお、リーダー自身が責任を取る姿勢を見せることで、他の社員・メンバーにも責任感を持ってもらい、業務・プロジェクトを自分ごと化してもらえることにもつながります。業務・プロジェクトに関わる全員が責任感を持つことで、仕事に対して一定の緊張感を持ち、高いパフォーマンスを発揮することができるでしょう。
判断力と決断力
リーダーシップでは、判断力と決断力も重要になります。リーダーの立場の者が迷っていると他の社員・メンバーは不安になり、あやふやな判断をされると不信感にもつながります。
もし、自分だけで対処できない問題、たとえば専門性が絡んでくる業務などでは、適切な能力を持つ部下にリーダーの権限委譲を行い、頼ることもリーダーシップでは重要な判断です。真のリーダーシップとは、立場・役職に固執して采配を行うのではなく、より大局的な視点を持って適材適所の人材を活かし、業務や課題に対処することも求められます。
目標達成において何が重要なのかを考え、思い込みやこだわりに捉われず、次のアクションを起こす判断力・決断力がリーダーシップには必要です。
業務遂行力=専門性
集団・組織におけるリーダーは、他の社員・メンバーのお手本になる業務遂行力=専門性も必要です。
業務遂行力を発揮するためには、まずリーダーができる業務は率先してやって見せ、可能な限り高い水準の成果を出すことが望ましいでしょう。仕事ができない上司よりもできる上司が信頼されるように、リーダーも仕事ができる方が他の社員・メンバーから信頼してもらえる可能性は高まります。
また、複数の業務で良い成果を出せる有能な人物だと認識してもらえれば、リーダーの立場にも説得力が生まれ、納得できる理由にもなります。社員・メンバーにつき従ってもらうには信頼を得ることが大切です。業務遂行力をアピールし、リーダーシップを存分に発揮できる環境作りをしましょう。
学習
学習能力についても、リーダーシップにおいて重要な要素に挙げられます。近年のビジネスは変化し続けており、新しい環境やテクノロジーなどに対応しなければなりません。そのような中でリーダーシップを発揮するには、変化する状況に順応できるよう新しい知識やスキルを学び続け、習得していかなければならないからです。
最新・最前線の情報をキャッチアップし、学習・習得できない場合、組織や企業において適切なリーダーシップを発揮することは難しいものです。リーダーシップにおいても、変化への対応は重要なキーワードになっていることを心得ておく必要があるでしょう。
リーダーがとるべき行動8選
リーダーが求められている要素を把握した上で、具体的にどのような行動を起こせば良いのでしょうか。ここでは、ビジネスの現場で優れたリーダーが起こす行動について確認しておきましょう。
➀率先してリーダーシップを発揮する
リーダーは自らが率先して良い例を示し、行動力を発揮しながらポジティブな姿勢を取ることで、他の社員・メンバーの信頼を得ることができます。自身が求める価値観を行動に落とし込みながら実践し、他の社員・メンバーに好影響を与えながら、チーム・組織全体を牽引していきます。
➁ディベートする
リーダーは1つの意見・情報に固執せず、他の社員・メンバーの多様な意見や新しい情報も受け入れ、テーマに必要な要素をすべて尊重しながら議論を行います。その際、ディベート的なやり取りも行い、批判や反対意見のポジションを取る人の存在も受け入れ、多様な視点から問題・課題を深く掘り下げていきます。
ただし、議論はあくまでもテーマに対して有益な結論を出すことが目的であり、議論の勝ち負けを競うわけではないと心得ておきましょう。そのため、他の社員・メンバーの気分を害したり、軋轢を生むような対立を起こしたりしないよう、十分な配慮を持ってディベートに臨みます。
③ディカッションする
リーダーが他の社員・メンバーと行うコミュニケーションとして、互いの考えやアイデアを共有するディスカッションがあります。定期的に開催することで、社員・メンバーについての理解を深めながら、業務上の問題・課題解決につなげ、意思決定に必要な合意形成なども図っていきます。
また、ディスカッションは社員・メンバー同士がお互いを理解し、関係性を深める場としても役立つため、集団・組織の運営の視点でも有用だといえるでしょう。
④合意形成する
リーダーは他の社員・メンバーと協力関係を作り、多様な意見・視点を考慮しながら全体を調整し、目標や問題・課題解決に向けて行動を起こすための合意形成を行います。合意形成は、組織やチーム全体の一体感を強め、同じ意識を共有することで、成果を生み出すための土台を作るステップです。
⑤相互フィードバックする
リーダーは社員・メンバー同士が意見を出し合い、お互いにフィードバックを行いながら共に成長していける環境を作ります。とくに、相互フィードバックは、社員・メンバーそれぞれの能力や思考力を高める効果があり、組織やチーム全体のパフォーマンス向上にもつながる重要な要素です。
⑥動機付け=相互フィードバックする
リーダーは、個々の社員・メンバーを励まし、モチベーションを高めてもらうために適宜フィードバックを行います。社員・メンバーが自己成長することで高いパフォーマンスを発揮できるようになり、結果として組織やチーム全体のパフォーマンスを向上させることができます。
前述したPM理論における、社員・メンバーのメンタルや関係性のケアを行うM機能(集団維持機能)に該当するアクションです。
⑦組織化する
リーダーは組織やチーム運用に必要なガイドラインを確立し、社員・メンバーそれぞれの役割や責任を明確にすることで、目標達成や課題・問題解決に向かう方向性を調整します。ガイドラインを作り込んだ組織やチームは統率が取れ、さらに状況に応じて変化できる柔軟性も有しているため、質の良い成果を生み出すことができます。
⑧模範となる
リーダーは自身が求めている行動を実践に移し、社員・メンバー全員がリーダーシップを発揮できるよう自らがお手本になることで、組織やチーム全体にポジティブな影響を与えます。言葉よりも実践、行動する姿を見せることが大切であり、誰よりもリーダーが動く姿勢を見せることでリーダーシップに説得力が伴い、社員・メンバーがその影響を受け行動を起こすようになります。
まとめ
現代の企業・組織では、複雑化したビジネス環境に合わせられる柔軟性と、社員・メンバーを巻き込んで業務にあたれる信頼されるリーダーが求められています。これまでは社内規範・業界の常識といった固定化された基準でテンプレート的な采配・指示・管理を行うリーダーが多く存在しました。
変化が激しく、企業や組織で働く社員・メンバーの価値観や働き方が多様化している現代では、旧来型のリーダーシップでは通用しません。リーダーはより細かく、社員・メンバーごとに個別最適化したリーダーシップをとりつつ、全体を統率しながら牽引する力が必要です。
またリーダー職はビジネスパーソンとして大きく成長できるチャンスでもあります。複雑なビジネス環境に対応するため、個々の社員・メンバーがリーダーシップを発揮し、協働する環境を作ることも、現代の企業・組織には必要になっています。ビジネスの荒波に負けず、自社を成長させるためにも、新時代のリーダーの取り組み・育成を実施してみましょう。