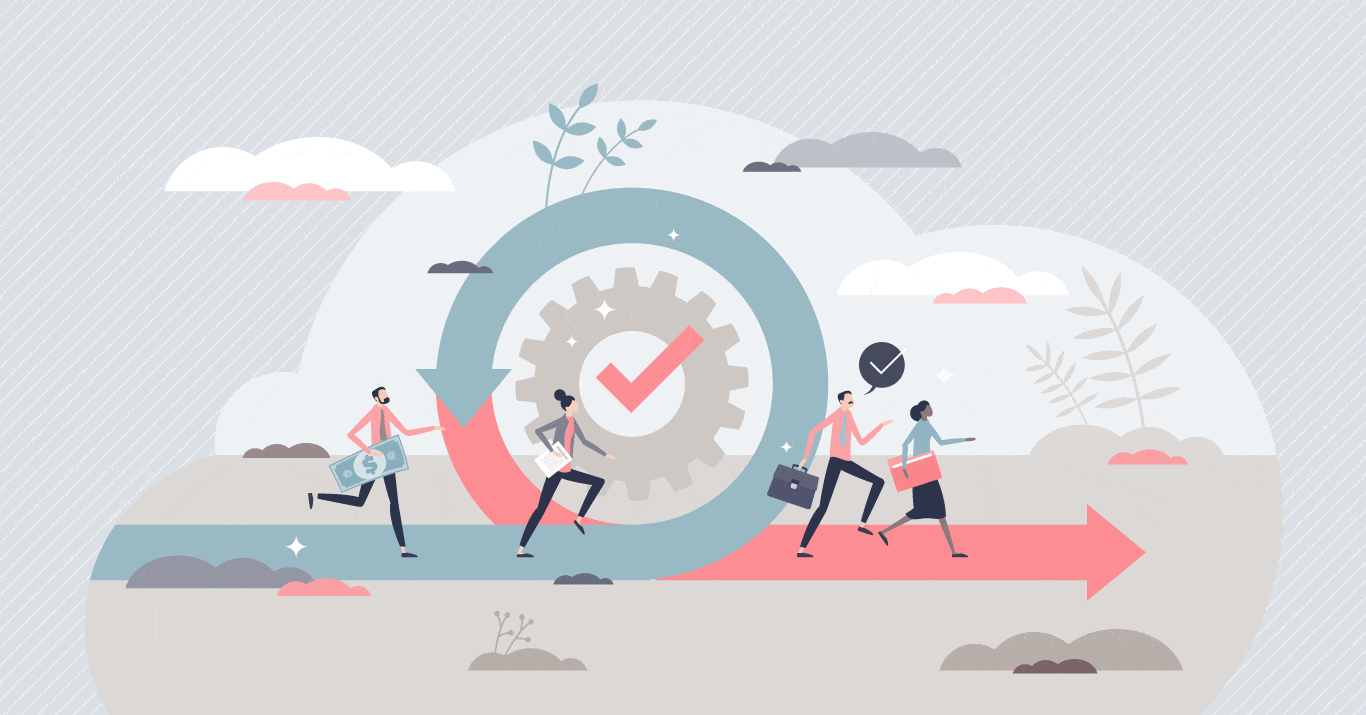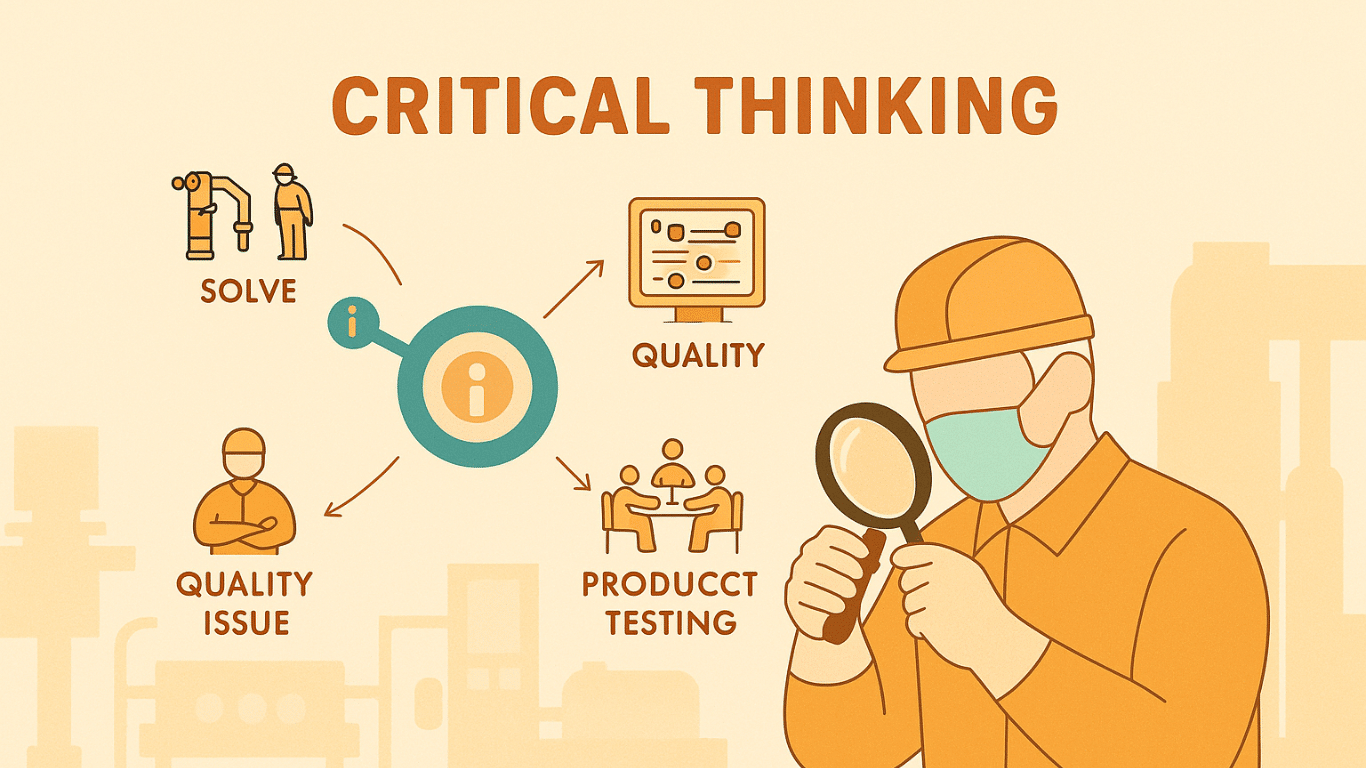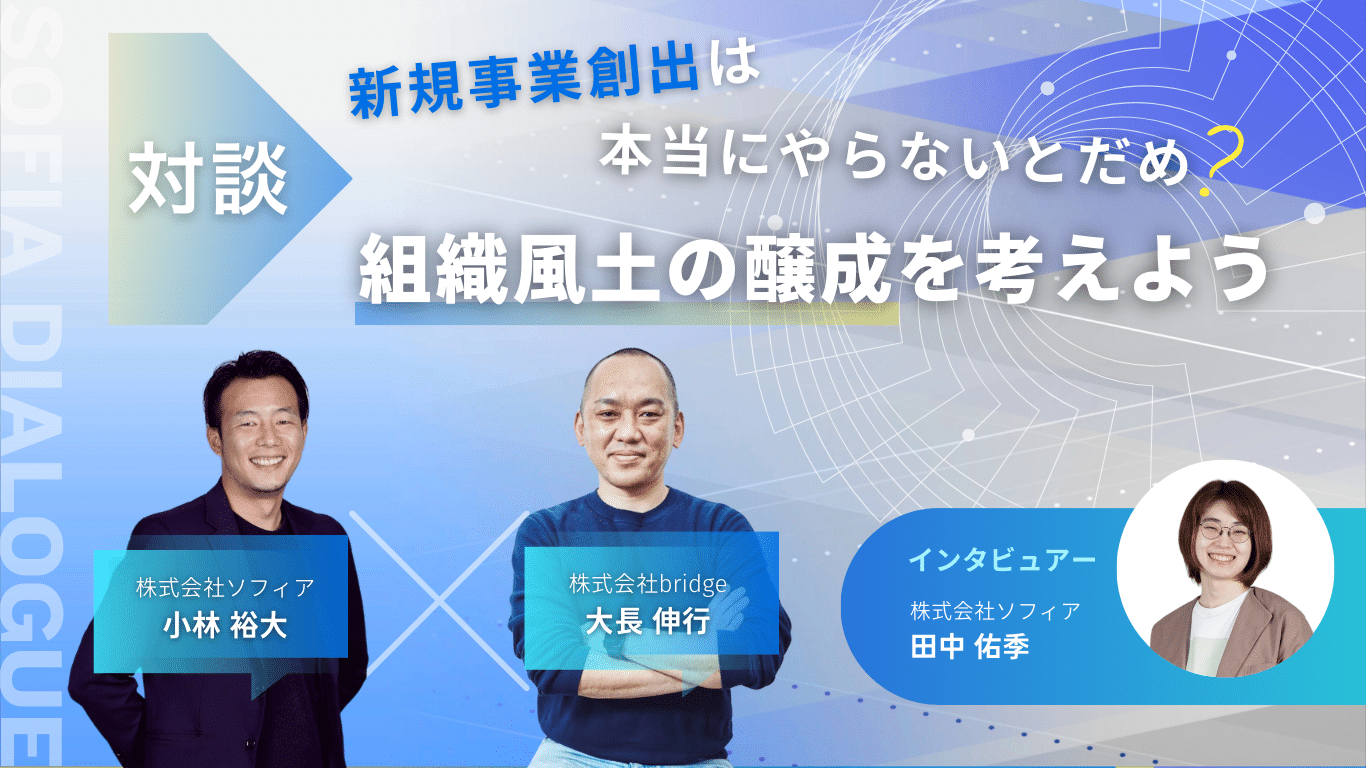言語化とは何か?重要性とビジネスへの応用、鍛える方法まで徹底解説
最終更新日:2025.07.15
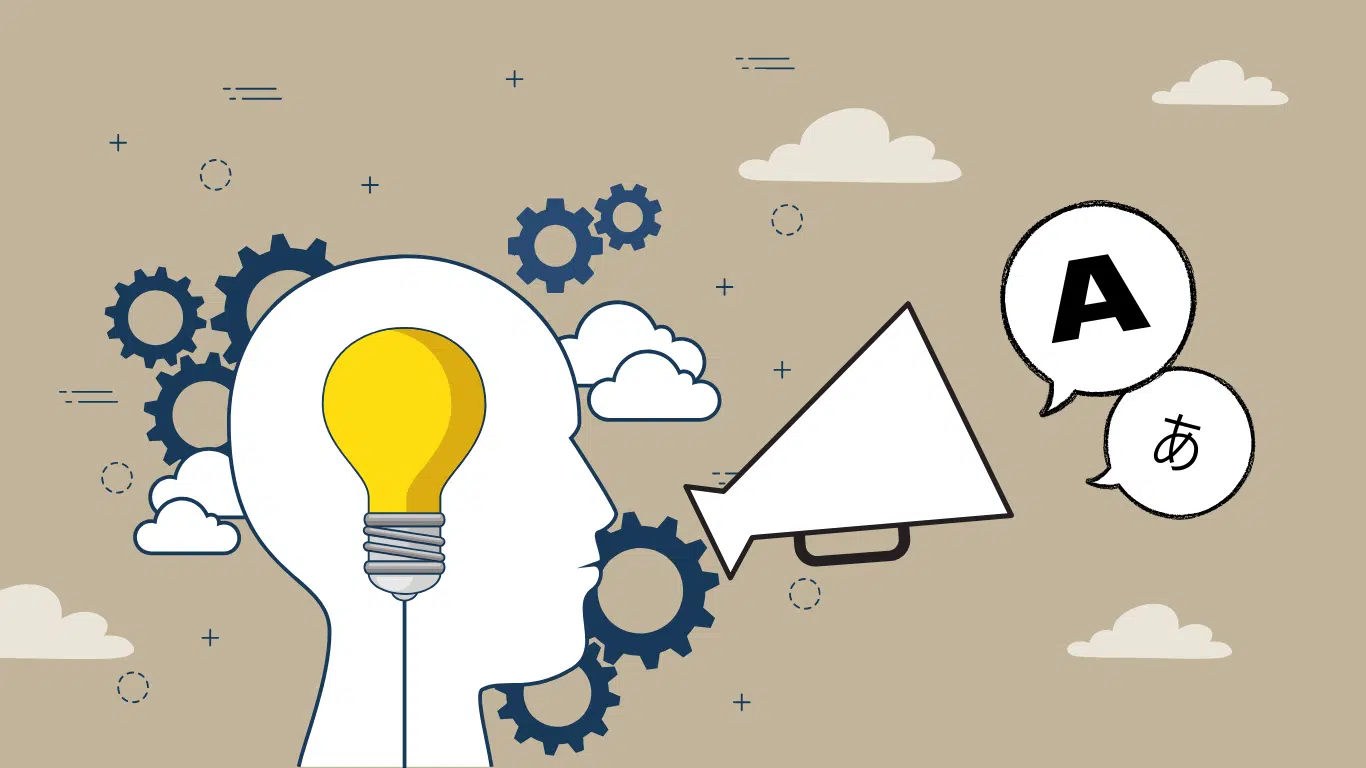
目次
「頭の中では色々考えているのに、いざ説明しようとすると上手く言葉にできない」──そんな経験はありませんか?近年、このような 「言語化」 の重要性が改めて注目されています。ビジネス書や研修でも「言語化力を鍛える」といったテーマがブームになっており、企業研修担当者の間でもホットな話題です。本記事では、言語化ブームの背景にある社会的要因から、ビジネス現場での活用方法、さらに言語化能力を鍛える具体的な方法までを解説します。
まず言語化とは何か? 定義を明確にし、なぜ今これほど言語化が重要視されるのか、現代の企業環境やコミュニケーション事情をもとに紐解きます。そのうえで、言語化がもたらす効果(情報共有、思考整理、感情コントロール、行動変容など)を体系的に整理し、言語の構造や人間への影響に関する理論(ヤコブソンや井筒俊彦の言語学など)にも触れ、理解を深めます。
さらに、ビジネス現場における言語化の重要性と具体的な実践についても紹介します。個人の「言語化する力」だけでなく、部下と上司の率直な対話が生まれる「言語化される環境」の重要性についても述べ、心理的安全性や対話の文化醸成などといった組織的な仕組みにも踏み込みます。
単なる知識の紹介にとどまらず、会議や1on1、自社研修設計や人材育成で活かせる考え方として、表層的な理解から理論的な土台まで探っていきます。言語化の基本とその効用がクリアになり、組織への適用アイデアも得られるでしょう。
言語化とは何か?定義と基本概念
まずは「言語化」とは何かを明確に定義します。広辞苑では、言語化の意味を「言葉で表現すること。とくに、思考や知識などを他者に説明したり共有したりするために、言葉を用いて説明すること」としています。平たく言えば、頭の中にある曖昧な思考や感覚を、他人に伝わる形で明確な言葉に置き換えることが「言語化」です。
つまりは、頭の中にある考え・気持ち・アイデアなどを適切な言葉に変換し、表現・伝達することです。
この定義から分かるように、言語化は単に「頭に浮かんだことを喋る」ことではありません。ポイントは「適切な言葉に置き換える」という部分です。頭の中のモヤモヤをそのまま垂れ流すのではなく、相手に伝わる形へと 翻訳するプロセスとも言えるでしょう。
もちろん、頭に浮かんだことを喋り、この言葉の適切性をいちいち確認している人は少ないかもしれません。しかし、適切な言語化のためには、それぞれの言葉をできるだけ正確に、共通の言葉で伝える力がどうしても必要です。
現代になって「言語化」という言葉がこれほど注目される背景には、実は社会構造の変化があります。ただ自分の考えを言葉にすれば良い時代から、なぜ今、言語化力が叫ばれるのかを考えてみましょう。
言語化ブームの背景:多様性と専門化が生み出すギャップ
かつて日本企業では年功序列・終身雇用のもと社員の価値観が比較的同質でした。しかし現在、事業のグローバル化や働き方の変化によって 組織内外の多様性が飛躍的に高まっています。年代・国籍・専門分野が異なる人々が協働する場面が増えた結果、それぞれの前提知識や専門用語が噛み合わず意思疎通が難しくなるケースが多発しているのです。
たとえば、現在の大企業は仕事が細分化・専門化されています。したがって、各部署内では通じる業界用語や略語が増えます。必然的に他部署とは話が通じにくくなります。いわゆる「サイロ化」と呼ばれる現象です。
DX推進部門が、現場の業務や細分化された業務をデジタル化する場合、サイロ化された現場業務の言語とDXのデジタル言語が、飛び交いまったく嚙み合わないという落語のような会議風景が出現するわけです。
サイロ間で共通の言葉(共通言語)が不足し、情報共有に障壁が生まれます。実際、「サイロ化が進むにつれ内部での専門用語が増え、サイロ間の共通言語を必要とする」と指摘されています。多様な専門性・価値観を持つ人材が共存する現代の職場では、互いの知識ギャップを埋める翻訳者としての言語化が不可欠なのです。
さらにコミュニケーションの困難さは社内に留まりません。取引先やグローバルな相手とのやり取りでも、文化やバックグラウンドの違いから 文脈を共有するのが難しい状況が増えています。お互いの「当たり前」が通じないため、ほんの一言のニュアンス違いが大きな誤解を生んでしまうこともあります。こうした背景事情から、「ちゃんと相手に伝わる言葉選びをする力」、すなわち言語化力が今まで以上に求められているのです。
現在における多様化・専門化によって共通言語が失われがちな職場では、適切に噛み砕いて説明する言語化能力がコミュニケーションの要となっています。一言で言えば、「人に分かるように語れること」が組織パフォーマンスを左右する時代になったと言えるでしょう。
コミュニケーション技術による簡便化が生みだす弊害
もう一つ、言語化ブームの背景にあるのが技術革新によるコミュニケーション手段の変化です。メールやチャット、SNSの普及によって、私たちはいつでも手軽にメッセージを送り合えるようになりました。スタンプ一つで「了解」「いいね」が伝えられる便利な時代です。しかし、この簡便さが裏目に出る側面もあります。
手軽なコミュニケーションは効率的な反面、文字情報だけでは感情や真意が伝わりにくいという欠点があります。対面なら表情や声のトーンから汲み取れるニュアンスも、テキストメッセージでは伝わりません。その結果、たとえば短い返信や既読スルーといった行為が、受け手には「怒っているのでは?」「自分が軽んじられた?」といった不安を招きがちです。実際、若い世代にとって未読無視・既読スルーは「自分への否定的サイン」に映り、大きな心理的ストレスになりうると指摘されています。
また、簡単な「いいね」ボタンで済ませるコミュニケーションに慣れすぎると、自分の気持ちや考えを深く言葉で説明する機会が減るという弊害もあります。「言葉にしなくても何となく伝わるでしょ?」という空気があると、あえて言語化する重要性に気づきにくくなります。しかし実はその「何となくの共有」が思わぬ誤解を生んでいることに、多くの人が気づき始めています。
「既読」という機能が、発信側は受信側が「承認」したと誤認識するケースや、すぐにコメントの返信がない事による発信者の受信に対する不信増大は、本末転倒であることを物語っています。
海外研究論文では、ビジネスにおいて長文によるテキストコミュニケーションと短文のチャットのやり取りでは、職場の生産性が長文でのコミュニケーションが優位になっているという結果もあります。だからと言って、チャットはやめた方が良いという単純な話ではありません
とくにビジネスでは、行間の読み違いが致命的なミスにつながります。メールやチャットで情報伝達が完結する現代だからこそ、「本当の意図まできちんと伝わっているか?」を確認し、補足説明や対話で言葉を補うことが重要になっているのです。コミュニケーションが便利になる一方で人間的な深い対話が減っている今、敢えて丁寧に言葉で伝える意識、すなわち言語化する姿勢が改めて見直されています。長いテキストは、時代遅れなようでいて決してそうではありません。専門化した世界だからこそ、くどいほどの確認が必要です。
現在会社の意思決定に関わっているほとんど幹部社員にとって、コミュニケーションの正確さは、死活問題です。彼らは若い世代とのギャップに悩み何とか克服したいと考えています。そんなとき時代遅れなように見える長い長文のテキストが、誤解や軋轢を避ける有効なツールになることを実は知っています。そうです。長いメールやテキストは、今でも十分に有効であり、とくにビジネスの重要な意思決定の場面では、チャットでのやり取りではなく、長文による解像度の高いやり取りすべきです。高齢者が若者の真似をして、絵文字入りのチャットを苦労して作り上げても、違和感があるだけ若者を笑われると肝に銘じましょう。
会議を始める際に、言葉や前提の定義を整理することに時間が掛かってしまって本題を話す時間がないという会社が非常に増えています。会議の前にできるだけ定義や前提については、正確に詰めておく必要はあります。解像度の高い長文のテキストが必要です。
“言葉にしたい”人間の根源的欲求
そもそも人はなぜ言語化にしたがるのでしょうか?実はその根底には人間の本質的な欲求があります。それは「他者とつながりたい」「自分の想いを理解してほしい」という社会的欲求です。
社会心理学者エーリッヒ・フロムは、人間は根源的に孤独を恐れる社会的動物であり、周囲とのつながりなしには生きられないと述べました。自由に個人として生きることを獲得した現代人ですが、同時に孤独感に耐えられず誰かに自分を分かってほしいと願う傾向があります。言語化はまさにその願いを叶える手段です。自分の内にある思いを言語化し、外の世界に送り出すことで、他者との共感や理解が生まれます。
たとえば、悩みを打ち明けて「わかるよ」と言ってもらえたとき、人は孤独から解放され安心感を得ます。また、成功体験やビジョンを語って仲間が「それは素晴らしい」と共感してくれれば、大きな充実感や連帯感が得られます。つまり、言語化にして伝えること自体が人と人との絆を作る行為なのです。逆に言語化しなければ、その絆は生まれません。心の中にどんなに熱い思いがあっても、他者には共有されず、共感も得られないのです。
心理学的にも、自分の感情を言葉に表すこと(感情のラベリング)は不安やストレスを軽減する効果があるとされています。これは、自分の中のモヤモヤを誰かに伝えることで「分かち合えた」と感じ、孤独感が和らぐためです。言語化には人の孤独をやわらげる癒しの力があるのです。
便利なデジタル技術により、私たちはいつでも、どこでも、効率よくやりとりできるようになりました。しかし、この現代でも人が心から求めるのは「自分を理解してくれる誰か」「本音で語り合える場」なのです。言語化とは、こうした深い思いを形にする手段です。 だからこそ現代において改めて重要視されていると言えるでしょう。
言語化するのはなぜか?――言語化の持つ効用
言語化が求められる背景を理解したところで、次に「人はなぜ言語化するのか」という問いに答えていきます。言語化には大きく分けて次のような目的・効用があります。
- 情報伝達・知識共有のため – 専門的な内容や頭の中のイメージを他者に正確に伝える。
- 思考整理・自己理解・感情コントロールのため – モヤモヤした考えや感情を言葉にすることで頭の中を整理し、理解を深める。言葉にして吐き出すことで不安や怒りを和らげたり、気持ちを整理したりする。
- 行動変容・モチベーション喚起のため – 言葉の力で自分や他者の行動を促したり、心を動かしたりする。
これらを順に見ていきましょう。
1. 情報伝達としての言語化 – 「知っていること」を他者に伝える
第一の目的は、情報伝達・知識共有です。自分が持っている知識や考えを他の人に理解してもらうためには、適切な言葉による説明が欠かせません。専門家が専門外の人に話す場合などの言語化はまさに「翻訳作業」です。難しい専門用語や暗黙知を、相手にも分かる共通の言葉に置き換える必要があります。
たとえば社内で新しいプロジェクトを立ち上げる際、エンジニアは技術的アイデアを営業チームにも理解できるよう噛み砕いて説明しなければなりません。このとき、エンジニアの頭の中にある専門知識を言語化して共有することで、初めて全員が共通認識を持てます。逆に言語化が不十分だと、「言っている意味が分からない」という状態になり、プロジェクトはスムーズに進みません。
言語学者ロマン・ヤコブソンは、言語の基本的機能の一つに 「指示的機能(referential function)」 を挙げています。これは「言葉を使って内外の世界を記述し、情報を伝達・記録する機能」のことです。まさに情報伝達における言語化の役割を表しています。私たちは言葉を使って世界を解釈し、それを他者と共有しています。言語化することによって、初めて知識は共有財産となるのです。
現代のビジネスでは「属人化した知識をチームで共有する」ことが非常に重要視されます。属人化を防ぐためのナレッジ共有には、ドキュメント作成やミーティングでの説明など、いずれも暗黙知を言語化するプロセスが必要です。
品質管理の現場では、ベテランの職人の「勘どころ(感覚的なコツ)」を文章やマニュアルに起こして共有する取り組みが行われています。それも立派な言語化活動です。職人技の秘訣を言語化して可視化することで、はじめて新人にもノウハウが伝承できるのです。
要するに、言語化とは自身の知識や考えを他者と共有するための手段です。 それによって、相手の理解が深まり、組織としての学びや協働が成り立つのです。 「わかりやすい説明ができる人」はビジネスでも信頼されますが、その土台にはこの情報伝達力としての言語化スキルがあります。
情報や知識の言語化によって、個人が持っている情報や知識が、チーム全体に共有されます。 私たちは言葉を使って世界を理解し、伝えることで、知識を広げていきます。 ビジネスにおいても、専門知や経験則を言語化できなければ、ノウハウの伝達や組織的な問題解決も難しくなります。
2. 思考や感情の整理 – 「モヤモヤ」を言葉にして可視化する
第二の目的は、自分自身の思考や感情を整理するための言語化です。頭の中だけで考えていると混乱してしまうようなことも、紙に書き出したり人に話したりすると整理できた経験はないでしょうか?まさに言語化には、自分の考えを客観視し、構造化する効果があります。
自分の感情を言語化すること(感情ラベリング)の効用が示されています。怒りなど強い感情について言葉にして表現させたところ、不安やストレスの軽減につながった経験をしている人は多いと思います。
つまり、怒りや悲しみを悶悶と頭の中にため込まず、日記などに書き出して言語化すれば、整理されるのです。
言葉にすることで漠然とした不安が正体を現し、人は対処しやすくなります。いわば、言語化は頭の中のカオスにラベルを貼り、整理整頓するような作用を持っているのです。
これはビジネスシーンでも同様です。会議でいきなり議論を始める前に、参加者がそれぞれ10分ほど使って、自分の意見を整理する時間を取るだけで、発言の質や量が大きく変わります。 頭の中で考えているだけでは参加者各自で論点の捉え方にずれが生じますが、言語化してから共有することで認識のずれが減り、建設的な議論がしやすくなるのです。
個人レベルでも、日記を書く習慣や定期的な振り返り(リフレクション)をすることは、自分の考えを客観視し、自己洞察を深める効果があります。頭の中でモヤモヤしていたことも、文章にして眺めると「自分はこんなことで悩んでいたのか」「本当は〇〇が不安だったんだな」と気づけるものです。言語化という行為は自分自身に対して鏡を見せるようなものと言えるでしょう。
脳科学的にも、言語化は思考を司る前頭葉の働きと深く関わります。何か漠然とした情緒(感情)が起こった際、それを「これはこういうものだ」と言語でラベリングする過程自体が前頭前野を活性化させ、感情に飲み込まれずに済む助けになるとも言われます。つまり言葉で書き出す・話すことで、感情や考えを脳内で整理整頓し、落ち着いて対処できるようになるのです。
ビジネスパーソンに求められるロジカルシンキング(論理的思考)やクリティカルシンキング(批判的思考)も、基本は言語化して考えを整理・可視化するプロセスです。
言語化する事で、感情と事実、主観と客観を区別しながら情報を筋道立てて並べられるようになります。とくに重要なのは感情です。日記や個人作業であれば、自身の感情を表に出すことは、恥ずかしい部分もありますし、共有する場所や対象によって、自身を危険にさらす恐れがあります。しかし、自身で行う言語化が本音でなければ整理する意味がありません。
言語化は思考・感情を「見える化」し、自分自身を客観視できる状態にします。悩みやアイデアを書き出すだけでも脳内の整理が進み、不安軽減や洞察深化につながることが研究でも示されています。頭の中を整理したければ、まず言葉にしてみることが有効なのです。
3. 行動変容と感情への影響 – 言葉が人を動かすメカニズム
言語化の第三の効用は、行動や感情に変化をもたらすことです。言葉には人の心を揺さぶり、行動を促す力があるというと少し大袈裟に聞こえるかもしれません。しかし歴史を見ても、偉大なリーダーたちは卓越した言語化力(スピーチや文章)で人々を動かしてきました。ビジネスにおいても、ミッションやビジョンを力強く言語化して示すことで社員の心が一つになり、行動が変わるというのはよくある話です。
哲学者・言語学者の井筒俊彦は「言語は論理であるとともに呪術である」と述べています。つまり、言語には世界を秩序立てるロジック(論理)の力と、世界を覆すほどの呪術の力があるということです。これは言葉が単なる情報伝達の道具を超え、時に人の深層心理に働きかけて感情や行動を変容させることを示唆しています。誰しも日常で心に刺さる言葉に出会って「ハッと目が覚めた」「勇気が出た」と感じたり、反対に傷つく言葉で落ち込んだりする経験があるでしょう。言語化されたメッセージは、人を泣かせたり笑わせたり奮い立たせたりする力を秘めているのです。
ビジネスの場面でも、言葉の使い方次第で相手の受け取り方や行動が変わることは日常茶飯事です。大企業向けの大型商材の法人営業のハイパフォーマーは、新規顧客の最初プレゼンで、その会社や業界の言説や用語を200語以上勉強して商談に臨むそうです。さらに、その言葉に、自社なり解釈を加えレトリックを作り出します。そして相手の状況をつぶさに調査し、相手に刺さる言葉を選び取り、自社の商材をあたかも購入するのが必然的であると伝えるのです。これは言語表現が相手の感情・行動に直接影響することの証です。
また、自分自身に対しても言葉は強力です。自己啓発の領域では「アファメーション(肯定的自己宣言)」という手法があります。毎朝「私は有能だ。今日はきっとうまくいく」と声に出すことで本当に行動が積極的になる、といった話を聞いたことがあるでしょうか。半信半疑に思う人もいるでしょうが、心理学的には言語化によるセルフトークが自己効力感に影響を与えることが知られています。前向きな言葉を繰り返し自分に言い聞かせると、不思議と気持ちが前向きになり行動も積極的になるという現象です。
他にも、何か目標を口に出して宣言すると実現率が上がるとも言われます。これは言語化することで曖昧な目標が具体化し、現実感を伴って自分にコミットメント(約束)する効果があるためです。「今年中に〇〇の資格を取ります!」と人前で言語化すると、不思議と勉強に身が入る…というのも多くの方が経験的に感じているのではないでしょうか。
以上のように、言語化には人の心と行動に働きかける呪術のような面があります。論理的な説得のみならず、情熱的なスピーチや魂のこもった一言が、人を動かすことがあるのです。組織の変革でも、トップが強いメッセージを発して社員の意識・行動を変えるケースがあります。たとえば経営理念をシンプルで力強い言葉に落とし込み浸透させると、社員の日々の判断や行動がそれに沿って変わっていくことがあります。言葉が行動を形作る好例と言えるでしょう。
言語化したメッセージは、人の感情や行動に影響を及ぼす力を持ちます。適切な言葉で鼓舞すれば組織を動かす原動力にもなりえます。井筒俊彦が言うように、言葉には「呪術的」な側面があり、人を変える可能性があるのです。
以上、言語化の主な効用を「情報共有」「思考整理・感情コントロール」「行動変容」の観点から見てきました。このように言語化は単なるコミュニケーション技術ではなく、個人と組織の知と行動を人と組織の知と行動を支える 根幹スキル だと分かります。
一定のトレーニングと実践における振り返りをすれば、再現性をもって育てることができます。
次は、少し視点を変えて深いレベルでの「言語そのもの」に注目してみましょう。言語化を語る上で役立つ言語学や社会学から言語の深層部分に迫っていくことで、単純な技術やスキルだけでは困難な言語化の背景にある深層部分に迫っていきます。
言語化を理論的に捉える – 言語の構造と人間への影響
ここでは、言語そのものの構造や働きについての理論をいくつか紹介し、言語化の背景にあるメカニズムを理解します。以下は古典的な理論ですが、現代にも十分通用する枠組みです。
ヤコブソンの「選択と結合」理論
ロマン・ヤコブソンという言語学者は、言語には「選択」と「結合」という二つの基本的側面があると指摘しました。話し手は発話の際、語彙から適切な言葉を選び取り、それらを文法に沿って繋ぎ合わせて文を作ります。
ヤコブソンは失語症(言語機能の障害)の研究から、これら二つの側面が独立して損なわれうることも示しています。一つのタイプの失語症では意味の似た語の中から適切な語を選ぶことが難しくなり(選択の障害)、別のタイプでは語と語を文脈に沿って繋げることが困難になります(結合の障害)。
言い換えれば、何かを言語化するという行為は、適切な表現を選択し、それらを論理的に結合していくプロセスといえるでしょう。
言語の6つの基本機能 – ヤコブソンのモデル
ヤコブソンはまた、コミュニケーションにおける言語の機能を6つに分類するモデルも提唱しました。言語化の目的を考える上で示唆に富む理論であり、現代でも十分に通用します。
感情的機能(エモーティブ)
話し手の感情や身体状態を表出する働きです。 例:「あー疲れた」「やったー!」
働きかけ機能(コナティブ)
相手に訴えかけ行動を促す働きです。 例:「手伝ってください」「締切までに提出せよ」
指示的機能(リファレンシャル)
物事や状況を記述し、情報を伝える働きです。 例:「今日は気温20℃です」「会議は3時からです」
詩的機能
メッセージそのもの(音の響きやリズム、言葉の選び方)に着目した働きです。 例: キャッチコピーや俳句のような表現美、「バザールでござーる」、「あめゆじゅとてちてけんじゃ」
交話的機能(ファティック)
言葉のやりとり自体で関係性を築く働きです。 例:「こんにちは」「最近どう?」といった挨拶や雑談
メタ言語的機能(メタリンガル)
言語そのものについて説明する働きです。 例:「『孫悟空』とは中国の物語に出てくる猿のことです」のような定義
言語化の多面的な機能
これまで述べてきたように、言語化にはさまざまな側面があります。情報伝達だけでなく、感情表現や説得、雑談による親睦など、用途に応じて言葉は多機能に働きます。
実際のコミュニケーションでは、これら複数の機能が同時に作用していることも珍しくありません。たとえば上司が部下に「最近調子はどう?」と声をかけるのは一見ただの雑談ですが、部下の感情を引き出して安心させる(感情的機能+交話的機能)狙いもあります。
言語化とは、「状況に応じて、考えや感情を適切な言葉に置き換えること」と一般に定義されます。 その「適切さ」は、 上述の6機能や言語化するための選択と結合で成り立っているわけです。
そして、こうした言語化の構造的プロセスは、すでに 現在の言語生成AIも獲得しています。
交話的機能の重要性
ヤコブソンのモデルでとくに注目したいのは交話的機能(ファティック)です。これは「とりとめのない会話でも、言葉を交わすこと自体に意味がある」というものです。極端な例ではSNSの「いいね」ボタン程度のやりとりでもつながりを感じられるのは、交話的機能の延長と言っても良いでしょう。
言語化には内容の伝達以上に、対話によって一体感を生み出す役割があることを示しています。この観点はビジネスでも重要で、雑談や何気ない対話が職場の心理的安全性やチームワークに寄与することが分かっています。単に有益な情報だけ話せばよいというものではなく、言葉を交わす行為そのものが組織にプラスになるのです。
以上のように言語化とは非常に多面的な行為であり、状況に応じて言葉の機能を使い分ける必要があります。
たとえば、自社の理念を浸透させたいなら詩的機能を駆使してキャッチーなスローガンに言語化するとよいでしょう。一方で部下のモチベーションを高めたいなら感情的機能と行動を促す働きかけ機能を織り交ぜて熱意あるメッセージを届けることも効果的です。
このように、言葉の持つ様々な力を理解し、目的に応じた言語化を行うことがよりよいコミュニケーションや組織づくりにつながります。
さらに一歩踏み込んで考えると、私たち人間の認知や社会そのものがどの程度言語によって規定されているのか、という問いも浮かび上がります。次のセクションでは、言語そのものが人間に与える影響について見ていきましょう。
「言語に支配されている」という視点
言語化の理論的背景としてもう一つ知っておきたいのが、人間の認識と行動は言語に規定されているという考え方です。クロード・レヴィ=ストロースは国や民族、各社会で人々が無意識に従っている隠れたルールを解明しようとした学者です。そして言語学者であるヤコブソンの言語学と出会い、協業したことによって、世界で初めて、人類や民族の深層に構造化されたものが存在するという事を発見し、構造主義を確立しました。これは私たち人類の文化や思考の根底に「言語構造」があるという発見です。つまり私たちは知らず知らずのうちに、自分が使う言語の枠組みに沿って物事を理解し、考えているということです。
構造主義は言語学のみならず哲学・文学理論にも波及し、記号論的な分析が様々な領域で試みられました。ヤコブソンの構造分析の手法は、まさに戦後欧米で一大知的ムーブメントとなった構造主義の核となり、言語学は社会科学・人文科学の分析の道具立てを提供したのです。
スイスの言語学者のフェルディナン・ド・ソシュールは言語の記号として機能(シニフィアン)と言語によって指示されるもの(シニフィエ)の間には、必然的には関連がないと論じました。必然性がない以上、「シニフィアン」と「シニフィエ」には、無限に解釈が生成されるという事です。
私たちの言語化の活動の深層には、言語という構造があり、普段気づかないうちに、複雑な仕組みの中で言葉を選び、意味を作り出しているのです。
どのような言葉が社内でよく使われているかによって、その会社の「文化」や「考え方のクセ」ができあがります。
そして、こうした言葉や文化は、ずっと同じままではなく、時代や人のやりとりによって少しずつ変わっていきます。 言葉の使い方を意識して工夫すれば、 関係性や風土、慣習に至るまで、変化を及ぼすことは可能であると言えます。
皆さんも職場の上司やリーダーが変わると職場や組織が変わるという経験があると思います。これは環境や物事は変わっていなくとも新しいリーダーや上司の解釈や価値観で、その環境や物事に新しい意味や価値を言語化して与えることで、職場や組織が変化するという事です。
したがって、私たちは言語化を考えるとき「どの言葉を使うか」に敏感になる必要があります。自分や組織が上記の深層にあるどのレベルの言葉を使うかによって、思考も行動もある程度方向づけられてしまうからです。裏を返せば、望ましい文化や行動を引き出したければ、その基盤となる言葉のデザインが重要だと言っても言い過ぎではありません。たとえば経営陣が組織文化を変えたいなら、新たなキーワードやスローガンを定めて繰り返し発信することで社員の認識を変えていく戦略が考えられます。
人間の思考は言語に完全に規定されていて言語が思考や認知に影響を与え我々の行動を規定しています。
言語と認識は相互作用しているので、「言葉遣いを変えると物の見方が変わる」、「考えを変えたければまず言葉を変えるべき」という示唆を与えています。
まさしく、言語は呪術であり世界を変える力を持つものです。であるにも関わらず、日本の企業でかくも軽んじられている理由はなぜでしょうか?
その理由の一つは、日本人が伝統的に、言語に重要性を見出さず、言語以外の雰囲気や空気といったようなものを重視してきたからだと考えられます。ところが、雰囲気や空気を通してコミュニケーションする時代は既に終わりました。
言語化の重要性が叫ばれている現在において、未だ「空気」でコミュニケーションすることが通用するという幻想は、捨て去るべきでしょう。
言語化したコミュニケーションが一定レベルで相手に刺さるには、協同的な体験が必要です。この共同的な体験が新しい言語に意味を付け加えて物事が変化していくのです。
重要なのはレトリックとしての言語化を新しく創り出すためには、構造を知ることです。つまり、この支配された言語の深層を知ることで言語化を深いものにすることが可能になります。
「言葉の論理」と「言葉の呪術」
言語の持つ論理的側面と呪術的側面についてもう少し掘り下げます。井筒俊彦の「言語は論理であり呪術である」という言葉を紹介しましたが、この背景には様々な思想があります。
井筒俊彦は著書『言語と呪術』の中で、古今東西の言語に関する知見をもとに言葉の二面性を論じました。論理としての言葉とは、先に述べた情報伝達や論理思考の道具としての面です。一方、呪術としての言葉とは、言霊(ことだま)の信仰に見られるような、言葉に内在する不思議な力の面です。日本でも「言葉には魂が宿る」といった考えがありますが、井筒は世界各地の言語文化を引き合いに出し、言葉は人間の深層心理や集団の無意識に働きかける力を持つと論じました。
また、小林秀雄の「直観を磨くもの」の中で、理屈や知識ではなく、「直観」こそが真理への手がかりであると言っています。たとえば、天才や芸術家は、知識でなく直観によって創造に到達すると述べ、ゴッホやモーツァルト、芭蕉などの芸術家を例に挙げています。この中で小林秀雄は「直観は育てることができる」と断言しています。読書や芸術鑑賞、日常の物事への深い観察などを通じて、直観の感度は高められるというのです。
直観を育てる鍵としては、「伝統」や「古典」の重要性を挙げています。古典には時代を超えて響く人間の本質が宿っており、それに触れることで現代に生きる私たちも、自らの直観を照らし出すことができるとしています。
井筒のいう「言葉は人間の深層心理や集団の無意識に働きかける力」というのは、直観的に「いいね」と感じるもので、感情を揺さぶれるものです。言語でも同じく、人に直観的に刺さる言語化は開発可能で、直観的な言語化のカギは、古くから時代を超えて残るものであるという事です。
これは、先ほどのレヴィストロースやヤコブソンが主張したような、私たちを支配している根本的な構造の部分であり、それは過去から現在まで時代を超えて残ってきたものです。
なぜ、小説家を目指す人に、古典落語を知る人が多いのか?また、なぜ、80年代の日本のシティポップなどが現代の海外でリメイクされYouTubeで流れているのでしょうか?
その理由は、古典落語や80年代にシティポップに、深く共同体に沈み込んだ深層構造があるからです。この皆が無意識に共有する深層構造こそ、私たちを動かしていく原動力であり、これに至るには一時的なトレンドでは不十分です。
時の流れに耐えうる普遍的な価値を持つものは古典です。80年代シティポップも、古典になりえたからこそ、現代のアーティストから称賛されているわけです。ビジネスを円滑に進めていくために、直接関係ないように思われる古典学習が如何に大事であるかを私たちは知るべきです。
海外でも一流のビジネスパーソンは、一流の趣味人なケースがあります。ビジネスに大きく成功している人の生涯をみれば、その教育過程において、芸術や音楽を含め、古典に耽溺した経験を持つものが多いことに気づかされます。
言語化をより高度なレベルで熟達するには、古典や伝統という古くから残るものを深く知る事がカギとなります。
しかし、ビジネスにおける言語化が芸術レベルで要求されることは一部のクリエイター系の職種です。また言語化はかなり深いレベルの内容になり、個人のスキルだけに頼るようなことだけでは、ビジネスにおける活用として片手落ちです。次は、実務レベルで必要な言語化について迫ります。
ビジネスにおける言語化の重要性
ここまで言語化の概念と効用、理論背景を説明してきました。それでは実際に、ビジネスの現場で言語化がどのように役立ち、なぜ重要なのかを整理してみます。ポイントは二つあります。
- 「言語化すること」の重要性: 個人が自分の考えを言語化できることが、業務遂行や問題解決、自己成長に直結する。
- 「言語化されること」の重要性: 組織として言語化を促進する環境(心理的安全性や対話の場)が整っていることが、チームの知的生産性やエンゲージメント向上につながる。
個人のスキル面(言語化する)と組織の環境面(言語化される)の両方から、ビジネスにおける言語化の意義を見ていきましょう。
自ら言語化できることは武器になる
まず、個人のビジネススキルとしての言語化力についてです。これは先ほど述べてきた効用そのものですが、改めてビジネス的な観点でまとめていきましょう。
- 課題発見・解決: 業務上の問題点を適切に言語化できれば、課題が明確になります。たとえば「売上が伸びない」という漠然とした悩みを、「新規顧客獲得数が目標比○○足りない」と言語化すれば、次に何をすべきか(マーケティング強化か営業プロセス改善か等)が具体的に検討できます。問題を正しく言語化することは問題解決の第一歩です。
- 論理的な提案・報告: 上司やクライアントへの報告・提案でも言語化力がものを言います。考えを構造的に説明し、根拠を言葉で示せる人は信頼されます。ロジカルシンキング研修などで学ぶように、PREP法(結論・理由・具体例・結論)などの型に沿って話を組み立てるのも一種の言語化のテクニックです。考えていることを筋道立てて言語化できる力は、あらゆるビジネスコミュニケーションの基盤となります。
- 創造性の発揮: 言語化はクリエイティブな仕事にも貢献します。頭の中のアイデアを言葉にすることでアイデア同士を組み合わせたり発展させたりできます。ブレインストーミングでも、口に出したアイデアから連想が広がって新たな発想が生まれることがあるでしょう。言葉に出さなければ存在しなかったアイデアが、言語化によって形を得るわけです。。直感をあえて言語化する作業は、創造性を鍛える上でも有効だと言われています。作家の小林秀雄も、対談の中で「まだ形に現れていなかったものを形にするのが発見だ」と述べ、詩人は言葉を信頼して新しい意味の世界を作り出すのだと語っています。ビジネスイノベーションも然り、漠然とした着想を言葉とコンセプトに落とし込むことで初めて周囲を巻き込んだ具現化が可能になります。
- 感情の整理と自己成長: 自分のキャリアや強み・弱みを言語化できることも重要です。自己分析や他者からのフィードバックを通じて「自分は○○が得意で△△が課題だ」と言語化できれば、伸ばすスキルや取るべき行動が明確になります。最近は1on1ミーティングなどで上司が部下に自己内省を促すケースが多いですが、まさに自分のことを言語化する力が成長の鍵です。漠然と「なんとなく仕事がうまくいかない」ではなく、「私は状況説明が主観的になりがちなので、データを交えて論理的に話す訓練が必要だ」などと具体的に言語化できれば、対策も立てやすいでしょう。
このように、個人が言語化できること自体がビジネススキルの向上と成果創出につながります。採用面接でも「自分の考えをしっかり言語化できる人か」は重要視されますし、リーダー候補には高い言語化力(=コミュニケーション力と同義の場合も)が求められます。どんなに優秀な人でも、自分の知識やアイデアを伝えられなければ周囲を動かすことはできません。逆に言語化上手な人は専門外の領域でも話が通じるため活躍の場が広がります。「言いたいことを的確に伝えられる」能力はそれだけでビジネスパーソンの武器になるのです。
マーケティング理論でよく目にする言葉に「キャズム」があります。キャズムとは、新規事業を立ち上げて、軌道に乗せていくとき、必ず事業の停滞や落ち込みを経験することがあるという事です。キャズム理論ではこうした停滞や落ち込みをある種の断絶ととらえ、断絶が起きた場合には、ブリッジング(橋架け)をしなければならないと説きます。このキャズム理論の橋架けこそ、本記事で述べている「言語化」であり、新商品や新規事業をマーケットが受容する上で「言語化」するプロセスのそのものです。この意味においても、言語化の重要性は、マーケティング理論でも強調されていると言えるでしょう。
言語化される職場環境が生むもの
次に、組織全体として言語化が促される環境について考えます。いくら個々人が優れた言語化力を持っていても、組織の風土として意見を言えない・言わない雰囲気では宝の持ち腐れです。逆に、普段からメンバー同士が何でも言い合えるオープンな職場であれば、一人ひとりの知恵が引き出され組織力が高まります。
凡庸な言語で言語化される関係性の方が重要
ここであるA社の事例を紹介します。
A社は、自社の大型プロジェクトを遂行するためには、将来の幹部候補生を選抜し、彼らをプロジェクトリーダーに任命して、社運を賭けたビジネスに乗り出しました。全社挙げてのプロジェクトでしたが、幹部候補生たちは、思うような成果を上げるようなことができませんでした。成果が挙げられない処か、まず、プロジェクトリーダーが退職し、彼に続いて退職するものが現れる始末でした。
では、大型プロジェクトは最終的に失敗に終わったのでしょうか?以外に思われるかもしれませんが、この大型プロジェクトは最終的には大成功し、A社の業績もみるみる上がっていったわけです。
これはなぜでしょうか?理由は簡単で、選抜された幹部候補生たちに、実力がなく、その彼らが、辞めていったことによって、ビジネスに障壁が取り払われていったからです。身も蓋もない言い方をすれば、大型プロジェクトの遂行によって、期せずして社員のレベルが向上し、結果的には大成功を収めることができたのです。
A社の経営者が他社に努める年来の友人Bに久しぶりに会った際、このような会話が交わされました。
A「うちの会社の幹部候補性が数人やめてしまったんだよ」
B「そりゃー大変だね。そのプロジェクトは損失が大きくなったんじゃないのかい?」
A「いや、それが、プロジェクトは大成功してるし、継続してるんだよ」
B「えーそうなの?だったら、その幹部候補性達は大して役に立っていなかったということだね」
年来の友人Bからの何気ない一言で、Aは大きな気づきを得ました。A社の経営者は、自社の社員のそれぞれの実力について、キチンと言語化できていなかったのです。その言語化を、A社と無関係なBが、「大して役になっていなかったんだね」というセリフで、鮮やかに描き出しました。
言語化の目的は、コミュニケーションを通じて、最終的に気づきや学びや、行動や感情が変化することです。
つまり、他者が自分の考えや気持ちを遠慮なくあけすけな言葉でコミュニケーションが取れる状態から「言語化」が生まれます。それは、ある意味無責任な率直な言葉の可能性すらあります。
言語化する事は重要ですが、率直な本質を突いた他者からフィードバックは、実は自身の本質に刺さる「言語化」を生み、大きな気づきや変化を与えます。言語化してくれる他者や職場を創り出すことは、生産性に大きな影響を与えます。
それには以下のような職場要件が必要になるのではないでしょうか?
-
- 心理的安全性: メンバーが意見や質問をしても馬鹿にされたり否定されたりしないという安心感。心理的安全性が高いほど、人は失敗や課題も率直に言語化して共有します。一方、安全でない職場では問題が隠蔽され、表面的な会話や当たり障りない会話しか行われません。本音を言語化できる環境こそが組織の健全さの指標です。
- あけすけな対話の文化: 単に雑談が多いだけではなく、建設的に対話と他愛ないお喋りもあけすけな交話的対話が、職場で本質的な問いについて腹を割って話し合える場があると尚良いでしょう。
- 共通言語と共通体験: 組織内で最低限の共通言語や前提が共有されていることも重要です。たとえば専門用語ばかり飛び交って新人が話についていけないようでは、言語化されるべき知識が社内に広がりません。共通言語を育むには、教育や情報共有の仕組み、そして経営理念やバリューといった共通の軸となる言葉を持つことが有効です。そこには、共通の軸となる言葉と一緒に共通の体験が不可欠です。
- コミュニケーションスキルの醸成: 社員一人ひとりのコミュニケーション能力向上も見逃せません。結局のところ人が話す内容・質は個々のスキルに依存します。そこで企業研修などで傾聴や対話、ファシリテーションの訓練をすることは、組織全体の言語化力を底上げすることに繋がります。とくに中間管理職に対して、部下の意見を引き出す問いかけ方や心理的安全性を高めるフィードバック方法などを教育すると、現場での会話の質が変わってきます。要は「話せる雰囲気を作れる人」が増えることが大切です。
このような条件が揃うと言語化が活発に行われ、「沈黙の螺旋」や「同調圧力」が起きにくくなります。沈黙の螺旋とは、人が多数派と思われる意見に同調して本音を言わなくなる現象ですが、心理的安全性と対話文化があれば少数意見もきちんと言語化されるにようになります。もし、同調圧力を感じるのであれば、「圧(アツ)を感じます」と言語化しましょう。
そうすることで、今まで埋もれていた課題や斬新なアイデアが浮かんできます。
実際、ある大手企業では次世代リーダー育成プログラムの一環で徹底的な対話の場を設けたところ、参加者たちが互いの価値観をぶつけ合いながら自社のカルチャーや戦略を再定義するという成果が出たそうです。これは「企業文化の言語化」とも言えるでしょう。普段は議論されない「我が社の存在意義とは?」といった深いテーマをあえて言語化する場を持つことで、参加者は自社への理解を新たにし、共通の認識を持って帰っていきました。このように、組織として言語化すべきことを言語化できる環境は、社員のエンゲージメントや組織学習に直結するのです。
さらに、言語化される環境は社員のメンタルヘルス面でもプラスに働きます。心理的安全性が高ければ悩みや不安も共有しやすくなり、問題が深刻化する前に対処できます。逆に言いたいことも言えない職場ではストレスが溜まり離職にも繋がります。「悩みや提案を安心して言語化できる風土」は、人材定着や職場活性化の観点からも非常に重要なのです。
日記で書けるレベルの個人のあけすけな心象を吐露できるのは、重要なエンゲージメント向上の観点です。
言語化できる人材に頼るのではなく、言語化させる職場や関係には、心理的安全性・対話の機会・共通言語の醸成・コミュニケーション教育といった環境整備が不可欠です。人は安全で対等な場があれば、凡庸な言葉でも本質的な気づきや学ぶにつながります。逆に環境が整わなければ、有能な人も沈黙します。言語化は個人の努力だけでなく、職場ぐるみでデザインすべきテーマなのです。
言語化が根付く 再現可能な職場づくり
言語化はビジネスに重要でありながらも、個人スキル開発においては、あまりにも奥が深い内容です。しかし、言語化のビジネスにおける効用や目的は気づきやアイデア創出です。言語化をビジネスに活かすには再現可能であり、多くのビジネスパーソンが成果を上げる必要があります。
ここでは、言語化を再現可能にする組織設計について考えてみます。先述した環境をさらに具体に落とし込んだ施策と言えるでしょう。研修企画を担う人事担当者の皆さんにとっては、ここが腕の見せ所かもしれません。
職場内共通言語と共通体験の醸成
組織でスムーズに言語化を行うには、共通言語の存在が大きいと述べました。共通言語とは必ずしも専門用語だけではなく、「何を大事にするか」という価値観レベルの合意や、皆が腹落ちしているビジョン・目標も含みます。これらがないと、人はそれぞれ勝手な前提で話すため議論が噛み合いにくくなります。
共通言語を育むためには、共通体験を増やすことも有効です。一緒に研修やプロジェクトをやり遂げたメンバー同士は、その経験を語る内輪言葉(「あのときの○○現象だね」等)さえ生まれます。このような内輪言葉は時に他部署には分からない排他性も持ちますが、逆に言えばチーム内の理解を深めコミュニケーションを円滑にする潤滑油になります。
ですから、人材開発の観点では敢えてクロスファンクショナルなプロジェクトを組んだり、合同研修で異部署交流させたり共通の体験と言葉を作る機会を提供すると良いでしょう。そうすることで「○○部の人とは話が通じない」というサイロ間の断絶を減らし、組織全体で共通の表現や理解が増えていきます。たとえば一括で全社員に浸透させたいバリュー(価値観)があるなら、それをテーマにワークショップを行い、皆でその言葉の意味するところを語り合うのも手です。ただ標語を掲げるより、自分の言葉で語った経験がある人の方がその価値観を本当に理解できます。
コミュニケーションスキルの開発
次に、社員のコミュニケーション能力向上施策です。とくに中堅・管理職向けには、部下や同僚の言語化を引き出すスキルを身につけてもらうことがポイントです。
具体的には、コーチング研修や1on1面談研修で「傾聴」と「質問」の技術を磨いてもらいます。傾聴によって相手が安心して話せる雰囲気を作り、上手な質問で相手の考えを深掘りする。これができれば、部下は自分の考えをどんどん言語化し、課題やアイデアが表面化してきます。ファシリテーター的な役割を担えるリーダーが増えれば、会議やチームでの対話も活性化し、生産的な言語化が進みます。
また、新人や若手にはロジカルシンキングやドキュメンテーション(文章力)の研修も有効でしょう。とくに技術職など「話すのは苦手…」という人ほど、トレーニングによって劇的に表現力が伸びることがあります。ポイントはアウトプット機会を設けて実践させることです。研修中に自社の課題についてミニ発表してもらうなど、自分の言葉で説明する場数を踏ませるのです。最初はたどたどしくても回数を重ねるごとに伝え方が洗練され、自信もついてきます。
最近では社内SNSやナレッジ共有ツールを導入し、社員同士が日常的に情報発信・意見交換できるようにしている企業もあります。テキストベースであっても、自分の知見を社内ブログに書いてみる、掲示板で議論してみるといった小さな言語化の実践が全体の底力を上げます。先進企業ではSlackなどで雑談チャンネルを設け、普段言わないアイデアを言いやすくしたり、業務ナレッジを気軽に共有したりする文化づくりをしています。「こんなこと言ってもいいんだ」「こう書けば伝わるな」と社員が体感することで、オープンなコミュニケーションが根付いていきます。
率直な言語が飛び交う場の設計と風通しの良い職場づくり
最後に根幹となる心理的安全性について強調します。Googleの研究のみならず、多くの調査で心理的安全性は高パフォーマンス組織の鍵とされています。では、人事施策として具体的に何ができるでしょうか。
一つは経営者や管理職自身が率先してオープンマインドなコミュニケーションをすることです。「何でも意見を言ってほしい」と口で言うだけでなく、経営トップが失敗談を語ったり社員のきつい質問にも真摯に答えたりする姿勢を見せると、現場も安心します。「上司も本音で語っているのだから自分も言おう」というムードが出てきます。逆に上層部が建前ばかりだと従業員も萎縮して黙ってしまいます。
定期的な従業員エンゲージメント調査などで匿名意見を募り、そこで出た声にしっかり向き合うのも大事です。「社員からこんな意見が出ています。改善策として○○を始めます」とフィードバックすれば、社員は「言えば聞いてくれるんだ」と感じ、次も意見を言いやすくなります。言語化しても無視される経験が重なると人は発言をやめてしまうので、言語化に報いる仕組みが必要です。
チームビルディングの一環で対話型のワークショップを企画するのもよいでしょう。心理的安全性は一朝一夕で生まれるものではなく、日々のコミュニケーションの積み重ねで醸成されます。
その手助けとして、プロのファシリテーターを招いてのワークショップや、部課単位のオフサイト(非日常の場でじっくり話す会)などを年に数回設ける企業もあります。こうした場で普段言えない意見を引き出し、お互いの人となりを知ることで、職場での遠慮が減り言語化が促進されます。
心理的安全性とは決して「仲良しグループになること」ではなく、率直なフィードバックを言い合える関係のことです。それを誤解するとぬるま湯組織になる恐れもあります。要は、お互いを尊重しつつも建設的に物申せる関係性をどう作るか?です。人事としては、そのための教育(フィードバック研修等)や仕組み(相互評価制度など)を検討すると良いでしょう。
以上、組織で言語化を根付かせるためのアプローチを見てきました。共通言語・対話・スキル・心理的安全性といったキーワードが出ましたが、総じて言えるのは「言語化しやすい土壌づくり」の重要性です。個人任せではなく、仕掛けとリーダーシップによって社員が思い思いに物を言える環境を作ること――それが結果的に組織の知的生産性や創造性を飛躍的に高める投資となるでしょう。

心理的安全性とは?定義や意味と誤解、本質的に高い職場状態や高める方法について解説!
注目されている概念に心理的安全性があります。心理的安全性の概念とは、取り入れる方法とは。本記事では、その起源…
まとめ
長文となりましたが、最後に本記事の内容を振り返り、言語化とは何か、そしてなぜ重要なのかを改めて整理します。
言語化の定義: 自分の考え・感情・知識を言葉にして表現し、他者に伝わる形にすること。単なる「話すこと」ではなく、相手や目的に合わせて適切な言葉へ翻訳するプロセスを指します。
言語化が重要視される背景: 現代のビジネス環境では、多様性・専門化の進展により共通言語が不足し、コミュニケーション難度が増しています。また、SNS等の普及で表面的なやりとりが増え、本質的な対話が減る中、誤解や不安が生じやすくなっています。こうした状況下で、意図や思考をきちんと伝える言語化力が改めて求められています。
言語化の効用: 人が言語化する理由は多岐にわたります。
- 情報共有: 暗黙知を顕在化し知識を伝達する。【例】業務ノウハウをマニュアル化して共有。
- 思考整理: 頭の中を可視化し自己理解を深める。【例】悩みを紙に書いて問題点を特定する。
- 感情処理: 感情を言葉にすることでストレスを軽減する。【例】同僚に不満を聞いてもらいスッキリする。
- 行動喚起: 言葉の力で人の心を動かし行動につなげる。【例】リーダーのビジョンメッセージが組織を動かす。
理論的視点: 言語には情報伝達、感情表現、働きかけ、交流促進など6つの機能があり、私たちの思考や文化は言語によって形作られています。言葉選び一つで相手の受け取り方や組織文化まで変えうることに留意すべきです。また、言葉には論理的道具としての側面と、人の深層心理に影響する呪術的側面があることを念頭に置き、効果的かつ配慮ある言語化を心がけることが大切です。
ビジネスへの効果: 言語化力が高い個人は、課題解決や提案力、創造性、自己成長の面で優位に立てます。組織としても、言語化しやすい職場は問題発見が早まり、イノベーションが生まれ、社員のエンゲージメントが向上します。「言語化されない沈黙」はリスクであり、「言語化し合える対話」は組織の財産と言えるでしょう。
環境づくり: 言語化を促進するには、心理的安全性を確保し、共通言語や対話の場を設け、社員のコミュニケーションスキルを育成することが必要です。経営トップ自ら開かれた対話を実践し、率直な意見交換を奨励する文化を醸成することが不可欠です。
以上を踏まえ、ぜひ皆さんの職場や研修で「言語化」という視点を取り入れてみてください。たとえば会議で「それはどういうことか言語化してみましょう」と問いかけてみる、研修でディスカッションを増やして受講者に自分の言葉で話してもらう、社内報やSNSで社員が自由に発信できるコーナーを作る等、アイデアは色々あります。言語化の機会を意図的に作り出し、フィードバックを通じて良質な言語化を称賛・定着させていくことが組織力アップの鍵です。
「言語化された組織」は強い組織です。一人ひとりが知恵と言葉を出し合い、互いに理解し高め合う職場は、どんな変化にも適応できるでしょう。ぜひ今日から、小さなことでも言語化して伝える一歩を踏み出してみてください。それがやがて大きな信頼と成果の積み重ねにつながるはずです。
最後までお読みいただきありがとうございました。言語化の実践によって、皆さんの組織がより風通し良く創造的な場になることを願っています。