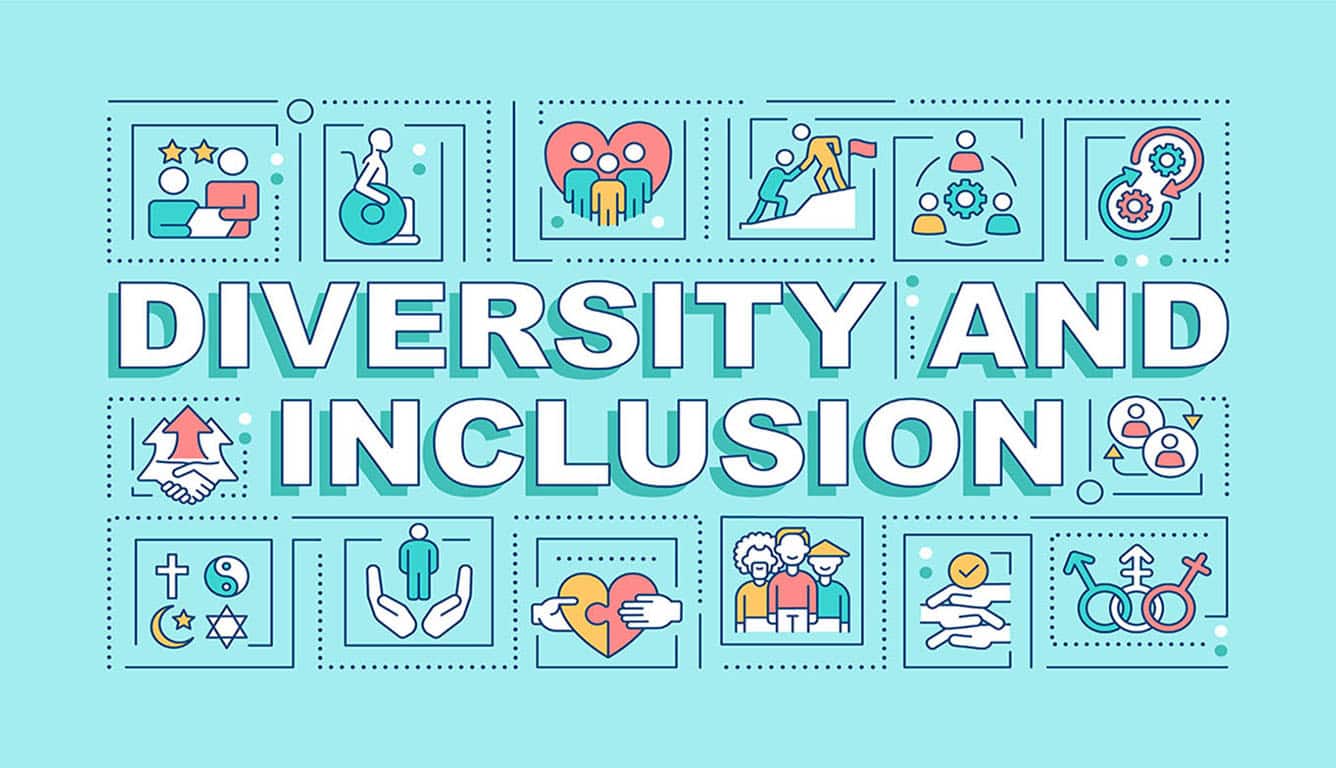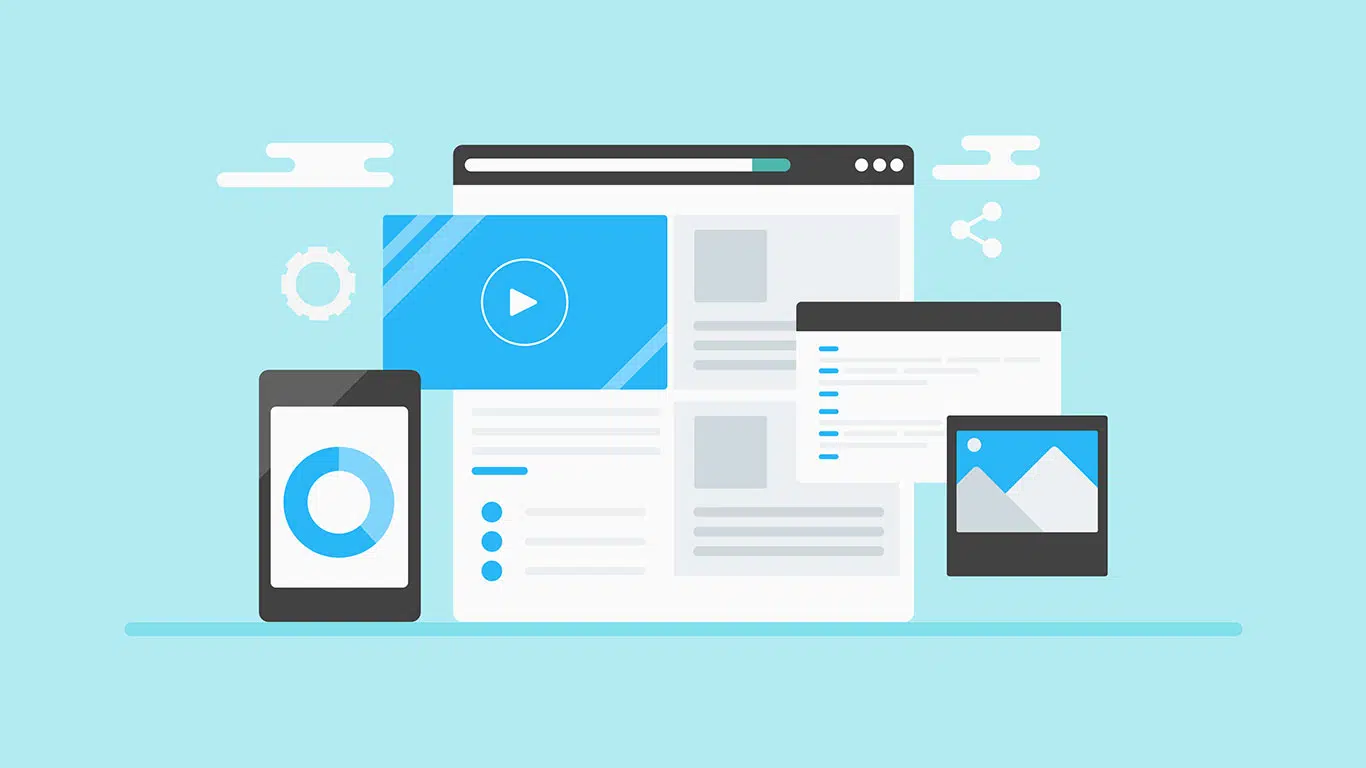「多様性を受け入れる」ために重要なことは?多様な時代に生きるうえでのコミュニケーションとは
最終更新日:2024.06.05

目次
昨今、さまざまな文脈で注目を集める「多様性」という言葉。一人ひとりが生きやすい社会を作るための意識が高まっています。これはビジネスの世界でも言えることで、多くの企業が多様性を追求した活動に勤しんでいます。この記事では、多様性について詳しく考えながら、どのようにすれば多様性ある組織を実現できるのかを紐解いていきます。
「多様性を受け入れる」とはどのような意味合いなのか
「多様性を受け入れる」という言い回しは、さまざまな場面で使われています。まずはこの表現について一度立ち止まって考えてみたいと思います。多様性と一口に言っても、実際にはその中身にさまざまな要素が含まれています。
そもそも多様性とは
そもそも「多様性」とは、どのような意味を持つ言葉なのでしょうか。辞書的な定義を確認しましょう。オックスフォード英語辞典によると、多様性(diversity)とは、「互いに非常に異なる多くの人や物の集まり」と定義されています。これを社会的な文脈に落とし込むと、異なるバックグラウンドや特性を持った人の集まりということになります。多くの場合、LGBTQ+や移民、障害、性別など、いわゆるマイノリティに関する文脈で語られます。マイノリティが排除されることなく、のびのびと暮らせる社会にするために、昨今声高に叫ばれているテーマです。
表層的ダイバーシティと深層的ダイバーシティ
ダイバーシティを受け入れる重要性については広く認識されていますが、ダイバーシティについて細分化して考えたことがある人はそう多くはないかもしれません。以下では、ダイバーシティを2つの種類に分けて考えます。
表層的ダイバーシティ
まずは表層的ダイバーシティをみてみましょう。以下のような項目が含まれます。
- 性別
- 人種
- 国籍
- 年齢
- SOGI(性的指向・性自認)
- 障害の有無
これらは一人ひとりのプロフィールを把握すれば認識しやすいもので、知識と情報次第で適切な配慮をとることが可能です。どのような対応をするといいのかマナーとして知っていれば、問題なく乗り越えられるでしょう。勉強して広く知見を深めておくことで、ダイバーシティを受け入れたり、受け入れてもらったりという働きかけが可能です。
深層的ダイバーシティ
続いて深層的ダイバーシティです。こちらは表面的には把握できないものになるので、配慮が難しい領域になります。主に以下のような項目が含まれます。
- 価値観
- 宗教
- 経験
- 嗜好
- 第一言語
- 受けてきた教育
- コミュニケーションの取り方
深層的ダイバーシティを気にしていない場合、無意識な思い込みで相手のイメージを決めてしまったり、不適切な対応をとってしまったりする懸念があります。社会構成主義の考え方につながりますが、哲学史の中では「事実・事物」は存在しておらず、物事は人の認識や解釈から存在するのではないかという議論があります。認識に際して使っているフィルター次第で、事実は変わってしまうということです。一人ひとりの深層的ダイバーシティに関わる項目を把握することは難しくても、バイアスを意識するだけで、無意識的な思い込みを排除することが可能となるでしょう。
「多様性を受け入れる」とは
これらを踏まえて、改めて「多様性を受け入れる」とはどういうことなのかを考えてみたいと思います。これは、マジョリティ(多数派)がマイノリティ(少数派)を受け入れるという構造に限りません。
自分にもなにか人と異なるところがあること、誰もが「受け入れられる側」でもあることを自覚することが、本当の意味での多様性への理解です。特定のマイノリティに対して線を引くことなく、互いが互いを受け入れ合っていく状態を目指しましょう。
多様性を受け入れる必要性
多様性を受け入れることがなぜ重要なのか、立ち止まって噛み砕いていこうと思います。必要性はさまざまにありますが、主に2つの観点から紹介します。
安心して暮らせる社会作り
多様性は、社会で暮らす人々の安心につながります。もし多様性が認められない社会の場合は、誰かが肩身の狭い思いをしているなど、いろいろな意味で犠牲になっています。家族や友人など大切な人がそれに該当する可能性もあれば、自分も犠牲になるかもしれないという恐れを感じるかもしれません。
多様性を尊重することで、何かに選択を制限されることなく、のびのびと生きていけます。それが、穏やかな人生を送っていくためにはとても大切なことなのです。
誰ひとり取り残さない社会作り
多様性を受け入れることで、誰ひとり取り残されない社会を目指すことができます。世の中の人間は、性別や人種、身体的特徴もさまざまであり、同じ物事に対する感じ方や考え方もバラバラです。得意分野、不得意分野も、人によって当然異なります。
多様性を重んじて、互いに助け合うことができれば、新しい発想や解決策を講じることができ、社会や経済が繁栄していきます。
ビジネスにおいてなぜ「多様性を受け入れる」必要があるのか
一般社会における多様性の大切さについて考えてきました。ここからは、ビジネスの世界においても多様性が重要である理由について考えていきます。昨今、グローバル化やテクノロジーの進化が著しく進み、企業を取り巻く経営環境は大きく変化してきました。
人々の生活や働き方、考え方もさまざまなパターンに分かれるようになり、人と人とのコミュニケーションの取り方も変わってきています。だからこそ、多数決のような従来の判断基準や、一部のトップに従う判断基準でもなく、少数派のアイデアも尊重することが求められます。新しい価値観から新しい観点を得ることが、組織におけるひとつの成功体験になる時代なのです。
多様性を深く受け入れるのは難しいし限界がある
多様性を本当の意味で受け入れることは、単純ではありません。たとえば根本的に価値観が合わない、信念が合わないという場合に、無理に受け入れようとすると、ストレスや緊張などの大きな負担がかかってしまうケースがありえます。
もちろん、異なる価値観も尊重して相互理解していくことが大切ではありますが、状況によっては、勇気をもって距離を置くことがベストな解決策になることもあります。
また、多様性を受け入れるためには、他者のナラティブを聴くことが不可欠となるでしょう。「ナラティブ」とは、物事や出来事に対して人々が自分の視点や経験を通じて語ることを指します。
上司と部下の関係や職場でのモヤモヤや心理的な葛藤は、言葉や論理だけでは解決しづらい場合があります。しかし、相手の主要なストーリーとその背後にある物語に焦点を当てた対話は、協力関係を築くための助けとなります。価値観や感情は言葉や論理だけでは乗り越えられないものですが、相手のナラティブに深く耳を傾けることで理解が深まり、共感や協力が生まれます。このような難しいコミュニケーションは時間と適切な場を要しますが、お互いが時間をかけてじっくりと向き合うことが重要となるでしょう。
多様な時代に生きるうえでのコミュニケーション
多様性を受け入れるために重要なのは、コミュニケーションです。コミュニケーションひとつとっても、文化や習慣によって大きな違いが生じます。たとえば、日本では当たり前となっているコミュニケーションが、他国では「感情が読めない」という印象を与えているケースがあるでしょう。
考え方や表現方法は、国によっても、個人によってもバラバラです。このような違いを違いとして認識していくのが、誤解なく共に過ごすための最初の足がかりになります。コミュニケーションは、自分が思っている以上に丁寧に、そして相手のことをしっかり見て理解していく姿勢が重要です。
とくにナラティブは、人々の意識、また無意識な部分にも影響を与えます。見えない考えや解釈は、言葉や行動に反映されるため、表面的な情報だけでなく、裏にある意味や背景を理解することが大切です。これは、暗示的に伝わるコミュニケーションとも言えます。
現代の職場では、タスクだけでなく人間関係も重視されています。信頼関係に問題がある場合は、職場やチームメンバーと時間をかけて対話し、相手のナラティブに耳を傾けることが必要です。
多様な時代に相手を理解するコミュニケーションのポイント
コミュニケーションの重要性について紹介したので、以下では、実際にコミュニケーションをとる際に重視するべきポイントを解説していきます。それぞれの要素を意識するだけでも、コミュニケーションスキルの向上につながるでしょう。
相手に伝わるように工夫する
まずは、相手に伝わるよう工夫することです。コミュニケーションの目的は多くの場合「伝える」ことに終始してしまいがちですが、伝えること以上に大切なのは、相手に伝わるように意識することです。
たとえば会話中、相手の表情やリアクションを見ていると、言葉にしていない感情を読み取れることがあるかもしれません。読み取った感情を踏まえてこちらからの伝え方を工夫することで、より相手と意思疎通しやすくなります。このような工夫が、コミュニケーションを充実させるでしょう。
会話のラリーを意識することが重要
会話のラリーを意識してみるのも重要なポイントです。互いが話す時間が4〜6割というバランスになると、コミュニケーションは活発になります。この割合だと、聞き手・話し手に分かれてしまうのではなく、双方が能動的に会話に参加しているという意識が芽生えるのです。
コミュニケーションの際は、自分の話しているボリュームや、相手の話す量を踏まえて、バランスを調整していきましょう。
メタ認知能力も重要
メタ認知能力も、コミュニケーションにおける大切な要素です。メタ認知とは、知覚、思考、学習、記憶などの認知を、高い位置からチェックすることです。メタ認知能力が高ければ、自分の話が相手にどう伝わっているのかなどを相手の立場からいち早く認識できます。必要があれば工夫を入れるなどができるので、コミュニケーションを進める上で効果的な能力です。
相手に興味を持つ
コミュニケーションの前提として大切になるのは、相手の話す内容や、相手自身に興味を持つことです。興味を持ってもらえないと話したくなくなり、感情を表に出しにくくなるものです。もし興味を持てない場合でも、なにかしらの取っ掛かりを探し、少しでも前のめりになれるように努力しましょう。
まとめ
昨今、多くの企業が多様性を追求した活動に勤しんでいます。多様性とは、異なるバックグラウンドや特性を持った人を受け入れることです。その際、特定の物差しでマジョリティとマイノリティを分けるのではなく、自分にも何か人と異なるところがあること、誰もが「受け入れられる側」でもあることを自覚することが大切です。多様性を受け入れることは、新しい価値観から新しい観点を得て、組織を強くすることにもつながります。
そのために重要なのは、コミュニケーションです。相手のことをしっかり見ながら、必要な工夫を凝らして、多様性ある環境をめざしていきましょう。