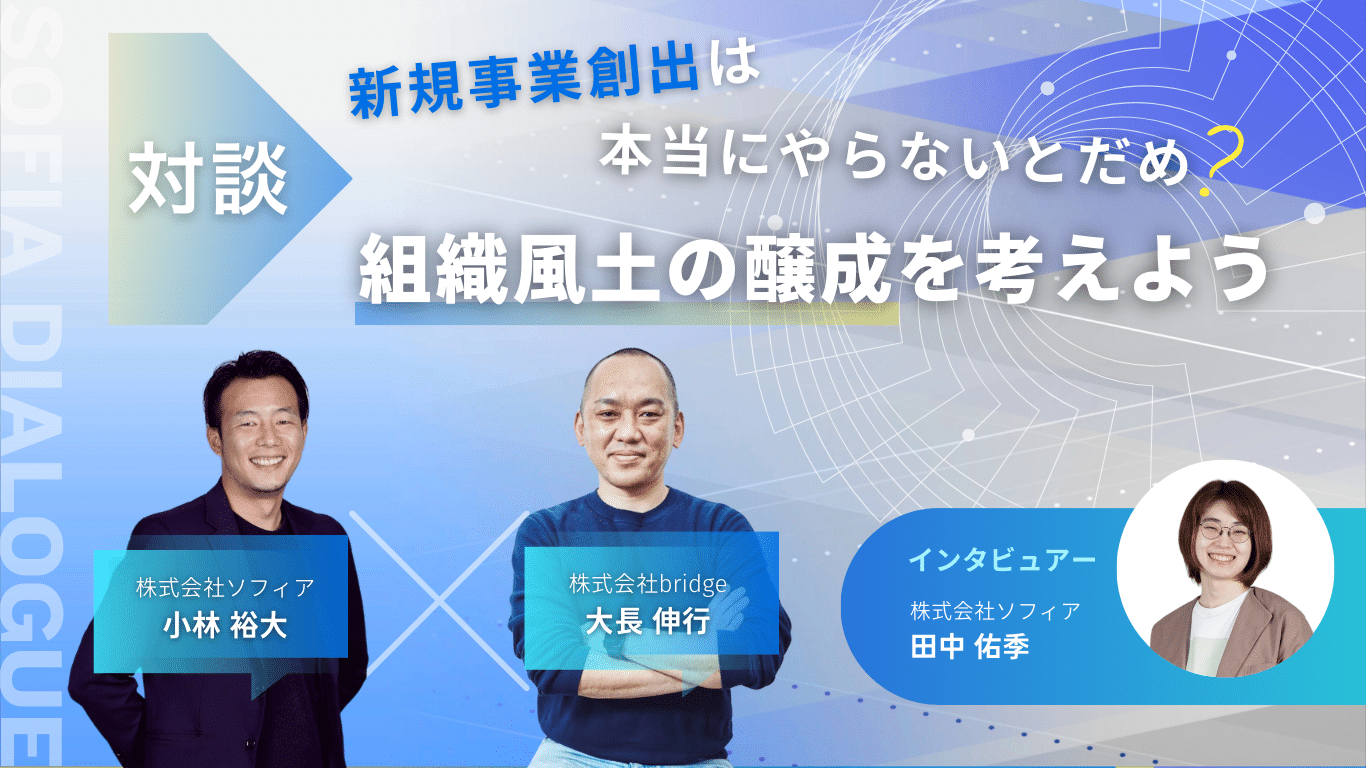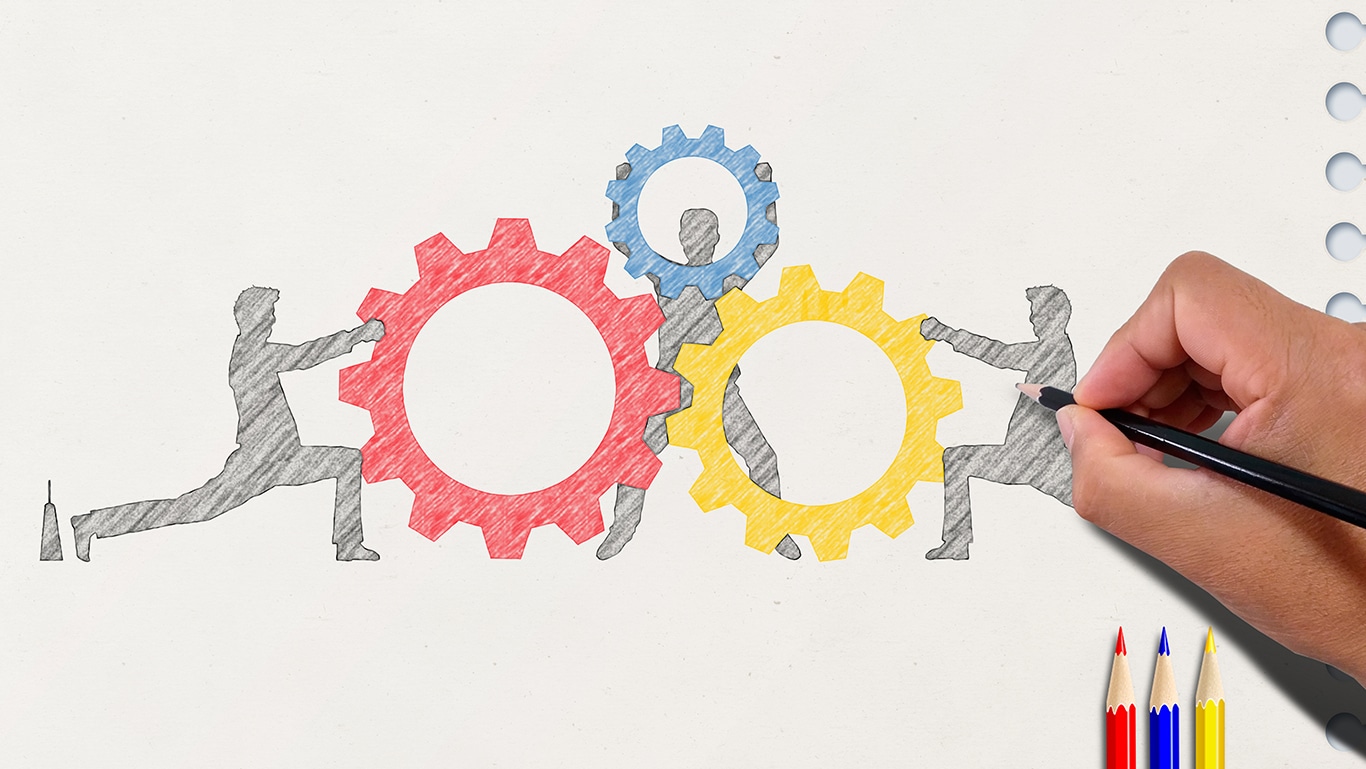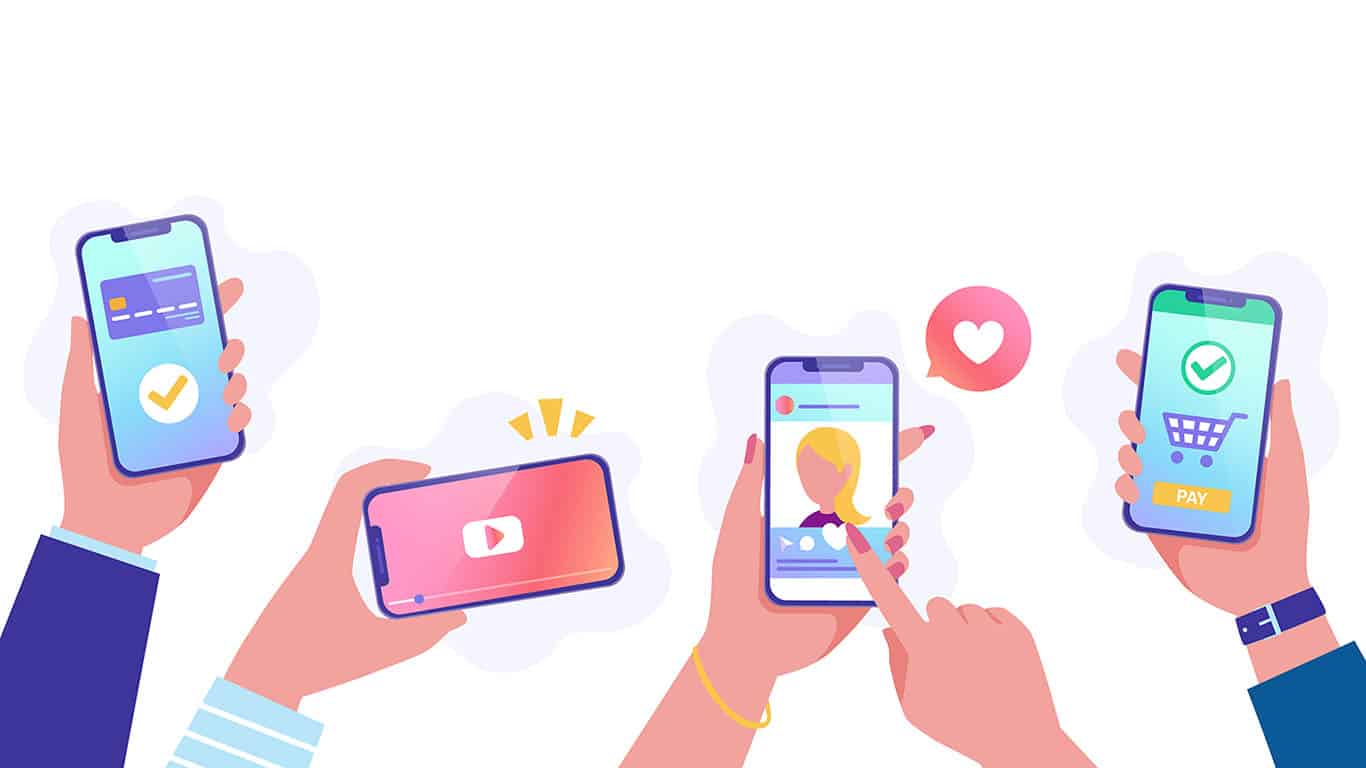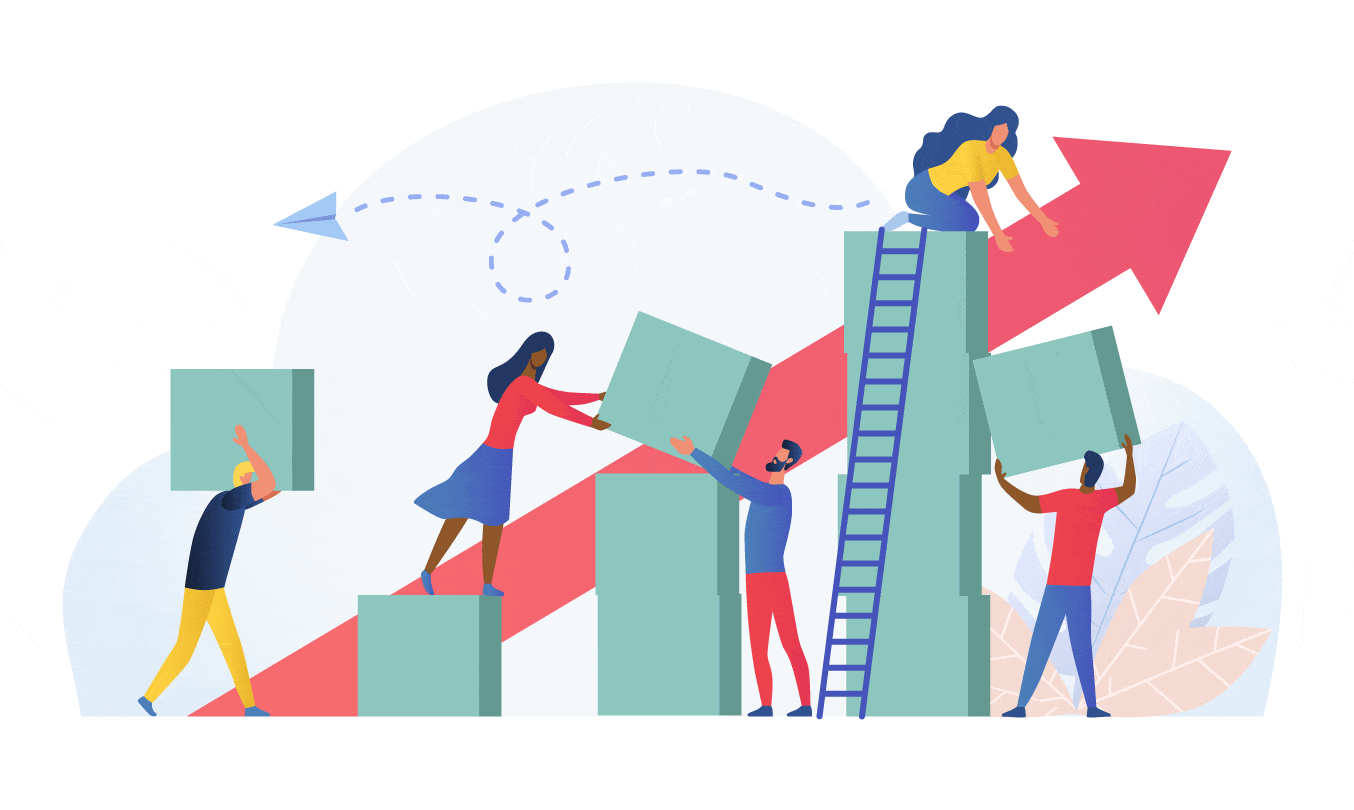大企業の新規事業が失敗する原因:調査データに見る課題と対策を解説
最終更新日:2025.07.09

目次
大企業で新規事業に挑戦しても、なかなか思うような成果が出ずに悩むケースは少なくありません。あなたの会社でも、「なぜ新規事業は失敗しやすいのか?」という疑問を抱いたことはありませんか?
本記事では、この疑問に答えるべく新規事業が失敗する典型的な原因を信頼できるデータや事例とともに探ります。そして成功確率が低い中で新規事業を軌道に乗せるにはどうすれば良いのか、組織全体からアイデアを引き出す文化づくりや社内コミュニケーションの在り方に焦点をあてながら考察していきます。
新規事業の成功確率は低い——それでも挑戦し続ける重要性
新規事業の成功確率が非常に低いことは、多くの調査で明らかになっています。例えば、アビームコンサルティングの調査(年商200億円以上の企業780社対象)では、取り組んだ新規事業のうち累積損失を解消できた(採算ラインに乗った)割合はわずか7%に過ぎないと報告されています。逆に言えば、93%もの新規事業が投資回収に至らず失敗しているという厳しい現実があるのです。このデータからも、新規事業がいかにハードルの高い挑戦であるかがお分かりいただけるでしょう。
しかし、だからといって挑戦を止めてしまっては将来の成長は望めません。「20回に1回しか成功しない」のであれば、より多くの打席に立つ(挑戦回数を増やす)ことが重要になります。実際、同調査では成功確率が低い以上、企業には多数の新規事業テーマに並行して取り組むことと、成功率自体を上げるための工夫が不可欠だと指摘されています。言い換えれば、一つ一つの失敗から学びつつ試行回数を重ねることが新規事業成功への唯一と言っていい近道なのです。
もちろん「数撃ちゃ当たる」とはいえ、新規事業への投資には限りがあります。そこで重要になるのが、失敗からの学びを次に活かす仕組みと、組織として失敗を許容し挑戦を後押しする文化です。新規事業は計画通りに進む可能性が極めて低く失敗がつきものですから、企業の上層部は多少の損失が出ても許容し、次の挑戦に繋げる度量を持つ必要があるのではないでしょうか。実際に失敗プロジェクトから学びを得て次の成功に結びつけた例もあります。
では、新規事業が失敗する具体的要因を分析すると共に、そうした失敗を乗り越える組織づくりのポイントを探っていきましょう。
新規事業が失敗する主な原因と失敗パターン
新規事業がうまくいかない背景には、いくつもの典型的なパターンがあります。ここでは大企業において特に見られがちな失敗要因を、信頼できる調査結果や実例を交えながら詳しく解説していきます。
1. 顧客ニーズの見極め不足によるミスマッチ
まず重要なのは、顧客の真のニーズを捉え損ねてしまうことです。どんなに技術力や製品力があっても、顧客が求めないもの・価値を感じないものを提供していては成功しません。経済産業省のデータを用いた試算でも、新規事業に「成功した」と答えた企業の約半数近くは、新規事業後も利益率が横ばいか減少しており、真の意味で収益化まで至った企業は全体の約14%程度にとどまることが指摘されています。この一因として考えられるのが、提供した新規事業の顧客需要を誤認していたケースでしょう。
具体的には、ユニクロ(ファーストリテイリング)が2000年代初頭に手掛けた生鮮野菜販売事業「SKIP(スキップ)」の失敗が典型例として挙げられます。ユニクロは衣料品で培った効率的生産・大量販売モデルを野菜にも応用し、「良いものを安く」提供しようとしました。しかし結果は1年半で撤退、累計26億円もの特別損失を計上する大きな失敗となりました。当時このプロジェクトを担当した柚木治氏(現・GU社長)は、失敗要因を「顧客起点の考え方に欠けていた」と総括しています。
平たく言うと、自社の都合(安く大量に売りたいという発想)ばかりに囚われ、顧客が本当に求める体験を十分に考慮できていなかったということです。実際、SKIPでは天候等で野菜が品薄になると店舗の棚がスカスカになることもありましたが、「高品質でも欲しい野菜が時々欠品している店」をお客様がどう評価するかという視点が欠けていたわけです。
このように、顧客ニーズを誤って捉えることは新規事業失敗の致命的な要因になります。回避するには、市場調査やユーザーインタビューなどを通じて顧客の課題や潜在ニーズを徹底的に検証するプロセスが不可欠でしょう。「作れば売れるだろう」という思い込みではなく、まず顧客の声に耳を傾け、ニーズ起点で発想することが成功への第一歩と言えます。
2. アイデアや戦略の質が低い・方向性が不明確
次に、新規事業のアイデア自体の質や事業戦略の不備も失敗につながります。闇雲に新しいことに手を出しても、きちんと筋の良いアイデアでなければ成果は望めません。社内でアイデアコンテストを実施して新規事業案を募る企業もありますが、本来の目的を見失い「コンテストで受ける企画」ばかりに偏ってしまうといったケースも散見されます。これは、新規事業を通じて何を成し遂げたいのかというビジョンやミッションが不明瞭なまま走り出してしまうことが原因でしょう。
また、「アイデアの質」に関連して指摘されるのが、新規事業に必要なマインドセットの不足です。新規事業には市場リサーチや財務管理など様々なスキルが必要とされますが、だからといって特定のスキルさえあれば成功する保証はありません。むしろ未知の挑戦には何度失敗しても諦めずにチャレンジし続ける情熱や粘り強さこそが重要です。しかし、大企業の中には「スキル至上主義」に陥りがちな風土もあり、「優秀な人材を集めたから成功するはず」と慢心してしまうケースがあります。
噛み砕いて言えば、新規事業はある種”博打”のようなもので、必勝のスキルは存在しない以上、必要なのは失敗を恐れず試行錯誤を繰り返すマインドなのです。「馬券は買わなければ当たらない」のと同様、新規事業もチャレンジしなければ成功しないというシンプルな原則を忘れてはいけません。
さらに、新規事業の方向性が社内で共有されていないと、部門全体が迷走してしまう恐れもあります。「何のためにこの新規事業をやるのか」を経営陣から現場までしっかり腹落ちさせ、全員が同じビジョンに向かってアイデアを出し合える状態を作ることが重要です。そのためには、経営トップが新規事業に期待する目的や位置づけを明確に示し、常に繰り返し発信していく必要があるのではないでしょうか。
3. 社内意思決定の遅さ・調整コストの高さ
大企業ならではの課題として、社内の調整に時間がかかりすぎることが挙げられます。組織の規模が大きく複雑になるほど、関係者の数も増え、稟議・合意形成のプロセスは煩雑になります。意思決定スピードの遅さは新規事業の機を逃す大きな要因です。せっかく良いアイデアや市場機会があっても、社内承認に時間を取られている間に競合に先を越されてしまうこともあるでしょう。
さらに厄介なのが、社内の抵抗勢力の存在です。大企業では、現在の主力事業を築き上げてきた経営層やベテラン社員が強い発言力を持っていることが多く、彼らは新規事業に対して懐疑的になりがちです。過去の成功体験に基づいて「そんなものはリソースの無駄だ」「うちの会社のやり方には合わない」と否定的な意見が噴出し、プロジェクトの足を引っ張るケースが散見されます。
実際、大企業の新規事業担当者に対する調査でも、「担い手となる人材の確保」(約39%)や「新規事業に必要な知識・ノウハウ不足」(約39%)に次いで、「意思決定の遅さ」と「現行の人事評価制度の不適合」を課題に感じる割合が約3割にのぼったとの報告があります。これは、迅速な判断や柔軟な評価ができない組織体質が、新規事業の推進を阻んでいることを示唆しているのではないでしょうか。
こうした問題を解決するには、まず社内の意識合わせとコミュニケーションが不可欠です。新規事業の背景や狙い、必要性について、関係者が事前によく理解していれば反発も和らぎます。部門や役職の垣根を越えて事前に情報共有・意見交換を行い、合意形成の下地を作っておくことが大切です。また場合によっては、経営トップ自らが旗振り役となって反対者を説得し意思決定を下す覚悟も求められるでしょう。新規事業推進のために組織横断の特命チームを作り、トップ直轄でスピーディーに進める仕組みを採用する企業もあります。
さらに、人事評価の面でも工夫が必要です。新規事業は短期的な売上や利益だけでは測れないものですから、失敗してもチャレンジしたこと自体を評価する制度や、一定期間は本業と切り離して成果ではなくプロセスを重視する評価軸を導入することも有効でしょう。そうすることで社員も安心してリスクの高い挑戦にコミットでき、組織全体で新規事業に取り組むムードが醸成されると思われます。
4. 人材・資金などリソースの不足
最後に、新規事業を成功させるための経営資源の不足も大きな障壁です。優秀な人材や十分な予算が割かれなければ、良いアイデアも絵に描いた餅に終わってしまいます。特に大企業の場合、既存事業が安定して収益を上げていると、どうしても人材もお金も主力事業に優先的に配分され、新規事業には「余ったリソースで細々と…」となりがちです。これでは重要度が社内で共有されず、本気度の低いまま失敗してしまうのも無理はありません。
前述のパーソル総合研究所の調査結果でも、新規事業担当者が感じる課題のトップが「担い手となる人材の確保」(約38.9%)であり、次いで「知識・ノウハウ不足」(38.6%)が挙げられています(※両者はほぼ同率)。この「人材不足・知見不足」という課題は、まさにリソースの不足を物語っています。社内に適任者がいない場合、外部の専門人材を招くなど、社外の知見を取り入れることも検討すべきでしょう。
例えば、新規事業領域のプロフェッショナル人材を社外から登用(採用やアドバイザー契約)することで、社内に足りない経験値を補う手法があります。また最近では、スタートアップ企業と協業するなど、CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)を通じて社外の技術・サービスに投資することで自社の新事業に活用する例も増えています。
資金面についても、十分な投資を覚悟できるかが問われます。投資余力がある大企業であっても、失敗を恐れるあまり少額の予算しか割かないのでは、大きな成功は望めません。ある程度の予算と期間を確保し、腰を据えて育てる姿勢が必要です。その代わり、撤退基準(どの程度の損失で見切りを付けるか)を予め定めておき、損失が膨らみ過ぎないうちに引き際を判断することも重要になります。ユニクロのSKIP事業は結果的に失敗しましたが、1年半という比較的早い段階で撤退を決断したため、親会社ユニクロ本体にとって致命傷にはなりませんでした。このように、的確なタイミングで撤退判断を下し損失を最小限に食い止めることも、新規事業マネジメントの重要なポイントと言えるでしょう。
新規事業成功のために企業が取り組むべきこと
前章では、新規事業が失敗する代表的な要因をご紹介しました。
では、こうした失敗を乗り越えて新規事業を成功させるには、企業は具体的に何に取り組むべきなのでしょうか?成功確率を高めるための組織文化・コミュニケーションの在り方と、大企業で新規事業を軌道に乗せた成功事例を見ていきます。
組織全体からアイデアを引き出す文化の醸成
新規事業の成功には、全社員から新しい発想を引き出せる組織風土が不可欠です。新規事業のアイデアは数が勝負です。できる限り多くのアイデアを出し、その中からビジネスになり得るものを選び取っていくには、社員一人一人が自由に発想を共有できる環境でなくてはなりません。玉石混交のアイデアでも、突拍子もない考えでも口に出せる雰囲気が重要だと指摘されています。
こうした文化を醸成するためには、まず経営層が率先して心理的安全性の高い場を作ることが大切です。社員が失敗を恐れて発言を控えてしまうようでは、新規事業の芽は出てきません。経営トップ自らが「チャレンジを歓迎する」姿勢を明確に示し、失敗したとしても頭ごなしに否定せず建設的に次につなげる評価をする——そうした姿勢が部下に伝わることで、組織の風土は徐々に変わっていくでしょう。
よく「イノベーティブな風土がないから新規事業が生まれない」と言われますが、実際には経営陣が挑戦する姿勢を示し続け、その結果に対するフィードバックの仕方が風土を形作るのです。したがって、トップが恐れずに新規事業にコミットし、周囲もそれを受けて挑戦する——このポジティブな挑戦の連鎖を生み出すことが文化づくりの第一歩となるのではないでしょうか。
具体的な施策としては、社内アイデアコンテストやハッカソンの開催、社員から自由提案を募る新規事業提案制度の導入などがあります。ポイントは、それらの場で否定や批判から入らずまず肯定し議論するルールを設けることです。ブレインストーミングのように「とにかくアイデアを出し切る」フェーズと、「現実性を検討する」フェーズを分けて運用することで、斬新な発想が潰されずに済みます。また提案が採用されなかった場合でも、提案した事実自体を評価する仕組み(インセンティブや表彰など)があれば、社員は安心してアイデアを出せるでしょう。
部署横断のコミュニケーションとナレッジ共有
社内コミュニケーションの活性化も新規事業成功の重要なカギです。大企業では縦割り組織になりがちなため、部署間の連携不足が新規事業を阻むことがしばしばあります。社内の合意形成がスムーズにいかず摩擦が生じる背景には、部門ごとに情報や問題意識が共有されていないことが大きく影響しています。
そこで、組織全体を見渡して役職・部門にとらわれないアプローチが必要になります。新規事業プロジェクトのキーマンや関連部門とは、正式な会議の前から非公式にコミュニケーションをとり、情報共有や意見交換を重ねておくと良いでしょう。事前に十分コミュニケーションを図っておけば、限られた会議時間内でも建設的な議論が可能になります。
さらに、アイデア創出の段階から多様な知見を持つメンバー同士がコミュニケーションすることが有効です。例えば、技術畑の社員と営業畑の社員が意見を交わすことで、新たな視点が生まれることがあります。部署横断のワークショップやクロスファンクショナルなチーム編成によって、社内のサイロ化を打破し知識を融合させる場を設けましょう。こうした異なる視点の交わりが、より質の高いアイデア創出につながると思われます。
現代ではオンラインの社内SNSやコラボレーションツールも発達しています。全社員がアクセスできる社内ポータルサイトに新規事業関連のナレッジを集約するなど、アイデア投稿・議論ができるコミュニティを社内に作るのも一案です。実際、三井不動産では社員のイノベーションマインド醸成に向けた社内ポータルサイトを構築し、部門を超えた共創を促す取り組みをしています。このように、情報共有のプラットフォームを整備し、社員同士が刺激し合える環境を用意することで、新規事業の芽を育てる土壌が整うのではないでしょうか。
社外の知見との共創(オープンイノベーションの活用)
自社内のリソースや知識に限界がある場合、社外との共創によって新規事業を加速させる方法も有効です。いわゆるオープンイノベーションで、スタートアップ企業や大学・研究機関、他業界の企業などと連携し、自社だけでは生み出せない発想や技術を取り入れるのです。
その好例として富士フイルムの取り組みが挙げられます。富士フイルムは写真フィルム事業がデジタル化で縮小する危機に直面しましたが、長年培ったコア技術を活かして化粧品・医薬品・再生医療など異業種への展開に成功しました。この背景には、社内の技術者たちに「自社の12のコア技術を誰にでも説明できるようトレーニング」し、外部の来訪者と対話しながら社会課題と技術をつなぐオープンイノベーション活動を推進したことがあります。富士フイルム本社には「Open Innovation Hub」という施設が設けられ、社外のパートナーとディスカッションし共創の方法を模索、試作品に落とし込む試みが続けられています。
その成果の一つが、在宅医療患者のニーズと自社のX線撮影技術を結びつけて生まれたポータブルX線撮影装置や、写真フィルム技術を応用した結核迅速診断キットといった社会課題解決型の新製品です。このように、自社の強みを軸にしつつオープンイノベーションを推進することで、富士フイルムは事業構造の転換(いわば”第二の創業”)に成功したのです。
また、日本郵政グループ(日本郵便)の例も注目に値します。日本郵政は、ネット通販拡大による宅配荷物増加に対し、慢性的な配達員不足という課題を抱えていました。そこで社外の物流系スタートアップYper(イーパー)社と協業し、置き配バッグ「OKIPPA(オキッパ)」という新サービスを開発しました。OKIPPAは折りたたみ式の簡易宅配ボックスで、玄関先に設置しておけば不在でも荷物を受け取れる仕組みです。
この手軽さと便利さから利用者は拡大し、配送各社の専用アプリと連携して配達状況も確認できるため再配達削減に効果を発揮しています。実際、2018年に日本郵便と東京・杉並区の1,000世帯で実施した実証実験では、OKIPPAの活用により再配達件数を約61%も削減することに成功しました。この成果を受け、日本郵便はOKIPPAを一般ユーザー向けに10万個無料配布するキャンペーンも展開しています。これは、自社だけでは解決が難しい社会課題に対し、社外の革新的な技術・サービスを取り入れて新規事業を創出した好例と言えるでしょう。
専門人材の登用とナレッジ習得
新規事業の推進には、必要に応じて専門的人材の力を借りることも検討しましょう。自社にノウハウがない場合、社内の人材育成を待っていては時間がかかりすぎることがあります。「人材不足・知見不足」は多くの企業が直面する課題です。たとえば、その業界に詳しいプロフェッショナル人材を外部からスカウトすることは有効な解決策でしょう。新規事業コンサルタントや該当分野の技術スペシャリストをメンターとして招くことで、チーム全体の知識レベルを底上げできます。
さらに、必要に応じて研修やコーチングを実施し、新規事業開発に必要なスキルセット(リーンスタートアップ手法やデザイン思考など)を身につけさせることも有益です。
ただし、外部の専門家に頼る場合でも、社内メンバーが主体性を持つことが大事です。外部人材はあくまで伴走者・助言者として活用し、最終的な意思決定や事業オーナーシップは自社内に残す形が望ましいでしょう。そうすることで、プロジェクト終了後にも社内にノウハウが蓄積され、次なる挑戦に繋がると思われます。
新規事業成功事例:富士フイルムと日本郵政に学ぶ
上記のような施策を実践し、大企業でありながら新規事業を成功に導いた企業も存在します。その代表例として富士フイルムと日本郵政のケースを詳しく振り返り、成功のポイントを確認していきましょう。
富士フイルム株式会社の事例
写真フィルムで世界的企業だった富士フイルムは、デジタル化の波で主力事業が縮小した際、培ったコア技術を活かしてヘルスケア・素材分野への大胆な転換を図りました。社内では「第二の創業」と位置づけ、新規事業発足チームに多くの研究者がワクワク感を持って参加したと言います。
成功の要因は、既存技術と新事業分野との連続性を活用しながら、オープンイノベーションによって社内外の知恵を結集したことです。例えばフィルムのコラーゲン技術を美容液に応用した独自の化粧品ブランドを立ち上げる一方、外部パートナーとの共創により新医薬品や診断機器も開発しました。
このように、自社の強みに軸足を置きつつ積極的に社外の力も取り入れたことで、富士フイルムは事業構造転換に成功し現在では「ヘルスケア企業」へと生まれ変わっています。
日本郵政(日本郵便)× Yper株式会社の事例
前述の通り、日本郵政はスタートアップのYper社と協業し、置き配バッグ「OKIPPA」という新サービスを創出しました。成功のポイントは、自社が持つ配送ネットワーク資産と、スタートアップの斬新なソリューションを組み合わせることで社会課題を解決したことです。
日本郵便は全国に郵便局網と配送インフラを持つ強みがありますが、自社だけでは再配達問題の解決策を生み出せていませんでした。そこにYper社のアイデアと技術を掛け合わせることで、従来になかった付加価値サービスを提供することに成功しています。
特に、大企業とベンチャーの協業はスピード感の差など課題も多いと言われますが、日本郵政は実証実験で効果を確認し迅速に全国展開(キャンペーン実施)に踏み切るなど、意思決定の素早さも光りました。この事例から学べるのは、大企業のリソースとベンチャーのアイデアを組み合わせれば、新規事業の成功確率を高められるということです。自社内に無い発想や技術は、社外から取り入れる柔軟性も持ち合わせるべきでしょう。
これら二つの事例に共通するのは、既存事業の延長線上に安住せず、新たな価値提供に挑戦した点と、組織の壁を越えて内外の力を結集した点です。富士フイルムも日本郵政も、一時は危機や課題を抱えましたが、それを原動力に社内の意識改革と積極的な改革行動を起こしたことで、新規事業の成功につなげています。大企業であっても、これらの成功要因を取り入れることで、新規事業開発における成果を上げることは十分可能なのです。
まとめ
大企業における新規事業が失敗に終わりがちな理由として、顧客ニーズの誤認、アイデア・戦略の不備、社内調整の遅さ、リソース不足といった典型パターンを見てきました。新規事業の成功確率が低いのは避けられない前提ですが、だからこそ数多く挑戦し、失敗から学び続けることが大切です。
対策としては、プロフェッショナル人材の活用による知見補強や、経営陣の明確なビジョン提示による方向性の共有が有効でしょう。また、社内コミュニケーションの活性化によって新規事業に関わる社員同士が積極的に意見を出し合い、チームワークを高めることも極めて重要です。
新規事業を成功させる土壌として、社員が心理的安全性を感じられる組織文化を醸成し、部署横断の連携や社外との共創を取り入れることで、失敗の確率を下げ成功の芽を育むことができます。富士フイルムや日本郵政の事例が示すように、自社の強みを活かしつつオープンマインドで新しいアイデアを取り入れる姿勢こそが、新規事業成功のカギと言えるでしょう。
要するに、新規事業成功には「多産多死を前提とした挑戦文化と、社内外の知見を結集する協創体制」が必要ということです。