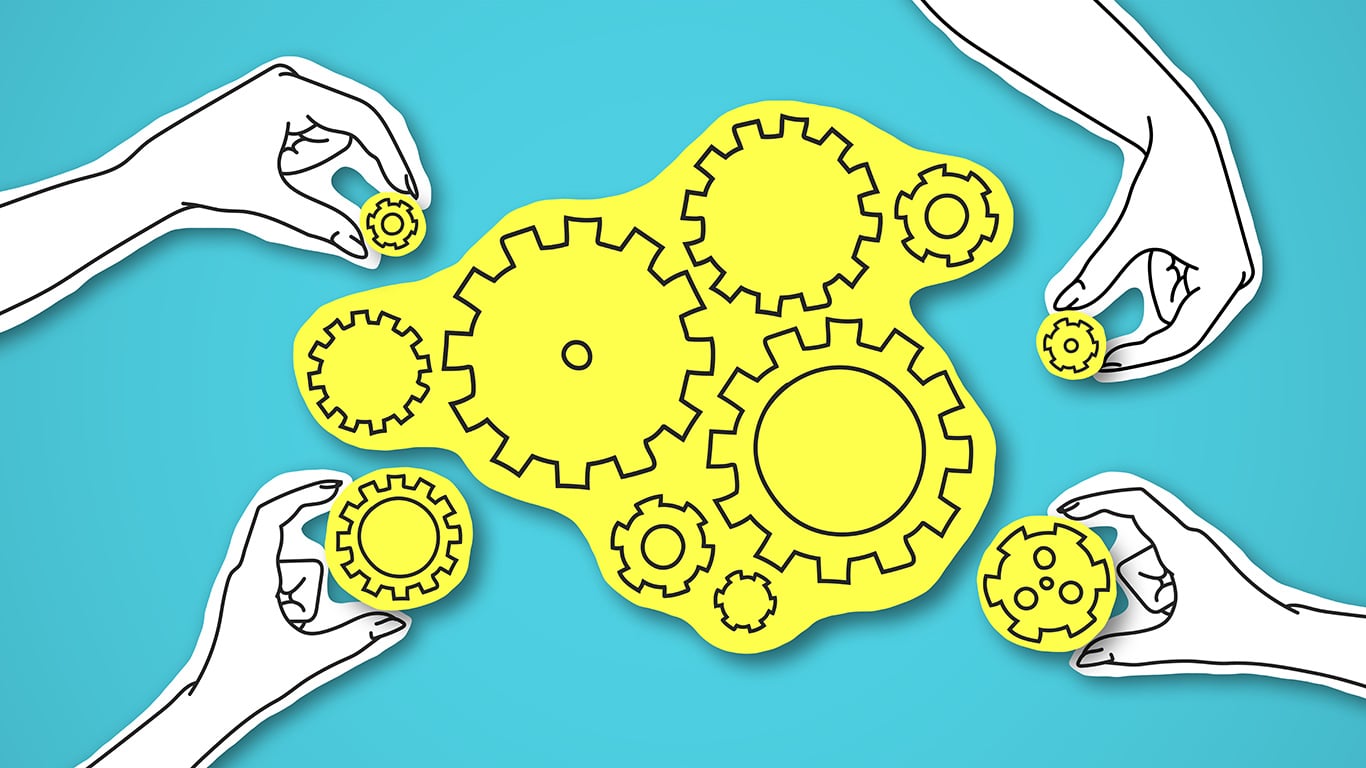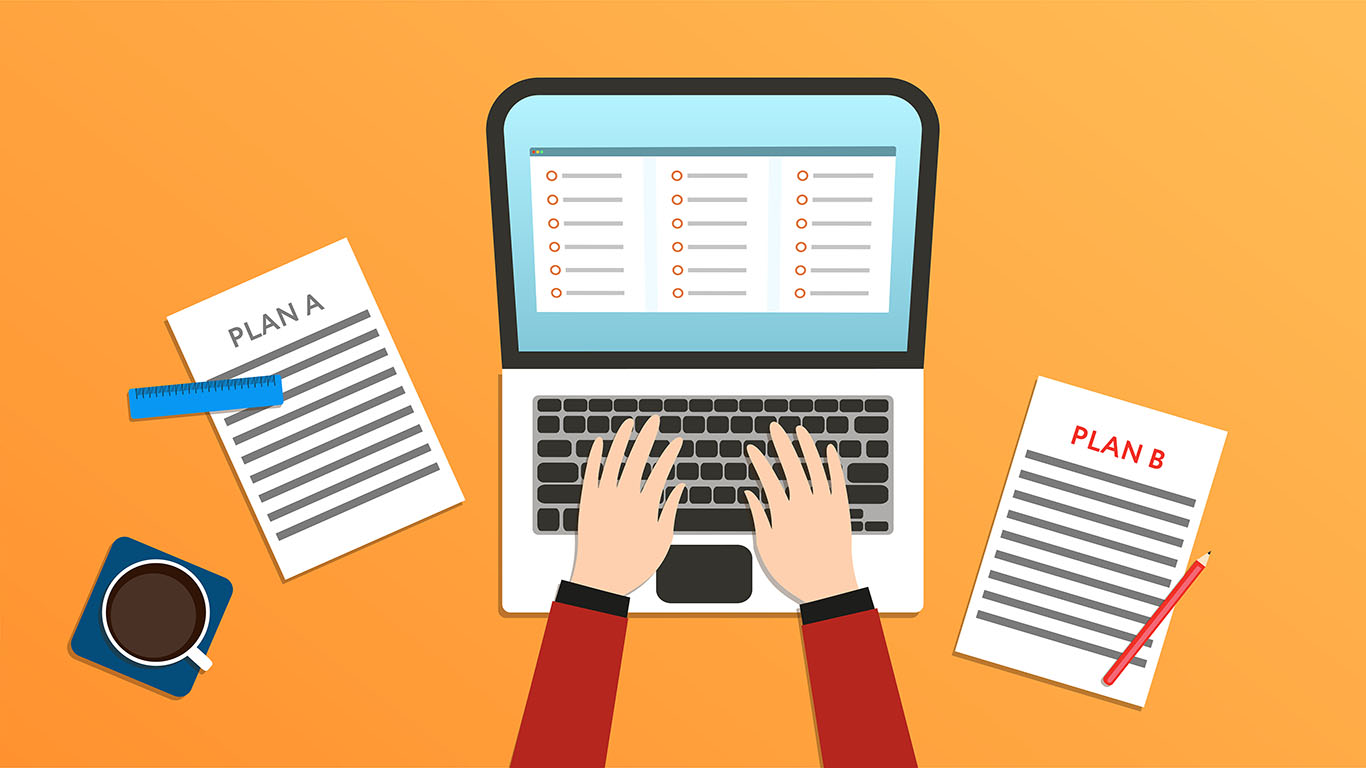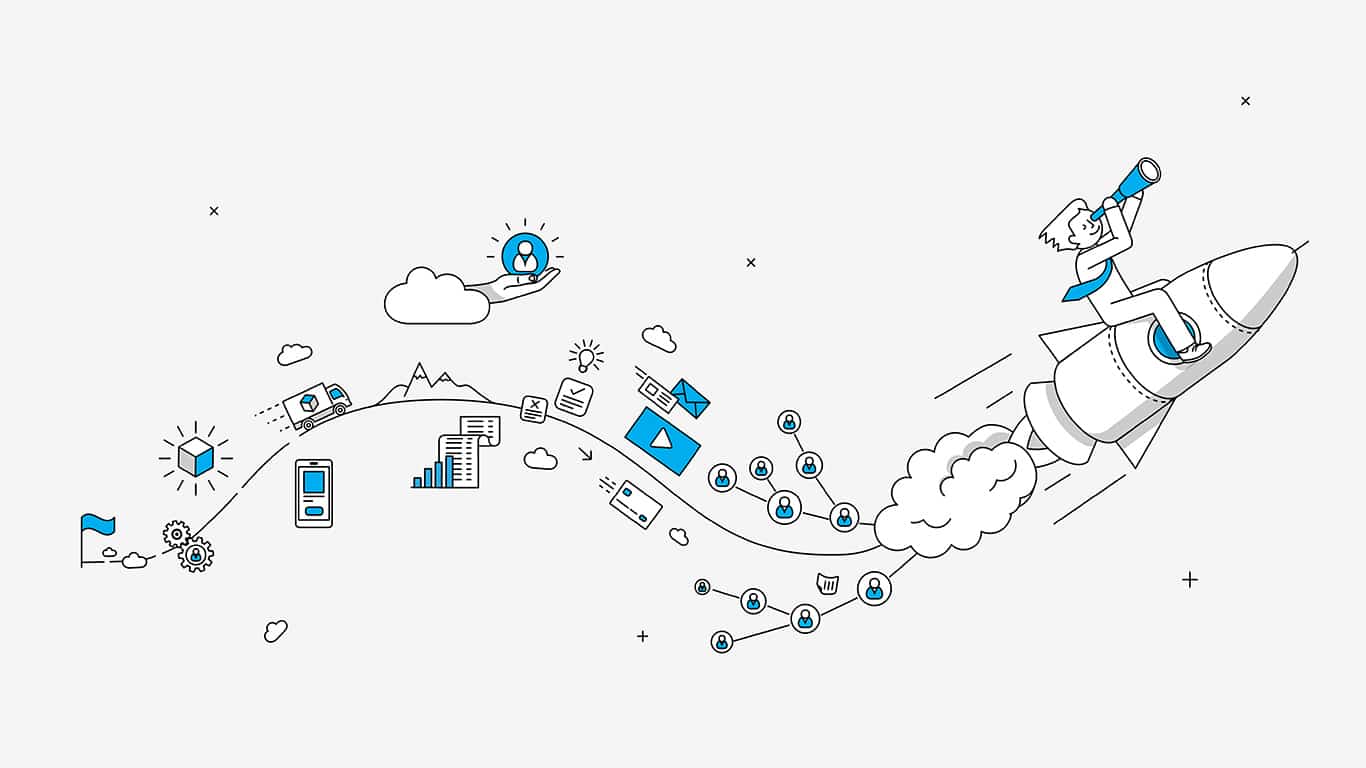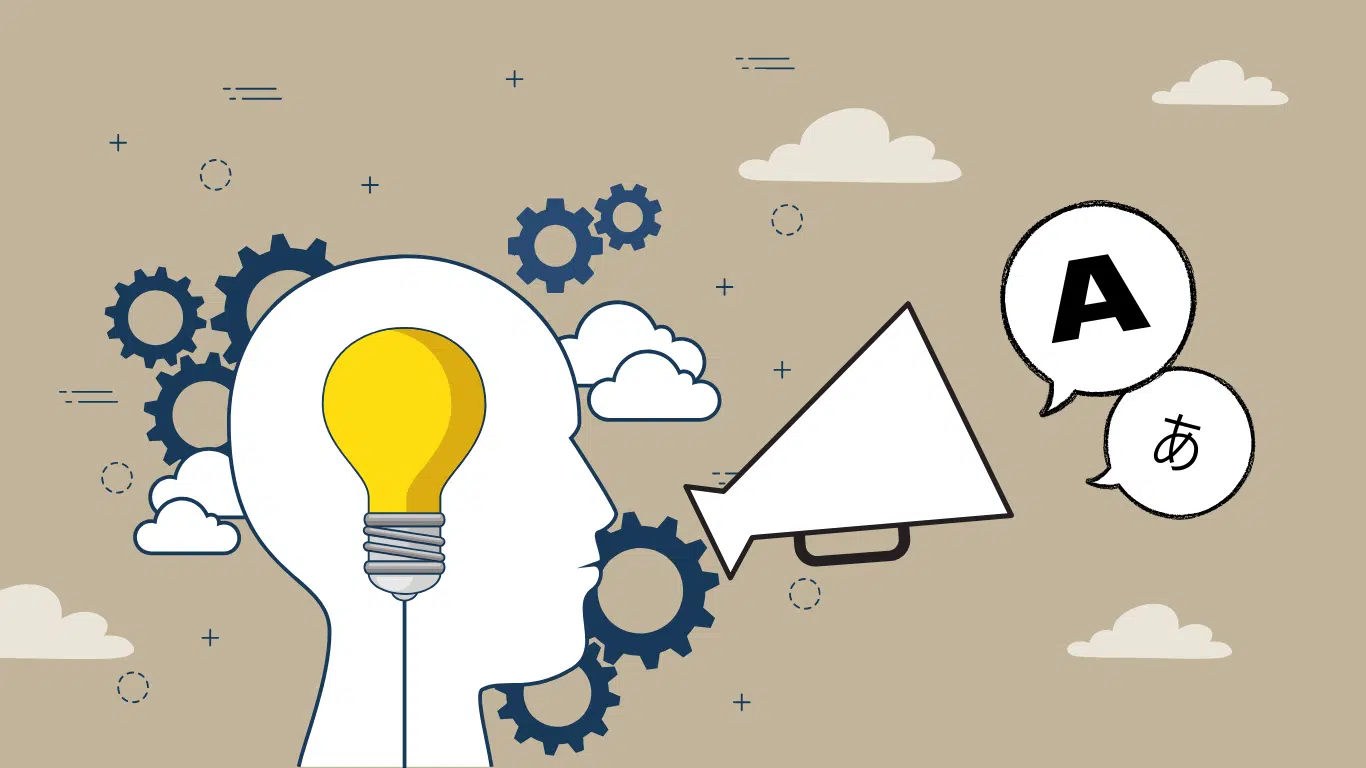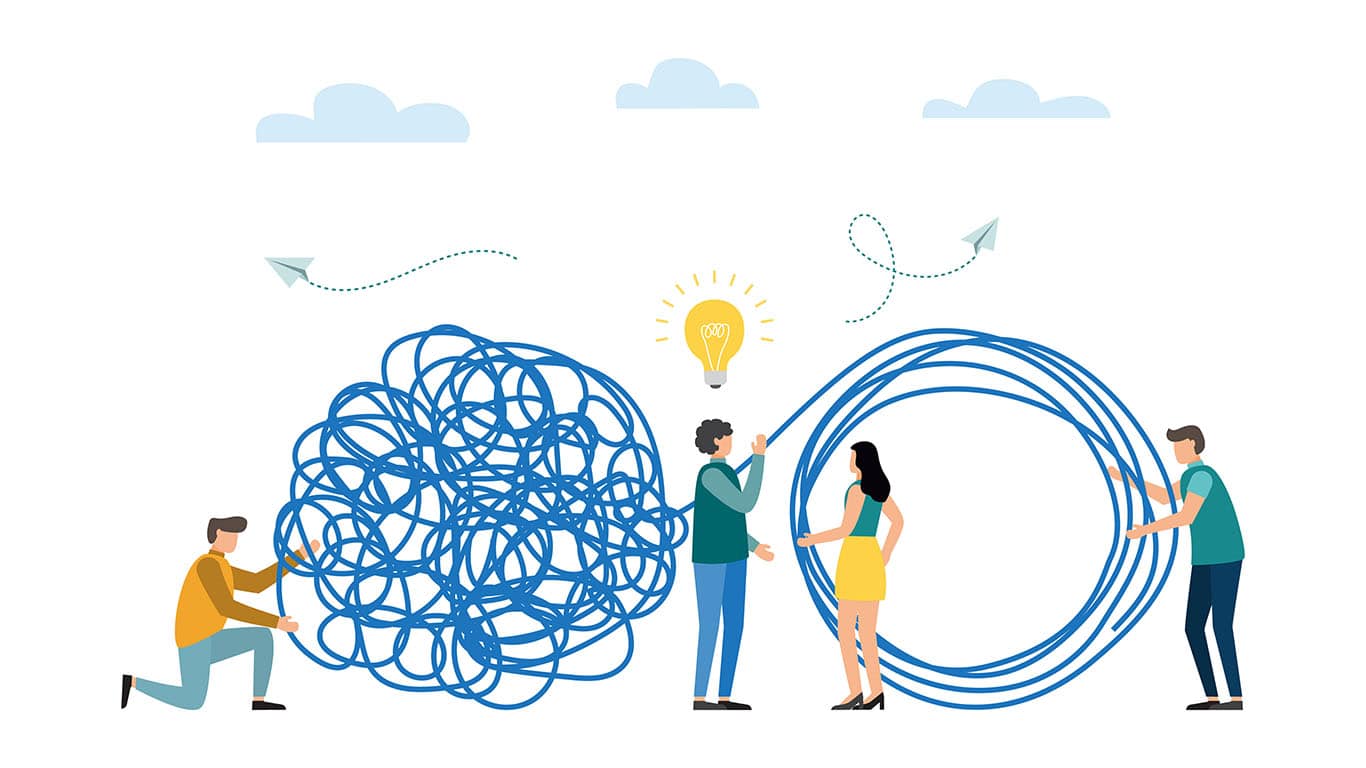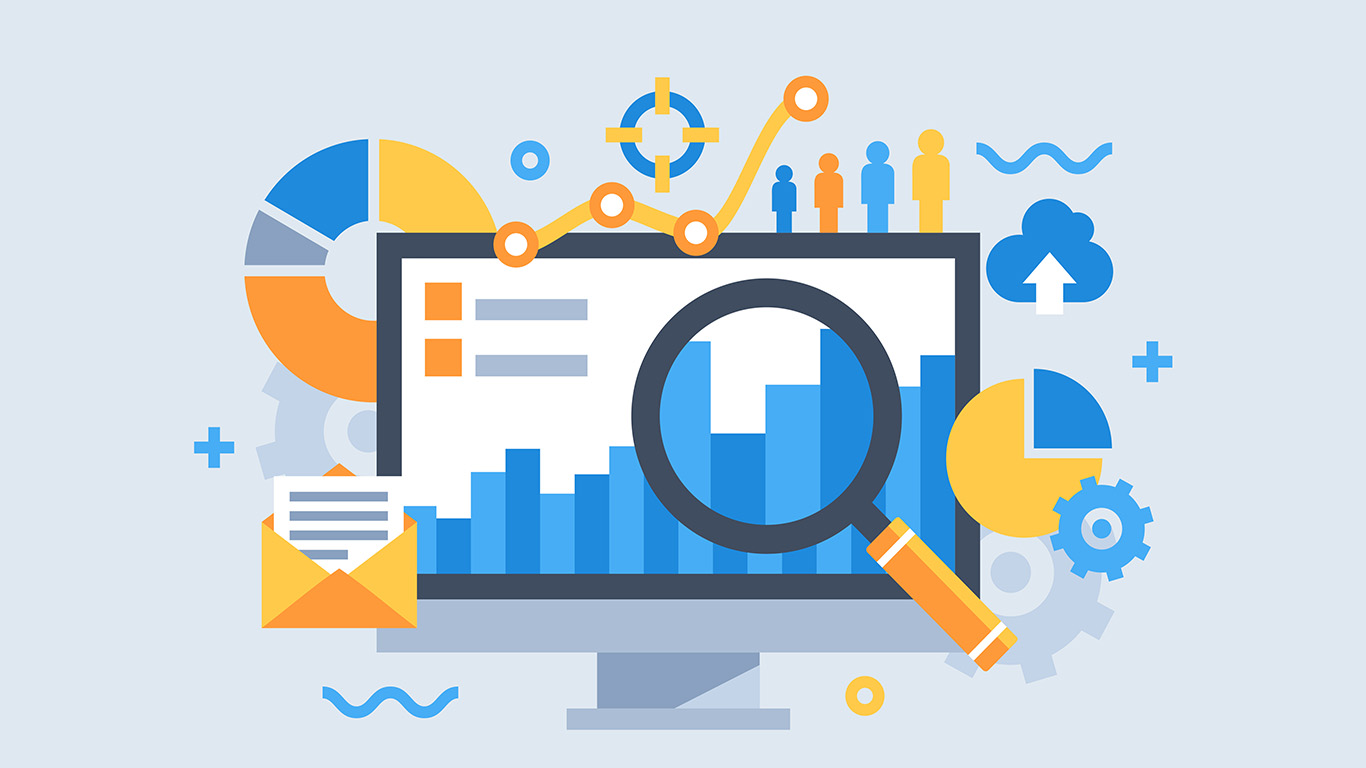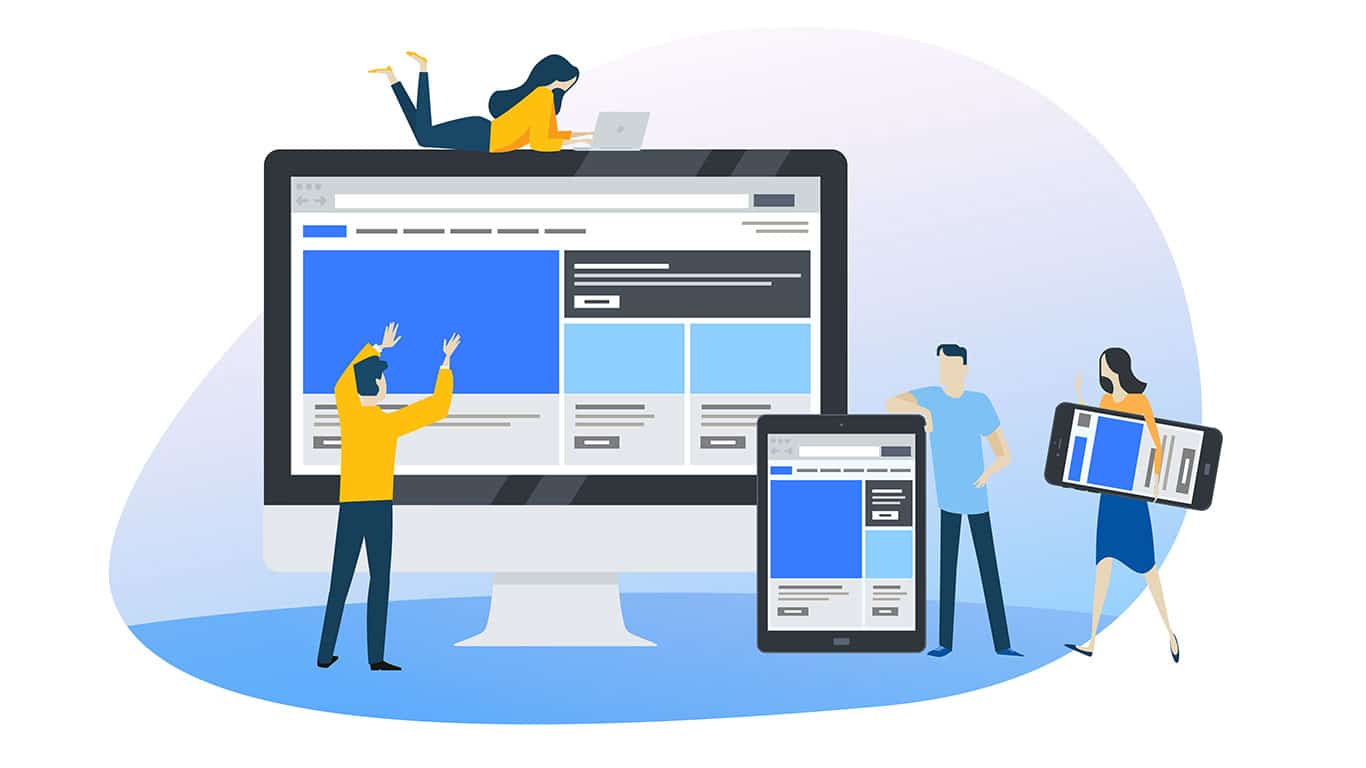新規事業企画書とは?7つの基本構成と成功のポイント【最新トレンドも解説】
最終更新日:2025.07.15
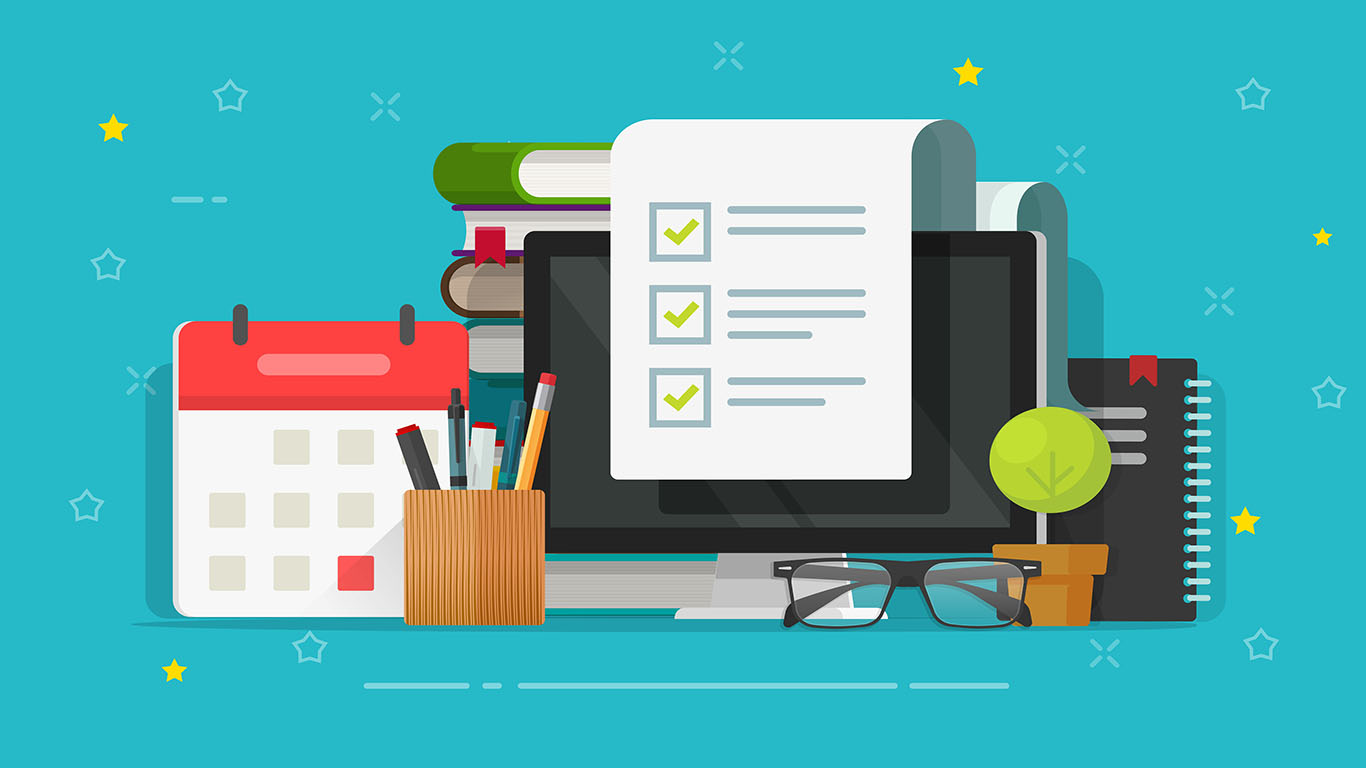
目次
新規事業企画書は、新たなビジネスを成功へ導くための設計図です。本記事では、新規事業企画書の役割や目的から始め、盛り込むべき7つの基本構成要素を徹底解説します。失敗しない企画書作成の手順や最新トレンド、リサーチデータ活用術、実務で使えるテンプレート・チェックリスト、さらによくある失敗例とその回避策まで網羅いたします。優れた企画書を作成し、新規事業の成功率を高めていきましょう。
新規事業企画書の重要性とは
新規事業企画書は、企業で新たなビジネスを立ち上げる際に欠かせない設計図といえるでしょう。画期的なアイデアがあっても、関係者を説得し賛同を得なければ事業は前に進みません。実際、一部の調査では新規事業が黒字化まで至る確率は7%程度という厳しい現実が示されています。つまり10件中9件以上は失敗に終わる計算であり、入念な準備と計画が求められることがお分かりいただけるでしょう。
そんな中で新規事業企画書は、社内の経営層から社外の投資家・パートナーまで、あらゆるステークホルダーに新事業の価値と将来性を伝える役割を果たしているのです。社内決裁を通し予算や人員を確保する場面、ベンチャーコンテストで出資を勝ち取る場面、さらには公的補助金の申請など、新規事業のプロセス各所で企画書が必要になります。新規事業企画書は単なる事業計画の説明資料ではなく、プロジェクトメンバーの情熱やビジョンを共有するツールでもあるのではないでしょうか。
本記事では、新規事業企画書の基本から最新動向まで網羅し、実践的な作成ポイントを解説いたします。成功する企画書を作るためのポイントを押さえ、未来を切り拓く新規事業を実現していきましょう。
新規事業企画書とは?その役割と目的
新規事業企画書とは、新たな事業アイデアを実行に移すために作成される計画書であり、経営層や投資家といった意思決定者への説明資料です。平たく言えば、「この新規事業で自社が目指す未来」と「その実現方法」をまとめたストーリーだと言えるでしょう。まずこの章では、新規事業企画書の基本的な役割と、作成する目的について整理していきましょう。
社内外の承認を得るためのツール
新規事業にはアイデア段階から多くのリソース投入が必要です。社内であれば経営陣の承認、社外では出資者や金融機関の理解が不可欠でしょう。新規事業企画書は、そうしたステークホルダーからの承認・支援を得るための説得材料となります。例えば社内の新規事業提案コンペ、ベンチャーコンテスト応募、補助金申請など、様々な場面で企画書が活用されています。
ビジョン共有とチームの指針
企画書は単に事業内容を説明するだけでなく、プロジェクトメンバー全員で情熱やビジョンを共有するための道具でもあります。良い企画書があれば、担当者だけでなく経営層も同じ目線で将来像を描けるようになるのではないでしょうか。
既存の事業計画書との違い
既存事業の計画書(事業計画書)は、過去の実績データやトレンドを根拠に短〜中期の計画を示すものです。一方、新規事業企画書はゼロから立ち上げる事業の計画書なので、社内に蓄積された実績データがなく不確実性が高い点が特徴となります。したがって、市場動向や将来予測に基づき、外部環境の変化を織り込んだストーリー構築が求められるでしょう。例えば、中長期的な視点で「5年後、10年後の市場や社会はどう変化しているか」「その変化に自社はどう対応すべきか」を踏まえてプランを描く必要があります。
将来のシナリオ提示
新規事業企画書では、現状と将来の間にあるギャップを示し、「そのギャップを埋めるためにこの新規事業が必要だ」という説得力あるストーリーを語ることが大切です。例えば近年であれば、脱炭素やSDGsなど世界的な課題や潮流を背景として示すことで、「なぜ今この事業に取り組む必要があるのか」に説得力を持たせられるでしょう。企業の将来ビジョンや社会課題を織り交ぜたシナリオを提示することで、読み手に事業の意義や重要性が伝わりやすくなるのではないでしょうか。
以上のように、新規事業企画書は新たな挑戦の羅針盤として、社内外の理解と協力を得るためのものです。逆に言えば、企画書が不十分だと関係者の心を動かせず、せっかくのアイデアも実現に至りません。次章では、その企画書に具体的に何を盛り込むべきか、基本となる7つの構成要素を見ていきましょう。
新規事業企画書に盛り込むべき7つの基本構成
説得力のある新規事業企画書を作成するためには、欠かせない7つの要素があります。これらを漏れなく盛り込むことで、読み手は新事業の全体像を容易に理解でき、企画の妥当性や魅力を評価しやすくなるでしょう。ここでは7つの基本構成を順にご紹介いたします。
1. 企業の基本理念(ビジョンとの整合性)
まず企業の基本理念を掲示します。新規事業が自社の経営理念や中長期ビジョンに沿ったものであることを明確に示しましょう。企業の存在意義やミッションに即した企画であれば、社内の共感も得やすくなります。「自社は何のためにこの事業に取り組むのか」を端的に述べることで、事業の目的と意義を伝えられるでしょう。
経営理念との関連性を示すことで、提案する事業が会社の方向性に合致したものだと証明できます。5年後・10年後も変わらない企業の核(理念)に根ざした新規事業であることを強調すると良いでしょう。
2. サマリー(事業概要の要約)
次にサマリー(概要)です。企画書全体のエグゼクティブサマリーとして、提案する新規事業の骨子を短くまとめます。日々多忙な経営層や投資家が短時間で企画の要点を把握できるよう、簡潔で分かりやすい要約を心掛けましょう。
サマリーに含める内容の例:
- 事業コンセプト:どのような事業か、一言で言うと何を提供するビジネスか
- 解決したい課題:その事業で解決を目指す社会や顧客の課題は何か
- ターゲット:誰(どの市場・顧客層)を対象にするのか
- 提供する商品・サービス:具体的に何を提供するのか
- 自社が手がける理由:なぜ自社がこの事業を行う意義があるのか
これらを箇条書きや短い文章でまとめ、企画書を読む相手がひと目で伝わるサマリーを作成しましょう。サマリー部分は企画書の顔でもあるため、最後に全体が書けた後で推敲し、ブラッシュアップするくらいの意識で臨むことをおすすめします。
3. 課題の提示(現状の問題点)
新規事業が取り組む課題(問題)を明確に示します。まず、現状の市場・社会にどんなギャップや不満があるのかを客観的データや事実に基づいて指摘しましょう。「○○なニーズが満たされていない」「△△という非効率が存在する」など、解決すべき問題点を具体的に述べます。
さらに、その問題が発生している原因や背景も分析できると説得力が増すでしょう。例えば「高齢化によって○○サービスの需要が増えているが、現状の供給は不足している」等、問題の根本にあるトレンドや構造的要因を示します。この部分は新規事業の必要性を訴える根拠になるため、可能な限りデータや調査結果を引用して裏付けることが重要です。
課題提起は客観的であるほど良いですが、問題意識そのものは主観でも構いません。提案者として「何をなぜ課題だと捉えているのか」という視点も補足すると、熱意が伝わりやすくなるでしょう。
4. 解決策の提案(提供するソリューション)
前項で挙げた課題に対し、どのような解決策(ソリューション)を提供するかを示します。ここでは提案する新規事業の核となる製品・サービスやビジネスモデルをご説明します。「○○という方法で課題を解決します」「△△というサービスを提供します」と具体的に記載しましょう。
解決策の内容とともに、実行した場合のポジティブな変化も描きます。例えば「このサービスを提供することで○○の手間が何%削減できる」「△△な体験価値をユーザーに与えられる」など、ベネフィット(得られる効果)を定量・定性の両面で示します。提案内容が実現した際にどんな良い未来が訪れるのか、読み手が具体的にイメージできる記述を心掛けましょう。
解決策の説得力を高めるために、参考になる事例を盛り込むのも効果的です。社内外の類似した成功事例があれば比較して優位性を示したり、逆に過去の失敗事例から学んだ点を強調したりすると、企画の現実味が増すでしょう。
5. 自社が最適な理由(独自の強み・優位性)
提案する新規事業をなぜ自社が手がけるべきか、その理由と自社の強みをご説明します。ここでは競合他社にはない独自のリソースやアセットにフォーカスしましょう。例えば以下のような切り口があります。
- 技術力・特許:自社が保有するコア技術や知財を活用でき、参入障壁を築ける
- ブランド・信頼:既存事業で培ったブランド力や顧客基盤が新事業にも活きる
- 人材・ノウハウ:経験豊富な人材や業界知見があり、競合より有利に立ち上げられる
- 提携関係:業界内外に強力なパートナーがおり、協業で価値を出せる
これら自社の強みを踏まえ、「だからこそ我が社ならこの事業で勝てる」という根拠を示します。例えば「当社は○○技術のパイオニアであり、この分野では他社に先駆けた実績があるため有利に戦える」などです。また、可能であれば既存事業や過去の取り組みとのシナジーも述べましょう。新規事業が自社の成長戦略上どんな位置づけかを示すことで、経営層にとっての意義も伝わりやすくなるでしょう。
独自優位性の説明では、「自社だけが持つ〇〇のおかげで成功可能」という勝算を提示します。競合との差別化ポイントを明確にし、「この新規事業で自社ブランドをさらに高められる」というストーリーでアピールすると効果的です。
6. 実現プラン(実施体制とスケジュール)
新規事業をどう実行に移すか、その具体的なプランを示します。ここではロードマップ(タイムライン)と体制(リソース計画)の2点が中心となります。
- ロードマップ(いつ何をするか):例えば「○年○月までに試作品開発、△年△月にサービスローンチ、△年末までに国内○○地域へ展開」など、大まかなマイルストーンを時系列で示します。フェーズごとの目標設定をすることで、実現への道筋が具体的に見えるようになるでしょう。長期計画の場合は3年後・5年後・10年後と区切って段階的に描くと良いでしょう。
- 実施体制・リソース計画(誰が何を使って進めるか):プロジェクトメンバーや必要な人材、予算や資金調達計画について触れます。チーム構成については、「どの部署・専門スキルのメンバーが参画するのか」「不足する人材は採用や外部協力でどう補うか」といった点を整理します。またリソース面では、「開発費用○○万円の投資が必要」「△△の技術パートナーと協業予定」など、必要な資源と調達方法を示しましょう。
スケジュール策定ではスピード感も重要ですが、焦るあまり戦略性を欠いた計画にならないよう注意します。競合動向や市場機会を見極めつつ、時間をかけるべきステップには十分な期間を確保しましょう。また、計画実現にあたり不足しているリソース(人手・資金・設備など)は何か、どのタイミングでどれだけ追加が必要かも具体的に検討しておきます。これにより企画の実現可能性がよりリアルに伝わるでしょう。

コミュニケーターが切り開く未来志向のAI戦略 世界のインターナルコミュニケーション最前線⑤
この記事では、急激に変容し続ける世の中で、この先の将来、企業のコミュニケーション部門、コミュニケーション職に…
7. 新規事業による効果(収支計画・KPI)
最後に、新規事業を実行した場合に見込まれる効果を定量的に示します。具体的には収支計画や主要KPIの予測値です。新規事業の売上高・利益見通し、市場シェア目標、獲得ユーザー数など、事業成功の判断指標となる値を試算して記載します。
- 収支計画:初期投資額やランニングコストに対し、いつ黒字化(損益分岐点到達)するのか、その時点の累積損益はいくらか、といった視点で損益シミュレーションを行います。可能であれば3年程度のPL(損益計算書)予測を立て、ROI(投資対効果)やNPV(正味現在価値)なども算出すると説得力が増すでしょう。
- KPI/KGI:事業の進捗や成功度合いを測る指標を設定します。例えば「1年目顧客○万人獲得」「3年目営業利益△億円」などのKGI(重要目標達成指標)や、それに紐づくKPI(重要業績評価指標。月次売上やユーザー数など)です。具体的数値目標を提示することで、読み手は事業規模や成長性をイメージしやすくなるでしょう。
また、新規事業にはリスクとリターンが表裏一体であることもご説明しましょう。新しい挑戦には失敗の可能性や既存事業への影響(カニバリゼーション等)も伴いますが、それを上回るメリットが期待できることを示すのです。例えば「初期投資○億円に対し、市場獲得成功時には年間△億円の収益が見込め、十分ペイする」等、メリットがデメリットを上回る根拠を数値で示します。
数字の裏付けは必須ですが、新規事業ではあくまで予測値であり不確実性も高い点を念頭に置きましょう。大胆すぎる楽観予測は信頼を損ねます。根拠データに基づいた現実的なシナリオを複数用意し、楽観ケースと悲観ケースでのシミュレーションを示すと丁寧です。特に投資回収シナリオについては、悲観的に見ても投資に値する事業だと示せれば、経営層の安心感につながるでしょう。
以上7つが、新規事業企画書に盛り込むべき基本構成要素です。企画書を書く際はこの流れに沿って情報を整理すると漏れが防げるでしょう。
新規事業企画書作成のポイント
新規事業企画書を作成する際に特に重要となるポイントを見ていきましょう。
失敗しない企画書作成のステップバイステップ
新規事業企画書を一から作成するには、闇雲に書き始めるのではなく段階的な準備とプロセスが重要でしょう。ここでは企画書作成の大まかなステップを追いながら、失敗しないためのポイントを解説いたします。
ステップ1:事業アイデアの整理と戦略目標の確認
最初に、新規事業のアイデア自体を再確認します。どんな発想であれ、自社の経営戦略やビジョンとの整合性が取れているかをチェックしましょう。経営陣から「うちの会社がやる意味は?」と問われたときに答えられるよう、事業アイデアの目的と狙いを明確化します。ここで企業理念や中期経営計画などを再度見直し、新規事業の位置づけを社内戦略と紐付けておくことが重要でしょう。
ステップ2:市場リサーチと課題仮説の設定
次に、徹底したリサーチを行います。ターゲット市場の規模や成長性、顧客ニーズの動向、競合プレイヤーの状況などを調査し、事業機会を定量・定性の両面から洗い出します。ここでは仮説検証型のアプローチが有効でしょう。最初に「この市場では○○が課題ではないか」「競合が対応していないニーズが△△にあるのでは」といった課題仮説を立て、その仮説をデータで検証していきます。リサーチの結果、当初想定と異なる事実が出てきたら柔軟に仮説を修正しましょう。このプロセスを通じて、企画書で提示すべき解決すべき問題とその根拠データが揃います。
リサーチには政府や業界団体の白書・統計、シンクタンクのレポート、市場調査会社のデータなど信頼できる一次情報を活用します。最新の数字やファクトを押さえることで、企画書全体の説得力が高まるでしょう。公的機関のオープンデータは積極的に参照することをおすすめします。
ステップ3:シナリオ・プランニングで未来像を描く
リサーチで現状分析ができたら、次は将来のシナリオを描く作業です。外部環境の不確実性が高い今日では、単一の予測ではなく複数の未来シナリオを想定して戦略を練る「シナリオ・プランニング」の手法が有効でしょう。5年後・10年後に起こり得る市場変化をいくつか想定し、それぞれのシナリオで自社の新規事業がどう活躍し得るかを検討します。
例えば、「楽観シナリオ:技術革新が追い風となり市場が大幅拡大」「悲観シナリオ:規制強化で想定より市場成長が鈍化」など複数の未来を描きます。そして、どのシナリオでも自社の新規事業の意義が失われないか、あるいはメインシナリオが崩れた場合のプランBは何か、といった点も合わせて考えておきます。企画書にはメインとなる一つのシナリオを中心に記載しますが、裏では他のシナリオも検討しておくことで、意思決定者からの質問にも柔軟に答えられるでしょう。シナリオ・プランニングによって長期視点での事業コンセプトの妥当性を確認することが、失敗を防ぐポイントです。
ステップ4:ストーリーの構築とアウトライン作成
現状分析と未来の見通しが得られたら、企画書の全体ストーリーを組み立てます。前章で述べた7つの基本構成に沿って、伝える内容の骨子を箇条書きで書き出してみましょう。この段階ではアウトライン(見出し案)を作るイメージです。「背景・課題」「解決策」「収支計画」など主要セクションに何を盛り込むか、手持ちの情報やデータを振り分けていきます。論理的な構成を検証するため、5W2H(Who/What/Why/When/Where/How/How much)がすべて網羅されているかチェックします。抜け漏れがないアウトラインになれば詳細執筆に入りましょう。
アウトライン作成時には関係者へのヒアリングも有用です。社内の関連部署や専門家にアイデアを話し、フィードバックをもらうことで構成の抜けや論点の甘さに気付けるでしょう。早い段階で第三者の視点を取り入れると、大きな手戻りを防げます。
ステップ5:ドラフト執筆とビジュアル作成
アウトラインに沿って各項目のドラフト(草稿)を書いていきます。文章はできるだけ平易で簡潔にまとめ、専門用語の多用は避けましょう。長文になりすぎないよう1文や1段落を短めに区切り、要点は箇条書きも活用して視認性を高めます。また、図表やグラフも積極的に使いましょう。大量のテキストだけでは読み手の理解が進まないため、市場成長率の推移グラフやビジネスモデルの模式図などを用意し、視覚的に情報を伝達します。グラフ等を挿入する際は、ラベルや単位を明記し、一目で意味が伝わるよう配慮しましょう。
ドラフト段階ではとにかく全体を一通り書ききることを優先し、細部の言い回しや表現は後の推敲で調整します。一度最後まで書いてみてから、全体を読み返して論理の流れや過不足を確認する方が効率的でしょう。
ステップ6:推敲とブラッシュアップ(何度も見直し)
ドラフトを書き上げたら、次は推敲(ブラッシュアップ)です。説得力のある企画書に仕上げるには、一度で完成させようとせず何度も書き直すことが大切でしょう。一晩おいて新鮮な目で読み直したり、同僚にレビューしてもらったりして、冗長な部分や論理が飛んでいる部分を洗い出します。特に読み手の心に響くストーリーになっているかをチェックしましょう。ただ正しく情報を詰め込んだだけでは人は動きません。メリハリのある構成になっているか、主張に一貫性があるか、データの裏付けは十分か、といった観点で磨き上げます。
企画書は隅から隅まで丁寧に読まれるとは限らないため、優先順位をつけて情報を取捨選択することも重要です。伝えたい核が埋もれてしまわないように、不必要な要素は思い切って削ぎ落としましょう。また、「ぱっと目を通しただけで概要が掴めるか?」という視点でレイアウトや見出し付けを最終調整すると良いでしょう。
ステップ7:関係者への共有と準備(プレゼン練習)
完成した企画書は、正式提出前に関係者と共有しておくのがベターです。上司や経営層との事前すり合わせが可能ならドラフト段階で意見を仰ぎ、指摘事項を反映させましょう。また、企画書提出後のプレゼンテーションも見据えて準備しましょう。資料を手渡すだけでなく、重要提案であれば発表の機会が設定されることも多いため、説明用スライドを作成したり、質疑応答の想定問答を用意したりします。
さらに、エレベーターピッチの練習もおすすめします。エレベーターピッチとは、エレベーターに乗っている短時間(30秒〜1分程度)で事業内容を簡潔に売り込むプレゼン手法のことです。企画書の要点をぎゅっと圧縮して15〜30秒で説明できるようにしておくと、経営層や投資家に話す場面で非常に役立つでしょう。実際、新規事業担当者にとってエレベーターピッチを作成・共有することは、事業内容を誰にでも分かりやすく伝える訓練になり、自身の考えを整理するメリットがあります。本番前に声に出して練習し、どんな場でも熱意を持って短時間で核心を伝えられるスキルを養っておきましょう。
以上が新規事業企画書作成の基本ステップです。一つひとつ丁寧に進めれば、抜けのない説得力ある企画書が出来上がるはずです。
成功するための最新トレンドと注目テーマ
新規事業の世界は常に動いており、企画書にも時代の流れを反映させることが重要でしょう。ここでは現在押さえておくべきトレンドやテーマをご紹介し、それらを企画書に盛り込む際のポイントを解説いたします。最新の動向を踏まえた提案は、読み手に「この企画は未来を見据えている」と印象付け、説得力を高める効果があるのではないでしょうか。
SDGs・ESG(持続可能性)への対応
近年、持続可能な開発目標(SDGs)やESG(環境・社会・ガバナンス)を重視する流れが世界的に強まっています。気候変動対策や脱炭素社会への移行は各国で政策的にも加速しており、企業にも対応が求められるでしょう。新規事業企画書でも、環境負荷軽減や社会課題の解決といった視点を組み込むと良いでしょう。例えば「本事業は〇〇の課題解決を通じてSDGsの△番(具体的な目標)に貢献します」のように言及すれば、社会的意義が伝わります。世界的な規制強化や価値観の変化を背景として示すことで、説得力のあるストーリーが生まれるでしょう。
DX・生成AIなどデジタル技術の活用
デジタルトランスフォーメーション(DX)は引き続き企業の重要テーマです。また、直近では生成AI(Generative AI)の登場がビジネスに大きなインパクトを与えています。企画書では、AI・IoT・ビッグデータ・クラウドなど先端デジタル技術をどう活用するかに触れると、競争優位性や革新性をアピールできるでしょう。例えば「生成AIをサービスのコアエンジンに用いることでパーソナライズを高度化する」「IoTデバイスから収集するデータをAI分析し、新たな付加価値を創出する」等です。ただし流行のバズワードを並べるだけでなく、事業の本質的価値向上にどう寄与するかを具体的に説明することが大切でしょう。
オープンイノベーションと共創
自社単独ではなく、他社やスタートアップ、大学との連携によって新規事業を進めるケースも増えています。いわゆるオープンイノベーションの潮流です。自社に足りないリソースを補完したり、新しい発想を取り入れたりするために、パートナーとの共創計画を企画書に盛り込むのも一案でしょう。例えば「〇〇大学と共同研究開発を行い技術検証を進める」「新進スタートアップ△社とのアライアンスで市場開拓を加速する」といった戦略です。共創の姿勢は、社内外に対し「柔軟で開かれた取り組み」をアピールでき、プロジェクト成功の可能性も高めるのではないでしょうか。
社会変化への洞察(ポストコロナ・少子高齢化など)
事業環境を語る上で無視できないのが人口動態や社会構造の変化です。少子高齢化の進行、労働力不足、ポストコロナの新しい生活様式など、現在進行中の変化が自社ビジネスにどう影響するかを織り込むと良いでしょう。例えば「高齢者人口の増加により○○市場のニーズが高まる見込み」「コロナ禍で定着したリモートワークが△△サービスの追い風となる」等です。こうしたマクロトレンドを踏まえた事業機会を提示すれば、企画の妥当性を裏付ける強力な材料になるでしょう。
業界X.Techの潮流
金融×ITのフィンテック、医療×ITのヘルスケアテック、教育×ITのEdTechなど、従来産業とテクノロジー融合によるイノベーションも注目テーマです。自分たちの業界でどんな「X Tech」動向があるか調査し、企画に活かせないか検討しましょう。例えば「製造業界ではIndustry4.0が進んでおり、当社もIoT活用でスマート工場化を目指す新規事業を提案」などです。最新トレンドに乗ったキーワードを適切に取り入れることで、今後の成長が見込める領域であることを印象付けられるでしょう。
以上のようなトレンドを企画書に反映させる際は、単なる流行語の寄せ集めにならないよう注意しましょう。あくまで事業の本質に即した形で盛り込み、企画全体の整合性を保つことが大切です。また、企画書のタイトルやリード文に最新動向のキーワードを入れると、読み手の関心を引き付ける効果も期待できるでしょう。
常にアンテナを張り、環境変化を先読みした提案ができれば、新規事業企画書の説得力と魅力は一段と高まるでしょう。
説得力を高めるためのリサーチとデータの活用法
説得力のある企画書に欠かせないのがリサーチに基づく裏付けと、適切なデータの活用でしょう。どんなに優れたアイデアも、客観的根拠がなければ絵空事に終わってしまいます。この章では、企画書の信頼性を高め読み手を納得させるためのリサーチとデータ活用のポイントを解説いたします。
信頼できるデータソースの活用
リサーチでは、なるべく一次情報に当たることが重要でしょう。政府の統計(総務省統計局、経産省の白書など)、公的研究機関・業界団体のレポート、大学やシンクタンクの調査結果など、信頼性の高い出典からデータを取得しましょう。たとえば市場規模や成長率を示す際には、「〇〇年の市場規模は△△億円(出典:経済産業省●●レポート)」のように出典を明記すると、読み手も安心して数字を受け取れるでしょう。
定量データで主張を補強
企画書内の主張には可能な限り数値データを伴わせましょう。例えば「高齢化が進んでいる」ではなく「65歳以上人口は〇年までに全体の△%に達すると予想されている」と書けば、一気に説得力が増します。グラフやチャートも有効な手段でしょう。市場トレンドを示す折れ線グラフ、シェア比較の円グラフ、調査結果の棒グラフなど、一見して状況が把握できるビジュアルを入れることで、読み手の理解を助けます。グラフ作成時はラベル・単位の明記を忘れずに行いましょう。
定量的な裏付けを示すことで、企画書の説得力は飛躍的に向上します。
例:(根拠なし) 「近年オンライン教育市場が急成長している。」 (データ提示) 「オンライン教育市場は2019年から2023年にかけて年平均15%成長し、市場規模は約2倍に拡大しています。この顕著な伸びは本事業にとって追い風です。」
このように具体的な数値を盛り込むだけで、主張の重みが増すのがお分かりいただけるでしょう。
顧客の声や現場のデータ
場合によっては、独自に収集した顧客の声や現場データを使うのも有効でしょう。例えば簡易なアンケート調査を実施してニーズを定量化したり、店舗現場の観察による発見をデータ化したりすることもできます。「自社内のパイロットプロジェクトで○人中△人が本サービスに高い関心を示した」など具体例を示せば、企画の実現可能性がよりリアルに伝わるでしょう。
事例やケーススタディ
定量データだけでなく、具体的な事例も説得力アップに役立ちます。成功事例はもちろん、失敗事例も教訓として引用できるでしょう。例えば「競合他社X社は類似サービスの展開で3年間で累積100万ユーザーを獲得した」や「海外の事例では△△の理由で失敗しており、当企画ではその教訓を踏まえた戦略として…」といった具合です。第三者の実例を出すことで、企画の現実味と差別化ポイントを明確にできるでしょう。
エビデンスを取捨選択する
データ活用で気をつけたいのは、盛り込みすぎも禁物という点です。やみくもに数値を羅列するとかえって要点がぼやけ、読み手が混乱する恐れがあります。重要なのは企画のキーポイントを裏付けるデータに絞ることでしょう。「この主張を証明するための決定的なデータは何か?」を自問し、それ以外の周辺データは思い切って省略するくらいでちょうど良いでしょう。エビデンスとして有用な数値や、前向きに検討してもらうための後押しになるデータを厳選して使いましょう。
データの見せ方工夫
提示するデータは、読み手に直感的に伝わる形で見せる工夫も大切です。比較を強調したいなら差分を色分けする、リストよりもアイコン入りの図解にする、などビジュアル面でのひと工夫で印象が変わります。「数値を強調したハイライトボックスを作る」「増減を示す矢印を付ける」といった小さな工夫でも効果があるでしょう。
最後に、データ出典の信用性にも留意しましょう。インターネット上の未確認な数字や、私的なブログ情報などは避け、信頼できる情報源にあたることが重要です。また、古いデータしかない場合は最新の状況を補足説明するなど、読み手が誤解しないよう注意しましょう。
リサーチとデータを駆使することで、企画書は客観性と説得力を備えたものになります。事実に裏打ちされた企画は意思決定者の心を動かしやすく、承認を得る可能性も高まるでしょう。
実務で使えるテンプレート・チェックリスト
一から企画書を書こうとすると大変ですが、基本的なひな形(テンプレート)やチェックリストを活用することで効率的に作成できるでしょう。この章では、新規事業企画書の作成に役立つテンプレート要素と、完成前に確認したいチェック項目をご紹介いたします。必要に応じてご自身の状況に合わせてカスタマイズしてください。
新規事業企画書の基本テンプレート構成
以下は、新規事業企画書の典型的な構成テンプレートです。前章までに解説した7つの基本項目を盛り込んだ形になっています。この順序で書けば論理の流れが自然になるため、一つの雛形として参考にしてください。
- 表紙・タイトル:事業名やキャッチフレーズ、提案者名、日付などを記載します(読み手の興味を引くタイトル設定が重要)。
- 経営理念・ビジョン:新規事業の方向性が自社ビジョンと合致していることを示す一文。
- サマリー(概要):事業コンセプト、狙う市場・課題、提供する解決策、収益モデル、成果目標などを短くまとめた要約。
- 市場背景・課題:市場動向や顧客ニーズ、現状の問題点とその根拠データ。
- 事業内容・ソリューション:提供する製品・サービスの内容、仕組み、付加価値。図やサービスイメージ図があると良い。
- ビジネスモデル:収益の出し方(マネタイズ方法)、価格設定、販売チャネル戦略など。必要に応じてビジネスモデルキャンバス等を図示。
- 自社の強み・差別化要因:競合との比較、自社ならではの優位性(技術・ブランド・ネットワーク等)。
- 実行計画:ロードマップ(開発・市場投入スケジュール)、マイルストーン、体制(体制作りやパートナー)。
- 収支計画・KPI:売上・利益予測、投資回収計画、主要KPI目標値。表やグラフで示す。
- リスクと対応策:想定されるリスク要因とその軽減策(オプションで記載)。
- 結論・提案の依頼事項:改めて本事業の将来性を訴え、読者に求めるアクション(承認事項や支援のお願い)を明確にする。
このテンプレートに沿って記入していけば、ひととおりの構成要素が揃った企画書になるでしょう。各社独自のフォーマットがある場合はそれに従いつつ、上記項目が網羅されているか確認しましょう。
企画書作成時のチェックリスト
企画書を書き終えたら、以下のチェックリストで内容を点検しましょう。漏れや甘さを最終確認し、完成度を高めます。
- 目的・意義は明確か?
– 新規事業の目的(解決したい課題)と取り組む意義が冒頭で明示されているか。読み手が「なぜこの事業をやるのか」を理解できる内容になっているか。 - 一貫したストーリーになっているか?
– 背景~課題~解決策~効果まで、論理の筋が通っているか。各セクションがバラバラな情報の寄せ集めになっていないか。ストーリー展開に無理や飛躍がないか。 - 定量データで根拠づけされているか?
– 主張や予測に対し、適切なデータやエビデンスが示されているか。出典の信頼性は高いか。数字の整合性(桁や単位の統一、計算ミスなど)に問題はないか。 - 誰が見ても分かりやすい表現か?
– 専門用語や業界用語の説明は十分か。過度に難解な表現になっていないか。文章は簡潔で冗長になっていないか。レイアウトや図表の配置は読みやすさを考慮しているか。 - 自社の強みを活かせているか?
– 提案する事業において、自社が持つリソース・経験・ネットワークが効果的に活用されていることを示しているか。「なぜうちの会社がやるべきか」の答えになっているか。 - リスクへの言及はあるか?
– 楽観的なことだけでなく、考え得るリスクや不確実要素にも触れているか。全く触れないと「リスクを見落としている」と評価者に思われる可能性があるため、主要なリスクとその対策案を示しているか(特に大きな投資を要する場合は重要)。 - 読み手への”お願い”が明確か?
– 企画書を読んだ人に次に何をして欲しいのかが明示されているか。承認決裁なのか、予算付与か、人員アサインか、パートナー紹介か等、「この企画書を受け取ったあなたに期待するアクション」は具体的に書かれているか。 - 熱意は伝わるか?
– データとロジックが固められているのは大前提として、提案者の熱量や想いが感じられる内容か。情熱とロジックのバランスが取れているかを確認します。硬い文面になりすぎていれば、結びの部分などで「この事業に懸ける思い」を少し付け加えても良いでしょう。
これらをチェックし、不備があれば修正して完成度を高めましょう。さらに可能であれば上司や同僚にもレビューを依頼し、客観的な指摘をもらうと安心です。自分では完璧と思っても、第三者から見ると思わぬ曖昧さが残っていることはよくあるのではないでしょうか。
エレベーターピッチでブラッシュアップ
チェックリストを終えたら、最後にエレベーターピッチを作ってみましょう。企画書の要旨を30秒程度でまとめる作業です。以下のようなフォーマットで簡潔に記述します。
- 「誰の」「どんな課題」を、
- 「何を使って」(どんなサービス/商品で)、
- 「どう解決するか」、
- そして「自社がそれをやる強み」は何か。
例えばエレベーターピッチ文にすると
「私たち〇〇社の新サービス△△は、慢性的な□□に悩む●●業界の企業向けに、独自の◇◇技術を活用して□□問題を解決します。他社にない◎◎の強みを持つ当社だからこそ実現可能な、新しいビジネスモデルです。」
このようにまとめることで、自分の企画書の核となるメッセージが再確認できるでしょう。もし30秒で説明するのに冗長な部分があれば、本編を修正するヒントになります。事業内容を簡潔に、誰にでも伝わる言葉で表現できるかという観点はとても重要でしょう。エレベーターピッチ作成のプロセスを通して、企画書全体のブラッシュアップにつなげましょう。
以上、テンプレートとチェックリストを活用すれば、実務上で漏れの少ない高品質な新規事業企画書を作成できるはずです。では最後に、ありがちな失敗例を確認し、その回避策を学んで締めくくりましょう。
よくある失敗例とその回避策
新規事業企画書の作成には多くのポイントがありますが、ここでは陥りがちな失敗パターンをご紹介し、それぞれの回避策を解説いたします。せっかくの企画が伝わらないものになってしまっては本末転倒ですので、最後にチェックしておきましょう。
失敗例①:情報を詰め込みすぎて焦点不明瞭
リサーチを念入りにしすぎるあまり、盛り込みたい情報を全部載せてしまうケースです。結果として企画書が冗長になり、何を伝えたいのかぼやけてしまいます。
回避策:メリハリをつけて情報に優先順位を付けましょう。
伝えるべき核(課題と解決策、その根拠)に直結しない細部の情報は思い切って省略します。簡潔な要約や図表で代替できる部分はテキストを削減し、読み手が一読してポイントを掴める構成にしましょう。「全てを読まなくても概要が理解できる」状態を目指すことが大切でしょう。
失敗例②:主張に根拠がなく説得力不足
企画者の思いは熱く書かれているが、客観的データやエビデンスが欠けているケースです。「市場規模が大きい」「必ずニーズがある」など断言しているものの、裏付けが示されず説得力に欠けます。
回避策:必ずデータや事実に基づいた主張にする癖をつけましょう。
思い込みや希望的観測だけで書かず、「その根拠は?」「数字で示せるか?」と常に自問します。信頼できる統計や調査結果を引用し、グラフや図表も交えて定量的に裏付けることで主張に重みを持たせます。自社データや実証実験の結果があればそれも活用しましょう。
失敗例③:専門用語だらけで読み手に伝わらない
技術者や企画者の視点が強すぎて、専門的な表現や社内用語ばかりになってしまうケースです。読み手(経営者や投資家)が詳しくない領域の専門用語が多いと、内容が伝わらず興味を失わせてしまいます。
回避策: 専門用語は、かみ砕いた説明や具体例を添えて使い、必要に応じて言い換え、読み手に伝わりやすくしましょう。
まとめ
この記事では、新規事業企画書のポイントについて解説しました。新規事業企画書は、アイディアを事業として成立させるために避けては通れません。読み手の視点を忘れないようにしながら、わかりやすく説得力のある企画書を作成しましょう。
しかし、本末転倒の話にはなりますが、実際のところ「新規事業に関する素晴らしい企画書ができたから、実際に発足した事業が成功した」という話は聞いたことがありません。結局は何をやるかではなく、誰がやるか、誰とやるかが大切です。
この内容は初歩中の初歩であることを踏まえたうえで、新規事業に向けた入口として参考にしてください。
お困りの際は、組織マネジメントを支援するソフィアまでどうぞご相談ください。