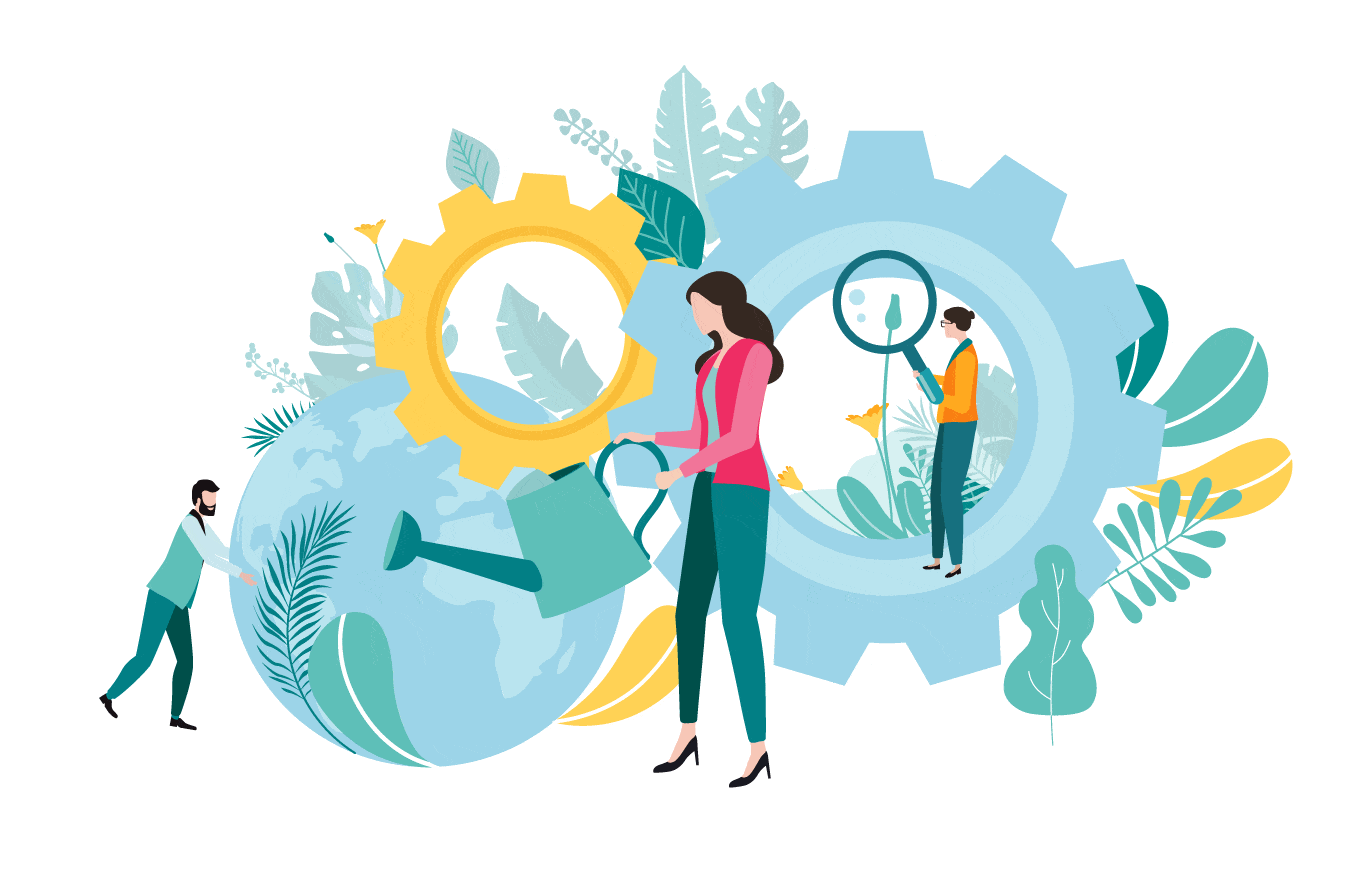良い職場とは?成果とエンゲージメントを高める職場コミュニケーション
最終更新日:2025.07.03

目次
「職場」は日常でよく使う言葉ですが、何を指すか考えたことはありますか。
多くの人にとって職場は単に仕事をする場所以上の意味を持ち、人間関係や雰囲気など目に見えない要素も含まれます。
テレワークが普及し働き方が大きく変わる中で、職場の在り方は今後どのように変化していくのでしょうか。
仕事は一日の大半を占めるだけに、人間関係の悩みがあると大きなストレスになります。
実際、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)が2017年に公表した『若年者の離職状況と離職後のキャリア形成』(調査シリーズNo.164)によると、21~33歳の若年正社員のうち約3割近くが「人間関係がよくなかったため」を退職理由として挙げています。
本記事では職場の意味や役割を改めて定義し、良い職場を作るために欠かせないコミュニケーションやリーダーシップのポイントを解説します。
未来の職場で求められるコミュニケーションスキルも紹介しますので、職場環境に悩む方や組織をより良くしたい方はぜひ参考にしてください。
職場の意味と定義
多くの人が長い時間を費やす「職場」とは、業務や執務を遂行する場所(設備や空間)という物理的な意味合いに加え、従業員同士の人間関係が構築される社会的空間という側面もあります。
言い換えると、職場には業務遂行や成果創出といった機能的・合理的側面と、日々モヤモヤした感情を生み出す人間関係といった情愛的・精神的側面の2つが共存していると言えるでしょう。
生産性を上げる場である一方で、悩みや葛藤の種にもなり得る職場とは一体どのようなものなのでしょうか。本節では、職場の意味と定義について解説します。
まず、「そもそも職場とは何なのか?」を捉え直してみましょう。
数多く存在する「組織」と呼ばれる集団の中でも、常に顔を合わせて直接コミュニケーションを取れる比較的少人数の集団が職場です。
現代のように物理的資本より人的資本が生産性やイノベーションのカギを握る社会においては、組織の人的資本のパフォーマンス向上には、職場における機能的・合理的側面と情愛的・精神的側面の均衡が重要です。
その均衡を調整するのは日々のコミュニケーションであり、職場で必要なコミュニケーションスキルを身に付けることが良い職場の形成につながります。
企業の職場環境に関する指針でも「職場環境」とは照明や設備などの業務環境から人間関係など精神的なものまで含めた従業員を取り巻く環境だと定義されています。
生産性だけを追求すると人間関係が二の次になり、殺伐とした雰囲気になりかねません。
一方で情愛を重視しすぎると単なる仲良し集団となり、良い意味での競争が生まれず成果も出なくなってしまいます。
生産性と情愛、この両面のバランスをどう取るべきなのでしょうか。
職場を分析するゲマインシャフトとゲゼルシャフトの2つの機能
ドイツの社会科学者フェルディナント・テンニースは、人の集まりをゲマインシャフト(共同社会)とゲゼルシャフト(利益社会)という2つの概念で類型化しました。
家族や村落、企業内のサークル、創業期のベンチャーのように情愛や精神的意志でつながる集団がゲマインシャフトです(「ゲマイン」はドイツ語で「共有された」という意味で、英語ではコミュニティに相当します)。
一方、国家機関や政党、大企業の部署など目的や合理的意志でつながる集団がゲゼルシャフトです(英語ではソサエティに相当します)。
平たく言えば、ゲマインシャフトは構成員の精神的つながりによる集団、ゲゼルシャフトは合理的利害による集団ということになります。
米国の社会学者チャールズ・H・クーリー(Charles Horton Cooley)は第一次集団(primary group)と第二次集団の概念を、ロバート・M・マッキーバー(Robert Morrison MacIver)はコミュニティ(community)とアソシエーション(association)の概念を提唱しました。
時代や用語は違えど、集団を情愛的側面と功利的側面で二分類する考え方は社会学において重要な理論的枠組みとなっています。
では、職場はゲマインシャフトとゲゼルシャフトのどちらに当たるのでしょうか。
大企業や機能分化された組織の一部である職場はゲゼルシャフト(合理的・功利的)的な性格を当然持つはずです。
しかし一方で、職場は比較的小人数の従業員で構成され日々顔を合わせて仕事をする環境であることから、従業員間のコミュニケーション頻度が高く、役割や権限を超えた濃密な人間関係が生まれやすい場でもあります。
つまり職場とは、合理的な機能と情愛的なつながりの両方が併存している複合的な集団なのです。
こうした二重構造を持つがゆえに、職場では「面従腹背」「忖度」「本音と建て前」といった表向きの合理性と内心の感情とのバランスを取る独特の文化が生じます。
また、困難な問題に直面した際には、必ずしも業務上の役割や責任を持たない同僚の助けで何とか乗り越えることもあるでしょう。
合理性だけでは現場の問題は解決できず、人間的な支えが必要になる場面が少なくありません。
職場はゲゼルシャフトを基本としながらもゲマインシャフトの機能も併せ持ち、それぞれの職場がこの両極のどこか中間点で均衡していると捉えることができます。
この視点で職場を見ると、すべての職場をある程度俯瞰できるでしょう。
職場内コミュニケーションと組織内コミュニケーションの違い
「組織全体」と「職場(部署など)」では、コミュニケーションの在り方にいくつか違いがあります。
最大の違いはコミュニケーションのスタイルです。従業員数が多い大企業では、多数の従業員に情報をできるだけリアルタイムに行き渡らせる必要があるため、一度に多くの情報を一方向に伝えるマス的なコミュニケーションがどうしても増えます。
内容も抽象度が高く演出過多になりがちなため、経営陣と社員の間に直接的な信頼関係を築くことは難しく、一社員が組織全体の状況を深く理解することも困難です。
また、「会社」は社員から見れば非人格的な存在なので距離を置きやすく、「会社は会社、自分は自分」と割り切れてしまいます。
言い換えれば、社員は組織に対して忠誠心や当事者意識を必ずしも持たずとも業務自体はこなせてしまうということです。この状態が良いと感じる人はいないでしょう。
一方、「職場」内での従業員同士のコミュニケーションは、顔を突き合わせて会話できる環境を前提とすると頻度も多く直接的で、お互いの人となりが色濃く反映されます。
職場という集団自体がゲマインシャフト(情愛的な結びつき)に近いため、従業員同士は否応なく精神的な繋がりやチームワークが求められる傾向があります。
組織全体では個人が一定の距離を取って働くこともできますが、職場では同じ空間で協働する以上、距離を置いて業務を進めるのは難しいでしょう。
職場はある意味で家族や友人関係に近く、日々の挨拶や何気ない雑談といった日常的コミュニケーションの積み重ねが重要となります。
生産性重視の「組織」と、人間関係重視の「職場」は区別して考えるべきなのです。
ゲゼルシャフトとゲマインシャフト両方の側面を持つ職場においては、各メンバーの属人的な価値観や考え方がコミュニケーションに大きく影響します。
とくに最小単位である職場のリーダー(直属の上司)のコミュニケーションの取り方は、職場全体の雰囲気や情報共有に強く影響します。
現在のように人的資本が価値創出の要となる時代では、職場で機能的側面と精神的側面のバランスを取ることが肝心であり、その調整役となるのは職場内のコミュニケーション以外にありません。
とはいえ、職場の社員の中にはコミュニケーションが得意な人もいれば苦手な人もいるでしょう。
様々な個性を持つ社員たちを、見えないツールであるコミュニケーションによって結び付けようとするとき、どうしてもリーダーからの意識的な支援や介入が必要になってきます。
リーダーとして社員同士のコミュニケーションをいかに円滑にし、生産性向上へと結びつけるかが次のテーマとなるでしょう。
職場にある社員エンゲージメントのラストワンマイル
職場では表と裏の二重構造のバランスが崩れることで、職場特有の問題が発生します。
たとえば「面従腹背」「忖度」「本音と建て前」といった文化が行き過ぎたり、コミュニケーション不全が起きると、「うつ病」「離職」「ミスコミュニケーション」など様々な問題が表面化します。
これらの原因は一見すると業務上の明確な理由で説明されがちですが、実際には必ず人間の心理や感情が絡んでいます。
職場特有の二重構造とうまく付き合うためには、経営陣や会社と従業員との公式なコミュニケーションによって企業理念やビジョンを共有し、従業員が共感を持てる関係性を深めることが必要です。
会社のパーパス(存在意義)や理念・ミッション・ビジョン、戦略計画といったものをただ頭で理解するだけでなく、従業員の心に響かせ自分ごととして捉えてもらうことでエンゲージメントが高まります。
しかし、こうしたトップダウンの働きかけだけで離職の低減や関係性の向上が実現するでしょうか。
本質的なエンゲージメント、すなわち職場内の人間関係による「絆」が生まれるでしょうか。
全社最適の組織内コミュニケーションだけで各職場(チーム)の部分最適まで包含することは難しいのです。
ここで強調したいのは、属人的な要素が職場の結束に大きな役割を果たすということです。
たとえば「なぜこの職場を辞めずにいるのか?」という質問に対し、「○○さんと一緒に仕事しているから」「尊敬できる△△上司がいるからこの職場にいる」といった声は少なくありません。
つまり、社員は会社そのものとの関係だけでそこに所属し続けているのではなく、ある個人との感情的な結びつきによって職場に踏みとどまっている場合が多いのです。
ここで大事なのはリーダーの存在感であり、そのリーダーがいることで社員が引きつけられているかどうかです。
欠点のない職場などありません。不満な点を挙げればきりがないでしょうし、それは大企業でも中小企業でも同じです。
多少の不満があっても社員が離職せず職場に留まろうと思えるのは、おそらく仲間同士の支え合いや尊敬できるリーダー、気付きや学びを与えてくれる先輩の存在が大きいでしょう。
職場は仲良しクラブではなく、必ず不満や葛藤が生まれるものです。それを乗り越えて社員が前向きに業務に取り組もうという気持ちになるためには、職場で影響力を持つ他者の存在が欠かせません。
そして多くの場合、職場で最も影響力を持つのはリーダーという立場の人です。
エンゲージメント調査や従業員満足度調査、あるいは社内SNSのログ分析などでは見えてこない「社員同士の関係性」や「リーダーとの関係性」が職場には存在します。
こうした一対一の関係性は日々の絶え間ない職場内コミュニケーションから生まれる、一種の物語のような連続性を持っています。
良きリーダーとは、職場でそのような良き物語を紡ぎ出せる人物であり、その物語に社員が心を動かされるからこそ、多少の不満があっても「この職場に貢献したい」「自分のスキルを活かしたい」と思えるようになるのです。感動のない職場、物語のない職場にはエンゲージメントは生まれません。
社員が離職を考える際、最後の一押しで踏みとどまる力になるのは「このリーダーについて行きたい」と信じられるかどうかでしょう。
リーダーが日頃からメンバー一人ひとりに向き合い、絶えずコミュニケーションを取ろうと努力するだけでなく、職場としての小さな物語(チームの目標達成談など)や会社全体の大きな物語を語り共有できるかどうか――そのスキルに職場の結束力も組織全体の活力もかかっていると言えます。
日々積み重ねられる人と人との関係性の中で小さな問題が発生し、それを適宜解決していくプロセスの中でエンゲージメントが育まれる場合もあれば、逆に関係性が崩壊してしまう場合もあります。
職場内の絶え間ない人間関係の中に、社員のエンゲージメントを生み出す「ラストワンマイル」――最後の決め手となる部分が存在しているのです。
事実、世界的に見ても社員のエンゲージメント(仕事への熱意)は高いとは言えません。
米国の世論調査・コンサルティング会社ギャラップ(Gallup)が2025年に公表した「State of the Global Workplace: 2025 Report」によれば、2024年時点で世界全体の従業員エンゲージメント率は21%に低下し、とくにマネージャー層の落ち込みが最も大きかったと報告されています。
大半の社員が自分の仕事に熱意を持てていない状況は、生産性やイノベーションにも大きな損失をもたらすとされています。
裏を返せば、職場内の人間関係や物語づくりを通じて社員の心に火を付け、本当の意味でエンゲージした状態に導くことができれば、組織全体の業績向上にもつながるでしょう。
職場は組織の中にあるさまざまな要素が相互作用する対面小集団
以上を踏まえると、職場とは組織の中でも様々な要素が相互作用する対面の小集団であるとまとめられます。現代の職場には次のような要素や変化への対応が求められています。
職場に求められる要素や変化への対応
· テレワークの浸透 – 場所や時間に縛られない働き方への対応
· 働き方改革 – 長時間労働の是正や柔軟な勤務制度の導入
· 従業員の多様性 – ダイバーシティ&インクルージョンによる多角的なチーム編成
· 人材の流動性 – 終身雇用の崩壊や社内外での人材の流動化
· 職場間連携 – 部門間・チーム間のコラボレーション強化
· 事業環境の不確実性 – 変化の激しい市場で迅速に適応する力
· デジタルトランスフォーメーション(DX) – 業務のIT化・自動化とそれに伴う役割変化
このように企業を取り巻く状況が複雑・多様化する中、職場という最小単位で機能的合理性と情愛的精神性のバランスを保つことはますます重要でありながら難しくなっています。
日常業務の中で試行錯誤しつつメンバー同士がコミュニケーションを図り、生産性と良好な人間関係の両立を目指して努力しているものの、実際には従業員エンゲージメントやモチベーションを高めることに苦戦している職場も多いのではないでしょうか。
その要因は山積しており複雑です。場合によっては、問題の多さに自分自身のやる気さえ失いかねない現状かもしれません。
均衡を最適化するにはメンバー間の相互理解を深めるコミュニケーションしかないのですが、それとは具体的にどのような取り組みなのでしょうか。
ここからは、「均衡を取るための具体的なコミュニケーション施策」について解説していきます。
職場における見えるものと見えないもの
組織で業務を遂行するプロセスには、見える要素と見えない要素の両面があります。
見える要素とは、業務プロセスやスケジュールの作成、担当者の役割分担など目に見えて把握しやすい事項です。
一方、見えない要素とは、メンバーのモチベーションや職場の雰囲気、人と人との関係性といった目に見えない事項を指します。
多くの企業は見える要素には意識的に対処しているでしょうが、見えない要素への対応は後手に回りがちです。
しかし、この見えない要素こそが社員を職場に繋ぎとめる一方で離職させる原因にもなり得るのです。
職場の目に見えない要素を軽視してはなりません。たとえば、人間関係の悩みといった心理的ストレスは目に見えないからこそ注意が必要です。
心理的ストレスはじわじわとメンタルや仕事のパフォーマンスに負の影響を与え、ひどい場合はうつ病に発展するケースもあります。
大きな問題に育つ前に対処することが肝心です。また、チームを率いる立場の人は自分自身だけでなくメンバーのストレス状態にも目を配る必要があります。
他者のストレスは表面からは分かりづらく、気付かないうちに限界に達して突然退職…という事態も起こり得るためです。
こうした「見えない部分」を支えているのがコミュニケーションです。前述のように、職場で起こる問題やその原因の大半はコミュニケーションに起因しています。
とくに現代の多くの職場では業務が複雑化し、社内外の様々なメンバーが関わるようになったことで、新たに人間関係を構築しなければならない場面が増えています。
その背景から、職場内コミュニケーションの重要性は以前にも増して高まっていると言えるでしょう。
もはや決まった相手と決まった日課をこなせば業務が回るような時代ではなくなりました。
職場の効果を発揮するためには
では、職場の持つ力を最大限に発揮し良好な成果を上げるにはどうしたらよいのでしょうか。
人が集まる理由は、個人で取り組むよりも効率よく大きな成果を上げられるからです。
その効果を高めるためにも、先に述べた職場の「機能的・合理的側面」と「情愛的・精神的側面」の均衡を取ることが大切です。
見える要素へのアプローチとしては、職場の目標達成に必要な業務を洗い出し、従業員の能力やモチベーションに合わせて適切にタスクを配分しましょう。
業務量が偏りすぎていないか、過度なストレスがかかっていないかを定期的にチェックすることも大切です。
社員一人ひとりにある程度の裁量権を与え、自律的に働ける環境を整えることで、効率的に成果を出しやすくなります。
一方、見えない要素へのアプローチについては、従業員同士の関わり合いをどう作るかがポイントです。
メンバーが日々の仕事の中でお互いを観察し気配りし合うためには、相手に関心を持って背景を理解する必要があります。
相互理解と日々の協働の積み重ねによって、共感的な理解と相互尊重の気持ちが育まれます。
お互いに寄り添いながら、困ったときには遠慮なく助け合える人間関係を構築できれば、その職場の成果に与える良い影響は計り知れません。
ただし、こうした変化は自然発生的には生まれません。重要になるのは、職場内で影響力を持つリーダーなどの存在です。
リーダーが上述のバランスの大切さを理解し、効率やスピード重視に偏りすぎず、遠回りに思えてもメンバー間の関係性を構築する機会やプロセスを意識して設けられるかどうか。
それが継続的に成果を生み出す職場になれるかどうかの分岐点と言えます。
リーダーが異動・交代するとチームががらりと生まれ変わるという話はよくありますが、それだけ職場に最適なリーダー配置が業績向上につながるケースは多いのです。
影響力のある役職者をどう立てるかに注意を払いながら、職場をデザインしていきましょう。
なお、リーダーの任命について固定化しないこともポイントです。その時々のタスクに合わせてリーダーが変わることは日々現場で起こっています。
課長や係長といったポストに就いている人が万能とは限りません。タスクによっては若手社員の方が年配社員より「有能である」「得意である」というケースもよくあります。
多様性は職場に柔軟性をもたらし、一方で従来の階層構造は職場に安定性をもたらします。
そのため職場単位では、より柔軟で俊敏な体制を目指すべきであり、実際、企業の多様性推進は業績にも好影響を及ぼします。
ハーバード・ビジネス・レビュー(Harvard Business Review)が2013年に発表した研究「How Diversity Can Drive Innovation」によると、多様性の高いチームは新しい市場を獲得する可能性が70%高いことが明らかになっています。
多様でインクルーシブな職場は市場への適応力が高く、より大きな機会と収益をもたらすとされています。
職場が生産性向上と情緒的な繋がりの双方を最大限に発揮するためには、リーダーの任命を柔軟に行うことが不可欠です。
もし若手社員がリーダーを務める場合には、その期間だけ給与を通常より大幅に上げるといったインセンティブを設けても良いでしょう。
GE(米ゼネラル・エレクトリック)は2014年頃から従来の年次ランク付け評価を廃止し、「PD@GE(Performance Development at GE)」と呼ばれるリアルタイムフィードバック制度を導入しました。
アクセンチュア、デロイト、ゴールドマン・サックス、IBM、マイクロソフトなども同様の「ノーレイティング」人事制度を採用し、より柔軟で現場に即した評価体系へと移行しています。
現場単位の課題が多様化し、それを遂行する人材も多様化する中で、全社統一の硬直的な人事制度では優秀な社員に十分報いることができなくなった背景があります。
下手をすると、現場レベルの優れた取り組みや優秀な社員に対して既存の仕組みが悪影響を及ぼす可能性すらあるのです。
どんな職場もワクワク感なしには長続きしません。そのワクワク感は往々にして若手から生まれてくるものです。
管理職は時にリーダーの座を若手に譲る柔軟性が必要でしょう。
また、ワクワク感は仕事内容そのものとは必ずしも関係ありません。
一見単調に見える事務作業でもワクワクしながら仕事をする人もいれば、最先端のデジタル技術を活用したクリエイティブな仕事でも何の感動もワクワクもない人もいます。
大事なのは職種ではなく、社員が目の前のタスクに夢中になれているかどうかです。
その情熱を職場全体に波及させるには、全員がリーダーだと思えるような状況を作り出すことが重要です。
オンラインの職場とオフラインの職場の違い
昨今の在宅勤務の増加に伴い、オンライン上の仮想的な「職場」で仕事をするケースも増えています。
オンラインの職場では、オフィスで顔を合わせて働くオフラインの職場に比べてメンバーが得られる情報量が少なくなりがちです。
またコミュニケーションもどうしても業務に直結する用件中心になり、お互いの背景や人となりを理解するための情報が得にくい傾向があります。
テキスト(チャットやメール)によるやり取りが多くなるため、情報伝達の行き違いや誤解が生まれやすいという大きな問題もあります。
とくに複雑な課題に取り組む場合には高度なコミュニケーションスキルが求められ、限られた情報で補完し合う工夫が必要です。
もっとも、オンラインの職場ならではのメリットもあります。物理的な距離の壁を越え、チームの垣根を超えてより多くの人とコミュニケーションを取れる点です。
時間の面でも、たとえばチャットツールを使えば必ずしも同時刻に集まらなくてもそれぞれが可能な時間に議論に参加し業務を進めることもできます。
一方で、普段関わりのない人との接点が増えることでコミュニケーションの難易度が上がる面も否めません。
やはり高度な意思疎通や信頼関係の構築を望む場合は、オフラインのコミュニケーションも組み合わせるなど両者の良さを取り入れる必要があります。
このようにオンラインとオフラインの職場には大きな差があるため、「やっぱり雑談が大事だよね」ということでオンライン上に雑談の場(バーチャル休憩室等)を設ける企業も多くなっています。
職場でメンバー間の関係性を築くことが重要だからこそ、オンラインでも意図的にコミュニケーションを取る必要があるでしょう。
ただし現時点の技術では、オンラインでオフラインと同等以上の情報量を伝えることは難しいという現実も心得ておかねばなりません。
オフラインの情報量に近づけるためには、オンラインで減少した分の情報を各人が想像力で補ったり、新たな共有方法を工夫したりする努力が求められます。
テレワークを主体としつつ見えにくくなった情報をいかに共有し、心理的距離を埋められるか。
そのためには適度にオフラインの機会も取り入れながら、新しい職場の在り方(ハイブリッドな職場環境)を模索していくことが今後の大きなテーマになります。
実際、コロナ禍を経て柔軟な働き方を望む社員は世界的に増えており、多くの企業がリモートワーク継続か出社回帰かで模索をしています。
社員側の柔軟性要求に応えつつ、オンラインでもオフラインでもエンゲージメントを高められる職場作りが求められているのです。
見えない要素のカギを握るのはリーダー
職場の「見えない要素」のカギを握るのはリーダーです。リーダーの言動が職場の価値観や文化を形作っていきます。
まずは適切なリーダーを選出しましょう。そして選ばれたリーダーは、組織内でコミュニケーションの場を積極的に作っていきましょう。
仕組みを作るだけでなく、リーダー自らが模範となる行動を取ることも大切です。
リーダーの行動は職場に大きな影響を与える存在であり、それゆえにメンバーに自分の行動を示すことが求められるのです。
目に見えない要素は非常にケアが難しいものです。リーダーは「目に見えないものをしっかり管理できるかどうかが職場の成果を大きく左右する」ことを肝に銘じ、日々の行動・業務に当たる必要があります。
とはいっても、実際にリーダーを経験してみないとリーダーという役割の難しさや苦労は理解しにくいのも事実です。
この点でも前述のようにリーダーの任命を柔軟に運用し、社員それぞれが一度は何らかのタスクでリーダーを経験できる職場が理想でしょう。
リーダーを経験すれば、かつて部下として従っていたときには見えなかった課題や困難に直面します。
その経験を経れば、他の人がリーダーになった時にも「どうすればその人が活躍できるか」といった支援意識が芽生えるはずです。
仮に正式なリーダーが一人でも、周囲の社員全員がリーダーの視点を持ってサポートするようになれば、職場の生産性は大きく向上するでしょう。
これからの職場に必要なコミュニケーションスキル
コロナ禍を経て働き方が大きく変わった昨今、職場において求められるコミュニケーションの形も大きく変化しています。
企業は自社の状況変化にフィットするよう新しいコミュニケーションの在り方を再考する必要があるでしょう。
変化を積極的に受け入れていく姿勢が大切です。またコロナだけでなくAI等の技術進化による変化の波も押し寄せています。
これからの職場では、人間がこれまで行っていた定型的業務はどんどんITや機械に代替され、人間はより創造的な業務を担うようになるでしょう。
従来とは異なる、より複雑でクリエイティブな会話や議論が必要になるはずです。以下では、これからの職場で重要となるコミュニケーション手法を紹介します。
対話(ダイアログ)
対話とは、お互いの立場や意見の違い、感情的な葛藤を理解し、そのズレをすり合わせることを目的としたコミュニケーションです。
職場では、普段は表に出ない本音や感情を引き出し言語化するのに役立ちます。
ただし自分の内面を打ち明けるには心理的な抵抗もあるため、1対1の面談(ワンオンワン)など安心して話せる場を設けることが効果的です。対話では、日常生活で意識していない気持ちを言語化して相手に伝え、互いの言葉を同じ地平で受け止め客観視することで、理屈では片付けられない対立や行き詰まりを突破するきっかけが生まれます。感情や共感の力を活用した対話は、職場の難しい問題に取り組む際に非常に有効なコミュニケーション手法です。
ディベート
ディベートとは、肯定側・否定側に分かれて自分たちの主張が正しいことを相手に認めさせることを目的とする討論ゲームです。
ディベートでは自分たちの正当性を証明するデータを集め、論理的に説明する必要があります。
公式戦では第三者が客観的に勝敗を判定しますが、非公式な場では最終的に双方が合意するか一方が折れることで決着します。
「ディベートなんて職場でやったら人間関係が悪化するのでは?」と思われるかもしれませんが、それは誤解です。
本記事ではここまで関係性(人間同士の絆)に焦点を当ててきましたが、そもそも業務や課題自体に矛盾や非合理が残ったままでは、いくら人間関係が良好でチームワークが強くても成果は出ません。
業務内容に筋が通っていなければ結果も伴わないのです。
ディベートというゲーム的手法を用いることで、感情にとらわれず反対意見や異論を整理してぶつけ合うことができます。
ゲームである以上、本気で感情的になる必要はありません。「どちらの論がより理にかなっているか」を競う遊びと捉え、勝っても負けても実利や実害はありません。
この気楽さがあるからこそ、普段は言いにくい意見も自由かつ柔軟に出せるのです。
こうした自由闊達さこそ職場を活性化し生産性を上げる上で重要なカギでしょう。
ディスカッション
ディスカッションとは、対立を深めず意見を出し合うことで皆が納得できる結論を見い出す作業です。
建設的な話し合いとも言えます。それは妥協的な合意かもしれませんし、挑戦的な合意かもしれません。
特定の課題を解決するために職場内で一次的かつ仮説的なコンセンサス(合意形成)を得たいときにもディスカッションが行われます。
ただしディスカッションは必ずしも何らかの意思決定を行う場面だけで使われるものではありません。
コミュニケーションの一環として日常的にディスカッションが行われることもあります。
形式ばった会議でなくても、職場に建設的に議論する姿勢が根付けば、生産性の高い雑談ができたり会議室できちんと構えたりしなくても済むでしょう。
レトリック
レトリックとは本来、説得やスピーチの文脈で使われる概念で、話し手が聞き手を説得し納得させるための表現技法を指します。
ビジネスにおけるレトリックが活きる場面としては、新規事業や新商品開発の担当者が上位者へプレゼンを行う、上司が部下に業務への動機付けをする、営業担当が顧客に提案をする――といったシーンが挙げられます。
レトリックは「詭弁」と訳されることもありますが、ビジネスにおいて将来や未来を語る際、ある意味すべてのコミュニケーションは確証のない仮説でありレトリックと言えます。
要するにレトリックとは、相手の心理的な抵抗を和らげつつ問題解決に向けた動機付けを行うコミュニケーションなのです。
レトリックには古代ギリシャ哲学から連なる長い伝統があり、「いかに自分の考えをより効果的かつ印象的に相手に伝えるか」を追求した学問でもあります。
かつては表現技法の効果ばかりに注目し言葉の内容がおろそかになるという批判もありました。
しかし内容が充実している前提に立てば、それを伝える言葉は効果的であるに越したことはありません。これがレトリックの力です。
ストーリーテリング
ストーリーテリングとは物語を語ることで相手に深く印象付け、理解を促す手法です。
ビジネスの世界ではプレゼンテーションや提案時など、話し手がより深く聞き手に内容を届ける必要がある重要な場面でよく用いられています。
人に何かを「語る」という行為は人間の深層心理に根差した行動であり、どの文化にも神話や昔話といった物語が存在します。
語り継がれてきた物語は何世代にもわたり口伝えで伝承されてきました。その過程で伝言ゲームのように言い間違いや記憶違いで内容が変化してしまうこともありますが、それでも残っている神話や昔話の核となる部分はほとんど変化せず残っています。
つまり神話や物語は人間の深層構造に迫る手段でもあり、たとえば「日本人とは何か?」と問う際に日本の神話や昔話を研究すると示唆が得られるとも言われます。
ビジネスにおいても、この物語を積極的に活用することで聞き手の心の深い部分に訴えかけることができます。
そのため広い意味で民俗学や哲学を学ぶ意義もここにあります。職場でもメンバーが共感できるストーリーを共有することで、一体感や目的意識がより強固になるでしょう。
ファシリテーション
ファシリテーションとは、メンバーの議論や協働を支援し、社内外の関係者との調整・折衝を円滑に行うコミュニケーション手法です。
現代の職場は常設の固定メンバーによるチームであっても、プロジェクトごとに目的が変化し短期間で成果が求められることが常態化しています。
問題自体も複雑化し、人間関係も摩擦が生じやすくなっています。
ファシリテーションでは職場のゴールに対するメンバーの納得感を醸成し、内外の変化に柔軟に対応しながらメンバーのモチベーションを高め、安心して協働できる場を作ります。
これは「業務」と「人」のバランスを保つうえで現在最も必要とされるコミュニケーションスキルと言ってもよいでしょう。
組織や人、プロジェクトそのものが複雑になっている昨今、その重要性は増すばかりです。
社外の専門ファシリテーターや研修講師にこの役割を依頼することも手段の一つですが、現場では日々多種多様なケースで問題が発生します。
したがって職場のとくにリーダークラスにおいてはファシリテーションスキルは必須とも言えるコミュニケーション能力です。
コミュニケーションスタンス
「VUCA(ブーカ)の時代」とよく言われます。
VUCAとはビジネス環境を表すキーワードで、変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)の頭文字です。
現代のビジネス環境は驚くべき速さで変化し、従来の常識が通用しなくなることが多々あります。
そのため状況に柔軟に適応するスキルが求められますが、皮肉なことにVUCA下では情報が不確かで曖昧なため、情報の信頼性や再現性を確保することが難しくなっています。
つまりビジネスパーソン同士が共通の前提を持ち互いに理解し合う基盤が揺らいでおり、コミュニケーションが困難になっているのです。
これがVUCA時代の現実です。しかしながら、現実世界をいくら詳細に分析して追随しようとしても限界があります。
むしろ視点を変えて、現実を“追いかける”のではなく“創り出す”姿勢に重点を置くことが重要ではないでしょうか。
ビジネスと人の多様性について細部まで分析し尽くすことは専門家に任せるとして、我々は価値を創造することに目を向けるべきです。
社員一人ひとりが「答えは与えられていない」「正解がないかもしれない」と覚悟を決める必要があります。
それがVUCA時代です。しかし、自分が現実を創造する側に立った途端に状況は一変します。
世界がどれほど混沌とし不安定でも、自分の内面に確固たる価値の源があれば、少なくともそこだけは頼ることができます。
かつてデカルトは「我思う、ゆえに我あり(自分は思考する存在である)」という言葉で近代哲学を切り開きました。
このVUCAの時代にあっても、「自分の内面だけは確実だ」というデカルトの示唆は示唆的です。
確固たる自分の軸を持ち、不安定な世界にどれほどの価値を提供できるか――それをビジネスパーソンは日々自問自答すべきでしょう。
まとめ
職場とは、所属する人たちが日々コミュニケーションを取り合い関係性を築くことで形成されていくものです。人間関係の悩みは放置すると深刻化しかねません。コミュニケーションの行き違いによる「つまずき」を早期に解消し、負のループを断つ努力が肝心です。相手に非がある場合でも、自分にコントロールできる範囲で働きかけ負の連鎖を食い止めることが解決への近道になります。職場の課題に真正面から向き合
い、メンバー同士が支え合いながら持てる力を発揮できる環境を作ることこそ、これからの時代における良い職場の条件と言えるでしょう。
組織開発の視点では、メンバーのモチベーション維持など目に見えない要素の鍵を握るのはリーダーだと言えます。リーダーによる適切な働きかけによってコミュニケーションが活性化され、良い職場づくりが進みます。また職場でコミュニケーションを活発にするためには、そうした機会を提供できる仕組みを整えることも効果的です。オンラインとオフラインの職場の違いにも留意しつつ、柔軟な働き方や多様性の受容、コミュニケーション活性化のための様々な施策を組み合わせることで、職場での社員の不安や懸念を払拭していきましょう。