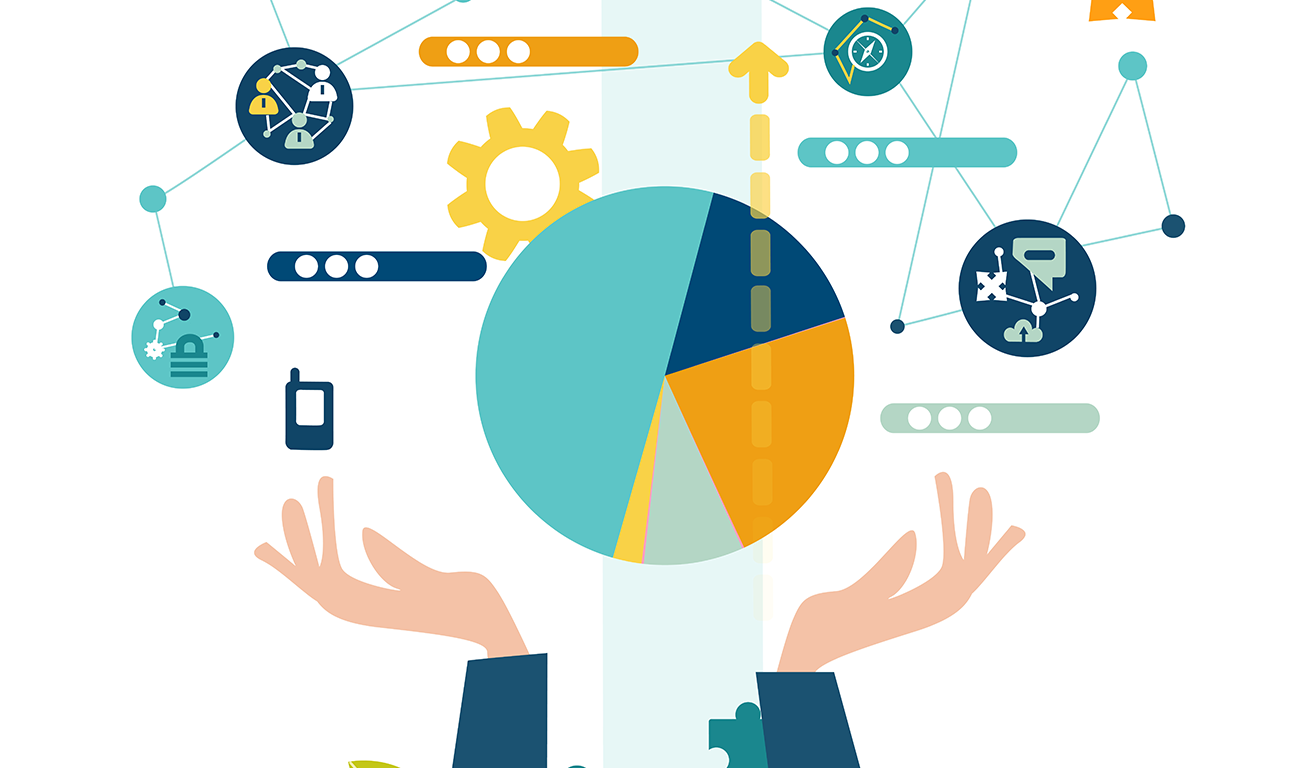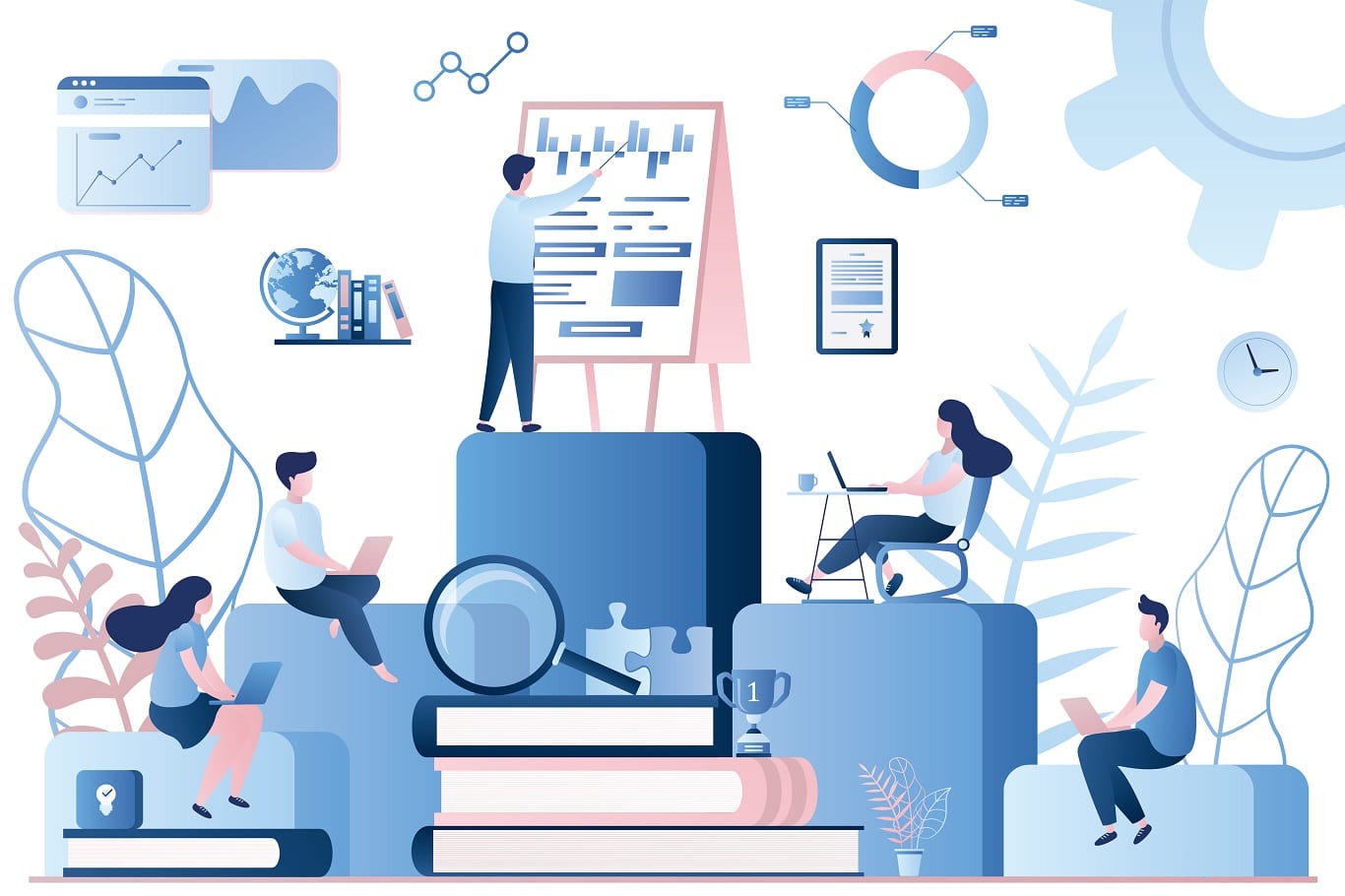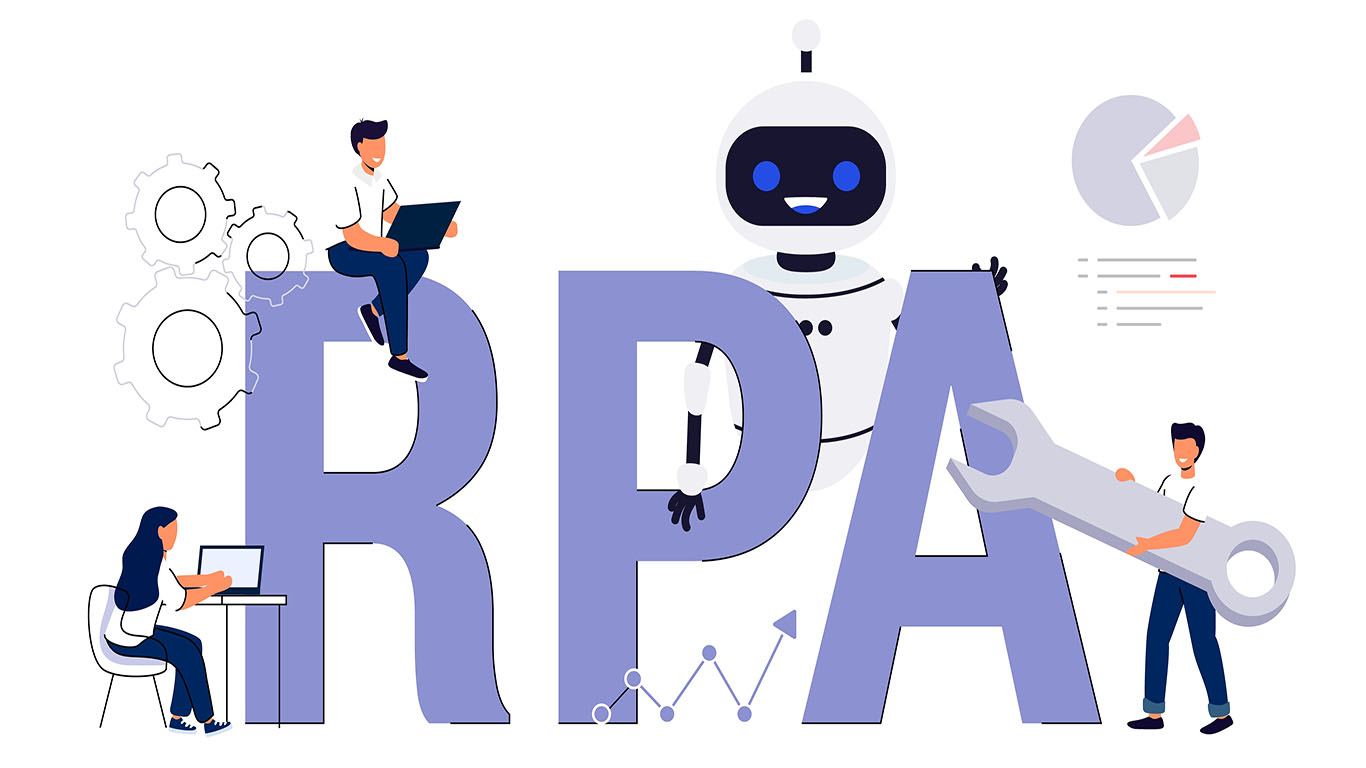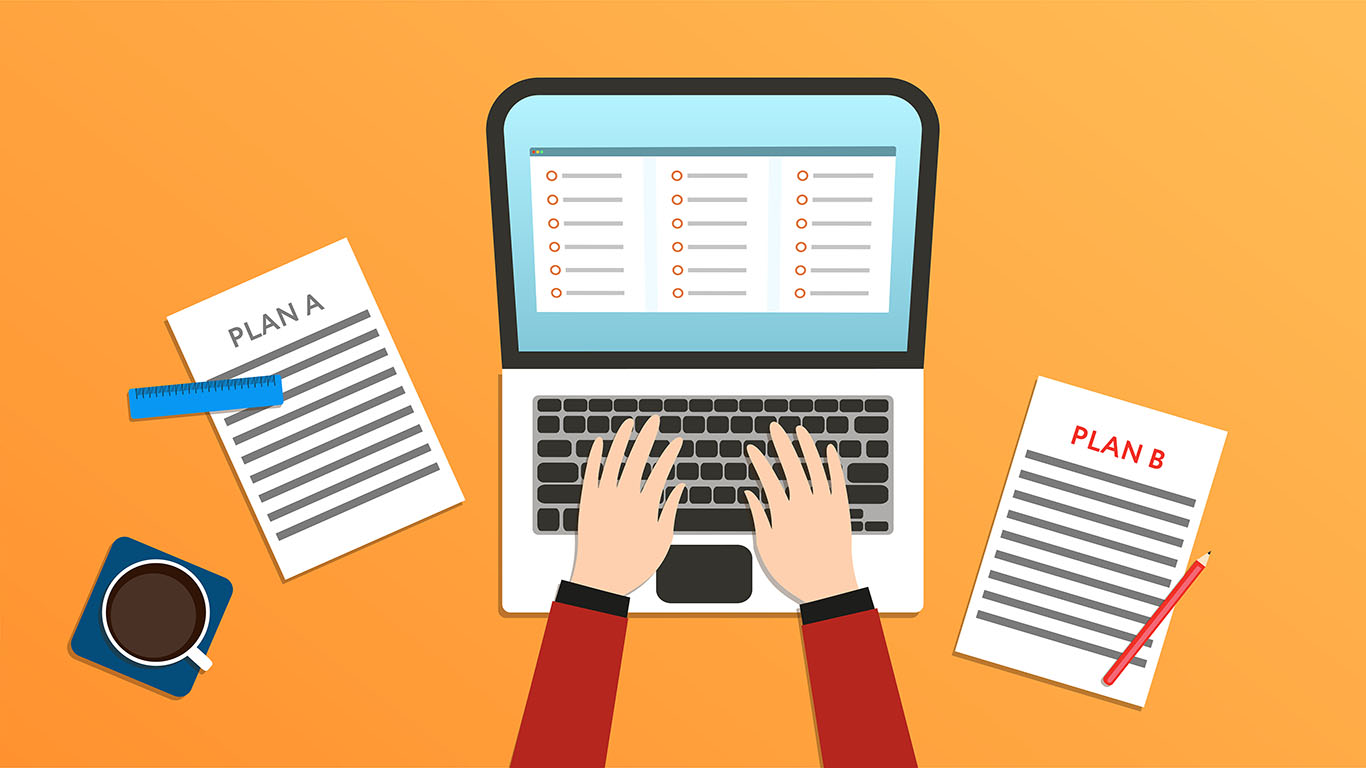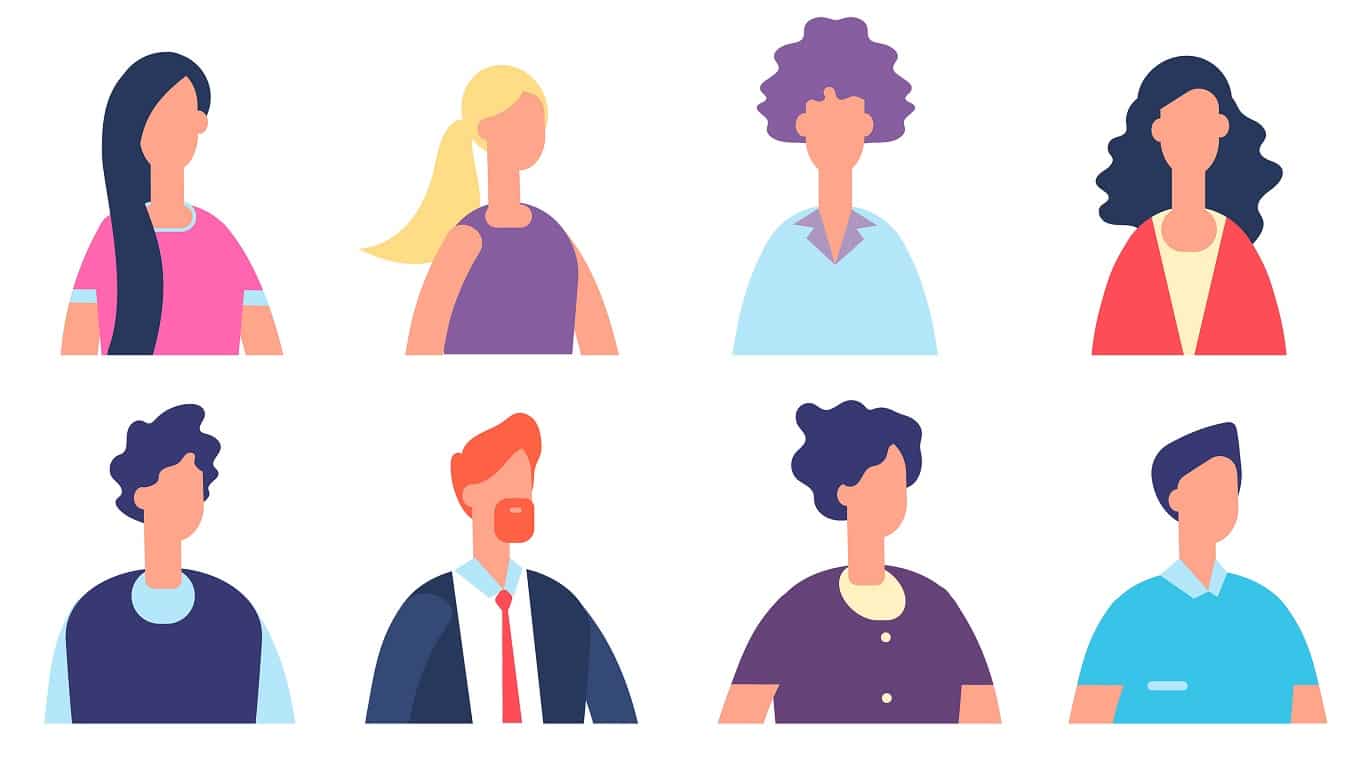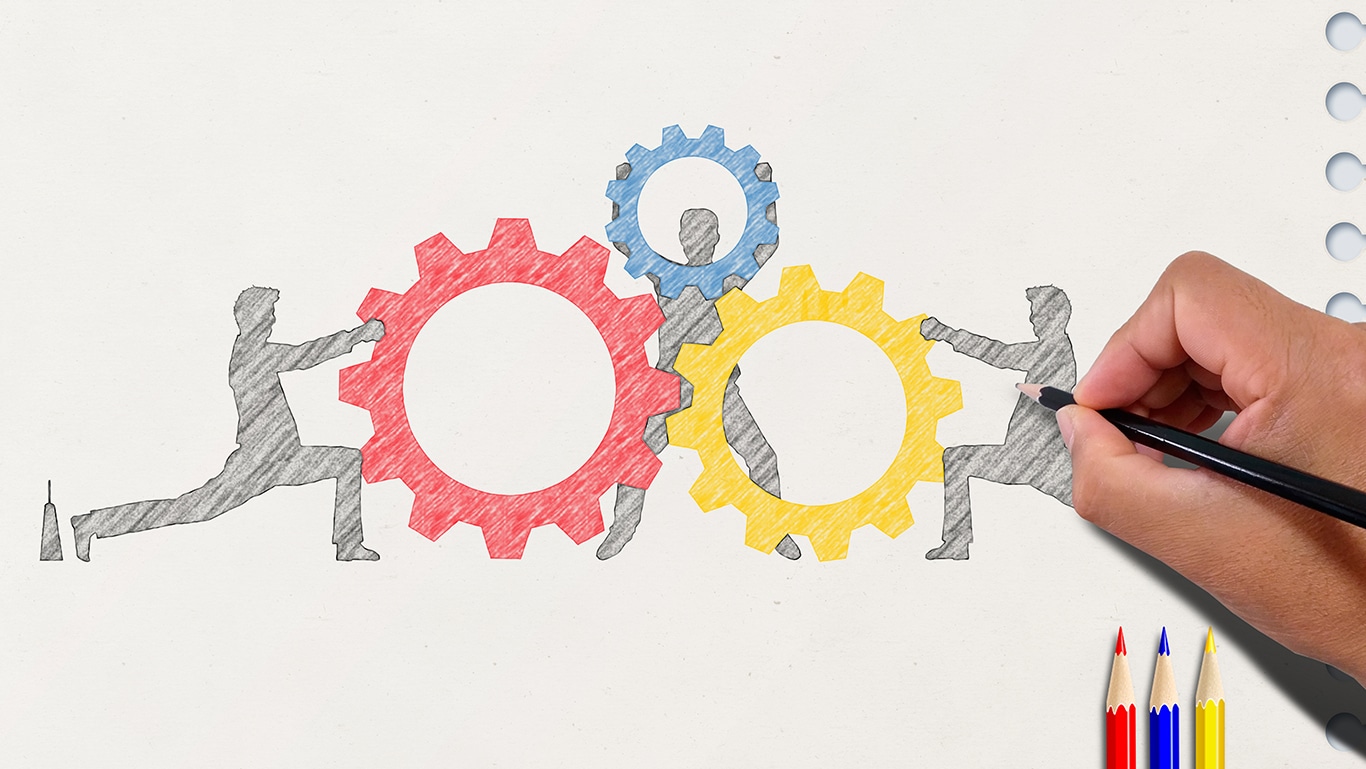データ利活用とは?DX時代のメリット・手法・事例【2025年最新】
最終更新日:2025.08.20

目次
現代のビジネス環境では、データの価値がますます高まっています。しかし、膨大なデータをどのように活用すればよいのか、多くの企業が頭を悩ませているのも事実です。データ利活用とは、単にデータを集めるだけでなく分析して意思決定に役立てることです。
本記事では、データ利活用の意味や重要性、そのメリットや進め方を大企業の経営管理部門・DX推進部門の部門長の方にもわかりやすく解説します。具体的な活用手順や企業事例、そして成功のポイントや直面しがちな課題と解決策まで網羅しています。「自社のデータをビジネスに活かしたいけれど、何から始めればいいの?」とお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
データ利活用とは
データ利活用とは、ビジネスや社会のさまざまな分野で収集したデータを適切に分析・活用し、新たな価値やインサイトを生み出すことを指します。
データから有益な情報を引き出し、経営や現場の判断に活かすことで、より効率的な意思決定や問題解決が可能となり、企業の競争力向上につながります。
また、データを可視化することで膨大な情報を直感的に理解でき、重要な洞察を得ることもできます。
近年はオンラインビジネスやIoTの普及により、企業が日々蓄積するデータ量は飛躍的に増大しました。こうした背景から、多くの企業がデータ利活用に取り組み始めており、大企業では約9割、中小企業でも半数以上が何らかの形でデータ活用を行っていると報告されています。データ利活用は今や一部のIT企業だけでなく、あらゆる業種においてビジネス成功に不可欠な要素となっているのです。
データ活用を導入する3つのメリット
データ利活用には、企業経営や業務推進にもたらす大きなメリットがあります。主なメリットは以下の3つです。
業務の効率化・コスト削減
データに基づいて業務フローの無駄やボトルネックを発見し、自動化や改善策を講じることで生産性向上とコスト削減が期待できます。経験や勘に頼ったやり方から脱却し、データを根拠とした合理的な業務改善が可能になります。
たとえば、製造現場で生産ラインのデータを分析すれば、不要な工程を省いて品質を向上させる施策が打てます。
顧客満足度・売上の向上
蓄積した顧客データを分析・活用することで、顧客のニーズに合った商品・サービスを提供でき、顧客満足度の向上や売上アップにつながります。データに基づくパーソナライズされた提案により、リピート率や新規顧客獲得率も高められるでしょう。たとえば、購買履歴やウェブ上の行動データを分析すれば、顧客一人ひとりに最適な商品提案やマーケティング施策を行うことが可能です。
意思決定の高度化(DX推進)
社内外のさまざまなデータを活用することで、より的確で迅速な意思決定ができるようになります。データに裏付けられた判断は客観性が高く、勘や経験に頼るよりも成果を測定・検証しやすくなります。
市場動向の予測や新戦略の立案でもデータ分析が威力を発揮し、経営戦略の精度が上がります。これにより企業全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)が推進され、ビジネスモデルの革新や新たな価値創造にもつながります。
それぞれのメリットを踏まえ、データ利活用を導入する意義は非常に大きいと言えます。次章からは、なぜ今データ利活用が注目されているのか、その背景を詳しく見ていきましょう。
なぜ今データの利活用が注目されているのか
2000年代以降、インターネットやIoT、スマートフォン、AIといったテクノロジーが急速に発達し、膨大で複雑なビッグデータを扱うことが可能になりました。クラウドの普及や分析手法の進歩により、以前は困難だったビッグデータの収集・蓄積・加工・分析のハードルが下がったことも大きな要因です。
こうした技術的背景から、単なるデータの「利用」だけでなく意思決定まで含めた「利活用」という視点でデータを見る機会が増えてきました。
さらに、ビジネス分野でデータ利活用がとくに注目されるようになったのには、技術進歩以外に大きく3つの理由があります。
(1)企業のDX戦略を進める上でデータが不可欠な鍵となっていること
(2)データ活用によって顧客や従業員のエクスペリエンス向上など具体的な効果が得られること
(3)AI活用のためには高品質なデータ基盤が必要であること
これらがデータ利活用が急務とされる主な理由です。以下で順に見ていきましょう。

なぜ、企業はデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組むのか?理由とメリットを解説
なぜ企業にデジタルトランスフォーメーションが必要なのでしょうか。企業を取り巻く環境からその理由を知り、DX推進…
DX(デジタルトランスフォーメーション)との関係
まずDX(デジタルトランスフォーメーション)との関係です。DXとは企業がデジタル技術を導入して業務プロセスを効率化し、新たなビジネスモデルを創出する取り組みですが、その実現にはデータ利活用が欠かせません。
企業がDXを推進する上で、蓄積したデータを活用して現状を正確に把握し、科学的根拠に基づいた意思決定を行うことが求められます。データ利活用とDXの関係は密接で、データなくしてDXの成果は得られないと言っても過言ではありません。
たとえば、多くの企業では長年経験や勘に頼って施策を進めてきましたが、データを使わなければ計画(Plan)が的外れになったり、効果検証(Check)ができず改善につなげられないケースが少なくありません。競争環境が激化する中で無駄な施策を避けるためにも、データに基づくDXの取り組みが必要不可欠なのです。
データ利活用が進めば、顧客の行動変化を捉えたマーケティング戦略の最適化や、新商品の開発改善、生産・物流の効率化、人材の適材適所の実現など、幅広い業務領域でプラスの効果が得られるでしょう。
一方で、DXは単にデータ活用だけを指すものではなく、より広範なデジタル技術の活用による企業変革を意味します。その点でデータ利活用はDXの中核的要素であり、これを推進することで企業は競争優位性を高めることができます。
顧客や従業員のエクスペリエンス向上
次に、顧客や従業員のエクスペリエンス向上という観点があります。データを利活用すれば、顧客体験(CX: Customer Experience)や従業員体験(EX: Employee Experience)を飛躍的に向上させることが可能です。たとえば顧客データを分析してサービスをパーソナライズすれば、顧客一人ひとりに合った丁寧な対応ができ満足度が上がります。
また、社内に蓄積されている従業員の活動データを活かせば、人材育成や働き方改革にも役立ちます。昨今では、社員のエンゲージメント向上や離職防止のために、タレントマネジメントシステムなどを導入して従業員データを分析・活用する企業も増えてきました。社内のあらゆる業務データを可視化し分析することで、これまで見えなかった問題点を発見し、働きやすい職場づくりにつなげることができるのです。
AI時代におけるデータ基盤の重要性
最後に、AI時代におけるデータ基盤の重要性です。
近年普及しているAI技術も、学習や分析のために大量のデータを必要とします。そのため、AIを効果的に活用するには品質の高い整理されたデータが不可欠です。
データに抜けや誤りが多いままではAIが正確な予測や判断を下せず、せっかくのAIも宝の持ち腐れになってしまいます。
逆に言えば、社内外のデータをしっかり整備しAIに学習させれば、人間には気づけないような予兆を検知したり、業務の自動化・高度化を実現したりできるということです。AIが正確かつ有用な結果を出力するためにも、データの整理・整備が非常に重要となります。
「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れればゴミが出る)」という言葉の通り、入力データが乱雑ではAIも意味のあるアウトプットを出せません。
したがってAI時代を勝ち抜くには、データ利活用の基盤であるデータ管理・整備に今まで以上に注力する必要があります。
企業はデータを適切に扱える人材の確保・育成も含め、社内体制を整備していかなければなりません。データを効果的に活用できる組織こそが、AI技術を最大限活かして競争力を高めることができるのです。
以上のように、DX戦略の鍵、エクスペリエンス向上への活用、AI活用の前提条件という3つの観点から、いまデータ利活用がこれまでになく重視されています。
それでは次に、実際にデータ利活用で成果を上げた企業事例を見てみましょう。具体的なケースから、データの力でどんな変革が起こせるのかを実感していただければと思います。
データ利活用によるエクスペリエンス向上の取り組み【企業事例】
ある企業でカスタマーエクスペリエンス(CX)の向上に取り組んだ事例をご紹介します。戦略的に対外コミュニケーションを設計した結果、顧客体験価値を7倍に向上させることに成功したものの、皮肉にも業界平均を大きく上回る高い離職率という課題が浮上しました。
そこで当社(ソフィア)は、この課題解決に向けて従業員の社内体験(エンプロイーエクスペリエンス=EX)を徹底的に見直しました。入社から退社まで、従業員が経験するあらゆるイベントを洗い出し、それぞれの局面でのモチベーションや心理状態を可視化したのです。
そして現状のEXを分析し、「理想とする従業員体験」を定義した上で、各イベントに対して具体的な施策を実施しました。その結果、離職率の大幅低下に成功し、従業員の定着によりサービスの質が向上したことで最終的には顧客満足度の向上にもつながりました。
このように企業の課題を解決するには、社内に眠るあらゆるデータを「見える化」して利活用することが重要です。データが可視化できていなければ、それはすなわち課題が可視化できていないのと同じことです。
最近ではEXの重要性が増しており、従業員の1日の業務体験や1週間・1か月間の仕事上の流れについても細かく設計し、改善していくことが求められています。
イントラネットや社内報、トップメッセージの閲覧ログなどデジタルツールで取得できる社員の行動データを分析すれば、社員と会社の情報接点を洗い出し、より良い職場環境づくりに役立てることも可能です。
社員のエクスペリエンス向上もデータ利活用の重要な分野であり、これからの人材戦略において欠かせない視点と言えるでしょう。
AI時代に不可欠なデータ整理の重要性
AIをビジネスに活用する上で、データをきちんと整理し整備することが今まで以上に重要になっています。AIは大量のデータを学習して初めて高精度な予測や判断を下せます。
そのため、社内に散在するデータを統合し、形式を揃えて品質を確保する「データの整理」が不可欠です。
たとえばデータに重複や欠損があったり、フォーマットがバラバラだったりすると、AIは誤った学習をしてしまい役に立たない結果を出力してしまうでしょう。逆に、データが正確に整理され一貫性が保たれていれば、AIは適切にパターンを学習し、正確で有用なインサイトを提供できるようになります。
また、多角的な視点で様々な種類の情報を収集してデータ化し整理することで、意思決定の信頼性を高めることも期待できます。複数のデータソースを組み合わせて分析すれば、一つのデータだけでは見えなかった相関関係や傾向を明らかにできるからです。
そのため企業は、データを適切に扱える人材やAIを活用できる人材を確保・育成するとともに、社内のデータ基盤を整備する必要があります。データ利活用を社内文化として根付かせ、全社員がデータの重要性を理解して活用できる環境を作ることが、AI時代に競争力を維持・向上させる鍵となるでしょう。
企業のデータ利活用の現状と課題
一部の先進的な大企業では、社内外の多様なデータを統合・分析し、経営戦略やマーケティングに活用する取り組みが進んでいます。たとえば音声データを分析して顧客対応を改善したり、データドリブン経営によって業績向上を図ったりといった事例も登場しています。
一方で、多くの企業ではデータ利活用に以下のような課題を抱えているのが現状です。
まず挙げられるのが、データの収集や管理にかかるコストの増大です。必要なデータを集め維持するには時間や人手がかかり、そのための費用負担も無視できません。
また「集めたデータをどう活用すればよいかわからない」「投資に見合う効果が得られるか不透明」といった声も多く、データ利活用の方法論やROI(費用対効果)の面で戸惑う企業もあります。
さらに、前述したようにデータを扱う人材の不足も深刻な課題です。データを整理・分析し活用するには専門知識やスキルが必要ですが、そのようなスキルを持つ人材が社内に十分いないという企業が少なくありません。
実際、総務省の調査によれば、パーソナルデータを活用できている日本企業は約52.8%に留まり、データ収集・管理のコストや社会的責任(プライバシー等)、そしてデータを扱う人材の不足が主な課題・障壁として挙げられています。
現代の急速に変化するビジネス環境に対応するには、データを収集・整理して活用することが不可欠ですが、こうした課題に十分対応できない企業では競争力が低下する一因となっています。
また、多くの大企業では社内システムやユーザー数が膨大で、部署ごとにデータ管理方法が異なるため、データを統合することが難しいという問題も顕在化しています。
たとえば各部門が個別に持っているデータがサイロ化(縦割り化)しており、全社横断でデータを共有・分析できない状態では、せっかくのデータ資産を十分に活かせません。とくにID管理が不十分だと同じ顧客や案件のデータが分散してしまい、一貫した分析が困難になります。
こうした状況に直面し、「どこから手を付けてデータを整理し、何のデータを抽出すべきか分からない」と悩む企業も多いのではないでしょうか。
まずはデータ利活用のメリットを社内で共有し、経営層から現場まで「なぜデータが必要なのか」をしっかり腹落ちさせることが重要です。その上で利活用の目的をはっきりと定め、段階的に着手することで、大きな投資をせずとも少しずつ成果を積み上げていけるでしょう。
次章では、収集したデータをどのような目的で活用できるのか、そして活用にはどのような種類があるのかについて解説します。
ビッグデータ活用の目的と種類
データの活用方法にはさまざまな種類がありますが、大きくわけて
「将来を予測・予防するために活用する方法」
「サービスを個別最適化(パーソナライズ)するために活用する方法」
の2種類に分けられます。ここではそれぞれの目的について具体的に見ていきましょう。
将来の問題発生を予見し、予測・予防を行うため
データ分析によって過去の事例や現状の傾向を深く掘り下げれば、様々な状況下で将来どんな問題が起こりうるかを予測することが可能です。
たとえば、不具合やクレームが起きた際のデータを分析することで、「どのような条件下で問題が発生しやすいか」を事前に把握できます。
問題が起きる原因や前兆となるデータパターンをあらかじめ認識しておけば、将来的なトラブルの予測や未然防止(予防策の実施)ができるようになります。
さらに、近年はAIを活用することで、膨大な過去データからリスクを早期に検知することも自動かつ瞬時に行えるようになっています。もちろん、そのためにはAIに学習させるデータ自体が正確かつ信頼できるものでなければなりません。
誤ったデータから得た予測や予防策では意味がなく効果も出ません。データを基に将来の問題を予測し対策を練るのであれば、正しく透明性の高いデータを用いることが必要不可欠です。
個人ごとに情報をパーソナライズされたサービスの向上を図るため
皆さんも、ウェブブラウザで商品サイトを閲覧した後に、別のサイト上でその商品や関連商品の広告バナーが表示される、といった経験があるのではないでしょうか。
これは、ユーザーの閲覧履歴データに基づいて広告内容をパーソナライズ(個人最適化)した結果です。
また、ECサイトで商品を検索すると「あなたにおすすめの商品」が表示されるのも、閲覧者ごとに情報をカスタマイズして提供している例と言えます。これらはデータ活用によって一人ひとりに合わせた情報提供を行い、サービス向上を図った事例です。
このようなパーソナライズの考え方は、実は社内の従業員に対しても有効です。たとえば社員研修において、社員ごとのスキルや経験に応じて最適な学習コンテンツを推薦してくれるLMS(Learning Management System:学習管理システム)を導入すれば、従業員一人ひとりに合わせた教育プログラムを提供できます。
社員データを活用しパーソナライズされた学習機会を提供することで、人材育成の効率と効果を高めることができるでしょう。もちろん、そのためには社員に関する各種データ(スキルや適性、経験、学習履歴など)の収集が不可欠です。
ただし、社員それぞれの個人データを収集し活用することに対しては、プライバシーの観点から不快感や抵抗感を抱く人がいるかもしれません。そこで重要なのは、データ活用によって得られる利便性やメリットを本人が実感できるようにすることです。
たとえば先述のタレントマネジメントシステムのように、人材のスキルや適性を可視化して適材適所の配置や公正な評価に役立てる仕組みについても、現場の社員にはあまり知られていないのが現状です。こうしたシステムの目的やメリットを社員にしっかり説明・理解してもらうことで、パーソナライズへの抵抗感を和らげ、より詳細なデータ提供への協力も得られるようになるでしょう。企業内でデータ利活用を進める際は、プライバシーへの配慮とメリットの周知徹底がセットで必要だという点に留意が必要です。
社内で蓄積されるデータが注目されている
上述のようにマーケティングなど市場向けの分野だけでなく、企業組織内のデータ利活用も近年注目を集めています。社内に蓄積されたデータを活用すれば、人材育成や業務改善、さらには人件費の削減につなげることも可能だからです。
代表的な活用例として挙げられるのがタレントマネジメントシステムの導入です。タレントマネジメントシステムでは、社員のスキルや経験をデータとして見える化し、人材配置や育成に役立てることができます。
たとえば各社員の業務実績やスキル習得状況などをデータ化しておけば、誰を次のプロジェクトリーダーにすべきか、どの分野の研修を充実させるべきか、といった判断が客観的なデータに基づいて行えるようになります。
社員のパフォーマンスや適性がデータ化されれば、人材の最適配置や育成計画を感覚ではなくデータに基づいて精緻に立てられるようになるのです。
結果として、「どの分野にコストや時間をかけるべきか」「成長を妨げている要因は何か」といったことも客観的に把握できるようになります。
もっとも、現在タレントマネジメントに取り組んでいる企業でも、せいぜい人事情報のデジタル化や従業員エンゲージメント調査(アンケート)の活用といった初歩段階に留まっており、データを本格的に活用できている例は多くありません。
たとえば従業員の行動ログデータやオペレーションデータと、アンケートで得られる認知データとを突き合わせて分析し、離職の予兆を察知したり、将来のハイパフォーマーを予測したりする――といった高度な利活用は、まだ発展途上と言えるでしょう。
しかし今後は、従業員に関するあらゆるデータを掛け合わせて分析することで、本質的な予測や継続的な人材マネジメントの改善につなげていくことが期待されています。社内に蓄積されているデータの利活用は、人材戦略のみならず全社の生産性向上にも大きく貢献しうるため、今後ますます重要性を増していくでしょう。
「データを利活用する」とはどういうことか
ここで改めて、「データを利活用する」というプロセスについて整理しておきましょう。ただ闇雲にデータを集めるだけでなく、適切に管理・分析し、得られた洞察をもとに業務や戦略を改善していく一連の流れがデータ利活用です。データを有効活用することで、企業は競争力を高め、より効果的な意思決定が可能になります。データ利活用のプロセスは下記のような段階を経て進みます。
データから知恵への変換プロセス
<データ>
データはただの事実や数値など、未加工の生データそのものです。たとえば売上数字や顧客数、温度計の示す気温など、生の数値記録が「データ」に当たります。
<情報>
データに意味を見出して解釈すれば、それは意味のある「情報」となります。単なる数値の羅列だったデータも、文脈や関連性を与えることで「◯◯の商品は今月100個売れた」というように情報として理解できるようになります。
<知識>
意味のある情報同士がつながり体系化されると、そこから関連性やパターンが見えてきて「知識」が生まれます。
たとえば「平日の売上は休日より少ない」「雨の日は特定の商品がよく売れる」といったパターン認識が知識と言えるでしょう。
<洞察>
蓄積された知識の中から、とくに重要なポイントや本質を見抜くことが「洞察」です。経験豊富なアナリストほど大量の知識から核心を素早く掴む洞察力を発揮できます。たとえば「顧客は◯◯な条件のとき購買意欲が高まる」といった発見が洞察に当たります。
<知恵>
洞察をもとに、多くの知識や情報から最適な判断や行動を選択し、「それをどう活用すべきか理解して実行に移す力」が「知恵」です。ビジネスでは、この知恵を働かせて具体的な施策を打ちPDCAを回すことで成果につなげます。
このように、「データを意味のある情報に変換し、情報同士をつなげて知識とし、そこから重要なポイント(洞察)を見つけ出し、実際に役立つ行動に結びつける」という流れが非常に大切です。
この流れを踏まずに、恣意的に都合の良いデータだけをつなぎ合わせて「データ活用したつもり」になってしまうと、陰謀めいた不透明な意思決定を招き、社員に不信感を与えてしまう可能性も否めません。データ利活用はあくまで客観的で透明性の高いプロセスを踏むことが重要であり、データを扱う際の倫理やガバナンスも忘れてはならないポイントです。
データ利活用のための分析手法
この章では、データを活用する際に用いられる具体的な分析手法について解説します。ビジネスでのデータ分析には様々な手法がありますが、代表的なものとして記述的分析・診断的分析・予測的分析・処方的分析の4つが挙げられます。それぞれ分析で答えたい問いや目的が異なり、組み合わせて活用することでデータから多角的な知見を得ることができます。
記述的分析(Descriptive Analytics)
記述的分析は、蓄積された大量のデータから傾向やパターンを導き出し、「何が起こったのか」を明らかにする分析手法です。棒グラフや折れ線グラフ、円グラフ、表などでデータを可視化し、過去や現在の状態を把握するのに役立ちます。
たとえば小売業であれば、過去数年間の販売データを分析することで売上の季節変動や人気商品の移り変わりなどを把握できます。これにより、需要が高まる季節に向けて在庫を十分に確保したり、販促キャンペーンのタイミングを最適化したりといった戦略策定に役立てることができます。
記述的分析では頻度分布や平均・中央値、分散など統計的な指標を用いてデータの特徴を要約します。組織にとって重要なKPI(重要業績評価指標)をモニタリングする際にも記述的分析が活用されます。
たとえば、Webサイト運営であれば日々の訪問者数やコンバージョン率の推移をグラフ化して追跡し、異変がないかチェックするといった具合です。
また、記述的分析はリソース配分の見直しにも有用です。どの部署やプロジェクトが最も効率的にリソース(人員・予算)を活用しているか、といった点をデータから明らかにすることで、経営資源の最適配分に役立てることができます。
さらに、製造業では生産プロセスのデータを分析して生産ラインのボトルネック(律速工程)や非効率な作業手順を特定するといった応用も可能です。
こうして現状の課題点を洗い出すことで、生産性や品質を向上させる改善策につなげることができます。
要するに記述的分析は、「過去に何が起こったか」を把握し、現状認識や問題発見に役立つプロセスです。一般的な手法としてはデータ集計、データマイニング、データ可視化などがあります。言い換えれば、膨大な過去データを整理して変化や傾向を理解するための帰納的なアプローチと言えるでしょう。
診断的分析(Diagnostic Analytics)
診断的分析は、過去のデータをさらに深掘りし、「なぜそれが起こったのか」の原因を理解しようとする分析手法です。記述的分析で「何が起こったか」を把握した後、その背後にある要因や原因を探る段階と位置付けられます。データの探索的な解析や相関関係の分析、さらには因果関係の検証などを行い、特定の結果が生じた理由を明らかにするのが目的です。
たとえば、ある製造企業で生産ラインに遅延が発生した場合を考えてみましょう。記述的分析では「◯月◯日に生産ラインで遅延が起きた」という事実が掴めますが、診断的分析では「なぜ遅延が発生したのか」を突き止めます。
データを掘り下げて分析した結果、特定の機械の不調が主要因であったと判明すれば、企業はその機械のメンテナンス計画を見直したり予備設備を用意したりといった対策を講じることができます。
このように、診断的分析は問題の根本原因を特定し、より効果的な意思決定をサポートするのに役立ちます。
診断的分析を行うことで、「売上が昨年より減少したのはなぜか」「特定の店舗で顧客満足度が向上した要因は何か」といった問いに答えることができます。
たとえば売上減少の原因を探る場合、地域ごとの販売データや広告施策、競合他社の動向など様々なデータを付き合わせ、何が影響を及ぼしたのかを分析します。その結果、「広告予算を削減したエリアで顧客来店数が落ち込んでいた」等の因果関係を突き止められれば、次回以降の施策改善に直結します。診断的分析はこのようにデータに基づいて問題の原因を解明する強力な手段なのです。
予測的分析(Predictive Analytics)
予測的分析は、過去および現在のデータを分析し、将来の出来事を予測する手法です。
統計モデルや機械学習アルゴリズムなどを駆使してデータ内のパターンや傾向を見出し、それを基に未来の状況を見通します。
ビッグデータの活用やAI技術の発展によって、予測的分析の重要性は近年ますます高まっています。マーケティングから需給予測、リスク検知まで、さまざまな分野で活用が進んでいます。
予測的分析の有名な例として、フィリップ・E・テトロックらによる「超予測力(Superforecasting)」の研究がしばしば引用されます。
彼らはアメリカ政府主催の予測トーナメントでプロの分析官を上回る成績を収め、「歴史は繰り返す」という前提のもと過去の事例を探究し、確率論的思考で新たな条件を加味しながら予測を磨いていきました。このような手法はビジネスにおけるデータ予測でも有効です。
たとえば小売業では、天候データと販売履歴データを組み合わせて分析することで「晴れた日の来店客数」や「雨の日の売上」を予測し、在庫管理やスタッフ配置の最適化に役立てることができます。
予測的分析では統計モデルや機械学習・深層学習などの技術を用いてパターン認識を行います。単純な相関分析を超えて複雑な非線形関係も捉えられるのが機械学習の強みです。
たとえばECサイトでは、顧客の過去の閲覧・購入履歴データを学習したモデルが「次にこの顧客が購入しそうな商品」を予測し、レコメンドに活用することができます。
また、金融業界ではクレジットカードの不正利用検知にリアルタイムの予測モデルが導入されており、異常な取引パターンを即座に察知して被害を未然防止しています。他にも製造設備の故障予知保全や、医療現場での疾病発生リスク予測など、予測的分析は多岐にわたる用途で活用されています。
処方的分析(Prescriptive Analytics)
処方的分析は、予測分析の先を行く手法で、ある状況下で取るべき最適な行動を導き出すことを目的とします。
「最も効果的な意思決定を行うには何をすべきか」を示す分析であり、しばしば意思決定支援システムに組み込まれて使われます。処方的分析では、予測モデルの結果に対してさらに最適化アルゴリズムなどを適用し、目標を達成するための具体的なアクションプランを提示します。
たとえば、医療機関では救急外来の混雑を緩和するために処方的分析が応用されています。
過去の来院データや天候・イベント情報などを総合して患者数を予測し、人員配置や病床の割り当てを最適化するといった具合です。
このように処方的分析は予測の結果を受け、行動すべき指針を示してくれるため、計画策定や自動制御などにも利用されています。
ビジネスにおいては、価格最適化や在庫の自動発注最適化、広告配信の最適化などで処方的分析が活躍しています。
たとえば小売店で「どの商品をいくらに値下げすれば在庫を効率よく捌けるか」を処方的分析で算出したり、Web広告で「予算内で最大の効果を得る配分」を計算したりといったケースです。
処方的分析を実践するには、高度な最適化モデルや大量のシナリオ計算が必要になるため、現状では課題も残されています。
とくに数理モデルの自動化や計算負荷の問題などがありますが、今後量子コンピュータのような技術革新が進めば、これまで解決できなかった大規模な最適化問題も解けるようになると期待されています。処方的分析はまだ発展途上ではあるものの、上手く活用できれば経営判断を次のレベルに引き上げる強力な武器となるでしょう。
データ利活用を実現するデータ基盤構築の進め方
それでは、実際に企業がデータ利活用を進めるにはどのようなステップを踏めばよいのでしょうか。「自社はあまりデータ活用の経験がない」という場合でも、段階を追って取り組めばハードルはそれほど高くありません。
ここでは、データ利活用のステップを5段階に分けて解説します。いずれの段階においても、ポイントは論理的に整理しながら進めることです。
ロジカルシンキングの基本であるMECE(モレなくダブりなく)のように、「分類して並べる」ことで本質が見え、データ利活用に最適な基盤構築へとつながっていくでしょう。
目的設定・計画
まず最初に、「何のためにデータを収集・分析するのか」という目的を明確に設定しましょう。
漠然とデータを集めても、目的が定まっていなければ有効な活用にはつながりません。たとえば最終目標を「売上を増加させる」ことに置くならば、「どんな条件下でどのような施策を取れば売上向上に最も効果があるか」を判断することがデータ収集・分析の目的となるでしょう。目的をはっきりさせることで、データ分析の焦点が定まり、プロジェクト全体に一貫性が生まれます。目的を達成するためには、まず成果に影響を与える要素を漏れなく洗い出す必要があります。
たとえば「店舗の売上」を伸ばしたい場合、売上は大きく来店客数 × 客単価で決まります。来店客数は季節や時間帯、広告キャンペーン、店舗の立地や看板など様々な要因に左右され、客単価も同様に季節・時間帯はもちろん接客の質や商品陳列によって変動するでしょう。
これまで販売時点管理システム (POS)データで行ってきた分析に加えて、店舗全体のオペレーションデータや周辺エリアの人通りデータ、本社側の施策データなども組み合わせれば、より詳細な要因分析が可能になります。
また、目的を具体化する過程で、「現場スタッフが感じている顧客のニーズ」や「サービス品質向上のヒント」「従業員エンゲージメントの状況」など、現場視点の要素も考慮に入れると良いでしょう。
データだけでは見えにくい定性的な情報も含めて整理することで、分析の観点が偏らず抜け漏れが減ります。このように、データ利活用の目的を明確化することで、次に取るべきデータ取得・分析の計画が立てやすくなります。
収集・蓄積
目的と計画が定まったら、いよいよ目的に沿ったデータを実際に集めて蓄積していきます。データ収集の入り口はさまざまです。
顧客に関するデータであれば販売時点管理システム(POS)や顧客管理システム(CRM)、社内業務に関するデータであれば基幹システム、人事系のデータなら勤怠管理システムやイントラネット、導入済みであればタレントマネジメントシステムなどが挙げられるでしょう。
近年はIoTの普及により、製造設備や車両に搭載したセンサーから稼働データや走行データを収集するといったM2Mデータの活用も広がっています。必要なデータは社内だけでなく外部から調達することも重要です。
たとえばオープンデータとして公開されている気象データや人口動態データ、他社とのパートナーシップで得られる市場データなど、自社に不足するデータは積極的に外部リソースも活用しましょう。
こうして集めた多種多様なデータを、一箇所に統合して蓄積することで全体像を掴みやすくなります。
近年はクラウド型のデータウェアハウスやデータレイクなど、様々なシステムを連携してデータを一元管理するプラットフォームが整ってきています。自社内に十分な技術やリソースがない場合は、外部の専門ベンダーに協力を仰ぐことも検討すべきでしょう。重要なのは、後の分析に耐えうるだけの十分な量と質のデータを確保することです。
データの整理・整形
データを収集・蓄積できたら、次は集めたデータを分析に適した形に整理・整形します。具体的には、人間や分析ツールが扱いやすいようにデータの形式や構造を整え、関連するデータ同士を結び付ける作業です。
たとえば日時のフォーマットを統一したり、カテゴリ名のゆれを修正したり、複数のテーブルに分かれているデータをキー項目で結合したりといった処理が含まれます。これらの前処理によって分析の効率と正確性が大きく向上しますが、担当者のスキルや知識によって結果が左右されやすい工程でもあります。
現代社会では扱う情報量が膨大かつ複雑であるため、データを体系的に整理するスキルが必須となります。もしデータの整理を誤ってしまうと、その後の分析結果も誤ったものになってしまうため注意が必要です。適切にデータを整理するためには、情報や知識を体系的に整理し因果関係や関連性を正しく捉える「整理学」の考え方を身につけることが有効でしょう。
具体的には、データ同士の関係をツリー状に分解して整理したり、MECEの原則で漏れや重複がないように分類したりといった手法です。
また、専門のデータエンジニアやデータアナリストの力を借りることも有効です。データのクリーニングや前処理に長けた人材が関与すれば、精度の高いデータ整形が期待できます。社内にそうした人材がいない場合は外部専門家に相談するのも一つの手です。
分析・可視化
データの前処理が終わり分析できる状態になったら、いよいよ本格的なデータ分析に着手します。ここでは設定した目的・課題に合わせて適切な分析手法を選択し、データから相関関係や因果関係を導き出したり、複数の情報を組み合わせて新たな知見を得たりします。
分析の結果、常にウォッチすべきKPIや目標に影響を与える要因などが明らかになったら、それらを一目で確認できるダッシュボードやレポートを作成することも重要です。
意思決定者がすぐにデータの示唆を得られるよう、見やすいグラフやチャートにまとめて組織全体で共有すると良いでしょう。定例会議などで常に最新のデータレポートを参照する習慣を付ければ、データに基づいた迅速な意思決定が根付くだけでなく、そこから新たな気づきや仮説も生まれやすくなります。
市場の変化が激しく将来予測が難しいビジネス領域では、前述の記述的分析で触れたような帰納的推論のアプローチが有効です。
たとえばアンケート調査やユーザーインタビュー、売り場観察からプロトタイプ(試作品)を作り、テストマーケティングを繰り返しながら、その都度データを抽出・分析して仮説検証を行う手法です。
このように小規模実験を重ねてデータから学ぶことで、不確実性の高い市場でも柔軟に対応策を見出せます。
他にも、自社と競合他社のデータを徹底比較して自社の強み・弱みを分析するといった手法もあります。
大切なのは、環境変化に取り残されないようデータに基づいて素早く学習・適応していくことです。データ利活用を継続し、状況に応じて分析手法を組み合わせながら、常に最適な意思決定につなげていきましょう。
ビジネスモデルへの展開
データ分析によって得られた裏付け(エビデンス)や、データが導き出した仮説に基づいて、実際の事業やプロジェクト、ビジネスモデルを展開・改善していくことが最終ステップです。
データ利活用はこの段階で終わりではなく、新たなビジネスモデルや施策からまたデータが生まれ、それをさらに収集・蓄積・分析し、次の改善につなげていく――このサイクルが大切です。
いわゆる「データドリブン」な経営とは、データ分析のサイクルを継続的に回し続けることであり、マーケティング領域では「データドリブンマーケティング」、経営では「データドリブン経営」と呼ばれています。
たとえばマーケティング施策の場合、データに裏付けられた仮説を基に新しいキャンペーンを実施し、その結果得られた反応データをまた分析して次の施策に反映するといった流れになります。このように連続性のあるデータ分析として捉えていただくと分かりやすいでしょう。
もし自社がまだ十分にデータを利活用できていない場合は、まず社内への理解促進から始める必要があります。各部門がデータ蓄積の必要性を感じておらず、分析に耐えうるデータがそもそも整理されていない、といった企業文化・風土の問題があるかもしれません。
その場合は、経営層や担当部門が中心となって「なぜデータ利活用が必要なのか」を社内に啓発し、データを集める土壌を作ることが優先です。
また、データ分析を行う上では「それが従業員にとってどんな利点があるのか」という観点から社内にアナウンスしておくと各部門の協力を得やすくなります。データは時にセンシティブなものですので、とくに個人に関わるデータ提供には抵抗を感じる社員もいるでしょう。
データ利活用の目的やメリットに加え、データ管理の体制についてもしっかり説明し、関係部門と信頼関係を築いた上でデータ提供を受けることが重要です。
以上のステップを踏むことで、企業はデータ利活用の基盤を構築し、成果に結びつけるサイクルを回すことができます。次に、データ利活用の過程で一般的に直面しがちな課題と、その解決策について見ていきましょう。
データ利活用における課題と解決法
データが企業競争力の源泉となりつつある現代において、データ利活用に伴う課題もますます顕在化しています。
ここからは、データ利活用の代表的な課題と考えられるポイントを取り上げ、それぞれに対する解決策を考察します。データの真価を最大限に引き出すために、どのようなアプローチが必要なのかを確認していきましょう。
データのサイロ化
データのサイロ化とは、組織内のデータや情報が部署やチームごとに縦割りで管理・保持され、横断的な共有や活用が困難になる状態を指します。
サイロ化が生じる主な要因として、組織文化の分断、担当者間のコミュニケーション不足、適切なデータ管理システムの不在などが挙げられます。
また、部署ごとにアクセス権限が厳しく区切られ過ぎていたり、そもそも情報共有への意識が低かったりすることもサイロ化を助長します。
データがサイロ化すると、組織内で情報共有が滞り、意思決定の遅れや誤解が生じやすくなります。
各部署がバラバラにデータを管理していると、全社的な最適化よりも部分最適が優先され、ひいては業務効率や顧客満足度の低下にもつながりかねません。
迅速な判断が求められる現代のビジネス環境において、データのサイロ化は放置すると致命的な障害となり得ます。
解決策
まず、組織全体でデータを共有しやすくする仕組みづくりが必要です。各部門・チームが保有するデータの壁を取り払い、横串で連携できる体制を整えましょう。データを部署横断で共有すれば、重複入力や不整合が防げ、全体最適な意思決定が可能になります。また、異なるシステムやデータベースを統合できるデータプラットフォームを導入するのも効果的です。たとえばデータレイクや統合データウェアハウスを構築して、全社で一つのデータソースから必要な情報を取得できる環境を作れば、データの一元管理が実現します。
さらに、データガバナンス(データの品質・セキュリティ管理の方針とプロセス)を確立することも重要です。データ品質基準やアクセス権限、メタデータの管理ルールなどを策定し、組織全体でデータを正しく扱う文化を醸成しましょう。あわせて、全社のデータを俯瞰できるダッシュボードや可視化ツールを活用すると、部署間でデータを共有するハードルが下がります。たとえば経営指標を全社員が閲覧できるようにすれば、共通の問題意識を持ちやすくなり部門間の連携もスムーズになるでしょう。
データの品質管理不足
データの品質管理が不十分だと、正確な分析や効果的な意思決定が難しくなります。データ品質の管理は、データの収集から保存、整理、分析に至るまでの全過程で重要です。
品質の低いデータに基づく分析結果は信頼性を欠き、誤った経営判断を招く可能性すらあります。したがって、データの品質を常に高く維持し正確性・信頼性を確保することが重要です。
たとえば顧客データで住所の表記ゆれや入力ミスが多ければ、顧客セグメント分析を誤解しかねません。センサーから取得する機械データでノイズ混入が多ければ、故障予測モデルの精度が落ちてしまいます。こうした例からも、データ品質管理の大切さが分かるでしょう。
解決策
まず、データの正確性と一貫性を確保するために、データ収集方法や処理プロセスを改善しましょう。たとえば入力フォームのバリデーションを強化して入力エラーを減らしたり、重複データのチェック体制を整えたりといった工夫です。
また、データ保存・管理の面でも適切なセキュリティ対策を講じ、データの破損や改ざんを防ぐことが欠かせません。権限管理やバックアップの徹底も品質確保に寄与します。
次に、データ品質を評価・監視する仕組みを導入しましょう。たとえば定期的にデータ品質チェック(欠損値の割合や不正な値の検出など)を行い、問題が見つかればすぐ対処できるようにします。データ品質向上のためのPDCAを回すことで、継続的にデータの信頼性を向上させることができます。具体的には、月次でデータ監査を行う、品質レポートを作成して関係者に共有する、といった取り組みが考えられます。
さらに、社内のデータ品質に対する意識向上も重要です。データ入力や管理に携わる従業員に対して、なぜデータ品質が大切かを啓蒙し、正しくデータを扱うための研修やガイドラインを用意しましょう。たとえば「この項目の入力ミスが分析結果にどんな影響を及ぼすか」を具体的に示すと効果的です。また、可能であればデータ品質管理の専門チームを設置し、常にデータクリーニングや品質改善に取り組む体制を整えることも有効です。専任のデータスチュワードを置く企業も増えてきています。組織としてデータ品質向上にコミットすることで、結果的に分析の精度が増し意思決定の質も向上するでしょう。
分析リテラシーの欠如
データを適切に理解・活用できる人材が不足している現状を踏まえると、分析リテラシーの欠如は非常に深刻な課題です。
データがあらゆるビジネスの鍵を握る時代において、それを使いこなすスキルが社内に十分でないことは、企業にとって大きなハンデとなり得ます。
データ利活用のプロジェクトが進まない、分析結果を現場が活かせない、といった問題の背景には往々にして「データを読み解く力」「分析の知識不足」が横たわっています。
実際、先述の総務省調査でも「データを扱える人材が不足している」ことが多くの企業で課題に挙げられています。
解決策
第一に、教育とトレーニングの強化が不可欠です。企業や組織は社員に対してデータリテラシーを高める継続的な教育プログラムを提供する必要があります。たとえばデータの正確性・信頼性の重要性、基本的な統計・分析手法の習得、データ可視化のスキルなどを学ぶ研修を実施することです。全社員がエクセルの基本関数を使ってデータ分析できるよう研修したワークマンの例もあります(いわゆる「Excel経営」)。このように社員のデータ活用スキルを底上げする取り組みは、長期的に大きな効果を生みます。
次に、データ駆動型の文化醸成も重要です。データに基づく意思決定を推進し、データドリブンな組織文化を築いていきましょう。具体的には、経営会議で直感よりデータ根拠を重視する姿勢を示す、社内にデータ分析ツールやBIプラットフォームを導入して現場がデータを活用しやすい環境を整える、といった施策です。また、優れたデータ活用事例を社内で表彰したり共有したりすることで、他の社員の刺激とすることもできます。
「データを使うと業務がうまくいく」という成功体験を広めることが、リテラシー向上への近道です。
最後に、外部専門家の活用も検討すべきでしょう。高度なデータ分析スキルを持つデータサイエンティストやコンサルタントの助言を得ることで、組織全体のデータ活用能力を引き上げることができます。たとえばデータ分析プロジェクトに外部の専門家チームを招き、社員と協働でプロジェクトを進めてもらうと、社員は実践的にスキルを学ぶことができます。
また、データサイエンティスト協会では効果的なデータ活用のために以下のようなスキルセットを推奨しています:情報科学の理解と実行力、ビジネス課題を解決する力、データ活用に基づく施策を運用する力。必ずしも社内にこれら全てを備えた専門人材がいなくとも、BIツールや外部サポートを活用すればスキル不足を補えます。自社に足りないピースを外部リソースで埋めつつ、徐々に内製化を進めていくのが現実的でしょう。
目的・目標の不明確さ
企業がデータを収集・分析する際に明確なビジネス目的が設定されていないケースも少なくありません。データを活用すれば得られるメリットは大きい一方、ゴールを持たずに取り組むとリソースの無駄遣いや効果の不明確さを招く恐れがあります。
何のためにどんなデータを集めるのか、どのような分析手法を用いるのかが定まらないままでは、せっかくのデータから得られた洞察や予測も意思決定や戦略に十分活かされない可能性が高まってしまいます。
現場から「分析してみたけれど結局どう使えばいいのか分からない」といった声が出るのは、目的やKPIが曖昧なまま進めてしまった典型と言えるでしょう。
解決策
まず、データ利活用に関するビジョンと戦略を経営層がしっかり策定し、データを活用する目的や具体的な目標を定める必要があります。
たとえば「顧客離れを減らすために契約更新率を5ポイント上げる」「生産リードタイムを20%短縮することでコスト削減を図る」といった具合に、データ活用の明確なゴール設定を行います。
その上で、関連部署やステークホルダーとの協力体制を築くために、組織内のコミュニケーション強化が不可欠です。定期的な部門横断ミーティングや進捗共有の場を設け、目的・目標を全員で共有しながらプロジェクトを進めましょう。こうした情報共有により、目的がぶれず施策の軌道修正もしやすくなります。
また、適切なデータ分析ツールや専門知識を持つ人材を活用することも重要です。ゴール達成に必要な分析を行うには、それに見合ったツールやスキルが必要となります。場合によってはデータサイエンティストのような専門家を配置するか、外部の力を借りて不足を補いましょう。目的達成に向けてチームに必要なリソースを整えることが成功の近道です。
さらに、成果の可視化と評価も忘れてはなりません。データ利活用の成果や効果を定量的に測定し、目標への達成度を把握することで、当初の目的が曖昧にならずプロジェクト全体を適切に修正できます。
たとえばダッシュボードでKPIの進捗をリアルタイムで確認したり、四半期ごとに成果報告会を開いて社内フィードバックを募ったりする方法があります。これにより、目的・目標の不明確さが解消され、今後の方針をタイムリーに修正できるようになります。
適切なツール・インフラの不足
データを適切に活用し価値ある情報を引き出すには、それを支えるツールやインフラが欠かせません。
しかし現状では、ビッグデータを処理・分析するための技術基盤が十分整っておらず、適切なツールやインフラの不足に悩む企業も多くあります。
たとえば膨大なデータを可視化・分析するためのBIツールやプラットフォーム、大量データを高速処理できるサーバーやネットワーク環境が不十分だと、データ利活用の効果が半減してしまいます。
また、セキュリティ対策やデータ保護の観点でも、適切な基盤がないと重要な情報の漏えいリスクが高まってしまいます。このように、せっかくデータ活用に意欲があっても、肝心のツール・インフラ不足がボトルネックとなるケースが散見されます。
解決策
この課題に対しては、まずクラウド技術の活用が注目されています。クラウドサービスを利用すれば、自社内に大規模なインフラを持たなくても必要な計算リソースやツールを柔軟に利用できます。
たとえばビッグデータ処理向けのクラウドプラットフォームを導入すれば、オンプレミス環境の制約を気にせずデータ分析を進めることができます。クラウドはスケーラビリティ(必要に応じた拡張)の面でも優れており、データ量の増加にもスムーズに対応可能です。
また、ビッグデータ処理ツールの導入も重要なポイントです。膨大なデータを迅速かつ正確に処理できる技術(たとえばHadoopエコシステムやSparkなどの分散処理フレームワーク)は、一昔前と比べ利用しやすくなってきました。扱いやすいBIツールやデータ可視化ツールも市場に多数登場しており、自社のニーズに合ったものを選定して採用する企業が増えています。ツール選定の際は、現場の担当者でも直感的に操作できるか、既存システムとの連携が容易か、といった点も考慮すると良いでしょう。
さらに、AI(人工知能)の活用もデータ活用効率を飛躍的に高める鍵となります。AIを組み込むことで、従来人手に頼っていたデータ分析や予測を自動化でき、生産性向上や意思決定の精度向上が図れます。たとえば需要予測に機械学習モデルを導入すれば、これまでは数日かかっていた分析が数時間で終わり、しかも精度が高まるということもあります。AIがもたらす洞察は戦略策定において極めて有益な情報源となるでしょう。ただしAI導入には相応の準備(データの整備や人材育成)が必要ですので、小規模なPoC(概念実証)から始めて徐々に本格導入するのがおすすめです。
以上、データ利活用にまつわる主な課題とその解決策を見てきました。では次に、データ活用を成功に導くためのポイントについてまとめます。組織としてデータ利活用を定着させるために何が重要か、引き続き確認していきましょう。
データ利活用がうまくいくポイント
データは現代のビジネスにおいて重要な資源ですが、その有効活用は決して簡単ではありません。ここでは、データ利活用を成功させるために押さえておきたいポイントに焦点を当て、成功への道筋を探っていきます。
全社的なデータ文化の醸成
データを活用し、意思決定や業務改善に役立てることは組織全体の効率向上につながります。データに基づいた判断を行えば、より客観的かつ的確な方針を立てられるため、ビジネスの成果も上がりやすくなります。
また、社内でデータを共有し共通の事実に基づいて議論することで、部署間の余計な誤解や対立も減り協力体制が強化されます。こうしたデータ文化が全社に浸透すれば、社員一人ひとりがデータ活用のメリットを実感し、組織の競争力強化にもつながるでしょう。
一例として、作業服・アウトドア用品販売で急成長を遂げているワークマンの「Excel経営」が挙げられます。
ワークマンでは全社員がエクセルを使って自社や店舗の状況を数字で把握できるようにし、データに基づく経営を推進しました。数字によるデータは主観や忖度が入り込む余地がないため、誰の目にも問題点や改善点が一目瞭然となります。
実際、ワークマンは基本的なITスキルで実践できるExcel分析を全社に定着させたことで、わずか数年で店舗数を1000店以上に拡大し、2024年3月期にはFC店含め1752億円の売上を達成するなど驚異的な成長を遂げました。
さらに同社は、全社員に数字を公開し透明性を高めることで、顧客ニーズへの素早い対応と心理的安全性の高い職場の両立も実現しています。このようにデータ文化を根付かせた企業は、市場の変化にも柔軟に対応できる強さを持つのです。
もっとも、データに基づく経営といっても最終判断は人間が行う必要があります。ワークマンの事例でも、Excelが出す結果を鵜呑みにせず経営者の目視でチェックするプロセスが組み込まれています。AIの判断もまだ完璧ではなく、データに基づく意思決定には人間の洞察が欠かせません。重要なのは、人とデータの適切な役割分担です。
データは客観的事実を示してくれますが、その意味を解釈し次の行動につなげる「知恵」は人間に委ねられています。データ文化を醸成する際も、単に数字だけに頼るのではなく、数字を理解し活かす人材育成とセットで進めることが大切です。
そうすることで、透明性と心理的安全性が高く、かつ俊敏な意思決定ができる組織体制が築かれていくでしょう。
スモールスタートと迅速な改善
データ利活用を成功させるには、小さな一歩から着実にプロセスを進めることが大切です。はじめから壮大なデータ基盤や高価なツールを導入しようとすると、準備に時間がかかり過ぎたり投資が先行して成果が見えにくくなったりしがちです。
そこで、まずは扱いやすい範囲のデータから分析を始め、少人数のチームや限られたプロジェクトでスモールスタートすることをおすすめします。
たとえば特定店舗の売上データ分析や、簡単な顧客アンケート結果の分析など、手元のエクセルや無料ツールでできることから着手します。小さな成功体験を積むことで組織内の理解も進み、徐々に規模を拡大していくのが良いでしょう。重要なのは、その過程で得られたフィードバックや成果を基に素早く改善を行うことです。
データ活用の効果が現れた部分はさらに伸ばし、うまくいかなかった点は次の施策で修正する、といった素早いPDCAが成功への鍵となります。
たとえば売上分析から仮説を立ててキャンペーンを実施したら、すぐにその結果データを検証し、期待通り効果が出ていなければ施策内容を見直す、といったサイクルをどんどん回します。ポイントは改善を先延ばしにしないことです。数か月単位の長期計画も必要ですが、小さな単位では週次・日次でデータを確認し修正を加えるくらいのスピード感が望ましいでしょう。
とくにデジタル分野では、市場環境の変化も早いため、データを活用してアジャイル(俊敏)に対応する姿勢が求められます。
また、チーム全体での情報共有と意思疎通も欠かせません。小さく始めたデータ活用プロジェクトで得られた知見や改善結果は、チーム内ですぐ共有しましょう。
成功事例は組織内に水平展開し、失敗事例からは教訓を抽出して皆で学びます。現在は社内SNSやコラボレーションツールも普及しているので、そうしたプラットフォームで気軽にナレッジ共有する文化を作るのも一手です。
スモールスタートで出た成果を迅速に全社に広めることで、次に取り組む別のプロジェクトの成功確率も上がります。
要するに、「小さく始めて素早く回す」ことがデータ利活用成功のポイントです。
大上段に構えるのではなく、手近なところからデータを使ってみて、結果を見ながら柔軟に軌道修正していきましょう。この積み重ねが、やがて大きな全社変革につながっていくのです。
経営層のコミットメント
データ利活用を本格的に推進するには、経営層のコミットメント(関与と支持)が欠かせません。
トップマネジメントがデータ活用の重要性を理解し、自ら率先して推進する姿勢を示すことで、組織全体にデータ活用文化を根付かせることができます。経営層が明確なビジョンを示しリーダーシップを発揮すれば、各部門の責任者や現場社員もその意図を理解し協力して取り組むことが可能となります。
逆にトップがデータ活用に消極的だと、せっかく分析チームが良い提案をしても採用されなかったり、現場がデータ提供に協力しなかったりと、文化は醸成されません。
経営層がコミットするメリットは、組織全体がデータを活用して迅速かつ正確な意思決定を行えるようになることです。
データに基づいた意思決定は勘と度胸だけに頼るものより客観的で効果的な場合が多く、企業の競争力強化につながります。トップダウンでデータ活用を推奨することで、重要な経営判断にもデータが組み込まれ、企業戦略がより科学的・合理的になるでしょう。
とくにDX推進を掲げる企業では、経営トップ自らがデータを見て判断する姿勢を示すことが、DX成功の鍵となるケースも多いです。
たとえば定例の経営会議で必ずデータレポートを確認してから議論を始める、といった習慣をトップが率先して取り入れるだけでも効果があります。「社長がデータを見ている」と分かれば、各部門長も準備にデータを揃えるようになりますし、自然とデータ品質にも気を遣うようになります。
もちろん経営層のコミットメントといっても、トップ自らが細かな分析作業を行う必要はありません。重要なのは、リソースと権限を適切に与えることです。
データ活用プロジェクトに十分な予算を付け、人材を配置し、場合によっては組織横断のプロジェクトチームを結成して推進する、といった意思決定を行うことです。
経営層がコミットしているプロジェクトだと社内で認識されれば、各部門からの協力も得やすくなります。
さらに結果が出れば経営トップが評価し、成功すれば賞賛・失敗しても次への学びとしてフォローする、といった姿勢を見せることで、社員も安心してチャレンジできる風土が生まれます。
総じて、経営層の強いコミットメントがある組織は、データ利活用に対して一貫した方針と十分なリソースを持って取り組めるため、成功する確率が格段に高まります。トップダウンとボトムアップの両輪でデータ活用を推進し、全社の知恵とデータを結集して課題解決や価値創造に邁進していきましょう。
KPI(重要業績評価指標)の設定と情報共有の透明性
データ利活用を最大限に活かすためには、KPI(重要業績評価指標)の適切な設定と、データや指標に関する透明性の高い情報共有が重要なポイントとなります。KPIを明確に定めることで、企業が目指すべき成果や進捗状況がはっきりし、データ分析の焦点が絞り込まれます。
具体的な数値目標を持つことで、データ収集や分析のプロセスにも一貫性が生まれ、効率的にプロジェクトを進めることができます。
たとえば「顧客解約率を◯%削減する」「製造不良率を◯%以内に抑える」といったKPIを設定すれば、何を分析すべきかが明瞭になるでしょう。
さらに近年、GoogleやAmazonなどGAFAMのリーダーたちによって「コンストラクタル」という考え方が提唱されるようになりました。
コンストラクタル理論によれば、川が海に向かうとき最も流れやすい経路を取るように、情報もできるだけ滑らかに社内を流れることが望ましいという考え方です。
滞りのないスムーズな情報共有は、企業内外の透明性を高め、信頼獲得・意思決定の効率化・イノベーション促進といったメリットにつながります。つまり、データやKPIに関する情報を組織内でオープンに共有することが、結果的に組織力を強化するのです。
具体的には、KPIの達成状況や分析結果を社内の関係者全員が見られる状態にすることが挙げられます。
たとえば営業部門・製造部門・管理部門など、それぞれが自部署のKPIだけでなく会社全体の重要指標をリアルタイムで確認できるようにします。KPIの透明性を高めることで、組織内に共通理解が生まれ、意思決定の根拠も明確になります。
結果として、部門間のサイロ化を防ぎ、目標達成に向けた協力体制が整いやすくなります。
さらに、データ分析の結果やプロジェクトの進捗に対する信頼性も向上し、迅速かつ的確な意思決定を支える基盤となります。社員同士が「今どの数値が目標に届いていないのか」「何が課題なのか」を共有できれば、議論も建設的になり、みんなで問題解決に向けた創意工夫を発揮しやすくなるでしょう。
要するに、KPIの設定と情報共有の透明性は、データ利活用を組織に根付かせ大きな成果を上げるための鍵となります。適切な指標を定め、それを組織の隅々まで見える化し共有することで、データから引き出せる価値を最大限に高めることができるのです。ぜひこの点を意識して、データドリブン経営を推進してみてください。
データ利活用の改革事例
すでに多くの企業がデータ利活用に踏み出し、成果を上げています。それもIT企業だけでなく、メーカーや食品、飲食業など実に様々な業界で見られます。ここからは具体的な企業事例を6つ紹介します。各社がどのようにデータを活用し、どんな効果を得ているのかを見ていきましょう。自社のデータ活用のヒントとしてご活用ください。
スシロー:売上データを分析し品出しの量をコントロールした結果…
回転寿司チェーン大手のあきんどスシローは、システム活用に非常に積極的な企業です。現場の勘や経験を軽視せず、むしろそれらの感覚をシステム化しようと試みている点が特徴的です。同社では、他チェーンに比べレーンに流す寿司の種類・量が非常に多く、その結果廃棄ロスが大きいことが長年の課題でした。そこで全く手付かずだった約400億件にも及ぶ寿司の売上データを分析・活用し、流す商品の種類や量をコントロールする仕組みを導入しました。その結果、年間で億単位のコスト削減に成功しています。また、この膨大なデータを活かして売上分析や新商品の開発も行われており、データ利活用の好例と言えるでしょう。寿司業界のような一見アナログに思える業態でも、データによる最適化が大きな効果を生むことを示した事例です。
富士通:気象・環境データを解析し収穫量を予測した結果…
大手総合電機メーカーの富士通は、農業分野でのデータ利活用に取り組んでいます。2012年に提供を開始した「食・農クラウドAkisai」というクラウドサービスでは、農作物の栽培や施設園芸、畜産業務における生産活動や経営を支援するアプリケーション群を展開しました。富士通は農業生産者やJA、流通業者、自治体などにこのサービスを提供し、作業実績や栽培状況、環境センサーや気象データなど多様なデータをクラウド上に収集・分析できるようにしました。たとえば温室の温度・湿度データをモニタリングして自動制御したり、生育データから収穫量を予測したりといったことが可能になり、サービス利用者である農家の生産効率向上やコスト削減に貢献しています。産業分野の異なるデータを統合し、新たな価値を生み出した好例と言えるでしょう。
ダイドードリンコ:アイトラッキングデータを分析し、陳列方法に新たな発見が…
飲料メーカーのダイドードリンコでは、自動販売機での売上向上にデータ利活用を役立てています。同社は自販機の商品の陳列方法を決める際に、ユニークなアイトラッキング・データを活用しました。アイトラッキングとは、人がどこを見ているかを追跡する技術で、消費者が自販機で商品を買う際に視線がどの商品に向かうかをデータ化したのです。その結果、飲料業界で長らく常識とされていた「Z型陳列(左上から右下に視線が動く配置)」よりも効果的な配置が判明し、自社データを基にした新しい陳列パターンを導入しました。これにより売上が実際に増加し、従来の常識をデータで覆した事例として注目されました。現場の思い込みにとらわれず、データに基づいて施策を変えることの重要性を示しています。
大阪ガス:車両走行データを活用し、現場のお客様対応が迅速に
関西圏のガス供給大手大阪ガスは、データ分析を強みとしてビジネスに貢献する社内専門部署「ビジネスアナリシスセンター」を設置しています。
この部署はデータ分析によるソリューションを社内に提案・導入するミッションを担っており、業務プロセスの改善に大きな役割を果たしています。たとえば、業務用サービス車両の待機拠点をGPS走行データから最適な場所に選定し、お客様対応の迅速化につなげるなど、実際に大きな効果を上げています。このように専任組織を作って分析結果を経営に活かす取り組みは、日本企業でも徐々に増えつつあります。大阪ガスの事例は、伝統的なインフラ企業においてもデータ活用が価値創出につながることを示しています。
野村証券:Xの投稿内容を集め独自の解析方法で景気動向を読む
大手証券会社の野村証券は、経済指標調査にSNSデータとAIを活用する革新的な試みを行いました。具体的には、旧Twitter(現X)のAPIを利用して投稿内容を収集し、それを指数化して景況感指数として活用しています。
この取り組みでは、投稿データから有用情報を抽出するAI(抽出AI)と、抽出データから景気感を評価するAI(評価AI)を組み合わせて運用しました。その結果、従来のアンケート調査に比べ大幅なコスト削減と迅速な情報発信に成功しただけでなく、毎月15,000件ものサンプルデータを収集することも実現しています。
SNSのビッグデータを経済分析に活かしたユニークな例であり、リアルタイム性とコスト面で優れたアプローチとして注目されました。異なるデータソースを組み合わせて新しい指標を作り出すという、データ利活用の可能性を示す好例です。
ワークマン:AIによる需要予測で在庫管理の精度が上がる
前述でも触れましたが、作業服・アウトドアウェアで知られるワークマンもデータ利活用の成功例として外せません。同社は従来「Excel経営」で有名でしたが、2020年代に入りさらにAI技術の導入を進めています。全社員に対するエクセル研修で社内のデータ分析力を底上げした上で、近年では需要予測にAIを取り入れ始めました。
たとえば各店舗の売上や在庫データなどをAIで分析し、商品ごとの需要を高精度に予測することで、発注業務の効率化や欠品防止を図っています。Excelによるデータ文化を基盤としつつ、さらに高度な分析手法へと挑戦しているわけです。
このように段階的にデータ活用を深化させていく姿勢は、多くの企業にとって参考になるでしょう。ワークマンの例からは、社員教育によるリスキリング(データ人材育成)と、新技術活用による分析高度化の両面がうかがえます。情報共有の円滑化や社員の意識改革など、Excel経営で培った文化を土台に、DXの次なるフェーズへ進んでいるのです。
以上、6社の事例を紹介しました。どの企業もそれぞれの業界・業種特有の課題に対し、データ利活用によって革新的な解決策や新たな価値創出を実現しています。「自社の業界ではデータ活用なんて難しい」と思われる方も、ぜひこれらの事例をヒントに、自社データの眠れる力を引き出す方法を検討してみてください。
まとめ
データ利活用は、DXやAIが叫ばれる現代において企業の競争力を高める重要な手段です。データを収集・分析してビジネスに活かすことで、効率的な意思決定や新たな価値創出が可能になります。ただし、多くの企業で人材不足やデータ整備不足などの課題も存在するのが実情です。
データ利活用を成功させるためには、目的の明確化や全社的なデータ文化の醸成、スモールスタートによる素早い改善、そして経営層の強力なコミットメントが重要となります。実際に紹介したような先進企業の事例を見れば、データの力で業務効率化や顧客満足度向上、さらには新ビジネス創出までも実現できることがわかります。
ぜひ、自社に蓄積されたデータに目を向け、積極的なデータ利活用に取り組んでみてください。それが企業の未来を切り拓く大きな一歩となるでしょう。
関連サービス