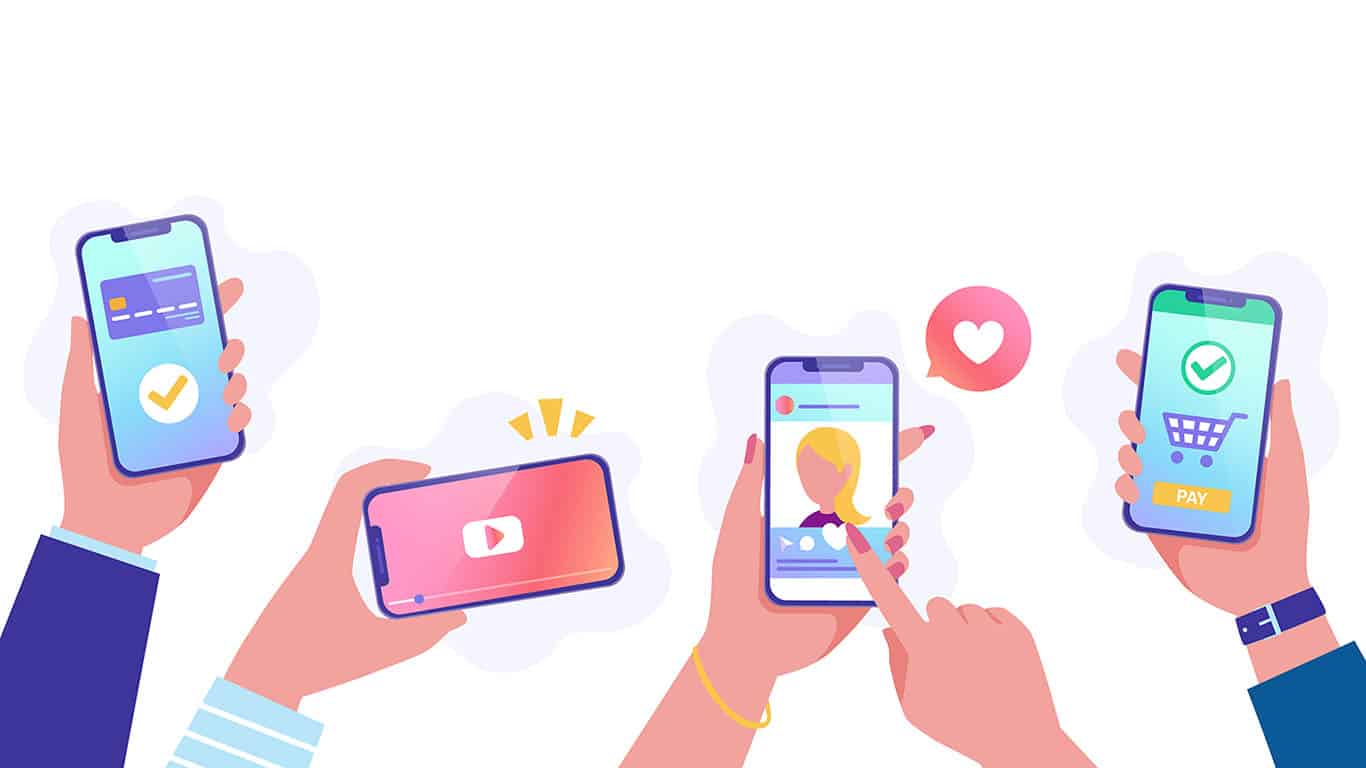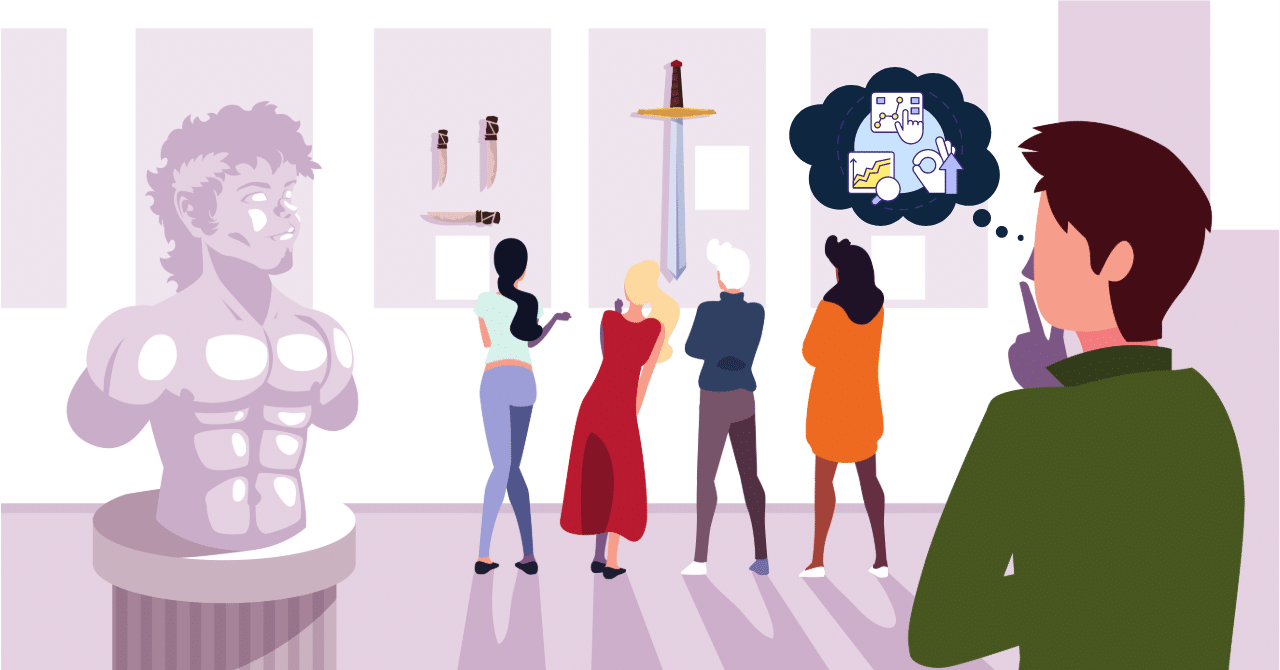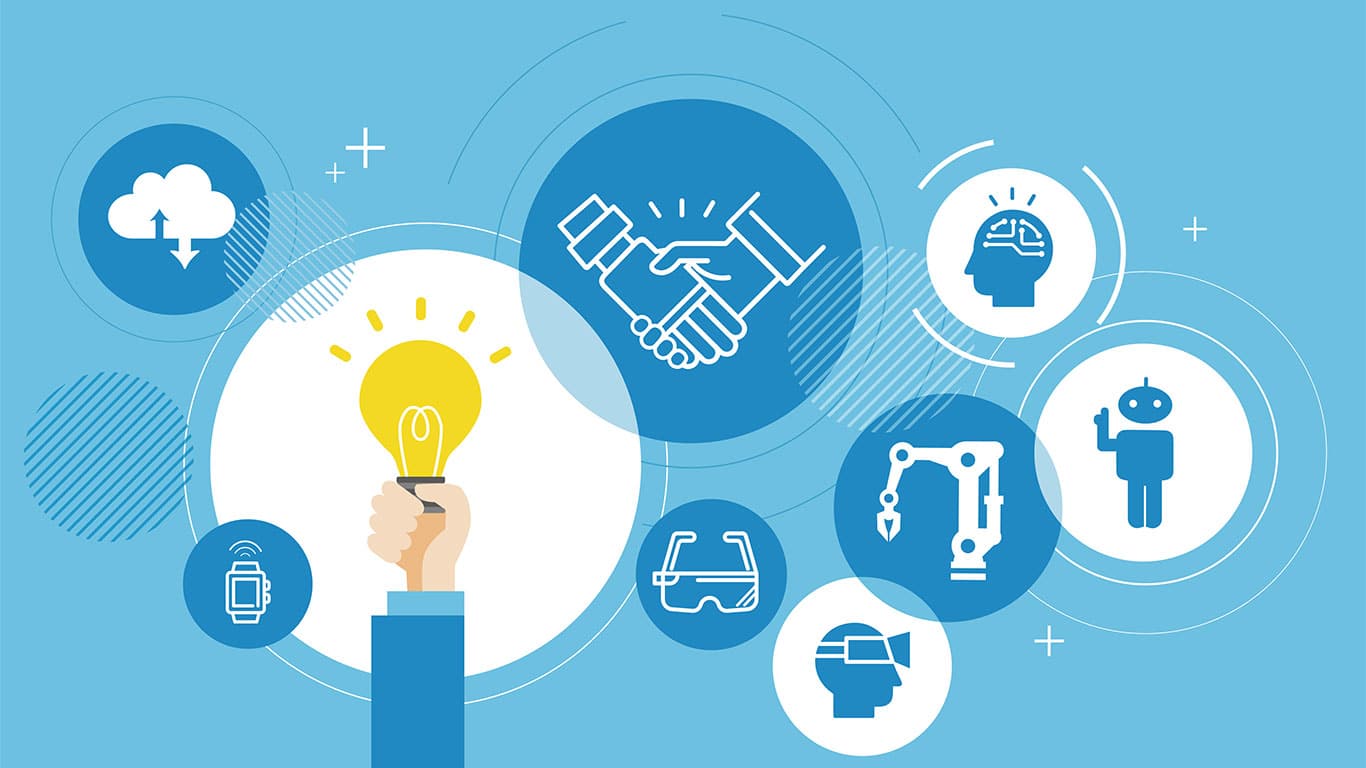ビジネスにおけるエンゲージメントとは?言葉の意味や高める方法について詳しく解説
最終更新日:2024.10.16

目次
「エンゲージメント」は、社員と企業・組織などのつながりを表す概念です。昨今のビジネスシーンで注目を集めており、人事領域では当たり前になりつつあるエンゲージメントですが、その全体像を掴み切れていない人も多いことでしょう。本記事では、エンゲージメントの概要やメリットをはじめ、エンゲージメントの高め方などについても詳しく解説します。
エンゲージメントとは?
現在、6割を超える日本企業が第三次産業に従事しており、とくに人的サービスを提供する企業は人手不足に陥っています。離職率が高いことが原因の1つですが、そこには企業・組織とのつながりを表すエンゲージメントが関係しています。
離職率が高まる理由はさまざまですが、エンゲージメントの側面から斬り込むと、労働者が定着する理由は給与・待遇だけではないことが見えてきます。一体、エンゲージメントとはどのような概念なのでしょうか。掘り下げてみていきましょう。
エンゲージメントの意味
エンゲージメントは、「エンゲージ」という動詞から創られた名詞です。エンゲージは、「関わり合う」「従事する」「交流する」という意味の動詞です。この動詞には積極的に他者や社会に関わっていこうという意味が含まれています。2000年代には、「コミットメント」という言葉がよく使われていました。しかし、コミットメントには、「責任を取る」の意味が強くあり世界的にも敬遠されるようになり、エンゲージメントという言葉に落ち着きました。
それ故、エンゲージメントには、「誓約」「約束」「契約」「婚約」といった意味が含まれるようになりました。近年ではビジネスの現場でも使われるようになり、社員エンゲージメント・顧客エンゲージメント・ワークエンゲージメントなどが代表的です。エンゲージメントには、明るく前向きに積極的に関わろうという意味があり、これがありうべき職場の雰囲気としてふさわしい言葉になったと思われます。
たとえば、企業と社員との関係性で用いる場合には、社員が企業に対して抱く「思い入れ」や「愛着」を指します。関係性上のつながりの深さを示す概念とも言え、エンゲージメントが高いほどより強く結びついている=離れる可能性や反発する可能性が低くなるとも言えます。
エンゲージメントは社員が企業に貢献する意欲や、仕事に対するコミットメントにも影響を与えるため、経営において重要な課題の1つになっています。愛社精神といった言葉もありますが、終身雇用が崩壊しつつある現代社会では、社員はポジションや待遇以外に企業を選ぶ理由を探すようになりました。そのため企業は、給与や役職だけでなく、社員に「この企業で働きたい」と思ってもらえる状況を作らなければなりません。
社員が企業を選ぶ理由は複雑であり、理念・経営方針などへの共感、人間関係、業務内容など、複数の要素をチェックし、総合的に判断しています。年収や役職、キャリアプランを提示するだけでは現代のビジネスパーソンを雇うことは難しいでしょう。また、転職が当たり前となった今、自社内に引き留めておくことも困難になってきています。
そこで役に立つのが、「思い入れ」や「愛着」に着目したエンゲージメントの概念です。エンゲージメントを意識することにより、ポジションや待遇だけでなく、「やりがい」「生きがい」といった目に見えない要素を含めて雇用条件を提示できるようになるでしょう。
また、エンゲージメントは顧客と企業、社員と仕事といった関係においても適応できます。社員と企業の関係と同じように、金額・サービス内容・業務内容など具体的な要素以外の、目に見えない感情的・感覚的な要素を考慮した、深い関係構築に役立つでしょう。
エンゲージメントの起源
人事の領域におけるエンゲージメントの概念が生まれたのは、1990年代のアメリカです。当時、アメリカ国内の企業での生産性への意識の高まりもあり、いかに社員が企業にエンゲージできる環境を用意するかという部分に着目したのが始まりです。
そのことを予言するかのように、ボストン大学の心理学教授ウィリアム・カーンは、1990年に発表した論文の中で、社員エンゲージメントについて次のように定義しています。
- 「組織で働く人々が自己を仕事上の役割に活かすこと」
- 「エンゲージメントをすることで、役割遂行中に身体的・認知的・感情的に自身を用い、表現すること」
エンゲージメント誕生以前は、社員に対し、給与・福利厚生を用意することで、仕事へのパフォーマンスが向上すると考えられていました。ですが、現実は異なり、社員が求めている雇用上の待遇を用意しただけでは、生産性向上につながらないケースが多々あったのです。
これは、考えてみれば当たり前のことで、昔から言われているように「人はパンのみに生きるにあらず」ということです。給与や待遇は良ければ越したことはありませんが、社会にある程度の富が行き渡り、皆が車を所有し必要な家電製品も揃っている今、給与を挙げて社員を引き留めようとする考え方は、時代遅れとして捨てられるでしょう。
この点については、ウィリアム・カーンのエンゲージメントへの考え方を参考にするとわかります。待遇だけでなく、社員の仕事への愛着・感情・企業への思い入れなどを含めた、情緒と身体性が発揮される場を用意することで、社員の仕事のパフォーマンスを引き出すことができたのです。
また、1993年には、アメリカの心理学者フランク・L・シュミットらが発表した論文の中でも社員エンゲージメントが登場しています。「仕事への満足度」の概念に対してエンゲージメントの重要性を説き、社員を雇用し続けるためには、エンゲージメントを意識した組織作りが必要であると主張しています。これは、仕事の満足度と組織へのコミットメントという、古典的な概念を統合する新たな組織論における概念となりました。
そんなエンゲージメントですが、日本国内の企業で導入されるようになったのは、少し遅れて2000年代に入ってからです。最初は外資系企業などから普及し、その後、景気の悪化や雇用の不安定化に伴い、国内企業でもエンゲージメントについて意識するようになりました。
ビジネスにおける「社員エンゲージメント」とは
エンゲージメントが当てはまる領域は広義ですが、ビジネスでは主に人事領域で用いることが多くなります。人事領域におけるエンゲージメントは「社員エンゲージメント」と呼ばれ、企業と社員の信頼関係の度合いや、社員の仕事・企業への愛着心を指す概念です。
また、ビジネスでは顧客エンゲージメントという概念も注目されており、こちらは自社のサービス・商品を購入してくれるユーザーや取引先企業との、信頼関係や愛着心について示したものです。
ここからは、さらに踏み込んで、ビジネスにおける社員エンゲージメントとはどのようなものなのか見ていきましょう。
エンゲージメントの日本の歴史
日本国内のエンゲージメントを語る上で重要になるのが、ビジネス史の変遷です。1970年代より高度経済成長を遂げる日本ですが、1980年代に入るとその勢いは加速し、バブルの煽りも受けてビジネス環境が急速に変化、多国籍企業が台頭し、国内企業もグローバル競争に参加することとなります。
この時期の日本の企業は、商品・サービスの品質向上に着目し、良い物を消費者・顧客に提供することで顧客満足度を向上させることを試みていました。
しかし、1990年代に入ると、商品・サービスの品質向上だけでなく、消費者・顧客といかに長期的かつ持続的な関係を作れるかに着目し始めます。ここから、現在まで続く1人ひとりの消費者・顧客に対し適切な対応を行う「顧客関係管理 =顧客管理システム(CRM)」の時代が始まっています。
その後、2000年代に突入すると、企業側から消費者・顧客に向け商品・サービスを提供する一方的な関係から、相互的な関係を構築することへ変わっていきます。この時期からは、消費者・顧客との対話機会を設けたり、協力関係が結べる仕組みを用意したりすることで、顧客エンゲージメントを高めるようになりました。
ここで解説したものは顧客エンゲージメントですが、社員エンゲージメントについても、似た流れを辿っています。
1990年代前半までは職能資格制度・年功序列システムにより、終身雇用という安定・安心できる待遇(商品・サービスでいう品質)で社員の愛社精神を強めていました。しかし、1990年代後半になると、バブル崩壊・ゼロ成長・就職氷河期世代の登場など社会的背景もあり、社員満足度という広義で包括的な概念を雇用に取り入れ始めます。これはつまり、社員と企業との間の「顧客関係管理 =顧客管理システム(CRM)」とも言え、より個人の主義主張、パーソナルな部分を重要視する雇用の流れになったことを表します。
顧客満足度を高めるためには、従業員満足を高める必要があるということに気づくことは自明の理でありました。製造業主導の輸出型からサービス業主導の内需型に日本の産業構造が変化していくタイミングであり、価値やサービスの提供する主体が機械からヒトに変化するタイミングでもありました。顧客満足を生み出すのはヒトであり、この「ヒト」つまり従業員が満足なりエンゲージメントすることは重要な経営の要素でした。
当時も従業員エンゲージメントと相似形の従業員満足度の研究も盛んになり、社員満足度や組織コミットメントという言葉で研究が国内の実証研究や国際比較もされました。この段階で、既に、日本の終身雇用と緩やかな賃金上昇は問題として指摘されており、入社7年目~10年目に転職が今ほどではないながらも多いことは傾向として存在していました。
具体的には、入社7年目~10年目で、一通りの仕事はこなしある程度は自走的に業務をこなせるようになっている中で、社員の成長や仕事のやりがいが、賃金や職責が見合わず、社員は「賃金が低い」「やりがいない」という人が増え、優秀な人財から転職したりするようになりました。ここで、昇給や昇格があれば、新たな職責や賃金上昇がある社員に関して、この不満は解消されるのですが、業容拡大しなくなり低成長になっている日本企業は、賃金や職位や職責を提供できなくなっていたというわけです。
従業員満足度や組織コミットメントの内容は、企業と社員という関係の内容が多く、現在の社員エンゲージメントは、会社ということよりは、職場やチームもしく、課題に対する関係に変化していきます。
さらに2010年代以降になると、社員エンゲージメントという概念が登場し、より企業と社員が対等な関係に変わり始めます。非正規雇用の拡大・ブルーカラーの切り捨て・ブラック企業・少子高齢化など、複数の社会的背景が原因です。そのため、働き方改革など政治介入を含めつつ、社員と企業の関係性、社員が抱く企業・仕事への愛着や愛情、やりがいといった要素が、社員エンゲージメントという概念を通して重要視されるようになりました。
従って従業員満足度より従業員エンゲージメントの方が、商品やサービスと人が直結するような内容に現在は変化していると言えますし、よりチームや職場の社員が直接的に認識できる範囲の設問が増えています。
しかし、社員がエンゲージする対象は、職場やチームもしくは商品やサービスの価値に直結し始める中で、職場やチームをマネージする組織や企業はエンゲージメントにおいて何ができるのか?また職場やチームは社員に対して何をすればエンゲージメントさせることできるのか?という疑問が浮上してきます。
社員は組織の何に対してエンゲージメントするのか?
社員が企業にエンゲージメントすることが重要とお伝えしましたが、具体的に社員は企業・組織の何に対してエンゲージメントするのでしょうか。その手がかりとなるのが、吉森賢氏の「日米欧の企業経営 – 企業統治と経営者」の中にある「企業はだれのものか-企業概念の日米欧比較」の中に記述された1991年のアンケート調査です。
「会社は誰のために存在するのか」の問いに対し、英米の多く人は株主のためと回答し、日独の多くの人は利害関係者のためと回答しています。これは、それぞれの国の国民によって企業や組織の存在理由が異なっていることを示唆しています。つまり、社員が企業・組織の何に対してエンゲージメントするかも国ごとに異なる事実を表していると言えます。
現在の日本の企業・法人は、機械や工場といったツールを資本の主軸にしておらず、人的資本を重要な位置付けにしています。テクノロジーの進歩や社会通念の変化に伴い、事業の推進や社会課題の解決における会社規模・財力・物的な資本力の優位性が下がっており、個人がつながり人が集まる場としての企業・組織の意義が高まっているからです。
これはつまり、1991年の調査「会社は誰のために存在するのか」の日本人のアンケート結果「利害関係者のため」の延長線上にあるとも言えます。日本企業の社員は、企業を利害関係者=企業・社員・その他関係各所とのスムーズな連携ができる場として捉え、個人が自己実現・やりがいなどを達成できる場所として、企業・組織が存在するという意識が強まっていることが分かります。
これらの事実を考慮すると、企業の理念・経営方針をはじめ、事業内容・解決を目指す社会課題、そして一緒に働く仲間や職場環境を総合し、雇用者と雇用される側の相互的な関係性そのものに社員はエンゲージメントしていると言えるでしょう。また、雇用者である企業・組織側も、社員に対してエンゲージメントの意識を持たなければなりません。給与・待遇だけで社員を惹きつけることはできなくなったのが、現代の企業・組織と社員の関係だからです。
社員エンゲージメントとワークエンゲージメント、組織コミットメント及び社員満足度
社員エンゲージメント・ワークエンゲージメント・組織コミットメントは、社員の態度と行動に関する概念で共通点がありつつも、それぞれ異なる側面があります。
共通点としては、社員の態度や行動への焦点、職場のパフォーマンスへの影響、組織の成功への貢献が挙げられるでしょう。異なる点としては、組織コミットメントが社員の組織への心理的結びつきに焦点を当てることに対し、社員エンゲージメントは業務・理念・チームなど広範囲に対象が及ぶことです。また、ワークエンゲージメントは個人の仕事やタスクへの情熱・熱意に特化しているため、組織コミットメント・社員エンゲージメントとはまた異なる部分への焦点と範囲を対象としています。
これらの概念は、似ているようで対象としている要素が違うため、社員エンゲージメントの指標としても意味が変わってきます。
社員エンゲージメントとワークエンゲージメント
では次に、社員エンゲージメントとワークエンゲージメントの具体的な違いについて見ていきましょう。ワークエンゲージメントとの違いは、言葉の意味からも何となくわかりますが、エンゲージメントに関しては混乱しやすいため、整理しておきましょう。各エンゲージメントの定義・特徴を以下に解説します。
社員エンゲージメントの定義:社員が自分の仕事・同僚・組織全体に対し、どの程度の意識・精神を持ってつながっているかを表す概念です。言い換えると、仕事への熱意、企業そのものや企業文化への愛情、同僚・上司との関係性に対する愛着心と言い表せます。
社員エンゲージメントの特徴:対象が広範囲に及んでいることが大きな特徴で、仕事だけでなく、企業の文化・リーダーシップ・提示するキャリアなど、広義にその判断基準が設けられています。
ワークエンゲージメントの定義:個々の社員が、担当する仕事や職務に対して感じる情熱・熱意・やりがいなどを指します。これは主に仕事の内容と実行性、自分の意思で物事が決められる裁量の範囲などが関係しています。
ワークエンゲージメントの特徴:特定の仕事・プロジェクト・事業などに対し、社員がどれだけ関与できるかに特化しており、組織全体ではなく個々の社員の仕事やタスクに焦点を当てていることが特徴です。
続いて、社員エンゲージメントとワークエンゲージメントの違いを見ていきましょう。違いは以下の2つです。
焦点の違い:社員エンゲージメントは、企業・組織全体と社員のつながりや関係性に焦点を当てます。対してワークエンゲージメントは、特定の仕事・プロジェクト・事業に対する個々の社員の情熱・熱意・やりがいなど熱量に焦点を当てています。一言で言えば、社員エンゲージメントは職場に愛着を持てるかどうかであり、ワークエンゲージメントは仕事に愛着を持てるかどうかだと言えるでしょう。
社員エンゲージメントとワークエンゲージメントの違いを理解することは、社員が仕事へのモチベーションを高めることはもちろん、企業・組織が経営戦略を立てる上でも重要です。社員エンゲージメントが企業・組織全体の視点から形作られることに対し、ワークエンゲージメントは個々の社員の業務・プロジェクトにフォーカスしてアプローチすることが大切です。
社員エンゲージメントと組織コミットメント≒社員満足度
次に、社員エンゲージメントと組織コミットメントの違いについて見ていきます。こちらも混乱しやすい概念で、似ている部分も確かにありますが、根本的には異なる概念です。とくに、人事や社員管理を行う際は違いを理解しておくことが大切です。
社員エンゲージメントは、社員が抱く仕事への熱意、企業そのものや企業文化への愛情、同僚・上司との関係性に対する愛着心など、総合的な企業とのつながりの強さの多寡を表す概念です。企業・組織とのつながりを軸に、社員が日々の仕事でのパフォーマンスの発揮し、積極的な関与の姿勢が見られるかどうかの指標でもあります。社員エンゲージメントを高めることで、生産性アップ・創造性の発揮・顧客満足度の向上といった効果が期待できます。
組織コミットメントは、社員が企業や組織に対して抱く、心理的な結びつきの強さや忠誠心を表す概念です。組織コミットメントは、さらに以下の3つのコミットメントに分解することができます。
- 企業や組織への愛着や自己との同一性(情緒的コミットメント)
- 企業や組織への依存による縛りが発生(継続的コミットメント)
- 企業や組織に対して抱く義務感や責任感が強い状態(規範的コミットメント)
組織コミットメントが強まることで、社員が長期的に企業や組織に貢献し続ける状態を生み出すことができ、こちらも生産性アップ・創造性の発揮・顧客満足度の向上といった効果が期待できます。
似た結果を生み出す2つの概念ですが、社員エンゲージメントと組織コミットメントには大きな違いがあります。それは社員エンゲージメントが社員満足度と比較的相関することに対し、組織コミットメントは相関しない場合も多い点です。組織コミットメントは、待遇や義務感・責任感によって企業や組織に社員を縛り付けてしまう側面があり、やりがいや納得感を持って働いているとは限らないためです。
社員エンゲージメントと組織コミットメントの根本的な違いはこの部分で、社員の感覚・感情面に訴求し、心の底から仕事・企業とつながりを生みやすい社員エンゲージメントに対し、組織コミットメントは待遇・責任・義務感といった、賞罰的な条件で社員をコントロールする手法です。
勿論、これからの企業は義務や縛りで社員で引き留めようとする組織コミットメントではなく、愛着や情熱によって、社員が自然に集まる社員エンゲージメントの手法を取るべきです。コミットメントという言葉が2000年代人気に無くなり徐々にエンゲージメントにという言葉が取って代わられたのは偶然ではありません。
物的エンゲージメントと心的エンゲージメント
社員エンゲージメントは主に、感覚・感情・主観といった、人の持つ心理的な側面にアプローチする概念です。それに対する概念として、物的エンゲージメントという考え方もあります。つまりこれは報酬・待遇・社会的地位といった、目に見える形でリターンを与え、企業・組織とのつながりを強化する手法です。
社員エンゲージメントは概念的であり、社員のリアクション・行動の結果でしかその効果を得ることができません。ですが、物的エンゲージメントであれば、給与などわかりやすい数値ですぐに社員に行動を促す=結果を得ることが可能で、インスタントではありますが、即効性と言う意味では高い効果を発揮してくれます。
しかし、物的エンゲージメントで問題になるのが、窓際族・働かないおじさんに代表される「意識の低い働かない社員」の問題です。彼らは企業にすがりつき、最小限の労力でいかに良い給与・待遇を得続けるかを考えており、企業・組織に不満があっても今の待遇を捨てることが嫌なので、転職をすることもありません。物的エンゲージメントで人を雇うと、このような物質的な利益のみを理由に企業・組織に在籍する社員を生み出すデメリットがあります。
企業も人的コストをできるだけ下げたいものの、簡単にリストラなどはできないため、この働かない社員への対処が経営上の大きな課題となっています。
しかし、大企業の出身者で早期に退職し、過去の大企業の経験を活かして企業向けにサービスやスモールビジネスを始め、自分で考えたサービスや商品を自分で営業し小さいながらも事業をやっている人も少なくありません。これまでも、大企業を退職した人で50歳前後に独立し、自分で仕事を外から獲得した上で加工し、商品に仕上げて販売するということをしている人たちはいました。
これからは、ほぼ全てのビジネスマンが自分の50代からの人生設計において、ある程度は従業員という立場から経営者に変わることを想定しなければならない時代です。この場合の経営者は、従業員では自分一人でも全く問題ありません。
大切なことは、大企業の時のコネで再びどこかに勤めさせてもらう、雇ってもらうという時代の遅れの天下りな考え方を早く捨てることです。
勿論、かつてのキャリアで築いたコネにより販路を開拓したり、案件を取ったりすることはあっていいでしょう。但しその時でも主体的に自分でそうしていることが大事であり、決して人から与え得られた仕事を命じるがままに只こなすという時代は、とっくの昔に終わっています。
人生100年代の50歳は折り返し地点でこれから如何様に人生を展開し、様々な出会いをし、活躍の場を探していくべきです。
大学卒業時の就職活動で人生が最後まで終わる様な時代は過去のものです。50代こそ経験もあり、コネもあり、いくらかの貯えもあるという20代では考えられない有利な地点です。これを活かさない手はありません。30代、40代、ゆくゆくは規模は大小問わず、経営者にならねばならないと覚悟を決め、そのつもりで働いていれば、50歳前後におのずと自分の前に自分の進むべきキャリアが現れてくるはずです。
社員エンゲージメントは心的エンゲージメントとも言い換えられ、心的、つまり社員の内面に働きかけることで、企業・組織に所属する理由を引き出します。企業や組織、仕事に対する愛着ややりがいといった目に見えない報酬が原動力となるため、給与や待遇の影響のみで社員のモチベーションや進路が左右されなくなります。物的エンゲージメントに意味がないわけではありませんが、用いるとしたら局所的(引き止め・ヘッドハンティング時の1つのメリットとして提示)ですし、汎用性・常用するなら心的エンゲージメント(社員エンゲージメント)が良いと言えるでしょう。
エンゲージメントサーベイの項目について
社員エンゲージメントを測定する方法として、エンゲージメントサーベイという調査方法があります。社員にアンケートを取り、企業・組織に対する「愛着心」「忠誠心」などをいくつかの項目から数値化し、エンゲージメントを計測する方法です。
アメリカのコンサルティング会社であり、世論調査も行うギャラップ社が提唱するエンゲージメントの調査項目は以下になります。
- あなたは仕事の上で、自分が何を期待されているかがわかっていますか
- あなたは自分がきちんと仕事をするために必要なリソースや設備を持っていますか
- あなたは仕事をする上で、自分の得意なことをする機会が十分ありますか
- 過去1週間の内で、仕事を褒められたり、認められたりする機会がありましたか
- 上司あるいは同僚は、あなたのことを気にかけてくれていますか
- 仕事上で、あなたのことを励ましたり、成長を後押したりしてくれる人はいますか
- 仕事上で、あなたの意見は尊重されていますか
- 企業が掲げる理念や目標は、あなたに誇りを感じさせてくれますか
- あなたの同僚は、成果を目指して質の高い仕事に取り組んでいますか
- あなたには仕事上で最高の友人と呼べる人がいますか
- この半年の間に、あなたの仕事の進展や成長について誰かと話ましたか
- 過去1年の間に、あなたは仕事上で学びを得て成長できましたか
上記の12の項目への回答を社員から聞き取り、社員エンゲージメントが現状どの程度か把握します。これらの項目からは、企業との信頼関係・上司や同僚との関係・成果・成長に加え、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の浸透具合を知ることができます。
社員エンゲージメントサーベイの設問は、社員のやる気やモチベーションの観点が記載されています。しかし、社員のやる気やモチベーションは、本当にこれだけでしょうか?
社員が会社や職場と心的にエンゲージメントされる要因は、仕事のする為のリソースが整えられていることや、上司に褒められたり、認められたりすることだけではなく、チームや職場のメンバーと一緒に大きな目標や挑戦をし、果敢に取り組んでいく中での失敗したり成功したりする体験や経験ではないでしょうか?
これは、エンゲージメントサーベイの設問では、見る事の出来ない内容であり、本質的なエンゲージメントを醸成するのであれば、挫折を乗り越えを含む物語が職場に必要でしょう。
従業員エンゲージメントと社員満足度やロイヤリティとの違い
社員エンゲージメントと類似するものに、社員満足度やロイヤルティといった概念があります。それぞれには共通する部分もありますが、厳密には異なる概念となっています。
社員満足度とは、簡単に言うと「その企業・組織で働くことに満足しているかどうか」の指標です。あくまでも満足度を計測するものであるため、満足している理由については、問われていないことがポイントです。たとえば、仕事を通して得る充実感や貢献意欲などは、社員満足度では計測することはできません。
ロイヤリティとは、「社員が企業・組織に対し、どれだけ忠誠心を持っているか」を測る指標です。ロイヤリティは基本的に上下関係を前提とし、何らかの理由により、社員が企業・組織に忠誠心を持って従っている状態を指します。こちらも社員満足度と同じく、忠誠心を持っている理由については問われていません。
社員満足度・ロイヤルティに対し、社員エンゲージメントは、社員が企業・組織に対して抱く「思い入れ」や「愛着」などの内から湧き上がってくる感情的・感覚的な情熱を基に、企業・組織とのつながりの強さを測る指標です。そこには、合理性や社会的な圧力は含まれておらず、シンプルに社員がその企業・組織で働きたいという気持ちが源泉になっていることが大きな違いです。
言い換えれば、社員エンゲージメントは、数値のしにくい定性的なモノだと言えます。ですから単に給与をいくら上げれば、社員のエンゲージメントがプラスになっていくというモノではありません。例え給与が上がらなくても、目前の仕事に没頭でき、やがては、自分が津創っている商品やサービスが、社会に受け入れられていくという手ごたえがあれば、社員は頑張るものです。
給与やベアを挙げるという方法は、経営者として、最もやり易い方法ではあってもそれで必ずしも社員を引き留められるわけではないことを、抑えておきましょう。大事なことは、数値された満足度やロイヤリティではなく、数値化はしにくいが、厳然としている存在している社員の充実感や貢献意欲こそ、企業の活力の源だということです。
エンゲージメントを高めるメリット
ここまで、エンゲージメントの概要について解説してきました。ここからは、エンゲージメントを高めることによるメリットについてご紹介します。エンゲージメントを高めることで、モチベーションの向上や離職率の低下など、企業の業績向上には欠かせない要素を得ることが期待できます。
従業員のモチベーション向上
エンゲージメントが高まることで、社員の働くことに対するモチベーションがアップします。企業とのつながりが強くなることで、社員は自分が必要とされている感覚を覚え、期待に応えるために主体的な努力を始めるからです。
努力によって能力が伸び、成果が出せるようになると成長も実感できるため、さらにエンゲージメントも強くなっていくポジティブなループに入ることも期待できます。また、たとえ成果が出せない場合でも、エンゲージメントが高まっているとモチベーションが維持され、内省しながら次につなげようとするチャレンジ精神も発揮できるようになります。
離職率の低下
エンゲージメントが高い状態になると、社員の離職率が低下します。理由としては、仕事上の関係性だけでなく、その企業・組織で働くことそのものに価値を見出しており、長くその職場で働きたいと考えているからです。
エンゲージメントを高めることで離職を防ぐことができれば、優秀な社員を確保しておくという、企業にとって大きなメリットが得られます。とくに、ノウハウや経験を持つ中堅・ベテラン社員の定着率の向上は企業の課題でもありますので、人事の面でもエンゲージメントを高めることは有用です。
企業の業績向上
エンゲージメントの高まりは、シンプルに社員の仕事へのモチベーションを向上させる効果もあります。企業・組織や仕事そのものに「思い入れ」や「愛着」を持っているわけですから、当然と言えば当然かもしれません。
社員が高いモチベーションで仕事に従事することは、そのまま商品・サービスの品質向上にもつながります。高品質の商品・サービスを提供できれば、併せて顧客エンゲージメントも高まり、企業・組織としても長期的な業績の好調が見込めます。さらに、株価の上昇にも期待でき、株主への還元にまでつながるため、その影響の範囲は大きなものとなるでしょう。
エンゲージメントが上がらない原因
企業にとって有効なメリットが期待できるエンゲージメントですが、社員のエンゲージメントが高い企業・組織もあれば、なかなか上がらない企業・組織もあります。その違いは一体何なのでしょうか。その原因について見ていきましょう。
コミュニケーションの不足
エンゲージメントが上がらない大きな原因として、企業・組織と社員の間で適切なコミュニケーションが行われていないことが挙げられます。必要十分な一定のコミュニケーションが行われないと、社員は企業・組織の経営方針や目標について理解できず、共有しながら仕事に従事できないため、エンゲージメントで重要な「思い入れ」や「愛着」以前の問題になってしまいます。
そのため、経営陣や上層部と社員は、透明性を持たせながら双方向のコミュニケーションを取り、エンゲージメントを高めるために必要な土台作りを行う意識を持たなければなりません。情報共有こそ、経営陣と社員を結ぶきずなであり、この情報共有が実行されず、社員の知らないことが上層部で勝手に決まり、説明もなされない状態こそ、社員エンゲージメントを低下させる要因です。
ブリッジウォーターという投資会社を運営していたCEOのレイ・ダリオは、会社の運営において、透明性を何よりも重視しました。ダリオは様々なアンケートを社員に対して実施し、その結果も、全て明らかにしました。その中には、社員にとって不都合な情報だけではなく、経営者であるダリオにとってもできれば隠したい情報もあったのですが、それを全て開示しました。
このことによって、ブリッジウォーターでは、社員のそれぞれが、会社の問題点により敏感となり、自分がどうすれば、会社に貢献できるかをよりクリアに考え、何よりも、不都合の情報でも隠さなかった経営陣のへの信頼が増したわけです。
このような会社の社員エンゲージメントが、高くなることは言うまでもありません。
フィードバックの不足
適切なフィードバックも、エンゲージメントを高めるためには不可欠な要素です。仕事は1人で行っているものではなく、上司・部下・同僚同士など、互いにサポートし合いながら行うものです。フィードバックが不足すると、社員は個人として成長の機会を損失する状況が増え、さらに上司・同僚の仕事への考え方が理解できず、自分自身が周囲から何を期待されているのか把握し辛くなるため、非常にストレスが溜まる状況に陥ります。
その結果、エンゲージメントは高まるどころか低下し、企業・組織とのつながりも希薄になってしまいます。エンゲージメントを高める意味も含め、社員を不安・ストレス過多な状態にしないためにも、上司・部下や社員同士での定期的なフィードバックを心がけるようにしましょう。
そのフィードバックは時に、当該社員にとって厳しい内容になるかもしれません。しかしそれを言わないで、放っておくと、当該社員だけではなく、企業のそのものにも、ダメージが及びます。わかっていても言わない。という態度は、企業経営において、思いやりではなく、むしろリスキーなことなのだと、強調しておきます。
目標の不明確性
企業・組織単位はもちろん、チーム・部署単位でも、社員が目標を理解できているかがエンゲージメントを高めるために重要になります。目標が理解できていないと、仕事に従事している理由がわからなくなり、従業員のモチベーションが低下してしまうからです。
目標とは行動を起こすための動機であり、行動の原動力となります。対策はシンプルで、明確な目標を定めて関係する社員全員に説明し、企業・組織、チーム・部署の中で共有するようにすると良いでしょう。また、社員一人ひとりが目標達成に必要不可欠な存在だと伝え、存在を承認することも大切です。
将来のキャリアが見えない
この企業・組織で働き続けることで将来的にどんなキャリアを歩むのか不明瞭な場合も、社員のエンゲージメントの高まりが阻害される要因です。多くの社員は自身のスキルを向上させ、役職を得るための機会を必要としています。そのため、キャリアアップにつながる挑戦の機会や、訓練になる実務の場が不足していると、社員の働くモチベーションが低下してしまうことは避けられません。
キャリアアップの見通しが付かないと、エンゲージメントを高めることが難しくなり、現在働いている企業・組織への「思い入れ」や「愛着」も薄れ、つながりが希薄なものとなってしまいます。キャリアを不透明にしないために重要なのは、社員がスキルを伸ばすための実務上での挑戦の機会を与えることです。そこで結果が出ると社員は自信もつきますし、チャンスをくれた企業・組織、または上司に対して感謝の気持ちを抱くようになり、エンゲージメントを高めることにもつながります。
一番好ましくないのは、社員がルーティンとなっている仕事を、延々とこなし続けているという状態です。ルーティンなわけですから、その仕事は社員にとって困難なモノではなく、一定のスキルも身についているでしょう。しかし、それと同時に、その仕事への緊張感も薄れ、何より、仕事に面白さを感じることができなくなっていきます。
大抵の社内不和は、実はこのようなルーティンだけで満たされた目前の仕事への不満が原因であることが大半です。新しい事業や新しい経験に立ち向かう時、社員は緊張し、ある種の高揚感を覚え、その時、小さな言葉遣いの一つ一つに、気をとめる余裕などなくなってきます。目前に仕事に集中できるわけです。
経営者は、社員にとって仕事がルーティン化しないように、マンネリ化しないように絶えず、職場に対して、刺激や新しさを提供することに気を配るべきです。次に経営陣からどんな課題が与えられるのだろうという不安と、挑戦のある職場であれば、社員はおのずとつまらない人間関係よりも仕事にそのものに没頭するはずです。
エンゲージメントはどうすれば高まるのか?
エンゲージメントが上がらない原因がわかったとしても、それをすぐに改善することは容易ではありません。まずはエンゲージメントがどうすれば高まるのか、根本的な仕組みの部分について知る必要があります。
物理的な満足度と心理的な満足度を高めなければならない
エンゲージメントを高めるためには、物理的(物質的)な満足度と心理的な満足度の両方にフォーカスしなければなりません。物理的な満足度とは、具体的には給与及び福利厚生、働く場所などファシリティを指します。人的資本経営が叫ばれる昨今では、一人辺りの教育投資額や有給取得率など、人的資本に対する姿勢を反映する指標を明示し、株主や求職者向けにPRしている会社は多いです。この物理的な満足度は、指標化が可能であり可視化ができる為、公表できPRできます。しかし、競合他社や業界標準など、相対比較が可能になる事も特徴です。従って、資本や規模が大きい方が必然的に、物理的満足度が高くなる傾向があります。
これは、ベンチャー企業や業界上位ではない会社にとっては、物理的満足度だけでは、競争に勝つことは困難であると言い変える事もできます。
一方、心理的な満足度とは、従業員が企業・組織の理念・ビジョン・目標などを共有し、共感できているかが関係しています。共感によって仕事にやりがいを感じ、誇りが持てていると心理的な満足度は充実します。
心理的な満足度が満たされない例としては、長らく市場に変化がない分野の企業・組織などのケースです。こういった変化に乏しい企業・組織の場合、しっかりとしたビジョンが用意されておらず、目標が社員にとって魅力的に見えない場合があります。とくに変化の激しい現代では、ビジョン・目標が欠如していると、企業・組織の将来を社員が疑ってしまい、エンゲージメントを低下させてしまう原因になります。
総括すると、エンゲージメントを高めるには、企業・組織はコストをかけて物理的な満足度を提示し、時代に則した理念・ビジョン・目標を設定した上で社員に説明し、共有する必要があると言えるでしょう。
物理的満足度と心理満足度を両方満たすことができれば、それに越したこことはありません。しかし、どちらも満たすことが難しいことが大半でしょう。その時には、やはり思い切って、心理的満足度に集中すべきです。一言で言えば、経営者がより明確に、社員に目批評と理想を熱心に語ることです。
経営者の熱意こそ、お金や資本に勝りうる社員の動機になり合えます。逆に物理的満足度が高くても、心理的満足度が低ければ、お金の為だけに仕事をしているという社員がどうしても増えてきます。企業に限らず、人間のいかなるコミュニティにおいても、成功するかどうか?究極的には、リーダーの熱意と実行力であり、お金ではありません。
物理的満足度に関わらず、職場全体としてプロジェクトが進んでいるという手ごたえがあったり、商品のサービスのクライアントからの評判が上がってきたりすると、すぐに自分の給与が上がらなくても社員は自然にもっとやろうという気になるものです。経営者の熱意と前進感が、鍵となります。
エンゲージメントは職場やチームの状態に直目するべき
社員のエンゲージメント高低に大きく関係しているのが職場やチームの環境です。エンゲージメントを高めるには、社員がどのような環境で仕事をしているのか見直す必要もあります。
とくに職場・チームといった集団単位の環境が重要になるのは、場を仕切っているリーダーの存在です。集団内のコミュニケーションがどのような方向性になるのかは、リーダーの舵取りによってほぼ決まるため、職場・チーム内の風通しの良さや良好な雰囲気を作るには、リーダー役の選定は重要になります。
また、目に見えない空気や風土といったものは社員だけではコントロールが難しいため、裁量権を持つリーダーが上手にコミュニケーションを促し、社員同士が適切に連携し、互いを尊重し合う環境作りを行うことも大切です。
具体的な方法としては、1on1や対話的な姿勢のやり取りをリーダーが率先して行う、互いを尊重し、理解し合うためのディスカッションをできる時間・場所を用意するなどです。社員同士が意思疎通をはかりながら、良い空気になるよう連携することで、適度な緊張感と居心地の良さを兼ねた理想的な職場空間にすることができます。社員全員にとって職場・チームが働きやすい空間になれば、必然的にエンゲージメントも高まっていくことが期待できるでしょう。
この環境づくりにおいても、リーダーの役割が重要です。これからの職場は、目的に併せたチーム単位で、取り組むことが、主流になってくると思われますが、この目的に中心のチームビルディングにおいては、良い雰囲気を創れるリーダーをどれほど確保できるか?が、企業の生命線です。
良いリーダーとは、スキルが高い・利益を叩き出せるよりも、日々の仕事の中で長時間接していても何気ない会話の中で信頼してもらえること、嘘をついていないと評価されること、こういった人格的な要素の方が重要でしょう。社員は、最終的には、信頼できるリーダー、嘘をつかないリーダー、人一倍仕事に熱意のあるリーダーを求めています。信頼や正直や熱意に比べれば、利益率や業績などは、二の次と言っても良いでしょう。
長い時間をともにする同僚やメンバーに対して表面的に付き合うことは実際にはできるようで難しく、在りままの状態で接することはリーダーシップの第一歩です。
エンゲージメントを高めるためには組織外の状態も重要
エンゲージメントの高低に関わっているのは、企業・組織内の環境や人間関係だけではありません。たとえば、海外のビジネスパーソンは、自身の働く企業・組織の良い部分や共感できる理念・経営方針について、家族に話すといったことがあります。この時、家族から所属する企業・組織への承認や共感を得られた場合、その人は自己肯定感を高め、さらに企業・組織への愛情や好意的な気持ちを強めることにもなり、エンゲージメントを高めることにもつながります。
つまり、社員が自社について、友人・知人・家族からどのような評価を受けているかも、エンゲージメントの高低を左右しているということです。第三者からの承認・共感は人を動かすだけの強力なパワーを持っているため、その社員がプライベートでどのような状況・人間関係であるか把握し、必要であれば良好な状態になるようサポートすることも、エンゲージメントを高めるための有効な方法の1つです。
とはいえ、個人的な領域には、土足でズカズカと踏み込むわけにはいきません。プライベートな話題はハラスメントにも直結しますし、「自社について周囲にポジティブに話してくれ」などと言うのもおかしなことです。だからこそ、社員のポジティブな面を、企業や職場が、オフィシャルな形で、家族が伝えるという方法があります。
幸いなことに、現在はSNSが発達し無料で企業や職場が社内を外部へとプレゼンテーションすることができます。もちろん、社員のプライバシーや個人情報をどこまで出すかは状況に拠りますが、ポジティブな情報出すと言われて拒否する社員も少ないことが事実です。
日々の業務や社員の仕事ぶりについては、それこそ日々いくつもの物語が発生しているはずです。その物語をポジティブな表現しそれぞれの社員がその物語の登場人物として描き出されるとき、その物語を社員の家族にとっても非常に興味ある物語であり、そこで感動や印象が伝わった場合、社員も家族もそれぞれに関して今までとは違った視点を持てるようになり、夫や妻を、父や母を他人の目から賞賛できるようになります。
このように家族の絆が強まった時、その社員の企業や職場への忠誠心は、強制しなくても自然に高まる事でしょう。SNSで物語を創り効果的なプレゼンテーションできるかどうかはほとんどの企業が気づいていない戦略であり、さらなるSNSの利用がこれから望まれます。
エンゲージメントとエンプロイーエクスペリエンス
エンゲージメントの高低は、社員のエンプロイーエクスペリエンス(従業員体験と価値)が大きく関係しています。具体的にどういったことなのか、見ていきましょう。
エンゲージメントが下がる時期
エンゲージメントは一定ではなく、実は波があるものです。一度高まったからと言って継続するものでもなければ、低い状態がずっと続くわけでもありません。
たとえば、若手時代はエンゲージメントが高かった社員でも、中堅・管理職などの立場にシフトした途端、エンゲージメントが低下するといったことはよくあります。とくに管理職の場合、人を束ねる裁量権は得たものの、現場で手と頭を動かしていた充実感がなくなるほか、事務的な作業が増え、仕事へのワクワク感がなくなってしまうことがあります。このように、仕事に対して意義や魅力を見出せなくなると、社員のエンゲージメントが低下することは避けられません。
しかし、企業・組織に所属している以上、経験を重ねたことでポジションや役割が変化することも回避しにくいものです。一般的に若手時代は現場で働き、中堅・ベテランに入ると管理する側に回るため、人によっては業務がミスマッチになる場合もあります。
一例としてプログラマーという職種では、苦手がマネジメントよりも、プログラミングにおいて、一流の仕事したいという気持ちから、管理者になることを断る例も見られます。このような社員の場合、希望通りプログラミングに特化したほうが職場の生産性としても社員のエンゲージメントの観点でも有利なはずです。敢えて管理職を拒否して、仕事へのエンゲージメントを高めようとする方法もあっていいでしょう。
これまでの日本企業では、管理職にならないと評価されていないという思い込みがありましたが、それはもう時代遅れです。これからは、社員一人一人にとっても職場のチームの観点からも企業の中でどれ程効率よく機能を果たせるか?どれほど満足感が得られるか?という観点で職場のレイアウトを創っていく必要があります。この点に関しては、チームビルディングの記事で、詳述していますので、そちらも参考にしてください。
エンゲージメントの源泉
社員のエンゲージメントを低下させてしまう要因はいくつもあります。前述した管理職の問題もありますし、企業・組織の理念・ビジョン・経営方針に共感できるか、仕事に対して熱意や活力を持って取り組めるかなど、目に見えない感情的・感覚的な要因が関係し、社員のエンゲージメントの高低が決まります。
エンゲージメントの源泉が何かを一言で表すなら、それは社員の感情です。たとえば、仕事を楽しい・やりがいがあると感じるのは感情ですし、企業・組織に対して愛着心を持つのも感情が起因しています。逆に、企業・組織の理念・ビジョン・経営方針に不満を感じることも感情ですし、マンネリ化した仕事にやる気が出ないことも根底には感情(的な反応)があるものです。つまり、社員からポジティブな感情を引き出すことができればエンゲージメントは高まり、ネガティブな感情を増長させるとエンゲージメントは低下すると言い換えられます。
給与・待遇など、物理的な報酬だけで社員のエンゲージメントが高まらない理由の1つはここにあり、どんなに良い扱いを受けても人はいずれその状況に慣れ、飽きてしまうからです。このことは子供時代を思い出すとよくわかります。喉から手が出るほど欲しかったゲーム機も、いざ購入すると1ヶ月もせずに飽きてしまい、別の遊びをするといった経験は多くの人がありますが、大人になっても、たとえそれが仕事だとしても構造は同じです。
社員のエンゲージメントを高めるには、社員と企業・組織とのつながりを強化する施策を打ち、ポジティブな感情=エンゲージメントを高める源泉をいかに引き出せるかにかかっていると言えるでしょう。
組織の状況及びインターナルコミュニケーション
エンゲージメントの高まる条件の1つに、職場環境が良いことが挙げられますが、それだけでは不十分です。風通しが良く、人間関係が良好で仕事がしやすくとも、企業・組織の状況や理念やビジョンが適切に社員に伝達され、共感を得ている必要もあります。
また、給与や待遇についてもしっかり提示する必要があります。エンゲージメントが感情をベースとした心的な要因が源泉であることは前述しましたが、だからと言って物的な要因の報酬・待遇・社会的地位などを無視しても良いわけではありません。社員にも生活や結婚・出世などライフプランがあるからです。
また、隣の部署・チームが何をやっているのか不明瞭である、キャリアに関する情報が提供されていないなど、企業・組織全体に不透明性があると、社員は不安や不満を覚え、エンゲージメントを低下させてしまいます。
そういった状況を作らないためには、インターナルコミュニケーション(社内広報)による情報伝達とコミュニケーションの活性化が有効です。インターナルコミュニケーションは、企業・組織の価値観・文化・理念・ビジョンなど概念を伝える手段としても、報酬・キャリアなどの情報を伝える手段としても活用することができます。
インターナルコミュニケーションについては、別の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
エンゲージメントが高い組織と職場
エンゲージメントが高くキープされている組織・職場にも理由があります。前述したエンゲージメントを高めるための要点を踏まえ、社員に対して適切な環境を提供していることがポイントですが、一体どのような環境設定なのでしょうか。
エンゲージメントを向上させる組織
物理的な報酬だけではエンゲージメントは高められないとお伝えしましたが、もちろん給与・待遇がまったく関係しないわけではありません。競合他社の用意している給与・待遇に対して悪い場合、エンゲージメントが低下することはあるため、一定の水準の給与・待遇を保っておく必要はあります。
また、近年は生成AIの登場などテクノロジーの進化・浸透により、事務などルーティンワーク的な業務が自動化されつつあり、社員が担う仕事は企画・創造性といった頭を使う仕事にシフトしています。企画・創造性といった能力を使う知的労働はやりがいを生みやすく、仕事をゲームのように楽しめるようにしてくれるため、エンゲージメントも高まりやすくなります。実際、こういった労働環境の変化に柔軟に対応できる企業・組織は、社員のエンゲージメントが高い傾向にあります。
エンゲージメントの高い職場では、ある種のゲーム性が不可欠です。次に何が起きるかを予想しながら、当たれば喜び、間違えれば反省し、絶えず目的意識をもって仕事に取り組み、それを共有できる職場は誰に強制されなくてもエンゲージメントの高い職場になるはずです。
私たちの中には、いつまでも子供時代のようなゲームへのワクワク感が消えずに残っています。年をとっても、それを忘れているだけで、きっかけがあれば、そのワクワク感は、年齢に関係なくよみがえってきます。仕事をある意味で、ゲームに変えていくこと、不定形な現実に対して、ゲーム感覚で、立ち向かうこと、これらが、ワクワク感の職場を創りだす源泉です。
ちょうど子供の時代のゲームのように。受注がとれれば、皆で喜び、ライバル社に負ければ皆で肩を落とすような感情をうまく仕事に結び付けていくマネジメントが理想でしょう。如何に社員の感情を仕事というゲームに一喜一憂させるか?こそ、人事や労務も含めて、管理者の腕に見せどころです。社員のエンゲージメントを低下させる第一の元凶こそ、慣れることであったり、飽きることであったりです。
慣れる事や飽きる事は、私たちの人生の質を劣化させ、人間関係もつまらなくさせてしまいます。これを防ぐためには経営者は、違うゲームを導入したり、メンバーを入れ替えたり、目標を変えることによって、常に新しさと緊張感を仕事に産み出すべきです。
そのためには、今の世の中で、新しいとはそもそもどういう事か?何が人の心を捉えているのか?という情報に経営者は人一倍敏感となり、社員に先駆けて世のトレンドを仕事の中に導入していく必要があります。今までのコンサルティング業務では、感性という言葉で語れていた物ある程度身に着けていく必要が経営者にあります。
エンゲージメントを向上させる職場チーム
企業・組織内におけるチーム単位でも、エンゲージメントの高低には差があります。とくに関係しているのは、チーム内での社員同士の関係性と社員の管理の仕組みです。
まず関係性において、エンゲージメントが高いチームは、リーダーとメンバーとの1対1の関係性を構築することだけではなく、チーム全体でコミュニケーションが取りやすい環境を作り、リーダー抜きでもチームとして機能する状態を用意している傾向にあります。リーダーと個々の社員の信頼関係だけではなく、社員同士が信頼し合える関係性の構築を優先し、社員同士がお互いを理解し、サポートしフィードバックし合う協働関係を作るための場作りを行っています。
リーダーは、エンゲージメントの高いチームの場合、配置換えがより易くなり リーダーの資質があれば、様々な場所で、リーダーを役割を果たし、経験を積み、視野を広げ、人脈を築いていくことができます。この意味では、様々な部署で、リーダーを経験し、広い視野を持った社員を揃えることが会社としての底力をなります。従来の日本企業では、ある分野一筋のようなリーダーが貴ばれましたが、そんな時代はもう終わりました。
経営者としても、リーダーには、様々な経験をさせ、人脈を広げてもらうように、場を設定するべきです。リーダーも社員も、フレキシブルに、集まっては離れを繰り返しながら、その時その時の目的に応じて、機敏に結果を出せる職場こそ、良い職場です。
また、エンゲージメントが高いチームは、必要以上の管理を行わないことも特徴です。個々の社員を1人の自立した存在として扱い、自己判断・自己決定といった裁量権を委ねることで、自主的・主体的に仕事に参加している意識を持つことを促しています。
エンゲージメントの測定方法として、エンゲージメントサーベイという調査手段がありますが、エンゲージメントサーベイは大まかな従業員の傾向がわかるだけなので参考程度にしかなりません。重要なのはエンゲージメントサーベイの結果を考慮し、具体的にどうエンゲージメントを意識したチーム運営を行うかです。そのためには、チーム内のリーダーと社員、あるいは社員同士のコミュニケーションを適切な形で活性化させることが大切です。
ワクワクする意味づけとチームの在り方
エンゲージメントを高めるには、仕事に対する意味づけを行うことが大切です。仕事に含まれる課題・責任にワクワクするような意味を持たせ、その仕事に取り組む意義ややりがいを刺激することが重要です。
課題・責任への意味づけが上手くいくと、各部署やチームなどのリーダー・管理職全員が適切な方向でリーダーシップを発揮している状態になります。すべてのリーダー・管理職がリーダーシップを発揮しているとはつまり、各自の集団内はもちろん、部署・チーム同士の連携においても信頼関係が発生していると言え、パフォーマンス自体も高水準になっている可能性が高いでしょう。
また、部署・チーム全体のパフォーマンスが向上すると成果も出やすくなり、各社員のエンゲージメントも必然的に高まってきます。部署・チームなど小集団単位のパフォーマンス・エンゲージメントが向上すると、企業・組織全体の事業や経営にも好影響を及ぼすため、意味づけによるチームの在り方は、ビジネスにおいてとても重要な要因だと言えます。
コピーを取るという何気ない作業を例にとってみましょう。そこに意味づけがない場合、コピー取りの仕事は退屈で、無意味なものでしかありません。一方コピーを取る社員に、その仕事の中身や意義が、周知徹底されていれば、同じをコピーを取るという作業においても、そこでミスをしないように注意配り、どうしたらもっと見やすいコピーになるかという問題意識も生まれてくるでしょう。
大事なことは社員の一人一人に、価値が使わっているか?物語が伝わっているか?です。ワクワク感を産み出すことこそ、価値であり物語です。経営者は、自社の仕事の価値と物語を、絶えず社員に語りかけ社員のエンゲージメントを高めていくべきです。
目前の仕事は時代の流れとともに変わっていきます。価値や物語も一定ではありません。経営者は絶えず、これまでとは違う価値や物語を社員の語りかけていく努力を忘れてはなりません。
エンゲージメントを向上させる施策
ここからは、エンゲージメントを高めるための施策についてお伝えします。経験・慣れは必要ですが、どの施策も特別なスキルは必要ありませんので、アレンジなどを加えながら実践してみてください。
課題や業務の再意味づけ
同じような業務やプロジェクトを続けていると、社員はどうしても惰性感に飲まれてしまい、徐々に仕事の目的や意義を見失ってしまうのと同時に、エンゲージメントも低下してしまうものです。そういった惰性の状態を脱するには、仕事上の課題や業務に対して、再意味づけを行うことが有効です。
その際、仕事を進める上での課題・問題を設定し、ナラティブやストーリーテリングを用いて、その課題・問題を解決することの目的や意義を説明すると良いでしょう。
ナラティブ・ストーリーテリングをかいつまんで説明すると、要は物語性を持って物事を話すことを指します。つまり、今仕事に対して社員が抱いているネガティブな印象を一旦引き取り、同じ状況に対し、ドラマティックな物語性を持ってポジティブな意味づけを行うことで、熱意・共感・やりがいといった、眠っていた感情を引き出す方法です。
たとえば、毎日同じような業務が続いてやる気が出ないと嘆いている従業員がいたとします。「なぜそう思うのか?」と質問すると、「成長の実感がない」といったネガティブな理由を語ったとしましょう。これに対し「仕事の成長ポイントは自身で見つけていくものだ」「繰り返しの中で自分なりの小さな変化を起こすことも大切」といった、まったく別のポジティブな課題・業務の再意味づけを、物語性=感情や共感に訴えかける言い回しで伝えるやり方です。
ナラティブ・ストーリーテリングを用いた再意味づけは、従業員の感情に訴えかけるため、エンゲージメントを高めるためにも有用な方法になります。
職場の新しさを常に吹き込むことも重要でしょう。確かの目の前の仕事は今までと同じかもしれませんが、社会が変化していくにつれて仕事の意味も価値も変わっていきます。経営者だけではなく、社員も、日々の仕事に没入するだけではなく、時事問題やニュースに敏感になっておくことは不可欠です。
コミュニケーションスキルの向上と信頼関係
コミュニケーションスキルを高め、上司と部下や従業員同士の信頼関係を構築することも、エンゲージメントを高める上で重要です。仕事は1人でするものではなく、他者との連携や関係性の上で成り立っているものであり、従業員のエンゲージメントにも直結しているからです。
企業・組織がどんなに良い理念・ビジョン・目標を掲げていても、人間関係が上手く機能していないと、従業員は企業・組織・仕事に対する「思い入れ」「愛着心」を抱くことは難しくなります。従業員同士の意思疎通が不十分だと不安になりますし、軋轢やトラブルなどがあれば大きなストレスとなり、エンゲージメントも低下してしまうものです。ですので、エンゲージメントを高めるためには、他の施策と併せ、従業員のコミュニケーションスキルを向上させる施策を行うことも大切になります。
従業員のコミュニケーションスキルを高める方法としては、企業・組織内で研修を実施したり、社外のコミュニケーション研修・講座を受講したりするといった方法があります。企業・組織内で行うと人的・時間的コストがかかってしまいますので、通常の業務を圧迫しないためにも、社外のコミュニケーション研修・講座を受講する方法が望ましいでしょう。
インターナルコミュニケーション
エンゲージメントを高めるためには、社内・グループ会社同士など、同一の組織内で行う広報活動インターナルコミュニケーションの実施も重要です。とくに企業・組織の理念・ビジョン・目標などの経営方針全般を従業員に共有することで、社員が納得と共感を持って仕事に従事している状況を作ることが望ましいでしょう。
経営理念を共有するインナーブランディングが機能すると、従業員1人ひとりが仕事を自分ごと化して取り組むようになり、企業・組織への「思い入れ」「愛着心」も強まるため、必然的にエンゲージメントも高まっていきます。
また、インナーブランディングを促す際も、従業員の感情に訴えかけるナラティブ・ストーリーテリングの手法を用いることが有効です。エンゲージメントは従業員の感情に起因して上下するものなので、ドラマティックに企業・組織の理念・ビジョン・目標を伝えると、共感を得やすいでしょう。
しかしながら、効果的なナラティブを創る為には発信者である経営者側にある程度の美意識や文学的スキルがどうしても必要になってきます。しかも日本の多くの企業の経営者に最も欠けている素質こそ、この美意識であり文学ではないでしょうか?
本当に素晴らしい商品やサービスを創りだしているのにも関わらず、うまく表現ができないために社員にその意義が伝わっていなかったり、社外から正当な評価が得られなかったりしている日本企業は実は多いのです。
自社の価値と意味を人の心を動かすイメージと言葉で社員に、顧客に、そして社会全体に伝えていきましょう。今までは各企業の広報部で日々の業務とは独立してこうしたPRが企画されてきましたが、社員の一人一人が自社の価値と意味を共有することが大事であり、社員の一人ひとりが自社の広報を担当するつもりで業務遂行すべきです。
これまで企業の広報部と言えば、あまり重視されてこなかった部署かもしれませんが、これからの新しい企業形態においては、PRを広報部を丸投げするのではなく、社員が一人ひとりが、広報を常に意識した仕事をしていくべきなのです。その時、その職場のエンゲージメントは何か特別なことをしなくてもおのずと高まっていき、社員の離職率も大幅に低下しているはずです。
まとめ
エンゲージメントは、報酬・待遇・社会的地位といった物理的なものを提供するだけでは高めることはできません。社員の内面、とくに感情がやる気の源泉となっていることを踏まえ、企業・組織・仕事に対して「思い入れ」や「愛着」を持ってもらう必要があります。エンゲージメント対策をすでに取り入れている企業も、これから取り入れようとしている企業も、本記事でお伝えした内容を基にエンゲージメントの理解を深めていただき、適切な施策によってエンゲージメントを高めて下されば幸いです。