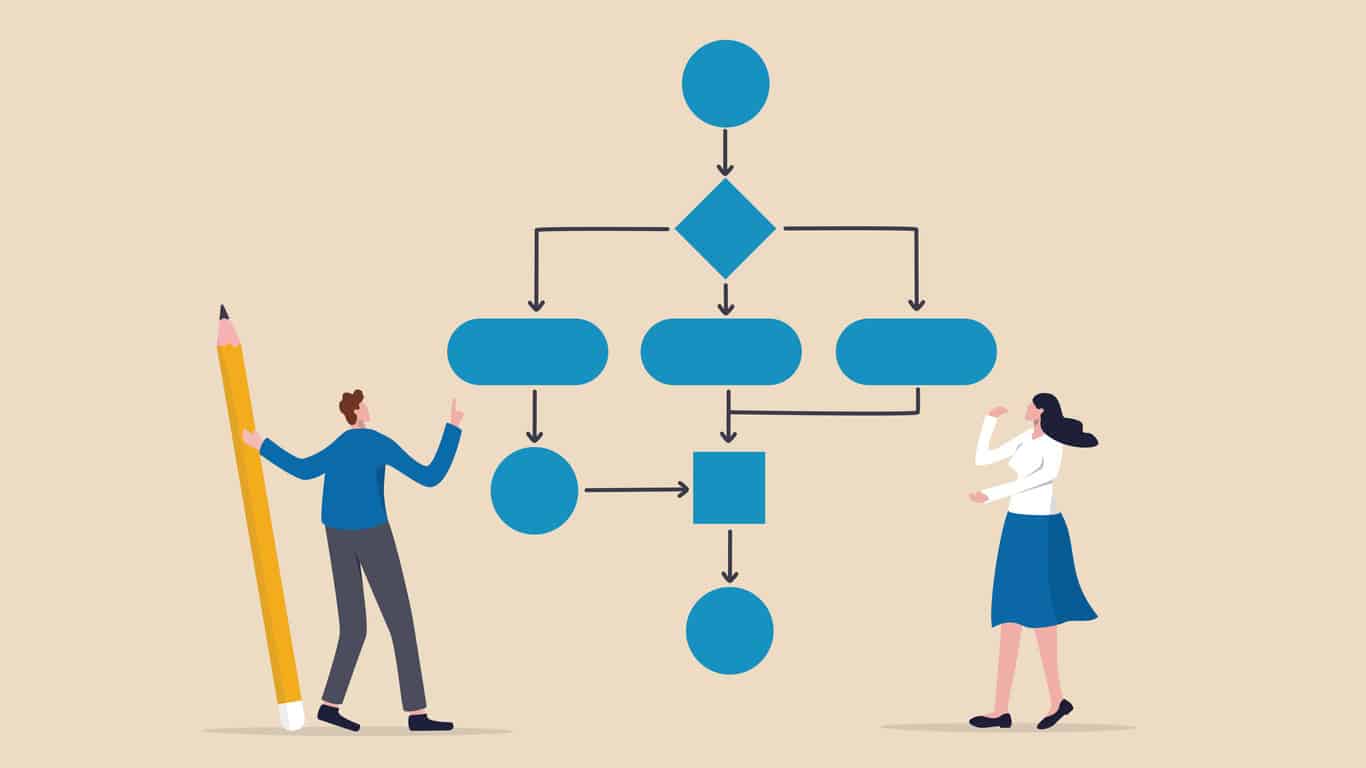コミュニケーション研修とは?ビジネスに必要なコミュニケーションスキルを効率的に学ぼう
最終更新日:2024.03.14

目次
現代のビジネス環境では、正しいコミュニケーションスキルを持つことが極めて重要です。
多くの企業や組織では、コミュニケーションの円滑化や効率化を図るために、コミュニケーション研修やコミュニケーション講座を開催しています。
この記事では、コミュニケーション研修の詳細な内容に触れながら、効果的なコミュニケーションスキルを身につけるためのポイントを紹介します。
異なる立場や意見を持つ人々と円滑にコミュニケーションを図るためのテクニックやコミュニケーションの基本原則について学び、ビジネスシーンでのコミュニケーション力を向上させましょう。
コミュニケーション研修とは何か
コミュニケーション研修とは、業務内外における適切なコミュニケーションについて学ぶためのプログラムです。
一般的に「コミュニケーション」といえば、何かを「伝える」という行動が想起されるかもしれません。
しかしコミュニケーションの語源はラテン語の「communis」で、日本語で「共通の」「共有する」「分かち合う」という意味を持つ言葉です。
この語源を見ると、コミュニケーションという言葉には「伝える」という意味以上に、物事を「共有する」という意味があると考えられます。
この記事でコミュニケーション研修の具体的な目的や種類について、詳しく見ていきましょう。
コミュニケーション研修の現在地
日本の高度成長を支えた強い同質性・凝集性は、以心伝心、いわずもがな、という話をしなくても考えがわかり気持ちが通じる組織風土を醸成しました。
しかし、1980年代以降、海外進出や多角化など既存事業で培った経験則では判断できない局面が多くなると状況と雇用慣行の変化により一変しました。
話さなくても気持ちが通じるメリットより、論理的・建設的議論ができないデメリットの方が勝るようになりました。
しかし、企業内の教育において、「コーチング」「部下育成」「○○思考」といったヒューマンスキルは、基本的にはコミュニケーションスキルをさまざまな状況や場面に応じて活用するものであり、基本的な手法はほぼ同じです。
一方で、基本的なトレーニングを行わずに応用編ばかりを実施している企業も多いと言えます。
コミュニケーションにはお互いが共通に理解している足場の上にしか成り立ちません。
我々は日常的に言語をベースとして、一般常識や、ビジネスであればビジネス常識や業界常識を、お互いが共通理解している前提でコミュニケーションをとっています。この足場がしっかりしているほどコミュニケーションはとりやすく、足場が脆弱であればいくら言葉を尽くしてもコミュニケーションは難しくなります。
つまり、コミュニケーションの基本的なスキルを獲得する前に、応用編や用途別を学習した経緯と強い同質性・凝集性は、以心伝心、いわずもがなという下地も通用しなくなったため、コミュニケーションの問題はむしろ増大しているといいかえることができます。
業界や職種、専門分野が同じならばコミュニケーションはとりやすいのに対し、異なる業界、異業種など、世代も性別も国籍も違うような人とコミュニケーションから理解を深めることは非常に難しくなります。
社会やビジネスの足場となる常識や慣習は、通用せず、人の足場となる価値観や文化は、同質性から多様性へと変化しています。
したがって、コミュニケーション研修は、基礎から応用へ、そして、若年層から経営層まで、また、ビジネス熟練者であってもアップデートする必要がある研修と言えます。
では次にコミュニケーションの重要性と不可能性という一見相反するこの性質をどのあたりで、融合させればいいのかを考えていきましょう。
現代にいたっては、ありとあらゆるものが多様に変化していき、なかでも言葉の意味や解釈はとくに変化しています。
対面でのコミュニケーション以外、Web会議、電話、チャットツールを用いるなど、シーンもその発信方法も選択肢が増えました。
会話以外にも配信動画、テキスト・・・・と、変数だらけです。
こうした有為転変とした現代のビジネスシーンでは、コミュニケーションスキル自体、一度学習すればずっと有効だとは言えないのではないでしょうか。
コミュニケーションの相手の変化だけでなく、世界の当たり前がこれまでにない速さで変化する時代に、多くの日本の企業では形式ばった新入社員や若手向けのコミュニケーション研修は多々あります。
当然新入社員へのコミュニケーション研修は必要なのですが、果たして新入社員だけが対象なのでしょうか。
先ほども述べた通り変化の波に直面しているのはすべてのビジネスパーソンであるため課長、部長、もっといえば、社長向けコミュニケーション研修がなければなりません。
コミュニケーション研修の目的
コミュニケーションは、それ自体が目的となることはあまりなく、あくまで相手があって、相手とのコミュニケーションを通して達成したい目的があって行われるものです。
企業が実施するコミュニケーション研修では多くの場合、コミュニケーションの目的として、正確かつ円滑に物事を進めることや、業務内外での人間関係を円満に保つことなどを想定しています。
なぜなら、仕事の中で関係者と意思疎通を図る際、もし双方の理解のずれや意見の対立を放置すれば、業務上の事故につながりかねないからです。
実際の業務に必要なコミュニケーションスキルは業種や業態、働き方、状況などで異なりま
す。また、何のためのコミュニケーションなのかも仕事の状況によって変わるでしょう。さらに、受講者によって得意不得意があり、コミュニケーションの習熟度も異なります。
そのため、研修の前に、「どのようなコミュニケーション能力を獲得するのか」を具体的に設定する必要があります。
そのうえで、そのコミュニケーションスキルが活用されるシーンも設定しなければ意味がありません。
コミュニケーションの相手となる人物は誰なのか、場所はどこなのか、コミュニケーションの相手とはどのような関係なのかを明確にして研修を行いましょう。
実際の研修では、まず業務内外のコミュニケーションに関する基礎知識を学んだうえで、実践を通してスキルを身につけていく形が理想的です。
そして、研修を設計する際に前提となる「コミュニケーションの目的」が漠然とした抽象度の高いものであれば、実務における再現性は低く、研修の効果性が薄くなります。
逆に、活用シーンをより具体的にし、受講者の状況を考慮してカスタマイズをすれば、研修の効果性は向上します。
具体的な活用シーンと、リアリティのある目標を設定し、「伝えるスキル」と「聴くスキル」の双方を学ぶことが、実践的なコミュニケーションスキルの習得につながるのです。
コミュニケーションスキルは、自分と相手の間にうまれる空気感を含めてそれが高いのか低いのかを規定します。
顧客向けに商品を紹介するためのプレゼンテーションを例に挙げると、プレゼンテーション研修を受けた直後から、実践にうつせる人はあまり多くはいないのではないでしょうか。
頭で理解できる研修よりも、経験に基づいた体を使うというのがコミュニケーションです。
実践の伴わないスキルは、いざ客先になると話すだけで精一杯だと相手は置き去りになってしまいがちですが、スキルを道具として考えた場合、使えば使うほど精度はあがります。
現場を意識した研修を行う場合、道具としてのスキルを身につけることを目的にしたうえで、いつ/どこで/誰に/どのスキルを使うのかを明確にした研修設計が必要ではないでしょうか。
コミュニケーションスキル研修の対象者
- 初めてのお客様とコミュニケーションをとることや関係を作るのが苦手と感じている方
- 社内での円滑なコミュニケーションにより、業務を効率的に進めていきたい方
- 会議での発言や合意形成について課題を持っている方
このような悩みをお持ちの方へ
- お客様との商談時の会話や、雑談などのコミュニケーションが難しい
- 上司や部下に伝えるべきことを明確に伝えられず業務の停滞が見られる
- 会議と業務の時間のバランスが悪い
- 社内コミュニケーションに課題を感じ、業務の効率化や職場環境の改善をしたい
コミュニケーション研修プログラムをカスタマイズすることで効果を狙う
当たり前のことですが、上記のようなシーンは個別の企業毎に違います。パッケージの汎用製品より、1回のカスタマイズで実施する方が受講者にとっては有用なものになります。
実施計画を立てる段階で、カスタマイズやレディメイドに対応できるベンダーを選定しましょう。
コミュニケーション研修の段階と切り口
コミュニケーション研修では、コミュニケーションをいくつかの段階に分けて学んでいくと理解しやすいでしょう。
コミュニケーションの段階分けにはさまざまなパターンが存在しますが、ここでは、コミュニケーションを「共有」「議論」「合意形成」の3つの段階に分ける考え方を紹介します。
ここでは受講後のコミュニケーションによって現場に立ったときに明暗が分かれるため、各フェーズにおけるポイントをおさえていきましょう。
共有
「共有」の段階では、お互いに気持ちや情報を「共有」しながら、相手がどんな人なのか、どんな考えを持っているのかを知っていきます。
ここでは、相手の話にしっかりと耳を傾ける「アクティブリスニング」のスキルを育てましょう。
相手の意見を聞き、理解することができたら、自分の考えとの相違点や今後の議論の焦点を明確にしていきます。
相手の考えやいいたいことをより明確にするには、適切な「問い」を立てたり、「ディベート」のように立場を分けたりするなどの方法が有効です。
議論
「議論」の段階は、「共有」の段階で発見したお互いの考えの相違点や、議論の焦点について、実際に議論・討論をしながら、問題点を発見し、解決方法を探っていくステップです。
問題解決の方法を考える際は、ブレインストーミングが効果的です。ブレインストーミングとは議論の手法の一つで、複数人で意見やアイデアを出し合います。
さまざまな視点から意見を出し合うことで、考えが整理されたり、創造的な発想が生み出されたりする効果があります。
合意形成
最後は、問題解決に向けた「合意形成」の段階です。合意形成とは、意見が食い違っている状況の中で、互いに納得がいくポイントを見出すことです。
ブレインストーミングで出した意見やアイデアから、合意できるポイントを見つけていきましょう。
なお、プロジェクトの遂行など、共通の目的を持って業務にあたる場合は合意形成がとくに重要になります。
参加者それぞれが心から納得していれば、全員が当事者意識を持って、同じ熱量で取り組めるようになるからです。
コミュニケーション研修の具体的な内容
さまざまな切り口のあるコミュニケーション研修ですが、ここでは実際の研修で取り組まれている具体的な内容や手法を紹介していきます。
ディスカッション研修
ディスカッション研修はその名の通り、コミュニケーションに欠かせない「ディスカッション」に特化した研修です。
参加者全員が納得する結論の導き方や、意見の整理の仕方を身につけていきます。
ディベート研修
ロジカルシンキングとクリティカルシンキングの能力を開発したい場合は、ディベート研修が効果的です。実際に論争を行いながら、論理的な意見の伝え方や、批判的に考える方法を、体験的に学習できます。
ファシリテーション研修
議論を先導していくスキルを育てるためには、ファシリテーション研修が最適でしょう。
人の意見を引き出したり、異なる意見をまとめたりというスキルに特化した研修です。
対話/問いの立て方研修
お互いの意見の違いをすりあわせたり、相手の意見をより深く理解したりするためには、対話や問いの立て方についての研修が最適です。
テーマに基づいて、それぞれの意見を述べ合い、より相手を深く理解することでお互いの意思疎通を図ります。
傾聴研修
1on1ミーティングにおいて、上司が部下の意見を理解するためには傾聴研修が有効です。
傾聴とは、平たくいえば、「きちんと耳を傾けて聴くこと」、つまりアクティブリスニングです。より深く相手を理解するために、聴く姿勢や質問の方法など、傾聴の具体的なやり方を知っておきましょう。
ロジカルシンキング研修
ロジカルシンキングは、述べることで説得力を持たせるための資質を持つことができます。
したがって、商談の際には、自社の商品やサービスの価値を科学的根拠に基づいて理解してもらうことができます。
また、ロジカルシンキングは、矛盾を生みにくく、相手にわかりやすく説明することができます。
多くのロジカルシンキングに基づいた企業は、仕事のデザインや改善に優れています。企業はリーダーを育成することでロジカルシンキングを習得できます。
研修を行うことで、学んだことを実践に移し、スキルとして発揮できるようになります。最終的には、問題解決スキルや生産性、そして、効率を高める能力を備えることができます。
クリティカルシンキング研修
クリティカルシンキングとは、分析的に物事を考え、本質的な問題を把握するための思考プロセスです。
クリティカルシンキングは、反証プロセス、弁証法、反証法のように、事実や根拠を用いてより高次元の問題を再構築します。
しかし、重要なのは、クリティカルシンキングが意見を否定することではなく、背後にあるエビデンスやデータを精査することで正しい答えを導き出すことであるということです。
クリティカルシンキングは、ロジカルシンキングと比較されることがありますが、どちらもビジネスシーンで重要な思考法です。
クリティカルシンキング研修は、実践的に活用することによって理解を深め、クリティカルシンキングに必要なスキルを身につけます。
実践的な場面では、先入観や仮定を疑い、客観的に分析しながら問題の本質を探究していきます。
ラテラルシンキング研修
ラテラルシンキングは、従来の思考の枠組みから自由で、創造的な解決策を導き出す思考法です。
ラテラルという言葉は英語で「水平の」という意味であり、慣れ親しんだ常識や前提を取り払うことで、物事を新たな角度から見ることができます。
このアプローチにより、多面的な考え方を育むことができます。ラテラルシンキングは、単に視点を変えるだけでなく、抽象的なテーマに対する具体的なアイデアの発想を促進するプロセスでもあります。
ビジネスにおいて、ラテラルシンキングを駆使することは重要です。ビジネスの世界では、学校の課題のように一つの正解が明確なわけではありません。
代わりに、あらゆる可能性を分析し、最適な解決策を見つけるために常に試行錯誤が必要です。
とくに現代のビジネス環境では、変化や不確定要素が多く、過去の常識や前提が通用しないことが多々あります。
ロジカルシンキングとラテラルシンキングは、ビジネスにおいて重要な思考技術であり、コミュニケーションスキルの向上にも役立ちます。
アサーション研修
お互いの価値観を尊重しつつ、自分の意見を明確に言葉にして深い議論を行うためには、アサーティブ研修が有効です。
アサーションとは、意見の対立があるシーンにおいて、相手と対等な立場で、自己主張や説得をするコミュニケーション方法です。
伝える状況に沿って自己主張や説得を行う練習をすることで、相手の立場を理解しつつも、無理なものは無理とはっきりと伝えて代替案を出すといったことができるようになります。
オンライン研修・リモート研修
上に紹介したようなさまざまなコミュニケーション研修を、オンラインで実施する企業も増えています。
オンライン研修・リモート研修を行う際には、対面の研修との違い、メリットとデメリットを理解して実施する必要があります。
オンラインやリモートで研修を行うメリットの一つに、デジタルツールを利用することで講師と受講者や、受講者同士の双方向コミュニケーションが容易になることが挙げられます。
チャット機能やリアクション機能、アンケート機能を活用しましょう。
デメリットとしては、どうしても画面越しのため参加者の表情や反応が読み取りにくい点や、通常業務とは異なる環境で受講する集合研修と比べて参加者が気持ちのメリハリをつけにくいなどの点が挙げられます。
これらの対策としては、受講者のラーニングエクスペリエンスに着目した研修設計を行うことが効果的です。
学習の各段階における受講者の心情を想像し、受講者が業務に結びつけやすい学習体験を得られるよう、研修を設計しましょう。
コミュニケーション研修の具体的な進め方
では、いざコミュニケーション研修を行うとなった場合、どのようにプログラムを組み、進めていけばいいのでしょうか。ここからは、具体的なプロセスを解説します。
目的の設定/活用シーンの明確化
初めに、研修の目的を設定することが大切です。
受講者にとってのコミュニケーションの相手として想定するのは顧客なのか、それとも上司、もしくは社員なのか、という対象を明確にしましょう。
また、コミュニケーションをとる場が会議なのか、商談なのかなどを定め、コミュニケーションのシーンを細かく設定していきます。
そこからさらに、意見相違を解消したいのか、相手の不安を解消したいのかなど、コミュニケーションの先にある目的を定めていきます。
前述のとおり、対象やシーンを詳しく設定すればするほど、実際の現場で起こるコミュニケーションに応用しやすくなり、より実践的な研修が可能になります。
しかし、目的や受講者の状況を具体的に設定すると研修内容をカスタマイズする必要が出てくるため、効果性は向上するものの一人あたりのコストは上がります。
研修の費用対効果を考慮してうまくバランスをとりましょう。
目的設定の際には、「コミュニケーションスキルを習得できた状態」や「コミュニケーションスキルが発揮されているシーン」を言語化することから始めることが重要です。
実践の場が明確になることで研修の結果を現場での実践に反映(研修転移)が容易になります。
また題材が、営業部員向けに実施する交渉や説得のコミュニケーションスキルと、M&Aの交渉のケースでは文脈が全然違います。
複雑なコミュニケーション設計が必要な場合は、外部のベンダーにヒアリングや自社のケーススタディを作成してもらうなどしましょう。
1_信頼構築
まずは相手と会話のペースやテンポを合わせ、相手が話しやすい雰囲気になるよう徐々に信頼関係を築きます。
2_相手の話を聞く
次に相手の話に耳を傾け、相手の話を引き出します。このとき、オウム返しを使って話の整理をしながら聞くことも大切です。
3_伝える
そして理解した内容をわかりやすく伝えます。
このときに意識することは、これまでに出てきた思考法を用いて、情報を整理しコミュニケーションの相手のゴールへ意識を向けることです。
思い込みで進めると結果的に遠回りすることにもなりかねません。
4_相互理解
最後に、相手から発信されるメッセージを理解し、相手の立場や視点、価値観に立って理解を深めます。
自分の立場で相手の意見を理解するだけでなく、相手の立場に立って考えると、より深く理解できるようになります。
研修で扱うコミュニケーションの種類や機能の洗い出しと定義
次に、現場において起こりうるコミュニケーションの種類(手段・ツール)や、コミュニケーションの機能を定義していきます。
やり取りはメールや電話で行われるのか、それとも直接会話するのか、他にもオンライン会議、ビジネスチャット、対面会議などさまざまなケースが考えられます。
どのような種類のコミュニケーションを研修で扱うべきかを明確にしましょう。
また、そこで行われるコミュニケーションがどのような機能を担っているのか、たとえば単なる連絡や調整なのか、合意形成や意思決定なのか、交渉なのか、なども具体的にしておきましょう。
実践と振り返り
研修で扱うコミュニケーションの種類や機能についての定義が完了したら、いよいよコミュニケーション研修を開催します。
集合研修やeラーニングによって、アクティブリスニングや質問スキルといった細かなスキルを身につけます。
必要な知識に関する学習を終えたら、ペアワークやグループワークなどでコミュニケーションの実践を行いましょう。
たとえば、コミュニケーションの目的が「部下に対する動機づけ・エンゲージメントの維持」だとします。
その場合、面談という設定のもとで1on1ミーティングのロールプレイを実施し、振り返りを行います。
振り返りを行う際の一つの着眼点として、「メタ認知」が挙げられます。「メタ認知」とは、自分自身の言動を客観的に把握し、モニタリングすることです。
参加者の声
- 後輩や同僚への接し方がこれまでとは別のアプローチができそうです。こちらからの声掛けやアプローチ方法について多くを学びました。
- 無意識のうちに思い込みにとらわれないよう、視点を変えようと思いました。多様性を意識して周囲と接します。
- 相手の判断軸を知ることや、自分の思ったことがすべて思い通りに伝わることはないことなど、会話の中で理解度を確認しながら先に進められるので、すれ違いのようなことが減りコミュニケーションをとりやすくなると思いました。
コミュニケーション研修は実務に転移させなければ意味がない
コミュニケーション研修で重要なのは実践です。
研修におけるロールプレイなどで模擬形式の実践を行うことも大切ですが、実際の業務の中で実践を行うとより早く効果を実感することができます。
そのため、コミュニケーション研修を行った後は、実際の業務において実践する機会を設けましょう。
コミュニケーションスキルの獲得においては、実践と振り返りの量を増やすことがもっとも早道です。
なお、コミュニケーション研修では外部講師に依頼するケースが多いかと思いますが、実践の量を増やすためには研修の内製化を検討することも必要です。
社員が研修を設計し、講師も社員が務めることによって、より現場の実情に即した研修プログラムを組み立てることができるだけでなく、研修内容に企業風土を反映することも可能になります。
これによって、より研修と実践を密接に結びつけることが可能になるのです。
コミュニケーションの要素はさまざまありますが、基本は「伝えるスキル」と「聴くスキル」です。
小手先の交渉術などを知っていたとしても、基本がおさえられていなければ効果的なコミュニケーションはできません。
時間をかけてでも、まずは基本的なコミュニケーションを身につけ、的確に伝え・聴くことによって相手の信頼を得ることが重要です。
そこから、さらに高度な知識やスキルを積み上げてスキルアップをしていきましょう。
まとめ
社内外とのやり取りを円滑化させるスキルを社員が身につけるうえで、コミュニケーション研修は重要なものです。
まず研修の目的を明確にし、自社に必要なコミュニケーションスキルは何かを洗い出していきましょう。
目的のないまま研修を行っても、思うような効果は得られません。
また、コミュニケーション研修を行った後は、学んだことを実践する機会を用意し、実践と振り返りを繰り返すことで、より早く効果的なコミュニケーションスキルを身につけることができます。