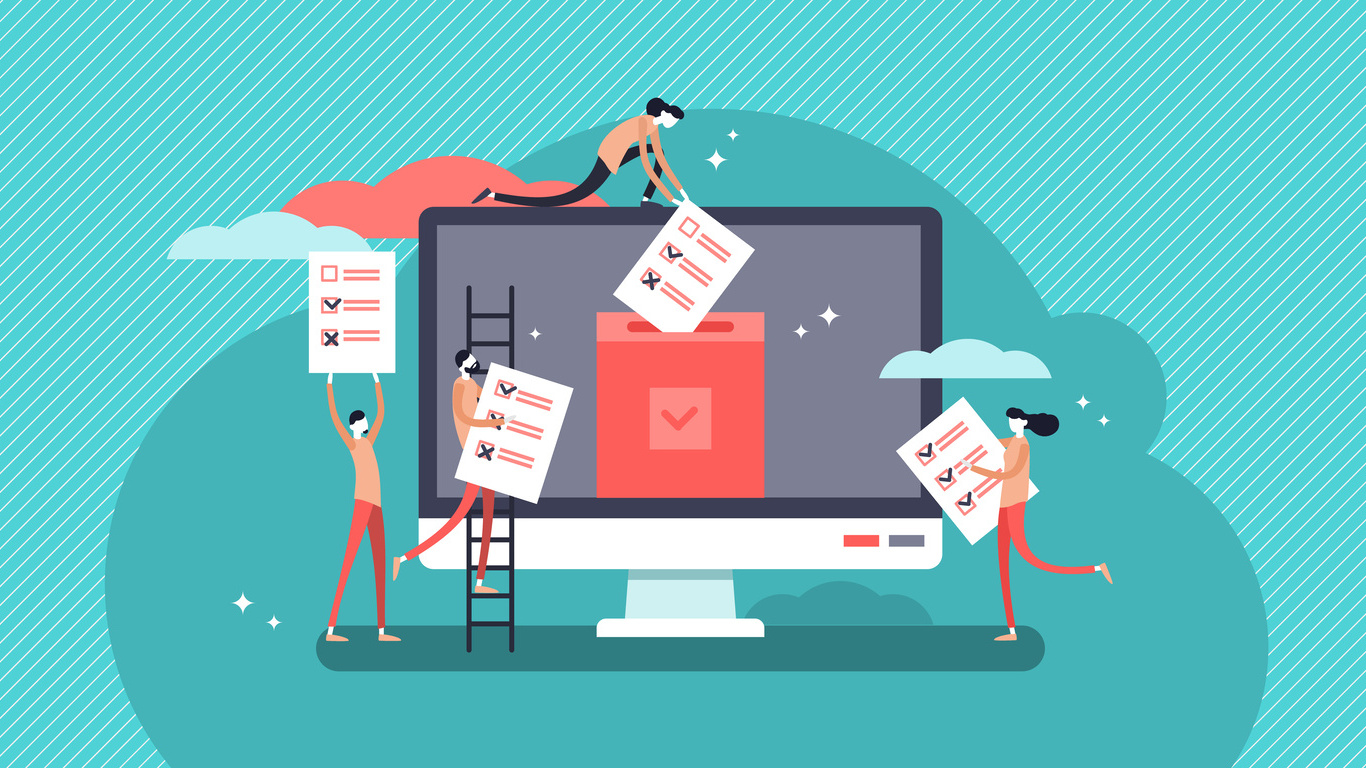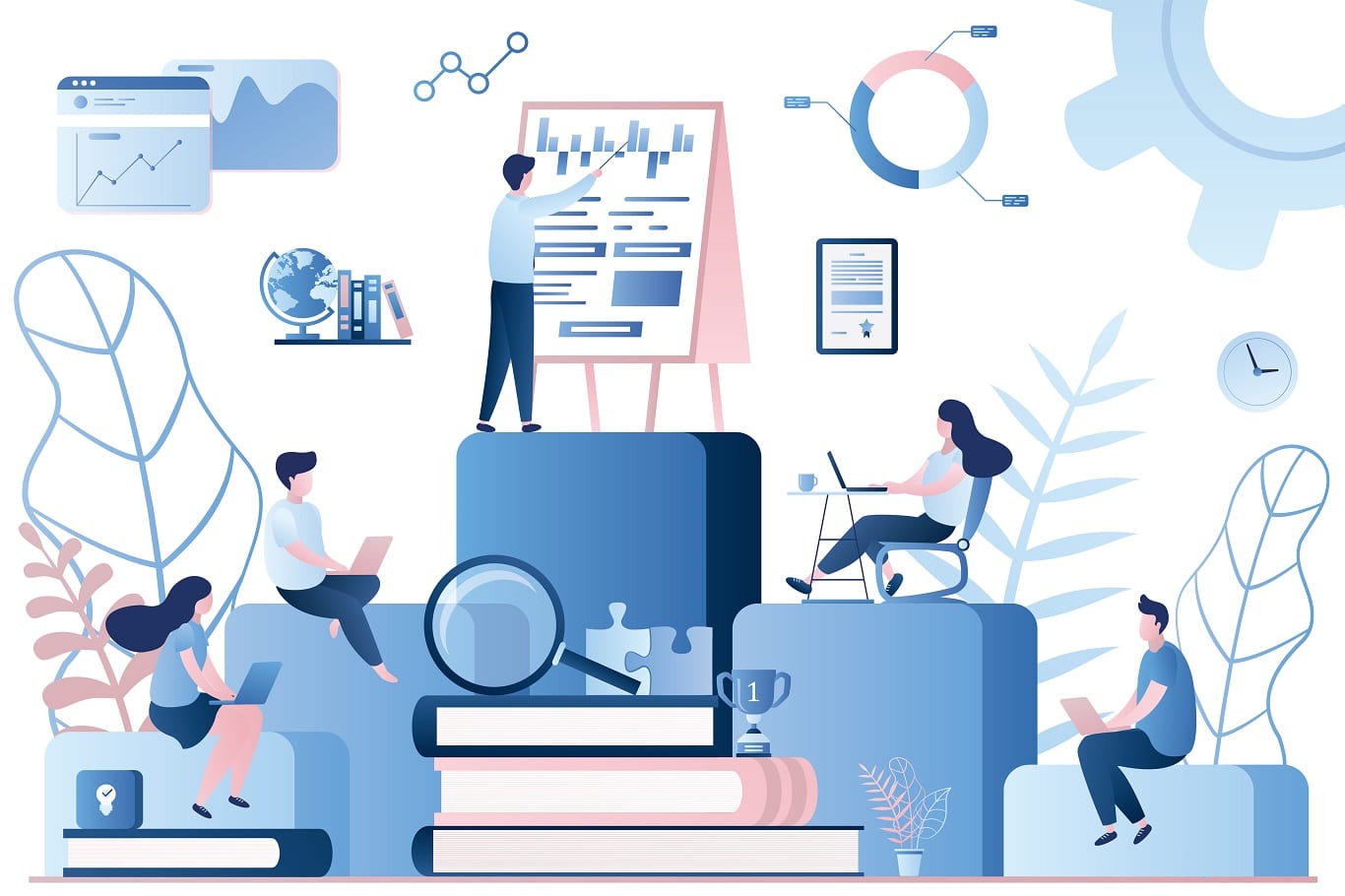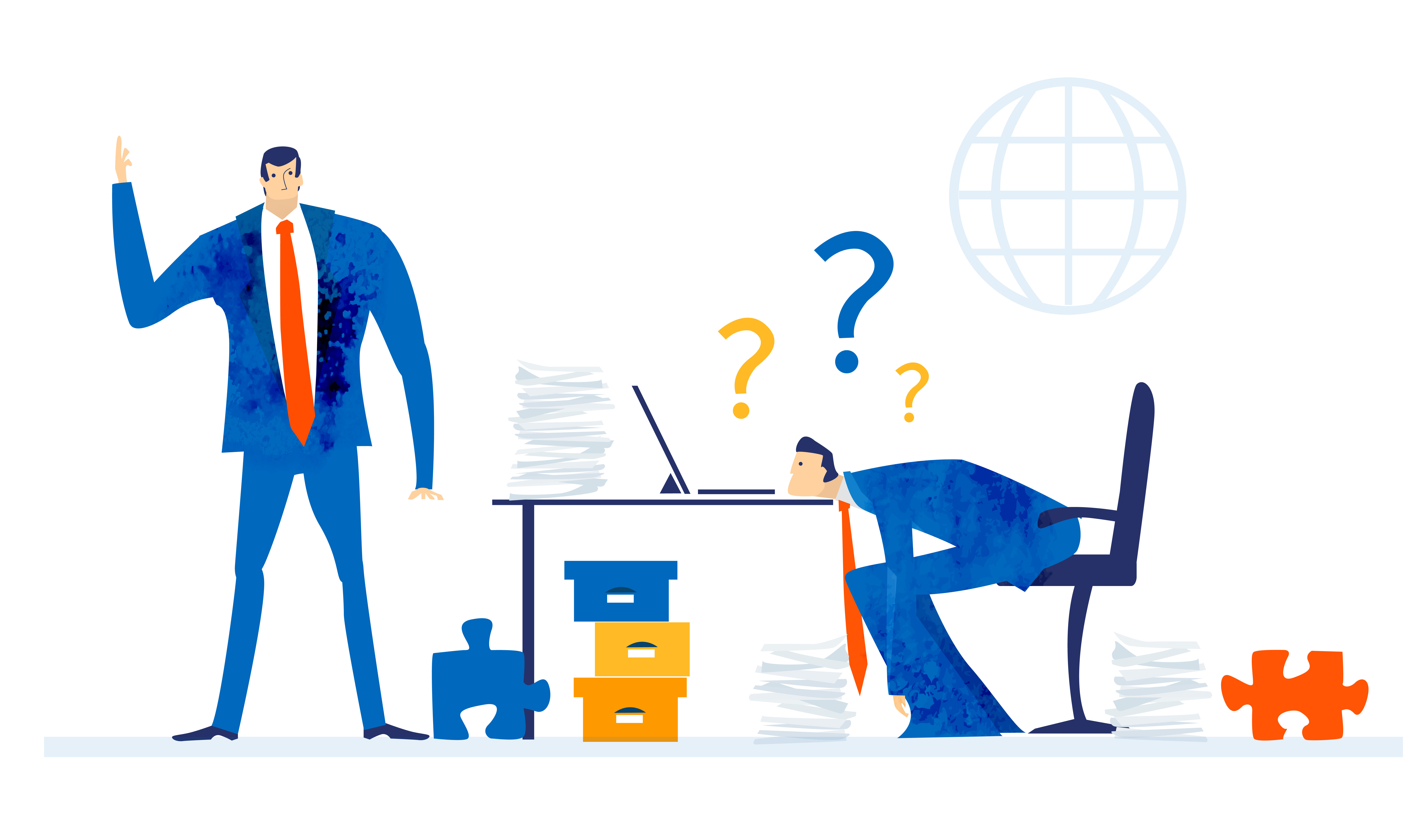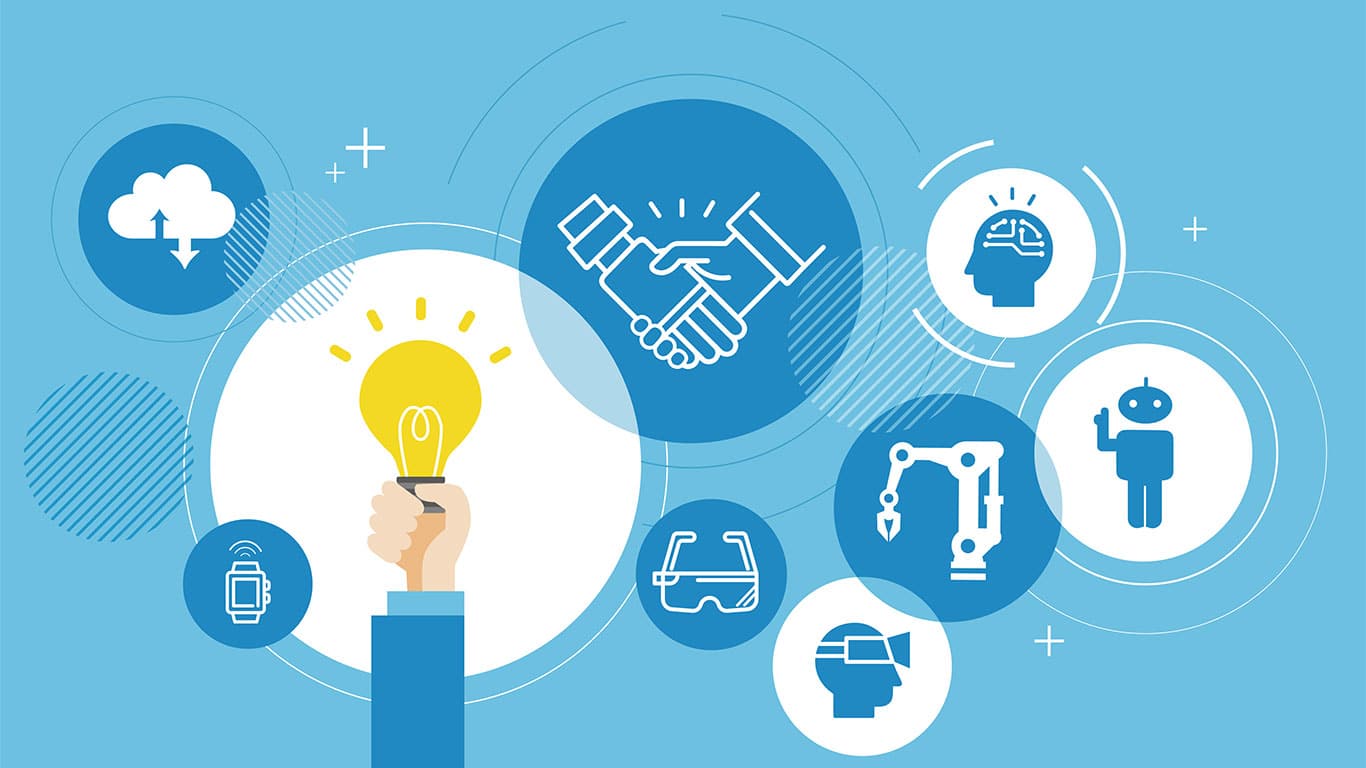従業員満足度とは?取り組み方と4つの事例をご紹介
最終更新日:2024.03.12

目次
従業員に対しての調査研究は、かつてはモラルサーベイ(従業員意識調査)を用いて調査することが一般的でした。
従業員満足度(Employee Satisfaction)調査が日本企業で定着したのは2000年に入ってからとされています。
今では、調査を実施している企業は大手企業の3割超に達しています。
従業員満足度(ES)とは?
この章では、従業員満足度の定義および構成要素について解説します。
従業員満足度の定義
従業員満足度とは、端的にいうと「従業員の組織への満足度」を指します。経営方針・労働条件・人間関係・職場環境などに対する従業員の満足度を指数化したものです。
従業員満足度への取り組みは、経営効率の改善・職場の問題点解決・社員の参加意欲喚起に加えて、社員のモチベーション向上による価値提供力強化を通じた顧客満足度向上をもたらします。
従業員満足度を構成する要素
従業員満足度への取り組みでカギとなるのが、調査項目の設計です。一般的には、以下のような切り口でアプローチします。
- 仕事面:
成長の実感があるか・業務の質量は十分か、仕事に面白さはあるか、やりがいはあるか - 処遇やキャリア:
人事評価やローテーションに納得しているか、将来のキャリアビジョンは持てているか - 会社:
経営方針や事業計画に納得しているか - 上司:
日常のコミュニケーションは十分か、監督指導は適切か - 職場風土:
本音が言える風通しのよさはあるか、メンバー間の意思疎通はできているか、他部署との連携はとれているか
ハーズバーグの二要因理論

従業員満足度にはハーズバーグの二要因理論が関連します。
これはアメリカの臨床心理学者であるフレデリック・ハーズバーグが1959年に導き出した理論で、仕事における満足度は一軸ではなく、「満足」に関わる要因(動機付け要因)と「不満足」に関わる要因(衛生要因)に分けられるというものです。
ハーズバーグの二要因理論によれば、動機付け要因に関わる「達成すること」や「承認されること」、「責任」や「昇進」、ひいては「仕事そのもの」が満たされると人は満足感を覚えますが、もし満たされていなくても「不満足」に至るわけではありません。
同時に、衛生要因に関わる「会社の政策・管理方式」や「業務監督」、「給与」や「作業条件」、「対人関係」などは、不足すると不満足を引き起こしますが、満たしていても満足度を向上させるものではありません。
すなわち本理論によれば、従業員満足度の高い企業は動機付け要因が満たされていることになります。
マズローの欲求5段階説

マズローの欲求5段階説は、アメリカの心理学者アブラハム・H・マズロー氏によって提唱された「人間の欲求構造」に関する理論であり、下層の欲求から順番に満たしていくことを通じて、人間の心理的行動を理論化したものです。この理論では、「生理的欲求」「安全欲求」「社会的欲求」「承認欲求」「自己実現欲求」という5つの欲求が重要視されています。5つの欲求が満たされている従業員が増えれば増えるほど、従業員満足度も比例して高くなる傾向があります。そのため、まずは自社の職場環境や制度が、これらの欲求に応えられるかどうかを振り返ることが重要です。それぞれ解説します。
・生理的欲求
生理的欲求は、生命を維持するために必要な最も基本的な欲求です。飲食欲や睡眠欲、排泄欲などがこれに当てはまり、動物に備わっている本能的な欲求です。「仕事が忙しくて十分な睡眠がとれない」「業務中に休憩やトイレに行けない」といった状況は、生理的欲求を満たすことができない環境であり、生命維持にすら悪影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
・安全欲求
安心欲求は、心身ともに健康で、経済的にも安定した生活を望む欲求です。精神的に不安定であったり、経済的な困窮にあったり、自身の将来が不透明な環境では、「安全欲求」は満たされず、少しでも快適な環境を求めるために行動するようになります。
・社会的欲求
社会的欲求は、家族や友人から愛情を受けたり、組織に受け入れられたりすることを求める欲求です。この欲求は「帰属欲求」とも呼ばれ、満たされなかった場合、孤独や社会的不安を感じる傾向があります。さらに、満たされない状態が続くと不安が増幅し、鬱症状を発症する可能性もあります。
・承認欲求
承認欲求は、他者からの認めや称賛を求める欲求です。自分の成果が褒められたり、行動が称賛されたりすることで満たされます。承認欲求が満たされると、モチベーションが向上し、成長意欲が湧く傾向がありますが、承認欲求が満たされないと、劣等感をおぼえやすくなる傾向があります。
・自己実現欲求
自己実現欲求は、自己の本来の姿で生きることを望む欲求です。「自分が本当にやりたいことを仕事にしている」「描いていた理想の生活を送ることができる」と感じる状態は、自己実現欲求が充足されている状態です。たとえ評価され、他人に羨ましがられるキャリアを築いていても、「本当に自分が望んでいること」を実現できていなければ、自己実現欲求を満たすことは難しくなります。
従業員満足度と従業員エンゲージメントの違い
次に、従業員満足度と従業員エンゲージメントとの違いについて見ていきます。
従業員の動機づけに関する有名な研究にアメリカの産業社会学者エルトン・メイヨー氏が行った「ホーソン実験」があります。
ホーソン実験は、人間の動機づけ要因に関する古典的な実験で、従業員のモチベーションを高めることや、業務に対するやりがいといった人間的な感情を持たせることこそが、生産性を高める上で重要であることを証明しています。只、この時代は、第1次産業や第2次産業が中心であり、生産性のカギを握る資本財は、設備や土地などになります。サービス業を中心とした第3次産業が進むにつれ、人が生産性の中心に移行していきます。
つまりは、職場環境や賃金、福利厚生といった衛生要因だけでなく、職場の人間関係やコミュニケーションといった動機付け要因が生産性や企業業績に影響を与えるとことが中心になり、企業によるマネジメントの対象になっていきました。
他にも、1960~70年代からビクター・ヴルーム氏、レイマン・ポーター氏とエドワード・ローラー三世、エドウィンA.ロック氏などの研究によって、企業の目的と社員の目的の一体化や、適切な目標や成果の設定など、働く人のモチベーションに関連する要素が生産性に影響することが明らかになってきました。一方で、衛生的要因が重要でないわけではありません。従業員の「満足」という状態には複数の要素が影響しており、結果的に生産性に影響しているということが、一連の研究からわかったのです。
現代の第3次産業もしくは、第4次産業革命が叫ばれる中で、社員と会社との関係は、時間と賃金の交換だけでは競争優位を生み出せないという事が確定的な事実になっているという事です。また投資家や株式市場では、2020年8月に米国証券取引委員会(SEC)が上場企業に対して、人的資本に関する情報開示を義務付けました。また、「ワークエンゲージメント」「従業員エンゲージメント」の論文や研究は2000年代から急激に増えています。
「従業員満足度」は「従業員エンゲージメント」に言葉が変わっただけでしょうか?
従業員エンゲージメントとは、社員自身が自発的な熱意を持ってコミットしている度合いのことを指します。従業員満足度は、従業員エンゲージメントを支えるものであり、従業員満足度が低ければ従業員エンゲージメントも高まりません。
従業員満足とは、組織と従業員との関係が、「賃金や処遇、福利厚生」で一定レベルは向上する事はできますが、従業員エンゲージメントは、「賃金や処遇、福利厚生」に加えて、組織の「理念やビジョン」「業務や職務」「組織風土や文化」などの構成要素に、従業員が共感しコミットしている事で向上します。
昨今、「やりがい搾取」という言葉がありますが、従業員への共感やコミットは高い状態を利用し、経営者が従業員にサービス残業や割増賃金の不払いをする逆手に取ったケースもあります。
今日的従業員満足を向上させるために、従業員エンゲージメントという視点を加えなければ、生産性を向上させることは難しいと言えます。
従業員の「満足」の状態に関わる要因は各社各様で、“これ”といって明確に定義できるものではありません。従ってより重要なっているのは、自組織において「従業員が満足することとは何なのか」を定義することです。
従業員満足はどちらかと言えば会社と個人の関係について、物的関係と心理的関係の研究が主で、海外では組織コミットメントという言い方になっています。
従業員エンゲージメントは、会社に対してももちろん含まれますが、チームや職場の心理敵関係に重きを置いています。従業員エンゲージメントも、従業員満足度も定義や質問紙を見るとバラバラで、異一定の支配定義はありません。
従業員満足度を高めることによる企業側のメリット
従業員満足度を高めることによる企業側のメリットを2つ紹介します。
離職防止、人材確保
多くの企業が人材不足に悩むなか、長く働きたいと従業員に思ってもらうことは重要です。働きやすい環境を整えて従業員満足度を向上させると、社内での居心地が良くなり、やむを得ない事情がない限り離職を考えなくなるでしょう。
従業員満足度が高まって離職が減り、人材が流出しなくなると、企業は長期的な人材育成が可能になります。さらに離職率が低く優秀な人が長く働いている企業は、求職者にも魅力的に映ります。その結果、より良い職場環境を求める優秀な人材の確保にもつながるというメリットが得られます。
顧客満足度の向上
従業員満足度が高まると、社員のモチベーションが高まり、より良い製品やサービスの創出につながります。また自社への愛着、ひいては自社の製品やサービスに対する愛着も高い状態で仕事に取り組むことで、自社プロダクトの価値を顧客にも感じてもらいたいと考えるようになり、接客品質も向上していくのです。
製品やサービスの質が良くなり、さらに社員の接客も良くなれば、顧客満足度も高くなり、結果的には企業ブランドのイメージアップや業績拡大にまでつながります。
従業員満足度の高い企業の状態
この章では、従業員満足度が高まることによって企業内に起こる変化について解説します。
企業理念・ビジョンへの共感度が高まっている
従業員の従業員満足度が高くなることで、従業員は自社に対して愛着や帰属意識を持つようになります。
これは、従業員がなぜ企業に集うのかという理由そのものともいえるでしょう。
企業が掲げる理念やビジョンに対して共感の度合いが高まり、事業に対する当事者意識が強化されます。
経営テーマを自分ごととして捉えることができる
従業員の当事者意識が高いと、企業における経営テーマを社員一人ひとりが自分ごととして捉えるようになります。
社員のコミットメントが高まることで、人事異動や評価制度、企業や事業の方向性などに対する納得感や腹落ち感も得やすくなります。
従業員間のコミュニケーションが活発になる
従業員の満足度が高い企業は、従業員にとって居心地のよい場所になります。
居心地のよい場所ではその空間を共有する人たちが交流を図りやすく、コミュニケーションの活発化へとつながります。
従業員満足度が低い状態
従業員満足度が高い状態の企業は多くのメリットを得られるのに対し、従業員満足度が低い状態が続くと多くのデメリットにつながります。
従業員満足度が低い社員は企業に対する愛着心や帰属意識を持てないため、離職率が高くなります。企業は常に人手不足に陥り、つぎつぎと空く穴に人を補充するだけで手一杯になります。採用コストがかさむのはもちろんのこと、長期的視野に立った人材育成も困難になり、優秀な人材が育ちません。
また、残っている社員も当事者意識やモチベーションが低いため、やらされている感が強くなり、業務効率は下がる一方です。従業員満足度が低い社員に自発的な取り組みをする意欲はなく、イノベーションの創出などは到底期待できなくなります。
従業員満足度の低い会社はコミュニケーションも少なくなることから、チームや組織への関心が薄まります、その結果誰もが自分の仕事以外に関心を持たなくなります。ちょっとしたことでトラブルや軋轢が生じ、製品・サービスの品質に悪影響を及ぼすのみならず、人間関係や業務環境への不満から離職へとつながる悪循環になるのです。
従業員にとっての「満足」が変わってきている

現代の労働環境では、従業員が求めるものや満足の基準が以前とは異なってきています。昔は給料や福利厚生が主な要素でしたが、最近ではそれだけでは不十分とし、従業員は、仕事の内容ややりがい、働きやすさ、キャリアの成長などさまざまな要素に重きを置くようになっているのです。
まず、仕事の内容ややりがいが従業員の満足度に大きく影響します。単調な作業や重要性を感じられない仕事では、従業員はやる気を失い、満足度も低下してしまうでしょう。一方で、やりがいや成果を実感できる仕事に従事している場合、従業員は自己成長を感じ、満足度も向上します。
また、働きやすさも重要な要素です。労働時間や休暇の取得、柔軟な働き方など、従業員が自分の生活スタイルに合わせて働ける環境が整っているかどうかが満足度に影響を与えます。ストレスの多い環境やワークライフバランスの悪い職場では、従業員は疲弊し、満足度も低下してしまいます。
さらに、キャリアの成長やスキルアップの機会も従業員にとって欠かせない要素です。従業員は自己成長や将来の展望を持ちたいと考えており、そのためにはキャリアの成長やスキルの向上が必要不可欠なのです。会社が従業員の成長をサポートし、キャリアパスや教育制度を提供することで、従業員の満足度を高めることができるでしょう。
その他にも、職場の人間関係やコミュニケーションの質、意思決定への参加度なども従業員の満足度に影響を与える要素です。従業員は自分の声が聞かれ、関わり合いのある職場環境を求めています。上司や同僚との良好な関係やチームワークの醸成は、従業員の満足度を高める一因となります。
従業員にとっての満足度の要素は多岐にわたりますが、これらの要素を把握し、従業員の求める環境を提供することが重要です。従業員の満足度が高まることで、生産性や企業の成果も向上することを忘れずに取り組んでいきましょう。
従業員満足度を高めるには?
この章では、従業員満足度向上のプロセスについて紹介します。
ゴールを設定する⇒ゴールに対して現状を把握する⇒施策を計画する⇒施策を展開する⇒効果を測定するという流れが一般的です。
定義とゴールを設定する
まずは、自社において「従業員満足度が高いとはどんな状態か」というあるべき姿をゴールを設定します。つまり、「自社の社員が満足している状態」を定義するということです。
多くの場合、ゴールを設定する際に競合や他社の満足度調査の内容を参考にしますが、競合や他社の事例が自社にもマッチするとは限らないということも忘れてはいけません。自社の社員の声に丁寧に耳を傾け、レポートにまとめる等で可視化した上で、自社なりのゴールを検討しましょう。
現状を把握する
設定したゴールに対して、現状満足度がどの程度なのかを把握します。その手段として、前述した満足度調査を行います。
従業員満足度調査の結果を分析する中で、従業員の現状を可視化するとともに、ゴールの達成を阻害している要因を課題として抽出します。
施策を計画する
課題に対する打ち手として施策を立案し、実行の計画を立てます。
同じ会社とはいえ、部門や部署によって職場環境や組織風土が異なり、抱えている課題もさまざまです。
だからこそ、トップダウンで一律の施策を実施するよりも、ボトムアップ方式で部門独自の課題を解決する施策を展開する方がより効果的とされています。しかし一方で経営トップによるリーダーシップのもと人事部門が会社全体の取り組みを主導していくためには、部門責任者による進捗報告と人事部によるモニタリングが欠かせません。
事業部門だけで解決できない課題は、人事部門などが吸い上げて横断的に解決を図りましょう。
施策を実施する
計画した施策を実施します。
施策の規模によって、計画立案から次節の効果測定までのサイクルを調整してください。
効果測定をする
施策実施後、効果はどうだったのか、目標とのギャップはどれくらいだったかを測定します。結果は従業員へフィードバックすると同時に、マネジメント層にも報告します。
上記のプロセスを定期的に繰り返し、持続的に取り組むことで、従業員満足度向上とゴールの達成が期待できます。
従業員満足度を調べる方法
自社の従業員満足度を調べる方法はいくつかありますが、一般的にはアンケートやインタビューを通じた「ES調査(従業員満足度調査)」がよく利用される方法です。従業員の満足度を調査することによって、自社が抱えている課題の状況やその原因など、多くの情報を可視化することができます。
近年は、様々なES調査に関するサービスが提供されており、これらのサービスの中から自社のニーズに合ったものを選んで利用することができます。
自社独自で調査を実施する際は、一般的に以下の手順を踏むことがあります。
・調査目的の明確化
従業員満足度の調査を行うには従業員に時間を割いてもらう必要があります。そのため調査を行う目的を明確にし、その内容を社内に周知します。
・設問の策定
調査目的に合わせて設問を策定します。管理職と一般社員など、従業員の属性によって設問構成を変える場合もあります。多すぎる設問は回答者の負担になるので、設問数には配慮しましょう。
・調査の実施
調査目的によっては、社内の人間関係や個人的な内容が含まれることがあるため、結果の共有範囲や利用方法などは事前に明確にする必要があります。回答内容を秘密に保つためには、外部機関や第三者機関に調査を委託するといった方法も考えられます。
・結果の分析
結果の分析には、項目ごとの合計や平均値を算出する単純集計や、条件を設定して異なる傾向を見るためのクロス集計、そして設問間の相関や因果関係を導き出す構造分析などの方法があります。これらを適切に組み合わせて、表面的な情報にとらわれずに本質的な課題や原因を見極めることが必要です。
・結果をもとにした対策の立案
可視化された課題について、解決のための対策や施策を検討します。課題の内容によって対策や施策は異なりますが、一般的には「賃金や労働時間、その他処遇条件の再評価」「人事制度や勤務体系などの仕組み・運用の再評価」「成長機会やキャリアビジョンの提示」「福利厚生の見直し」といったものが挙げられます。
いずれの場合も関係各所の協力が不可欠となるため、周りを巻き込んで解決に取り組むことが必要になると考えられます。
従業員満足度を高める施策例
従業員満足度を高める施策は、先述の動機要因を高めるものが有効です。
施策を通じて従業員が「働いていて充実している」「何のために働くのかをしっかり見いだせている」と思えるようになることが重要です。
本記事では、経産省が主導する人材マネジメント研究会における、「MVV浸透を通じたエンゲージメント向上施策」を紹介します。
ステップ①MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の共有
MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)とは、企業の使命・あるべき姿・企業の価値観を指します。
これらを定義することは、従業員のエンゲージメントにも影響を与え、リテンション(離職の防止)や人材採用にもつながります。
ただし、MVVは社員へ浸透して初めてその成果を発揮することに注意してください。
従業員満足度を高める施策を成功させるには、社内報やイントラネットなどを活用したメディアコミュニケーションや、社内表彰やワークショップの対話型コミュニケーションを活用し、MVVそのものの浸透を図るとともに、施策実施の背景や目的を共有することが必要です。
ステップ②貢献意欲の醸成・エンゲージメントの向上
従業員満足度を向上させるためには、社員一人ひとりとの対話を踏まえて、主体的なキャリア開発を促すためのサポートプロセスが重要となります。eラーニングやキャリアカウンセリング、さらには部門責任者や役員との1on1ミーティングや小集団活動により、従業員それぞれの貢献意欲醸成を図ると同時に、エンゲージメント向上を促しましょう。
ステップ③組織能力の向上・連携強化
MVV浸透施策を最終的に従業員満足度の向上へとつなげるために、組織活動との連動は欠かせません。
改善活動や新規事業提案、社長賞といった社内表彰や、評価制度の見直しと業績目標への反映、社内報などのメディアを利用したベストプラクティスやロールモデル紹介などを通じて、MVVを組織内で具現化していきます。
ドラッカーもマネジメントの重要な要素としてMBO(目標管理)を提唱しています。
どういった行動が褒め称えられるのかという具体的なイメージを持って従業員が行動することで組織風土を醸成し、従業員の意識改善につなげるのです。
ただ、こうした手法はすでに多くの会社が採用しているはずです。
うまくいく会社とそうでない会社の違いはどこにあるのでしょうか。
MVV浸透施策を展開しても上層部が一方的に発信するだけでは、従業員満足度向上は期待できません。ワークショップ、社内広報さらにはカウンセリング面談など、さまざまな接点を通じた、ひろがりのある社内コミュニケーションが不可欠といえます。
従業員満足度調査を実施する際の注意点
「従業員満足度向上のプロセス」で触れたとおり、施策実施の前段階においては現状把握のための調査が必要です。この章では、従業員満足度調査を行う際の注意点を解説します。
この調査は定点観測のために繰り返し行うものです。組織の現状を的確に把握できる調査結果を得るために、必ず下記の2点を押さえておきましょう。
調査目的を明確にして従業員の理解を得ること
満足度調査はその目的を従業員に明示することが重要です。
回答によって評価への悪影響や人事異動があるのではないかと懸念すると、従業員からはなかなか本音を聞き出すことができないためです。
調査は組織全体を良くする目的で行うものであり、回答者個人が特定されるものではないことを、しっかりと伝えておきましょう。
調査項目を複雑化しないこと
調査項目はなるべく簡潔にしてください。
記名式で多くの項目に答えさせる調査を行うと、前述したように従業員の『人事評価に影響するのでは』などの不安につながりやすく、本音を聞き出すことが難しくなります。
なお、海外では1分ほどで完結する5〜15問程度の項目で構成された「パルスサーベイ」が活用されており、今後は日本でもトレンドになると予測されます。脈拍を定期的に測定するように、「高い頻度で企業と従業員の健全性を測る」ことがパルスサーベイの目的であり、現在発生している問題や事案をすぐに把握し速やかに解消できるメリットがあります。
アンケートは会社と従業員のコミュニケーション接点となるため、自由記述の項目にたくさんの意見を書いても会社から何のレスポンスもなく、施策にも反映されなければも従業員からは不満を招きやすくなります。
従業員の意見を聞くことが目的ではなく、単に全体の現状把握のみを行いたいのであれば、質問項目はなるべく少なく、シンプルにまとめましょう。
従業員満足度が高い企業の取り組み例
最後に、従業員満足度向上の成果を発揮している企業がどんな取り組みを行っているのか紹介します。
三井不動産株式会社
三井不動産グループは、持続可能な社会実現を軸に置いた長期経営方針「VISION2025」というものを掲げています。その理念のもと具体的な6つの目標を取り上げ、社長以下のマネジメント層をメンバーとする「経営会議」が具現化に向けた取組を推進していますが、その1つが「多様な人材が活躍できる社会の実現」です。
具体的にはグループミッション「個の力を高め結集してグループの力へ」を念頭に置きつつ、人材マネジメントの充実・ワークライフバランス改善・働き方改革といった課題の解決を進めています。
●人材マネジメントの充実
一人ひとりの社員がプロフェッショナルとして個の力を高めつつ、多様なスキルを結集してチームとしての付加価値提供力を向上させるべく、同グループでは4つのサイクルを有機的に組み合わせることで人材育成体制の充実を図っています。
①OJT
人材育成の基本となるOJT(ON THE JOB TRAINNING)を重んじ、業務遂行における気付きや社員同士のコミュニケーションを通じて、個々の成長を促します。
②面談
希望するキャリア・ビジョン実現を支援すべく、所属長・人事部門との面談を通じ、育成上の課題・本人の不安・労働環境や育成状況の把握に努めます。
③ジョブローテーション
複数領域を経験させるために定期的なジョブローテーションを実施、環境変化にも柔軟に対応できる真の専門性を身につけます。
同社はオフィスビル・物流施設・ホテル商業施設さらにはグローバルと多様な領域を手掛けており、やる気次第でさまざまなフィールドでの活躍を可能にしています。
④研修
実務面での専門性習得の研修の提供だけでなく、経営問題を議論し合う「MEET21研修」やロールモデル発見をサポートする「クロスエキスパート研修」を開催しています。社員の多様な能力を向上させる研修プログラムを、個人の能力に合わせて受けられる体制を整えています。
●ワークライフバランスへの取り組み
同社では生産性の向上を通じた労働時間削減により、従業員のプライベート充実・自己改革の意欲増進・育児や介護との両立を促し、個々の従業員が能力を十分発揮できる労働環境の実現をめざしています。結果として顧客への付加価値も拡大し、持続的成長につながるという考え方です。
具体的には、フレックスタイム制、連続休暇制度、ファミリーデー、フレッシュアップ休暇制度等を通じて残業時間削減・有給休暇取得を促しています。
とくに育児支援に関しては、法定制度だけでなく事業所内保育所・法定を超える育児休業期間・費用補助制度などに取り組み、結果として正社員の復帰率100%を20年にわたり維持しています。
●働き方改革
同社では多様なライスステージの人材が活躍できる組織づくりをめざし、意識改革・組織単位での業務改革、インフラ整備を柱とする働き方改革をすすめています。
・意識改革
広報や社内イントラを通じた経営トップによる情報発信や好事例紹介に加え、男性の育児支援促進を目的とする施策(育パパトレーニング休暇制度等)の展開
・業務改革
部門別の業務効率化推進と事務局(働き方企画推進室)のサポート
・インフラ整備
シェアオフィス「WORKSTYLING」の活用、在宅勤務制度の定着、事業所内保育所の活用等
カナダマクドナルド
カナダのマクドナルドでは、店舗従業員(社員・アルバイト)向けにスマートフォンアプリを開発しました。
このアプリは、業務上必要不可欠なシフト調整やメンバーとの連絡が可能なツールであり、かつ、アプリ上にカナダマクドナルドの想いや取り組みを高頻度で配信することで、企業のメッセージが自然と目に入るようになっています。
カナダマクドナルドはこのアプリを開発したのは、安全性問題の発生などによってブランドに傷がつきかけていたタイミングでした。アプリを通じて業務における利便性を提供するとともに、「こんな時だからこそ改めてしっかりやっていく」という前向きなメッセージを発信し続けることで、従業員からの共感や納得を醸成することに成功しています。
大山乳業農業協同組合
大山乳業は、自社商品である「白バラ牛乳」からネーミングをとって「白バラ大学」という取り組みを行っています。
今の新卒や若手社員は、企業に属することで成長したいという思いを持っています。
それを、自社に入社・在籍することで知識やスキルを得られるという形に具現化したのが「社内大学」という制度です。
シラバスや学生証づくりから始まる白バラ大学はエンターテイメント性をも含んでおり、社員は楽しく主体的に「大学へ通う」ことができるわけです。
また、学生証があると社外(パートナー企業や地域住人)を巻き込むことができたり、ニュース性に富んだりというメリットがあるほか、従業員が自社へ愛着を持つことにもつながる、社内研修とは異なる取り組みといえるでしょう。
株式会社ソフィア
4つ目は、2020年と2021年に2年連続で日本における「働きがいのある会社」中小企業部門のベスト100に選出されたソフィア(当社)の取り組みです。
当社はインターナルブランディング・インターナルコミュニケーションの専門家集団であり、自社でも同じく働きがいを生む社内コミュニケーションの活性化を取り組みとして実施し、従業員満足度の向上を図っています。
①フリーアドレス制
毎日異なるメンバーと隣り合わせで座ることで、新たな会話を促進しています。
普段の業務とは異なるメンバーとの交流から革新的なアイデアが生まれることもあるとのことです。
②夏合宿
全員参加の夏合宿を創立から毎年行っています。
社員が自分たちでその年ごとのテーマと内容を企画し、グループワークや課題に取り組むことで効果的なチームビルディングを実現しています。
③社員同士の対話の機会を増やす
四半期ごとのキックオフに加え、会社の課題について話し合う「ソフィア会議」、金曜夜にテーマを持ち寄って話し合う「TGIF」など、通常業務の枠を越えた対話の機会によって相互理解が生まれています。
なお、従業員同士の相互理解はコミュニケーションコストを下げるというメリットがあります。
④「自律した個人」の集まりを目指した勤務体系
リモートワークやフレックスタイムを積極的に取り入れており、2017年には総務省より平成29年度「テレワーク先駆者」にも選定されています。
また、業務やスキル習得に必要な書籍を自由に購入することができ、会社がその費用を負担することで従業員の就労への動機づけや意欲の向上を図っています。
まとめ
従業員満足度への取り組みは、単に調査だけを意味しません。現状の課題を抽出したうえで組織一丸となって満足度向上を目指さなければなりません。経営層から現場まで、あらゆる層を巻き込みながら取り組みを推進するためには、インターナルコミュニケーションの活性化が重要となります。
まずはこの記事を参考に、ゴールの設定や現状調査に取り組んでみてはいかがでしょうか。進め方に迷ったときや、課題にぶつかった際には、ぜひソフィアにご相談ください。
組織が内側から変わり、継続的な成長へ動き出す ~「組織変革」成功のポイントとは~
関連サービス