大企業の新規事業は成功率向上ではなく挑戦回数と体制構築こそがカギ
最終更新日:2025.07.03
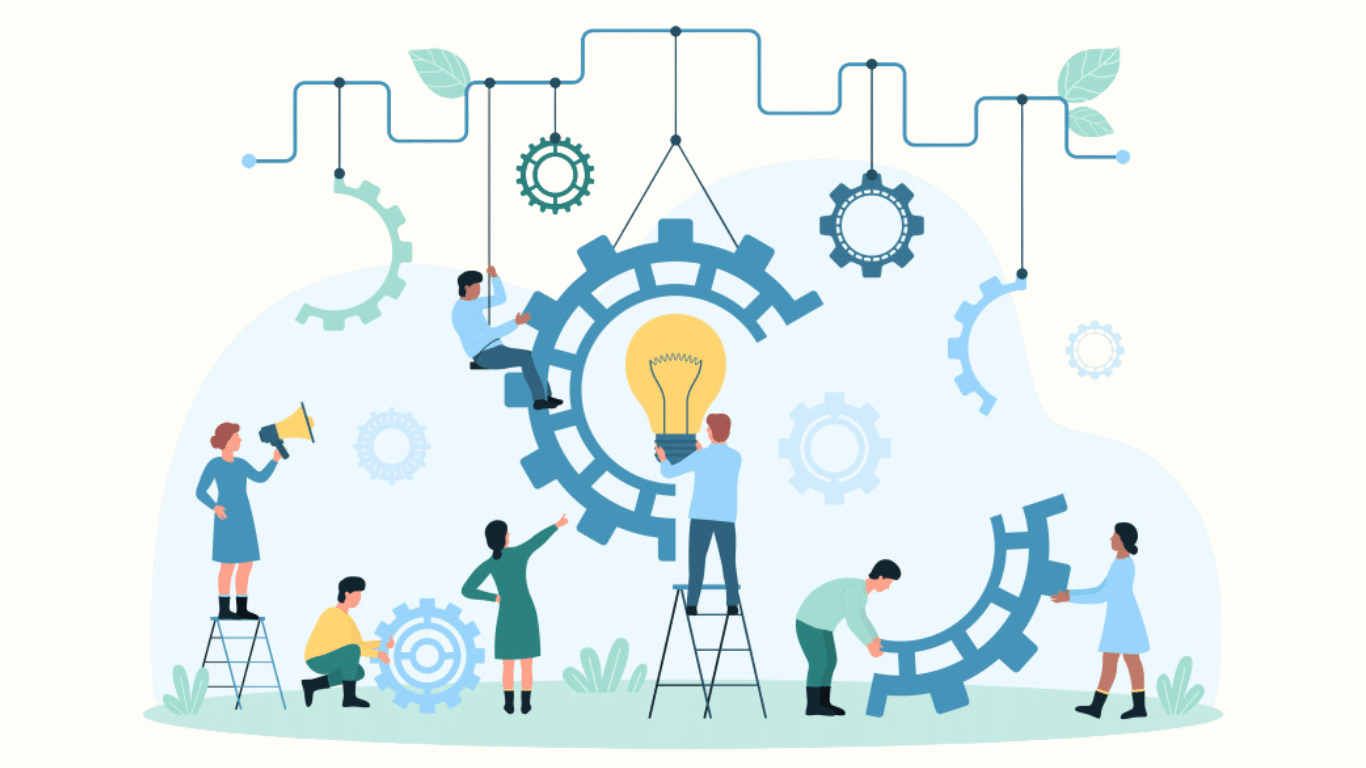
目次
新規事業という言葉を耳にしたとき、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか?社内から革新的なアイデアを募り、大ヒット商品を生み出す光景を想像するかもしれません。しかし現実には、大企業における新規事業の成功確率は驚くほど低いのが実情です。では、大企業はどのように新規事業に取り組めば良いのでしょうか。実は、成功率を魔法のように高める秘策を探すよりも、挑戦の回数を増やし、組織として新規事業を支える体制を構築することこそが成功への近道なのです。本記事ではその理由を豊富なデータや事例とともに紐解き、変化の激しい時代に新規事業で成果を出すためのポイントを考えていきます。
新規事業とは何か?大企業にとっての定義と背景
まず、新規事業とは一般的に「企業が既存の延長線上にはない新たな事業領域に乗り出すこと」を指します。新しい製品・サービスの開発や、これまで進出していなかった市場への参入など、従来のビジネスモデルにとらわれない挑戦を含みます。平たく言えば、企業にとって「第二の創業」とも言える大胆な一歩であり、持続的成長や生き残りのための重要戦略です。
特に大企業の場合、既存事業で確立した強みや経営資源を持つ一方で、新規事業には独自の困難さがあります。大企業ほど事業の意思決定プロセスが複雑であったり、既存の成功体験に縛られて変化に消極的になったりしがちです。それでも新規事業に挑む意義が高まっているのは、企業を取り巻く環境が劇的に変化しているからに他なりません。
なぜ新規事業が必要とされるのか
現代は技術革新や市場トレンドの変化が非常に速く、企業の平均寿命はかつての半分以下に短縮しているとも言われます。実際、1960年代には50~60年あった米国S&P500企業の平均寿命が、2010年以降は約18年にまで劇的に縮んだとの分析があります。これは、現在順調なビジネスに安住していては生き残れない時代になっていることを示しています。「イノベーションを起こし続けない企業は短命に終わる」と言っても過言ではないでしょう。
こうした背景から、企業規模を問わず新規事業創出は経営課題の最前線に浮上しています。実際、マッキンゼーのグローバル調査によれば、世界のCEOの62%が新規事業の構築を自社の3大優先課題の一つに位置付けており、その傾向は年々高まっています。また別の調査では、多くの経営幹部が「今後5年で自社総収益の半分は新規事業から生まれる」と予測しているとの報告もあります。つまり、企業トップ自らが将来の成長エンジンとして新規事業に強い期待を寄せているのです。
加えて、国もスタートアップ支援やオープンイノベーション促進に本腰を入れ始めました。日本政府は2022年に「スタートアップ育成5か年計画」を策定し、大企業にもベンチャー企業との提携や社内ベンチャー制度の活性化を促しています。このように、新規事業創出を取り巻くエコシステムが整いつつある今、チャンスを逃さず自社の未来を切り拓くために新規事業への取り組みが求められているのです。
大企業における新規事業の現状:成功率はなぜ低いのか
新規事業の重要性が叫ばれる一方で、その成功率が低迷している現状も直視しなければなりません。調査によれば、大企業における新規事業の成功率は概ね20~30%程度にとどまるとされ、裏を返せば半数以上、場合によっては8割近くが満足な成果を上げられていないのです。経済産業省の分析でも、新規事業に取り組んだ企業のうち「売上や利益が増加傾向にある」と答えた企業は3割前後に過ぎないと指摘されています。つまり、実際に収益拡大まで達成できている企業は3社に1社程度という厳しい現実があります。
さらに、利益面に着目するとそのハードルの高さが浮き彫りになります。アビームコンサルティングの調査(2018年)によれば、大企業が立ち上げた新規事業のうち累積赤字を解消できた(損益分岐点を超えた)ものはわずか7%にとどまったとのことです。裏を返せば93%もの新規事業が投下資本を回収できず失敗していることになり、新規事業の収益化がいかに難しいかが分かります。
このようなデータから、新規事業開発は「十中八九失敗する」、極端に言えば「千に三つ(千の挑戦のうち成功するのは数えるほど)」とも形容される厳しい挑戦だと言えるでしょう。事実、国内のアンケートでも「自社の新規事業は成功していない(あまり/全くうまくいっていない)」と感じる企業が全体の6割に上った例もあり、多くの企業が新規事業の難しさに直面しているのです。
新規事業が失敗する主な原因
なぜここまで新規事業の成功は難しいのでしょうか。その背景には、失敗の要因が実に様々な面に及ぶことがあります。とある調査では、新規事業が「成功に至っていない」理由として次のような項目が上位に挙げられました。
- アイデアの質の問題(約21%): 「そもそもアイデアがあまり良くなかった」という声です。市場のニーズに合致していなかったり、独自性・優位性に欠けていたりと、種そのものの妥当性に問題があるケースです。
- 社内調整の不備(約20%): 「社内調整がうまくいかなかった」。関係部署間の連携不足や経営層との合意形成が不十分で、必要なリソース確保に至らずプロジェクトが頓挫するケースです。
- 市場環境・競合要因(計約30%): 「強力な競合がいた」「市場環境が悪かった」など、市場側の要因です。競争優位を築けないまま埋もれてしまったり、参入のタイミングが悪く市場が縮小してしまったりといったケースが該当します。
- 顧客ニーズの誤認(約10%): 「顧客のニーズがあまりなかった」。顧客の本当の課題を読み違え、作った製品・サービスが顧客に刺さらなかったケースです。
- コスト・収益性の問題(約17%): 「想定よりコストがかかりすぎた」。開発やマーケティングに予想外の費用がかさみ資金不足に陥ったり、収益モデルの見積もりが甘く赤字が拡大したりしたケースです。
以上を総合すると、特に「アイデアの妥当性」と「社内の推進体制」(実行力・調整力)の不足が、大きな失敗要因になっていることが浮かび上がります。実際、同じ調査では「今後新規事業成功のために強化すべき能力」として「実行に向け多様な人材を巻き込む力」がトップに挙げられており、良いアイデアを出すことと社内外を巻き込んで実行することの両面が課題であると分析されています。
さらにフィンチジャパンの分析では、新規事業の失敗パターンは大きく4つの類型に整理できるとされています。
-
顧客ニーズの見極め不足: 十分な市場リサーチをせずに顧客の真の課題を捉え損ねたケース(経営層の思い込みや社内論理が優先され、市場ニーズとズレてしまう)。
-
市場参入のタイミングミス: 製品・サービス投入の時期が早すぎたり遅すぎたりして機会を逸したケース(技術やトレンドの成熟度を見誤り、せっかくのアイデアも時機を逃す)。
-
経営資源の不足: 必要な人材・資金・技術などが足りず計画倒れになるケース(大企業でも、兼務ばかりで専任チームを置かず予算も不十分なまま進めて途中で息切れすることがある)。
-
協業判断の誤り: 他社との提携や他部門との連携に失敗したケース(自社に足りないコア能力を補えず単独で突き進んだり、逆に外部パートナーに頼りすぎて主導権を失ったりする)。
これらのうち1と2は企画・マーケティング段階での躓き、3と4は事業立ち上げ後の拡大・運営段階での失敗と言えるでしょう。つまり、新規事業の失敗は「企画段階」と「実行段階」の双方に潜むことが分かります。
大企業の場合、以上の要因に加えて特有の組織的な課題も指摘されます。よく言われるのが、「失敗を恐れる社風」や「社内手続きの遅さ」です。既存事業で成功体験があるほどその延長線で物事を考えがちになり、革新的アイデアを阻む風土が生まれてしまい、短期業績を優先するあまり長期投資に二の足を踏む傾向が強まると言われます。実際、ソフィア総合研究所の分析でも「既存事業の成功モデルに固執して新しいアイデアを排除する」「短期業績を優先し長期投資を躊躇する」といった大企業特有の失敗要因が挙げられています。
また、既存事業部門からの非協力も障壁です。社内で新規事業に熱心な現場があっても、中間管理職層が既存業務に固執して新規事業の足を引っ張るケースは少なくありません。前述の調査でも、新規事業担当部署の悩みとして「ノウハウ不足」や「既存事業側の非協力・部門間の壁」が上位に挙がりました。要するに、社内の理解不足や協力体制の欠如が大企業の新規事業を難しくしている大きな要因なのです。
新規事業の失敗は「企画の甘さ」「実行の弱さ」「組織の壁」という三重の課題が絡み合った複合的な問題なのです。
新規事業を成功に導くポイント:成功確率を高めるために
ここまで見てきた失敗要因の数々は、新規事業のハードルを高く感じさせるかもしれません。しかし逆に言えば、これらの課題をあらかじめ認識し対策を講じることで失敗確率を下げ、成功確率を上げることも可能です。実際、数少ない成功例を分析すると、新規事業を成功に導くための共通ポイントが浮かび上がります。本章では、専門家の指摘する戦略的アプローチも踏まえ、新規事業成功のために注力すべきポイントを整理していきます。
顧客起点のアイデア創出と市場適合性
新規事業のアイデアは何より顧客ニーズに根差していることが重要です。ただ奇抜なだけの着想ではなく、市場の不満や潜在ニーズを的確に捉えたものであることが成功への第一歩となります。成功した新規事業の多くは、ローンチ前に徹底した市場調査とユーザー検証を行い、自社が提供すべき価値を磨き上げています。
具体的には例えば、
- 潜在顧客へのヒアリングや観察を通じて真のペインポイント(困りごと)を発見する
- 試作品やテストマーケティングでユーザーフィードバックを集め、アイデアを洗練させる(リーンスタートアップ的な手法)
- データに基づき、経営層の勘や思い込みではなく客観的根拠に沿ってGo/No Go判断を下す
といったプロセスが挙げられます。ポイントは「良い製品を作れば売れる」は幻想だと認識し、「売れる製品とは何か」を顧客から教わる姿勢を持つことです。また、社内のアイデアを活性化する取り組みとして社内ビジネスコンテストの開催なども有効でしょう。社員から幅広くアイデアを募り、多様な発想を引き出すことで、自社の強みを活かしつつも市場に響くテーマを発見するチャンスが生まれます。
経営トップのコミットメントと全社的な推進体制
新規事業の成功には、経営トップの強力なコミットメント(関与と支援)が不可欠です。極端に言えば、CEO自身が本気になれないのなら新規事業に手を出すべきでないとも言われるほどです。トップマネジメントが果たすべき役割は多岐にわたりますが、主なポイントは以下の通りです。
- 明確なビジョンの提示: 新規事業を企業戦略の中でどう位置付け、何を目指すのか、トップ自らが明確に語り組織に共有する。
- 迅速な意思決定: 大企業特有の稟議・承認フローの遅さが致命傷にならないよう、場合によってはトップ直轄で重要事項をスピーディーに判断できるガバナンス体制を敷く。
- 人的・資源的支援: 有望な人材を抜擢し十分な予算を配分するなど、新規事業チームに必要十分なリソースを与える。
- 心理的安全性の確保: 万一失敗しても即座にキャリアを傷付けたりはしないと約束し、安心して挑戦できる環境を用意する。
CEO自らが「失敗しても責めない、一緒に学ぶ」という姿勢を示すことは、社員のチャレンジ精神を引き出す上で極めて重要です。逆に、トップが新規事業に関心を示さないと社員は本気になれず、形だけの取り組みで終わってしまいます。
また、経営トップだけでなくミドルマネジメント層の理解と協力も欠かせません。先述の通り、中間管理職が既存業務に固執して新規事業の足を引っ張るケースは少なくありません。そこで最近では、ミドル層にも新規事業の意義を腹落ちさせ巻き込むために、経営トップと現場リーダー層の定期的な対話の場を設けたり、新規事業に貢献した人を正当に評価する人事評価制度の見直しを行ったりする企業も出てきています。要は、組織全体で「新規事業は会社の未来に不可欠だ」という共通認識を醸成することが成功の土台となるのです。
十分なリソース投入と外部リソース活用の柔軟性
「新規事業は小さく生んで大きく育てるもの」とはよく言われますが、それでも初期段階から最低限必要な人材・資金は惜しまず投入する覚悟が必要です。専任チームを置かず社員が本業の片手間で担当するようではスピードが出ず、気付けば競合に先を越されてしまいかねません。実際、兼務ばかりで進めた結果スピード不足で失敗するケースは大企業で多く報告されています。有望な人材には思い切って新規事業専任にアサインするくらいの決断が求められるでしょう。また資金面でも、前述のとおり多くの企業は数百万円~数千万円程度の小さな予算で実証を開始していますが、成果が出始めた段階で適切に追加投資を行うことが成長加速の鍵となります。初期に芽が出たプロジェクトを、タイミングよく潤沢な水と肥料(人・金)で伸ばす判断が重要です。
さらに、自社に不足するリソースを外部で補う柔軟性も成功には欠かせません。技術的に足りない部分は大学やスタートアップとの協業で補完する、資金が必要ならコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)や外部VCからの出資を仰ぐ、使える公的助成金があれば積極的に活用する──といったオープンイノベーションの発想です。特に近年は自治体や政府系の新規事業支援策も充実しつつありますから、アンテナを高く張り「ないものは外から」と割り切って活用する姿勢が成功確率を上げるでしょう。事実、新規事業開発支援に特化した外部コンサルタントやアクセラレータープログラムを利用する企業も増えています。社内だけですべて完結させようとせず、自社の足りないピースを埋める外部リソースは恥ではなく賢い戦略だと捉えるべきです。
迅速な実行と学習サイクルの重視
かつて大企業の新規事業は「腰を据えてじっくり検討する」傾向が強いものでした。しかし昨今はスピードの重要性が強く認識され始めています。BCGの調査では、大企業の48%が「自社の新規事業の市場投入スピードはスタートアップより遅い」と自己評価しており、多くの経営者が「検討に時間をかけすぎているうちに競合に先を越された苦い経験」を持つといいます。こうした反省から、「初期段階で迅速に動けば成功率は高まる」という認識が広がり、アジャイル開発やリーンスタートアップ手法を取り入れて開発リードタイムを短縮するケースが増えています。
実際、ある大手企業ではアイデア着想から1年以内に試作品を市場投入し、ユーザーからのフィードバックを基に改良を重ねることで、従来は数年かかっていた市場投入までの期間を大幅に短縮した例も報告されています。平均的には新規事業のアイデア創出から事業化まで5~6年を要するとの調査もありますが、近年は可能な部分から素早く市場に出し「走りながら学ぶ」姿勢が主流になりつつあります。成功企業は総じて試行錯誤のサイクルをいかに早く回すかに注力しており、小さな失敗があっても迅速に方向転換(ピボット)することで大きな失敗を防いでいます。要するに、完璧を期してローンチを遅らせるより、不完全でも市場に出して学習する方が最終的な成功に近づくという考え方です。
ポートフォリオ戦略による多数の挑戦と集中投資
最後に強調したいのが、複数プロジェクトを並行して進めるポートフォリオ戦略の重要性です。前述のように新規事業の成功確率が低い以上、一度のチャレンジに全てを賭けるのはリスクが高すぎます。むしろ、複数の新規事業を小さく産んでは見極め、伸ばすべきものに集中的に資源を投下するというアプローチが合理的です。言い換えれば、「多産多死」を恐れず打席(挑戦機会)を増やす戦略です。
これは単に数を撃てば当たるという話ではありません。組織として継続的に新規事業創出に取り組む過程で、社員の知見やスキルが蓄積し挑戦するたび能力が向上していくという効果もあります。実際、連続的に新規事業を立ち上げる企業では、失敗した案件から学んだ知見を次に活かすことで、非常に高い成功率を実現している例もあると言います。またEYパルテノンの調査によれば、大企業の約45%は過去に年間1億ドル以上の売上を生む事業を立ち上げた経験を持つ一方で、それが10億ドル超の企業全体を変革するような巨大事業に育ったケースは全体の10%未満だったとされます。だからこそ、企業全体を牽引するような大ヒットは1つ生まれれば御の字という発想で、同時に10の種を蒔いて1つ当たれば成功くらいに考え、多くの挑戦を行う価値があるのです。
ポートフォリオ戦略を実践するには、社内のリソース配分の考え方も変える必要があります。限られた人材・資金をどう振り向けるか、どの段階でどの案件に集中投資するか──といった投資判断のフレームワークを整備する企業もあります。例えば「リーン・ステージゲート法」など段階的に投資判断を行う仕組みを導入し、効率よく多数の案件にトライして有望株を見極める取り組みです。重要なのは、失敗を前提にポートフォリオ全体で成功を目指すマインドセットを組織に浸透させることです。新規事業は個々で見れば失敗が多くても、全体で成功を掴めれば良いという発想に立つことで、経営陣も現場もリスクを取り挑戦しやすくなるでしょう。
以上、成功のポイントを一言でまとめるなら、「顧客」「組織」「資源」「スピード」「戦略」の5つの観点で周到な準備と柔軟な運営を行うことだと言えます。顧客の声に耳を傾け、組織一丸となって取り組み、必要なリソースは惜しみなく投入し外部とも連携、スピード感を持って学び続け、複数の種を蒔いて育てる──。こうした姿勢を貫くことで、新規事業成功の可能性は飛躍的に高まるはずです。
新規事業成功の鍵は「顧客中心」「トップ主導」「十分投資」「高速学習」「分散挑戦」の5要素を組み合わせることなのです。
成功事例に学ぶ:大企業が新規事業を開花させたケース
ここで、大企業が新規事業を立ち上げ成功させた具体的な事例を二つ紹介しましょう。どちらも従来の主力事業から一見かけ離れた新規ビジネスに挑戦し、大きな成果を収めた例です。それぞれのケースから、前章までに述べた成功要因がどのように体現されたかを見てみます。
ケース1:富士フイルム — 写真フィルムからヘルスケアへの事業転換
「写真フィルムの会社が化粧品や医療機器?」と聞くと驚かれるかもしれません。しかし、富士フイルム株式会社はデジタルカメラの台頭で写真フィルム需要が激減した2000年代、培ってきたコア技術を活かして全く新しい分野に活路を見出しました。その一つが化粧品事業「ASTALIFT(アスタリフト)」です。
フィルム素材の研究で蓄積したコラーゲンや抗酸化に関するナノ技術が、実はスキンケアに応用できる──そこに着目した富士フイルムは「フィルム会社が化粧品?」という常識を打ち破り、自社技術の異分野展開に挑戦しました。写真フィルムの主要成分ゼラチン(コラーゲンの一種)を極限までナノ化する技術や、フィルムの色褪せを防ぐ抗酸化技術は、そのまま肌のハリ維持やエイジングケアにつながります。まさに「非連続の連続」とも言うべき発想転換で、既存技術の新用途開拓に成功したのです。
この挑戦を可能にしたのが、当時の経営トップ古森重隆氏(社長、のち会長)の強いリーダーシップでした。古森氏はフィルム事業の斜陽産業化を早期に察知し、「第二の創業」としてヘルスケア分野に舵を切る決断を下します。周囲に十分な確証がない中でも直感を信じ大胆に事業転換を図ったと言われ、研究所内にも「新しいことをやらねばならない」という前向きな空気が生まれました。このようにトップが先頭に立って変革を推し進めたことが社員の意識を変え、組織の壁を超えた挑戦を後押ししたのです。
また、平時から温めていた技術の芽を活かした点も見逃せません。富士フイルムではフィルム事業が最盛期の頃から細々とコラーゲン研究を続けており、そうしたシーズ(種)があったからこそ追い詰められてから慌ててゼロから始めるのではなく「余裕のあるうちに新事業の芽を摘まずに残していた」ことが奏功したと分析されています。実際、化粧品以外にも長年培った写真現像の化学技術を活かして医療用診断機器や再生医療に乗り出すなど、同社は既存技術の応用で次々と新規事業を開花させました。
結果として、富士フイルムのヘルスケア・高機能材料部門は写真関連部門を上回る収益の柱に成長し、事業構造の転換(第二の創業)を見事に成し遂げた成功例として国内外で高く評価されています。このケースは、自社の強みを活かした大胆な事業転換とトップの強い意思、そして有事に備えて芽を育てておいた先見性が功を奏した好例と言えるでしょう。
ケース2:日本郵政×Yper — オープンイノベーションで生み出す宅配ソリューション
2つ目の事例は、日本郵政グループがベンチャー企業と協業して開発した宅配サービス「OKIPPA(オキッパ)」です。日本郵便(日本郵政グループ)はご存知の通り郵便・宅配事業の大手ですが、近年のEC市場拡大に伴い宅配需要が急増する中で再配達の多発や人手不足が深刻な課題となっていました。自社単独で解決するのが難しいこの課題に対し、同社はスタートアップ企業のYper(イーパー)株式会社と提携し、折りたたみ式の簡易宅配ボックス「OKIPPA」を共同開発したのです。
OKIPPAは集合住宅のドアに吊して使える簡易バッグ型の受け取りBOXで、不在時でも配達物を中に入れて置ける仕組みです。従来の大型宅配ボックスは高価で設置場所も取るため普及が進みませんでしたが、OKIPPAは低コストかつ場所いらずで導入できる点が画期的でした。さらに専用アプリと連動して配達通知を受け取れたり、盗難防止ワイヤー付きで安心して使えたりと、ユーザー目線の工夫も凝らされています。
日本郵便は2020年に実証実験を行い、OKIPPAの有効性を確認すると、翌2021年には10万個を無料配布するという思い切った施策に踏み切りました。その結果、利用者が急増し再配達率の低減や配達員の負担軽減につながることが期待されています。
この事例は、大企業が新規事業を成功させる上でオープンイノベーションの力を最大限に発揮した例と言えます。日本郵政グループには自社内にもノウハウやネットワークがあったと思いますが、あえてベンチャー企業の斬新なアイデアとスピード感を取り入れる道を選びました。自前主義にこだわらず「ないものは外から」という柔軟さが奏功したのです。また、実証実験で効果を確認した後に大規模な無料配布で一気に市場に浸透させた判断力にも注目すべきです。これは、成功の兆しが見えた段階で積極投資に踏み切った例でもあり、前述の「十分なリソース投入」のポイントを体現しています。
以上二つのケースの他にも、例えばソニーでは社内ベンチャーから生まれた家庭用ゲーム機「プレイステーション」が既存の家電事業を凌ぐ世界的ヒット事業に成長した例がありますし、リクルートは創業以来の企業文化として社員の事業提案を奨励し続けることで「ホットペッパーグルメ」など数多くの新規事業を世に送り出しています。またヤマト運輸はEC時代を見据えて宅配ロッカーや仕分け自動化システムなど新サービス開発に積極投資して成果を上げていますし、ダイハツ工業は高齢者向け送迎支援サービス「らくぴた送迎」を立ち上げ、自動車メーカーとしての新たな付加価値提供に挑戦しています。
これら成功企業に共通するのは、やはり顧客ニーズへの深い洞察と社内外のリソースを結集した実行力、そしてトップの後押しの下でスピード感を持って試行錯誤を重ねた点です。富士フイルムのように自社の強み技術を活かして大胆に事業転換した例、日本郵政のように外部パートナーとの協業で新サービスを創出した例など、大企業の新規事業成功ストーリーからは多くの示唆が得られるのではないでしょうか。
まとめ:挑戦を重ね、未来を拓く
新規事業開発は決して容易な道のりではありません。しかし、だからこそ挑戦する価値がある営みでもあります。成功確率の低さに尻込みしてしまえば成功は永遠に訪れませんが、挑戦を続ければ0%だった成功率を少しずつ上げていくことができます。幸いなことに、ここまで見てきたように成功企業の実例や数々の調査データから学べる教訓は豊富です。大企業であっても社内の意識と仕組み次第で、新規事業の成功確率を着実に高めることは可能なのです。
重要なのは、本稿で整理した知見を踏まえつつ、自社の状況に合った戦略で粘り強く取り組むことです。顧客視点を忘れず、社内に新規事業志向の文化を根付きさせ、必要なリソース投入とスピーディーな実行を恐れず、何度でも打席に立ち続ける──そのような企業にこそ、新規事業成功の女神は微笑むことでしょう。
最後になりますが、新規事業のスムーズな立ち上げには組織内のインターナルコミュニケーション(社内の意思疎通・協力体制)も欠かせない要素です。異なる部門を巻き込み新たなプロジェクトを推進するには、社内の共通認識づくりや風土改革が土台となります。私たちソフィアでは、そうした社内コミュニケーション活性化の支援サービスを提供しています。自社で新規事業に挑戦する中で組織面の壁を感じるようなことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。皆様の挑戦が実を結び、次代を担う事業が生まれる一助になれれば幸いです。


















