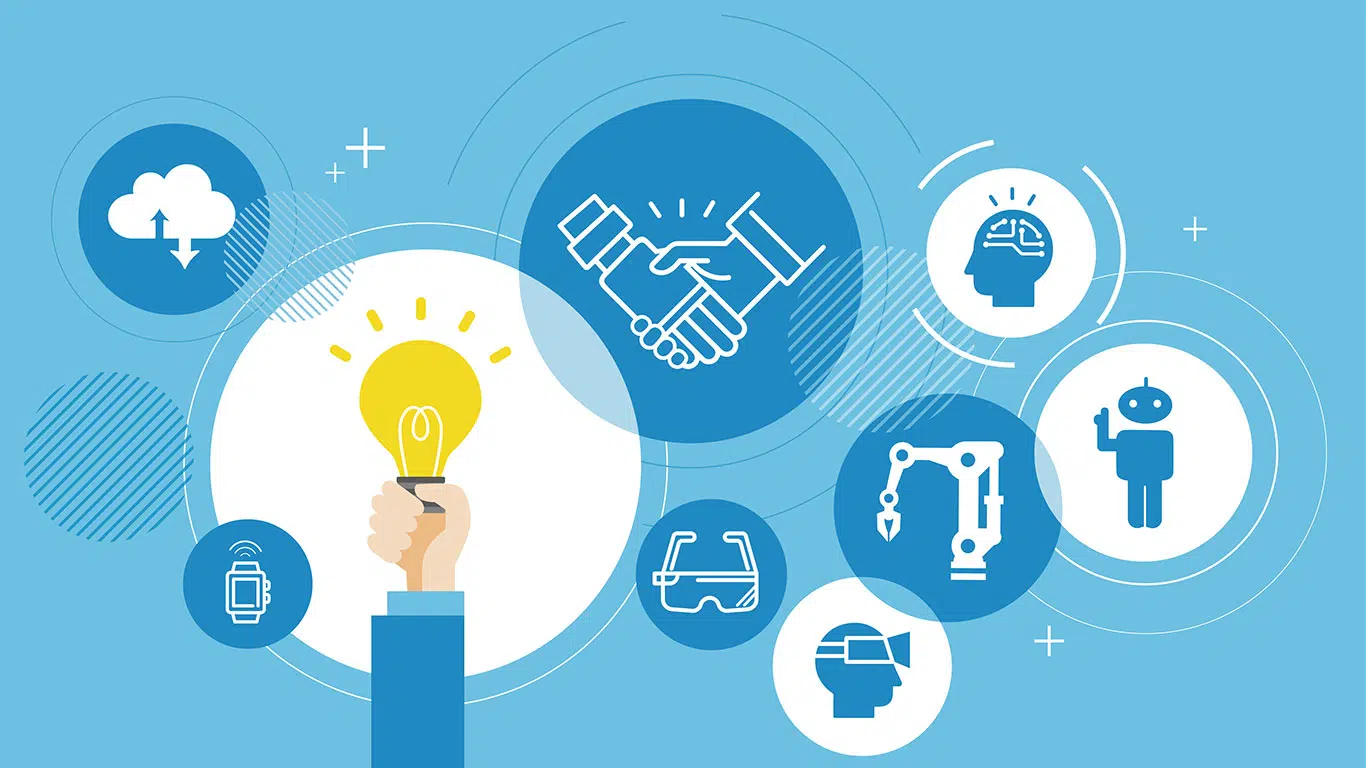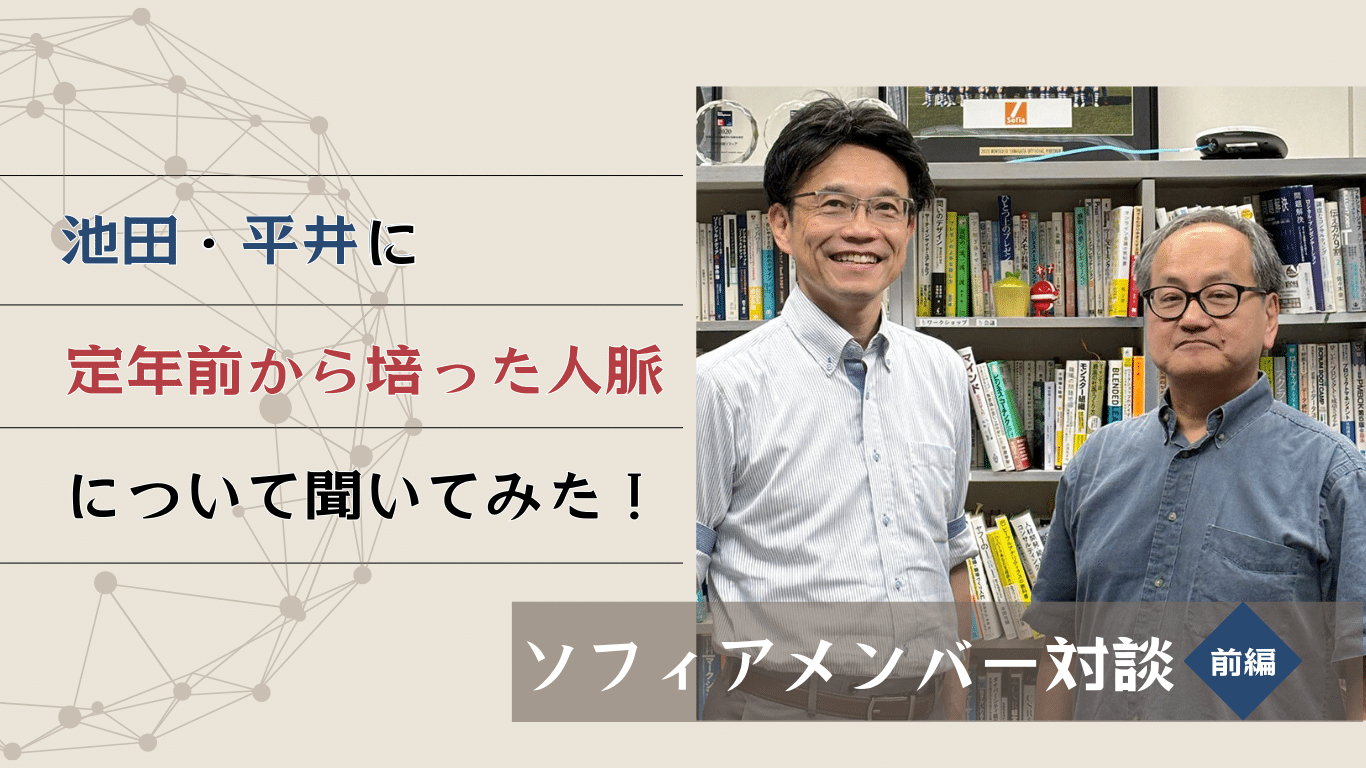暗黙の了解(不文律)とは?組織の不文律を事例から読み解き、その改善策を解説
最終更新日:2025.07.07

目次
たとえば、「上司が帰るまでは帰れない」「女性社員は課長止まり」など、社内規定にないのに皆が従っている暗黙の了解(不文律)が貴社にも存在しませんか?これらは組織文化の一部としてチームワークを支える反面、環境変化や多様化に対応できず成長を阻むリスクもあります。本記事では、企業組織における暗黙の了解(暗黙のルール)とは何かを解説し、具体例やその功罪、そして人事・経営企画担当者が現場で活かせる改善策をご紹介します。
暗黙の了解(暗黙のルール)とは?
暗黙の了解(暗黙のルール)とは、口に出して明言しなくても集団内で皆が了承している決まり事を指します。言葉にしなくても全員が了解している暗黙の規範であり、個人ではなく組織や集団の文化として生まれる概念です。「ここではこうすべきだ」という共通認識・ルールとも言えます。また、文書化されていないルールという意味で「不文律」とも呼ばれ、対義語は明文化された公式ルールである「成文律」です。
日本の職場では、阿吽(あうん)の呼吸で意思疎通を図るハイコンテクストな文化が根強く、口に出さずとも互いの暗黙の前提を読み取って行動する傾向があります。暗黙の了解(不文律)はまさにそのようなハイコンテクストな組織文化に根付いたものでしょう。もちろん、暗黙の了解のすべてが悪いわけではありません(後述するようにプラスに働く場合もあります)。しかし、明文化されないこれらの「暗黙の前提」は往々にして外部から見えづらく、問題が起きても表面化しにくい特徴があります。
組織における暗黙の了解・暗黙のルールの例
組織(企業)においては、日常生活ではみられない独特な暗黙の了解(暗黙のルール)が存在します。組織によっても異なりますが、例えば以下のようなものです。
- 電話は新入社員が取る
- 上司が帰るまでは帰れない
- 上司の誘いは断らない
- メールの返信がなければ「承知した」とみなしてよい
こういった暗黙の了解(暗黙のルール)は、誰しも一度は経験したり、見聞きしたりしたことがあるのではないでしょうか。
先に挙げた組織の不文律は人の行動をコントロールするものですが、逆に以下の例のように不文律があることによってコミュニケーションがとりやすくなる面もあります。
- 相手のことを「さん」付けして敬う
- チームの誰かが困っていたら助ける
- 雑談をすることはあっても、プライベートなことには口をはさみすぎない
これはいわゆる「空気を読む」といった意味合いであり、それによってコミュニケーションが円滑に進む場合もあるということです。
暗黙のルールは「空気」と「水」の関係
日本には「空気を読む」という表現がありますが、暗黙の了解や暗黙のルールはまさに組織の「空気」のようなものだ、と指摘する見方があります。これは評論家・山本七平氏の著書『空気の研究』で提唱された概念です。同書では「空気」とは現代で言う同調圧力やグループシンク(集団浅慮)に近いものを指し、戦時下の日本社会を題材に「空気」が人々の意思決定を支配する様子が論じられています。
暗黙のルール(不文律)は文字通り明文化されないがゆえに、いちいち言葉で確認・共有されることもなく、次第に組織の中で見えない「空気」へと変化していきます。組織や集団に新しく入ってきた新人社員や中途社員は、その「空気」に戸惑いや疑問を感じつつも、大概の場合は組織に受け入れられることを優先するため、いちいち理由を質問することなく周囲のやり方を真似て順応しようとします。こうして暗黙のルールの背景や理由は誰にも語られないまま受け継がれ、気づけば「なぜそれを守らなければならないのか誰も知らない」という状況になりかねません。
では「空気」を変えるにはどうすればよいのでしょうか。『空気の研究』では、「空気」に対比するものとして「水」という概念が挙げられています。この「水」とは、「それはおかしくないですか?」「なぜ皆さんそのような行動をされるのですか?」といった問いかけのことです。場の空気を読まないこうしたコメントが発せられると、組織や集団の参加者はハッとし、一瞬空気が凍り付く――これが「水を差す」という状況です。つまり暗黙のルールという“空気”に対して疑問を投げかける行為であり、暗黙のルールが組織の現実に合わなくなっている場合には、この「水を差す」行動が非常に重要になります。
暗黙の了解(暗黙のルール)そのものが問題というより、「水を差す」コミュニケーションをメンバーが恐れたり避けたりしてしまう風土に問題があります。誰も空気を乱したくないばかりに疑問を口にしない状態では、不文律は半永久的に温存され、組織は変化に対応できません。裏を返せば、状況に合わない不文律には勇気を持って「水を差す」ことのできる関係性を作ることが、組織健全化の第一歩だと言えるでしょう。
自社の暗黙の了解・暗黙のルールに不安を感じたら
暗黙の了解は、先述のように必ずしも悪いものばかりではありません。しかし時代の変化や組織の多様化に伴い、以前はプラスに作用していた不文律が弊害に転じるケースも増えています。実際、企業の戦略や外部環境が大きく変化した際に、従来の暗黙の了解がかえって組織の弱点となり、成長を阻害してしまうリスクが指摘されています。事業環境の激変や人材の価値観の多様化に直面すると、それまで暗黙の前提としていたやり方が通用しなくなることがあるのです。
「自社には暗黙の了解が多すぎて居心地が悪い」「このままでは将来が不安だ」「現状の風土を変えていきたい」──そのように感じている方もいるでしょう。ここからは、そうした組織の不文律を健全な形に見直すために人事・経営企画部門の立場で現場に働きかけられる具体的な方法を紹介します。
暗黙の了解や暗黙のルールが根強い職場では、「それを話題にしてはいけない」という暗黙の前提自体ができあがってしまっている場合があります。そのような状況では、敢えて空気を読まずに問題提起することが個人にとってリスクとなり、社員は内心疑問を抱いていても黙って従いがちです。この前提を変えるには、ゲームやワークショップなど普段とは異なる手法を用いて議論の場を作るのが効果的だとされています。いつもの上下関係や利害を一度脇に置き、メンバーが自由な発想で意見できる場を設けることで、「語られないルール」を疑い直すきっかけが生まれます。
具体的なアプローチとして、以下のような発想法や討議手法を取り入れてみましょう。
シックス・ハット法
客観的・直感的・肯定的・否定的・革新的・俯瞰的という6つの異なる視点で物事を考える発想法です。1つのテーマについて参加者が6色の帽子を順番にかぶり、それぞれの視点で発言することで、新たなアイデアや問題点を発見します。例えば「電話は新人が取る」という不文律を題材に、6つの帽子それぞれの立場で見直してみると、「新人に電話を取らせるのは客観的に見て妥当か?否定的な視点ではどうか?」といったように、当たり前すぎて疑問を持たなかった前提を多角的に検証できます。普段は語られない暗黙のルールの背景や是非を議論し直すきっかけになるでしょう。
ディベート(討論)
賛成派と反対派の二手に分かれてテーマについて議論する手法です。ルールに基づいて肯定派・否定派の役割を演じるため、個人の立場や人間関係にかかわらず安心して議論できます。これにより、普段はタブー視される暗黙の了解の長所・短所の双方について率直に語り合うことが可能です。例えば「男性社員はヒゲを剃らなければならない」といったテーマで、あえて賛否両論に分かれて討論してみると、それぞれの立場から暗黙のルールの意味を考察でき、従来語られなかった前提への理解が深まります。自社の不文律について建設的に見直す土壌作りに役立つでしょう。
問いを立てて議論する
シックス・ハット法やディベートに共通する大事な前提は、「唯一無二の正解はない」ということです。正解が一つではないと考えるだけで、暗黙の了解も「絶対に守るべきもの」ではなくなり、多様な意見が出やすくなります。実際に不文律について話し合う際には、現状の課題に焦点を当てた「問い」から始めてみましょう。例えば「どうすれば新人にもっと電話を取らせるか」と正解探しをするのではなく、「なぜ『電話は新人が取る』という暗黙のルールがあるのか?」「新人が電話を取らないことの何が問題なのか?」といった問いを立ててみるのです。答えではなく問題に焦点を当てることで、新しい視点や議論の余地が生まれます。暗黙の了解を問い直す有効な一歩と言えるでしょう。
このように、普段は当たり前とされている前提に意図的に揺さぶりをかけ、新たな価値観を組織に吹き込むことで、暗黙の了解を見直すきっかけを生み出せるのです。
なんでも言い合える関係性を作る
望ましくない暗黙の了解(暗黙のルール)がはびこっている場合でも、「この風潮はおかしいのではないか」と率直に指摘できる人がいれば、悪弊を打破しやすくなります。そうした何でも言い合える関係性を構築するには、メンバー同士の信頼と心理的安全性を高める取り組みが重要です。心理的安全性とは、メンバーが安心して本音を言い合える状態を指します。上司に遠慮して沈黙したり、同調圧力に屈して意見を飲み込んだりする必要がなく、失敗や異論を口に出しても責められない安心感があるチームは、問題が起こればすぐに誰かが「水」を差すことができます。逆に言えば、心理的安全性の低い組織では誰も不文律を疑問視できず、表向き何事もないように見えても水面下で課題が蓄積してしまいます。

心理的安全性とは?定義や意味と誤解、本質的に高い職場状態や高める方法について解説!
注目されている概念に心理的安全性があります。心理的安全性の概念とは、取り入れる方法とは。本記事では、その起源…
では、心理的安全性を高めるために具体的に何ができるでしょうか。まず社内コミュニケーションを活性化する施策が考えられます。例えば、部門を超えたミーティングやプロジェクトを増やして視野を広げたり、1対1の定期的な面談(1on1)を通じて現場の本音を汲み取ったり、社内SNSやチャットツールで上下関係なく意見を交換できる場を設けたりする方法が有効です。社員同士が日頃からフラットに交流できれば、些細な疑問も共有されやすくなり、問題が大きくなる前に議論し解決できるようになります。
また、最近では組織に潜む不文律や課題を「オバケ」に見立ててチームで探し出し“退治”するというユニークなゲーム型ワークショップも登場しています。例えば、職場やチームに潜む目に見えない課題を12種類の可愛らしいキャラクター(オバケ)に擬人化し、メンバー各自が「どのオバケを見かけたことがあるか」を回答し合います。その結果をもとに皆で「オバケ退治(課題の解決策)」について対話することで、誰か特定の個人を責めることなく全員が率直に職場の問題を指摘・共有できる仕組みになっています。このような手法を活用すれば、普段は口にしづらい不文律の話題でもゲーム感覚で楽しみながらチームで話し合い、建設的に解決策を導き出すことが可能です。
さらに、組織風土の改革には管理職の姿勢が大きく影響します。現場を変えたいと本気で願う部長級の管理職が旗振り役となれば、不文律解消への近道となります。逆に、部長自らが「うちの会社では○○は無理なんだよ」といった不文律を肯定・諦観し、改革に白けた態度を取っていては、組織は何も変わりません。この手の管理職は、自部門内で順当に出世しその部門の不文律のDNAを色濃く受け継いでいる場合が多いとも言われます。そうした状況を防ぐためにも、トップやマネージャー層が率先してオープンな対話を推進し、メンバーが安心して意見できる関係性を築くことが不可欠です。
現状、日本企業では「仲良し」「和」を重んじるあまり、表立った衝突を避けて事なかれで過ごしてしまう職場も少なくありません。一見平穏なようでも、意見の対立を避けているだけでは問題は水面下に潜んだままです。健全な組織には適度な議論や対立(コンフリクト)も必要だと認識し、管理職を含めた心理的安全性の高い風通しの良い職場づくりを目指しましょう。日頃からメンバー全員が忌憚なく発言し、間違いや失敗を許容し合えるチームは、暗黙の了解が悪影響を及ぼす前に自然と軌道修正できる強さを持つのです。
チームの暗黙の了解・暗黙のルールを明文化する
組織やチーム内に存在する暗黙の了解(暗黙のルール)を文字に起こして見える化することで、不文律を客観的に捉え直すことができます。例えば、メンバーで「自社(自部署)の不文律にはどんなものがあるか」をブレインストーミングし、付箋やホワイトボードに書き出して一覧化してみましょう。トップが「遠慮なく挙げてみよう」と号令をかければ、「新しい提案をして失敗すると左遷される」「会議では異議を唱えない方が無難」など、普段は口にしないような社内の不文律が次々と出てくるかもしれません。その上で、それら不文律の中から重要度・影響度の高いものにフォーカスして優先的に対処していくと効率的です。ポイントとなるのは、自分たちの部署・組織の競争力や業績に直結する活動に関わる不文律を見極めることです。まずは業務上クリティカルな暗黙ルールから見直しに着手しましょう。
ただし、この洗い出し作業を社内で行う際には注意が必要です。複数人が集まって自社の不文律を挙げようとすると、「こんなことを書いたら角が立つのではないか」という同調圧力が働きやすく、参加者が萎縮してしまうケースが多々あります。そのため、前述の「前提を変える」発想法を取り入れて場を和ませたり、ファシリテーターを立てて匿名のアンケートを集めてから公開したりするなどの工夫をしつつ進めると良いでしょう。大切なのは、組織の不文律を誰も責めることなく安心して指摘・共有できる雰囲気を作ることです。そうすれば、役職や立場に関係なく建設的な議論が可能になります。
いざ洗い出してみると、暗黙の了解の中には「元々は合理的な理由があってできたのに、時代に合わなくなっているもの」や「本来の意図から離れて形骸化してしまったもの」が少なくないと気付くはずです。実際、多くの企業で「かつて意味があって生まれた不文律が、時代の変化に伴い合目的性を失い、かえって非効率を生んでいる」というケースが見受けられます。そのような現状に合わない不文律が放置されていると、新たに入った社員は「なぜそんなルールがあるのか理解できない」と感じて適応に苦労し、組織に対する不信感を抱くかもしれません。そうした状態から脱却するには、前述の方法で社内で暗黙の了解を洗い出して明文化し、気軽にその是非を発信・見直しできるようにすることが大切です。暗黙の了解それ自体に善悪の判断を下すのではなく、必要に応じて見直し・更新できるかどうかが組織運営のカギだと言えます。
場合によっては、暗黙の了解をそのまま公式のルールや目標として成文化してしまうのも一つの方法です。先述の「女性社員は課長止まり」という不文律に悩んでいた企業の例では、経営トップが単に「女性を積極登用せよ」と号令するだけでなく、あえて「管理職に占める女性比率○%以上」と数値目標を明示しました。さらに「主要プロジェクトのリーダーには女性を必ず起用する」と社内ルール化するなど、暗黙の了解を新たな公式ルールに置き換える取り組みを行ったのです。加えて、女性活用に消極的だった幹部社員に対しては研修を実施し、意識改革を図りました。このように、必要に応じて暗黙のルールを明文化し、それに基づいて研修で固定観念を変えることは、不文律を刷新する王道的な手段と言えます。ただしこれは、「漢方薬」のように効果が出るまでに時間のかかる方法でもあります。組織文化は一朝一夕には変わらないため、腰を据えて継続的に取り組む姿勢が必要です。
一方で、前述のショック療法のように、短期的に組織にインパクトを与えて不文律を揺さぶる施策も併用すると良いでしょう。例えば360度評価(同僚や部下も含めた多面評価)などを実施し、本人が「自分は正しくやっている」と信じている行動と周囲からの評価とのギャップを突きつけるといったやり方です。往々にして、長年不文律と表裏一体で過ごしてきた人ほど自分のやり方に疑いを持たなくなっています。そういった人に対してこそ、客観的なフィードバックで現実を見せ、「水」を差すことが必要です。もちろん、現状を変えようと挑戦する社員を経営陣が徹底的に支援することも重要になります。組織に根付いた暗黙の了解を変えていくには、地道なルール化・教育による改革と、時に大胆なショックを与える改革の両輪で臨むと効果的です。
最後に肝心なのは、暗黙の了解(暗黙のルール)自体を「良い・悪い」で決めつけるのではなく、状況に応じてアップデートできる柔軟性を組織が持てるかどうかです。不文律がいつまでも絶対視され疑問すら持てない状態こそが危険信号であり、それを避けるために上記のような見直しの仕組みを導入しましょう。
まとめ
繰り返しになりますが、暗黙の了解(暗黙のルール)はそれ自体が「良い・悪い」で単純に判断できるものではありません。企業の戦略や外部環境の変化によって、今ある暗黙の了解(不文律)がいつしか周囲に理解されない形骸化したルールとなり、組織の力を弱め、成長を阻害する要因となってしまうことが問題です。そのような状況を変えていくためには、上述した様々な方法によって発想の転換を促したり、社内コミュニケーションを活性化させたりする地道な取り組みが重要になります。一度、自社にはどんな暗黙の了解(暗黙のルール)が存在するか棚卸ししてみて、「やはりこの不文律は変えるべきではないか?」と感じるものがあれば、まずは社内の対話促進やルールの見直しに着手してみてください。小さな一歩でも着実に現状を変えていくことで、暗黙の了解は少しずつ健全な形へとアップデートされ、組織の持続的な成長につながっていくでしょう。