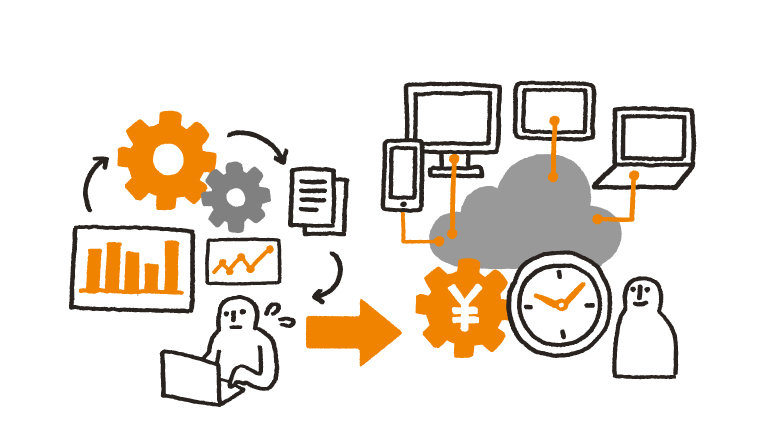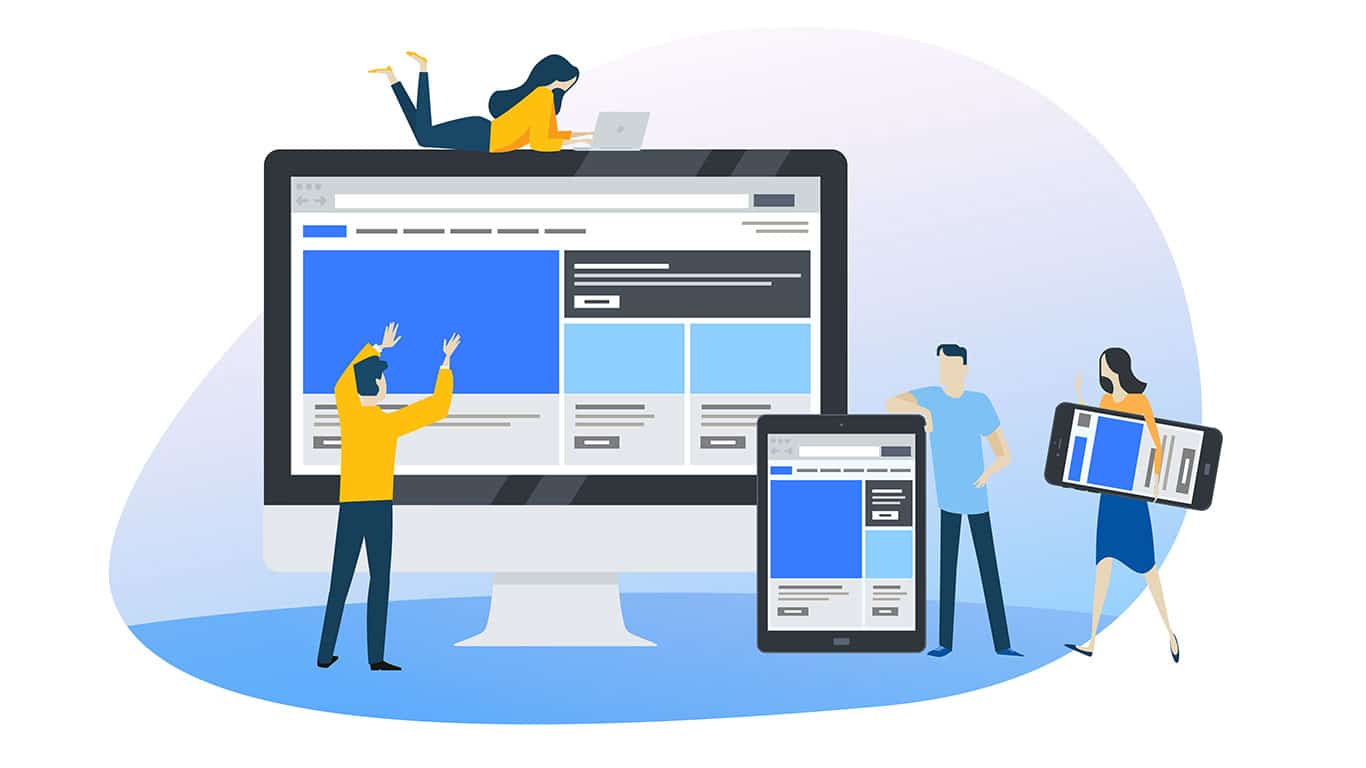イントラネットとは?代表的なサービス、導入時の注意点を解説
最終更新日:2023.05.01

目次
電話やFAX、手紙やeメール、電報などは昔から使われているコミュニケーションツールですが、近年はインターネットの普及により、新たなコミュニケーションツールが台頭しています。例えば、プライベートで用いるツールとしてすっかり市民権を得た「LINE」などは、インターネット普及後に生まれ定番化したツールです。コミュニケーションツールにはそれぞれ特徴があり、適した用途やメリット・デメリットが存在します。そのため、利用シーンに応じて適切なツールを用いることが求められます。この記事では、主に社内で用いるコミュニケーションツールに焦点を当てて、おすすめのツールを紹介します。
社内コミュニケーションツールとは
社内コミュニケーションツールは、社員間での情報や意思の伝達をスムーズに行うために活用されるツールです。業務上必要となる意思疎通や、知識・ノウハウといった情報を素早く共有し、効率的に業務を遂行していく目的で導入されています。近年は、インターネットの普及により情報取得の方法が変わり、新聞などで得ていた情報はニュースサイトやアプリのようなWebメディアに掲載され、デジタル化しました。同様に、社内報など社内における情報取得もデジタル化が進み、社内外ともにデジタルを活用した情報の発信・受信が当たり前になっています。
また、社内で利用できる情報伝達ツールも変わってきています。発信者と受信者の関係性がフラット化し、今までは情報を出す側と受け取る側の一方通行の構図だったものが、双方向にやり取りするコミュニケーションの場へと変化しました。情報伝達ツールの変化を受け、昨今では社内コミュニケーションツールの需要が高まってきています。特に2020年初頭から猛威をふるっている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響と、働き方改革の推進に伴い、オフィス外で業務を行うテレワークの需要が拡大したことが大きな要因です。テレワークによって社員同士が対面で交流する機会が減り、社内コミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーションツールに一層注目が集まるようになりました。
コミュニケーションツールが、実際に円滑なコミュニケーションを生むために
社内コミュニケーションツールを実際に導入する中で重要なのが、ツールがあるというだけで円滑なコミュニケーションが生まれるわけではないということです。これまで対面で行われてきたことが文字・テキスト(それと少しのアイコンや画像)に置き換わる際に生じる問題は、「見ているファイルが違った」「既読がついたので確認されたと思った」などなど、思いもよらないものも含めて数多くあります。これまでも起きていたコミュニケーション上の問題が、オンライン化をあくまできっかけとして表面化するということもあるでしょう。ある企業内の社内調査を経年比較した際、コロナ禍によるロックダウンの前後で、「業務の指示が不明瞭」「背景が共有されない」といった意見が大きく増加したケースがあります。そうした意見を深堀りするためヒアリングを行ったところ、口頭で交わされていた情報量とテキストでやり取りされる情報量は変わらないかむしろ増えており、「これまではオフィスで細かい雑談も含めて共有されてきた文脈」が無くなったことによるものであると結論付けられました。
しかし、そうした「暗黙のうちに察する」ということが自然と求められてきた慣習に対し、「空気を読むのがうまい社員のみが出世する」というような不満も出ていたでしょうし、それよりも、複雑化・不確実化するビジネスや市場環境の中で容易には共通認識を持つことが叶わなくなってきたことにより問題となっています。そして、そもそも関係性の悪い個人間・部門間でのやり取りにおいて、オンラインコミュニケーションがそれらをさらに悪化させ、なおかつそれを不可視なものにしてしまうリスクもあります。指示や依頼と、それに対する承諾といった“タスクコミュニケーション”のみが表面上ではやり取りされ、背景にある目的や意図、不満やストレスが裏で蓄積されるという問題が起きる可能性をコミュニケーションツール導入時にしっかりと想定しておくことが何よりも重要です。
テレワークが普及し、オンラインでの業務推進やコミュニケーションにメリットは勿論たくさんあり、それらを享受していくことは積極的に考えるべきです。しかし、「対面で」「同期的に」やり取りされる情報量を、「非対面で」「非同期的に」やり取りされる情報量が超えることはできません。メリットを捉えつつ、同時に問題を解決していかなければならないということです。
これらの、①情報量の減少 ②個人間の関係性の問題について、もう少し詳しく見ていきます。
-
情報量の減少・・・オンラインのコミュニケーションにおいて交わされる情報量が減るというのは、文脈や前提情報が大きく削ぎ落されるということです。同じものを見聞きし、それを対象に話すということが無くなるので、互いの認識を慎重にすり合わせなければなりません。
-
社員間・部署間の関係性・・・会話の「その場」における目的や文脈にとどまらず、価値観や目標、あるいはより具体的な計画や業務内容などが影響します。
これらを解決するのは本来、話者のコミュニケーションスキルです。自分と相手の目的を理解し、会話の前提となっていることを明確化し、互いの認識を言語化して確認する、といった一連の工夫と習慣がそれにあたります。しかし、全ての社員のそうした能力を向上させる、というのは一朝一夕に実現可能なものではありません。個人の取り組みではなく、コミュニケーションの場の設計と、共有される「規範」によって解決することが求められます。コミュニケーションツール上でどんな問題が起きうるか?それについてどんな工夫が必要か?などをガイドラインといった形で示し、ツール導入時に合わせて情報発信し、また現場側でもそうしたリスクを認識し、改善する意識付けが必要です。こうした問題は実際のところ、オンラインコミュニケーションツールが生んだ問題というわけではありません。これまでも起きていたことが、オンラインで更に悪化してしまうというものです。であるからこそ、ツール導入を一つのきっかけとして、解決に取り組むことが非常に重要です。
社内コミュニケーションツールの機能・できること
多くのコミュニケーションツールには、情報発信や会話を行う以外の機能も備わっています。ここでは社内コミュニケーションツールの機能について紹介します。
チャット・グループチャット機能
社内コミュニケーションツールのチャットは、リアルタイムで文章のやり取りを行い、コミュニケーションを取ることができます。1対1のテキストチャット、複数の人とテキストチャットを行うグループチャットなどの機能があります。チャット上の内容をタグ付けすることや、検索といったテキストならではのやり取りも可能となっているため、業務忘れが減少することにも期待できるでしょう。PCだけでなく、スマホやタブレットからも利用でき、ファイルの保存・共有も可能です。また、音声通話やビデオ通話機能を搭載したチャットツールもあり、オンライン会議やチャットでは伝わりにくい内容を伝えることができます。
ファイル共有
会話の中で画像やドキュメント、各種データを共有する必要が生じた際、ツールの中でファイルを共有できます。別途メールソフトを立ち上げてファイルを送る必要がないためシームレスな情報共有が実現します。また最近では、Microsoft 365に代表されるように共有したファイルを複数人が同時に編集する機能などを備えたものもあります。
タスク管理(スケジュール管理)
ビジネスにおいて徹底したタスクとスケジュール管理は自身のためにもチームとしても不可欠です。特にチームでの業務においては今どの作業工程にあり、誰がバトンを持っていてネクストアクションは何かをしっかりと全員が共有して認識をすり合わせておく必要があります。こうした管理ツールをコミュニケーションツールが内包していることがあるので、あわせて使うとツール活用の幅が広がります。また、ツール自体に管理機能がなくてもAPIを利用して会社内のタスク管理・スケジュール管理ツールと連携をさせられることもあるので、システム担当者へ確認をとってみるとよいでしょう。
通話・オンライン会議機能
テキストでのやり取りで意思疎通が困難な場合は、社内コミュニケーションツールに搭載されている通話・オンライン会議機能が役立つでしょう。その場合、必要になる資料やデータを別途コミュニケーションツールで共有しつつ、音声やビデオ通話によってやり取りすることが可能です。とくにテレワークが推進されている昨今では、Zoomを筆頭とした多くのオンライン会議サービスが誕生し、カメラ機能や音声機能を使った社員同士のやり取りは一般化しています。
社内コミュニケーションツールの種類
社内コミュニケーションツールの機能について解説しましたが、ここでは主な社内コミュニケーションツールの種類について紹介します。
テキストチャットツール
冒頭で紹介したLINEのように、テキストで会話を行うツールです。メールと比べて速報性に優れるほか、1対1だけでなくチームでの会話ができるツールもあります。モバイルデバイスで操作することもあるため、基本的にはメールほどの長文は送らず、短い文章(ショートメッセージ)によるコミュニケーションが主になります。
Web会議(テレビ会議・ビデオ会議)
端末に搭載された(あるいは別途準備して取り付けた)カメラとマイク機能を使い、インターネット回線を利用して遠隔地で画面越しに顔を合わせながら話すことのできるツールです。回線速度に大きく依存するものの、技術の進歩によりビジネス利用であればほぼ遅延や乱れはなくなりました。また参加者の端末に表示されている画面を全員に共有でき、ビデオ通話だけでなく「会議」ができるように工夫されていることが特徴です。
イントラネット・Web社内報
イントラネットと呼ばれる社内の人間だけがアクセスできるネットワークを介して設置するポータルサイトや、かつては冊子が中心だった社内報をオンライン上で展開するWeb社内報も社内コミュニケーションツールのひとつです。イントラネットには掲示板を設けることもできるので、トップメッセージに対する意見を社員が書き込んで交流したり、Web社内報に機能をつけて読者と双方向にやりとりしたりといった使い方もできます。昔は大規模なシステムを必要としましたが、今はクラウドサービスを利用して手軽に導入することが可能です。
社内SNS
「Facebook」などの個人向けSNSに似た社内限定のSNSを活用している企業もあります。ネットワークを介してグループ内で個人同士が交流したり各々の投稿を読んだり「フォロー」をしたりと、全員が顔を合わせる機会の少ない大手企業において部門の垣根を越えて交流する際などに活躍します。
動画配信社内YouTube
こちらは「YouTube」を思い浮かべるとわかりやすいですが、情報伝達の手段として文字だけでなく動画も活用されるようになってきました。動画は文字と比べると情報量が圧倒的に多く、短い時間で印象的なメッセージを発信できます。あらかじめ録画した動画を掲載できるほか、ストリーミング配信という形式でライブ中継も可能です。
グループウェア
グループウェアは、メールやチャットといったコミュニケーションを重視しているツールです。タスク管理やスケジュール管理、連絡先の一覧といった多様な機能が1つになっています。社内外での業務に必要な機能が集約されており、メールや掲示板、共有ファイルなどが1つになっているため、特に企業や組織間での情報共有に適したツールです。
社内コミュニケーションツールを導入するメリット
社内コミュニケーションツールの導入にはいくつかのメリットがあります。ここからは、具体的なメリットについて解説します。
コミュニケーションの流動性が向上する
社内コミュニケーションツールを導入すると、柔軟で気軽なコミュニケーションを取ることが可能になります。コミュニケーションの機会が増えることでチームや社内の風通しが良くなり、知識やノウハウの伝達もスムーズに行われるため、ナレッジの蓄積が期待できます。また連絡メッセージの通知がすぐにされるため、スピード感を持った報告・連絡・相談が行え、業務の修正やミスの予防に役立ちます。さらに、プロジェクトや業務に関する情報の共有を行うことで、社員がノウハウのインプットを円滑に行える点もメリットでしょう。
担当業務がわかりやすくなる
社内コミュニケーションツールは、個人やチーム単位でメッセージを送ることができるので、誰がどの業務を行っているかを明確にしやすいというメリットがあります。またグループごとに社員を分けて情報を共有できるため、社員それぞれが役割を理解しながら業務の全体像を掴める点もメリットのひとつでしょう。社内コミュニケーションツールを導入することで社員の進捗状況を把握し、マネジメントがしやすくなります。
コストの削減
チャットツールを活用することで対面での会議にかかるコストを削減できることもメリットです。また、必要な状況に合わせてチャットではなくオンライン会議を開くことにより、コミュニケーションの齟齬を抑えることもできます。チャット・オンライン会議・対面の中から、内容に適したコミュニケーションを選択することで、コストの削減が期待できます。
社内コミュニケーションツールを選ぶ際のポイント
ここからは、社内コミュニケーションツールを選ぶ際のポイントについて解説します。選定には自社のコミュニケーションの状況を加味して、「必要な機能が揃っているか」「使いやすい仕様になっているか」を重視しましょう。
必要な機能が揃っているか
社内の業務状況に合わせ、検討している社内コミュニケーションツールに必要な機能が揃っているか確認しましょう。多くのデータを扱う場合は、ストレージ容量の確認も必要になります。導入前に現状の業務の課題と、必要なツールの機能を洗い出し、改善に適したツールなのか確認しておきましょう。
使いやすい仕様になっているか
社内コミュニケーションツール全体のUIが、使いやすい仕様・デザインになっているかも重要です。導入したはいいものの、使いにくくてやり取りに時間がかかったり、使えない人が出たりしてしまっては意味がありません。誰でもスムーズに利用できるツールかどうかを確認しましょう。特に情報共有やタスク管理は、社員やメンバー全員で行う必要があるため、使いやすい機能かどうかは必ずチェックしておきましょう。
おすすめの社内コミュニケーションツール12選
ここからは、機能別におすすめの社内コミュニケーションツールをご紹介します(重複あり)。自社の環境に適したものを探してみてください。
おすすめのビジネスチャットツール
ここでは、おすすめのビジネスチャットツールをご紹介します。
Slack
Slackは米国で開発され、主にIT系やWeb系の企業で使用されることの多いクラウド型ビジネスチャットツールです。海外発のツールではありますが、日本語にローカライズされているため利用に際して困ることありません。ブラウザ版、アプリケーション(PC、Mac、モバイルデバイス)版が存在するマルチデバイスのコミュニケーションツールです。特徴としては、1対1のダイレクトメッセージ機能のほかに、ワークスペース内に存在する話題別のチャットルーム(チャンネル)を設けられます。このチャットルームには入室制限や表示・非表示もできるので、職能が異なる人たちが混在する場合でも役立ちます。さらにAPI連携が豊富なことでも知られており、非常に多くのツールと連携して機能する点は大きなメリットでしょう。
無料プラン:あり
有料プラン:1ユーザー925円〜/月(2022年11月16日現在)
Chatwork
Chatworkは、国産のクラウド型ビジネスチャットツールとしては利用者数No.1を誇るツールです。業界・職能問わずさまざまな企業で導入されており、日本企業が運用していることからサポート体制も安心です。また、公式サイトで操作マニュアルや活用の手引き書をPDFファイルにて配布しているので、用途に応じて活用することもできます。Chatworkには話題ごとのチャットルームはないものの、社外のChatworkユーザーとやりとりできる点や、官公庁が採用するほどの高セキュリティ、主要WebサービスとのAPI連携など、安心して使える水準を保っています。
無料プラン:あり
有料プラン:1ユーザー500円〜/月(2022年11月16日現在)
Microsoft Teams
Microsoft TeamsはWindowsでおなじみのMicrosoft社が提供する「Microsoft 365(旧Office 365)」に含まれるクラウド型ビジネスチャットツールです。セキュリティが堅牢であることはもちろん、Microsoft Teamsを使いながら後述するファイル共有ツール(Microsoft OneDrive)のファイルを参照したり、その中のWordファイルやExcelファイルをチャットと平行しながら共同編集したりと、作業をシームレスに行える大きなメリットがあります。チャット機能としてはSlackのようなチャネル機能を設けているほか、1対1、1対他のメッセージのやりとりも可能です。大手企業で導入されるケースが多いのですが、Microsoft 365がとても便利なのであわせて利用することも視野に入れておくとよいでしょう。
無料プラン:あり
有料プラン:1ユーザー約430円〜/月(2022年11月16日現在)
ファイル共有のおすすめツール
ここではコミュニケーションを円滑にするための「ファイル共有」ツールを3つご紹介します。
Google Drive
Google Driveは、Google社が提供するクラウドストレージです。Googleアカウントを持っていれば15GBまで無料で使用できます。ドキュメントや写真、動画などファイルを形式にかかわらず保存できるほか、Google社の提供するGoogleドキュメントやスプレッドシートであれば容量は無制限です。セキュリティに関してはいうまでもなく、また検索エンジンのテクノロジーを生かしたドライブ内のファイル検索機能も強力です。さらに、Googleドライブに保存したファイルは1つ1つにURLが割り当てられるため、共有が簡単でもあります。
最近ではWordやExcelの代替としてGoogleドキュメントやスプレッドシートを使う企業も増えてきたので、有料サービスであるGoogle Workspace(旧G Suite)を利用しているのであればあわせて活用するとさらに便利でしょう。
無料プラン:あり
有料プラン:1ユーザー1,360円/月〜(2022年11月16日現在)
Microsoft OneDrive
Microsoft OneDriveはMicrosoft社提供のクラウドストレージで、最大のメリットはOffice製品との相互性です。WordやExcel、PowerPointといったデータファイルをローカルに置いておくことなく、保存の際にMicrosoft OneDriveを指定するだけで一箇所にまとめることができます。さらに、Microsoft OneDrive上でこれらのファイルを共同編集できる点も大きな強みでしょう。Google DriveのようにURLでファイル共有ができる点も及第点です。
無料プラン:あり
有料プラン:1ユーザー約540円〜/月(2022年11月16日現在)
Dropbox
Dropboxは、クラウドストレージサービスのパイオニアたる存在です。リリースが2008年なので、ブロードバンドが浸透し始めたころにはすでにサービスを開始していました。URLでの共有や共同編集機能はDropboxが他社に先駆けて開発したようです。ローカルに保存したファイルとDropbox上のファイルとの同期が可能なので、ローカルでも作業をしたい場合にはおすすめです。
無料プラン:あり(トライアル)
有料プラン(法人):1ユーザー2,000円〜/月(2022年11月16日現在)
タスク管理・共有ツール
次に、タスクを可視化・管理できるツールを3つご紹介します。
Trello
Trello(トレロ)は、タスクを記載した「カード」をプロジェクトの進捗状況に応じて「カンバン」上でスライドさせながらタスク管理ができるタスク管理ツールです。世界中で数百万人ものユーザーが利用しています。簡単に解説すると、はじめは「Things To Do(すべきこと)」にカードを並べて、開始したらら「Doing(着手)」にカードを移動し、終わったら「Done(完了)」に移動する、といったように使い方が明快です。この画面を全員で共有することでどんなタスクが誰に割り当てられていて今どの状態かを知ることができます。海外産のツールながらローカライズもしっかりしており、利用者も多いことから使い方には困りません。無料で使用できるので、まずは実際に使ってみることをおすすめします。
無料プラン:あり
有料プラン:1ユーザー5ドル/月(2022年11月16日現在)
Backlog
Backlogは、株式会社ヌーラボが提供する国産のタスク管理ツールです。チャット機能も備わっており料金体系がユーザー数ごとではないので、全社でアルバイトや派遣社員など全員で使う際などに力を発揮するでしょう。タスクは担当者や進捗状況、対応期限が一覧で表示されるため俯瞰しやすく、ガントチャートにもできるほか、リマインドメールも送られるようになっています。ヘルプセンター、ユーザーコミュニティ、お問い合わせ窓口がすべて国内にあるというのも大きなメリットであり、海外産のツールはたとえローカライズされていても浸透が不安という場合にはおすすめです。
無料プラン:なし(30日間のトライアルあり)
有料プラン:2,640円~/月(2022年11月16日現在)
Asana
Asana(アサナ)は、Facebookの共同創業者と元Googleエンジニアが立ち上げたタスク管理ツールです。2015年にフルリニューアルを行ってから人気が高まっています。タスク管理画面はTrelloのようなカンバン形式にもBacklogのようなリスト形式にもできます。各タスクにはコメントが記載できるため、個々のタスク確認も楽です。ガントチャートはありませんがカレンダー(タイムライン)形式にも対応しており、Googleカレンダーとの連携も可能です。自由度が高いぶん初心者にはハードルが高いかもれませんが、かゆいところに手の届くカスタマイズ性がAsanaのウリなので、ほかのタスク管理ツールで物足りない方は試してみてください。
無料プラン:あり
有料プラン:1ユーザー1,200円〜/月(2022年11月16日現在)
Web会議(テレビ会議・ビデオ会議)のおすすめツール
テキストではなく動画で社内コミュニケーションをとりたい場合に便利なおすすめツールをご紹介します。
Google Meet
Google MeetはGoogle社の無料ビデオ会議サービスです。有料プランでは1回あたりの会議時間を延長できます(無料プランは1時間まで)。GoogleカレンダーやGmailと連携しており、カレンダーやメールから直接ビデオ会議に進めるのは便利です。招待の際もURLを発行して相手に送信するだけなので手軽であり、社外の人も参加できます。
無料プラン:あり
有料プラン:1ユーザー7.99ドル〜/月(2022年11月16日現在)
Zoom
ビデオ会議を世に知らしめて普及させた立役者がおそらくZoomでしょう。2020年初頭から使われ始め、一時期は業界シェアNo.1を獲得していました。セキュリティ面で懸念があり多くの企業が離れたものの、問題はすべて解決しており、現在はセキュアにWeb会議を実施できます。機能面ではGoogle Meetとほぼ同様ですが、背景を仮想化できる「バーチャル壁紙」はZoomならではの人気機能です。
無料プラン:あり
有料プラン:1ユーザー20,100円〜/年(2022年11月16日現在)
Microsoft Teams
Microsoft TeamsもMicrosoft 365(旧Office 365)に含まれるツールで、Web会議のためのツールです。やはり特筆すべきはOfficeツールとの連携で、会議をしながらその場でWordの議事録を全員で編集したりExcelのグラフを参照したりと利便性に優れます。また、Zoomに続いてバーチャル背景を導入していますので、テレワークで自宅を見られたくない場合には有用でしょう。こちらも単体で使うのではなく他のMicrosoftとともに活用すると効果的です。
無料プラン:あり
有料プラン:1ユーザー約430円〜/月(2022年11月16日現在)
無料ツールと有料ツールの違い
社内コミュニケーションツールには無料のものと有料のものがあります。無料のオープンソースのものは、セキュリティー面の問題や利用人数に制限があるため、一定のITリテラシーがある社員向けのツールとも言えます。有料のものはデベロッパーに企業が付いており、セキュリティー面が堅牢で、利用人数も無料のものより大人数に設定されています。他にも無料のものと有料のものでは、広告の非表示、トークのログ、アップロード容量といった違いが出てきます。社内で使用する場合は、無料のものだと機能面に不足を感じるケースもあるでしょう。
社内コミュニケーションツールを利用する際の注意点
コミュニケーションツールはこうして一覧で並べてみるととても便利に思えますが、実際にビジネスで社内に導入するときには注意すべきことがあります。それは、「導入しただけでは意味がない」という点です。詳しく見ていきましょう。
ツールが社内に浸透するよう働きかけが必要
こうしたツールを導入した際、勉強会やレクチャーを行う企業はまだ少ないのではないでしょうか。ITリテラシーの高い社員であれば特に説明がなくてもすぐに使いこなせるようになりますが、人によっては使い慣れず放置してしまうこともあります。そして使えない人が増えてくるとだんだんと利用離れが加速してしまうこともあります。コストや労力はかかるかもしれませんが、「なぜ導入するのか」「導入するとどうなるのか」「どうやって利用するのか」「わからないときはどうすればよいのか」を明らかにし、全社に浸透させるよう積極的に働きかける活動が不可欠です。たとえどんなに便利なツールでも使われなければ意味がありません。
ツールに頼りきりにならない
チャットツールが浸透してくると、オフィスが静かになりがちです。人によっては息が詰まると感じることもあるようです。コミュニケーションツールは既存のコミュニケーション手段の完全な代替というわけではなく、あくまでコミュニケーション手段のひとつとして捉えましょう。顔を合わせられるならこれまで通り口頭でのコミュニケーションも大事にしつつ、簡単に済ませられる用件であればチャットツールを使ったり、在宅ワークの社員とはWeb会議を利用したりと、ツールに頼りきるのではなくうまく使い分けることが重要です。
コミュニケーションを整理する
さまざまな社内コミュニケーションツールを紹介しましたが、これらを自在に使い分けるためには、まず「コミュニケーションの整理」が必要です。コミュニケーションが整理されていないと、これらのツールをいつどこで使えばいいかがわからなくなってしまいます。コミュニケーションの目的と手段を整理し、適切にツールを活用できるようになる必要があります。
まとめ
社内コミュニケーションツールは、情報の伝達、チャットツールによる迅速なやり取り、ファイルの共有やタスク管理といった、ビジネスにとって必要な機能が集約されたツールです。しかしその恩恵を受けるには、社員同士にコミュニケーションの土台ができていることが前提で、便利な機能だけを目的に導入しても上手く機能しません。ツールはあくまでも業務自体を効率化するものです。ツールが人同士のコミュニケーションを改善してくれることはなく、ツールの機能のみに頼った機械的なやり取りは、逆にコミュニケーションを悪い方向へ向かわせてしまう場合もあるでしょう。
社内の人間関係に問題がある場合は、意見交換などのアナログな手法によってしっかりと向き合うようにしましょう。場合によっては、コミュニケーションの専門家を呼ぶ必要があるかもしれません。その上で、改善点や向上すべき部分に適用する形で社内コミュニケーションツールを導入し、活用していくようにしましょう。社員同士のコミュニケーションの土台ができている状態であれば、社内コミュニケーションツールの導入によって、知識・ノウハウといった情報が社員で共有され、社内全体の業務スキルが向上する恩恵を受けることができます。社内の状況に適したコミュニケーションツールを実装できれば、効率的でスムーズな業務進行を行うことができるでしょう。
関連サービス
- 調査・コンサルティング ―さまざまなデータから、課題解決につながるインサイトを抽出―
- ICTシステム活用支援 ―課題解決や目的達成に最適なシステム導入のお手伝い―
- メディア・コンテンツ ―読者と発信者、双方の視点に立った企画、設計―
- 業務プロセス最適化 ―インターナルコミュニケーションの視点で業務を再設計―