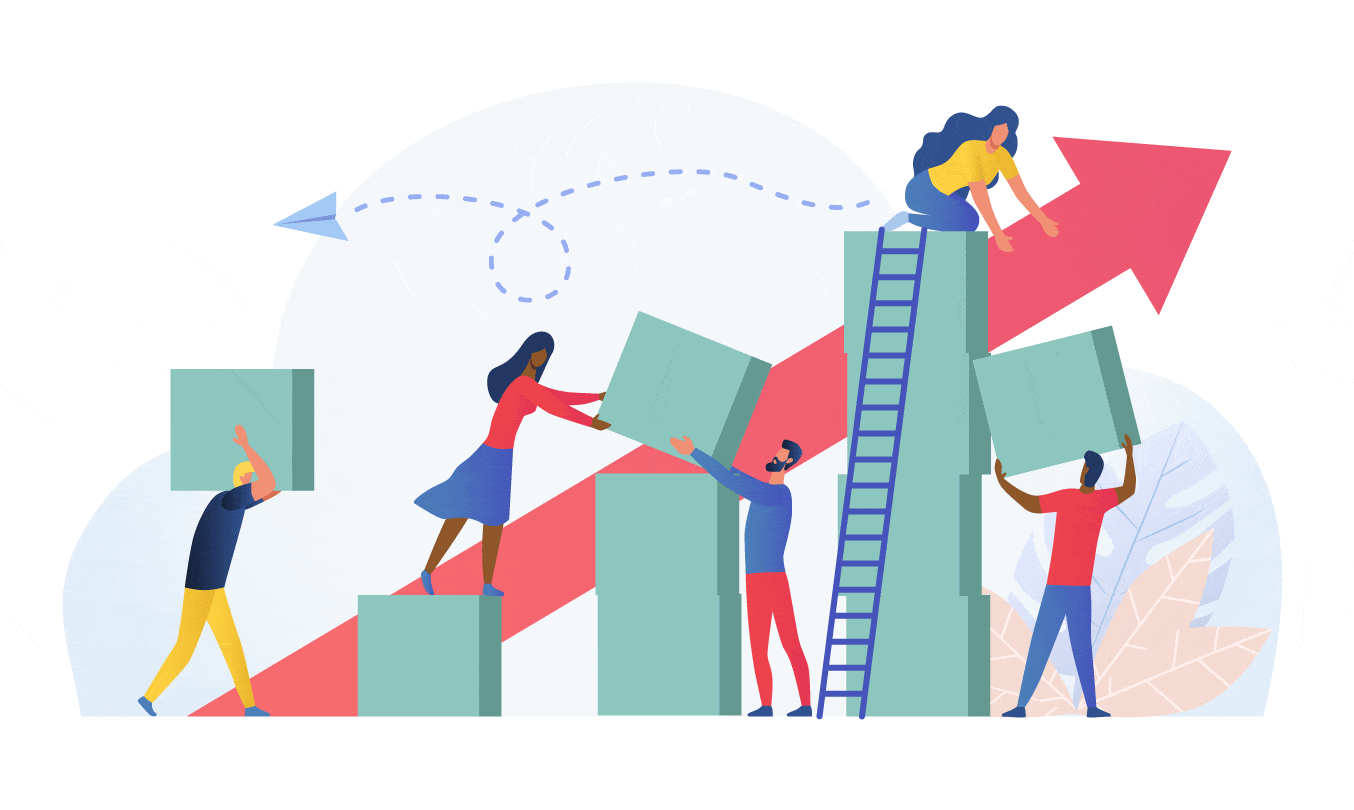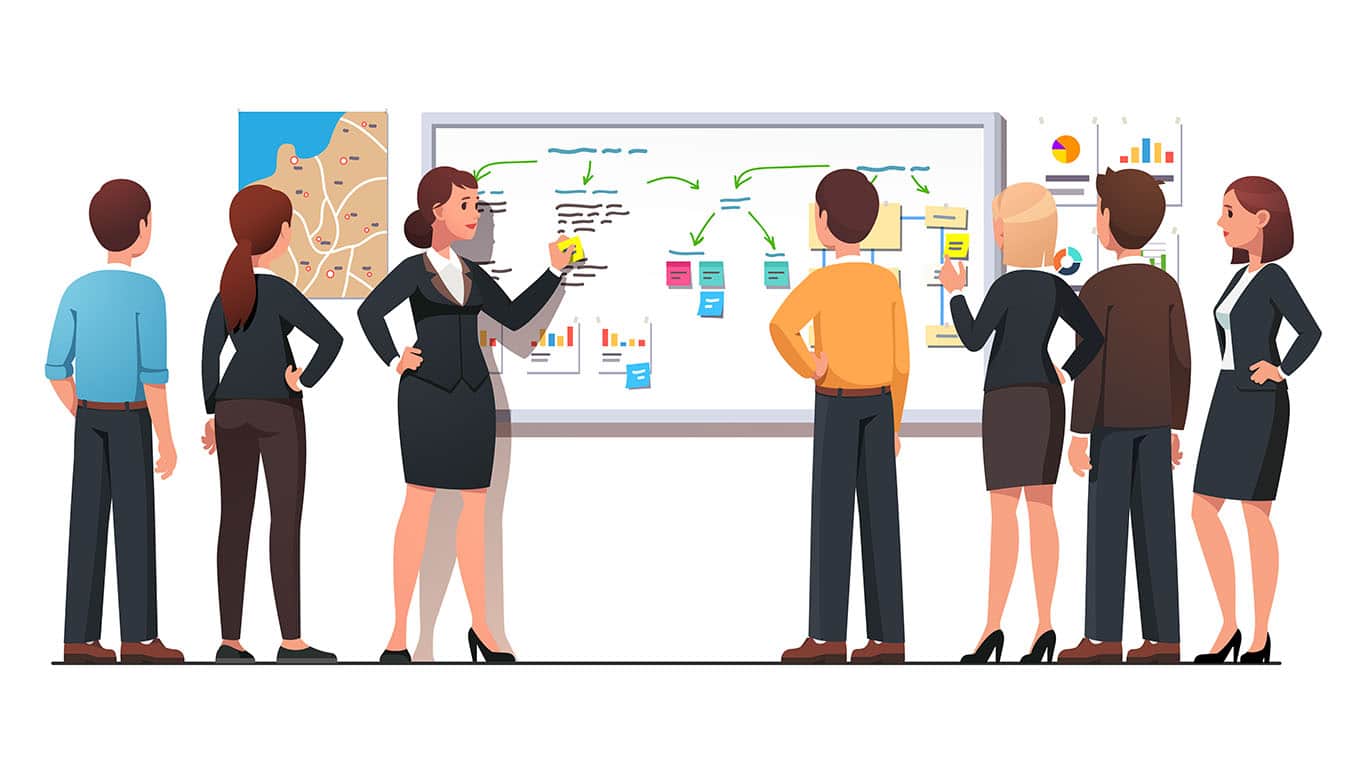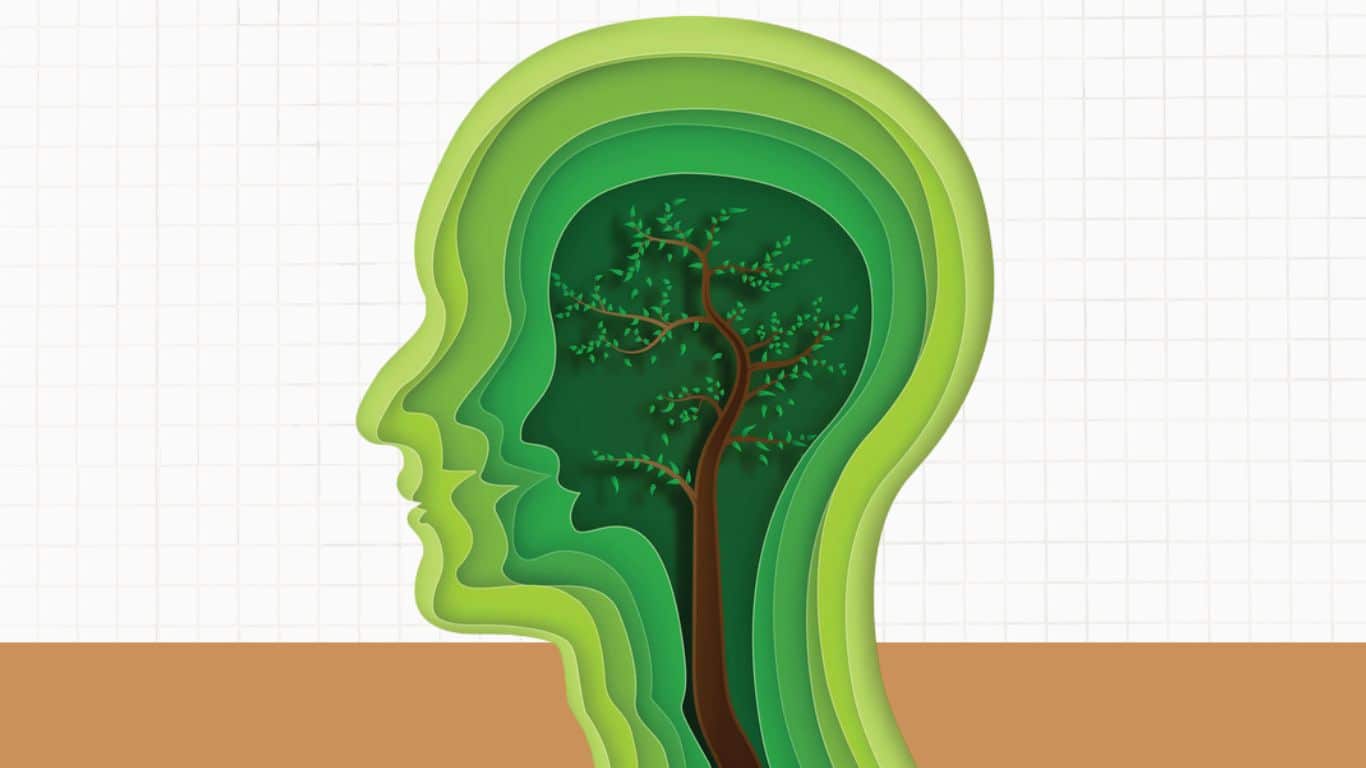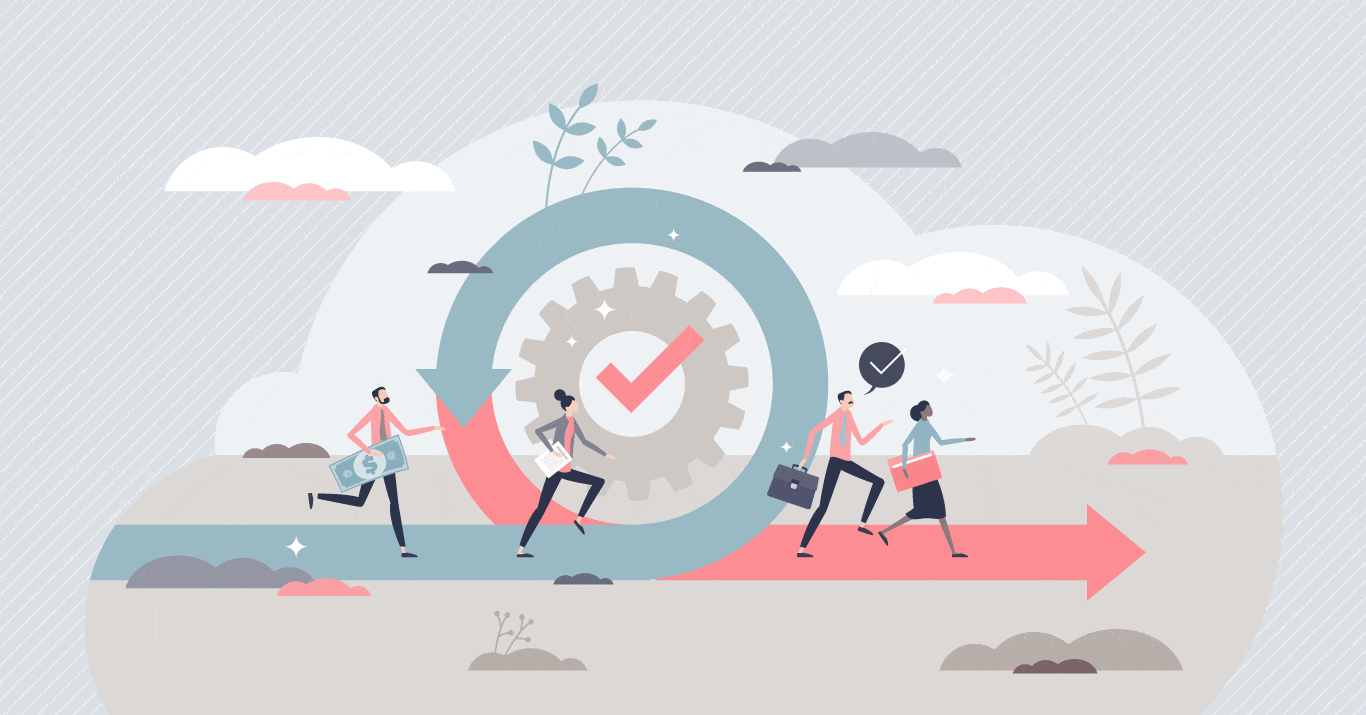OJTとは?意味や目的、メリットや効果的に進める方法を紹介
最終更新日:2023.12.26

目次
昨今のビジネスシーンでは、人材育成の手法として「OJT」が多くの企業で実施されています。OJTは、日本の現場力の中心的な機能として、あらゆる仕事の現場で用いられています。しかし、現在、OJTを支えてきた終身雇用という日本独自の雇用形態が崩壊し、劇的な変化の時を迎えています。
本記事では、OJTの背景・概要・メリット・デメリットや機能させるためのポイント・効果が発揮されない原因などについて詳しく解説していきます。
OJTとは
OJTは「On the Job Training」を略した用語で、実務を行いながら知識・スキルを身に付ける人材育成の手法です。在籍する従業員が育成が必要な新入社員などの人材に対し、実務上で伴走しながら指導を行います。
OJTが適用される範囲は広く、営業の同行から工場などでの個別作業、細かい業務では電話対応や簡単な資料作成に至るまで、業界・職種を選ばず行われています。実務を通して業務を学ぶため、口頭での指導や座学などとは違い、より実践的な形で能力向上と経験を積めるのがポイントです。
伴走しながら指導やコーチングでインプットし、現場や実機でアウトプットするというかなり効率的・教育的なアプローチだと言えます。
OJTの意味
OJTとはそもそも、アメリカの造船所で現場監督を務めていたチャールズ・R・アレンが、1917年に提唱した「4段階職業指導法」がベースになっています。「4段階職業指導法」には以下の4つのステップがあります。
- Show:やってみせる
- Tell:教える
- Do:やらせてみる
- Check:指導する
OJTも上記の4つのステップを基本としており、形は変わっているものの、実践的にかつ効率的に物事を教えるという点は受け継がれています。「4段階職業指導法」こそがOJTの始まりであり、1942年~1945年ころの第二次世界大戦中のアメリカで誕生する企業内訓練プログラム「TWI研修」(Training Within Industry for supervisors)にも派生しています。
「TWI研修」は日本にも1950年(昭和25)に導入され、1955年から始まる高度経済成長期の中で体系化し、日本独自のOJTの基本形が作られました。現代でも、まずは先輩がお手本を見せてから説明し、実際に後輩にやらせてみて修正点を指導する流れは定番の指導法です。部活でのスポーツ・音楽・美術から始まり、ビジネス上の指導に至るまで、OJTに通ずる指導法は広く根付いているのではないでしょうか。
OJTする側であるトレーナーが保有する技術や技能を、OJTされる側であるラーナーが見様見真似でやってみて学習する流れです。
ビジネスにおいて研修でOJTを行う目的
ビジネス上のOJTは、現在約6割の事業所で実施されています。卸売・小売業、電気・ガス・水道業などのインフラ、通信事業・金融業・医療に至るまで、業種を問わず人材育成の手法として取り入れられています。主な目的としては、以下の4つが挙げられます。
- 企業に必要な能力を持つ人材の育成
- 従業員の定着率の向上
- 社内コミュニケーションの活性化
- 不安の解消・動機付け
企業に必要な能力を持つ人材の育成
「企業に必要な能力を持つ人材の育成」の目的は、業界・職種ごとに必要な能力を、計画性を持って可能な限り短期間で習得することにあります。OJTでは、従業員に習得して欲しい能力に応じた適任の指導者を振り分け、マンツーマンの指導によって効率的に人材育成を行います。たとえば社内業務であれば、電話対応・PCの操作法などそれぞれの適任者に育成を任せるでしょう。OJT担当者はあくまでもプロデューサー的な立ち位置であり、自分よりも技術の高い指導者に任せることで、効率的で質の高い指導を担保します。
従業員の定着率の向上
「従業員の定着率の向上」は文章の通り、OJTを通して知識・技術スキルを高めてもらうことによる、従業員の職場の定着率の向上を目的としています。従業員が短期間で実務能力を身に付けることにより活躍できる場が増え、仕事へのやりがいを感じられるようになるでしょう。その結果、自信も付いてくるためモチベーションに繋がり、今の仕事を続ける原動力が生まれやすくなります。
社内コミュニケーションの活性化
「社内コミュニケーションの活性化」は、OJTの特性を活かして従業員同士のコミュニケーションを活性化させる目的のことです。OJTは指導者と指導される側がマンツーマンで行うため、1対1の密な関係性を作りやすい側面があります。さらに、OJTは固定化された指導者が居るわけではなく、必要に応じて指導者が入れ替わりながら、部署・チーム全体で個々の従業員を育成する仕組みです。これは、職場や組織にある一定の「共通言語」を生み出します。ある意味で、ツーカーな言説が生まれコミュニケーションコストが劇的に下がるのです。従って、社内や職場全体での一体感と効率性を高め、コミュニケーションが乗数的に活性化されます。
不安の解消・動機付け
「不安の解消」は、OJTを行う中で部下が抱く小さな疑問・心配事などを上司と共有し、不安を解消することを指します。とくに、新入社員・中途入社の従業員は新しい職場環境に不安を抱いているものですが、すぐに不安を解消できる社内環境が整えられていれば、より効率的に知識・スキルの習得ができるでしょう。従業員が不安を抱える問題を放っておくと、人間関係の悪化に波及し、「知ってはいるがやりたくない」という関係性の問題になり解決が困難になります。
上記の4つの目的から、OJTは個々の従業員の知識・スキルの習得のみを目的としていないことがわかります。業務内容・社内の人間関係・組織風土を包括的に学ぶことで、企業にとって総合的に必要な人材に成長してもらうことが、最大の目的だと言えるでしょう。
OJTとOFF-JTの違い
OJTと似た概念にOFF-JT(Off The Job Training)があります。OJTとOFF-JTは人材育成という観点では同じものですが、アプローチの方法が異なります。
OJTは、上で解説したように育成を担当する指導者が部下・後輩などに対し、業務を実践しながら必要な知識・スキルを指導する人材育成の手法です。指導者が育成の対象者と実務を通して伴走することで、業務の具体的な流れを教えつつ、個別の知識・スキルを習得するための実践的な指導を行います。現場の従業員が指導者を担当するため、通常の業務を進めながら指導できることがポイントです。
OFF-JTはOJTとは異なり、実務の現場を離れて行う人材育成の手法を指します。通常の業務を行いながら実践的な指導を行うのではなく、座学のような形で指導するのが基本です。外部から専門の研修講師を呼んだり、上司・先輩が講師となってレクチャーする場合もあります。OFF-JT中は通常の業務を遂行することはできず、別途時間と場所を確保しなければなりません。
OJT・OFF-JTは人材育成の手法として一長一短があるため、高い効果を発揮するためには運用の工夫が必要でしょう。OJTの実践的な指導だけでは細かな理屈を理解することはできません。それと同様にOFF-JTの座学的な学びだけでは現実的な業務遂行能力は磨かれません。双方の欠けている部分を補うように、OJT・OFF-JTを適宜使い分けることが、より効果的に人材育成を行うために大切です。
また、OFF-JTは、仕事場の日常業務から離れ、事実や経験を俯瞰的に見つめる機会を提供します。この距離を置くことで、振り返りやリフレクションが容易になり、実務経験をより広い視野で理解し、抽象化することができます。
OFF-JTの種類
OFF-JTの種類にはそれぞれ以下のようなものがあります。
Eラーニング
インターネットを通じて行われる電子学習の形式で、オンラインコース、ウェブセミナー、ビデオ講義などが含まれます。従業員は自分のペースで学習し、場所や時間に制約を受けずにトレーニングを受けることができます。
ワークショップ
グループセッションやトレーニングイベントを通じて、参加者が特定のスキルや知識を共に学びます。ワークショップではディスカッションや実習を通じて学習が促進されます。
セミナー
専門家や講師が特定のトピックについて講義し、参加者に知識を伝える形式です。セミナーは一般的に講演やプレゼンテーションを中心に行われます。
コンファレンス
業界内での最新情報やベストプラクティスを共有するために開催される大規模なイベントです。プレゼンテーション、パネルディスカッション、ネットワーキングが含まれます。
ロールプレイング
従業員が特定の役割やシナリオを模倣することによって、コミュニケーションスキルや問題解決スキルを向上させるためのトレーニング方法です。
読書と自己学習
書籍、オンラインリソース、研究論文などを通じて、自己学習を行う方法です。従業員は自分でトピックを選択し、学びたい分野に焦点を当てることができます。
モックアップやシミュレーション
仮想的な環境やシミュレーションを使用して実際の業務状況を模倣し、訓練を行う方法です。とくに危険な状況や複雑なプロセスのトレーニングに有用です。
企業によるOJTの過去と現在地
企業はOJTによる人材育成に取り組むことで、さまざまな恩恵を得られますが、注意すべき点もあります。ここでは、企業によるOJTの現在地について解説します。
企業成長を支えていたOJT
高度経済成長期においては、OJTは一定の効果を発揮しており、さまざまな業界・産業にとって必要な人材育成の手法でした。企業の成長・繁栄の支えになっており、日本が世界的な経済大国になった要因の1つと言っても過言ではないでしょう。
しかし1990年代に入ると、OJTは人材育成の手法として劣化が始まります。とくにダメ押しとなったのがバブル崩壊による景気の悪化で、リストラの増加・非正規社員の増加・過熱する成果主義・人材の流動化などが重なり、OJTによる人材育成の意義が薄れていきました。また、OFF-JTに関しても中途半端に実施される状況が増え、もはや形骸化されたある種の社内儀式として残っているケースも増えていきます。
現代の企業でもOJTは行われていますが、果たして高度経済成長期のような効果を発揮しているかは疑問が残ります。それどころか、1990年代~2000年代よりも意味を成していないとすら考えられ、その大きな理由としては、テクノロジーの進歩・普及により、ビジネス形態が大きく変わったことが挙げられます。
一言で言えば、OJTする側の過去の経験や技術を活かせる業務は、既に機械やテクノロジーによって変化しているため、教えることができない部分が増えてきているという事です。
変化が激しい現代において、従業員に求められるのはこれまで必要とされていた「注意深さ・ミスをしないこと」「責任感・まじめさ」ではなく、「問題発見能力」「的確な予測」「革新性」といった先を見通す力と創造性です。現行のOJTは、現代の企業・ビジネス全体の状況に合わせた指導内容にアップデートしなければ効果を発揮できないでしょう。AIの登場など、テクノロジーによって不要になる業務が増える昨今、人間が注力すべき仕事は移り変わっており、過去の指導法を続けるだけでは適切な人材育成にならないことを心得る必要があるでしょう。
OJTとリスキリング
テクノロジーの進化・普及が急速に進む昨今、とくにデジタル技術の領域においては、これまでになかったツール・システムが登場しています。近年で言えば、その代表的なものとしてAIが挙げられるでしょう。その進化の速度は驚異的で、黎明期である現在でも一定のクオリティで文章・画像・音声・簡単なプログラミングなどをAIで行うことができます。将来的には、コンテンツ(音楽・映画など)・マーケティング・研究開発・会計など、さまざまな領域でAIが高度な知的作業を行うとの予測が立てられています。
AIを始めとするテクノロジー技術は日進月歩、それ以上に秒進日歩レベルで進化を続けており、企業で働く従業員は日々変化する情報をキャッチアップする必要があります。これからの時代は社内の役職によって学ぶ範囲や段階が決まるのではなく、年齢・職位・社歴を問わず同じラインで学ぶ姿勢を持たなければなりません。新時代のOJTはリスキリングの文脈を取り入れ、新入社員だけでなく中堅・ベテランの従業員も必要に応じ、OJTもしくはそれに等しい学習環境で学び続ける必要があるでしょう。
自社の技術や技能が、顧客や市場に現在でも価値を提供しているのであれば、可視化し、構造化を進め、デジタル技術と掛け算することで競争優位を保持できます。そうでなければ従業員が時代に取り残され、人材の質が低下し、ひいては企業として生き残ることが困難になってしまうことは明らかです。高度な技術や技能を保持している人材こそ、リスキリングによってデジタル技術を身に付けるべきではないでしょうか。
手段の目的化
OJTの目的は、そもそもの課題や必要に迫られた業務が先にあり、それらに対して必要なアクションを起こせる人材を育てることです。必要な内容が育成方針に盛り込まれており、OJTが機能していれば運用法として適切ですが、中にはOJTを行うこと自体が目的化しているケースも多々あります。
OJTの手段の目的化は人材育成によってスキル・能力を向上させ、企業にとって必要な人材に成長してもらうゴールを見失っている状態です。OJTの育成計画も練られておらず、マニュアルや手引きがしっかりと構造化されていないため、ただ実務を通して形式的に学ぶだけという効果的ではない育成を行っていると言えます。
このようなOJTの手段の目的化を起こさないためには、OJT自体を見直す機会を設けることが大切です。1年・1年半など一定の期間の育成が終わったら、OJT育成担当者・管理職・携わった人全員が集まり、次年度のOJTに向けて育成計画自体を見直すことで、手段の目的化を防止できるでしょう。また、見直しを定期的に繰り返すことにより、OJTそのものの質も向上させていくことができます。
企業がOJTを実施するメリット
企業がOJTを実施すると得られる主なメリットは以下の5つです。
- 個々の従業員に合わせた指導でスピーディーに実務能力を向上できる
- 複数の恩恵が得られる社内コミュニケーションの活性化
- 指導者側のスキルアップに繋がる
- 実務を通じて学習することで即戦力になる従業員を育成できる
- 企業内の従業員が育成を担当するため低コストで実施できる
それぞれについて、項目ごとに見ていきます。
従業員一人ひとりに合わせた指導
OJTの大きなメリットの1つが、個々の従業員の知識やスキルレベル・性格・その他の個性などのタイプを考慮し、成長速度に合わせた育成を行うことができる点です。マンツーマン指導が基本のOJTであれば、集合研修の欠点をカバーすることができます。
個々の従業員の苦手な箇所を重点的に指導でき、細かな不安の解消や即座にフィードバックも行えるため、より質の高い研修として機能させることが可能です。また、それぞれの従業員のタイプを考慮し、指導方針・内容を変更するなど、柔軟なカスタマイズができることも集合研修との違いです。
指導者側のコミュニケーションスキルアップ
OJTを実施することによる副次効果は、指導者側へのポジティブな影響も挙げられます。中堅・ベテランであっても、OJTを通して知識・スキルをアウトプットし、より深く理解しながら記憶に定着させることができるためです。
自分以外に他人に、何を教えるもしくは伝えるという事は、自分が実行している業務や仕事の進め方を一旦、自分の中で整理し、構造化するという論理的に自分の仕事を客観視するというプロセスを踏みます。
また整理された内容を、相手の状態に併せて伝えるというコミュニケーションも必要です。しかし、整理されていないもの、構造化されていないものは、いくら言葉巧みに話してもほとんど伝わりません。
OJTにおいては、指導が必要な従業員に教えることで知識・スキルを再認識し、役職者としても上司としても能力を向上させることができます。これは、自身の業務効率や仕事の質の向上につながるでしょう。
人を育てることができるリーダーは、自分の業務や仕事を自分自身で客観視し、整理し構造化されていることが前提であり、更にそれを伝えるコミュニケーションスキルが重要であることを押さえておくべきでしょう。
即効性のある人財育成
OJTの大きなメリットとして、即戦力になる従業員を育成できる点もあります。実務を通して指導を受けるため、従業員はより実践的な知識・スキルを身に付けながら、OJT終了後に地続きで業務を担当することができます。
一方、集合研修では大まかな業務の流れ・作業内容について学ぶケースが多いので、いざ実務を担当すると戸惑う従業員も多いものです。OJTであれば、学びの段階からすでに実務に慣れることができ、学習と実践の間にギャップを感じることなく即実務を遂行できます。
教育コストを投資に変えることができる
OJTは企業内の従業員が現場における育成を担当します。人財開発部などは、外部に研修を依頼したり、セミナーやEラーニングを提供したりします。
しかし、研修やセミナーなどで活用される一般的な教育メソッドを、そのまま現場に活かすことはできません。また、現場側は実践の中で学ぶため、構造化や俯瞰をし難いという側面があります。その結果、人財開発が提供する一般熟練と現場のOJTが実現する個別熟練は、常にちぐはぐな状況で社員に提供されています。これが研修やセミナー、OJTが能力や成果に転移していない根本的な原因なのです。
現場の課題や必要スキル軸に据え、OJTと連携としてOFF-JTやSDを行うことで、低コストでかつ効率的に人材育成を行うことができます。また、OJTは実務の中で指導を行うため、業務を圧迫する時間的コスト・人的コストを抑えて実施できるのもメリットでしょう。
企業がOJTを実施するデメリット
OJTには複数のメリットがある反面、デメリットも存在しています。大きくは以下の2つになります。
- 指導者の能力によって研修の質が変わる
- 指導者の負担になる場合がある
それぞれについて見ていきましょう。
指導者によって研修の質が変わる
OJTのデメリットとして、指導者が必ずしも高い実務能力・指導能力を持っているわけではない点が挙げられます。指導者になった上司・先輩の知識・スキルによって育成の質やスピードが変わり、OJT後の従業員の成長にもバラつきが生じてしまう可能性があります。
指導者による研修の質の差を小さくするためには、企業が指導者をサポートすることが必要です。OJT指導者への研修を実施し、あらかじめ指導法について教育するなどの仕組みを用意しておくことが重要でしょう。また、OJT自体をマニュアル化しておくことや、OJTの結果に対して指導者を人事評価する評価基準を設けるなど、指導者のモチベーションを高める施策も有効です。
指導者側の負担になる場合がある
指導者となる上司・先輩は、通常の業務と並行させてOJTに取り組みます。そのため、OJTが負担となって本業務に支障が出たり、キャパシティーオーバーになって心身を壊してしまったりするなどの可能性も考えられます。
OJTは、スキルや技能を教えるという中で、教える側と教わる側で時には、厳しいフィードバックや失敗などのプレッシャーの強い状況もあるでしょう。そこに人間関係という土台がなければ、人間関係など早々に壊れ、伝わることも伝わりません。また、自分の業務と並行しながら実行するため、指導者の精神的なプレッシャーは少なくありません。
指導者側の負担を軽減させるには、しっかりとしたフォロー体制を用意することが大切です。たとえば、OJTを担当している間は本業務の量や担当の配分を軽減する、メンタルケアなどを行うといった対策が必要でしょう。また、OJT自体と当該の担当だけに任せるのではなく、管理職などは、教える側と教わる側の関係性に着目しましょう。関係性に亀裂が入ってしまった際には、第三者が介入することで問題が容易に解決できる場合が多いものです。しかし、この微細な人間関係のプロセスを見て見ぬふりをすれば、後々大きな問題になることは間違いないでしょう。
若手から見るOJTの現在地(事例)
実際の企業の現場において、OJTの実態はどのようになっているのでしょうか。ここでは、OJTする側とされる側の視点について解説します。
OJTする側の視点
OJTの指導者側における最大の悩みは、OJTに時間的なリソースを割くことが難しいことです。多くの企業では常時ギリギリの人員で業務を回しているのが現実であり、新入社員が入社した場合でも、既存の従業員が仕事を教える役割を担うことが困難な状態となっています。
また、ビジネスの業務自体が複雑化していることも影響しています。近年では、ルーティン化された定形業務だけでなく、状況に合わせて調整・企画を立ち上げる必要のある非定型業務も増加しており、OJTの指導者側の実施難易度が高まっていることも実態としてありますす。OJTの指導者も、つい最近始めたばかりの業務を素人同然の新人に指導することは難しく、ましてや業務を体系的に教えることは不可能に近いと言えるでしょう。
現状、OJTの仕組み自体が現代ビジネスに適合しているとは言えず、何らかのアレンジが必要です。OJTの指導者の時間的な制約や、複雑な業務をどのように指導すれば指導される側の従業員に伝えられるかが大きな課題となっています。
OJTされる側の視点
OJTで指導される側にとって悩みとなっているのが「配属ガチャ」問題です。「配属ガチャ」とは、企業・組織において、どのような部門・部署に配属されるかを表現した言葉です。良い部門・部署に配属されればアタリとなり、逆の場合はハズレと言われます。
とくに新卒社員にとっては、最初に働いた職場環境の影響は大きなものとなります。最初の段階で関わる上司・先輩の仕事観は仕事の姿勢にも反映されますし、仕事の内容は以後のキャリアにも関係してきます。OJTにおいても同じことが言え、上司・先輩の指導能力によって成長速度が変わります。OJTがそもそも機能していない職場では、必要なことを教えてもらえないまま複雑な業務を担当させられるといった事態にもなりかねません。
上記のような、「配属ガチャ」においてハズレの職場を引いた場合、新卒社員は思っていた職場とのギャップに戸惑ったり、ストレスを感じてモチベーションの低下に繋がる可能性もあります。つまり、どこに配属されるかという運の要素こそが、OJTにおいて指導される側の最大の懸念事項だと言えるでしょう。
OJTを機能させるには「学び方を学ぶ」ことが重要
OJTの指導者側に時間がなく、さらに状況に合わせて業務内容の調整・企画の立ち上げる非定型業務が増えた現状において、OJTを機能させるには「学び方を学ぶ」姿勢を持つことが重要です。
これまで行われていたOJTは、個々の従業員や企業が溜めてきた経験・ナレッジをマニュアル化し、形式的に新人に伝える方式が取られてきました。変化が緩やかであり、現代社会ほどビジネスが複雑ではなかったため、それが効果的とされていたのです。
しかし、非定型業務が増えた現代の業務においては、これまで溜めた経験・ナレッジ・暗黙知などが活きる業務ばかりとは限りません。そのため、OJTの指導者が新人に教えながらも「学び方を学ぶ」ことが必要になります。新人への指導を通して、指導者側の上司・先輩従業員自身が、新たな技術・仕組みを吸収するための土台を作り学び続けなければ、現代のビジネスに対応することはできません。何よりも、OJTの指導者が「学び方を学ぶ」ことで、OJTも旧来の指導法から刷新されていきます。
この学び方とは、「学習とはどういう構造なのか」「振り返りやリフレクションはなぜ必要なのか」「他者へのフィードバックとは何なのか」ということです。それらを学ぶことにより、指導者から指導される側に知識・スキルを一方的に教える場から、双方向にフィードバックが飛び交う場に変化させ、現代のビジネスで機能するOJTにアップデートできるということです。これからの時代のOJTのキーワードの1つは、「学び方を学ぶ」ことだと言えるでしょう。
OJTを機能させるための学習起点の仕組みとコミュニケーション
前項でお伝えした、「学び方を学ぶ」にはどのような仕組みやコミュニケーションが必要なのでしょうか。ここから具体的に掘り下げて解説していきます。
問いかけ次第で学びの広さや深さが変わる
OJTを行う上で大前提になるのが、OJTの指導者が指導を受ける側の従業員が学びの主体であると理解することです。なぜなら、上司・先輩の立場であるOJTの指導者は、対象の従業員が実務を通して学ぶ中で気づいた疑問や教訓に寄り添いながら、学びの質を高めることが必要であるためです。
新入社員などのOJTを指導される側の従業員は、経験を重ねるごとに知識・スキルといった実務能力を高めていくものです。しかし、視野・視座といった物事を俯瞰で見る力については、経験豊富な上司・先輩と同じ水準にすぐに達することは困難です。そこで重要になるのが、OJTの指導者である上司・先輩が新入社員に対し、視野・視座を広げることに繋がる深い学びを促せるよう、適切な問いかけを行うことです。
深い学びは、OJTを指導される側の従業員だけでは得ることができません。従って、OJTの指導者が実務を振り返る中で問いかけ、従業員が自身で気づけるようにサポートする必要があります。
PDCAからPDSAの時代へ
これまでのビジネスでは、業務管理・品質管理における改善方法として、PDCAサイクルを用いるケースが多くありました。OJTにおいても同様で、最初に指導・教育のプランを立て、実務を通して経験・学びを得てもらい、OJT指導者による評価と反省を行い、次の実務に取り掛かるサイクルを行ってきたのではないでしょうか。
ですが、このPDCAサイクルは現代のビジネスには適切とは言えません。今後求められてくるのは、PDSAサイクルです。PDCAが、Plan (計画)、Do(実施)、Check (評価)、Act(改善)のサイクルであることに対し、PDSAはPlan (計画)、Do(実施)、Study (学ぶ)、Act(改善)のサイクルです。これまでのマニュアル・手順書通りに業務を進める上で大切だったCheck (評価)が、業務の手法が変化する現代の業務進行に合わせてStudy (学ぶ)へと変化しました。変化の激しい現代のビジネスでは、合っているかどうかを測定するCheck (評価)よりも、変化に対応するための学びの姿勢、Study (学ぶ)が重要視されるようになったのです。
また、テクノロジーの進歩・普及によって業務上でやれることが増え、さらに部署間・異業種間での連携も増えたことにより、業務が複雑かつ非連続性のある内容に変化したことも、PDSAサイクルが求められる理由の一つです。このような仕事の進め方においては、状況・ケースごとに対応する必要があり、PDCAによる管理・改善の手法では賄いきれなくなってきた現実があるためです。
OJTにおいても、PDCAからPDSAに変更することが重要です。従来のPlan (計画)、Do(実施)、Act(改善)の要素は残しつつ、Check (評価)をStudy (学ぶ)に置き換え、実務を終えるごとに振り返り、その時々で教訓を得ながら次の業務に活かすサイクルを取り入れることが必要になるでしょう。
必要なのはOJTをアップデートすること
ここまで、これからのOJTでは「学び方を学ぶ」ことが重要であると紹介してきました。最後に、その具体的な取り組み方についてご紹介します。
OJTする側される側の垣根を越えて一緒に学習を楽しむ
OJTを実施する際の古い考え方として、指導者と指導される側を分けて考えてしまうことが挙げられます。前項でお伝えした通り、現代のビジネスは変化が激しく、リスキリングが注目されるように、誰しもが新しい技術・仕組みを受け入れなければなりません。中堅・ベテランの従業員であろうと常に学ぶ立場にあり、OJTにおいてもその点は変わりません。OJTの指導者も指導される側の従業員と共に学ぶ側であると意識しておく必要があります。新入社員などと同じく、未経験の業務に携わることもあり、上司・先輩という立場が意味を成さない場合もあるでしょう。
とはいえ、OJTの指導者の方が基本的には上司・先輩であるため業務で経験を積んでおり、指導される側の従業員よりも学び方についての知識・知恵があるものです。OJTの指導者は、自身も学ぶ側である意識を持ちながら学び方の知識・知恵を活かし、新入社員などOJTを指導される側の従業員が経験を深い学びに変えるために必要な学習のサポートをすることが大切になります。
OJT担当者の持っている仕事を一緒にやる
OJTに限らず、人が何かを学ぶ時は、まずは習得が容易な物事から取り組むのがセオリーです。しかし、仕事に関しては、簡単な定形業務やすぐに覚えられるルーティン作業などを学んだところで、複雑な業務・非定型業務などに対応する知識・スキルを身に付けることはできません。仕事で実務能力を向上させるには実践第一であり、高いレベルの仕事を行うには、高いレベルの実践的訓練で鍛える必要があります。
そこで重要になるのが、OJTの指導者である上司・先輩が携わっている業務を一緒に行ってみることです。もちろん、簡単な業務も並行して実践しますが、複雑でより上位工程の業務に取り組むことで、ビジネスで必要な筋力・思考力を実践レベルで鍛えていくのです。
たとえば、上司と一緒にアイデア出しと企画書をまとめる業務を行ってみる、営業に同行するのであれば、取引先とのやり取りについて具体的に共有し、現場で発言を行ってみるなどです。OJT中は、まだ知識・スキルが身に付いていない従業員が挑戦・テストできる場でもあります。この状況をより大きな成長に活かさない手はありません。
こういった試みは、従来のマニュアル・手順書を教えるだけだったOJTの枠を越えるものであり、現代のビジネスに合わせたOJTのアップデートだと言えるでしょう。
一緒にやりながら「思考のプロセス」を共有する
上司・先輩や新人・部下がOJTを通して業務を共にする場合、一緒に業務を進めながら思考のプロセスを共有することも大切です。これまでのOJTでは、業務の作業手順や機器の操作を上司・先輩からコピーするように学ぶことが重要でした。しかし、現代のビジネスの現場は業務が複雑化しており、身体性によって進められる物理的な業務ではなく、思考力によって進められる非定型業務が主流になっています。
たとえば、先輩が以前作成した企画書・プレゼン資料を見ただけでは、どういった思考プロセスで資料を構成し、なぜそのゴール設定をしたのか、過去のどんな業務を参考にしたのかなど一見しただけでは分からない要素が多く、新人が同じようなものを作成することは難しいでしょう。
そのため、OJTの指導者は指導される側の従業員に対し、自身の仕事への考え方を細かく伝えていくことが重要になります。しかし、言語で伝えることには限界がありますし、間違った方向で伝わる可能性もあります。自分の中では感覚としてつかめていることでも、言葉にするには難しいといったケースもあるでしょう。そのような場合は、5W1Hやロジックツリーなどの思考のフレームワークを使うようにし、紙・PDF・アプリなどで共有すると伝わりやすくなります。
OJT担当者だけでなく多様な人と組む
OJTから学びを得ているからといって、他の学び方を捨てる必要はありません。むしろ、積極的に他の学び方を取り入れることで相乗効果が生まれ、知識・スキルの定着が期待できます。実務を通して学ぶOJT以外にも、座学的な学習を行うOFF-JTや、社内外のセミナーや書籍から学ぶSD、最近では社外のビジネス系のオンラインサロンに加入して学びを得ている人も多くいます。
OJTに限定したとしても、その学び方に決まりがあるわけではありません。OJTを実施する中でさまざまな役職者・従業員と組むことにより、幅広い経験を積むこともできるでしょう。それは必ずしも上司・先輩である必要はなく、再雇用された従業員から組織の中での立ち回り方を学んだり、子育てなどの理由で時短勤務をする人から効率的な業務遂行について学ぶことも可能です。多様な視点・角度から学びを得ることで、OJTで指導される従業員が大きく成長することができます。
これまでのOJTは、必要な業務に応じて適切な従業員を指導者にするやり方をしていましたが、この「必要な業務」というのが曲者で、決まった業務の決まった範囲のみを実践することに終始しがちです。しかし、従業員として成長に繋がる種は、必ずしも目の前の業務だけにあるとは限りません。とくに現代のビジネスにおいては、多様な視点・創造性などが重要になってくるため、多様な人と組んで経験を積むことで、従業員の引き出しを増やすことが大切になります。
OJTで期待する効果が得られない原因
OJTの効果は、2日間で期待以上の効果を得られる場合もあれば、半年続けても思ったような効果が得られない場合もあります。ここではOJTで期待する効果が得られない場合の原因について解説します。
まず挙げられるのが、動機付けができていないことです。動機付けが適切に行われていないとモチベーションが上がらず、目的の知識・スキルを身に着けることも困難になります。形式的にOJTを行うのではなく、OJTのゴールを指導者と指導される側の従業員に理解してもらうことで、動機付けを行うことができます。
また、指導者のスキル不足もOJTが上手くいかない原因になります。業務上の能力と指導者としての能力は異なるため、優秀な社員でも教えることに適性がないことはよくあることです。対策として、指導者が指導のスキルを学べる場を設けることも有効です。
続いて、振り返りを実施していないことも原因の一つです。実務を通して知識やスキルを学ぶOJTですが、ただ業務を体験するだけでは十分な効果は得られないでしょう。経験した実務の結果にフィードバックを行い、課題から改善を行うことで、知識やスキルが身についていきます。
OJTを成功に導くポイント「経験学習サイクル」
経験学習サイクルのベースになっているのは、アメリカの教育理論家であるデイビット・A・コルブが提唱した経験学習モデルです。経験学習モデルの理論をシンプルに表現すると、自ら実際に経験することで学び、成長していくプロセスを指しています。このプロセスをステップに分け、実用的に取り組めるようにしたものが、経験学習サイクルです。
実践を通じて学ぶのは当たり前だと感じるかもしれませんが、経験を糧にするには適切な段階があり、それを説いたのが経験学習モデルであり経験学習サイクルです。経験学習サイクルはさまざまな場面で活用でき、ビジネスにおいても通常の業務だけでなく、研修などの学びの場にも取り入れることができます。
経験学習サイクルについては別の記事で詳しく解説していますので、より詳細に知りたい方は併せてご覧ください。
まとめ
OJTは従業員の実務能力を向上させる研修として有効な手段です。しかし、従来行われてきたOJTを続けるだけでは、現代のビジネス環境に適合する人材育成を行うことは難しくなってきています。そこで、OJTの流れの中にあるPDCAをPDSAに変更し、さらに経験学習のサイクルを取り入れることで、変化に対応できる従業員を育成する新時代のOJTにアップデートしていく必要があります。
また、OJTを指導する側の能力が指導結果を左右していることも、押さえておく必要があります。従業員として能力が高いからと言って、必ずしも指導者の資質があるとは限らないため、指導スキルを学べる場を別途用意することも必要になってくるでしょう。
OJTを適切に機能させることができれば、確かにスピーディーに従業員の実務能力を向上することができます。しかし、万能の人材育成の手法ではないため、OFF-JTやSD、あるいは外部のオンラインサロンなどで学ぶことも必要です。OJTは、あくまでも人材育成の1つの手段であるため、多角度的に従業員が成長できる環境作りをしていきましょう。