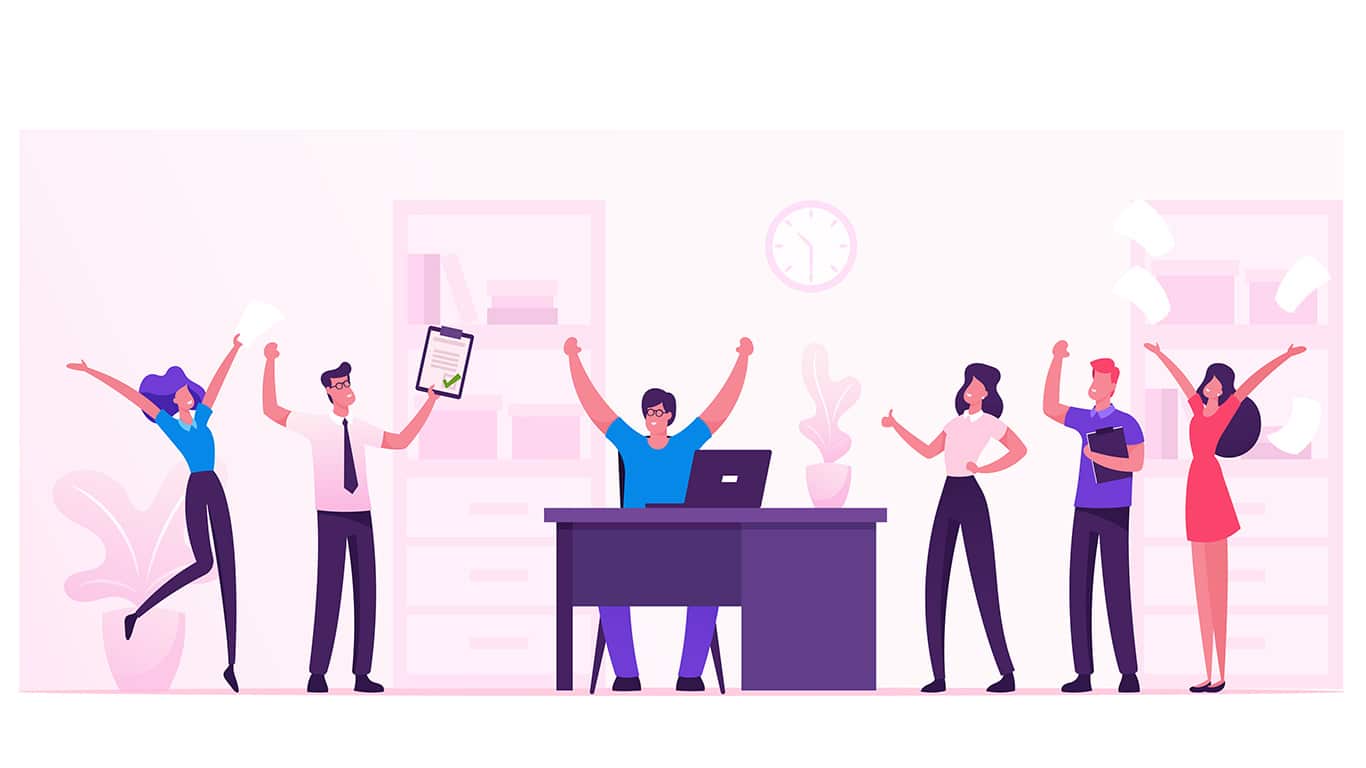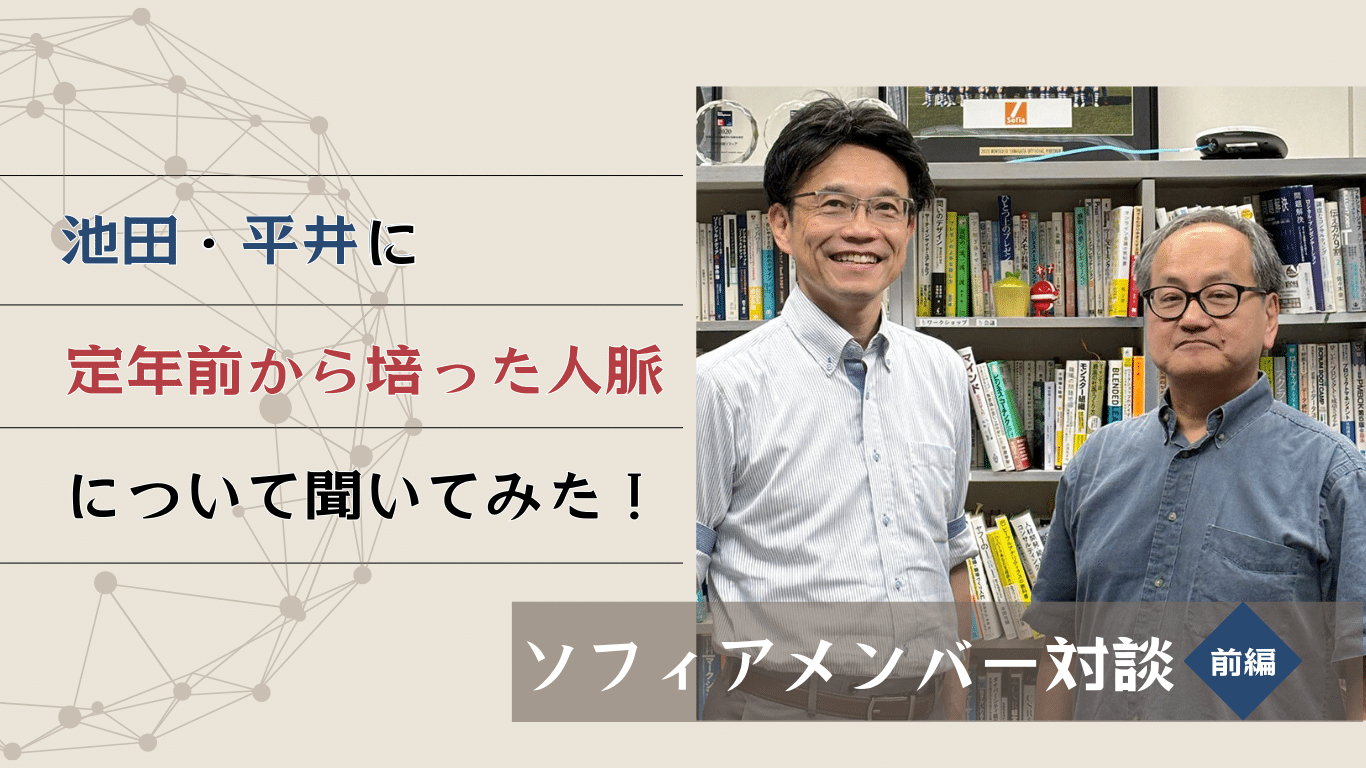アンラーニングとは?企業がVUCA時代を生き抜くための3つのポイント
最終更新日:2024.03.13

目次
アンラーニングは、教育関係や人材育成、経営などにおいて注目を集め、力を注がれるようになってきています。VUCA時代への突入という背景やコロナの影響で自立型人材育成の需要が拡大している今、企業も個人もアンラーニングするべき時代と言っても過言ではありません。
そこで、今回は、そもそもアンラーニングとはなにか、VUCA時代でなぜ必要とされているのかについて詳しく解説していきます。
アンラーニング(学習忘却)とは?
アンラーニング(学習忘却)とは、これまでに学習してきたことを「忘れ去る」ことではなく、既存の価値観を認識し、個人や仕事をより進化させるために今の習慣やスキルを「修正する」ことをいいます。これまで重要だと言われていた概念や価値観から脱し、新たな考えや価値観を身につけることが大切です。ここでいう「価値観」とは、ビジネス上での価値観を指します。
例えば、「営業は足が命」「24時間働けますか?」のようなCMが昔はありました。もちろん、営業がお客様に直接会いに行くことに効果がないわけではありません。しかし、「足が命」というと、行動レベルと価値観が直結し硬直化しています。また、「24時間働く」ということも、今の時代にそぐわない労働スタイルです。つまり、従来の信念とルーティーンが直結し、さらにそれが硬直化してしまうと、時代の変化が激しい昨今のビジネスシーンに対応できません。そのために、アンラーニングが必要となります。
アンラーニングは変化、リスキリングはアップデート
アンラーニングは、既存の知識やスキルを捨て、新しいものを学ぶことを指します。 一方、リスキリングはアップデートするために必要な行動です。リスキリングとは、働き方の変化によって今後新たに発生する業務で役立つスキルや知識の習得を目的に、勉強してもらう取り組みのことです。現代は「第4次産業革命」に突入しており、人間に代わってAIが業務を担うケースが増えると言われています。
業務がAIに置き換えられると、その業務に携わっていた従業員たちは、働く場を失ってしまう恐れがありますが、AIに置き換えられたとしても、プログラムの設計、社内システムの管理といった新たな業務も出てくるでしょう。
とは言え、スキルを習得していなければ上記のような業務をこなすことは困難です。リスキリングによって、これらの業務に関係するスキル・知識を習得しておけば、従業員は別の業務に就くことができます。アンラーニングとリスキリングは、変化に対応し、成長し続けるための重要な要素です。
アンラーニングがビジネスで重要視される理由と背景
アンラーニングがビジネスで重要視されているのは、VUCA時代への突入という背景やコロナの影響で自立型人材育成の需要が拡大したことなど、予測困難かつ不安定で変化が激しい時代だからこそです。これまで常識ではなかったことが、今では一般的な価値観として受け入れられていることが多く存在します。今まで積み重ねられてきた技術や知識の習得だけでは、太刀打ちできなくなってきているとも言えるのです。
これは個人だけの問題ではありません。組織の中でも同じような問題が存在します。たとえば、組織風土、経路依存性、大企業病などの問題は行動レベルと価値観レベルが直結し硬直化しています。このような問題を解決するために、組織的なアンラーニングを行うことも重要です。
個人レベルでは、時代や価値観の変化により組織の在り方について疑問を感じることも多いでしょう。部署や部門はもちろんのこと、会社を越えて行う越境学習は、個人のアンラーニングにもつながります。
組織レベルでは、絶えず変化する時代の中で、価値観の再構築(リフレーム)や経営理念の再解釈が非常に重要です。経営理念を起点にした学習・アンラーニングを行うことにより、経営理念や価値観を基準として、企業活動を通じた体験や学習のサイクルなどを見直すことができます。成功や失敗、業績と成果の定義などの根本的なところから学習を重ね、経営理念の実現に向けて組織に変化を起こし続けることが可能です。
近年ビジネスは複雑化し、それに対応するためにはスピードが重要とされています。アンラーニングは組織風土や習慣などを前提レベルで学び直すことが重要です。しかし、組織レベルでのアプローチを同時並行しない場合は、効果がない場合もあります。
例えば、デジタル化に伴い、個人レベルのITリテラシーが必要不可欠であり、自分の仕事に必要となる技術を学ぶことも多いでしょう。しかし、個人のITリテラシーやIT技術レベルだけ向上して、業務効率やITツールは活用できても、IT技術やデジタルを活用したビジネスの思想や考え方も含めて学び直すアンラーニングを進めない限り、変化やイノベーションは起きません。また、リスキリングも併せて理解しておくことも大事です。
アンラーニングを企業活動に取り入れるメリット
アンラーニングを取り入れる場合、個人レベルと組織レベルで取り入れる方法が異なります。
個人で取り入れる場合の行動習慣レベルであれば、ITリテラシー教育や機械操作方法などのものが多いです。思考価値観レベルであれば、「そもそも、何を大事してるのか?」など自分の価値観に問いを立て、解像度を大きく下げて俯瞰してみると、見え方が変わってきます。前述した「営業は足が命」の例であれば、「そもそも、営業とは何か?」という振り返りを行いましょう。
組織で取り入れる場合の行動習慣レベルであれば、BPRやITリテラシーなどです。思考価値観レベルであれば、経営理念やパーパスなど組織の価値観に問いを立て、解像度を大きく下げて俯瞰してみましょう。業務や組織風土、組織習慣として染みついている行動も多いため、これらを俯瞰して見ることによりアンラーニングのポイントが見えてきます。
アンラーニングを取り入れることにより、従来の価値観を捨てて新しい知識を獲得し、現在の業務を異なる視点で見直したうえで業務に反映・活用できるようになり、企業・組織として成長し続けることが可能になります。今の時代に即した新しい着想の反映や適切な業務フロー改善を行える効果も望め、事業を伸ばしていくチャンスにもつながるのです。
個人レベルのアンラーニング推進のポイント
現代の企業におけるアンラーニングで個人レベルに求められている要素は、次の2つです。
- 「既存の前提」を捨てて、新たな知識や能力の習得
- 予測不可能なことに対する肯定的なマインドへの変化
個人レベルにおいては、「既存の前提」を捨て、新たな知識や能力の習得を優先しましょう。従業員にアンラーニングの重要性を伝え、新しい知識や能力の習得を促進することが求められます。
また、予測不可能なことに対する否定的なマインドは組織全体の指揮を下げることにもつながるので、仕事に対する価値観を認識し、肯定的なマインドへ変化させることが必要です。
具体的には、ダブルループラーニングといわれる、1970年代にアメリカの組織行動学者クリス・アージリスによって提唱された学習理論を用いて行うのが一般的です。ダブルループラーニングとは、既存の前提や習慣の枠組みでの学習を繰り返しながらも、さらに既存の前提や習慣の枠組みを超えて新たな思考の枠組みを加える学習プロセスのことをいいます。
組織レベルのアンラーニング推進に不可欠なポイント
現代の企業におけるアンラーニングで組織レベルに求められている要素を一つずつ解説していきます。
従業員のモチベーション低下に留意する
アンラーニングの導入によって、長年慣れ親しんできた仕事の信念やスタイルを変えることには、多かれ少なかれ心理的な抵抗感が伴います。「今まで自分が学んできたことを否定されるのでは」といった不安や恐れから従業員のモチベーションが格段に低下することもあるでしょう。また、やり方を変えた結果、一時的にパフォーマンスが低下することもしばしばあります。アンラーニングはあくまでも自己否定ではなく、成長のための見直し、検証の機会であると位置付けることが重要になります。
必ずチーム単位で行う
アンラーニングに取り組む場合には、必ずチームあるいは組織単位で行うことを心がけましょう。誰か一人が仕事の進め方・やり方を何の予告もなく変えてしまうと、周囲に迷惑が掛かるのは自明の理です。
また、アンラーニングは個人の弱みと向き合わなければならないため、痛みが伴います。誰かと共にアンラーニングを行うことで痛みも軽減されるでしょう。
アンラーニングに取り組む際は、すべてを変えようとするのではなく、有効性が下がってきた仕事を優先的に切り出し、課題意識を共有することも重要です。そのためにも、まずは業務の優先順位や重要度を整理することから着手していきましょう。
認知と内省
アンラーニングを行うには、従業員のマインドセットが重要となります。まずは個人レベルで行動する前の「認知」と、行動した後の「内省(リフレクション)」の作業を行い、仕事に対する自分の考え方ややり方を見つめ直すと良いでしょう。
一例として、内省するにあたっては、日々の業務において成功したことや失敗したこと、その理由を記録するというのも有効な手法となります。「時代に合わないやり方をしていないか」、「これまで続けてきたことは今後も価値があるか」などと考えながら書き込んでいくうちに、新たな気づきを得ることもあるでしょう。それと同時に、内省を繰り返していく過程で自分がどうしても譲れない信念を再認識できることもあります。
リフレクションと反省の混同に注意する
アンラーニングの過程で経験や知識を取捨選別していくと、「自分の知識はこんなにも時代とマッチしていなかったのか」と反省したり、落ち込んでしまったりする従業員が出てくることもあります。しかし、アンラーニングに際して行う内省は、個人を責めることではなく、客観的に自分を見つめ直すことです。あくまでも、新しく学んだ知識を習得する受け皿を作る取り組みであると位置付けるようにしましょう。
他部署・異業種と交流を図る
他部署や異業種、幅広い年代の人との交流を図ることも、推奨したい取り組みです。新たな価値観に触れたり、刺激を受けたりすることでアンラーニングが進みやすくなるのです。また、自分自身を客観視することで、何を捨てるべきか、何を新たに取り入れるべきかがより明確になる点も他部署・異業種と交流を図ることによる大きなメリットです。
知識や経験の取捨選択を意識する
アンラーニングは、これまでの知識や経験をすべて捨て去ることではありません。残すべき、そしてアップデートすべき知識や経験を取捨選択することがポイントとなります。大切なのは、アンラーニングによって視界を広げるとともに、今後何がより重要になっていくかを捉え、身につけていくことです。そのサイクルの中で、「新たな価値観をより多く知りたい」という知的好奇心が開花する状態を目指しましょう。
ラーニングを否定しない
個人や組織が成長するにはアンラーニングだけでなく、ラーニングも欠かせません。時代に合わせて知識を捨てることにばかり目が向いてしまうと、知識をインプットするラーニングに疑問を抱いてしまいがちですが、学習したものに価値があるかどうかは、実際に行動して初めてわかるものです。従業員がラーニングし続ける姿勢を保てるよう組織は配慮する必要があります。
専門家であっても学習を放棄しない
経営層やマネジメント層が注意すべきは、役職に甘んじて学習を放棄しないことです。自社に長く属し、物事に精通している人、熟練した技術者など、ある程度の知識や技術を習得して「専門性を高めた」という人こそ、学習を放棄せずアンラーニングを行うことが重要です。
従業員がアンラーニングを通して変化に強く、時代に即した人材になったとしても、会社の方向性を決める経営層やマネジメント層が変化に適応できなければ、柔軟な判断ができず会社としては意味をなしません。
専門性が縦軸だとすれば、アンラーニングは横軸です。専門性ばかりを高めても、固定概念化したり知識に固執したりすれば、逆効果になります。時代の変化により、一昔前の知識は役に立たなかったり、専門的な一部の作業が機械化されたりしていることも多々あります。そのような状況に臨機応変に対応するためにも、専門家であっても学習を放棄しないようにしましょう。メタで自分の行動や学習を俯瞰し、価値観レベルで検討してみることも重要です。そのような行動を取ることで、自身の専門性を他の専門領域に活用できるかという視点が生まれます。
つまり「専門性を高めた」という人こそ、学習を放棄せずに、変化に対応する考え方や知識を持つ必要があります。
学習をベースにする企業運営にする
多くのビジネスパーソンにとって、意思決定する際の価値基準、判断のよりどころとなっている評価軸は経済合理性、つまり損得勘定である場合がほとんどでしょう。働くという時間を儲かるかどうかなどの損得勘定で判断してしまうと、学びは後回しにされて目の前の業務に没頭するだけの日々を過ごすことになります。
企業規模で考えた場合でも同じです。企業利益を重視した考え方をベースにしていてはアンラーニングは進みません。企業全体として、未来を見据えて今何を取り入れるべきか、学ぶべきかを判断する必要があります。
アンラーニングしやすい環境や仕組みを整える
人事担当者やマネジメント層は、より良い人材育成を目指すために、アンラーニングを会社全体で必要と認識しているのであれば、下記環境や仕組みが重要です。
実践の場づくり
学びを実際の業務に反映することで、学習の効果がより期待できます。学びをより深く理解するためにはアウトプットの場を用意する必要があります。ワークショップや演習などたとえ小規模なアウトプットの場でも、実践の機会を得ることで学びの定着は格段に変わります。受け身の学習ではなく、アクティブな学習環境がアンラーニングにおいて重要です。
学びを評価・表彰する仕組みづくり
ときには、学びを評価・表彰する制度やテスト、コンペなどで競い合うことも必要です。横並びにするのではなく競争をすることで、競争心が成長へと導いてくれるでしょう。
異論反論を受け入れるクリティカルシンキングを行う
クリティカルシンキングとは「物事の前提の正誤を検証したのち、その事象の本質を見極めていくこと」をいいます。自分自身が学んだことを整理したうえで、今後のビジネスにおいて必要かどうかを考え、整理する時間をつくることも大切です。学んだことを単にアウトプットするだけでなく、現在の会社でどのように活かせるのかを考えて実践するまでがアンラーニングの一部だと言えます。
リベラルアーツの視点を取り入れる
多様化する社会の中で、他者を尊重しながら自分の意見や立場を明確にし、他者を排除したり否定したりせずに、共存していく姿勢を養う学問がリベラルアーツです。
「人文科学」「自然科学」「社会科学」「哲学」「倫理」「心理学」など、広範な分野を学ぶことにより、新たな組み合わせに気づき、それを商品化する道筋をつけやすくすることができます。
変化が激しいうえにAIが普及し、機械的・事務的な作業が自動化されていく現代のビジネスの世界において、人間が担う業務の領域は創造性が問われるものへと舵を切ることは避けられません。将来のビジネスパーソンに求められるのは、問題の設定や問いの立て方、アイデアの発想力など、創造性を活かす能力です。
AIを含むテクノロジーと人間が共存するためにも、リベラルアーツの学問を学んでおくことは有用でしょう。詳しくは下記記事をご覧ください。
越境学習を行う
越境学習とは、普段働いている会社や職場、または部署から離れて、一定期間違う環境で働くことです。社外留学、他社留学などの言葉で表現されることもあります。
具体的には、ワークショップに参加したり、ビジネススクールや社会人大学院に通ったり、ボランティア活動に参加することなどが挙げられます。分かりやすく言えば、所属している企業や組織から一定期間離れ、越境先で得た新しい経験や体験を企業や業務に還元することです。越境学習において、越境者は最初「希少性の高いお客様」状態になることは避けられません。そこから自分を環境に定着させていくことで、ようやく学習がスタートします。本格的に学びが始まるとその時点で、従来培ってきたスキルや価値観、過去の実績は使い物にならなくなります。大事にしていた信念が揺らぎ、自分を正当化するために既存の価値観を越境先に押し付けたくなるかもしれません。自己否定に似た、心理的な抵抗と向き合う必要も出てくるでしょう。この経験こそがアンラーニングそのものなのです。
越境先についてひとつずつ理解を高めていき、成果を急ぎすぎずにじっくり学んでいきましょう。新入社員のように振舞うイメージを持つとやりやすいかもしれません。
まとめ
変化していく環境に対し柔軟な対策を取るためのアンラーニングの必要性を紹介しました。アンラーニングをビジネスで活用するには、組織風土や仕組みづくりがカギとなります。組織風土改革や仕組みづくりを行うためには、組織内のコミュニケーションを活性化させなければなりません。
組織マネジメントを支援しているソフィアでは、インターナルコミュニケーションの活性化や組織変革人材育成などにおいて多くのお客様企業をサポートしてきた実績があります。自社のアンラーニングを進めていきたいとお考えの方はぜひご相談ください。