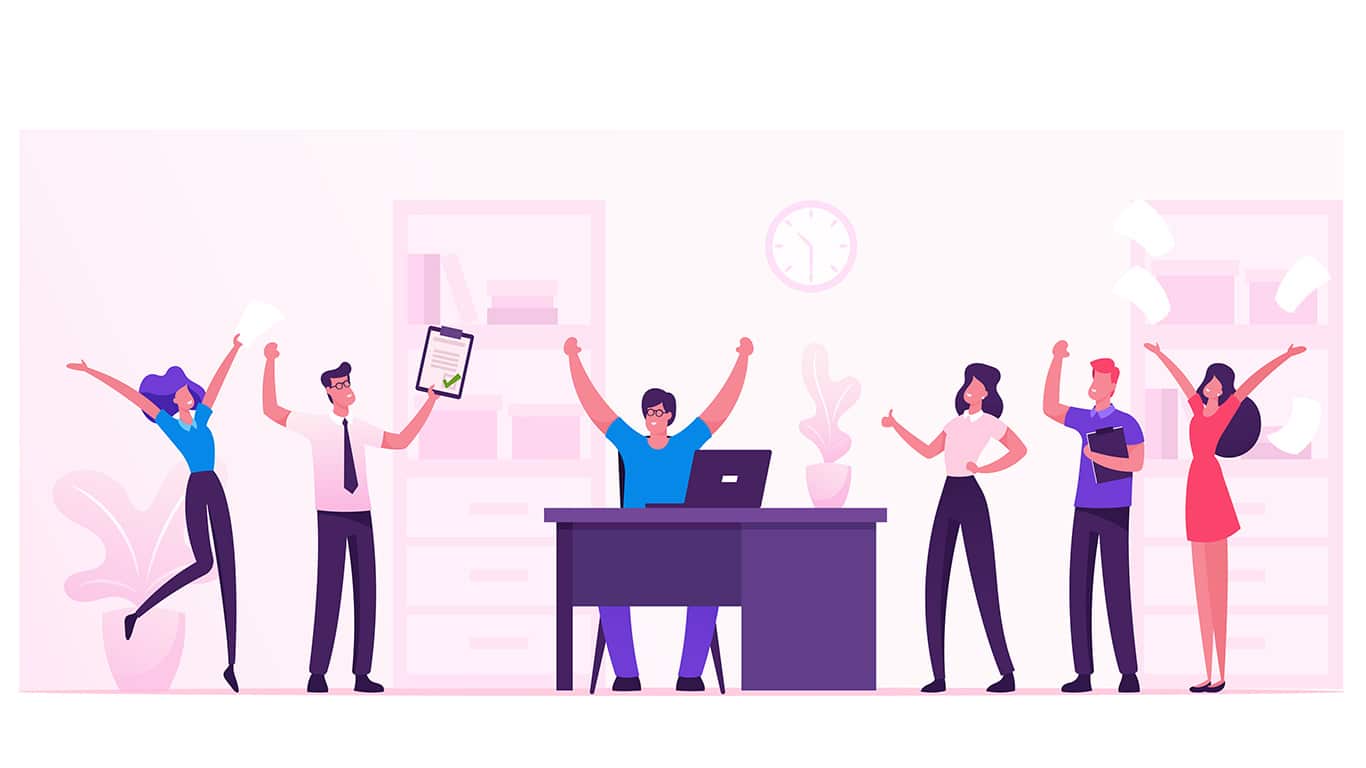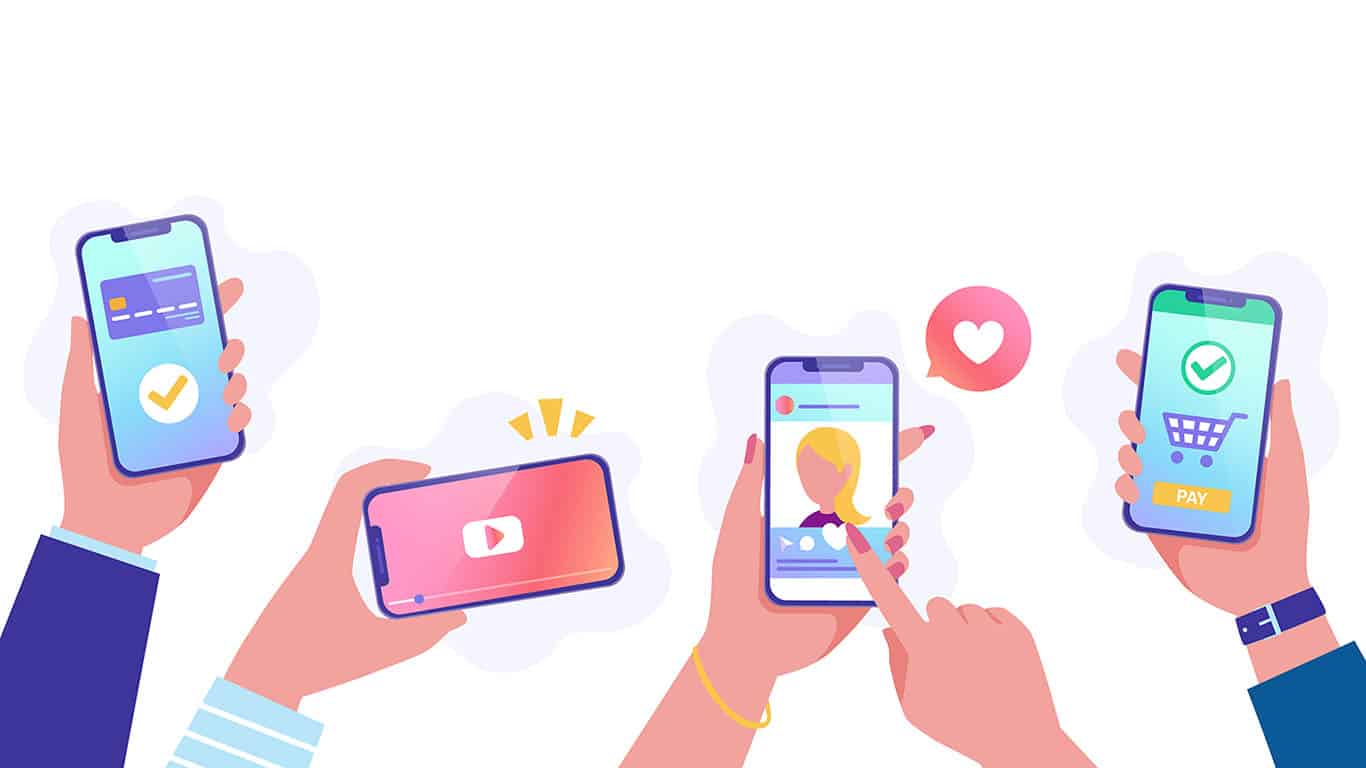NotesからSharePoint移行で失敗する3要因と成功のポイント
最終更新日:2025.10.08

目次
IBM Lotus Notes(ノーツ)はかつて多くの企業で使われてきましたが、クラウド化の波によりNotesからSharePoint Onlineへの移行を検討する企業が増えています。さらに、2024年に主要バージョンのサポートが終了し、対応は待ったなしの状況となっています。
しかし、その移行プロジェクトは残念ながらしばしば失敗に終わってしまうのが現実です。では、なぜこのような状況が生まれるのでしょうか。また、どうすれば成功に導くことができるのでしょうか。
本記事では、Notes文化やツールの理解不足など移行がうまくいかない背景を探り、成功への処方箋をご紹介します。あなたの企業でもこのような課題に直面していませんか?一緒に考えていきましょう。
なぜNotesからSharePoint Onlineへの移行は失敗するのか?
長年にわたって培われた社内のノーツNotes文化
Notes(ノーツ)は非常にカスタマイズ性が高いため、自社の大規模システムのベースとして使われたり、社内申請などさまざまな業務フローに深く組み込まれてきました。長年社内でNotesを使う中で、各企業は業務に合わせてNotesをカスタマイズし、あるいはNotesに業務を最適化してきたのです。その結果、社内には「Notes文化」とも呼べる独特の慣習やワークフローが形成されていきます。
つまり、まさにNotesに最適化された社内業務やNotesの使用を前提とした職場の文化が出来上がっていたのです。あなたの職場でも、「Notesならではの使い方」が定着していませんか?
しかし、SharePoint Online(以下、SPO)は元々Notesの掲示板やデータベース機能と同じものではなく、文書管理を主目的とする全く別種のプラットフォームです。設計の思想も「できること」「できないこと」も両者で全く異なるため、「NotesをそのままSPOに置き換える」のはそもそも無理があると言えるでしょう。
NotesとSPOではデータ構造もインターフェースも異なり、無理にすべてを移行しようとするとSPOを改造してNotes化する羽目になってしまいます。本来はSPO標準でできることをベースに業務プロセスを再設計する必要がありますが、業務フローの変更は現場にとって負担が大きくメリットも伝わりにくいため、「移行したらかえって不便になった」「Notesの代用になるようにSPOをカスタマイズしてくれ」といった現場からの不満につながってしまうのです。
また、長年Notesを運用してきた企業では、Notes環境に精通した担当者の退職や異動によりシステムがブラックボックス化してしまっているケースも少なくありません。誰も詳細を把握できないままでは必要な要件定義や移行計画の策定も難しく、プロジェクトが途中で頓挫してしまう一因となります。
さらに、Notesに精通した専門人材の不足も移行を難しくしています。Notes技術者は高齢化や引退が進み、外部に委託しようにも希少なスキルゆえに運用コストも増大しがちです。こうした状況の中、十分な知見を欠いたまま見切り発車で移行を進めてしまえば、システムの不具合や現場からの反発を招き、移行失敗に直結しかねません。
NotesとShare Pointの違いに対する理解不足の経営層と現場
NotesからSPOへの移行は、たとえるなら「馬車」から「自動車」への乗り換えにも似ています。馬車と自動車は「人や荷物を運ぶ」という機能だけ見れば共通しますが、動力も形態もまったく異なりますね。
日常的に馬車に慣れ親しんだ人々に、断片的な情報だけで自動車の利便性やリスクを理解させるのは難しいのと同様に、Notesしか使ったことがない現場やそれを支えてきた経営層に、新しいSPOのメリット・デメリットを十全に理解してもらうのは容易ではありません。なぜならそのためには、SPOを構成するMicrosoft 365の各種サービスの仕様まで熟知しておかなければ説明しきれないからです。
現実にはそこまで準備できないまま移行プロジェクトが走り出してしまい、NotesとShare Pointの設計思想の違いに対する理解不足に陥るケースが多く見られます。その結果、「こんなはずじゃなかった」「聞いていない」といったトラブルが導入後に頻発しがちなのです。
たとえば、Notesでは当たり前にできる機能がSPOでは難しかったり、別の方法で実現する必要があったりします。代表的な例をいくつか挙げてみましょう。
未読/既読の管理:
Notesではユーザーごとに文書の既読・未読を簡単に管理できますが、SPOはWebシステムであるため、こうした既読管理は容易ではありません。
発信文書への返信機能:
Notesには掲示板の投稿に対して返信しスレッド化する機能がありますが、SPOの設計思想上そのような機能は存在しません(発信情報へのフィードバックはMicrosoft 365ではYammerのスレッドやTeamsのチャットなどソーシャル機能で行う想定となっています)。
ワークフロー機能:
Notes上で構築された申請・承認フローなどは、SPO単体では同様に再現できません。SPOでワークフローを実現するにはPower Automate(旧称Flow)等の別ツールを組み合わせる必要があります。
このように、NotesとSPOには根本的な機能思想の差異があります。にもかかわらず移行前に両者の違いが社内で十分共有されていないと、機能面・カスタマイズ面・運用面・費用面あらゆる点でギャップが生じて、「移行したらこんなはずじゃなかった!」という不満やトラブルに発展しがちなのです。
このような理解不足を防ぐためには、移行前の準備段階で十分な検証と説明の機会を設けることが重要だと思われます。

社内コミュニケーションの目標設定|KPI設計と成功事例で組織を変える【2025年最新版】
社内コミュニケーションの目標設定にお悩みですか?本記事では、大企業のDX・広報・人事担当者向けに、定量・定性デ…
魅惑の「開発」をめぐる、IT部門とベンダーの共犯関係
企業がMicrosoft 365を導入する背景には、働き方やビジネス環境の急速なデジタル化=いわゆるデジタルトランスフォーメーション(DX)の波があります。従来、企業内のグループウェアとして長年使われてきたNotesやオンプレミス型の旧システムは、「自社の業務に合わせて独自に開発して使うもの」という前提がありました。
一方、モダンUIを採用したクラウドサービスであるSPOはモバイル利用を前提として最適化されており、大掛かりな開発を伴わなくても設定変更や軽微なカスタマイズで活用できるようになっています。もちろん必要に応じてSPO上での開発も不可能ではありません。
しかし、過度な開発には大きなリスクが伴います。たとえばShare Pointの設計思想を無視した開発を行えば、モバイル端末からアクセスした際に画面が崩れるなどの不具合が生じたり、SPO本体がアップデートされた際に開発部分が非互換となりバージョンアップできなくなる(あるいはアップデートのたびに修正開発が必要になる)恐れがあります。
前述のように根本の設計思想が異なる以上、どれだけ開発を加えてもSPOをNotesと同じにはできません。本来であれば「開発せず、SPO標準機能の範囲内でできること」をベースに業務を見直すことが必要になります。
しかし実際には、IT部門にとって膨大な手間をかけて現場を説得・教育して回るより、現場の要望通りにシステムを作り込んでしまった方が短期的には「楽」な場合があります。また、多くの企業がSPO移行時に相談するSIベンダーの側も、本来は「システムを開発すること」が主たる業務です。SPOの設計思想や標準機能の活用よりも、顧客の要望に応じたカスタム開発を提案した方が受注金額につながり、以降の保守運用契約も得られるため、ベンダーとしては開発路線以外の提案をしにくいのが実情でしょう。
こうして、「現場はすぐ開発を要求し、ベンダーも喜んで開発する」という構図、すなわちIT部門とベンダーが暗黙の共犯関係で開発に突き進む状況が生まれがちです。しかし、このようにして進められる「開発ありき」の移行は、長期的に見れば決して会社のためにならないどころか、せっかくのSPOの利点を殺してしまいかねません。
開発にリソースとコストを割きすぎた結果、肝心のユーザー教育や業務改革に手が回らず、システムだけ新しくなっても社内に定着しないという失敗も起こり得るのです。視点を変えれば、この開発偏重の問題は、組織全体でSPOの本質的な価値を理解する機会を奪ってしまうとも言えるでしょう。
ここまで移行が失敗する主な要因を見てきました。では、どうすれば成功に導けるのでしょうか。一度内容を整理してから次の論点へ進んでいきましょう。
NotesからSharePoint Onlineへの移行を成功させるには?
ここまで、NotesからSPOへの移行が失敗する主な原因を見てきました。それでは、どうすれば移行プロジェクトを成功に導けるのでしょうか。
以下に、実際に有効だと考える3つの処方箋(解決策)をご紹介します。これらはSPOに限らず、Notesから他のシステムへ移行する際にも有効だと思われます。
なお、本格的な施策に取りかかる前に現行Notes環境の現状分析(アセスメント)を行い、移行対象の業務やデータを把握しておくことが大前提となる点は言うまでもありません。その上で、以下の方策を段階的に実践していきましょう。
処方箋1:プロトタイピングとスモールスタート
新しいものの使い心地やメリット・デメリットは、頭で想像するだけではなかなか掴めませんね。とくに、長年Notesを使って業務を回してきた現場社員にとって、SPOに切り替えた後の業務イメージを事前に完璧に描くのは困難です。
多くの部署を巻き込んで長時間かけ検討し、大規模開発を行って万全を期したつもりでも、いざ出来上がったものが使いにくければ元も子もありません。
そこで重要なのが、まずは小さく試してみること、すなわちプロトタイピングによるスモールスタートです。「SPOを使ってどんなことができるのか」「どう使えば業務に活かせるのか」を伝えるには、実際に使ってもらうのが一番手っ取り早いのです。
具体的には、SPOの基本機能で簡単なサイトを作成し、テスト運用で不都合な点を潰していくような小規模導入を繰り返します。たとえば、まずはある部門の限られたメンバー向けに、文書共有用のシンプルなSPOサイトを構築して試してもらいます。利用者から操作性や業務フローに関するフィードバックを集め、必要に応じて設定や運用ルールを調整します。
こうした試行を何度か繰り返しながら改善を重ねることで、全社展開の前に「どの部分でユーザーに戸惑いが生じるか」「定着のためにどんなコミュニケーションが必要か」といったポイントも明らかになってくるでしょう。小さな成功と失敗を積み重ね、安価に軌道修正していくこのスモールスタートのアプローチは、結果的に大規模移行を成功させる近道となります。
平たく言うと、「いきなり完璧を目指さず、小さく始めて徐々に拡大していく」ということですね。
参考情報:SharePoint Onlineの基本機能について>>
処方箋2:フラッグシップアプローチ
SPOではNotesの全機能をそのまま再現することはできません。そのため、長年「Notes流」のやり方に慣れている人ほど、最初は「前にできたことができない。使いにくい」と感じてしまうことがあります。
人はメリットがはっきりしない新しいツールを敬遠しがちですが、逆に身近な同僚が「これを使って業務が楽になった」「成果が出た」と言っているものには興味を持つものです。そこで有効なのがフラッグシップアプローチ、つまり社内にお手本となる成功事例をつくる方法です。これは前述のスモールスタートともつながります。
全社導入に先立ち、まずSPOの基本機能のみを使ったモデルケースとなるサイトを一部の部門で構築し、そのサイトを社内に公開します。たとえば営業部門でSPOサイトを立ち上げ、提案資料やナレッジを共有してもらい、「具体的にどんな場面でどのように活用でき、どんな成果が出たのか」を社内報やイントラブログで紹介します。
身近な部門のリアルな成功体験としてそれを示すことで、「SPOを使えばこんなに便利になった」「自分の部署でも使ってみたいかも」という前向きな声が他部署にも広がっていきます。実際に社内で「今までより便利だ」という驚きや「これは使える」という納得感が生まれればしめたものです。人は自分が体験していなくても、知っている人の成功談を聞くだけで心理的抵抗感が下がるものです。こうして社内にポジティブな評判を醸成できれば、全社展開時のスムーズな定着につながります。
なお、このアプローチでは「NotesでできなくてSPOでできるようになること」にも目を向けることが重要です。Notesでは難しかった社内情報共有のオープン化や、他のMicrosoft 365アプリとの連携による業務効率化など、SPOならではの利点を積極的にアピールしましょう。
社員の多くは日常生活でSNSやクラウドサービスに慣れています。Notesを無理に再現するのをやめて発想を切り替えさえすれば、「SPOならこんなこともできる」という新しい価値にユーザーも気付き、抵抗感なく受け入れてくれるはずです。
つまり、「成功事例を作って、その良さを社内に広める」ということですね。あなたの会社でも、このような取り組みができそうではないでしょうか。

コミュニケーション手段に最適な社内SNSとは?おすすめツールの紹介
社内SNSツールはコミュニケーション活性化の有効な手段です。社内SNSとは、FacebookやInstagramなど誰もがフォローで…
参考情報:Microsoft 365の各種アプリ連携機能について>>
処方箋3:教育・研修と多様なコミュニケーション施策
新システム導入時には、教育・研修と多様なコミュニケーション施策でシステム変更の背景を伝えることが欠かせません。移行プロジェクトを成功させるには、単にシステムを提供するだけでなく、人の側の意識改革とスキル習得を伴わせる必要があります。
現場の社員は新しいシステムに不安や抵抗を感じるものです。その不安を和らげ、前向きに受け入れてもらうために、企業は様々な角度から働きかけを行うべきでしょう。
たとえば、導入時だけでなく継続的な学習機会を設けることが重要です。以下のような施策を組み合わせて、社内浸透を図りましょう。
社内メディアで情報発信:
社内報やイントラポータルサイトで、移行の目的やメリット、成功事例を定期的に発信します。現場社員の声(「SPOを使って○○が改善された!」など)を載せると効果的です。
研修プログラムの実施:
eラーニングや集合研修でSPOの基本操作やTeams/Yammerなど関連ツールの使い方を教育します。初心者向けハンズオンやQ&Aセッションを通じて安心感を醸成します。
社内SNS・コミュニティの活用:
社内の掲示板やチャットで質問を受け付け、担当者が迅速に回答する仕組みを用意します。ユーザー同士がコツを共有できるコミュニティを育てるのも有効です。
現場からの声の収集:
定期的にアンケートやヒアリングを行い、困りごとや要望を吸い上げます。得られた声をもとに追加研修を企画したりマニュアルを充実させたりすることで、現場主導の改善サイクルを回します。
これら施策を通じて大切にすべきなのは、「なぜ今このシステムを導入するのか」「この業務見直しが自分たちの仕事にどんなメリットをもたらすのか」を丁寧に説明し続けることです。単なるITツールの説明に終始せず、自社の経営理念やビジョン、昨今の市場動向など背景となるストーリーと結び付けて語ることで、現場の理解と納得感は格段に高まります。
業務プロセスの変更は現場にとって負荷であり、「お客様対応の時間が削られるだけだ」とネガティブに捉えられかねません。しかし、「この変革は会社がDX時代に生き残り、更に働き方改革によって社員の働きやすさを向上させるために必要なステップなのだ」と腹落ちしてもらえれば、現場も主体的な当事者として協力してくれるようになります。システム移行をきっかけに社員一人ひとりのデジタル活用意識が高まれば、一石二鳥と言えるでしょう。
また、移行推進にあたってはIT部門だけでなく、人事・研修担当や社内広報といった部署も含めた横断的チームで取り組むことが効果的です。現場社員へのアプローチにはそれぞれ専門のノウハウがありますので、組織横断で知見を持ち寄って継続支援していきましょう。
そして、トップマネジメントからの発信も欠かせません。経営層自らが新システムに期待する効果や将来ビジョンを語り、現場を巻き込んでいくことで、社員も「会社全体で取り組んでいるのだ」という意識を持つようになります。
噛み砕いて言えば、「技術的な説明だけでなく、なぜ変革が必要なのかを社員全員に理解してもらう」ということですね。
まとめ
移行プロジェクトを組織変革の機会に
現在、多くの企業が従来のオンプレミス中心のITからクラウド活用へと舵を切っています。Notesからの移行も、その大きな流れの一環と言えるでしょう。経営層、IT部門、そして各部門の現場社員まで、企業全体にデジタルに対する意識改革が求められる時代です。
システムを新しくすれば即DXが実現するわけではありませんが、Notesからの移行は社内の意識変革を促す絶好のチャンスにもなり得ます。移行プロジェクトを通じて社員のITリテラシーや部門間の情報共有が活性化すれば、業務効率向上や新たな価値創出にもつながっていくでしょう。

基幹システム導入に対する業務改革 ~チェンジマネジメントの風土醸成とコミュニケーション施策~
概要 / Overview 企業規模: 企業グループ 人数規模: 10,000名以上 目的は『システム導入…
重要なのは、Notes移行を単なるシステム刷新ではなく「人と業務の改革プロジェクト」と位置づけることです。新しいプラットフォームへの移行をきっかけに組織全体が学び、成長する機会と捉えましょう。
もし自社だけでの推進に不安がある場合は、技術面と人材育成面の両方に精通したパートナー企業に支援を仰ぐことも検討してください。これまでの経験から培った知見が、これからNotesの移行を検討する皆様にとって少しでも参考になれば幸いです。
移行の成功を通じて、企業の更なる発展と従業員の働きやすさ向上につながることを願っております。あなたの会社でも、このような組織変革の機会として移行プロジェクトを捉えてみてはいかがでしょうか。