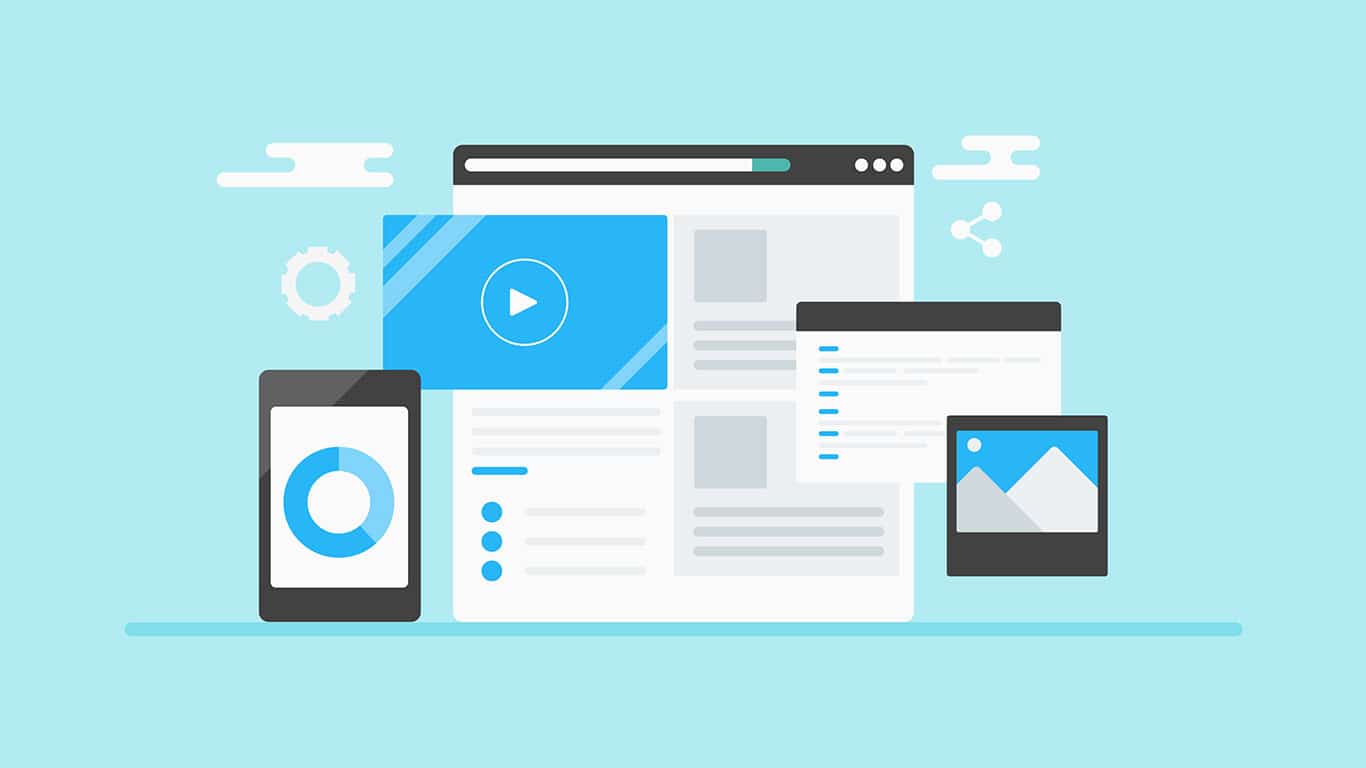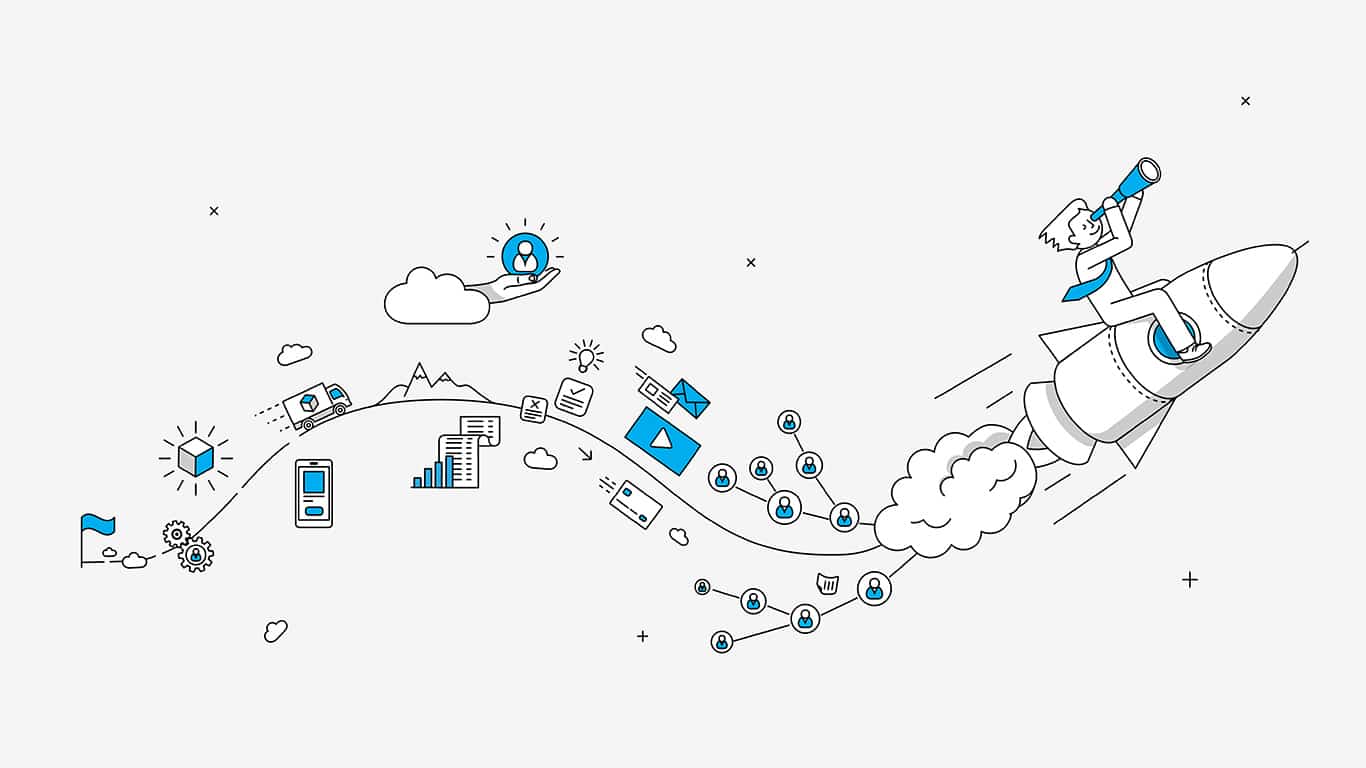組織のアジリティを高める5つの施策!注目企業の事例を紹介!
最終更新日:2022.10.14

目次
アジリティとは、状況に応じて素早く的確に判断を下し、行動する能力のことを指します。変化の多い現代のビジネスにおいては、組織のアジリティが重要とされています。
この記事では、アジリティの高い組織を作るために有効な施策をいくつか紹介します。注目企業の事例にも触れながら、効率的な経営改善への道筋を解説していきます。
アジリティとは 組織におけるアジリティの重要性
「アジリティ(Agility)」という言葉には、「機敏さ」「素早さ」「敏しょう性」などの意味があります。単にスピードが速いというだけではなく、状況に応じて素早い判断・行動ができるというニュアンスがあります。最近はビジネスの文脈で頻繁に耳にするようになりました。ここでは、企業組織においてアジリティが重要視されている理由について見ていきます。
なぜアジリティが注目されるのか?
なぜビジネスシーンでアジリティという言葉が使われるようになったのでしょうか。背景にあるのは、ビジネスのスピード感が飛躍的に上がったことです。目まぐるしい速度で変化するビジネスシーンにおいて、的確な判断を下しながら、素早く変化していくことが今の企業にとって重要な能力となっているのです。
IT分野における開発プロジェクトでは、システムやアプリケーションの全体像を設計してから計画通りに開発を進める従来の「ウォーターフォール型」から、機能やパーツ単位での開発と修正を繰り返すことで柔軟な対応が可能になる「アジャイル型」の開発が主流となりつつあります。「アジャイル開発」とは、アジリティの高い開発手法と言い換えることができます。
プロジェクト単位など小さい組織では、アジリティの高い状態を保ちやすい一方で、グローバル規模の複雑な企業組織においてアジリティを高めることは容易ではありません。企業組織そのものだけでなく、サプライチェーン、ファイナンスなど、ビジネスにおいて影響のある範囲が広ければ広いほど、それだけアジリティを高く保つのは困難になります。そのため、大企業は、規模の小さいベンチャー企業と比べ、変化への対応スピードが遅いケースが目立ちます。規模を生かしてビジネスの仕組みを最適化し、競争力を高めてきた結果、組織のアジリティが犠牲になっていることもあるのです。
多くの大企業にとって組織のアジリティ向上が課題になっているからこそ、アジリティに対する注目度が高まっていると考えられます。
組織のアジリティが低いことによる問題点
組織のアジリティが低い企業は、社内外の環境に対応することができません。
社会や環境は日々変化しますし、法律や技術は日々アップデートされていきます。市場環境が変化し、それが事業機会につながる場合には、素早く製品・サービスにつなげていかなければ他社に先を越されてしまいます。また、環境の変化が事業の脅威となる場合は、事業の方向修正や縮小・撤退、組織の変革や情報発信など、迅速に対応することができなければ、損失が膨らんでしまったり、企業の評判低下、信頼の失墜につながってしまう場合もあります。
つまり、組織のアジリティが低いことは、企業にとって命取りになりかねない大問題なのです。
組織のアジリティを高めるための施策
組織のアジリティを高めるためには「規制力の排除」と「推進力の向上」を両面で進める必要があります。
組織におけるアジリティの規制力となるものを排除するには、組織の階層をできるだけなくしてフラットな構造に変えるとともに、事業にかかわるさまざまな情報やデータにすべての社員がアクセスできるようにすることです。これによって上下関係や情報格差のない、オープンなコミュニケーションが可能になります。また、アジリティの推進力を高めるためには、企業の理念やビジョンを明確化し、仕事における価値観や判断基準にできるよう社内に浸透するとともに、権限移譲を進めて個人の裁量を高めることが必要です。
以下、「規制力の排除」と「推進力の向上」に向けた具体的な施策の例をご紹介します。
業務プロセスの可視化
事業環境の変化に柔軟に対応するためには、状況に合わせて迅速な業務改善を積み重ねていくことが必要です。そして、スピーディーな改善のために大切なのは、現状の業務プロセスが正確に可視化されていることです。
たとえば技術的にはデジタル化が可能なはずの業務に手作業や紙ベースのやりとりが残っているなど、業務プロセスの一部に古い仕組みが残っている場合は、そこがボトルネックになって業務全体の改善を妨げてしまう場合があります。積極的に見直しを行いましょう。
撤退基準の設定
事業単位で切り分けて業務プロセスや収支の状況を可視化すると、長らく利益が出ていない事業が見つかるかもしれません。利益の出ない原因が製品・サービスや業務プロセスの見直しで対応可能なものであれば即座に対応する必要があります。また、原因が外部環境にあって改善が見込めない場合などは、事業からの撤退や売却も視野に入れる必要があるでしょう。撤退に踏み切る基準をあらかじめ決めておいて、事業プロセスとして確立しておくとスムーズです。
情報共有ツールの導入・活用
組織のアジリティ強化のためには、スムーズな情報共有のための仕組みづくりも重要です。昨今では、ビジネス向けの便利なチャットツールが多数存在します。ツールを整備することで、連絡事項の伝達や、各種書類の申請・承認を円滑に行える環境を整えましょう。また、社内外の情報が集まる場を設け、そこにすべての社員がアクセスできるようになれば、社内に情報格差ができることを防ぎ、立場にかかわらず同じ情報を参照しながらコミュニケーションや意思決定が行えるようになります。
仕組みづくりの際に忘れてはならないのが、組織内にある情報やデータを正しく共有することです。個々の情報は、出し手の意図や受け手の解釈によって、バラバラの意味合いで広がってしまう場合があります。その情報がどこから出てきて、どのように利用されるべきものなのか、その情報の文脈や意味合いまで含めた的確な発信・受信が行われなければ、組織にとって有効な判断材料とはなりません。的確な情報共有を実現するために、社員の情報スキルにも着目しましょう。
個人の裁量
アジリティを高め、変化に対応できる企業になるためには、できる限り組織をフラットにして社員それぞれが権限を持つようにする必要があります。個人の裁量が小さかったり、権限の行使を阻害するような細かいルールや仕組みがあったりするなど、規制が多い場合は、現状を見直しましょう。
ただし、やみくもに個人の裁量を広げると組織が混乱に陥るリスクもあります。そのため、個人の裁量を拡大する際は、前述のように企業の理念やビジョンの明確化・浸透とセットで進めましょう。個人の権限を規制するルールを最小限にする場合、ルールのない部分については各自勝手に判断するのではなく、理念やビジョンを拠り所としながら、社内のコミュニケーションで補っていく必要があります。
つまり、組織のアジリティ向上のためには、社内コミュニケーションの活性化と、個人のコミュニケーションスキル向上が不可欠なのです。
コミュニケーションの活性化
社内の情報共有を促進するには「情報共有ツールの導入・活用」が必要ですが、それだけでコミュニケーションが活性化するとは限りません。仕組みの整備と並行して、積極的に情報共有が行われる企業文化の醸成に取り組みましょう。
例えば、メルカリでは2020年6月に、Slackの社内利用ガイドラインを公開しました。その中には「オープンであることを意識する」という項目があります。風通しの良い社風を維持するためにオープンなやりとりを推奨するとともに、「チャンネルへのinvite/leaveは誰でもいつでも可能」、「紳士的であること」などの項目も設けています。社員同士が互いに気遣いをしつつ、積極的に関わり合う。そんなフラットさを組織のあるべき姿として明示しているため、社員は安心してコミュニケーションをとることができるのです。
実際に変化対応していく際には、トップダウンでコミュニケーションを取ることも必要ですし、現場からトップへと、ボトムアップ的にやりとりすることも大切です。同時に、部門間・個人間のフラットな連携も重要でしょう。組織のアジリティ向上のためには、オープンな情報共有によって情報格差を防ぐとともに、立場にかかわらず誰でも平等に発言できるような場づくりや、社員のコミュニケーションスキル向上に向けた教育などにも力を入れると良いでしょう。
企業の理念・ビジョンの浸透
組織のアジリティを高い状態を保つには、これまで紹介してきたような施策によって、変化に対応できる体制を整えておくことが重要です。そして、すべての施策のベースとなるのは、判断や意思決定の基準となるべき企業の理念・ビジョンです。社員一人ひとりが理念・ビジョンを理解し、自分ごととして納得し、判断の拠り所としていれば、権限移譲を進めて個人の裁量を広げても、一貫性のある事業活動を行うことができます。
ただし、現場の権限を広げるとはいってもまた、全体としての戦略は経営側が持っておく必要があります。緊急事態時の対応を予め定めておくBCP(事業継続計画)のように、予想される環境変化に対して複数のシナリオパターンを先んじて用意しておくことで、いざという時に備えることができます。プランをいくつか持っておけば、状況が変わった際に1から戦略を立て直す必要がないため、素早く意思決定を下せるようになります。
なお、状況によってはどうしても、これまでとまったく異なる業態の新規事業を立ち上げるなど、理念やビジョンに沿わない意思決定が下さざるを得ないこともあるかもしれません。その場合、既存組織とは別の会社で事業を行うというアプローチも考えられます。あくまで理念・ビジョンの一貫性を保ちつつ、事業の幅を広げていくためには、子会社を作るなど方法も検討しましょう。
まとめ
顧客の変化やニーズに対応するために重要な要素がアジリティです。組織のアジリティを向上するためには、この記事で紹介してきたような各種施策が効果を発揮します。組織のアジリティ向上を図りつつ、外部環境の変化を常に把握し、外部と内部とのバランスを見極めながら柔軟かつ迅速に、状況に対応していきましょう。アジリティの高い企業になるための施策についてお悩みの場合は、どうぞソフィアまでご相談ください。