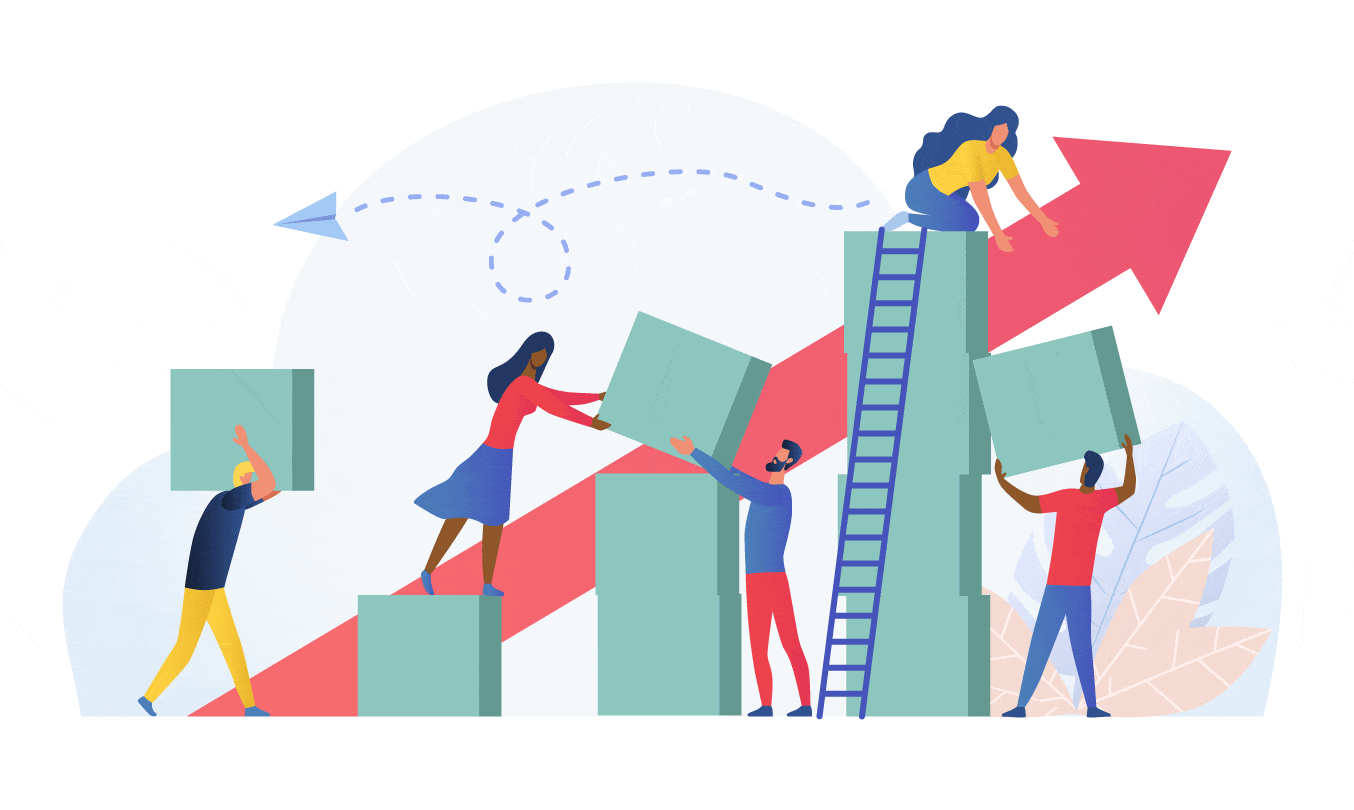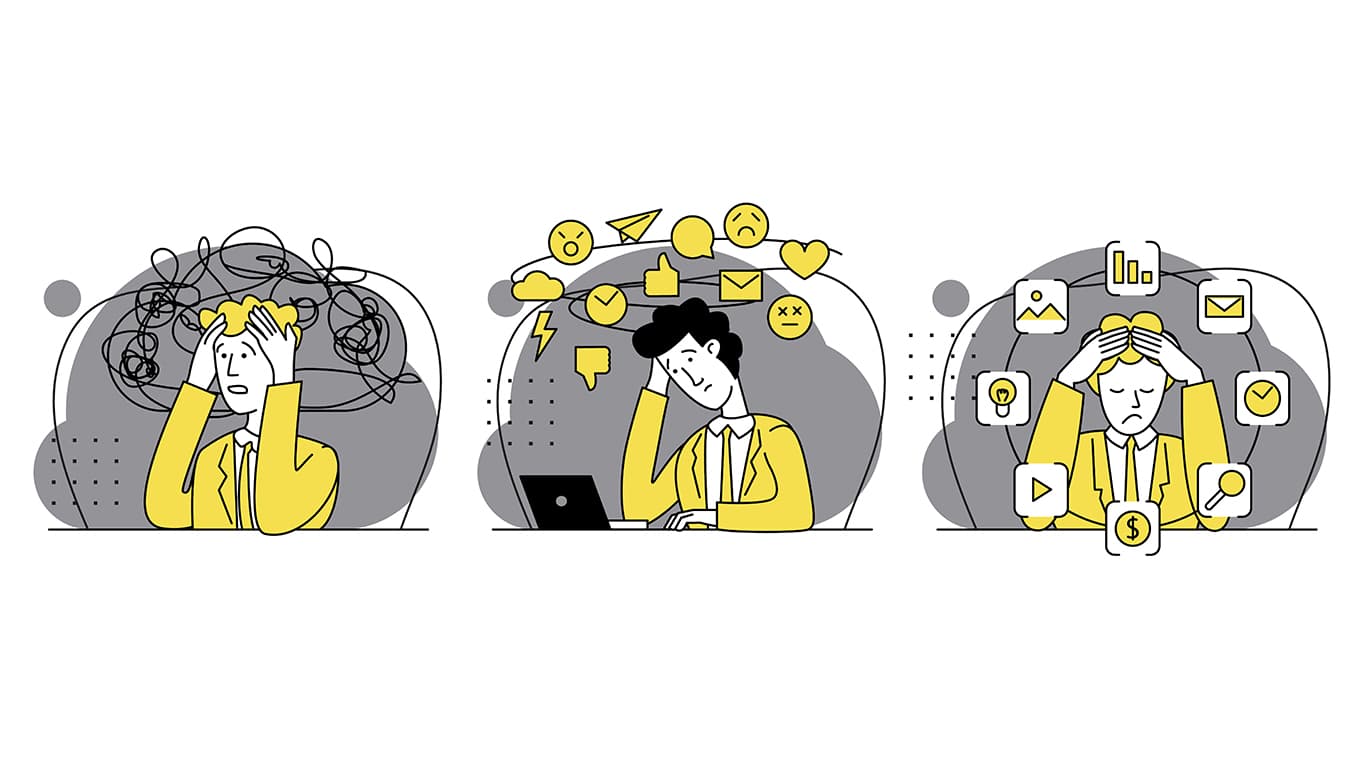HRBPと人事との違いとは?戦略人事との関係性もわかりやすく解説
最終更新日:2025.09.08

目次
HRBP(Human Resource Business Partner)は、従来の人事とは異なる新しい人事の形として、多くの企業で注目されています。一方で、「人事と何が違うのか?」「戦略人事とはどう関係するのか?」といった疑問を持つ方も少なくありません。HRBPは単なる制度運用者ではなく、経営戦略と人材施策をつなぎ、事業部門と連携しながら現場の課題を解決する存在です。
本記事では、従来の人事との違いや、戦略人事との位置づけについて、わかりやすく解説します。
HRBPの主な業務内容と具体的な役割
HRBPは、人事制度を現場に展開するだけでなく、経営戦略や事業課題を理解したうえで、最適な人材戦略を企画・実行する役割を担います。ここでは、現場との連携から育成、評価に至るまで、HRBPが担う具体的な業務について整理し、現場でどのように価値を発揮しているのかを見ていきます。
経営戦略に沿った人材配置・育成の推進
HRBP(Human Resource Business Partner)は、経営戦略の方向性を深く理解し、それを人材配置や育成方針に反映させる重要な役割を担います。たとえば、新規事業の立ち上げに伴って必要となるスキルやマインドを定義し、それを満たす人材を育てるなど、適任者を配置する計画を立案・実行します。
また、事業の持続的な成長を見据えた次世代リーダーの育成にも取り組みます。タレントプールの形成や選抜研修の企画・運営を通じて、企業の未来を担う人材を計画的に育てていきます。ここで重要なのは、単なる教育プログラムを用意するのではなく、事業戦略と紐づいた「成果につながる人材開発」を意識することです。
そのためには、現場で実際にどのような課題が生じているのかを正確に把握し、人材戦略へとつなげる必要があります。
現場課題のヒアリングと人事施策立案
経営戦略に沿った人材配置・育成を実効性あるものとするために、HRBPはまず現場との継続的な対話を通じて組織の実態を把握します。これは単なる情報収集にとどまらず、現場マネージャーや従業員と密にコミュニケーションを取りながら、人間関係の課題、採用ミスマッチ、育成プロセスのボトルネック、モチベーション低下の原因といった、深層的な要因を見極めていきます。
こうした現場の声を的確に吸い上げることで、採用基準の見直し、OJTの再設計、評価制度や育成プログラムの改善といった具体的な人事施策を立案・実行することが可能となります。
このように、HRBPは現場の実態を踏まえた施策を通じて、人材開発の質とスピードを高め、結果として経営戦略の実現に貢献します。
タレントマネジメントやパフォーマンス管理への関与
HRBPは、企業にとって将来的な競争力の源泉となる「人材」の見極めと活用を担う重要な存在です。タレントマネジメントでは、優秀な人材を見つけ出し、適切に配置し、成長を支援する施策を企画・運用します。たとえば、ハイポテンシャル人材の可視化、個別キャリアパスの設計、定着に向けたフォローアップ施策などがその一環です。
また、パフォーマンス管理の領域では、評価制度の設計・改善に関与し、業績と連動したフィードバックや報酬制度の整備も推進します。人材の成果や成長を正しく捉え、それを組織全体の生産性向上につなげるための仕組みづくりは、HRBPが担う中核的な業務のひとつです。
従来の人事職とHRBPの違いとは?
HRBPは近年注目されている新しい人事の役割ですが、従来の人事職とどう異なるのかを明確に理解することが重要です。業務範囲、視座、成果指標(KPI)、そして求められる役割には大きな違いがあります。ここでは、具体的な比較を通じて、HRBPの特徴とその価値を整理します。
従来の人事職とHRBPのKPIの違い
従来の人事職では「中央管理型」のKPIが多く、人事業務の実行状況や制度の運用率など、プロセス管理を重視した指標が中心です。たとえば、「採用充足率(計画30名に対し何名採用できたか)」「研修参加率(新任研修の出席率)」「評価面談の実施率」「異動手続きの完了率」など、業務が予定通り完了したかどうかが重視されます。しかしこれらは、事業への直接的貢献が見えにくいという課題もあります。
一方、HRBPのKPIは、事業目標の達成度合いに直結した成果指標です。売上や利益などの事業KPIを分解し、必要な人材配置・育成・評価施策をリアルタイムで柔軟に調整する力が求められます。つまり、プロセスよりもアウトカムが重視され、より経営寄りの成果責任を負うのがHRBPです。
人事の一般的な業務範囲(採用・労務・制度運用)
従来の人事職は、会社全体の制度や仕組みを支える役割として、幅広い業務を担っています。主な業務には、新卒・中途採用の実務、勤怠や給与、社会保険などの労務管理、福利厚生制度の運用・見直し、法改正対応、就業規則の管理などが挙げられます。これらの業務は、社員が安心して働ける環境を維持するうえで非常に重要であり、いわば“組織を安定的に回す”ための基盤づくりです。
ただし、こうした業務の多くはルーティンワークであり、経営戦略への関与や現場の意思決定支援といった戦略的要素は限定的です。従来の人事は「管理部門」の一翼としての役割が強く、現場に密着して課題解決を図る動きは比較的少ない傾向にあります。
HRBPと人事職との視座と役割の違い
HRBPは、単なる人事のオペレーターではなく、経営視点と現場視点の両方を持つ「戦略パートナー」です。経営層と密に連携しながら、経営戦略を人材戦略に落とし込み、現場へ展開していく役割を担います。同時に、現場のリアルな課題や声を吸い上げ、経営にフィードバックするという双方向の機能も持ちます。
これは従来の人事職が担ってきた一方向の制度運用とは大きく異なり、現場と経営の“橋渡し役”としての視座と責任が求められる点が特徴です。HRBPには、「課題をどう制度に落とし込むか」「現場が成果を出すにはどんな人材が必要か」といった問いに対して、自ら仮説を立て、提案し、実行していく行動力が求められます。
HRBPと人事職との業務内容の比較
HRBPと従来の人事職の業務内容を比較すると、目的・アプローチ・関与の深さに明確な違いが見えてきます。以下の表は、その主な違いを整理したものです。
| 項目 | 従来の人事職 | HRBP(Human Resource Business Partner) |
| 主な目的 | 制度運用・労務管理の安定運営 | 事業部門の成果達成を人材面から支援 |
| 活動スタンス | 全社共通ルールに基づく対応 | 事業部門に密着し、個別最適に対応 |
| 主な業務 | 採用事務、勤怠・給与、制度運用 | 人材要件定義、育成・配置施策、現場支援 |
| 関与レベル | 事務的・運用的 | 戦略的・提案的 |
| 成果の測定指標(KPI) | 運用完了率、参加率、手続き完了率 | 事業KPIの達成支援、部門パフォーマンスの向上など |
HRBPは、制度や仕組みを動かすだけでなく、施策の提案から現場での実行・改善まで一貫して関与し、成果に責任を持つポジションです。
HRBPが注目される背景と導入の目的
HRBPは、単なる人事支援ではなく、経営と現場をつなぐ戦略的な役割として注目されています。背景には、ビジネス環境の急速な変化や人的資本経営の重要性の高まりがあり、これらに対応する人材戦略が不可欠となっています。
以下では、その具体的な背景と導入による効果を整理します。
市場の変化
現在のビジネス環境は、デジタル化やグローバル化、働き方の多様化などによってかつてないスピードで変化しています。この変化により、現場が抱える課題も複雑化・多様化しており、従来の中央集権的な人事体制では、個別のニーズに迅速かつ柔軟に対応することが難しくなっています。
こうした状況に対応するため、HRBPは各事業部門に深く入り込み、実情を踏まえた上で人材戦略を立案・実行します。結果として、現場の意思決定スピードが上がり、変化への対応力が強化されるとともに、企業全体の競争力を高める効果が期待されています。HRBPの導入は、変化の激しい市場での成長に不可欠な施策のひとつといえるでしょう。
人的資本経営の台頭
近年、人的資本を「コスト」ではなく「投資すべき資源」として捉える人的資本経営の考え方が、経営の中心に据えられつつあります。企業は、社員のスキル、エンゲージメント、離職率、配置状況などの人材データを可視化し、それを経営判断に活用する流れを加速させています。このような取り組みを現場レベルで支える実行主体として、HRBPの存在が求められているのです。
HRBPは経営と密に連携し、人的資本に関する戦略を現場に展開するとともに、従業員のパフォーマンスを引き出す施策を推進します。人的資本の最大化は、持続的な企業成長を実現する鍵であり、それを現場で支える役割としてHRBPの導入は不可欠となっています。
経営課題と人材課題をつなぐ存在として
企業が直面する「売上拡大」「海外展開」「新規事業の創出」などの経営課題は、最終的には人材に起因するものが多く存在します。HRBPは、そうした経営課題と人材課題の接点に立ち、事業の成否を左右するスキルセットや人材要件を明確化する役割を担います。たとえば、新たな市場に対応するにはどのような人材が必要か、既存の社員にどのような育成を施すべきかといった問いに対し、現場の実態を踏まえて具体的な施策を設計します。
また、経営戦略を現場で実行可能なレベルに変換し、実行支援を行うこともHRBPの役割です。戦略の浸透と人材活用の質を高めることで、企業全体の成長を人事の側面から支えるのが、HRBPの本質的な価値です。
導入により得られる組織への効果
HRBPを導入することで、経営戦略と現場の人材施策がより密接につながるようになり、意思決定のスピードと正確性が高まります。現場に適した施策が展開されやすくなることで、従業員の納得感や主体性が育まれ、結果的にエンゲージメントや働きがいの向上にもつながります。また、経営・人事・現場の連携が強化されることで、組織としての一体感が増し、組織の変化耐性や成長力が高まるという効果も期待できます。
HRBPは、単なる“人事の一機能”ではなく、人材と経営の橋渡しをする戦略的パートナーとして、企業文化の変革や従業員体験(EX)の向上にも貢献する存在です。導入による組織的なインパクトは非常に大きいといえるでしょう。
まとめ
HRBPは、従来の人事職とは異なり、経営戦略と人材施策を結びつけ、現場の課題に深く関与しながら成果を生み出す「戦略人事」の中心的な存在です。人事が制度を守り運用する役割だとすれば、HRBPは制度を活かして事業を前進させる役割を担います。
特に、現場に密着してリアルな声を拾い上げ、経営に反映させる双方向の機能は、変化の激しい環境下において不可欠です。HRBPの導入は、人事部門の価値を「管理」から「経営支援」へとシフトさせる大きな一歩と言えるでしょう。