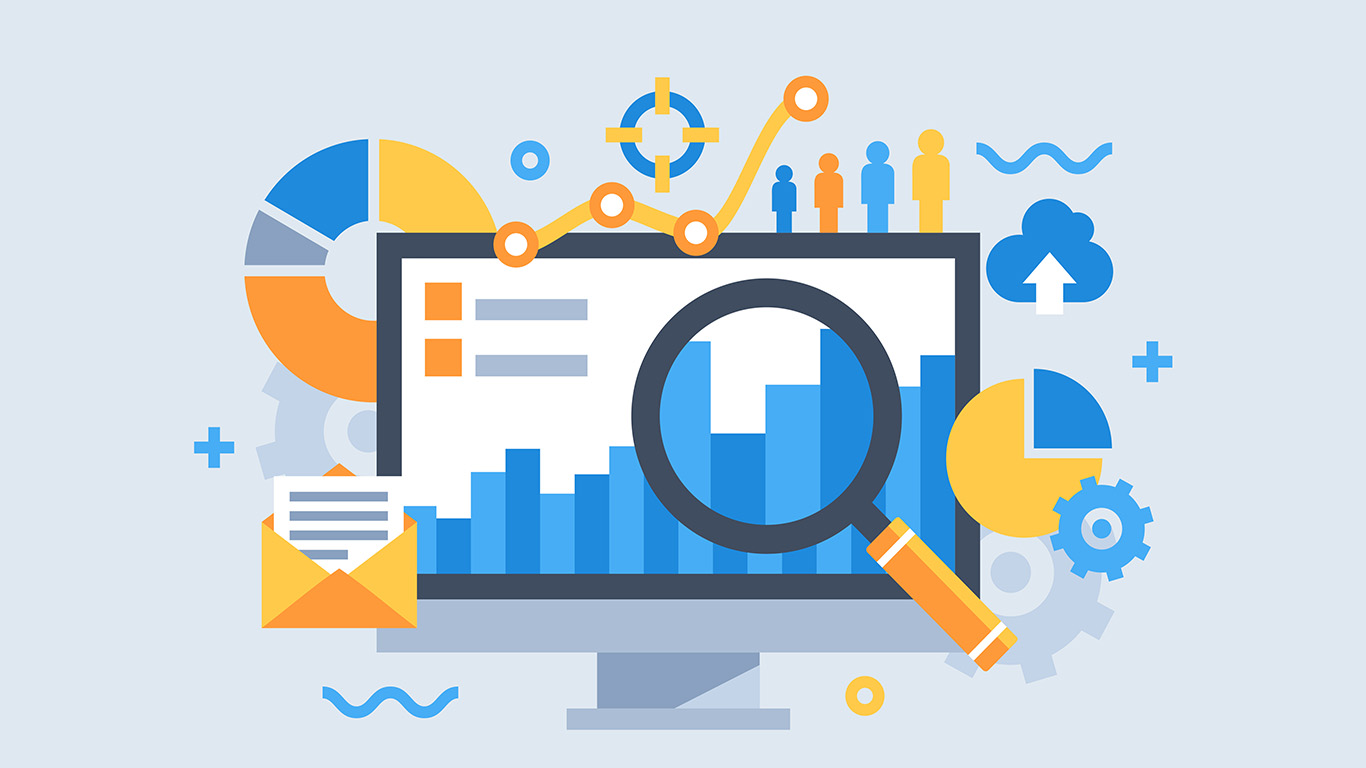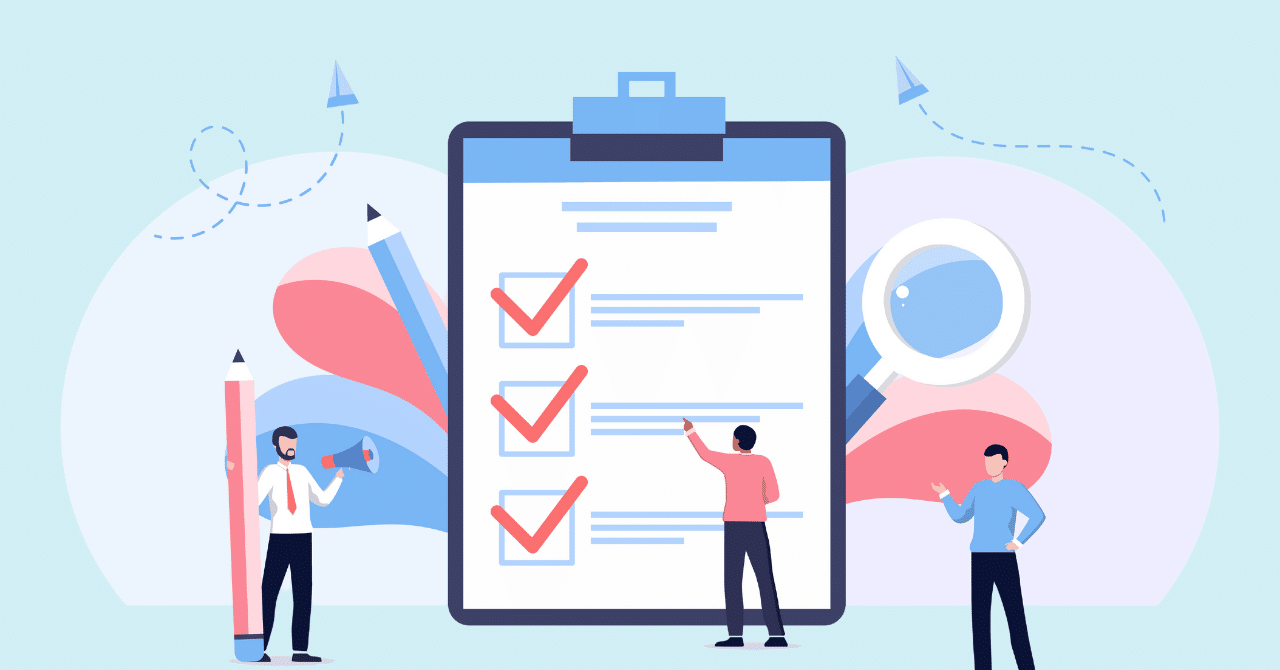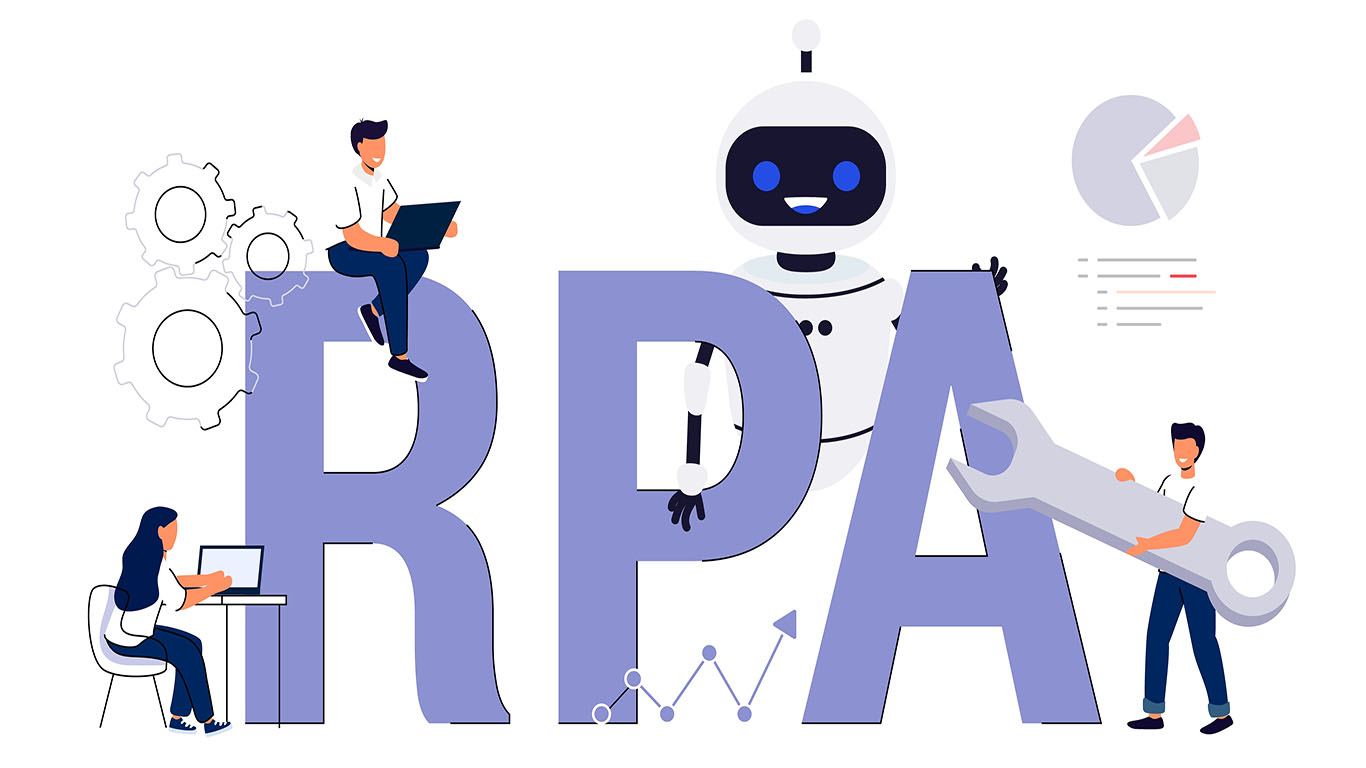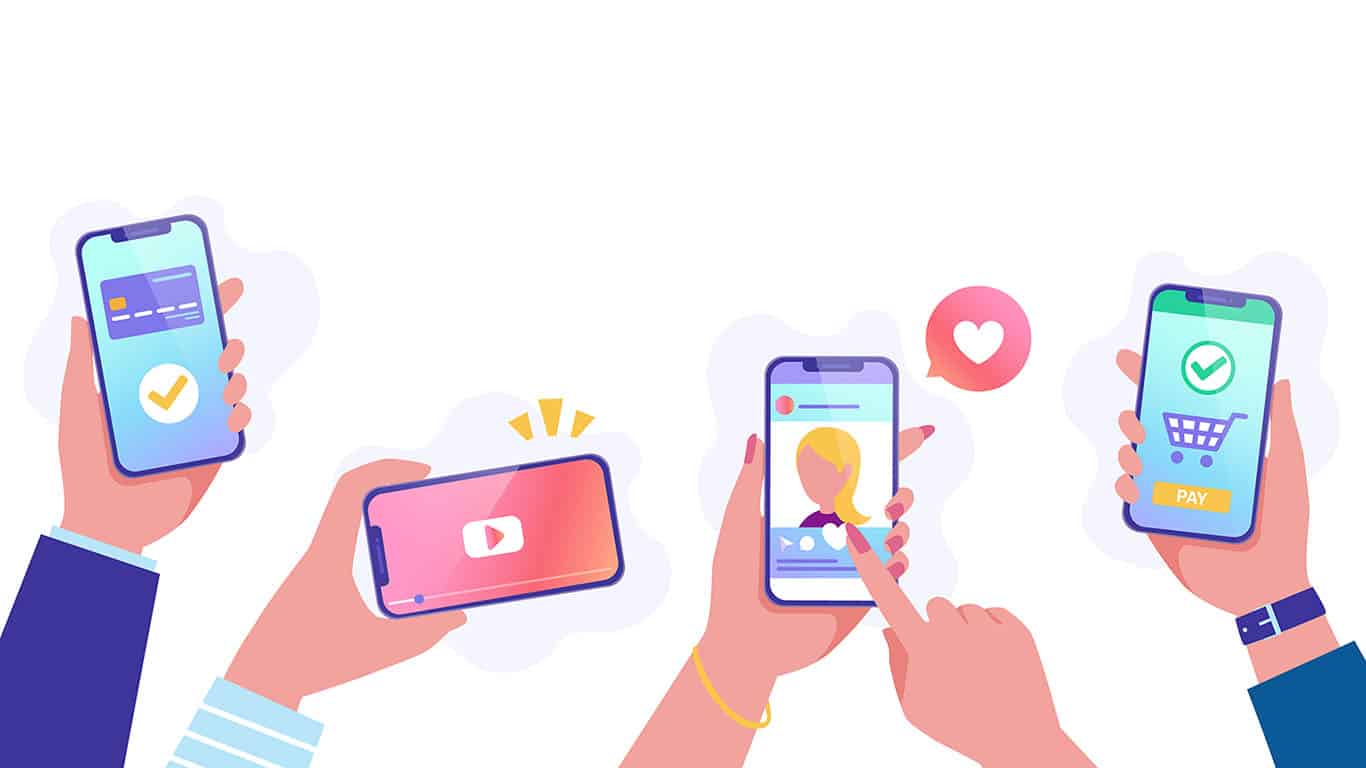人的資本経営に必要なデータとは?企業が押さえるべき指標と活用方法を徹底解説
最終更新日:2025.09.08

目次
人的資本経営とは、従業員を「コスト」ではなく「資本」として捉え、企業価値向上の源泉と位置づける考え方です。近年、人的資本の情報開示が義務化されるなど、注目が高まっています。しかし、実効性のある経営を行うには、感覚や経験だけでなく、客観的なデータに基づいた判断が欠かせません。
本記事では、人的資本経営を推進するうえで企業が押さえるべき主要なデータ指標や、その活用方法について詳しく解説します。
人的資本経営とは?
人的資本経営とは、人材を単なる費用ではなく、企業の成長を支える資産=「資本」として捉える経営アプローチです。従業員のスキルやモチベーション、働きがいといった要素を可視化・分析し、経営戦略に組み込むことで、持続的な企業価値の向上を目指します。
特に人的資本の情報開示が重視される昨今、数値による客観的評価と定性的な視点を融合させたマネジメントが求められています。
人的資本経営で活用すべきデータの種類
人的資本経営においては、多様な視点から人材の状態や価値を可視化する必要があります。特に国際的に評価されている指標や、現場の実情を反映する定性・定量のデータを適切に組み合わせることで、より実効性の高い戦略策定が可能となります。ここでは具体的なデータの種類を見ていきましょう。
ISO30414で定義されている人的資本情報の指標一覧(概要)
ISO30414は、企業が人的資本に関する情報をどのように開示し、管理すべきかを国際的に定めたガイドラインです。この規格では、人材の採用・育成・多様性などに関する定量・定性のデータを収集し、透明性ある報告を行うことが推奨されています。特に以下の11領域49項目が人的資本開示の枠組みとされています。
11領域49項目
- コンプライアンスと倫理
- コスト
- ダイバーシティ(多様性)
- リーダーシップ
- 組織文化
- 組織の健康・安全・福祉
- 生産性
- 採用・異動・離職
- スキルと能力
- 後継者の育成計画
- 労働力確保
これらの指標は、従業員のエンゲージメントや職場の健全性、将来的な人材戦略に活かす基盤となります。国際基準を理解することで、自社の人的資本の現状把握と課題設定がより明確になります。
定性データ(価値観、組織風土、リーダーシップ等)
人的資本の質を正しく捉えるには、社員一人一人の価値観や組織風土、マネジメントスタイルなどの「定性データ」が不可欠です。数値では測れないこのような情報は、企業文化や働きがいの実態を浮き彫りにする要素となります。
具体的には、エンゲージメント調査の自由記述欄、1on1での会話記録、社内イベントや懇親会での声、社内SNSでの発言などが参考になります。特に、現場の声を拾い上げることで、制度や方針の形骸化を防ぎ、働きやすい職場環境づくりに直結させることが可能です。
定性データは単体では活用が難しいこともありますが、定量データとあわせて読み解くことで、実態をより深く把握できるようになります。
定量データ(離職率、従業員エンゲージメント、生産性 等)
離職率や採用数、研修受講率などの定量データは、組織の健全性を示す客観的な指標として活用されます。特にエンゲージメントや労働生産性といったデータは、経営成果との相関が高く、企業の持続可能性を測る重要な指標です。
定量データは次のようなものが代表的です。
-
- 離職率
- 採用数、内定辞退率
- 従業員エンゲージメントスコア
- 研修受講率・時間
- 人件費あたりの生産性(付加価値額など)
- 有給休暇取得率
- 平均残業時間
- 従業員構成比(年代・職種など)
これらの数値は、経年で追うことで変化の兆しを把握でき、他社との比較(ベンチマーク)にも活用できます。人的資本を経営の成果に結びつけるには、継続的なモニタリングと適切なKPI設計が欠かせません。
人的資本データは活用されていない
人的資本経営の重要性が叫ばれる一方で、実際の現場では人材に関するデータが十分に活用されているとは言えません。多くの企業では、データが散在していたり、分析のための体制が整っていなかったりと、実務上の課題が山積みです。ここでは、なぜ人的資本データの活用が進まないのか、その背景を具体的に見ていきます。
各部門の人事データは、統合されず、分析されない
近年、多くの企業でタレントマネジメントシステムの導入が進んでいますが、それは「データが見えるようになった」だけにとどまっているケースが大半です。労務や賃金、評価などの社員情報は、システムの入力項目に従って最低限登録されているにすぎず、実際には人事部が保有するその他の情報や部門ごとのデータとは連携されていません。
特に問題となるのは、データが部門や機能ごとにバラバラに存在し、統合的なデータセットとして構築されていない点です。たとえば、採用部門と育成部門で異なるデータフォーマットが使われていたり、従業員の異動履歴や評価結果が定量的に扱われていなかったりと、分析以前の課題が多数存在します。
認知データ単体での分析の限界
人事の現場では、従業員アンケートやエンゲージメント調査といった“認知データ”の活用が広がっています。これらは社員の「気持ち」や「印象」といった主観的なデータであり、組織の温度感を把握する上では一定の価値があります。しかし、これだけに頼った分析では限界があります。
なぜなら、認知データはあくまで「感じ方」であり、日々の行動や業務実績とは必ずしも一致しないからです。本質的な改善を目指すには、出退勤時間、残業時間、評価スコア、業務プロセスの遅延率などの“オペレーションデータ”や“ハードデータ”と組み合わせて分析することが不可欠です。
このような分析を行うには、単なるデータ処理スキルだけでなく、人事制度や組織開発に関する深い理解も求められます。しかし、こうした両面のスキルを兼ね備えた人材は社内に少なく、多くの企業ではデータ分析が表面的な施策止まりになっているのが現状です。つまり、人的資本経営を支える分析体制そのものが未成熟なままなのです。
データを構造化し整理することが第一歩
人的資本データの活用を進めるには、まず「データの構造化」と「整理」が出発点になります。ここで重要なのは、単にデータを集めるだけではなく、それらを比較可能な形に整え、業務データと認知データを突き合わせられる状態にすることです。
たとえば、異動や昇進に関する履歴データと、エンゲージメントスコアや離職傾向などを照合し、因果関係を把握できるようにデータを並べる必要があります。そのためには、データベースの設計から見直し、部門間で連携可能な入力ルールや共通フォーマットを定義しなければなりません。
つまり、人的資本経営の出発点は、すでにあるバラバラの情報を正しく整理し、意味のある形で構造化することに他なりません。ここをクリアできなければ、どれほど高機能なシステムを導入しても、施策は形だけのものになってしまいます。
人的資本データを経営判断に活かす方法
人的資本に関するデータは、単に収集・蓄積するだけでは意味がありません。経営判断の材料として機能させるためには、戦略との結びつきや数値の解釈力が問われます。ここでは、人的資本データを実際の経営や事業施策にどう組み込むか、その活用ステップを具体的に解説します。
データをセットする
人的資本経営を効果的に機能させるには、まず経営判断に資するデータ項目を明確に定め、整備することが出発点となります。どんなデータを、なぜ集めるのかという「目的」から考え、経営目標との関係性が高い指標を選ぶことが重要です。
たとえば、出退勤データや労働時間、業務量などのハードデータ、従業員の評価スコアや目標達成率などのオペレーションデータは、業務の負荷状況やパフォーマンスの把握に役立ちます。また、離職率や人材の配置状況、スキルの分布、エンゲージメントスコアといったソフトデータも、人的資源の配置最適化に欠かせません。
重要なのは、これらのデータを部門横断的に統合・整備し、共通の定義で運用できる状態にすることです。ばらばらな形式で管理されていては、分析や意思決定に活かすことはできません。まずは必要なデータ項目を選定し、構造化・セットアップすることが人的資本経営の第一歩です。
経営KPIと連動した人材戦略の設計
人的資本データを本当に経営に役立てるには、事業戦略と連動したKPIを人材面でも設計し、施策の軸に据えることが欠かせません。経営目標と人事指標を分けて考えてしまうと、現場にとっても経営にとっても意味のある施策にはなりません。
たとえば、営業組織の拡大フェーズであれば「採用充足率」「新人研修の完了率」「初期パフォーマンス水準の到達割合」といったKPIが重要です。製品開発部門であれば、「専門スキル人材の確保率」や「プロジェクト完遂人員の稼働率」など、部門に即した指標が求められます。
事業部門と共通言語で対話できる指標設計こそが、人事を経営のパートナーに押し上げるカギです。また、定義や目標値を明確に共有し、進捗をタイムリーにフィードバックすることで、施策の実効性も大きく高まります。人材データは、戦略を推進する“動力”として設計する必要があります。
人材投資効果(ROI)を数値で示す
研修や採用などの人材施策に対して、どれだけの成果があったかを客観的に示すことは、人的資本経営の信頼性を高めるうえで非常に重要です。経営における投資判断では、費用対効果を数値で示すことが常識となっており、人材に関しても同様のロジックが求められます。
たとえば、「リーダー研修を受けた社員の昇格率が受講前より30%向上」「中途採用者の半年以内の離職率が改善された」「人材育成投資に対する売上貢献度が明確になった」といった形で、実施した施策が事業成果につながっていることを裏付けるデータを示すことが重要です。
経営会議・投資家向けのデータプレゼンテーションの工夫
人的資本に関する情報を経営層や投資家に提示する際には、単にグラフや数値を並べるだけでは不十分です。意思決定層がデータの意味を直感的に理解し、判断材料として受け取れるように構成することが求められます。
たとえば、離職率の改善を伝える場合でも、単に数値の変化を示すのではなく、「どのような背景で」「どんな取り組みを行い」「どの層に効果があったのか」を説明することで、より深い納得と共感が得られます。ストーリーを持って提示することで、単なる数値報告から、価値ある戦略共有へと変わるのです。
人的資本データの収集・可視化・管理方法
人的資本経営を実現するには、データの収集・整理・分析・活用の各段階が滞りなく行える基盤が不可欠です。特に複数部門にまたがる人事データを一元管理し、可視化する体制を構築することが重要です。ここでは、具体的な収集・可視化・管理の進め方を解説します。
社内データ基盤(人事・労務・評価・研修など)の整備
人的資本の可視化には、まず組織全体の人材情報を統合管理する基盤づくりが求められます。現状、多くの企業では人事・労務・評価・研修・勤怠といった情報が別々のシステムやExcelファイルに分かれて存在しており、データの全体像を把握しづらい状況にあります。
この課題を解決するためには、複数の社内システムを連携させた統合的なデータ基盤の構築が必要です。HR系のシステムだけでなく、業務システムや生産性指標などとの接続も視野に入れ、人的資本データを多角的に扱える環境を整えます。
BIツールやHRテックの活用
膨大な人的資本データを効率よく分析・活用するには、テクノロジーの力を借りることが不可欠です。特にBI(ビジネスインテリジェンス)ツールやHRテックの導入は、データドリブンな人材戦略を推進するうえで有効です。
BIツールを活用することで、勤怠状況・離職率・スキル保有状況・エンゲージメントスコアなど、部門横断のデータを一元的に可視化し、グラフやチャートで直感的に把握できます。また、経営層向けにはダッシュボードをカスタマイズし、重要指標のみを簡潔に表示することで、判断スピードが向上します。
HRテックを活用すれば、AIによる離職予測やスキルギャップの可視化、パフォーマンスとエンゲージメントの相関分析なども実現可能です。これにより、従来の属人的な判断から脱却し、根拠のある人材マネジメントへと進化できます。
アンケート・360度評価など現場データの取得方法
人的資本の状態をより正確に把握するためには、現場の声を定期的かつ信頼性の高い形で収集する必要があります。そのための手段として有効なのが、エンゲージメントサーベイや360度評価などのアンケート手法です。
エンゲージメントサーベイでは、従業員の働きがいや業務への満足度、心理的安全性などを可視化できます。これにより、職場の雰囲気やマネジメントの質を継続的にモニタリングすることが可能になります。一方、360度評価は、本人だけでなく同僚や上司、部下など多方面からの評価を収集でき、リーダーシップや協調性といった定性的な情報を多角的に把握できます。
これらのアンケートは、無記名かつ継続的に実施することで、より率直な意見や実態に即した情報を得やすくなります。加えて、サーベイ結果を本人にもフィードバックし、対話の材料とすることで、組織開発にもつながります。
定量データだけでは見えない“人の気持ち”や“行動の背景”を読み解くには、こうした現場起点のデータ取得が不可欠です。
人的資本経営を支えるデータを収集するためのコミュニケーション
人的資本経営を進める上で、これまで注目されてきたのは主にインプット(採用・スキル・研修など)やアウトプット(評価・業績・離職率・360度評価など)の指標でした。しかし、組織における実際の成果や課題の背景には、それらをつなぐ「プロセス」が存在します。そしてそのプロセス、すなわちスループットに該当するのが、従業員間の「コミュニケーション」です。
かつては、このスループットの可視化は困難でした。会議、雑談、メール、チャットといった日々のやりとりは定性的であり、定量化しづらい領域とされていたのです。しかし現在では、リモートワークやDXの進展により、業務の多くがオンラインで行われるようになり、SlackやTeams、Zoomなどを通じたコミュニケーションのログをデータとして取得することが可能になりました。
人的資本経営の本質は、人と組織の価値を最大化することにあります。そのためには、成果(アウトプット)だけを見るのではなく、そこに至るまでの過程(スループット)に注目し、改善の仮説を立てることが欠かせません。スキルやエンゲージメントだけでなく、「どう協働し、どう意思疎通しているか」というプロセス自体をデータ化し、分析・改善する視点が、これからのHRに求められています。
なお、こうしたデータ活用を成功させるには、信頼関係に基づいた現場との丁寧な対話も不可欠です。データの取得・活用が従業員の不安を生まないよう、「なぜ取るのか」「どう使うのか」をオープンに伝える姿勢が、持続的な人的資本経営の基盤となります。
まとめ
人的資本経営を実現するには、単にデータを集めるだけでは不十分です。採用・育成・エンゲージメントなどの多様な指標を経営と結びつけ、戦略的に活用することが求められます。
そのためには、データの整備や可視化に加え、現場との信頼関係を築き、質の高い情報を引き出す仕組みづくりが欠かせません。経営層と人事が一体となり、人的資本を「見える化」し、「伝わる」形で発信することが、企業価値の持続的な向上につながる鍵となります。