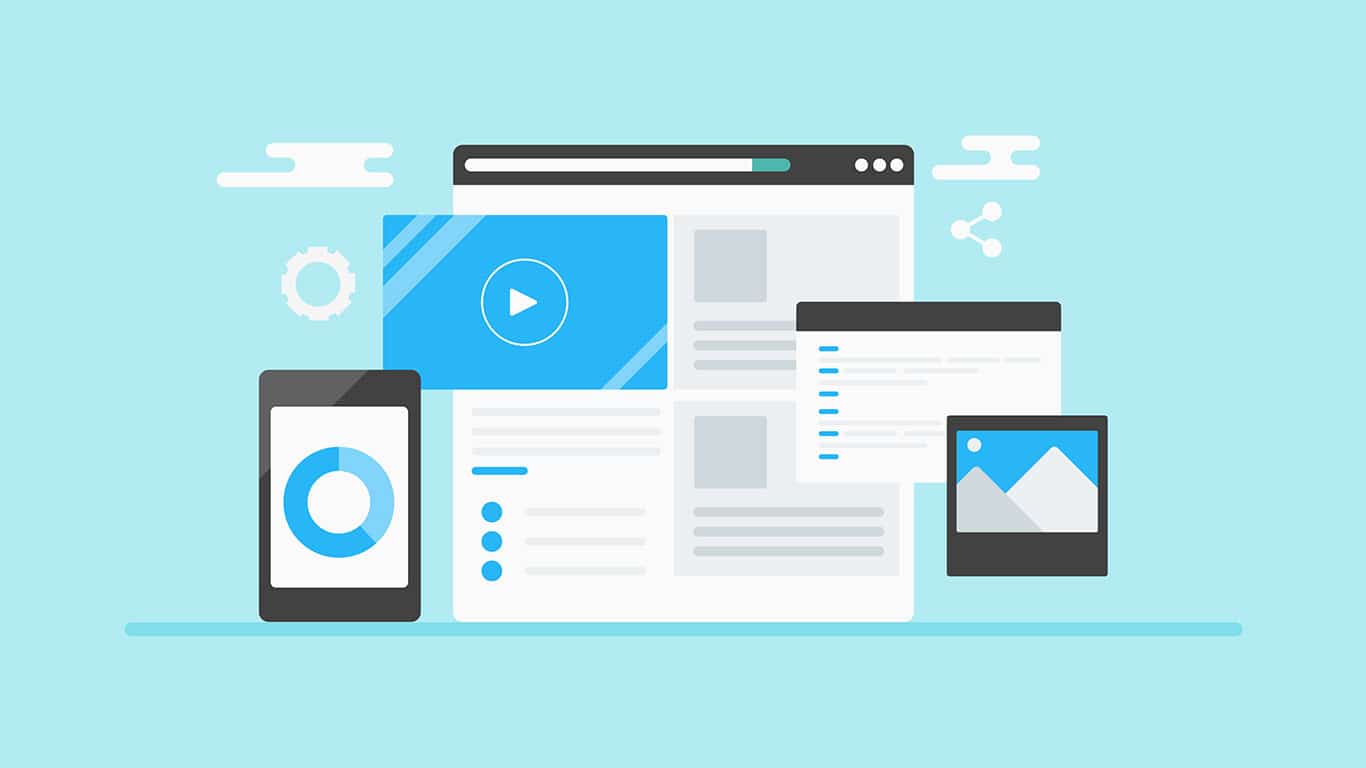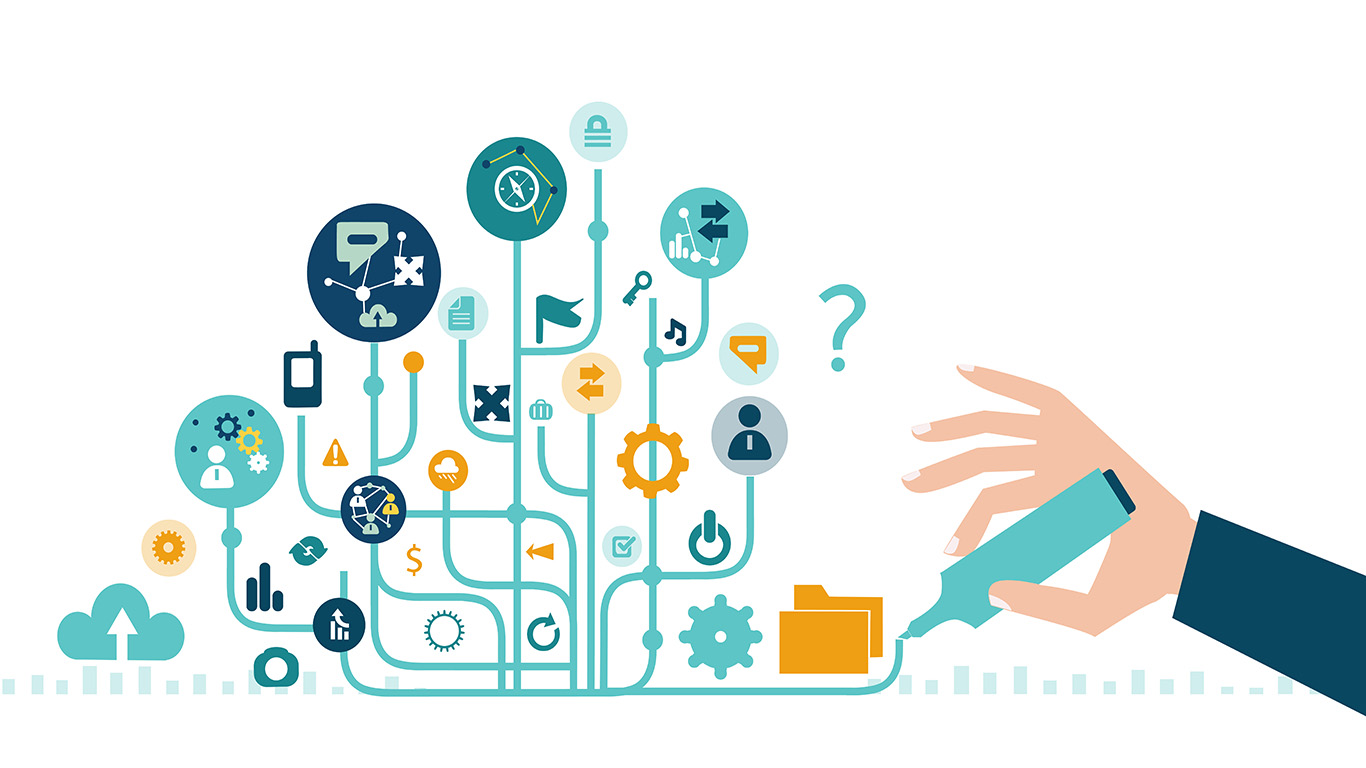職場の雰囲気が悪い原因は?雰囲気を良くする方法を解説
最終更新日:2023.03.01

目次
職場の雰囲気が悪いと、従業員の仕事に対するモチベーションや業務効率が下がる可能性があります。業務効率が下がると、いずれは業績の悪化にもつながっていくでしょう。そのため、職場の雰囲気は良い状態に保ちたいものです。
本記事では、職場の雰囲気が悪くなる原因について解説します。さらに、良好な雰囲気に切り替えていく具体的な方法も紹介するため、職場の雰囲気を良い状態に保ち、業務効率を維持する際の参考にしてみてください。
職場の雰囲気が悪くなる原因
まずは、職場の雰囲気が悪化してしまう要因を整理しましょう。コロナ禍でオンラインでのやりとりが増加した結果、雑談や会話をする機会が少なくなり、ちょっとした相談のための声掛けなどが困難になりました。こうして全体的にコミュニケーションの濃度が下がった結果、互いに対する信頼関係を構築するのも難しくなっています。
そのため、意見があっても交わしにくかったり、新しい意見を言いづらかったりする雰囲気の職場が増えてきています。また、社内の共通言語が作れないため部門間の連携が希薄化し、建設的な議論が困難になってしまうこともあります。前例のないことの実行が困難になり、イノベーティブな仕事に取り組みにくくなった組織も多いのではないでしょうか。職場でこのような問題が発生していても、オンライン上では問題そのものに気付くことすら困難です。
スペインの哲学者ホセ・オルテガ・イ・ガセットは人の存在を「人間とは、人とその周囲の環境である」と定義しました。人間がその周囲の環境を創り、その創った環境にまた影響されるのです。つまり、職場の雰囲気を創っているのは、職場の人自身ということです。さまざまな社会課題にさらされ、労働環境も大きく変わっている現代の職場では、対策を講じていなければ、コミュニケーションに関する様々な問題が生じてしまいます。職場は組織内における小さな組織です。そのため、職場の問題は、最終的に組織の問題へとつながっていきます。
職場の雰囲気を良くするためにはコミュニケーションの改善が重要
職場の雰囲気を改善していくために、コミュニケーションはとても重要なものです。HR総研が実施した「社内コミュニケーションに関するアンケート2022」によると、「社内コミュニケーション不足は業務の障害」と思う人は9割以上という結果が出ています。また、経団連が2018年に行った「新卒採用に関するアンケート調査結果」では、企業が新卒を採用する際に重視する点として「コミュニケーション能力」が16年連続で1位となりました。
これらの結果からも、コミュニケーションが職場の雰囲気に与える影響の大きさがわかります。従業員一人ひとりが、職場の雰囲気を作っているのは自分なのだという意識と自覚を持つことが大切でしょう。

社内コミュニケーションの目標設定|KPI設計と成功事例で組織を変える【2025年最新版】
社内コミュニケーションの目標設定にお悩みですか?本記事では、大企業のDX・広報・人事担当者向けに、定量・定性デ…
職場の雰囲気を左右する2つの要素とは?
組織開発においては、業務を形成するために必要なプロセスをメンテナンスプロセスとタスクプロセスに分けて考えることができます。
タスクプロセスは、業務ステップやタイムスケジュール、誰がどの業務を担当するのかという割り振りなど、目に見える要素です。メンテナンスプロセスは、モチベーションやコミュニケーション、職場の雰囲気や人と人との関係性といった目に見えない要素です。
タスクプロセスのように可視化できるものは把握しやすいので、多くの業務現場でケアされていますが、メンテナンスプロセスのケアは後手に回りがちです。特に、現代の多くの職場では、さまざまな業務をメンバーが入れ替わりで行うようになり、新しいプロジェクトが発生するたびに人間関係が新たに形成される傾向が強くなっています。だからこそメンテナンスプロセスもしっかりケアする必要があります。
職場の雰囲気を創るメカニズム
コミュニケーションやモチベーションといった目に見えない要素は把握するのが難しいですが、職場の雰囲気を形成する重要なものです。職場の雰囲気を良好なものにするためには、従業員のモチベーションが高い状態に保たれているか、職場の雰囲気や人と人との関係性は良好かどうかを意識的に管理しましょう。
組織風土と職場風土の関係
職場の雰囲気は、しばしば「組織風土」や「組織文化」という切り口で語られることがあります。両者は似ている言葉ですが、意味が異なります。組織風土がいつのまにか定着してしまった組織の習慣である一方で、組織文化は意図的にデザインすることが可能な習慣です。
組織心理学の権威であるエドガー・H・シャインの組織文化の3段階モデルを用いると、組織文化を構成する要素は、以下の3つであると説明することができます。1つ目の要素は、組織体制、社訓、経営理念、戦略、トップの人物像など、目に見える形で存在するものです。いわゆるハード面の意味合いを持つ要素となります。2つ目の要素は、暗黙のルール、社内コミュニケーション、責任の所在、トップの影響力など、目に見えないものです。こちらはソフト面の意味合いを持つ要素といえます。3つ目の要素は基本的過程です。簡単に説明すると、組織の大多数が当然と思い込み、疑うことがなくなってしまっている価値観や行動などです。
職場の雰囲気は、この3段階の要素から成る組織文化に影響を受けます。どのようにコミュニケーションを取るか、トップはどんな人か、どんな価値観があるかが、職場の雰囲気を左右し、ひいては職場風土として確立されていくのです。職場のような組織内組織では、職場の雰囲気はリーダーや構成員が創り出すものです。また、職場では構成員の個性や心理が、日々変化しています。そのため、「上司が変わって、職場の雰囲気が変わった」ということもあるでしょう。職場の雰囲気の問題は、リーダーが原因の場合もあれば、メンバー同士の相性に起因する場合もあります。
職場風土は、構成員の行動が全て
職場風土は、所属する従業員がいかに組織文化をデザインするかにかかっています。良好な雰囲気の職場を作るためには、従業員の行動が全てです。その中でも、特にリーダーの行動が重要です。リーダーが「どんな意見でも歓迎する」と明言し、職場が安心安全な場所であることを態度で示すことができれば、従業員の本音やアイデアが引き出されます。場合によっては、リーダー自身が、普段口にしないことをあえて話すなど、感じていることを積極的に伝えていく姿勢が大切になります。
もし、リーダーが職場の雰囲気の悪化に困っている場合、自分自身もその困難な課題を作ったひとりであることを理解しましょう。自分自身を客観的に見て評価すれば、組織の人たちはどのように関わり合っていたのか、そして自分自身がそこにどのように関係していたのかがわかるでしょう。俯瞰で把握することで、組織における自身の課題を認識することができ、職場の雰囲気改善につながります。
また、コロナ禍で対面でのコミュニケーション機会が少なくなり、社内コミュニケーションに関する問題は大きくなりました。コミュニケーションコストが増えていることは否めません。しかし、重要なのはコミュニケーションスタイルを革新しレベルアップを図っていくことです。そうすれば、組織内および組織間の連携も深まり、ケイパビリティ(組織能力)も向上します。コミュニケーションをコストからプロフィットに変えていく取り組みが必要なのです。
職場の雰囲気を良くする方法
職場の雰囲気を良くするチャンスは、異動などの構成員の物理的な変化のタイミングになります。管理職やリーダーが変われば、職場の雰囲気が良くなるケースもあるでしょう。しかし、異動は自分自身の考えのみではなかなか実行に移せません。では、構成員の物理的な変化以外で、どうすれば職場の雰囲気を良くすることができるのでしょうか。それは、目に見えない要素を強く意識しながら抜かりなく管理していくことです。以下では、そのために取り組める具体的なアクションを紹介します。
業務を見直して業務量を調整するもしくはリソースを増やす
業務の内容や量は、職場の雰囲気に直結します。業務量に不満を持っている社員が多い場合は職場の体制を見直したり、その他の問題点について議論したりましょう。業務量を見つめ直すことで雰囲気が改善するケースもあるので、業務量軽減のための方法や仕組みを考えてみましょう。
社内イベントを行う
業務以外で、つながりの場を作るのも効果的です。部活動や勉強会を行ったり、レクリエーションを開催したりすることで、コミュニケーションを活発にすることができます。業務以外にコミュニケーションの場を設けることで、より社員同士の情報を知ることができ、信頼関係の構築を促すことができます。
コミュニケーションツールを取り入れる
社内にコミュニケーションツールを取り入れるのもおすすめです。社内報への投稿募集や、Web社内報のコメント欄などの他、個人が直接情報発信できる社内SNSなどの仕組みを導入すると、誰でも発言しやすい環境を作ることができるでしょう。
1on1ミーティングを行う
1on1ミーティングは特に若いメンバーにとっては、率直な意見を上司に伝えやすい場になるでしょう。日頃考えていることや不満、違和感などにじっくり耳を傾けることで、課題を見つけていきましょう。向かい合ってまとまった時間会話をすることで、上司と部下の距離感が縮まり、信頼が高まるという効果も期待できます。
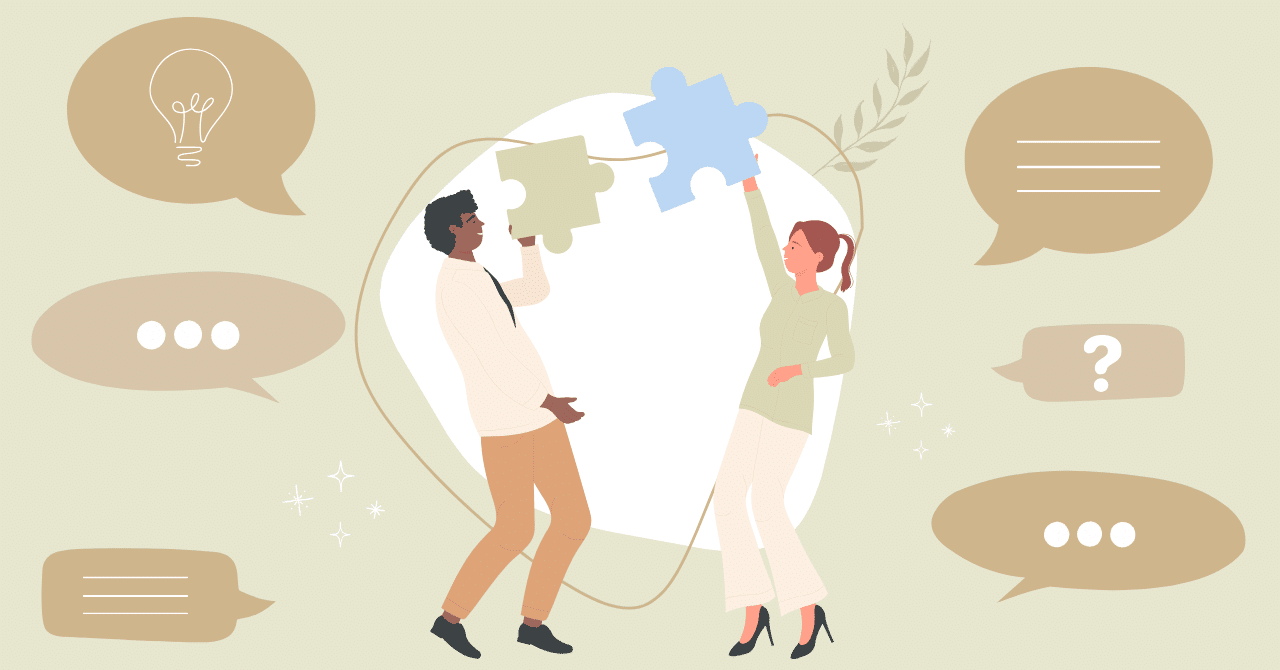
1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介
最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…
コミュニケーションスキルを向上させる
以下のコミュニケーションスキルを身につけることも、雰囲気づくりのためには有効です。職場では特にリーダーの影響が大きいため、リーダーは以下のスキルを向上させて積極的にコミュニケーションを取る必要があります。
- 対話
対話は何かしらのテーマに基づいて、それぞれの意見を述べ、お互いの立場や意見の違いを理解し、擦り合わせることを目的に行うものです。通常の会話とはちがい、自分の行動や発言の根源にある感情や考え方、価値観などについて掘り下げて語ります。普段の聞けない事や普段話すことのないビジネス以外の内容を話すことも職場の雰囲気に影響与える因子です。仕事の延長線上だけでは、情報だけでは本質な関係構築に至ることは難しいでしょう。対話についてのより詳しい解説は、下記をご確認ください。
- 傾聴
「聞く」と表記せずに、「傾いて聴く」と書いている通り、「相手の話に耳を傾けて注意深く聞くこと」が重要です。これは姿勢や態度という意味合いも含んでします。傾聴によって話を聞いて理解できる人材は、関係者と信頼関係を築き、仕事を円滑に運ぶことができます。相手の声に耳を傾け過ぎて職場の雰囲気が悪くなることはありません。傾聴の姿勢やスキルの使い方、傾聴についてのより詳しい解説は、下記をご確認ください。
- ディスカッション
特定のテーマに対し、解決すべき問題を発見したいとき、つまり不確定な問題について真理を追究したいときにディスカッションが行われます。また、特定の課題を解決するために、合意形成(コンセンサス)を取りたいときにもディスカッションが行われます。ディスカッションについてのより詳しい解説は、下記をご確認ください。
- ディベート
「ディベートなんてやったら職場の人間関係がもっと悪くなる」とご指摘されるかもしれませんが、それは大きな間違いです。職場の雰囲気を、関係性や感情面だけに焦点をあてると大きな間違いを起こします。つまり、そもそもの目標や業務在り方自体がずれている場合は、結果も成果もでず、自ずと職場雰囲気は悪くなります。安心安全に実施するならばゲームとしてのディベートを実施することで、反対意見や異論を感情を気にせずに、業務や目的を論理的に整理できます
- ファシリテーション
ファシリテーションとは、職場のゴールに対する職場のメンバーの納得感を醸成し、職場内外の状況の変化に柔軟に対応しながら、所属メンバーのモチベーションを高め、安心して活動ができるような場づくりを行います。これは、業務と人の均衡を保つ現在一番必要なコミュニケーションスキルと言ってもよいでしょう。組織や人、職場そのものが複雑になっている昨今、その重要性はますます高まっています。
まとめ
職場の雰囲気は、業務効率や業績にも関係する重要なものです。職場の雰囲気を良くするためには良い組織文化を構築し、コミュニケーションを活性化させることが必要です。具体的な施策として業務量の見直しや社内イベントの開催、コミュニケーションツールの導入などに効果を期待できます。意識的に社内コミュニケーションを活発化させることで、良好な雰囲気の職場を作っていきましょう。