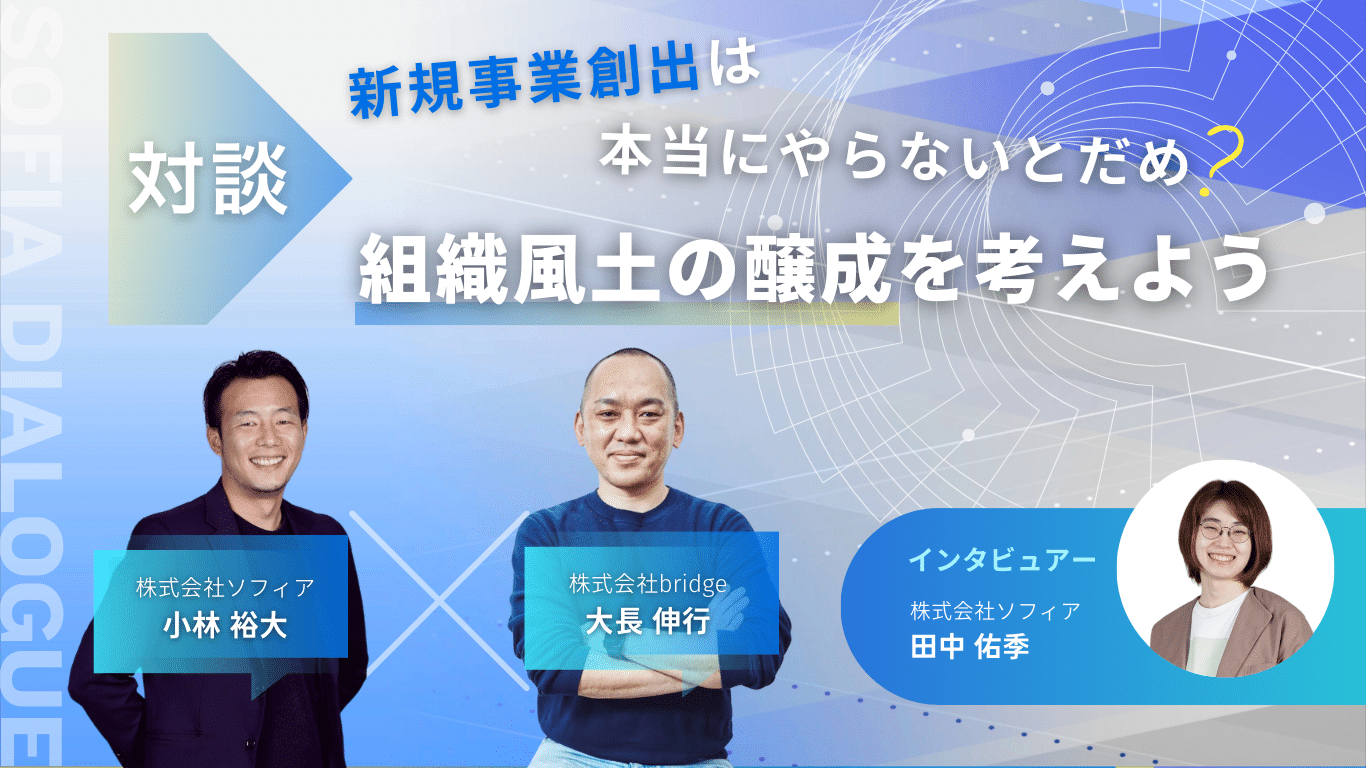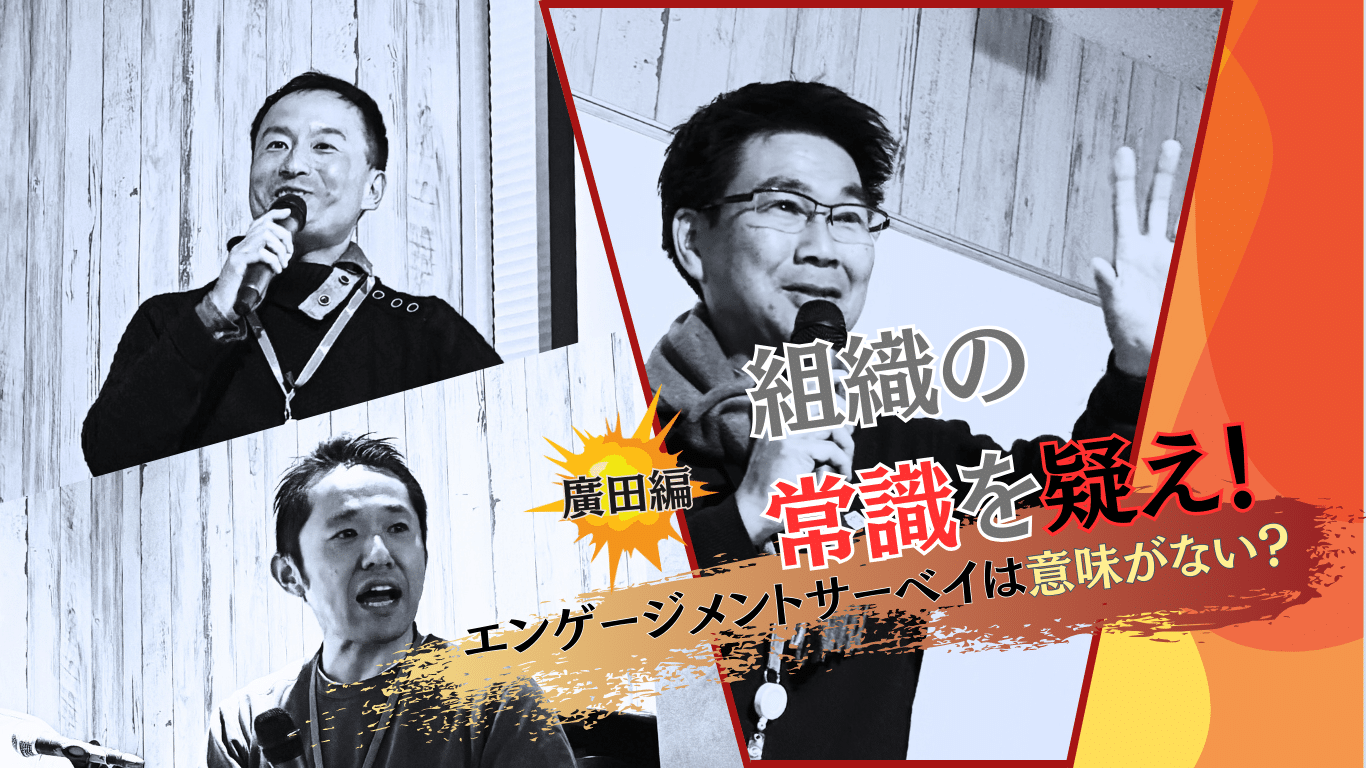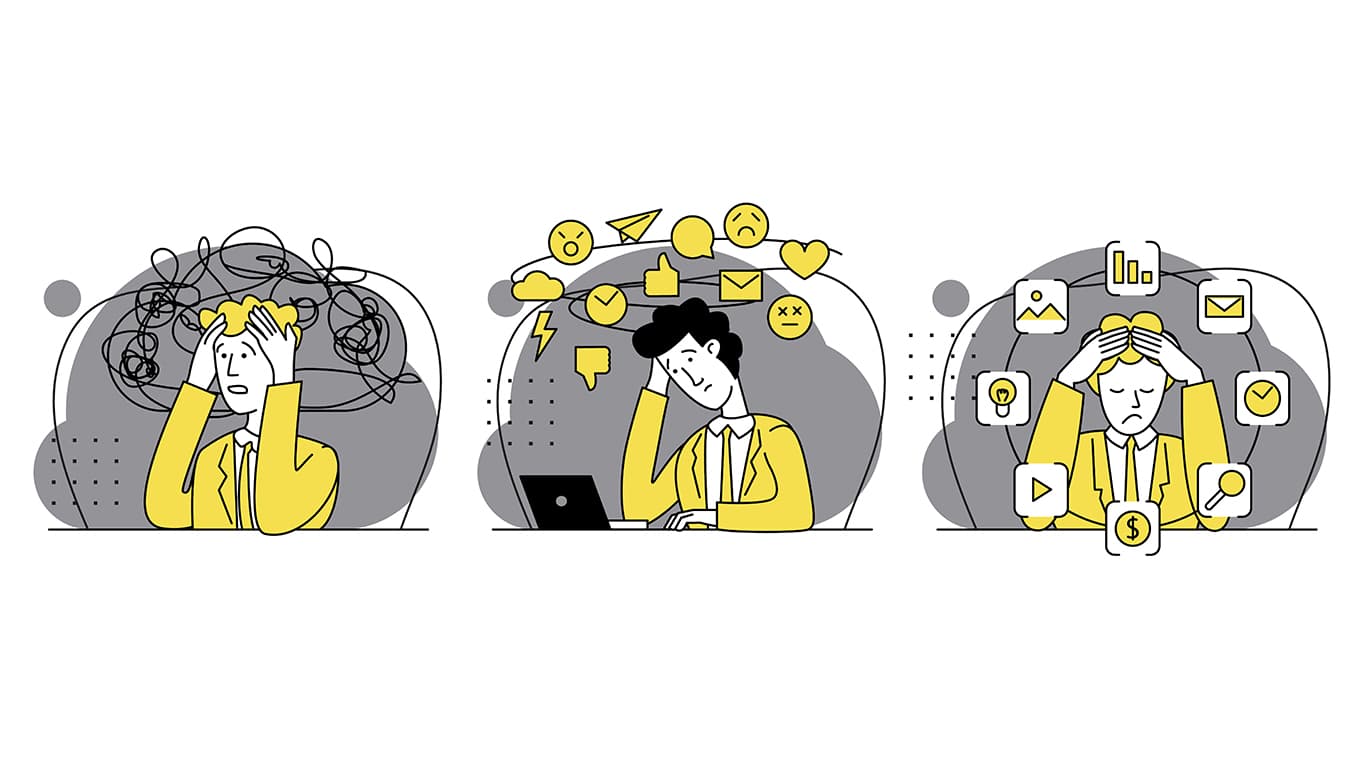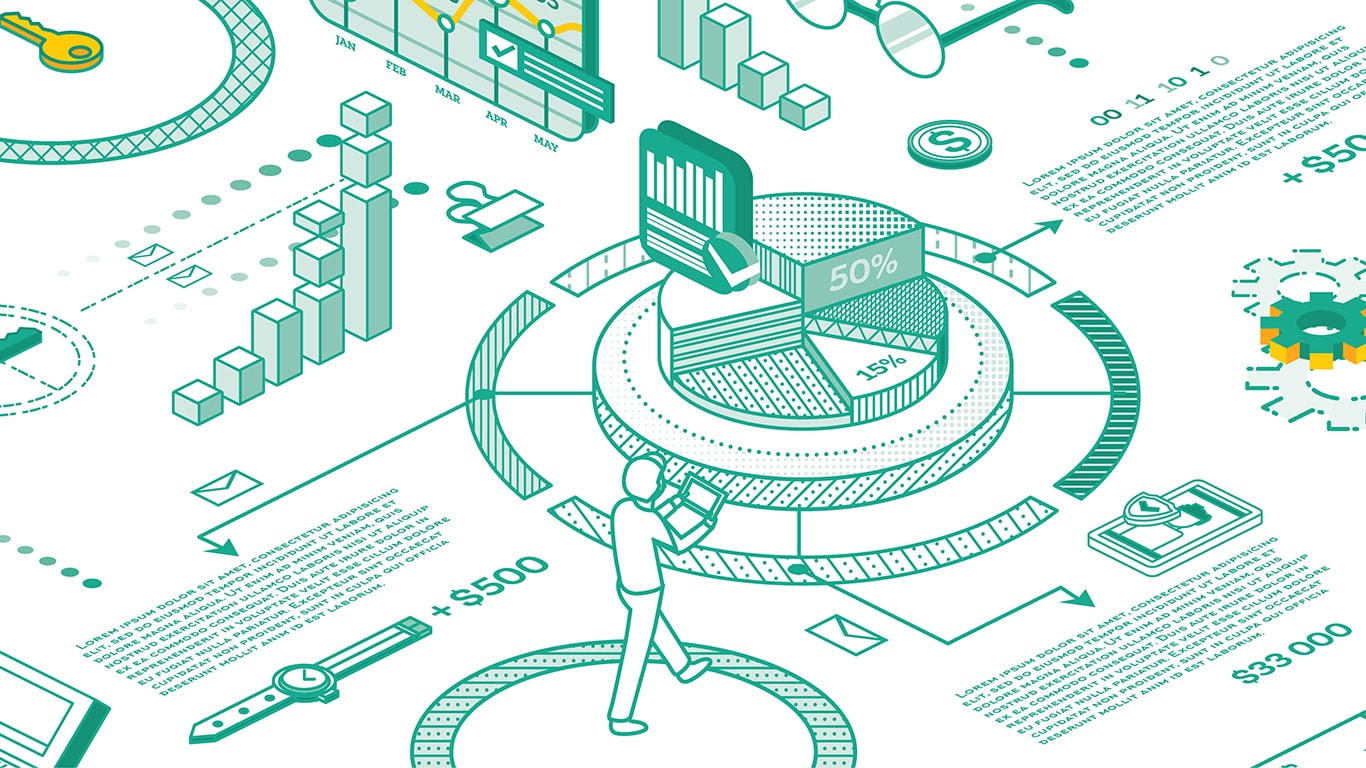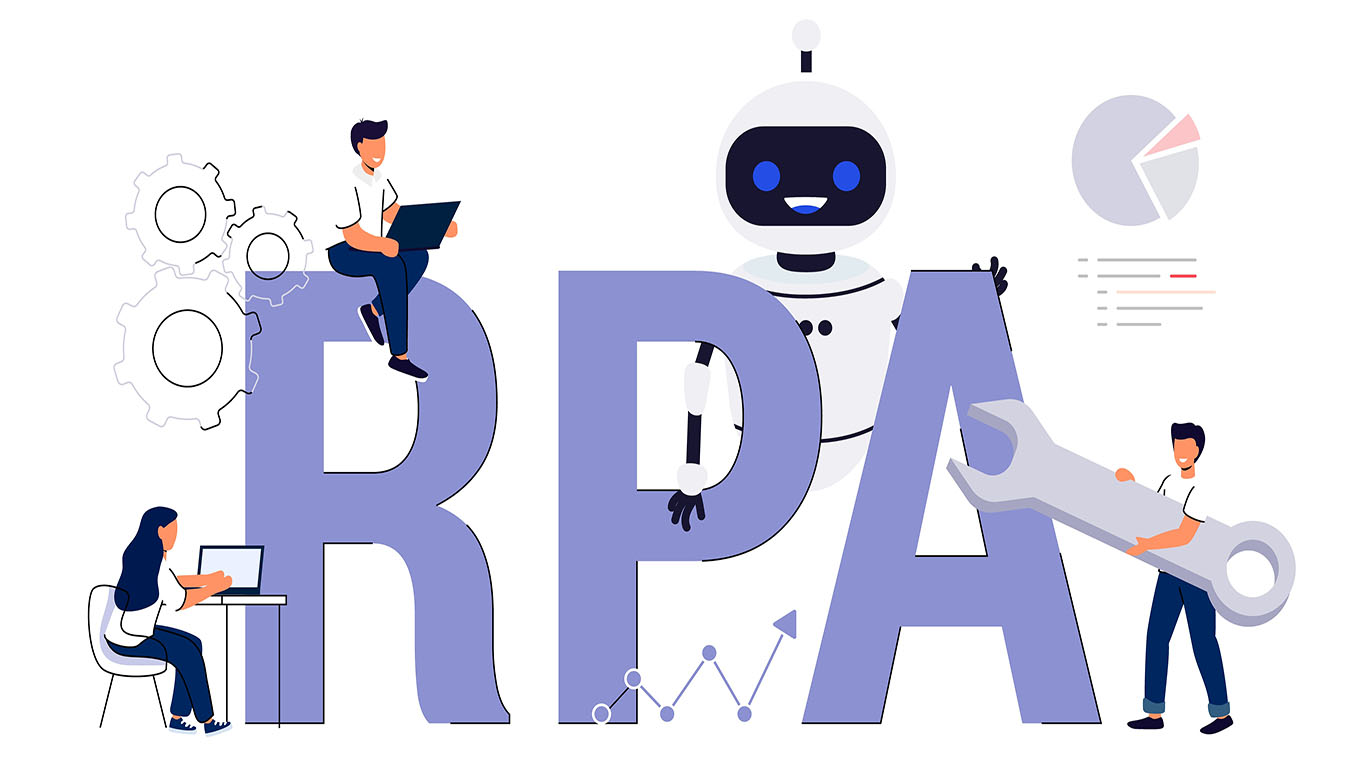コンフリクトとは?コンフリクトが起きる原因から解決方法まで徹底解説
最終更新日:2025.05.26

目次
私たちの生活や仕事の中で、意見の対立や価値観の違いによって生じる「コンフリクト(対立・衝突)」は避けて通れません。チーム内の意見の食い違い、職場の人間関係のトラブル、家庭内でのすれ違いなど、さまざまな場面で発生します。コンフリクトが放置されると社員のストレスや生産性の低下につながることもありますが、適切に対処すれば相互理解が深まり、より良い関係を築くきっかけにもなります。
本記事では、コンフリクトが起きる原因を明らかにし、効果的な解決方法を詳しく解説します。円滑なコミュニケーションと良好な関係を築くために、コンフリクトへの理解を深めていきましょう。
コンフリクトとは?
コンフリクト(Conflict)とは、英語で「衝突」「対立」「争い」を意味する言葉です。日常生活におけるものだけでなく、ビジネスシーンにおいても用いられ、異なる意見や価値観、利害がぶつかる場面を指します。例えば、チームのメンバー同士がプロジェクトの進め方について対立したり、企業間での契約条件が折り合わなかったりするケースが挙げられます。
しかしコンフリクトを避け続けようとすると、常に中庸的な判断を行い、チームメンバー全員に八方美人的に振る舞うことが求められてしまいます。
コンフリクト自体が悪いものなのではなく、むしろ、適切に対応することで新たなアイデアやイノベーションを生むきっかけとなることもあるのです。
チームの活性化や新しい視点の発見につながり、組織の成長を促す建設的なコンフリクトとなるか、感情的な対立や不信感を生み、チームのパフォーマンスを低下させる破壊的なコンフリクトとなるかは、チームのメンバーやマネージャーがそのコンフリクトにどう向き合うのかによって決まります。全てのコンフリクトを“トラブル”として扱い、処理的に対応したり、解決を先送りにしてしまうと、組織は変わらないままか、徐々に衰退、あるいは崩壊してしまうでしょう。
ここからは、コンフリクトの基本概念を整理しつつ、それをイノベーションや価値創造に変える方法について詳しく解説していきます。対立を恐れるばかりとなるのではなく、うまく活用することで組織の成長やチームワークの向上につなげましょう。
日本人はコンフリクトを避ける傾向にある
日本人は、コンフリクト(対立)が発生した際に、直接的な対決を避ける傾向が強いと言われています。これは、日本の文化が調和を重視し、空気を読むことを大切にする背景があるためです。
たとえば、会議で意見が分かれた際、対立を表面化させず、暗黙の了解や非言語的なコミュニケーションで解決しようとする場面がよく見られます。これは、農耕社会の発展とともに築かれた「和」を尊重する文化によるものと考えられます。
しかし、コンフリクトを避け続けることにはデメリットもあります。問題が表面化せず、長期的に蓄積されることで、後になって深刻な対立へと発展するケースも少なくありません。特に、グローバルな環境では、明確な意思表示が求められる場面が多く、日本式の「察する文化」が通用しないこともあります。そのため、適度にコンフリクトを受け入れ、建設的な議論を行う姿勢が求められます。
フッサールの現象学は、こうした人々の認識の違いに焦点を当てた学問です。彼は、人々が世界をどのように認識し、共通の理解を形成するかを探求しました。対話を通じて互いの認識をすり合わせることで、共通の理解を築くことが可能になります。これは、コンフリクトを乗り越え、より良い意思決定を行う上で重要な考え方と言えるでしょう。
コンフリクトが発生する原因
コンフリクトが生じる背景にはさまざまな要因がありますが、大きく分けると「条件の違い」「価値観や認知の違い」「感情の違い」の3つが主要な要因となります。これらの違いが積み重なることで、職場のコミュニケーションに摩擦が生じ、対立へと発展することがあります。それぞれの原因について、具体例を交えて詳しく見ていきましょう。
条件の違いによる対立
職場では、業務の分担やリソースの配分が公平でない場合に、条件面での対立が生じることがあります。例えば、特定のメンバーにばかり業務が集中し、他のメンバーは比較的余裕がある状態が続いたとします。この状況が続くと、負担の大きいメンバーは「なぜ自分ばかりが忙しいのか?」と不満を抱え、チームの雰囲気が悪化してしまいます。
また、昇進や評価の基準が明確でない場合も、不公平感が生まれやすくなります。例えば、成果を上げているにも関わらず、評価されるのは特定の人ばかりであると感じた社員が、上司や同僚に対して不満を持ち、組織のモチベーション低下につながることがあります。
価値観や認知の違いによる対立
人はそれぞれ異なる文化的背景や価値観を持っており、それがコミュニケーションのズレや誤解を生む原因になります。特に、多様なバックグラウンドを持つチームでは、仕事の進め方や優先順位の違いが対立を引き起こすことがあります。
たとえば、グローバルなチームでは、時間の使い方に対する価値観が異なることがあります。ある国のメンバーは「締め切りを厳守することが最も重要」と考えるのに対し、別の国のメンバーは「質の高い成果を出すためには、多少のスケジュール変更も許容されるべき」と考えている場合、両者の間で摩擦が生じます。
また、上司と部下の間でも価値観の違いが対立を生むことがあります。たとえば、上司が「とにかく結果を重視する」タイプで、部下が「プロセスを大切にしたい」と考えている場合、部下は「やり方を無視して結果ばかり求められるのは納得できない」と感じ、対立が生じる可能性があります。
感情の違いによる対立
感情的なコンフリクトは、職場のストレスやプレッシャーが原因で発生しやすいものです。なかでも、指導やフィードバックの伝え方によって相手が不満や怒りを感じることはよくあります。チーム内で長期間にわたって小さな不満が蓄積されると、ある日些細なことがきっかけで修復が困難な軋轢に発展することもあります。
たとえば、上司が部下に対して厳しい指摘をしたとします。上司としては「業務の質を向上させるための建設的な指摘」のつもりでも、部下にとっては「自分の能力を否定された」と受け取ることがあります。このような誤解が積み重なると、部下は上司に対して不信感を抱き、結果として関係が悪化してしまいます。
コンフリクトが与える影響
コンフリクトは、組織に良い影響を与えることもあれば、逆に組織のパフォーマンスを大きく低下させることもあります。その違いは、コンフリクトがどのように管理され、活用されるかによって決まります。ここでは、コンフリクトがもたらす良い影響と悪い影響について詳しく見ていきます。
悪い影響:組織を破壊するコンフリクト
コンフリクトが人間関係の対立に発展すると、チームの信頼が損なわれ、生産性が低下します。組織の士気が下がり、最終的には離職のスパイラルにつながるケースもあります。
たとえば、プロジェクトの進め方を巡ってメンバー同士が異なる意見を持っているとき、その対立が解消されないまま互いに納得していない仕事の進め方をした結果、重大な齟齬が遅れて発見され、納期の遅れに繋がります。このトラブルの責任を押し付け合いながら、社員同士の関係が悪化し、意見を出し合う場が減少すると、協力体制が崩れ、業務効率が著しく低下します。
チーム・会社は多様な問題を解決するために、様々な意思決定に柔軟性を持つべきですが、コンフリクトをきっかけに、「あの人は~だ」「このチーム(もしくは会社)は~だ」といった偏見が生まれます。そのため、議論に対してオープンな関係が崩れ「どうせ言っても無駄だ」という諦念と共に、決まりきった行動を繰り返すことになります。
このような破壊的なコンフリクトを放置すると、組織の成長どころか崩壊につながるため、適切なマネジメントが求められます。
良い影響:組織に成長をもたらす建設的なコンフリクト
コンフリクトが適切に管理されると、異なる意見が交わされ、新たなアイデアが生まれやすくなります。また、課題解決能力やチームの協力体制が強化され、組織全体の成長につながります。
たとえば、新商品の開発会議でメンバーの意見が対立したが、議論を重ねることで画期的なアイデアが生まれ、競争力のある商品が完成することがあります。同様に、営業戦略を巡る対立を通じて、それぞれの考えが整理され、最適なアプローチが導き出されることで、成約率が向上することがあります。
また、上司による部下の評価においてもコンフリクトが生まれることがあります。不公平感をチームのメンバーが感じていたとして、それを聞いてすぐに評価を翻すわけにはいきません。メンバーが評価されるべきと考えている強みや行動と、マネージャーが実際に評価している要素を洗い出しながら、チームや会社が求める成果との結びつきを議論することが重要です。このプロセスを通じて、評価の仕組み自体が変わらなくても、メンバーは自身の強みや行動をどのように評価し、成果につなげるかを見つけ、行動を変えることができます。一方で、マネージャーは評価に現れづらいメンバーの一面を改めて見出しながら、より明確な行動目標をメンバーに提示することができます。
そして、評価すべき項目がより適切に変更されれば、チーム全体の動きも変わっていきます。制度や仕組みは多かれ少なかれ、マネージャー側・経営側の熟慮の上で導き出されているものでもあり、固定的で、かつその決定の経緯は明かされないままブラックボックス化しやすいものです。
重要なのは、不平・不満のようなネガティブな形であったとしても実際にコンフリクトとして表出しなければ、こうした会話がなされることはないということです。
コンフリクトを促すマネジメントが必要な理由
ここまで触れてきたように、コンフリクトは決して避けるべきものではなく、むしろ適切に活用することで組織の発展に繋げることができます。チームのリーダーは、問題が水面下で悪影響を与え続けるくらいなら、いっそ意図的にコンフリクトとして表面化させ、それを適切に管理するという姿勢が求められます。
たとえば、世界最大級のヘッジファンド「ブリッジウォーター・アソシエイツ」の創業者であるレイ・ダリオは、組織内で徹底的に意見を言い合える環境を作るために、社員同士の意見の違いを数値化し、相互評価を行う仕組みを導入しました。このような環境を整えることで、組織内の議論が活性化し、建設的なコンフリクトが生まれやすくなります。
つまり、リーダーは以下のようなマネジメントを意識することが重要です。
- チームメンバーに対し、敢えて異なる視点を提示し、議論を促す
- 意見の対立が起こった際に、双方の立場をフォローし、相互対話を深める
- コンフリクトが感情的な対立に発展しないよう、ルールを設ける
- 最終的にはリーダーが責任を持って判断を下し、対立者側にその責を求めない
もちろん、非常に難易度の高いものです。リーダー自身が公平な態度を心がけながら、客観的な観点や判断基準を用意することで、コンフリクトの当事者が冷静な議論にいつでも立ち戻れるようになります。
ロジカルシンキングやディベートのような、問題に対して論理的に立ち向かう姿勢や作法がチームメンバーに根付いていることもコンフリクトマネジメントに大きく役立つことでしょう。
コンフリクトマネジメントのメリット
適切なコンフリクトマネジメントを実施することで、組織にはさまざまなメリットがもたらされます。
チーム全体のパフォーマンス向上
コンフリクトが建設的に解決されることで、チームの課題解決能力が向上し、成果が高まります。異なる意見が活発に交わされることで、さまざまな視点から問題を分析し、より効果的な解決策を導き出せるようになります。また、対話を通じて意思決定の精度が向上し、チーム全体の柔軟性や対応力も高まります。
さらに、適切な議論が行われることで、プロジェクトの成功率が上がり、チームの成長や組織の競争力強化につながります。リーダーがコンフリクトを前向きな議論へと導くことで、メンバーのモチベーションが向上し、チームワークが強化されるため、より良い成果を生み出すことが可能になります。
社内コミュニケーションの活性化
自由に意見を言える環境が整うことで、社内のコミュニケーションが活性化し、情報共有がスムーズになります。コンフリクトが発生した際に、対話を通じて相互理解を深めることができれば、単なる対立ではなく、建設的な議論が促されるようになります。その結果、社員同士の関係が良好になり、チームメンバー間の協力が生まれやすくなります。
また、組織全体として風通しが良くなり、業務の進行がスムーズになるだけでなく、社員が安心して意見を述べられる文化が根付くことで、組織の一体感も高まります。円滑なコミュニケーションは、組織の持続的な成長にとって欠かせない要素となります。
離職率の低下
コンフリクトを適切に管理することで、社員の不満が解消されやすくなり、結果として職場環境への満足度が向上します。職場での意見対立が放置されると、社員は自分の意見が尊重されていないと感じ、モチベーションが低下します。
しかし、建設的な対話の場が整備されることで、社員は自分の考えを積極的に表現できるようになり、不満の蓄積を防ぐことができます。特に、上司や同僚との関係性が良好であれば、社員は安心して働き続けることができ、離職率の低下につながります。職場環境が改善されることで、社員の定着率が上がり、組織の安定性も強化されます。
社員満足度とエンゲージメントの向上
建設的なコンフリクトが積極的に活用されることで、社員は自分の意見が尊重されていると実感し、組織への信頼を深めることができます。意見を自由に発信できる環境では、社員は自らの役割を明確に認識し、仕事への意欲が高まります。
また、上司や同僚と率直に意見を交わすことで、チーム内の結束力が強まり、社員のエンゲージメント向上にもつながります。企業文化として、オープンな対話を推奨することで、社員が積極的に組織の成長に貢献しようとする姿勢が生まれます。その結果、職場の活気が増し、組織全体の生産性も向上するという好循環が生まれます。
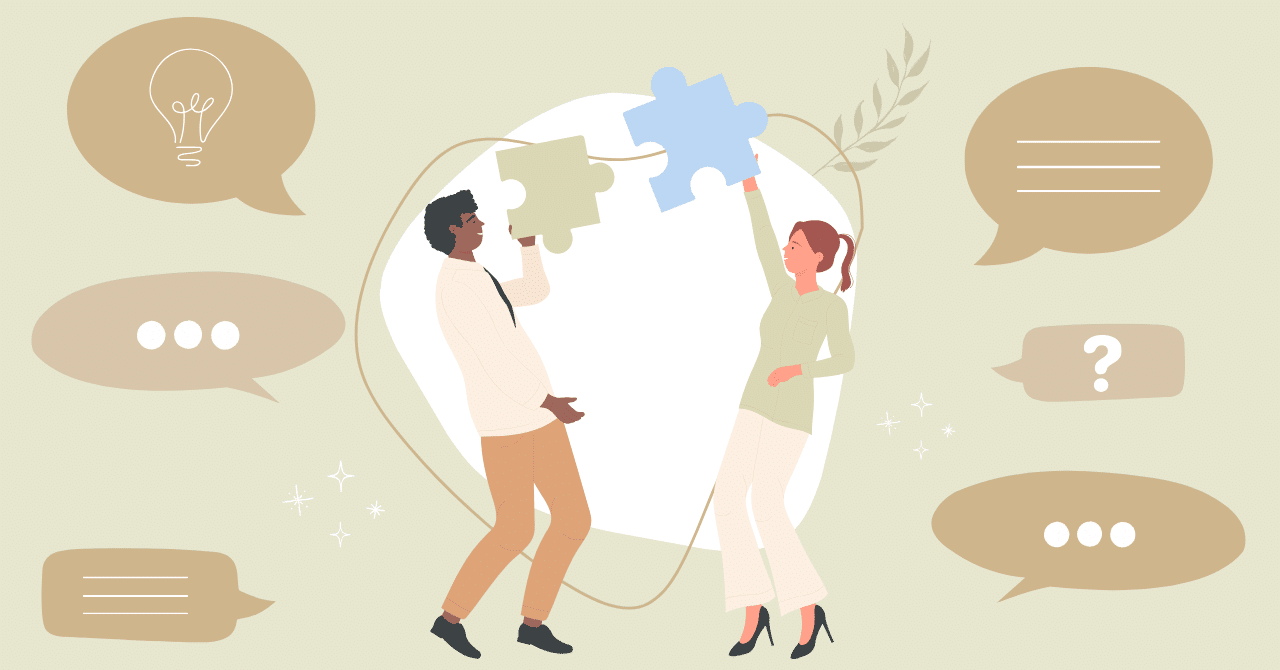
1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介
最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…
コンフリクトに対する5つの態度
コンフリクトが発生した際、人々はさまざまな方法で対応します。その態度は、大きく5つのタイプに分類され、それぞれメリットとデメリットがあります。どの方法を選択するかは、状況や目的に応じて変わります。ここでは、それぞれの態度について詳しく解説します。
回避
コンフリクトを避け、無視することで対立を回避する方法です。解決にかかるコストが高い場合や、問題が小さく深刻でない場合に有効です。例えば、些細な意見の食い違いを深掘りせずに流すことで、不要なエネルギーを消耗しないという利点があります。しかし、根本的な問題が未解決のまま放置されると、後々大きなトラブルに発展する可能性もあります。
また、日本文化では「和を重んじる」価値観が根付いており、明確な対立を避ける傾向があります。しかし、問題を長期間放置するとストレスが溜まりやすくなるため、適切なタイミングで向き合うことも重要です。自己認識を深めるために、仏教の「ラベリング」や「メタ認知」を活用し、感情と事実を切り分けることが有効なアプローチとなります。
強制
自分の意見を貫き、相手を説得しようとする方法です。短期間での意思決定や、緊急性が高い状況においては有効ですが、相手との関係が悪化するリスクを伴います。例えば、企業の意思決定で強力なリーダーシップが必要な場面では、断固とした決断が求められます。しかし、この方法を頻繁に用いると、チーム内の対話が減少し、メンバーが萎縮してしまう可能性もあります。
この態度は、ディベートのように「勝ち負け」を前提とした議論に適していますが、長期的な信頼関係を築くには向いていません。組織内でこの方法を用いる場合は、論理的な主張だけでなく、相手の立場を理解しながら進めることが重要になります。
服従
上位者の判断に従い、指示通りに行動する姿勢です。組織の効率を重視し、迅速な意思決定が求められる場面では有効ですが、個人の意見が抑えられるため、創造性の発揮が難しくなる可能性があります。例えば、軍隊や厳格なヒエラルキーのある企業では、リーダーの指示に従うことが重要視されます。
この方法は、チームの和を保つために有効ですが、長期的には組織の柔軟性を失うリスクがあります。トップダウンの意思決定が機能する場面では効果的ですが、従業員のモチベーション低下や主体性の喪失を招かないように注意が必要です。
妥協
双方が納得できる中間案を模索する方法です。対立を完全に解消するのではなく、お互いが少しずつ譲り合うことで合意を形成します。例えば、価格交渉で双方が歩み寄ることで、どちらも大きな損をせずに合意に至るケースが挙げられます。
この方法は、短期的な問題解決には適していますが、根本的な課題を解決できないこともあります。長期的な関係を築くためには、単なる妥協ではなく、双方にとって最善の選択肢を探る姿勢が求められます。
協調
対話を通じて互いの意見を尊重し、最適な解決策を見つける方法です。双方が納得できる結果を目指し、長期的な関係構築を重視します。例えば、企業のイノベーションプロジェクトでは、多様な視点を持つチームメンバーが協力しながら最適なアイデアを生み出します。
この方法は時間がかかるものの、関係性の強化や創造的な解決策を生み出すのに適しています。特にチームの信頼関係を築く場面では、協調の姿勢が重要になります。
コンフリクトを解決するための要点
様々な背景と経緯のあるコンフリクトを一挙に解決する万能の方法論はありませんが、「喧嘩して怒鳴り合って涙を流して仲直り」というわけにはいかない職場におけるコンフリクトにおいて、解決するために意識しておきたい3つのポイントを紹介します。
早期に対応する
問題が発生した際、放置せずにすぐに対応することで、不要なトラブルを防ぐことができます。時間が経つほど感情的な対立やレッテルとしての認知が深まり、解決が難しくなるため、早期のアクションが鍵となります。
これまでは、職場で同じ部屋の隣同士で働くチームであれば、顔色を見たり話している様子を見たりして、何かが起きていることに気付くことができました。しかしリモートワークが普及していたり、あるいは外勤の多いチームにあっては、その機会がほとんどありません。移動時間や雑談の時間を節減しながらタスクは何の問題もなく回っているとしても、敢えて時間をとってコミュニケーションを取ったほうがチームにとって重要であるかもしれません。
例ⓐ:
リモートワーク下、各自黙々とチャットを駆使しながら仕事をこなす中で、メンバーに怪訝な顔をされようとも、毎日「調子はどうか?」と聞いて回る上司。面倒くさそうに「大丈夫っすよ」と返すばかりだったAさんが、最近どうも口ごもっている。続いてAさんと直近同じプロジェクトに参加しているBさんの様子を伺うと、Bさんは仕事の量に圧倒され、余裕の無さそうな状態であることに気付いた。(例Ⓑへ続く)
原因を突き止める
表面的な対立だけでなく、その背景にある根本原因を探ることが重要です。単なる意見の違いではなく、リソースの不足や役割の不明確さが原因であることも多いため、冷静に分析し、適切な対応を行います。
例Ⓑ:
Aさんの状況を聞いてみると、Bさんに依頼した仕事が、おざなりな状態で返ってきたとのこと。仕事量が多いのは分かるが、それで雑な仕事をされても困ってしまい、かといって忙しい中で指摘するのも憚られる。とはいえ、これが初めてのことではない。「Bさんはそういう人だから」とAさんは諦め半分である。しかしその後、Bさんに対して同様の不満を抱えているメンバーが他にもいることが判明。
Aさんをはじめチームにとって「Bさんにしか出来ない仕事」の必要性が高いのであれば、Bさんにそれ以外の仕事が偏ってしまっているのは機会損失なのでは?(例Ⓒへ続く)
ポジティブな雰囲気をつくる
対話が円滑に進むためには、心理的安全性を確保し、建設的な議論ができる環境を整えることが重要です。相手の意見を尊重し、否定せずに聞く姿勢を持つことで、前向きな解決へと導くことができます。
例Ⓒ:
「みんながBさんに不満を持っている」という状況からコンフリクトが発生しかけているのだが、実際にはBさんの高い専門性への信頼と依存から生まれている状況であった。この不満をBさんに不満としてぶつけるのではなく、チーム全体のタスクを整理しながら、より良い連携の方法があることを、Aさんにも協力してもらいまとめることにした。
その結果「自分の依頼をBさんが丁寧にやってくれるのであれば、喜んでBさんの他の仕事を代わる」というメンバーが多いことが分かった。
昔に比べ中途採用者も増え、多様なメンバーと仕事をし、“阿吽の呼吸”が通じづらくなった職場では、こういったコンフリクトを表面化し、昇華するという営みのためにも、意図的にコミュニケーション機会を増やすことが重要です。
コンフリクトがイノベーションに代わる瞬間
コンフリクトは対立を生むだけでなく、適切に管理すればイノベーションの源泉となります。その鍵を握るのが、アダム・グラントの『GIVE&TAKE』で提唱される「ギバー(与える人)」の存在です。
コンフリクトの本質は異なる視点のぶつかり合いであり、これを「より良いものを生み出す機会」として捉えれば、新たな価値の創造につながります。
特に、他者志向的なギバーは、対立を建設的な議論へと導き、最適な解決策を見出す力を持っています。例えば、新商品の開発で技術者とマーケティング担当者が対立する場合、双方の視点を融合することで競争力のある商品が生まれます。
アダム・グラントは、人を「ギバー」「テイカー」「マッチャー」に分類しました。自己犠牲的なギバーや自己中心的なテイカーは対立を悪化させますが、他者志向的なギバーは対立を調整し、Win-Winの解決策を生み出します。
コンフリクトをイノベーションに変えるには、対立をチャンスと捉える、相手の意見を尊重する、多様な視点を受け入れる、長期的な視点を持つことが重要です。短期的な勝敗ではなく、より良い成果を目指すことで、組織の成長とイノベーションが促進されます。
まとめ
コンフリクトは組織やチームにとって避けがたいものですが、適切に対処すれば成長やイノベーションの機会となります。対立が発生する原因は、条件の違い、価値観の違い、感情の衝突など多岐にわたりますが、放置せず早期に対応し、根本原因を突き止めることが重要です。また、心理的安全性を確保し、建設的な議論ができる環境を整えることで、コンフリクトは新しい価値を生む力へと変わります。
さらに、対立を乗り越え、より良い成果を生み出すには、互いの意見を尊重し、Win-Winの解決策を模索する姿勢が不可欠です。コンフリクトを「避けるべき問題」と捉えるのではなく、「発展のチャンス」と考え、適切に活用することが、組織の成功と継続的な成長につながるでしょう。