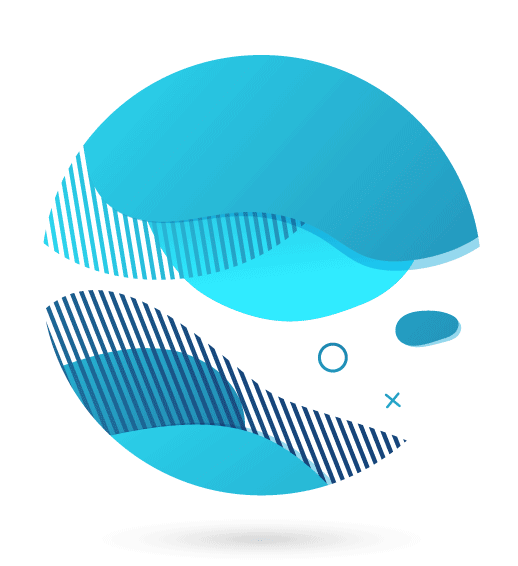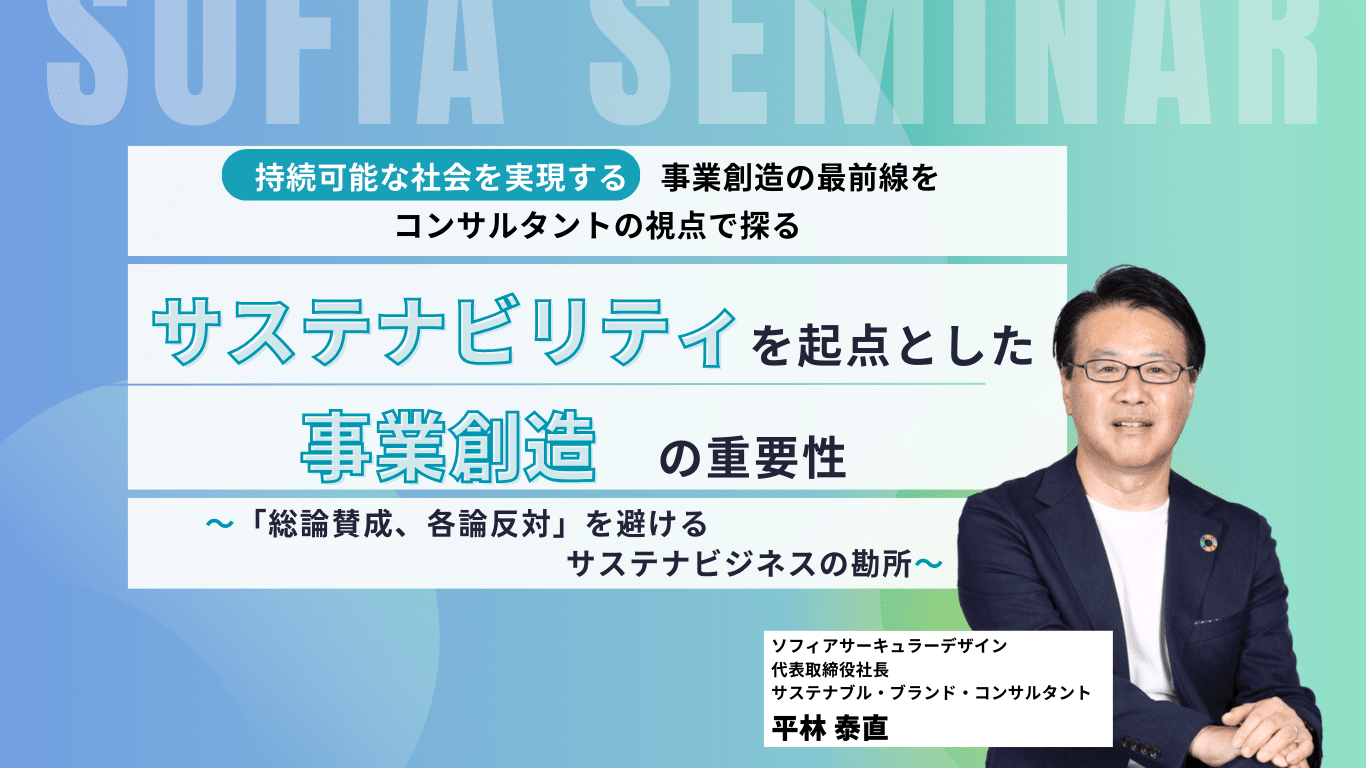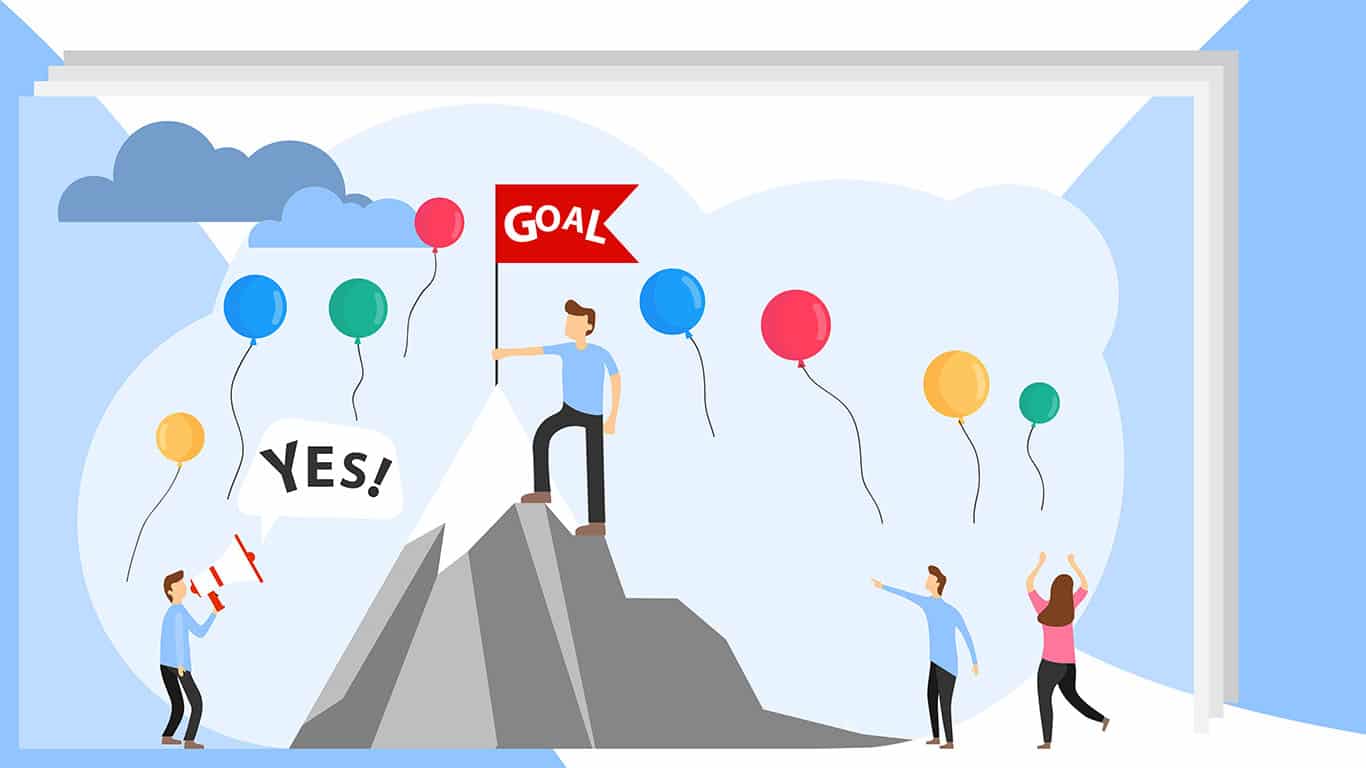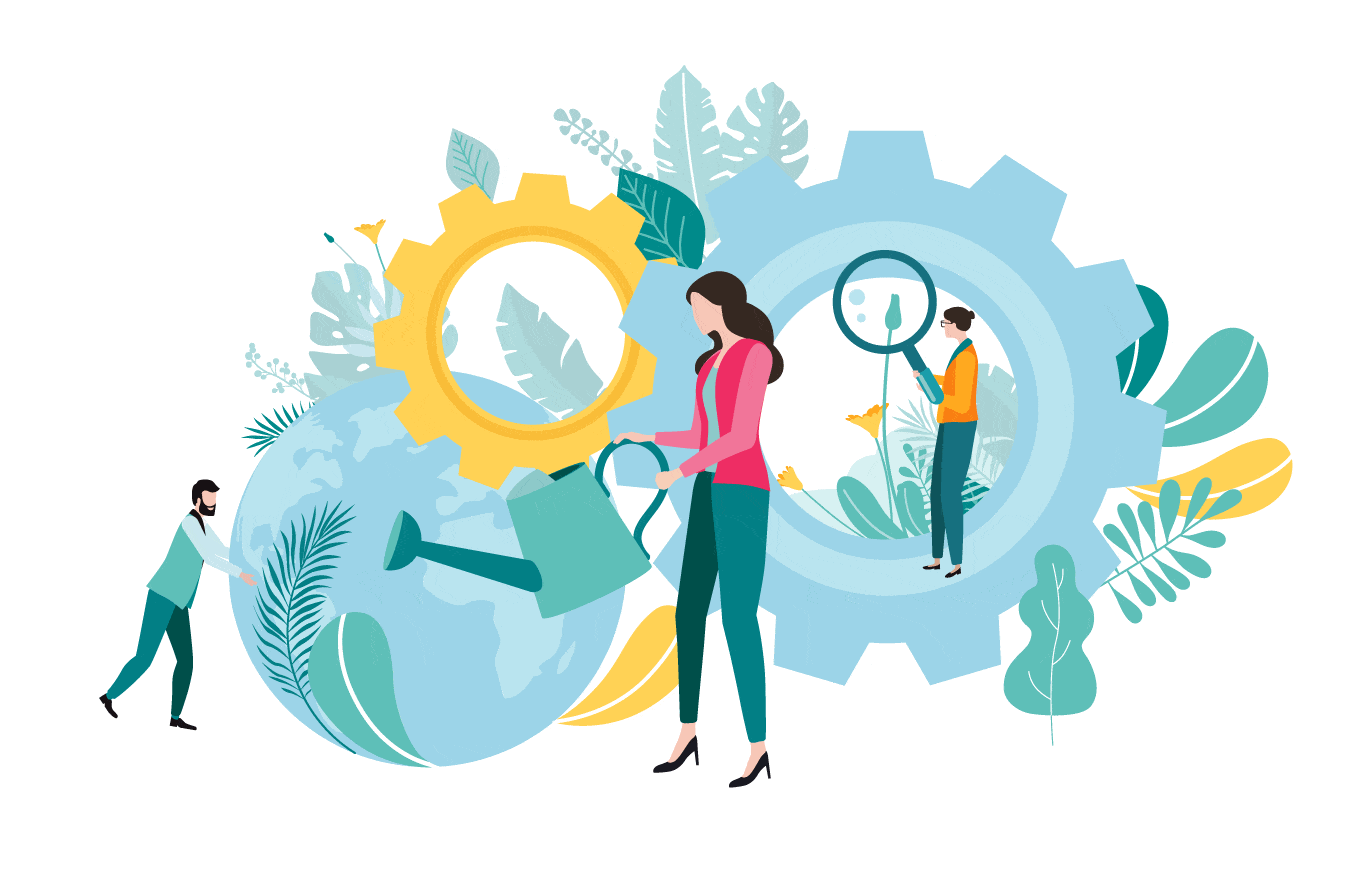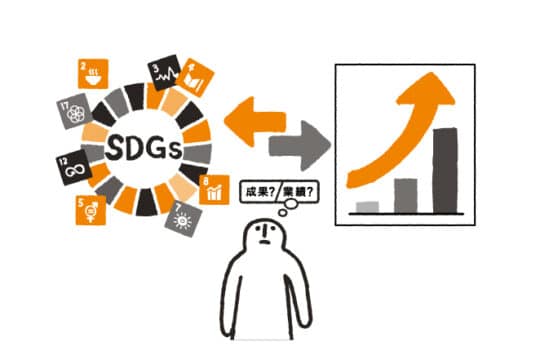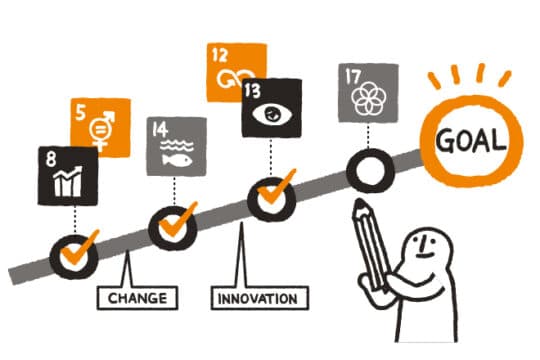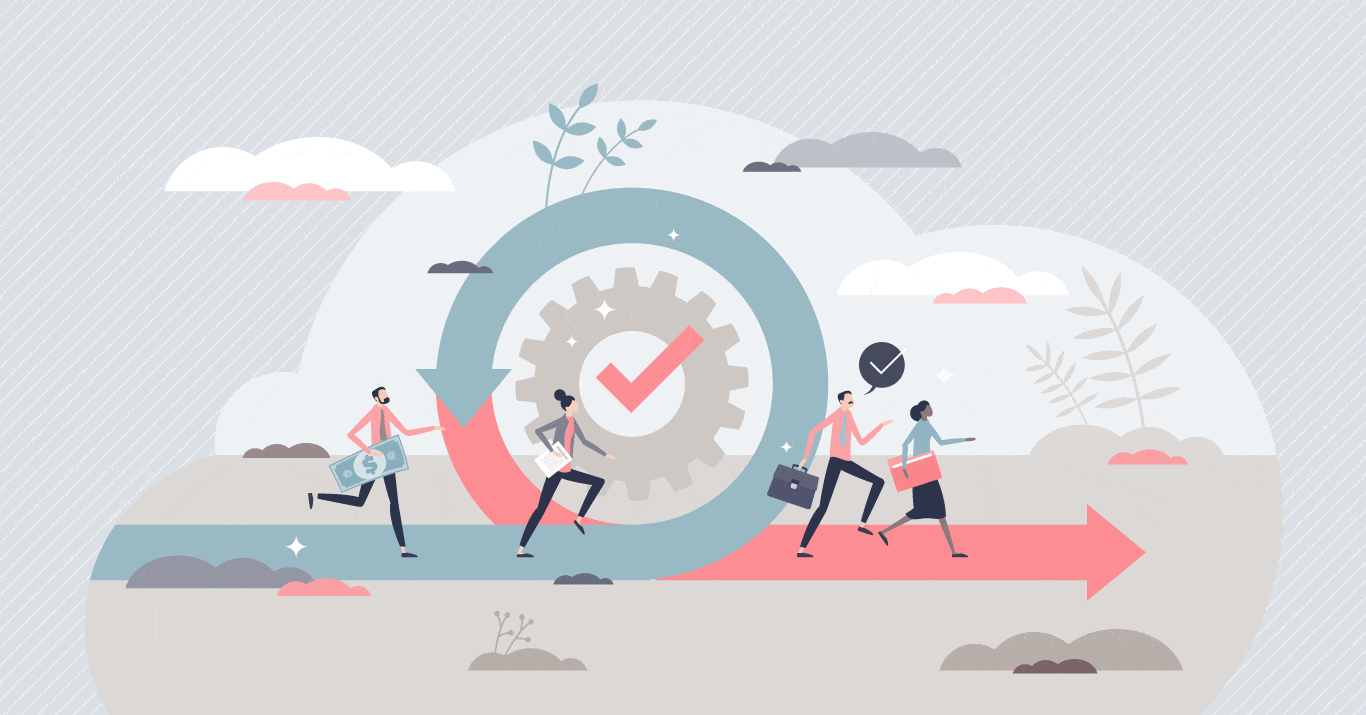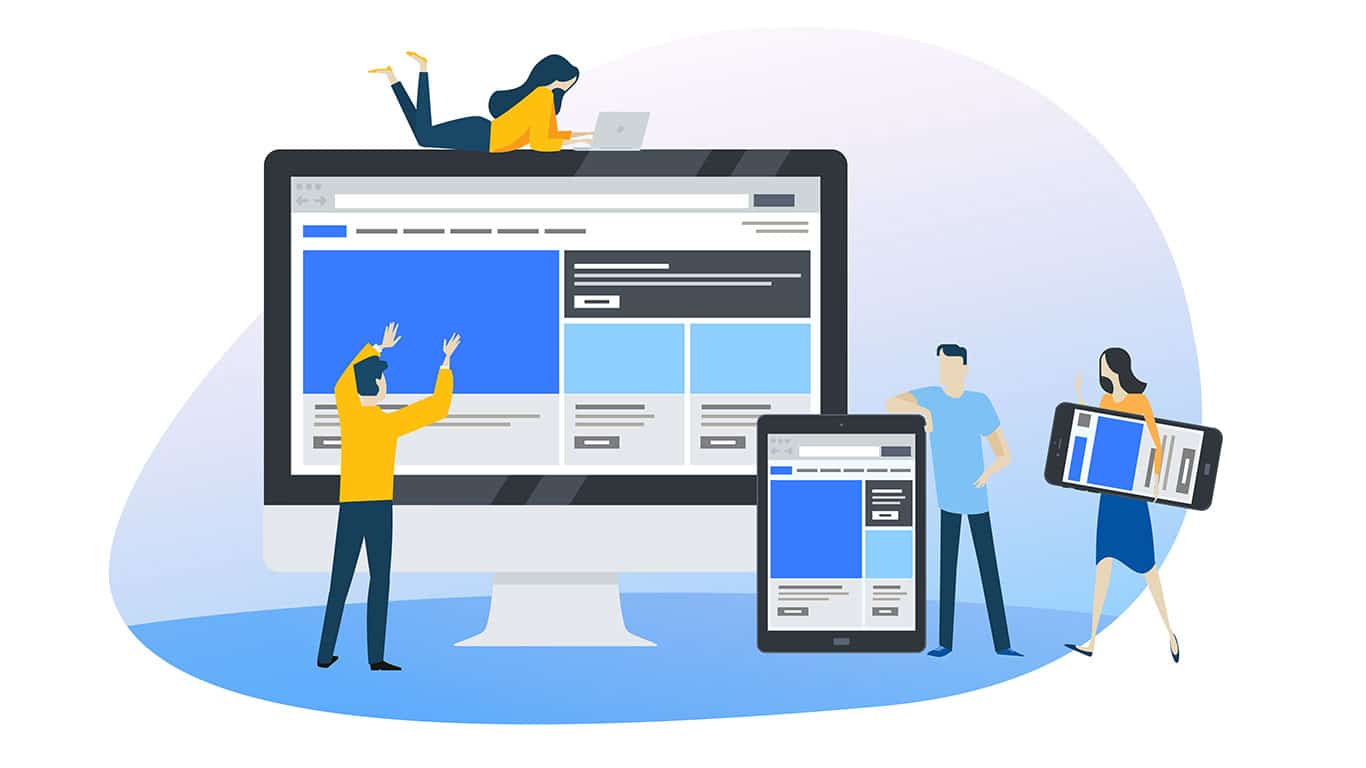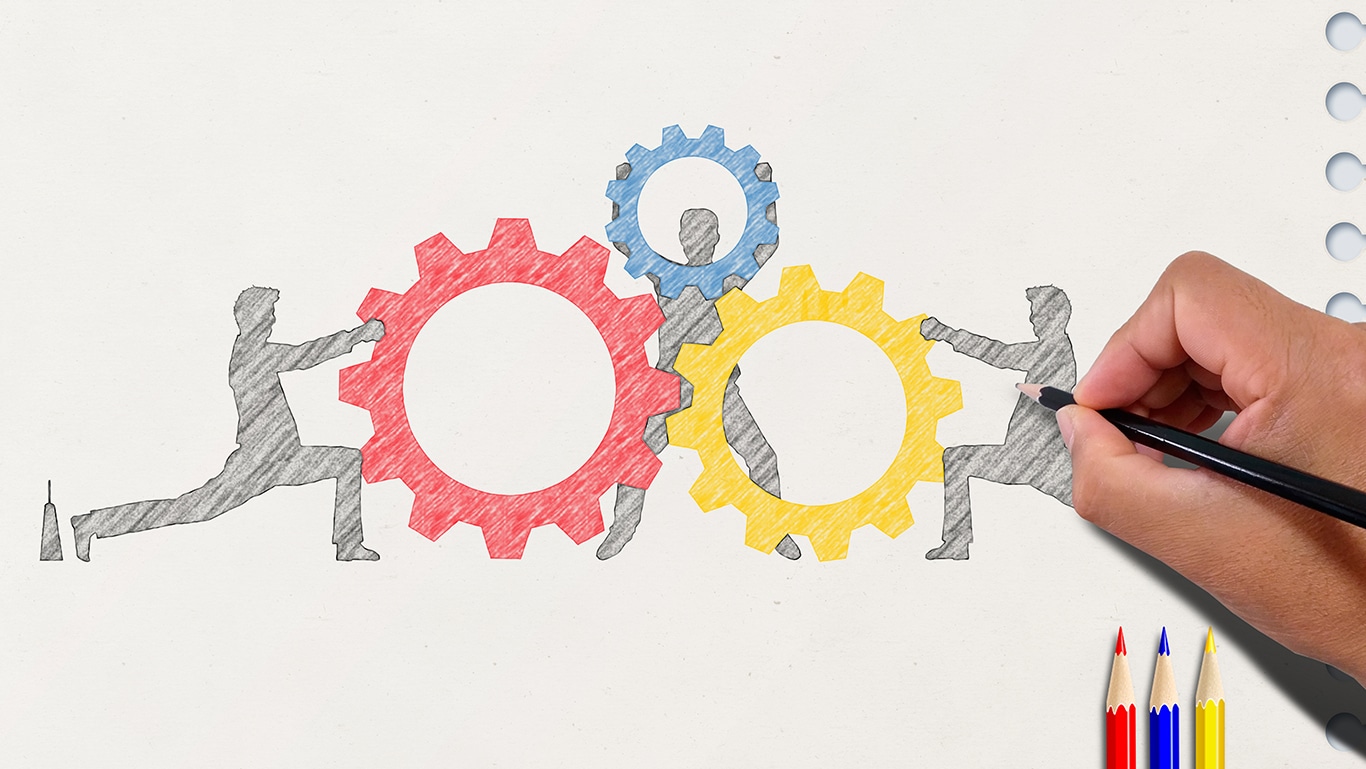【2025年最新】SDGsに取り組むメリットとは?企業価値を高める経営戦略と成功事例を徹底解説
最終更新日:2026.02.17

目次
2015年9月、ニューヨークの国連本部で「国連持続可能な開発サミット」が開催されました。このサミットを経て、2030年までに達成すべき国際社会共通の17の目標として掲げられたのがSDGs(=Sustainable Development Goals)です。
SDGsへの意識が世界的に高まる中で、日本においてもSDGsに取り組むことが企業のメリットとして捉えられるようになってきました。
しかし、2020年代半ばを迎えた現在、SDGsへの取り組みは「推奨事項」から「必須事項」へとフェーズが移行しています。欧州におけるサプライチェーン・デューディリジェンス指令(CSDDD)の発効や、人的資本情報の開示義務化など、企業を取り巻くルールは急速に厳格化しているのです。もはやSDGsは「取り組むと良いこと」ではなく、「取り組まなければ市場から退場を余儀なくされるリスク」となりつつあります。本記事では、従来のCSR(企業の社会的責任)的な文脈を超え、経営戦略としてのSDGsのメリットを「攻め」と「守り」の両面から徹底的に分析していきます。
SDGsに取り組む目的
SDGsは現在、世界各国で注目されています。では、なぜ各国はSDGsの取り組みを進めているのでしょうか。まずはSDGsに取り組む目的を見ていきましょう。
SDGsの取り組みが始まったきっかけ
SDGs(持続可能な開発目標、Sustainable Development Goals)は2015年の国連サミットで採択された目標で、「持続可能性」が重要なテーマとなっています。それまで、世界では経済成長に重きが置かれていて、20世紀には各国が大幅な経済発展を遂げることに成功しました。しかしその裏では、自然環境の破壊や格差の拡大など、多くのひずみもあったのです。
そうした世の中の負の状態を正すため、将来の世代から搾取することなく現在の世代のニーズを満たす「持続可能な開発」という考え方のもと、国際社会が一丸となって取り組みを進めることになりました。このような背景からSDGsが採択され、世界各国でさまざまなステークホルダーがSDGsを推進するようになったというわけです。
SDGsで達成すべき17の目標
SDGsは、17の目標と169のターゲットで構成されています。多様な観点から世界の優先課題を取り上げていますが、ここでは「社会活動」「経済活動」「地球環境」という分類で掘り下げてみましょう。
これらはしばしば「SDGsのウェディングケーキモデル」として説明され、環境(生物圏)が土台にあり、その上に社会、そして経済が成り立つという構造を示唆しています。
社会活動
「社会活動」とは、飢餓をなくすことや健康、教育など、人が社会活動を営む上でもっとも基本的な事柄です。「目標1:貧困をなくそう」「目標3:すべての人に健康と福祉を」などがここに分類でき、発展途上国で顕著な課題も多いものの、「目標5:ジェンダー平等を実現しよう」などは日本を含めた先進国でもさらなる取り組みが必要だと言えるでしょう。
経済活動
「経済活動」には、たとえば「目標8:働きがいも経済成長も」「目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう」などが含まれます。現在の地球だけでなく将来の世代に対しても責任のある経済成長に向けた行動が求められており、企業が率先して取り組むべき課題も多くあります。
地球環境
「地球環境」は、気候変動や生物多様性などグローバルな課題に対処するものです。「目標13:気候変動に具体的な対策を」「目標14:海の豊かさを守ろう」などが当てはまり、近年はとりわけ関心の高い課題となっています。
実際には17の目標それぞれにさまざまな要素が絡み合っているため、分類の方法は1つではありませんが、このように大まかに色分けをしてみることで、SDGsが対処しようとしている地球の課題が理解しやすくなるのではないでしょうか。
日本企業のSDGsへの取り組み状況
SDGsに取り組む企業が増えている
日本でもSDGsに対する企業の理解が進み、SDGsの推進に取り組む企業は年々増加しています。
企業の意識変容と現在の到達点
2021年に帝国データバンクが行った、「SDGsに関する企業の意識調査」では、前年の調査より15.3ポイント多い39.7%の企業が、SDGsに対する取り組みに積極的な姿勢を示しました。実際の取り組みも年々活発になってきており、コーポレートサイトの中で自社のSDGsへの取り組みを紹介する企業も多くみられるようになっています。
さらに最新の動向を見ると、この傾向は加速しています。2024年の同調査(帝国データバンク)によれば、「SDGsに積極的」と回答した企業は54.5%に達し、調査開始以来最高を記録しました。特に大企業においては、その割合は高く、サプライチェーン全体への影響力を持つプレイヤーとして、自社だけでなく取引先を含めた対応が求められるフェーズに入っています。
しかしながら、関心はあるもののSDGsへの取り組みに着手していない企業が多いことも事実です。前述の帝国データバンクの調査では、半数を超える50.5%の企業が、SDGsという言葉は知りつつも、具体的に取り組んでいないと回答しました。また、SDGsに積極的な企業は「大企業」では55.1%、「中小企業」では36.6%で、SDGsに対する意識には企業規模で差があることが分かっています。
企業がSDGsに取り組むメリットにはどのようなものがありますか?
ここでは、企業がSDGsに取り組むメリットと取り組む際の留意点をご紹介します。
SDGsに取り組むメリット
SDGsへの取り組みは企業に課せられた義務ではありません。貧困や環境問題に取り組むことは企業にとって一見コストがかかることでもあり、負担に感じる企業も多いのではないでしょうか。
では、なぜSDGsに取り組む企業は年々増加するのでしょうか。企業がSDGsに取り組むメリットをいくつかご紹介します。
1. ビジネスチャンスにつながる
SDGsは貧困や飢餓をなくすことや、教育機会の拡充、持続可能なエネルギー確保、気候変動への対策など17の目標からなり、これらの目標は世界が直面している解決すべき課題でもあります。ということは、この課題を解決するための取り組みは新しいビジネスのチャンスとなります。
2017年のダボス会議では、SDGs達成に向けた取り組みによって、2030年までに年間少なくとも12兆ドル(約1,300兆円)の新たな市場機会が生まれると推計されました。これは既存の市場を奪い合う「レッドオーシャン」ではなく、社会課題解決という未開拓の「ブルーオーシャン」への進出を意味します。
SDGsの17目標を起点にして、問題解決のための新規事業の創造や、他業種との協働など、さまざまな働きかけができるはずです。売上という目標ではなく社会課題の解決を中心に考えることで、これまでにないイノベーションやビジネス開発の可能性が広がるのです。
バックキャスティング思考: 「現在の延長線上」ではなく「あるべき未来(2030年のゴール)」から逆算して現在の事業を構想することで、破壊的イノベーションが生まれやすくなります。
パートナーシップの拡大: 1社では解決できない課題に対して、異業種、自治体、NGO/NPOとの連携(目標17)が進み、新たなエコシステムが形成されます。
「未来志向」のSDGsに取り組むことで、より一層自社の戦略に磨きをかけていきましょう。
2. ステークホルダーとの関係性向上
SDGsに取り組む企業は世界が直面する課題解決に取り組む企業です。SDGsは世界共通の目標であり、企業がSDGsに取り組むということは、CSR活動として非常に重要な意義をもちます。
企業がCSRを果たすことで、ステークホルダーとの関係性も向上していきます。逆に、SDGsに取り組まない企業は、世界で取り組む課題に無関心という表明になりかねず、将来的にサプライチェーンから外されたり、株主や地域の支援を得ることができなくなったりする可能性も少なくありません。
特にBtoBビジネスを展開する大企業にとって、サプライチェーン管理は喫緊の課題です。欧州の「企業持続可能性デューディリジェンス指令(CSDDD)」など、人権や環境への配慮を義務付ける法規制がグローバルで強化されています。取引先選定において「サステナビリティへの対応」が品質や価格と並ぶ、あるいはそれ以上の決定要因となりつつあります。SDGsへの取り組みは、将来的な取引停止リスクを回避し、事業継続性(BCP)を確保するための「ライセンス」としての側面も持ち合わせています。
3. 企業のブランディングに効果的(優秀な人材の採用にも有利に)
SDGsの掲げる目標には、貧困をなくすこと、飢餓をなくすこと、ジェンダー平等や気候変動に対する取り組みなどさまざまなものがあります。いずれの目標も世界全体で取り組むものであるため、SDGsに取り組む企業は社会に対して責任を果たす企業として認識され、企業イメージの向上やブランディングにも非常に効果的であると言えるでしょう。
採用市場において、特に「Z世代」やミレニアル世代の求職者は、給与や福利厚生だけでなく「企業の社会的意義(パーパス)」を重視して就職先を選ぶ傾向が顕著です。
また、こういった先進的な取り組みを行い、高い企業イメージ、高いブランドイメージをもつ企業には、先進的な思考をもった優秀な人材が集まります。SDGsに積極的に取り組む企業は、人材の採用においても有利になります。
採用コストの削減: ブランドイメージの向上は、母集団形成を容易にし、採用マッチングの精度を高めるため、結果として採用単価(CPA)の低減に寄与します。
リテンション(定着)効果: 自社が社会に貢献しているという実感は、既存社員のエンゲージメントを高め、離職率の低下につながります。
4. ESG投資が重視される中、資金調達が有利になる
近年ESGを考慮した投資(※)が投資家に重視され、拡大しています。
SDGsの17の開発目標には、貧困や飢餓をなくすことだけでなく、気候変動への対策や海の豊かさ、陸の豊かさを守ることなど、環境問題への対策も多く含まれています。SDGsに取り組むことは環境や社会、あるいはその両方に貢献することとなります。
企業が環境や社会に配慮し、CSRを果たすことは資金調達の観点からも非常に有利となります。
※従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素も考慮した投資
機関投資家は、気候変動リスクや人権リスクを「財務リスク」として評価するようになっています。非財務情報の開示が充実している企業は、長期的なボラティリティ(変動性)が低いとみなされ、資本コストの低減につながります。また、グリーンボンド(環境債)やサステナビリティ・リンク・ローンなど、SDGs達成を条件とした有利な資金調達手段も多様化しています。
5. コスト削減と業務効率化(DXの推進)
SDGsの視点は直接的なコスト削減にも寄与します。
省エネルギー: エネルギー効率の高い設備への更新は、CO2削減(目標13)に貢献すると同時に、光熱費の削減をもたらします。
ペーパーレス化とDX: 森林資源の保護(目標15)の観点からペーパーレス化を推進することは、紙代や印刷代、保管コストの削減だけでなく、ワークフローシステム等の導入による業務プロセスのデジタル化(DX)を加速させます。これにより、リモートワークなどの柔軟な働き方(目標8)が可能となり、生産性の向上に直結します。
企業がSDGsに取り組む際の留意点
SDGsに興味をもち、これから取り組んでいこうとする企業も多くあると思います。取り組むにあたっては注意が必要なポイントがあります。ここでは、SDGsに取り組む際の留意点をご紹介します。
経営理念との統合が必要
SDGsに取り組むことは、ビジネスチャンスやブランディング、CSR活動などさまざまな意義があります。しかし、この取り組みに企業の経営理念との乖離があれば、そのひずみはやがて大きくなっていくことでしょう。SDGsの導入にあたっては、まず「SDGsコンパス(SDG Compass)」に沿って、経営理念・指針との統合を行い戦略の方向を決定する必要があります。
SDGsは「後付けのラベル」ではなく、経営の中核に据えるべき羅針盤です。自社のミッション(使命)やビジョン(将来像)とSDGsのゴールを照らし合わせ、一貫性のあるストーリーを構築することが重要です。
社会的価値と経済的価値の両立を目指す
SDGsに取り組むことは、社会的価値と経済的価値の両立を目指すことです。これまで、この二つの価値は相反するものであり、「トレードオフ」の関係にあるとされてきました。トレードオフとは、経済活動(経済的価値)と引き換えに、新たな社会課題が生まれてしまう状況をさします。
たとえば企業が経済的価値を上げるために雇用を減らしたり給与をカットしたりすれば、失業や貧困といった新たな社会課題につながります。一方で、企業がSDGsに積極的に取り組んでも、それが大幅なコスト増につながって経営が成り立たなくなれば元も子もありません。
SDGsへの取り組みは直接的・間接的に経済的価値と社会的価値の両立「トレードオン」であることが大切であり、それを実現するためには自社のみではなくさまざまなステークホルダーとの連携・協業や、発想の転換、イノベーション創出が必要となってくるのです。
SDGsウォッシュを防ぐ
SDGsウォッシュ(SDGsウォッシング)とは、SDGsへの取り組みを掲げながらその実態が伴っていない、実際と異なることを揶揄する言葉です。
たとえば、環境に配慮した農業経営を謳いながら、その農地では幼い子どもたちが低賃金で働かされているような場合です。
ひとたびSDGsウォッシュを行った企業として社会に認識されると、企業のイメージや価値がマイナスに転じてしまいます。SDGsに取り組んでいるようにみえて、実態が伴っていないビジネスとならないよう、企業はしっかりと取り組みの実態を把握する必要があります。
近年はSNSでの拡散力が強いため、一度の不誠実な対応が致命的なブランド毀損を招くリスクが高まっています。これを防ぐためには、サプライチェーン全体の透明性を確保することと、次項で詳述する「社内への浸透」が不可欠です。
【重要】SDGs推進の鍵となる「社内浸透」と従業員エンゲージメント
社内の問題
経営活動そのものであるSDGsは経営層や一部の部署だけで取り組むものではなく、社内全体で進めていかなければいけないものです。そのため、前述の「SDGコンパス(SDGs Compass)」も活用しながらSDGsの活動方針を策定したら、次のステップとしては社内に向けた情報発信に力を入れる必要があります。現場で働く従業員のレベルにまで活動を落とし込むことで、全社的な取り組みにしていきましょう。
多くの大企業において、SDGs推進室や経営企画部が立派な統合報告書を作成しているにもかかわらず、現場の社員にはその熱量が伝わっていないという「温度差」が課題となっています。この温度差こそが、SDGsウォッシュを引き起こす最大の内部要因です。
経営戦略への「共感」はわずか1割という現実
弊社ソフィアが実施した「インターナルコミュニケーション実態調査2024」(対象:従業員数1,000人以上の企業勤務者496名)において、衝撃的な実態が明らかになりました。
弊社ソフィアの調査では、デジタルツールの導入は進んでいるものの、それが必ずしも経営理念やSDGs戦略の浸透にはつながっていないことが示唆されています。情報が物理的に届いていても、心理的に届いていない(共感されていない)状態では、社員の行動変容は起きません。
従業員エンゲージメントを高めるコミュニケーション
そのためには、社内での共感を高めるためのコミュニケーションを進めていきます。投資家などに向けたSDGsの発信を強化する企業は増えていますが、社内への情報発信がおろそかになっている事例は少なくありません。SDGsをきっかけとして社内にイノベーションをもたらすためにも、社内向けのコミュニケーションに留意しましょう。
SDGsを「自分事」化するためには、以下のようなインターナルコミュニケーションの施策が有効です。
対話(Dialogue)の場の創出: 一方的な通達ではなく、SDGsについて社員同士、あるいは経営層と社員が語り合うタウンホールミーティングやワークショップを開催する。
ストーリーテリング: 数値目標だけでなく、SDGsに取り組むことで誰がどのように幸せになるのか、具体的なストーリーとして発信する。
称賛の文化: SDGsに貢献する小さな行動を称賛し、共有する仕組み(アワードや社内報でのピックアップ)を作る。
社員が「自分の仕事が社会課題の解決につながっている」と実感することは、働きがい(従業員エンゲージメント)を大きく向上させ、結果として組織の生産性や創造性を高めることにつながります。これが、人的資本経営の観点からもSDGsに取り組むべき大きな内部的メリットです。
日本企業のSDGsへの取り組み事例
2021年時点のSDGsに対する日本企業の取り組み状況をみていきましょう。
「週刊東洋経済」2021年7月3日号では、日本企業を対象にした独自のSDGs企業ランキングが特集されています。
同ランキングで1位を飾ったのは、オムロンでした。オムロンでは、そのトップである立石会長自らが、ESG・サステナビリティ分野の責任者を務めています。またオムロンは、SDGsに対する取り組みを、中期経営計画に反映させました。立石会長は、もともと会社の掲げる理念とサステナビリティとが関連しており、サステナビリティを理解しやすいと語っています。SDGsの達成に向け、経営理念にSDGsを統合し、社内体制の構築に励んでいると言えるでしょう。
また同社は、同社が排出する温室効果ガスを、2050年度に事実上ゼロにすることを宣言しています。実際に2020年度には、同社が設定したCO2削減目標を大幅に上回る成果を達成しました。また2021年からは、企業のサステナビリティに対する取り組みの指標である、非財務情報の開示を進めていくとのことです。目標や理念ばかりでなく、実態の伴う取り組みが行われているように見えます。
なお、このように総合的に高い評価を受ける企業がある一方で、日本企業のSDGsへの取り組みは特定の領域において課題がある、ということも同誌では指摘されています。同誌に掲載されている企業の女性部長比率ランキングでは、ランキング1位となった化粧品メーカー、シーボンをはじめとして、もともと女性従業員の多い企業がランクインする傾向にありました。SDGsランキングで上位に入った企業であっても、女性部長比率ランキングでは必ずしも評価が高いとは言えず、いまだ多くの企業にとって女性活躍が課題であることが分かります。
SDGsに取り組む日本企業の事例
では、SDGsに取り組む日本企業の事例をいくつかご紹介します。17あるSDGsのどの目標に対してどのように取り組んでいるかを解説します。
三陽商会「エシカルブランドで、リブランディング」
三陽商会は、SDGsの目標12:「つくる責任、つかう責任」を念頭に、「地球を、愛する。」「服を、愛する。」の2つのカテゴリーに活動を分け、さまざまな取り組みを推進しています。
取り組みの事例としては、ビニール製ショッピングバッグを廃止したり、リアルファーの使用を禁止しているほか、サプライチェーンの現場が働く環境において公正であるかどうかに注視し、人権や環境に配慮した服づくりを行っています。サステナブルアクションプランの総称を「EARTH TO WEAR」と名付け、取り組みの姿勢を社内外へ示し続けながら、取り組み推進を強化していくことを目指しています。
花王「消費者の利便性を守りながら、プラスチック使用量削減」
花王は、プラスチック使用量削減を目指し、SDGsの目標14:「海の豊かさを守ろう」に取り組んでいます。
プラスチックによる海洋汚染は深刻で、特に近年はプラスチックが砕かれて微細化したマイクロプラスチックが海洋生物に与える影響が大きな問題になっています。
プラスチック使用量削減を目指しながら、消費者にとって使いやすいつめかえ・つけかえ容器を開発し、日本国内で発売しているトイレタリー製品におけるプラスチック使用量を約75%削減しました。今後は、「海洋プラスチック廃棄ゼロ、内容物残存ゼロ、100%リサイクル可能」を目指し、さらなる取り組みを進化させていく方針です。
第一三共株式会社「パリ協定の目標に沿って2030年までにCO2排出量27%削減」
第一三共株式会社ではCO2削減目標達成を目指し、SDGsの目標13:「気候変動に具体的な対策を」に取り組んでいます。
2019年10月に同社グループの小名浜工場(福島県いわき市)内に、医薬品業界では国内最大級となる自家消費型太陽光発電設備(出力3.3MW)の導入を決定し、2020年12月より稼働を開始しました。この太陽光発電設備により、同工場からのCO2年間総排出量の約20%相当(約1,800トン/年)の削減が見込まれています。
トヨタ自動車「トヨタ環境チャレンジ2050」
世界的な自動車メーカーのトヨタ自動車は、持続可能な社会の実現に貢献するために「トヨタ環境チャレンジ2050」を打ち出しています。重点的に取り組む事柄を6つのチャレンジと題し、新車の二酸化炭素排出量をゼロにするチャレンジ、工場の二酸化炭素排出量をゼロにするチャレンジ、製造から廃棄までのライフサイクルで排出される二酸化炭素をゼロにするチャレンジ、水使用量の最小化と排水の管理を行う水環境インパクト最小化チャレンジ、循環型社会・システムを構築するチャレンジ、そして人と自然の共生に向けたチャレンジを行っています。
中でも「新車の二酸化炭素排出量ゼロチャレンジ」では、製造する自動車の電動化を進めて電動車の選択肢を増やすための開発に力を入れていて、電動車を当たり前にしようと活動しています。自動車の世界販売台数がトップレベルのトヨタ自動車がこのような活動を行うことで、世界的なインパクトも大きくなるでしょう。
事業の特徴を活かしてSDGsの目標にコミットしている好例と言えます。
アサヒホールディングス「産業廃棄物の適正処理拡大」
貴金属事業などを営むアサヒホールディングスも、SDGsへの意欲的な取り組みを行っています。サステナビリティ推進体制を強化し、代表取締役社長を筆頭に、施策立案やモニタリング、コミュニケーションなど、一元的に戦略を立てているのです。
特筆すべき具体的な取り組みの1つに、「産業廃棄物の適正処理拡大」というテーマがあります。現代の大量消費社会が生み出す産業廃棄物やマイクロプラスチックによる海洋汚染などといった事柄に問題意識を抱え、自社事業で排出する産業廃棄物を適正に処理することで無害化に努めているのです。同社によると、2019年度の産業廃棄物の適正処理量の実績は35万トンですが、これを2030年度までに50万トンに増やすという意欲的な目標を掲げています。
「目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう」「目標12:つくる責任つかう責任」といった複数のSDGsに貢献する目的のもと、事業内容に適した活動を行っていることがわかります。
旭化成「Cs+(シーズプラス) for Tomorrow 2021」
総合化学メーカー旭化成のグループ理念は、「世界の人びとの”いのち”と”くらし”に貢献します」。SDGsの価値観との親和性が非常に高いものです。このグループ理念に沿う形で、旭化成は2019年度に中期経営計画を発表し、「Care for People, Care for Earth(人と地球の未来を想う)」という言葉でグループの姿勢を表しました。持続可能な社会に貢献するという目的のもと、サステナビリティ推進委員会を設置し、さまざまな取り組みを行っています。
主要テーマの1つは、「環境との共生」。二酸化炭素の排出量削減に貢献する素材などの開発を進め、「循環型社会の形成」や「気候変動対策」への取り組みを進めています。また、「健康で快適な生活」というテーマのもとでは安全で快適な空間を創り出すための住宅領域における技術開発にも力を入れています。
イオンモール「ハートフル・サステナブル」
日本国内のみならず海外にも大規模商業施設を展開するイオンモール。SDGsの実現に寄与するため、「ハートフル・サステナブル」というスローガンで活動を進めています。
イオンモールの事業に即した取り組みの一例が、地域の防災拠点としての役割を果たすための活動です。展開する商業施設では自然災害に備えて定期的な防災訓練を実施するだけでなく、非常用の電力や飲料水を確保することで、地域社会への貢献を目指しています。
また、地球環境保全のために進めているのが「次世代スマートイオン」です。国内外のモールに電気自動車の充電器を設置したり、太陽光発電を採用したりするなど、二酸化炭素の排出量を削減するための技術の導入を進めています。目的は、2050年に「脱炭素社会」を実現すること。イオンモールの事業を活かして、SDGsに貢献するまちづくりを進めているのです。
中小企業でも取り組めるSDGsの事例
さてここまで、大企業の取り組みを見てきましたが、ここからは中小企業の取り組みをご紹介します。
SDGsは大企業だけのものではなく、地域に根差した中小企業にこそ、独自の強みを発揮できるチャンスがあります。
有限会社ワールドファーム「持続可能な農業を目指して」
有限会社ワールドファームは、同社の「持続可能な農業」に対する取り組みを通じて、持続可能な社会を実現することを目指しています。同社は、野菜の栽培から加工・販売までを一貫して行う、農業の「6次産業化」を推進している企業です。農業を6次産業化することで、大規模かつ効率的で「儲かる農業」を可能にするほか、次世代農業者の育成や、国産野菜の利用推進なども実施しています。
同社はホームページにて、これらの取り組みが、安心・安全な野菜の提供、食糧自給率の向上につながるだけでなく、耕作放棄地の解消や雇用創出にも貢献するという考えを示しています。実際にこれまでの取り組みが評価され、35か所の自治体から招請を受けているとのことです。
株式会社ワンプラネット・カフェ「バナナペーパーでザンビアに雇用創出」
「人と地球の持続可能性の追求」を掲げる、株式会社ワンプラネット・カフェ。ザンビアで廃棄されているバナナの茎を買い取り、その繊維をバナナペーパーに加工・販売しています。同社は、深刻な貧困問題を抱えるザンビアに雇用を生み出すだけでなく、捨てられるはずの資源を有効に活用し、木材に代わる資源を用いた紙を社会に提供することで、生態系の保全にも貢献しているのです。
同社は、SDGsに総合的に貢献する商品として、バナナペーパーを積極的にPRしており、社会的価値と経済的価値の「トレードオン」を狙った良い事例と言えるでしょう。実際にバナナペーパー製の製品は、SDGsに関心の高い企業に採用されています。同社はこのほか、現地の子供の教育支援や、物資の提供など、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。また、SDGsをテーマにした企業向けの講演やワークショップ、コンサルティング、視察ツアーなど、SDGsの普及促進事業も実施しています。
株式会社大川印刷「人にも環境にも優しい『環境印刷』」
横浜の老舗印刷メーカー、株式会社大川印刷は、「ソーシャルプリンティングカンパニー」というコンセプトを掲げ、印刷事業を通じてSDGs達成を目指しています。石油系溶剤を含まない「ノンVOCインキ」や、違法伐採への不関与が証明されたFSC森林認証紙を使用することで、人にも環境にも優しい「環境印刷」に取り組んでいます。
同社はSDGsを経営計画に統合し、SDGsに関連する新規プロジェクトチームを立ち上げるなど、社内の体制構築にも余念がありません。視覚にハンディのある方でも読みやすい卓上カレンダー、4か国語に対応したお薬手帳など、SDGsを意識した新製品の開発も行っています。こうした取り組みが評価され、持続可能な調達に関心の高い企業や団体との取引が始まり、売上が増加したとのことです。
株式会社茨城製作所「小型の水力発電機でネパールに電気を届ける」
モーターや発電機の製造・修理を行う株式会社茨城製作所は、同社の技術を生かして社会問題解決型ビジネスを展開しています。社会にとって欠かせない、電気というインフラを支える企業として、高品質の製品やサービスの提供、また環境にやさしいエネルギー事業への製品提供を通じて、SDGsに貢献することを目指しています。
同社は、大人2人だけで持ち運べ、川や水路に入れるだけで発電ができる、小型の水力発電機「Cappa+++」を開発しました。実際に同製品を利用して、ネパールの学校に電気による明かりを提供し、現地の子供たちの学習環境を改善した実績があります。2015年のネパール地震の際には、JICAと連携して同製品を現地に提供しました。
まとめ
日本は、SDGsの達成度ランキングで2019年度は15位、2020年度は17位、2021年度は18位と少しずつ順位が下がっているものの、決して世界的に取り組みが遅れているわけではありません。しかし、世界的にSDGsへの取り組みが加速していく中で、企業が自社のミッションに基づいたサステイナブルな取り組みを行うことは、持続可能な開発を実現するために不可欠となっています。まずは自社の商品・サービスがSDGsの17の目標に対しどう働きかけることができるのか、SDGsへの理解を深めるところからスタートしていきましょう。
企業にとってSDGsは、リスクマネジメント(守り)とビジネスチャンス(攻め)の両面で不可欠な要素です。そして、その推進において最も重要なのは、経営層の意志だけでなく、現場社員の「共感」と「行動」です。弊社ソフィアの調査では、戦略への共感が1割にとどまるという課題が浮き彫りになりましたが、これは裏を返せば、インターナルコミュニケーションを見直すことで、企業の潜在能力を大きく解放できる可能性を示唆しています。SDGsを「やらされること」から「やりたいこと」へ。社内の意識変革こそが、持続可能な未来への第一歩となります。
関連サービス