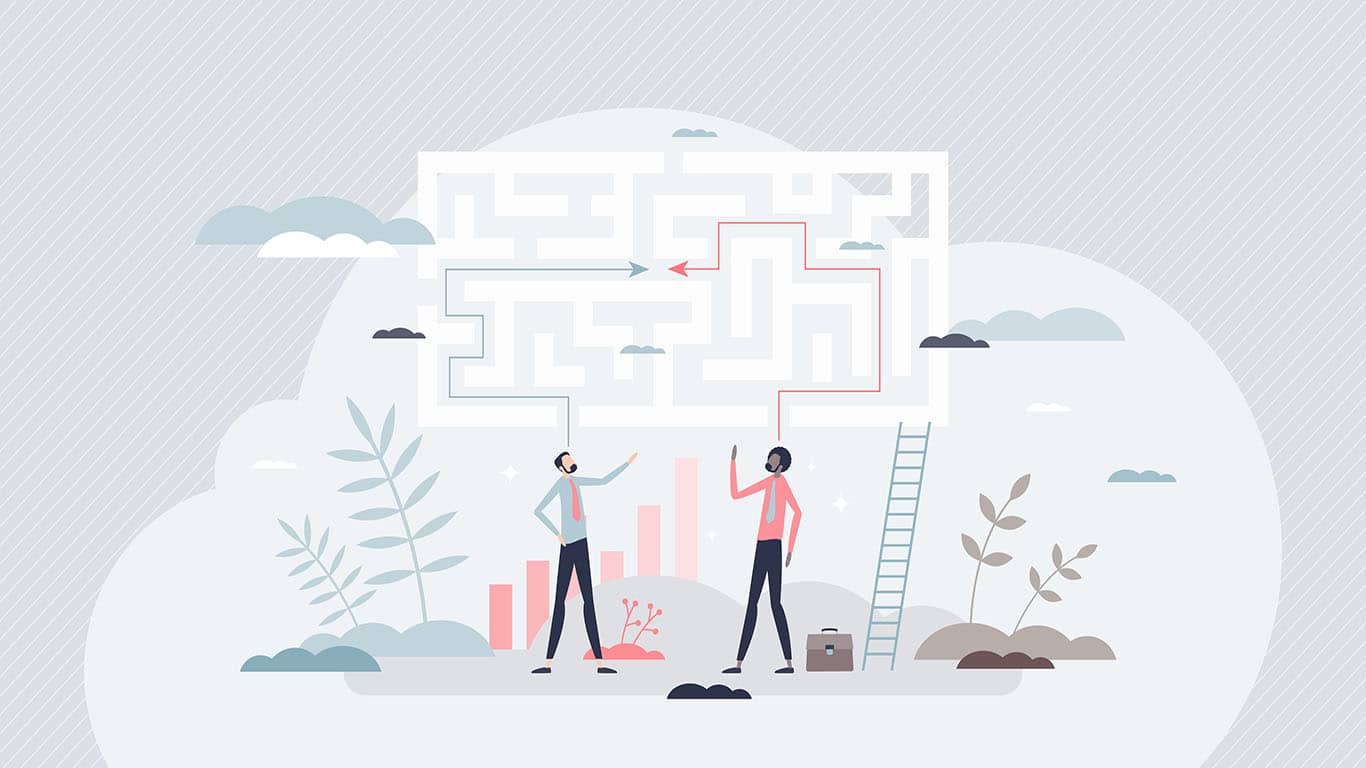レジリエンス経営とは?サイロの壁を越え組織の回復力を高める方法
最終更新日:2025.06.27

目次
大企業では部署ごとに情報が閉じ、社員がサイロ化してしまう――そんな課題を感じていませんか?急激な変化が常態化する今、組織の「回復力」を高めるレジリエンス経営が注目されています。本記事ではその定義から必要性、具体的な方法まで解説します。
レジリエンス経営とは(定義)
「レジリエンス(resilience)」とは、日本語で「回復力」や「復元力」を意味します。
もともとは物理学で素材が元の形に戻る弾性を指す言葉でしたが、現在では心理学や経営の分野で「逆境から適応・回復する能力」を指すようになっています。
ビジネスの文脈で使われるレジリエンスには個人レベルと組織レベルの2種類があります。
個人のレジリエンスとはストレスや失敗にも柔軟に対応し前向きに行動し続ける力ののことで、一方で組織のレジリエンスは環境変化に柔軟に対応し自らを変革できる企業文化や職場環境を指します。
つまり、人で言う「適応力・回復力」を組織全体が備えている状態が「レジリエンス経営」と言えるでしょう。
レジリエンス経営とは「予期せぬ困難が起きても折れずに素早く立ち直れるしなやかな強さ」を組織に持たせる経営手法です。単なる社員個人の頑張りに頼るのではなく、組織ぐるみで困難に対応できる力を育むアプローチということになります。
ところで、「レジリエンス=個人の資質」と捉えられがちな面もありますが、それだけでは語れません。
実はレジリエンスは周囲のサポートや職場環境などにも大きく影響されることが研究で示されています。
例えば2024年のある分析では、「周囲から得られる支援(ソーシャルサポート)が充実した人ほど困難に対してレジリエント(折れずに立ち直る)な反応を示しやすい」との報告があります。
このように、レジリエンスは決して一人だけで完結する能力ではないのです。
そこで本記事では、個人の精神力頼みではない「組織全体で育むレジリエンス」に焦点を当て、その背景や高め方を探っていきましょう。
ビジネス環境の変化とレジリエンス経営が注目される背景
現代のビジネス環境は変化のスピードがかつてないほどに速く、将来を正確に予測することが困難な時代です。
想定外の事態が次々と起こる中で企業が生き残り成長していくには、突然のショックにも素早く立て直し柔軟に対応できる力、すなわちレジリエンスを備えておく必要性が一段と高まっています。
直近の例では、新型コロナウイルスの世界的流行が企業活動に大きな試練をもたらしました。
行動制限による業務停滞、サプライチェーンの寸断、物資不足、急なリモートワーク導入、職場の感染対策など、企業は未知の困難に直面しました。
その中でレジリエンスが高い企業は混乱の中でも柔軟に働き方を変えたり、新しいサービスを打ち出すなどしていち早く軌道修正できています。
一方、変化に対応しきれない企業は大きく業績を落としたり、最悪の場合は経営危機に陥る事態も見られました。
さらに日本企業にとっては、地震や台風など自然災害リスクが高い点も無視できません。
予期せぬ外的ショックがビジネスを直撃する可能性が常にあり、またテクノロジーの進歩による市場の破壊的変化や地政学リスク(国際情勢の変化でサプライチェーンが寸断される等)も存在します。
換言すれば、ビジネスを取り巻く困難がいつどこでどんな形で発生するか分からないのが実情です。
そのため、「何が起きても立ち直り事業を継続できるしなやかな企業」であること、すなわち高いレジリエンスを備えた組織であることがこれまで以上に重要視されているのです。
わかりやすい例で言えば、コロナ禍で多くの企業がテレワークへの転換を余儀なくされましたが、素早く対応できた企業とそうでない企業の差は明確でした。
レジリエンス経営の必要性と「個人頼み」の限界
以上のような環境下で、企業が事業を持続・発展させていくためにレジリエンス経営は欠かせない取り組みだと言えるでしょう。
環境変化への「適応力」や「復元力」を組織として備えていれば、新たなリスクにも耐えうるだけでなく、逆にピンチをチャンスに変えて成長することも可能です。
たとえば想定外の市場変化にも柔軟に対応して新規ビジネスを立ち上げたり、危機から得た教訓でより強い経営基盤を築いたりといった具合に、レジリエンスは企業の長期的な競争力の源泉となりえます。
そして肝心なのは、そのレジリエンスを組織として発揮できる状態にしておくことです。仮に組織内に非常にレジリエンスの高い個人がいたとしても、組織全体がレジリエント(しなやかで復元力のある状態)でなければ、急激な事業環境の変化に十分対応することは難しいでしょう。
実際、Harvard Business Review(HBR)も「個々の社員のレジリエンスだけでは組織全体の改善や支援の代わりにはならない」と指摘しています。
組織としてレジリエンスを備えるには、組織構造や意思決定プロセスといったハード面の整備と、企業風土や社内コミュニケーションといったソフト面の醸成の両方から取り組む必要があるのです。
レジリエンスを鍛えるときは周囲と協力する
社員一人ひとりの「心の強さ」だけに頼るアプローチでは限界があります。むしろ、社内の人と人との「関係性」や企業の「文化」にこそレジリエンス強化のカギがあります。
上司が部下に「もっと頑張れ!」とハッパをかけたり、個人研修でメンタルタフネスを鍛えさせたりするだけでは、本質的な解決にならないのではないでしょうか。
大切なのは、お互いを支え合える関係性や心理的安全性のある職場文化を育むことです。
日本でも専門家が「レジリエンス研修が誤って広まると『心が折れない社員を育成する』というイメージばかりが先行してしまう」と警鐘を鳴らしていますが、社員に無理を強いて心をすり減らすような”根性論”では真のレジリエンスは生まれません。
支え合う風土こそが組織の回復力を高めるのです。
以上のように、レジリエンス経営は単に個々人の問題ではなく組織全体のあり方に関わるテーマです。
社員任せの対応では限界があるからこそ、人材の配置・仕組みから社内の風通しや文化づくりまで包括的な視点で臨む必要があります。
言い換えれば、個人の努力に頼る従来型アプローチから、組織全体で支え合う仕組みへの転換が必要ということです。
それでは具体的に、組織としてレジリエンスを高めるにはどんな取り組みが有効なのでしょうか。
ここからは現場・経営・部門といった各レベルでのポイントや、社内コミュニケーションの整備について詳しく見ていきましょう。
レジリエンス経営を組織で実践するには
レジリエントな(回復力の高い)組織を築くためには、ハード面(構造やプロセス)とソフト面(人や文化)の両側面からアプローチする必要があります。
具体的には、企業内の異なるレイヤー(現場・チームレベル、全社・経営レベル、部門間レベル)それぞれで環境づくりを進めることが大切です。以下では各レベルでの重要なポイントを順に解説します。
現場レベル:余裕と権限で現場の対応力を高める
まず現場(チーム)レベルでは、日々の業務プロセスに柔軟な余裕(バッファ)を持たせ、状況に応じて多様な対処ができるようにしておくことが重要です。
平時から一つのやり方に固執せず複数の選択肢を用意しておけば、いざ予期せぬトラブルに直面した際にも慌てずに対処できます。
また、その前提として、現場で自主的に判断・対応できるよう権限委譲がなされていることも欠かせません。
トップダウンで細部まで指示待ちの状態では、刻一刻と変わる状況に素早く対応するのは難しいためです。
このような現場のレジリエンス強化の考え方は、ビジネス用語で「冗長性」とも呼ばれます。
一見するとムダを排除し効率を追求する従来型の考え方に反するようですが、不確実性が高まる時代には長期的なリスク管理の観点で冗長性が重視されつつあります。
たとえば現場レベルでは次のような工夫が挙げられます。
納期に余裕を持たせる:
全てのスケジュールをギリギリにせず多少のバッファ日を設けておくことで、想定外の遅延が起きても慌てず対応できます。
バックアップ要員・拠点の確保:
特定の人や部署だけにノウハウが集中しないようにし、誰かが欠けても業務が回る体制を整えます。重要業務においては代替要員を育成し、複数拠点で業務を分散するなどの対策です。
収益源や手段の多重化:
単一の製品・サービスに依存せず、複数の収益モデルや対応手段を用意しておきます。例えば対面販売だけでなくオンライン販売も展開しておけば、一方が不振でも他方で補えるため、変化への耐性が増します。
収益源や手段の多重化:
状況に応じてリーダーや方針を変更する場合でも、メンバー同士が円滑に合意し協力できる文化を育みます。平時から「お互い様」の意識で仕事を進め、誰か一人に業務が属人化しないようにすることがポイントです。
上記のように結果(アウトプット)への執着を少し緩め、プロセスに余地を残して現場を信頼して任せることが、レジリエンス向上のポイントです。
こうした「現場のレジリエンス」の成否は、現場を率いるマネジメント層の手腕にかかっています。従来の効率重視型マネジメントでは、納期や手順を厳格に管理し、少数精鋭で決まったやり方を突き詰めるのが常道でした。
しかし不確実性が高い現在は、あえて”冗長さ”を管理する発想が求められます。
そのためには、現場を統括するマネージャーが日頃からメンバーに対してより高い視座の目的を示し、細かな指示ではなく「何を成し遂げるべきか」というビジョンを共有して任せる姿勢が重要です。
言い換えれば、上司は細部まで指示を出すのではなく大枠の目標や意図を伝え、実行方法は現場の裁量に委ねるマネジメントへのシフトです。
もっとも、現場レベルでいくら冗長性を確保し柔軟な対応力を高めようとしても、経営層からの理解と支援がなければ現場だけで実行するのは難しいでしょう。
一言でいえば、現場レベルでは効率性よりも柔軟性を重視し、現場に判断権限を委ねることが重要です。
納期に余裕を持たせるにも、追加の人員配置を行うにも、経営判断やリソース投資が伴います。したがって次に、経営トップ層での取り組みについて見ていきます。
経営層レベル:ミッション共有と情報開示で組織の方向性を一致
次に全社・経営レベルでのレジリエンス強化ポイントです。経営トップや本社部門が果たすべき役割は、平時から組織全体に高次元な目的意識(ミッション・ビジョン)を浸透させておくことにあります。
変化の激しい環境下では、中長期の経営計画でさえ状況に応じて柔軟に修正する必要が出てきます。
あらかじめ複数のシナリオを用意し、状況変化に即応して計画を見直す――そんな「計画が変更される前提」で経営を舵取りすることも不可欠です。
ここで重要なのは、計画そのものよりも「我々は何のために存在し何を成し遂げたいのか」という根幹のビジョン・使命が全社員に腹落ちしていることです。
仮に経営計画が途中で変更になる場合でも、社員一人ひとりが企業のビジョンや価値観を共有していれば各現場で柔軟に判断・対応でき、組織全体のレジリエンスの土台が揺らぎません。
逆に言えば、社員が判断に迷ったとき立ち返れる共通の軸(理念)があれば、細かなルールを多少緩めても自律的に動ける組織になるということです。
そのために経営層が果たす具体的な役割として、例えば次のようなものが挙げられます。
ビジョンに基づく計画の共有:
中期経営計画を策定する際には、単なる数値目標の羅列ではなく「我が社は何を目指し社会にどう貢献するのか」といった企業のビジョンや価値観を明示します。計画を全社に展開し共有する際も、数字の裏にある目的を語り、仮に計画変更が生じる場合にも根底にあるビジョンとの関係性を説明して社員の理解を促します。
外部環境情報の積極提供:
業界動向や技術トレンド、社会課題など、会社に影響を及ぼしうる外部環境の情報を社内報や朝会等で継続的に社員に共有します。社員が日頃から自社を取り巻く環境変化を把握し、「次に何が起こり得るか」を主体的に考えられるよう支援する狙いです。
理念・バリューの浸透:
社是やクレド(行動指針)を形骸化させず、日常業務で引用・活用することで企業理念を社員の行動判断の拠り所として根付かせます。例えば会議で意思決定に迷った際にクレドに立ち返って考えるなど、共通の価値基準を持たせます。これにより部門や職位を超えて判断基準がブレない一体感が生まれます。
このように経営陣が示すビジョン共有や情報提供、価値観の共有は、レジリエンスの高い組織を築くうえで非常に重要です。
言い換えれば、社員が自律的に動ける前提を整えてあげることが経営トップの使命とも言えるでしょう。
株式会社ソフィア(本記事の執筆企業)では、このようにビジョン・バリュー・カルチャーを社内に浸透させ、社員が自ら体現し外部に発信できる状態を目指すコミュニケーション活動を「インターナルコミュニケーション(IC)」と定義しています。ICを通じて「社員が企業理念を深く理解し、自らの言葉で語れるようになる」ことは、社員一人ひとりの行動判断を支えると同時に組織全体のレジリエンス強化にも直結するのです。
例えば、コロナ禍で多くの企業が経営計画の見直しを迫られましたが、理念が浸透した企業ほど素早い方針転換ができました。
部門間レベル:サイロの打破と知識共有で全体最適化
最後に部門間(部署横断)レベルでのレジリエンス強化策について考えます。
企業全体で見た場合、事業領域やアプローチ手段が一つしかない組織よりも、複数ある組織の方がレジリエンス(耐久力)は高まると言えます。
極端な例を挙げれば、雨傘だけを売っている店は日照り続きでは経営が立ち行きませんが、晴雨兼用の日傘も扱っていれば雨が降らなくても一定の売上を確保できます。
つまり事業や戦略の多様性が高ければ、一部の不振を他で補えるため組織全体としての復元力が増すのです。
ここで重要になるのが、企業内の各部門同士の連携です。
複雑な環境変化や予期せぬ事態に対処するには、営業・開発・カスタマーサポートなど異なる専門性を持つ部署が協力して多角的な解決策を講じることが求められます。
しかし実際には、多くの企業で部門間の壁は厚く、部署ごとに分断された「サイロ化」と呼ばれる状態に陥っています。
他部門の状況や業務内容がほとんど共有されず、各部門が自部門の目標達成だけを優先して縄張り意識すら生じているようでは、組織横断的な協力など望むべくもありません。
このような状態では新しい発想も生まれにくく、環境変化への組織対応力は低下してしまいます。
レジリエントな組織を目指すなら、部門間の壁を打ち崩し情報やリソースを融通し合う風土を醸成する必要があります。
そのための具体策として、まず部署横断的に情報を共有する仕組みを整えましょう。たとえば社内ポータルサイトやグループウェアなどのデジタルツールを活用して、各部署の活動状況や知見を全社にオープンにします。
また、部門間連携を促すためには評価制度や目標管理の仕組みに工夫を凝らすことも有効です。
部署ごとに数値目標を与えて競わせるだけでは部門間に対立が生まれる恐れがあります。そうではなく、全社共通の目標に対して各部門が協働した成果を評価するKPI設定にするなど、連携インセンティブを高める方法が考えられます。
さらに日常的にも、部門の垣根を越えたコミュニケーション活性化を促すことが大切です。単に雑談の機会を増やすだけでなく、業務上の情報交換やナレッジ共有が活発に行われる状態を目指します。
例えば定期的なクロスファンクション会議(複数部署合同の打ち合わせ)を設けたり、プロジェクト横断型のタスクフォースを編成したりするのも有効です。
最近では社内SNS等を導入し、他部署の人にも気軽に質問・相談できるようにしている企業も増えています。
こうした「組織内の知の巡り」を良くする施策によって、いざという時に迅速に部門横断チームを組んで問題解決に当たれる柔軟性が生まれるでしょう。部門の縦割りを解消し、組織横断的な協働を促す仕組みづくりが不可欠です。
以上、現場・経営・部門という3つのレベルからレジリエントな組織づくりのポイントを見てきました。
ここで改めて浮き彫りになるのは、ハード面以上にソフト面(人や文化)の重要性です。どんなに制度やプロセスを整備しても、人材育成や企業風土といったソフト面がネックになるとレジリエンスは発揮できません。
次章では、このソフト面(社内コミュニケーションや文化)の変革についてさらに掘り下げてみましょう。
心理的安全性と企業文化:レジリエンスを支える「ソフト面」
レジリエンス経営を実現する上で最後の鍵となるのが、社内コミュニケーションや企業文化といった目に見えにくい「ソフト面」の改革です。
いくら立派な仕組みや計画を導入しても、日々の職場でのコミュニケーションや風土が変わらなければ組織は変わりません。
実際、以下のような企業文化上の問題を抱えていては、組織がどれほどレジリエンスの潜在能力を持っていてもそれを発揮できないでしょう。
情報の独占・不足
重要な情報が特定の人や部署に閉じてしまい、現場に十分共有されていない。情報が偏在すると、いざという時に現場で適切な判断を下す材料が不足してしまいます。
トップダウン過多で現場が受け身
上意下達の命令が絶対で、部下が指示待ちになり自ら考えて動かない風土。これでは想定外の事態に直面した際、現場から創意工夫が生まれず対応が遅れてしまいます。
異論が出ない同調圧力
「空気を読む」ことが優先され、多様な意見が出ない職場文化。ハイコンテクストなコミュニケーションが支配的で、異なる視点を持つ人材が声を上げにくい雰囲気では、新たな発想や変革の芽が摘まれてしまいます。
このような文化的課題を放置していては、どれほど構造的にレジリエンス強化のポテンシャルを持っていても実際には力を発揮できません。
情報共有を促進するITツールの導入などハード面のテコ入れは比較的容易ですが、文化・風土といったソフト面の改革は一朝一夕にはいかない難しさがあります。
たとえ表面的に人材育成プログラムを刷新しても、各職場での日々のコミュニケーションが変わらなければ組織は変わらないのです
では、こうしたソフト面を変革し組織のレジリエンスを高めるにはどうすれば良いのでしょうか。
ポイントは、先述の経営層レベルの取組でも触れたように、まず経営トップが組織の目指す方向性(ビジョン)を明確に打ち出すことです。
そのうえで、それを踏まえて社内コミュニケーションの取り方や人材育成のあり方を見直すことが重要になります。
トップ発信のビジョンが社員に浸透していれば、多少ルールを緩めても各自が判断基準を持って動けるようになります。
ルールでがんじがらめに統制するより、社員が主体的に考え発言できる環境を整える方が、非常時にも創造的な対応が生まれやすいのです。
その具体策の一つが、社内コミュニケーションの活性化です。前述のとおりITツールの導入で情報の見える化を進めるのも有効ですが、それ以上に心理的安全性の高い職場づくりが欠かせません。
心理的安全性とは、ハーバード大学のエイミー・エドモンソン教授が提唱した概念で、「チームの中で対人リスクをとって発言しても大丈夫だとメンバー全員が信じられる状態」を指します。
言い換えると、「こんな基本的なことを聞いたら恥ずかしいかな」「失敗したら責められるかも」といった不安を感じずに、誰もが率直に質問・提案・ミス報告できる雰囲気です。
この心理的安全性が確保されたチームでは、メンバー同士が助け合い、議論が必要な場面では忌憚なき意見を出し合う関係性が本領を発揮するはずです。
まとめ
レジリエンス経営とは、困難に直面しても柔軟に対応し、速やかに立ち直る力を組織全体で育む経営手法です。個人の根性に頼らず、支援体制や心理的安全性を重視し、現場・経営層・部門間が連携することで、しなやかで強い組織を実現します。結果として、事業の継続性や革新性が高まり、離職防止や組織活力の向上が期待されます。