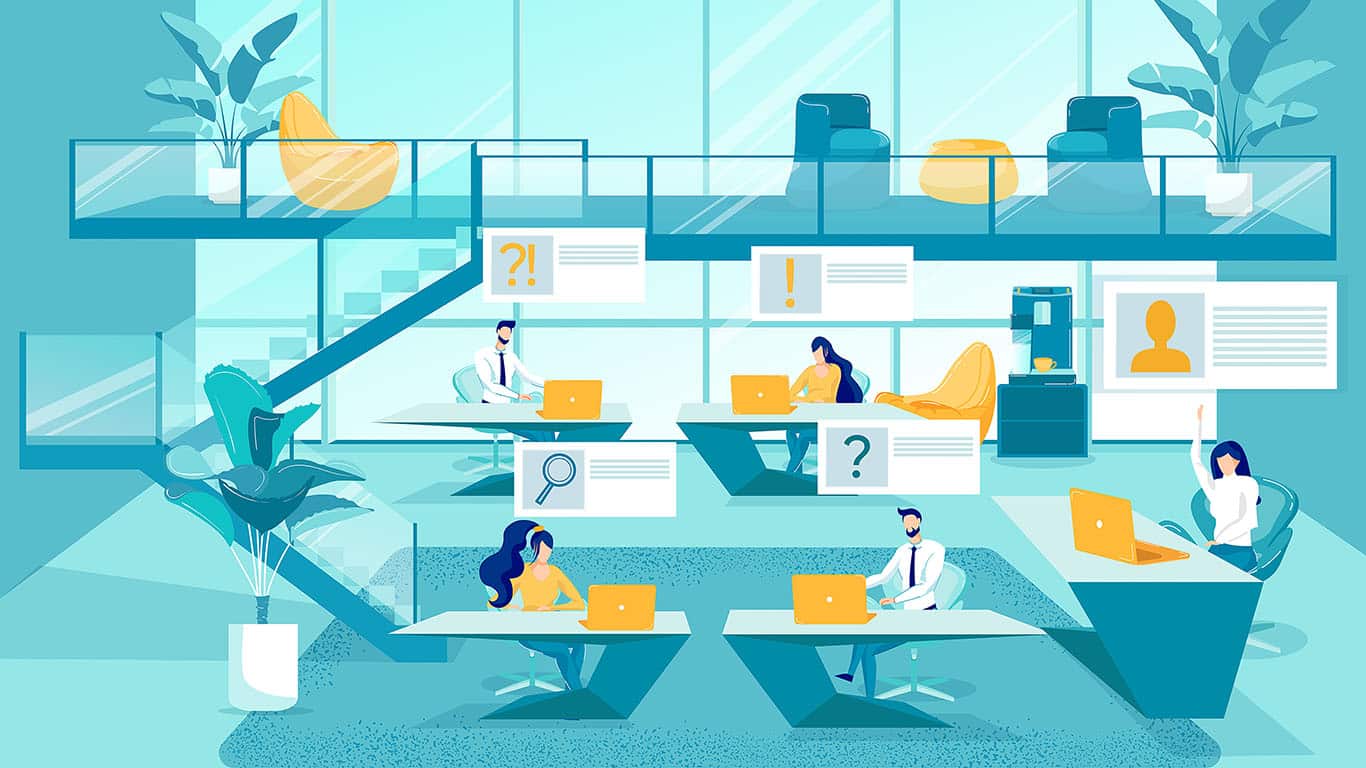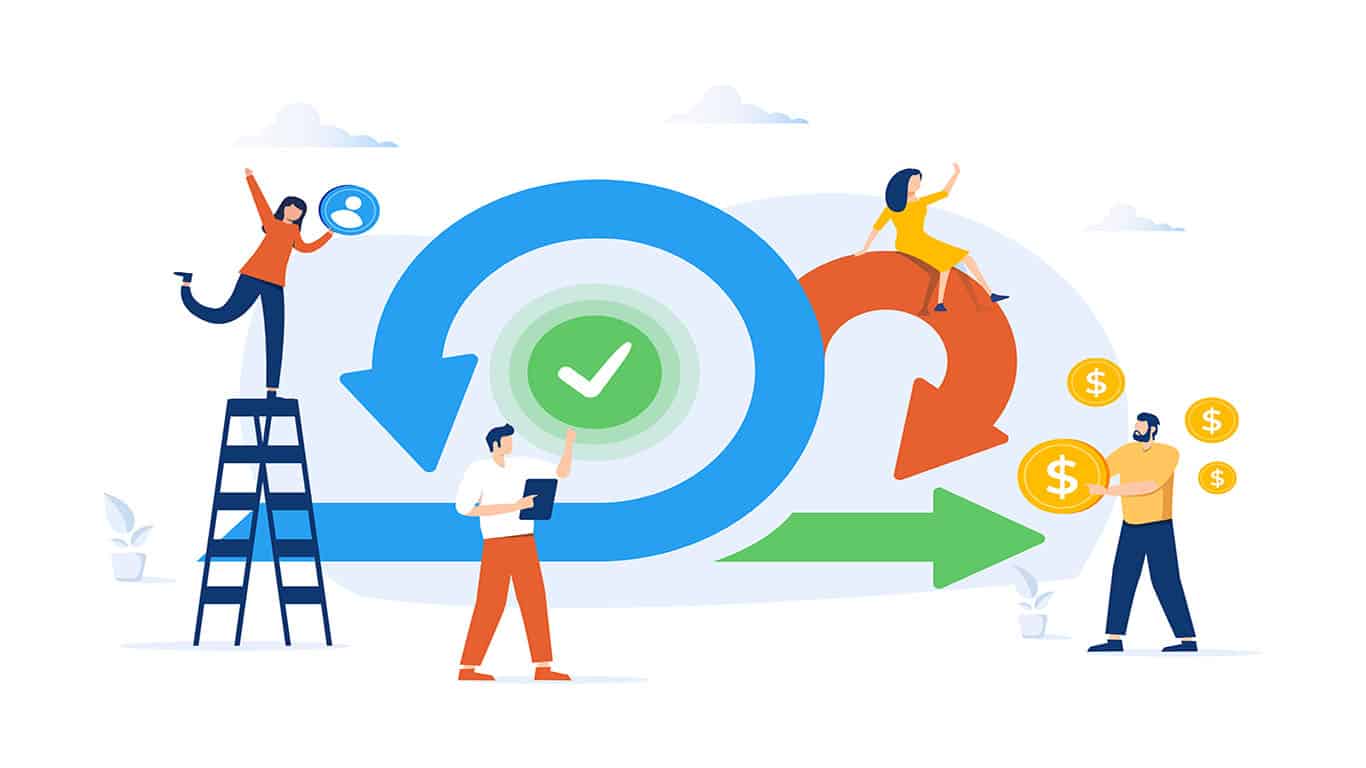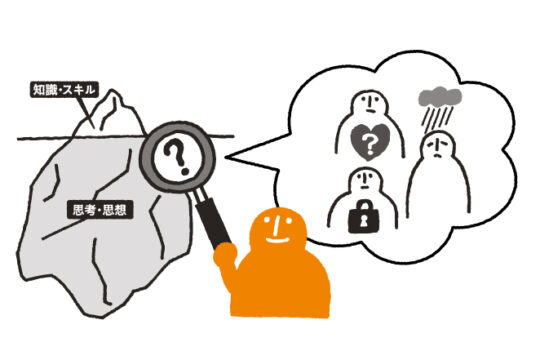【完全版】DXを推進するための組織づくりとは?成功へ導く6つの型と、組織の壁を越えるコミュニケーション戦略
最終更新日:2026.02.17

目次
デジタル技術の進化は不可逆的な潮流となり、DXは全企業にとって喫緊の課題となっています。AIやIoTは産業構造そのものを再定義しつつありますが、日本企業の多くは未だ「ツールの導入」や「業務の電子化」の段階に留まり、本質的な「変革」には至っていないのが現状ではないでしょうか。
経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」の本質は、単なるシステム老朽化の問題ではありません。レガシーシステムの維持に貴重なリソースが奪われ、未来への投資機会を失い続けることこそが、経営における真の危機と言えるでしょう。それにもかかわらず多くの企業が足踏みをする最大の要因は、技術的な難易度ではなく「組織の硬直性」にあります。縦割りの弊害、前例踏襲の文化、そして経営と現場の乖離といった「見えない壁」が、変革のスピードを致命的に鈍らせているのです。
この記事では、DXの成功要因を「技術」ではなく「組織」の観点から徹底的に解剖します。最新の独自調査や成功事例の分析を通じ、既存の枠組みを打破し、持続的な成長を生み出す「勝てる組織」をいかに構築すべきか、その具体的な道筋をご提示いたします。
DX推進には専門の部門が必要?
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がデジタル技術を活用してビジネスモデルを変革するだけでなく、業務そのものや組織のあり方も変革することで、競争上の優位性を確立することになります。これは、言うは易く行うは難しであり、大きな変革必要です。この変革を推進するためには、大企業になればなるほど、先導的な役割を担う部門があったほうが動きやすくなるでしょう。ここではDX推進に取り組む日本企業の組織体制について紹介します。
DXを推進する組織体制
IT専門調査会社であるIDC Japanが2018年に行った調査によると、DXを推進する国内企業は、DX専門の「第2のIT部門」を設置してリーダー組織とするケースがもっとも多くなっています。
また、第2のIT部門を設置した企業の多くは、同時に「チーフデジタルオフィサー(Chief Digital Officer: CDO)を設置していることも特徴です。
DXを推進する組織編成
今回は参考として3つの型を例示します。
・IT部門拡張型
その名のとおり、すでに存在するIT部門を拡張してDX部門を設ける型です。
もともとITのスペシャリストで組織された部門ということもあり、デジタル化に際してのツールやサービス、システム開発を検討・導入する際に力を発揮します。
一方で、IT部門は保守やメンテナンスを専門とする部署であるため、提案力に欠けるというデメリットも存在します。伝統的に、事業部門の仕事を理解している人間を現場からIT部門に、あるいはIT部門の部門から現場に派遣するなどのジョブローテーションを取り入れてきました。あるいは外部の知見を取り入れ、現場とITの二者の橋渡しを行うことなどが必要です。
・事業部門拡張型
こちらは自社の事業部門を拡張した型です。
自社のプロダクトやサービス、テクノロジーに深く携わってきた人材がDXを主導し、IT部門が後方支援を担います。より現場目線での変革を得意なフィールドとします。
なお、この体制をとる場合、IT部門との連携を密に行う必要があります。IT部門との折衝を先導するメンバーがいると円滑に進めることができるでしょう。
・専門組織設置型
DXを推進してイノベーションを起こすべく、各部署のみならず、テクノロジーベンダーやコンサルティングファームなど外からも人材を選りすぐって専門組織を立ち上げる場合もあります。さまざまな部門で活躍した人材を集めることで、イノベーティブなアイディアが創出されやすくなります。
異なる部署の人材が一堂に会することになるため、最初はチームの組織力が弱い状態です。
チームビルティングに長けたマネジメントの担当者も加えて部門をまとめる必要があります。
DXは推進の実行プロセスに応じて、さまざまな人材を必要とします。
推進計画を立案する際に、自社のどのような人材をいつアサインすべきか検討をつけておくと、実際の運用時にスムーズとなるでしょう。
DXの本質は「組織そのものを変えること」
DXという言葉は多様な解釈で使われていますが、組織づくりを論じる上では、その定義を明確にしておく必要があるでしょう。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がデジタル技術を活用してビジネスモデルを変革するだけでなく、業務そのものや組織のあり方も変革することで、競争上の優位性を確立することを意味します。
ここで重要なのは、「組織のあり方も変革する」という点です。平たく言うと、新しいビジネスモデル(例えば、サブスクリプション型サービスやデータ活用型プラットフォーム)を運用するためには、従来の「製造・販売」に最適化された組織構造では対応できないということです。意思決定のスピード、部門間の連携、人材の評価制度など、組織のOS(オペレーティングシステム)そのものをアップデートする必要があります。
専任の推進部門が必要な理由
DXは全社的な取り組みであるべきですが、「全員でやる」という掛け声だけでは責任の所在が曖昧になり、頓挫するリスクが高まるのではないでしょうか。既存の業務プロセスを守ることがミッションである既存部門にとって、プロセスを破壊・再構築するDXは、本能的に避けたい活動になりがちだからです。
この変革を推進するためには、大企業になればなるほど、先導的な役割を担う部門があったほうが動きやすくなるでしょう。
専任組織は、変革の旗振り役(フラッグシップ)として、以下の機能を果たします。
- 求心力の醸成: 変革のビジョンを掲げ、社内の関心を集める。
- 利害調整: 部門間のコンフリクト(対立)を解消し、全体最適の視点で調整を行う。
- リソースの集中: 予算と人材を集中的に投下し、短期間で成果(クイックウィン)を生み出す。
実際に、IT専門調査会社IDC Japanの調査(2018年)によれば、DXを推進する国内企業の多くが、DX専門の「第2のIT部門」を設置してリーダー組織とするケースが最多となっています。さらに、第2のIT部門を設置した企業の多くは、同時に「チーフデジタルオフィサー(Chief Digital Officer: CDO)」を設置していることも特徴です。経営権限を持つCDOと実行部隊である専門組織の組み合わせは、DX推進のスタンダードな体制となりつつあると言えるでしょう。
DX組織体制のパターンと作り方
DXを推進する組織体制に「唯一の正解」はありません。企業の規模、業種、DXの成熟度、そして解決すべき課題によって最適な形は異なります。ここでは、代表的な3つの基本型と、IPA(情報処理推進機構)が定義する詳細な6パターンを統合し、それぞれの特徴と適性を分析いたします。
組織体制の3つの基本型
まず、DX組織の基礎となる3つの基本型をご紹介します。
IT部門拡張型(守りから攻めへの転換)
その名のとおり、すでに存在するIT部門を拡張してDX部門を設ける型です。
- 概要: 情報システム部門(情シス)にDX推進の機能を持たせます。
- 強み: もともとITのスペシャリストで組織された部門ということもあり、デジタル化に際してのツールやサービス、システム開発を検討・導入する際に力を発揮します。セキュリティ対策、基幹システムとの連携、ガバナンスの維持において高い信頼性があります。
- 課題: 一方で、IT部門は保守やメンテナンスを専門とする部署であるため、提案力に欠けるというデメリットも存在します。多くの情シスは「現場からの要求を受けてシステムを作る(受動的)」文化に慣れており、「ビジネスを変える提案(能動的)」に不慣れなケースが散見されます。
- 対策: この課題を克服するためには、人材の流動化が鍵となります。伝統的に、事業部門の仕事を理解している人材を現場からIT部門に、あるいはIT部門から現場に派遣するなどのジョブローテーションを取り入れてきました。あるいは外部の知見を取り入れ、現場とITの二者の橋渡しを行うことなどが必要です。
事業部門拡張型(現場主導のイノベーション)
こちらは自社の事業部門を拡張した型です。
- 概要: 営業部、マーケティング部、製造部などの各事業部内にDXチームを設置します。
- 強み: 自社のプロダクトやサービス、テクノロジーに深く携わってきた人材がDXを主導し、IT部門が後方支援を担います。より現場目線での変革を得意なフィールドとします。顧客ニーズに直結した「攻めのDX」をスピーディに推進できる点が最大の特徴です。
- 課題: 各事業部が独自にツールを導入することで、システムが乱立(サイロ化)し、全社的なデータ統合が困難になるリスクがあります。また、セキュリティ基準のばらつきも懸念されます。
- 対策: なお、この体制をとる場合、IT部門との連携を密に行う必要があります。IT部門との折衝を先導するメンバーがいると円滑に進めることができるでしょう。
専門組織設置型(破壊的創造の拠点)
DXを推進してイノベーションを起こすべく、各部署のみならず、テクノロジーベンダーやコンサルティングファームなど外からも人材を選りすぐって専門組織を立ち上げる場合もあります。
- 概要: 「デジタル戦略室」「DX推進本部」などの名称で、既存組織から独立した部署を新設します。
- 強み: さまざまな部門で活躍した人材を集めることで、イノベーティブなアイディアが創出されやすくなります。既存業務のしがらみから解放され、破壊的なイノベーションに集中できる環境を作れます。
- 課題: 異なる部署の人材が一堂に会することになるため、最初はチームの組織力が弱い状態です。また、既存部門から「現場を知らない特権階級」と見なされ、協力が得られない(いわゆる「出島」の孤立問題)が発生しやすい傾向にあります。
- 対策: チームビルディングに長けたマネジメントの担当者も加えて部門をまとめる必要があります。また、経営層が全面的にバックアップし、この組織の権限と重要性を全社に周知することが不可欠です。
DXは推進の実行プロセスに応じて、さまざまな人材を必要とします。推進計画を立案する際に、自社のどのような人材をいつアサインすべきか検討をつけておくと、実際の運用時にスムーズとなるでしょう。
IPAが定義するDX推進組織の6つのパターン
さらに解像度を高めるために、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が『DX白書』などで示している組織類型を参照し、各パターンの特徴を整理します。これは前述の3つの型をより詳細に分類したものと言えるでしょう。
| パターン | 特徴・詳細 | 適している状況・メリット | デメリット・課題 |
|---|---|---|---|
| 1. 企画部門推進型 | 経営企画部などがDX推進を兼務する。 | 試行段階(PoC)に最適。全社戦略との整合性が取りやすく、トップダウンで指示を出しやすい。 | 実務部隊を持たないため、具体的な実装フェーズでスピード感が落ちる。現場との距離が遠くなりがち。 |
| 2. IT部門推進型 | 情報システム部門が主導する。 | 守りのDX(業務効率化・基盤刷新)に強み。既存システムの知見を活かせる。 | ビジネス視点が不足しがちで、手段(ツール導入)が目的化しやすい。 |
| 3. その他部門推進型 | 研究開発(R&D)や特定事業部が主導。 | 特定領域の深化(例:製造ラインのIoT化、新素材開発のAI活用)。専門性を活かした高度なDXが可能。 | 全社への波及に時間がかかる。部分最適に留まるリスク。 |
| 4. 組織新設型(部門内) | 既存部門の中に専任のDXチームを設置する。 | 現場の業務フローに精通した変革が可能。現場の抵抗感を抑えつつ推進できる。 | 全社的な変革権限を持たない場合が多く、活動範囲が限定される。 |
| 5. 組織新設型(独立) | 社長直轄などの独立した専門組織を設置する。 | 本格的な全社変革。予算と権限を持ち、スピード感を持って大規模な改革を実行できる。 | 「出島」として孤立するリスク。既存部門との軋轢が生じやすい。 |
| 6. プロジェクトチーム型 | 各部門から選抜されたメンバーによる混成チーム(TF)。 | 特定の課題解決(例:全社ペーパーレス化)に対して、機動的に対応できる。 | メンバーが兼務の場合、本業にリソースを取られ活動が停滞しやすい。 |
多くの日本企業では、「1. 企画部門推進型」からスタートし、徐々に成果が出てきた段階で「5. 組織新設型(独立)」へと移行するステップを踏むケースが一般的です。しかし、2025年の崖が迫る中、最初から権限を持った「CDO+独立専門組織」を立ち上げ、トップダウンで変革を断行する企業も増えています。
DX組織に求められる3つの大切な要素
どのような組織形態を選択するにせよ、DX推進組織が機能不全に陥らないためには、以下の「3つの要素(ケイパビリティ)」を備えている必要があります。これらは単なるスキルセットではなく、組織としての「機能」であり「文化」と言えるでしょう。
ビジネスモデルや経営戦略を実行に移す力
DX部門は、デジタルの専門家であると同時に、経営の設計者でなければなりません。
DXによって自社事業の形が大きく変わった場合、ビジネスモデルや経営戦略にも軌道修正が必要です。DX部門にはこの設計と実装を行うことが求められます。
例えば、製造業が製品販売(モノ売り)から、稼働データに基づく予知保全サービス(コト売り)へ移行する場合、収益モデルはフロー型からストック型へ変化します。これに伴い、営業のインセンティブ制度、会計処理、顧客契約、サポート体制など、経営のあらゆる側面を再設計する必要があるでしょう。
デジタルトランスフォーメーションは、成功している企業が世界でも5%ほどしかないという調査結果から、企業を創業・継続させることと同程度に難易度が高いと言われており、DX部門は複雑な全社横断改革を担うことになるでしょう。この「全社横断」をやり切るための政治力、調整力、そして構想力が「実装力」の正体です。
人材を育てて活かす力(リテラシーの底上げ)
高度なAI人材を採用しても、現場の社員がAIを使いこなせなければ意味がありません。DX組織には、全社的な「デジタルリテラシーの底上げ」を主導する教育機関としての役割も求められます。
DXの過程で、新たなツールやシステムを導入することが多々あるはずです。その際に現場が新しい環境での業務にいち早く慣れるよう、全社をあげてITリテラシーの向上に取り組む必要があり、DX部門にはその育成を行うことが求められます。
さらに、人材の流動性を高めることも重要です。DXにはフェーズの段階ごとに必要な人材を必要に応じてアサインすることが求められます。自社の人材を有効活用できるようコーポレート部門と協働しながら動くようにしてください。人事部門と連携し、デジタルスキルの習得を人事評価に組み込む、社内公募制度でDX人材を発掘するなど、制度面からのアプローチも必須と言えるでしょう。
未来から逆算してイノベーションを生み出す力
最も重要なのが、思考プロセスの転換です。従来の日本企業が得意としてきた「カイゼン(改善)」は、現状を起点に積み上げる「フォアキャスティング」のアプローチですが、非連続な成長が求められるDXには不向きではないでしょうか。
イノベーションを創出するためには、過去や現状を分析して未来を予測するフォアキャスティングよりも、未来のあるべき姿を想像してそこから逆算的に今何をすべきかを考えるバックキャスティングとしての考え方が求められます。
- フォアキャスティングの限界: フォアキャスティングは現在を起点として未来を予測するために、遠い目標を定めにくいというデメリットがあります。「今の予算・技術・人材でできること」に縛られ、小規模な改善に留まりがちです。
- バックキャスティングから考えるイノベーション創出力 :イノベーションを創出するためには、過去や現状を分析して未来を予測するフォアキャスティングよりも、未来のあるべき姿を想像してそこから逆算的に今何をすべきかを考えるバックキャスティングとしての考え方が求められます。
フォアキャスティングは現在を起点として未来を予測するために、遠い目標を定めにくいというデメリットがあります。
一方でバックキャスティングは、想像できる未来を起点として道筋をプロットするため、長期ビジョンを策定しやすいです。
過去の成功体験に縛られて革新的な未来を描けないという事態に陥ることを防ぐため、重要な視点といえます。
過去の成功体験に縛られて革新的な未来を描けないという事態に陥ることを防ぐため、重要な視点といえます。この思考法を組織全体にインストールすることが、DX組織の最大のミッションの一つです。
データで見える「組織の壁」と社内コミュニケーションの大切さ
組織の「箱(体制)」を作っても、その中を流れる「血液(コミュニケーション)」が滞っていれば、DXは機能しません。ここでは、株式会社ソフィアによる最新の「インターナルコミュニケーション(IC)実態調査2024」のデータを基に、DX推進を阻む「見えない壁」の実態と打破策を分析いたします。
気になるデータ:戦略への共感度は「わずか10%」?
調査結果の中で最も衝撃的なのが、「会社戦略への共感度」が約1割(10%)に留まるという事実です。
| 調査項目 | 結果 | DX推進への影響・示唆 |
|---|---|---|
| 会社戦略への共感度 | 約10% | 経営層が「DXで変革する」と高らかに宣言しても、9割の社員は腹落ちしていない。現場は「また上が何か言っている」と冷めた目で見ており、これがDXの浸透を阻む最大の障壁となっています。 |
| チャットツール導入率 | 76% | ツールの導入自体は進んでいるが、「活用度」には組織間で大きな格差がある。単にツールを入れるだけではコミュニケーションは活性化しません。 |
| 1on1ミーティング | 実施率1位だが「効果なし」 | 最も行われている施策であるにもかかわらず、「効果がない」と感じられている。形式的な面談が増えただけで、本質的な対話(Dialogue)が欠如している「1on1のパラドックス」が発生しています。 |
このデータは、DX推進における「笛吹けど踊らず」の現象を数字で裏付けています。経営層のビジョンが現場に届いておらず、ツールを入れても魂が入っていない状態と言えるでしょう。
コミュニケーションを良くする「3つの柱」
この状況を打破するために、以下の「3つの柱」をバランスよく強化することが提言されています。DX組織は、単なるシステム導入だけでなく、この3つの柱を用いたコミュニケーション設計を行う必要があるでしょう。
- 対話(Dialogue):
一方的な通達(Information)ではなく、双方向の対話が必要です。タウンホールミーティングや、役職を超えた座談会などを通じ、DXの目的(Why)について納得するまで話し合う場を設けます。形式的な1on1を見直し、心理的安全性(何を言っても否定されない安心感)を確保した上での本音の対話を促進します。
- 教育(Education):
デジタルツールへの忌避感を取り除くためのリテラシー教育です。使い方のマニュアルだけでなく、「これを使うと自分の仕事がどう楽になるか」「どんな新しい価値が生まれるか」というメリットを具体的に教育することで、能動的な活用を促します。
- ツール(Tools):
チャットツールやコラボレーションツール(Microsoft Teams, Slackなど)です。ただし、導入するだけでなく、運用の「作法」を浸透させることが重要です。例えば、「メールのような儀礼的な挨拶は不要」「スタンプでのリアクション推奨」など、スピード感を重視した独自のルールを設けることで、ツールのポテンシャルを引き出します。
部門ごとの「見えない壁」をなくすために
調査では「組織内のズレ(ミスマッチ)」や「部門の壁」も課題として挙げられています。DX推進組織は、この壁を壊すための「横串機能」を果たさなければなりません。
- クロスファンクショナルチームの組成: 課題ごとに各部門からメンバーを集め、部門の利益ではなくプロジェクトのゴールを共有する。
- 情報の透明化: 部門ごとのデータを全社で可視化し、情報の非対称性をなくすことで、相互理解を深める。
参考リンク
- 株式会社ソフィア「インターナルコミュニケーション(IC)実態調査2024」
DX組織づくりの成功事例
理論だけでなく、実際に組織変革を行い、成果を上げている日本企業の事例を深掘りします。これらの企業は、自社の文化や課題に合わせた独自の組織論を持っています。
住友商事:全社横断から「事業実装」への進化
住友商事株式会社は、住友商事グループ全体におけるICTやデジタル技術活用の重要性が高まっていることを機に、DXの推進をいち早く開始した日本企業です。
組織の進化
- 2016年: 全社横断組織「IoT & AIワーキンググループ」を発足。まずは有志や兼務者による「バーチャル組織」としてスタートし、知見の蓄積と社内ネットワークの構築を行いました。
- 2018年: 専任組織としてデジタル事業本部内に「DXセンター」を設置しました。より強力な権限と予算を持つ組織へと進化させました。
役割と成果
- このDXセンターが主体となって、デジタル技術の活用による既存事業のバリューアップ、新たなサービスの創出、さらに業界横断のビジネスモデル変革に向けて取り組んでおり、これまでに工場の稼働状況見える化、物流・倉庫事業の高度化、ホワイトカラーの生産性向上などを実現しています。
成功のポイント
- DX推進の専任組織であるこのDXセンター設置を機に、各営業部門・地域組織との連携をより一層強化していく考えを示しています。専門組織を「象牙の塔」にせず、現場である営業部門や地域組織と密接に連携し、泥臭く現場の課題解決に取り組んだ点が、社内の信頼獲得に繋がっています。
花王:「人」中心のDXを推進するSIT
花王株式会社では、グループのDXを推進するために先端技術戦略室(SIT)を発足しました。
設立の背景
- 長年にわたり蓄積されたデータを活用することが不可避の課題となっていましたが、当時は牽引できる部署がなかったため、先陣を切ってDXを推進する「ファーストペンギン」としてSITを立ち上げたといいます。
独自の哲学
- SITは、従業員が意欲的に取り組める仕事や、社会に対して価値を生み出せる仕事になることを主軸に置き、それらを先導できるシステムづくりを目指しました。
- 「効率化」や「コスト削減」を前面に出すのではなく、あくまでも主体は従業員であるとし、従業員が受け入れやすいシステム構築を目指したことが特徴です。「人に優しいDX」を掲げることで、現場の抵抗感を和らげ、自然な形でのデジタルシフトに成功しています。
NEC:「出島」を作らない、デジタル人材の活用
日本電気株式会社(NEC)もDXの推進に取り組む日本企業の一社ですが、同社ではDX事業を別会社にしたり、別組織として場所を隔離したりして推進する、いわば「出島」は不要だとしています。
組織戦略
- 同社ではDX専任組織として「Digital Business Office」を設置しましたが、これはDXを推進し、全社組織をシフトしていけるような体制として「デジタル人材」を組織の中に据えるという型であり、これまで挙げた2社のように切り出していないことが特徴です。
狙い
- DXを一部の特権的な部署の仕事にするのではなく、全社ごとの変革(コーポレート・トランスフォーメーション)につなげるため、あえて内部に組織を埋め込んでいます。
- これは、既に社員のITリテラシーが高いIT企業だからこそ可能なモデルとも言えますが、「DXが当たり前の業務になる」という最終的なゴールを見据えた高度な組織設計です。
その他の注目事例
- 島津製作所: 全部門を対象とした独自のデータ活用人材育成プログラムを展開し、現場主導のDX(内製化)を推進。
- ニトリホールディングス: 「製造物流IT小売業」を標榜し、システムの内製化を徹底。2025年までにデータ分析人材を1,000名規模で育成する計画を推進中。
- トヨタ自動車: マテリアルズ・インフォマティクス(MI)による材料開発の可視化など、研究開発部門(R&D)主導のDXで成果を上げています。
DX組織を成功させるためのステップとアジャイルな進め方
最後に、これからDX組織を立ち上げる、あるいは再編する企業が踏むべき具体的なステップを解説します。特に、変化の激しい時代に対応するための「アジャイル型組織」への転換が鍵となるでしょう。
小さく始めて大きく育てる!アジャイル型組織への移行
最初から巨大なDX組織を作り、全社一斉に変革しようとすると、調整コストだけで疲弊してしまいます。成功の鉄則は「小さく産んで大きく育てる(スモールスタート)」です。
PoCチームの発足
特定の課題(例えば、経理業務の自動化やある工場の予知保全)に絞ったタスクフォースを立ち上げ、短期間で成果を出します。この「小さな成功体験」が、社内の懐疑論を払拭します。
アジャイル型組織の導入
従来の「計画重視・ウォーターフォール型」ではなく、「仮説検証・アジャイル型」の組織運営を取り入れます。
- 権限委譲: 現場のチームに意思決定権限を与え、上長の承認待ち時間をなくす。
- 高速PDCA: 完璧な計画を立てるより、プロトタイプを早く作り、フィードバックを受けて改善するサイクルを回す。
- 失敗の許容: 「失敗=悪」ではなく、「失敗=学習の機会」と捉える文化を醸成する。
「丸投げ」をやめて自分たちで作る(内製化)
多くの日本企業が陥る最大の罠が、ベンダーへの「丸投げ」ではないでしょうか。DXのコアとなる企画力、データ分析力、アジャイル開発力は、社内に蓄積しなければなりません。
内製化の定義
全てのコードを自社で書く必要はありませんが、「何をどう作るか」を決定し、プロジェクトをコントロールするオーナーシップ(主導権)は自社で持つ必要があります。
パートナーとの関係性
外部ベンダーを下請けとして使うのではなく、共にビジネスを作る「パートナー」として対等な関係を築きます。
評価制度とキャリアパスを見直そう
DX人材が既存の評価制度(例えば、減点主義や年功序列)の中で評価されると、モチベーションが低下し、離職に繋がるのではないでしょうか。
ジョブ型雇用の導入
DX人材の専門性を評価し、市場価値に見合った報酬を提供します。
挑戦を評価する制度
失敗しても、そこから学びを得ていれば評価する「加点主義」への転換が必要です。
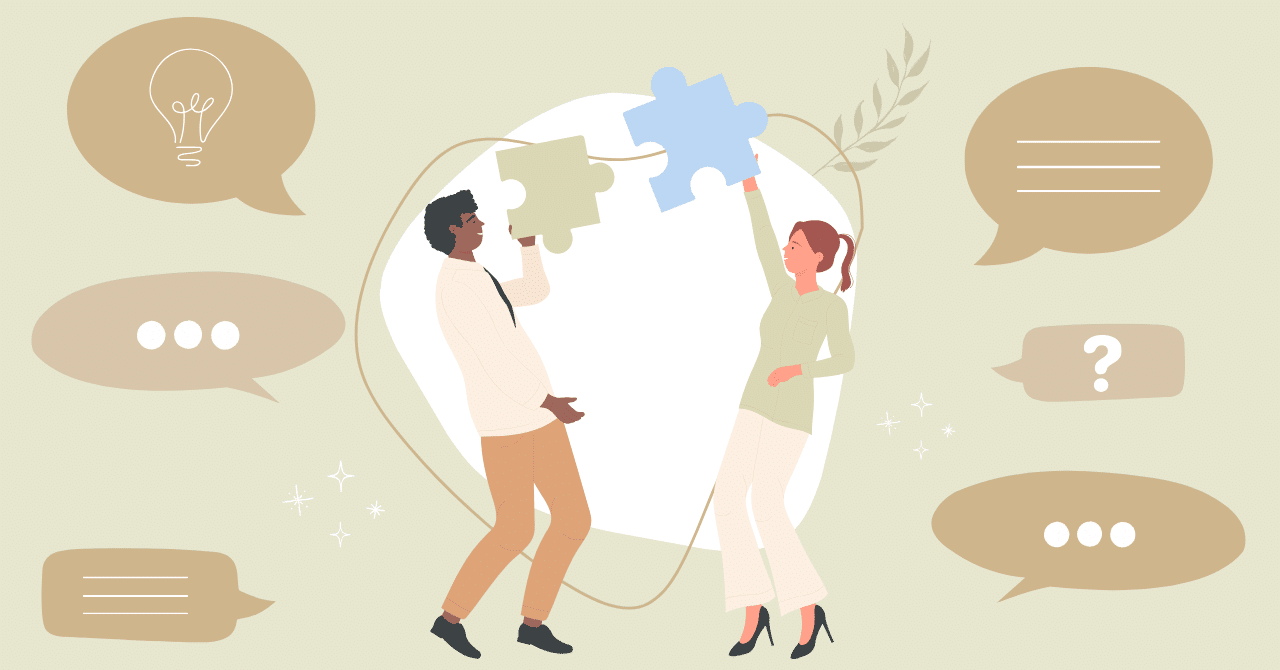
1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介
最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…
まとめ
今回は、DXというテーマの中で、「組織づくり」に主眼を置いて解説しました。実際にDXを推進する際は、こうした専門部署を設けることに加えて、その部署が主導して社内の各部署やパートナー企業と連携しつつ、様々な施策を推し進めていくこととなります。
DX推進組織は、単なる「箱」を作って終わりではありません。その箱の中で、社員がどのようなマインドで働き、どのようにコミュニケーションを取り、どうやって価値を生み出すか――その「文化」を醸成することこそが本質と言えるでしょう。
まとめると、以下の3つのポイントが重要です。
- 自社に合った「型」を選ぶ: IT拡張、事業拡張、専門組織のいずれが最適かを見極める。
- 3つのケイパビリティを磨く: 戦略実装力、人材育成力、バックキャスティング思考を組織に埋め込む。
- コミュニケーションの壁を壊す: 対話と教育で、戦略への共感度を高める。
これまでも様々な目的で日本企業は組織変革を行ってきました。組織変革の成果を出すには、変革した新組織が上手く社内外の関係者と連携して動けることが最も重要です。DXにおいてもその点は同様であることを忘れないようにしてください。
組織が変われば、人が変わり、人が変われば、ビジネスが変わります。DXという終わりのない旅路において、柔軟に変化し続ける「学習する組織」を作ることこそが、2025年の崖を越え、その先の未来へ進むための唯一の鍵となるでしょう。
関連サービス