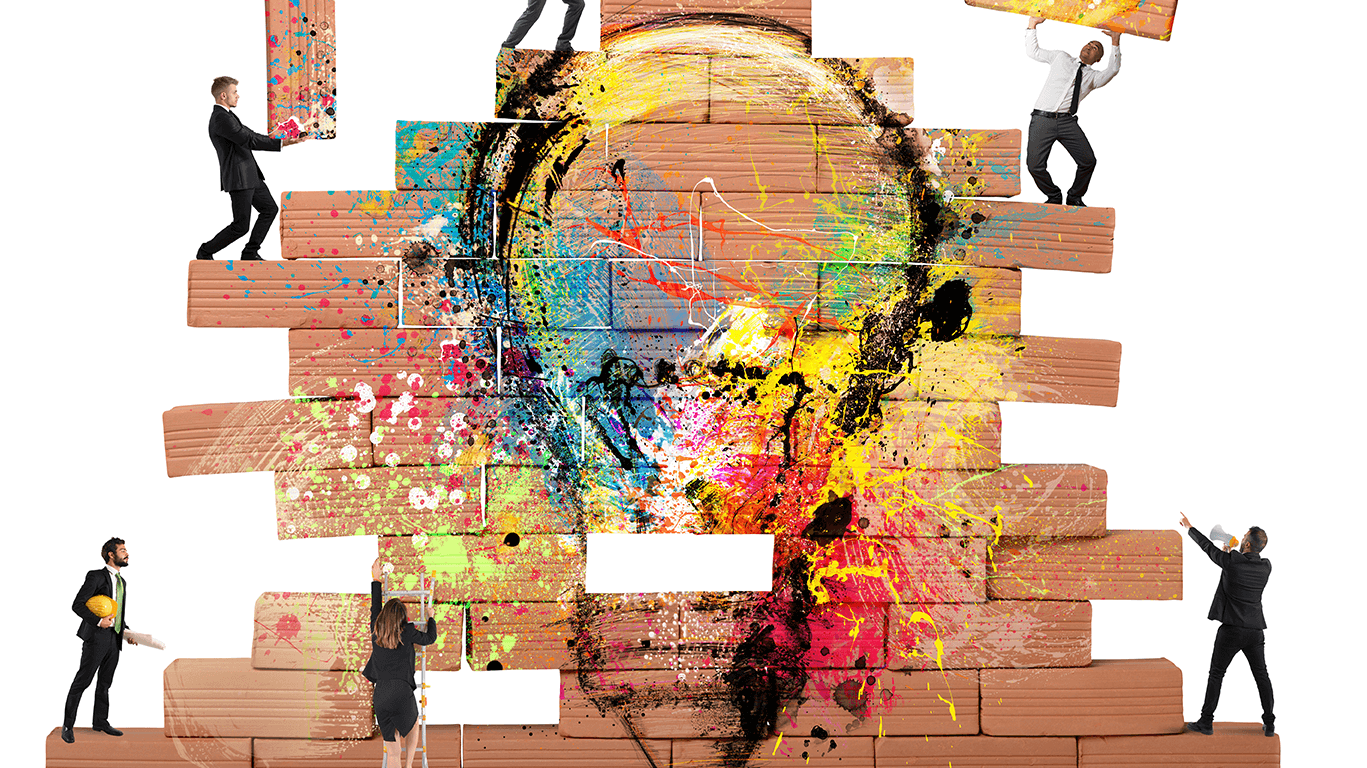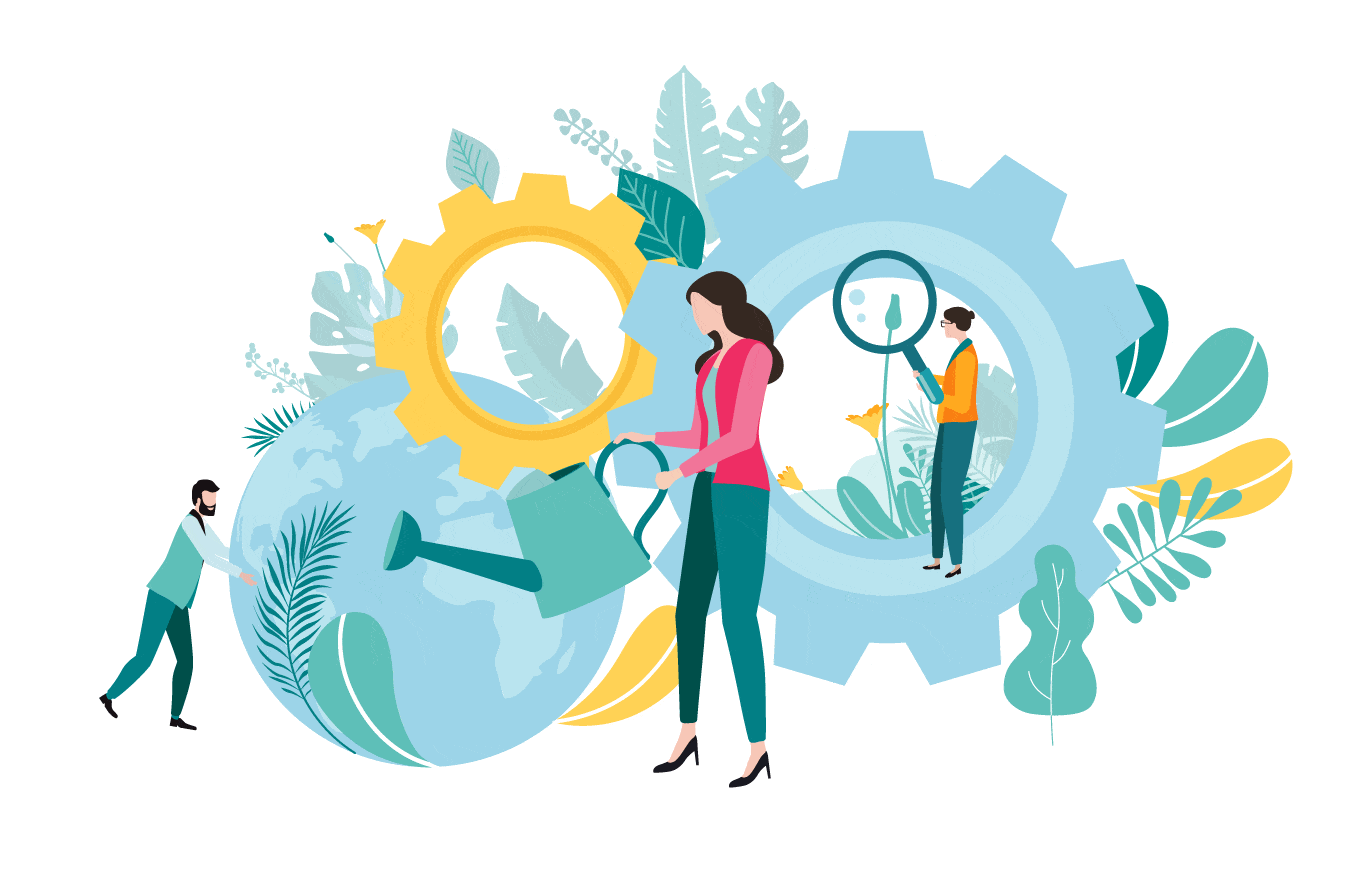企業の組織力向上の必要性とその方法について解説!
最終更新日:2023.10.19

目次
企業が生き残るために組織力を強化し向上させることは必要不可欠です。しかし、一口に組織力の向上といってもそのハードルは一般的に考えられているよりもずっと高く、その方法も多岐にわたります。
本記事では、企業が組織力を向上させる必要性と方法について解説します。
組織力とは
組織力にはさまざまな定義がありますが、ソフィアでは、組織力が高い状態を「組織内の意見調整や意思決定がスムーズに進む状態」であると考えています。
コミュニケーションが重要
組織のビジョン実現や戦略遂行に向けて日々の業務やタスクを行う上では、大小さまざまな意思決定が必要となります。そして、複数人の意見を調整して意思決定を行う際には必ずコミュニケーションが発生します。社会人が仕事の中で感じるストレスの多くは業務そのものではなく、人とのコミュニケーションに起因するのではないでしょうか。
就職・転職サイトを運営するエン・ジャパン株式会社の調査によれば、9割のサイトユーザーが「コミュニケーションの円滑さが仕事にも影響する」と回答しています。企業におけるコミュニケーションの重要性が調査結果からもうかがえます。
そもそも組織とは?
組織力が発揮される場所である「組織」とはそもそもどのようなものなのでしょうか。
アメリカの経営学者であるチェスター・アーヴィング・バーナード(1886-1961)は、組織が成立するための「3つの要素」を提唱しました。組織は2人以上の人々の間で意識的に調整された活動ないし諸力の体系であり、「コミュニケーション」「貢献意欲」「共通の目標」の均衡(アライメント)が取れていることが重要であるとしています。これによってバーナードは、「科学的管理法」で知られるフレデリック・テイラーと並んで称されるようになり、世界的な経営学者としての名声を確立しました。
また、アメリカの政治学者・認知心理学者・経営学者・情報科学者であるハーバート・アレクサンダー・サイモン(1916-2001)は、組織を「意思決定とその実行の過程を含めた、人間集団におけるコミュニケーションとその関係のパターン」であると定義しています。なお、サイモンは大規模組織の経営行動と意思決定に関する生涯の研究で、1978年にノーベル経済学賞を受賞した人物でもあります。
両者の定義は微妙に異なるものの、コミュニケーションが重要であることは一貫しており、組織にとってコミュニケーションが不可欠であることは、これまでの歴史の中でも言及されています。こうしたことからも、組織内の円滑なコミュニケーションが「組織力」につながると考えられるのです。
組織力が向上する企業の特徴
組織力が向上する企業には、どのような特徴があるのでしょうか。
企業のビジョンや価値観を社員が前提としている状態
組織力の高い企業では、社員一人ひとりが企業のビジョンに共感し、それに基づいた行動ができるため、自発的な行動の一致につながります。日頃から企業のビジョンや価値観に関心を向け、自らの行動が組織全体の方向性となることを理解しているので、組織全体が同じ目標に向かって進むことができます。
さらに、経営層と現場の連携が強く、明確に打ち出されたビジョンの浸透とともに、社員一人ひとりが企業のビジョンや価値観を体現し、共通の信念や行動様式によって、組織内で一体感や調和が生まれるのです。
社内のコミュニケーションが自由気ままな状態
次に、社内のコミュニケーションが公式であれ、カジュアルなものであれ、活発な状態であることがあげられます。社内のあらゆる情報が円滑に共有され、情報がすべての部署や従業員に適切に伝わる状態です。また、上司・部下間のコミュニケーションにおいても、フィードバックやリフレクションが当たり前のように行われていることで、チームのパフォーマンスが向上します。
このほか、意思決定のスピードと効率化にも影響を与えます。問題解決や新たなアイデアの実現が迅速に行われる背景には、従業員が意見やアイデアを自由気ままに発言し、受け入れてもらえる環境が整っていることで、従業員の参加意識や貢献度が高まります。さらに、従業員のモチベーションや満足度にもつながるのです。
ただ「自由気まま」と聞くと、ゆるく楽しく何でも話せるような関係をイメージする人もいるかもしれません。しかし、発言する側も、受け入れる側も、意見の相違などによって心の葛藤を引き起こすこともあります。そのような中で、お互い意見や感情を尊重し、落としどころを見つけられるようなコミュニケーションが必要不可欠なのです。
心理的安全性を保つことに努めている。
心理的安全性が保たれている組織では、意見やアイデアを発言しやすい環境が整っており、自分の考えを恐れることなく表現できます。他のメンバーと積極的に意見を交わすことが定着しているため、チームのクリエイティビティやイノベーションが促進されやすい状態といえます。
また、このような環境下では従業員の満足度も高まり、組織に対して強い結びつきを感じ、自己成長やチームの成功に貢献したいという意欲を持つことができます。
しかし、何でも言い合える環境であっても、そこに生産性がなければ「ぬるま湯組織」となってしまいます。そのためには、業務に対する意欲やモチベーションが従業員にあるかどうかをしっかり見極め、対応することが重要となります。
経営戦略に基づいた柔軟な人材が配置されている状態
経営戦略に基づいて人材が配置されることは、組織の目標達成に不可欠です。適材適所の配置により、各個人の能力を最大限に生かすことができます。また、人材の配置は組織内のチームワークを高める効果もあるため、チームメンバーが互いの役割や責任を理解し、協力し合うことで目標に向かって取り組むことができます。
また、柔軟な人材配置は組織の変化に対応する能力を高めます。経営環境や市場の変化に迅速に対応できるよう、必要なスキルやリーダーシップを持った人材を、適切なポジションに配置することが重要です。このような柔軟性がある組織は、変化に対応しながら成長し続けることができます。
人材育成制度が充実していて各々が成長を実感できる状態
各々が成長を実感できる状態であるということは、社員それぞれが自身の役割や責任を理解し、チームとしての目標に向かって取り組むことができるため、組織全体のパフォーマンス向上が期待できます。成果を実感できる環境が整っていることは、社員の仕事に対するエンゲージメントや高いモチベーションを持続させる要素となります。
そのためには、各階層における研修プログラムを充実させ、企業の文化や価値観を学ぶだけでなく、必要なスキルや知識の習得を積極的に提供しましょう。新入社員の研修のほか、中堅社員や管理職向けのリーダーシップトレーニングや、マネジメントスキルの研修も、同様のことが言えます。社員のキャリア開発をサポートする仕組みも整え、自身の能力や興味に応じて、さまざまなプロジェクトに参加し経験することで、異動や昇進の機会を得ることができます。
とくに、どのような場面においても社内コミュニケーションスキルは必要不可欠です。社内コミュニケーションにおける研修やワークショップなどを積極的に取り入れることが、組織力向上に有効となります。
企業に組織力向上が必要な理由
なぜ企業には組織力の向上、つまり、より「組織内の意見調整や意思決定がスムーズに進む状態」を目指すことが必要なのでしょうか。その理由を3つ紹介します。
不確実性の高い時代に対応するため
現代は、「VUCA(ブーカ)」と呼ばれる不確実性の高い時代であるといわれており、企業は外部環境の激しい変化、雇用の流動化、人材の多様化、勤務形態の多様化など、さまざまな変化に直面しています。このような社会情勢に適応するためには組織力向上が必須なのです。
数年先の未来でさえ見えない状況下で企業が生き残っていくには、企業のパフォーマンスを最適化していく必要があります。経営層と従業員が一つのビジョンを共有して同じ方向を目指しながらも、事業環境の変化に各々の判断で行動し、素早く柔軟に戦略や計画を修正できる能力が求められます。そこで、立場や部署に縛られないフラットなコミュニケーションが、組織力向上のカギとなります。
組織に多様な人材を集めるため
企業に組織力向上が必要な2つ目の理由は、組織に優秀な人材を集めるためです。
昔は多くの場面で企業が社員より優位に立っていましたが、今は人が働く場所を主体的に選択し、より良いキャリアを求めて転職する時代です。その変化の中で、企業が従業員に対して提供できる価値、すなわち「EVP(Employee Value Proposition)」の重要性が問われるようになってきました。EVPは金銭面などの面だけでなく、働きがい、モチベーションなど社員の内的な動機にもかかわってきます。また、若手社員は給与の多寡ではなく「成長できる環境」を求めて就職先を決める風潮も高まっています。
組織内のコミュニケーションが良好で、意思決定のスムーズな組織においては、従業員の体験価値(エンプロイーエクスペリエンス)が高まり、EVPの向上にもつながります。組織力の向上によって、優秀な人材の採用に有利な状況を作ることができるのです。

HR業界のトレンド「エンプロイーエクスペリエンス(EX)」とは?向上させるポイントを解説
エンプロイーエクスペリエンスとは「従業員の経験(体験)」。社員満足度・育成状況・スキル・働き方・心身の健康状態…
自身の企業活動や活動結果に対して見直し・振り返り・学習を行うため
3つ目は、組織力が高い状態が、組織の学習においても良い影響を及ぼすためです。組織力の高い企業では、目指すべきビジョンや共通の価値観が浸透しており、それらを判断の基準や指針にしながらスムーズに意見調整や意思決定ができています。こういった組織では、自分たちの企業活動や行動の目標について具体的なKPIを設定し、目指す状態に照らして結果がどうだったのか振り返りや見直しをすることができます。これらの取り組みは、より良い企業活動に向けた社員や組織全体の学習につながります。
一方、組織力が低い企業においては目指すべきビジョンや共通の価値観が浸透していないため、活動のKPIを設定し、共通の判断基準を用いた納得感のある振り返りを、組織全体で行うこと自体が困難です。しかし、たとえよそから借りてきた方法論や他社事例を参考に学習を重ねても、採用した方法論が自社に合っていなかった場合は、無駄な取り組みになってしまう恐れもあります。
組織力向上のために必要なこと
隅々まで目の届く規模の組織(職場、小規模ベンチャー企業など)の組織力を向上させることと、全体に目が届かない規模の組織(大規模組織、分業型組織など)の組織力を向上させることはまったく異なります。
小規模の組織であれば、トップが一人ひとりに直接指導できます。しかし大規模企業では、トップが一人ひとりに指導を行うことは不可能です。トップの目が行き届かない社員にも、企業の目指すべき姿を理解・共感してもらい、活動に反映してもらうことが、組織力向上において必要となります。
ここでは、大規模組織における組織力向上を行う際の、具体的な方法について解説します。
情報発信できる場を作る
情報発信できる場を作る必要性を、「コミュニケーションの活性化」と「失敗を許容する風土」の2点から見ていきます。
コミュニケーションの活性化
高い組織力の土台には、組織内の良好なコミュニケーションがあります。そしてそのコミュニケーションは、経営から現場に向けたトップダウンのみではなく、現場から経営への提案や、部署や部門を越えた状況の共有など、あらゆる方向から行うことが大切です。
コミュニケーション活性化に有効な方法の一つに、社員が気軽に情報発信できる場づくりがあります。現場の社員が情報発信する場のない組織は、社員が社内に意見やアイデアを表明するための方法として、上司を通じた提案や表彰制度への応募など、ハードルの高いものになりがちです。しかし、さまざまな人が自ら情報発信できる場があれば、失敗を恐れず意見やアイデアを表明する風土が醸成されやすくなります。
失敗を許容する風土
米Amazon社は、失敗を恐れない文化が浸透していることで有名です。CEOのジェフ・ベゾスは、以下のようにコメントしています。
- 『私たちが他社と一線を画す領域のひとつは「失敗」だ。おそらくアマゾンは、「世界一失敗できる会社」だと思う。発明と失敗とは紙一重であり、イノベーションを生むためには実験が欠かせない。けれど、はじめからうまくいくとわかっていることは実験とはいえない。多くの大企業は多くのアイデアを持っているけれど、失敗が続くことの苦難を喜んで受け入れようとしてはいない。』
失敗を許容できない風土は、無言の圧力を生み、社内コミュニケーションは不活発になり、結果として組織力の低い状態になります。
不確実性の高い社会で企業が生き残るには、新たなアイディアやイノベーションが欠かせません。失敗を許容する風土を浸透させ、安心して意見を言い合える関係性を社内に作り出すためには、気軽に情報発信する場を作る必要があるのです。そもそも、「失敗」とは「学びのための結果」にすぎません。考えを行動に移し挑戦した証でもあります。マイナスに捉えられてしまいがちですが、失敗があるからこそ学びが生まれるのではないでしょうか。
業務以外のコミュニケーションの場を用意する
組織力向上の土台となる社内コミュニケーションを活発にするには、社員が業務以外のつながりを持てるようにすることも必要です。部活動や勉強会、TGIFなど、組織内で業務とは別の人間関係を構築できる場があると、仕事上の上下関係や、部署や部門などの枠を越えたコミュニケーションを促す効果があります。そのため、業務にも良い影響を及ぼすことが期待できます。
組織力の向上を、企業そのものの変化につなげる
組織力を向上させるうえで、その土台となる社内コミュケーションの活性化が重要であることはこれまでお伝えした通りです。そして、企業におけるコミュニケーションのあり方が変わることで、企業の風土も変化します。つまり、なんらかの目的のため、組織力向上に取り組むプロセスは、企業そのものを変化させるプロセスでもあるのです。
ここでは、企業が組織力の向上に取り組む目的別に、コミュニケーション活性化のポイントをお伝えします。
新規事業創出のための組織力向上
これまでの企業活動にない新たな取り組みに全社を挙げて挑戦することは、リスクや苦しみは伴うものの、組織力を強化し向上させるまたとないチャンスであるともいえます。
新規事業を生み出すためには、企業のビジョンに立ち返る必要があります。そのためには、「企業が社会の中でどのような存在でありたいのか」「社会に対してどのような価値を提供していくべきなのか」、企業活動の原点となる考え方や価値観について、トップは積極的に情報発信を行いましょう。また、経営と現場との対話や、現場の中での対話を促しつつ、現場からの積極的な提案を経営側が歓迎する姿勢が必要です。こういった取り組みは、新規事業の創出のみならず、企業ビジョンの浸透、社内コミュニケーションの活性化にもつなげることができます。
新規事業の立ち上げは、苦難を受け入れながら、イノベーティブな実験を繰り返し行います。そこに関わる社員や、社内メディア等を通じて、その過程を見守る社員が企業ビジョンを体感することになります。こういった経験から、自社に新たな事業が加わるだけでなく、組織風土も新しくなり、組織力が強化されることでしょう。
既存事業の生産性改善のための組織力向上
既存事業を効率よく進めていくには、社員同士の密なコミュニケーションが不可欠です。ひとりで仕事をするのではなく、お互いにフォローし合う体制や、ボトムアップで改善案が生まれる環境など、組織内のあらゆる人が自分の力を発揮しやすい仕組みづくりが必要となってきます。
こういった取り組みも、組織のコミュニケーション活性化と組織風土の変革、結果として、組織力の向上に寄与します。
DXの推進、SDGs推進、働き方改革など、組織変革のための組織力向上
企業においてDXやSDGs、働き方改革などに取り組むには、組織における判断の軸や優先順位、仕事の進め方なども変化させていく必要があります。そのためには、組織の変革に向けた明確なビジョンや目標の共有と、それらに基づいた密なコミュニケーションが必要です。
ここでも、カギとなるのは経営から社員へのメッセージ発信や、経営と現場との対話、社員同士の対話です。そういった取り組みを通じて、掲げられたビジョンや目標に対する社員の理解、納得、共感を醸成し、社員がそれらの目標を自分事として発言したり、行動したりできる環境を作っていきます。それがゆくゆくは組織力の向上へとつながるのです。
まとめ
組織力の高い企業の特徴や組織力向上の必要性について、詳しく解説しました。
まず、組織力の高い企業の特徴として、経営トップのリーダーシップが挙げられます。経営者が明確なビジョンを持ち、それをチーム全体に伝えることで組織が一丸となります。また、社員が企業のビジョンに沿った行動ができていることも重要です。コミュニケーションが活発であり、社員同士が助け合いの精神を持って協力し合う環境が整っていることも組織力の特徴です。さらに、経営戦略を元にした人材配置や心理的安全性の維持、人材育成制度の充実なども組織力を高める要素となります。
一方、組織力の弱い企業の特徴としては、優秀な人材を集めることができず、自身の企業活動や活動結果に対して見直しや学習を行わない傾向があります。
組織力を向上させるためには、情報発信できる場や業務以外のコミュニケーションの場を作ることが重要です。さらに、企業そのものの変化に組織力の強化を結びつける必要があります。新規事業創出や既存事業の生産性改善、DXやSDGsの推進、働き方改革など、組織変革を促進する目標を明確にし、それに向けた組織力向上の取り組みが必要です。
組織力の高い企業を目指すためには、経営トップのリーダーシップや社員のビジョンに沿った行動、積極的なコミュニケーションの促進、適切な人材配置や育成制度の整備などが重要です。これらの要素を意識し、組織力の強化に取り組んでいただきたいと思います。