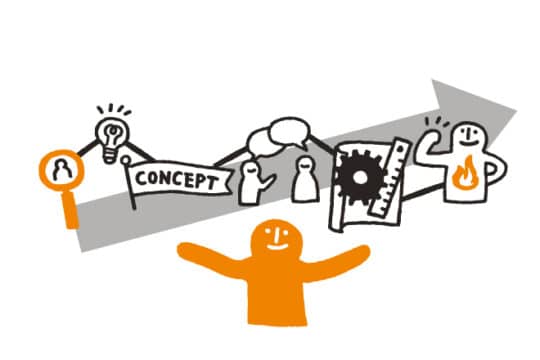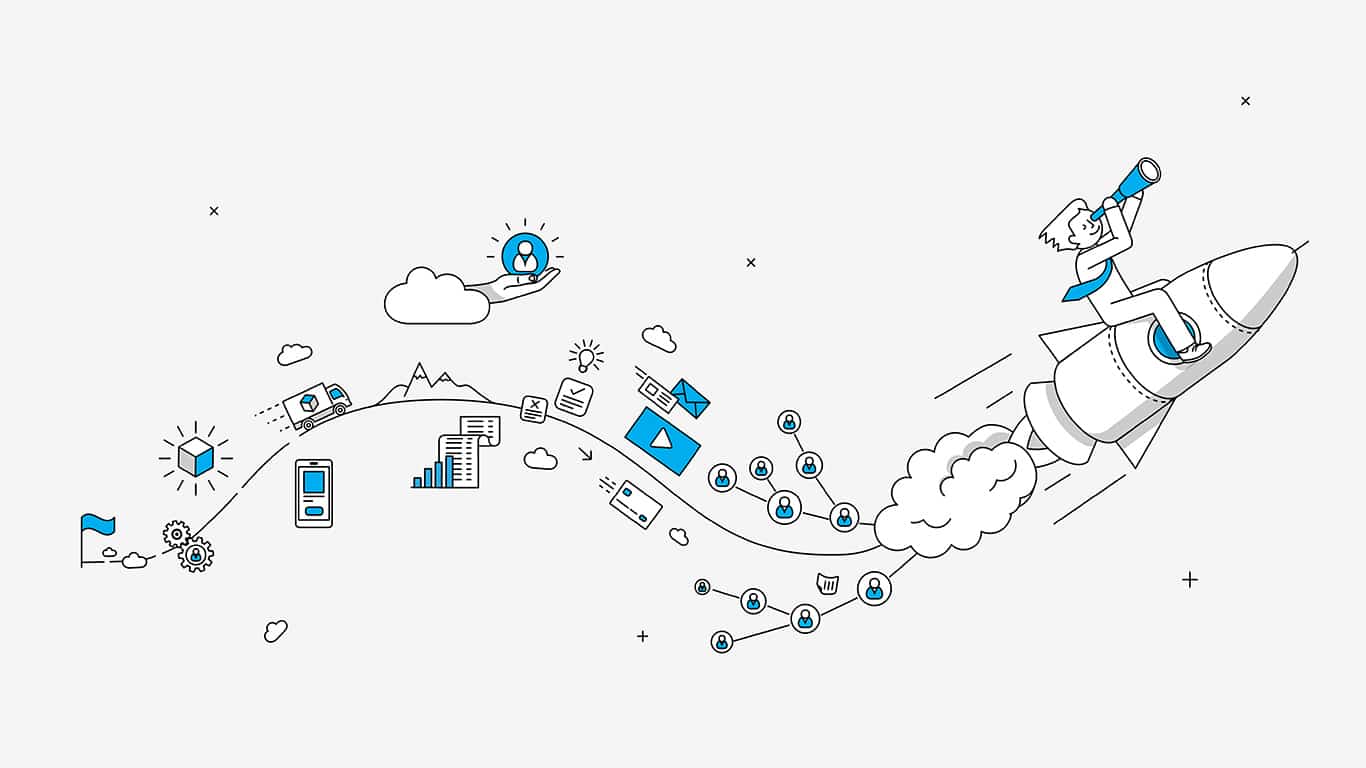営業部門が抱える7つの課題と組織強化における解決策を紹介!
最終更新日:2024.06.03

目次
営業部門は、企業にとって売り上げの創出を担う重要な部門です。しかし、多くの企業では営業部門がなんらかの課題に直面し、期待されている成果を出せていないということが少なくありません。
この記事では、営業部門で起きやすい課題にはどのようなものがあるのか、7つの課題を取り上げました。課題に対する解決方法についても解説しているので、営業部門のマネジメントを行っている方はぜひ参考にしてください。
社内コミュニケーションのソフィアが考える 『営業組織の構築』 とは?
セールスイネーブルメント
営業部門で起きやすい7つの課題と解決方法
以下では、営業部門に生じる7つの課題をご紹介します。それぞれの解決方法についても説明しているため、自社の営業部門の状況に応じてお役立てください。
課題① 組織的な営業の実行
【スタートアップや中小企業のケース】
こちらでよく見られるのは、営業関連の業務のすべてや場合によっては製品・サービスの提供関連業務も含めて一人の社員が行っているケースです。本来、営業先の獲得や商談、商品の発注、納品といった業務を複数人で分担することで効率化されますが、規模が小さい組織などは体制が整っていないため、すべての業務を個人プレーで行っていることが多くあります。
1人の営業担当に大きな負荷がかかるだけでなく、個人が処理できる業務量には限界があるため、商談数が少なくなったり、連絡の不備が多くなったりして売り上げが伸び悩むだけではなく、過剰業務負担による営業社員の離職を招くこともあります。
【メガベンチャーや大企業のケース】
こちらでよく見られるのは、分業による意識の低下です。インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサポート等、営業領域の活動を分けることにより、効率化はなされます。しかし、役割を明確に分けることで「売り上げをつくるのはフィールドセールスの仕事」という意識が強くなりすぎ、結果として売るチャンスを逃したり、顧客の課題解決のための提案をタイミングよくできなかったりして、売り上げが伸び悩みます。
解決策「負担分散と目的を見失わない仕組みづくり」
上述した前者(スタートアップや中小企業)の課題の解決には、インサイドセールスチームを設けるなど、組織を分けることで効率化を図るのが定石です。
ただし、後者(メガベンチャーや大企業)のようなケースは、組織を分けると組織間連携の齟齬が発生し、かえって効率を落とすこともあるため、業務設計やKPI設計、コミュニケーション設計をしっかり行うことが重要です。
課題② 業務の属人化問題の解消
業務が属人化しているケースも多く見られます。
本来であれば、各営業担当が蓄積しているノウハウや業務の進め方などは組織内で共有され、特定の個人がいなくても業務に大きな支障がない状態にすることが求められます。しかし、営業という職務特性上、属人化は比較的起こりがちです。とくにBtoB営業や高額商材を扱う営業は、型通りではなかなか好成績を上げられないことも多いため、実戦を通して個々がスキルを身につけていくこととなります。よって、ノウハウは個人の中に溜まりがちとなり、結果として優秀な営業担当の退職が、部門の成績を下げることにつながります。
解決策「営業ノウハウの可視化と伝承」
【新入社員・ローパフォーマーの場合】
業務が属人化している場合、解決策の1つとなるのが、マニュアル作成であると言われています。しかし、マニュアル化するには言語化・パターン化する必要があります。新卒社員向けなら、最低限のお作法を書いたものになり言語化やパターン化はそう難しくないでしょう。しかしながら、パフォーマンスを高く維持し続けるためのマニュアル作成はなかなか困難です。
課題となっているのが、ローパフォーマーの業務の属人化ではなく、ハイパフォーマーの業務の属人化であるのなら、それを解決するのはマニュアルではありません。
【ハイパフォーマーの場合】
ハイパフォーマーの業務の属人化を解決したい場合は、ハイパフォーマンスを上げている営業担当に動機付けをして、情報共有の場を与えることが良いでしょう。営業実績のある社員が積極的にノウハウを共有するようになれば属人化が回避されるだけでなく、営業部門全体の能力が底上げされます。
ノウハウ共有の基盤として、ファイルストレージ機能とコミュニケーション機能のあるツールを導入すると効果的です。チャットなどのコミュニケーション機能によりお互いのノウハウ活用が促されます。単にツールがあるだけでは活用されないということも起こりがちですので、マネージャー自ら率先して使い、ノウハウを共有した社員を賞賛する仕組みやインセンティヴを用意し、社員にノウハウ共有の動機を与えることも必要です。
もちろん、ノウハウが共有されただけで、ローパフォーマーやミドルパフォーマーがすぐにそのノウハウを使って高成績をあげられるわけではありません。そのノウハウを使って営業活動を行ったことで、顧客がどう反応したのか、うまくいったことや、うまくいかなかったことは何だったのかを振り返る場や、そういったことを組織で共有する場を用意することも重要です。そうすることで、そのノウハウはどういう状況で役立ち、どういう状況で役立たないのかという組織知を得ることにもつながります。
課題③ 成約率の伸び悩みの解消
成約率が低い状況が続くことは、営業部門の存在意義に関わる重要な問題が発生していると言えます。営業担当個人の成約率はそのスキルや経験に依存します。しかし、営業部門全体の成約率が低い場合は、何か顕在化していない大きな問題があると考えられます。
成約する見込みが薄い中で営業活動を続けると、営業担当のモチベーションも低下しがちです。成約を重視するあまり無理なアプローチをかけ、結果的に顧客の信頼を損ねてしまうことで、さらに売れなくなるといった悪循環も起こり得ます。
解決策「営業部員のマインド以外の部分で対処する」
一番簡単な方法として、営業部員を叱咤激励するという手段がとられることが多くあります。しかし、その方法でうまくいかないのなら、要因を探って、営業部員のマインド以外の部分にしっかり対処することが大切です。
組織全体の成約率が低い場合、商品・サービスが粗悪である、価格が不適切、ターゲットとしている市場(顧客)がマッチしていない、売り方が適切ではないといったことが考えられます。商品・サービスが時世にあっているか、同様の価値を提供する商品・サービスと比べて価格に問題はないか、顧客がいる可能性の高いリストに当たれているのか、個々の見込み客にあった売り方ができているのか、といった点を見直しましょう。
セールスプロセスが個人、もしくはチームとして管理できていないことも考えられます。適切なタイミングで適切なコミュニケーションをとり、記録することでプロセスの断絶を防ぎましょう。ITツールの自動リマインド機能などを使うことで抜け漏れを容易に防止することも可能です。
部署間の連携不足などの組織の問題が成約率を落としているケースもあります。マーケティングやインサイドセールス、営業、各セクションの情報共有がうまく行われておらず、顧客対応に不備が生じ、顧客の不信を買っていることも考えられます。現状をしっかりと把握し、問題を見つけて積極的に是正しましょう。
商品によっては、そもそも営業担当が手売りをすべきかどうかを見直す必要があるかもしれません。成約率が低く、利益率も低い、さらに営業担当のモチベーションも上がらない商品に関しては、場合によってはECサイトなどを使って販売を自動化できないか検討することも大切です。
課題④ 社員のモチベーション向上
社員のモチベーション管理は、営業部門にとって重要かつ困難な課題です。モチベーションが低い状態で営業活動に臨めば結果的に営業成果にも悪影響が生じます。
マネージャーや同僚、顧客とのコミュニケーションだけでモチベーションが上がるケースも多々ありますが、組織的な課題として取り組んでいく必要があります。
解決策「評価制度やその運用の見直し」
社員のモチベーションを刺激する最もシンプルな方法が、報酬制度・評価制度の導入です。「転職理由ランキング【最新版】みんなの本音を調査!(PERSOL調べ)」によると、総合1位は「給与が低い・昇給が見込めない」であり、5位に「会社の評価方法に不満があった」がランクインしています。(残念ながら最新のデータでは職種別のものは公開されていませんが、「転職理由ランキング2020年度<職種別>(PERSOL調べ)」によると、営業系職種では「給与に不満がある」が4位、「会社の評価方法に不満がある」が9位となっていました。)
成果に紐づいた魅力的な報酬制度と正当に評価される仕組みがある場合は、自然と社員のモチベーションが高まっていきます。若手や入社から日が浅い社員にとっては売り上げという明確な成果を上げるのがなかなか難しいケースも考えられますので、KPIとその報酬を設けるなど、プロセスを評価する仕組みも必要な場合があります。また、評価制度があっても適正に運用されず、「好き嫌い評価」と思われてしまうとモチベーションが下がりますので、都度運用のチェックや評価者研修を実施することも重要です。
また、個々のメンバーの能力や持っている顧客、市場(担当エリアなど)によって、KPIの設定が高すぎる、低すぎると感じられてしまうとモチベーションの低下要因となります。先述の調査によると、30代の転職理由の4位に「スキルアップしたい」がランクインしています。目標設定が高かったとしても無暗に下げるのではなく、組織的にフォローしながら目標達成させることで、達成感を与えると共に、給与・報酬も上げていくことができれば、モチベーションを維持向上することができるでしょう。いずれにせよ、個々のメンバーとしっかりコミュニケーションをとって目標設定をし、継続してフォローしていくことが大切です。
課題⑤ 若手などの人材育成
営業部門の未来を担う若手を育成できていないケースもあります。とくに営業担当が少ない営業部門では、日常的な業務に追われて若手の人材育成がおろそかになりがちです。 「転職理由ランキング【最新版】みんなの本音を調査!(PERSOL調べ)」の20代転職理由ランキングの3位には「社員を育てる環境がない」が入っていることから、若手社員に対する育成を十分に行わず、精神論のマネジメントで業務を推し進めると若手が早々に他社へと移ってしまうことも考えられます。
若手の人材育成は、新入社員研修の他は現場マネージャーや先輩社員に丸投げされているケースが多々あります。しかし、それぞれが数字のプレッシャーを抱えているため、どうしても「見て覚えろ」という教育になりがちです。
昨今では、TeamsやZoomなどのシステムを使ったオンライン営業が多くなっているのと共に、営業人員の採用が難しくなっていることもあり、「フルリモート勤務OK」と打ち出して採用を行っています。そのような環境においては、若手社員は先輩のオンライン営業へ同席し、見て覚えようとします。優秀な若手であれば、自主的に先輩の発言と顧客の反応を分析し、先輩に質問をすることで学びに変えていくことができますが、それができるのは少数です。
オンラインではなく訪問であれば顧客先への移動中に商談の前提が共有され、帰りに商談の振り返りが会話されることもあったでしょう。つまり、「見て覚えろ」と言いつつ、「自然と」前後のフォローができていたということです。しかし、現状のオンライン営業をベースとした環境では業務フローの中で「意図的に」そういった時間を作り出さなくてはいけません。そういった時間がとれるならば良いですが、高度に効率化されてしまったオンライン営業スタイルでは、次々とオンライン商談が入り、そのような時間がとれないこともよくあります。また、例え時間がとれたとしても、先輩社員の力量により指導のばらつきは大きくなりがちです。
解決策「現場の過度な負担とならない教育機会を提供する」
営業部門のリソース不足を補いながら、なおかつばらつきを抑えるために、外部の研修サービスを利用することは有効な手段となります。普段の業務で経験したことをあらためて研修の場で振り返ることで、それぞれの社員の中で知識として体系化できるようになります。
その際、選ぶ研修会社は、元スーパー営業マンが講師を務めるような研修よりも、自社の業務や状況に寄り添って研修を組み立ててくれる会社を選ぶと良いでしょう。なぜならば、研修を行って受講者が学びを得ることも重要ですが、その学びが現場で実践される(研修転移がなされる)ことがより重要だからです。現在の業務に即した実践的な学びを提供することが、すぐに役立つスキルを身につけることにつながります。また、研修後は研修内容を職場で共有し、マネージャーや先輩社員は研修が活かされるようサポートしましょう。
その他、社員が自発的に学習できるeラーニングなどもあると良いでしょう。
研修やeラーニングの他には、スキルやノウハウを共有するツール(ファイルストレージ機能とコミュニケーション機能があるもの)を用意し、そこで随時共有していくことで、若手に限らずベテラン社員も日々、他のメンバーに学びながら業務を遂行することができるようになります。勝ちパターンが言語化され、チームの垣根を越えて勝ちパターンが発信される営業組織は若手が実績をあげるのも早く、組織全体の成績が安定します。
課題⑥ モノ売りからソリューション型営業への転換
「ソリューション型営業」は、顧客の課題をヒアリングしたうえで、自社製品やサービスの活用による解決策を提案する営業です。対して、商品・サービスの単なる紹介に終始している状態は、いわゆる「モノ売り営業」と言われています。
モノ売り営業では、商品やサービスに決定的な優位性がない限りは、顧客にとっては購入する決め手がないため、価格勝負になりがちで、収益がなかなかあがりません。また、そもそも購買側にニーズがなければ話を聞いてさえもらえません。
そこでよく言われるのが「ソリューション型営業への転換」です。しかし、形だけ取り入れようとするとなかなかうまくいきません。よくある失敗は、大きく分けて二つあります。
【1、ヒアリングの失敗】
商談の第一声で「課題は何ですか?」と聞いてしまうケースです。よっぽど心が広いか、その商品やサービスに非常に興味が惹かれている担当者でなければ、いきなり自社の課題をペラペラと話し出すことはしません。結果、ものすごく浅い課題感が話されるか、いいから商品説明をしてくれと言われるか、ホームページ等に出しているからを読んでくれと言われてしまいます。
【2、課題と自社商材の紐づけの失敗】
顧客の課題を引き出せたとしても、それに連なる解決策を提示できていないケースは多々あります。新規商談において、相手が自社の課題について多く話をしてくれたのなら、1つハードルをクリアできたと言えるでしょう。しかしながら、いろいろ課題を聞いておきながら、定型的な提案がなされることも少なくありません。原因として、いろいろ聞いたは良いが、解決のストーリーが組み立てられないということが挙げられます。
解決策「事前の仮説構築と協働できる組織文化づくり」
ここで強調したいのはヒアリングの前準備です。顧客から話を聞く前にその企業のことをよく調べ、課題を想定しておくべきです。
「御社の課題は何ですか?」とストレートに聞いてしまうと、質問が漠然としすぎていますし、顧客側からすると営業担当が何を知りたいのか、何を教えると自分にとってのメリットがあるのかがわからないままでは、質問に答えようがありません。何かを答えてくれたとしても漠然とした回答になったり、営業側が自分達の商材では到底解決できない課題が話されたりします。 顧客との限られた対話の中で、ある程度自社商材の範疇において解決できそうな課題を引き出すためにも、インターネットなどであらかじめ情報を集め、課題を想定し、顧客にその仮説をぶつけた上でヒアリングしたり、仮説が正しいとした場合の他社事例を用意したりするなどの情報提供が重要です。
しっかり調べて仮説を準備した上で、その仮説をぶつけながら質問することで、たとえ仮説が外れていたとしても顧客から情報を引き出すことができます。そうして得られた回答をもとに、その会社にあった解決策を考えていきます。
仮説をもとにヒアリングすることで、まったく解決できない課題が出てくることは少なくなりますが、そうとはいえ、自社商材だけで解決できないものや、営業担当個人の経験では過去にない課題が話されるケースももちろんあります。そうした時に問われるのが、組織のナレッジや職場内または組織を越えた協働力です。組織で常にナレッジが蓄えられており、アクセスしやすい状態であれば、営業個人の知識・経験で対処できない顧客課題に対しても解決策を示すことが可能です。また、組織内で経験がなかったとしても、気軽に職場やさまざまな組織協働で解決策を練れる風土・文化があれば、対処することができます。
ナレッジの蓄積や協働できる風土・文化は一朝一夕ではできませんが、「ソリューション型営業」を標榜するのであれば、時間をかけてでもしっかりと構築していく必要があります。

ナレッジマネジメントとは?AI活用と失敗しない導入手順【2025年版】
ナレッジマネジメントの定義からSECIモデル、ISO30401、最新の生成AI(RAG)活用までを網羅。組織の暗黙知を資産に変え…
課題⑦ 営業のDX(デジタルトランスフォーメーション)
DXとは、総務省の情報通信白書で定義づけされていますが、一般的にDXと言った場合、デジタルに引っ張られてデジタルツールを導入し、使用することをDXと考えがちです。しかし、デジタルは手段であり、目的は『価値(顧客提供価値)を創出し、競争上の優位性を確立すること』です。
したがって、営業組織もデジタルを導入・活用することで価値を創出し、競争上の優位性を確立することが重要です。営業の顧客提供価値とは、顧客や世間の顧客候補に自社および自社製品やサービスの存在を知らせるとともに、課題⑥で述べたように、個々の顧客(候補含む)に解決策を提示することで選択肢を提供し、購入してもらうことで顧客課題を解決することです。
国内BtoB商材であれば、国内368万社のうち、ターゲットを絞った上で、上記目的をもってアプローチすることになります。昨今のデジタル技術の進歩により、アナログ的なアプローチより数多く、より効率的にアプローチができるようになりました。
自社の商品やサービスで解決できそうな課題を意識的・無意識的に持っている企業に、既存の自社の人的リソースで、より数多く、より深くアプローチできる状態にすることが、営業のDXです。
しかし残念ながら、こういった目的が意識されぬまま、最新のSFAやMAなどのツールが導入され、結果として十分に活用されないまま、ツールの費用だけが膨らんでいくという状態に陥る営業組織も増えています。営業社員は、訳もわからぬまま入力業務が増え、その分顧客に向き合う時間が減るという本末転倒の事態が起こっています。
解決策「ありたい状態や営業部員の心理も考慮したツール導入と運用」
営業のDX化を進めるためには、まずは営業組織としてどうありたいかを考えてみると良いでしょう。「客層を中小企業から大企業へ広げる」「客層を大企業に絞り、客単価を上げていく」「個別に人が介在することなくデジタル上でリード育成し、アポイント獲得をできる限り自動化する」「フィールドセールス担当者が顧客(候補)に接する前にデジタル上の接点において、その顧客の興味関心を捕捉することで、初回から仮説提案ができるようにする」など、観点としてはさまざまあります。
まずは制限を設けず“ありたい姿”を出してみて、幹部だけでなく若手の意見も取り入れながら、自社の営業DXで目指す状態を描きましょう。
その際、「自社の儲け」の観点はもちろん重要ですが、「顧客への価値提供」もセットで考えるようにしましょう。理想の状態を描いたら、業務の棚卸をするなどして現状を確認しましょう。その際、何にどれだけ時間がかかっているかなど定量的なものを確認するだけではなく、何が嫌なのか、何にストレスを感じているのかという心理的な部分も含めて把握するようにしましょう。面倒だなと思うかもしれませんが、情報通信白書のDXの定義に記載してある「内部エコシステムの変革」には必要な手続きです。
ありたい状態(トランスフォーメーション後の姿)と現状を確認したら、有効な施策を考え、その施策を推進するのに役立つツールを選定しましょう。ツールは理想的な業務を実現するための手段であるということを意識することが大切です。ツールを導入する場合はその目的(導入によっていかに顧客提供価値が増大し、自社競争力が高まるか)についてもセットでしっかり営業メンバーに浸透しましょう。導入したら終わりではなく、メンバーをしっかり巻き込みながら運用し、成功・失敗を繰り返しながら自社にあった運用方法を確立していきましょう。
同じ組織がこの世に二つとないことを考えると、自社が抱えている課題は基本的には自社独自のものです。また、ツールの導入には決して安くはない費用が発生します。そのため、他社の成功事例を鵜呑みにし、ツールを安易に導入するということは避けましょう。ツール導入の効果が感じられない場合は、ありたい姿と現状の確認に立ち戻ってから、運用設計を見直すと良いでしょう。
まとめ
多くの営業部門が今回ご紹介した課題に直面しています。読んでいただいてわかる通り、単一的な仕組みの導入などでは決して万能なソリューションとはなりません。複雑で複合的な取り組みが必要となります。
ソフィアは、貴社の営業部門が直面しているさまざまな課題に応じて、貴社における適切な解決策の導出や、実行をサポートします。営業部門の課題解決にお困りの場合は、ぜひソフィアにお問い合わせください。