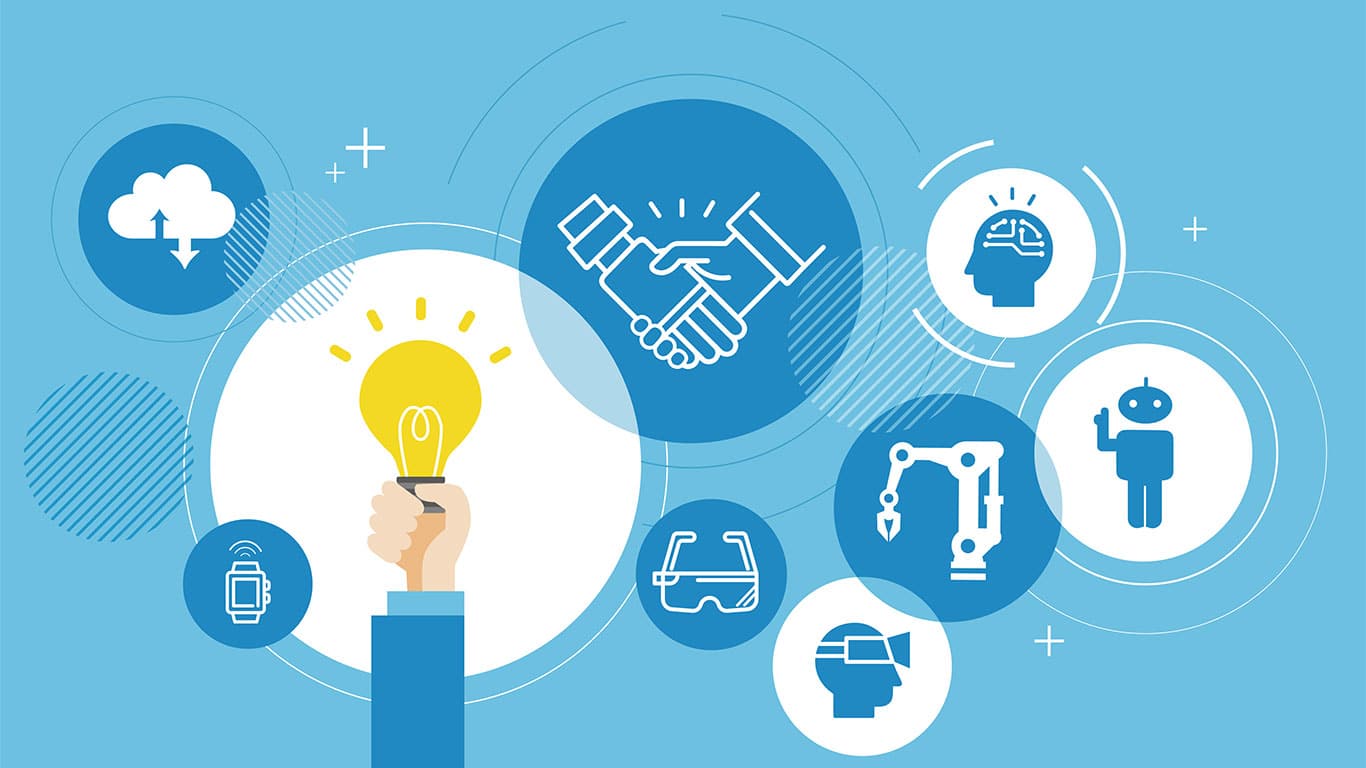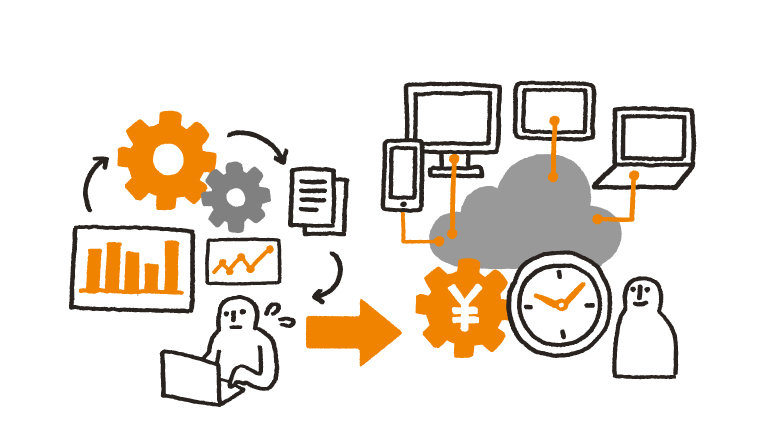【事例で解説】社内コミュニケーションを活性化するメリットや施策とは?

目次
ビジネスの多様化に伴い、社内コミュニケーションの在り方は変化を続けています。そのような状況下で多くの企業が社内コミュニケーションに課題を感じつつも、抜本的な改善にはいたっていません。社内コミュニケーションが活性化されていないと生産性の低下や離職率の上昇といった問題を引き起こすでしょう。
ここからは社内コミュニケーションを活性化させるメリットや、具体的なアプローチ方法を詳しく解説します。社内コミュニケーション活性化に成功した代表的な事例も交えてご紹介するのでぜひ参考にしてみてください。
社内コミュニケーションとは
社内コミュニケーションとは、社内で行われている会話や情報共有など社員同士のコミュニケーションを指し、プライベートのコミュニケーションとは異なる性質を持っています。同一組織内における社内報や社内セミナー、対話集会といったインターナルコミュニケーションを通して社内コミュニケーションは活性化されます。インターナルコミュニケーションには3つの目的があります。
1つ目は経営層から社員へトップダウンで行うコミュニケーションです。経営理念やビジョンを共有し、組織風土を形成します。
2つ目は現場の社員から経営層に課題を定義するボトムアップのコミュニケーションです。現場で実際に起きている現状を経営層が把握し、課題解決のための行動を取ることができます。
3つ目は部門間、社員間のコミュニケーション活性化です。別の部署でどのような取り組みをしているのかが見えないと、組織の生産性向上の妨げになるだけでなく新しいアイデアの捻出や気付きを得ることができません。インターナルコミュニケーションで社内の情報共有が活性化していると、会社全体を理解しやすくなるメリットがあります。

多くの企業が社内コミュニケーションに課題を抱えている
日本経済は年功序列、終身雇用、企業内組合という日本的経営のもとに成り立っていました。しかしグローバル化によりコミュニケーションの対象が国内外に広がったことや、派遣・外注・嘱託など雇用形態が異なる従業員が増えたことを背景に、転職、出向、外部連携がいつでも起こる状態に変化しました。
このような状況下において、「阿吽の呼吸」「以心伝心」といった日本の伝統的コミュニケーションは通じなくなってきています。HR総研の「コミュニケーションに関する調査」では7割以上の人が社内コミュニケーションに課題があると答え、9割以上の人が社内コミュニケーション不足は業務の障害になると答えています。多くの企業が社内コミュニケーションに課題を抱えていると同時に、抜本的な改善にいたっていないのが現状です。
社内コミュニケーションの重要性
社内コミュニケーションの不足は、組織全体の生産性の低下、社員のモチベーション低下や離職率の上昇、イノベーティブなアイデアが捻出されない、といった業績にも関わる問題を引き起こす可能性があります。
しかし現代社会の企業は社内コミュニケーションが取りにくい環境に置かれています。上記でも解説したようにグローバル化によって同じ文化や言語でコミュニケーションを取ることが難しくなり、日本独自のコミュニケーション手法は通用しなくなっているのです。
また、企業内でのサイロ化も大きな課題です。部門間で業務が完結し、利用しているシステムが独立している状態では、部門間の連携が取れません。企業内の縦割り構造が社内コミュニケーションを阻害しています。さらに、雇用形態の多様化や遠隔地で仕事をするテレワークの推進も社内コミュニケーションを複雑にしている要因です。
企業がおかれている環境が変化した際には社内コミュニケーションの在り方を見直し、改善を続けていくことが必要です。社内コミュニケーションが活性化すれば多くのメリットが得られるでしょう。具体的なメリットは次の見出しで後述します。
社内コミュニケーションの活性化に多様性をつなぐことで生まれるメリット
多様性や複雑性は外部環境や競争環境からの要求事項であり、これがイノベーションや生産性を産み出します。
しかし社内コミュニケーションを強化し多様性をつないでいかない限りは、多様性におけるメリットは享受できません。
つまり、多様性や複雑性と社内コミュニケーションをセットで考えることが重要です。ここからは多様性を社内コミュニケーションでつなぐことで生み出されるメリットについて解説していきます。
社員エンゲージメントの向上
社員エンゲージメントとは会社に貢献したいという帰属意識や愛着を表す言葉です。終身雇用であれば勤続年数が帰属意識を産みます。
しかし転職が常態化し人材の流動性が高まる中で社員エンゲージメントを向上させるためには、より社内コミュニケーションの活性化に注力しなければなりません。派遣や外注、嘱託など雇用形態が違う社員同士が同じ職場で働くことも増えました。
このような多様な人材を社内コミュニケーションでつなぐことができれば、社内の情報共有が活発になりインプットする情報量が増加します。
会社が目指しているビジョンや部署を越えた取り組みを知ることで働く意味を自分の中で確立できるようになるでしょう。主体的に業務に取り組むようになり、業績向上にも期待ができます。
離職率の低下
会社を辞める理由の多くは人間関係によるものです。相談したいことがあっても言い出しにくい雰囲気があり、会社で孤立をしていれば会社を辞めたくなります。
とくに人材の流動が激しい現在では、複雑なコミュニケーションが求められますが、うまくいかなければ、社員にストレスがかかってしまいます。そのため、企業内において多様な人材をつなぐことができるような社内コミュニケーションが必要です。コミュニケーションが活発な組織は、良好な人間関係を築くことができ、仕事の悩みを相談しやすい環境であれば、ストレスを溜め込む必要がなくなります。
また、同僚とのランチや飲み会を通してリフレッシュすることも、離職率を低下させることに有効です。社内コミュニケーションの活性化は、より良い人間関係やメンタルを良好に保つだけでなく、エンゲージメントにも影響を与えます。そのために、企業における社内コミュニケーションの取り組みや上司と部下における双方向のコミュニケーションの活性化を行うことが大切です。
生産性の向上
多様性を社内コミュニケーションでつなぐと生産性が向上します。社内コミュニケーションの活性化で部署間での連携が円滑になり、これまでになかったイノベーティブなアイデアが生まれるかもしれません。トラブルが起こった際も、部門間で連携して対応することができるでしょう。
社内で円滑なコミュニケーションが取れることで、業務上で生じる課題をスムーズに解決することも可能となります。顧客からの要望を自分だけで解決するのは限界があり、上司に報告をして会社としての対策を取ることが求められます。報告、連絡、相談、が活性化されると提供するサービスの品質や業務スピードが向上します。
社内コミュニケーション活性化に効果的な施策アイデア(社内コミュニケーションツール)
社内コミュニケーションツールの活性化に向けた施策やアイデアに焦点を当て、効果的なコミュニケーションツール導入のメリットや成功事例について探究していきます。
チャットツール
チャットツールはリアルタイム性が高く、迅速な情報共有やコミュニケーション促進に役立ちます。従来のメールよりも手軽に利用でき、質問や相談・アイデアの共有などがスムーズに行えます。さらに部署や立場を超えてコミュニケーションが促進されるため、組織全体の情報共有や意思疎通が円滑になります。
チャットツール導入の際は、適切な使い方やルールを定めることが重要です。たとえば、業務時間外の利用を制限する、情報の整理整頓を徹底する、適切なコンテンツ管理を行う、など効果的な利用のためのガイドラインを策定することが必要です。
web会議
テレワークやリモートワークが増える中で、web会議はオフィス外の従業員同士でもコミュニケーションを円滑に行うための貴重なツールとなっています。地理的な距離を超えたコミュニケーションが容易になり、リアルタイムで多くのメンバーが参加し意見交換や情報共有が可能となります。さらに、ビデオ会議機能を使用することで、非言語コミュニケーションも促進され、コミュニケーションの質が向上します。重要なポイントは適切なweb会議ツールを選定し、全従業員が容易にアクセスできるようにすることです。また、適切な設定やトレーニングを行い、円滑なweb会議の運営ができる環境を整えることも重要です。
社内報
社内報は組織全体に情報を伝達し、メンバー同士の共有を促進するためのコミュニケーションツールとして機能します。社内報を通じて、経営方針や会社のビジョン、業績、重要なプロジェクトの進捗状況などの情報を従業員に適切に伝えることができます。そのため、組織全体の方向性を理解しやすくし、従業員のモチベーション向上や組織への帰属意識を高める効果も期待できます。
定期的な発行やデジタル化などの工夫によって、効果的かつ効率的に情報を提供することができます。さらに、社内報を双方向のコミュニケーションツールとして位置付け、従業員からのフィードバックや意見を収集する仕組みを導入することで、より活発なコミュニケーションの構築につながるでしょう。
社内SNS
社内SNSを導入することで、社員同士のコミュニケーションを促進し、情報共有や交流を円滑に行うことが可能です。社内SNSはリアルタイムで気軽に投稿できるため、業務上の質問や意見交換、日常の近況報告などがスムーズに行えます。さらに、同じ部署以外の社員との交流も可能となり社員同士のつながりを深められます。 また、グループチャット機能やファイル共有機能などが備わっておりプロジェクトチームや部署内の連携強化にも役立ちます。上司や管理者と部下やチームメンバーとの距離を縮め、コミュニケーションの壁を取り払う効果も期待できます。

コミュニケーション手段に最適な社内SNSとは?おすすめツールの紹介
社内SNSツールはコミュニケーション活性化の有効な手段です。社内SNSとは、FacebookやInstagramなど誰もがフォローで…
社内YouTube
社内YouTubeを活用することで情報の共有やコミュニケーションの促進が可能となります。具体的な施策として、社内YouTubeチャンネルを作成し社内イベントやトレーニング動画、社長メッセージなどを定期的に配信することが挙げられます。また従業員同士の知識共有やアイデア発信の場として活用することで、意見交換やコラボレーションを促進することができます。
ファイル共有
ファイル共有は社内コミュニケーションの効率化に欠かせない要素です。まずクラウドストレージサービスを活用することでファイルへのアクセスを容易にし、リアルタイムでの共有や編集が可能となります。
さらに共有フォルダやプロジェクトごとの専用フォルダを設けることで、情報の整理や管理を効果的に行うことができます。 またバージョン管理システムを導入することでファイルの更新履歴を管理し、誤った編集や情報の混乱を防ぐことができます。定期的なファイル整理や整頓を促す取り組みも重要です。
タスク管理
社内SNSやチャットツールを使用することでタスクの進捗状況をリアルタイムで共有し、メンバー間での連携を強化することが可能です。さらに、タスクごとに専用のチャットグループを作成し状況や問題点をすばやく共有することで円滑なタスク管理が実現できます。
また、タスクの重要度や緊急度に応じた優先順位設定や期限の設定機能を活用し、タスク全体の可視化を図ることで、スムーズな業務進行が可能となります。さらに進捗状況や成果を定期的に報告するための機能を活用し、チーム全体での情報共有を促進することでタスク管理の透明性と効率性を向上させることも可能です。
社内コミュニケーション活性化に効果的な施策アイデア(対面・イベント)
対面・イベントを活用した社内コミュニケーション活性化の施策に焦点を当て、その効果的な展開方法や成功事例について探求します。
1on1ミーティング
この形式は直接的な対話を通じて上司と部下、同僚同士の信頼関係を構築し、コミュニケーションを円滑にするのに役立ちます。1on1ミーティングを成功させるためには以下の点に留意することが重要です。
まずミーティングの目的や議題を明確にし、共有しておくことが重要です。次に、お互いの意見を尊重しオープンな気持ちで対話することで建設的なコミュニケーションを促進します。さらにフィードバックや改善点に対する受容性を高めることで、相手の声に耳を傾け、協力関係を築くことができます。
1on1ミーティングでは相手の意見や感情に対して真摯に向き合い、問題解決や目標達成に向けた具体的なアクションプランを立てることが重要です。このように、適切な準備やコミュニケーションスキルを活かすことで1on1ミーティングは社内コミュニケーション活性化に効果的な施策となります。
社内サークル・部活
社内サークルや部活動は社員同士が共通の興味や趣味を持ち、それを通じてコミュニケーションを深める機会を提供します。たとえば、読書サークルや料理サークルなど、様々なテーマをもとにしたグループを作ることで社員同士の交流が促進されます。また、定期的に開催されるイベントや活動を通じて社内のコミュニケーションを活性化する効果が期待されます。
社内サークルや部活動は社員のストレス解消やリフレッシュにも役立つことが多いため、働きがいやチームワークの向上にも寄与するでしょう。
シャッフルランチ
シャッフルランチは従業員がランダムにグループ分けされ、ランチを共にする取り組みです。これによって社内の横断的なコミュニケーションを促進します。普段一緒に仕事をすることが少ないメンバー同士が交流できる機会となり、新しいつながりを築くことにもつながります。シャッフルランチを通じて、部門間の垣根を取り払い、社員同士の理解を深めることができるでしょう。さらに、異なる立場や経験を持つ人々が交流することで新たなアイデアや視点が生まれる可能性も高まります。
社内コミュニケーション活性化に効果的な施策アイデア(設備)
設備面での改善や新たな設備を取り入れることで、社内コミュニケーションの活性化を促す施策に焦点を当て、その効果的な展開方法や成功事例について探求します。
社員食堂やカフェ
社内食堂やカフェは社員同士がリラックスした雰囲気でコミュニケーションを取る場を提供し、業務時間外でも交流が促進されます。
社員食堂では、定期的にテーマランチや特別メニューを提供し、新しい話題や興味を共有しやすい環境を作ることもできます。またカフェスペースでは、コーヒーや軽食を楽しみながら気軽に会話ができるようなデザインや設備を整えることが重要です。
さらに、定期的なイベントやワークショップを開催し、社員同士の交流を深めるといったアイデアも効果的です。
社内バー
社内バーを設置することで仕事の合間や終業後に同僚とリラックスしてコミュニケーションを取ることができ、チームビルディングや社内ネットワーキングの場として有効です。また、社員同士がオフィス外でのコミュニケーションを楽しむ必要がなくなり、業務効率を向上させる効果も期待できます。お酒だけでなくノンアルコールドリンクや軽食なども提供することで、より多様な社員のニーズに対応することが可能です。
ただし社内バーを導入する際には、アルコール管理や社内ルールの明確化など適切な運営が求められます。
ミーティングスペース
ミーティングスペースは効果的なコミュニケーションを促進し生産性を向上させるために欠かせない要素です。
ミーティングスペースの配置は重要であり、オープンスペースに配置することで社員同士のコミュニケーションが活性化する効果が期待できます。またモバイルホワイトボードやデジタルボードを設置することで、アイデアの共有や議論を円滑に進めることが可能となります。さらに、ビデオコンファレンス機能を備えばリモートワーカーや他の拠点とのミーティングもスムーズに行えます。
快適な座席や照明、エアコンなどの設備も社員の集中力を高め、効果的なミーティングを実現するために重要です。最新のテクノロジーを活用しインタラクティブなコミュニケーションを促進するミーティングスペースを整備することが社内コミュニケーション活性化に効果的な施策となるでしょう。
リフレッシュスペースの確保
リフレッシュスペースは会議室やオフィス作業スペースとは異なり、くつろげるソファや椅子、植物などを配置しリラックスできる環境を整えることが求められます。
またリフレッシュスペースに音楽を流す装置や読書スペース、ボードゲームなどのアクティビティを取り入れることで従業員が日常の業務から離れてリフレッシュできる場を提供することができます。さらにコーヒーマシンや軽食の設置など身近なものを用意することで、気軽に交流が生まれやすくなります。最適なリフレッシュスペースは従業員の健康や働きやすさだけでなく、コミュニケーション促進にも効果を発揮します。
フリーアドレス制度
フリーアドレス制度は従業員が自由に席を選べる取り組みです。社内の壁を取り払い、部署間や階層間のコミュニケーションを促進する効果があり、新しいつながりが生まれやすくなります。また柔軟性が高まり、創造性やアイデアの共有を促進する効果も期待されます。
従業員が異なる部署やチームのメンバーと隣接して座ることでコミュニケーションが円滑になり、情報共有も活発に行われます。情報のシームレスな流れが生まれ、業務全体の効率化につながります。
ただしフリーアドレス制度を導入する際には従業員のプライバシーや集中力の確保などの課題があります。適切なスペースの確保やプライバシーを配慮した工夫が必要です。
社内コミュニケーション活性化に効果的な施策アイデア(その他)
社内コミュニケーションを活性化させる上記以外の施策も紹介します。
サンクスカード
サンクスカードは従業員同士や上司から部下への感謝や労いの気持ちを伝える手段として利用されます。この取り組みは従業員間の関係性を強化し、チームの結束力を高める効果が期待されます。
サンクスカードを通じてメンバーがお互いに気持ちを伝え合うことでコミュニケーションの円滑化が図られます。さらに従業員のモチベーション向上にも貢献し、業績向上につながる可能性があります。業員間の信頼関係や励まし合いの文化を育むことで、より良い職場環境が構築されるでしょう。
ただしサンクスカードの配布が定期的に行われ、率先して積極的に感謝の気持ちを示す文化が根付いていなければ効果は発揮されないでしょう。従業員が自由に感謝のメッセージを書き、配布できる仕組みの整備が必要です。
全社員出社日の設定
全社員が同じ日にオフィスに出社することでチームビルディングやコラボレーションが促進され、社内コミュニケーションが活発化します。ただ出社するだけではなく、出社日には社内イベントやワークショップを開催し全社員が参加できる機会を設けることで交流を深めることができるでしょう。また定例のミーティングや情報共有の時間を設けることで、全体の目標や進捗状況を共有し一体感を醸成することができます。出社日を利用して社員同士個々人の交流を促進する時間を設けることも重要です。
全社員が出社する日を定期的に設定することで、社内コミュニケーションの活性化だけでなく社員のモチベーション向上や組織の連帯感の強化にも貢献する施策と言えます。
社内コミュニケーションの施策・アイデアの実施にあたって
社内コミュニケーションを活性化させるため、さまざまな施策やアイデアが存在します。しかし重要なのは、自社に合った施策を選択し状況や状態に応じて適切に導入することです。
たとえば、テレワーク環境下ではオンラインツールを活用したコミュニケーションが効果的です。チャットやビデオ会議を積極的に導入しリアルタイムでの情報共有を促進することが重要です。
通常環境下では、社内イベントやワークショップを通じて従業員同士の交流を深めることも有効です。さらに、社内報の定期的な配信やフィードバックの仕組みを整えることで情報の透明性や従業員間のコミュニケーションを促進することができます。
自社の特性やニーズに合わせて、柔軟かつ効果的な施策を取り入れることが成功の鍵となります。社内コミュニケーションの活性化は組織全体の連携やモチベーション向上につながり、生産性や企業文化の向上にも繋がる重要な取り組みであると言えます。
社内コミュニケーションを解決する一般的アプローチ
社内コミュニケーションが活性化することで、さまざまなメリットが得られることがわかりました。ここからは社内コミュニケーションを解決する一般的なアプローチについて紹介します。
社内コミュニケーションの現在地を可視化
社内コミュニケーションの課題を解決するためには、社内コミュニケーションの現在地を知るところから始めます。感覚的に知るのではなく可視化することが重要で、客観的な知見を活用できる状態にします。
サイロ化している業務やシステムは何か、部門間の壁はあるのか、生産性は低下しているのか、社員のエンゲージメントにはどのような変化が起きているのか、など定性的でなく定量的な情報を可視化します。
何が問題?課題定義
社内コミュニケーションの課題の要因を探ります。課題定義をしてから解決策を導き出すようにし、PDCAサイクルを回しながらブラッシュアップしていくことが大切です。
課題は目先に見えているものだけではなく、その背景に要因が潜んでいることが大半です。
「誰もが意見を言い合える会社を目指しているが、コミュニケーションが活性化されない」という問題の要因は、想いの浸透度かもしれませんし、コミュニケーションツールの力不足かもしれません。
課題が定義されないと解決策を生み出すことができず、解決に動いた結果どう変わったのかを知ることができなくなってしまいます。
情報の接点の問題解決
会社の経営理念や進むべき方向性・ビジョンが社内で共有できていなければ、社内コミュニケーションが機能していないも同然でしょう。社内の浸透活動の中で情報が伝わりにくく共有がなされていない場合、情報の接点部分が問題であり、解決策を考える必要があります。
社内にあるイントラネットや社内報、メディアコミュニケーションなどを見直し、課題を明確化させます。社内広報の現状を調査した上で社内広報ツールの活用方針やコンテンツの改善プランを作成しましょう。
情報を共有する場やメディアの問題と解決
社内コミュニケーションが活性化されていない原因として「情報を共有する場がないケース」では、場所と提供するメディア問題を解決する必要があります。 コミュニケーションを取りたい社員が多くても、発信する場所や連絡を取り合う場所がなければコミュニケーションは活性化されません。
理想的なコミュニケーションを取るために社内のコミュニケーションツールを1から作成しようと思うと時間と手間がかかるので、コミュニケーションのあるべき姿に合わせるのではなく、すでに用意されているコミュニケーションサービスに合わせる施策を取ると解決までのスピードが早くなります。
組織風土の問題解決
組織風土により社内コミュニケーションが取りにくい状態になっている場合は、組織変革から取り組みます。マネジメント層と一般社員層の意思疎通が取れていない場合、マネジメント層の組織改革を実践しなければなりません。
現場で働く社員のエンゲージメント向上に向けて全社の改革につながる価値観やテーマを検討しましょう。そして実際に改革を進めていくプロジェクトを組成し、推進していきます。
個々人の関係性の問題と解決
個々人の関係性が薄くコミュニケーションが取れていない場合は、社内イベントやクラブ活動といった施策が有効です。人間関係が良好になることで、社内コミュニケーションも活性化されていきます。
個々人の関係性を良化させるためには、全社員を対象とした参加型のイベントが適しています。イベントの準備段階から社員を巻き込むことで普段は関わることがない人と部署を越えて関わることができ、共体験を通じてモチベーション向上につながります。
個々人のコミュニケーションスキル問題
個々人のコミュニケーションスキルが低くコミュニケーションが取れていない場合は、研修やワークショップを行います。
まずは研修に参加する動機づけから始めましょう。ワークショップの目的を明確にして時間を捻出する動機づけをすることで研修の成果が出やすくなります。
社内コミュニケーション活性化の事例を紹介
社内コミュニケーションの活性化に取り組んでいる企業の事例を紹介します。
ソフィアでは大小さまざまな企業で、生産性向上や社員のモチベーションアップを導く社内コミュニケーションへの取り組みを実施しています。企業内でどのような問題が起こり、どのような解決策を取ってきたのか、自社の状況と照らし合わせながら参考にしてください。
株式会社ニチレイフーズの事例
冷凍食品やレトルト食品の製造・加工・販売を手掛ける株式会社ニチレイフーズでは「ハミダス(とらわれず、明るく)」を従業員のモットーとして、社内・社外問わずに活動しています。生活者向けの営業活動支援、全国の工場での地域社会貢献活動や食育活動に始まり、従業員同士のコミュニケーションを良くするためのバーベキュー大会や社員旅行まで、さまざまな活動の運営・支援に取り組んでいます。
そんな中、社内システムが「Lotus Notes」から「Office365」に移行することになり、これまでNotesで発信していた内容がOffice365のSharePointで実現できるのか不安を感じていました。社内インフラの構築方針によって、社内基盤が変わることは良く起こります。これまでに蓄積していた社内コミュニケーションの経験値を、新しいインフラ環境でも活かすためには具体的な完成イメージを持つことが大切です。
株式会社ニチレイフーズでは、Webサイトを通して相互にコミュニケーションが取れるような場所にしたいという想いを実現しました。今後は、情報発信すると同時に今までの情報を蓄積していく場にすることを目指しています。
株式会社ユーグレナの事例
ユーグレナでは、年に2回、グループ各社が一堂に会するグループ総会を開催し、グループ総会の場で、ユーグレナの考え方や方針、これからのビジョンなどを発表しています。しかし、総会を「点」として捉えるのではなく、今後の活動を踏まえた「線」にしていく必要がありました。グループ内に考え方を浸透させるためには、継続的に会社に対する想いをつなげていかなければなりません。そこで、MicrosoftのSwayという簡易的なWebサイトを作れるアプリケーションを使って、総会の内容を発信するコンテンツを作成しました。
株式会社ポーラ・オルビスホールディングスの事例
株式会社ポーラ・オルビスホールディングスは、化粧品の訪問販売、百貨店やファッションビルでの販売、エステティックサロン併設店舗の展開などをしている企業です。株式会社ポーラ・オルビスホールディングスでは、既存のグループウェアの老朽化に伴い新しいシステムへのリプレイスを検討していました。コロナ禍で働き方に変化が起こり、在宅勤務の環境構築のため、Microsoft365を選択しました。
また、リプレイスを機にグループウェアの単なる入れ替えではなく、会社のありようや文化を変えていくために活用したいと考えていました。そこで、SharePointOnlineを活用し、全社発信のサイトを構築、従業員へ会社の思いを浸透させることにしました。Microsoft365にはさまざまなツールが用意されており、これから活用範囲を広げていく可能性があります。Teamsを用いたコミュニケーションの良化はリモートワークで働く人を含めた社内のコミュニケーション良化につながっています。
まとめ
社内コミュニケーションを活性化させるためのアプローチ方法や代表的な企業の解決事例をご紹介しました。社内コミュニケーションの活性化のためには、その場限りで課題を解決するのではなく継続的に取り組んでいかなければなりません。
経営層の思いを伝え、社員同士のコミュニケーションが活性化するためには、自社の状況に適したコミュニケーションツールの活用やインフラの整備を行うことも重要です。
社内コミュニケーションが活性化すると、従業員が働きやすい職場を整えるだけでなく、生産性向上や離職率の低下といったメリットを得ることができます。